テーマ: 読書(8213)
カテゴリ: 読書
 西郷札
■
西郷札
■わたしの勤める新聞社が企画した展覧会への出品資料として、宮崎支局から西郷札とその「覚書」が送られてきた。
興味を抱いたわたしは覚書を筆写した。
内容は以下のように始まる。
日向国佐土原生まれの士族・樋村雄吾の家は、明治の廃藩置県を受けて世禄を失った。
父は後妻とその連れ子・季乃を迎える。
季乃は雄吾を兄さまと言って慕ったが、雄吾は素直に感情を出せず、何となく拗ねた態度に出ていた。
雄吾は西南戦争に参加したが、その間に父は死去、家は戦火で焼かれ、継母と季乃は行方知れずとなっていた。
雄吾は悄然と故郷を去り、東京へ向かう。
無為のうちに過ごす雄吾だったが、やがて俥(くるま)を曳く車夫として収入を得るようになる。
ある夜、エリート官吏・塚村圭太郎を深川清住まで送った雄吾は、屋敷の近くで季乃の顔を発見し、動揺する…。
 松本清張(マツモトセイチョウ)1909-1992。
松本清張(マツモトセイチョウ)1909-1992。小倉市(現・北九州市小倉北区)生れ。
給仕、印刷工など種々の職を経て朝日新聞西部本社に入社。
41歳で懸賞小説に応募、入選した『西郷札』が直木賞候補となり、
1953(昭和28)年、『或る「小倉日記」伝』で芥川賞受賞。
’58年の『点と線』は推理小説界に“社会派”の新風を生む。
生涯を通じて旺盛な創作活動を展開し、その守備範囲は古代から現代まで多岐に亘った。
 読みたいと思っていた「西郷札」がやっと読めた。
読みたいと思っていた「西郷札」がやっと読めた。「西郷札」の他にも、幕末から明治期の動乱の時代を描いた作品(★)が多かった。
★★は、徳川時代を背景にしている。
普通の作家だったら、どれも代表作と言われるような作品なのに、これらは、デビュー後数年の作品というから、さすが松本清張。
「西郷札」を書いた翌年、『或る「小倉日記」伝』(これも読まねば)を書いて、芥川賞を受賞。
直木賞にノミネートした作品を書いた翌年、芥川賞なのだ!!
どの作品も、哀しい。
 ★西郷札
★西郷札*西南戦争の際に薩軍が発行した軍票をもとに一攫千金を夢見た男とその破滅を描く。
東京から横浜まで汽車。
横浜から郵便汽船に便乗して神戸に。
そこから別の船便で瀬戸内海を西へ西へと航行する。
船はあちこちに寄港してやっと臼杵(うすき)港に到着。
ここから馬車また馬車に乗り継ぎ10日あまりで東京からの旅は終わった。
江戸時代よりも大分早くなっている。
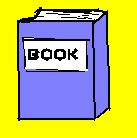 ★くるま宿
★くるま宿「くるま」とは、人力車のことで、明治2年ごろに作られたとのこと。
当初は、くるまの胴に蒔絵で、金時や児雷也や、波を描いて美麗を競ったが間もなくすたれた。
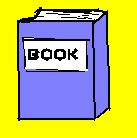 ★梟示抄(きょうじしょう)
★梟示抄(きょうじしょう)*江藤新平の末路を実録的に描いて、同じ権力機構内にいるものの軋轢、対照的な勝敗を浮びあがらせた。
明治期に、「赤ゲット」という言葉ができたが、赤毛布が後に、赤ゲットという単語に変わる。
《「ゲット」は「ブランケット」の略》
〔ゲットはブランケットから〕
田舎から都会見物に来た人。お上りさん。
明治初期、東京見物の旅行者が赤い毛布を羽織っていたところからいった。
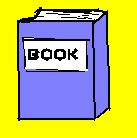 ★啾々吟(しゅうしゅうぎん)
★啾々吟(しゅうしゅうぎん)*幕末に、大名、家老、軽輩の子として同じ日に生れた三人の子供が動乱の時代に如何なる運命を辿ったかを追及した
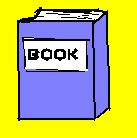 ★★戦国権謀
★★戦国権謀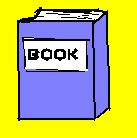 ★権妻
★権妻◎「権妻(ごんさい)」とは、正妻でない妻。めかけ。ごん。明治初期に用いられた語。⇔本妻。
一夫一婦制が確立されるのは、明治三十一年(1898年)の民法によって・・・
お妾さんは、多くの時代で日陰の身であり、何の権利も無いのが普通でしたが、これが、明治の一時期だけ、正式に認められた事があったんですね~
明治三年(1870年)に制定された『新律綱領(しんりつこうりょう)』・・・これは、江戸幕府や中国の刑法典をもとにして、明治政府のもとで作成された最初の刑法典なので、もちろん、このお妾さんの事以外にも、身分制度など様々な事が定められているわけですが、その中で、妻とお妾さん(二親等)の二人の妻の持つ事が公認されていたのです。
このお妾さんは権妻(ごんさい)と呼ばれました。
当時は戸籍に「権妻」を記す欄があった。
 ★★酒井の刃傷
★★酒井の刃傷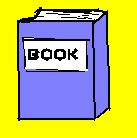 ★★二代の殉死
★★二代の殉死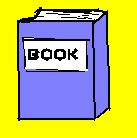 ★面貌
★面貌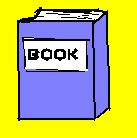 ★★恋情
★★恋情
■ (▲このような浅瀬をフォードという) ■
◎牛津(オックスフォード)・・・この頃は、地名も漢字。
■ 地名にあるフォードは、 ■(歩いて渡れる)浅瀬を意味する。
ストラトフォードは、ストラト(古英語のストリート)の浅瀬。
オックスフォードという地名があるが、「牡牛の渡る浅瀬」。
イギリスから帰ってから調べてみたら、日本では「洗い越し」といい方をするそうだ。
 ★噂始末
★噂始末 ★白梅の香
★白梅の香◎島根県の南西に位置する町、津和野から参勤交代で江戸へ。
一行は周防(今の山口)に出て船に乗る。
瀬戸内海を家紋をつけた帆をはらませ、海上百七十里を走って大坂の川口に着く。
伏見までは川船、ここから京都、大津・・・と東海道を下った。
三月半ばに出立して、江戸に着いたのは四月初めだった。
◎鼠鳴き(ねずみなき)
ねずみの鳴き声をまねて口を鳴らすこと。人を呼んだり子供をあやしたり、遊女が客を呼び入れたりするときにする。「ねずみなき」とも。
にほんブログ村
・・・・・・・・・・・・・・・・・
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書] カテゴリの最新記事
-
手紙のなかの日本人:半藤一利 2024.05.27
-
残り者:朝井まかて:江戸城明け渡し 2024.05.25
-
グリーンピースの秘密:ベルリン日記:小… 2024.05.24
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
6月14日 金曜日 イ…
New!
ジェウニー1072さん
梅雨じめり New!
桐山陶子さん
New!
桐山陶子さん
「一緒に学ぼう! … New! machiraku_hokkaidoさん
みちばたかれん New! 歩楽styleさん
昭和レトロジャズバ… New!
maki5417さん
New!
maki5417さん
梅雨じめり
 New!
桐山陶子さん
New!
桐山陶子さん「一緒に学ぼう! … New! machiraku_hokkaidoさん
みちばたかれん New! 歩楽styleさん
昭和レトロジャズバ…
 New!
maki5417さん
New!
maki5417さんFreepage List
◆はるな的◆
メモ

memo
らくがき帳・地球

春の落書き

夏の落書き

秋の落書き

冬の落書き

ときなし

写真

写真2
◎地球を救う127の方法◎

ごみを減らす

エネルギー

水

食

交通機関

有害物質・汚染物質について

命をいつくしみ身近な所から変革を

頭の使い方・考え方

みどり学
父の諺★母の言葉
父の麦わら帽子・目次
おしゃれ手紙◆目次
ちゅん太、その日その日
シェーグレン症候群
★映画★2002~2006

映画★2007

映画★2008

映画★2009

映画★2010

映画★2011

映画★2012

映画★2013

映画★2014

映画★2015

映画★2016

映画★2017

映画★2018

映画★2019

映画★2020

映画★2021

映画★2022

映画★2023

映画★2024

**
旅2007・2008

旅2009

旅2010

欧州2010

欧州2011■2012年旅■

旅2014

旅2015

旅2016

旅2017

旅2018 *旅2019

旅2023
◎
Comments
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
© Rakuten Group, Inc.








