PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Comments
まだ登録されていません
カテゴリ: 観照

1月に奈良国立博物館に出かけたことは既に拙ブログに書き込みました。
JR奈良駅から三条通を東に上って行き、猿沢池の北西辺が見え始める辺りで、道路の左側に見える興福寺への石段道を上り、南円堂を眺めつつ右折して興福寺境内を横切って行き、奈良公園に向かいます。それがいつもの私の往路ルートです。
冒頭の景色は、石段の途中から三重塔へむかう道を撮った景色 。
この日、久々に三重塔への道に何気なく足を踏み入れました。三重塔までは幾度も行っています。
手前の大木の前に立つ 板碑 には、右から「 救世観世音菩薩 出世地蔵尊 延命能師地蔵尊 水子地蔵尊 」と刻されています。ここには数多くの石仏が祀られています。

地蔵尊の傍に小児が寄り添うように立っています。台座の正面には「 延命地蔵尊
この辺りの石仏等は以前にご紹介していますので省略します。
 少し先に、「 三重塔
」があります。
少し先に、「 三重塔
」があります。
 その手前で北方向への坂道
その手前で北方向への坂道

南方向は というと、 境内の門が閉まっています 。扉の隙間から撮った景色。
三条通へ出られる坂道 です。ここはずっと閉鎖されていますので、今まで気にしたこともありませんでした。
この北への坂道を歩くことがありません。遠回りになるのを承知でこの坂道を上がって、普段と違った視点からの景色を見つつ、興福寺境内を横切ることにしました。

この三重塔は普段は非公開 7月7日のみ内陣公開 」と公開情報の記載がありますので、その日だったか、あるいは何らかの特別公開期間に該当していたのでしょう。
この三重塔婆は 国宝 です。平安時代末期の1143年、崇徳天皇の中宮の皇嘉門院聖子が建立しましたが、1180年に焼失し、間もなく再建されたと言われています。鎌倉時代の建物で、平安時代の建築様式を伝えているそうです。興福寺の伽藍の中では、北円堂と共に最古の建物になります。 (資料1)
丘陵上の境内地では一番低い位置に立地する建物です。通常の年に中金堂や五重塔あたりに観光客を大勢みかけても、この三重塔前ではあまり観光客を見かけません。

正面に見えるのが「北円堂」 だとわかります。
坂道の左側は築地塀、右側は木柵です。


右に「南円堂」の 普段は目にしない 背後からの景色 が移ろっていくのを眺めつつ坂道を歩むと、正面には北円堂が少しずつ大きく見えてきます。
 北円堂
北円堂
運慶一門が作った 本尊弥勒菩薩坐像 とその脇侍される 無著・世親の像 が安置されていることで有名です。
創建堂とその後2回の焼亡と再興の時代は藤原氏、 氏人の追善供養堂 でしたが、平重衡の南都焼き討ちで焼亡しました。その後28年の歳月をへて鎌倉時代に現在の北円堂が再興されました。その時には法相宗祖「弥勒の太閤」と位置づけられ、僧侶達の 宗祖師堂へ とその機能が変容していったそうです。 (資料2)

北円堂の南側の道路から、 「中金堂」と北側の「仮講堂」を眺めた景色 。
まだまだ周辺の整備作業(/調査)進行中のようです。

北円堂の南側の道を進み、右折して 南円堂の方に戻ります 。
定規筋の入った築地塀と門が見え、その南側に 二階建の建物「納経所」 が見えます。
納経所の右側にみえる 八 角形の屋根が南円堂 です。その間に低く見える 寄棟造屋根の建物が「一言観音堂」(興善院) です。
三条通から石段を真っ直ぐに上がってくると、境内地の突き当たりに一言観音堂、斜め左側手前に南円堂、一言観音堂の右側に納経所の建物という景色が目に入ります。
この納経所まで戻れば、左折して無料休憩所の前を過ぎ、左側に中金堂の南面を眺めながら五重塔前まで横切り、さらに東金堂と五重塔の間の道を東進することになります。
一言観音堂は「霊験七観音巡拝所」の一つ です。一言だけ願いを聞いてくださる観音さまだそうです。「古くから霊験あらたかにして諸々の願い事を一つづつ聞き届けて下さる御仏であります。一度に多くを願わず成就すれば次のお願いをするようにしましょう」という説明が掲示されています。 (資料3)
奈良には、葛城一言主神社があります。一言主神への祈願と同じような祈り方ということになりますね。
この一言観音堂は4月17日の「放生会」の法要が行われるお堂 でもあり、貫首が金魚たちに仏教の戒律を授けるというユニークな儀式をおこなって、猿沢池に放つそうです。 (資料3)

奈良公園に入れば、奈良国立博物館常設の展示案内板です。


奈良公園内 の道を奈良博に向かって歩き 途中で立ち止まって前方と振り返った景色 を撮ってみました。平日の昼間だったとはいえ、こんな様子です。コロナ禍の影響が大きく影響しています。

少し先で、北東方向を見ても、人の姿は見えません。
右奥に見えるのは奈良国立博物館の旧館です。 北側の大きい建物が「なら仏像館」 と現在は名称を変えています。中央の大きなホールを軸にして、南北に張り出した建物の部分が展示スペースと回廊になっています。それに繋がっている 一番手前の建物が「青銅器館」 として使われ、中国古代青銅器<坂本コレクション>の常設展示室となっています。 (資料4)
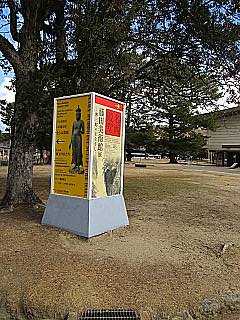



新館の手前まで来ても、こんな感じで 休館かと勘違いしそうな閑散さ でした。
あとは、奈良博の西新館の1階テラスからの 庭の冬の景色 を、記録を兼ねご紹介します。



プシュ式のスライド・ドアからテラスに出ると、ほぼ長方形の池が庭園内の池と繋がる形で存在し、庭園公開時以外は、庭側の門扉が閉まっています。外に出た辺りで 南東側から南西側を眺めた景色 です。


立ち位置を少しずつ変えて眺めて行きます。


池に水草がないので、庭園内の池との接合部もスッキリと見え、少し位置を変えることで、水面に映る樹木や空が変化し、雰囲気も変化します。

萱葺き屋根の建物は茶室「八窓庵」 です。

テラスには、 「八窓庵」の案内 が設置されています。
江戸中期に創建され、草庵式・入母屋造萱葺平入屋根、柿葺の土間庇という様式で、古田織部好みの茶室です。
「もとは興福寺大乗院の庭園(現在の奈良ホテルの南)に建っていた古茶室。奈良の篤志家たちにより、明治25年(1892)に博物館に寄贈、移築された。一名、含翠亭という。
東大寺四聖坊にあった隠岐録( おきろく 、東京に移築、戦災で焼失)、興福寺慈眼院の六窓庵(東京国立博物館に移築)と併せて「大和三茶室」と称された。創建当初の姿を良く保っており、茶室(四畳台目)に相の間(四畳)と水屋(三畳)が附属する。織部好みとされるこの茶室は、千利休の好む極端に狭い茶室から、小堀遠州が好んだ四畳半台目のゆったりとした茶室に移行する中間のきわめて貴重な遺構である。」 (転記)

テラス側のほぼ長方形の池と、庭園内の池とはこのように繋がっています。

西新館側から庭に入り、宝篋印塔が置かれた手前の小径を西に歩めば、上掲の平石の架け橋に至ります。

池の奥側つまり南側には、 もうひとつの木橋 が架けてあります。

木橋の東詰には待合の建物 が立ち、 橋を西に渡ると茶室への門扉 が見えます。
門扉から八窓庵の躙り口までの景色を奈良博の「茶室 八窓庵」のページに360度の展望ができるように工夫してあります。 こちらからご覧ください。 (今回、調べていて気づきましたので・・・・ご紹介)

テラスから、 八窓庵の妻側(側面)の眺め

手前に、 「宝塔(国東塔)」 が置かれています。石製で鎌倉時代14世紀の作とのこと。 (資料5)
この宝塔の姿を関西では殆ど見かけません。ユニークさに溢れる形状です。
法華経見宝塔品に基づく一種の宝塔で、天沼俊一博士により「国東塔」と命名され て以来、これが愛称されるようになったと言います。塔身の首部に穴が作られていること。塔身の直下に蓮華座や反花よりなる台座があること。相輪の頂上に火焔のあることなどの特徴を持っています。九州の国東半島に分布し、その周辺にも点在すると言います。ある時点での酒井富蔵氏の調査結果によれば、有銘32基、無銘113基計145基に及んでいるそうです。西三郷(西国東)に圧倒的に多くが分布し、東三郷(東国東)には数量は少ないが優秀品が集まっていると言います。鎌倉末期から南北朝期に有銘塔が多く、室町期には殆ど無銘塔になるとか。石材は一部凝灰岩を除き、ほとんどが角閃安山岩だとか。銘文の調査によれば、納経、供養、逆修(生前供養のため)、あるいは墓標として建立されています。
国東仏教文化遺産の代表としては 弘安6年(1283)造顕の岩戸山国東塔(重文) があります。岩戸寺は六郷山・末山本寺の名刹です。 (資料6)


西新館の南西隅から北方向の景色 。 南西隅から東方向を眺めた景色 。
テラスに沿い設けられた池は西新館の北、西、東の三方を囲っていることがわかります。

同じ位置から庭側を眺めた景色
そして、

小ぶりな石造物が木の根本にちょこんと置かれているのに気づきました。
これは何? 人物像のように見えますが、石塔の欠損部材でしょうか・・・・ 正体不明 。
課題が残りました。
ご覧いただきありがとうございます。
参照資料
1) 三重塔 :「興福寺」
2)『比べてもっとよくわかる仏像』 熊田由美子著 朝日新聞出版 p195
3) [興福寺一言観音堂]放生会の会場にもなる小さなお堂で「一言」の祈りを捧げる :「奈良まちあるき風景紀行」
4) なら仏像館 建物について :「奈良国立博物館」
5) 宝塔(国東塔) 画像データベース :「奈良国立博物館」
6)『国東文化と石仏』 文 大嶽順公 写真 渡辺信幸 著 木耳社 p92-93,p98
補遺
興福寺 ホームページ
境内案内
葛城一言主神社 ホームページ
一言主神社(御所市) :「いかすなら」
妙法蓮華経見宝塔品第十一 :「広済寺と近松門左衛門」
国東塔 :ウィキペディア
岩戸寺(国東市) :ウィキペディア
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
1月の奈良博での特別展については、こちらをご覧いただけるとうれしいです。
観照 奈良国立博物館 名画の殿堂 藤田美術館展 -傳三郎のまなざし-

1月に奈良国立博物館に出かけたことは既に拙ブログに書き込みました。
JR奈良駅から三条通を東に上って行き、猿沢池の北西辺が見え始める辺りで、道路の左側に見える興福寺への石段道を上り、南円堂を眺めつつ右折して興福寺境内を横切って行き、奈良公園に向かいます。それがいつもの私の往路ルートです。
冒頭の景色は、石段の途中から三重塔へむかう道を撮った景色 。
この日、久々に三重塔への道に何気なく足を踏み入れました。三重塔までは幾度も行っています。
手前の大木の前に立つ 板碑 には、右から「 救世観世音菩薩 出世地蔵尊 延命能師地蔵尊 水子地蔵尊 」と刻されています。ここには数多くの石仏が祀られています。

地蔵尊の傍に小児が寄り添うように立っています。台座の正面には「 延命地蔵尊
この辺りの石仏等は以前にご紹介していますので省略します。
 少し先に、「 三重塔
」があります。
少し先に、「 三重塔
」があります。 その手前で北方向への坂道
その手前で北方向への坂道
南方向は というと、 境内の門が閉まっています 。扉の隙間から撮った景色。
三条通へ出られる坂道 です。ここはずっと閉鎖されていますので、今まで気にしたこともありませんでした。
この北への坂道を歩くことがありません。遠回りになるのを承知でこの坂道を上がって、普段と違った視点からの景色を見つつ、興福寺境内を横切ることにしました。

この三重塔は普段は非公開 7月7日のみ内陣公開 」と公開情報の記載がありますので、その日だったか、あるいは何らかの特別公開期間に該当していたのでしょう。
この三重塔婆は 国宝 です。平安時代末期の1143年、崇徳天皇の中宮の皇嘉門院聖子が建立しましたが、1180年に焼失し、間もなく再建されたと言われています。鎌倉時代の建物で、平安時代の建築様式を伝えているそうです。興福寺の伽藍の中では、北円堂と共に最古の建物になります。 (資料1)
丘陵上の境内地では一番低い位置に立地する建物です。通常の年に中金堂や五重塔あたりに観光客を大勢みかけても、この三重塔前ではあまり観光客を見かけません。

正面に見えるのが「北円堂」 だとわかります。
坂道の左側は築地塀、右側は木柵です。


右に「南円堂」の 普段は目にしない 背後からの景色 が移ろっていくのを眺めつつ坂道を歩むと、正面には北円堂が少しずつ大きく見えてきます。
 北円堂
北円堂
運慶一門が作った 本尊弥勒菩薩坐像 とその脇侍される 無著・世親の像 が安置されていることで有名です。
創建堂とその後2回の焼亡と再興の時代は藤原氏、 氏人の追善供養堂 でしたが、平重衡の南都焼き討ちで焼亡しました。その後28年の歳月をへて鎌倉時代に現在の北円堂が再興されました。その時には法相宗祖「弥勒の太閤」と位置づけられ、僧侶達の 宗祖師堂へ とその機能が変容していったそうです。 (資料2)

北円堂の南側の道路から、 「中金堂」と北側の「仮講堂」を眺めた景色 。
まだまだ周辺の整備作業(/調査)進行中のようです。

北円堂の南側の道を進み、右折して 南円堂の方に戻ります 。
定規筋の入った築地塀と門が見え、その南側に 二階建の建物「納経所」 が見えます。
納経所の右側にみえる 八 角形の屋根が南円堂 です。その間に低く見える 寄棟造屋根の建物が「一言観音堂」(興善院) です。
三条通から石段を真っ直ぐに上がってくると、境内地の突き当たりに一言観音堂、斜め左側手前に南円堂、一言観音堂の右側に納経所の建物という景色が目に入ります。
この納経所まで戻れば、左折して無料休憩所の前を過ぎ、左側に中金堂の南面を眺めながら五重塔前まで横切り、さらに東金堂と五重塔の間の道を東進することになります。
一言観音堂は「霊験七観音巡拝所」の一つ です。一言だけ願いを聞いてくださる観音さまだそうです。「古くから霊験あらたかにして諸々の願い事を一つづつ聞き届けて下さる御仏であります。一度に多くを願わず成就すれば次のお願いをするようにしましょう」という説明が掲示されています。 (資料3)
奈良には、葛城一言主神社があります。一言主神への祈願と同じような祈り方ということになりますね。
この一言観音堂は4月17日の「放生会」の法要が行われるお堂 でもあり、貫首が金魚たちに仏教の戒律を授けるというユニークな儀式をおこなって、猿沢池に放つそうです。 (資料3)

奈良公園に入れば、奈良国立博物館常設の展示案内板です。


奈良公園内 の道を奈良博に向かって歩き 途中で立ち止まって前方と振り返った景色 を撮ってみました。平日の昼間だったとはいえ、こんな様子です。コロナ禍の影響が大きく影響しています。

少し先で、北東方向を見ても、人の姿は見えません。
右奥に見えるのは奈良国立博物館の旧館です。 北側の大きい建物が「なら仏像館」 と現在は名称を変えています。中央の大きなホールを軸にして、南北に張り出した建物の部分が展示スペースと回廊になっています。それに繋がっている 一番手前の建物が「青銅器館」 として使われ、中国古代青銅器<坂本コレクション>の常設展示室となっています。 (資料4)
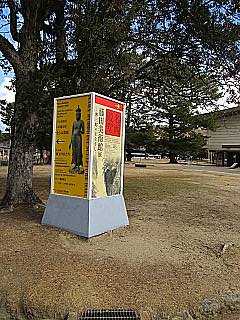



新館の手前まで来ても、こんな感じで 休館かと勘違いしそうな閑散さ でした。
あとは、奈良博の西新館の1階テラスからの 庭の冬の景色 を、記録を兼ねご紹介します。



プシュ式のスライド・ドアからテラスに出ると、ほぼ長方形の池が庭園内の池と繋がる形で存在し、庭園公開時以外は、庭側の門扉が閉まっています。外に出た辺りで 南東側から南西側を眺めた景色 です。


立ち位置を少しずつ変えて眺めて行きます。


池に水草がないので、庭園内の池との接合部もスッキリと見え、少し位置を変えることで、水面に映る樹木や空が変化し、雰囲気も変化します。

萱葺き屋根の建物は茶室「八窓庵」 です。

テラスには、 「八窓庵」の案内 が設置されています。
江戸中期に創建され、草庵式・入母屋造萱葺平入屋根、柿葺の土間庇という様式で、古田織部好みの茶室です。
「もとは興福寺大乗院の庭園(現在の奈良ホテルの南)に建っていた古茶室。奈良の篤志家たちにより、明治25年(1892)に博物館に寄贈、移築された。一名、含翠亭という。
東大寺四聖坊にあった隠岐録( おきろく 、東京に移築、戦災で焼失)、興福寺慈眼院の六窓庵(東京国立博物館に移築)と併せて「大和三茶室」と称された。創建当初の姿を良く保っており、茶室(四畳台目)に相の間(四畳)と水屋(三畳)が附属する。織部好みとされるこの茶室は、千利休の好む極端に狭い茶室から、小堀遠州が好んだ四畳半台目のゆったりとした茶室に移行する中間のきわめて貴重な遺構である。」 (転記)

テラス側のほぼ長方形の池と、庭園内の池とはこのように繋がっています。

西新館側から庭に入り、宝篋印塔が置かれた手前の小径を西に歩めば、上掲の平石の架け橋に至ります。

池の奥側つまり南側には、 もうひとつの木橋 が架けてあります。

木橋の東詰には待合の建物 が立ち、 橋を西に渡ると茶室への門扉 が見えます。
門扉から八窓庵の躙り口までの景色を奈良博の「茶室 八窓庵」のページに360度の展望ができるように工夫してあります。 こちらからご覧ください。 (今回、調べていて気づきましたので・・・・ご紹介)

テラスから、 八窓庵の妻側(側面)の眺め

手前に、 「宝塔(国東塔)」 が置かれています。石製で鎌倉時代14世紀の作とのこと。 (資料5)
この宝塔の姿を関西では殆ど見かけません。ユニークさに溢れる形状です。
法華経見宝塔品に基づく一種の宝塔で、天沼俊一博士により「国東塔」と命名され て以来、これが愛称されるようになったと言います。塔身の首部に穴が作られていること。塔身の直下に蓮華座や反花よりなる台座があること。相輪の頂上に火焔のあることなどの特徴を持っています。九州の国東半島に分布し、その周辺にも点在すると言います。ある時点での酒井富蔵氏の調査結果によれば、有銘32基、無銘113基計145基に及んでいるそうです。西三郷(西国東)に圧倒的に多くが分布し、東三郷(東国東)には数量は少ないが優秀品が集まっていると言います。鎌倉末期から南北朝期に有銘塔が多く、室町期には殆ど無銘塔になるとか。石材は一部凝灰岩を除き、ほとんどが角閃安山岩だとか。銘文の調査によれば、納経、供養、逆修(生前供養のため)、あるいは墓標として建立されています。
国東仏教文化遺産の代表としては 弘安6年(1283)造顕の岩戸山国東塔(重文) があります。岩戸寺は六郷山・末山本寺の名刹です。 (資料6)


西新館の南西隅から北方向の景色 。 南西隅から東方向を眺めた景色 。
テラスに沿い設けられた池は西新館の北、西、東の三方を囲っていることがわかります。

同じ位置から庭側を眺めた景色
そして、

小ぶりな石造物が木の根本にちょこんと置かれているのに気づきました。
これは何? 人物像のように見えますが、石塔の欠損部材でしょうか・・・・ 正体不明 。
課題が残りました。
ご覧いただきありがとうございます。
参照資料
1) 三重塔 :「興福寺」
2)『比べてもっとよくわかる仏像』 熊田由美子著 朝日新聞出版 p195
3) [興福寺一言観音堂]放生会の会場にもなる小さなお堂で「一言」の祈りを捧げる :「奈良まちあるき風景紀行」
4) なら仏像館 建物について :「奈良国立博物館」
5) 宝塔(国東塔) 画像データベース :「奈良国立博物館」
6)『国東文化と石仏』 文 大嶽順公 写真 渡辺信幸 著 木耳社 p92-93,p98
補遺
興福寺 ホームページ
境内案内
葛城一言主神社 ホームページ
一言主神社(御所市) :「いかすなら」
妙法蓮華経見宝塔品第十一 :「広済寺と近松門左衛門」
国東塔 :ウィキペディア
岩戸寺(国東市) :ウィキペディア
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
1月の奈良博での特別展については、こちらをご覧いただけるとうれしいです。
観照 奈良国立博物館 名画の殿堂 藤田美術館展 -傳三郎のまなざし-
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[観照] カテゴリの最新記事
-
観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15
-
観照 大阪 あべのハルカス美術館 [徳… 2024.06.14
-
観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.09 コメント(3)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










