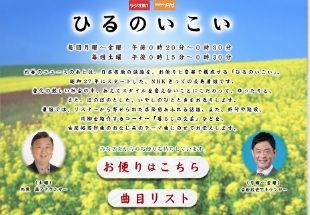PR
X
Free Space
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(0)映画 Cinema
(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube
(268)TVラジオ番組 television & radio programs
(374)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad
(148)外国語学習 Studying Foreign Language
(67)花 Flowers
(329)グルメ Gourmet
(204)介護 Nursery Care
(20)中高年の資格取得Qualification for middle
(15)散歩 Taking a walk
(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life
(121)フィットネスクラブ Fitness Club
(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath
(10)旅行 Travel
(88)読書 Reading
(54)健康 Health
(44)絵画 Picture
(25)Japanese TV Drama with English
(2)季節
(32)災害
(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス
(88)リンク修正、内容追加
(180)政治
(156)宗教
(121)写真
(27)グリーティング
(45)人生
(19)科学
(17)ダイエット
(7)少子・高齢化社会
(11)生き物 creatures
(5)月と星空
(26)不動産
(2)Comments
Freepage List
カテゴリ: ナンチャッテ経済学・ファイナンス
9月20日の週の、中国の不動産会社の破綻懸念やFOMCの量的緩和縮小問題はどうなることかと思いましたが、市場が平穏さを取り戻したようでほっとしています。
慶応大の小幡先生は今回の急落の原因を、「株をそろそろ売りたい」という投資家がほとんどであったことが理由のすべてだ、と分析されていますが、なるほどと思います。
量的緩和縮小は、株・不動産の下落につながると自分では思いこんでいるので、そろそろ脱出の準備をしたほうが良いかなと思って準備中です。
久々に拝見した植草先生の記事では、リーマンショック時とは派生金融商品残高が違う点、総選挙状況が急変して自民の大敗は免れそう、米緩和縮小は半年程度で完了してしまう方向が示唆されたというご指摘を見ると、まだまだ大丈夫かなとも思ってしまったりもします。
去年の2,3月の新型肺炎時の市場の混乱のように、いつ最悪の事態が起きてもいいように、心がけたいと思います。
■参考リンク

抜粋
そして22日。予想以上に、FOMCの声明はタカ派だった。普通ならこれで売られそうなものであるが、今回はともかくFOMCが終わった、ということ、そしてほかの投資家たちも今は投げ売りをするのではなく、少しだけ売ったことがはっきりしたので、売った分を買い戻す動きになった。
今回の急落の理由は「株を売りたい」がすべて
とにかく不動産のニュースや状況の中身はどうでもよかった。だからこそ、どこまで売るかは、ほかの投資家がどこまで売るか、すなわち、どのくらい下がるか、にかかっていたのである。だから、投資家同士のにらみ合いになり、2日間かけて下落幅を確認していったのである。
そして「中国の不動産」というのは、きっかけや合図にすぎないから、本当に重要なニュースは、アメリカの中央銀行であるFEDの意向であった。だから、そのニュースを待ったのである。
日銀もついに「テーパリング」するときが来た日本銀行が犯した「5つの間違い」とは一体何か小幡 績 : 慶應義塾大学大学院准教授 2021/09/05 5:00東洋経済ONLINE
抜粋
1度目は、世界金融危機(2008年のリーマンショック)のときのベン・バーナンキFRB議長(当時)だ。2013年に「バーナンキショック」などと投機関係者には八つ当たりされたが、しかし、自分が広げた風呂敷は、しっかりたたむメドをつけて去っていった。
だから、その後FEDのバランスシートはしっかりと縮小し、今回のコロナショックへの対応で、国債などの資産買い入れを大規模に行うことができた。そして、また、今回もその資産買い入れ政策の役割が終わったら、さっと引き揚げることに成功しつつある。資産買い入れ政策は危機対応の緊急政策であって、ドカンとやって、さっと引き揚げる。これが戦略の要諦である。アフガニスタンが、その反対の例だ。
一方、日本銀行は、言ってみれば昨今のアフガニスタンよりもひどい状況だ。2001年に量的緩和を開始し、福井俊彦総裁(当時)が2006年に解除した。これは、パウエル議長と同様、きちんと幕引きをして去っていったのだが、現在は見るも無残な状況になっており、国債発行残高の半分は日本銀行が保有するという有様だ。
2021年9月25日 8時30分市況 植草一秀の「金融変動水先案内」 -山積するリスクのはざま-第67回 山積するリスクのはざま
●注目される習近平政権対応
コロナ、金融政策転換、恒大懸念、さらに日本政局変動とビッグイベント山積の金融市場ですが、株式市場の基調の強さが伺われます。恒大グループは9月23日に期限を迎える社債の利払いのうち人民元建ての支払いを実施すると22日に発表しました。この発表で安心感が広がり、世界の株式市場で株価反発の流れが強まりました。
しかし、恒大グループは23日期限のドル建て社債の利払いを30営業日以内に実施しなければ債務不履行に陥るほか、これからその他の多額の利払いの期限が相次ぐことから、不透明な状況が続く状況に変化はありません。
恒大グループの債務残高は33兆円水準と見られ、破綻処理に移行する場合には連鎖的な影響が懸念されています。中国の習近平政権は共同富裕政策を掲げており、中国社会の格差拡大の是正に取り組む姿勢を示しています。このため、政府主導での企業救済の可能性は低いと見られます。とはいえ、金融危機を招来させれば政権のダメージも大きくなるため、政府主導での問題処理が模索されることになるでしょう。
現時点での手放しの楽観は許されませんが、2008年から09年にかけて生じた世界規模の金融危機到来の可能性は限定的であるとの見立てが有力になっているように思います。リーマン・ショック時の金融波乱のマグニチュードが大きくなったのは派生金融商品の組成残高が膨大であったことが背景で、この点に今回のリスクとの相違があると考えられます。
菅義偉首相が辞意を表明して自民党が党首を交代させることになったため、衆院総選挙情勢に大きな変化が生じています。菅内閣の支持率は3割を割り込み、重要な国政選挙、地方選挙での自公推薦候補の敗北が相次いでいました。このまま衆院総選挙に突入すれば与党議席の激減が現実化する恐れがありました。
ところが、自民党の党首が交代し新しい内閣が発足すると内閣支持率が跳ね上がります。このタイミングで衆院総選挙が実施されることになるわけで、与党大敗の可能性が低下しています。政治状況が大きく変化しないことが長期的に日本にプラスであるかどうかについては意見が分かれるところだと思いますが、短期的には政局の混乱が回避されるとの安心感が広がる可能性は否定できません。
立憲、共産、社民、れいわの野党4党が政策協定を締結して共闘体制を構築していますが、野党第一党の立憲民主党の野党共闘への取り組みに熱意が感じられないため、2009年総選挙に見られたような野党ブームは生じていません。自民党党首に誰が選出されるのかによって総選挙情勢は変化すると思われますが、与党大敗の可能性は低下しつつあると思われます。
これまでの最重要問題のコロナは急激な新規陽性者数の減少が確認されています。この変化を受けて菅内閣は9月末をもって緊急事態宣言解除に進むと見られますが、発出と解除の繰り返しでは進歩がありません。年末から1月にかけて感染再拡大の懸念があり、次の感染拡大への対応策を具体的に示すことが求められています。
●パウエル議長は続投か
政権とFRBの橋渡しをしているのがイエレン財務長官。イエレン女史はFRB議長を務めていたときにパウエル副議長とコンビを組んでいました。両者の関係は良好で、イエレン女史がバイデン大統領にパウエル続投を要請したとも伝えられています。
9月22日のFOMCでは、2022年末まで利上げなしとする見通しが22年中の利上げ着手に変更されました。テーパリングと呼ばれる量的金融緩和の縮小開始は11月のFOMCで決定される方向が示されましたが、緩和縮小を半年程度で完了してしまう方向も示唆されました。
利上げ実施もテーパリング加速も強い政策姿勢ですので株式市場が急落反応を示しても不思議ではないのです。ところが、金融市場は逆に強い政策スタンス方針の提示を受けて株高で反応しているのです。
市場の一瞬先は闇ですので手放しの楽観を抑制しなければなりませんが、パウエルFRB議長が金融市場との対話を巧みに実現している現状はひとつの安心材料と言えそうです。9月米雇用統計の発表は10月8日に予定されています。数値によっては金融市場が大きく反応することがあり得ますので要注意になることに留意しておきたいところです。
慶応大の小幡先生は今回の急落の原因を、「株をそろそろ売りたい」という投資家がほとんどであったことが理由のすべてだ、と分析されていますが、なるほどと思います。
量的緩和縮小は、株・不動産の下落につながると自分では思いこんでいるので、そろそろ脱出の準備をしたほうが良いかなと思って準備中です。
久々に拝見した植草先生の記事では、リーマンショック時とは派生金融商品残高が違う点、総選挙状況が急変して自民の大敗は免れそう、米緩和縮小は半年程度で完了してしまう方向が示唆されたというご指摘を見ると、まだまだ大丈夫かなとも思ってしまったりもします。
去年の2,3月の新型肺炎時の市場の混乱のように、いつ最悪の事態が起きてもいいように、心がけたいと思います。
■参考リンク

抜粋
そして22日。予想以上に、FOMCの声明はタカ派だった。普通ならこれで売られそうなものであるが、今回はともかくFOMCが終わった、ということ、そしてほかの投資家たちも今は投げ売りをするのではなく、少しだけ売ったことがはっきりしたので、売った分を買い戻す動きになった。
今回の急落の理由は「株を売りたい」がすべて
とにかく不動産のニュースや状況の中身はどうでもよかった。だからこそ、どこまで売るかは、ほかの投資家がどこまで売るか、すなわち、どのくらい下がるか、にかかっていたのである。だから、投資家同士のにらみ合いになり、2日間かけて下落幅を確認していったのである。
そして「中国の不動産」というのは、きっかけや合図にすぎないから、本当に重要なニュースは、アメリカの中央銀行であるFEDの意向であった。だから、そのニュースを待ったのである。
日銀もついに「テーパリング」するときが来た日本銀行が犯した「5つの間違い」とは一体何か小幡 績 : 慶應義塾大学大学院准教授 2021/09/05 5:00東洋経済ONLINE
抜粋
1度目は、世界金融危機(2008年のリーマンショック)のときのベン・バーナンキFRB議長(当時)だ。2013年に「バーナンキショック」などと投機関係者には八つ当たりされたが、しかし、自分が広げた風呂敷は、しっかりたたむメドをつけて去っていった。
だから、その後FEDのバランスシートはしっかりと縮小し、今回のコロナショックへの対応で、国債などの資産買い入れを大規模に行うことができた。そして、また、今回もその資産買い入れ政策の役割が終わったら、さっと引き揚げることに成功しつつある。資産買い入れ政策は危機対応の緊急政策であって、ドカンとやって、さっと引き揚げる。これが戦略の要諦である。アフガニスタンが、その反対の例だ。
一方、日本銀行は、言ってみれば昨今のアフガニスタンよりもひどい状況だ。2001年に量的緩和を開始し、福井俊彦総裁(当時)が2006年に解除した。これは、パウエル議長と同様、きちんと幕引きをして去っていったのだが、現在は見るも無残な状況になっており、国債発行残高の半分は日本銀行が保有するという有様だ。
2021年9月25日 8時30分市況 植草一秀の「金融変動水先案内」 -山積するリスクのはざま-第67回 山積するリスクのはざま
●注目される習近平政権対応
コロナ、金融政策転換、恒大懸念、さらに日本政局変動とビッグイベント山積の金融市場ですが、株式市場の基調の強さが伺われます。恒大グループは9月23日に期限を迎える社債の利払いのうち人民元建ての支払いを実施すると22日に発表しました。この発表で安心感が広がり、世界の株式市場で株価反発の流れが強まりました。
しかし、恒大グループは23日期限のドル建て社債の利払いを30営業日以内に実施しなければ債務不履行に陥るほか、これからその他の多額の利払いの期限が相次ぐことから、不透明な状況が続く状況に変化はありません。
恒大グループの債務残高は33兆円水準と見られ、破綻処理に移行する場合には連鎖的な影響が懸念されています。中国の習近平政権は共同富裕政策を掲げており、中国社会の格差拡大の是正に取り組む姿勢を示しています。このため、政府主導での企業救済の可能性は低いと見られます。とはいえ、金融危機を招来させれば政権のダメージも大きくなるため、政府主導での問題処理が模索されることになるでしょう。
現時点での手放しの楽観は許されませんが、2008年から09年にかけて生じた世界規模の金融危機到来の可能性は限定的であるとの見立てが有力になっているように思います。リーマン・ショック時の金融波乱のマグニチュードが大きくなったのは派生金融商品の組成残高が膨大であったことが背景で、この点に今回のリスクとの相違があると考えられます。
菅義偉首相が辞意を表明して自民党が党首を交代させることになったため、衆院総選挙情勢に大きな変化が生じています。菅内閣の支持率は3割を割り込み、重要な国政選挙、地方選挙での自公推薦候補の敗北が相次いでいました。このまま衆院総選挙に突入すれば与党議席の激減が現実化する恐れがありました。
ところが、自民党の党首が交代し新しい内閣が発足すると内閣支持率が跳ね上がります。このタイミングで衆院総選挙が実施されることになるわけで、与党大敗の可能性が低下しています。政治状況が大きく変化しないことが長期的に日本にプラスであるかどうかについては意見が分かれるところだと思いますが、短期的には政局の混乱が回避されるとの安心感が広がる可能性は否定できません。
立憲、共産、社民、れいわの野党4党が政策協定を締結して共闘体制を構築していますが、野党第一党の立憲民主党の野党共闘への取り組みに熱意が感じられないため、2009年総選挙に見られたような野党ブームは生じていません。自民党党首に誰が選出されるのかによって総選挙情勢は変化すると思われますが、与党大敗の可能性は低下しつつあると思われます。
これまでの最重要問題のコロナは急激な新規陽性者数の減少が確認されています。この変化を受けて菅内閣は9月末をもって緊急事態宣言解除に進むと見られますが、発出と解除の繰り返しでは進歩がありません。年末から1月にかけて感染再拡大の懸念があり、次の感染拡大への対応策を具体的に示すことが求められています。
●パウエル議長は続投か
政権とFRBの橋渡しをしているのがイエレン財務長官。イエレン女史はFRB議長を務めていたときにパウエル副議長とコンビを組んでいました。両者の関係は良好で、イエレン女史がバイデン大統領にパウエル続投を要請したとも伝えられています。
9月22日のFOMCでは、2022年末まで利上げなしとする見通しが22年中の利上げ着手に変更されました。テーパリングと呼ばれる量的金融緩和の縮小開始は11月のFOMCで決定される方向が示されましたが、緩和縮小を半年程度で完了してしまう方向も示唆されました。
利上げ実施もテーパリング加速も強い政策姿勢ですので株式市場が急落反応を示しても不思議ではないのです。ところが、金融市場は逆に強い政策スタンス方針の提示を受けて株高で反応しているのです。
市場の一瞬先は闇ですので手放しの楽観を抑制しなければなりませんが、パウエルFRB議長が金融市場との対話を巧みに実現している現状はひとつの安心材料と言えそうです。9月米雇用統計の発表は10月8日に予定されています。数値によっては金融市場が大きく反応することがあり得ますので要注意になることに留意しておきたいところです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.09.27 00:00:08
[ナンチャッテ経済学・ファイナンス] カテゴリの最新記事
-
目指せ年間配当100万円! 2024.06.10
-
2024.5.1TBS: “空き家0円で譲ります” 無償… 2024.06.06
-
5/31BB:日本のラウンドワン、衰退する米シ… 2024.06.03
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.