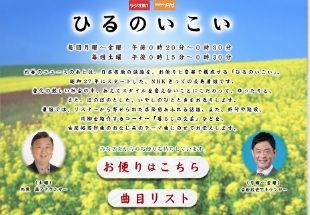PR
X
Free Space
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(0)映画 Cinema
(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube
(268)TVラジオ番組 television & radio programs
(374)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad
(148)外国語学習 Studying Foreign Language
(67)花 Flowers
(328)グルメ Gourmet
(203)介護 Nursery Care
(20)中高年の資格取得Qualification for middle
(15)散歩 Taking a walk
(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life
(121)フィットネスクラブ Fitness Club
(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath
(10)旅行 Travel
(86)読書 Reading
(54)健康 Health
(44)絵画 Picture
(25)Japanese TV Drama with English
(2)季節
(32)災害
(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス
(88)リンク修正、内容追加
(179)政治
(156)宗教
(121)写真
(27)グリーティング
(45)人生
(19)科学
(17)ダイエット
(7)少子・高齢化社会
(11)生き物 creatures
(5)月と星空
(26)不動産
(2)Comments
Freepage List
テーマ: 仏教について思うこと(1037)
カテゴリ: 宗教
以前読んだ、釈徹宗さんと大平光代さんの対談の「この世を仏教で生きる 今から始める他力の暮らし」に紹介されていた、兵庫県小野市にある阿弥陀三尊像の動画を2つ見つけました。
このお寺は、戦乱で荒廃した東大寺再建を担った重源が兵庫の拠点として1197年に建てたものです。独特の建築方法による建物と、仏師快慶による浄土堂の阿弥陀三尊像には特殊な仕掛けがあり、三尊像の裏の戸をすべて開けると、夕暮れ時には、阿弥陀三尊像が背面から光に包まれ、西方浄土から雲に包まれやってくるように見えるそうです。実際NHKの動画を見て美しいと思いました。昔の人はこれを見て信仰心を篤くして、東大寺への寄進を行ったのでしょうか。
釈撤宗さんの解説によれば年に2回、春と秋のお彼岸の中日には夕日が阿弥陀三尊像の真後ろに落ちるように設計されていて、太陽と阿弥陀三尊像の間には無数のため池が昔はあって反射光が綺麗だったそうです。
ちょっと遠いですが、いつか行ってみたいお寺です。神社仏閣、城郭巡りも今後の趣味には良いかと思いました。
大昔でもこのような建築、仏像で人々を感動させられたのなら、科学・建築・映像技術の発達した現代なら、VR等を駆使してもっとすごい仏教建築・仏像等の作品ができてもよさそうに思います。

■参考リンク
この世を仏教で生きる 今から始める他力の暮らし:釈徹宗/大平光代
Wikipedia:浄土寺 (小野市)
歴史
この地から西に約2キロのところに、奈良時代の僧・行基が建立したとされる広渡寺があった。この広渡寺が浄土寺の前身寺院とされる。荒廃していた広渡寺を浄土寺として復興させた実質的な開山は、平安時代末から鎌倉時代の僧で、東大寺大仏・大仏殿の復興に尽力した重源である。治承4年(1180年)、平重衡の軍勢による南都焼討で、東大寺や興福寺は壊滅的な打撃を受け、東大寺の大仏殿も焼け落ちた。この大仏・大仏殿の再興の大勧進(総責任者)となったのが、当時61歳の重源であった。重源は大仏再興事業の拠点として、伊賀国(現・三重県)、周防国(現・山口県)など日本の7か所に東大寺の「別所」を創設した。七別所のうちの「播磨別所」がこの浄土寺である。この地は播磨国大部荘(おおべのしょう)といい、東大寺領であった。
こうして建久5年(1194年)に広渡寺を現在地に移転して寺名を浄土寺へ改めた。建久8年(1197年)に本堂の薬師堂と浄土堂が大仏様で建立された[1][2]。
薬師堂は明応7年(1498年)に焼失するが、永正14年(1517年)に再建されている。
浄土堂
国宝。浄土寺浄土堂(「阿弥陀堂」ともいう)は重源によって建てられたもので、本尊として快慶作の阿弥陀三尊の巨像を安置する。堂は建久5年(1194年)に上棟し、同8年(1197年)に完成し供養を行ったと記録されている。渡宋経験のあった重源は、大仏殿をはじめとする東大寺諸堂の復興や各地の別所寺院の建築に際し、当時の宋の最新式の建築様式を採用した。これが現代において大仏様(かつては天竺様とも呼んだ)と呼ばれる建築様式で、鎌倉時代以後の寺院建築に大きな影響を与えたが、重源が手がけた大仏様建築で現存するものは他に東大寺南大門と同寺開山堂のみである。
堂は方三間(正面・側面とも1辺に柱が4本立ち、柱間が3つあるという意味)の単純な平面構成になるが、1つの柱間が約6メートルもあり、内部空間は広大である。屋根は宝形造(ほうぎょうづくり、四角錐状の屋根形)、本瓦葺きで平面の大きさの割に立ちが低いことと、屋根の形づくる線にほとんど反りがなく直線的であることが特色である。比較的地味な外観に比し、堂内部は貫(ぬき)、梁(はり)などの構造材をそのまま見せたダイナミックな構成になっている。天井を張らず、屋根裏に空間をつくらず、構造材をそのまま見せて装飾を兼ねる化粧屋根裏となっていること、貫(複数の柱を貫通する水平材)を多用することなどが大仏様建築の特色である。
阿弥陀三尊像
国宝。浄土堂中央の須弥壇に安置される。仏師快慶の代表作。巨大な三尊像で、阿弥陀如来は像高5m30cm(須弥壇を含めると7m50cm)、両脇侍、右・観音菩薩と左・勢至菩薩の像高は各々3m70cmある。快慶は重源とは近い関係にあり、熱烈な阿弥陀仏信者だったことが知られている。快慶の作品には像高3尺(約1メートル)の阿弥陀像が多いが、本作は珍しい大作である。3体とも立像であり、各像の立つ蓮華座の下には雲が表されていて僅かに阿弥陀三尊が前に傾いていることから西方極楽浄土から飛雲に乗って来迎する情景を表現したものである。また中央の阿弥陀如来像の特徴として、人々に差し伸べられているのは右手、ほかの阿弥陀仏が左手なのとは逆の造りで、爪は長く伸びている。当時流行の宋風が顕著である。
浄土寺の阿弥陀三尊の脇侍は左右逆配置である、この配置は密教寺院に存在する形式で「阿唎多羅陀羅尼阿嚕力経」や「観自在最勝心明経第九品」などの「密教系経典には右観自在・左大勢至とす」云々の記述があり、それを取り入れたものか。
浄土堂は境内の西、すなわち極楽浄土の位置する側に建てられ、阿弥陀三尊は東向きに立つ。堂の背後の蔀戸(しとみど、建物の内側または外側へ跳ね上げる形式の戸)を開け放つと背後からの西光が入り、晴れた日の夕刻には堂内全体が朱赤に深く輝くように染まり、雲座の上に位置する三尊像が浮かびあがって来迎の風景を現す劇的な光の演出効果を備えている[3]。その際、遠方の溜池群が西方の光を運び込む装置として機能することを、作者重源は巧みに計算していたようである。
安藤忠雄に影響
安藤忠雄による設計で1991年(平成3年)に竣工した兵庫県淡路市にある真言密教の寺院で真言宗御室派の別格本山である本福寺本堂の水御堂は、西から入る光が極楽浄土を現出させるこの浄土寺での重源の手法を踏襲したものである[3]。
このお寺は、戦乱で荒廃した東大寺再建を担った重源が兵庫の拠点として1197年に建てたものです。独特の建築方法による建物と、仏師快慶による浄土堂の阿弥陀三尊像には特殊な仕掛けがあり、三尊像の裏の戸をすべて開けると、夕暮れ時には、阿弥陀三尊像が背面から光に包まれ、西方浄土から雲に包まれやってくるように見えるそうです。実際NHKの動画を見て美しいと思いました。昔の人はこれを見て信仰心を篤くして、東大寺への寄進を行ったのでしょうか。
釈撤宗さんの解説によれば年に2回、春と秋のお彼岸の中日には夕日が阿弥陀三尊像の真後ろに落ちるように設計されていて、太陽と阿弥陀三尊像の間には無数のため池が昔はあって反射光が綺麗だったそうです。
ちょっと遠いですが、いつか行ってみたいお寺です。神社仏閣、城郭巡りも今後の趣味には良いかと思いました。
大昔でもこのような建築、仏像で人々を感動させられたのなら、科学・建築・映像技術の発達した現代なら、VR等を駆使してもっとすごい仏教建築・仏像等の作品ができてもよさそうに思います。

■参考リンク
この世を仏教で生きる 今から始める他力の暮らし:釈徹宗/大平光代
Wikipedia:浄土寺 (小野市)
歴史
この地から西に約2キロのところに、奈良時代の僧・行基が建立したとされる広渡寺があった。この広渡寺が浄土寺の前身寺院とされる。荒廃していた広渡寺を浄土寺として復興させた実質的な開山は、平安時代末から鎌倉時代の僧で、東大寺大仏・大仏殿の復興に尽力した重源である。治承4年(1180年)、平重衡の軍勢による南都焼討で、東大寺や興福寺は壊滅的な打撃を受け、東大寺の大仏殿も焼け落ちた。この大仏・大仏殿の再興の大勧進(総責任者)となったのが、当時61歳の重源であった。重源は大仏再興事業の拠点として、伊賀国(現・三重県)、周防国(現・山口県)など日本の7か所に東大寺の「別所」を創設した。七別所のうちの「播磨別所」がこの浄土寺である。この地は播磨国大部荘(おおべのしょう)といい、東大寺領であった。
こうして建久5年(1194年)に広渡寺を現在地に移転して寺名を浄土寺へ改めた。建久8年(1197年)に本堂の薬師堂と浄土堂が大仏様で建立された[1][2]。
薬師堂は明応7年(1498年)に焼失するが、永正14年(1517年)に再建されている。
浄土堂
国宝。浄土寺浄土堂(「阿弥陀堂」ともいう)は重源によって建てられたもので、本尊として快慶作の阿弥陀三尊の巨像を安置する。堂は建久5年(1194年)に上棟し、同8年(1197年)に完成し供養を行ったと記録されている。渡宋経験のあった重源は、大仏殿をはじめとする東大寺諸堂の復興や各地の別所寺院の建築に際し、当時の宋の最新式の建築様式を採用した。これが現代において大仏様(かつては天竺様とも呼んだ)と呼ばれる建築様式で、鎌倉時代以後の寺院建築に大きな影響を与えたが、重源が手がけた大仏様建築で現存するものは他に東大寺南大門と同寺開山堂のみである。
堂は方三間(正面・側面とも1辺に柱が4本立ち、柱間が3つあるという意味)の単純な平面構成になるが、1つの柱間が約6メートルもあり、内部空間は広大である。屋根は宝形造(ほうぎょうづくり、四角錐状の屋根形)、本瓦葺きで平面の大きさの割に立ちが低いことと、屋根の形づくる線にほとんど反りがなく直線的であることが特色である。比較的地味な外観に比し、堂内部は貫(ぬき)、梁(はり)などの構造材をそのまま見せたダイナミックな構成になっている。天井を張らず、屋根裏に空間をつくらず、構造材をそのまま見せて装飾を兼ねる化粧屋根裏となっていること、貫(複数の柱を貫通する水平材)を多用することなどが大仏様建築の特色である。
阿弥陀三尊像
国宝。浄土堂中央の須弥壇に安置される。仏師快慶の代表作。巨大な三尊像で、阿弥陀如来は像高5m30cm(須弥壇を含めると7m50cm)、両脇侍、右・観音菩薩と左・勢至菩薩の像高は各々3m70cmある。快慶は重源とは近い関係にあり、熱烈な阿弥陀仏信者だったことが知られている。快慶の作品には像高3尺(約1メートル)の阿弥陀像が多いが、本作は珍しい大作である。3体とも立像であり、各像の立つ蓮華座の下には雲が表されていて僅かに阿弥陀三尊が前に傾いていることから西方極楽浄土から飛雲に乗って来迎する情景を表現したものである。また中央の阿弥陀如来像の特徴として、人々に差し伸べられているのは右手、ほかの阿弥陀仏が左手なのとは逆の造りで、爪は長く伸びている。当時流行の宋風が顕著である。
浄土寺の阿弥陀三尊の脇侍は左右逆配置である、この配置は密教寺院に存在する形式で「阿唎多羅陀羅尼阿嚕力経」や「観自在最勝心明経第九品」などの「密教系経典には右観自在・左大勢至とす」云々の記述があり、それを取り入れたものか。
浄土堂は境内の西、すなわち極楽浄土の位置する側に建てられ、阿弥陀三尊は東向きに立つ。堂の背後の蔀戸(しとみど、建物の内側または外側へ跳ね上げる形式の戸)を開け放つと背後からの西光が入り、晴れた日の夕刻には堂内全体が朱赤に深く輝くように染まり、雲座の上に位置する三尊像が浮かびあがって来迎の風景を現す劇的な光の演出効果を備えている[3]。その際、遠方の溜池群が西方の光を運び込む装置として機能することを、作者重源は巧みに計算していたようである。
安藤忠雄に影響
安藤忠雄による設計で1991年(平成3年)に竣工した兵庫県淡路市にある真言密教の寺院で真言宗御室派の別格本山である本福寺本堂の水御堂は、西から入る光が極楽浄土を現出させるこの浄土寺での重源の手法を踏襲したものである[3]。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022.06.05 18:41:11
[宗教] カテゴリの最新記事
-
2024.6西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.06.01
-
2024.5清正公寺の掲示板:人身は持ちがた… 2024.05.01
-
2024.4 西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.04.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.