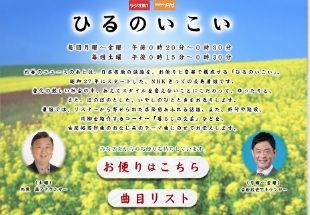PR
X
Free Space
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(0)映画 Cinema
(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube
(268)TVラジオ番組 television & radio programs
(374)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad
(148)外国語学習 Studying Foreign Language
(67)花 Flowers
(328)グルメ Gourmet
(203)介護 Nursery Care
(20)中高年の資格取得Qualification for middle
(15)散歩 Taking a walk
(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life
(121)フィットネスクラブ Fitness Club
(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath
(10)旅行 Travel
(87)読書 Reading
(54)健康 Health
(44)絵画 Picture
(25)Japanese TV Drama with English
(2)季節
(32)災害
(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス
(88)リンク修正、内容追加
(179)政治
(156)宗教
(121)写真
(27)グリーティング
(45)人生
(19)科学
(17)ダイエット
(7)少子・高齢化社会
(11)生き物 creatures
(5)月と星空
(26)不動産
(2)Comments
Freepage List
テーマ: 仏教について思うこと(1037)
カテゴリ: 宗教
福井旅行の2日目、雨の中を永平寺まで行きました。あいにくお寺の中には入れず、境内を散歩中に見つけたのがこの葉っぱの舟に乗った一葉観音です。
てっきり仏様が舟に乗って川遊びしていると思ってました。調べると、曹洞宗の開祖道元禅師が中国に勉強されて舟での帰途、嵐に遭い、観音経を唱えたところ、蓮華の花びらに乗った観音菩薩が現れ、風雨が静まり助かったとのことです。
見ていると穏やかな表情で、心が癒されます。人生の嵐に遭った時、この写真を見れば元気が出そうです。撮影時、気づかなかったカエルも愛嬌があっていいです。
キリスト教でも、同様な話があります。イエスは嵐を𠮟りつけて鎮めましたが、一葉観音のほうが、平和的で好きです。
観音様について調べました。インドで誕生した当初は男性の仏様だったそうですが、中国に渡った際、男尊女卑の儒教倫理に悩む人たちがすがるものとして、女性の観音菩薩が誕生したという話は面白かったです。女性の仏教界進出第1号かもしれません 。
。



■参考リンク
ぶらり加賀たびさん:永平寺
巨大かえるが永平寺に出現!|福井カエルスポット2021年2月2日:福井かえる道さん
マタイによる福音書8章18-34節 「嵐を静める主イエス」:心に響く聖書の言葉
2.嵐を静められる (参照マルコ4 :35-41)
8:23 それからイエスが舟に乗られると、弟子たちも従った。
8:25 弟子たちは近寄ってイエスを起こして、「主よ、助けてください。私たちは死んでしまいます」と言った。
8:26 イエスは言われた。「どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。」それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。すると、すっかり凪になった。
8:27 人々は驚いて言った。「風や湖までが言うことを聞くとは、いったいこの方はどういう方なのだろうか。」
Wikipedia:観音菩薩
観音菩薩(かんのん ぼさつ、梵: Avalokiteśvara)は、仏教の菩薩の一尊。観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)、観自在菩薩(かんじざいぼさつ)、救世菩薩(くせぼさつ・ぐせぼさつ)など多数の別名がある。一般的に「観音さま」とも呼ばれる。
名称の由来
観音菩薩という呼び名は、一般的には観世音菩薩の略号と解釈されている。[9]
日本語の「カンノン」は「観音」の呉音読みであり、連声によって「オン」が「ノン」になったものである。
性別
古代より広く信仰を集め、日本では各地に建立されることが多い観音像
観音菩薩は男性と女性の両方の姿を取ることから、欧米の研究者のあいだではジェンダー・フリーの体現者であると解釈され、評価されている[10]。しかしながら、本来は男性であったと考えられる。
例えば、松原哲明は、梵名のアヴァローキテーシュヴァラが男性名詞であること、華厳経に「勇猛なる男子(丈夫)、観世音菩薩」と書かれていることから、本来男性であったと述べている[6]。植木雅俊も、
『法華経』のサンスクリット原典(ケルン・南条本)の第31偈には、観音が導師となる阿弥陀仏の浄土に女性は誰も生まれてこない、と書いてある。なお、この部分は鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』にはない。
『法華経』のサンスクリット原典では、観音は16の姿を現すとされ、その全てが男性である。
『法華経』の初期の漢訳である 竺法護訳『正法華経』(286年)では、観音は17の姿を現すとされ、その全てが男性である。
鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』観音偈
ところが鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』(406年。現在、最も普及している法華経)では観音は「三十三身」を現すとされ、そのうち7つが女性の姿である。
たしかに、中国では「慈母観音」などという言葉から示されるように、俗に女性と見る向きが多い。また、例えば地蔵菩薩を観音と同じ大悲闡提の一対として見る場合が多く、地蔵が男性の僧侶形の像容であるのに対し、観音は女性的な顔立ちの像容も多いことからそのように見る場合が多い[12]。観音経では「婦女身得度者、即現婦女身而為説法」と、女性に対しては女性に変身して説法することもあるため、次第に性別は無いものとして捉えられるようになった。また後代に至ると観音を女性と見る傾向が多くなった。これは中国における観音信仰の一大聖地である普陀落山(浙江省・舟山群島)から東シナ海域や黄海にまで広まったことで、その航海安全を祈念する民俗信仰や道教の媽祖信仰などの女神と結び付いたためと考えられている[要出典]。
また、妙荘王の末女である妙善という女性が尼僧として出家、成道し、観音菩薩となったという説話が十二世紀頃に中国全土に流布し、『香山宝巻』の成立によって王女妙善説話が定着、美しい女性としての観音菩薩のイメージが定着したとする説もある[13]。
Wikipedia:道元
道元(どうげん、正治2年1月2日(1200年1月19日) - 建長5年8月28日(1253年9月22日))は、鎌倉時代初期の禅僧[3]。日本における曹洞宗の開祖[3]。晩年には、希玄という異称も用いた。宗門では高祖承陽大師と尊称される。諡号は仏性伝東国師、承陽大師。諱は希玄[3]。道元禅師とも呼ばれる。
教義・思想
ひたすら坐禅するところに悟りが顕現しているとする立場が、その思想の中核であるとされる[3]。道元のこの立場は修証一等や本証妙証と呼ばれ、そのような思想は75巻本の「正法眼蔵」に見えるものであるとされるが、晩年の12巻本「正法眼蔵」においては因果の重視や出家主義の強調がなされるようになった[3]。
一葉観音像:長田晴山 作
てっきり仏様が舟に乗って川遊びしていると思ってました。調べると、曹洞宗の開祖道元禅師が中国に勉強されて舟での帰途、嵐に遭い、観音経を唱えたところ、蓮華の花びらに乗った観音菩薩が現れ、風雨が静まり助かったとのことです。
見ていると穏やかな表情で、心が癒されます。人生の嵐に遭った時、この写真を見れば元気が出そうです。撮影時、気づかなかったカエルも愛嬌があっていいです。
キリスト教でも、同様な話があります。イエスは嵐を𠮟りつけて鎮めましたが、一葉観音のほうが、平和的で好きです。
観音様について調べました。インドで誕生した当初は男性の仏様だったそうですが、中国に渡った際、男尊女卑の儒教倫理に悩む人たちがすがるものとして、女性の観音菩薩が誕生したという話は面白かったです。女性の仏教界進出第1号かもしれません



■参考リンク
ぶらり加賀たびさん:永平寺
巨大かえるが永平寺に出現!|福井カエルスポット2021年2月2日:福井かえる道さん
マタイによる福音書8章18-34節 「嵐を静める主イエス」:心に響く聖書の言葉
2.嵐を静められる (参照マルコ4 :35-41)
8:23 それからイエスが舟に乗られると、弟子たちも従った。
8:25 弟子たちは近寄ってイエスを起こして、「主よ、助けてください。私たちは死んでしまいます」と言った。
8:26 イエスは言われた。「どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。」それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。すると、すっかり凪になった。
8:27 人々は驚いて言った。「風や湖までが言うことを聞くとは、いったいこの方はどういう方なのだろうか。」
Wikipedia:観音菩薩
観音菩薩(かんのん ぼさつ、梵: Avalokiteśvara)は、仏教の菩薩の一尊。観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)、観自在菩薩(かんじざいぼさつ)、救世菩薩(くせぼさつ・ぐせぼさつ)など多数の別名がある。一般的に「観音さま」とも呼ばれる。
名称の由来
観音菩薩という呼び名は、一般的には観世音菩薩の略号と解釈されている。[9]
日本語の「カンノン」は「観音」の呉音読みであり、連声によって「オン」が「ノン」になったものである。
性別
古代より広く信仰を集め、日本では各地に建立されることが多い観音像
観音菩薩は男性と女性の両方の姿を取ることから、欧米の研究者のあいだではジェンダー・フリーの体現者であると解釈され、評価されている[10]。しかしながら、本来は男性であったと考えられる。
例えば、松原哲明は、梵名のアヴァローキテーシュヴァラが男性名詞であること、華厳経に「勇猛なる男子(丈夫)、観世音菩薩」と書かれていることから、本来男性であったと述べている[6]。植木雅俊も、
『法華経』のサンスクリット原典(ケルン・南条本)の第31偈には、観音が導師となる阿弥陀仏の浄土に女性は誰も生まれてこない、と書いてある。なお、この部分は鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』にはない。
『法華経』のサンスクリット原典では、観音は16の姿を現すとされ、その全てが男性である。
『法華経』の初期の漢訳である 竺法護訳『正法華経』(286年)では、観音は17の姿を現すとされ、その全てが男性である。
鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』観音偈
ところが鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』(406年。現在、最も普及している法華経)では観音は「三十三身」を現すとされ、そのうち7つが女性の姿である。
たしかに、中国では「慈母観音」などという言葉から示されるように、俗に女性と見る向きが多い。また、例えば地蔵菩薩を観音と同じ大悲闡提の一対として見る場合が多く、地蔵が男性の僧侶形の像容であるのに対し、観音は女性的な顔立ちの像容も多いことからそのように見る場合が多い[12]。観音経では「婦女身得度者、即現婦女身而為説法」と、女性に対しては女性に変身して説法することもあるため、次第に性別は無いものとして捉えられるようになった。また後代に至ると観音を女性と見る傾向が多くなった。これは中国における観音信仰の一大聖地である普陀落山(浙江省・舟山群島)から東シナ海域や黄海にまで広まったことで、その航海安全を祈念する民俗信仰や道教の媽祖信仰などの女神と結び付いたためと考えられている[要出典]。
また、妙荘王の末女である妙善という女性が尼僧として出家、成道し、観音菩薩となったという説話が十二世紀頃に中国全土に流布し、『香山宝巻』の成立によって王女妙善説話が定着、美しい女性としての観音菩薩のイメージが定着したとする説もある[13]。
Wikipedia:道元
道元(どうげん、正治2年1月2日(1200年1月19日) - 建長5年8月28日(1253年9月22日))は、鎌倉時代初期の禅僧[3]。日本における曹洞宗の開祖[3]。晩年には、希玄という異称も用いた。宗門では高祖承陽大師と尊称される。諡号は仏性伝東国師、承陽大師。諱は希玄[3]。道元禅師とも呼ばれる。
教義・思想
ひたすら坐禅するところに悟りが顕現しているとする立場が、その思想の中核であるとされる[3]。道元のこの立場は修証一等や本証妙証と呼ばれ、そのような思想は75巻本の「正法眼蔵」に見えるものであるとされるが、晩年の12巻本「正法眼蔵」においては因果の重視や出家主義の強調がなされるようになった[3]。
一葉観音像:長田晴山 作
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022.10.05 07:38:21
[宗教] カテゴリの最新記事
-
2024.6西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.06.01
-
2024.5清正公寺の掲示板:人身は持ちがた… 2024.05.01
-
2024.4 西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.04.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.