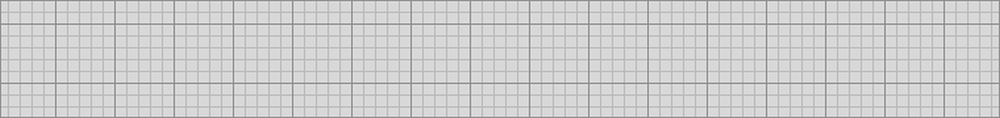2024年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 13完〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 13完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。典侍(すけ)という女性が源氏に心を寄せようとする一方で、源氏は典侍を煩わしく感じていた。このように、源氏は時折、女性との関係を重荷に感じることがあり、彼の人間性の一端が垣間見えた。頭中将は、源氏とのやり取りを楽しみながらも、彼をからかうことに喜びを見出していた。源氏と頭中将の関係は単なる競争だけでなく、互いの弱さや恥ずかしい部分を共有しつつも、それを軽く受け流すことができる親密さが描かれている。特に、この一節では、二人が公の場で真面目な顔をしつつも、目が合った瞬間に笑ってしまう人間味あふれる場面が強調されている。この章では政治的背景も描かれ、源氏や頭中将のような貴族たちが、単なる恋愛や友情の問題を超えて、帝位の継承や宮廷の権力闘争に巻き込まれている様子がうかがえる。藤壺の宮が中宮に擬されることや、帝の寵愛を受ける源氏の立場など、物語は単なる個人の感情の問題だけでなく、政治的な力関係が複雑に絡み合っている。この一節は、源氏と頭中将の微妙な友情、競争心、そしてそれに伴う軽いユーモアや感情の揺れ動きを巧みに描き出している。それと同時に、宮廷の権力構造や政治的背景も織り交ぜられ、物語に奥行きと緊張感を与えている。紅葉賀では、光源氏が20歳の時、藤壺中宮に対する彼の秘めた恋心が物語の中心となり、宮廷での様々な出来事が描かれる。秋に宮中で催される紅葉を愛でる宴が舞台で、この場で源氏は優れた舞を披露し、その美しさと才気が称賛され、彼の存在感が一層際立つ。この時、源氏の舞を見た藤壺中宮は彼の美しさに胸を打たれ、源氏への想いをさらに深めるが、それを表に出すことができず、帝は源氏の才能を高く評価し、源氏の未来に大きな期待を寄せている。また、この巻では源氏と頭中将の友情が描かれ、彼らの親密な関係が強調されている。頭中将は源氏に対して深い信頼を寄せ、共に権力の世界を生き抜いていくことを誓う。宮廷の雅やかな日常が描かれる一方で、登場人物たちの秘められた感情や人間関係の葛藤が巧みに表現され、物語の核心に迫る重要な巻となっている。明日より「8帖 花宴(はなのえん)」の研鑽を公開して行きます。
2024.09.30
コメント(23)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 12〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 12〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。夏の夜、源氏は夕立の後の涼しさに誘われて温明殿を歩いていると、琵琶を弾く典侍(すけ)の姿に出くわした。典侍の琵琶の演奏は、恋に悩む彼女の内面を反映しており、その音色は源氏の心を動かすが、典侍が琵琶に合わせて唄った「瓜作りになりやしなまし」という歌には少しの反感を抱いた。白楽天がかつて耳にした鄂州(がくしゅう/湖北省)の女の琵琶を連想し、源氏は典侍の演奏に心惹かれながらも複雑な感情を抱いた。源氏は典侍の歌に応じて「催馬楽の東屋」を歌うが、彼女の歌声に込められた切ない感情に心を打たれた。典侍は源氏との再会に深い期待を寄せながらも、その願いが叶わないことに歎息する。物語の後半では、頭中将が再び登場し、源氏と典侍の密会を覗き見する。源氏は典侍の元を去ろうとするが、源氏の動きを察した頭中将が現れ、源氏は戸惑う。頭中将は典侍との関係を隠そうとする源氏の行動を見て楽しんだが、典侍は年老いた自分の姿に恥じ入りながらも、なおも源氏を思う気持ちを捨てきれなかった。最終的に、源氏はこの関係が公になることを恐れつつも、頭中将が気づいていない振りをし続ける様子が描かれている。典侍との関係は秘密裏に進行し、源氏と頭中将、典侍の三者の間で微妙な駆け引きが繰り広げられている。この一節は、源氏の複雑な恋愛遍歴を通して、彼の感情の揺れ動きや周囲の人々との微妙な人間関係が描かれている。源氏と頭中将の関係の微妙なバランスを描いており、物語全体を通じて、源氏と頭中将はしばしば競争し、互いにライバル意識を抱きつつも、深い友情を持っていた。この一節では、源氏と頭中将の二人がいたずらをし合い、ほほえましいやり取りを繰り広げるシーンが展開され、夜、二人はふざけ合いながら互いに衣装を引っ張り合い、縫い目がほころびてしまう。頭中将はそれを詩的に表現し、源氏もそれに対して負けじと和歌を詠み返すという知的な応酬が行われた。この詩のやり取りは、単なる遊びではなく、互いの関係性を象徴するような深い意味を含んでいる。源氏と頭中将は、自分たちの立場や身分を自覚しつつも、親密でありながらも、軽い緊張感を伴う関係を維持している。その後、源氏はその晩の出来事を思い返し、複雑な感情を抱き、典侍(ないしのすけ)という女性とのやり取りも、彼にとっては面倒に感じられる部分があった。
2024.09.29
コメント(23)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 11〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 11〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。典侍が扇で顔を隠しながら見返る場面では、典侍の老いが感じられる描写が描かれており、源氏がその扇を見て「森の下草老いぬれば駒もすさめず刈る人もなし/大荒木の森の根本に生えてる草も成長しすぎ古くなり、馬も食べないし、刈る人もいない」という歌が書かれているのに気づく。この歌は、老いてしまった草が誰にも刈り取られず、馬も喜んで食べなという内容で、典侍自身の老いを象徴的に表現している。この一節を通じて、源氏物語の「紅葉賀」の巻では、源氏の複雑な感情や人間関係、そして彼を取り巻く宮廷社会の力学が詳細に描かれている。特に、源氏が紫の上に対して抱く深い愛情や、典侍との不釣り合いな関係が、源氏の内面的な葛藤や時代の価値観と絡み合い、物語全体に深い人間模様を生み出している。源氏が典侍(すけ)と関わりを持ち、また、頭中将がその様子を覗き見るという場面を描いている。この部分の物語は、典侍の恋愛における情熱や、源氏との関係を通じて、当時の貴族社会における複雑な恋愛模様や人間関係の微妙な駆け引きが描かれている。源氏は典侍が不相応な恋歌を口にするのを聞きながら、苦笑しつつもその場にとどまる。典侍は源氏に対して感情を露わにし、恋愛に悩み苦しむ様子を見せるが、源氏はその気持ちに完全には応えず、どこか冷めた態度をとっていた。典侍は、私はこんなにまで煩悶をしたことはありませんと涙ながらに語り、彼女の恋情の深さが強調されるが、源氏は、いつもそう思いながら実行ができないと、彼女の望む形での愛の約束を果たせない自分を暗に弁解する。その後、典侍が源氏を引き留めようとする場面に、帝が現れて彼らのやり取りを目にします。この場面は、帝が恋愛に対して冷笑的な見解を持ちながらも、二人の不似合いな関係を面白がる様子が描かれており、典侍はこの時、自分の立場や行動に対して少しの恥を感じながらも、恋しい人のために濡れ衣であっても受け入れようとする姿勢を見せている。この後、源氏と典侍の関係は御所内でも噂となり、頭中将の耳に入ることとなる。彼は源氏が持つ秘密の恋愛関係に強い興味を持ち、やがて典侍との関係を知るに至った。頭中将は源氏の恋愛に介入し、彼女と関係を持つことになりますが、典侍にとって本当に大切な存在はあくまで源氏であることが明示された。典侍の心の中での源氏への一途な思いと、彼女の多情さが対比されて描かれている。
2024.09.28
コメント(26)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 10〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 10〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。源氏の行動を見ていた侍たちの中には、左大臣家に伝える者もおり、左大臣家の人々が源氏の行動について噂し始める。彼らは、二条の院へどこのお嬢さんが嫁いだという話もないことだし」という点を問題視しており、源氏が何か秘密の関係を持っているのではないかという疑念が浮かんだ。特に、彼らは源氏が、女房級の人を二条の院へ連れて来たことを、批難させまいと思っているのではないかと考え、源氏の行動を批判的に見ており、この噂は御所にまで届き、左大臣も心配し始めた。この状況に対して、帝(天皇)もまた源氏に対して、小さいおまえを婿にしてくれて、十二分に尽くした今日までの好意が分からない年でもないのに、なぜその娘を冷淡に扱うのだと諭す場面が描かれている。帝は、源氏が左大臣の娘に対して冷淡であることを問題視し、源氏に対して責めるような口調で話すが、源氏はこれに対して明確な返答をしなかった。このような源氏の態度は、彼が感情や行動を表に出さず、内に秘めている性格を反映している。また、帝は、なぜそんな隠し事をして舅や妻に恨まれる結果を作るのかと心配し、源氏に対して忠告をする。帝自身も美女が好きで、多くの女官や女御たちが宮廷に仕えてたが、源氏はそうした美女たちに対して特に興味を示さず、冷淡な態度を取っていた。これに対して、女官たちの中には源氏の冷淡さに不満を抱く者もおり、彼の行動に物足りなさを感じる者もいた。その中で、特に注目されるのが、年を重ねた典侍(すけ)との話である。この典侍は、世間からは高い評価を受けている才女でありながら、多情な性格であり、その点で周囲の顰蹙を買っていた。源氏は、彼女が「なぜこう年がいっても浮気がやめられないのだろう」と不思議に思いながらも、ふとした衝動で彼女との関係を持ってしまう。この関係は源氏にとっても不釣り合いであり、恥ずかしいものだったが、典侍はこの関係が冷淡に扱われることを常に恨んでいた。源氏と典侍の関係が進むにつれて、典侍が帝のお召し替えを奉仕している場面で、源氏は彼女の美しさに目を引かれる。典侍がいつまでも若作りをしていることに対して、源氏は少し不思議に感じながらも、その様子に興味を持ち、彼女の裳の裾を引いてみるという行動に出た。
2024.09.27
コメント(23)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 9〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。「紅葉賀」の一節は、源氏の禁断の恋や秘められた愛情、更にはそれが引き起こす苦悩や葛藤が描かれている。源氏物語の中でもこの紅葉賀では、感情の交錯が強調され書かれている。「よそへつつ見るに心も慰まで露けさまさる撫子の花/遠くから見つめるだけでは、心が慰められることはなく、露に濡れている撫子の花がますますしおれているように見える」花に対する比喩的な愛情を示しており、ここでは、撫子(なでしこ)の花を子供のように慈しみ、守ろうとする気持ちが描かれている。しかし、実際にはその愛情を十分に表現し、守ることが難しいという現実的な気づきを意味していいる。撫子の花は、可憐で儚い存在として象徴され、源氏の心中にある切ない感情を暗示しており、撫子の花は、繊細で儚い美しさを持つ花で、平安時代の和歌では女性や恋愛に関連して詠まれることが多い。「よそへつつ見るに心も慰まで露けさまさる撫子の花」この歌は、藤壺が抱く切ない思い、特に源氏との距離や隔たりからくる悲しみや涙を表現している。続いて、命婦(召使)が宮に返事を求める場面において、宮(葵の上)は深い悲しみに沈んでおり、葵の上が源氏に向けたわずかな返答が得られる。ここで詠まれた歌「袖濡るる露のゆかりと思ふにもなほうとまれぬやまと撫子」は、撫子の花に象徴されるように、愛する人への切ない想いが込められている。袖が露に濡れるほど涙に沈む様子は、源氏の心情と共鳴し、その切なさが深まっていく。源氏は、返事が来ることを予想していなかったため、源氏が宮からの返事を受け取り、感激して涙を流し、その突然の贈り物に胸を打たれるが、この感情の揺れは、源氏の内面の脆さや、愛情に対する強い執着を表している。源氏は、少し乱れた髪や部屋着姿の紫の上を見て、愛おしさを募らせ、紫の上が源氏に、すねている様子や、源氏が紫の上を慰めるために歌を口ずさむ場面から、二人の親密な関係と、幼さゆえの純粋な愛情が感じられ、さらに、源氏が琴を紫の上に弾かせようとする所では、若紫の成長や才能が描かれ、源氏は、若紫が一度で難しい調子を覚えるほど賢く成長していることに満足し、誇りに思っている。最後に、源氏が出かける予定を取りやめ、紫の君と一緒に過ごす決断をする場面では、彼女を安心させたいという彼の優しさが強調されています。源氏は、紫の君が自分の外出に対して寂しさを感じていることに気づき、彼女を慰めようとします。このやりとりは、彼らの関係が単なる愛情以上のもの、すなわち深い信頼と依存の絆で結ばれていることを示唆している。
2024.09.26
コメント(24)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 8〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。王命婦は、源氏が、昔結べる契りを嘆く言葉に応じて、世の人の惑う闇を例えに出し、二人の間にある困難は同じく辛いものだと慰める。命婦は源氏の悲しみに共感しながらも、源氏の立場に同情しつつ、藤壺に対しても微妙な距離感を保とうとしていた。命婦は、藤壺が源氏との関係に苦しむことを知りながら、その中でどのように行動するべきか悩んでいた。一方で、藤壺は自分の感情を抑え、表には出さないが、源氏に対する思いは複雑で、王命婦に対しても冷たく接するようになっていた。これは、藤壺が自らの不倫の事実を隠し通すために、周囲に対して感情を抑えなければならないという強い圧力を感じていた。藤壺は、源氏に対する愛情と、それを社会的に許されないという現実の狭間で揺れ動いていた。藤壺との間に生まれた若宮(皇子)の存在で、若宮は帝と藤壺の子供として育てられているが、その実父は光源氏である。若宮の成長につれて、彼の容貌がますます源氏に似てきたことが、藤壺にとって大きな不安となっていた。藤壺は、若宮の顔立ちが源氏に似ていることに気づき、世間からの批判や噂を恐れていた。若宮が成長して宮中に入ると、帝(天皇)は若宮を非常に愛し、特別な存在として扱い、帝は若宮を「瑕なき玉(完璧で欠点のない人)」と称し、若宮の美貌を賞賛していた。しかし、藤壺にとっては、帝が若宮を愛すること自体が苦痛であり、源氏との関係が明るみに出るのではないかという恐れがますます強まっていた。若宮の存在は、藤壺と源氏の秘密を象徴するものだった。帝が若宮を抱きしめ、おまえだけをこんなに小さい時から毎日見てきたと語り、帝は若宮に対する深い愛情を示していたが、この愛情は源氏にとって非常に複雑なものであり、心を乱していた。源氏は、若宮が自分の子であることを知っているため、帝の愛情に対して嫉妬や罪悪感、そして父としての誇りが交錯していた。源氏は、若宮が自分に似ていることを嬉しく感じる一方で、帝の前でその感情を隠さなければならないという苦しみに苛まれた。彼の内面には、若宮に対する父性愛と、自分の立場に対する恐れが同時に存在しており、その感情の入り交じった状態が彼を苦しめていた。若宮の姿を見るたびに、源氏は自分の秘密が露見するのではないかという不安を抱きつつも、若宮への愛情を抑えきれない状況に置かれていた。
2024.09.25
コメント(27)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 7〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。源氏は、藤壺が無事に出産できるかどうかに強い関心を寄せていた。この状況で、藤壺が命を落とす可能性があるのではと怯え、源氏の心は暗く沈んでいたが、二月になって無事に皇子が誕生したことで、帝や三条の宮の人々は安堵し、喜びを分かち合うことができた。一方で、藤壺自身は自分の立場を苦しく感じ、自分が世間に知られれば、源氏との秘密が露見し、非難を受けるだろうと恐れていた。特に、誕生した若宮(皇子)が源氏に生き写しであるため、誰が見ても源氏の子であることは明らかであり、藤壺はそのことに苦しみを感じていた。藤壺は、この子を見れば、誰もが自分の過失を察するだろうと考え、その結果、自らが不幸な運命を背負うことになると感じていた。このような状況で、藤壺は涙を流し、自らの過ちに対する後悔と苦悩を強く感じていた。源氏は、この状況を何とかしたいと思い、少しでも藤壺に会う機会を求めようとしたが、その試みは成功しなかった。藤壺は、新皇子を他人に見せることを拒み、特に源氏には見せたくないという気持ちが強くはたらいた。これは、皇子が源氏に似すぎているため、世間にその秘密が露見してしまうことを恐れていた。藤壺は、この状況において自分がどれだけ不幸な立場に置かれているかを痛感し、源氏との密かな関係に対してますます苦悩を深めていった。源氏と藤壺の宮との関係が深く描かれ、特に源氏の苦悩や心の葛藤が強調されている。紅葉賀の冒頭では、源氏が藤壺に対する秘められた思いと、皇子の父としての感情が入り交じり、紅葉賀の緊張感を高めている。この紅葉賀の冒頭で中心となるのは、源氏と藤壺の宮が直接会話できないという苦しい状況で、源氏は、藤壺との間に交わされた昔の契りを想い、現在の心から打ち解けない隔てに深く嘆いていた。源氏は、いつまた藤壺と直接、話ができるのだろうと涙ながらに語り、藤壺に対する愛情と、その愛情が叶わない苦しみを話した。源氏の内面の孤独感と未練、更には源氏が抱える禁断の恋の苦悩を象徴的に描いている。この苦悩を目の当たりにしているのが、藤壺に仕える王命婦で、王命婦は、源氏と藤壺の関係を理解し、かつて仲介者としての役割を果たしていた。しかし、今や二人の関係が表に出ることを恐れ、藤壺は命婦に対しても距離を置き始めていた。このことにより、命婦は源氏と藤壺の関係に関して責任を感じつつも、その役割を果たせない無力感に苛まれている。
2024.09.24
コメント(26)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 6〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。紫の上は源氏に対し冷たく接していたが、しかし、夫人も源氏の魅力に抗えず、余儀なく返答している。夫人は源氏より四歳年上で、そのことを自分でも気まずく思っていたが、まだ美しく、源氏もそれを認めている。源氏は、自分の多情さが夫人に怨みを負わせる原因だと自覚し、夫人が高貴な家柄であることや、自分の立場に自負を持っていることが二人の溝を深めていると感じていた。この夫婦の間には感情のすれ違いがあり、左大臣もまた源氏の心を不満に感じつつも、源氏を愛しているため、歓待を尽くしていた。この夫婦とは、桐壺帝と藤壺を指しており、具体的には、桐壺帝が藤壺に対して抱く感情や関係性が焦点となる場面が多く、また、源氏の不満や複雑な感情は、彼自身が天皇と藤壺に対して抱く思いが根底にあり、それが物語に影響を与えている。物語では、左大臣と光源氏の関係、そして藤壺と源氏の間で交錯する複雑な感情が描かれ、左大臣は、源氏に対して嫉妬や不満を抱いているものの、優れた才能や立場を認めざるを得ないという心情を抱いている。左大臣は源氏が娘・葵の上と結婚していることから婿としての関係を大切にしようとしていた。特に、源氏が正装して参内しようとしている時、大臣は石の帯という名高い宝物を自ら持参して源氏に贈り、その帯をつけさせようとし、左大臣が源氏に対して抱く親心が感じられる。左大臣は源氏の後姿を整え、まるで父親が息子を大切に世話するかのような姿勢で接しており、娘婿としての源氏への期待と喜びを感じており、表向きの礼儀と親心を交えつつ、源氏を高く評価しつつも、内心では複雑な感情を抱いている様子が描かれている。その後、源氏は参賀のために東宮や一院、藤壺の三条の宮を訪れ、藤壺との再会においては、周囲の女房たちが源氏の美しさや優雅さを賞賛しているが、藤壺自身はその美しい姿を見るたび、心の中で複雑な感情を抱いていた。藤壺は、源氏との間に密かに子を成した罪悪感と、それに伴う世間からの噂に怯えていた。藤壺はその子を出産する時期が過ぎ、周囲の期待が高まる中で、彼女は身体的な不調を感じており、出産の遅れや病の原因をもののけの仕業とする噂が広がる。このような状況に、藤壺は非常に不安を感じ、出産をめぐり、自己責任の意識に苛まれる。その間、源氏も藤壺の苦しみを心配し、密かに藤壺のために寺院で修法を行わせ、彼女とその子供の無事を祈っている。源氏もまた、自らの関与が明るみに出るのではないかという不安を抱えていた。
2024.09.23
コメント(26)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 5〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。若紫はまだ幼く、雛人形を出して遊びに夢中で、若紫(のちの紫の上)は三尺(一尺30.3で約91センチ)の棚にさまざまな小道具を並べ、源氏が若紫に与えた小さな家にいくつも座敷いっぱいに置いて遊んでいる。若紫は、源氏が宮中の儺追い(なやおい祭)という儀式に参加する場面で、この儺追いは、鬼や悪霊を追い払う宮中の行事で、年の初めに行われていた。「犬君が儺追い」という言葉の犬君とは犬のように動き回る様子を指しており、源氏が悪霊を追い払う役割を果たすことを表現して書き、「儺追い」とは、疫病神や邪気を祓うための儀式であり、宮中行事の一つである。源氏の優雅で力強い一面を表して、このような場面を通じて、源氏の活躍や美しさがさらに強調されている。若紫がまだ子供でありながら、周囲から大切にされ、特に源氏から強い愛情を注がれていることが分かる。また、彼女の幼さと源氏との深い絆が対照的に描かれ、物語の先行きを暗示しつつも、純粋で愛らしい瞬間が描かれている。物語には源氏の複雑な人間関係が描かれているが、ここでは、源氏の春の新しい衣装が描かれ、源氏の出発を女房たちや若紫が見送る場面が続く。若紫は幼さゆえに、雛人形遊びに夢中になっているが、周りの者からは少し大人らしくなるべきだと助言されている。少納言は、もう今年からは少し大人になって、十歳を過ぎたら雛人形遊びは控えるべきと紫の君に言い、彼女を恥かしい思いをさせる。だが、紫の君は心の中で、私にはもう夫がいる、源氏の君が私の夫だと思い、他の女性たちの夫よりも源氏が美しいことに初めて気づく。この考えは紫の君が少し大人びたためで、周囲にもその幼さが知られるようになってきたものの、まだ彼女が名ばかりの夫人であることを誰も知らなかった。一方、源氏は御所から左大臣の家へと退出するが、そこでは夫人である葵の上との関係が冷え切っており、夫人は、源氏が二条院に別の女性を迎え入れたことを聞き、その女性が源氏の最愛の人で正夫人として公表されるだろうと聞き嫉妬していた。源氏は夫人に対し、今年からは暖かい心で私を見てほしいと言うが、夫人は冷たく接していた。
2024.09.22
コメント(23)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 4〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。若紫(のちの紫の上)が将来自分を滅ぼす道であると自覚しながらも、強く思い続けている。この恋は源氏にとっては積極的であり、藤壺の宮にとっては消極的で、二人の間には大きな隔たりがあった。源氏の優雅さや抱える複雑な感情、そして宮中での華やかな宴が詳細に描かれている。少納言(尼君の侍女)が、亡くなった尼君が紫の上(若紫)のために絶えず仏に祈ったことが、現在の彼女の幸福につながっているのだと考えている。少納言は、紫の上の未来を心配しつつも、彼女が権力の強い左大臣家の夫人や源氏の他の愛人たちとの複雑な関係に巻き込まれることを恐れ、源氏は愛人が大勢いたので、真実の結婚がどうなるか不透明であり、それが紫の上の将来に影を落とすのではないかと危惧していた。しかし、少納言は一方で、源氏がすでに若紫を愛していることから、彼女の未来は明るいのではないかとも考えた。若紫がまだ少女であるにもかかわらず、源氏は彼女に対して深い愛情を抱いており、その愛が彼女の人生を支えるものになるだろうと期待していた。若紫の祖母であった尼君の喪が三か月で明けた時、年末である師走の三十日に若紫は喪服を替えた。母代わりを務めていた祖母の死を悼む気持ちが残っていたため、派手さを避け、穏やかな色調の衣服を選んでいた。紅や紫、山吹色といった落ち着いた色の小袿(こうちぎ)を身に着けた元日の若紫は、突然大人びた美しさを見せ、まるで近代的な美人のようになったようである。その日、源氏は宮中での朝拝の儀式に向かう前に、若紫がいる西の対を訪れた。若紫がいる西の対(たい)とは、平安時代の邸宅の建築様式の一部で、主に寝殿造りと呼ばれる形式で、中央の「寝殿」に対して東西南北に配置された別棟のことを指しており、若紫が暮らしていた場所で、源氏は若紫を自分の邸宅に引き取り、大切に育てていた。西の対は、彼が頻繁に訪れる場所で、若紫がまだ幼く無邪気な時期の生活が描かれている。この「西の対」は、物語の中で若紫が成長する場として重要な意味を持っており、後に源氏の深い愛情の象徴的な場所となる。源氏は若紫に、もう大人になりましたかと微笑みながら、若紫に声をかけた。源氏の美しさが際立っている様子が暗示され、若紫にとって源氏の存在は特別なものとなる。
2024.09.21
コメント(28)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 3〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。源氏は。その後、行幸の日に帝が親王や公卿を伴い、池の船で奏楽を繰り広げた。唐や高麗の曲で舞われ、宴の盛り上がりは頂点に達した。特に源氏が舞楽の予行演習の日に披露した舞は、その美しさから帝が心配するほどで、仏門に願をかける場面もある。宮中の人々は、帝と源氏の親密な関係に感慨を抱き、東宮の母である女御だけがその寵愛をねたんでいた。源氏の舞いが始まると、その美しさは紅葉舞う中で絶妙な光景を作り出し、見ている人々はこれ以上の美がないと感じている。舞の途中で、風が吹き挿していた紅葉の葉が散り、源氏は代わりに菊の花を挿し直す場面も、優雅さと儀礼が織り交ぜられた瞬間だった。日暮れ前に小雨が降りだし、まるで天もその美しさに心を動かされたかのように思われた。源氏の舞が終わると、彼の舞いに対する賛美はさらに高まり、観衆も感嘆し声をあげる。源氏の舞姿は神々しいほどの美しさで、下人でさえその光景に涙を流すほどだった。続いて、第四親王(夕霧のこと。光源氏の長男で、紫の上ではなく、葵の上との間に生まれた子供)が幼い姿で秋風楽を舞うが、この舞も非常に優れており、観衆の心を捉えていた。しかし、これ以降の舞は人々の関心を引かず、源氏の舞の輝きに霞んでしまった。この一連の舞楽の後、源氏は正三位に昇進し、彼の周囲の人々も多くが昇進している。これはすべて源氏の恩恵とされ、彼の高い徳がこの世に喜びをもたらしていると評された。その後、藤壺の宮が実家へ帰ると、源氏は彼女に会う機会を得ようと宮邸を訪れた。左大臣家の夫人への訪問は少なくなり、彼女の心は一層恨めしく感じ、源氏は夫人を深く尊重していたが、その感情を明確に表すことはできず、夫人の嫉妬に対してどうにもできない状況が続いていた。それでも、源氏は夫人が軽率な行動を取る性格ではないと信じ、永遠の夫婦としての結びつきを感じていた。若紫は次第に源氏に慣れ親しみ、その美しさと性格の良さで源氏の心をさらに惹きつけていく。源氏は彼女を無邪気に愛し、教育にも力を入れ、父親のような存在になっていった。若紫は尼君を恋しがって時折涙を流すものの、源氏の愛情によって慰められ、日々が過ぎていった。源氏が藤壺の宮の自邸を訪れ、彼女の女房たちと応対する場面があり、源氏は藤壺の宮への思いを抑えつつも、彼女への恋心を捨てきれずにいた。
2024.09.20
コメント(25)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 2〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。東宮の母君である女御は、源氏に対して、あの美しさに神々が惹かれ、何か災いが起こらないかと心配になってしまい、気味が悪いと言うのを、若い女房たちは情けなく感じて聞いていた。藤壺の宮は、自分に後ろめたい思いがなければ、なお一層美しく見える舞だっただろうと思いながらも、夢のように感じられた。その夜の宿直の女御は藤壺の宮であった。今日の舞楽の予行演習では青海波が王様のようだった。どうご覧になりましたか?と尋ねられ、宮は答えにくく、特別に素晴らしかったですとだけ返事をした。もう一人も悪くはなかった。曲の意味の表現や手の使い方など、貴公子の舞には良いところがある。専門家の名人は上手でも、無邪気な艶っぽさはなかなか見せられない伝えた。これほど舞楽の予行演習の日にみんなが見てしまうと、朱雀院での紅葉の日の楽しみが大分減ると思ったが、君に見せたかったからねと仰せになった。翌朝、源氏は藤壺の宮へ手紙を送った。どうご覧になりましたか。苦しい思いに心を乱しながら舞いました。物思いに沈んで立ち舞うことができないこの身で、袖を振る舞の心を理解して頂けたでしょうか。失礼をお許しくださいと書かれていた。目が眩むほど美しかった昨日の舞を無視することができなかったのか、宮は返信を書いた。「から人の袖ふることは遠けれど起ち居につけて哀れとは見き」「から人」は「唐(から)人」、つまり異国の人、特に中国の人々を指し、異国の人が袖を振ることは遠く、物理的な距離や心理的な隔たりを表している。「起ち居につけて哀れとは見き」は日常のふとした動作や様子を意味し、「哀れとは見き」は哀れだと思ったという意味。日常の動作の中で、ふとした瞬間に哀れだと感じていたと解釈できる。全体意味は「から人の袖ふることは遠けれど起ち居につけて哀れとは見き/異国の人が袖を振る様子は遠いものの、日常の中で哀れだと感じていた」というものか。歌全体は、遠く離れた人やものに対する感傷や、ふとした瞬間に抱く哀れさの感情を詠んだものだろう。源氏が宮中での宴の場で、短い手紙を受け取ったことで喜ぶ様子や、華麗な舞楽の披露が中心で、まず、源氏が手にした手紙は、中国の伝承である青海波にまつわる詩歌に関連したもので、それが源氏にとって后としての品格を示すものだとされ、源氏は微笑みつつその手紙を大切に扱った。
2024.09.19
コメント(29)
-

源氏物語〔7帖紅葉賀 1〕
源氏物語〔7帖紅葉賀 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語7帖紅葉賀(もみじのが)の研鑽」を公開してます。未雀院の行幸は十月の十幾日ということになっていた。未雀院(みじゃくいん)の行幸(ぎょうこう)は、架空の天皇の離宮「未雀院」への行幸を指し、天皇が紅葉を楽しむために訪れるこの未雀院は、物語の中でも重要な出来事である。具体的には、桐壺帝が未雀院へ行幸し、宮中での大規模な宴や舞の披露が行われ、この際、源氏は舞を披露し、その美しさや優雅さが帝や周囲の人々に深く感銘を与えた。この行幸は、源氏の美しさや才能が一層際立ち、彼の地位がさらに高まるきっかけの一つとなる象徴的な場面だ。また、この場面での源氏の踊りは、彼の公的な成功と個人的な苦悩の交錯を象徴しており、物語全体のテーマである栄光と裏側の悲しみを深く反映している。その日の歌舞の演奏は特に選び抜かれて行われるとの評判だったので、後宮の女性たちはそれが宮中ではなく、高貴な方々に随行して見物できないことを残念がっていた。帝も、藤壺の女御に見せられないことを心残りに思い、同じ内容を試楽として藤壺の前で行わせてご覧になった。源氏の中将は青海波を舞い、人よりも優れた風采を持つこの公子も、源氏の隣では、桜に比べると深山の木に過ぎない。夕方前の明るい日差しの中で青海波が舞われ、青海波(せいがいは)は、古代日本で伝統的に行われていた雅楽の舞の一つで、この舞は、海の波の動きを表現するもので、名前の通り青海波模様に由来している。二人で舞うことが多く、その相手は左大臣家の頭中将であった。緩やかな動きが特徴的で、優雅で壮大な雰囲気を醸し出す。舞の動きは、手や体を波のように滑らかに動かし、ゆったりとしたリズムで舞台を縦横に広がるように進むため、観客に広大な海を連想させる。衣装は通常、豪華で色鮮やかであり、これも海や波を象徴する色や模様を取り入れている。演奏の音も一際冴えわたり、同じ舞でも、面遣いや足の運びなどが見事で、他の場で舞う青海波とは全く異なる印象を与えた。舞い手が歌う声は、まるで極楽の迦陵頻伽(上半身が人で下半身が鳥の仏教における想像上の生物)のように聞こえ、源氏の舞の巧みさに帝は涙を流され、陪席していた高官たちや親王たちも同じように感動した。歌が終わり、袖が下げられ、楽器の音が待ち受けたように鳴り響き、舞い手の頬が紅潮し、源氏はいつも以上に輝いて見えた。東宮の母君である女御はその美しさを認めつつも、心は平穏ではなかった。
2024.09.18
コメント(25)
-

源氏物語〔6帖末摘花 13完〕
源氏物語〔6帖末摘花 13完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。源氏も一緒に末摘花の似顔絵を描いてみた。長い髪の女を描き、鼻に紅をつけてみた。絵でもそれは醜く感じた。源氏は鏡に映る自分の美しい顔を見て、筆で鼻を赤く塗ってみた。どんな美貌でも、赤い鼻が一つ混じっていると目を背けるほど見苦しく思われた。若紫はそれを見て、面白がって笑った。源氏が、もし私がこんな醜い顔になったらどうだろうと言うと、若紫は、やはりいやでしょうねと答え、鼻の紅がしみ込まないか心配していた。源氏は白い紙で拭く真似をして、どうしても白くならない。ばかなことをした。陛下は何と言うだろうと真面目な顔で言った。若紫は同情してそばに寄り、水を含ませた紙で鼻の紅を拭き取った。平仲の話のように墨なんかを塗ってはいけませんよ。赤のほうがまだ我慢できますと源氏は冗談を言い、二人は若々しく大きな声で笑いながら戯れていた。初春らしく霞を帯びた空の下、いつ花を咲かせるのかと、たよりなく思われる木々の中で、梅だけが美しく花を咲かせ、特別な木のように感じられた。特に、緑の階隠し(寝殿造りの殿舎で、正面の階段上に、柱を2本立てて突出させた庇)のそばの紅梅は早く咲き、枝が真っ赤に見えた。源氏は、「くれなゐの花ぞあやなく疎まるる梅の立枝はなつかしけれど/紅の花が何の理由もなく疎ましく思われるように、梅の立派な枝ぶりには愛着を感じるのに、どうしてこの紅い花は愛おしく思えないのだろう」と詠んだ。くれないの花は末摘花(紅花)のことを指しており、末摘花という名前自体が紅色の花を指し、彼女の外見や象徴がこの紅の花と結びついている。「あやなく」は理由もなく、疎まるるは疎ましく思われるという意味で、特に理由もないのに、紅い花が末摘花の容姿や振る舞いに自然と心が遠ざかってしまうという感情を表し、梅の立枝はなつかしけれどは梅の木の立派な枝ぶりを指し、これは美しさや気品を象徴し、魅力的で気品のある女性には自然と惹かれるのに、末摘花の紅い花には惹かれないと表現している。源氏は末摘花に対して、純粋さや気品には惹かれつつも、容姿や振る舞いにはあまり魅力を感じていない。末摘花や若紫、これからどうなるのだろうかとため息をついた。明日より「7帖紅葉賀(もみじが)の研鑽」を公開します。
2024.09.17
コメント(28)
-

源氏物語〔6帖末摘花 12〕
源氏物語〔6帖末摘花 12〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。源氏は、末摘花のことを思い、この人の顔が美しく見える時が訪れるだろうかと、未来に対する期待を抱きながら格子を上げた。かつて雪の夜明けに彼女を完全に見てしまったことを後悔したことを思い出し、格子を完全には上げず、脇息を寄せてそれを支えにした。源氏が乱れた髪を直していると、非常に古びた鏡台や支那製の櫛箱、掻き上げ用の箱などを女房が運んできた。これらは、普通の家では少しそろえてある程度のものであり、男専用の髪道具もあったので、源氏は面白く思った。末摘花が現代風になったのは、三十日に贈られた衣箱の中の物がそのまま使われているからだということには、源氏は気づいていなかった。よい模様だと思った袿だけは、見覚えがある気がした。春になったのですからね。今日はその声も少し聞かせてください。ウグイスよりも何よりも、それが待ち遠しかったのですと言うと、末摘花は、「百千鳥囀る(さへづる)春は物ごとに改まれども、われぞ古り行く/たくさんの鳥たちがさえずる春は、すべてが新しく美しくなっていくけれども、私はただ年老いていくばかりです」とだけ、ようやく小声で言った。源氏は笑いながら、ありがとう。二年越しにやっと報いられたと、「忘れては夢かとぞ思ふ/忘れてしまうと、まるでそれが夢だったかのように思えてくる」という古歌を口にしながら帰ろうとした。そのとき、末摘花が袖で口を覆って見送っていたが、その袖の陰から例の赤い鼻が見えていた。源氏は「見苦しいものだ」と歩きながら思った。二条の院に戻ると、源氏は若紫の半分大人びた姿を見て、可愛らしいと感じた。その紅色の感覚は、末摘花からも受け取れるものだが、この人の紅色は懐かしく感じられるものだった。無地の桜色の細長を柔らかに着こなす彼女の無邪気な身の取りなしが、美しくて可愛らしかった。昔風の祖母の好みでまだ歯を黒くしていなかったが、そのことが美しい眉を一層引き立たせていた。源氏は、自分のすることであるが、どうしてこんなに可憐な人とだけいられないのだろう。なぜ他のつまらない女たちを情人に持ってしまうのだろうと思いながら、いつものように彼女と一緒に雛遊びをした。紫の君は絵を描いて彩色もしていた。彼女の美しい性質が、何をしても溢れ出しているように見えた。
2024.09.16
コメント(24)
-

源氏物語〔6帖末摘花 11〕
源氏物語〔6帖末摘花 11〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。源氏はこの屋敷を去り、朽ち果てた門や寂しい景色を目にしながら、詩的な世界に生きながらも、恋する力を失った女性だと判断した。源氏は、「ふりにける頭の雪を見る人も劣らずぬらす朝の袖かな/頭に降り積もった白い雪、年を取って白くなった髪の毛を見ている人も、その人自身の涙で朝の袖をぬらしている」と詠んだ。さらに「霰雪白紛紛、幼者形不蔽/霰や雪が白く激しく降りしきり幼い子どもたちはその身を覆う衣服もなく寒さに震えている」と白楽天の詩を吟じていたが、詩の終わりに鼻のことが言及されているのを思い出し、微笑した。頭中将があの新婦を見たらどのような批評をするだろうか、どのような譬喩を用いるだろうかと考えると、自分の行動を見逃さない彼が、この関係に気づくのも時間の問題だと思い、源氏は救われがたい気持ちに襲われた。もし女王が普通の容貌であったなら、源氏はすぐに離れることもできたかもしれないが、彼女の醜い姿を見た瞬間、かえって哀れみの心が強くなり、良人として物質的な補助をしてやるようになった。黒貂の毛皮ではないが、絹、綾、綿、老いた女たちが着るものや、門番の老人に与えるものまで贈った。こうしたことは自尊心のある女性には耐えがたいことに違いないが、常陸の宮の女王はそれを素直に喜んで受け取ったので、源氏は安心し、せめて彼女に対して世話をしようという気持ちになり、生活費なども後で与えた。空蝉の横顔は美しいものではなかったが、その優美な姿態は十分に魅力的だった。常陸の宮の姫君も、それより下品な身分ではないはずだと思うと、上品であるということは外見によらないことがわかる。源氏は、男に対する洗練された態度や強い正義感、そしてついには彼女に負けて退却したことを思い出し、何かにつけて空蝉のことを思い出すことが多かった。その年の暮れ、大輔の命婦が源氏の御所に訪れ、髪を梳かせるなどの用事をしていたが、恋愛関係のない、しかも戯談ができる女を選んでいたため、彼女がよくその役を務めていた。ある日、命婦は、変なことがあったと微笑しながら、常陸の宮からの手紙と贈り物を源氏に渡した。手紙は香り高い薫香がつけられており、歌も添えられていた。贈り物の中には、悪趣味な直衣が入っており、源氏はその粗野な趣味に不快感を覚えたが、返事として、「なつかしき色ともなしに何にこの末摘花を袖に触れけん/親しみを感じるような美しい色でもないのに、どうしてこの末摘花を袖に触れることになったのだろうか」と書き、命婦を笑わせた。
2024.09.15
コメント(25)
-

源氏物語〔6帖末摘花 10〕
源氏物語〔6帖末摘花 10〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。命婦は一晩中心配し、物音を聞いていたが、何も言わずに源氏を見送らなかった。常陸の女王がまだ一度も顔を見せず、恥じらいを捨て去ろうともしないまま、ただ時間だけが過ぎていった。源氏がこの女性を一目見た瞬間に心を惹かれる可能性もあったが、そんな兆しはこなかった。手探りでこの女性を理解しようとする中、彼女の顔を一度だけ見たいと思うこともあったが、幻滅してしまうかもしれないという不安もあった。誰も訪れることを想像しないような、まだ深夜にもならない時間に、源氏はそっとその家に行き、格子の隙間から覗き込んだ。しかし、姫君はそんな所から見えるものではなかった。部屋には古びた屏風がきちんと立て掛けてあり、源氏は隙間を探しながら縁側を歩いたが、見えたのは数人の侍女だけだった。彼女たちは古びた支那製の食器で夕食を取っており、寒そうにしていた。服は煙で煤け、侍女たちは古風な髪型をしていた。その姿に源氏は、内教坊や内侍所で見かける女房たちのようだと興味深げだった。しかし、こうした女房たちがここで暮らしているとは源氏も知らなかった。寒い冬でも特に冷える冬で、袖をばたつかせながら寒さに震えていた。聞くに堪えないような、生活の厳しさを嘆く話ばかりで、源氏は気まずくなり、そっと立ち去った。源氏が再び格子を叩くと、女房たちは灯を明るくして源氏を迎えたが、屋敷はどこか野暮ったく、侍従も不在で、外では雪が増々激しく降り、吹雪の中で灯が消えても、誰もつけ直す者はいなかった。源氏はかつて物怪の出た夜を思い出したが、それに劣らない荒廃した家であった。夜が明けかけた頃、源氏は格子を自ら開け、雪に覆われた庭の景色を見た。何も踏み固められていない白い雪が広がっていた。彼は立ち去る前に、姫君に夜明けの美しい空を一緒に眺めましょうと声をかけた。源氏は姫君の姿に失望しつつも、その背中の長い線や奇妙な鼻に目を奪われた。普賢菩薩の乗った象を思わせるような高く長い鼻は、特に目立っていた。顔は青白く、全体的に長く、痩せた体つきは痛々しく、源氏は見るに堪えなかった。しかし、髪型だけは美しく、源氏は何とも言えない気持ちでそこを去ろうとした。源氏は、朝日が差し込む軒の氷柱が解けながら、どうしてこれほど固く結ばれているのだろうと詠んだが、返歌はなかった。
2024.09.14
コメント(24)
-

源氏物語〔6帖末摘花 9〕
源氏物語〔6帖末摘花 9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。命婦は一晩中心配し、物音を聞いていたが、何も言わずに源氏を見送らなかった。常陸の女王がまだ一度も顔を見せず、恥じらいを捨て去ろうともしないまま、時間だけが過ぎていった。源氏がこの女性を一目見た瞬間に心を惹かれる可能性もあったが、そんな兆しはこなかった。手探りでこの女性を理解しようとする中、彼女の顔を一度だけ見たいと思うこともあったが、幻滅してしまうかもしれないという不安もあった。誰も訪れることを想像しないような、まだ深夜にもならない時間に、源氏はそっとその家に行き、格子の隙間から覗き込んだ。しかし、姫君はそんな所から見えるものではなかった。部屋には古びた屏風がきちんと立て掛けてあり、源氏は隙間を探しながら縁側を歩いたが、見えたのは数人の侍女だけだった。彼女たちは古びた支那製の食器で夕食を取っており、寒そうにしていた。服は煤け、侍女たちは古風な髪型をしていた。その姿に源氏は、内教坊や内侍所で見かける女房たちのようだと面白がった。しかし、こうした女房たちがここで暮らしているとは源氏も知らなかった。今年はやけに寒い年だ。長生きするとこんな冬に遭うこともあるんだと嘆く女房もいた。また、ある女房は、宮様がいらした時代に、なぜ私はこんな寂しい家だと思ったのだろう。今はさらにひどいが、それでも奉公を続けていると、袖をばたつかせながら寒さに震えていた。聞くに堪えないような、生活の厳しさを嘆く話ばかりで、源氏は気まずくなり、そっと立ち去った。源氏が再び格子を叩くと、女房たちは灯を明るくして源氏を迎えたが、屋敷はどこか野暮ったく、侍従も不在だった。外では雪がますます激しく降り、吹雪の中で灯が消えても、誰もつけ直す者はいなかった。源氏はかつて物怪の出た夜を思い出したが、それに劣らない荒廃した家でもあった。夜が明けかけた頃、源氏は格子を自ら開け、雪に覆われた庭の景色を見ていた。何も踏み固められていない白い雪が広がっていた。源氏は立ち去る前に、夜明けの美しい空を姫君に一緒に眺めましょう。いつまでもよそよそしいのは辛いですと声をかけた。源氏は姫君の姿に失望しつつも、その背中の長い線や奇妙な鼻に目を奪われていた。
2024.09.13
コメント(26)
-

源氏物語〔6帖末摘花 8〕
源氏物語〔6帖末摘花 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。源氏を縁側に座らせるのは失礼です。無理強いはしないでしょうから命婦自身が襖をしっかり閉め、丁寧に隣の部屋に座る準備を整えていた。襖を確実に閉め、隣室に源氏の座を準備した。源氏は少し恥ずかしさを感じながらも、初めて会う女性にはどのように接して良いか分からず、命婦が取り計らってくれるだろうと思いながら座った。年老いた侍女たちは部屋に入り、宵のうちに目を閉じていましたが、若い侍女たちは有名な源氏の訪問に心を躍らせていた。その間、末摘花自身は何の動揺もなく、心静かに別室で控えていた。源氏は美しい姿を見せないように化粧を控えめにしていましたが、今夜は特に艶やかに見えていた。命婦は、美しさを理解できる人がいないこの場にいる源氏が少し気の毒に感じていたが、末摘花が大らかであることに安心していた。彼女は会話において失敗することはなさそうだと思ったが、しかしながら、命婦は、自分の軽率な行動が末摘花をさらに不幸にしてしまうのではないかと不安を抱いていた。源氏は、彼女が控えめで大らかな性格であることを好ましく思っていた。襖の向こうで女房たちに促され、末摘花が少し前に進んだとき、微かな衣被香(えびこう/衣裳に焚きしめる香)の香りが漂い、源氏は自分の予想が間違っていなかったと思っていた。長い間思い続けていた恋について語ったが、末摘花からは返答はなかった。源氏は、一体どうすればいいのかと嘆息し、恋心を告白する歌を詠んだが、末摘花はまだ返事をしなかった。やがて、彼女の侍従という気さくな若い侍女が見るに見かねて、末摘花の代わりに答えた。侍従の返答は少し甘えた態度に見えたが、源氏は彼女がようやく言葉を発したことに喜びをあらわした。源氏はさらに言葉を交わそうとしたが、末摘花からの返答は依然としてなく、彼女の態度に源氏は自分が軽んじられているように感じていた。そして源氏は素早く襖を開けて末摘花の部屋に入った。その時、命婦は不意をつかれ、末摘花を気の毒に思いながら、自分の部屋に引き下がりました。侍従などの若い侍女たちは源氏に好意を抱いており、末摘花を守ることに積極的ではなかった。こうして、準備もないままに関係が結ばれ、末摘花は羞恥心に包まれていた。源氏は結婚の最初の段階ではこのような女性が良いと考えていたが、彼女の様子に納得できない部分もあり、新たな愛情が芽生えることはなかったが、源氏は夜明けに近い頃に帰ろうと決意した。
2024.09.12
コメント(20)
-

源氏物語〔6帖末摘花 7〕
源氏物語〔6帖末摘花 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。私を無視したのが恨めしくて、こうして送りに来たと歌を詠んだ。源氏はその男が頭中将であることに気づいて安心し、またおかしさを感じた。頭中将は失敬なことをする者はあなたのほかにありませんと憎らしそうに言う。こんなふうに私が始終あなたについて歩いたら困るでしょうと話し続けたが、頭中将は、しかし、恋の成功はよい随身をつれて行くかどうかで決まることもある。これからは一緒にお連れください。一人歩きは危険ですよと話す。源氏は頭中将が得意がっていることを残念に思ったが、あのナデシコの女が自分のものになったことを頭中将が知らないことだけは誇らしく感じていた。二人の貴公子は戯れ言を言い合いながらも、共に車に乗り、左大臣家へと向かった。彼らは朧月夜の暗い時分にそっと邸に入り、直衣に着替え、素知らぬ顔で笛を吹き合いながら源氏の住んでいる方へ向かった。左大臣はその笛の音に促され、高麗笛を持ち出して源氏に贈った。その笛を得意気に吹く源氏の姿に、頭中将は心中複雑な思いを抱きながらも、あの荒れ果てた邸で聞いた琴の音が脳裏に浮かんでいた。その後、二人の貴公子は常陸の宮の姫君へ手紙を送ったが、返事はなかった。源氏はそのことを笑って頭中将に伝えたところ、頭中将は源氏の言葉を真に受け、女王の返事を待つ自分を悔しく思っていた。その後、源氏は大輔の命婦に真剣に仲介を頼み、女王への思いを伝え続けた。やがて秋が訪れ、源氏は頻繁に手紙を送るようになったが、返事は変わらず、源氏はその冷淡な態度にいら立っていた。命婦は、源氏が女王を本当に好きなのか疑問を抱きながらも、源氏の強い要望に応じて彼女を取り持つことに決める。源氏は女王の住む古い邸へと再び訪れ、月明かりの下で彼女の姿を見つけると、彼の心に深い愛情が湧き上がってきた。どんな貴婦人であっても、親がしっかり保護してくれている間は、子どもらしく振る舞っているのは良いのだが、このような寂しい暮らしをしているにもかかわらず、あまりにあなたのように羞恥心が強いのは、間違っているよと、源氏は忠告していた。人の言うことに逆らえない内気な性格の末摘花は、返事をしなくてもよいというのであれば、格子を下ろしてここに座っていますと答えた。
2024.09.11
コメント(27)
-

源氏物語〔6帖末摘花 6〕
源氏物語〔6帖末摘花 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。命婦は才気のある女性であったため、名手の域に達していない音楽を長く源氏に聞かせ続けることが女王の不利益になると考えていた。源氏に対して今夜、私の方にお越し頂く約束があったので、私がいないとわざと避けたと思われてしまうので、また改めてゆっくりと弾かせて下さいと言って、命婦は琴を長く弾かせずに部屋に戻った。源氏は、あれだけでは十分に楽しめないし、どの程度の名手かも分からず、つまらないと源氏は思ったが、女王に好感を持っているように見えた。できれば、もう少し近い場所で女王さんの衣擦れの音でも聞かせてもらえないかと言うが、命婦はそれを許さず、むしろ想像をかき立てることを優先した。それは無理です。女王様は気の毒な暮らしをしていて、男性と引き合わせることなどできませんと命婦が言うと、源氏もそれはもっともだと思った。男女が思いがけなく会うような関係には到底入らない方であると考えた。だが、将来のために私のことを少し話しておいてくれないかと頼んだ後、源氏はほかに約束のある人のところへ帰ろうとした。すると、命婦は笑いながら、真面目すぎるところがあり、陛下も困られることがあると聞いていますが、私にはそんなお姿が時折おかしくてなりません。こんな浮気なお忍び姿を陛下がご覧になることはありませんからねと話す。源氏はその言葉に二足三足戻りながら笑って、何を言っているのだ。品行方正な人間でも言うように。これを浮気と言うなら、君の恋愛生活は一体何だと言うのだと返していた。源氏は命婦を多情な女性だと思っており、彼女も恥ずかしさを感じて何も言わなかった。女の暮らす家の座敷の物音を聞きたいと思った源氏は、静かに庭へ出ていく。庭には、以前から立っていた男がいて、源氏は、その男が誰なのか、女王に恋する好色男だろうと考え、暗がりに隠れて立っていた。実は、その男は頭中将で、今日も源氏の後を追い、邸に入って行った。頭中将は、夕方、源氏が御所を出てから途中で別れたことを妙に不審に思い、源氏の後をつけて行った。琴の音が聞こえ、源氏が庭に出てくるのを待っていた。源氏はまだその男が誰かに気づかず、顔を見られないように庭を抜けようとしたが、男が近づいてきて声をかけてきた。
2024.09.10
コメント(23)
-

源氏物語〔6帖末摘花 5〕
源氏物語〔6帖末摘花 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。源氏は、「あれだけでは物足りない。彼女がどれほどの腕前なのか分からず、何ともつまらない」と感じ、女王に対して好感を持っている様子を見せた。そして、「できれば、もっと近い所の座敷に案内して、せめて遠くからでも女王の衣擦れの音でも聞かせてくれないか」と頼んでみたが、命婦は彼女に近づかせず、むしろ想像を膨らませておきたいと思っていた。命婦は、「それは無理です。気の毒な暮らしをして、深く思い悩んでいる方に、男の方を引き合わせすることなどできません」と断り、その言葉に源氏も納得し、この女性が貴族の中でも、男女が思いがけなく会話をするような階級には属していないと考えた。源氏は、将来的には交際ができるように、私のことを話しておいてくれと命婦へ頼んだあと、源氏は他に約束があることを思い出して帰ろうとした。命婦は、あまりに真面目すぎるので、陛下が困るとよく話しているのが、私には時折おかしくてたまらないし、こんな浮気なお忍び姿を陛下はご覧にならないでしょうと話した。すると、源氏は二三歩戻ってきて笑いながら、何を言っているんだい。品行方正な人間でも言うように。これを浮気と言うなら、君の恋愛生活は何なのだと言い返した。源氏が命婦を多情な女性だと決めつけており、時々こうして面と向かって言われるのを命婦は恥ずかしく思い、何も言い返せなかった。源氏は、女暮らしの家の座敷から聞こえる物音を感じたいと思い、静かに庭に出ていった。ほとんど朽ちてしまった透垣の影に身を隠していた源氏は、そこに以前から立っていた男を見つけ、女王に恋する男だと思い、暗がりに隠れて様子を伺っていると、それが頭中将だった。今日も夕方、御所を同時に退出した後、源氏が左大臣家にも行かず、二条の院にも戻らずに途中で別れたのを見た中将は不審に思い、自身も行く予定の家があったのに、それをキャンセルして源氏の後をつけてきた。わざと貧弱な馬に乗り、狩衣姿でいた中将に、源氏は気づかなかったが、こんな思いがけない邸に入っていったのを見て、中将の疑念はさらに深まることになる。
2024.09.09
コメント(22)
-

源氏物語〔6帖末摘花 4〕
源氏物語〔6帖末摘花 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。父の大輔は宮邸には住んでおらず、継母の家へ行くのを嫌って、命婦は祖父の宮家へ帰っていた。源氏は言った通り、十六夜の月が朧に霞む夜に命婦を訪れた。「困ります。こうした天気は音楽に適していません」と命婦が言うと、源氏は「まあいいから御殿へ行って、一声だけでいいからお弾かせしてくれ。聞かないで帰るのではつまらない」と強く頼んだ。命婦はこの貴公子を自分の部屋に残すことを申し訳なく思いながら、寝殿へ行くと、まだ格子をおろさずに梅の花が香る庭を女王が眺めていた。命婦は「とてもよいところだ」と心で思った。琴の音を聞かせていただけるならと思い、部屋を出てきましたと言う。私はこちらに寄せていただいていますが、時間が少なくて、伺う間がないのが残念ですと命婦が言うと、女王は「あなたのような批評家がいては手が出せない。御所に出ている人たちに聞かせるような芸ではありません」と答えた。それでも女王が琴を持って来させるのを見ると、命婦はかえって驚いた。源氏が聞いていることを思うからである。女王はほのかな爪音を立てて弾いた。源氏は興味深く聞いていた。それほど深い芸ではないが、琴の音は他の楽器にはない異国風の響きがあり、聞きにくいとは思わなかった。この邸は非常に荒れていた。しかし、こんな寂しい場所に住んでいる女王が、大事にされていた時代の名残もない生活をしているのでは、どれほど味気ないことが多かろうと、源氏は考えた。昔の物語にもこんな背景の中で佳人が現れることが多かったなと思い、今から交渉の手がかりを作ろうかとも考えたが、無礼に思われることが恥ずかしくて立ち上がれなかった。命婦は才気のある女性だったため、名手とはほど遠い女王の音楽を長時間源氏に聞かせることは、かえって女王の評価を下げることになると考えていた。「雲が出て月が見えなくなりがちな晩ですね。今夜、私の方に訪問するお約束の方が来られるので、私がここにいないと、わざと避けたように思われるかもしれません。またゆっくりと聞かせていただきますので、今は格子を下ろしておきましょう」と言って、命婦は琴を長く弾かせずに部屋に戻って行った。
2024.09.08
コメント(25)
-

源氏物語〔6帖末摘花 3〕
源氏物語〔6帖末摘花 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。源氏の好奇心は、少しでも良さそうな女性に対しては、すぐに向いた。まず短い手紙を送ると、女性の方から好意を示すことが多かった。しかし、冷淡な態度を取る女性はほとんどおらず、それが源氏を失望させた。時には条件が合っている女性もいたが、頭に欠陥があるか、理智一方の女性であって、源氏に対して一度は思い上がった態度を見せるものの、自分を知らないようであったり、結局はつまらぬ男と結婚してしまうこともあった。そのため、源氏が話をかけただけで終わってしまうことが多かった。源氏は時折、空蝉のことを思い出し、敬服する気持ちが湧くこともあった。また、軒端の荻に時々手紙を送ることがあったようである。灯火の影で見た彼女の美しい顔を思い出し、源氏は彼女を恋人としておいてよいかと感じた。源氏の君は一度でも関係を持った女性を忘れて捨てるようなことはなかった。左衛門の乳母という女性がいて、彼女は大弐の乳母に次いで源氏に大切にされていた。その一人娘が大輔の命婦といって、御所で勤めをしていた。彼女の父は王氏の兵部大輔であった。彼女は多情な若い女性で、源氏も宮中の宿直所では女房のように使っていた。左衛門の乳母は今は筑前守と結婚し、九州へ行ってしまったため、命婦は父の兵部大輔の家を実家として女官を勤めていた。常陸の太守であった親王が晩年にもうけた姫君が孤児となって残っていることを、命婦が源氏に話した。源氏はその話を聞き、姫君のことを詳しく尋ねた。どんな性質なのか、容貌のことなど。内気でおとなしい方ですから、時々は几帳越しにお話しする程度です。琴がいちばんの友だちらしいと命婦は答えた。それはいいことだね。琴と詩と酒を三つの友と呼ぶんだ。酒だけはお嬢さんの友達にはいけないと源氏は冗談を言ったあとで、私にその女王さんの琴の音を聞かせてほしい。常陸の宮さんは、音楽などに優れていたようで、平凡な芸ではないだろうと思うと言った。そんなふうに考えて聞く価値があるかどうかと命婦が答えると、源氏は、思わせぶりをしなくてもいいじゃないか。このごろは朧月があるからね、そっと行ってみよう。君も家へ退いていてくれと熱心に言った。大輔の命婦は迷惑になりそうなことを恐れながらも、御所が暇な時だったので、春の日が長い時に退出した。
2024.09.07
コメント(21)
-

源氏物語〔6帖末摘花 2〕
源氏物語〔6帖末摘花 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。源氏の君は、夕顔を失った悲しみを、月日が過ぎ去っても忘れることができなかった。左大臣家にいる夫人も、六条の御息所も、非常に誇り高く、源氏が他の愛人をもつことを許すことができない難しい性格のため、彼女たちと接することは容易ではなかった。だからこそ、源氏は、気楽で自由な気持ちを与えてくれた夕顔を特に恋しく思っていた。源氏は、女性の身分があまり高くなく、気軽に付き合える女性を見つけたいと考えていた。源氏は、少しでも魅力的だと思われる女性にすぐに興味を示し、手紙を送って接近しようとする。すると、たいていの女性はすぐに好意を示してくれるが、源氏は逆にそのことに失望してしまい、条件に合う女性がいても、頭の良くない人や理性的すぎる人が多く、そうした女性たちは源氏に対して一時的に傲慢な態度を取ることがあった。最終的には、傲慢な人を侮るような女性は、あまりにも自分に見合わないと感じ、のちに案の定つまらない男と結婚してしまうこともあった。そのため、頭の良くない女性や理性的すぎる女性は、話が途中で終わってしまうことも多くあった。源氏は時折、空蝉のことを思い出し、彼女に対して敬服する気持ちが湧いていた。また、軒端の荻にも、今でも時々手紙を送っていた。灯影に見た彼女の美しい顔を思い出し、彼女を愛人としてそばに置いておきたいと無性に思うことがあった。源氏の君は、一度関係を持った女性を忘れて捨ててしまうことはなかった。左衛門の乳母という女性がいたが、彼女は源氏に大切にされていた。その娘は、大輔の命婦という女官で、御所に仕えていた。彼女の父親は王氏の兵部大輔で、多情な若い女性だった。源氏も宮中の宿直所で彼女を女房のように使っていた。左衛門の乳母は今、筑前守と結婚し、九州に行ってしまったため、命婦は父親である兵部大輔の家を実家として女官を務めていた。ある日、命婦が源氏に、彼女の姫君が孤児となって残されていることを話した。気の毒に思った源氏は、その姫君について詳しく尋ねていた。源氏の君の夕顔を失った悲しみは、月がたち年が変わっても忘れることができなかった。左大臣家にいる夫人や六条の貴女は、強い思い上がりがあり、他の源氏の愛人たちを寛大に許すことができない気難しさも持っていた。彼女たちが扱いにくい性格であったために、源氏はむしろあの気楽で自由な気持ちを与えてくれた恋人を懐かしんでいた。源氏は身分が低く、素直で、世間的にもあまり恥ずかしくない恋人を見つけたいと思い続けていた。
2024.09.06
コメント(25)
-

源氏物語〔6帖末摘花 1〕
源氏物語〔6帖末摘花 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語6帖末摘花の研鑽」を公開してます。源氏物語の第6帖末摘花は、光源氏の数多い恋物語の中でも異色の存在で、この巻は、源氏の恋の対象となる末摘花(すえつむはな)という女性との関係を中心に描かれている。末摘花は紅花と呼ばれ山形県の県花にも指定されている花だ。末摘花の鼻が赤くて長いことから、花の一部である「末摘花」に例えられた。源氏が、ある日の夕暮れ、桐壺の更衣の縁にゆかりがある一人の女性の存在を知ることになり、その女性は、六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)や葵の上(あおいのうえ)のような華やかな女性たちとは異なり、ひっそりと寂しい生活を送っている宮中の女性だった。源氏は彼女に興味を持ち、彼女の住む荒れ果てた邸宅を訪れることになった。源氏は、訪問先で末摘花と出会うが、彼女は外見こそ決して美しいとは言えないものの、純粋で素朴な人柄であった。特に、その赤くて長い鼻は彼女の外見の特徴として描かれていて、それは当時の美的感覚からはかけ離れたものだったのだろう。源氏は彼女の容姿失望するものの、その内面の純粋さと高貴な生まれに惹かれ、彼女との関係を続けることにした。しかし、末摘花は非常に慎み深く、内気であり、源氏のアプローチに対しても慎重な態度を崩すことはなかった。物語の中で、源氏は末摘花を自分の邸宅に迎え入れるなど、彼女に対して誠実に接しているが、彼女は終始一貫して控えめな態度を貫いている。源氏もまた、彼女を自分のものにしようとする執念を燃やしつつも、彼女に対する扱いには注意深くなる。その微妙な距離感を保ちながら関係を続けていくことになった。末摘花は、源氏物語全体の中でも特異な存在であり、他の女性たちとは一線を引く性質で、彼女の外見の特徴と、それにもかかわらず源氏が彼女に興味を持ち続けることは、外見だけでなく内面の美しさや高貴さが重要であるというメッセージを込めている。また、末摘花の巻は、源氏の女性観や恋愛における姿勢を深く掘り下げる物語としても位置づけられている。結局、源氏と末摘花の関係は大きな進展を見せることはなく、物語の終盤では源氏の興味も徐々に薄れていき、この巻は源氏物語の多様な女性像の一つを描き出す重要な部分となっている。
2024.09.05
コメント(21)
-

源氏物語〔5帖若紫 26 完〕
源氏物語〔5帖若紫 26〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語5帖若紫の研鑽」を公開してます。源氏物語の「若紫」巻の最終部分は、物語の中で非常に象徴的で、後の展開に大きな影響を与えた。若紫が源氏に引き取られ、二条院に移ることで、彼女の運命が大きく変わり、物語全体の流れが決定づけられた。若紫は、藤壺の女御に似た美しさを持ち、その純粋さと無垢さが源氏の心を捉えた。源氏は若紫を理想の女性として育て上げたいと願い、また彼女を守りたいという強い思いを抱く。源氏は純粋な動機から、若紫を自分の元で育てる決意をした。この時点での源氏の感情は、彼の父性や保護者としての側面が強調され、恋愛感情とは異なるものとして描かれた。尼君との話し合いにより、若紫が源氏に託されることが決まり、若紫は新たな生活を始める事となった。この話話は、源氏の保護のもとで若紫が成長し、後に「紫の上」として物語の中心的な存在になることを予感させていた。また、若紫を引き取るという源氏の行動は、源氏の性格や価値観、そして彼が追い求める理想の女性像が垣間見える場面で、若紫の巻の終わりは、源氏と若紫の運命が交わり、二人の関係が物語の中心に据えられることを暗示していた。物語が進むに連れ、若紫は源氏の人生における重要な人物となり、若紫と源氏の関係が物語全体に深い影響を与えることになっていった。「5帖若紫」の章は、光源氏の女性観や理想の追求、また紫の上の成長過程を描く上で非常に重要な章である。また、幼い少女を理想の女性に育て上げるという源氏の行為は、その時代の貴族社会の価値観や倫理観を反映しており、後世の文学や美術にも大きな影響を与えた。5帖若紫この章を通して、光源氏と紫の上の関係が深まり、その後の二人の物語の基盤が築かれることになった。光源氏が偶然に若紫と出会い、その美しさと無垢さに強く惹かれ、彼女を自分の理想の女性に育てたいという願望を抱いた。源氏は若紫との出会いを通じて、若紫を保護し、彼女を二条院に引き取ることを決意することとなり、この行動は、彼の父性や保護者としての側面を強く反映しているが、同時に源氏が抱く理想の女性像を若紫に投影していることも示していた。若紫が二条院に移り、源氏のもとで育てられることで、二人の関係が徐々に深まっていく。若紫は次第に成長し、源氏にとって特別な存在となり、後に「紫の上」として知られるようになります。彼女は源氏の理想に近づくように成長し、源氏にとって最も重要な女性となった。この章で築かれた二人の関係は、物語全体の中で中心的な役割を果たし、紫の上は、源氏の正妻として彼の生涯に渡って重要な存在であり続け、彼女との関係は源氏の人生や感情、さらには他の女性たちとの関係にも深く影響を与えることになっていく。
2024.09.04
コメント(25)
-

源氏物語〔5帖若紫 25〕
源氏物語〔5帖若紫 25〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語5帖若紫の研鑽」を公開してます。「紫の故」とは、紫草(むらさき)という初夏から夏にかけ白い花を咲かせる植物を指し、源氏物語の中で具体的な植物として登場している。紫草の根から染め出される紫色は、美しさや高貴さの象徴とされ、若紫が後に「紫の上」となることを示唆し、彼女の高貴さや美しさを暗示している。若紫が無邪気に応じるでは、子供らしい素直さが源氏の心を打つ。源氏は、まだ幼いながらも、その筆跡から彼女の将来の成長を予感し、亡き尼君を思い出しながら感慨深く感じている。若紫が和歌を詠んだり、字を書く様子を見た源氏は、その無邪気さや子供らしさに心を動かされ、若紫が上達する可能性を感じつつも、純粋な愛おしさを覚える様子が描かれ、源氏は若紫と共に過ごし教育や遊びを通じて、彼自身の心の慰めを得ている。若紫の成長を見守りながら、関係が徐々に深まっていく。若紫が源氏の元にいることは周囲には秘密にされ、これによって物語の展開に緊張感が加わり、尼君への思慕: 源氏がいないとき、若紫は亡き尼君を思い出して悲しんでいる。しかし、父宮を、ほとんど知らない彼女にとって、源氏が実父のような存在となり、源氏に深く慣れ親しんでいっている。若紫は源氏が帰ってくると、自ら出迎えて懐に抱かれるなど、親しい関係を築いていき、この異常なまでの親しみは、当時の社会的な常識から外れており、源氏自身もその異質さに気づいている。源氏は若紫との関係を、大人の女性との恋愛と比較している。大人の恋には複雑で面倒な面がある一方、若紫との関係にはそのような問題がなく、純粋な心の慰めを得られると感じている。通常、父親が娘と必要以上に親しく接することは許されない。しかし、源氏はこの異常なまでの親しさを楽しみ、特別な関係を築いていることに気づいている。源氏は、元服してから数年が経過し、20代半ばの若き貴公子として物語に登場する。美しさと才能に恵まれた源氏は、多くの女性たちと恋愛関係を持ち、心の奥底で理想の女性像を求めていた。源氏は北山に参詣のため出かけ、その途中で、目に留まった寺で、後の紫の上が遊んでいるのを目にする。彼女は、若くして亡くなった源氏の初恋の藤壺の女御によく似ていた。源氏が出会ったこの幼い少女は、桐壺帝の兄である典侍の姪で、母親は早くに亡くなり、祖母の尼君によって育てられた。
2024.09.03
コメント(23)
-

源氏物語〔5帖若紫 24〕
源氏物語〔5帖若紫 24〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語5帖若紫の研鑽」を公開してます。源氏が幼い姫君(後の紫の上)を彼のもとへ引き取ろうと思い悩みながら源氏の心情や社会的な背景が緊張感をもって描いている。少納言たちは源氏の行動に対して戸惑いと懸念を抱いている。源氏が幼い姫君を連れ去ろうとすることで、彼女の将来や運命が大きく変わることを心配していた。少納言が、どうしたらいいのと躊躇しているところや、姫君が泣き出した場面から、彼らがどれほど不安に感じているかが伝わってくる。源氏は、姫君を彼のもとへ引き取ることを決めて行動しますが、その過程で周囲の反対や懸念を押し切ります。彼が姫君を連れ出そうとするとき、少納言が止められず、ただ従うしかない様子が描かれ、また、源氏は姫君に対して優しく接し、彼女の恐れや不安を和らげようとするが、その行動は源氏の意志の強さや、姫君に対する特別な思いを表している。この姫君を連れて行こうと決めたが、源氏の行動が周囲にどのような影響を与えるかという社会的な背景が描かれ、少納言が、宮が自分をどうお責めになるだろうと心配するところは、源氏が権力者であり、その行動が他者に対してどれだけ影響力を持つかを示している。このような社会的な力関係が、この物語全体に緊張感を与えている。姫君の心理も詳細に描かれ、突然の出来事に驚き、不安を感じている様子が、恐ろしく思うとか、震えが出るといった描写で表されている。しかし、姫君は泣くことをこらえ、源氏の言葉に従うしかない状況に置かれている。 源氏と姫君の関係を通して、源氏と姫君の関係がどのように始まったのかが分かるところである。源氏は姫君に対して優しさを見せながらも、彼女を自分の手元に置くことで運命を決定づけようとしていた。姫君と源氏の関係は、物語が進むにつれ、さらに深まっていき、源氏物語の中でも緊張感と心理描写が豊かな部分で、少納言たちの不安や、源氏の強い意志、姫君の幼い心情が描かれ、物語全体に重要な影響を与える出来事が描かれている。この部分を理解することで、物語の中での登場人物たちの関係性や、源氏の行動がもたらす影響について深く考えることができる。源氏は二、三日御所へも出ずにこの姫君を懐けるのに一所懸命、手本帳に綴じさせるつもりの字や絵を色々と書いて見せたりしていた。源氏は、姫君のことをまだよく知らないにもかかわらず、彼女を見たときに自然と心が引きつけられると感じて、その感情を、武蔵野に生える紫草に例えている。武蔵野という地名を聞くだけで、その野原に紫草が咲き誇る様子を思い浮かべ、自然と心が動かされるように、姫君の姿に強く引きつけられる。
2024.09.02
コメント(22)
-

源氏物語〔5帖若紫 23〕
源氏物語〔5帖若紫 23〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語5帖若紫の研鑽」を公開してます。少納言は源氏の使者である惟光に対して、心の内を語った。少納言は、源氏の求婚が将来どうなるかはわからないが、現時点では不釣り合いな関係だと思っている。若紫はまだ幼く、源氏の意図を理解できる年齢ではないと思う。そんな中、源氏が熱心に縁組を進めようとしていることに、少納言たちは不安を感じている。少納言はさらに、今日も藤壺の宮様が、この子は女の子だから、しっかり守ってあげなさい。油断してはいけませんと仰った時、私たちはなんだか心が落ち着かなくなり、昨晩の出来事を思い出しては話しあっており、源氏が若紫と一夜を共にしたことをほのめかしていた。少納言は心の中で嘆きつつも、あまりに悲しげな様子を見せると、惟光に若紫の純潔を疑われるのではないかと心配していた。このような感情の葛藤が少納言の中で繰り広げられていた。惟光は少納言の話を聞き、源氏に報告した。これに対して源氏は、若紫が住んでいる家の状況を哀れに思いながらも、一夜を共にした以上、責任を取って引き続き訪れる必要があると考えた。しかし、源氏はその行動をためらっていた。なぜなら、世間がこの関係を、酔興の結婚(軽はずみな関係)と批評するかもしれないからだった。源氏は悩んだ末に、若紫を二条の院へ迎え入れるのが最良の策だと考え、源氏は頻繁に手紙を送り、日が暮れると惟光を見舞いに出していた。源氏は手紙に、やむを得ない事情があって伺えないのを、不誠実と思われていないか不安だと書いていた。これに対して少納言たちは、宮様が急に明日迎えに行くと仰ったため、準備に追われていると返事した。源氏は、若紫を二条の院へ連れて行く計画を立てていた。しかし、それが彼女にとってどのような影響を及ぼすか、また世間からどのように見られるかを深く考えていた。源氏は自分の行動が軽はずみではなく、若紫のために最善の選択をしたいと思い悩んでいた。翌朝、源氏はまだ夜明け前に行動を起こしていた。彼は静かに大納言家へ向かい、少納言と対面する。少納言は、源氏がなぜこんなに早く来たのかを不思議に思いながらも、源氏が宮様のもとへ向かう前に一言話したいと伝えたことで、少し安心していた。深く読んでいくと、源氏の内面の葛藤と、少納言たちの不安が描かれている。源氏は若紫に対する愛情を深め、彼女を守るためにどうすべきかを慎重に考えており、その過程で源氏の誠実さと優しさが垣間見えている。
2024.09.01
コメント(22)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- ビーシュリンプ、クリスタルレッド
- エビ水槽、「さと美えびフード」を与…
- (2018-10-29 19:27:33)
-
-
-

- ゴールデンレトリーバー!
- 【まとめました】大型犬の北海道引っ…
- (2024-09-26 07:44:12)
-
-
-

- MIX(雑種)だってかわいい!
- 今年も予防シーズンのお知らせが届い…
- (2025-03-06 12:17:49)
-