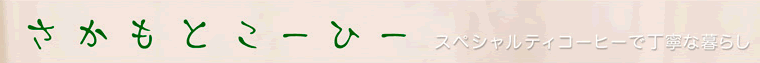カテゴリ: コーヒーの焙煎を考える
なんだか、野暮用が多くて、バタバタしてます。
間があいてしまいましたが…
「コーヒーの焙煎を考える(27)」
です。
「味のしくみ」から、
*香りをつくる物質(香りの正体)乾熱調理
「糖類のカラメル化」「脂肪の加熱と香り」
「メラノイジン」ときて、
今回は、
「よいおこげ」をつくるには、
温度調節が大切です。
蒸したり、煮たりの湿熱調理は、
水の沸騰温度が1気圧のもとで100℃なので、
水があるかぎり通常100℃以上に上がる事が
ないですが…
焼く調理の乾熱調理は、
調節しないでおくと相当高くまで温度が
上昇してしまいます。
「よいおこげ」の香りをだすためには、
カラメル、ディープフライフレーバー、
必要です。
そのためには、
100℃以上の高温が必要ですが、
長時間加熱したり、
必要以上の高温になると、
嫌なにおいがでたり、
炭化して黒くなり、
口当たりがわるくなります。
よい香りを得るための温度の範囲は…
だいたい150℃から200℃の間です。
しかし、
200℃以上になるとたいていのものは、
においが悪いほうへ変化します。
あまり、
急速に加熱するよりは、
ある程度ゆっくりと加熱したほうが、
よい香りを得るのに適している。
この辺に、
焙煎のロースティング行程のポイントが
あると思います。
ある温度から、ある温度までを
ロースティング行程と考え、
その間をどの位のスピードで焙煎するか。
早くても遅くてもいけない、
と、言うよりも、
一番効果的なスピードを見つけることでしょうか。
早くても遅くても、
成分の発達が悪いと思います。
間があいてしまいましたが…
「コーヒーの焙煎を考える(27)」
です。
「味のしくみ」から、
*香りをつくる物質(香りの正体)乾熱調理
「糖類のカラメル化」「脂肪の加熱と香り」
「メラノイジン」ときて、
今回は、
「よいおこげ」をつくるには、
温度調節が大切です。
蒸したり、煮たりの湿熱調理は、
水の沸騰温度が1気圧のもとで100℃なので、
水があるかぎり通常100℃以上に上がる事が
ないですが…
焼く調理の乾熱調理は、
調節しないでおくと相当高くまで温度が
上昇してしまいます。
「よいおこげ」の香りをだすためには、
カラメル、ディープフライフレーバー、
必要です。
そのためには、
100℃以上の高温が必要ですが、
長時間加熱したり、
必要以上の高温になると、
嫌なにおいがでたり、
炭化して黒くなり、
口当たりがわるくなります。
よい香りを得るための温度の範囲は…
だいたい150℃から200℃の間です。
しかし、
200℃以上になるとたいていのものは、
においが悪いほうへ変化します。
あまり、
急速に加熱するよりは、
ある程度ゆっくりと加熱したほうが、
よい香りを得るのに適している。
この辺に、
焙煎のロースティング行程のポイントが
あると思います。
ある温度から、ある温度までを
ロースティング行程と考え、
その間をどの位のスピードで焙煎するか。
早くても遅くてもいけない、
と、言うよりも、
一番効果的なスピードを見つけることでしょうか。
早くても遅くても、
成分の発達が悪いと思います。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[コーヒーの焙煎を考える] カテゴリの最新記事
-
プロのつぶやき1105「さかもとこーひーの… 2021.05.02
-
プロのつぶやき1104「スペシャルティコー… 2021.04.25
-
プロのつぶやき1076「さかもとこーひーの… 2020.10.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(128)スペシャルティコーヒー
(1414)ニカラグア・エルサルバドル産地巡り
(9)美味しい暮らし
(279)コーヒーのコク研究
(49)コーヒーの焙煎を考える
(61)さかもとこーひー、5つのこだわり
(11)フードペアリングの方程式
(56)僕の好きな紅茶
(34)サンプリング倶楽部21
(23)コーヒービジネスを考える
(77)Comments
© Rakuten Group, Inc.