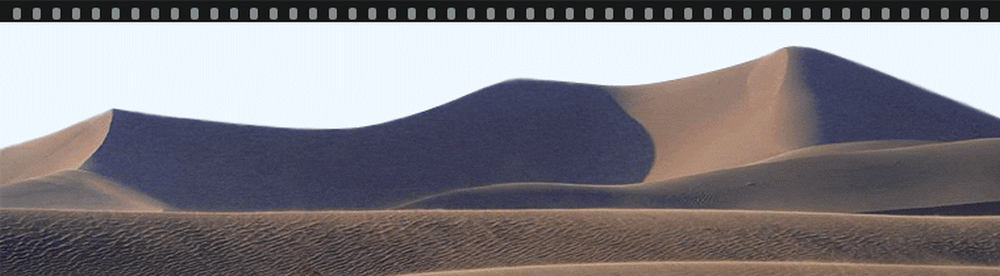[カテゴリ未分類] カテゴリの記事
全4696件 (4696件中 1-50件目)
-
2070000ヒット、ありがとうございました!『ラズーン』第七部 4.白亜燃ゆ(1)
**************** それは封じられた物語のはずだった。「ラシル!」 悲痛にも聞こえる叫びが、『氷の双宮』の門扉の前で震えながら待っていた父親の喉から搾り出される。「こっちよこっち! 早く!」「お母さん、お父さん!」「お前、なんてことをお前!」 門の外から泥だらけになりながら駆け込んできた幼い少女は、片足が千切れた布の人形を抱えている。「ごめんなさいごめんなさい、でもどうしても、アサドちゃんのものだから!」「ああああ!」 悲鳴を上げて母親が少女を掻き抱く。少女の手から滑り落ちかけた小さな人形は、今にもばらばらになりそうで、あちらこちらに血の跡がある。「落としちゃったの、お椀は溝に、落としちゃった!」 安全な場所で、温かな父母の腕に抱えられて、無力を嘆く少女は気づいていない、自分がどれほど幸運だったのか。そのささやかな幸運さえ手に入らず、この門に辿り着けずに果てた命のことを、少女が思い及ぶのはいつだろう。数日後か………それとも数十年後か。『ラズーン内壁の中はもう戦場だ』 門の際に立ち、人々と『運命(リマイン)』を選別し終えたアシャのことばに、誰もが凍りついて彼を眺めた。 まさか、と微かな声が広がる。 まさか、そんなことが。 まさか、あなたが、そう言うなんて。 だがそのざわめきは、不安の色を濃くする。 『金羽根』が門の中へ戻り始めたのを見たからだ。 なぜだ。 問いは酷い答えを返す。 既に、この門の外に守るべきものはいない。 人々は沈黙したまま、俯きがちに項垂れて門の中へ入ってくる『金羽根』を見つめる。 美しい『銀羽根』は? 誠実な『銅羽根』は? 武勇に優れた『鉄羽根』は? ラズーン外壁に敵さえ寄せ付けない『野戦部隊(シーガリオン)』は? いない。 もういない。 もう誰も、この門の外で守りを固めて戦うものはいない。『これより先、再びこの門が開かれることがあるのか、それとも、もう二度と人の世に戻れないのか、誰にもわからない』 『氷の双宮』の奥で『太皇(スーグ)』が招いてくれていると、一時の安堵に緩みかけた心を引き絞る、冷徹で静かな声だった。 ラズーンの光の王子と呼ばれていた青年が、明るい希望の象徴だった存在が、自分達の命を容赦無く秤にかける、そんな冷ややかな断罪者だったなんて。 静かに視線を投げるアシャに、怯えた顔で両親は幼い子どもを抱え込み、引き下がり、その視線に触れぬように我が子を背後に庇った。 食い入るように見上げる瞳を、アシャは無表情に見返し、呼ばれたように視線を上げる。 『双宮』の彼方に、水を満たさぬ噴水の向こうに、佇む一人の老人を認めた。 穏やかな表情のまま、『太皇(スーグ)』がゆっくりと頷く。 行くが良い。 アシャも頷き返す。 参りましょう。「アシャ!」 思わずびくりと体が震えた。「俺達も戻ってるぞ、アシャ!」「…イルファ…」「俺達が必要か!」 野太い声は響き渡った、沈み落ちる人々の上に。「……必要だ」 アシャは掠れた声で返した。「この先の世界に、必要だ」「……お前もだ!」 イルファが一瞬、胸が詰まったような顔で淀み、すぐに言い放った。「お前も、この先に必要だ!」 違う。 アシャの呟きを察したのだろう、イルファの顔が赤らむ。側に立ち竦むレスファートの頬に次々と涙が伝わっている。敏感で繊細なレクスファの王子には、アシャが何に成り果てるのか、気づいてしまうのだろう。その側に、やはり凍りついたように立つレアナの顔は青白く、かつて見た柔らかさも朗らかさもない。 それが正しい、この世界の『人』ならば。 破滅のありかを察したならば、覗き込もうとさえしないはず。「帰って来い!」 イルファが吠える。「帰って来るんだ!」 お前は、俺の、アシャだろう!「…相変わらず」 苦笑いをアシャは浮かべる。「どうしようもないことを」 くるりと背中を向ける。視線は背中に叩きつけられている。憎悪と恐怖と懇願と悲哀に満ちた、『人』の視線。 歩みを止めるな。 言い聞かせながら、アシャは開いた門を離れていく。 立ち止まるな。 既に全ての流れは崩壊に向けて動き始めている。 背後で重々しく音を響かせながら、『氷の双宮』の門が閉まる。 アシャはようやく振り返った。 聳え立つ、白く清冽な、守りの壁。 『人』の命を保持し、『運命(リマイン)』の命を断ち切るシステム。「……本当は、ずっと昔に」 アシャは雨が止んで深く澄み上がり始めた空を見上げる。「ずっと昔に、滅んでいたはずなんだ」 最後の因子の俺が消えれば、全てが終わるはずなんだ。 体から金色の光が舞い上がった。見る見る光度を上げ熱を帯び、広げた掌から踏み締めた足元から、乱れる髪と呼吸に弾む体から、炎が立ち上がり白い壁に這い寄っていく。 やがて壁に炎は辿り着いた。あっという間に壁を伝って範囲を広げ、世界を焼き焦がしていく。 それは封じられた記憶の中に宿る光景そのものだった。 かつて繁栄の限りを尽くした人類という生命体が、己の欲望から自らを焼き尽くす業火を生み出し、世界を崩壊させていく光景だった。**************** 今までの話はこちら。(ラズーン用)2070000ヒット、ありがとうございました!遅れてしまい、申し訳ありません。が、地道にぼつぼつ書き溜めておりますよ!メルマガの『ドラゴン・イン・ナ・シティ』と同じく、おおよその骨格はありますが、毎日の中での発想やふと引っかかったことなどを含めて展開しているようなので、色々とギリギリで書いている感覚です。構築とか伏線とか難しいことが考慮されていません(こら)キャラクターも変わっていってしまう恐れがありまして、ヒヤヒヤしています。元々考えていたタイトルは『AD3500』でした。このAD3500というのは、『DRAGON NET』に関わるお話です。けれど、それを読んでいなければ読めないわけではない……ほんと、作者のお遊びです。実は『ラズーン』の方が元ネタで、それが『DRAGON NET』に流れた感じです。でも、『DRAGON NET』に流れたおかげで、自分の中に意味合いが深くなり、少し変わった部分もあります。一時期「わーこうなると全部繋がる!」と楽しくなって組みましたが、逆にこだわりすぎると身動き取れなくなるなあと考えているとことです。後々真実に迫る人も、実はこの人じゃなかったです。イルファも思ったより立派だった(笑)頑張って繋いでいきます。楽しんでいただけると嬉しいです。
2024.10.18
コメント(2)
-
2060000ヒット、ありがとうございました!『ラズーン』第七部 3.武君散る(4)(5)
**************** ひや、と首を竦めながらも、咄嗟にユーノの体は反応した。 雨が降り、夕闇の中で一つ一つ敵を誘い込み追い込む場所を確認し終わって、レスファート達のところへ戻ろうとした矢先、南門付近で響いた激しい叫びと怒号に振り向いた瞬間のことだった。 抜き放った剣を構える前に体を引いたのは正しかった。首間近を掠めた切先、既に懐まで接近を許したと気づいて、体を捻りながら周囲を睥睨する。降り始めた雨の中、通りを前後から満たすようにじりじりと迫る集団、マントを羽織っていたのをそれぞれに脱ぎ捨てていく。奇襲を避けたユーノの挙動で、マントが邪魔になると判断した辺りが並ではない。「…貴公らは何者か」 呼び掛けたのはこちらの緩みを演出している。こんな状況で、まだ「何者か」を問うような神経では、さっきの動きは偶然だろうと思わせたかった。同時に薄暗闇の中、灯ひとつも掲げずに詰め寄る敵の情報が欲しかった。「…」 沈黙が返る。集団の長はいない様子だが、統制が取れている。誰一人、動揺を見せることもなければ、こちらの問いに応じる気配もない。騎乗しているのが8割、残りは徒士だが巧みに物陰へ身を潜めていく。緩まない。こちらが誰だか、十二分に知っていて、油断をしない。 南門近くの騒乱は次第に静まりつつあった。鎮圧されたのではないだろう。地を響かせる振動は平原竜(タロ)のものに似ていた。ラズーン内側の準備は十分ではないのに、南門付近で戦闘があった。平原竜(タロ)が入り込んでいるのなら、答えは一つだ。 「何者か」が南門を開け放ち、外で戦っていたジーフォ公の背後を強襲、挟撃された『鉄羽根』は必死に防戦で野戦部隊(シーガリオン)を引き連れ南門へ退避、外部から攻め込んでくる『運命(リマイン)』軍を防いだ。けれども、南門を開いた「何者か」も恐らくはラズーン内に戻っている。だから『鉄羽根』と野戦部隊(シーガリオン)は無闇に追撃せず、「何者か」の動きを伺っている。 ここは既に戦場となった。(レアナ姉様、レス…) 駆け去っていった少女が脳裏を横切る。 あそこにはイルファが居る、アシャも『氷の双宮』から戻ってくる。大丈夫だ。 むしろ、こちらに少しでも「何者か」の戦力が裂かれれば重畳、多少でも削れれば時間が稼げ、まだ生き延びる道がある。「一つ、わかった」 ユーノは馬上で微笑んだ。「貴公らは、私の敵だな」 気合いも発語もなく、一斉に前後から徒士が駆け寄ってきた。我が身を踏み潰させても足止めをする策、命じた者は居ないだろうに剣を振り上げ大手を広げて駆け寄ってくる。声を出さないのは所在を明らかにしないため、では意外にこちらの勢力も南門内に戻って来れているのかも知れない。 ならば。「うぉあああああああ!」 肚の底から大声を張り上げ、ユーノは自ら一番手前の群れに突っ込んだ。元より騎馬で駆け抜けられるとは思っていない。数人を蹴散らし、その死骸を蹴り付けて飛び上がってくる相手を見定め必死に薙ぎ払う。四方八方背後から押し包むように飛び掛かる敵の動きに、ふと奇妙なものを感じた。(なぜ?) 戦況は動いている。ここに集められた兵士は精鋭だ。『運命(リマイン)』を思わせる鋭くて重い剣捌き、一太刀で躱せる攻撃などなく、二度三度と切り結びながら、ようやく退ける。(なぜ、これだけの兵を私一人に集めている?) ユーノに余裕など全くない。かろうじて切り抜けているが、それほど待つまでもなく馬を捨てなくては身動きできなくなるし、捨てた瞬間に雪崩れ込まれては、さすがに防ぎ切れないはずだ。なのに、その好機を待つこともなく、仲間の消耗さえ気にしない攻め方に違和感がある。(まるで、私が誰だか知っているみたいだ) 優れた剣士と見做しただけではなく、ユーノが『誰』だか知っているから、どれだけ兵を使い捨てようと、ここで始末をつけようとしている。「っっ」 その瞬間、身体中の毛が立つような怖気が過った。 怖さではない、むしろ意外さの余り、けれど気づいてみれば、ユーノの死を願うこの粘着度合いはよくよく見知った男のものではないか。「…カザディノ…?」 一瞬の隙に振り上げた顔、呟いた声が聞こえたはずもないが、襲いかかる兵士の彼方、男達の中でただ一人まだマントを着ている男が、ゆっくりと頭の布を背後に払い落とすのが見えた。薄く笑っている顔は、カザディノと似ても似つかない、けれどもその笑みには他の誰とも区別できる下卑た昏い嘲りが満ちている。「何……?」 ユーノの脳裏に閃いたのは、『運命(リマイン)』に体を明け渡した相手との一戦、別人の顔をしたカザディノだと理解した途端、次々飛び込む兵に馬が囲まれ、飲み込まれそうになる。舌打ちしながら、手近の兵を切り捨て、その体を踏み台に、視察官(オペ)の剣を奮いながら、もう一度相手を見遣るが、そこにはもういない。「く、そっ!」 理由は分からない、方法も不明、ただ一つ、直感が告げるのは、誰よりもユーノを惨たらしく殺すことを願う男が、今ここに、しかも生来のぶよついた脂肪の塊のような体ではなく、一廉の剣士として迫っていると言うことだ。(焦るな、不安に煽られるな) 周囲を囲んでいた数人を切り倒し、わずかにできた時間と空間に、ユーノは呼吸を整えた。既に周囲は死体の山だ。なのにためらうことなく走ってくる兵達は虚ろで死んだ瞳をしている。下の方に積み重なっている体は溶け崩れ始めているのだろう、腐臭が周囲の空気を侵す。ふ、と小さく息を吐いた瞬間、四方から突き出された剣を払い、最後に目の前に突き出された剣先を受け止めた。「久しぶりだな、ユーノ・セレディス」「…ずいぶん、見栄えが良くなったじゃないか」「今ならレアナに似合いだろう?」 噛み合った剣の向こうで、相手はへらへらと嗤った。弾き返そうにも力が強い。蹴りを加えようとしても体勢が崩れた瞬間に、周囲から兵が飛び込んでくるだろう。今取り囲んで手を出さないのは、ユーノを殺すつもりなら、相手もろとも刻む気でないと難しいとわかっているからだ。そうして、この相手を切り刻む予定は、周囲の兵には、ない。 好機だった。生きては戻れない襲撃に、僅かな綻びを生み出せるかも知れない。「どんなイカサマ薬を使ったんだ」「…我らは入れ替わることができるのだ」 ひゅ、と相手の瞳が小さな点のように縮まった。ギシギシと剣を鳴らしながら、首を左右にゆっくり傾ける。人形のような、何か別の生き物のような、折れ曲がる場所ではない箇所で無理やり曲がっているような不気味な動きだ。「感謝しろ、お前を屠るために、こんなところまでやってきたんだ」「お前の体はどこにある」「言わぬわ。安全な場所に、と言っておこう」 くつくつ楽しげに笑う相手に、ユーノは思考を巡らせる。なるほど、『運命(リマイン)』は別の体に乗り移ることができる、その秘法の一つなのだろう。カザディノはユーノを自分の手で始末したくて、『運命(リマイン)』の体を使い戦場に出てきているが、自身の体は離れた場所で傷つかぬように保管されているのだろう。たとえこの体を倒したところで、カザディノは傷一つついていないと言うわけだ。「見下げた奴だな」 ユーノは吐き捨てた。「少なくとも、他国の王は自分で軍を率いたぞ」 剣の間からギチっと耳障りな音が響いた。「勝利を得ればいいのだ」 じりじりと押される。「どんな手段を取ろうと、勝利を得れば正しいとされる。それが戦と言うものだ、女子どもには分からんだろうが」 ぬらりと唐突に唇の間から灰色がかった暗紫色の舌がはみ出た。そのまま下唇を舐め、上唇へと回っていく。生臭い息が溢れ出す。「お前にどれほど苦しめられたか……あの苦痛を、さてどれほどの痛みで…示せばいいのか……悩んでいるのだ」 周囲の兵がゆっくりと囲みを狭めた。一重ではなく二重三重と囲みを増やす。「今も多くの兵を失った……子飼いの兵を幾度となく屠られた……指を1本ずつ切り落とし、その度ごとに女として悦ばせてやるのはどうだ? 痛みと快楽を繋ぎ、もっと酷く扱って下さいと頼むように薬で馴染ませてやろうか? ああ、それとも…」 力押しでのしかかってくる圧力は増すばかりだ。体を引けば突き出された剣の垣に串刺しになるだろう。膝を折って沈めば、そのまま押し切られて四肢を飛ばされ、今この場で蹂躙されるかも知れない。 残る体力と気力、唯一無二の反撃を狙う。命を惜しむ一瞬があれば負ける。 べろん、と舌が長々と口からはみ出て伸びた。先から唾液が滴り落ちる。「今ここで、全てを晒すのはどうだ。薄汚く傷まみれの体を、手首足首押さえつけて衣服を弾きはぎ、もうやめてくれと懇願するのを聞きつつ、剣で刻みながら貫いてやろう、もちろんここにいる全員で、お前の相手をしてやろうとも」 ふっと相手の瞳が呆けた。妄想が勝ったのか、勝利を確信したのか、あるいは故意に作った隙だったのか。それでもユーノには千載一遇、天啓が降り落ちた瞬間だった。「…っは…?」 圧を凌いでいた剣を離す。崩れ込む相手の腹に飛び込む。視界の端に捉えた斃れた兵の剣は二振り、片方は角度が悪くて掴みきれなかったが、もう片方は引き抜けた。相手の足首を力の限り薙ぎ払う。頭の上で絶叫が上がり崩れ込んでくる体を盾に、もう一振りを掴み直し、そのまま真上に突き上げる。咄嗟に飛びかかってきた兵が、主人はこれまでと見切ったのだろう、次々とユーノの上に覆い被さった体もろとも貫けと剣を振り下ろしてくる。(それでも、ここなら) カザディノの体に匿われたまま、死ぬまでになお時間が稼げ、反撃ができる。 死を覚悟してユーノが唇を歪めた瞬間、がしりと腕を掴まれた。「っっ!」「よくも…よくも」 がぼがぼと血泡に溺れながら、のしかかる相手がユーノを覗き込んでいる。「こんなことを……小賢しい……」「っく」 突き立てた剣はもう掴み直せず、新たな剣を得る手段はない。もぞもぞ動く主人の体に攻撃が一旦こやみになる。「しかし愚かだ、私は死なない、こんなことは意味がないのだ、元の体に戻ればなんと言うこともない………」 ユーノを除いた両方の瞳が大きくなったり小さくなったりを繰り返している。握られた腕の先は血の気が引いて痺れるほどだ。はみ出した舌をゆらゆらさせながら、笑みらしきものに唇を釣り上げてようとした相手の顔が、ふいに固まった。「……戻れぬ………戻れない……なぜだ……戻れぬ……このままでは……死ぬ……シリオン……戻れると言ったのに……どういうことだ……どういうこと…………戻れ………」 ぶわりと瞳が開いた。開いた目から黒々とした液体が滴り流れ落ち始める。腐臭が濃くなる、いつかの『運命(リマイン)』の死体のように、カザディノを名乗った男の体が蕩けていく。(何が起こった?) 顔を歪めながらユーノが考えた瞬間、「ぎゃああああああ!!」 周囲を圧する悲鳴と轟音がいきなり周囲を満たした。耳を抑え、地に伏せる。「あ、つっ!」 熱風が吹きつけた。頭の後ろを熱くて痛い風が吹き抜ける。覆い被さっていた体の圧迫感が幻のように消え失せ、周りに攻め寄っていた兵の気配も消える。(この熱、この、炎……アシャ…?) 背中を叩きつけるような熱が残るが、周囲に広がった静けさに体を起こし、ユーノは呆然とした。「な…に……?」 周囲のあちらこちらが燃えている。「何……これ…は…」 見回して息を呑む。 先ほどまで囲んでいた兵は、下半身しか残っていなかった。しかも薄黒く焦げたような塊となって、腰から下が並んでいる。緩い風が吹いて、そのうち一体が揺れた。傾いで、隣の腰にぶつかり、がさっと音を立てて倒れ、粉々に崩れていく。「何…だよ…これは……」 零れた自分の声があまりにも頼りなくて、思わずユーノは口を手で覆い……視線を感じて目を上げた。「………アシャ…」「……」 少し離れた場所に、アシャが立っている。 無事かとも聞かず、微笑みもしない。 静かにユーノを眺めた後、ゆっくりと背中を向ける。「アシャ………アシャ!」 張り上げた声では引き止められなかった。遠ざかろうとする相手を追おうとして、足に力が入らずに転がった。震えている、全身、この世ならぬ力を見せられ、しかもそれがどれほどの代償もなく放たれたと理解して。(あのアシャを、葬る?) 誰にそんなことができるのか。「く、そおっっ!」 力の抜けた足を殴った。傷つけられていた部分が新たに血を吐く。「くそ、くそおおおおっ!」 必死に力を取り戻そうと叩き続ける。(アシャ、待って) 視界がぼやけた。(一人で行っちゃ駄目だ) 振り仰ぐ。どんどん小さくなる後ろ姿、炎が舞い飛ぶ中に消えそうだ。「アシャあああああああ!!!」 天を仰いで呼んだ。「置いてくなああああ!!!」****************今までの話はこちら。2060000ヒット、ありがとうございました!(ぜいぜい)とは言え、もう次が迫っております。今回のだって、2分割にして2070000ヒットに回せばよかったのにという声も聞こえるんですが、そもそも書かない自分を追い込もうとしてのヒット連載なので、書けたら上げなきゃでしょうと言い聞かせております。(4)(5)となっているのは、他のサイトでは二分割してあげたからです。もしこの長さは辛いよと言うことでしたら、こちらでも二分割しますね。アシャがブチ切れちゃいました。あらあら。歯止め効かない様子です。あらあらあら。どうするんでしょう。頑張ります。
2024.08.28
コメント(2)
-
2060000ヒット、ありがとうございました!
と言ってる間に、既に5000オーバー、しかも3000/日越えヒットと言う、いつぞやの方、もしくは方々の気配が濃厚ですが(苦笑)。2060000ヒット分、地道に書いておりますよ。どう言う形であれ、どう言う意図であれ、ヒットを上げて下さったことを活かしたいです。ありがとうございます。色々物騒なことが起こって、心配が募っている世界で、読んでくださってありがとう。頑張りますね。以下、続きを少し。もうしばらくお待ちください。**************** ひや、と首を竦めながらも、咄嗟にユーノの体は反応した。 雨が降り、夕闇の中で一つ一つ敵を誘い込み追い込む場所を確認し終わって、レスファート達のところへ戻ろうとした矢先、南門付近で響いた激しい叫びと怒号に振り向いた瞬間のことだった。 抜き放った剣を構える前に体を引いたのは正しかった。首間近を掠めた切先、既に懐まで接近を許したと気づいて、体を捻りながら周囲を睥睨する。降り始めた雨の中、通りを前後から満たすようにじりじりと迫る集団、マントを羽織っていたのをそれぞれに脱ぎ捨てていく。奇襲を避けたユーノの挙動で、マントが邪魔になると判断した辺りが並ではない。「…貴公らは何者か」 呼び掛けたのはこちらの緩みを演出している。こんな状況で、まだ「何者か」を問うような神経では、さっきの動きは偶然だろうと思わせたかった。同時に薄暗闇の中、灯ひとつも掲げずに詰め寄る敵の情報が欲しかった。**************** 今までの話はこちら。
2024.08.14
コメント(0)
-
2050000ヒット、ありがとうございました!『ラズーン』第七部 3.武君散る(3)
****************「…そろそろここも危なくなってきたようです」 イルファの声にレアナが顔を上げた。『氷の双宮』で退避する人々の選別をするアシャに付き添って、そのまま残るかと思われたのに、アシャと一緒に戻ってきて、労うイルファ達に強張った笑みを見せながら、それでもことば少なく沈み込んでいる。 アシャはレアナを気遣う素振りは見せたものの、ユーノがラズーン内を見回って、未だ夜になろうというのに戻らないと聞いて、あっさり出かけた。もちろん、夜が明け次第、イルファやレスファートには早々に『氷の双宮』への退避を命じていたが、表情は厳しく、心ここに在らずという様子だった。「…お支度を」「…はい」 促しに応じて、レアナはふらふらと立ち上がり、部屋の隅で持ち物を確認しているレスファートやジノの元に近寄り、それでもとても手伝える様子もなく、ぼんやりと座り込んでしまう。が、ふと、何を感じたのか、顔を上げて振り向いた。「…アリオ様は」「『西の姫君』は」 ジノが幾分冷ややかな声で言い捨てる。「アシャ様が戻られるまで動かないと言われて、お部屋に籠もられたまま、侍女も全て追い出されていますよ」「部屋に?」 不安そうにレアナが眉をひそめ、立ち上がる。「先ほどアシャが戻ったのを誰も伝えていないのですか」「お伝えはしました、が」 ジノは溜息をついた。「返答はありませんでしたので」 忌々しげな口調から、どれほどアリオが周囲に疎まれていたのかよくわかる。だが、イルファもレアナと同じ不審を抱いた。「出てこない? あのアシャを追いかけ回すことしか考えていない女が?」「イルファ様…」「一緒に見に行きましょう」 アシャも関心がないのは明らかだが、それでも一人捨て置くわけにはいかないだろう。イルファは気がかりそうに頷くレスファートに頷き返し、レアナとともにアリオの居室に赴く。イルファ一人では踏み込めないが、レアナが同行しているのなら問題ないだろう。 屋敷は不安げなざわめきに包まれていた。部屋を出ると確かに遠くに轟くような音が響いている。外壁の向こうの音にしては近いと気づく。「ちょっと失礼」 イルファは帯剣してレアナの前に立った。「敵、でしょうか」「かも知れないですね」 レアナが頷き、イルファの背後に身を寄せる。賢い姫君なのだろう、とイルファは思う。平和な世であれば、十分賢くて魅力的な姫君だ。けれど、今この動乱の時期においては、自分で自分の身を守れない、それだけでも荷物になってしまうのは確かだ。ましてや、自分の闇を必死に背負おうとしているアシャには何の助けにもならない、可哀想だが、と肩を竦める。 アリオの居室近くには人の気配がなかった。ほとんどがアシャの命令に応じて、退避の荷物をまとめ、レスファートやジノ達の側へ集まり始めている。「…アリオ様」 閉められた扉を、ことこととレアナは叩いた。「お休みですか、アリオ様。アシャ様が戻られ、『氷の双宮』へ退避するようにと命じられています。一緒に参りましょう」 応答はない。頷いたイルファに、唇を引き締めて、レアナは扉を開いて呆然とする。「いない……」 イルファは部屋に踏み入った。窓がしっかり閉められており、部屋に荒らされた様子はない。飾り物や荷物をまとめた様子はないが、人の気配が全くない。「…イルファ様……上着の類がないようです」「ふん……自分で出て行った、か?」「でも、どこへ」 確かにアリオは強気で負けず嫌いな女性だが、それでも『姫君』であり、一人でどこかへ向かうことはあり得ない。しかも、雨が降り風も出てきた悪天候の中、夜にかかろうとするこの時間に動き出すとは思えない。「…」 イルファは扉近くに跪いた。床に落ちている黒々とした泥を見つける。「泥…? どこから、そんなものが」「……こちらへ続いていますね」 イルファは注意深く床を眺めた。廊下をそれと知って探せば見つかる泥汚れは、足跡に見えないこともない。奥まった方に進んでいく標を追って、イルファは庭に出る扉に辿り着き、開け放って顔を引き締めた。 一面に広がる、重い武具をつけた足跡が雨に叩かれ濡れている。「イルファ様?」「…朝では遅い」 イルファはすぐに向きを変えた。レアナを急き立て、廊下を戻る。背中に冷や汗が流れる。頭の中で素早く屋敷に残った人員を数え、舌打ちをする。戦えるものは数名に過ぎず、守る女子どもが多すぎる。いつの間に、あんなところまで侵入を許し、しかも誰にも気づかれず立ち去られた? 意図は何だ? そいつらはどこにいる? 今何をしている?「すぐに『氷の双宮』に向かいましょう」「で、でも」「もうここは、戦場です」「っ」 レアナが青ざめる。そうだろう、こういうのが普通だな、とふいに苦笑が湧いた。ここのところ常識はずれの連中ばかりと付き合ってきたから、ずいぶん『当たり前』の反応が新鮮に見える。「大丈夫ですよ、レアナ様」 にかっと笑って見せる。「外にはアシャもユーノもいる。まだ奴らが雪崩れ込んできているわけじゃない。何とかなります」「あ…」「おっと」 ぱん、と背中を叩いてやると、相手がよろめいたから慌てて支える。レスファートに見られていたら、だからイルファは、と詰られるところだ。「ただ奴らの意図がわからないのが……誰だ」 ふ、と少し先に気配が動いて、イルファは身構えた。レアナを背中に素早く庇う。「ここに居た連中は、今南門内で野戦部隊(シーガリオン)とやり合っている」 静かで虚ろで冷ややかな声が応じた。「…セシ…公…?」「『金羽根』にも『氷の双宮』への撤収を命じた」 薄暗い廊下の端から揺らめくように姿を現した相手に、イルファは呆気に取られる。乱れた髪の毛、雨に濡れたのだろう、泥に汚れ、いつも冷然と煌びやかな美しさとは全く重ならない姿で、それでも瞳だけは異様に鋭く、セシ公はイルファを見据える。「あんた、どうしたんだ」 思わず尋ねたイルファに、セシ公はそそけ立ったような頬に苦い笑いを浮かべた。「礼を失しているのは謝ろう。しかし今夜中に『氷の双宮』へ待避するのは正しい。ここももう、そう長くは持つまい」「…どういうことだ。まさかラズーン外壁が破られたのか」「…カート……いや、ジーフォ公が没した」「は?」 なぜそれを知っている、と続けようとしたイルファに、セシ公は首を振る。「予定より早く、南門は開かれ、敵が入り込んだ。ラズーン内へ引き入れて展開する策は、不十分にしか展開できない。籠城するしか手がなくなるかも知れない」「…アシャとユーノは知ってるのか」「おそらくは、気づいているはずだ」「……連絡も出せないほど、こっちが分断されているのか」 セシ公が頷き、イルファは大きく息を吐く。「わかった。急ぎ、『氷の双宮』へ避難だな。その後は、状況を見て俺も出る。守りはあんたに頼むぜ」 それぐらいはできんだろ、と胸の奥で唸った声が聞こえたのかどうか、生気がない様子で頷くセシ公に、レアナが一歩踏み出す。震える声で、両手を握りしめながら問う。「アリオ様がいらっしゃいません。何かご存知でしょうか」 イルファは少しレアナを見直した。これだけ無茶苦茶な状況を突きつけられて、それでも踏ん張ろうとする努力は認めてやってもいい。「…アリオも逝ったよ、ジーフォ公とともに」 背中を向けたセシ公が密やかに答えを返し、微かに歯軋りの音を響かせた。**************** 今までの話はこちら。 いやいや、もう2060000に近いのに、今更上げるなんて、と胸の中で声はするのですが。 すぐに2060000来るから、置いておいてもいいのに。 いや、それでもほら一応、全然間に合ってないけど、書けたから。 次がまた10000ぐらい遅れそうだけど、それでもとにかく進められてるなら。 と言うことで、再びの感謝を皆様に。 なんだかラズーンはどうにもならないような気配がしてきましたが、それでもちゃんと予定通りには進んでおります。人の想いとは別に淡々と進んでいく現実が否応なく押し寄せてきて、誰が生き残れるのかいささか危うい様相です。 それでもこれは、ハッピーエンドになります。 何年かかろうとも。 人生の変わり目と言うのは、いろいろ思いもかけないところで降りかかってきます。 予想外。想定外。今回もそれだ。変わり目に突っ込まれてる最中です(笑)。 けれどその翻弄されつつある中で初めて、メルマガ3本満杯までセットできました! ご愛読くださっており、しかも遅刻を繰り返す書き手を、温かく見守ってくださってる読者様。 ありがとうございました。8月中旬までは予定通りに届きますよ!(当たり前ではないのか) で、『猫たちの時間』の『そして、別れの時』と『SSSシリーズ』とが終わったら(『ドラゴン・イン・ナ・シティ』はまだまだ終わらないです)、その空き枠で『これは〜』と『闇を〜』メルマガでやりますね。そうでもしなければ、書けないのかも知れないし。 ではでは。 お楽しみくださいませ。
2024.07.10
コメント(0)
-
2040000ヒット、2050000ヒット、ありがとうございました!『ラズーン』第七部 3.武君散る(2)
**************** 何を考えているのか。「私が聞きたいところだ」 冷ややかに嗤いながら、リヒャルティを置き去りに、セシ公は自室から持ち出した紫の布包みを手に、パディスへ馬を走らせた。長丈草(ディグリス)を風を読みながら巧みに馬を駆けさせる。昔ながらの技だ、造作もない。懐かしささえ感じるぐらいだが、腹に抱えた布包みの冷たさが、いや背中を伝い落ちる冷や汗が、ただ不安だけを増幅させる。 なぜ踏み込まない、あの『氷の双宮』の中へ。 ユーノは『氷の双宮』の外を巡回し、逃げ遅れた民を誘導し、レアナやイルファ、レスファートが『氷の双宮』に入った後、その外側で野戦部隊(シーガリオン)と共に、押し寄せてくる『運命(リマイン)』軍に立ち向かうと言っていた。アシャもまた、全ての民の避難を見届けた後、ユーノと同様、『氷の双宮』の外の守りに着くと話している。 それでは、誰が戦後の混乱や民の統率を引き受けるのかと言う問いには、『太皇(スーグ)』がおられると、一言で済んだ。アシャの気配の危うさは、既に多くの知るところとなりつつある。かつて、ラズーンの第一正統後継者としての輝きは見る影もなく、誰も口には出さぬが、この戦乱が終結した際に、その命が残っていない方が良いのではないかと囁く者さえ居る。 そうしてそこに、セシ公の名前が浮上する。 『太皇(スーグ)』お一人では心許ないが、四大公のセシ公が居られれば、実務にも支障あるまい。権威と実績、その両方が備われば、ラズーン復興も成し得るだろう。 だからこそ、本来セシ公は、こんな場所に居るはずがなく、単騎で動き回るなどあってはならない。 望んでいたはずだ、世界の全てを知ることを、何を犠牲にしても、何を代償にしても。 自身の魔性は十分に心得ている、今更恥じるものでもない。 なぜアシャの前をさらりと通り過ぎ、この内側で守りを務めると言い放てない。 全ては計算尽く、しかも一番安全な方法で、セシ公はラズーン内部の謎を暴き、手にすることができると言うのに、なぜこうも言いようのない不安だけが胸を塗り潰していくのだろう。「まさか」 未知のものへの恐れだと? いや違う、この不安の正体を、セシ公はよく知っている。 万に一つ、億に一つ、決して間違えてはならないものを、間違ってしまった時の感覚だ。 セシ公は何か致命的な過ちを犯しており、しかもそれに気がついていない。 戦局から離れ、頭を冷やして、全ての要因を考えてもみた。打てる限りの手を打った。可能な限りの策を講じた。ラズーンはぎりぎり生き延びられるはずなのだ。多くの兵と民衆を差し出し、肉を削ぎ落とし、かろうじて中心の骨格だけは残るはずなのだ。 何を見落としている。 何を。 放っておかない方がいいような気がする。 リヒャルティに話した瞬間、思い出せそうな気がした。けれどその代わりに、脳裏に閃いたのは、パディスから持ち帰った水晶の玉だ。未来が見えると言う、その伝え。 馬鹿馬鹿しいが、どうせ戦乱の中で破壊されるか失われるだろう、パディスに戻しておこう。 戦局が進めば、パディスも火の海となるかも知れない、行くなら今しかない。 西は不思議なほど静まり返っていた。 降り始めた雨のせいかもしれない。見る見るあたりが薄暗くなっていくが、セシ公は速度を緩めない。遺跡に着く頃にはかなり濡れてはいたが、それほど苦労なく馬を待たせて遺跡に上がる。 世界の混乱をよそに、遺跡の像の腕の中に、布包みを解いた水晶玉は、ずっとそこにあったかのようにずれ一つもなく収まった。「…アリオ・ラシェット…」 瞬間、脳裏に蘇った名前に、セシ公は訝る。 なぜ、今急に、ジーフォ公の婚約者のことが浮かぶ? 眉を寄せた途端、水晶玉の中に光が揺らめいた。はっとする間もなく、見る見る光が広がり溢れ、紅蓮の色を帯びる。覗き込むセシ公の頬を熱いほど照らす激しい炎。「『氷の双宮』が……燃えている……?」 見慣れた壁が、炎に這い寄られ纏いつかれて紅に染まっている。炎の勢いは強く、周囲に渦を巻きながら荒れ狂い、他には何も見えない。「…む」 違う。 炎の壁が中央で割れた。一筋細く走った道を、誰かがゆっくりと歩いてくる。業火の中とは思えない落ち着いた足取りだ。「…アシャ…」 『氷の双宮』を緩やかに振り返る仕草、水晶玉がその顔をよく見ようとでもしたように、画面が動き、歩いている人物の顔に焦点が定まる。 黄金色の髪、紫水晶の瞳、滑らかな頬、薄紅の美しい唇。 穏やかで静かな微笑はこの世ならぬ光を帯びているように見える。「アシャが……『氷の双宮』を……?」 画面が揺れた。ぐるりと回されるように、様々な光景が水晶玉の中を過って行く。 だが、光景は変わるのに、画面の光は変わらない。 燃えている。 ただただ燃えている。 ラズーンが全て、燃えている。 そして、その元凶であると思われる男は、慌てた様子も怯えた様子もなく、淡々とその場を歩み去ろうとしている。「…待て……」 セシ公は呻いた。「どこへ行く気だ」 アシャは振り返らない。「何をする気が」 声は届かない。「何を…したんだ」 画面はアシャの後ろ姿を追い続け、やがてアシャは焼け焦げた扉のようなものの前に立つ。「…南門……」 僅かに残る意匠でわかる、当たり前だ、死守すべく毎日毎日見つめてきた門だ。「やめろ…」 アシャは門に手を触れる。押し開く素振りさえなく、ただ指先を当てただけ、けれど門が軋みながら開いていく、どんな抵抗も許されぬように。「あなたは……何を…」 門の外に炎は及んでいなかった。内側だけを焼き尽くしていた業炎は、門を開かれ、新たな天地を見出して喜びに溢れたのだろう。アシャの後ろ姿を包むように追いかける。 ふと、アシャが振り返る。 まるでセシ公が見つめているのに気づいたような訝しげな顔。 片手を差し伸べて掌を立てる、視界を遮るかのように。 けれど、その半身振り返った姿の先には。「……」 ことばが出ない。 強く握りしめた指先が掌に食い込む。だが、緩められない。どれほどの窮状に追い込まれたとしても揺らぐことさえなかった意識が霞みそうになるのを、セシ公は必死に堪えている。 目の前の水晶球に映し出された光景が、紛れもなく真実だと、本能が告げていた。「…カート…」 雨降りしきる中、泥で汚れた女性を守るように抱え込む一人の姿がある。背中には無数の矢、体は切り刻まれて、紅蓮の炎に焼かれた目には薄黒く見えるが、恐らくは流れ出ている大量の血。その少し後ろに、主を守るかのように大手を広げて立つ姿にも見覚えがあった。 ならば、抱え込まれた女性の名前もわかろうと言うもの。 放っておかない方が良かった。 カートの妄執に近い情念を理解していたのに。 何かの手を、打てたはずだった。 打てたはずなのに、打たなかった。 たった一人の馬鹿な女のために、かけがえのないものを、失った。 初めて経験する、とめどなく流れる涙に呆然とするセシ公の前で、水晶玉のアシャは僅かに困ったように微笑み、ゆっくり掌を画面一杯に押し付けてきて、次の瞬間、水晶玉が砕け散った。 **************** 今までの話はこちら。 改めまして、2040000ヒット、及び2050000ヒット、ありがとうございました。 どなた様なのか、それともどなた様達なのか分かりませんが、1〜2日で数千カウントして頂いて、現在に至リます。それでも、ヒットはヒット。 何とか2040000ヒットの間に上げたかったのですが、なりませんでした。 ようやく1話上げたのですが、もう既に2050000ヒットから1800ほど経過しております。 ううむ、地道に先を書くしかあるまい。 あまりにも長く書いているので、文章だけでなく、ひょっとするとキャラクターも変わってきているかも知れない。終わるころには皆んな別人になっていたらどうしよう。けれども、これだけの戦乱なんだから、多少はみんな変わるかしら。 意外に大筋は変わっていません。 一番初めに書き出した頃から、この流れは考えていたし、今後の展開も多分変わらない。 変えていたらもっと描きやすかったかも知れない。 もっと違う流れも考えてはみたのですが、結局はこうなるみたい。 大筋を変えなかったから書けなかった、年齢も経験も全然足りなくて。 書ける人は書けただろうけど、私には無理でした。 書けるとわかっている今でも、これほど渋ってますもの。 何が苦手なのか。 書き終わったらわかるだろうか。 ううむ。 とにかく、まず1話。 こうでもしなくちゃ書かないのか、私。 筆不精な書き手(笑)を叱咤激励して下さるヒット、本当にありがとうございました。
2024.02.10
コメント(2)
-
2040000ヒット、ありがとうございます!でもごめんなさい。
え、あれあれあれ?正直なところ、そんな気持ちです。先日でしたよね、2030000ヒットにお礼申し上げたの。お約束の『ラズーン』が一章分もかけていなくて、一節だけ上げさせて頂いて。このペースでは次の2040000ヒットが来てしまう、と冗談半分のつもりだったのですが。ヒットカウント確認すると、3500/日ほどのヒットが2日。そりゃあ、行きますわ、2040000ヒット。けれど、このヒット、読まれた記事はカウントされていない。つまり、ヒットだけ、ってことなのかな?で、2040000ヒット越えてから、また再び3000台のヒットが1日。で、既に2045000近くになろうとしております。さて、これをどう考えたものだか。読んで頂いた記事はなさそうと言うのが何とも切ないですね。ヒットを上げて下さった、と言う事実だけが残っておりますが。しばらく考え込みましたが、単純に向き合うことにしました。つまり、2030000ヒットで一節挙げただけの『ラズーン』、次の一節をもう上げなくてはならない事態です(笑)。でもごめんなさい、まだ書けておりません。今はまずメルマガ『ドラゴン・イン・ナ・シティ』の先週分+今週分(をい)を地道に書いておりますので、それが済み次第、『ラズーン』の続きにかかりたいと思います。昔よりペースはうんと落ちていて、中身も書いている瞬間はよくわかっていなくて、あとで見直すときに初めて「ああそうか」って意味がわかると言う繰り返しなので、時間がかかります。しかも面倒くさがり、しんどいところにはできたら向き合いたくない……そんな風に書いているのは自分のくせに。もう少し、お時間頂きます。そうして改めて、2040000ヒットのお礼申し上げたいと思います。
2023.12.06
コメント(0)
-
2030000ヒット、ありがとうございました!『ラズーン』第七部 3.武君散る(1)
****************「走れ走れ走れえっっ!!」 シートスの命令が響く。「1人でも多く少しでも早く門に滑り込めっ!」 テッツェの伝令は必死に辿り着いた。 だが、南門が解放され、アリオを放り出した一団が現れた時点で、シートスは撤収を命じていた。ましてや、アリオが切られジーフォ公が駆け付け、テッツェがなおも外へと戦線を押し出そうとした動きで、全てを察した。 ぐったりしたパルスを拾い上げたユカルを先頭に、野戦部隊(シーガリオン)は泥を蹴立ててラズーン南門へ駆け戻る。平原竜(タロ)は馬を蹴散らし人を踏み潰すのには十分だが、どの獣よりも速いというわけではない。アリオを放り出した一団は、扇形に南門へ集結していく野戦部隊(シーガリオン)を嘲笑うかのように、見る見る南門内側へ戻って行く。 南門が閉じられれば終わりだ、と戦場に残されていた誰もがわかっていた。 どこから入り込んだ兵かは分からぬが、ラズーンに味方するものではないのは火を見るより明らか、アリオひとりを餌にジーフォを崩し『鉄羽根』をラズーン外へ貼り付けたまま、野戦部隊(シーガリオン)も外壁から放り出して南門を閉める意図は、既にラズーン内部に十分な戦力を引き入れている証拠、南門が閉じられたが最後、ラズーンは残された守りの兵だけで応戦する事になり、遠からず蹂躙が始まる。ましてや、『氷の双宮』に守られているのは無力な民なのだ。「うおっ!」 吠え声と共に槍が投げられた。紅の房飾りが乱れる。続いて数本、その槍に身を貫かれても良いとばかりに突っ込み先行する中にシートスが居る。戦列の一番外縁まで押し出していたはずだが、もう既に南門近くに迫っている。「閉じろ閉じろ閉じろおおおっ!」 予想外に素早く対応した野戦部隊(シーガリオン)に、余裕綽々で退却していた一団に焦りが生まれた。速度を上げて南門内に駆け込み、並行してゆっくりと門が閉じられ始める。平和な時代を守っていた、近年では開け放し出あったことさえある門だ、動きは緩やかだった。「させるかあっ!」 シートスが槍を投げる。力の限り投げられた槍の狙いは逃げ込んだ一団の背中ではない、閉められ始めていた門の下方の大地、槍は巨大な門を食い止めるには足りなかったが、締め切ろうとする力に砕けながらも抵抗する。シートスの意図を理解した面々が、次々と門の隙間めがけて槍を投げ入れる。斜めに突き立ち、地面に刺さってすぐに抜けても次に飛び込む槍に引っ掛かり、閉門を阻む。 ラズーン外壁の周囲に堀が掘られていたならば、野戦部隊(シーガリオン)とて進入するのは難しかっただろう。しかし、この200年、ラズーンは外敵の襲撃を受けたことがない。籠城するような作りにはなっていないのだ。「飛び込むぞ! 覚悟しろっ! オーダ・シーガル! オーダ・レイ!」「オーダ・シートス! オーダ・レイ! レイ、レイ、レイ、レイ!」 シートスの声に怒号が応じた。「ぎゃあっ!」 命知らずに南門開口部で迎え撃とうとした数人が平原竜(タロ)に蹴散らされた。槍を引き抜き南門を何とか閉めようとする決死の試みが続く。外から次々に雪崩れ込んでくる野戦部隊(シーガリオン)の後続を断ち切ろうとしているのだ。 シートスは素早く周りを見渡した。幸いに乱戦となっているのは南門付近のみ、当然配置されていると思っていた兵の姿は周囲にはなく、火の手が上がっている様子もない。 だが、侮るな。 シートスは自分に言い聞かせて振り向いた。後方彼方の土煙の中で、『鉄羽根』は次々屠られており、その向こうにいる『運命(リマイン)』軍も時を置かずに進軍してくるだろう。開門していた方が有利なはずだが、この一団は死に物狂いで南門を閉めようとしている。ラズーンを締め切った方がいい『理由』があるのだ。「シートス、門が!」 必死の乱戦の中、ついに南門が閉じられた。数騎仲間が取り残されたかと案じたが、何とか生き残ったものは南門内に滑り込んだようだ。「奴らが逃げる!」「追うなっ!」 南門を締め切った途端に四方八方に飛び離れて逃げ去っていく一団、シートスは狼狽えた顔で動こうとする配下を叱咤する。「追うな! 固まれっ!」 死に物狂いで南門へ駆け戻った興奮、卑怯な手管でジーフォ公を屠ったことへの怒り、仲間を失いつつもラズーン内へ戻れた安堵、それらに突き動かされて散ろうとする周囲を鋭く見渡した。「ユカル!」「ここに居ます!」「数人連れて索敵しろ」 シートスは目を細めて、ゆっくりと慣れ親しんだはずのラズーンの街並みを眺める。確かにほとんどの住民は避難し、兵達も『氷の双宮』周辺に集められているから、外壁近くに人気がないのはわかる、が。「静かすぎる。おかしい」「わかりました」 ユカルは向きを変えた。数人に合図して合流し、ゆっくりと平原竜(タロ)を進ませていく。「水分補給、武器確認、怪我の手当てにかかれ!」 荒い息を吐きながら頷く男達の中、シートスはじっとユカルの背中を見守り続けた。**************** 今までの話はこちら。(ラズーン用) まず2030000ヒット、誠にありがとうございました!連載も途切れ、過去の作品しか残っていない状況なのに、来て下さっている皆様には感謝しかありません。 そして、大変申し訳ありません。 10000ヒットごとの作品掲載が、遅れに遅れております。既に2000オーバーです。ようやく上げられた本文も、いつもなら1章分あげるはずの一部です。このままでは2040000ヒットが先に来てしまう、どうしよう。 メルマガ1回/週に3本が既にキャパオーバーなんだろうとは自覚していますが、それでもようやく『猫たちの時間』は最終話まで漕ぎ着けたし、ショートストーリーの方もぼちぼち手持ちを吐き出し終わるし、残るのは『ドラゴン・イン・ナ・シティ』の連載のみになるだろうと思うのに、『猫たち』の後は『闇』か『これは』の連載をするかとか考えるあたりが終わってる。かと言って、このままで時間制限切られないで、残りに2作品を完成させる自信がないし(こらこら)。 うん、頑張ろう。地道に。 今はただ、ありがとうだけをいっぱい言いたい。 ありがとうございます。 読んで下さってありがとう。 楽しんで下さることを祈ります。
2023.11.15
コメント(2)
-
2020000ヒット、ありがとうございました!『ラズーン』第七部 2.『羽根』の誇り(3)
****************「互角だな」 厳しく断じてテッツェは剣を振る。目の前に押し寄せて来る兵はクェトロムトの王シーラ、カザドのカザディノ率いる混合軍だが、両者とも主人は後方に控えたままなのか姿を見せず、下級兵を中心として力押しで攻め立てる様は、人の壁を作るかのようだ。それほどまでして守りたいものが背後にいるというよりは、褒賞をちらつかせられて押し出された印象が強い。それでも数が勝る、圧倒的に不利な状況をジーフォ公の膂力と『羽根』の練度で凌いでいる。「もう少し前へ攻めろ!」 降り出した雨の天幕は声を遮る、それでもジーフォ公の声が響き渡る。「まだ引くな! 野戦部隊(シーガリオン)に嘲笑われたいか!」「おう!」「おおうう!」 叱咤に応じて『鉄羽根』がじりじりと戦線を南へ押し下げる。 長引かせたくない戦いだが、結局は物量で競ることになる、とテッツェが冷ややかに考えた瞬間、目の前の兵にわずかに動揺が走った。隙を突いてすぐに数人切り倒すと、今までならすぐにその場を埋めに来たものが、二の足を踏んで視線を泳がせる。「どうしてあちらに」「どういうことだ」「俺たちは」 必死に剣を振るっているはずの兵士の顔に不安がよぎり、不穏な呟きが雨の隙間を抜いて届く。その中で一際はっきりと、「アリオ?」 まぎれもないジーフォ公の呆然とした声が響いて、テッツェは数歩踏み込み敵を切り倒した後振り向いた。「っ!」 南の門が開門されている。門と『鉄羽根』の間を保持していた野戦部隊(シーガリオン)が散開していた陣形を収束させていく。その中央に一団の塊、しかもラズーン内側から歩み出して来るのは全て徒歩、さもあらん、先頭に一人押し立てられているのが、マントを纏っているものの明らかに兵士ではなく民衆でもなく、濡れたドレスに足元を奪われながらよろめく女性の姿だ。「アリオーっ!!」「公!」 止める間などなかった。止められるはずもなかった。 怒号とともに馬を翻し、まっすぐに女性に駆け寄っていくジーフォ公の後ろ姿が、困惑と不安と怒りに満ちている。 なぜ?なぜ?なぜ? なぜアリオがここに。周囲の一団は何者だ。しかもラズーン内側から。南門はまだ開かれないはずだ。 視界の端で『鉄羽根』も動揺している。 主人が戦線を放って女の元に駆け寄っている。背後からの奇襲。野戦部隊(シーガリオン)は機動力を生かして背後に広く大きく展開しており、隙を見て『鉄羽根』を追撃して来るクェトロムト・カザド両軍を包み込み左右から押し寄せる策だったから、すぐには収めきれない。シートスの唸り声が聞こえるようだ。 不思議なことに押し寄せる兵士も動揺していた。 南門の開放は予定外、しかも出て来た一団の中にどうやらシーラかカザドがいる様子。背後から野戦部隊(シーガリオン)と『鉄羽根』を討つには兵が少なく、しかも南門が開放されたままなのは、このまま下級兵には『鉄羽根』と消耗戦を強いて切り捨て、後方への退路を確保し、精鋭だけをラズーンに乗り込ませるつもりか。「アリオーーーーーっっ!!」 ジーフォ公の絶叫に微かに応じるように悲鳴が上がった。びしょ濡れのアリオが突き出されるように放たれて、よろよろと両手を伸ばしつつジーフォ公の元へ駆け寄っていく。「そういうことか!」 見て取ったテッツェの頭に冷徹な計算が成り立った。「野戦部隊(シーガリオン)に伝令!」「はっ」 必死にアリオの元へ駆け続けるジーフォ公を視界に命じる。「すぐさま奴らの背後を取り、南門から入りラズーン内に戦線を戻せ」 さすがに次の一言は胸を突いた。「ラズーンは落ちた」 伝令兵の顔が青ざめる。「『鉄羽根』は外側の兵を抑える。野戦部隊(シーガリオン)はラズーンに戻った後、閉門せよ」「…っっっ」「復唱っ!」「野戦部隊(シーガリオン)は南門よりラズーンに戻って閉門、ラズーン内にて戦われたし。『鉄羽根』は門外側にて戦線を保持する」「…ご武運を、と伝えよ。お前には悪いが、野戦部隊(シーガリオン)とともに死んでくれ、パルス」「……承りましたっっ!」 飛沫を上げて走り去る配下、見送る彼方に高い悲鳴が響き渡る。「きゃあああああっっ!」「アリオーっっっ!!」 ジーフォ公の目の前で、今もうすぐに手が届こうとしたその先で、背後から駆け寄った男に一刀を受け、アリオが崩れ落ちた。叫んだジーフォ公が馬を飛び降り、身を翻す男に襲いかかって倒し、そのまま倒れたアリオに駆け寄り抱え込む。 ラズーンの四大公ともあろうものが、戦線を放り出し、女のために体を投げ出し、雨の泥飛沫に身を埋める。 ジーフォ公が。「…」 くるりとテッツェは主人に背中を向けた。混乱し動揺し、先ほどの緊張感が薄れ味方も敵もおたおたと曖昧な剣をぶつけ合っている戦場を睥睨する。 くすり、と笑った。「どこまでいっても、迷惑ばかりかけるお人だ」 小さく呟き、すうっと胸に息を吸い込み、かつてない熱く激しい叫びを上げる。「死守せよ!!」 びくっと戦場が震えた。「我らは『羽根』ぞ!! ラズーンを守り、主を守る!! 『羽根』の誇りを示せ!!」 う、ぉおおおおおおお! 吠えながら切り進むテッツェに浮き足立っていた『鉄羽根』が応じる。 わああああああああ! 叫びながら切り刻む剣の波を押し抜けていく。 雨が激しく降り注ぐ。 だが、もう温存する必要はない。「はあっははははあっっ!」 テッツェは高笑いしながら剣を振るった。 後に、ラズーン南門外で行われた戦場には一つの物語が作られた。 婚約者であるジーフォ公を裏切り、敵の甘言に乗って戦線を崩壊させた『西の姫君』アリオ・ラシェット、そのアリオを最後まで欲し望み手に入れようと足掻いた武君ジーフォ公。 泥の中に切り倒されたアリオの表情はなぜかほっとした安堵を浮かべており、彼女を覆い被さるように蹲ったジーフォ公の体は切り刻まれ四肢は砕かれていたが揺るぎもせず、その背中を守るように仁王立ちしたテッツェは無数の槍と矢を受けても倒れなかったと。 愛を知らない女のために、愛しか知らぬ男が散った、と。**************** 今までの話はこちら。2020000ヒット、ありがとうございました!もうすぐかな、近いな、そう思っていたら、あれよあれよとヒットが伸びて過ぎてしまいました。お待ちいただいているのかなととても嬉しく、書けるのか私と怖かったです。他の楽しいお話と違って、如何にもこうにも悲劇的な要素の多い作品ですので、ついつい登場人物に入れ込み過ぎて筆が止まります。でも、こうしか進まないよな、という絶対的な流れみたいなものがあって、それを必死に汲み取りつつ書き進める、川の側で洗濯をしている昔話の老婆になった気分ですが、ぞわぞわするような瞬間を目指して書いて行きます。長らくお付き合い頂いてくださる皆様、今初めてご覧くださった皆様。たくさんたくさんお礼申し上げます。とにかく、アシャとユーノには幸せになって欲しいので頑張ります。これからもよろしくお願いいたします。
2023.05.15
コメント(2)
-
E2:夏日
**************** 小さな用水路と目を射るほどの鮮やかな緑を窓枠の中に閉じ込めた部屋は、外から入ると静かで冷たくてひんやりとしていた。 部屋の隅に積まれている木の机を一つずつ並べていく間に、暑さはじんわり体の内側にこもっていく。机の前に、墨で汚れた座布団がひしゃげて煎餅のようになっているのを置いていく頃には、先生が機械仕掛けで擦った墨汁の様子を覗き込んでいる。 吊るされた、書き上がったばかりの手本の乾き具合を確かめ、つるりとした半紙、少し上等のざらりとした紙を組み合わせて、やって来る生徒達の今日の課題を準備する、先生のこめかみから、すうっと汗が流れていく。「こんにちはー」 間延びした挨拶は来た道の照り返しに疲れた子ども達の声。てんでに課題を取って、吊るされた紙の間に折り込まれたような先生の前にもじもじと座る。ぬるついた足をくっつけたくないから、ぺったりとお尻を落として。チロリ、と先生が眼鏡の向こうから見るのに慌てて足を直し、背筋を伸ばす。 小さな子ども達は、醤油差しに入れられた墨汁を各々の机の硯に流し込むが、私は水を入れて墨をゆっくり磨り始める。微かな動き。窓の外で鳴く蝉の声に呑み込まれて混ざり合う。ざわめく子ども達のおしゃべりに踏みつけられて。磨っている音は聞こえない。重ねた脚の間から、汗が滲んで座布団へ吸われていくのを感じている間は。 墨を磨る。 心を追い詰める筆先に、耐えられるほどの濃さになるまで。****************
2023.04.16
コメント(0)
-
E1:道祖神(3)
**************** 書く意欲を失い気力を失い、けれど発表する手段は失うことなく日々が過ぎる。いや、捨てようと思えば、手段だっていつでも手放せる。止めてしまえばいい、きっと過去の栄光にすがっているだけだ、美しい記憶に誤魔化されているだけだ、神さまの甘言に乗ってしまい、今更の後悔に気づきたくないだけだ。 未練がましい、忸怩たる思いを抱えながら、鮮やかに活躍する書き手達を眺める。羨望だと認めれば道が開けるのかと思う自分、書き手であることに時間と努力を費やさなかったから当然と思い切れない自分が情けない。 相変わらず、それで生活を支えられるような、多くの人に求められるような、業界に認められるような、名だたる賞を受けるような、そんな作家ではないままに、日々の生活を支える仕事の合間に、時間を削り、体を削り、心を削り、時に大切な繋がりさえ失って、書き続けている。世界から反応はなく、時に訪れる読者に感謝しつつも願いに応じることなく、ただただひたすらに、自分が望む方向へ、自分が求める文章で、時に自分にさえ理解できない道筋を歩む物語に付き添い続けている。 けれどそのうち、不思議な感覚が宿るようになった。 誰が褒めるのでもなく、どこで認められるのでもないが、書き上げていく物語、その書いている最中にはよくわからないのに、日を置いて読み返してみると、なるほどまさに十二分に良いと思えることがある。 正しい、と言うか。 この物語は、このことばで、この展開で、この流れで語られるのが、一番「正しい」。 自分が書いたものなのに、まるで誰かが書き上げた完成した物語を読むような納得と驚き。 なるほど、ここのこれは、このように繋がるものだったのか。このことばは、過去に描いたあれを生かし、なおかつこのように物語の中心に届くものであったのか。 思い返してみれば、この感覚は書き始めの頃に、迷いなく筆を運んだ時と似ている。あの時は物語の先が見え、選ぶべき道筋が見え、そうして最後まで書き手である自分が読み手である自分を導き切ることに満足した。しかし今は、書き手である自分は読み手をどう導くべきかわからないまま書き、読み手である自分はどこからこの表現が降り落ちてきたのか訝りながら読んでいる。 でも、ああ、いや、そうか。 まさに、この文章を綴りながら、理解がようやく届く。 私は、私が今まで読んだことのない物語を書くために、書いているのか。 目まぐるしく思考が反論する。 しかし、それは何と無謀な。 この数十年で目にし耳にした物語の数は数万を超えるだろう。いや、あらすじや1話だけのもの、1シーンだけのものも入れるなら、十数万に及ぶのではないか。 けれどしかし、それらに何一つ被らない物語を書いた時、初めてあの感覚が起こるのではないか。 書いた覚えのない、読んだ覚えのない、よくわからない、物語。 いやいやひょっとして私は、誰も読んだことのない物語を書きたいと望んでいるのではないか。 驚きと、納得。 私は書くことで何を得ようとしているのだろう。 答えは明瞭だ。 未知。 全く、知らぬ、何か。 そんな無茶な。 立ち止まった瞬間、ふいに足元を掬われて、派手に転んでしまった。転んで手を突く、その下に、何だろう、紅の布が敷かれている。体の下からまっすぐ前へ、遠く遠く、はるかな彼方へ、一筋の布が伸びている。 その布の端を、あの神が、しっかり握って立っている。にこにこ笑いながら、慣れた口調で話しかけて来る。「ほら、転んだやろ。お前さんの限界は、今、そこや。おいで、おいで。立たんでもええ。赤ん坊のように、這いずってもええで。なあに、わしのところまでは、だいぶある。来る頃には立てるやろ。立つことが大事なんやない。ここの道を、ここまで来ることが大事なんや。それでもお前は安楽や、道の上には辿り着けた。道さえ見つからんのはもっと辛い。そやけど、どうや、緋毛氈やで。何と鮮やかなもんやないか」 私には『物書きの神』が憑いている。 この神は実に『いい』性格をされている。 ひたすら歩めと唆される、今日も、明日も、その先も。 見知らぬものが、その先にあると。 ので、苦笑いしつつ、立ち上がる。 道の長さを、喜ぼうと思う。****************
2023.04.11
コメント(0)
-
E1:道祖神(2)
**************** ある夜、神がやってきた。「いや、ここのところ、忙しゅうてな、済まなんだ。え、何、書くのを止める? 今更何言うてんのや、アホくさい。自分の力不足を痛感した? ああ、そら、確かに、今のお前は力が足りん、そやけど、未来永劫、足りひんことなどあるもんか。それに、今、お前が、周りの子ぉに書いたってる話な、あれ、ええやんか。欲しがられるんやろ? 書き写したりされてんのやろ? 冊子にまとめたら思いの外売れたんやろ? あれ、頑張ってみいな。あれ、出版社にも送ったり。え? 迷惑ちゃうか? 何言うてんね、それが向こうの商売やろが。迷惑やったら断ってきよるがな、万が一、万が一やで、上手いこといったら、こっちも潤う、向こうも潤う。悪い話やないで? な?」 神さまは口車のプロだった。私はまたもや乗せられた。出版社に、自分の作品を送り続けて数年、ついに「書いてみるか」と誘いがあった。持っていたネタを数本、一つの書き出しを送ってみた。だが、私の作品は求められるものに至らなかった。丁寧な断りが届き、掴みかけたチャンスの喪失に混乱し、狼狽え、諦めきれずに数年もがいている間に、ようやく一つの問いが浮かんだ。 なぜ、私は書いているのか。 すでに、欲求不満解消だけではなくなっていた。身近の読者は、就職や結婚、出産や子育てなどなど、一身上の変化で減りつつあった。描きたいと思って書いた作品と、周囲の求めも噛み合わなくなりつつあった。書くことの喜びも残っていたが、それに伴う心身共の負担も重くなっていた。 私は神さまに訴えた。書くべきか、書かざるべきか、それが問題、どちらを選べば良いでしょう、と。神さまは非常にそっけなく、こう宣われた。「書こうが書くまいが、まあ、どっちでもええで。お前の人生や、好きなようにしたらええ。ここで書くのをやめたら、今まで書いてきたことはどうなるね、とも言えるやろうが、人生にムダはつきもんやしな。物にならへんとしたら、この先のムダは省ける、ちゅうもんや」 うむ、そうか。では、止めてしまえと思い始めた私に、神様はいよいよ本領発揮、一筋縄ではいかない手管の数々を見せられた。 まず、新聞や小冊子に投書が載り始めた。読者の便り、詩、意見、短歌まで乗った。投稿作品も評価された。地方の文学賞佳作、童話のアイディア賞や佳作、小エッセイ佳作。作品をまとめて出していた個人誌も、一つのシリーズが終わると、周囲に望まれて次のシリーズを出すような段取りとなった。加えて、色々な機会に、あらゆる人が、何度も何度も尋ねてくる。「それで収入を得ているプロの作家でもないのに、なぜ書き続けているんですか」 書いていることの意味。 自分が何を目的としているのか。 それを一番知りたいのは私だった。 自分が楽しむためなら、発表する必要はない。人に楽しみを与えるためなら、在り方に悩む必要はない。お金のためなら書くことに拘らなくていい。名誉を得たいならもっと認められやすい道を探せばいい。なぜ、ある物語を、まとまった収入にさえならず、掲載される媒体が待っているわけでもなく、誰が読むとさえも考えずに、最善の努力をして、或いは周囲に迷惑をかけても、書き続ける必要があるのか。 私は書くことで何を得ているのだろう。 手探りのまま、書き手として何か仕事があるのかと、色々なものに手を出してみた。二次創作に踏み込み、WEBゲームのライターを請け負ってみた。どれも読者を得て喜ばれ、熱狂的に支持されることもあった。だが、なるほどこちらかと喜び勇んで、その分野に進もうとする度に、仲間を失い受け入れ先を失い、新たな場所も能力不足と判断されて、得ることは叶わなかった。 再び書き手の私から、世界が遠のいていった。いやむしろ、世界は私が書き手であることを望んでいないようにしか思えなかった。 恐らくはきっと、私は書き手である必要はないのだろう。いつかの問いは、なぜいつまでも見当違いの方向ばかり探し歩いているのか、本分たるものをちゃんと見極め、それに全力を尽くせという神さまからの遠回しな警告だったのだろう。ならばなぜ、この道に引き込んだのかと詰りたいところだが、それもまた人の身には分かりかねる何かの理由によるのだろう。 私は他の誰より自分の不出来さにがっかりした。****************
2023.04.10
コメント(2)
-
エッセイ開始。E1:道祖神(1)
ずいぶんご無沙汰しています。なのに、いつもご訪問ありがとうございます。短い作品・童話・SS・BL新ネタ・猫たちの時間シリーズはメルマガ展開し、『ラズーン』はこちらで10000ごとの展開、あと動かせていないのは『闇シリーズ』と『これは〜』シリーズ。面倒臭がりの私には、発表を仕事化する必要があるようで、2シリーズのどちらかは『猫』の後にでもメルマガ展開してやれば進むかもしれません。お話の続きも滞っていて、申し訳ないと思いつつ、手持ちしている文章をとりあえず吐き出してしまえば進むのかもと思い、書き溜めてあったエッセイ・小文もアップしようと思います。よろしかったら、ひとつまみどうぞ。**************** 私には『物書きの神』が憑いている。 この神は実に『いい』性格をされている。 例えば、9歳の私に向かって、優しげに、とても素晴らしいことを教えるように、こう囁かれた。「なあなあ、たくさん本読んだけど、どうや、何か、今ひとつ、いう感じがせえへんか? もっとこう、ぴったりくるもんが欲しい、と思わへんか?」 この時、神さまは、私の読書量の少なさや読書範囲の狭さについては指摘されない。そんなことを教えてしまったら、未熟な私が自ら文章を書くことなんて始めないだろうと見抜かれていたからだ。「ほら、好きなん読んでも、落ち着かへんやろ。この辺りでこう、と思うところにヤマがない。そらそうや、あんたと、この本か書かはったお人とは違うし、仕方ない。そやけど、自分の心にぴったりきたい、こら、人情やと思う。あんたもそう思てるやろ。そやから、な、どうや、一つ、好きなもん、書いてみいひんか? いや、なに、別にどんなもんでもええ、どんなもんでもええんや。それはそれなりに、まあ、なっていくさかいに」 そこでにんまり笑われた神さまの、意味ありげなことばに気がつけばよかったのだが、私は、それもそうか、と書き始めてしまった。 始めた時に調子が良ければ、いつの間にか抜き差しならないところへ追い込まれるのが世の常で、この神さま、なかなかしたたかな方だった。 まず、原稿用紙に書かなくてもいい、と言う。レポート用紙や残り紙を適当にホッチキスで止めて、鉛筆でずらずら書いていけ。形にこだわらなくていい。手元の本を見て、それが読みやすい形と思えば、そのように書けばいい。起承転結も構わない。欲しいものを欲しい形で書き出してごらん。 神さまの指示は私にぴったりだった。 私は長文も短文も詩も、ことばを山盛り、好きなように紙に飾った。うまく盛れないと手持ちの本でレシピを探し、似たような盛り方を参考にした。学校で習っていない漢字も、書くリズムや空間の線のバランスに魅かれて盛り付けた。何度も盛り付けていくうちに、好きな材料とテーマがあるのに気がついて、それに拘って書き込んで、とうとう始めと終わりのある作品が仕上がった。「ようやった、ようやった。その歳でその才能、いや、大したもんや。わしの目も狂うてなかった、いうことやな。どうや、どう思う、物を書くのは。楽しないか、面白ないか。この話はお前だけのもんや、どこも、お前にぴったり、来るやろ」 神さまは手放しで褒めてくれたが、私は納得できなかった。本当に欲しいものに今一つ及ばない部分を知っていた。そこを満たすためには、ことばも感覚も未熟だった。それを埋めたいと感じていた。神さまの指示を待たず、私は作品を書き上げ続けた。一度に一作では物足りず、三作四作、並行して書いた。飽きる気配はなかったが、神さまは手を替え品を替え、私をそこから離れさせるまいとされた。 学校で作文を褒めさせた。辛く苦しい出来事を日記や作品を書くことで乗り越えられると感じさせた。友人を読者に仕立て上げ、なおかつ、熱狂的に支持させて、私にとって作品を書いていくことは、人々の役に立ち喜ばせ豊かにさせるものであると思わせた。 十二分に機を熟して、神さまはこう囁かれた。「随分と腕が上がったやないか。わしも鼻が高いで。そやそや、今な、こう言う『公募』をやってるで。漫画の原作募集中、や。どうや、力試し、運試し、一つやってみたら。なあに、あかんで元々や。プロ、アマ、問わず、とあるやろ。ここで賞もろたら、大したもんやけど、もらわいでも落ち込むことあらへん。お前はプロちゃうしな。宝くじよりましなもん、と思て、どないや」 この挑発に私は乗った。結果、二度目のトライで佳作を取り、東京の出版社で受賞式となった。19歳。初めての一人での上京。聳える出版社の建物。幾枚もの名刺。閃くフラッシュ。見知らぬ大人達との会食。どれも舞い上がるには十分なものだった。そして、もちろん、神さまは、私の受けた賞が『佳作』であって『大賞』でないことは指摘しなかった。私にとって人生を変えるような晴れ舞台でも、出版社側にとっては毎年一回行われる出来事の一つでしかない、とは言わなかった。ましてや、作家志望の新人予備軍など、星の数以上いて、その中で一回の受賞から煌めく作家になる者など、銀河系のもう一つの生命種と遭遇するようなことだとは教えなかった。 私は一人前のつもりでプレッシャーを感じて書けなくなった。神さまにお伺いを立てようとしたが、忙しいと断られた。出版社にそれまで書き溜めたものを送って見たが、反応は鈍かった。そこでようやく、自分が、井の中の蛙どころか、井の中の微生物だと思い知った。書くのをやめようと思った。私程度の力は世の中に捨てるほどある。今回の受賞は、これまで書き続けてきたご褒美だったのだ、と。****************
2023.04.09
コメント(2)
-
『青の恋歌(マドリガル)』9.キューバの人の楽の調べ(2)
****************「あれ?」 本屋から帰って机の上にポートレートと読みかけの本がないのに気づく。「あいつが持ってったのかな」 とりあえず、周一郎の部屋を訪ねる。ノックに応じて返答があり、書斎に入った俺は、元のところに自分の能天気な笑い顔が飾られているのにうんざりして、寝室との境のドアを開けた。射し込む陽の中、周一郎はしっかり読みかけの本の続きを読んでやがった。「あのなあ」「何ですか?」「黙って持ってくなよ」「僕がもともと借りていた本です」「にゃあ」 そーだそーだ、と主人の横になっているベッドの足元に丸くなっていたルトが鳴く。「そりゃあそうだが……あのポートレートぐらい、外したっていいだろ?」「どうして?」「どうしてって、ああ言う顔はもう一つ気に入らん」「じゃあ」 パタリと本を閉じ、周一郎はこちらを見つめる。「撮り直しますか?」「あ、あのな……そーゆー問題じゃない……んだが……」 俺はしばらく黙り込んで、周一郎がポートレートを外そうとは露ほども考えていないらしいのを理解した。「…まあ……いいか」「滝さん?」「わかった。いいよ別に」「そうですか」 ほっとしたように笑った周一郎は、次の瞬間、そういう自分が心底嫌になったと言いたげに、不愉快そうに口をつぐみ、冷たく言い放った。「では、さっさと出て行ってもらえますか。読書を続けたいので」 それでも、俺が部屋を出て行く寸前、なぜかひどく優しい目で見送っていた気がした……。「だめ、だろうなあ」「え?」 コーヒーのカップを両手で包む。「結局、俺は手を出しちまうよなあ…アホだとは思うけど」 どんな得があるわけでもないのにな。「あなたのそういうところって」「ん」 コーヒーを含む。「とっても好きよ」「ごふっ!!」 喉に入ったコーヒーが急に針路修正して気管に飛び込み、目一杯むせた「こっ…ごほっ! ごほんっ…らっ、お由っ……ごほごほん! 一体…ごほっほっ…何を……ごほっ!!」「それでね」 咳き込んでいる俺を放って立ち上がり、くるりと背中を向けながら、「貸してるお金を返してくれたら、もっと好きなんだけど」「お由宇ーっ!!」 俺は咳の合間に一声、必死に喚いた。 終わり****************これにて『青の恋歌(マドリガル)』終了です。ご愛読ありがとうございました。
2022.12.03
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』9.キューバの人の楽の調べ(1)
****************「サンティアゴへ行こう…」 開いた本の詩は繰り返す。水の馬車に乗って、椰子の天井が歌う、バナナがくらげになる、ロミオとジュリエットのバラを持ち、と続けながら。「結局、スペイン旅行の間中、ガルシア・ロルカを読んでたわね」 コーヒーを運んできたお由宇が、俺の手の本を覗き込んだ。「なんとなく、あいつの守り札みたいな気がしてな」 コーヒーの香りを味わいながら目を閉じ、ソファにもたれかかる。本を閉じて横に置いた。「ま、それも、もう終わりだ」「そうね。無事に日本に帰ってこられたし。周一郎はどうしてるの?」「高野に見張られて、大人しくしてるよ」 帰国して1週間、ようやく日本にいるらしいと言う実感が湧いてきた頃、俺はお由宇の家でコーヒーを飲んでいた。一つには、帰国前後のドタバタで話せなかった、最後の『青の光景』と礼拝堂の関係の話を聞きたいとお由宇が言ったためであり、もう1つには、上尾や『ランティエ』、マイクロフィルムがどうなったのかをお由宇に訊きたかったためでもあった。「上尾君とは?」「あれから会っていない」「そう……また、スペインへ行ったと言う話だけど。呼び寄せる何かがあるのね」「ああ……。『ランティエ』は?」「嬉々として贋作づくりに勤しんでるわよ。アンリに売る気みたい」「過激な奴だな」 俺は溜息をついてコーヒーを含んだ。ああ言う『天才』のやるこた、一般人の俺にはわからん。「マイクロフィルムはどうなった?」「ああ、ICPOに渡したわ。この間イルン空港でひと揉めあったでしょ、あれがその成果ってわけ」 …つくづく、世の中には過激な人間が多い。「でも、その礼拝堂のシーン、見たかったな。さぞかし凄かったんでしょ?」「ああ。人間てのは、あんなことがやれるんだよな」 深く深く溜息を重ねる。 今でも目の奥に浮かぶ、青白い光の中の光の群れと影の群れ。交錯する青と黒、滲む光、揺れる影、混じり合う不思議な空間………そして、周一郎の涙。「『青の光景』……光と影の永遠の恋歌(マドリガル)というわけね……互いを捜して、求めあ合って……」「考えてみるとさ」 ぼんやりと呟いた。「あいつ、朝倉大悟が死んだ時、心から泣けなかったんだろうな」「え?」「どっかで引っ掛かってさ、………で、やっと大悟が死んだのを悲しめたんだよ、あいつ」「志郎…」 俺はコーヒーを飲もうとして、呆気に取られたようなお由宇の顔に気づいた。「どうした?」「あなたって人は…」「何だ? 俺がどうかしたのか? 俺は正気だぞ」 何だ何だ、あまりにも不似合いな台詞だったか。「…そう……そうよね」 くすりと唇を綻ばせる。「気づいてなかったのよね」「何が」「今言ったことの重大さ」「重大なのか?」「まあ、光と影についても、周一郎の価値観をひっくり返しときながら、気づかないような人だものね」「周一郎の価値観? ひっくり返す?」 えーい、くそ。お由宇と話すと、いつもこれだ。「光が強いほど、出来る影は濃い」「うん?」「なのに、あなたったら、光がなけりゃ影は出来ない、って言い切るんだもの」「うん?」「影がある……それはすなわち光があること。これ以上の反論がどこにあるかしら」「あ、あのな」 俺はついにいつもの台詞を吐く。「もうちょっと、わかりやすく言ってくれる気はないのか?」「んー…あのね、志郎」 机に肘をつき、顎を乗せ、小首を傾げる。さらりと流れたセミロングの髪をそのままに、きれいな弧を唇に描かせて、俺を見つめる。「スペインではね、巡礼者が通った道を『サンティアゴの道』と言うの。サンティアゴ、つまりキリスト十二使徒の一人、ヤコブはスペインの守護人で、巡礼者の目指す先がそこ、と言う訳。……きっとあなたは、周一郎にとってのサンティアゴなのね」「おい!」 俺は悲鳴を上げた。「それがわかりやすい言い方かよ!」「仕方ないわね」 お由宇が溜息をつく。「つまりね、あなたって、結局、周一郎のことに首を突っ込むわけでしょ。それで何かいいことがある訳?」「いいこと…と言うより、どっちかっつーと災難の方が多い気も…」「それじゃあ、もう周一郎に関わらない?」 お由宇のことばに、数日前のことがふいに思い浮かんだ。****************
2022.12.02
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』8.夏の恋歌(マドリガル)(5)
****************「お前、勘違いするなよな。俺が厄介ごとに突っ込むのは『習性』なんだからな」「…」「今度だって、断ろうと思えば断れたんだ。それをいつものお節介で、俺が勝手に飛び込んできたんだからな。お前が責任感じる必要ないんだからな」 10年も前の恨みを背負い込んで、痛めつけられて、傷ついて、それで十分なんだからな。これ以上、お前が負い目を持つこた、ないんだ。「………」「聞いてんのか?」「…でも」「でももへったくれも何もない! お前はそれでいいんだ!」 俺は続けた。「いいか? よく聞けよ、お前はそれでいいんだから。お前がお前だってことを負い目に思うこたないんだから。お前はお前であって、お前でないってことはありえなくって、つまりお前はお前でないはずがなくって…」 ええい、くそ!「だから、影があろーがなかろーが……え? 影?」 ぎょっとした。「おい、周一郎」「…はい?」 足元にチラチラするものを凝視する。どこか滲んだような甘酸っぱい声が応じたが、それよりも今。「この部屋、窓ってなかったよな?」「はい」「で、窓がないってことは光が入らないはずで、光がなきゃ、影は出来んよな?」「………はい」「で……この下に動いてる奴、何だと思う?」 それはもう、尋ねるまでもなかった。 ついさっきまでは幻のように蠢いていた『それ』は、いまははっきりとした形を取りつつあった。「光だ!」 慌てて天井辺りを振り仰ぐ。「どこからか、光が入ってくるようになってる!」 波打つような壁、僅かに曲面になっている天井を区切る曲線の群れ、おそらくはそれらに巧妙に隠された明かり取りがあるのだ。「滝さん!」「っ」 周一郎の低い叫び声に、指差す方を見つめてぎょっとした。 十字架の斜め右上あたり、ぼうっとした光条が重なり合って白い光の塊を作っている。それは、月の移動に伴って次第に強くなる光に、見る見る、淡い、けれどもそれとはっきりわかる形を作った。二本の光条が交差してぴんと伸びた白い羽根を思わせる。いくつもの細い光条が重なり合ってふっくらとした体を作り、光り輝く存在になる。「天使だ…」「滝さん、あそこにも…」「う…」 天使の群れはぼんやりと、けれど次第に辺りに増えていった。それぞれの光条が波打つ壁で跳ね返って、部屋をほの明るく照らす。光条に照らされなかった部分は床にのたうち、黒々とした人の塊を思わせる形に凍てついていく。「おい……こんなことが出来るのかよ……」 思わず呟いた。 十字架を囲み、部屋の四方に浮かぶ天使の白い光の群れ、呼応するようにモザイクの床に固まる影は時に伸び上がり、時に蹲り、救いを求める人々の姿に似て天井を振り仰ぐ。茫然として、ただその光景に魅入られている俺たちの目の前で、光と影は、ゆっくりと互いの位置を変えていった。光の群れが次第に降りて行く。影がじわじわと伸び上がる。天と地、二つの世界を象徴していた場面が、青白い光に照らされた部屋の中、天は地に手を差し伸べ、地は天を求めるように混じり合っていく。「…『青の光景』…」 天上の青、地上の黒、光と影、生と死が互いを求めて絡みつく。それは果てることない求愛の想いに似て、ただひたすらに抱きしめ合うだけの苛立たしさ………そこには尽きることない昇華への願いがある。 ふっ、と唐突に、ある一筋の光が部屋の隅の床に落ちた。周一郎が無意識めいた動きで近寄って、覗き込み、手で埃を払う。低い呟きが漏れた。「…我を求めよ……我は全てを受け入れ、全てを与える。我はいつも汝の側にいる……滝さん」「うん?」「そのモザイク、赤っぽい石、動きませんか?」「これか?」 俺は近づいて触った。ごとっと重い感触があって数センチ石が沈む。「その周りの石で、どこか、その上にずれ込みませんか?」「周り…な……うん、これが動くぜ」 左隣の黄色の石が、じりじりと赤っぽい石の上に重なった。「次はその周り」「周り、と」 同じことを数回繰り返すと、ふいに、石を動かした下に、5センチ四方ぐらいの穴があった。中に何かが入っている。「フィルム…かな。それに写真…」 『スペインにて』。裏にそう書かれた写真をひっくり返す。側に来ていた周一郎がびくっと体を震わせた。頬に煌めいて雫が零れ落ちる。小さな呟きが掠れて響く。「大悟…」 それは、他ならぬ周一郎の、カメラに向かってあどけなく笑いかける子どもの頃の写真だった。****************
2022.12.01
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』8.夏の恋歌(マドリガル)(4)
**************** コンコン。「…」 コン…コン。「ん……」 夢の中で響いたノックがまだ聞こえてやがる、と思いながら寝返りを打つ。 昼間見た光景のせいか訳のわからない夢で、あの礼拝堂の扉を誰かが叩き続けている、そのくせ開いて中には入ろうとしない、そんな夢だった。入りたい、とにかく中に入りたい。一途な焦燥が訪問者の心を乱れさせている。どうしても入りたい、なのに入れない。訪問者は誰もいない礼拝堂の扉を一人、叩き続ける、返ってこない答えを求めて……。 コ…ン……コン……。「っ」 ひどくためらいがちなノックが再び聞こえてきて跳ね起きた。左へ滑り降りようとして、嫌というほど頭と足を壁にぶつける。「いてっ?!」 首を傾げる。どうしてこっちに壁がある?「滝さん?」「へ?…え、周一郎? え? ここ? …あ、そうか」 俺はようやく、自分がスペインにいる事、あの女主人の家に泊まった事を思い出し、頭を摩りながら、ベッドから右側へ滑り降りた。 腕時計は真夜中近いと教えている。眠気で重い体をのろのろ引きずってドアを開けると、外に居た周一郎がはっとしたように顔を上げた。「……おい、寒くないか、その格好」「大丈夫です」 周一郎は青い縞のパジャマに軽く上着を引っ掛けただけだ。「で……何だ?」 ふぁあ、とあくびが出た。「…大悟のことばがあるんです」「んー?」「『青の光景』を見たければ、満月の夜中に礼拝しろって。『青の光景』の裏にミッセージがありました………今夜は完全に満月じゃないけど…」「うん…?」「…だから…」 周一郎は口ごもって俯いた。「その、高野を起こすのは、可哀想だし……」 あれ、こいつ、ひょっとして。 ふと閃いた。確認とからかい半分で返答してみる。「んじゃ何か、俺は可哀想じゃないっつーのか?」「そんな訳じゃないんですけど……ただ………。わかりました。もう結構です」 周一郎は唐突にふてた口調になった。「夜中にお起こししてすみません。おやすみなさい」 くるりと背を向ける。「待てよ。一人で行くには危なっかしいだろ」 部屋に戻ってパジャマの上からセーターを着た。コートを片手に戸口に戻る。ばさっとコートを周一郎に掛けてやって、軽く相手の頭を叩いた。「じゃ、行こうぜ。一人で行かせて、庭でこけられでもしたら、俺が高野に恨まれる」「一人じゃありません」「にゃい」「お、何だ、お前もいたのか」 キラッと闇の中に緑の火を光らせて、ルトが姿を表した。しっかり洗ってもらったせいで、元通り『ピカピカ』の青灰色猫になっている。「まあこっちに来いよ。またシッポ踏むぜ」「にゃぐ」 企むところがあって、俺の足に身を擦り付けていたルトは、我が意を得たりと言わんばかりに、『明るく可愛くあどけなく』俺の手に爪を立ててよじ登った。「ちちっ…あ、あのな、ルト」「にゃ?」「いい加減に爪を立てずに肩に登る方法覚えてくれ」「にー」 無理だよそんな事、そう言いたげに、ルトは鼻に皺を寄せて鳴く。 わかった俺がバカだった、お前に説教なぞしても無駄だってことをころっと忘れてた。 ルトの温もりにちょっとほっとしながら、周一郎と一緒に歩き出す。 コト……コト……コト……コト……。 邸に松葉杖の音が響く。 ふと理由もなく、ようやくこいつも人間になってきたな、と思った。そうだ、少なくとも『人間』なら足音を立てるもんだ、うん。 内庭(パティオ)は、昇った月にお伽話じみた空間に変わっていた。地に映る建物と木々の影。それは昼間見る太陽の影とは違った、優しい甘さをたたえている。「スペインの内庭(パティオ)は、夜、影を落として最も美しいように造られているんです」「へえ…」 周一郎の口調もどこか優しい、頼りない響きをたたえている。 ギッ……。 礼拝堂の鍵は、周一郎が女主人から貸し与えられている。鍵を回して開いた礼拝堂の中は、深い闇に身を沈める昔語りの魔の洞窟のように、人の侵入を拒む気配があった。怯みもせずに足を踏み入れた周一郎が、促すように俺を振り向く。「う…うん」 まあ、日本の幽霊もスペインくんだりまで海外出張はしないだろう。そろりそろりと入り込み、ゆっくり扉を閉める。たちまち、窓のない部屋は、墨一色に変わった。「……どうだ? 何かわかるか?」 黙っていることの重さに問い掛ける。答えはなかったが、少しずつ闇に慣れてきたらしい目に、周一郎がかぶりを振るのがぼんやり見えた。「そうか…」 俺はもぞもぞと身動きした。ゆっくり辺りを見回す。十字架のキリスト像は、骨ばった体を広げてこちらを見ている。静まり返った邸内には、物音の一つもない。「……きっと…」「ん?」「ぼくを一番愛してくれたのが、イレーネなんでしょうね」「…」 沈んだ声に、答える術なく黙り込んだ。「どうして…なのかな…」 暗闇に安堵したのか、迷ったように低い呟きが続く。「光が強くなればなるほど、影も濃くなっていく………それで、ぼくは結局……自分の影に滝さんまで引き摺り込んで……」「おい…」 周一郎の言おうとしていることに気づいて、思わず口を出した。****************
2022.11.30
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』8.夏の恋歌(マドリガル)(3)
****************「滝さん!」 苛立たしげな声に、我に返る。 バルセローナ、ゴシック地区の一角、大悟の知り合いの家とかを、周一郎は探し当てたらしい。「何をぼうっとしてるんですか」 はいはい、これだからなあ。元気な時は、何せ強気なんだ、この意地っ張りは。「今度眠れないっつっても、子守唄も歌ってやらんぞ」 ぼやくと、側に居たお由宇がくすくす笑う。「本気?」「当たり前だ。まあ…実行できるかどうかわからんが」「ふふふふっ」 お由宇の楽しげな含み笑いに眉を寄せる。 まあたぶん、出来ないだろうな、うん。俺が居ることで周一郎が眠れると言うなら、何やかやと理由をつけて、結局俺はあいつの側に居てやるんだろう。どこまで阿呆なんだろうと悩みながら。「Mucho gusto,Sr.Taki. Me alegro de conocerte.」 戸口に立ち、周一郎達を迎え入れた年配の婦人は、黒い目を細め、豊かな体いっぱいに笑みを湛えながら俺に言った。「は?」「初めまして、お会いできて嬉しい、と言ってるのよ」「あ、あ……その、えと……ムーチョ、グスト」 お由宇の通訳に、ようよう覚えたスペイン語の挨拶を口にした。相手がにっこりと笑い、続ける。「Por aquí por favor.」「こちらへどうぞ」「あ、どうも、じゃない…グラシアス」 お由宇が訳してくれるのに慌てて返答する。 周一郎はすでに奥の方へ入って行ったのか姿がない。きょろきょろ見回しながら歩く俺をよそに、お由宇は女主人と話をしている。「ふうん…」「どうした?」「…バルセローナじゃ珍しくないけど、この家にもアントニー・ガウディが造ったと言われる礼拝堂があるんだって……もっとも、今では新しいのが出来て、ほとんど使っていないらしいんだけど」「この辺りには、結構そういったのがありますからね」 『ランティエ』がさらりと言う。「ガウディが手を加えた天井だの、内庭(パティオ)だの柱だの……どうやら、この天井もそのようだが…」「Sí」 お由宇が『ランティエ』のことばを伝えると、婦人は誇らしげに頷いた。(へえ…これがガウディの…) 天井は不思議な曲線の浮き彫りに覆われている。波打際、或いは水面に広がる波紋のように、緩やかにくねった線に率いられた繊細な曲線が、まるで水中から表面を見上げているように天井に張り付き、広がりうねっている。「グエル公園、グエル邸、聖家族協会、ラ・ペドレラ、バトリョの家……中でも聖家族教会は未完だけど、この街のシンボルになっている。ガウディの残した計画全部を完成させようとすれば、少なくとも後200年はかかると言われてるけど」「はあ…」 200年先の未来へ向けて聳える塔……その時、人間て奴は何を考えているのだろう。 イレーネ・レオニは周一郎だけを追って10年を過ごしてきた。200年、その塔を追い続けようとしたガウディや、彼の遺志を引き継いでいく人々は、一体何を求めて追い続けていくのか。「…生は愛、愛は犠牲……神の創造は 継続し、創造主は被造物を利用する」「?」「ガウディが生と創造について言ったとされています」 『ランティエ』は少し肩を竦めた。 始めの部分は納得できるようなできないような気分だが、後の方はよくわかる。俺なんか、しょっちゅう創造主の気まぐれに利用されている。 俺達はやがてこじんまりとした居間に通された。「滝さん」「ん? …それが『青の光景』か?」「はい」 先に入っていた周一郎が、B4程度の大きさの額入りの絵を手渡す。「でも、これにマイクロフィルムはないみたいです」「ふうん?」 受け取って、しみじみとそれを眺めた。と言っても、別にそれほど変わった絵じゃない。ピカソが描いたにしちゃ、極めて地味な愛想もくそもない絵で、どこの部屋だろう、正面に十字架と小さな祭壇を配した質素な小部屋が、ありとあらゆる青で描かれているだけだ。もちろん、その青の種類の豊富さは絶品と言えるんだろうが、幻の名画と言えるほどの作品とは思えない。「どう思う、お由宇?」「どうって……それほどの価値とは思えないわね、『ランティエ』?」「そうですね」 『ランティエ』は曖昧に笑って見せた。「贋作家の力量を問われる作品ではありますが……なにせ、この青の色ときたら……ちょっとでもイメージが狂えば別物になり兼ねませんし」「Señor…」 周一郎が振り返り、滑らかなスペイン語で女主人に何かを尋ねた。少し頷いて、相手が俺達に移動を促す。「その部屋へ案内してくれるそうです」「あ、うん」 不自由そうに松葉杖を操る周一郎に、高野がさりげなく手を貸した。そのままゆっくりと女主人の後についていく。 母屋から出、内庭(パティオ)を隔てた庭の隅の小さな建物に、女主人は俺達を導いた。「ここだそうです」 鍵を開ける。木製の重そうな扉を、微かに軋ませて静かに開く。 外見上は母屋よりなお平凡な、立方体の上に四角錐が載っているような建物で、そのイメージは中に入ってもそれほど変わりはしなかった。八畳ほどの大きさ、正面に、アーチのように波打つ曲線で彫り込んだ壁に祭壇と十字架、左右の壁は微かに波打っているようだが見た目にはわからないし、窓は一つも無い。扉を開けたことで入り込む日差しが照らす床は、複雑なモザイク模様……だが、それだけのことだった。ガウディと聞いて想像するような、あの独特の空間の存在感はない。むしろ、最近あまり使っていないという婦人のことばを証明するように、うっすらと積もった埃が舞い上がり、『青の光景』に描かれた、身の縮まるような森閑とした『青』のイメージはなく、ただ干からびた夢の残骸があるだけだ。「ピカソの作品であることは間違いないけど……どうして、彼はこの部屋を描いて『青の光景』なんてタイトルをつけたのかしら」 何も発見も納得もできず、とりあえず部屋を出た俺の耳に、お由宇の呟きが妙にはっきりと残った。 ****************
2022.11.29
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』8.夏の恋歌(マドリガル)(2)
**************** そうやって、過去の傷は時折深く、周一郎の心に口を開けていく。 再会したイレーネは、RETA(ロッホ・エタ)と組んで、周一郎の口からなんとか『青の光景』の行方を引き出そうとした。同時に、追っ手である俺達にアルベーロを接触させて動きを探り、あちらこちらと引き廻させようとした。だが暢子が渡欧し周一郎を追い始める。これはまずいとアルベーロに始末させようとしたが、そこまで手を汚す気は無いと拒否したのか、アルベーロを殺し、暢子も『ヒラルダの塔』へ呼び出し殺した。 あとは痛めつけた周一郎が『青の光景』の在り処を吐くのを待つだけになったイレーネの心に、この10年間が蘇る。求め続けた周一郎は手の中にある、自分はその周一郎を渡して、この10年の代わりに一体何を手に入れようというのか、と。『青の光景』を探し出して、それだけをRETA(ロッホ・エタ)に渡し、彼女が周一郎を抱き締めていては、なぜいけないのか、と。 けれども、RETA(ロッホ・エタ)との交渉は決裂し、イレーネはRETA(ロッホ・エタ)を屠り、周一郎を連れて死の逃避行に至る……。 これが、お由宇と周一郎がしてみせた謎解きだった。 コンコン。「はい」「どうも…」 ノックの音に続いて、ドアを開けて入って来た上尾は、暗く沈んだ表情で弱々しく微笑した。「上尾…」「滝君の忘れ物だよ」「ガルシア・ロルカ詩集…」「僕はこれから日本に帰る」 上尾は低いハスキーヴォイスで呟いた。ことさら周一郎の方は見ないように、「イレーネの埋葬も済んだし…」「ああ…」「じゃあ…」 出ていきかけて、上尾は背を向けたまま、唐突に熱いものを飲み下したように体を反らせた。「朝倉さんに言っても、仕方のないことだとは思うけど」 掠れた声が響く。「僕はきっと…あなたを許せない」「上尾!」 バタン! 上尾は咎める俺の声を振り切って飛び出し、勢いで閉まったドアが、それ以上の追及を拒んだ。椅子から腰を浮かせた俺は、そろそろと周一郎を振り返った。「…いいんです」 周一郎は微かに笑った。どこか幼く、「憎まれるのも慣れてるから…」「ばか」 手を伸ばして周一郎の頭をどつく。「そんなのに慣れてるやつなんか、いるかよ」「っつ」「わ、悪い!」 周一郎が眉をひそめ、俺はうろたえて手を振り上げた。傷に近いところを叩いたらしい。ったく、『ばか』なぞと人に言えたものじゃない、俺の方がよっぽど『バカ』だ。「そ、そうだ。せっかく詩集を持って来てくれたんだ、これでも読んでやろうか」「…そうですね」 周一郎は少し唇の両端を上げた。「えーと、これなんかどうだ? 明るそうだぞ、『夏の恋歌(マドリガル)』」 目次だけ見て、ページを捲る。「『夏の恋歌(マドリガル)』……」 周一郎の声が重い憂いを湛えた。「ちょっと待てよ……えーと………っ」 さっと目を通し、慌てて本を閉じた。「滝さん?」 不審そうに目を上げる周一郎に、引きつり笑いをしながら弁解する。「いや、そのな、ちょっと俺には難しそーでな、その、うん、あ、読めない漢字があってな! うん! そーなんだ!」「……ふ」 周一郎は小さく笑いだした。瞳が分かっているといいたげに揺れ、俺のうろたえぶりを静かに見つめる。「だから……そーだ! お前、もう寝ろ! うん! 良い子はおネンネする時間だ!」「まだ真昼ですよ?」「ここには昼寝(シェスタ)ってのがあるだろーが! ごちゃごちゃ言ってないで、病み上がりなんだ、とにかく寝ろっ!」 喚いた俺に、気持ちよさそうに目を閉じながら、周一郎は大人しく応じた。「はい、おやすみなさい」「ああ。……ぐっすり眠っとけよ」 微かに頷く。無理やり寝かしつけた割りには、数分待つまでもなく、すうすうと安らかな寝息が聞こえだし、ほっとした。「いいところ、あるじゃない」「…お由宇……いつの間に入って来た?」 声をかけられてぎょっとして振り返ると、スーツ姿のお由宇がにこやかに笑いながら、俺の手の中の本を覗き込んだ。指を伸ばし、『夏の恋歌(マドリガル)』のページを探し当てる。「こんなもん、読めるかよ……ただでさえ落ち込んでるのに」 『夏の恋歌(マドリガル)』に俺も目を落とす。 静かで仄暗く深い情念、相手が自分を愛さなくとも、自分は相手を愛するだろうと語る内容だ。 イレーネのことばが重なる、誰よりも愛していて、誰よりも憎かった……。「…にしても」 お由宇は軽く腕を組んで、ベッドの周一郎を見つめ、溜息をついた。「よく寝てること」「だろ? やっぱり疲れてんだよ、こいつ」「…だけじゃないでしょうけど。私がいるって言うのに、安心しきっちゃってるわね」 まるで絶対の安全圏に居るみたい。 ぼそりと付け加えた声が殺気を含んだ気がして、思わず尋ね返す。「だけじゃない? お前が居ると、あいつが眠れん理由でもあるのか?」「あなたは、わからなくって、いいの」 お由宇は極上の聖母じみた笑みを返してい言い放った……。****************
2022.11.28
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』8.夏の恋歌(マドリガル)(1)
**************** バルセローナ。 スベイン北東、カタルーニャ地方の都会。ピカソが育ち、天才建築家ガウディが育んだ街。新しい思想と芸術、植民地戦争の敗北、政治の激動、20世紀末のこの都市は、興奮と絶望の泡立つような混沌の中、スペインを代表する芸術家達を深く豊かに熟成させていった。「ほら…」「大丈夫です」 差し出した手を見向きもせず、周一郎は左手で松葉杖を操って、巧みに車から降りた。右手はまだ首から吊っていて、ちょっとしたことでバランスを崩し、羽織った背広と共に体をふらつかせる。「無理すんなよ」「無理なんかしていません」 慌てて差し出した手で支えると、周一郎は憎まれ口をきいて手を振り払い、先に立って歩き始めた。影のように高野が付き添い、俺を振り返りもしない。(ちぇっ) 差し出して放り出された手のやり場に困って、胸の中で舌打ちする。 ったく。ちょっと元気になるとこれだ。あれがちょっと前までベッドで大人しくしていた人間の台詞かよ。 数日前のことが思い浮かぶ。「おい…何してるんだ?」 一応ICPOに報告だけはしておくわ。 そう言って、『ランティエ』と一緒に病院を出て行ったお由宇を見送って病室に戻った俺は、周一郎が不自由そうにベッドの上に体を起こそうとしているのに呆気にとられた。「滝さん…」 なぜかほっとしたような優しい声で応じてこちらを見返し、再び周一郎は横になった。「何だ? 何か用があったのか?」 問い掛ける俺を奇妙に透明な目で凝視する。「仕事ならさせんからな。高野もしばらく見合わせるように連絡したって言ってたし……何か欲しい物があるのか? 水か? 果物か? 飯か? パンか?」 くす、と周一郎は唇をほころばせた。「…いえ…」「本か? テレビか? ラジオか?」「もう…いいんです」「? …んじゃ、何をしようとしてたんだ?」「別に…」 答えて、周一郎はわずかに赤くなった。「? …トイレか?!」「違いますっ!」 喚いてますます赤くなる。 そりゃ、こいつの『突発性赤面症』には結構慣れてはきたが、今回はどうも原因がわからない。「わからんなー」「もういいんです」 いつものように、どこか怒った声音で唸って、周一郎はベッドに潜り込んだ。拍子にどこかぶつけたのだろう、あっ、と小さく呟き、微かに眉を顰めた。「だから動くなってってだろ? 欲しい物があったら、持ってきてやるから」 俺はぶつぶつ言いながら、掛け布団を引っ張り上げてやった。大腿骨中央部にひびが入り、打撲、裂傷4ヶ所、右肩裂傷3ヶ所、左の額からこめかみにかけて裂傷2ヶ所、そのほか細かな傷や打撲は数え切れず、全身疲労困憊、イレーネの逃避行がうまく進んでいれば、もう数日で限界に達していただろう体力ぎりぎりのところ、と聞いて、坊っちゃま思いの高野は半狂乱になり、医師の言う絶対安静期間を、独断と偏見で更に5日延ばす事を命じていた。背こうものなら『切腹』でもしかねない勢いに押され、さすがの周一郎も今度ばかりは大人しく言いつけに従っていた。「ったく、よく生きてたな」「人間、そうすぐには死にませんよ」「お前がよくても、高野が先に狂い死にする」「そうですね」 高野の剣幕を思い出したのだろう、周一郎はくすくすと小さく笑った。「笑い事じゃない」 いささかむっとする。「だいたい1人で何もかも背負い込んじまうから、こう言う事になるんだろうが。アランフェスでだって、1人にならなきゃ、拐われるこた…」「知ってたんです」 物憂げに周一郎は吐いた。深く沈んだ瞳の色を隠そうとするかのように目を伏せ、淡々と続ける。「アルベーロが動き始めたことも、滝さんの大学に汀暢子がいることも、イレーネ・レオニが行方不明になった後、RETA(ロッホ・エタ)に接近したらしいことも。だから、佐野さんの警告があった時に全てが読めた……もっとも、佐野さんがあのリストのことで、ぼくと話したがっているとは知らなかったけど」「なら、尚更だろ」 俺は噛み付いた。「わかってたんなら、どうしてわざわざアランフェスまで行ったんだよ。あのカードのことだって、高野まで騙して…」「あのカードがどうして日本にあるのかはわからなかったんです。……イレーネが、アルベーロを通じて暢子に渡させたと話すまで」 頭の中を上尾の声が通り抜けていく。 暢子はアルベーロに殺意を抱いてはいたが、当面の敵は朝倉周一郎、アルベーロがこれで周一郎をおびき出せると教えたときには、自分を殺そうとしているのも知らないでバカな男と嗤いながら、表面上はおとなしやかにカードを受け取ったのだと上尾に話したそうだ。 だがその実、暢子もイレーネの指先に操られていたのだったが。「だけど、お前のことだ」 湧いてくる疑問になおも言い募る。「カードのことがわからないにせよ、罠だってことぐらいはわかってたんだろ? 何も、好んでそこに飛び込むこたないじゃないか」「……知っていた、と言ったでしょう」 周一郎は気怠げに唇を動かした。「イレーネが何を望んでいるか、イレーネがぼくをどう思っているか、10年前から知っていたんです。だから、あの計画を動かした時、いつか、必ずイレーネはぼくを追ってくると思っていた………そして、たとえ大悟が生きていたとしても、『その時』ぼくを助けてはくれないことも」 アランフェスでの高野の話が蘇ってくる。高く澄んだ青紫の空、荒涼たる大地の狭間、豊かに緑たたえる沃野、その中に1人佇みながら、僅か9歳の少年はそんなことを考えていたのだ。自分の計画と相棒、未来にかけられた代償の鎖、救いのない道の果て、暗闇の中を歩いていて、唐突にぶつかる死の匂い……。『周一郎は、ローラに嫉妬したのかも知れないわね』 周一郎が病室に軟禁状態になっている間、訪れたお由宇は不思議に甘い笑みを浮かべた。『計画の相棒などと言う条件なしで、つまりは「無条件」で、大悟に受け入れられたローラ・レオニと自分を比べて。まだ9歳の少年だったのよ、肉親にも等しい人の愛を探し求めても不思議はないでしょう? 「だから」周一郎は、より熱を持って計画を進めたのかも知れないわ。大悟を自分に惹きつけようとして、そしておそらくは、その反面、大悟が計画に反対することを願って、ね。………彼にとって、大悟がローラを裏切らないと言うことは、他でもない、周一郎をも裏切らないと言う、ほんの小さな、けれど何よりも欲しい、保証のように思えたのかも知れない』 けれど大悟は計画を進め、ローラ・レオニは死に、周一郎は大悟の片腕としての高い評価を受け……そして、周一郎『自身』は、大悟という出口を永遠に見失った。「いつか、必ず、イレーネはぼくを狙ってくる…」 皮肉な笑みが周一郎の唇に広がった。大人びた口調で、「イレーネだけじゃない、僕も待っていたんです、10年間」 風が吹き寄せてくる。異国の乾いた風が、窓から入り込み、枕に乗せた周一郎の髪を嬲り頬に乱れさせる。左手で不器用にそれを掻き上げながら、周一郎は低く話し続けた。「アランフェスでレオニの配下に囲まれて、それからイレーネと再会して………僕らは同じ種類の人間なんです。光が明るければ明るいほど、強ければ強いほど、できる影がより濃く、より深くなるように、僕らは光を追えば追うほど、自分の中にある影に目を向けずにいられない。それに取り憑かれて、いつもいつも身動きできなくなっていくのをじっと見ているだけなんだ」****************
2022.11.27
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』7.村(6)
**************** 汚れた床の上、倒れたイレーネの側に上尾が膝をついている。左腕に巻いたハンカチを右手で解き、片手で不器用に広げ、無言のままイレーネの顔にかけた。ステンドグラスの破れ目から光が一筋差し込み、上尾とイレーネの遺体を照らす。 美しいと言うには、あまりにも痛々しい光景だった。「死者の覆いを取るわけにはいきませんね」 『ランティエ』がネクタイを緩めながら上尾の側に寄る。上尾の頬に伝わっていくものに、誰もが気づかぬふりをした。「にゃん」「お、ルト」 ふいに猫の声が聞こえ、俺達は近づいて来る小猫を見つめた。「お手柄だったな」「にゃい」 当たり前だと言いたげにルトが鳴き、周一郎の側へ寄る。心配そうな金色の目をして、にゃあう、と体を主人に擦り付けた。「大丈夫だよ。すぐに病院に連れていくってさ」「はい、もちろんです」 高野が頷き、上尾の腕にネクタイを巻き終えた『ランティエ』と共に、周一郎を運びにかかる。お由宇は上尾を促して車へと急ぎ、後を追って古ぼけた教会を出た俺は、ふと背後を振り返った。『誰よりも愛していて、誰よりも憎かった!』 イレーネの叫びが谺のように聞こえて来る。それは、怖いけれども懐かしい悪夢の切れ端に似て、俺の胸に妙な切なさを残した。もっとも、あの時死んでしまってりゃ、こんな悠長なことも言っていられなかったのだが。「ま…生きてられて良かったよ」「にゃん。にゃあ…」 ま、ね。けれど、それはいいとして。 そう言う感じでルトは立ち止まって、俺を見上げた。「何だ? 何か言いたいことがあるのか?」「にゃい。にゃー…」「毎回言うようだが…」 俺はしゃがんで抗議した。「俺は猫語は受講(と)ってない」「にゃあ…」「ま、お前に人間語をしゃべろとは言わんが……何? 何だ? 胸になんか、ついてるのか?」 ルトの視線に胸元を見た俺は、ふと気付いた。あの教会へ駆け込むまでは、ルトはここに居たよな。で、いつ、こいつ降ろしたっけ?「あれ?」「にゃ…」 そう言えば、教会に駆け込む寸前、何か『落とした』気がする。ついでに何か、『細い紐』みたいな物を踏んだ気がする。あれって、ひょっとして…。「に、や、あ……」 ルトは牙を剥き出し、ひょいと尻尾を立てて見せた。ゆっくりとそれをくねらせる。「あ…あは、あれ…ひょっとして……お前の尻尾か?」 思わず引きつった。「にーやーあーあーあーあ…」「悪い! そうとは知らなくってさ、その、別に悪気はなくって……どああああっ!!」 ルトが不気味な鳴き方をした次の瞬間、俺の指は見事に報復にあっていた。****************
2022.11.26
コメント(0)
-
2010000ヒット、御礼!『ラズーン7』2.羽根の誇り(2)
****************「南で『鉄羽根』と『運命(リマイン)』が再びぶつかり出したそうだぞ」「大丈夫なのか、『鉄羽根』は」 与えられた私室の扉の外で、声高に話す者がいる。 アリオは臥せっていたベッドからゆっくりと体を起こした。 侍女はうるさく言うので追い出してしまった。『氷の双宮』への避難が始まっている、すぐさまお向かい下さいませ、と何度も何度もしつこいぐらいに言い募ったので、それほど怖いなら出て行っておしまいと叩き出したのだ。 ミダス公の屋敷には多くの侍女が残っていたし、主人亡き後もセシ公が手配を怠らず、人の気配は日増しになくなっていくが、それほど不自由は感じない。何より、アシャの側に、あのレアナとか言う辺境の礼儀知らずの小娘が侍り続けているのに、どうしてアリオがさっさと身を引くことができよう。 確かにアシャは長く病床にあり、いささか窶れた気配もあるが、それでも衣装を改めれば、その美しさは全く衰えていなかった。むしろ儚げで妖しげな気配も加わり、アリオの胸に強く焼け付くような思いを与えるほどだ。今は『氷の双宮』で敵味方を区別すると言う厳しい任務についているが、それだからこそ憩いと癒しを求めに、いずれはきっとアリオの元にくるはずなのだ。そうでなければならないし、そうであるべきだ。なぜなら、アリオは『西の姫君』、ラズーンにあってもその人ありと褒め称えられ続けた美貌なのだから。「雨が降ってきている」「恵みの雨となると良いが」 扉の外の無礼な会話は続いている。「ジーフォ公もついに前線に出られたらしい」「四大公が欠けていくばかりではないか」 ジーフォ公が欠ける? アリオは思わず薄く微笑んだ。 アリオを欲し、アリオを束縛し、アリオの人生を歪めてしまう、あの男が。 アシャがいなければ、多少の拠り所とはなったろうが、アシャがいるならば話は別だ。レアナに我が物顔に振舞われるのも、アリオがあの無骨な男のものだなどと認識されているからだ。「いっそ、散って仕舞えば良いのに」 あの男は戦いが好きなのだ。血の臭いを喜び、剣を振り回して武功を立てれば女が寄ってくると思い込んでいる馬鹿者だ。ましてや、アリオを手に入れるために、武功などは意味がないと何度言ってやってもわからない。戦果を挙げる度に、今度はどこのならず者を抑えた、どのように競り合って勝ち、どのように賞賛されたと話をしてくる。 そう言えば、一度雨の中での戦いの難しさを話していた。けぶる視界、体温を奪う氷雨、足元はぬかるみ、剣の切れ味も鈍り、馬は疲れ切り、声は通らない。士気を高め、戦術を練り、体力を温存しながら戦い続けることの厳しさ難しさ、だが、それを凌いだ時の達成感は何物にも代え難いのだ、と。 私よりも、と尋ねたものだ。いつもは聞き流すだけなのに。 私を手に入れることよりも、喜ばしいものですか。 ジーフォ公は明かりに向けていた顔を、ゆっくりと振り向けた。底光りするような瞳だったと覚えている。背筋が寒くなるような強い視線だったとも。戒められると思った。押し倒され、奪われるとも。 けれども、その瞳をジーフォ公は伏せた。 そなたは手に入らなくて良い、と静かに応じた。 ただそこに居てくれたことが、勝利の証なのだと。 窓の方を見やった。 先ほどまでは晴れていた。明るい日差しが差し込み、アリオの判断全てを正しいと後押ししてくれているように感じた。 だが今は? 日差しが陰り、薄雲が空を覆い、冷たい風が吹き下ろしている。 ジーフォ公が欠ける。 侍女は追い出した。 アシャにはレアナが侍り、統合府ラズーンからは人が消えていく。 この先は、どこに繋がっているのだろうか?「…っ」 アリオはベッドを滑り降りた。扉に近づき、一気に引き開ける。 驚いたように身を引く二人の兵士が居た。見たことがない気もしたが、そもそも下級兵士の顔など覚えていない。誰であろうと良い、質問を聞く耳と答える口があるなら。「今の話を聞かせなさい」「…え」「南で『鉄羽根』と『運命(リマイン)』とやらがぶつかり出したのですか」「あ、あの」「私はアリオ・ラシェットです」「ああ、ジーフォ公の」 なんと忌々しい称号か。「ええ、そうです。しかし、ご安心下さい」 若い兵士が笑った。「ジーフォ公は百戦錬磨、『鉄羽根』のテッツェは無限の策を繰り出せます。『運命(リマイン)』がどれほど攻め寄ろうとも、ラズーンの門は通しますまい」 それでは困る、と胸の中で囁く声がした。 ジーフォ公が見事に『運命(リマイン)』を防ぎ切っては、『太皇(スーグ)』の覚えもめでたく、アリオがジーフォ公に嫁ぐことを誰もが喜ばしいと言うだろう。しかし、ジーフォ公が南の戦地で果てれば、アリオは愛する婚約者を失った哀れな女性、庇護が必要なのは自明の理、アシャとて無視するわけにはいかなくなるはずだ。「…それでも心配なのです」 アリオは訴えた。「無事なお姿を一目見たい、そう願ってしまうのは無謀でしょうか」「…それは…」 ちらりともう片方の兵士が若い兵士を見やる。「お気持ちはお察しします、しかし戦場へ姫が出向かれるのは無理なことです」「遠くからでも、無理でしょうか」 アリオは両手を組んで強請る。「あそこにおられると、見るだけでも……それだけでも夜の眠りが得られそうで」「……ご心配、なのですね」 若い兵士が目を細めた。何かを考え込むような顔になり、「……ひどく遠くになりますが」「構いません」「雨が降っております」「濡れるのも覚悟です」 この先の自分の未来が、少しでも明るくなるのなら、多少の汚れは我慢するしかないだろう。「…では、我らと共にいらっしゃいますか」 若い兵士は頷いた。一瞬瞳が妙に揺らいだようにも見えたが、幻だったのだろう、すぐにまっすぐアリオを見つめてくれた、熱心に真摯に。「実は我々はジーフォ公に合流する隊に属するものです」 こちらへ、と導かれるままにアリオは歩き出した。「南の戦いを少しでも支えようと、セシ公に命じられて、これから出ようしているのですが、遊軍として極秘に動くことになっております」「あなたは運が良かった」 もう一人が感慨深げに呟いた。「お一人では戦地に向かうのは無理だったでしょうから」「ええ、ええ、本当に」 アリオは出来るだけ、艶やかに微笑んで見せる。「幸運でした、お二方のお話を聞けて」「中にいらっしゃるとは思わなかったのですよ」「扉も閉まっておりましたし」「侍女の姿も外にはなく」「てっきり空き部屋とばかり思っておりましたので」 交互に語る二人の兵士に導かれて、アリオは進む、今まで歩いたことのない回廊を、薄暗く明かりが灯されていない理由を、密かに旅立つための準備と疑いもせずに。人の気配が全くしないのを、すでに使われていない部屋部屋があるためだとも考えずに。 そうして、なぜ、遊軍を密かに差し向けるような状況だったのに、この二人だけがアリオの部屋の前で、たまたま、南の戦況の話を声高に語っていたのかも不思議に思わずに。「さあ、ご覧下さい」「あなたをお守りして進む部隊ですよ」 薄暗い廊下を抜けた扉の向こうに、数十人の集団が居た。雨が降り始める中、それぞれに重い旅装を身につけて、長旅をしてきたようにも思える姿、フードを深くかぶっているのは、雨も予想していたせいか。 誰とも視線が合わない。 不意にアリオは立ち止まった。「どうされました?」 若い兵士が訝る。「何かご不安でも?」 もう片方の兵士が覗き込む。「いえ、あの」 このまま進んではいけないのではないか。 初めてアリオは疑った。「余りにも、多くの方が、おられたので」「それはそうでしょう」 くすりと若い兵士が笑みを漏らした。黒い髪を掻き上げる。瞬きした瞳が、一瞬うす赤く光った気がした。「あの、私、準備、そう、準備が必要なものを忘れました」「大丈夫ですよ。すぐに戻れますから」「戻れる?」「当たり前ではないですか。『西の姫君』を戦地へお連れするのに、それほど長くお留めするはずもない、戦場は危険ですから」 若い兵士は笑う、人懐こく、明るく穏やかに。「さあ、お手を」 差し出された掌を、アリオは凝視した。 いけない。 この手をとってはいけない。 拳を握って身を翻そうとした矢先、「先ほどレアナ姫にもお声掛け頂きました」 若い兵士は歌うように話した。「我らの任務を労って下さいました、白く綺麗な指先を頂き、力づけられました」「私も」 アリオはきっと振り返った。「あなた達を鼓舞できますわ」「ええ、もちろん」 若い兵士が頷く。「アリオ様の指は、我らを見事にまとめあげ、導かれることでしょう」 おい、みんな、と若い兵士は声を張り上げる。「アリオ様が来て下さったぞ。我らに勝利を下さるために!」 数十人がゆっくり振り返り、静かに拝跪の礼を取る。「どうぞ、アリオ様」 差し出された手にアリオは指先を預けた。 ひやりと冷たい、人の温もりのない掌を、アリオは雨のせいだと言い聞かせる。 垂れ込めた雲は大粒の雨を振り落とし始めた、頬を伝う哀れみの涙のように。**************** 今までの話はこちら。 ずいぶんお待たせしました。 2010000ヒット連載、『ラズーン7』です。 どの作品もそうですが、最近何を書くにも、書き出しは鈍く、何を書いているのかよくわからないことが多いです。元々は『見える光景』を描いていたのですが、最近は『流れることば』を拾っている感じです。拾って拾って拾ってするうちに、書いている内容や光景が見えてくる。読み直すと、なぜ今この内容なのかの意味が読めてくる。 すごく不自由で、あまり楽しくない書き方なのですが、読み返すと「うん、これでいい、内容も文章も異論はないな」となるので、大丈夫だと思いますが、さてこれを読まれている読者の方はどう思われていることやら。自分の能力のぎりぎり限界で書いているから、書いている最中は全体像や意味がうまく掴めないんですね。 書き上げて、少ししてから読み直し、ようやく「うんできてるな」とわかる。 でも「できてる」からどうなの。 「できてる」から評価されたり人気が上がったりしたことはあまりない。 むしろ、「できてる」と感じた作品の方が評価は低い気がする。 それって「できてない」ってことじゃないのか。 そもそも「できてる」って、何がどうできてるの。 とか色々考えるわけですが、「こっちの方がいい」という感覚は、もう数十年物を書いたり読んだりしてきた結果出てくるものなので、どうしようもない。「できてる」=「一番いいところにきちんと収まってる」って感じですね。 写真や絵画にもある。「ああ、ここが全てにおいて完全に一致してるな」みたいなところ。 面白いことに、日常生活の本当に何気ない場所に「できてる感じ」は見事にある。 電線と電柱と空の配置とか。 植木と置かれたゴミ袋と側を自転車が走っていく距離感とか。 何もかもがぴったり「整ってる」。治す必要がない。一番いい場所に、一番適切なものが置かれている。 「できてる」って言うのはそんな感じです。 陰陽師とかの、足運びやものの配置が「正しい」みたいなところ。 一つわかることは、この「できてるかどうか」の感覚に従って仕上げても、現金収入には繋がらない。 けれども、いろんなところで、そのものどんぴしゃりな恩恵がやってくる。 急にお金げが入用になったのに、数百円単位のズレだけで手元にあったり。 急ぎでエレベーター前に駆け込むと、誰かが呼んでくれたらしい(けれど今そこには誰もいないけど)エレベーターがばっちりとやってくるとか。 運の良さ、みたいなものが返される。 今はそれを頼りに書いてます。
2022.11.25
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』7.村(5)
**************** 改めて見れば、本当にとびきりの美人、どうしてこんな『忙しい』ときにしか美人と関わらんのだろーか。俺は平時にこそお付き合いしたいと切に切に願っているんだが。まあ、カッコつけて飛び出してはみたものの、なにせ美人を前にすると言語障害に陥るのが常、まともな啖呵がが切れるわけもない。「あ、あのさ、ちょ、ちょっと待ってくれません?」 俺はぽかんとしているイレーネに、へらへら笑いかけた。笑いたかったわけじゃない、断じて、自分の命が危ない時に笑いたかない。ただ、怖さで引きつった顔をなんとかしようとしたら、両頬が引きつって、で、つまりはそれが直らなくなったのだ。「そりゃ、その、待ってもどーという事はないわけで、何の得があるかと言われたら、これが何にもないわけで、俺としても非常に困るわけなんですが…あ…ははっ」 だめだ、笑い声までたててしまった。無事に帰しては……くれんだろーな、やっぱり。「もちろん、俺が困ったところで、あなたがどーというわけではないわけで……その…別に悪気があって笑ってるわけじゃないんですが、ちょっと、なんか止まんなくて……はっはははっ♡」 ぐわ……♡マークまでついてしまった。イレーネの顔がだんだん険しくなる。うん……やっぱり、普通は怒るよな、こういう場合。「あなたが…滝…ね?」「え? はあ…まあ…そーなんですね、これが……あははっ」「さすがに大物ね、こういう時に笑えるなんて」 違うっつーのに! 笑いたかないんだ、どっちかっつーと泣きたいんだってば! 今更ながら、毎度毎度己のアホさを、またもや後悔している最中なんだってのに。イレーネを愛していた上尾でさえ、ズドンと一発意識消失、俺ならきっと、ズドンと一発生命消滅、が最低ラインだろうなあ。「いや、ははっ、大物だなんて……はははっ」 俺の引きつり笑いは主人の意思を無視して続いた。それでも、人並みに膝だけは大笑いをし始めてくれている。今、走れと言われたら、俺は『絶対』こけてやる。「滝さん…」 背中で弱々しく、周一郎が俺を呼んだ。「危ない…から…」「危ない? うん、俺も実はそー思ってるところだ」 あ、ダメだ。頭の中が完全に崩壊している。ったく、肝心な時にポップコーン化を始めやがって。俺の両親はきっと、かなりひねた『とうもろこし』だったに違いない。 だが、その周一郎のことばに、イレーネは違う反応を見せた。呆気に取られ、続いて次第に目の光を強めて行く。「周一郎……『誰』なの、この男」「え? 俺? 俺、滝志郎です」「肉親…? いいえ、聞いたことがない……それに、肉親だって、あなたがそこまで甘えるとは思えない」 俺のことばには取り合わず、イレーネは呟いた。「誰なの? あなたにとって、この人はどういう人なの?」「あはは…単なる友人です」 おい! 俺の守護霊! 何とかしてくれ、この体ときたら、自殺する気だぞ!「答えなさいっ、周一郎!」「うわっ…」「滝…さんっ!」 次の瞬間、いくつもの事が同時に起こった。叫んで拳銃を向けたイレーネ、指にかかる力が俺の胸元を狙う。声を上げた周一郎が、銃口から逃げようとして半身ひねった俺の体に斜め後ろから飛びついてきて、銃口からかばうようにイレーネに背を向け、体を投げ出して無事な左腕で俺の首にしがみつく。勢いで流れかけた周一郎の体を支えはしたものの、爆笑している俺の膝が衝撃に耐えられるはずもなく、壁に押し付けられて座り込み…。 ごんっ。「てっ」 嫌というほど頭を打った。瞬時空白になった意識にも、次には弾丸が飛んで来るとわかっていて、思わず目を閉じる。静まり返る瞬間、凍りつく時間……。「……?」 が、いつまで待っても、熱いキスはやって来ない。そろそろと目を開けた俺は、イレーネがだらりと右手を下げて、固まったように俺たちを見つめているのに気づいた。その瞳に浮かんだ大粒の涙にも。「周一郎…」 掠れた声が絶望に満ちていた。「そこまで私を拒むのね…?」「…」 周一郎は何も答えない。熱っぽい体を俺に預けて、身動きしようともしない。「10年間、あなたのことだけを考えていたわ…」 ついに、光るものがイレーネの頬を伝った。それは、割れ砕けたステンドグラスの隙間から差し込む真昼の日差しに眩く煌めいて、埃の積もった床に零れ落ち続けた。「いつも、あなたのことばかり想っていたわ」 針の落ちる音さえしない静けさの中で、異様な告白は続いた。「私はあなただけを愛していたわ」 すうっと右手が上がった。彼女のこめかみ辺りの髪を、銃口が優しく搔き分ける。「誰よりも愛していて、誰よりも憎かった!」「!!」 ドンッ!! 思わず目を閉じ顔を背けた俺の耳に、どさりと言う鈍い音が響いた。まるでそれを待っていたかのように、するりと周一郎の腕が解ける。「周一郎?!」「坊っちゃま!」「志郎!」 ぎょっとした俺の目に、蒼白な顔に伝わった血の筋が映った。いつの間にきたのか、お由宇達が戸口から飛び込んで来る。「おい!」「揺さぶらないで! 気を失ってるのよ」 お由宇が俺を制した。手早くハンカチを取り出し額に巻く。高野がネクタイを外し足に縛り付けた。右肩は、カッターシャツの腕を裂いて手当てした。「あ…上尾は?」「大丈夫ですよ、擦り傷です。もっとも、『心』の方は知りませんが」 『ランティエ』の声に、俺は振り向いた。***************
2022.11.25
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』7.村(4)
**************** 仰け反って頭を打ち、泡立った脳味噌の整理にうろたえる俺の耳に、聞き慣れたハスキーヴォイスが届く。(上尾?) どうしてここに、と思うまもなく、上尾は振り返ったイレーネの前に立って叫んでいた。「やめてくれ、イレーネ! 一体何をしてるんだ?!」「上尾…」 寂しげな顔立ちに不似合いな、朱色の唇が柔らかくことばを紡ぐ。それが何かの呪文でもあったかのように、イレーネの頬に哀れむような微笑が浮かんだ。「そうね……あなたも来ていたわね……」「イレーネ、説明してくれ、君は……君……暢子さんを殺したのも君なのか?」「そうよ、上尾……」「朝倉さんを連れ去ったのも…」「…そうよ、上尾…」 イレーネは甘く笑った。「どうして…何で…」「それだけじゃないのよ、上尾。アルベーロを殺したのも私……どうして、あなた達がすぐに私の後を追って来れたのか、不思議だったけど…」「アルベーロが札を握って教えてくれたんだ。だけど、どうして、イレーネ! アルベーロは君を愛して……そればかりか、RETA(ロッホ・エタ)の仲間だったんじゃないか!」「そう……アルベーロは教えたの…」 懇願するような上尾の声に、イレーネは笑みを深めた。それはアランフェスでの暢子の笑みに似て、どこか仄暗い翳りを見せる笑みだった。「私に暢子さんを殺させまいとしたのね……でも、私の愛はそこにはないのに…」「イレーネ!」「そう……始めは『青の光景』を取り戻して、RETA(ロッホ・エタ)に戻るつもりだったわ……父の汚名を晴らして、朝倉周一郎を出し抜いて……でもね、上尾」 きらり、と面立ちに背く激しい炎が、瞳の中で光を放った。「『影』が私を呼んだのよ、周一郎という影が」 周一郎に半身背中を向けたまま、拳銃を構えた右手で周一郎を指す。「朝倉さん? …影? ……」 上尾の呟きは、そのまま俺の問いかけでもあった。「……10年前…私の父、パブロ・レオニは、周一郎と朝倉大悟に陥れられたわ。たまたま友達の家に居た私だけが助かって……恨んだわ、2人を。いつかこの手で、必ず闇に突き落としてやろうと思い続けて来た……けれどもね、上尾…」 イレーネは濃い睫毛を一瞬伏せ、緩やかに上げた。「今でも覚えている……父が死んで数日後、沈んだ私を友人が闘牛場へ連れて行ってくれたの。陽のあたるソルの席……昔は、ちゃんとソンブラの席に座れたのにね。悔しい想いを噛み締めて見上げたソンブラの席に……周一郎が来ていた」 声が深い震えを帯びた。「私達を破滅に追いやった男……睨みつけていたのに、もう一方でどうしようもなく魅かれていった……影の中、側に保護者を控えさせて、じっと闘牛を見つめる歳下の男の子……憎い、けれど、何を犠牲にしても手に入れたい………牛が倒された瞬間、そう思っている自分に気づいたの」「…『真実の瞬間』…」 上尾が吐くように呻いた。「そうね…」 イレーネが微かに頷く。「それから、父の汚名を晴らすため、とか、バスクの誇りを守るため、とか、いろいろな理由をつけてRETA(ロッホ・エタ)に近づいたし、アルベーロを利用したし、暢子さんを殺したけど……そのどれも、きっと私には意味がなかったんだわ……。真実は1つだけだったのよ……周一郎が憎い、他の誰よりも憎い……そして、周一郎が欲しい……他の誰よりも」「イレ…!!」 ドギュンッ!! ことばと同時に持ち上げられていた拳銃が、いつの間にか上尾を狙っていた。上尾が青ざめる間もなく、銃声が響き、腕を撃たれて上尾は吹っ飛び、扉まで転がった。「ごめんなさい……上尾…」 相変わらず、寂しげな顔立ちに不似合いな、酔ったような甘い笑みを浮かべて、イレーネは続けた。「もう…周一郎を誰にも渡す気はないの……RETA(ロッホ・エタ)にも、神様にも」 イレーネは振り返った。朱い唇が至上の天使のことばにも似た優しさでことばを紡ぐ。「愛してるわ、周一郎」 しなやかな指先が、周一郎の胸元に狙いをつけた拳銃の引き金を引こうとする。その時、俺は指の先を嫌というほどルトに噛まれて悲鳴を上げた。「ぎゃわ!」「誰っ?!」 ええいっ、くそっ! 身を翻すイレーネの手には拳銃がある。んなこた、わかってる。でも、仕方ねえだろ、俺の足がまた勝手に走り出しちまったんだから。「滝…!」「志郎!」 前後からぎょっとした声が同時に響いた。俺の頭の中はスローモーションからコマ送り、一歩一歩に3~4倍の速度になったような心臓の鼓動の効果音付きだ。「待てよっ!」 日本語がわかるなら話が早い。俺は考える間もあらばこそ、半分、壁から崩れ折れかけている周一郎を庇ってイレーネに向き合っていた。****************
2022.11.24
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』7.村(3)
**************** それほど大きな丘でなかったにせよ、俺がそこへ辿り着くまでには、数回ルトに指を齧られていた。「ぎゃわ!」 指先に激痛が走って、思わず跳ね上がり立ち止まる。はあはあと息を荒げながら、コートの隙間から俺の行き先を監視しているルトにお伺いを立てる。「ど…どっちだ、ルト」「にぃ」 小さく鳴いたルトが、ある方向へ体を押し付ける。俺はそっちへ向かって再び走り出す。 丘の裾にしがみついている白壁の建物は、アンダルシア特有の眩さで照り輝いていた。その街並みの中を、ルトの指示に従って右へ左へと走り続ける。近くに寄れば、丘は荒れ果てた地肌に黒々とした木立をへばりつかせ、なだらかに、けれども素直には人を近づけ得ぬ複雑な路を連ねて、人を十字架に導いた。「はっ…はっ…はっ…」 透明で高く澄んだ空の下、十字架は骨のように白白とした石のキリストを支えていた。素朴な風雨に晒された十字架、両手を広げ、少し首を傾げているキリストの顔も、初めの頃にはあっただろう目鼻立ちが薄れ、夢見るように遠い視線を遥か先の村に投げている。それは、救いへの祈りと言うよりは、救いを求めるのに疲れ果てた人々が自ら闇に走り込んで行くのを嘆きもしないが責めもしない、ただ無限の哀しみを湛えて見つめる聖母マリアの慈悲にも似て、沈痛で優しい不思議な表情だった。「ルト……これからどこ……」 ドギュンッ!「どあっ!」 唐突に響いた音に、俺は思わず首を竦めた。聞こえてきた方向をそろそろと振り返る。(今の……ひょっとして……銃声、だよな?) 少し離れた場所に、古ぼけた教会が建っていた。鋭角に支え合った屋根の頂上に、朽ちかけた十字架があるのでようやくそれとわかるような廃屋、左右にあるステンドグラスの窓もひび割れ砕け落ち、色とりどりの光を差し込ませた窓の桟だけが残っているような有様、こちらに半ば正面を向けている扉も、片方は傾いて今にも外れそうだ。 ドギュンッ! ドギュンッ!「っ!」 ぼんやりと考えている間に、再び銃声は、干からびて優しい十字架のキリストと、丘の上の乾いた風を揺り動かした。何かが心に弾け飛ぶ。天啓に似た鮮やかさで、想いは胸の裡で砕け散り、無意識に走り出していた。 周一郎が居る。「周一…!」 ドギュゥンッ! 木の扉に達して叫ぶのとほとんど同時に、三度銃声は空を裂き、思わず本能的に立ち止まった。視界に飛び込んできた光景に、全ての感覚が意識の外へ押しやられる。 正面、朽ちて埃だらけになった祭壇、古ぼけた十字架に苦悶と安らぎを交錯させてキリストが身を預けている。左右、空間を支える緩やかな弧を描く薄汚れた白い壁の所々には、手を胸に交差させた天使達の像が浮き彫りにされている。そしてそれらの下、十字架のキリストの視線を浴びて、1人の少年が立っていた。「…」 きつく唇を噛んで背けた顔に乱れた髪、頭と数十cmも離れていない場所に黒い小さな物がめり込み、パララ…と思い出したように、壁土が穴から右肩に零れ落ちる。カッターシャツ1枚の肩は、異様などす黒い紅に汚れていて、落ちた壁土が白く目立った。似たような紅は左足、大腿部のあたりもべっとりと濡らし、立つのさえやっとで壁でようよう体を支えている。それどころか、今にも崩れ落ちそうな身体を、凄まじい意志力で保っているのがわかった。 やがて、壁にすがったまま、周一郎は閉じていた目を薄く開いた。乱れた髪の間を透かし、顔を背けたまま一瞬こちらを見つめ、すぐに目を伏せる。ほうっ、と深い溜息を漏らした。「…どうして、すぐに殺さない?」 弱々しい、けれどもはっきりと嘲りを響かせた声で尋ねた。つうっ、と額の辺りから滲んだらしい紅が、筋を作って頬をかすめて這い降りる。言われてみれば、周一郎の首近く、脚近く、腹近くのあたりの壁にも弾丸のめり込んだ跡があった。きっと威嚇射撃だったのだろう、さっきからの銃声は。「…10年、待ってたのよ」 アクセントの少し違う、けれども滑らかな日本語が聞こえた。俺からは、波打つ黒髪としなやかに伸びた手足しかわからない、女性の後ろ姿から発せられたものらしい。「バスク人の私がアンダルシアで暮らし続けて、あの日から10年……毎日毎日、あなたのことだけを考えていたわ、周一郎」「……」「いいえ、出会った時から、きっとこの瞬間を待ち続けていたんだわ」 不思議に甘い声だった。瀕死の相手、10年も恨みを抱き続けた相手を前にしていると言うよりは、前世より焦がれ続けた永遠の約束の相手に向かって話しているような、蠱惑と喜びに満ちた声だった。「あなたは、私のことなんて忘れたでしょうけど……」「…忘れてなんか…いない…」 低く掠れた声で周一郎は応じた。「覚えていたよ……いつか……必ず来ると思っていた…」「そう…嬉しいわ」 女性の声ははにかんだ。「私達の繋がりが『青の光景』だけじゃなくて」 沈黙しか戻らない、けれど女性は微かな殺気を込めて続けた。「それも、もう終わりだけど。これが最後よ、周一郎。『青の光景』を返しなさい」「…嫌だ…と言ったら…」 微かな笑みが周一郎の唇に滲んだ。「……ねえ、周一郎」 女性があやすように優しく話しかける。「私も、この10年、何も知らない小娘のままではいなかったのよ。いろんな情報の手に入れ方も覚えたわ」 ぎくり、と周一郎が小さく体を強張らせる。「今、どんな情報が新しいのか教えてあげるわ。『朝倉周一郎誘拐事件に、身代金として、滝と言う男が「青の光景」を持ってスペインに来た』……何なら、その男性に聞いてもいいのよ」「滝さんは関係ない!」 はっとしたように、周一郎は叫んだ。急な体の動きに、傷が痛んだのだろう、小さく呻いて壁に体を押し付ける。噛み締めた唇の色は既に白くなって来ている。が、周一郎はそっと口を動かして、囁くように呟いた。「滝さんじゃない……『青の光景』は僕しか知らないんだ……」「じゃあどうして、あんな情報が流れたわけ? 出所も確かだし、滝と言う男がきているのも事実よ。そればかりか、その男があなたの『秘書』と一緒にあなたを追いかけているわ。赤の他人がそんなことをするとは言わせないわ」「滝さ…んは…」 ふっと一瞬、周一郎の体がよろめいた。壁に沿って崩れ落ちようとするその時、思わず飛び出しかけた俺を突き飛ばし、俺の足を思いっきり踏みつけて、教会の中に飛び込んだ奴が居た。「あぎゃ!」「イレーネ!!」****************
2022.11.23
コメント(2)
-
『青の恋歌(マドリガル)』7.村(2)
****************「けれど、わからないのは」 お由宇の声に我に返る。「どうして、イレーネはあの2人を殺したのかってことね」 俺は、再び、お由宇から丘の上の十字架に目をやった。 俺達がイレーネの後を追って、セビーリャから南西に下り、ここより少し北にある街で一夜の宿を求め、情報を探った矢先に引っ掛かったのは、その日のシェスタに起こった殺人事件だった。 女1人、男2人、そしてどう見てもまともな連れとは思えないぐったりした青白い顔の少年という奇妙な一行が宿を取り、部屋に落ち着いたのはいいが、夕方、女と少年が宿を出たまま帰らなかった。訝しんだ宿の者が部屋を改めてみると、部屋の中では2人の男が絶命している。飛んで来た医師の検死で毒殺とまではわかったが、女と少年の行方は知れない、とんだ事件もあるものだ、と言う話だった。「2人の男はレオニの配下、つまり、言わずと知れたRETA(ロッホ・エタ)……イレーネにとっては味方のはず……いいえ、味方どころか、『青の光景』を手土産に父の汚名を晴らし、RETA(ロッホ・エタ)に入ろうとしていたイレーネにとって、味方以上の大切な人間だったはず…」 だが、イレーネはRETA(ロッホ・エタ)に返り咲く機会を自ら断ち切ってまで、周一郎を連れ去った。 『青の光景』を手に入れる為に、イレーネが払ったものは決して少なくない。父と母は昔のこととは言え、幼馴染のアルベーロを死なせ、自らの手で暢子を殺し、そして恐らくは、RETA(ロッホ・エタ)で約束されていた新しい生活をも失い。が、最後の瞬間、イレーネはそれらの絆を一切捨てて、周一郎を連れて夜に消えた。「手がかりはここまでよ」 お由宇が振り返った。鋭い目になって、『ランティエ』、上尾、高野を見回し、最後に俺に目を落ち着ける。「後はこちらが追いつくのが早いか、イレーネが行き着くのが早いか………何れにしても、あの傷じゃ、周一郎君の時間が限られてくる」「坊っちゃまを死なせるわけには参りません」 高野がきつい声で断じた。「お捜しします、何としてでも」「僕も及ばずながら、お手伝いします」 上尾が沈んだ声で続ける。「まだ、イレーネがそんな事をしているとは信じたくない」「結構。『青の光景』にもう一目会いたいものです」 『ランティエ』が両手をポケットに入れて歩き出す。「じゃ、志郎。あなたはここで待っててくれる?」「っ、俺だって!」「スペイン語、喋れるようになった?」「ぐ」 悪かったな! どーせ俺は日本人だよ!「心配しないで。私もライバルを失う気はないもの、全力を尽くすわ。ここに居て、連絡役をお願い」 お由宇達が四方に散ると、俺はふて腐れて車のシートに埋まり込んだ。(くそっ!)『十字架の立つ丘(カルヴァリオ)』を睨みつける。いつもこーなんだ。いつも肝心のところで、俺は周一郎の役に立ってやれない。(だからなのか?) 心の中で問いかける。赤い染みのついたベッドに、周一郎の顔が重なる。(だから、俺に一言も言わずに行っちまったのか?)「んなろっ!」 俺は喚いて体を起こし、車を降りた。勢い良く、ドアを叩きつけて閉める。ふんっ、何が連絡役だ! 犬も歩けば棒に当たる。俺だって、刑事の真似事ぐらいは出来るんだ。頭の巡りは良かないが、せめて捜して歩き回るぐらい……。「べ!!」 歩き出した瞬間、すっと足元を過ぎった白いものにどきりとして、出した右足を引っ込めた。ただ問題は、その時左足も既に地面から浮いていたと言う状況で、俺はもちろんそのまま思い切り、前方に叩きつけられていた。 目の前に星が散る。星だけではなく、カラスも飛んでいく、アホーアホーと鳴きながら。 もう、本当に泣きたい。俺が何をしたってんだ、前世に何をやったから、神様ってのは、ここまで主人の命令に逆らう足をつけてくれたんだ。(俺が歩けば地面に当たる…) 冗談じゃないっ! んな、しょっちゅう当たってたまるか! 俺だって、一応は25年間、地面の上を歩いて来たわけで、何も最近、地球に来たわけじゃ…。「に…ゃあ…」(にゃあ?) 掠れた弱々しい声が足のあたりで聞こえて、俺はむくりと体を起こした。起きる拍子に足に力が入り、同じ声が抗議する。「にぎゃ!」「ルトぉ?!」 俺は慌てて、道の端にへたり込んでいる小さな体を抱き上げた。いつも奇跡的につやつやしているはずの青灰色の毛並みはずず黒く汚れ、所々固まってしまっている。額のあたりに黒くこびりついたものは、底に血の赤さを秘め、尻尾や前足などにも傷があった。「おい……本当にルトか?」「に…ゃん…」 瞳を上げる、その金色の虹彩にすがるような色があった。そっと出した桃色の舌で俺の指先を舐め、体をすり寄せ、小さく鳴く。「にゃ……あ…ん…にゃ……にぃ…」「大丈夫か? お前……ひょっとして、周一郎を追ってたのか?」「にぃん」 ルトは頷くように顔を上下させると、のろのろと疲れ切ったように『十字架の立つ丘(カルヴァリオ)』を見遣った。俺の頭に天啓が閃く。十字架の立つ丘(カルヴァリオ)。周一郎がそう書き残しているのに、俺達はどこを捜そうと言うんだ。「ルト」 呼びかけて、コートの中、胸元にルトの体を入れた。ボタンを上の方まで留め、腰でしっかりベルトを締める。少々走っても落ちないとは思うが、一応手を入れて、その体を支えた。「あいつの居場所を教えろ」「にゃ」 ざらついた舌が応じるように指先を舐めた。「走るぜ、落ちるなよ!」 俺は『十字架の立つ丘(カルヴァリオ)』に向かって走り始めた。****************
2022.11.22
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』7.村(1)
**************** きっ、と軽い音とともに車が止まる。ドアを開けて足を下ろすと、靴の裏で乾いた土が音を立てた。「志郎」「ああ…」 助手席から先に降りたお由宇の白く細い指がさす先、いじけたような草が地を覆い、小さな村が蹲る背後に、同じく小さな丘があり、そこに十字架がぽつりと立っていた。「十字架の立つ丘…」 高野が重い足取りで車を回ってきて見つめ、呟いた。「変わっていない……10年前のままです。あの十字架の後ろの方に、小さな教会があるのです」「ここが、ローラ・レオニの生まれ故郷…」 頭の中に、昨日のことがゆっくりと戻ってくる。「!」 安ホテルの女将に嗅がせた鼻薬の効き目を待つ間ももどかしく、俺と『ランティエ』は、古ぼけ煤けた階段を駆け上がり、イレーネが泊まっていたらしい3階の一室のドアを開け放ち、瞬間凍りついた。「……」 無言で部屋の中に踏み込む。一目で、ここに暮らしていた何者かがうろたえて出て行ったことがわかる荒れ方、古風な木の椅子が、安っぽいプラスチック製のドレッサーには不似合いに転がっていた。机の上に汚れたコーヒーカップ、机の下にもう一個が砕けている。白い陶器の肌が妙につやつやと、小さな窓から差し込む陽を跳ね、薄汚れたベージュの壁紙に淡い光の影を揺らせている。 だが、俺がショックを受けたのは、イレーネが既に消えていると言うことだけではない。「滝さん」「あ…あ」 『ランティエ』の声に、俺はようよう声を絞り出した。渇ききった喉を騙すように唾を飲み込む。だが、そのわずかな水分さえも、脇の下や背中や掌に滲む冷たい汗となって流れ出して行ってしまうように、ほんの少しも喉を潤してはくれなかった。「どうやら、朝倉さんの傷は、掠り傷ではなさそうですね」「……」 『ランティエ』の声に、殴りつけてやりたいような凶暴な気持ちが溢れる。だが、俺の眼は振り返ろうにも、部屋の奥にある粗末なベッドに惹きつけられたまま、どうにも動かせない。 血の汚染(しみ)。 べっとりと粘りつくような、表現し難い粘稠性を持って、それはベッドの中央と枕のあたりに染み付いていた。どす黒く変色しているのは周囲だけ、中央の方は、まだその源を語ろうとするように、生々しい温かさと紅を保っていた。ベッドの端、丸めてくしゃくしゃになっている茶色の背広をそっと手に取る。それで止血しかけたのか、所々に黒々とした血がこびりついている。 コト。「っ」 小さな音が背後で響き、俺は慌てて振り返った。「お由宇…」「遅かったようね。『ランティエ』、伝言ありがとう」「どういたしまして」 『ランティエ』の側をすり抜けたお由宇の後ろから、高野と上尾が姿を現わす。上尾がひっ、と息を呑み、棒立ちになった。高野がゆっくりと部屋の中を見回し、俺の手の物に目を止める。掠れた叫びが高野の口を衝いた。「それは坊っちゃまのものです!」「まだ死んではいないはずよ」 お由宇は厳しい声で言いながら、ベッドのあたりに屈み込んだ。「死んだなら、イレーネが連れて行くはずが……うん?」「何かあったのか?」「これ……周一郎君の字?」 硬い声でお由宇が尋ねた。差し出した小さな紙切れに、乱れたたどたどしい字が読み取れた。「ああ」「カルヴァリオ……わかる?」「知らん」 素っ気なく答える声が一体誰のものかと思えば、自分の声だった。はっとしたように高野が応じる。「カルヴァリオ………ひょっとして、十字架の立つ丘、のことではないでしょうか。ロルカの詩にあります。それに、確かローラ様の生まれ故郷は、ここよりもう少し南西の小村、十字架の立つ場所の近くと伺ったことがございます」「ロルカの『村』ね」 きらっと目を光らせたお由宇が、くるりと身を翻らせた。「あの女主人、まだこの部屋を見てはいないわね」「たぶん。1時間ほど前にイレーネと2人の男、それに抱えられるように1人の少年が出て行った、と言っていましたからね」 心得たように『ランティエ』が答える。「じゃあ、さっさと出ましょう。ここで女主人に見つかったら、周一郎君を追うどころじゃなくなるわ」「同感ですな」「お由宇」 部屋を出て行きながら尋ねた。「『村』って、どんなのだ?」「……見捨てられた村を詩ったものよ。十字架の立つ丘、オリーブの木々と澄んだ水、顔を覆った人々、塔の上に回る風見……不吉で侘しい光景のね」 伏せた睫毛の下の瞳が、珍しく頼りなく揺れた気がした………。****************
2022.11.21
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』6.騎手の歌(4)
**************** 回教徒のモスク跡に1402年から100年ほどかかって建てられた116m×76mの規模はスペイン最大のカテドラル、入り口のパロスの門を足元に、『ヒラルダの塔』はある。 高さは97.5m、大小28個の鐘が並んだ70mの高さの展望台から最上にある風見(ヒラルダ)までの部分は16世紀、その下は12世紀に建てられたらしい。正方形の塔の内部には階段がなくて、内側を伝う緩やかな坂が、セビーリャを見渡せる展望台へと導いてくれる。 『ランティエ』を入り口に、高尾と上尾を坂の中ほどに残して、俺とお由宇は9時の開場を待つのももどかしく、『ヒラルダの塔』展望台への坂を登り続けていた。昨夜のカー・チェイスの後、車で仮眠をとっただけの体は、ともすれば安らかな眠りを求めてのめり込みそうになる。重い足を引きずりあげながら、俺はこう言う酔狂なものを建てた人間と言う代物を呪っていた。「ったく……こんな高いものを作り上げやがって…」「そうね」 対照的に軽々と足を運びながら、お由宇が不思議に甘い笑みを浮かべた。「どうして人は塔を作るのかしらね」 俺達を追い抜かして行った男が、すれ違いざまにお由宇ににっと笑っていく。「バベルの塔然り、アントニオ・ガウディの聖家族教会然り、近代の高層建築然り。何を求めて天空へと手を伸ばしたがるのかしらね、届かないとわかっていながら懸ける恋人への想いのよう」「んな良いもんでもないだろ。狭い所にたくさんの人を詰め込むのに都合がいいだけで」「教会に人が住むわけ?」「いや、そう言うわけじゃないけど」「人を詰め込む為なら、地下を掘ってもいいわけでしょう? 地下に建造する技術と、地上に積み上げていく技術、そう大差があるようには思えないけど」 そうだな。どうして人は空に焦がれるのか、と言う歌が昔あった気もする。重力から逃れて、支えるものも縛るものもない空を目指す数々の塔の行き先に、人は何を見ようとしたのか。「だけどさ、お由宇」「え?」「暢子の行き先は、本当にここでいいのかな」 前後の人々の中に、あの娘の顔を見つけられないまま、お由宇を、それから再び前を見つめた。「上尾だって、はっきりここだって聞いたわけじゃないし、あの『覚え書』からの発想だって、怪しいと言や、怪しいもんだろ?」「まず間違いないと思うわ」 お由宇はに薄く魔的な笑みを浮かべた。「RETA(ロッホ・エタ)が追ってきたことで、暢子がセビーリャに来ているらしいのはほぼ確かだし……何より、アルベーロがそう教えてくれているものね」「アルベーロ?」 きょとんとする。俺達が辿り着いたのは、アルベーロが死んだ後だ。いくらお由宇が人の心が読めるとは言え、死人の心まで読めるとは思えない。 俺がぼやくと、お由宇はくすりと笑って、久しぶりに例の決まり文句を口にした。「ばかねえ」「どーせ、俺はバカだ」「いじけないの。アルベーロが紙幣を握ってたって言ってたでしょ、『ランティエ』は」「ああ?」 ますますわけがわからず首を傾げる。「あれ、旧100pts.紙幣だったって聞いた?」「いや…でも、それがどーしたってんだ?」「グスタボ・A・ベッケルの姿が印刷された100pts.紙幣の裏には『ヒラルダの塔』が描かれているの」「さよーで」 一度、お由宇の頭の中を覗き込んでやりたい。きっと常人の数倍の速さで神経のパルスが飛び回っているに違いない。「ふう…」 ようやく展望台に辿り着き、次第に増えてくる人々の間から、眼下を眺める。冬だと言うのに、弱々しくなるにはまだ早いと言いたげに日差しはきつく、独特な猛々しさで辺りを照らし出している。南から東にかけてはアルカサルとマリア・ルイサ公園、東から北は茶色の屋根と陽をなお白く輝かせる白壁の街並み、西側へ目を向ければカテドラルの建物が、そしてその後方には円形の闘牛場が見える。彼方にはグァダルキビール河が大きくうねりながら流れているはずだった。(周一郎…) 色と形が鮮やかに交錯する光景を見渡しながら、胸の中で呼びかける。(お前……この風景の…どこにいるんだ?)「ん?」 視線を移していった俺は、展望台の隅にどこかで見たような顔を見つけた。寂しげな、けれどもきれいな顔立ち、朱い唇が不似合いに目立つ。(え?) 確かあれは、あの小さなタブラオで踊っていた舞姫、そう思い出すと同時に、女性が被っていた帽子を深く引き下げ、俺はぎょっとした。広い帽子のつばの下、朱色の唇が魔的な色合いに変わる。エレベーターですれ違った女とそっくりだ。 だが、俺が本当に驚いたのは、女性が次にとった行動だった。展望台の隅、トレーナーを着てジーパンを履いたショートカットで小柄な人間に、踊るような足取りで忍び寄ると、何のためらいもなく体を強く押し付けた。ぎくりとして振り返った顔が驚愕に、続いて激痛に歪む。「うっああああああ!」「暢子!」 俺の警告はほんのわずか遅すぎた。少年のような格好をした暢子は叫び声を上げて崩れ落ち、必死に抱え込んだ身体から大量の血が流れ落ちる。周囲の観光客から悲鳴が上がり、逃げようとするもの覗き込もうとするもの呆然と立ちすくむものが入り乱れた。その中を1人悠々と体を翻して坂を駆け下りていく女性の姿が、まるで影の中に逃げ込もうとする魔性の何かにも見えたのか、慌てて道を譲る人々をすり抜け舞姫は姿を消していく。「んなろっ!」(あいつ!)「志郎!」 お由宇の呼び声を耳に、俺は人にぶつかりながら後を追った。怒鳴り声と罵声の中、蹴り上げた誰かの足と押しのけた腕の向こう、のめりそうになりながら先を急ぐ。重力は俺の味方をしていて、転がるように坂を走り降りていく。(イレーネだ) なんの根拠もなく、だが、この上なく確信を持って、俺は思った。 パブロ・レオニの娘、ローラ・レオニの娘、アルベーロの最愛の恋人、考えても見ろ、スペインでも名の知れたトップ屋が、あのタブラオで、いくら日本語がわからないからと言って、どうして俺達の側を離れて、飛び入りのフラメンコなぞを踊ったのか。情報を渡すべき相手が居たからだ。そして、俺達の側に居るよりは、イレーネの側に居た方が俺達の話がよくわかったからだ。 上尾のことばが頭の中を駆け抜けていく。日本語を習うのに異常なほど熱心だったイレーネ・レオニ、俺達の話を踊りながらアルベーロに通訳する、スペイン後の密やかな囁きで。(けれど、どうしてなんだ? イレーネは上尾のことが好きだったんじゃないのか?)「滝様?!」「滝くん?!」 高野と上尾の叫びを無視して、俺は走り続けた。弾け飛びそうになる心臓と、安物のエンジンよろしく焼け尽きそうになる頭、ふいごのように鳴り響く呼吸の中で考え続ける。 やっぱり本筋は暢子じゃなかったんだ。暢子はイレーネの軌跡に混じり込んだ火花、一瞬煌めいて消え失せた。だが、どうしてここにイレーネがいた? どうして、暢子がイレーネに殺された? そして何より、周一郎は一体どこにいるんだ?「滝さん!」「ぐえっ!」 ぐっとカッターシャツの襟あたりを掴まえられ、俺は危うく縛り首になりかけた。かっと昇った血の助けを借りて、引き止めた『ランティエ』を怒鳴りつける。「人を殺すなよなっ!」「どうしたんですか?」「暢子が刺された!」「ノブコさんを殺したのは、私ではありませんが…」「んなこたわかってる! イレーネだよ! イレーネ・レオニ!」 俺は慌てて周囲を見回した。今彼女を見失ったら、今度こそ本当に周一郎の行方がわからなくなっちまう。バタン、と音がして、振り返ると『ランティエ』はいつの間にか車に乗り込んでいた。「こっちです、滝さん!」「ああ!」 こける寸前、ようよう『ランティエ』の車に転がり込む。待つまでもなく、『ランティエ』は乱暴に車を発進させた。「い…行き先……わかっ…わかってるっ……るのかっ…」 乱れた呼吸にことばにならない。ちょい、とバックミラーを直した『ランティエ』が薄く笑った。「もし、滝さんの前を走っていたご婦人がそうならね。タクシーに乗り込むときに、ちらっとホテルの名前が聞こえましたよ。少し遠いが小さな安ホテルです、うまくいけば追いつくでしょう」「てめえ!」 俺は『ランティエ』の気障な背広の胸ぐらに掴みかかりながら喚いた。「それが聞こえるぐらい近くにいて、どうして捕まえなかった?!」「私にイレーネ・レオニだと分かるわけはないでしょう? 彼女は14歳の時から行方不明のまま、あの由宇子さんだって、今のイレーネの顔を知らなかったんですからね。あなたがわかった方が不思議なぐらいで……」「でも、おかしい、ぐらいはわかったろーが!」 塔の中で起きた叫びと怒号、溢れ出すような人の流れの中で、1人追い立てられないで走り抜ける女性の姿は目立たなかっただろうか。「だからと言って、私が捕まえる義理はないでしょう。私は警察じゃないんですから」 『ランティエ』の台詞は薄々気づいていたことを語っている。「あ…あのなっ! そりゃ、そうだがな! そりゃ……」 ことばに詰まった俺を面白そうに見ていた『ランティエ』は、チチチッ、と軽く舌を鳴らして生真面目な表情になった。相手の視線に振り向く俺の目に、前方十数メートル、2台の車が接触して大破しているのが映る。「事故のようですね。まずいな……逃げられないといいんですが」「っ」 一気に片方へ押し付けられて舌を噛みかけた。車が勢いをつけてカーブする。「少々回り道になります」(…周一郎) また遠ざかる。 嫌な予感が心の中にじんわりと広がった。****************
2022.11.20
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』6.騎手の歌(3)
****************「由宇子さん」 唐突に『ランティエ』の声が響いて、俺は我に返った。「『ヒラルダの塔』と言うのは当たってたみたいですよ。残念ながら、すぐには行けそうにないが」「え?」 道に迷ったのかエンジントラブルか。だが、お由宇はちらっとバックミラーに瞳を動かして、少し目を細めた。「はあん」 納得したように呟き、セミロングの髪に軽く触れる。「ちょっと見えなくなったと思ってたら、懐かしい友人の登場、と言うわけね」「友人?」「そ。ご丁寧にパッシングライトして、位置を知らせてくれてるわ」 くい、と立てた親指で後ろを示す。振り返る俺の目に、いつの間に現れたのか、黒い大型の外車が、すぐ後ろに迫って来ていた。チカッとライトを点滅させる。続いて数回瞬くライトに、お由宇に目を戻した。「知り合いか?」「私とあなたと共通の、ね」「俺はスペインに知り合いなんていないぞ」「あら…」 お由宇はひょいと肩を竦めて見せた。「居るじゃない、RETA(ロッホ・エタ)が」「RETA(ロッホ・エタ)ぁ?!」 ちょっと待ってくれ、RETA(ロッホ・エタ)ってのは、暢子を狙ってんじゃなかったのか?「何言ってるの」 お由宇は呆れた。「さっき言ったでしょ、RETA(ロッホ・エタ)が本当に狙ってるのは『青の光景』だって」「わかってるって。だから、周一郎を連れてる暢子を…」 言いかけて、顔から血の気が引いた。「わかったようね」 お由宇が笑みを含んで応じる。「事実はどうであれ、『情報』では『青の光景』を持っているのは『あなた』でしょ?」 お…おわっ…。「それを突いただけで、私達までずっと尾行して来てくれた輩が、獲物を目の前にして周一郎君に拘ると思う? 心配しなくても、復讐心に燃えた暢子は周一郎君を葬るのに躊躇しないでしょうし、そっちの始末は彼女に任せて獲物を取り戻そうとするのが『常道』でしょ?」 んな『常道』があってたまるか! 俺は『大物』じゃない、ただの一般大学生だ!「弁解が通じる相手じゃないしね」 お由宇は俺の気持ちを見抜いたように呟いた。「それよりも、どうしてこんなに早く、私達の位置が掴めたのかしら。そう、足取りをすぐに追えるようなのんびりした移動はしていなかったはず……志郎!」「わっ、はっ、はいっ」 いきなり呼ばれて硬直した。「ちょっとその辺り、コートの裾とかポケットとか衿とか探してみて。1㎝四方、もっと小さいかも知れないけど、黒いプレートみたいなもの、ない?」「プレート?」「そうか!」 はっとしたように高野が頷き、俺の体を撫で回し始めた。「そう言えば、あの時、一人の女性とすれ違いましたね」「こっ、こらっ、やめろっ! 気色悪いっ! 自分でやるっ、自分でっ!!」 高野の手を振り払い、コートのポケットの中を探った俺は、くしゃくしゃのハンカチと映画の半券、スーパーのレシートなんかと一緒に、丸い小さなボタンのような物を掴み出した。何せ、ポケットなんて、物を放り込むだけで中身を探るなんてことも滅多にしない。煙草も吸わない俺にとって、特にコートのポケットなぞ、移動式簡易ゴミ箱ぐらいの役割しかない。「?」「ありました、佐野様」「なんだ?」「TEー33型。電波発信器よ。追われるのもわかるわね」 お由宇は受け取った黒ボタンを指の間から滑り落として、ぐっと踵で踏みつけた。微かな音がして、表面のくすんだ黒の金属が凹む。「今更遅い気もするけど」「だけど、いつ?」「まあ、相手があなただから…」 どーいう意味だ。「チャンスは山ほどあったでしょうね。誰か綺麗な人に見惚れている間にでも入れられたんじゃない?」「綺麗な人?」 脳裏に、初めてスペインへ来た時のことが思い浮かんだ。エレベーターから降りる時、すれ違った女性、広いつばの下で笑った朱色の唇……。(あの時か?)「とにかく…」 『ランティエ』が後続の車との距離を目測しながら言った。「撒きます!」「ひえいっ!」 ぐんっ、と車が振り回されて、俺達が乗った車は横滑りしながら向きを変え、そのまま速度を落とすことなく、角を曲がって突っ走った。俗に言う四輪ドリフトと言うやつか、複雑に入り組んだ街路に入っても、ほとんどスピードを落とさず走り続ける。狭い路、すれすれの幅、壁を掠めて走り抜けるが、敵もさる者、多少は離されてもしっかりついてくる。「仕方ありませんね」 『ランティエ』は小さく溜息をついて、やや広い路を選んでスピードを上げた。前方に小広場、さすがに深夜のこと、人影が少ないのをいいことに、そこへ突っ込んで行く。「ちょっと派手ですが」「ひえええいっ!!」 ぎゅいんっと嫌な音がして、ふいにかかった急ブレーキに車の後ろが大きく回った。ハンドルを回す『ランティエ』は平然として、ブレーキをかけるや否や、アクセルを踏み込む。次の瞬間、俺達の車は180度方向転換、尾けて来た車と正面に向き合っていた。広いとはいえ、車が2台、並んで走り抜けられる幅なぞさらさらない。身を竦める俺に『ランティエ』の叱責が飛ぶ。「右へ寄って!」「っ」 とっさに高野に引っ張られ、体が浮いた俺は高野と上尾を下敷きにせんばかりに右へ突っ込んだ。ふわっと車体が傾く。ギャギャギャギャッと鼓膜を痛めつける音が響いて、車は片輪走行で追手とすれ違った。慌てた相手がハンドルを切り損ねてスピンしながら流れて行く。やがて背後でグワッシャッ、とお決まりの衝撃音、数秒後に紅蓮の焔が夜を焼いた。「ま…この程度ですかね」 ことばもない上尾と俺に、『ランティエ』はあっさり言い放って、バックミラーの中からにやりと笑った。****************
2022.11.19
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』6.騎手の歌(2)
****************「くっ……はっはははは…」「?!」 唐突に『ランティエ』が大笑いを始めてぎょっとした。反対に、高野が苦り切った顔で黙り込む。ただ一人、お由宇が肩越しに視線を投げ、歌うように言った。「それで?」「それでって……後はそうたいしたことじゃないんだ」 笑い続ける『ランティエ』を横目に付け加える。「たださ」「ただ?」「『ランティエ』の方はわかったけどさ、どうしてお由宇が関わってるのかなと思ってさ」「駄目ですねえ、由宇子さん」 『ランティエ』は喉の奥でくつくつ笑いながら俺を見た。細くなった瞳の底に、ぞっとするほど冷たい光があった。「なかなかどうして、大した『大物』じゃないですか」「『ランティエ』」 お由宇がにっこり艶やかに微笑した。「志郎と付き合ってみれば、もっと驚くわよ。彼、マイクロフィルムのマの字も知らないで、今のセリフを言ったんだから」「え」 どきりとしたように『ランティエ』はバックミラーの中から俺を見つめた。で、肝心の俺はといえば、頭の中は見事にパニック、交通整理のお巡りさんが一個連隊で欲しい。「頼むから、お由宇」 言い飽きたことばを口にする。「謎掛けは、もうちょっとヒマな時にしてくれ」「わかったわ。構いませんね、高野さん」「…仕方ありません」 高野がむっつりと答える。「仕方ないって……なんだ? まだ何か俺に隠してたのか?!」「今までの話で納得しててくれれば、こっちの手間が省けたんだけどね」 お由宇は軽くウィンクして前に向き直った。「話は10年前に戻るけど、アルベーロの事に気付いたなら、どうして大悟のことに気づかなかったの、志郎?」「大悟?」 あの、周一郎の義理の父親がどーしたんだ。「考えてもごらんなさい、10年前、政局の不安定なスペインに、いくらパブロ・レオニの名を借りたとは言え、どうして朝倉大悟が食い込めたのかしらね。どうして、ETAは手出しをしなかったのかしら。首相をダイナマイトで吹っ飛ばすなんて、派手なことをしているのに? そして、パブロはどうして、そこまで『青の光景』に拘ったのかしら。仮にも裏の世界で『青(アスール)』と異名を取るほどの男、大悟1人に手こずるなんて? 付け加えれば、パブロ・レオニはバスク人よ。アンダルシアの、それもスペイン人には歓迎されないジプシーの娘、ローラを手に入れるのに、どうしてそこまでこだわったのかしらね」「……」「どうしたの?」「悪いが、予備の脳を使い果たした。3分待ってくれ、湯をかけて作る」「別に作らなくても、事は簡単よ。大悟は切り札を持っていたの」「切り札?」 俺は眉をしかめた。「スペードのエースとJ(ジャック)か?」「武器密売人のリストを写したマイクロフィルム」 お由宇の声は淡々と続いた。「ほんの手違いだったのよ。ある情報屋が『青の光景』に隠したリストは、RETA(ロッホ・エタ)の作戦では『青(アスール)』のコードネームを持つパブロに渡り処分されるはずだったの。なのに、どうしたことか汀佳孝の手に渡ってしまい、おまけにそれをRETA(ロッホ・エタ)が取り戻す前に、朝倉大悟に押さえられてしまった。大悟は朝倉財閥の情報網を動かして、その辺の事情は知っていたんでしょう。それを盾にRETA(ロッホ・エタ)とパブロを抑えたの。パブロの方はと言えば、汀が『青の光景』をローラに託したと思い込んで彼女を娶れば持っていない、それどころか、競争相手の朝倉大悟に押さえられてしまっている。けれど、大悟はその絵を渡そうと申し出た。諸手を挙げて賛成し、絵を取り戻すのと引き換えに南欧の貿易網を開放したパブロは、マイクロフィルム入りの絵さえ手に入れば、いつだって大悟を葬れると思っていた。ところが、渡された絵にマイクロフィルムはなかった。詰め寄っても知らぬ存ぜぬで押し通され、南欧貿易網の要は取って代わられ、もうRETA(ロッホ・エタ)を動かすしかないと決心したパブロだったけれど、先手を打った周一郎の罠が待っていた………そして、あの、惨劇」 お由宇は肩越しに薄く笑った。「私が来たのは、リストを手に入れるようにICPOから頼まれた為よ。最近どうやらまた動きが激しくなって来たようだから………10年間は長いけど、特殊なルートでもあるから、それほどメンバーが変わってないはず。朝倉大悟が手に入れたところまでは突き止めていたから、あとは周一郎君と交渉するだけだと思って、あの学園祭の日に会う予定だったんだけど」 お由宇のことばが蘇る。何が学園祭に誘ったら?だ。何が喜ぶわよ、だ。なんのこたない、俺をダシにしてただけじゃないか。「日本にアルベーロが来てるって情報が入ったでしょ。おまけに、周一郎君を追っているみたいだって言うし。そっちに先に連絡を取ってたら、一足違いでスペインに飛ばれちゃったし……一応、警告はしておいたんだけど」「私が……不注意だったのです」 高野が絞り出すように吐いた。「佐野様から御連絡があったと言うのに……坊っちゃまをお一人にすべきではなかったのです」「お前が悪いんじゃないさ、高野」 俺は落ち込んだ高野を慰めた。そーとも、大体何もかも一人で背負い込んじまうあいつが一番悪い! そりゃ、俺が知ってたところで、せいぜい睡眠薬か枕の『代わり』で、助けらしい助けにはならなかったと思うが……。(けど、待てよ?) アルベーロは、俺達が日本に居る時に、既に『誰か』からの依頼を受けて、周一郎を追ってたわけだ。『誰か』ってのは、誰なんだ?****************
2022.11.17
コメント(2)
-
『青の恋歌(マドリガル)』6.騎手の歌(1)
**************** 夜を衝いて走る車の中には、外の闇よりも重苦しい沈黙が満ちていた。ハンドルを握る『ランティエ』、助手席で前方を見つめているお由宇、後ろで暗い表情で体を強張らせて座っている高野に上尾、そして俺も一言も口に出せないままだった。(周一郎) 窓の外を見ようと目を凝らしても、そこには黒々とした夜景が、しがみつこうとしては置き去られる魔物のように、妙にねっとりと流れているだけだ。(一体どこにいるんだ) ぼんやりと考える頭に、俺の部屋でぽつりと一人、立ち竦んでいる姿が思い浮かんだ。そっと忍び込んだ部屋、机の上にポートレートと読みかけの本を置いて、ベッドで眠り込んでいる俺を振り返る、そしてそのまま、身動きできずに立ち竦み……やがて、ゆっくりと身を翻して部屋を出ていってしまう周一郎。 重なるようにガルシア・ロルカの詩の一節が浮かぶ。 拍車を鳴らして歩む黒い子馬が死んだ騎手を運んでいる。身動きせぬ体、響く音、刃が幾重にも花のように重ねられる。(冗談じゃない) ぶるぶると首を振った。どーもいかん。何を考えても悪い方ばかりになっちまう。「お由宇」「え?」 気を取り直して、声をかけた。「なあに?」 意外に明るい声でお由宇が答える。「いや…そのさ、これって素人考えかも知れんが…」 もごもご呟いた。「ずっと引っかかってたんだが」「なにが?」「いや、そのさ、アンダルシア人とバスク人って、そんなに仲が悪いのか?」「…そうね」 窓ガラスに映ったお由宇が面白そうに頷く。「イスラム勢力が染み込んだアンダルシアは、最もスペインらしいかも知れないわね。他のヨーロッパ諸国とスペインの違いは、どれほどイスラムの影響を受けたかの違いとも言えるかしら。特徴的なのは時間に対する考え方……アンダルシア人にとって大切なのは現在だけ、未来も過去も関係がない、いかに今を楽しく生きるかが生活の基本」 片手で、さらさらと滑るセミロングを肩に流した。「そう言う人間の集まりが経済的に発展しにくいのはわかるでしょ? アンダルシア地方8県の平均所得は下位を低迷している。根強く残っている土地所有制度から逃れようとするなら、バスク、カタルーニャ地方への出稼ぎか移住……けれど、そうして移っていった先での彼らの評価は『ビーノばかり食らって仕事をしない怠け者』。まあ、アンダルシア人に言わせれば、バスク人達は『仕事ばかりしていて人生を知らない馬鹿者ども』と言うことになるけど」 くす、とお由宇は微かに笑った。「きっと日本人も、その『馬鹿者ども』に入るんでしょう。そのアンダルシア地方と対照的なのがバスク、カタルーニャ。天候や雨量もそうね。アンダルシアが『目が痛くなるほどの青空』なら、バスクは『曇って暖かい雨の日』。陽気で怠け者のアンダルシア人、陰気で勤勉なバスク人なんて言われてるらしいわ。生活水準はトップクラス、所得でも上位3位を占めるバスク……けれど分離主義の力が強くて、ETAの本拠地でもある。警官数も多いけど、アンダルシア出身が多いのを揶揄して、『警官という職業は体格さえよければ誰でもなれる』とバスク人は言う…」 上尾の話を思い出した。アンダルシア出身の警官である父親、周囲の侮蔑に耐えきれず、アルベーロは飛び出した。「だからなんだ」「え?」「だから、そこで引っ掛かってる」 ちらりと高野が横目で見た。上尾も興味を惹かれたようにこちらを振り向く。凝視されるのがくすぐったくて、もぞもぞしながら何とかことばを押し出した。「アルベーロはアンダルシア人だよな? ってことは、バスクでもあまり『受け』が良くなかったわけだろ?」 くっくっく、と『ランティエ』が笑った。 ふん、悪かったな、『一般的』な物言いで。「…ええ、そうね」 振り返らないお由宇の声は、なぜか淡い笑みを含んでいるように聞こえた。(いいさいいさ、笑いたきゃ笑え。どーせ、俺はプロじゃない) 心の中でぼやきながら先を続ける。「で、それが嫌で、父親のとこを飛び出したんだろ?」「ああ。イレーネはそう言ってた」 と、こいつもピンとこない様子で上尾が同意する。ほらみろ、俺だけがアホじゃない。「で、ETAってのは地方主義の塊で……つまりは、バスクがいっちばん、って奴らだよな?」 『ランティエ』は何がおかしいのか、低く含み笑いを漏らした。 あ、とふいに上尾が小さく声を上げた。「そうか…」 どうやら俺の言いたいことがわかったらしい。ふんっ、察しのいいヤツなんか嫌いだ。思わず相手を睨みつける。「?」「…だ、か、ら」 俺の視線を浴びてもきょとんとする上尾にぐったりしかけたが、気を取り直した。「RETA(ロッホ・エタ)ってのは、その中でも過激なんだろ? で、そのバスクが最高って連中が、まだRETA(ロッホ・エタ)に入ってもいない人間……アンダルシア人のためにわざわざ犯人を追うのか? いや、そもそもさ、アルベーロがRETA(ロッホ・エタ)に入れるってことが不思議…」****************
2022.11.16
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』5.晩鐘(4)
****************「話してもらおうか」 コルドバでも指折りの4ツ星のホテルの最上階の一室で、俺は上尾を睨めつけた。もっとも、俺1人ではたいした凄みはなかっただろうが、手持ち無沙汰な様子で凝った造りのナイフを放り投げている『ランティエ』、俺の左右に陣取るお由宇と高野に凝視されては、さぞかし居心地が悪いだろう。 生憎、俺達4人の誰一人として、上尾の為に周囲の環境を整備してやろうとはしなかった。「話せと言われても、どこから話せばいいのか……」 上尾は眩そうな目をして俺たちを見回し、この場の主導権のありかを探していたが、最終的にお由宇に目を向けた。「そうね、とりあえず汀暢子との関わりなんか、どう?」 お由宇はあっさりと応じた。「それとも、どうしてあそこに居たのか、でもいいし、どうして周一郎君の居場所を教える気になったのか、でもいいわ」「それが『とりあえず』なのか」 突っ込む俺に、「まあ『幾分か』は確信に近いかも知れないけど」「さよーで」 俺は諸手を挙げて、お由宇に尋問を任せることにした。「そう、だな…」 上尾はぼんやりと、急に気だるさに襲われたみたいに呟き、両手で顔を擦った。そのまま途中で手を止め、俯く。やがて絞り出すように、「あの子にはドゥエンデが憑いているんだ」「あの子?」「…汀暢子。イレーネの異父妹だよ」(あれ?) 鈍い俺でもそれなりに、暢子の名前とイレーネの名前に含まれた響きの差に気づいた。俺が気付くほどだから、お由宇がわからないはずもなく、もの柔らかく問いかける。「『イレーネ』だったのね、あなたの恋人は?」「ああ」 深い声で上尾は吐いた。(待てよ?) 思わず首を傾げる。 それならアランフェスでの痴話喧嘩は何だったんだ?「僕と暢子はイレーネを通じて知り合ったんだ。暢子は僕を盲目的に愛してくれた。僕を追って、日本にまで来た。けれど僕は、どうしても彼女を妹以上に思えなかった」「そして『あなた』が盲目的に愛したのがイレーネだったというわけね?」「…小さなタブラオで知り合ったんだ。日本にひどく憧れていて、熱心に日本語を習った。覚えも良かった。僕も夢中で教えているうちに……イレーネを愛してることに気づいた。………日本へ帰る直前に告白したけど……母親が辛い恋をしたのも、その恋が無惨に裏切られたのも見ているから、二度と恋はしない、と言った。自分は母親似なのだと笑った顔で淋しそうで、帰国してからも頭を離れなかった……。そこへ暢子が僕を追って来たんだ。僕は……これ幸いとイレーネのことを尋ねた」「恋は時に残酷なものです」 『ランティエ』が回想しているように優しい口調で受けた。「恋人以外の心は秤にかけることさえしない」「…そうだね」 上尾は同意した。「僕の頭にはイレーネのことしかなかった。暢子は激しく拒んで……そして僕を忘れる為に、日本へ来たもう一つの目的に没頭していった」「それが」 お由宇が物憂げに口を挟む。「父親を破滅に追いやった朝倉周一郎に復讐すること」「…何とか止めようと思って」 頷いた上尾は、ことばを継いだ。「暢子の後を追って渡欧したけれど、もう、遅かった。朝倉さんは行方不明になっている……それでも暢子の足取りを追いかけて、辿り着いてみれば」「アルベーロの死だった」 上尾は溜息をついた。「アルベーロは僕より先にイレーネを愛していた。同じ故郷、このアンダルシアの生まれで、父親がバスクで警官をするのに母ともども付き添ってアンダルシアを出たが……バスク人のアンダルシア人に対する侮蔑は根強かった。父の跡を継ぐのも嫌、かと言って、バスクでアンダルシア人がまともな職につけるわけもなく、バスクを飛び出し転々とするうちにトップ屋になったんだと、イレーネが教えてくれた。…それを暢子が知って……僕の為にいつかアルベーロを葬ってあげる、と言ってよこした。アランフェスで諌めたけれど無駄だった。……アルベーロと一緒に堕ちていくのを見ろ、そう言って、姿を消してしまった」 上尾はしばらく黙り込んだ。やがて身もがくように体を揺すり、「アルベーロを殺したのは暢子だろう……だが、あの子は知らないんだ、アルベーロのもう1つの顔を」「もう一つの顔?」「彼はアンダルシア人なのに、RETA(ロッホ・エタ)に属していたんだ。朝倉さんの死亡と朝倉財閥のルート崩壊を手土産に、RETA(ロッホ・エタ)の正式メンバーとして認められるはずだった」「それで」 高野が干からびた声で応じた。「RETA(ロッホ・エタ)が動いていたんですね」「だから!」 上尾は焦ったそうに唸った。「だから、早く暢子を見つけないと……あの娘はRETA(ロッホ・エタ)に報復されてしまう」「それで、俺達に周一郎の居場所と思われる場所を教えたのか? RETA(ロッホ・エタ)の報復から彼女を保護させ、そして、これ以上、人殺しをさせないために」「ああ…だって、見捨てるなんて出来ないだろう? 彼女はイレーネの妹なんだ!」 血を吐くような上尾の叫びに考えた。 イレーネの妹。 それは、暢子に取って、この上なく残酷なことばではなかったのか。 暢子がどれほど上尾を愛そうと、彼女は彼にとってはいつまでも『イレーネの妹』でしかない。いつまでたっても、彼女は『暢子』として上尾の眼に映ることはなく、おそらくは永久に、イレーネの影でしかない。 アランフェスで上尾を見据えた暢子の表情が浮かび上がる。 黒い瞳が奥に宿していたのは、手出しをするなと叫んだ口調に含まれていたのは、自分を愛してくれない上尾への憎しみや怒りではなく、ただただ、自分を『イレーネの妹』としてではなく、『暢子』として見て欲しいという、激しい憧れだったんじゃないか。 けれども、上尾はそれに気づかなかった。そして暢子は、アルベーロを抱き込んで、暗闇の中へとひたすら堕ちていこうとする……。 静まり返った部屋の中に、突然電話が響き渡った。『ランティエ』が受話器を取り、数分話して電話を切る。振り返った目が野獣じみた猛々しい色に染まっている。「今日の夕方頃、ノブコさんと思われる女性がコルドバを出たそうです。一人、連れはなし、行き先はセビーリャ……それから、RETA(ロッホ・エタ)が本格的に動き出したそうですよ。既に追っ手と思われる二人連れの男が彼女を追っています」 黒々とした影が、一瞬、部屋の中を高笑いを響かせながら駆け抜けたようだった。そして、それが導く先には、闇だけを湛える夜があった。 ****************
2022.11.15
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』5.晩鐘(3)
**************** 夜は深々と、家々の壁に、黒い鉄の茎で支えられた8本のカンテラの真下に、その明かりに浮かび上がった十字架のキリスト像の、削げたような頬に、あばらの浮いた体に、その身を食い込ませて、一層影を濃くしていた。「アルベーロが刺されたのはここではないかも知れませんが、発見されたのはここです」 淡々と『ランティエ』は十字架の周囲の柵の外、キリストの正面あたりの黒々とした染みを顎で示して見せた。「救いと絶望の見事な構図でしたが、コルドバ随一と言われる広場を汚してしまいました」 普通人とやっぱり感覚が違うのか、『ランティエ』はアルベーロの死にも大して動じた様子はなかった。むしろ、側に控えている高野の方が寒々とした顔つきだ。「彼からの最後の連絡は、手がかりを掴んだというものでした。『燈火のキリスト広場』で売ろうとのことだったのですが、その時にはもう、刺されていたのかも知れませんね」 アルベーロの傷は背後から一突き、力が弱い刺し方だったらしく、しばらくは生きていて、何とかここまで辿り着いて逝ったらしかった。「見つかった時は片手に紙幣を握って蹲っていたようです。私は、そうそう表に出るわけにはいかないので……」『ランティエ』はひょいと肩を竦めて見せた。「物陰から冥福を祈りましたが、神の御前です、悪くはない死に方だ」 上品に十字を切ってみせる仕草が、不思議に嫌味がなかった、が。「く、そっ!」 信心深い人間がいたら、さぞかし驚いただろう激しさで、俺は舌打ちした。「手がかりを掴んだと思えば、片っ端から消えて行きやがる!」 重苦しい沈黙が辺りに澱む。「Señor.」「ひっ」 唐突に間近で声が響いて、飛び上がるほど驚いた。 いつの間にそこに居たのか、建物と建物の間の陰に、薄ぼんやりと小さな黒い影が浮かび上がる。続いたスペイン語をお由宇が訳してくれた。「人を捜しているなら、占ってあげよう、と言ってるわ」「え?」 時が時だけにどきりとして、俺は相手の姿を透かし見た。男とも女ともつかぬしわがれた声、黒衣に身を包み、指先まで覆った黒布の中に、小さな水晶玉が抱かれている。「私は長い病気の果てに人に見せられぬ体となったが、未来を見る目は確かだ。見ればお困りの様子、神の前だ、代金は要らないから聞いていきなさい、ですって」「わかるのか?」 思わず口走った。「あいつの行方がわかるのか?」「その人は小さな男の子だろう。魂の放浪者、彷徨う中で傷ついている。しかし神は見捨てない。その少年は風見の中に居る」 お由宇の通訳に体が強張った。『覚え書』の一文を思い出した。わたしが死んだら……埋めてください……風見の中に……。「もう…死んでるって言うのか?」 干からびた俺のことばを、お由宇が相手に伝える。相手のことばがゆったりと、夜の空気を伝わって戻ってくる。「まだ死にはしていない。だが、急ぐことだ。生命の火は尽きようとしている」「そうか!」 ふいに高野が叫んだ。「風見……ヒラルダだ。『ヒラルダの塔』です、滝様。もし坊っちゃまを葬るために、あのカードを使ったのなら、『風見(ヒラルダ)の塔』ほどぴったりしたところはありません」 相手は重々しく頷くと、のろのろと立ち上がり、向きを変えた。と、どうしたのか、お由宇と『ランティエ』の間に素早い目配せが飛び、次の瞬間『ランティエ』が相手に襲いかかった。「あっ!!」「へっ?」 どこかで聞いた声が黒衣の人物の唇を突く。「演出効果はあったけど…」 お由宇がにっこりと艶やかに笑いながら続けた。 「少しばかり乗りすぎたみたいね、上尾さん?」****************
2022.11.14
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』5.晩鐘(2)
****************「知り合い?」「知り合いと言うか……確か、上尾旅人とか言う奴だよ」 大学に居たろ、と振ってみたが、お由宇は覚えがなさそうに首を傾げる。「気のせいか、俺達の行く所行く所に居やがるな…」「行く所行く所? どう言う意味?」 お由宇の声がわずかに緊張したのに、思わず振り返った。「いや、たぶんだけど、バラハス空港にも居たし、アランフェスじゃ痴話喧嘩してたし」「どんな?」 お由宇が突っ込む。 珍しい。こんな噂話にお由宇が興味があるとは。「うん、確か…」 思い出しながら話すと、お由宇は次第にきつい目になった。「暢子? 暢子と言ったの?」「ああ。それがどうかしたのか?」「ちょっと待って」 お由宇はハンドバッグの中から、数枚の写真を取り出した。そのうちの1枚を俺に見せる。「その子って、こんな感じ?」「え?」 スナップを見つめる。学内の食堂近くの写真、確かにあの娘の顔があった。そればかりじゃない、それは…。「どうなの?」「あ、ああ、この子だ」「あなたの才能に感謝なさい。私達、見当違いを捜していたのかも知れないわよ」「見当違い?」「この娘の名前は汀暢子。佳孝とローラの一人娘なの」「っ」 どきっ、と心臓が跳ね上がった。瞬く間に頭の中の空白が埋まる。 そうだった、去年の学園祭でフラメンコを踊って見せた娘の名前が汀暢子、スペイン系のハーフだと聞いたことがある。「佳孝から『青の光景』を奪ったのは朝倉周一郎、恨んでも不思議はないわ」「ちょっと待ってくれ」「まだ何かわからないことがあるの?」「いや、その例のカード、ほら、話したろ、ローラ・レオニのカード」「あれが?」 学園祭の時に、いやにきつい目で俺を睨みつけていた娘がいた。化粧っ気がないのでピンとこなかったが、あれに相応の化粧をすれば、汀暢子にひどく似てくる。あの時、暢子は俺を睨んでいるのだとばかり思っていた。けれど、本当に睨んでいたのは、周一郎の方だったのかも知れない。 それに、だ。 確か、あのカード、あの娘が消えた後に落ちていた気がする。「罠、ね」 お由宇が冷ややかに断じた。「ローラ・レオニのカードで周一郎をおびき出せるとわかっていたんだわ」 そして、周一郎は俺にポートレートと読みかけの本を返し、さよならも言わないで旅立ってしまったのだ。「¿Hay algún mensaje para mí?」「Aquí está.」 ホテルへ帰り着いた俺達を『ランティエ』からの伝言が待っていた。さっと目を通したお由宇が凍てついた声で言った。「アルベーロが殺されたそうよ。『燈火のキリスト広場』で待つ、とあるわ」 どこか遠い夜の国から、黄色い塔に宿る鐘が響き始めたようだった。****************
2022.11.13
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』5.晩鐘(1)
**************** ぽつりぽつりと建つ黄色の塔で弔いの鐘が鳴っている。一本の道を萎れたオレンジの花を頭に乗せた『死』が歌いながら通っていく……不吉でやり切れない、乾いた光景。(読まなきゃ良かった) 俺は本を閉じ、頭に広がったイメージに顔を顰めた。 この家の女主人らしい婦人に送られて戸口を出てくるお由宇に気づき、凭れていた白い壁から身を起こす。 これが夕方なら、旅行者そのものの俺は人目を引いただろうが、午前中の今は老人が珍しそうに見て行くだけだ。「どうだった?」 陽射しの眩さに目を細めながら問い掛ける。 お由宇はわずかに頭を振って見せた。「この街へ連れてこられたのは確かみたいだけれど……そこから先がどうしても掴めないわ」「せっかくの手掛かりも消えた、か」 お由宇と並んで歩きながらぼやく。 アルベーロは、引き続き周一郎の情報を集めてくるとどこかに姿を消し、高野と『ランティエ』は『青の光景』の方から探りを入れ始めている。 俺達はと言えば、周一郎の足取りを追って、ようやくあいつの泊まったホテルは突き止めたが、その後の行方がさっぱりわからず、立ち往生しているところだった。(生きてるんだろうな?) ホテルに連れて来られた時、周一郎は男に肩を支え上げられるようにして入って来たと言う。高野の渡した数枚の札で口の滑りが良くなった男は、あれはどこかでリンチでも受けたんだろうよ、といやらしい笑い方をした。『そうだな、片足ぐらいは折れてるんじゃないのかな…逃げ出せないようにさ』 お由宇の通訳に、俺はさりげなく側の電話のコードで相手の首を絞め、さりげなく近くの机に頭を叩きつけ、ついでにもって、『さりげなく』釜茹でにしてやりたいと言う欲求を抑えるのに、ひどく苦労した。 頭の中にズタボロになった周一郎とガルシア・ロルカの『晩鐘』が重なる。(冗談じゃねえぞ!) 人がこれだけ捜し回ってやってるのに、どっかで死んでるなんて酔狂なことをやっててみろ、あの世だろうがこの世だろうが、首に縄つけて引っ張って来て、お詫びの手紙と感謝状を嫌っつーほど書かせてやる。 俺はやり場のない怒りを持て余して、一つ大きく首を振り、無理やり違う話題を口にした。「それよりお由宇」「何?」「この間さ、高野が、パブロが怨恨と復讐のために、汀…なんとかから『青の光景』を奪おうとしたって言ってたろ? あれ、どう言う意味なんだ?」「…本当に、何も知らないで飛び込んで来たのね」 お由宇は呆れた。「よくそれで周一郎捜しなんかしようと思ったわね?」「ほっといてくれ。どーせ俺はアホだ」「いいわ」 小さく溜息をついて、お由宇は髪を払った。すれ違った男のじろじろと舐め回すような視線を気にした様子もなく、ことばを継ぐ。「パブロとローラが夫婦だったことは知ってるわね?」「ローラにとっては不本意な結婚だったんだろ?」「おそらくは、パブロにとっても、ね」「へ?」 俺は首を傾げた。 何もお互い嫌いな同士なら、結婚なんぞしなくても良さそうなもんだが。「なぜなら、ローラはパブロと結ばれる前に1人の男性と結ばれていたの。それが汀佳孝」 ちくん、と頭の裏側あたりに微かな痛みが響いた。 どうも引っかかる、この名前。「ローラは元々定住のジプシーだったの。今から何年前になるのかしらね。若かったローラは、ちょうどスペインを訪れた青年画商、汀佳孝と激しい恋に落ちた。ロムニとガージョが結ばれないのは常だけど、2人はジプシーから抜け出し、ささやかな家庭を築こうとしたわ。けれども、佳孝の父が急死して、彼は急ぎ帰国しなくてならなくなり、ローラとの暮らしは終わりを迎えたの。ローラは今更ジプシーに戻るわけにもいかず、孤独な生活を続けていたけれども、彼女の美貌にもう1人の男が目をつけた……それがパブロと言うわけ」「でも、ローラは佳孝を愛していたんだろう?」「愛だけでは生きていけない、と言うのも通説ね」 お由宇は憂いを含んだ微笑を浮かべた。「パブロは生活を保障し、ローラを手に入れた。けれども、ローラの心までは手に入らなかった。そればかりじゃない、パブロは以前から趣味で画商もしていたけれど、そこでも悉く対立する相手が汀佳孝だった」「……」「『青の光景』はピカソの隠された作品、とてつもない価値を秘めているのは当然だけど、パブロにとってはもう1つの価値があった……父を亡くし、ローラを失ったことで力が衰えて来ていた佳孝にとっての唯一の切り札が『青の光景』、それがもし奪われたとしたら、彼の希望は全て失われたのと同じことになる……これほど、素晴らしい復讐はない」「復讐、か」 復讐のためにローラと結婚し、イレーネを引き取り、佳孝を破滅させようとした。 人間って奴は、そこまで人を憎み切れるものなのか。「『ランティエ』は、どうして『青の光景』を捜してるんだ?」「ああ、彼ね」 くすっ、とお由宇は可愛らしい笑みを漏らした。「彼らしいけど……もう一度贋作するためよ」「はあ?」「自分の作品が、一度ぐらいの鑑定で見破られたのが気に入らないそうよ」「はあ……」 ったく、人間って奴は……。 溜息をつきながら角を曲がりかけて、向こうから来た人間と嫌という程ぶつかった。「わぎゃ!」「¡Perdóname!」「No se preocupe. 」 とっさにスペイン語が飛んで来て、答えられない俺に代わってお由宇が応じてくれた。済まなそうに顔を上げた男が俺を見つめ、ぎょっとした顔になる。その顔を見て、俺も思い出した。「あれ、あんた、確か」「失敬!」 俺の問いかけを遮り、相手は慌てたように俺達の側を擦り抜けた。そのまま駆け足で、白い壁に囲まれた小路に消えていく。****************
2022.11.12
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』4.騎手の歌(4)
****************「だから、『ランティエ』に贋作を依頼して、それを渡した、と」 考えはお由宇の声に遮られた。「パブロは最後まで気づかなかったでしょう。彼にとって、必要なのは『あの絵』ではなく、『あの絵を手に入れること』だったのですから」 高野が冷徹に応じる。「そして、パブロの娘、イレーネ・レオニは、周一郎の身柄と引き換えに、本物の『青の光景』を要求してきたと言う訳なのね?」「はい、おそらく。『島の庭園』で坊っちゃまを囲んでいたのはレオニの配下でしたし……あの事件の後、『青の光景』を鑑定させたのでしょう」「おい、高野」 俺は唸った。「んなこと、お前、一言も言わなかったじゃないか」「滝さまは『正直』な方ですので」「違いない」 高野が曖昧な笑みを含んで答え、加えて『ランティエ』が口を合わせ、俺は思い切り落ち込んだ。「悪かったな、すぐに顔に出て」「でも、結果としては良い方向に転がってるわよ」 お由宇が慰め顔になった。「今のところ、あなたにばかり焦点が合っているし……少なくとも、あなたがどう出る気なのかわかるまで、周囲も動かないでしょうね。だって、『氷の貴公子』を救出にしに来るほどの『大物』だから」「それは嫌みか?」 お由宇をねめつける。「あら、真面目に言ってるのよ」 どーだかな、怪しいもんだ。だがあえて、それは口に出さない。500通りぐらい反論を聞かされるはずだ。「それより、本物の『青の光景』、本当にあなたが持っているの?」「『大物』じゃないんで持ってない」「いじけないの」 お由宇はちょっとウィンクを送ってきてから表情を一変させ、高野に目を向けた。厳しい口調で、「高野さん? 状況はあまり好ましくないですね。RETA(ロッホ・エタ)もそうそう待ってはくれないでしょうし、私たちと手を組むのも、周一郎君のためになると思いますが」「…わかりました……けれども」 高野は渋々頷いて、苦しげに続けた。「『青の光景』の在処は、坊っちゃましかご存知ではないのです。秘密は少人数の方がよく保てると仰って…」「らしいわね。あなたを巻き込みたくもなかったんでしょうけど。その周一郎君は姿を消してしまっているし」 軽く桜色の唇を噛む。珍しく焦燥が見えた。「何か手がかりがあれば良いのだけど」「そう言えば…」 高野が思い出したように口を開いた。「大したことではないのかもしれませんが……アランフェスに呼び出された時、坊っちゃまが独り言のように呟いておられたのです、『赤い月に導かれた騎手だな』と。その時はRETA(ロッホ・エタ)のことを指して言われたのかと思っていたのですが」「コルドバだわ」 唐突にお由宇が言い放ち、ぎょっとする。なんだなんだ超能力か。「はあん、なるほど。『騎手の歌』ですね」 意を得たように『ランティエ』が頷いた。「何のことだよ」 鼻白む俺に、お由宇がきらりと瞳を光らせた。「ガルシア・ロルカの詩の中に『騎手の歌』があるの。2つあるけれども、そのうちの1つに赤い月が出てくるわ。死が自分をコルドバの塔から狙っているという内容が続くのよ」「っ」 わああっと笑い声と歓声が沸き起こり、思わず舞台を振り向いた。いつの間にか、あの黒衣の女性が踊りを始めている。いつ俺達のテーブルから離れたのか、アルベーロが相手を務めていた。オーレ、オーレ、と掛け声が入り乱れる中、2人の踏み鳴らす足音が、かきむしられるように激しいギターの音色を鋭く刻む。「行くんでしょ、志郎」「ああ」 その女性の唇が、周一郎を死へと誘う、赤い巨大な月に見えた。****************
2022.11.11
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』4.騎手の歌(3)
****************「何?」「その様子じゃ」 お由宇はほ、と軽い溜息をついた。「今度も、訳が分からずに飛び込んで来たみたいね」「今度も、とは何だよ」 むくれて言い返した。「言っとくが、俺は自分から厄介事に飛び込んだこた、一度もないんだ。文句を言うなら、その辺りでサイコロを振ってる神様に言ってくれ。今度のことだって、高野に引っ張り出されたんだ。俺が来たがったんじゃない」「どうだか」 お由宇は髪をかけた左耳だけにつけたパールのイヤリングに軽く触れた。「おい」 唸る俺にさらりと問いかける。「それより、あなたのことが巷でどう言う噂になっているか、知っている?」「俺のこと?」 ふ、ふ、ふ、と微かな含み笑いが聞こえて、『ランティエ』を見る。だが、相手は微笑んだまま答えない。仕方なしに、再びお由宇に向き直った。「一体何だよ。俺はこっちに知り合いなんかいないぞ」「じゃあね」 お由宇は物分かりの悪い子どもを相手にするように、噛んで含める口調になった。「このアルベーロ、スペインでも名前の知れたトップ屋が、どうしてあなたの名前を知っているのか、考えたことは?」「…そりゃ…高野といたからだろ?」「ターゲットは高野だと思ってるのね?」「だって…」 口の中でもごもご答える。「俺がどうして注目される理由がある…?」 ふう。 お由宇は息を吐いてヘレスのグラスを上げ、芝居の台詞のように一気に言い切って酒を口にした。「『朝倉周一郎誘拐事件に、身代金として、滝という男が「青の光景」を持って渡欧した』」「は?」「それが私達の掴んだ情報の全て、よ」 お由宇はどこかうっそりとした視線を俺に向けた。俺がどうにも飲み込めないと言う顔をしていたせいだろう、くすりと軽く笑う。「つまりね。かの有名な『氷の貴公子』が行方不明って事だけでも随分な出来事なのに、事もあろうに、その身代金として要求された『青の光景』を運ぶ為に、高野が日本から呼んだのが、『滝』と言う、こう言う舞台じゃ全く『無名』の男だったと言う話。トップ屋じゃなくても、『滝』と言うのは何者だろうと探りたくなるもんじゃない?」 諭すように話されて、ようやく意味が染み込んだ。同時に、火の中へ投げ込んだとうもろこしの粒のごとく、頭の中が一瞬にして疑問塗れのパニック状態に陥る。もちろん、素直な俺の体が反応しないわけがない。手からフォークが滑り落ち、ぎょっとして上げた手が皿に引っかかり、押さえようとして別の皿を弾いて飛ばし、落ちたフォークは跳ね上がってコップを倒した。派手な音が響き渡り、周囲の視線が集中しただろう、だが、俺はそれに気づけるほど落ち着いていなかった。「な…何?」「ん?」 予想していたのか咄嗟に立ち上がって惨状に巻き込まれるのを防いだお由宇は、散乱した食べ物を片付けるウェイターに小さく会釈し、続いて非常に楽しそうに俺を見下ろした。「ちょ、ちょっと待ってくれ」「はい、どうぞ」「周一郎が誘拐? 身代金? 『青の光景』? 俺?」「そう、あなた、よ」 お由宇は席に戻りながら、にっこりと笑った。「高野さんが朝倉家の当主救出にわざわざ日本から呼び寄せるぐらいだから、『大した』男なんでしょうね、『滝』って言う男は」「聞いてない!」 思わず高野を振り返る。「俺は聞いてないぞ、高野!」 高野は神妙な顔でお由宇を凝視している。「高野さんを責めないで上げなさい。この情報の出所は彼なんだから」「高野ぉ?!」「そっ」 お由宇は美味しそうにパエジャを掬って口に運んだ。「そう言う事にしておけば、少なくともしばらくは、『気になる眼』があなたに惹きつけられて、周一郎君からは外れるでしょう? ダークホースだっただけに、このカムフラージュは最高に効果的だったわね」「カム…フラージュ…」 俺は椅子にへたり込んだ。だからこう言う裏表のあるやつは嫌いなんだ。ったく、人を夜店のクマのぬいぐるみか何かと間違えてやがる。 殺気立って睨み付けると、高野はわずかに目を伏せ、淡々と答えた。「坊っちゃまのためでした」「あ…あのなあ… んじゃ、俺はどーなってもよかったっつーのか!「RETA(ロッホ・エタ)の眼が光っている以上、坊っちゃまが何の護りもなしにスペインに放り出されていると思わせることは危険でした。そう判断されたが最後…」 高野の穏やかな面差しに、射るようなきつい光が走る。「坊っちゃまは殺され……朝倉財閥は崩壊します」 断固とした口調に怒る気力が失せた。悪い癖だと思うが、ここまで坊っちゃま一筋を通されると、仕方ねえなと言う気になってしまう。別に殺されてもいいなぞと言う意味ではさらさらないのだが。やれやれと溜息をついた俺は、ふとあることに気づいた。「え? 待てよ? 『青の光景』って、パブロ・レオにとやらに、ずっと昔に渡したんだろ?」「はい…但し…」 高野は幾分苦い顔になった。『ランティエ』が後を継ぐ。「但し、私の描いた贋作、の方ですが」「贋作?」 俺はぽかんと口を開けた。「んじゃ何か、贋作を餌にパブロを釣ったのか?」「パブロ・レオニは喰えない人間です」 高野は冷ややかに言い放った。「自分の手は汚さずに、汀佳孝から『青の光景』を奪い取る気だったのです。怨恨と復讐のために」 ほうら引っかかった。 頭のどこかで声が響いて、思わず眉をしかめた。汀……佳孝。何か引っかかるものがある。汀…佳…孝。どこかで聞いたような覚えが……。****************
2022.11.10
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』4.騎手の歌(2)
**************** 彼に続いて恐る恐る小さな暗い間口を潜って入ると、中は小舞台風に中央を空けた、居酒屋のような店だった。まだ時間が早いせいだろう、人影は少なく、外国人の俺達を舐め回すような視線がきつかった。 席を予約していたのか、1つの席に滑り込みながら、アルベーロは早口で何か話した。「え?」「誰かと待ち合わせたようです。もう少し待たなくてはならないようですが」「ああ」 時計は19時過ぎを指している。「タブラオ…のようですが、あまり安全な所とは言えないようですね」「タブラオ?」「フラメンコを売り物にしたレストラン、とでも言いましょうか。大抵は、夜の11時過ぎから、フラメンコが始まるものですが……」 アルベーロが注文したらしい料理が運ばれてきて、高野はことばを切った。揚げ物が多く、魚介類の料理、混ぜご飯風のものもある。「paella」 アルベーロはにやりと笑って、混ぜご飯を指差した。「ぱ…?」「パエジャ、です」 きょとんとする俺に、高野は運ばれてきたものを見ながら説明してくれた。「米に魚、貝、海老、鳥肉、牛肉、豚肉などをサフランで煮込んだものですが、サフランは高値ですから、この辺りのタブラオでは着色料を使ってるんでしょう。スペインの名物と言われていますが……それより、待ち合わせの相手は女性のようですね」「女性? どうしてわかるんだ?」「酒……ビーノと言って葡萄酒の一種ですが、マラガが用意されていますし……それに、シェリーのヘレスもありますね。両方とも、女性の方がよく飲まれるものです」「へえ」 何のこたない、ガイド付きでスペイン旅行をしているようなもんだ。もっとも、事態はそれほど気楽ではなかったが。 ビーノを勧めるアルベーロを、高野を介して押し問答を続けること十数分、ようよう納得してもらった。何せ葡萄酒とは言え、女性用のマラガでさえ、かなりアルコール度が高いと言うのだから。それからはひたすら料理を突くのに専念していた俺は、高野に肘を突かれて振り向いた。「何だ?」「むやみに食べないほうがいいですよ。オリーブ油が苦手な人なら、2、3日はトイレ暮らしですからね。ホテルなどではその辺りを考慮して、オリーブ油を使うにしても質のいいものを少量使いますが、こういった所は地元の客がほとんどですから、そう言う配慮はしないでしょう」「2、3日ね…」 ぎくりとして手を止める俺を、微笑を浮かべて見やった高野は、アルベーロのことばに全身を緊張させた。「何て?」「……今夜来るのは、アルベーロに坊っちゃまの調査を依頼した人間だそうですよ」「周一郎の?」「はい」 高野はきらりと殺気立った目になった。「朝倉周一郎とパブロ・レオニの関わり、今回の旅行の意図を探って欲しいとのことだったそうです」「じゃ、ひょっとすると、イレーネ・レオニ…」「生きているとすれば、23、4歳。考えられないことではありません」 いつの間にか増えた客達の間から、ざわめきが上がって、俺達は小舞台の方に目を向けた。 舞台奥手の方に、ギタリスト、歌手、踊り手が現れ、椅子に座る。ギターの音合わせが始まり、ざわめきの合間を縫っていく。「少し時間は早いようですが……始まるようですね」 高野の低い呟きを合図にしたように、突然、正確できっぱりとした手拍子が起こった。歌が湧き起こり、踊り手全員が入れ替わり、立ち替わり、短時間の踊りを見せる。「始めの歌は『ハレオ』と言います。顔見せが済むと、1曲ずつ踊りが始まります」 黒にピンク、水色に紅、黄に緑、紫に水色、色とりどりの舞姫達が足を踏み鳴らし、指を鳴らし、手首や腕、肩で様々なポーズを作る。ギタリストの整った顔立ちは淡々と引き続ける弦を追い、歌い手の声が深々と舞姫の体に喰い込み、縛り上げ、目に見えない何かを引き出していく。「あの女性は?」 次々と踊り続けていく舞姫の背後に、まるでひっそりと咲く黒バラの大輪のような女性に目を惹き付けられた。朱色の唇が憂えるような表情に不似合いだ。高く結い上げた髪に黒玉を散らし、黒いレースを被っている。それは、誰かの喪に服しているとも取れる、妙に沈痛な姿だった。「おそらく『真打ち』でしょう」「『真打ち』?」「この中でも優れた踊り手なのでしょう。生粋のジプシーという感じではありませんね」 オーレ! オーレ! 周囲から声が上がった。舞台に立っている踊り手は、体を仰け反らせ、伸ばした指が虚空に形を紡ぐ。それを肩が追い、腕が抱く。踏み鳴らされる床、響き渡るバリトン、テノール、人々の掛け声。「滝様」「ん? …え……あ…」 音楽が次第に盛り上がり、周囲の雰囲気も熱狂的になってきたところで、高野が呼んだ。 どうやら相手がきたらしい。椅子から腰を浮かせるアルベーロの向こう、1組のカップルが姿を現す。その男の顔、東洋系らしことはわかるが、何処の生まれかもう一つ掴めない容貌の男には見覚えがあった。相手も俺に気づいたらしい。穏やかな笑みを浮かべた唇が、これはこれは、と動く。彼は連れを突いて俺達を示し、振り向いた相手が一瞬目を開いて、静かに微笑し、俺は、その辺りでビー玉遊びでもやっているんだろう、運命の神様とやらの首を引っこ抜いてやりたくなった。「滝という名前が平凡だとは思っていなかったけど…」 女性が近づいて来ながら、ことばを継ぐ。「ここであなたに会うっていうのも、出来過ぎだわね、志郎」「お由宇……『ランティエ』……どうしてこんな所にいるんだ?」「お久しぶりですね、滝さん。質問はそっくりそのまま、お返しします。それに加えて…」 『ランティエ』は物柔らかい笑みの後ろから、鋭い視線で俺を見据えた。「『青の光景』の行方もお尋ねしたい」「『青の光景』?」 俺達が知り合いらしいと知ってぽかんとしているアルベーロの横で、高野が表情を固くした。****************
2022.11.09
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』4.騎手の歌(1)
****************「おっ…おいっ…」 俺ははあはあ言いながら、前を歩くアルベーロと高野に呼びかけた。緩やかになったり急になったり曲がりくねる坂道を登り、入り組んだ街並みを通り抜けはじめてから、かなりの時間になる。「まだかよ…」 高野が手早く俺のことばをスペイン語に直して伝えてくれたが、アルベーロはいつものようににっと笑い、一言答えた。「Si.」「あ…そう…」 いくらスペイン語に疎いからと言っても、これぐらいの意味はわかる。つまりはまだまだですよってことなんだろう。俺は溜息を吐きながら、重怠い足を持ち上げる。 グラナダ。マドリッドの南、491km、N4号線でマドリッドからバイレンまで、続いてN323号線を走って辿り着く、荒涼とした厳しさを感じさせる大地と空。ガルシア・ロルカも、このグラナダ郊外で生まれ、内乱で処刑された。かの有名なアルハンブラ宮殿もあるにはあったが、俺達はダーロ川を隔てたアルバイシンの右手に続く聖なる山、ジプシー達の住むところとして名高いサクロモンテの丘を、アルハンブラに背を向けて進んでいた。「この辺りに住んでいるのは…定住のジプシーです」 さすがに息を切らせながら、高野が説明してくれた。「ジプシーにも、大別して2つあります。1つは…昔から知られている通り……国の中を、あるいは国々を流れ歩くジプシー……もう1つは…この辺りを……中心として…定住生活を……しているジプシー……」 岩を彫り抜いたような錯覚を起こす戸口から、物珍しさだけではないような視線が俺達を追う。「流れているジプシーに……『ガージョ』が近づくのは難しいですが……最近…定住ジプシーの間では……『ガージョ』と縁組をする者も増えていますし……比較的…接触はしやすいでしょう…」「『ガージョ』?」「ジプシー以外の人間を……ジプシー達はそう呼んで区別しているんです………彼らは『自然の王者』…ロムニで……私達とは違う…という訳です。……流れているジプシーは……『ガージョ』との結婚はほとんどありませんし……もし結婚した場合は……状況によってはジプシーからの追放も……あります」 高野は少し足を止め、照りつける陽射しに眩そうに目を細めて、息を吐いた。「ジプシーは集団の民です。仲間からの追放は、彼らにとっての死をも意味します。仲間から離れ、1人で生きること、孤独は彼らの最大の脅威です」「ふうん…」「Sr.Takano!」「Si! 行きましょうか」「ああ」 俺達は再びアルベーロの後について、サクロモンテの中を歩き始めた。 陽は次第に傾き、家々は夕暮れの中へ沈み込んで行こうとする。賑やかさを取り戻してくる街並みを歩く俺達の側を、子どもが2人、じゃれ合うようにすばしこく走り抜けて行った。踊るような軽い足取り、一陣の風のように通り過ぎる。「滝様」「ん?」「貴重品には気をつけて下さい」 さりげなく肩を並べながら、高野が囁く。「盗みは悪いことではない、富んでいる者から貧しい者に金品が与えられるのは、当然の事という思想があります」「でも…あんな子どもが…?」「子どもでも一人前の稼ぎ手ですよ」「ふうん…」 流浪の民、ということばほどロマンチックな存在ではないということか。けれども、歴史の裏に追いやられ、戦争時には狩り立てられ、飢えと渇きに耐え、なお生きることに情熱をも燃やし、昨日を悔やまず、明日を憂うことなく、今日の祭りに生命を捧げる彼らを、単なる同情や憧れで見るのは間違っている、と熱く語った書き手もいた。彼らの生き方には、現代人が失ってしまった『生きること』への深い悼みと問いかけ、慈しみと情熱があるのだとも。「Sr.!」 先を歩いていたアルベーロが、1つの入り口の前に立ち止まって振り向いた。 どうやら目的地に着いたらしい。 ****************
2022.11.08
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』3.月と死神(3)
****************「ふ…う…っと」 ソファから反動をつけて立ち上がる。スペインに来て、2日目の夜が来ようとしていたが、周一郎の行方は相変わらずわからないまま、最後の頼みの綱と掛けたお由宇への電話も、虚しくコール音を続けるだけ。 ったく、お由宇はいない、周一郎もいない、それで俺に何をしろと言うんだ。 可哀想に、高野はすっかり窶れて、今日も終日、黙り込んで窓の外の道路を行く人波ばかりに目を走らせていた。 コンコン。「はい…じゃない、えーと、その…」 唐突にノックが響き、俺はドアを振り返った。高野も不審そうに眉をひそめて椅子から立ち上がる。 俺達がスペインにいることを知っている人間はほとんどいないはずだし、ましてや尋ねてくる人間なぞ、論外だ。「¿puedo entrar?」 ドアの向こうから、聞き覚えのある甲高い声が問いかけて来た。「Adelante.」 高野がドアの側に寄って応じる。身についた職業意識というのか、執事風に入って来た男を迎え、静かに会釈した。「Buenas noches.……Mucho gusto,Sr.Taki,Sr.Takano.」 柔らかなウェーブのかかった短髪を浅黒い肌にまとめ、にっ、と邪気のない笑みを浮かべて、昨日の男は俺と高野を等分に見比べた。いくらスペイン語に疎い俺でも、相手が行き当たりばったりに訪ねて来たのではないことはわかる。顔写真と名前を確認して覚えて来たのか、男は正しく俺と高野を区別した。「…… Disculpe, ¿cuál es su nombre?」「No se preocupe.」 高野の問いに、男はにやりと笑って、肩から掛けた金属のケースを軽く叩いた。どうやらカメラマンらしい。「Me llamo Alvaro.Alvaro Martinez.」「アルベーロ・マルティーネス」「知ってるのか?」「ええ。まあ知られたカメラマンです。もっとも、トップ屋と言った方が通りがよろしいでしょうか」 高野は上品に眉を寄せて見せたが、すぐに卒なく椅子を勧めた。ルームサービスでコーヒーを頼み、ソファでアルベーロと向かい合っている俺の背後に立つ。「何だ? 座ればいいだろ」「いえ、仕えている身ですし」「…俺にスペイン語で話をしろなんて言うなよ。そんなこと言ってみろ、俺はここで荷物をまとめて日本に帰る」「わかりました」 高野は軽い溜息をついて、隣に腰を降ろした。興味深そうに黒い瞳を輝かせているアルベーロに穏やかに問いかける。「¿En qué puedo servirle?」 何の用事かとでも尋ねたのだろう。アルベーロは金属ケースから茶封筒を出してテーブルに置いた。ゆっくり芝居掛かった仕草で押しやってくる。「¿Qué es esto?」「Es una fotos.」「なんだって?」「写真だそうです。一体…」 茶封筒を開け、中身を取り出した高野の顔色が、それとわかるほど変わった。「周一郎…」「坊っちゃま…」 十何枚か全て、周一郎の写真だった。半分近くはスペインでの物らしいが、残りは日本でのもの、いつ撮ったのか、学園祭の奴まであった。肩を並べる俺と周一郎、周一郎の方から話しかけている表情が他に比べて驚くほど子どもっぽい。「滝様!」「…ああ」 その中の1枚、ことさら下の方に隠すようにしてあった1枚を引き出し、高野は小さく叫び声を上げた。明らかに『島の庭園』と思われる場所で、両側を背の高い男に囲まれた周一郎が、冷ややかに相手を凝視しているものだった。「¿Qué pasa?」 飄々とした様子で、相手は写真を覗き込んだ。「高野、ひょっとして、こいつ……」「坊っちゃまの行方を知っていそうですね。掛け合って見ます。¿Cuánto vale esta fotos?」 アルベーロは薄く笑みを零し、ゆっくりと話し始めた。 ****************
2022.11.07
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』3.月と死神(2)
****************(人が必死に探していたのに、心配するなとは) 高野もさすがにムッとして周一郎の側に立つと、少年はついと河の方を指差した。「高野」「はい」「もし、ぼくがここに落ちたら、大悟はどうすると思う?」「もちろん、お助けになりますよ」「今は、ね」 少年は高野を振り返って皮肉っぽく笑った。真意を図りかねていると、「ぼくは、今の計画のパートナーだからね」「…」 そこで高野は、ようやく、この10歳にも満たぬ少年が何を言っているのか理解した。大悟は、今の計画に周一郎が必要だから助けるのであって、周一郎個人の価値で助けるのではない、言い換えれば、もし計画に周一郎が必要でなければ、いつでも見殺しにできる、そう言うことなのだと。「そんな、まさか」「まさかと言うの? ぼくはできるよ。おかしいね、高野」 幼い顔にかけたサングラスの後ろの瞳が、ひたりと高野を見据える。「ぼくがローラにならないと断言できるってわけ?」(ああ) 高野は思い起こした。大悟が、ローラ・レオニに彼女の好きなガルシア・ロルカの本を贈り、片言の日本語を教えていたことを。パブロ・レオニと意に染まぬ結婚をしたローラにとって、大悟は例えようもなく魅力的な存在であり、義理とは言え、その息子の周一郎は大切な人の子どもだった。 だが、大悟の好意も、結局はパブロを落とす為の餌であり、RETA(ロッホ・エタ)に襲撃される計画でローラが死ぬとわかっても、大悟は何一つ手出しをしなかった。「………」「答えられないだろう。お前は『いい人間』だね、ぼくらと違ってさ」 言い放った周一郎はなおも川面を見つめ続けた、その目に深く重い影を宿して。 そんな時からか。 胸の中で呟く。 そんな時から、自分は1人だと思っていたのか。 どんなに哀しかったろう。自分が他の誰にも必要じゃないと思い続けて、ようやく、能力(ちから)を認めてくれた相手は、いつでも自分を見殺しに出来るのだと思い知らされるってのは。 いつの間にか、目の前に開けたタホ河は、緩やかな流れをゆったりと広げていた。 日本とは川は川でもサイズが違う。広さが違う。 だからこそ、こんな広い景色の中で、ああそうか、どんなに頑張ってもどんなに有能であっても、やっぱり自分は誰にも要らないんだなと必死に飲み込もうとしている9歳の子どもと言うのは、ただただ痛々しくて、辛くて。 それでもな、周一郎。 もう、そこには立っていない少年の姿に呼びかける。 それでも、俺は、お前が生きててくれた方が嬉しいんだからな。馬鹿なことを考えるなよ。自分で自分を諦めちまうなよ。何の役にも立てん俺だって、スペイン語どころ英語もろくに出来んし、電柱にぶつかるし自分の足に蹴躓くしバイトは馘になるし、テストは白紙だし女には振られっぱなしだし、オタオタするしか能のない俺だが、お前の八つ当たりの場所ぐらいにはなってやれるんだから。「一体…どこへ…」 滲むように高野の声が響いた。「どこへ行かれたんでしょう」「暢子!」「っ」 答える術なく黙り込んだ俺は、次の瞬間響き渡った声にぎょっとして振り返った。 日本語だ。「観光客、のようですね」「ああ、そうだな」「待ってくれ、暢子!」 植え込みの向こう、木立の端に一組の男女が言い争っている。「あれ? あいつ…」 肩に触れるぐらいの茶髪の男は、離れようとする女の手首を掴み、激しい勢いで怒鳴る。「馬鹿なことはやめるんだ!」「何が馬鹿なこと?!」 負けず劣らず激しい語調で叫び返し、振り返った女が男を睨み付ける。「あなたとのことはもう終わったのよ! 私に指図なんかしないで!」「見てられないんだ」 苦しげな声で男が唸った。「君だってわかってるはずだ。そんなことをして、君に何が残る?」「わからないわ! わかりたくもない!」 女は怒りと憎悪を込めた目で男を凝視している。「後に何が残ろうと構わないわ! 破滅だと言うなら、それでも喜んで受け入れるわ。あなたにはわからないでしょうけど」「…君は取り憑かれているんだ」 男は疲れたように重く応じた。「この国の影に毒されて、自分を見失っているんだよ」「構わない、と言ったでしょう」 女は手首を掴んだ男の手を、汚らわしいもののように振り払い、皮肉な笑みに唇を歪める。「自分なんていらないのよ。私は、ただ…」 目鼻立ちのはっきりした異国的な顔立ちに細めた瞳、表情のそこここで凶暴な光がちろちろと炎の舌を吐く。にっこり笑った唇が、酔うように甘く一言紡いだ。「滅びたいの」「君は…」「でも、1人ではごめんだわ。『彼』を巻き込んで、もろともに堕ちて行きたいの。あなたが居たいと言うならば拒まないけど、その代わり、最後まで私の堕ちていくのを見届けてちょうだいね。一瞬でも目を逸らせたら…」 冷たい光がとってかわり、女は笑みを引っ込めた。「絶対に許さない」「暢子…」 男は哀れなほど肩を落とした。のろのろと首を振りながら、「君はまるで魔物(ドゥエンデ)だよ」「魔物(ドゥエンデ)?」 は、と嘲るように嗤って、女は肩をそびやかせた。「そうだ。とても人とは思えない」「違うわ」 男のことばを途中できっぱり遮る。「人だからこそ、魔物(ドゥエンデ)にもなれるのよ。人でない魔物(ドゥエンデ)なんて…」 白い歯を見せて妖しく笑う。「御伽噺にもなりゃしない」「……」「いい? これが最後よ。私の邪魔をしないで」 一言もない男に言い捨て、くるりと身を翻らせて女は足早に立ちさった。残された男は重い溜息を吐いて、立ち竦んでいる。「…行こう」「はい」 俺は高野を促してその場を離れた。ただでさえ、面倒ごとに飛び込んじまってるのに、この上、他人の痴話喧嘩に巻き込まれる気は毛頭なかった。「ご存知の方ですか?」 十分遠ざかってから、高野が問い掛けてくる。「ご存知って言うほどご存知でもないんだが……大学の奴だよ。名前は確か……上尾、とか言ったはずだ」「それは…奇遇なことで」「奇遇ね…」 奇遇、奇遇か。奇遇なら、俺はひじょーに嬉しいのだが、この妙なもやもや感をどう説明すればいいのだろう。何となく、嫌な予感がする。背後霊どころか、守護霊もおいでおいでをしだした気がする。二度ある事は三度あるという奴の、いよいよ三度め、と言った感じだ。 それに、あの女、どこかで見たような気がする。それも、そんなに昔のことじゃない、割と最近だ。紅い唇が笑う、その後ろにあったイメージ、炎と燃えた瞳の色、どことない異国的な顔立ち……。(どこでだ? どこで見ている?) 別にわからなくてもどうと言うことはないに違いない。知り合いと言っても、学園祭で一方的に見掛けただけの男の痴話喧嘩。首を突っ込む必要もないのだ。だが、何かが引っ掛かる。何か、ひどく重要なこと。「うー」 呻いて俺は頭を掻きむしった。高野がぎょっとしたように、珍動物でも見るように俺を見る。「どうなさったんですか」「いや……脳味噌のマーボードーフを何とかピラフにできないかと…」「は?」 高野はきょとんとした。「つまり……その……いやーな予感がするんだ」「いやーな予感、ですか」「そう、そのいやーな予感……」 ズドッ!! ビシッ!「ひっ」 突然耳の側を何かが通り抜けていき、目の前の木の幹に食い込んだ。「 Señor!!」「ぐわっ」 ほとんど同時に、甲高い、よく通る声が後頭部を殴りつけた。続いて、思い切りよく叩きつけられた両手が、俺を前へつんのめらせる。もちろん、素直な俺が倒れないはずがない。 ドウッ! ドウッ、ドウッ!!「な、何だ何だ!」「銃声です」「んなこた、俺でもわかる!」 地に伏せながら、冷静な高野の声に噛み付く。「要はどーしていきなり撃たれてんのかってことで…んぎゃ!」「¡Cuidado con la cabeza!」 きびきびした男の声とともに、俺は頭を地面に押し付けられた。高くもない鼻を思い切りぶつけ、目から火花が出る。「¡Perdóname! Hasta pronto.」 この野郎、と喚こうとした次の瞬間、男は銃声の途切れた間を狙って立ち上がり、言うやいなやで駆け出して姿を消した。それを追うように、見る見る銃声も遠ざかっていく。 辺りが再び元の静けさに戻ると、高野は感極まったように、地面で果てている俺に頷いた。「なるほど。滝様の予感とはよく当たるものですね」「あ、あのな…そこに感心するか、今?」 俺は再びその場で果てた。****************
2022.11.06
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』3.月と死神(1)
****************「…象牙の…歯を……」「滝様!」 高野の声に本を閉じる。 タホ河河畔、乾いたスペインの中で豊かに水をたたえる沃野、アランフェス。そこには、河の蛇行に沿って緑溢れる庭園と王宮が広がっている。『アランフェス協奏曲』と言う音楽は、ここの自然の美しさを題材にしたものらしい。 そして。 周一郎が姿を消したのも、この地だった。「詩集、ですか」 午後の3時過ぎ、まだシェスタから醒めきらぬマドリッドを出て、正面玄関の右手で切符を買い、王宮に入る。ガイドを断った高野は、俺の手にしていた本をみやり、訝しげな表情になった。「なんだ?」「……失礼いたしました。滝様がそのようなものを好まれるとは思っておりませんでしたので」「俺は文学部だぞ?」「他にどのようなものを読まれましたか?」「…………」 ったく! 人の弱みを、そんな生真面目な顔して突くなって言うんだ!「…わかったよ。どーせ俺と文学は不似合いだ」「いえ、そう言う意味では」「じゃ、どーゆー意味だ? 言ってみろ、え?」「ガルシア・ロルカでございますね」 絡んだ俺を、高野はさらりと躱した。「お好きなのですか?」「そう言うわけじゃなくって………まあ、その、『覚え書』とやらも、こいつの作品なんだろ?」 俺に『こいつ』呼ばわりされては、ガルシア・ロルカもさぞかし腹立たしいだろう。「これに何か、周一郎が消えた手がかりがないかと思ってさ。……で、あいつが消えたのはここなのか?」 辿り着いた部屋をぐるりと見回す。壁も天井もびっしりと絡みつくように、草花や人物や動物を象った陶器で飾られている。人物はちょっと中国っぽいと言うか、異国情緒溢れると言うか、不思議な造形だ。白い壁に浮き上がる極彩色の装飾に圧倒される。「いえ、ここは『陶磁器の間』ですから。ぼっちゃまが姿を消されたのは『島の庭園』です」「『島の庭園』?」「はい」 高野は先に立って、王宮の部屋部屋を早足で通り抜けながら頷いた。歩いても歩いても果てがないような広さ、とにかくスケールが違う。「タホ河に囲まれたような形になっている庭園……こちらです」 唐突に目の前に空間が開けた。日本で思うこじんまりとした庭園とは違って、あちこちに木立が茂り、石造りのドームみたいなものや彫刻が点在し、その間を通路が縦横に渡っている。空へと水を吹き上げる噴水が陽射しに煌めきながら散っている。伸び上がっても端が見えない。朝倉家の庭よりもでかそうだ。「坊っちゃまと私は、ここに呼び出されました。しばらく待っても何者も現れず、坊っちゃまは少し1人で歩いたみたいと仰られて、離れて行かれました。お姿を見失うほどではありません。けれど、スペインに来られてずっと沈んでおられたので、少しの間なら大丈夫だろうと考え、見守っておりました」 高野の声に口惜しさが滲む。 周一郎は『島の庭園』をタホ河の方へ向かって歩いていた。小さくはなっても、その姿ははっきりと見えていたし、他の人影もなかったので、高野もつい気を緩めてしまっていた。ふいに風がざわめき、木立が揺れ、一瞬光が高野の視界を眩ませ………瞬きをした後には周一郎の姿は消えていた。「10年前のように、私が追えばよかったのです」「10年前?」「はい」 重い表情の高野は、その頃の周一郎の跡を追うように、ゆっくり歩き出した。 ローラ・レオニが、パブロ・レオニと共に凶弾に倒れた後、さすがの周一郎も塞ぎ込むことが多くなっていた。このままでは後々の仕事に差し障ると考えた大悟は、高野を付き添わせ、気分転換にと風光明媚なアランフェスへ送り出した。「坊っちゃま?! 周一郎ぼっちゃま!」 だが、周一郎は塞いだ表情のまま、付き纏う高野を振り払うように、この『島の庭園』で姿を消した。夏の盛り、鮮やかな緑の園には観光客が溢れ、小柄な少年の姿はどこにも見当たらない。「坊っちゃま! …¡Perdóname!」 人に突き当たり、緑を掻き分け、探し続けた高野は、ようやくタホ河を臨む岸に立っている少年に気がついた。「周一郎様!」 苛立たしさが先に立って、声を荒げながら駆け寄る高野に、少年はぽつりと一言、振り向きもせずに返答した。 「No se preocupe」「ちょ、ちょっと待ってくれ」 俺は慌てて高野の話を遮った。「のーせ、何?」「No se preocupe. ご心配なく、と言う意味です」「スペイン語なのか?」「はい」「はいって……その頃、周一郎は9歳だろ?!」「坊っちゃまは、その頃既に英語独語をマスターされていました。スペイン語はまだ片言でしたが」「…片言、ね…」 反論する気力が萎えた。今後あいつが広東語やユーゴスラビア語をマスターしてると言っても、驚かないことにしよう。「何か?」「いえ、どーぞ、先をお続け下さい」 それでは、と高野は平然と話を再開した。****************
2022.11.05
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』2.三つの河の小譚詩(4)
**************** ガタッと音を立てて急に車が止まり、高野は話を止めた。運転手に札を渡す。ちらりとこちらを見た相手は、にっ、と唇の端で笑って見せた。「¡Buen viaje!」「Gracias. どうぞ、滝様」「あ、うん」 さらりとスペイン語(?)で応対した高野に促されて、俺は車を降りた。走り去っていく車を見ながら尋ねる。「なんて言ったんだ?」「良い旅を、です。……そうなると良いのですが」 再び重い憂いを浮かべる。 その高野と対照的に、街は明るく光を受けていた。 スペイン首都、マドリッド。 日差しに刻まれた建物の影がとんでもなく濃い。足元に落ちた影が地面に焼き付けられている。視界を移しても、網膜に物の形が刻み込まれて行く気がする。どこで聞いたのだろう、頭に蘇ったことばに納得する。スペインの影はどこより深い、スペインは光と影(ソル・イ・ソンブラ)の国なのだ、と。「こちらです、滝様」 高野がぼんやりと落ちた影を眺めている俺に声を掛けてきた。「ああ…すまん。昼間の割には人通りが少ないな。ここはそんなに賑やかなところじゃないのか?」「いえ…グラン・ビアはマドリッド一の繁華街です。今は昼寝(シエスタ)の時間ですから」「シエスタ?」「はい。スペインでは午後1時半~4時半ぐらいまで、ほとんどの店が休みます。日本語では『昼寝』と言う文字を当てることが多いようですね……こちらへ」 高野が導いた場所は立派な佇まいのホテルだった。「Sr. Takano」 鋭い目をした男が親しげに話しかけてくる。高野の早口な問いに、気の毒そうな表情で答える。「No sé. Aquí está la clave de su habitación.」「Gracias.……¿Tienes un mensaje para mí?」「Yo no sé.」「Muchas gracias.」 高野は片手に鍵を握りしめて、気怠そうに黒いスーツ姿を運んで来た。「なんだって?」」「留守に間に何か連絡がなかったのかと尋ねたのですが、なかったようです」「周一郎は朝倉家のトップだろ? どうして朝倉財閥を動かさないんだ?」 エレベーターへ向かう高野に肩を並べながら問いかける。高野は、周囲の重厚な様式にぴったりの憂鬱そうな顔を向けた。「既に捜させています……けれども、それほどには動けないのです」「どうして?」「…坊っちゃまが朝倉家の唯一の後継者だということは、業界の中でも半分ほどしか信じられていません。坊っちゃまが居て、なおかつ、他にブレーンが居る。そう思われているのです。また、それを、私どもとしては逆に利用できていますから、今ここで朝倉家の総力を挙げて捜させますと、坊っちゃまこそが朝倉財閥の要であることがわかってしまい……そうなると、別の意味で坊っちゃまを狙う輩が現れるでしょう」「ふうん…」 俺は一般人に生まれて、ほんっとに良かった、うん。「それに」 エレベーターの回数は無制限に跳ね上がっていく。高野は憔悴した様子で、エレベーターの壁に体をもたせかけながら続けた。「RETA(ロッホ・エタ)が再び活動を始めたのです」「?」 俺はきょとんとした。「それがどうして周一郎失踪と関係があるんだよ?」 エレベーターがようやく最上階に止まり、高野は首を振ってことばを切った。開いたエレベーターのドアの外に待っていた女が、俺達と入れ替わりに中に入っていく。つばの広い白い帽子で、朱赤の唇が一瞬開いて白い歯を見せた気がして、思わず立ち止まった。「滝様!」「えっ、あっはいはい」「こんな時に、何に見惚れていらっしゃるんですか」 棘のある高野の目付きに慌てて弁解しようとしたが、高野は見事にそれを無視した。ドアの鍵を開け、部屋に入る高野に続く。「うわ…」 部屋は凝ったゴシック風の作りになっていた。広い窓から入り込んだ陽射しは部屋の隅々までを照らし、分厚い敷物を踏んだ高野は、その明るさをことさら避けるように、重厚な椅子に深々と身を沈めた。「10年前…」 深く重い声で高野は切り出した。「RETA(ロッホ・エタ)がパブロに目をつけたのは、ある情報のためです。……パブロ・レオニは、外国企業と結託し、スペインの地元産業を衰退させようとしている、と」「え? だけど」 ボストンバッグを近くのソファに下ろしながら尋ねる。「朝倉財閥のスペイン進出は極秘だったんだろ? 一体誰が…」「『それが』坊っちゃまの立てられた『計画』だったんです」 そのことばが、俺の頭に染み込むのには、なお数秒かかった。「じゃあ…全部…」 ようやく絞り出した自分の声が、他人のもののように掠れて遠くから聞こえる。それがなぜか情けなかった。「はい。『全て』坊っちゃまの計画でした」 その後の沈黙は、嫌になるほど重かった。「もっとも、RETA(ロッホ・エタ)の方は、なぜ動き出したのか、まだわかっていないのです。もし10年前のことで坊っちゃまを狙ったとしたら、あのような方法を取らなかったでしょうし」 高野は気を取り直したように続けた。「あのような方法? カードか!」「はい。あれは、ローラ様が坊っちゃまのために、お好きな詩をを日本語で書かれて贈ろうとされていたものでした。遺品となりましたが、カードは坊っちゃまの手には渡されず、ただ一人、友人の家にいて無事だったイレーネ様が受け取られたと聞いております」「イレーネ…レオニか。…や、待てよ!」 俺がどきりとした。「だって、え、あのカード、学園祭の時に拾ったぞ? スペインにあるはずのものが、どうして日本にあるんだよ?」「だからこそ」 苦い口調で高野は答えた。「坊っちゃまが来られたのです。あのカードがどうして日本にあったのかを知るために……それに、朝倉財閥の当主としても、それが『何の為に』坊っちゃまの前に現れたのかを確かめておく必要があると仰られて………結果は最悪です」 ふいに日差しが強くなり、俺は無意識に窓へと首を巡らせた。薄く陽を覆っていた雲が切れたのだろう、青紫がかった空は、眩いまでに光を含んでいる。 だが、その光が地上に焼き付けているのは、一層濃くなった影の色だけだった。****************
2022.11.04
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』2.三つの河の小譚詩(3)
**************** 今から約10年前の夏。「その頃、南欧、特にスペインを中心として手を広げている貿易商で、パブロ・レオニと言う者がおりました。もっとも、それは表向きのこと、裏では『青(アズール)』と呼ばれる古美術売買の裏取引をしていた男でした。大悟様はちょうどその頃、スペインにおける市場を開拓しようとされていましたが、スペインは既にパブロ・レオニの網が行き届いており、大悟様が食い込める余地はないように思われました………」「ふ…うん」 軽く唸った大悟は、私室の重厚な木製の机の上に書類を投げ出した。「難かしゅうございますか」「そうだな……ああ、すまない」 高野の置いたコーヒーに気づき、大悟は指を伸ばしてカップの縁を撫でた。考え込んでいる時によくする仕草で、こういう時に余分なことばを交わすのは邪魔になるだけだ。心得ている高野は、黙ってソファの方に座っている周一郎の前に、熱いココアを置いた。「ありがとう、高野」 少年が微かに笑って答えるのに、頭を下げる。 大悟が拾ってきた、どこの馬の骨ともわからないこの少年は、数年で見る見る才能を開花させた。大悟のすば抜けた実行力の裏にはいつも、周一郎の研ぎ澄まされた感覚と水も漏らさぬ計画がある。大人びた口調は不思議と終日サングラスを掛けたままの異様な容姿に似合い、周一郎は今や朝倉家の次代当主として衆目の一致するところとなっている。実際、現時点でも既に周一郎が朝倉家を動かしていると言っても過言ではない。だが、それを知るのは朝倉財閥の中でもごく僅か、大悟に高野、岩淵の数人だけだ。「何を悩んでいるの、大悟」 大悟、と呼び捨てるのも、以前は気に障ったが、今はそれほど不自然にも思わない。「南欧に食い込めたら、と思っている」 くすっ、と小さく笑った周一郎は、ゆっくりココアを含みながら応じた。「ぼくにそんな言い方をしなくてもいいのに。ずばり言えば? スペインを征したい、と」「…」 きらりと目を光らせる大悟に、たじろぎもせず、ことばを継ぐ。「それとも……パブロ・レオニを落とす方が好み?」「出来るのか?」「どちらを?」 ココアから顔を上げた周一郎の目が輝いているのを、高野は見て取った。それは、これまで成功してきた数多くの計画に周一郎が乗り出した際に、何度も出くわしてきた目だった。「パブロ・レオニ」「資料を見せてよ」 周一郎は薄く笑った。大悟が重々しく付け加える。「スペインだけじゃない、南欧を狙うなら、パブロ・レオニの失墜は大きい」「言われなくても、そうだと思ってたよ」「…」「はい」 大悟の無言の促しに、高野が書類を周一郎に渡す。怯む様子もなく無造作に受け取って、次々と目を通しながら、周一郎は時々きゅっと幼い顔立ちをしかめた。「大悟……パブロ・レオニの家族構成は?」「妻1人、子どもは出来ずに養女を引き取っている。友人の娘だそうだ」「名前は?」「妻がローラ・レオニ、娘がイレーネ・レオニ」「!」「はい」 聞いた名前にどきりとした俺に、高野は頷いて見せた。 車は降り注ぐような陽射しの中、ゆっくりと右折する。かなり大きな広場、中央に影を濃く澱ませた像を配した噴水があり、躍り上がった水が日光に煌めいて降り落ちている。「ここがシベーレス広場……マドリッドを縦断している通りの交差点です。中央に立っているのは大地の女神(シベーレス)像。近くにプラド美術館もありますよ」 高野が静かに解説してくれる。「詳しいんだな」「…10年前、坊っちゃまがスペインに来られた時に同道いたしましたので」「9歳の時のスペイン旅行?」「はい」 高野は再び話を始めた。 それは周一郎の初めての海外進出だった。 相手はパブロ・レオニ、まずくすれば、進出し始めた朝倉財閥など、気配を知られただけで激しい拒否に合うだろう。それでなくとも、スペインは各地方の自治の思想が強く、極端な例はETAと呼ばれるバスク、ナバーラの過激派グループに現れる。1973年の12月にはフランコ首相をダイナマイトで吹き飛ばすなどと言うことをやってのけたほどだ。確立した地方自治の中、外国企業が入り込むのは容易ではない。だが、周一郎はためらうことなく、「つまり、朝倉財閥でなければいいわけだね」「どういう意味だ?」「パブロ・レオニ、だよ。利益に個人の名はつかない」 にやりと笑って、あっさり続ける。「表向きはパブロ・レオニで構わない。要はぼくらがそこへ入り込んでしまえばいいわけだ」「なるほど……その手があったか」 周一郎と大悟は高野を伴いスペインに飛んだ。大悟はパブロ・レオニと貿易上の親交を深めに行くために、周一郎は大悟の息子として個人的にローラ・レオニとその娘に近づき、パブロ側の情報を得るために。 幸いにと言うか、当然と言うべきか、ローラ・レオニは異国の聡明な美少年を大いに気に入った。娘のイレーネは、13、4歳下の少年に対し、時には弟のように、時には幼い恋人のように心を寄せ、睦まじく語り合っていた……そう、傍目には。パブロ・レオニと朝倉大悟がいくら虚々実々の取引と化かし合いを繰り返していたところで、誰一人として、この僅か9歳の少年が、朝倉大悟よりも危険な存在と思わなかった。 眩い日射しの中、ローラやイレーネと笑い合いながらも、周一郎はパブロ・レオニが仕事の範疇を越えて熱中しているものを探り出していた。幻の名画、ピカソの青の時代の一作と思われるもので、『青の光景』と呼ばれる作品だ。それを手に入れようとパブロは全力を尽くしており、商売も最近停滞気味だと言う。 周一郎はそれを見逃さなかった。どうにも隙の出来ないパブロの意識を外らすべく、朝倉家の総力を挙げて絵の行方を捜させ、次いでパブロ側に朝倉家が手に入れたと言う情報をわざと漏らした。 パブロが手を組もうと話を持ちかけてくるのに、大した時間はかからなかった。大人しく相手のことばに従った振りで、朝倉大悟がパブロの交易網に食い込む。 じわじわと朝倉家が自分達の交易範囲を吸収していくのに気づいたパブロが、表向きは友好関係を保ちつつ、防御策を講じ始めた時には全てが遅かった。交易網の70%がパブロの名前を保ったまま朝倉財閥が運営している状態になったことから、ようやく周一郎の存在を疑いだしたが、パブロには再び交易網を取り返す余力は既になく、手に入れた『青の光景』ばかりが救いという有様、パブロ・レオニは緩やかに朝倉財閥の配下に加わるのだろうと思われた。 だが、予想はいつも人の頭の内側にしかないもの、とんでもない客がパブロに目をつけていた。 ある日、パブロの屋敷を、突然ETAの一派、RETA(ロッホ・エタ)が襲った。RETAはETAの中でも過激な一派で、常からパブロを地方自治体制を崩壊させる者として狙っていたのだ。 一陣の嵐のように飛び込んできた男達はパブロを始めとする家族の悉くを葬り去った。知らせに駆けつけた周一郎達が見たのは真紅の血の海、白い壁に血の飛沫が飛び散った中、内庭(パティオ)にまで転がった死体の中には、美しい黒髪を乱して倒れているローラ・レオニの姿もあった。 当主を失ったパブロの貿易網はあっさり朝倉財閥の手に落ちた。朝倉大悟は名前だけの当主を立て、その実、スペインポルトガルを始めとする南欧貿易網の一大ルートを掌握した。****************
2022.11.03
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』2.三つの河の小譚詩(2)
****************「ぐ、ぐわ…っ」 空港に降りて、寒さに思わず呻く。「だ…誰がスペインを南国だと言った……っ」 周囲の注視を避けて小さくなりながらぼやく。 とにかく冷え込む。日本の冬ととんとん、バラハス空港じゃなくて、北海道、千歳空港と言っても通るんじゃないか。慌てて搔き合せたコートの中にも、寒気は容赦なく入り込んできて、ぽつぽつと置いてある暖房装置に擦り寄りたくなる。「火……火をくれ…せめてカイロを……」 ぶつぶつ言いながら見回す視界に、一瞬見たような顔が通り過ぎた。肩までの茶色の髪、背中に負ったギター。(あれ? あいつ…)「滝様!」 見定めようと首を伸ばした俺の耳に、珍しく大きい高野の声が通った。「高野!」「よくお越し下さいました! とりあえず、こちらへ」 駆け寄らんばかりに足早に近づいいてきた高野の目の下には隈が出来ている。きっと碌に眠っていないのだろう。空港を出たところで止まっていた車に乗り込み、早口に運転手に話しかける。「Sí, señor」 黒髪の下で鋭い目を光らせた運転手は、軽く頷いて車を走らせ始めた。重い息を吐いて高野がシートに沈み込む。ぐったり疲れているところに悪いとは思ったが、とにかく何があったのか聞かなくては落ち着かない。「一体、どうしたっていうんだよ、高野」 数日で2、30歳は歳をとってしまったような高野の横顔を見つめた。初老と言え、いつもきびきびしていて若々しい顔が、今は老け込んで疲れ切っている。「どうして周一郎が行方不明になったんだ? 朝倉家は動いてないのか? 一体、今回の旅行はなんだったんだ?」 ふと訳もなく、学園祭の時のカードを思い出し、口走った。「まさか、ローラ・レオニが関係してるんじゃないだろうな」「っ!」 明らかにぎっくんと体を強張らせ、狼狽した顔で高野は俺をまじまじと見た。「どうしてそれを……佐野様からお聞きになったのですか?」「お由宇?」 またもや予想外の人間が引っ掛かって、俺は混乱した。「どうしてお由宇が関係してる?」 そういやあいつも家にいなかった。まさか、こっちへ来てるとかじゃないだろうな。そんなことがあった日には、俺はただひたすらに厄介事目指して突っ走っていることになっちまう。 だがもちろん、俺の願いも虚しく、高野は上品に首を振りながら応じた。「関係しているどころか……今回坊っちゃまの命が狙われていると教えて下さったのは、あの方なのです。坊っちゃまが傷つかれると、あなたが悲しまれるからと仰って…………まこと、昨日の敵は今日の友とはよく言ったものだ……」 最後の方は独り言になって、俺の頭は混乱の度合いを増すばかりだ。 わかっていることといえば、どうやら周一郎は命を狙われていて、行方不明というのも連れ去られたか殺されたかという意味らしく、加えてこのまま訳のわからない問答を続けていたら、完全に俺の頭はショートしてしまうだろうということだけだった。「あ、あのな、高野」「はい」「俺は頭が回転しにくいタチで」「存じております」 あ、あのなあ……。「それなら、もっと筋道立てて話してくれ。何が何だか、俺にはさっぱりわからん。一体どうして、周一郎は急にスペインなんかに来たんだ? ローラ・レオニってのは何者なんだ? どうしてお由宇が周一郎が危ないって知っている……いや、どうしてあいつが周一郎に関わってるんだ?」 立て続けの俺の質問に、高野は宇宙人が関西弁をしゃべっているのを聞くような妙な表情で、俺を見た。「本当にご存知ではないのですか?」 深く、深ーく溜息を吐く。「うん」「坊っちゃまはお話しにならなかったのですか」「ああ」「佐野様も?」「しつこいな、あんた」「なのに、何も訊かれなかったのですか、あなたは」 おいおいおい。どういう突っ込みだ、それは。「何を訊けっていうんだよ」 反論する。「何か事情がありそうだとはお気づきでしょう」「いや、事情はあるだろうけど、俺に話したいとは限らないし」「興味はないと」「いや、だからさ、興味はあるけど」 誰かの秘密に興味は持つ。けれどもそれを暴くのは別問題だし、話せない秘密なら突っ込まれても困るだろう、相手が。「話したくなかったなら訊かないほうがいいだろうし、知らなくても周一郎やお由宇の何が変わるわけでもないし」 むしろ、知っていて欲しいなら話してくれるだろうし、そうでないなら、知って欲しくないのだろうし。「なるほど」 高野はもう一つ溜息を重ねた。「ありのままを受け入れて拘らないと。……だから、坊っちゃまはあなたにはお心を許された……」「いや…そんな立派なもんじゃないような…」 もぞもぞして窓の外へ視線を反らせた。 そうとも。現に見ろ、そんな危ない橋を渡ることが、あいつにわかっていなかったはずがない。部屋を片付けたのも、ポートレートを返して来たのも、読みかけの本さえ戻したのも、今思えば帰れないかも知れないと考えていたからだろう。 だが、そんな時でさえ、やっぱり周一郎は俺に一言の相談もなく、さっさと旅立ってしまっている。 心を許している人間に対する振る舞いか、それ?「…恐らくは……あなたに知られることを怖れていらっしゃったと思うのですが」 高野はシートに再び身をもたせかけた。振り返る俺の目を、今度は高野が避けるように目を伏せる。 「始めからお話しします、滝様」 ****************
2022.11.02
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』2.三つの河の小譚詩(1)
****************「ったく…何だ?」 俺はぼやきながら、受話器を置いた。「お由宇もどっか行ってんのか?」 どうも周一郎のことが気になって(第一、今までの商用旅行に高野が付いて行ったことなどない)お由宇に相談しようと2、3日前から連絡を取ろうとしているのだが、電話に出ない。「おまけにルトの奴もいないし」 溜息をついてベッドに寝転がる。学校は休みに入っている。就職を急ぐわけでもない俺にとって、毎日は暇で暇で仕方がない。「ん…」 こつ、と頭に何か当たって、枕にしかけた本を引っ張り出した。周一郎の部屋で見つけたもので、『ガルシア・ロルカ詩集』のタイトルが紺地の背にくすんだ金文字で押されている。学園祭の時の『覚え書』とかが気になって、ひょっとしたらと思って探したら、やっぱり持っていたから借りてきた。「…『三つの河の(小譚詩)バラディリア』…」 誰が読んだのか、所々に小さな黒い星印が付いていて、おそらく、これを読んだ人間のお気に入りだったのだろう、ページの端が薄黒く汚れていた。周一郎だろうか。本は結構古そうだ。他の人間も読んでいたかも知れない。「……去り行きて………戻らなかった愛……か」 ふっ、俺にはいつものことだがな。 ちょっとだけカッコつけて苦笑しながら、次のページを捲ろうとしたら、「滝様!」「ん?」 うろたえた声がドアの外から響き、体を起こした。岩淵が青ざめた顔で飛び込んできた。「何だ?」「高野さんからお電話です! 周一郎様が…っ」「周一郎が?」 いつにない岩淵の慌て方に、嫌な予感がした。「電話回してるんだろ?」「え、ああ、はい!」 それにようやく気付いたように岩淵が頷く。受話器をとると、どこか遠い高野の声が届いた。『滝様? 滝様ですね?』「ああ」『良かった。すぐにスペインにお越し下さい』「は?」 とんでもない要望にぎょっとする。「そりゃ無理だろう。第一、パスポートだってないし」『そちらは岩淵に手配させました。正規のルートではありませんが、証明は本物です』 どういうことだそりゃ。 きょとんとしつつ続いたことばに血の気が引く。『お願いします。坊っちゃまが行方不明なんです!』「何っ…?」 一気に広がった不吉な予感とともに、厄介事が『おいでおいで』をしているのが見えた。 ****************
2022.11.01
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』1.覚え書き(3)
****************「ん…うにゃ」 身動きして、部屋の眩さに開きかけた目を閉じる。手探りで探した目覚まし時計はどこにもない。仕方なしに体を起こして、寝ぼけ眼で見渡すと、どうしてそこまで飛んだのか、ソファの向こう、壁際に転がっていた。「…?」 頭を掻きながら、毛布ごとベッドからずり下り、時計を拾いに行く。 そういや、夢の中で投げたような気がしなくもない。時計は白目を剥いて、つまり長針短針ともに6を指して吊り下がり、揺らすとブラブラ動いた。「ちぇっ……壊れてやがる」 ぼやきながら、再びベッドに戻ろうとして、ふとソファ前のテーブルに置かれているものに気づいた。画像は入ってきているが、学園祭の打ち上げで飲み慣れない酒を付き合った次の日だから、どうにも頭がうまく働かない。 それは、1枚のポートレートと1冊の本だった。 ポートレートのほうは能天気な笑いを浮かべている男の顔、毎日鏡で見ている顔だ。本の方は確か周一郎に貸した奴で、栞が中ほどに挟んだままになっているところを見ると、読みかけらしい。「……」 のたのたとソファに近づき、時計をテーブルに置いて、腰を下ろす。 どうにも飲み込めない。二日酔いのせいばかりじゃない。この光景自体が妙だ。「……どうして、こんなとこにあるんだ?」 ようやく疑問が形になり、のろのろとポートレートを取り上げた。そうだ、こいつは周一郎の部屋にあったはずだ。それがどうしてこんな所にある? もう一方の手で本を取り上げる。こいつもおかしいと言えばおかしい。今まで周一郎が読みかけで本を返してくるなんてことはなかったのに。「……………」 両手のポートレートと本を交互に見やる。どーしてなんだ、どーしてなんだと頭の奥でぼんやり繰り返し、唐突に我に返る。 おかしい。 とにかく、訳はわからんが、確かめておいたほうがいい。 俺は急いで服を着替えた。ジーパンに脚を突っ込み損ねて2回コケかけたことを考えても、俺にしては『スムーズに』慌てられたと思う。ポートレートと本を抱えて2階へ駆け上がる。腕時計は10時を指している。周一郎ならとっくに起きて仕事中だ。 ノック。「周一郎?」 静まり返った邸内、俺の声が無遠慮に響く。もう少しノックを強めて、声をかける。「周一郎? 入るぞ」 返事がないまま、それでもドアは無抵抗に開いた。「周一郎?」 部屋の中に姿はなかった。俺の部屋と違って、きちんと整頓された机の上には塵一つなく、そればかりか、いつも載せられている書類の類さえ片付けられている。書棚の本は1冊も抜き出されていないし、ゴミ箱の中も空だ。 とりあえずポートレートと本を机の上に置いて、そっと隣室との境のドアを開けた。「……………」 声をかけるまでもなく、そこにも周一郎の姿はなかった。カーテンが引かれ、薄暗く闇を澱ませている寝室に乱れた様子はない。整いすぎるほど整ったベッドに皺もないし、枕元の本もない。 変だ。 黙ったまま、寝室のドアを閉める。机に戻って、ポートレートと本を持ち、部屋を出る。 綺麗すぎる。 これじゃまるで、人が住んだことがない部屋みたいじゃないか。「滝様」「ん?」 声を掛けられ、ぎくりとして振り返った。高野の補佐、岩淵がきょとんとした顔で俺を見ていた。「周一郎様はお出かけになりましたよ。ご存じじゃなかったんですか?」「いや…いつ?」「今朝早くです。滝様のお部屋から出て来られたので、てっきりお話になったのだと思っておりました」 今朝。 手にしていたポートレートと本を見た。 そうすると、周一郎はこれを置いて、黙って部屋を出て行ったらしい。「どこへだ?」「スペインです。長期になるかも知れないと仰って……あ、高野さんもついて行かれましたけど」「スペインか…」 それぐらいなら、俺に一言あっても良かっただろうに。ひょっとするとあれか、学園祭の時に旅行話で微妙に落ち込んだのを悟られたのか。そう言うことには聡いからな、人の気持ちには疎いんだが。 ちょっとふてた俺に気づいたのか、岩淵は穏やかに微笑んでことばを継いだ。「お急ぎのようでしたし…きっと滝様がお休みだったので、お声をかけられなかったのでしょう。他に何か?」「いや、別に…」「それでは、朝食の御用意ができております。食堂の方へお越し下さい」「あ、うん」 俺はなんとなく拍子抜けした気分で頷いた。 何かあったのではなくて、ただの旅行、おそらくは仕事がらみの長期。だから高野がついてった。 そういうことだ。うん、たぶん。 一瞬、頭の隅を、あの『覚え書』の一節が掠めて行った気がした。****************
2022.10.31
コメント(0)
-
『青の恋歌(マドリガル)』1.覚え書き(2)
**************** ……にしても。 俺は溜息をつきながら、『たこ焼き』を食べている周一郎を見やった。 にしても、だ。一体、たこ焼き食って、様になる男がどこにいるんだ、どこに! ああここか、ここにいたよな、うん!「…ふ…ん…」 ベンチに座った周一郎は、発泡スチロールのトレイに載った『たこ焼き』を、面白そうに突ついている。生まれの良さか、それとも躾か、食べ方もいやになる程上品で、そのくせ全く嫌味なく本人と『たこ焼き』の両方に似合っているものだから、否応無く人目を引いて、さっきから側で歩速を落とす女が後を絶たない。露骨なのになると、立ち止まってしきりに秋波らしいものを送ってきてはいるが、当の周一郎は、経済学の最新論がトレイに載っているのだとでも言いたげに『たこ焼き』に熱中していて、気づかないのか気づかぬふりをしているのか、とにかく一度も顔を上げなかった。 おかげで俺は、振られた女の呪いの視線をまともに浴びることになって、さっきからどうにも居心地が悪い。今しも、妙に目の光にきつい、化粧っ気の全くない女にじろりと睨みつけられた。 俺じゃない。周一郎がそちらに気を向けないのは、絶対俺のせいじゃない! 胸の中で必死に弁解し、嘆願の目を向けようとしたが、あまりにも険しい顔をされたせいで正視することもできず、慌てて知らぬふりをする。相手は睨みつけるだけ睨みつけると気が済んだのか、ふん、とばかりに波打つ黒髪を翻し、足早に去って行った。「…ふうう」「?」「いや、なんでもない。気にせず食ってろ」「はい」 にっこり笑う周一郎、またもや足を止める女。エンドレスかよ。ひょっとして今日は一日中、隣に座りたいのを無粋に邪魔している気の利かない男として恨まれ続けるのか? だからと言って、サングラスをかけさせて端正な顔を隠そうとしても、余計に目立つかも知れないし。「…やれやれ」「では、次のプログラムです! どうぞ!」 ルトに焼きそばの残りをさらわれた俺は、響いた音にステージの方へ目をやった。屋外ステージでは、ちょうど演者が上がったところで、ギター1本持った男がマイクを掴んでいる。「えー、今日はどうも。上尾旅人です。名前の通り旅から旅で、今年も留年となりましたぁ」 わあっ、と笑い声が上がった。知らない人間じゃない。学園祭だけではなく、喫茶店やカフェでミニ・コンサートをやっていて、なかなかの評判になっている男だ。「とりあえず、自己紹介がわりに一曲。タイトルは『青の光景』です」 ギターの音色が澄んで響く。「照る日射し 吹き抜ける7月の風 君は少女になって笑う 彫りつけた影の重さを 軽く道に投げ捨てて タホ河の川面をゆく スペインの旅情の色 諦めと天空への憧れが合う街で………」 甘い切なげな声だった。少し強くなってきた雪の中、茶色の髪を肩辺りまで垂らした上尾の顔には深い翳りが浮かんでいた。「許されぬ愛ならば この身を削っても貫く いつの日か結ばれる日 想っては胸に広がる苦さ 思い返せばいつも君は 影の中で笑った その背に金の羽根が 宗教画のように光る 旅立てば不死の祈り 誰のことばだと訊いた 名も知れぬ詩人の後を 追うように君は発っていく 優しい日々の温もりも 涙色の想いも振り捨てて 祈りさえ届かぬ闇 金の羽根輝かせて 残されたぼくの心を 閉じ込めて君は行くのか…」 ふうん。 こいつの歌を聴くのは初めてだったが、悪くないじゃないか。何よりも声と歌詞が合っている。どこか掠れ気味のハスキーボイス、けれども高音の辛さを感じさせない。「…どうもでしたー」 拍手が湧き起こった。旅人さーん、と嬌声が上がる。いやあ、俺も一度でいいから、あんな風に呼ばれて見たいもんだが、女の子に呼ばれて楽しいことに繋がった記憶がない。「えーと、これ、僕の初めての失恋の歌です」 MCにいやーんと女の子が騒いだ。可哀想、と声が続く。「あははっ」 上尾は照れ臭そうに笑って、一転、生真面目な表情になった。「ちょっとスペインに行ってたことがありまして……その時に惚れた女性がいるんですよね」 いやーん、と再び女の子が騒ぐ。惚れてもいやーん、振られてもいやーん、だったら、どうせえっちゅうんじゃ、全く。「不思議な人で、こう、2つの面が共存してるんですよね。激しいところと脆いところ、冷たいところと優しいところが。で、柄にもなく焦って告白したんですが、見事振られてしまいまして……えーと、タイトルの『青の光景』には、その辺りの意味合いがあるんです」 意味がわからないのだろう、観衆がざわめいた。「スペインの青っていうのは独特の意味があるんです。俗に、スペインの色っていうのは『黒』なんですが、それへと移り変わる前段階に『青』があるんですよね。で、この『青』っていうのは『黒』が死を示すのと同様、1つの意味がある。天上の青、そう呼ばれます」 上尾は熱っぽく語り続けた。「死へと続く、けれどもっと違った、救いを求める色と言うのか、それが『青』なんですよね。で、その…僕の惚れた女性っていうのが、ちょうど、その『青』と『黒』の境に立っているような女性でして、彼女の周りが夜なのに、羽の輝きでその黒い色が青に見えてしまうって言うか、そう言う感じの女性で……まあ、何を言ってるのか、よくわからなくなってきましたが、そう言うイメージで作りました。えっと、それじゃ、次の曲、『心を傷つけて』…」「…ごちそうさまでした」「あ、うん」 周一郎の声が突然聞こえて、我に返った。視線を巡らせると、なぜか沈んだ表情の周一郎を見つける。「どうした?」「いえ…」 問いかけに、周一郎は曖昧に笑って見せた。「…スペインにはあまりいい思い出がないので」「いい思い出がないって…行ったことあるのか?」「ずっと昔ですけど。9歳…ぐらいかな」「へええ」…? 9歳でスペイン旅行ね。俺はその時何をしていただろう? 有難い義務教育を受けながら、施設と学校の間を往復していただけのような気がする。 ……やめよう、自分から進んで落ち込むこたない。「…ん?」 溜息混じりに前方へ目を向け直した俺は、目の前の地面に白いカードが落ちているのを見つけた。さっきまではなかったはずだ。訝しく思いながら拾い上げる。 表面に、たどたどしい感じの紺色の女文字で、次のように書かれている。『わたしが死んだら ギターと一緒に 埋めてください、砂の下に オレンジの木々と薄荷の間に 風見の中に』「?」 カードをひっくり返す。かなり古いものなのだろう、あちこち黄ばんでいる。隅の方に小さく、表と同じような女文字で年号と名前が書かれている。「……年、ローラ・レオニ」 その右端に、赤黒い、妙なシミがある。「…血…?」「何ですか?」 興味を惹かれたように、周一郎が声をかけてきた。「いや……これ、さっきの子かな、落としてったんだろ、ほら」「…」 手を伸ばしてカードを受け取った周一郎が瞬間、体を強張らせる。「? 何かあるのか?」「…いえ」 僅かな沈黙の後、ポツリと応じた。それでも、周一郎の眼はカードから離れない。「詩、か?」 話の接ぎ穂を失って、俺もカードを覗き込む。「…ガルシア・ロルカの『覚え書』」「ふうん?」「…に、似ています」「遺書みたいだな」 今度はあからさまにぎくりとした周一郎は、やがてゆっくりと振り向いた。「そうですね」 淡く笑ったその目が深く、妙に頼りなげで、それ以上詮索するのはやめにした。なおもカードを見つめている周一郎の頭を軽く叩く。「まあいいや。宮田から寄れって言われてるんだ、行こうぜ」「どこへ?」 いつもは子ども扱いされるとむっとした顔になるはずの周一郎は、素直に俺を見上げた。「美少年フォトコンテスト。ったく、あいつの趣味は年々ひどくなる」 くすりと笑って、周一郎はカードをポケットにしまい込みながら立ち上がった。****************
2022.10.30
コメント(0)
-
2010000ヒット、ありがとうございます!『青の恋歌(マドリガル)』連載開始。1.覚え書き(1)
****************「えーっ…と…」 学園祭で賑わう人混みを掻き分けながら、俺は周囲をキョロキョロ見回した。「…っかしいな……この辺にいるって…」 別名2月祭とも言われる学園祭には、毎年多くの外部からの客が詰めかけ、人口のそれほど多くない街にしては珍しいほどのお祭り騒ぎとなる。ほぼ1年がかりで準備する各クラブの出し物もそうだが、並ぶ模擬店はプロ顔負けの連中が多く、受験ランクでは下位の大学の呼び物の一つになっていた。 試験が済んだ後の熱気と開放感というのはどこも同じで、そこに学園祭が重なっているとくれば、散らつき出している雪もなんのその、人波は絶えることなく学内へ流れ込んでくる。「痛っ!」「あ、すみません」「気をつけろよ!」「あ、どうも」「きゃああああ! 痴漢!」「ちっ、違いますっ!」「嘘! 今、私の体に触ったじゃない!」「えっ? こいつ…」「違うってば!!」 一歩間違えりゃお化け屋敷の住人かと言うほど無茶苦茶に化粧を施した相手に目一杯の金切り声で喚かれ、慌ててその場を逃げ出した。人混みの中をすり抜け掻き分け、ようやく騒ぎから離れられたと気を抜いた次の瞬間、ぐっ、と何かに足を引っ掛けられ、思いっきり前へつんのめる。「どべ!」 目の前に飛んだ星はご丁寧にも三色カラー、じんじん痛む鼻を抑えて起き上がった俺に、パチパチと場違いな拍手が聞こえた。続いて、皮肉っぽい取り澄ました声。「いやー、すごいすごい。そこまで派手にこけられるのは一種の才能だよ」「山…根ぇ…」「おいおい、そう睨むなよ」 左前方に格好つけたポーズで立っていた山根は、気障ったらしく肩を竦め、両手に花の羨ましい状態を見せつけるように胸を張った。「一般人はそこまで見事な『ダイブ』は出来ないなあ」「あら、そんな事言っちゃ、可哀想よ、ケイ」「そうよ、滝くんだって『一所懸命』やってるんだもの」「そーよ、いくら何もないところで空中飛ぶぐらいこけられるからっ……て……っくふっ」 慰め顔に頷いていた女が我慢の限界がきたのだろう、吹き出してしまう。それをきっかけに周囲がどっと笑い出した。ひとしきり笑った後、それらを軽く制して、山根は手を振る。「いやいや、待ってくれ、彼は『何もない』ところで転んだんじゃないんだ」「え?」「嘘、どうしてえ?」「彼は、『自分の足』に躓いたんだから」「まさかあ!」「山根っ!」 俺もさすがに言い返す。「どこの世界に自分の足に躓くアホが」「……」 言い返しかけて、山根が無言で指差す先を見ると、確かに転んだあたりには何もなかった。木の根も石ころも花壇の柵も、出っ張りどころか凹みさえない、真っ平らなアスファルト。「え? でも、俺は確かに何かに躓いて」 嫌な予感に足元を見る。そこには汚れたジーパンの裾と嬉しくなるほど見事に絡んだ俺の足が。「はっはっはっは」 HAHAHAHA。 山根の笑い声がそんな書き文字で空中に弾けた。「きゃーっはっはっは!」「くはっはっは!」 取り巻き諸共に爆笑する、その笑い声の渦の中心で、俺は歯を食いしばって唸った。 ったく! どこの世界に主人の行動を邪魔する足があるんだよっ! 周一郎のバイトの件以来、事あれば俺を陥れようとしている山根に、見ろ、まんまと笑い者にされただろうが!「…どこの世界に、自分の足に躓く『アホ』が、いるって?」 嫌味ったらしく、薄笑いを浮かべて山根がからかう。「え? 滝君?」 んなろ……月夜の晩ばかりだと思うなよ、そのうちに、猫という猫を掻き集めて、てめえの家の送り…つけ…て……。「お?」 笑い続ける山根の足元に、そろそろと忍び寄る青灰色の塊を見つけてきょとんとする。 あれ? なぜこいつがここにいる? っていうか、いつの間に来ていた? そいつは主人似の気配を殺した歩き方で山根まで辿り着くと、くるりんと尻尾を相手の足に絡みつけ、にゃあう、と実に可愛く鳴いた。「はっはっは………? ……にゃあう……?」「……そこだ」 笑顔を強張らせる山根に、ゆっくりと足元を指差してやる。 化け物がそこにいると言われた男のように、引きつって青白い顔で見下ろした山根は、次の瞬間、文字通り跳ね上がった。振り飛ばされかけたルトは、空中で尻尾を解いて鮮やかに離脱する。「△□☆□☆!!」「ちょっと!」「山根くぅん!」「どうしたのよ!」 意味不明の絶叫を残して逃げ出した山根の後を、訳もわからず取り巻きが追っかけて去っていく。「はっはっはっはー! ざまあみろ、やーいやーい!」 残された俺は久しぶりの大勝利に大笑いした。その膝に、ルトがとことこやってきて、ひょいと片足を乗せる。「にゃうん」 わかるけど、ちょっと落ち着け。 そんな感じでルトが鳴く。「おーよしよし! お前は可愛い奴だ、うんっ!」 俺はルトを抱き上げて立ち上がった。ぎゅううっと抱きしめると、よせやい、と言いたげに牙を剥かれる。「にぎゃ」「あ、悪い悪い、苦しかったか。けど、お前のご主人は一体…」 くすくすくす。 背後で小さな笑い声がした。俺の腕から身を捻ってすり抜け、地面に飛び降りたルトは、足音軽く主の元へ駆け寄っていく。「ご苦労様、ルト」 どこか幼い声で応じて、ベージュのシャツに焦げ茶のトレーナー、黒のスラックスと珍しく砕けた格好をした周一郎が屈み込み、飛びついてきたルトを抱き上げた。「御招待、ありがとうございます、滝さん」「へえ」 まじまじと相手を上から下まで眺める。雪が散らついての薄曇りの天候、これなら眩しくないと考えたのだろう、いつものサングラスはかけておらず、腹の立つほど整った顔立ちがフルオープンだ。「何です?」 訝しげに眉をひそめる、その表情一つで人目を引く。「いや…そうしてると、まるで『一般』高校生に見える」「そうですか?」 周一郎は僅かに瞳を陰らせた。「学園祭……なんて、縁がなかったので」 ゆっくりと周囲を見回す表情に、好奇心とも羨望ともつかぬものが漂っている。「だろうと思ってさ」 肩を並べて笑いかける。「俺ももう4年だし、こんなことでもなきゃ、お前、こういうのって知らず終いだろ?」「僕の……ため…」「え?」「いえ……でも、就職活動で大変でしょう?」「半分諦めてる」 苦笑いしながら歩く。「何せ、身寄りがないし保証人がいないし頭も悪いし体力も平凡、閃きもなけりゃ根性もない。気長にバイトでもするよ」「…にしては」 周一郎は微かに笑った。「今回は気が利いてますね」「ははっ、バレたか」 引きつった。 まあ、周一郎のことだから、見抜くんじゃないかとは思っていたが。 実は、今回のお膳立てはお由宇がしてくれたことなのだ。俺がたまたま、「周一郎に1回、学生生活ってのをさせてやりたいな」なぞと呟いたのににっこり笑い、「それなら学園祭にでも誘ったら? 喜ぶわよ」と宣った。俺にしてもうまくいけば、大学最後の学園祭ということで、悪かあないな、と周一郎を誘うことにした。「実はお由宇の案なんだ」「佐野さんの」 一瞬、周一郎は外見のおとなしやかな雰囲気に不似合いな鋭い目になった。「そうですか」「何だ?」 含みがある気がして相手を覗く。「何かあるのか?」「いいえ」 問いにくるりと表情を変え、邪気なくこちらを見上げる。それは、普段朝倉家で見せるより数段幼い顔で(或いは外しているサングラスのせいかも知れないが)、俺は単純に気分が良くなった。「じゃ、とにかく回ろうぜ、で、何か食おう」「構いませんが…」 くすっ、と周一郎はまた笑った。「支払いは大丈夫ですか?」「大丈夫! ただし」 ポケットから、宮田から交渉で巻き上げたタダ券を出して見せる。「この中にあるものだと、大変嬉しい」「わかりました」「あ、でも他のでもいいぜ、欲しいものがあったら言え、買ってやる!」「…はい」 素直に頷いた周一郎は、何がおかしいのか、くすくす笑い続け、ルトもにゃい、と牙を剥いて見せた。****************2010000ヒット、ありがとうございました!地道に続けていればヒットが増える、ありがたいことです。来て下さっている方々に、心より御礼申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。で。『ラズーン7』は現在執筆中です。今しばらくは『青の恋歌(マドリガル)』にお付き合いくださいませ。アルファポリスと小説家になろう!ではすでに連載を開始しているのですが、ちょうどキリ番に近づいていたため、見合わせておりました。その間に何とか『ラズーン』の続きをと言う、いささかせこい発想ですが(いつぞや修羅場上等などとうそぶいておりましたっけ/汗)、結果的に間に合わなかった、ごめんなさい。先日職場の健診を受けたところ、身長が1㎝縮んでおりました。測定して下さった方が「去年も縮んでますね、もう1回計りましょうか?」と親切に言って下さったんですが、今更伸びると言うものでもなし、大丈夫です、と、そのまま記載して頂きました。来年も1㎝縮むのかな。どのあたりで減ってるんですかね。足の裏の脂肪とか髪の毛の量とか骨の厚みが減るとかかな。来年を楽しみにしたいと思います。
2022.10.29
コメント(0)
-
『これはハッピーエンドにしかならない王道ラブストーリー3』25.鉱虫(4)
****************「シャルン!」 さすがにこれ以上の悪趣味を重ねる気になれず、レダンは声を張り上げた。「大丈夫だ。こいつら……ガーダスは、俺達に興味がないようだ!」 ことばだけでは足りないと思って、ごそごそ動き回るガーダスの合間をすり抜けて、シャルンの元へ駆け戻る。「陛下……っ……レダン……っっ!」 飛びつくようにしがみついたシャルンは、全身震えていて、それほどの恐怖と不安を与えたのが辛く、同時にそれほどに自分を欲して案じてくれたのがたまらなく嬉しくて、唇が綻び…。 がつっ!「つっ!」「…何を嬉しそうにニヤニヤされているんですかこの変態俺様王は」 冷ややかな声とともに頭を抱えて蹲るほどの打撃が降ってきた。「ルッカ!」「ああそうじゃ今のは駄目じゃ殴られても仕方がない何なら私がもう一発殴っても良いと思うがどうじゃろうか?」 シャルンの声に被せるように大きな深い溜息をつき、ミラルシアも罵倒する「…ミラルシア様まで! どうなさったのですか、一体」 シャルンが必死に庇ってくれる。「陛下がご無事だったのですよ、なぜお二人とも陛下を叩かれるのですか?」 ああ可愛い。本当に可愛くてならない。 レダンは綻ぶ口元をさすがに覆った。「…説明しなさい変態王」「もちろん弁明するのじゃろうな、レダン」 ルッカとミラルシアの容赦ない糾弾に、レダンは頭を摩りながら立ち上がった。「それよりもまず謝罪なんだろう? 済まなかった、シャルン。あなたを怯えさせたね?」「わ…私は…」 何を思い出したのか、振り向いたシャルンの瞳に光る粒が膨れ上がる。悲しげに切なげに息を引くから、そっと目元にキスして舐め取っておく。驚いたのか、涙が止まったから、できるだけ笑顔を見せてレダンは話し出した。「最初に剣を収めた時に、どうもガーダスはこちらに敵意がないようだと感じたんだよ。ガーダスにとって人間は、羽虫程度のもののようだ。側に居ても岩くれと変わらない……いや、岩くれだったら食べられるから、まあ、砂粒のようなものか」「砂粒…ですか」 まだ涙に滲んだ声で応じて、シャルンは首を傾げた。「まあ、あの大きさだしな。それに多分、ガーダスは見ることができないと思う。匂いか、動きみたいなもので、俺達を感じ取っているんじゃないかな」 レダンは広間を振り返った。 バラディオスとガストはまだ興味深そうにガーダスの側に立って、動きを眺めている。戻り始めたサリストアがシャルンに気づいて、明るい笑顔で手を振ってみせる。「恐らく、あの広間にはガーダスが好む岩があちらこちらに埋まっているんだろう。ここはガーダスのお気に入りの餌場だということだな」「餌場…」「あちらこちらからやって来て、思い思いに岩を食べ、移動して行く。ほら、あそこの数匹はもうここを離れるようだ」 指差して見せると、シャルンは出て来た通路と違う通路へ入って行くガーダスをしげしげと眺めた。「陛下…」「もう大丈夫だよ、安心していい、シャルン」「…いえ、あの…あの、少しくすんだ色のガーダスが、一匹だけ全く違う方に向かいます」「違う方向?」 シャルンに示されてレダンは振り向く。ガストも気づいたようだ。確かに1匹だけ、他のガーダスと全く違う方へのろのろと向かって行く。しかも、並外れてゆっくりな速度、シャルンでさえ追い付けるぐらいに見える。「…ひょっとすると」 レダンはルッカにこれまで通り、来た道に印をつけさせた。シャルンを伴い、広間に戻る。すぐ側でガーダスの巨体を見上げたシャルンが息を呑む。 近づいてレダンも気づいた。よく見ると体の表面がボロボロだ。えぐれたような傷もあり、どす黒く見えるほどの穴も空いている。「ガスト、このガーダスは」「ええそうです、他のものみたいに頻回に岩場を掘り込まない。むしろ、どんどん動きが鈍くなって来ている気がします。さっき触れて見ましたが、他のガーダスよりひんやりとした感触がある。ひょっとすると、こいつは」「死にかけている、か?」 ガストが大きく頷く。「死にかけたガーダスは墓場に向かうんじゃないでしょうか。こいつが向かう先に、アルシアで見たような繭があれば」「その近くに巨大なミディルン鉱石と、龍、がいる可能性がある」「はい」 レダンはシャルンを振り向いた。さっきまで涙で濡れていた瞳が、強くきらきらと光っている。「シャルン、聞いたか?」「聞いておりました。そこに、母が居るかも知れません」 レダンの愛してやまない暁の星を思わせる瞳で、シャルンはレダンをしっかり見上げた。「陛下、そこへ私をお連れ下さいませんか」「もちろんだ、シャルン……っってえっ!」 頼ってくれたことが嬉しいと唇を綻ばせたレダンは、再びルッカに蹴飛ばされた。**************** 今までの話は こちら
2022.09.16
コメント(0)
-
『これはハッピーエンドにしかならない王道ラブストーリー3』25.鉱虫(3)
****************「いやああっ!」 シャルンの高い悲鳴が響いた時、レダンの胸に愛おしいとも誇らしいとも言えぬくすぐったい感情が溢れた。同時に自分の非情さに呆れもした。「男と言うのはどうしようもないな」「は? 何それ、今それを言う?」 サリストアが怒りに瞳を煌めかせて振り返る。「シャルンが泣いてるじゃないか! あんな中途半端な声をかけるから!」 ああ、もう、と地団駄踏みそうになってはいるものの、目の前の巨大なガーダスに完全に気を緩めているわけではない。「今からでも、こいつはやめとけって説得してこようかな、私」「正しい判断ですね」 こちらも唇を歪めたバラディオスが冷ややかな口調で断罪する。「あれほど心配させて平気な男だとは思いませんでした」「知らなかったんですか、初めからこうですよこの人は」 せっかく庇ってやったのに、恩も忘れてガストまで口を揃えた。「…まあ、この状況を見抜いたのは多少褒めてもいいとは思いますが」 冷や汗ぐらいは滲んだのだろう、頭上高々と動くガーダスの体を見上げて、額を擦った。 ガストの背後から追いかけるように現れたガーダスに、命の危険があると感じて走ったのは間違いない。次々と現れるガーダスに退路を塞がれ、ここまでかと覚悟を決めたのも嘘ではない。 だが、1匹目のガーダスが頭を下ろして足元を掘り込んだ一瞬、相手が自分達に全く意識を向けていないと気づいた。 確かに囲い込むように這い出てきたガーダスが迫っているが、どの個体もレダン達を気にしていない、いや、気づいていないと言った方が正しいか。「レダン、何を!」「静かにしろ」 レダンが剣を収め、すぐ間近を這うガーダスに近づいて行くのに叫ぶガストに命じ、ゆっくりと手を伸ばす。 艶やかな表面だった。磨き抜かれた飾り石のような、近づけば顔が映り込むのではないかと思えるぐらいの滑らかな体に、軽く息を止めて掌を当てる。 ざわっ、と表面が動いた気がした。 だがそれだけだ。 レダンが触れたままで、ガーダスは静かに歩みを続けて行く。よくよく見れば、体の下に細かな毛のようなものがあって、それが波立ちながら体を運ぶのだった。「…羽虫のようなものか」 レダンは苦笑しながら離れた。「おい……なんてことしやがる」 すぐ側に、剣を構えたままのバラディオスが近づいてきていた。いざとなればガーダスを斬り、レダンを確保してくれるつもりだったのだろう、緊張に青ざめた顔で微かに呼吸を乱している。「正気か?」「俺達など、餌でさえないらしい」「手は?」 サリストアが剣を収めて尋ねてくる。「なんともなってないのか」「ああ。意外に肌触りは悪くないぞ」「……ったく、寿命が縮んだぞ」 サリストアは大きな息を吐いて、顔を振った。「早くシャルンを安心させてやれ、泣かせたくない」「ああ、そうだな」 レダンは少し離れた岩場を振り仰いだ。大丈夫だ、安心しろ、と笑顔を見せて呼びかける。「シャルン」「陛下…っ」 掠れた小さな声が戻ってきた。続いて、「いや…嫌です、陛下…っ」「あれ?」「返答がおかしくないか?」 サリストアも訝る。確かにルッカに押さえられながら、懸命に手を伸ばすシャルンは、幼子のように必死で、あまりに可愛らしくて、レダンはつい見惚れてしまい……今に至る。**************** 今までの話は こちら
2022.09.15
コメント(0)
全4696件 (4696件中 1-50件目)
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 山内志朗『中世哲学入門―存在の海を…
- (2024-11-16 13:18:58)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 紅殻のパンドラ 1巻読了
- (2024-11-16 11:12:58)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- IMA 2024 Autumn/Winter Vol.42 の続…
- (2024-11-12 15:36:41)
-