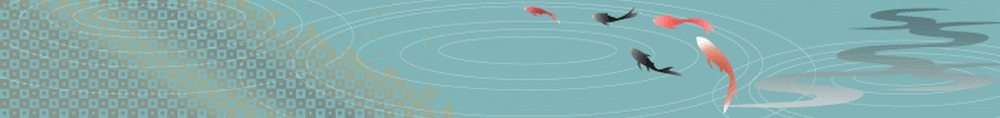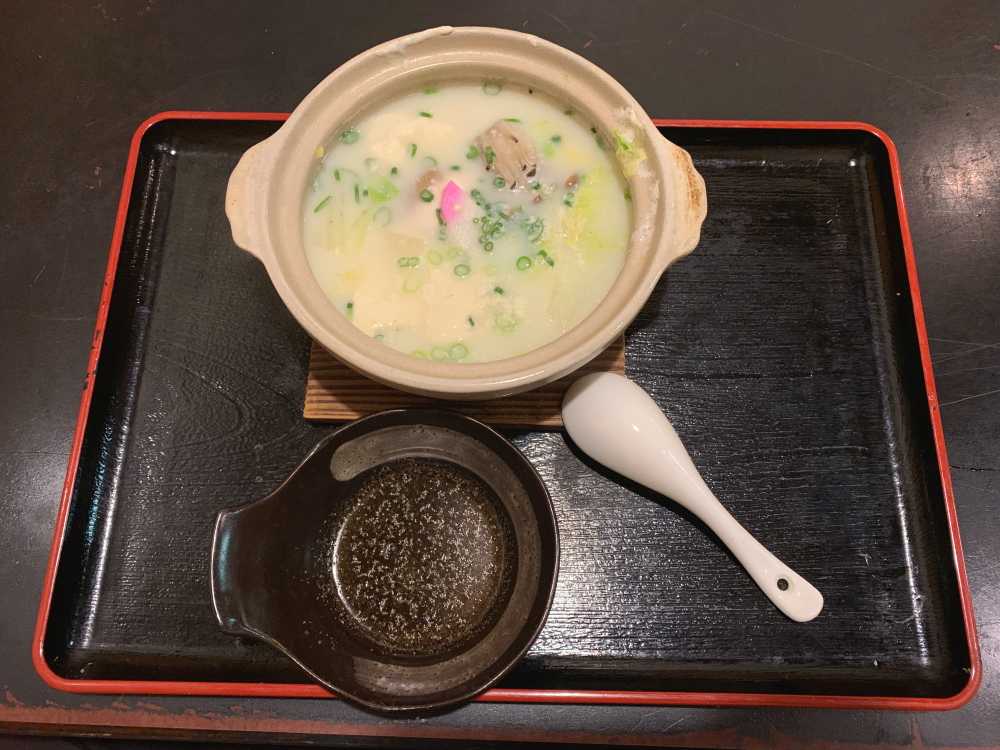-
1

独眼竜に目があった!!
上 伊達政宗 身長159センチ 血液型B型 「独眼竜」とはいわずと知れた戦国時代から江戸時代を生き抜いた伊達政宗のことですね。 彼は子供のころの病気で片目を失ってから目が一つしかなかったのですが、上の肖像画、目がちゃんとありますね。 伊達政宗は生前に描かれた肖像画には両目をちゃんと描くよう命じていたといわれています。政宗死後、木造が造られたのですが、これはちゃんと片目になっています。 彼は山形の米沢城で産まれのち、会津に乗り込み東北最大の戦国大名になります。 しかし、西から豊臣秀吉の支配が進み、降伏します。秀吉に許してもらった代わりに、会津から宮城の岩出山というところに左遷されます。 秀吉死後、徳川家康と通じ、関が原で家康の味方になり、岩出山から交通の便のよい千代に本拠地をうつし「仙台」と命名します。 のち、家康の孫、徳川家光まで仕え、激動の人生を終えることになりました。 政宗のお墓は仙台に復元されていますが学術発掘調査で身長155センチ、血液型はB型だと判明しています。 政宗が残したものはやはり東北一の大都市「仙台」でしょう。 次回ブログでは仙台に政宗が築いた「仙台城」の当時の姿を見てみましょう。
2005年12月11日
閲覧総数 530
-
2

謎の土まんじゅう??
田んぼのなかに花が咲いた「土まんじゅう」これはいったいなんでしょうか???田んぼの持ち主の趣味のお花畑なのでしょうか?? 実は信じられないかもしれませんが、この土まんじゅうは今から1400年以上前、五重塔が建っていた基壇の跡なんです。すなわちここの田んぼはお寺があったのです。 当時の建物は瓦で葺いていましたから、建物を乗っける基壇は何十にも土を踏み固めて造りました。建物がなくなると基壇が残るのですが、それもだんだん削れてきて最後にはこのような土まんじゅうになって残っているのです。ここだけ土が硬いので田んぼに出来ないんですね。 奈良や京都にはこのような「遺跡にみえない遺跡」がたくさんあります。
2006年11月09日
閲覧総数 350
-
3

金閣を作った義満はちょっとたれ目!!
上 足利義満画像 金閣(本当は鹿苑寺という)を作った足利義政とはどんな人だったのでしょうか? 上が足利義満の肖像画です。当時は似顔絵の技術が発達していたので、室町時代の人でも顔がわかります。義満の顔はその目じりの下がった目がチャームポイント?です。他の肖像画や木造もそのような顔なので本当に似顔絵だったのでしょう。 彼は生まれたときお祖父さんの尊氏の死後だったこともあり、諸国を逃げ回る子供時代をすごします。そんな時のエピソードをひとつ。 逃亡時あるとき美しい山と海を目にした11歳の義満は家来の「この景色が美しいのでもって帰れ!」と命じます。当然そんなことはできないのですが、自分の権力が高まると次々と破天荒なことをやってのけます。 京都に自分の屋敷の庭園を作るのに日本全国から季節の花を持ってこさせ、一年中花の咲いている「花の御所」を作ります。 また一休さんの話の中で「屏風の虎を縛ってみろ」と命じたえらいお坊さんが出てきますが、これが義満です。これは一休さんが今の金閣寺に招かれたときのエピソードです。 実現不可能なことを次々とやってのけた義満が最後にたどり着いたのがあの金閣造営でしょう。現代に残る義満唯一の作品です。 義満死後、「花の御所」は後に戦争で跡形もなくなり、北山山荘も金閣以外は義満のことを嫌いだった長男義持にことごとく破壊されました。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年08月30日
閲覧総数 637
-
4

これが弥生人が着ていた着物??
上 弥生人の服(推定) 弥生時代は先史時代なので、当然文字に書いた資料はありません。そこで参考になるのが「埴輪」です。当時の文化、とりわけ衣装についてはかなり参考になるはずです。 上の写真はそこから参考に作られたのだと思いますが、生地は麻などよりごわごわですね。何の生地だかは忘れてしまいました。 当時の衣服は貫頭衣(かんとうい)という頭からかぶる形が多かったようです。 ちなみに弥生時代の「弥生」とは文京区の地名から来ています。明治時代に東京帝国大学が置かれたとき、そこの先生が弥生町ですでに知られていた縄文土器とは違う高温で焼いた土器を発見。「弥生式土器」といわれたのが始まりです。 弥生人たちは後世で自分たちが「弥生人」なんていわれているのはどう思うでしょうかね?□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年08月18日
閲覧総数 1113
-
5

囚人から飼育係へ!!(ラストエンペラーの生涯8)
上 晩年の溥儀 再婚した妻と 再教育を受けた溥儀ですが、ついに収容所からででることが出来ました。 これには当時首相であった周恩来の計らいがあったといわれています。 溥儀は後、一平民として人民政府で仕事をしたり図書館で仕事をしました。そして最晩年は北京動物園で勤務していました。かつての皇帝は動物園にいたのです。 上の写真は溥儀がかつて住んだ紫禁城の前の天安門で再婚した看護婦さんの奥さんと撮ったものです。 一平民になった溥儀ですが、中国に文化大革命の嵐が吹き荒れはじめたころに体調を崩し1967年(昭和42年)他界しました。当時は医療施設が十分でなかったのです。 皇帝⇒尊号のみの皇帝⇒租界生活⇒皇帝⇒囚人⇒平民とまさに激動の人生でした。 次回は溥儀が大好物だったあるものを取り上げたいと思います。久々の「食」ですが、ご期待ください!!
2006年02月09日
閲覧総数 633