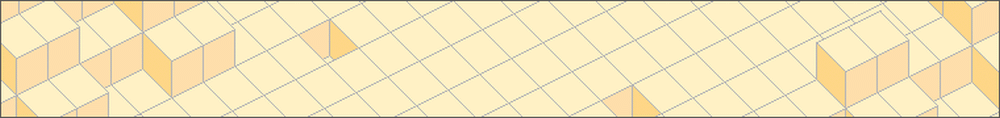先ほどの続き。
米国にあったもの。そもそもは1905年(明治38年)に早稲田大が初めて
米国に遠征した際に学んできたに過ぎない。
それまで、「武士道」の一環として野球というスポーツを考えていた日本に
とって、「バント」とは正々堂々としない卑怯な戦法としてとらえられていた。
例えば、 安部磯雄
(当時、早稲田大野球部部長)の「バント」に関する発言に
こういったものがある。
※以下は早稲田大入学前、神戸中在学時に外人のアマチュア選手たち
(主に神戸に寄港する米艦の船員)がバントを多用するのを見て、それを
真似してバントを試みた 泉谷祐勝
に対してのもの。
「泉谷君、そんな卑怯な真似(バントを指す)をしちゃいかん。打つなら打つ。
避けるなら避けるでどっちかはっきりし給え。打つのか打たないのか分からない。
まるでいやいやバットを振っているようだ。そんなことをしてはいかん」
(『日本野球史』国民新聞運動部編、昭和4年発行)
ところが---。
米国遠征の第1戦(1905年4月29日)、相手のスタンフォード大はランナー
が出るごとに(送り)バントをした。また三塁にいる時も同様、打者と走者が
息を合わせたようにバント(スクイズ)を繰り返した。
卑怯な戦法と考えていたためか、「バント」の際の守り方がまるでわからない
早大の内野陣。なす術なく茫然と立ち尽くすしかなかった。結局スコア1-9で
敗退してしまった。
帰国後、安部はバントについての考え方をあらためた。そして最新の野球術
を様々な方法で日本国内に広めることに努めた。もちろん、その中に「バント」
に関することもあった。
「バントを練習し、それによってバントエンドランとかスクイズプレーを行って、
野球の玄妙に触れねばならぬ」
(同上)
「玄妙」とは、道理や技芸などが、奥深く微妙なこと。趣が深くすぐれている
という意味(大辞泉)。米国遠征を通じ、初めてバントは「趣が深くすぐれている」
戦法として認められたのだった。
(※本文中、すべて敬称略)
◇ 安部磯雄
の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。
「野球術を普及した安部磯雄と橋戸信」
(2009.6.24) →
こちら
へ。
「米国遠征の夢と財布の中身」
(2009.7.9) →
こちら
へ。
この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。
→ (第3期)「1905年(明治38年)早稲田大がアメリカに遠征した時」に属します。
(第3期)に属する他の記事は以下のとおり。
◇ 「ボクにとっての日本野球史」
(2009.7.1) → こちら
へ。
「日米大学対決は104年前に始まった」
(2009.6.23) → こちら
へ。
「野球術を普及した安部磯雄と橋戸信」 (2009.6.24)
→ こちら
へ。
「米国遠征の夢と財布の中身」
(2009.7.9) → こちら
へ。
-
【東京六大学2025秋】小早川毅彦氏の始球… 2025.09.28
-
【東京六大学2025秋】開幕カード。慶應、7… 2025.09.14
-
【東京六大学2025春】東京大学vs.横浜高校… 2025.03.08
>なるほど、
>面白いですねぇ・・・
>貴重な情報をありがとうございます。
-----
こちらこそ、コメントありがとうございました。
(2009.07.13 00:21:21)
PR
Keyword Search
Calendar
【東京六大学2025秋】開幕カード。慶應、7点差を追いつき、同点引き分けに。
【東京六大学2025春】東京大学vs.横浜高校の歴史的一戦
【1890(明治23)年】インブリ―事件が生んだ『精神野球』
【1903年】早慶の初顔合わせの日。
【1901年】東京専門学校(後の早大)に野球部が誕生
【東京六大学1931春】八十川ボーク事件
【甲子園1927春】珍事?大阪代表校ゼロは92年ぶり。調べてたどりついた小川正太郎、そして八十川ボーク事件
【東都2024秋入替戦(1部2部)】第1戦は、東洋大がサヨナラ本塁打で先勝!
【甲子園2024夏】大社、31年ぶりのベスト8へ。昭和6年夏は映画『KANO』の題材となった中京商ー嘉義農林の決勝戦があった大会
Comments