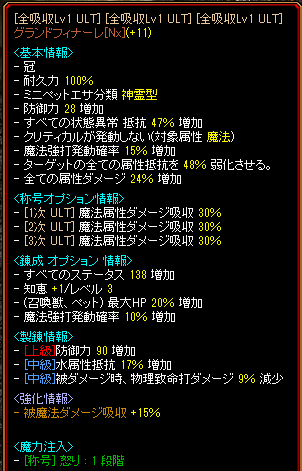2014年07月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
縦書き・横書き
「縦のものを横にもしない」とは怠け者や無精者をいう言葉だしかし 縦のものを横にしない方がいい場合もあることも忘れてはならないまた もともと横様の状態にあるものはそのままにしておけばよい危険なのは横書き文化が縦書き文化よりすぐれているかの如き思い込みである例えば英語教育が国語教育より大事であるとか何でもかんでもIT化・横書き化への流れこれらによって無意識のうちに失われるもののあることを危惧するのである1443年李氏朝鮮四代の王世宗がつくり1446年訓民正音の名で公布されたハングル世宗がこの文字をつくった動機は久しく中国の文化に支配されて、漢字・漢文を正統な文字・文語としていたのを民族的自覚によって朝鮮固有の文字を作る必要を感じかつ人民の日常の用にも供しようとしたところにあったしかし やがて漢字・漢文を正統化する傾向が根強くなり、ハングルは李氏朝鮮の終わるまでの啓蒙的な意味しかもちえなかったこの文字が真に朝鮮の国字に復活したのは第二次世界大戦後の朝鮮の<解放>以後であるそして反日による漢字廃止政策から1970年以来学校でも教えなくなりいまや 自分たちの古典すら読めない文化断絶が起きているこれこそ 縦のものを見境もなく横にしてしまった恐るべき失策以外のなにものでもない
2014.07.29
コメント(0)
-
コピペについての私見
朝の散歩の途次ふと思ったことがある人類の遠い先祖が二足歩行を始めてこのかた人は何万年も歩いてきたとすると散歩という行為も類人猿の行動の延長であり猿真似 つまり広義のコピーではないのかとそして路傍にはそのとき桜が咲いていたが日本の桜は 往古の中国では「ゆすらうめ」のことだったらしいとすれば 桜はゆすらうめの改竄にあたるのではないかとそもそも科学者の世界ではダーウィンの法則やらメンデルの法則やら万有引力やら相対性理論やらもろもろの理論・法則・定理をば寸分の疑念も持たず自家薬籠中のものとして無断で取り込み己の論文の背景に利用してきたではないかだからコピペといい改竄といい不正引用とか剽窃とか声高にいう学者の周辺も胡散臭さが拭い切れないのだコピペという言葉自体コピーという語からきたコピペだから厄介だつまり こういうこと世の中には完璧なオリジナルなんて存在しないってこと
2014.07.28
コメント(0)
-
サシバのこと
青空をけふ渡り来しサシバかな 田中政子鷹一つ見付けてうれしいらご崎 松尾芭蕉都会の雑踏のなかをすいすいと一風変わった見慣れないTシャツを着た男が行く背中に漢字で「鸇」と大書してあるえっ?これはこれは何と読むのかなかなかの難訓であるがとよくよく見れば漢字の下に「SASHIBA]とローマ字表記してあった「さしば」は刺羽とも書く鷹の一種で万葉集にも出てくる渡り鳥稀に鷹狩にも使ったらしいとするとあの日雑踏にまぎれて消えたあの男は古い狩猟法を受け継ぐ鷹匠の一人ででもあったのだろうか
2014.07.25
コメント(0)
-
鷹乃学を習う
皇居のクスノキの樹上にオオタカが営巣しているのが見付かったそうだ。6月に3羽のひなが確認され、親が餌を与えるのも目撃された。3羽とも無事に巣立ったようだという。都内の緑地が増えるのにつれ、野鳥類の生活圏が広がりつつあり、「鳥類の都市化現象」が起きているらしい。とき、あたかも暦の七二候では、小暑末候「鷹乃学を習う」(たかのわざをならう)(およそ7月17日~7月21日ごろ)つまり鷹のひなが、飛び方をおぼえるころで巣立ちし、獲物を捕らえ一人前になっていく季節なのだ。鷹一つみつけてうれし伊良湖崎 松尾芭蕉鷹来るや蝦夷を去る事一百里 小林 一茶鷹の羽を拾ひて持てば風集う 山口誓子鷹すでに雲を凌げり雲流る 加藤楸邨白骨の一樹に鷹の動かざる 角川春樹鳥類のなかでも、ワシタカ目ワシタカ科のうち、比較的小型の種を一般的にタカと呼ぶらしい。ミサゴ・ハチクマ・ノスリ・ツミ・チュウヒ・サシバ・クマタカオオタカなど、ワシタカ目の16種が日本で繁殖し、13種が秋冬に渡来するという。
2014.07.20
コメント(1)
-
一筆啓上
F紙のニュース時評欄での評論家K.O氏の言。 『7月10日に閉幕した第6回米中戦略・経済対話」で、両国政府は年内に投資協定の大枠を固める方針で一致した。この席で、中国の習近平国家主席は米国代表団を前にこんな演説をした。 「天高く自由に鳥が飛び、広がる海を魚が跳ねる。『広い太平洋には中米両大国を受け入れる十分な空間がある』と感じる」 「鳥は中国軍機で、魚は中国潜水艦のことらしい。何をバカなことを言っている、太平洋はこの2国だけのものではないだろう、といいたい。」と述べたあと・・・・・ 最後にこうもおっしゃる。「中国にはやはり反論したほうがいい。日本は歴史を忘れようとしているが、中国は歴史を歪曲しようとしているからだ」と。 親中か嫌中か、右か左か、保守か開明かにかかわりなくこの見解には若干の違和感がある。 それにはこういう理由がある 「天高く自由に鳥が飛び 、広がる海を魚が跳ねる」という文言は、おそらくは中國の古典「詩経」からの引用かと推測されるからである。「鳶飛戻天 魚躍于淵 豈弟君子 遐不作人」(詩経・ 大雅・ 旱麓) 鳶飛ンデ天ニ戻リ 魚 淵ニ躍ル 豈弟ノ君子 遐ゾ人ヲ作サザランヤ 鳶は飛んで天に戻り 魚は淵に躍りて楽しむ 安らけく楽しき君は 何ぞ人を作興せざらんや(海音寺潮五郎訳)習近平に肩入れする気は毛頭ないが引用された詩を知らずに曲解してやれ軍機だ、潜水艦だと歪曲するのも大人気ないし、建設的でないと思うのである。
2014.07.19
コメント(0)
-
お絵描き猫
ある日曜日何日ぶりかで一人暮らしの娘に電話した受話器の遥か向こう側から「ニャオー」と猫のなきごえが聞こえてくる「エレオノーラだね」娘は五匹猫を飼っていてそれぞれに名前をつけているのだが物覚えの悪いわたしは何故か「エレオノーラ」しか覚えていない明治期ラグーザ(Vincenzo Ragusa 1841~1927)というイタリア・シチリア島生まれの彫刻家は日本に近代洋風彫刻を紹介した明治9年(1876)日本政府の依頼により来日し工部美術学校彫刻科の教師として日本に初めての西洋彫塑の基本的技術を教えた明治22年(1889)に帰国したが明治32年(1899)に東京美術学校(現東京芸大)ができるまで、その弟子たちによって、洋風彫刻の命脈はよく保たれたのだったラグーザの遺作の多くは夫人 玉(清原 玉・ラグーザお玉 1861[文久元年]~1939[昭和14年])によって寄贈されたが、玉もまた画家としてよく知られているそして 玉のイタリア名がエレオノーラ・ラグーザ(Eleonora Ragusa)だった受話器の向こう側でないている猫のエレオノーラきみはきっと「もしかしてだけど」の「お絵描き猫」じゃないのか近いうちに必ず会いに行くからね
2014.07.15
コメント(0)
-
トートロジー
「いにしえの昔の武士の侍が馬から落ちて落馬して・・・」こういう同語反復をトートロジー(tautology)というらしい集団的自衛権についての国会論戦をきいているとこの言葉を思い出す質問する野党の側も答える政府の側も非建設的なトートロジーを弄していたずらに時間を空費するだけもはや、不毛の論議を繰り返している段階ではない基本的理念を憲法九条におき集団的であれ個別的であれ非戦、平和の道を如何に進むかそれこそ国を挙げて真摯に考えるべきときが来ている
2014.07.14
コメント(0)
-
蓮の花
日本人は日本の自然について太陽暦の春夏秋冬の四季に分けそのうえで一年を二十四等分した二十四節季さらに七十二等分した七十二候を考えた七十二候は季節それぞれの出来事をそのまま名前にしている今日七月十二日は四季のうえではいうまでもなく夏二十四節季では小暑小暑とは梅雨が明けて本格的な夏になるころのこと七十二候では七日~十一日ごろは小暑初候で「温風至る」という十二日~十六日ごろが小暑初次候にあたり「蓮始めて開く」という さはさはと蓮うごかす池の亀 鬼 貫 蓮の香や水をはなるる茎二寸 蕪 村 利根川のふるきみなとの蓮かな 水原秋櫻子 前の人誰ともわかず蓮の闇 高浜 虚子 興亡や千万の蓮くれないに 山口 青邨
2014.07.12
コメント(0)
-
蜩
確かこの辺にあったはずだが住宅街の家並みの奥近くにお稲荷さんの祠もあったようないちまいの表札そこには「蜩」と書かれていたその読みをそのときは知らなかった難しい苗字 何と読むのだろうずっと気になっていたあるとき北原亜以子の時代小説を読んでいたその小説の題が「慶次郎縁側日誌」のうちの『蜩』「ひぐらし」だったのだひぐらしさんを探して再び住宅街の奥を訪ねてみたが記憶の迷路はボーッとかすんで二度と見付からなかった
2014.07.11
コメント(0)
-
スニーカーは走れ
天高く重いシューズを放り投げ忍び足でなくスニーカーは走れ書を捨てよ野に出でよスニーカーは走れ思考は広く回路は深く忍び足でなくスニーカーは走れ
2014.07.11
コメント(0)
-
ヒコバエの思える
櫱という漢字がある「ヒコバエ」と読む櫱の下半分の木の部分を米に替えると糵「モヤシ」子に替えると孼「ワザワイ」となるしかし音読みではすべて「ゲツ」だま、それはそれとしてわたしなんぞは木の幹に簇生するサルノコシカケかヒコバエみたいなものだろうし日陰に育ったモヤシかも知れず生存していること自体がもはやワザワイなのかしらとつねづね思ったりするのだが・・・まてよ或る日 里山でのこと年経る桜のヒコバエが返り咲きの花を付けているのを見つけたその一輪は凜とした気韻を漂わしいかにも潔い風姿を見せていたー満更ヒコバエも捨てたものでもないー 以来 老桜にあやかってこのわたしというヒコバエもあとしばらく せめて十年位は咲いてみることにした
2014.07.10
コメント(0)
-
みさご
「オスプレイ」「オスプレイ」って言うけれどよく知られているのはいま問題のアメリカ海兵隊の垂直離着陸輸送機MV22のことしかし 英語「OSPRAY]のもともとの意味はタカ科の鳥「みさご」のことなのだ「みさご」は垂直に降下して魚を捕るみさごは夫婦仲がとてもいいらしい雄と雌のみさごが河の洲でのどかに鳴き交わしているさまが中国の古典「詩経」(国風)に詠まれている海音寺潮五郎は次のように訳出している『河の洲に みさご二つゐて 鳴きかわすや ほろほろと よき家に しら玉のたをやめこもりゐて よき若人の迎え待つらむ』いまや日本の防衛上の課題としてすったもんだの「オスプレイ」がこよなく夫婦仲のいい愛すべきみさごのことだなんてちょっとしたブラックユーモアではないか
2014.07.09
コメント(0)
-
花
五年前反日蔭の露地の一角に丁寧に植えた石楠花が今春やっと花を着けた庭石の裾に去年植えこんだ春蘭の一株にもひっそり花が咲いた卯月初め咲き誇る桜の季節をよそに『秘すれば花』と申し合わせたかのように咲きそろった石楠花と春蘭なにか佳きことの予兆めいて春は束の間卯の花くたしの季題をよぎりいま 梅雨のさなか梔子(くちなし)の白い花が重たげに匂っている
2014.07.08
コメント(0)
-
認知症って何だ
こころは体の容器で体もまたこころの容器に違いない雅楽の世界にいう呂と律こころと体が陰陽お互いに共鳴し合っている状態がいちばん健康なのだろう人間もそろそろ耐用年数を過ぎるころ心と体の呂律が合わなくなってくるそして認知症という魔物に取り憑かれたりするのだしかし よっく考えてもみよそもそも認知症って何なのだ胃に癌ができれば胃癌肺に癌ができれば肺癌わかりやすい筋委縮性側索硬化症なんて難病もあるがだいたいの意味は解るところが認知症の認知という語は工学・哲学・心理学にも使われるし法律用語でもあるしたがって認知症とはだれがつけたか概念のはっきりしない語だなあ・・・といったい認知機能が人一倍優れた芸術家は認知症ということになるのか認知機能のネガティブな障害だけをいうのなら認知障害といえばいいではないかそれ以前に医学上の認知の概念をはっきりさせておくことだきりがないからこのへんで止めておこう
2014.07.07
コメント(0)
-
マトリョーシカ
いまにして思えば もう半世紀も昔のこと ロシアはまだソ連邦だった 当時の首相は フルシチョフだったか 或いはブルガーニンだったか 東欧からソビエト歴訪の 旅の土産にと ある方から マトリョーシカ人形をもらった ずっと大事にしてきた 老いの記憶には いまも マトリョーシカは生きている 木製の入れ子になった人形を 一つずつ取り出しては 思い出を紡いでいる 記憶の連鎖は ときとして 思いもかけぬベクトルへと繋がるもの 一月のとある日 「イシカワケン ホースグン アナミズマチ シュッシン オイテカゼべヤ・・・・」 大相撲初場所のテレビ中継 呼び出しの声に なに ホースグン? フゲシグンの間違いだろう? 老人の記憶の抽斗にも 入れ子のハコにも 鳳至郡はあっても 鳳珠郡などなかったのだ ファンの興奮と歓声のなか 何故か マトリョーシカの記憶が甦った そして一月 ロシア・ソチでの冬のオリンピック ゲレンデの雪中に聳え立つ おお 巨大なマトリョーシカ 群衆の大歓声と国旗の波 老人の前頭葉の回路は まるで スクランブル交差点の 渦中にいるかのように なにもかもが パニックの極致 収拾がつかないのだった
2014.07.06
コメント(0)
-
しわぶき
「コン コン」と 目の前で そのひとは 二つ 三つ 空咳をした あれは 心中に なにか 鬱屈があったせいなのだろうか 「ひとは何故 空咳をするのか」 とりたてて言うほどの 哲学的命題でもないが ほんのちょっぴり わたしは考え込んだ そして 冷めた 卓上の コーヒーカップをはさんで しばし沈黙のときが流れた
2014.07.05
コメント(0)
-
5月の思い出
あれは たしか 若狭湾に向って 小さく突出した 常神(つねがみ)半島でのことだった なだらかな丘陵に 夕日の光(かげ)が耀(かがよ)うていたしz さわやかな5月の風に 一面の茅花(つばな)の花穂が まるで 近くから遠くへと 銀色の波となって 揺れていた 海鳴りとて届かない 半島の静寂(しじま)のなかで お下げ髪の少女が 茅花の穂を抜いては 虫籠に編んでいたっけ 狐の親子が コンとひと声鳴いて 現われそうな 半島のかわたれどきだった あれは
2014.07.04
コメント(0)
-
夏バージョン
カレンダーを一枚めくったら 今日から夏バージョン 杜は青嵐 花ならハイビスカス 卉(くさ)は半夏(はんげ) 雲の峰遥か 蒼穹のキャンパスに 白いチョークで 何の詩を書こうか
2014.07.03
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1