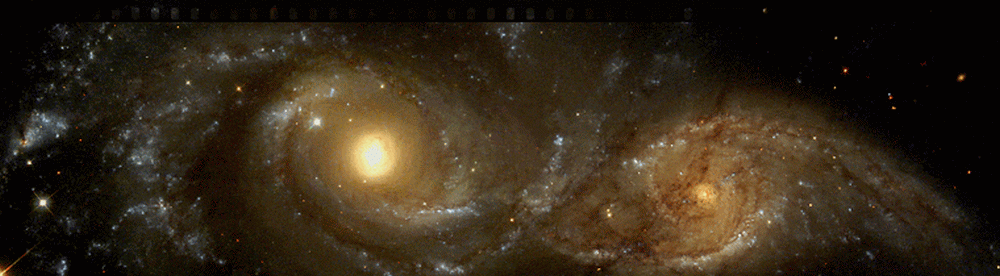-
1

イタリア語の2つの動詞「essere」と「stare」について。。。
私は、この2つの動詞の過去分詞が同じであることを、結構最近まで知らなかった。どちらも過去分詞は「stato」になる。今、見つけたのだが、これは元々「stare」の過去分詞を「essere」に借用したものらしい(Bescherell italien les verbes、出版社 Hatier)。このため、essere も stare も複合時制は全く同じになる。(io) sono stato/ta (noi) siamo stati/te(tu) sei stato/ta (voi) siete stati/te(lui/lei) e' stato/ta(loro) sono stati/teただ、こう活用表には載っていても、実際に2つの動詞の複合形に用法上の違いがあるかどうかわからない。ただ、、essere と stare は、非常に密接に関わっているのは確かである。特に stare は、「-ando, -endo」を活用語尾に持つ gerundio と一緒に使われて、英語の be 動詞を使った現在進行形に近い用法になる。フランス語には無い用法であるのも面白い。Sto cercando un lavoro. (仕事を探しています)stare のもう一つの用法は、「per + 不定詞」で、「~しようとしている」という意味になる。sta per partire. (彼/彼女は、出発しようとしている)実は、andare(行く)と venire(来る)という2つの動詞も、essere のように過去分詞を取って、受け身の表現や、更に gerundio を取って動作の進行形も表現することが可能である。詳しい文法の参考書をいろいろと引っ張り出してきて、ようやく全体像が見えるようになったのであるが、できれば、この4つの動詞を一緒に始めから解説している本に最初から出会いたかった。
2020.03.20
閲覧総数 1413
-
2

言語の起源から、言語学の起源へ。。。
私は、ソシュールの残した「言語には、正の項が無く、差異しか無い」という命題を証明する為に研究を続けてきたのだが、割と早い時期から、言語の本質を理解する事は、人間の本質を理解する事であるという結論に達した。最近は、考察が更に進み、言語と哲学の関係に迄、言及するようになってきている。私は、今まで30年の間、常に「言語とは何であるのか」と、自問自答を繰り返して来たのだが、最近は、この問いと並行して、同時に、別の考察をする様になってきているのだ。言語に留まらず、言語学の起源に関しても、考察の幅が広がっている。言語学というのは、元々、西洋で生まれたのだが、非常に長い伝統のある西洋哲学によって、予め骨抜きにされた状態で言語学が生まれたという結論に達したのは、自分でも予想外だった。哲学は人間の思考、言語学は文法という、一種の棲み分けが行われているのである。この点に関してソシュールは、普通の言語学者とは違うと私は考えている。それは、彼が文法記述に手を染めなかった点である。これに対してチョムスキーは、自ら、生成文法と普遍文法を引っ提げて、文法学者としてデビューした。言語の真のメカニズムを理解した事で、私は現在、人間の知の再編成をする事になったのだと思う。
2025.11.23
閲覧総数 8
-
3

離散性理論と離散的記号。。。
少し前から、記号(シーニュ)に関して新しい考察を加えている。フランス語の「signe」には、直接的ではないが「意味」という概念が入っている。ソシュール言語学的に言えば「シニフィアン」と「シニフィエ」の合わさったものとなるが、ここで使われる動詞は「signifier」であり、これは「意味する」となる。この「意味」というのは、人間の認知行動と関係が深い。認知とは問題解決式行動だが、実践される行動は「意味あるもの」でなくてはいけない。ソシュールは、これを受けて「シーニュ」としたのであろうが、私は人間のレベルでは新たなレベル、つまり新しい離散化ループによる記憶の進化であると考える。言語を使うという場面においては、人間はやはり「意味」を意識する。これは自然なことだ。しかし、動物が行動で意味を示すのに対して、人間は初めから意味をシーニュと言う形で知覚現象を通して提示する点にある。そして、そのシーニュはひとつだけではない。次々と繰り出されるシーニュの連鎖によって、その意味がどんどんと話者と対話者の記憶の中で進化していくのである。ここで、まず話者だけに限ってみよう。つまり、意味が対話者に伝わるのではなく、話者の意識の中で意味が進化する場合を考える。最初のシーニュは、まず「記憶喚起」つまり「思い出すこと」から始まる。新しい言葉を造語する能力は人間に備わっているが、ひとつの特定の言葉を使う場合は、その語彙の数や種類は既に個人個人で定義あるいは制限されている。「シニフィアン」を使って思い出す「シーニュ」は、元々自分自身で「シニフィエ」を感じ取り、その定義をパラダイム的に理解し記憶したものである。これはカテゴリー的ともいえる。例えば、犬は動物であって植物ではないという、離散的区分が幾重にも重なってひとつの概念が生まれる。「シーニュ」は、話者自身のアイデンティティーそのものではないが、あくまで話者のアイデンティティーの一部であるといえる。離散的に整理された記憶の中で、シニフィアンという「形」を思い出すことによって、シニフィエという「意味」も一緒についてくる。ひとつのシーニュに対し、直ぐに何かを続けることで、「Syntagme」つまり一つの表現となり、さらに「Syntagme」を連鎖していくことにより、複雑な意味を持つ文章へと進化していく。嘘でも誠でもかまわない。物語はこのようにして紡がれていく。文を続けるという作業は、一つのシーニュをまず覚えておいて、それに対し、また別のシーニュを思い出し追加し、新しくできた意味を覚え、さらに別のシーニュを続けるという作業になる。これは、胚の細胞分裂と似ている。胚はあくまで一つのアイデンティティーを持つ個体として成長するが、中身は細胞分裂を繰り返してその数がどんどん増えていく。今考えているのは「Signe discret」つまり「離散的記号」である。言語では、あくまで人間のもつ動物の面が不可欠であるという考察から、ソシュールの記号という用語は残したいと思う。そして発話という作業は、個人の記憶から「呼び出す」という作業によって成立していることを中心にすえたいと考えている。
2015.07.09
閲覧総数 306
-
4

私の最終的な目的は、西洋哲学を滅ぼす事。。。
私は哲学を将来的に滅ぼす事を目的として言語学をやっている。西洋哲学の形而上学というのは、英語では「Metaphysics」で、これを直訳すると「高次の物理学」となる。結局のところ、物理的な存在が宇宙の大元にあるという思想の下に生まれた学問であるのだが、私は、これに異論を唱える。私が提唱する「進化する自己記憶の存在論」では、そもそも物理現象というのは、自己記憶の蓄積によって生じる混沌から離散化が起きて誕生したものである。つまり、宇宙を満たすことで支える物質というのは、自己記憶の進化の第一段階によって誕生したのである。
2025.11.22
閲覧総数 16
-
5

自動書記?。。。
ブログの記事を書くときは、まず何か気になったことや、インスピレーションを受けた出来事があって、それをああでもない、こうでもないとやっているうちに出来る。詰まったときは、直ぐに他の事をする。頭がちょっと空っぽになったところで、再び読み返すと、またさらさらと文章が出てくる。最初に考えたことと、全く違う結論になったり、全然違うことに話題が移ってしまってタイトルを変更することもしばしば。自分でも、思いつきで書いているのだなと感心することがある。以前、何かをノートに書き始めると、ほとんど何も考えずにペンがすらすらと文章を綴っていくことがあった。言葉が次々と頭の中に浮かんできて、それを書き留めるのに必死なくらいだった。でも、それが続く限界は大体10ページ。ガス欠みたいになって筆が止まる。一度書いたノートは一応とってはあるが、かなり前のものを紐解くことはほとんどない。読み返してもちんぷんかんぷんなことも多いのであまり意味がない。私は、一種の「自動書記装置」なのだと感じることがある。多分、この運命は既に小さい頃には決まっていたのだと思う。いい答えを得るには、いい質問をしなければいけないというのは、今までずっと独学でやってきて出た結論だが、今から思うと、私は小さい頃から疑ってばかりいた気がする。博士論文の担当教官には「奇抜なことばかり(farfelu)」と言われていたが、私の疑問や好奇心は、そんなことで消えるようなものではなかった。今はとにかくインスピレーションが枯れるまで続けたい、それだけである。
2015.05.06
閲覧総数 114
-
6

シーニュと単語
以前から気づいていたのだが、ソシュールのシーニュ理論の最大の誤解は、これが「単語」の理論と思われている事だと思う。つまり「形態論(モーフォロジー」や「統語論(シンタックス)」に発展するすることはないのだ。シーニュというのは、人間の認識単位の二極化によって生じた言語の最小単位である。この単位の持つ「離散性」が、複数のシーニュの結合を可能にする。これは単なる結合ではない、1+1+ ... n =1なのである。異なるシニフィエを持った複数のシーニュが,結合する事により,1つのコンテクストを生み出す。言語の分析によくみられる「ツリー構造」は、これを既に出来上がったコンテクストの分析をする場合に出てくる。つまり、シーニュからのコンテクストの発生とは,全く逆の視点からの分析である。ソシュール(本人が書いたのではないが)の「一般言語学講義」の中にも、直接的ではないが、シーニュの結合によるコンテクストの発生のことは書いてある。1つの単語の中の「アソシエーション」がそれに当たる。今手元にないので、覚えているままに書くが、フランス語で danger が dangereux になるように(意味:「危険」と「危険な」)場合である。接尾辞が変わる事によって、意味に変化が起きる,いわゆる派生の事である。しかし、これも、あくまでも単語レベルであって(それでも形態論の領域には入るのだが)、統語論までは踏み込んでいない。シーニュの結合と言う視点からの統語論が、将来どういうものになるかは、今の段階では何ともいえないが、現在の統語論が、文法中心の言語学の「伝統」の上に成立しているのに対して,かなり違ったものになるはずである。チョムスキーの普遍文法では、言語にどんな統語法則があるかを確立する事によって、言語の本質を理解しようとしているようだが,実は彼が探しているものは既にシーニュ理論の中にあるのである。特定の言語の、統語法則という形ではなく、もっと本質的な、シーニュ同士の結合のメカニズムがそれに当たる。シーニュ理論を、きちんと理解していれば,普遍文法などと言うものを「追い求める」必要はなかったのである。チョムスキーは、シーニュを使わない。伝統的な文法の「単語」が出発点になっている。シーニュを使っている人達も(少なくとも、大学の講義の言語理論の部分で)、結局は「シーニュ」を「単語」に置き換えてしまっている。シーニュの本質が分かっていれば、こういう短絡的な発想は不可能であるが、分かった様なふりをしてきた言語学者達によって、ソシュールのシーニュ理論は、変質させられてしまったのである。セミオロジーに関しては、もしソシュール本人が本気で手話を研究していたら、セミオロジーが、音声言語と手話の2つだけしか該当しないことが分かったかもしれない。しかし、音声言語のみを言語と定義したことにより、逆にそれ以外の、言語に似たシステムが全てセミオロジーの対象になってしまった。この誤解は今後、解いていかないと行けないだろう。そう簡単にいくとは思わないが。
2009.08.17
閲覧総数 10
-
7

記憶は神なのだろうか。。。
記憶と時間の関係について今考えている。記憶というのは時間を紡ぐ循環サイクルである。それは正しく生きている。これに対して時間というのは、記憶の辿る軌跡であり、それは一つの記録でしかない。記憶と時間の関係を考える時、やはり空間も範疇に入ってくる。記憶は神なのだろうか。
2021.07.10
閲覧総数 95
-
8

量子力学の「波動関数の収縮」。。。
英語で数学&物理:波動関数の視覚化量子力学の「波動関数の収縮」について、考え始めている。私が提唱する「離散分裂(再)融合更新循環サイクル」とシンクロする可能性があるからで、この考察は、離散化のベースとなる混沌が波動によって成立していると気が付いた事から始まった。正しい疑問は、正しい答えを絶対に導いてくれる。「波動関数の視覚化」という日本語字幕付きの英語の動画を視ているのだが、時空間の軸が存在する所から説明が始まっているのが気になる。量子力学では、原子を「より小さな離散的な量」に分解する事から始まるが、この「離散的な量」が、どう生まれるかを私は知りたい。
2024.04.27
閲覧総数 19
-
9

言語学の大きな誤りの一つは、言語を「コミュニケーションの道具」であると定義した事。。。
言語学の大きな誤りの一つは、言語を「コミュニケーションの道具」であると定義した事だと思う。これにより、言語の持っている本来の機能である創造性が、単に、文脈と言う意味のバリエーションを生み出す事に制限されてしまった。私の提唱する「進化する自己記憶の存在論」では、知能を発揮する為の認知システムを構築している認知的な記憶の蓄積が生み出す混沌から離散化によって進化が起き、そこから、知能をベースにしていながら創造性を生む言語が誕生する。人類は言語のお陰で文明を築くことが出来るようになった。つまり、言語学者は、「言語はコミュニケーションの道具である」と予め定義した事で、言語の本質を、最初から、とんでもなく誤解して研究を始めたという事になる。最初の問題設定から間違っていたなんて、きっと誰も思わないだろう。では、何故私は、この言語学のボタンの掛け違いから脱する事ができたのだろうか。単純な答えは、私がソシュールの残した「言語には、正の項が無く、差異しか無い」というニュートラルな命題から研究をスタートした事だと思う。私にとって、これこそが言語学的な真実であって、それ以外のものを疑ってかかった。この「言語には、正の項が無く、差異しか無い」と言う命題には、何ら主観的な視点が入り込む余地が無い。後になって認識した事であるが、これは言語学的な価値を定義した命題である。価値の善し悪しではなくて、価値自体がどの様にして構築されるのかに焦点を当てるのである。
2025.11.22
閲覧総数 13
-
10

野矢 茂樹著「言語哲学がはじまる (岩波新書 新赤版 1991)」が届いた。。。
野矢 茂樹著「言語哲学がはじまる (岩波新書 新赤版 1991)」が実家に届いていた。丁度「哲学が言語学を骨抜きにした」と投稿したばかりで、非常にタイムリーである。野矢先生は哲学者なので、その観点から言語を見ている。そして、当然の様にソシュールが登場しない。この本の主役は、フレーゲ、ラッセル、ヴィトゲンシュタインという西洋の三人の哲学者である。「はじめに」を読むと、言語哲学と言語学の間には明確な役割分担があり、言語学が文法を扱うのに対して、哲学こそが「言語とは、何なんだ」という問いに答える事ができると主張しているようである。ここに面白い事が書かれている。それが「二十世紀の哲学を特徴づける言葉としての言語論的転回」で、「哲学の諸問題は言語を巡る問題として捉え直されるべきだとして、言語こそが哲学の主戦場だと見定まれたのです」とある。哲学が最初に棚上げにした言語という問題に、改めて取り組むという事である。この本では「言語とは何か」という大風呂敷を広げるのではなく「ミケは猫だ」というシンプルな文にこそ「言語とは何か」という大問題が絞り込まれていくとしている。残念ながら野矢先生も、ソシュールの一般言語学の記号の恣意性を誤解なさっている。記号の構造にこそ、言語とは何かの答えがある。「言語哲学がはじまる」の冒頭から、大きな問題がある。 それは、言語の考察をする前に、意味を所与としている事。 ただ、意味を「個別な猫と猫一般」という二つのカテゴリーに分けるというアプローチ自体は、確かに的を得ている。 本の目次にざっと目を通してみたが、問題設定は面白いと思う。私は西洋哲学を毛嫌いしているので、様々な著作をまともに読んだ事がない。この本は、そう言う哲学に無知な私には、丁度良いかもしれない。
2025.11.22
閲覧総数 6
-
11

音素神話という怪物。。。
「音が声に変わる瞬間」と言う表現を使ったが、これを記号学的に言うと「音声言語の音韻体系を構築する事」になる。日本語のオノマトペ特徴として、擬声語に加えて擬態語が多いと言う事。日本語の音韻体系は、聴覚で捉える音を、音素に分節するのではなく、そのまま声として変換する。「ゆる言語学ラジオ」の動画で紹介された「言語の本質ー言葉はどう生まれ、進化したか」を日本から注文した。本の目次や動画から察すると、オノマトペを研究対象としているのがわかるが、オノマトペが成立する為には、その音声言語の音韻体系が確立している必要があるという視点はなさそうである。もう一つ「ゆる言語学ラジオ」で紹介されていた「動物言語学者」の方の動画を見た時も、同じことを感じた。シジュウカラの鳴き声を、例えば「ピーツイ」と記述した途端に、その「音」は日本語の音韻体系に変換されていると思うのだが、日本語の音韻体系の役割に関しては全く触れていない。我々が「音」として認識しているものは、物理的な空気の振動が聴覚を通して創り出される「クオリア」であるが、人間が認識している発話を構成する形としての音声は、クオリアとしての音とは違った次元を持っている。只、「音としてのクオリア」がどうやって生まれるのかに関しては分かっていない。今でこそ私もクオリアという単語を使うようになったが、以前は「認知的な記憶」と呼んでいた。クオリアというのは物理化学的な自然界には存在しない。それは、生物認知的な時空間が生まれた時に同時に誕生したものである。更に「声」というのは、更にその上の段階の言語的な時空間に展開する。言語学では一般的に、先ず「音」が存在することが前提になっており、さらに「音素に分節可能な音声」も同様である。いや違う。先ず「人間が言語として認識する音声」があって、そのベースとして「音」が存在するはずなのに、そんな事など誰も気に留めていないというのが正しい見方だろう。この論理を進めて行くと、音素というのは物質の元素が存在する様に自然界に存在するという極論に達するのだが、誰もこれが極論であると気が付いてはおらず、音素は自然界に存在するという前提で言語学という学問が行われている。物理的な空気の振動が、聴覚クオリアとなり、更に音声に変換される。物理的な空気の振動を語る前には、時空間を持つ宇宙の誕生から始めなければならないのだが、それはここでは触れない。聴覚に特化した音声言語を考えるとき、空気の振動が聴覚クオリアになり、更にそれが音素で構成された音声に変換されるという、少なくとも二重の変換プロセスの通過を必要とする。の言語学では、音声/音素が誕生する為の、この二重の変換プロセスについては全く触れることがないし、そういう発想さえ皆無である。私はこれを「音素神話」と呼ぶ。この神話を確固たるものとしたのが、皮肉な事に、ソシュールの「記号の恣意性」であると私は考えている。もが持っていた音素に関する漠然とした知識を、ソシュールが使った美しい「記号の恣意性」という表現により、これこそが言語の本質であると大多数の人間が誤解してしまったのだと私は考えている。この場合の記号のシニフィアンは、既に数も種類も識別された音素で構成されている。
2023.12.07
閲覧総数 187
-
12

哲学に骨抜きにされた、西洋の言語学。。。
今、西洋で、言語学という学問が誕生した経緯に関する考察をしている。西洋哲学は、その起源において、言語のメカニズムの理解を棚上げした事で存在理由を獲得した。簡単に言うと、哲学者は、言語を使った屁理屈で世界の理を説明しようとしたのであり、それが長い年月をかけて西洋の伝統となった。この「悪しき伝統」の中でも、西洋人は、やはり言語に関しても、自ら哲学しようとする欲求を抑えられずに、言語学という学問分野を生み出したのだと思う。只、歴史的には、言語学が登場する前に、西洋では既に文法学が確立されており、その延長線上として言語学が誕生する事になる。西洋で生まれた言語学は、この時点で、西洋哲学を補足する存在としての地位を無理強いされた可能性がある。つまり、言語自体が持っている論理を、全て哲学に持っていかれて、残ったのが「コミュニケーションの道具」なのである。ソシュールの一般言語学を完成させる事が、同時に、哲学を滅ぼす事になると言う理由が、今、明確に理解出来た。自分が、哲学を毛嫌いしている理由が、やっと理解出来た。少々乱暴な表現であるが、西洋において言語学は、哲学の伝統によって骨抜きにされてしまったのである。本来なら、言語というのは、人間の自己意識を進化させるための道具であるのだが、何処で、何を間違えたか、単なるコミュニケーションの道具に成り下がってしまった。正に、悲劇である。
2025.11.22
閲覧総数 11
-
13

過去の自分が感じる「今」と現在の自分が感じる「今」を繋げる。。。
過去の自分が感じる「今」と現在の自分が感じる「今」を繋げ、更に、これらの二つの「今」を融合し、「今」を更新する事で、新しい「今」を生成し続けるという循環ループによって我々は自意識を保っているのだが、酔っぱらった時、自分が「今」何をしているのか、分からない経験をした人はいると思う。「心頭滅却すれば火もまた涼し」というのは、過去の今と現在の今を、どう扱うかによって実現できるのかもしれない。我々の心、つまり自己意識の維持は「離散分裂(再)融合更新循環ループ」によって行われ、これが我々の「今」を、常に更新しながら持続させている。睡眠に入る、或いは意識が無くなるというのは、この更新循環ループが途切れるという事で、例え意識があっても、身体の制御が出来なければ死と同じ。
2025.11.22
閲覧総数 11
-
14

「言語とは何か」という問いから「言語学とは何か」という問いに。。。
今、私の関心は「言語とは何か」という問いから「言語学とは何か」という問いに移ってきている。これは、ソシュールの一般言語学の記号の正しい理解が出来た事により、新しい段階として人間の知の再編成をする事になったと考えている。こう考えるとソシュールの評価も大きく変わってくる事になる。言語学者ソシュールの偉大な所は、意味という問題に真っ向から取り組んだ事だと私は考えている。ソシュールの記号には、シニフィアン(signifiant)とシニフィエ(signifié)という二つの側面があるが、この二つの用語は、仏語の「signifier(意味する)」という動詞が、其々、現在分詞と過去分詞に活用したものである。記号の意味の側面であるシニフィエというのは、一般的な概念に該当するのだが、これに対する個別の文脈に関しては、ソシュールは沈黙してしまった。そこに目を付けたのが、文法学者チョムスキーである。彼は、生成文法を掲げ、普遍文法の存在をちらつかせながら、言語学界に颯爽と登場した。「ソシュールの一般言語学講義」という本は、本人が著したものではなく、講義を受講していない二人の弟子によって、師の没後、講義メモや講義ノートを基に編纂されたものである。ソシュールは晩年、アナグラム研究に身を投じたとされているが、彼は、自分の研究の限界を感じていた可能性がある。言語学者ソシュールが、西洋の思想界に大きな影響を与えたのは事実であるが、彼の評価は、彼の一般言語学理論の間違った解釈の上に成り立っていると私は考えている。その誤解の最たる例が、記号の恣意性である。これは、音声言語には概ね該当するのだが、視覚的な手話には全く当てはまらない。現在の言語学の問題の一つは、音声言語と手話という二つの自然言語を全く平等に扱う事の出来る言語理論を構築する事なく、聴覚発声チャンネルに特化した音声言語の観察によって得られた特徴を、視覚身振りチャンネルの手話に強引に当てはめてしまっている事に、疑問を持つ人が非常に少ない事である。「ソシュールの一般言語学講義」には、実は、もう一つの記号の恣意性がある。それが「記号のラディカル(根本的)な恣意性」である。これに最初に注目したのは、フランス手話言語学を牽引してきた Cuxac 先生である。先生の授業でこれを知った時、本当にワクワクしたのを覚えている。この「ソシュールの記号のラディカルな恣意性」というのは、二つのタイプの自然言語である音声言語と手話の両方に当てはまる概念であるが、この為には、先ず、記号の定義からやり直す必要がある。私のソシュールの記号の定義:記号の形の側面に対応するシニフィアンと記号の意味の側面に対応するシニフィエという其々独立した二層の価値体系であり、其々の価値体系の特定の座標同士が一致する所に特定の記号が成立する。また、記号の意味の側面であるシニフィエは、一般的な概念に該当する。私の提唱する記号の新しい定義とソシュールの記号のラディカルな恣意性が、どのようにシンクロするかであるが、二層の其々の価値体系の特定の座標が一致する所に特定の記号が成立するのだが、この場合の、シニフィアンとシニフィエの間の関係がラディカルに恣意的であるという事になる。記号のシニフィエが価値体系であると言うのは、割と理解が楽だと思う。例えば、辞書で「左」と「右」の二つの概念を記述する為には、左は、右の反対、また、右は、左の反対という方法が取られるのだが、これこそ、二つの概念が、二つの相反する価値であるという事を示しているのである。では、記号の形の側面であるシニフィアンに関しては、どうだろう。この場合、記号がどの知覚運動チャンネルに特化したかで大きく変わってくる。シニフィエに関しては、音声言語と手話と言う二つのタイプの自然言語の間でも、概念の成り立ちに関して大きな違いがないのと比べて、差が顕著である。ソシュールの記号とは、其々独立した二層の価値体系あると既に述べたが、この記号が二つの異なる知覚運動チャンネルに特化する事で、視覚身振りチャンネルの場合は手話、聴覚発声チャンネルの場合は音声言語という、記号を共通要素とした二つのタイプの自然言語が確立する事になる。まだ、完璧とは言えないが、今までずっと私が目的としてきた「手話と音声言語に共通する何か」を、ようやく解明する事が出来た。結局の所、それは、ソシュールの記号であったのだが、一般的な解釈の記号ではなく、ソシュールの記号の再解釈を反映させた新しい定義の記号になった。記号が特化する知覚運動チャンネルの特徴によって実現される記号の形の側面であるシニフィアンに関する考察に戻ろう。先ずは、聴覚発声チャンネルに特化して誕生した音声言語のシニフィアンであるが、これには、所謂、音韻体系が該当するのだが、現行の音素の記述方法は、現実的に全く使えない。現行の音韻体系では、音素の二大カテゴリーである子音と母音の存在がデフォルトであり、音韻体系における記述は子音と母音が全く別々の表という形で行われているのだが、ここに問題がある。子音と母音が確立する為には、音声の連続的な塊である音節の時間軸上の前後への離散化が不可欠なのであり、この連続的な音節を構成する聴覚的な認知記憶が、どのようなメカニズムを通して、時間軸上で前後に離散的に分裂して、子音と母音という子音の二つのカテゴリーが構築されるのかを解明する必要がある。音声を支える聴覚記憶というのは、認知システム上では、一次元である時間軸上に展開するのだが、まず、音節という形で連鎖的に分節されたものが、其々前後に離散的に分裂する事で、時間軸上の上に垂直に展開する一種の空間軸が生じる事になる結果、特定の音声言語の音韻体系が確立される事になる。これに対して、記号が視覚身振りチャンネルに特化して確立される手話の場合、音節の離散化によって確立される空間軸が、最初から視界の中に存在するという利点がある。後は、視覚的に連続的に流れるシーケンスが離散的に分裂される事で、離散的な時間軸が獲得されるようになるのである。
2025.11.23
閲覧総数 4
-
15

「言語には、正の項が無く、差異しか無い」という中立的な視点。。。
私は「ソシュールの一般言語学講義」という本の中にある「言語には、正の項が無く、差異しか無い」という命題を出発点にして、30年間ずっと言語に関する考察を続けてきたのだが、この非常に中立的な視点を基本とする事で、自分でも予想しなかった結論に達する事になった事に非常に驚いている。言語に関する考察をする学問は、実は二種類ある。それは言語学と哲学なのだが、この二つの間には奇妙な棲み分けが為されている。哲学は言語を使って記述をするという方法論であるにも拘わらず、言語のメカニズムの解明を封印した状態で出発する事になったのだが、これが現在迄、尾を引いている。西洋に於いて、哲学という学問は、その誕生から継続的に、重要な思考ツールとして機能しており、近代的な科学分野とも密接な関係を築いている。これに対して言語学というのは、言語を思考ツールとして捉える視点はなく、言語によって文脈をどのように構築するかの文法規則の記述に専念してきた。西洋における文法記述を中心とした言語学の伝統に、一石を投じたのが「ソシュールの一般言語学講義」という本であった。実際、この本には、文法的な記述は皆無である。その代わり、「言語学的な価値」という章に「記号のラディカルな恣意性」という、言語の本質に迫る記述がある。ところが、この本は、ソシュールの没後、二人の弟子によって編纂された事もあり、欠席裁判の様相を呈している。ソシュールの一般言語学講義に関する最大の誤解は「記号の恣意性」の解釈にある。これには、音声言語のみを研究対象としてきた言語学の伝統による偏見が反映されてしまっている。
2025.11.23
閲覧総数 4
-
-

- みんなのレビュー
- 飲んでみた☕ 1杯/16円以下 アバン…
- (2025-11-24 10:48:49)
-
-
-

- ニュース
- きざはし個展・最終週!
- (2025-11-24 10:21:18)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 乾燥しにくいクリーンな暖房**部屋の…
- (2025-11-24 08:30:03)
-