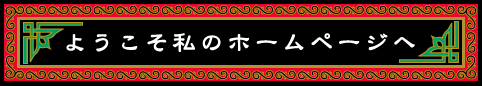フリーページ
テーマ: 中国&台湾(3328)
カテゴリ: カテゴリ未分類
3.3 日本産果物の対中輸出の機会
3.3.1 中国経済の高成長と富裕層の出現
1978年から実施された改革開放の政策により、中国の経済は目覚しい発展を成し遂げた。2003年史上初めて1人当たりGDPが1000ドルを超えた。2004年中国のGDPは13兆6515億元で、前年比9.5%の成長を遂げ、イタリアを抜いて世界第6位にランクされている。特に2001年11月10日にWTO閣僚会議で中国のWTO加盟が正式承認され、以後、徐々に中国もグローバリズムの中での競争に晒されてきた。
表3.2 中国の国内総生産額と成長率の推移(略)
中国では最も経済成長が進んでいる地域が三つある。一つは香港と隣接している広東省の珠江デルタ地域、二つ目は上海と上海市の周辺地域、つまり長江デルタ地域、三つ目は渤海湾地域、つまり北京、天津、青島、大連の四つの都市とその周辺地域である。2003年時点で人口100万人以上、1人当りGDP3,000ドルを超える大都会は24あり、そのうち21はこの三大成長エリアに集中している。この三大成長エリアが最も豊かな地域で、巨大市場そのものである。この三つの地域の総人口は約3億人にのぼる。
中国国家統計局によると、2004年の長江デルタ地域の一人当たりGDPは3万5147元に達し、現在の為替レートで換算すると4247米ドルになった。世界銀行の発展報告によると、一人当たりGDP3000米ドル前後は近代化の境界とされている。統計専門家は、長江デルタ地域は中進国水準に達したと考えている。統計によると、2004年、長江デルタ地域のGDPは2万8775億元で、全国シェアは前年の20.4%から21.1%に上昇した。長江デルタ経済の成長平均は15.6%に達し、全国平均水準より6.1ポイント上回っている。長江デルタは既に全国経済成長の重要貢献地域となっている。長江デルタ地域は、上海、江蘇省の8市、浙江省の7市から成る。2004年、上海のGDPは7000億元を突破し、蘇州、杭州、無錫、寧波のGDPは2000億元を超え、南京のGDPは2000億元に近づいている。上海では年収10万元以上の富裕層が、既に100万人を超えた。北京では、100万元以上の家庭財産を持っている人も100万人を超えた。
2004年の中国人の海外旅行者は、前年比40%増で2850万人と爆発的に増えている。中国の新車販売台数であるが、2004年は439万台で前年に比べ114万台増加した。この114万台の増加は世界でも例のない数字である。ドイツのBMW最高級車がドイツ以外で最も売れているのが中国であり、その背景にも富裕層の存在がある。全国で何千万人の富裕層の出現は、ビジネスの観点からは非常に大きな意味をもっている。大きな潜在能力があり、新たな可能性が広がっている。
3.3.2 中国の消費者の健康・環境意識の高まり
消費者の健康・環境意識の高まりの中で、より環境や安全性に配慮した果物の生産・供給が求められている。
食品の品質と安全について、「非常に重視」が40.3%、「比較的重視」が35.4%、合計で75.7%の人が「重視する」と回答しており、関心は相当に高かった。市場で販売されている食品を安全だと思うかについて、「とても安心」が23.3%、「比較的安心」が21.3%、合計で44.6%が「安心している」と回答し、「普通」の31.6%と合わせると76.2%の人が市場での買物にそれほど抵抗を感じていないという結果が出た。一方、「少し不安」が21.3%、「とても不安」が2.5%、合計で23.8%の人が「不安」を感じていた。食品を購入するときに最も関心があることは、1位が品質で42.4%。2位が新鮮さと安全でともに36.5%であった。それから価格が25.4%、信頼できる生産者かどうかが11.2%と続いている。どうすれば安全な食品を購入できるかについては、1位が正規店で購入することで31.4%、2位が知名度のある食品を買うことで23.8%、3位がよく見て慎重に選ぶことで17.9%、4位が天然で栽培・成長した食材を選ぶことが14.3%となっている。このほかに国家の検査・認証の有無を基準にする人が5.4%、知人からの推薦が4.3%であった。
こうした調査結果から見ると、消費者は食の安全に対して強い関心をもっているため、買い物をする際にはできるだけ安心できる生産者及び正規の流通ルートをもつ販売者を選んでいることが分かる。生産の面では、同じ食品品目において数多くの銘柄が激しい競争を繰り広げているが、知られていない銘柄よりも知名度がある方を安全だと考えている。また、販売の面ではデパートやスーパーは確かに食品の品揃えがよいし、果物や野菜などもトレイに載せ、パック包装を施しているので、見た目に美しく、新鮮さがアピールされている。品質検査も定期的に行われ、売り場には検査済の標示が置いてあり、衛生的で安全であるという印象を与えるのに効果的である。注目したいのは、比率は低いが、安全な食品を購入するために国家の検査・認証を基準にしている消費者がいることである。これは農業部や国家環境保護総局などの行政が取り組んできた食品認証制度が生活の中に浸透してきたことを意味している。生産者である農場や企業が「有機食品」「緑色食品」「無公害農産品」という各種認証を受けるものだが、生産プロセスで使用する農薬、肥料、飼料添加剤、食品添加剤、栽培技術などに関する数々の条件をクリアして初めて認められるものである。
この調査の結果から見ると、日本産果物は中国大都市の消費者のほぼすべての関心や要求を満たすことができる。
3.3.3 WTO加盟とFTA(自由貿易協定)
2001年11月に中国はWTOに加盟して、関税が大幅に下がってきた。2000年、中国の農産物輸入関税率は平均21.3%であったが、中国政府は、2004年1月1日から、中国の農産物関税を17.5%に引き下げ、2005年には15.6%に引き下げた。果物の関税率はもっと低く、2004 年までにかんきつ類の関税率を 11~12%まで、バナナの関税率を 10%まで、ブドウの関税を 13%まで、干ブドウの関税を 10%まで、リンゴ、ナシ、サクランボなどの主要な温帯果物の関税率を 10~12%まで下げた。さらに、中国政府は2010までに農産物の関税率を8.9%まで引き下げることを約束している。その上、WTOの規定によれば、WTO加盟後、中国は農産物の輸入量を制限することができない。
また、お互いに対外経済関係に占める重要な位置にかんがみ、中日間の経済相互依存関係を展望するプロセスの中で、経済連携強化の方途について自由貿易協定(FTA)と経済連携協定(EPA)の可能性も排除することなく検討していくと思われる。
3.3.4 人民元の為替制度改革
中国の通貨・人民元の為替レートは、国家管理の外国為替市場で決まり、1ドル=8.277元前後でほぼ固定している。中国政府が外貨交換を厳しく管理しているためで、日米欧のように金融機関が値動きを見て売り買いするようなことは、中国ではできない。輸出入などに伴い、ドルの売買が必要になるときだけ許される。中国は輸出超過で、外資の進出も多く、国内でドルが余っている。中国政府はレートの変動幅を前日の平均値から上下0.3%以内と決めており、中国人民銀行がドル買いをすることで、実質的な固定相場を維持している。高成長を続けた中国の経済実力からすれば、2~4割は割安との見方が強い。
しかし一方で、中国側からすれば、これは世界の人民元に対する過剰評価であり、この切り上げ要求に応じられない内部事情を抱えている。高度成長を支える輸出産業へのダメージ、不良債権問題などの脆弱な金融システム、深刻な失業率、農村経済の貧弱さなど、人民元の切り上げはこれら爆弾の導火線に火をつけるほどの危険性もはらんでいる。だから、中国はできるだけ切り上げ実施の引き伸ばしにかかると予測される中、各国の微妙な駆け引きは続くだろう。
しかし、人民元の切り上がりがタイミングの問題でしかないという考えは広がっている。長い目で見れば、元高円安が日本産果物の対中輸出を大きく推進していく。
3.3.1 中国経済の高成長と富裕層の出現
1978年から実施された改革開放の政策により、中国の経済は目覚しい発展を成し遂げた。2003年史上初めて1人当たりGDPが1000ドルを超えた。2004年中国のGDPは13兆6515億元で、前年比9.5%の成長を遂げ、イタリアを抜いて世界第6位にランクされている。特に2001年11月10日にWTO閣僚会議で中国のWTO加盟が正式承認され、以後、徐々に中国もグローバリズムの中での競争に晒されてきた。
表3.2 中国の国内総生産額と成長率の推移(略)
中国では最も経済成長が進んでいる地域が三つある。一つは香港と隣接している広東省の珠江デルタ地域、二つ目は上海と上海市の周辺地域、つまり長江デルタ地域、三つ目は渤海湾地域、つまり北京、天津、青島、大連の四つの都市とその周辺地域である。2003年時点で人口100万人以上、1人当りGDP3,000ドルを超える大都会は24あり、そのうち21はこの三大成長エリアに集中している。この三大成長エリアが最も豊かな地域で、巨大市場そのものである。この三つの地域の総人口は約3億人にのぼる。
中国国家統計局によると、2004年の長江デルタ地域の一人当たりGDPは3万5147元に達し、現在の為替レートで換算すると4247米ドルになった。世界銀行の発展報告によると、一人当たりGDP3000米ドル前後は近代化の境界とされている。統計専門家は、長江デルタ地域は中進国水準に達したと考えている。統計によると、2004年、長江デルタ地域のGDPは2万8775億元で、全国シェアは前年の20.4%から21.1%に上昇した。長江デルタ経済の成長平均は15.6%に達し、全国平均水準より6.1ポイント上回っている。長江デルタは既に全国経済成長の重要貢献地域となっている。長江デルタ地域は、上海、江蘇省の8市、浙江省の7市から成る。2004年、上海のGDPは7000億元を突破し、蘇州、杭州、無錫、寧波のGDPは2000億元を超え、南京のGDPは2000億元に近づいている。上海では年収10万元以上の富裕層が、既に100万人を超えた。北京では、100万元以上の家庭財産を持っている人も100万人を超えた。
2004年の中国人の海外旅行者は、前年比40%増で2850万人と爆発的に増えている。中国の新車販売台数であるが、2004年は439万台で前年に比べ114万台増加した。この114万台の増加は世界でも例のない数字である。ドイツのBMW最高級車がドイツ以外で最も売れているのが中国であり、その背景にも富裕層の存在がある。全国で何千万人の富裕層の出現は、ビジネスの観点からは非常に大きな意味をもっている。大きな潜在能力があり、新たな可能性が広がっている。
3.3.2 中国の消費者の健康・環境意識の高まり
消費者の健康・環境意識の高まりの中で、より環境や安全性に配慮した果物の生産・供給が求められている。
食品の品質と安全について、「非常に重視」が40.3%、「比較的重視」が35.4%、合計で75.7%の人が「重視する」と回答しており、関心は相当に高かった。市場で販売されている食品を安全だと思うかについて、「とても安心」が23.3%、「比較的安心」が21.3%、合計で44.6%が「安心している」と回答し、「普通」の31.6%と合わせると76.2%の人が市場での買物にそれほど抵抗を感じていないという結果が出た。一方、「少し不安」が21.3%、「とても不安」が2.5%、合計で23.8%の人が「不安」を感じていた。食品を購入するときに最も関心があることは、1位が品質で42.4%。2位が新鮮さと安全でともに36.5%であった。それから価格が25.4%、信頼できる生産者かどうかが11.2%と続いている。どうすれば安全な食品を購入できるかについては、1位が正規店で購入することで31.4%、2位が知名度のある食品を買うことで23.8%、3位がよく見て慎重に選ぶことで17.9%、4位が天然で栽培・成長した食材を選ぶことが14.3%となっている。このほかに国家の検査・認証の有無を基準にする人が5.4%、知人からの推薦が4.3%であった。
こうした調査結果から見ると、消費者は食の安全に対して強い関心をもっているため、買い物をする際にはできるだけ安心できる生産者及び正規の流通ルートをもつ販売者を選んでいることが分かる。生産の面では、同じ食品品目において数多くの銘柄が激しい競争を繰り広げているが、知られていない銘柄よりも知名度がある方を安全だと考えている。また、販売の面ではデパートやスーパーは確かに食品の品揃えがよいし、果物や野菜などもトレイに載せ、パック包装を施しているので、見た目に美しく、新鮮さがアピールされている。品質検査も定期的に行われ、売り場には検査済の標示が置いてあり、衛生的で安全であるという印象を与えるのに効果的である。注目したいのは、比率は低いが、安全な食品を購入するために国家の検査・認証を基準にしている消費者がいることである。これは農業部や国家環境保護総局などの行政が取り組んできた食品認証制度が生活の中に浸透してきたことを意味している。生産者である農場や企業が「有機食品」「緑色食品」「無公害農産品」という各種認証を受けるものだが、生産プロセスで使用する農薬、肥料、飼料添加剤、食品添加剤、栽培技術などに関する数々の条件をクリアして初めて認められるものである。
この調査の結果から見ると、日本産果物は中国大都市の消費者のほぼすべての関心や要求を満たすことができる。
3.3.3 WTO加盟とFTA(自由貿易協定)
2001年11月に中国はWTOに加盟して、関税が大幅に下がってきた。2000年、中国の農産物輸入関税率は平均21.3%であったが、中国政府は、2004年1月1日から、中国の農産物関税を17.5%に引き下げ、2005年には15.6%に引き下げた。果物の関税率はもっと低く、2004 年までにかんきつ類の関税率を 11~12%まで、バナナの関税率を 10%まで、ブドウの関税を 13%まで、干ブドウの関税を 10%まで、リンゴ、ナシ、サクランボなどの主要な温帯果物の関税率を 10~12%まで下げた。さらに、中国政府は2010までに農産物の関税率を8.9%まで引き下げることを約束している。その上、WTOの規定によれば、WTO加盟後、中国は農産物の輸入量を制限することができない。
また、お互いに対外経済関係に占める重要な位置にかんがみ、中日間の経済相互依存関係を展望するプロセスの中で、経済連携強化の方途について自由貿易協定(FTA)と経済連携協定(EPA)の可能性も排除することなく検討していくと思われる。
3.3.4 人民元の為替制度改革
中国の通貨・人民元の為替レートは、国家管理の外国為替市場で決まり、1ドル=8.277元前後でほぼ固定している。中国政府が外貨交換を厳しく管理しているためで、日米欧のように金融機関が値動きを見て売り買いするようなことは、中国ではできない。輸出入などに伴い、ドルの売買が必要になるときだけ許される。中国は輸出超過で、外資の進出も多く、国内でドルが余っている。中国政府はレートの変動幅を前日の平均値から上下0.3%以内と決めており、中国人民銀行がドル買いをすることで、実質的な固定相場を維持している。高成長を続けた中国の経済実力からすれば、2~4割は割安との見方が強い。
しかし一方で、中国側からすれば、これは世界の人民元に対する過剰評価であり、この切り上げ要求に応じられない内部事情を抱えている。高度成長を支える輸出産業へのダメージ、不良債権問題などの脆弱な金融システム、深刻な失業率、農村経済の貧弱さなど、人民元の切り上げはこれら爆弾の導火線に火をつけるほどの危険性もはらんでいる。だから、中国はできるだけ切り上げ実施の引き伸ばしにかかると予測される中、各国の微妙な駆け引きは続くだろう。
しかし、人民元の切り上がりがタイミングの問題でしかないという考えは広がっている。長い目で見れば、元高円安が日本産果物の対中輸出を大きく推進していく。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.