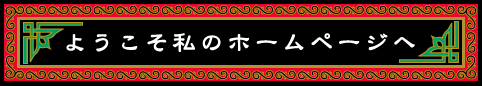フリーページ
テーマ: 中国&台湾(3328)
カテゴリ: カテゴリ未分類
3.2 日本産果物の対中輸出の弱み
日本産果物は大きなハンデを負っていると言わざるを得ない。
3.2.1 同種、同季節のため市場が重なっている
日本は中国と大体同じ緯度に位置して、日本の果樹種類は中国にも全部あるし(但し、品種が違うことがある)、果物の成熟期も大体同じなので、両国の果物市場はある程度重なっている。中国と違う緯度に位置する他の国家に比べて、これは日本産果物のハンディキャップである。
中国の経済発展と国際交流に従って、日本の新しい果樹品種と栽培技術もどんどん中国に導入され、日本産果物の品種優位がだんだん弱くなっていくと思われる。
3.2.2 高いコストと価格
日本は国土が急峻、狭隘であることや、地価、人件費、エネルギー価格が割高であること等を背景として、農産物の生産・流通コストが割高にならざるを得ない。
日本の果樹は中山間傾斜地での栽培が多く、特に温州みかんでは、約半数が15度以上の傾斜園地で栽培されている。また、りんご等の落葉果樹では相対的に平坦地が多いものの、地域によっては傾斜地も多く、園地の整備が遅れ、機械化・省力化が進みにくい状況にある。さらに、園地が小規模でしかも分散しており、経営規模の大きな農家ほど分散化の傾向は大きくなっている。例えば、栽培面積2ha以上の農家では6箇所以上に分散している割合が多くなって、園地整備が進めにくいことや作業効率が悪いことから経営の効率化・規模拡大が進まない原因の一つとなっている。
10a当たりの労働時間を見ると、水稲やキャベツ、ダイコン等の他作物が機械化や省力化技術の導入を通じて削減を図っている中で、果樹については依然として横這いないしは増加傾向にある。例えば温州みかんについては、昭和55年頃までは、防除や農道整備の促進と生産物の搬出の機械化等により労働時間の一定の減少が図られたが、その後は、園地整備や収穫作業等の機械化の遅れにより停滞する傾向がある。特に近年は、高品質化への取り組みの中で、摘果等結実管理に要する時間が増加し、これに伴って全体の労働時間もやや増加ないし横這い傾向にある。りんごについても、わい化栽培の導入等による栽培管理の省力化が図られる一方、着色管理等に要する作業時間が増加し、全体としては横ばいないし増加傾向にある。
図3.1 みかんの10a当たりの生産コストと投下労働時間の変化(略)
表3.1 みかん農家の栽培規模と所得の変化(略)
高いコストの一つの原因は生産構造にある。果樹の一戸当たり平均栽培面積は近年60a台で推移して、生産農家の規模拡大意欲が低いことから、農家数の減少にもかかわらず経営規模の拡大はなかなか進んでいない状況にある。この原因としては、省力化が立ち遅れていること、永年性作物であることから売買・賃貸借の契約に際して園地の評価が難しいこと、園地整備がなされていない園地では借り手のメリットが少ないこと等から園地の流動化が進みにくいことがあげられる。だから、大規模栽培農家層の生産シェアは徐々に拡大しているが、依然として小規模層の生産シェアが大きい。
だから、日本産果物の価格は高い。中国で日本産果物の販売価格は、関税も加わって日本国内より30%高、中国産の10倍になってしまう。上海では熊本県の「新高」梨の小売価格が1個88元(約1200円)である。
表3.2 日本四大市場国産果物卸売価格(1999年―2003年) (略)
日本産果物は大きなハンデを負っていると言わざるを得ない。
3.2.1 同種、同季節のため市場が重なっている
日本は中国と大体同じ緯度に位置して、日本の果樹種類は中国にも全部あるし(但し、品種が違うことがある)、果物の成熟期も大体同じなので、両国の果物市場はある程度重なっている。中国と違う緯度に位置する他の国家に比べて、これは日本産果物のハンディキャップである。
中国の経済発展と国際交流に従って、日本の新しい果樹品種と栽培技術もどんどん中国に導入され、日本産果物の品種優位がだんだん弱くなっていくと思われる。
3.2.2 高いコストと価格
日本は国土が急峻、狭隘であることや、地価、人件費、エネルギー価格が割高であること等を背景として、農産物の生産・流通コストが割高にならざるを得ない。
日本の果樹は中山間傾斜地での栽培が多く、特に温州みかんでは、約半数が15度以上の傾斜園地で栽培されている。また、りんご等の落葉果樹では相対的に平坦地が多いものの、地域によっては傾斜地も多く、園地の整備が遅れ、機械化・省力化が進みにくい状況にある。さらに、園地が小規模でしかも分散しており、経営規模の大きな農家ほど分散化の傾向は大きくなっている。例えば、栽培面積2ha以上の農家では6箇所以上に分散している割合が多くなって、園地整備が進めにくいことや作業効率が悪いことから経営の効率化・規模拡大が進まない原因の一つとなっている。
10a当たりの労働時間を見ると、水稲やキャベツ、ダイコン等の他作物が機械化や省力化技術の導入を通じて削減を図っている中で、果樹については依然として横這いないしは増加傾向にある。例えば温州みかんについては、昭和55年頃までは、防除や農道整備の促進と生産物の搬出の機械化等により労働時間の一定の減少が図られたが、その後は、園地整備や収穫作業等の機械化の遅れにより停滞する傾向がある。特に近年は、高品質化への取り組みの中で、摘果等結実管理に要する時間が増加し、これに伴って全体の労働時間もやや増加ないし横這い傾向にある。りんごについても、わい化栽培の導入等による栽培管理の省力化が図られる一方、着色管理等に要する作業時間が増加し、全体としては横ばいないし増加傾向にある。
図3.1 みかんの10a当たりの生産コストと投下労働時間の変化(略)
表3.1 みかん農家の栽培規模と所得の変化(略)
高いコストの一つの原因は生産構造にある。果樹の一戸当たり平均栽培面積は近年60a台で推移して、生産農家の規模拡大意欲が低いことから、農家数の減少にもかかわらず経営規模の拡大はなかなか進んでいない状況にある。この原因としては、省力化が立ち遅れていること、永年性作物であることから売買・賃貸借の契約に際して園地の評価が難しいこと、園地整備がなされていない園地では借り手のメリットが少ないこと等から園地の流動化が進みにくいことがあげられる。だから、大規模栽培農家層の生産シェアは徐々に拡大しているが、依然として小規模層の生産シェアが大きい。
だから、日本産果物の価格は高い。中国で日本産果物の販売価格は、関税も加わって日本国内より30%高、中国産の10倍になってしまう。上海では熊本県の「新高」梨の小売価格が1個88元(約1200円)である。
表3.2 日本四大市場国産果物卸売価格(1999年―2003年) (略)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.