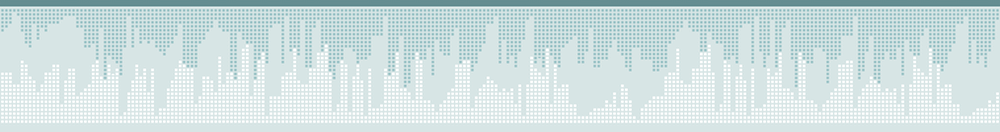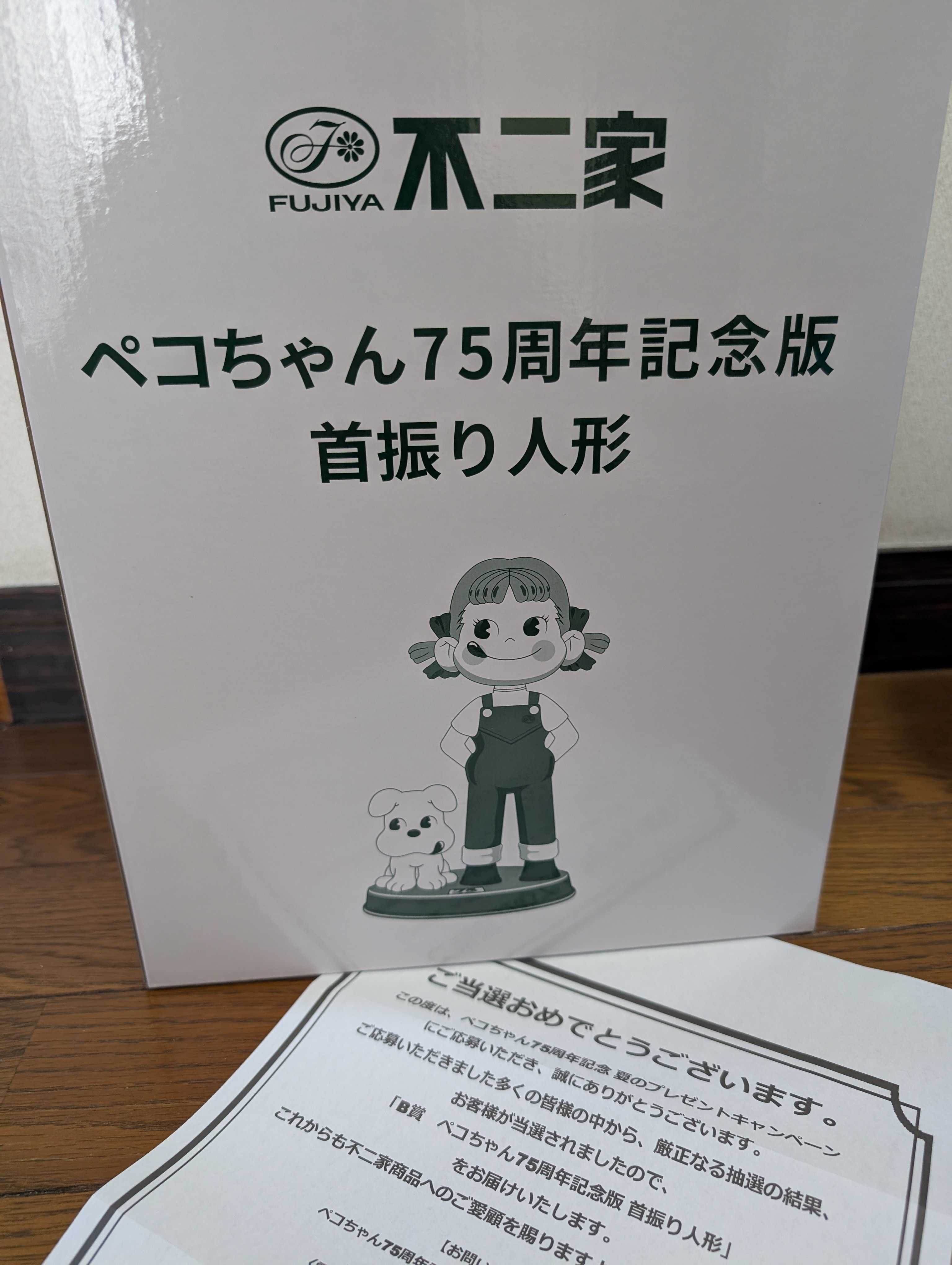全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
口腔癌と認知症
訪問診療の依頼がありました。患者さんは認知症の強い、85歳の男性です。一昨年の春に義歯の下の歯茎が痛むと言って来院されました。義歯が強く当たっているところが潰瘍になっていましたので義歯を削って調整しましたが潰瘍はなかなか小さくなりませんでした。2週間経っても潰瘍が消えませんでしたので、口腔癌の疑いで大学病院に紹介しました。結果、扁平上皮癌でしたが、高齢であることから、手術はせずに化学療法と放射線療法を受けて退院しました。その後大学病院で管理していただいているものとばかり思っていましたら、デイサービスに隣接する内科の主治医さんに見てもらっているということでした。今回も義歯の下の歯茎が痛むという主訴でした。訪問すると、大学病院で化学療法と放射線療法を受けた部分がニワトリの玉子ぐらいに大きくなって、義歯の床の部分が浮き上がっていました。本人も癌であることを知っていて、奥さんが私に何度も「癌があるからしゃあないけどなぁ・・・」と淡々と繰り返されます。本人も「そやそや」と・・・。以前、「呆けるということは神様からの贈り物だ」と何かの本で読んだことがあります。「十分呆けたら死ぬことが恐いと思わなくなる。」ということでした。ここ数年この言葉を思い出すことはなかったのですが、今日はふと、こんな考え方も良いのではないかと思いました。
2005.06.18
コメント(2)
-
遷延性意識障害のYさんが笑った!!
グループホームの寮母長Fが訪問衛生士をしていた頃(と言っても5年ほど前)のお話しです。脳腫瘍の後遺症で遷延性意識障害のYさんは経口摂取ができなくなり経鼻経管栄養となりました。介護者である妹のTさんから「鼻のチューブを外して、もう一度口から食べさせたい。」と相談を受けて私と歯科衛生士のFが訪問しました。Yさんは体幹保持ができず、20度程度のギャッヂアップがやっとの状態でした。そこで、ケアマネジャーのMさんに口腔の保清、座位時間の確保と頚部の筋力増強、口腔機能の改善を加えたケアプランの組み直しを依頼しました。すると、Mさんは早速Yさんの摂食機能改善のための口腔ケアチームを作ってくれました。ホームヘルパーはYさんをベッドから車椅子へ移乗させて30分後に車椅子からベッドへ戻し、毎日2回、午前と午後に座位時間を確保しました。作業療法士は80キロを超えるYさんの移乗のためにリフターを導入しホームヘルパーに操作方法を指導するとともに頚椎の可動域訓練と身体障害者給付事業を使ってオーダーメイドの車椅子を導入しました。訪問看護師は口腔清掃とアイスマッサージの方法を見学に来て、日頃の訪問時に実施しました。歯科衛生士のFはバンケード法による口輪筋刺激訓練とスポンジブラシによる口腔清掃、歯ブラシによる舌のマッサージ、嚥下反射を引き出すためのアイスマッサージと“綿棒に様々な味をつけたアイス棒”を利用した舌運動訓練を実施しました。2週間後追視がみられるようになり、咬反射は弱くなりました。3週間後、座位に慣れて、訪問時には車椅子に座ってテレビの相撲を見るようになりました。咽頭雑音がなくなり、開口を指示しながら衛生士が口を開けると一緒に口を開けてくれるようになり、タベラックを使って少量のミキサー食を経口摂取することができました。1ケ月後タベラックで十分ミキサー食を摂取することができるようになったので主治医にマーゲンチューブを外してもらいました。これで一応初期の目的を達成することができましたが、今度は、タベラックを使わずにスプーンで食べさせたいという妹のTさんの希望がでました。そこで車椅子にテーブルを付けることになりました。作業療法士が車椅子にベルト固定したテーブルにYさんの前腕をつけました。車椅子の背板からYさんの背中が離れましたが、前腕をつけたままテーブルに顔から突っ伏してしまいました。しかし、鼻がテーブルに付きそうになると上半身を徐々に上腕で支え直しました。こんな力がYさんにあったのがとても頼もしく思えたとき、今度は顔を上げてもの珍しそうにキョロキョロと部屋の中を見回しました。Fが「Yさん、今日はこの夏みかんを食べてみましょうか?」と大きな夏みかんをYさんに持たせました。自分の手にのった夏みかんをじっと見ていたYさんの親指の先がじわじわ動き出しました。まさに皮をむく動作でした。意外な成り行きに作業療法士と顔を見合わせました。私はYさんが自分でむいたようにこっそり手を出し、ひと房をYさんに持たせました。すると次ぎにYさんは右手の親指と人さし指で綿皮をつまんではがそうとしました。こんどは作業療法士がさっと綿皮をはがしました。せっかくYさんがむいたみかんを取り上げるのも申しわけないので、喉に詰らせないか多少心配はありましたが、Yさんが手を口に持っていこうとしていたのを手伝いました。やっと夏みかんの房を口に入れたYさんは、突然「ヒェヒェヒェヒェ」と笑い声を立てました。妹のTさんは驚きながら、「姉さんの笑い声を聞いたのは何年ぶりやろ・・・」と、目頭を押えておられました。(しかし、なんでこの時Fが夏みかんを持っていたのか、未だに聞いた事はありません。)
2005.06.11
コメント(1)
-
物盗られ妄想と歯科治療
強い物盗られ妄想のあるグループホームの利用者さんが歯科を受診されました。歯科衛生士のTちゃんはいつも丁寧な口腔ケアをしてくれます。今日も歯槽膿漏の処置と口腔ケアを終えて、「先生、虫歯の治療は終っています。次は義歯の型採りですね。」と型採りの用意をしています。私には思うところがあって、「F呼んできて・・・」とグループホームの寮母長を呼びに行ってもらいました。寮母長のFも元職は歯科衛生士です。私の在宅診療の相棒のひとりでした。私と組んで在宅を訪問していた頃は他の衛生士達に「どんくさい」「のろい」と言われ、本人もそう思っていました。しかし、彼女は戦場のような外来ではあまり(全くと言っていいほど)光りませんが、認知症や失語症・遷延性意識障害など重度のコミュニケーション障害の患者さんを前にすると周囲の空気がひとつにまとまるような、患者さんと同化してしまうような衛生士でした。そんな彼女は認知症介護では絶対に光ると思ったので、ショートステイを18床つくる予定でしたが、2階の9床はグループホームにしました。今でもFが音を上げて「自信がありません、もう辞めますから・・・」と言って来る度に「ええよ、辞めるのやったら2階のグループホーム切って持って行きや!!」と言うことにしています。訪問衛生士時代に比べると自信を付けて2倍も3倍も大きくなったFが診療室に来てくれました。「Tちゃんが、義歯作ったらって言うねんけど・・・F、どうする?」「義歯作ったら、枕の下に入ったり、盗まれたりする物が1つ増えますね。2歯欠損ですよね。無くても食べられますよね・・・」と、歯科医師と歯科衛生士の発言とは思えない会話となりました。私達の会話を聞いたTちゃんはキョトンとしています。もちろんTちゃんの考え方は正しいのですが・・・・・・。
2005.06.10
コメント(2)
-
やんちゃばあさん診療所でも暴れる。
昨日Hさんのエピソードを書いたらうちの施設長(私の旦那)が「ぼくにも書かせろ!!」と乱入してきました。しょがないなぁ、上手いこと書いてや!!******************やんちゃばあさんは、昨日1泊2日の予定で、自宅へ帰らはりました。朝、皆さんと一緒に食事してもらおうと、8時頃に起こすと、「ギエー」とか「コラーなにすんねん」とか大きな声が出ます。大きな声が出ないと大概熱発してはります。そうなると、体力の備蓄の少ないお年寄りの事、SPO2は下るわ、血圧は上がり下がりするわ。車椅子で、近所のお医者さんのところまで走ります。(ここのお医者さんにいつもお世話になっているので、よく把握してくださいます)待合室では、しなびた菜っ葉みたいになっているのですが、診察室で聴診しようと服を脱がせた途端、「なにすんねん、男が触らんといて」と大きな声。先生も看護師さんもワーカーも、つねられ、蹴られて、大騒ぎ。「これだけ大きな声が出て、動ければ大丈夫です」と、先生も、看護師さんもニコニコ。良い先生が近くにおられて、ありがたい事です。
2005.06.08
コメント(3)
-
やんちゃばあちゃんショートステイに帰る!!
Hさんはショートステイの常連というより居続け利用者。入院中の調査で要介護5・認定期間延長24ケ月なので特別な理由がなくても概ね12ケ月はショートステイを利用できます。30日利用しては、1日か2日帰って行く、やんちゃなおばあさんです。風呂に入ろうというと、「何で今ごろ風呂に入らんなんねん。」「そんなこと言わんともう3日も入ってないから今日は入ってください。」と頼んでも、「うるさいなぁ!!」と手がとんできました。「何でわしはこんな処にいんなんのや。帰る!!帰せ!!」と言って、職員をつねりました。「帰って何するの。ここで美味しいもの食べて泊まって行ったらええやん。」「牛に餌やらんなん。」「Hさん、そんなにヨロヨロでは、牛の餌やり大変やろ、私ら若い者が代わりにやっとくさかい、ご飯たべよう。」と言うと、「おまえなんかに世話できひん・・・うるさいわい。」と足がでました。お茶碗も飛んでいきました。職員全員があざだらけになって、気の長い相談員も「もうあきません。他の利用者さんが恐がって萎縮してます。今度は他所でお願いしようと思います。」と、言い出すほどスタッフ全体が弱気になっていました。そのHさんが急性疾患で入院しました。入院した翌日からショートステイは何処かに何かを忘れてきたような、気が抜けたような妙な静けさに包まれていました。1ケ月も経つとスタッフの誰からともなく「Hさんどうしてはるやろ。」「まだ退院できひんのやろか。」「家に帰えれへんのやったらうちに来るように言うてあげてください。」「お見舞いにいっても良いですか。」などの声が聞こえてきました。そしてHさんは皆の期待どおり2ケ月後、入院先からうちのショートステイに直行してきましたが、前回とは打って変わってシュンとした小さなおばあさんになっていました。そして1週間が経ったころ、パートのFちゃんが「先生!!見てください!!Hさんがつねりました。ほら、こんなに跡ができたんですよ。」と、ニコニコ嬉しそうに報告にきました。相談員は「今日はオムツ換えるとき3発なぐられて2回蹴られました。1発はまともに顔にとんできました。」と、笑っていました。スタッフがそれぞれ殴られた、蹴られた、つねられたと報告してくれますが、誰ひとり「痛かった」と言う者はいませんでした。Hさんお帰りなさい!!
2005.06.07
コメント(3)
-
認知症患者さんの入れ歯づくり
特養からショートステイ利用者さんの入れ歯を紛失したので、できるだけ早く作って欲しいと依頼されました。これは利用者さんも特養もお困りだろうと思い、昼休みに連日訪問して4日間で義歯を仕上げたことがあります。患者さんは伝い歩き5m程度、認知症はかなり強く、自分の名前も言ってくれません。息子さんの顔だけは何とか解っていそうな方でした。私は訪問に白衣は着て行きません。普段着の方が患者さんに言いたいことを言ってもらえますし、介護者さんも医療に限らず生活全般について話しやすいだろうと思います。しかし、白衣の力を借りることもたまにはあります。特に認知症の強い方には制服は視覚に訴えて理解をしていただきやすいものです。そんな時はお宅に着いてから白衣を着させていただきます。入れ歯の型採りはミラー・ピンセットや型を採るトレーなどを並べ、問題もなく口を開けていただけました。噛んでくださいという指示を通すのが一番難しいのですが、薄いビニールを「ちょっと失礼します」と噛みあわせの場所におくと、自然に噛んでもらえて誘導できます。これも何とか成功しました。ところが、でき上がった入れ歯を口の中に装着した後で、微調整するために外そうとした時、患者さんが私の手を払おうと叩いてきます。ここは叩かれながらも得意の早業で入れ歯を外させていただきました。しかし、入れ歯を盗まれたと思った患者さんは小さな歯茎で私の腕にがぶっと噛みつきました。驚いた介護者さんが患者さんを大声で叱りながら羽交い絞めにしました。患者さんは羽交い絞めにされながら手をバタバタさせて泣きだしました。今度は私が、「そんなことしないで!!」と介護者さんの手を振り解いて患者さんを奪い取りました。患者さんの悲壮な気持ちが乗移り、涙が出てきました。同行していた技工士さんが磨いてくれた入れ歯を患者さんの口に戻してあげると、腕の中の患者さんがぐっと私に寄りかかって、先ほど自分が噛んだ私の腕をなでてくれました。「大丈夫!ぜんぜん痛くないですよ。入れ歯盗ってごめんね。」と言うと、両手を合せて、にっこり笑ってくれました。まずい!!また涙腺のゆるむ瞬間を技工士さんに見られてしまった。
2005.06.05
コメント(5)
-
認知症と入れ歯
以前、歯科訪問診療の患者さんに認知症の末期で全く意思疎通もできず、痛み刺激にも反応せず、目の焦点は合わず、耳も聴こえていないであろうと思われるCさんがおられました。しかし、食事時間には家族2人がかりで、ちゃぶ台の前の座椅子に座らせてもらい、義歯を入れてもらって5種類も6種類もある軟菜と粥食を全介助で食べさせてもらっていました。唇にスプーンや箸が触れると口を開けてくれます。口の中に食べ物が入ると下顎が動き出し咀嚼運動がおこります。時間がかかり、時々むせたりしますがなんとか嚥下されていました。ところが、時々、パタッと咀嚼運動が止まることがあります。すると、娘さんが下顎の義歯の前歯を箸でカンカンとたたきます。するとまた咀嚼運動がよみがえりました。これは下顎反射が起こって咀嚼運動に結びついているのです。それでもちゃんと食べられていました。このご家族は食事の時は必ず義歯を装着してもらうことと座って食べることを実行されていたので、ほとんど植物状態であっても義歯を使って口から食べられていたのだろうと思います。
2005.06.03
コメント(7)
-
嚥下会席はいかがですか
私は12時と6時になると診療室を抜け出してショートの食事風景を偵察に行きます。Aさんはお箸もお茶碗も持てるのにスプーンフィーディングをしてもらっています。Aさんの食介をしているスタッフに、「何でAさんに食介してるの?」と訊ねました。「どんどん口の中に入れて送り込めへんのです。全介助の指示が出てます。」「指示って誰が出したんや?」「ケアマネさんです。」厨房では料理旅館の板前さんを定年退職した通称“おっちゃん”が「こんな食材ではたいしたもんは作れませんなぁ・・・」と今日もぶつぶつ言っています。そこでおっちゃんにまだ手付かずになっている検食を会席風に小さなお皿や器に一口ぐらいずつ分けてもらいました。さすがに板さんの盛り付けはみごとに美味しそう!!Aさんが一皿食べてゴックンしたら次ぎのお皿や器が出ます。Aさんはご機嫌で自分で食べる事ができます。介助は介護を知らない仲居さんでも勤まります。これがうちのショートステイ名物の嚥下会席です。盛り付けが下手だと“わんこそばもどき”になることもあります。
2005.05.30
コメント(1)
-
胃瘻をしててもビールは飲みたい!!
嚥下障害で胃瘻・失語症のある男性Gさんが初めてのショートステイに来られました。3泊4日の予定です。昼食後Gさんの部屋の前がにぎやかです。Gさんが出口を探してウロウロしています。表情も険しく制止すると手が出たようです。そこへ最年少スタッフK君が出勤してきました。K君にGさんのお供をしてもらうことにしました。「Gさん、何処か行きたいところがありますか?」「カイモノ・・・」K君に携帯と5千円札を持たせて、危険がない限り絶対に制止しないで、どこまでもついていくこと、帰れなくなったら電話することを指示して2人を送り出しました。10分後携帯から電話が入りました。「Gさんがビールを買いますが良いですか?」「・・・・・!!」私が慌ててノンアルコールビールを買いにスーパーに行くとK君とGさんが大きな袋を持って出てきました。さっきまで険しい表情をしていたGさんはニコニコ顔です。「あーらGさん、何を買ったの?」・・・それにしても大きな袋。「ビール・・・パーティー・・・」ノンアルコールビールを持ってショートに帰ると看護師が仁王立ちで、「先生!!どういうことですか!!」・・えらいのに見つかった!!「ICFの発想は**がしたいから始まるやろ、Gさんはビールが飲みたいから始まるのよ、Gさんがビールを飲めるようになるには何が必要か、みんなで考えよう!!」「では、何時にビールを胃瘻から入れたら良いのですか?」・・・恐い看護師の目が笑っていました。
2005.05.28
コメント(4)
-

パーキンソン患者さんの摂食姿勢
本日はちょっと特殊な摂食姿勢を紹介します。この利用者さんはパーキンソン患者さんです。車椅子の前輪に注目してください。前輪を15cmほど上げて車椅子を後方にたおしています。この利用者さんは舌の運動障害が著しいため、食べ物を咽頭に送り込むことが難しく、通常の姿勢では食べ物が口からダラダラとこぼれて食べられません。他所ではリクライニングで全介助です。胃瘻の話も出ていますが、ご本人は自分で食べたいのです。この姿勢のポイントは小鼻と耳の穴(正確には耳珠)を結んだ線(鼻聴道線)を床面に平行にするところです。くれぐれも車椅子の転倒にご注意ください。パーキンソン患者さんの嚥下障害は舌の運動障害による送り込み障害が著明で、嚥下反射は比較的保たれていることが多いのです。それでも飲み込めない時には少し上を向いてもらうと気持ちの良いゴックンという音が聞こえます。
2005.05.23
コメント(3)
-
嚥下体操
スタンダードな間接的嚥下訓練用の体操を紹介します。深呼吸 おなかに手を当てゆっくりと深呼吸>3回 吸う→5秒間息を止める→はく>3回 休んで 3回首の体操 前後左右に曲げる。ゆっくり回す。咀嚼訓練 歯を噛み合わせて舌を上アゴに押しつける>3秒3回 歯を噛み合わせて舌で上アゴを前後になめる>3回唇の体操 「イ-」と「ウ-」を繰り返す。>10回 「パ、パ、パ」をはっきり発音する。>20回舌の体操1 上唇、下唇をなめる。 左右の口角をなめる。>20回舌の体操2 「タカ、タカ、タカ」とはっきり発音する。>20回大きな声を出す 机や車椅子の肘掛けを強く押しながら、「えい!」 >10回休んで10回息止め嚥下 息を止めて→唾液を飲む→咳払い>3回(飲み込みの練習) 口を閉じ鼻から大きく息を吸って 唾液を飲み込みすぐに咳払いをする もう一度深呼吸ある訪問看護さんが利用者さんと一緒にこれを訪問の度にやっていました。ある時、その訪看さんが訴えました。「先生、もう少し短い体操にしてもらえませんか、私がヘトヘトになります。」訪看さんは汗びっしょりでした。できるところは回数を減らしても良いです。3ケ月ぐらい続けると嚥下障害の利用者さんの口腔機能が上がります。チューブの外れた方も結構あります。
2005.05.20
コメント(3)
-

ポリグリップの出前講習
ポリデントといえばテレビのコマーシャルで入れ歯関連グッズと誰もが知っています。でも、ポリデントやポリグリップの使い方って歯医者や衛生士も詳しく知りません。私は元々義歯安定剤否定派(多くの歯科医師が反対派です)でしたが、うちの併設施設の利用者さん達は良く持ってきますし、訪問診療先でもほとんどの家に置いてあります。患者さんより種類や使い方を知らないのは少し恥ずかしく思います。そこで、ポリデントを出しているグラクソ・スミスクラインさんに、義歯安定剤の講習をしていただくことにしました。歯科だけで聞くのももったいないので隣のショートステイ・グループホームの職員にも声をかけました。するとショートステイのスタッフが「講習の間、利用者さんの見守りができませんが・・・」と言ってきたので、「利用者さんにも聞いてもろたらええやんか!!為になるやん!!」と・・・・・・・。講習担当の方も歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士・社会福祉士・ホームヘルパー・ケアマネジャーと80歳から100歳までの認知症や難病の利用者さんの構成には少し戸惑われたようでした。言葉選びに随分苦労されているのがちょっと気の毒でしたが、知識習得に関するバリアフリーを推進させていただきました。希望があれば全国どこでも来てくれるようです。グラクソ・スミスクラインさんびっくりさせてごめんなさい。
2005.05.19
コメント(2)
-
機能的口腔ケア
スタンダードな機能的口腔ケアを紹介します。これは、様々な講習などでもう5年以上使用しているものです。うちの衛生士も訪問口腔ケアで実施しています。1.問診2.バイタルチェック血圧、脈拍呼吸数、頚部の聴診・呼吸音体温SpO2コミュニケーションの状況/他の日との比較が大切です。3.頚部のストレッチ、顔面(表情筋)のマッサージ、口輪筋の刺激訓練4.口腔内観察/見にくいところから見やすいところへと進めると見落としがない。特に最初に口を開けさせると口腔前庭を見落とすことがありますので、最初はイーから始めます。次にはアーと言わせて口峡部をみます。5.口腔清掃6.口唇、舌の運動訓練など7.呼吸訓練/ブローイングなど/ゲーム感覚でやってみて下さい。8.構音訓練/自分の名前、母音、50音(50音はかなり痴呆の進んだ人でも言えます)タ、カ、ラ(舌の微妙な動きを必要とする音です)パ、ム、ウー、イー(口唇の運動が必要な音です)などを組み合わせた楽しい短文を作っておくと良いですね。良く使うのはやはり「パンダノタカラモノ」です。9.プッシングエキササイズ/声門内転訓練
2005.05.18
コメント(1)
-
口腔ケアって何だろう?
口腔ケアとは口腔機能の回復、維持、口腔機能障害や嚥下性肺炎等の予防をすることによるQOL(生活の質)の向上を目的とするキュアを包括したケアです。山中は口腔ケアを「口腔の疾病予防、健康の保持増進、リハビリテーションによりQOLの向上を目指した科学であり技術である。」と定義しています。 最近、口腔ケアは器質的口腔ケアと機能的口腔ケアに分類されることが多くなりました。器質的口腔ケアは口腔の保清、衛生管理など狭義の口腔ケアを指します。機能的口腔ケアは口腔リハビリテーションを指します。来年から実施される予定の介護予防の口腔ケアは機能的口腔ケアです。口にだって廃用萎縮はあります。とっておきの機能的口腔ケアは大きな声で顔をくしゃくしゃにして笑う事。大きな声で歌う事。美味しいものを食べる事。そうです!!口腔ケアって究極のQOLなんです!!
2005.05.17
コメント(2)
-
グループホームの日曜日
日曜日はグループホームに訪問者の多い日。毎週訪問する家族もいれば半年に1度ぐらいしか訪問しない家族もいる。いつも他の住人さんに車椅子で「とおせんぼ」をしたり、大きな声で脅かして寮母長に何度も始末書を突きつけられている100歳の悪ガキKさんの所へも珍しくお孫さん(と言っても50を過ぎている)が来てくれた。リビングでは「4人娘」と呼んでいる、短期記憶は低下していてもその場を繕うのが上手なグループがお茶を飲みながらテレビを見ていた。突然、「そんな事を言ってると私はもう来ません!!!私はおじいさんよりお父さんの方が大事です!!!」と50過ぎのお孫さんの声がグループホーム中に響き渡り、唖然とする職員に挨拶もなくエレベーターが閉まった。4人娘はそれぞれいつの間にかリビングから消えていった。そして声をあげて泣いていた100歳の悪ガキKさんが言った。「お風呂もう沸きましたかいなぁ?」
2005.05.15
コメント(0)
-
寝かせての食介は抑制行為!!
ケアマネジャーMとショートステイの相談員Sの会話です。利用者さんにはパーキンソン症候群があります。舌の運動機能障害がありますが、嚥下反射は残存し喉頭挙上量もあります。M/家族が絶対に寝かせて全介助で食べさせてくれって言われてます。S/食事が置かれると素早く自分でスプーンを持って食べ始める人にこぼす量が多いという理由だけで、最初から寝かせて全介助はできません。寝かせたら自分で食べ物を取れません!!チルト姿勢にして、眼耳平面を上げたら送り込みができます。自分でスプーンを持って食べることは、彼女が唯一自分でできることなんです。***えらい!!Sくん!!今年も社会福祉士失敗したけどケアマネに負けるな!!M/デイサービスで最初から寝かせて全介助したら10割摂取できているんですよ。ショートではこぼして全量摂取できてないでしょう!!本人にスプーンを持たせないで最初から寝かせて全介助してください!!S/うちは抑制はしません・・・と理事長が言ってました。***おい!!Sくん、それってアンタの意見じゃなかったの?
2005.05.14
コメント(4)
-

民家改修型小規模多機能歯医者
午前の診療がやっと終わったのが1時半。「難病や障害のある方の受け入れ可能な歯科医院のパンフレットを作るので取材させてください。」と、地域振興局のお姉さんが来られました。うっ~。ワスレテタ!!お腹すいた~っ、ふっうー。「先生の医院で受け入れに関して工夫されているところは?」「え~、特にないですが・・・」う~ん、お腹すいた~っ。「例えばスロープとか、エレベーターとか?」「車椅子の方はどのようにして入って来られますか?」「3人がかりでお神輿みたいにして・・・」あいゃ~、かっこわる~お腹すいた~っ。「手摺とかありますか?」「私や衛生士が手引きしてますが・・・そうそうサイドケインならありますが・・・歩行器もありますが・・・車椅子型の診療台もありますけど・・・」ニック 側方型歩行器 NR-203 LBR 「楽天シニア市場」「監視装置なんかありますか?」「看護師がバイタルの管理ぐらいしますが・・・」【ナショナル】上腕血圧計EW3152松下電工 手くび血圧計 EW3032P-Sパルスオキシメーター(一体型)「車椅子トイレありますか?」「ショートステイにありますが・・・」「駐車場は何台ありますか?」「そんなにたくさんありませんが・・・運転手さんがリフト車で迎えに行きますが・・・」「写真を撮らせていただきたいのですが、極めつけのバリアフリーなところを!!」「私の心でも撮りますか!!」お金かけんとあかんのかい?バリアフリーってハードだけか?うちは民家改修型の小規模多機能歯医者です。うちの衛生士はみんな移乗・トイレ介助や食事介助ぐらいできますがな。痴呆研修の専門課程終わってるのも2人程いまっせ。技工士なんかこの5年でヘルパー1級・社会福祉士・ケアマネジャーも取りましたがな。うちみたいな歯医者は変ですか?
2005.05.13
コメント(3)
-
介護系歯科事情
私は歯科医師です。18年程前に叔父が施設長をしていた特養に往診したのがきっかけで要介護高齢者さんの歯科治療を続けてきました。その間、歯科の往診が歯科訪問診療という言葉にかわり、機材もポータブルの切削器具ができ、口腔ケアの必要性がいわれ出し、介護保険ができて居宅療養管理指導という言葉もできました。当初は診療室以外の場所で診療室と同じ治療を提供すること、つまりは歯科医院の出前を目標としておりましたが、介護現場に足を運ぶうちに外来の患者さんとはどこか違うことに気がつき、何らかの新しい取組みが必要であると考えるようになりました。ある時、40回近く義歯の調整に行って、私たちがするべきことは全部したのにかかわらず上手く食べられない、薬が飲めないと頻回に訴える患者さんに遭遇しました。もうお手上げ状態で、どんなに食べられないのか見てやろうと思い、食べるところを見に行くことにしました。見に行って驚きました。食べる口元が予想と大きく違っていてびっくりしました。口の中に入れた物をいつまでもモグモグとしていて飲み込めません。これは義歯が悪いのではなく口の機能が悪いのです。訴えが義歯にあったので私が摂食機能障害に気がつかなかったのです。このケース以来、在宅で「入れ歯の調子が悪い」と言われたら「上手く食べられない」と訴えられていると解釈することにしました。あれから10年経ちました・・・。このブログでは在宅診療に携わってきた歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士が培ってきた“食べるための支援”関連する話題について記載していこうと思います。
2005.05.12
コメント(1)
全18件 (18件中 1-18件目)
1