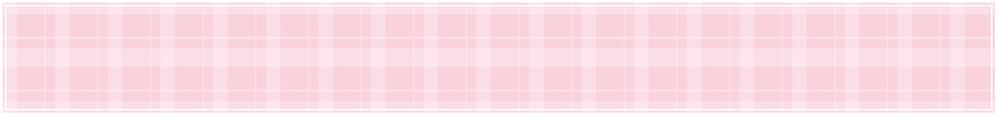2010年04月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
鎌倉に 生きて出でけん 初鰹
新緑の眩しい季節を迎えました。この時期を表す俳句といえば山口素堂の「目には青葉 山ほととぎす 初鰹」が有名です。この句は延宝六年(1678年)素堂が鎌倉材木座海岸で詠んだものと言われています。江戸時代、鎌倉は鰹の産地として知られ、俳聖松尾芭蕉も「鎌倉に 生きて出でけん 初鰹」という句を残しています。鎌倉でとれた鰹は、すぐに八挺櫓の早船で江戸に送られ、びっくりするような高値で売買されました。明け方の魚河岸に着く前に、「夜がつお」と称して活きのいいのを食するのが“通”と言われたものでした。グルメばやりの昨今ですが、ちゃんと江戸の昔から“通”と言う言葉がありました。青葉輝くこの季節、そんな食通の皆さんにお届けしたいのが花見煎餅吾妻屋の「柏餅」。北海道産小豆をたっぷり使った白生地のこしあん・よもぎの香りのつぶあん・京の白味噌を使った紅生地のみそあん、それぞれの味をお楽しみ下さい。
2010年04月20日
コメント(0)
-
鎌倉寿福寺で高浜虚子忌
こんにちは、鎌倉由比ガ浜の花見煎餅吾妻屋です。昭和30年代に弊店の近所の江ノ電由比ガ浜駅近くに俳人高浜虚子が住んでおり、現在他者が居住していますが虚子庵として保存されています。俳人高浜虚子は明治7年愛媛県松山市生まれ。同郷の俳人正岡子規の後を継ぎ句誌「ホトトギス」を主宰。明治43年鎌倉由比ガ浜の虚子庵に移り住み、昭和34年に85歳で亡くなるまで五十年にわたり鎌倉由比ガ浜で過ごしました。虚子庵には「波音の 由井ヶ濱より 初電車」の句碑が江ノ電踏切脇に残されています。虚子の祥月命日に当たる4月8日には、菩提寺の鎌倉五山の一つ寿福寺に於いて年忌法要とホトトギス社・玉藻社主宰の虚子忌句会が古刹の名庭を囲んで開催されます。虚子さんは大の甘党、とくに豆大福には目がない。という訳でこの虚子忌句会にご出席の皆さんに振舞われるのが花見煎餅吾妻屋の「豆大福」。当日は虚子ゆかりの、250人以上の方々が集まり、故人の遺徳を偲び、古刹の名庭を眺めながらの大句会が催されます。散り行く桜をながめながらどんな名句が浮かんでくるのかな。
2010年04月06日
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- どのイベントで買うか迷っているもの
- (2025-11-16 07:21:10)
-
-
-
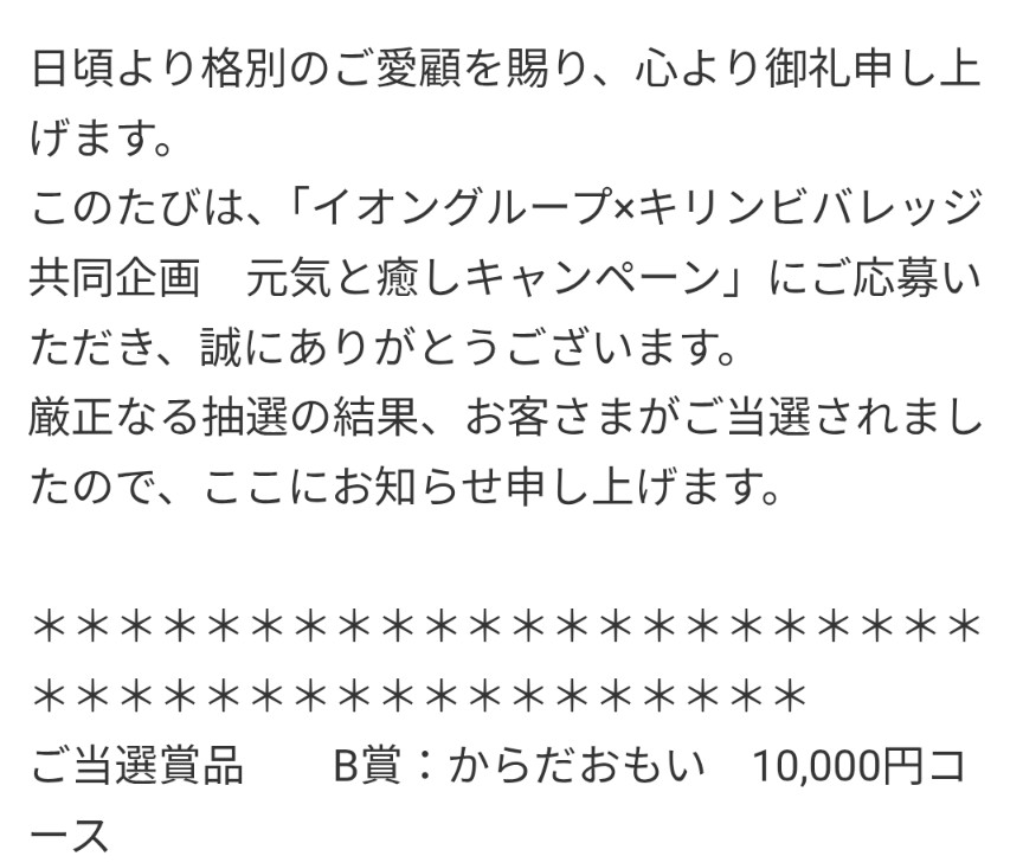
- 懸賞フリーク♪
- からだおもいデジタルカタログギフト
- (2025-11-16 00:56:51)
-