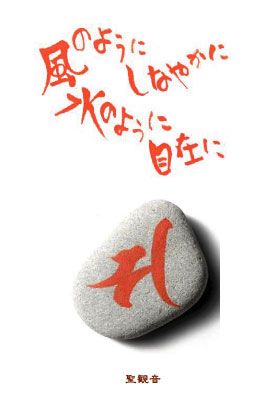テーマ: 日記を短歌で綴ろう(3844)
カテゴリ: TNK楽歌31
♪ 夜と朝のあわいに目覚め啼く鳥のこえ聞く中に半跏趺座する
鳥たちは朝が早い。まだ暗い4時ごろになると盛んにさえずり始める。
それに呼応するように起きて階下へ。フローリングの床に座布団を二つ折りして半跏趺坐する。
掃き出し窓になっているので網戸の向うに隣家の庭がぼんやりと見える。今はまだ朝の気温は高くなく、とても清々しい風が入って来る。
理想は日の出の方を向いて座るのがベストだが、家の構造上それは叶わず南西向きに座ることになる。
30~40分の座禅。その間、ピピと遊ぶために来る近所の飼い猫・モモ(勝手にそう呼んでいる)がやって来た。その通路になっている目の前にオッサンが座っていて、一瞬目が合って慌てて逃げて行った。
鳥の鳴き声も聞こえなくなり直ぐに夜は明けて、昨日と同じ振りをした今日という日がまた始まった。
800年前、1212年に鴨長明が58歳の時に「方丈記」を書いた。あの頃(23歳から31歳)は、火事や地震や竜巻、飢饉や疫病が次つぎと襲い、政治もうまく機能しなかった。為す術のない人々は「無常」を思わずにはいられなかったという。
『行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまる例なし。世の中にある人と栖と、またかくの如し。』
『あしたに死し、ゆふべに生るゝならひ、たゞ水の泡にぞ似たりける。知らず、生れ死ぬる人、いづかたより來りて、いづかたへか去る。』人も栖(すみか)も消えてはまた新しく生まれていく、留まる事を知らない儚いもの。どうせ消えていく運命なのだから、家なんかに金を掛けて執着するのは如何なものかと嘆く。
今日、これから何が起こるかは誰も分からない。ましてや明日の事なんか分かるはずがない。無力で自然に翻弄されて生きている人間であるからこそ、柔軟にブレながらそれらに対応していくことが肝要と説く。
玄侑宗久著 『【 無常という力 】「方丈記」に学ぶ心の在り方』を読む。「無常」を心の根底に据えて生きることを唱えている。
決めつけない事、諦めない事、粘り強く、そして柔軟に・・・。
◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[TNK楽歌31] カテゴリの最新記事
-
◆ ジョーク、冗談、ユーモアは生活の調味… 2014.10.22
-
◆ 消えていってこそ虹 2014.10.21 コメント(2)
-
◆ 映画っていいね。色々あるから良さも… 2014.10.20
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
キーワードサーチ
▼キーワード検索
サイド自由欄
◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。
◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。
◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。
◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。
◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。
◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
「アーカイブ」
◎ Ⅰ 短歌
◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編
◎ Ⅲ 興味深いこと
◎ Ⅳ 興味深いこと パート2
◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など
◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。
◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。
◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。
◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。
◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
「アーカイブ」
◎ Ⅰ 短歌
◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編
◎ Ⅲ 興味深いこと
◎ Ⅳ 興味深いこと パート2
◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.