カテゴリ: 一日一首
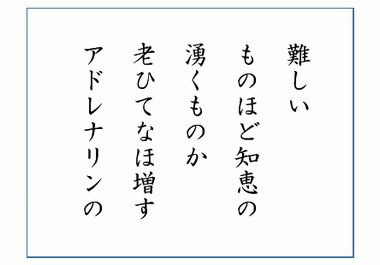
♪ 難しいものほど知恵の湧くものか老ひてなほ増すアドレナリンの
元気がなかった原因は、どうも最近耳が遠くなったのと、目が見えにくくなったことが影響しているらしい。そんな事があの怪物のようなにも親方堪えるんだなあと思うと、妙に哀れな感じがした。
メガネ屋で目を診てもらい、眼鏡を掛けてもあまり視力が戻らないと言われてたらしい。80近くまで眼鏡を掛けずにいられた人が、これから良く見えるようになるなんて無理だと言われ、”高い金を出して視力が出ないなんて、どういうことだ!”とあれこれイチャモンつけて店員を呆れさせたとのこと。
目はどうやら白内障らしいが、医者には未だ行ってないという。御年77歳というからまだまだ元気でいられる齢、老け込むのはまだ早い。
太鼓の台の製作を頼まれたらしい。一見簡単そうな構造に見えるがこれがけっこう難しいのだという。江戸時代に作られた台座がまだ健在のものがあり、それと同じ作り方でやるのだという。一度組むともう絶対にバラせないシロモノで、「X」に組んだ足は切り欠きを作って折りたたみ出来るようにしてある。その二組の足の「X」部分を通した軸に秘密があるのだとか。
単純に直径4cm程の丸棒の軸から、1cm程の棒(細いため樫の木が使ってある)が出て「X」部の軸受に通って固定されている。この軸が絶対に抜けないようになっているらしいのだ。
そして、軸と平行に左右の足を固定する横木は、ほぞ繋ぎで完全に固定されている。そのため、全体を全て同時に組みつけていかないと、組み上げることが出来ないのだという。
今、各地で使用されたり市販されている台座は、横木はほぞ継になっていないし、中心の軸はボルト締めで、足の広がりはロープで調整・固定する様に簡略化されている。本来はこんな造りではないのだという。技術が無いため従来の方法では造ることが出来ず、今風の略式の構造になっているのだ。
現在の太鼓の台の一形式
この軸の部分の秘密は、簡単に分解も出来ないので素人には絶対に分からないという。その秘密の構造を聞いてきた。横軸に差し込んだ細い樫の棒が、絶対に抜けない様な細工がしてあるらしい。
その差し込む中心部分が太くしてあり、穴の方も口の部分より奥が少しだけ広く彫ってあるのだろう。槌で叩きこんでしまえばもう抜けない。このテーパーを付けたほぞと、穴のサイズとの兼ね合いが難しいらしい。
長胴太鼓台
形は、真ん中の横軸が丸い以外はこれとほぼ同じ
江戸時代に造られた現物を前に、親方もあれこれ考え知恵を絞って漸く出来たのだが、軸が折れて失敗したことが数度あったという。最後の最後に待っている工程が一番の難所ときては、今どきの大工では手が出ないのは頷けるところか。
理屈はわかっても、それが出来るか否かは別問題。そんな当たり前の事をちゃんと努力してクリアきたのが先人の職人魂・心意気というものなのだろう。
◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。
◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。。◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
☆ 短歌集 「ミソヒトモジ症候群」 円居短歌会第四歌集2012年12月発行
● 「手軽で簡単絞り染め」
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[一日一首] カテゴリの最新記事
-
◆ 満10年となりました。 2016.05.07 コメント(2)
-
◆ 長年の便秘が治った様な爽快な気分。 2016.05.06
-
◆ 思い付きの出たとこ勝負 2016.05.05
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
キーワードサーチ
▼キーワード検索
サイド自由欄
◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。
◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。
◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。
◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。
◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。
◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
「アーカイブ」
◎ Ⅰ 短歌
◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編
◎ Ⅲ 興味深いこと
◎ Ⅳ 興味深いこと パート2
◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など
◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。
◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。
◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。
◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。
◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
「アーカイブ」
◎ Ⅰ 短歌
◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編
◎ Ⅲ 興味深いこと
◎ Ⅳ 興味深いこと パート2
◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.














