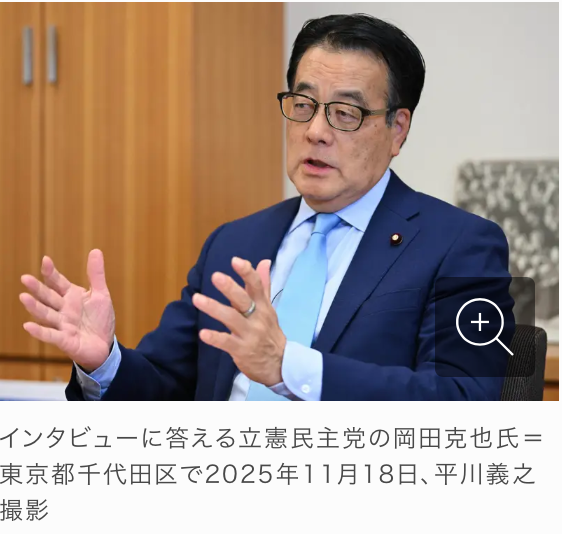全45件 (45件中 1-45件目)
1
-

マネーパートナーズCM でんじろう告白篇
サイエンスプロデューサー・でんじろう先生が、FX取扱業社、マネーパートナーズのCMに登場!マネーパートナーズについては、以前のエントリーを参照。実験に没頭するでんじろう先生をみつめる一人の女性。密かに先生に思いをよせている。そして、ついに先生…。先生は少年のように、夢中になっているが、果たして…どうなる。絶妙のタイミングでナレーションが。。。
Jul 4, 2006
-

FXというきっかけ
FXは、少ないお金でチャレンジできる投資です。マネーパートナーズが提供する「パートナーズFX」では、初回入金3万円からはじめることができます。(ただしキウイ円を取引するには3万でOKですが、ドル円を取引するには5万となります。)手数料は、1万通貨あたり400円ですが、デイトレなら無料となります。また楽天グループが資本参加している点も注目されます。儲かるということはその反面、それと同等のリスクがあるというわけでして、リスクを背負う覚悟が必要です。人間、儲かっているときはリスクを忘れがちなんですね。つい、良いように、良いように考えてしまい、またちょっとの負けを認められず、大きく負けてしまう。損切りがとても大切ですね。
May 19, 2006
-
団地
小学生のとき、団地に住んでいた。市の一番外れたところにある団地だった。団地の北側には、大きな川が流れていた。どうやら人の手で作った運河らしい。しかし直線的で、深く、濃い緑色の水を湛えており、引きずり込まれそうな感覚を覚えた。実際、川でおぼれて亡くなった子どももいて、何度か全校集会が開かれ、校長先生からの注意があったことを記憶している。団地の西側は、交通量の多い、大きな道路であった。南側には小学校があり、東側には、いろいろな店が並んでいた(一応商店街になるかな)。商店街は、北から順に、診療所(アレルギーの注射を打ってもらっていた)銭湯(煙突から出る煤が時々被害を及ぼした)郵便局(友だちのおじさんが窓口で働いていた)郵便局の東隣りには、近所で唯一のスーパーがあった。私がまだ社会のルールを知らなかったころ、アイスを勝手に持ってきたらしい。スーパーの東側には、大きな公園があった。遊具のほかに、野球グランド、テニスコート、ゲートボール場などがあった。公園の東には、一軒家の家々が拡がっていた。郵便局から道路を挟んで向い側には、バス停(終点である)、道路を斜めに挟むと、ラーメン屋(何時の間にか、つぶれた)雑貨店(じいちゃんの煙草を買いに行った)床屋(雑貨店の2F)があった。うちは団地の中でも、一番立地条件のいい場所で、商店街のすぐ隣りで、バス停にも近かった。
Sep 18, 2005
-
将校患者
別府の陸軍病院で療養していた将校の、1945年5月7日の日記です。「五月七日 朝食を済ませた途端に、空襲警報となった。今日は晴天で飛行機がよく見えるところへもってきて、実に久しぶりといおうか、待望久しき友軍機の邀撃戦が見られた。みんな天を仰いで大喜びしたのだった。 まず中津方面へ向かった敵編隊に、わが戦闘機ただ一機、若武者のように追いすがってゆく。空の要塞B29の巨体にくらべれば、わが戦闘機はちょうど蝉と蝿位の対照ではあるが、この蝿が最後尾から二番目のB29の胴腹に無我の境地そのもの、一直線に体当りを敢行したのだ。 既に神風特攻隊のことはニュースで知っていたが、おそらく、特攻機が敵航空母艦や戦艦に目標を定めて急降下突撃を試みるのもこれと同じ状態と思われた。 B29の巨体が、一瞬グラッとしたと見るや、この時早く、かの時遅くサッと吹き出した黒煙の中に、友軍機は定かには見えずなり、やがてモツレ合った如くに落下してゆくのだ。彼我一緒くたに。」(田邊重信『将校患者』金剛出版、1965年、169-170頁)B29に対して航空機による特攻が行われ、空中戦の模様を地上から、日常的に目撃できる時代。
May 7, 2005
-
史料としての日記
録画してあった、NHK・BSの日露戦争のドキュメンタリーを見ました。ロシア人兵士の手紙やニコライ2世の日記によって、番組が構成されていました。ロシア皇帝の日記が残っているんですね。日本に置き換えると、天皇の日記になるでしょうか。天皇の日記が残っていて、そこに心情が吐露されているとは、全く想像もつかないことです。日記に関して、加藤陽子先生が面白いことを言っています。日記から浮かび上がるのは、世界がその書き手を中心に廻っていると感じられるような、「天動説」的な世界像だと言うのです。それゆえ日記を読むことで、ある時代を単純化して眺める視座をいったんは持ち得る。 そして、日記の書き手の「天動説」的な世界像をまず把握上で、その「天動説」的な世界像を崩すような、ほかの文献にあたり、それらを照らし合わせて読むことが大切である、と。 日記だけではなく、他の史料についても同様なことがいえると思います。歴史家も自分が集めた史料だけで、「天動説」的な世界像を構築してしまうかもしれません。いかにそれを自覚し、より多くの史料に当たって、説得力のある歴史叙述を為していくか。それが大切ですね。
Apr 27, 2005
-
海軍労友
海軍艦政本部発行の『海軍労友』は、海軍工廠の工員向けの冊子です。以下のものは、投稿された詩の一節ですが、そこでは、軍隊のもつある種の平等性がよく表わされています。斎藤芳郎(空技廠総務部)「兵営」兵営――ここはすばらしく人間の再出発 するところだ!体に潮のしみついた漁夫も肩に筋肉の凝固つた農夫も眼鏡の奥に考へ深さうな眼を した大学生も会社員も商人も前生活の習慣や知識 集積を 止揚して兵隊として茲で鍛へ直される(海軍艦政本部『海軍労友』165、1941.8.1)また次の詩は、戦時下の勇ましい雰囲気がよく出た作品です。粟野茂夫「検査工の朝」早春三月の空は素晴らしく晴れ、朝の緑は窓を越して冷徹の定盤へ沈潜する!精巧なマイクロとノギスを持てば、冷えた器具の触感が眠り足りた脳髄にしむ。見ろ! 曲線に直線にステンレス鋼の磨かれた製品を、そは皇軍精兵に似て整然たる横の散兵!私は光栄ある閲兵に取掛る!インヂケーター用意!縦に横に厳格な点検!やげて私は完成マークを打つハンマーの快音に朝の陽は小波の如く躍つて聞け! 遥かに大東亜戦完遂への号笛が鳴つてゐる――(『同』174、1942.5.1)
Apr 18, 2005
-
中国の歴史教科書
中国の歴史教科書について、あやふやな情報に基づいて議論するのではなく、冷静に実態を見定める必要があると思います。以下では、中国の歴史教育の一端を並木頼寿「中国教科書の世界・日本像」(山内昌之・古田元夫編『日本イメージの交錯』東京大学出版会、1997年)によってみていきたいと思います。(1)教育の方針国家教育委員会が制定した『全日制中学 歴史教学大綱』(1991年)には、次のようにあります。「中学の歴史教学は、学生に対して、社会発展法則の教育、革命伝統の教育、愛国主義教育、四つの基本原則堅持の教育、および国際主義教育を行って、学生が社会主義祖国を熱愛し、社会主義事業を熱愛し、共産党を熱愛する真摯な感情を育て、歴史上の優秀な人物の尊い人格に学び、社会主義現代化建設のために貢献する精神を樹立することが求められる」(並木論文、45-46頁)並木氏が指摘するように、「中国の歴史教育には、中国共産党が指導する中華人民共和国という国家に国民を統合させようとする、たいへん強い意志が働いて」います(同47頁)。そこでは、マルクス主義の発展段階論が歴史観のベースとなります。○初級中学『世界歴史』1992年 巻頭「なぜ世界歴史を学ぶか」「私たちは世界歴史を学ぶことによって、歴史唯物主義の正しさ、たとえば社会発展法則の正しさをいっそう良く身につけることができる。私たちは歴史の発展に確固とした法則があること、後の社会には前の社会よりも進歩していること、資本主義社会が必然的に社会主義社会にとってかわられることは、社会発展法則によって決定されていることを、より明確に理解することができる。未来の世界が発展していく基本的な方向は、あともどりすることのないものなのである。これによって、私たちの社会主義に対する信念はいっそう強化されるであろう。 中国歴史を学ぶことによって、私たちは愛国主義の尊さを深く教えられるが、では、世界歴史の学習からも同様の教訓を学ぶことができるだろうか。やはり学ぶことができる。…」(同50-51頁)(2)時代区分初級中学『世界歴史』では、「世界古代史」、「世界近代史」、「世界現代史」と時代区分されています。「中世」がないのは、「封建社会」を古代とすることに由来しています。中国史では、戦国時代(前403-前221)から「封建制」になったとみられており、その発展段階規定と関連しているわけです。地主制を基礎とする封建制は、20世紀の中国革命で打倒されるまで続きます。その後は、植民地主義と結託した封建勢力が民国の政権を牛耳ったとされ、中国近代の社会体制は、「半封建」と規定されています。近代から現代への大きな画期は、ロシア革命に置かれますが、1949年の共和国成立から現代とする見解もあり、その評価は揺れているようです。(3)日本との関わりについて以上のような時代区分を背景に、日本との関係は以下のような主旨で記述されています。中国の古代文明は世界歴史を牽引する先端的文明であり、世界に絶大な貢献を果したとされます。しかしアヘン戦争を境に立場が逆転します。近代アジアの歴史は、欧米植民地主義の圧迫に対抗する民族解放運動の歴史として描かれていきます。そして、その中で中国は、「反帝国主義・反封建」の課題を担う世界の革命的な人民の先頭に立っていたことが印象づけられる記述となっています。アジアのなかで著しく異質な存在として、「帝国主義化」した日本がとらえれています。「主な帝国主義国家―日本」の項には、次のようにあります。「大地主と大ブルジョアを代表する天皇専制政権は、極力軍国主義の発展につとめ、内には弾圧政策を行い、外には侵略拡張を行った。日本の侵略の矛先は朝鮮と中国に向けられた。早くも七〇年代に、日本は朝鮮に迫って門戸を開かせ、その侵略勢力を浸透させようとした。一八九四年にはさらに朝鮮への侵略を進めるため、中日甲午戦争〔日清戦争を指す〕を挑発した。ツァーロシアと朝鮮および中国の東北地方を争奪して、一九〇四年、日本は日露戦争を起こした。日本は帝国主義にむかう過渡的な過程において、一面では従来西洋の資本主義国家と結んでいた不平等条約を徐々に廃棄して、西洋に従属させられる危険から脱却するとともに、別の一面では自らすすんでみだりに武力を好む侵略的な傾向の強い帝国主義国家に変わっていった。」(同62頁)近代以前の日本については、中国から絶大な影響を受けて社会と国家を形成したこと、そして「倭寇」の侵略的イメージが主になるのでしょう。古代の対外関係においては、中国の大王朝による朝鮮や東南アジアに対する遠征や征服は、あまり触れられていません。「元寇」についてもありません。また中国を中心とした冊封・朝貢関係をもとにした地域秩序についても記述されていません。近代になると、日清戦争から日中戦争に至る日本の軍事行動の広がり、および中国の抵抗運動に関して、日本の教科書の記述をはるかに超える情報が盛り込まれています。
Apr 11, 2005
-
歴史認識について
歴史研究者の安田常雄氏は、近年の歴史認識をめぐる状況を次のように述べています。「多くの人の歴史知識の中に、データや事実をベースにして、ある特定の固有の時代の歴史像を定型的に描き出していくのではなく、現在の自分から見て快適な要素を歴史の中に探していくという形がとられているのではないか。だから時代を超えるわけです。どの時代でもかまわない。自分が快く思われるものが歴史の貯蔵庫の中から拾い出されてきて、それが一種のイメージ連鎖のように並べられていくという状況が、とくに八〇年代、九〇年代に進展していっていると思います」(国立歴史民俗博物館編『歴史展示のメッセージ』アム・プロモーション、2004年、85頁)『国民の歴史』が売れる背景が的確に説明されていると思います。ネットの発達は、「現在の自分から見て快適」な、断片的な情報を「イメージ連鎖」のように並べることをますます容易にしたのではないでしょうか。私は歴史をみるうえで重要なのは、史実の本質、ものごとの本質がどこにあったのかを捉えることだと思います。自分にとって快い、あるいは国家にとって快いかどうかという視点では、その本質を見誤るのではないでしょうか。そのような視点では、、ある事実をどう評価するのかということだけではなく、事実の認定それ自体についても、限界を生じさせることになるでしょう。学問とは、“普遍”を追求することです。それは、そもそも、国家利益から超然たることを宿命づけられているものだと思います。国家もそれを認めざるを得ないでしょう。
Apr 6, 2005
-
朝鮮王宮占拠
1894年7月23日、日清が対峙するなかでの日本による朝鮮王宮占拠は、重要な史実だと思います。その経緯について、外務省の記録は次のように述べています。○2 日清韓交渉事件記事/一 朝鮮関係ノ分(対韓政策関係雑纂/日韓交渉略史 松本記録) アジア歴史資料センター:B03030190200「平和ノ手段ニヨリ我目的ヲ達スルノ見込殆ント尽キタルヲ以テ大鳥公使ハ朝鮮政府ノ異議アルニ拘ハラス京城釜山間軍用電線ノ架設ニ着手セシメ兵営ノ設置ヲ促カシ中朝商民水陸貿易章程中江通商章程及吉林通商章程ヲ廃棄スヘキコトヲ照会シ又在牙山清兵ノ撤回ヲ清国政府ニ請求スヘキ旨ヲ照会シ此最後ノ請求ニ対シテハ廿二日ヲ期シテ回答スヘク若シ其期ヲ後ルヽニ於テハ処決スル処アルヘキ旨ヲ言送リタルニ期ニ至リ甚タ漠然タル回答ヲ送リ到底満足ヲ得カタキコト判然タルニヨリ翌廿三日早朝我兵ヲ以テ王城ヲ圍繞センカ為メ之ヲ王宮ノ方ニ進マシメタルニ僥倖ニモ彼ヨリ発砲シタルニヨリ我兵之ニ応砲シ逐ヒ退ケテ闕内ニ進入セリ続テ大院君ハ国王ノ召ニ依リ参内シ間モナク国王ハ外務督辧ヲ使トシテ大鳥公使ヲ召請シタルニヨリ公使ハ直ニ参内シタルニ大院君国王ニ代リテ進謁ヲ受ケ同君カ国王ヨリ政務統轄ノ任ヲ受ケタルコトヲ披露シ併セテ将来大鳥公使ノ賛助ヲ請フヘキ旨ヲ述ヘタリ」4画像目(適宜改行)大院君の擁立も日本側が画策したことです。渋る大院君の腰を漸く上げさせています。大鳥大使は、次のように報告しています。「兼テ申進候通金嘉鎭安■(馬+冏)壽、岡本、小川等ヲ利用シ先ツ大院君ヲ入閣セシムルコトニ尽力致候得共同君ハ今一歩ノ処ニ至リ決シ兼ヌル様子有之誠ニ隔靴ノ感有之候」そこで幽閉中の大院君の腹心を脱獄させて、説得に当てさせますが、大院君は態度を決めかね、そうこうしているうちに日韓の戦闘が始まります。「我兵ト韓兵トノ間ニ発砲起リ遠クヨリ望見スルニ或ハ国王陛下闕後ニ落行カレタル事アル間敷ヤノ疑慮有之候ニ付本官モ一方ナラス心配シ遂ニ杉村書記官ヲ大院君邸ニ遣シ速ニ出世方相促シ候処同君ノ心中全ク出世ニ意アルモ日本人ニ強ヰラレ出テタリト云ハヽ当国人間ノ評言モ有之候ニ付態ト我勧告ニ応セサル様子ヲ仮装シ只管国王陛下ヨリ勅使ノ至ルコトヲ待チ居タリ此時安■(馬+冏)壽、兪吉濬等ハ大闕ト同君邸トノ間ニ奔走シ遂ニ勅使ヲ差立ツルコトニ至リタルニ付大院君此ニ断然決意ヲナシ勅使ノ帰邸ニ引続キ直チニ参内セラレタリ」39画像目大院君への勅使の派遣も日本軍の占拠下で、強いられたものであることが容易に想像されます。
Apr 4, 2005
-
植民地としての朝鮮
「併合」という語句を最初に用いた、外務官僚・倉知鐡吉は、次のように述べています。〇朝鮮総督府外事局長・小松緑宛前外務次官・倉知鐡吉覚書 1913.3.10「当時我官民間に韓国併合の論少からざりしも、併合の思想未だ十分明確ならず、或は日韓両国対等にて合一するが如き思想あり、又或は墺匈国の如き種類の国家を作るの意味に解する者あり、従て文字も亦合邦或は合併等の字を用ひたりしが、自分は韓国が全然廃滅に帰して帝国領土の一部となるの意を明かにすると同時に、其語調の余りに過激ならざる文字を選ばんと欲し、種々苦慮したるも遂に適当の文字を発見すること能はず、因て当時未だ一般に用ひられ居らざる文字を選ぶ方得策と認め、併合なる文字を前記文書(引用者注―小村外相意見書)に用ひたり。之より以後公文書には常に併合なる文字を用ふることゝなれり」(春畝公追頌会編『伊藤博文伝』下巻、1940年、1013-1014頁)「併合」とは、従来の「保護国化」政策から転換し、「韓国が全然廃滅に帰して帝国領土の一部となるの意」であって、その際、「語調の余りに過激ならざる文字」として選ばれたものでした。なお「帝国領土の一部となる」といっても、内地の一地域になったわけではありません。国際法学者・有賀長雄は、「合邦の形式」に関して、次のように述べています。○有賀長雄「合邦の形式如何」『政友』120号、1910年7月「合邦の方法には対等と不平等の二あり。対等にて合法〔合邦カ〕すとは国際法に所謂実体合一なるが、此の如きは日韓の場合に於ては問題外なり。不平等の地位にありてする合邦は仏語のアネション(合併)にして、之れに三種あり。(一)属邦としての合邦、(二)殖民地としての合併、(三)地方としての合併、之れなり。皆各々法理に於て異なれり」(海野福寿編『外交史料 韓国併合』下、不二出版、2003年、621頁による)以下、有賀はその三者に関して説明を加えていきますが、それをまとめると次のようになります。http://kurokayo.fc2web.com/ariga.htm一進会が構想していたのは、有賀がいうところの、「宗属関係」であったようです。〇「日韓合邦問題ニ関スル件」警視総監より統監宛 190912.2「近来、喧伝セラルヽ日韓合邦問題ノ径路ニ関シ更ニ探聞スル処ニ依レハ、過般来ヨリ宋秉■(しゅん ※機種異存文字のため表示不可)ト一進会長李容九トノ間ニ於テ屡々交渉ヲ重ネツヽアリシハ事実ニシテ、其成立セル連邦案ノ細目ハ左ノ如キモノナリト伝フ。 一、大韓国ヲ韓国ト称スルコト。 二、皇帝ヲ王ト称スルコト。 三、王室ハ現今ノ儘韓国ニ存在ス。 四、国民権ハ日本国民ト同等タルヘキコト。 五、政府ハ現今ノ如ク存在スルコト。 六、日本官吏ハ悉ク傭聘トシ、現今ヨリ其数ヲ減少スルコト。 七、人民ノ教育、軍隊教育ヲ振起スルコト。 八、本問題ハ韓政府ヨリ直接日本政府ニ交渉スルコト。」(海野-前掲書、645頁)実際に併合された朝鮮は、「直轄植民地」に当ります。〇閣議決定 1910.6.3「一、朝鮮ニハ当分ノ内、憲法ヲ施行セス、大権ニ依リ之ヲ統治スルコト。一、総督ハ天皇ニ直隷シ、朝鮮ニ於ケル一切ノ政務ヲ統轄スルノ権限ヲ有スルコト。一、総督ニハ大権ノ委任ニ依リ、法律事項ニ関スル命令ヲ発スルノ権限ヲ与フルコト。但、本命ハ別ニ法令又ハ律令等適当ノ名称ヲ付スルコト」(海野-前掲書、696-697頁)朝鮮には憲法が施行されず、天皇に直隷する総督が置かれ、「制令」の制定ほか一切の政務を統轄する権限をもって統治にあたります。政府は、「内地延長主義」の建前から、朝鮮等を「植民地」と称するのを嫌いましたが、「植民地」と明言している史料も少なくありません。〇閣議請議案「殖民地官庁雇員ノ俸給最高額増加ノ件」1919.11.3「今般内地官庁在勤雇員ニシテ特別ノ技術ヲ要セサルモノニ対シテハ一箇月月五拾円ヲ超エサル範囲内ニ於テ俸給ヲ支給シ得ルコトニ閣議決定相成タル処朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁及樺太庁竝其ノ所属在勤ノ本邦人タル雇員ノ俸給ニ付テハ…」→アジア歴史資料センター:A01200163700(公文類聚・第四十三編・大正八年・第十二巻・官職十・官制十・官等俸給及給与二(外務省~旅費)) 〇拓殖事務局『殖民地便覧』1923「本書ハ我ガ殖民地ト称セラルル朝鮮・台湾・樺太・関東州及ビ南洋群島ニ関スル大正十年中ノ概略ノ計数竝ビ既住数年間ノ比較ヲ掲ゲ以テ大勢ノ推移ヲ知ルニ便ナラシメタリ」→アジア歴史資料センター:B03041709500(帝国施政関係雑纂)〇拓殖事務局長「拓殖省設置ニ関スル意見書」1924「我国殖民地統治ニ関スル中央機関トシテハ内閣総理大臣管理ノ下ニ拓殖事務局ヲ置キ朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁、樺太庁及南洋庁ニ関スル事務ヲ掌ルノ外満鐵、東拓等特殊会社ヲ監督セシム」「惟フニ我国ニ於ケル殖民地ハ日清日露ノ両役、韓国ノ併合竝世界大戦ヲ経テ増大シ…」→アジア歴史資料センター:A03023581500(公文別録・内閣・大正十二年~昭和十九年・第一巻・大正十二年~昭和八年)〇朝鮮軍「朝鮮ニ於ケル青年訓練ニ関スル件」1929「大正十五年内地ノ青年訓練ノ施設創設セラルルト共ニ殖民地ニ於テモ出来得ル限リ青年訓練ヲ実施スヘキ旨ヲ閣議ニ於テ決定セラレシモ朝鮮人ノ取扱方等ノ特種ノ事情ニヨリ荏苒日ヲ閲シ昭和三年ニ至リ教育当局ノ交迭ト共ニ朝鮮ニ於ケル教育制度ノ根本改革ヲ為サントシ当時僅ニ三割ノ就学率ニ過キサル小学教育ヲ拡張シテ一面一校主義ヲ採リ別ニ国民学校ヲ設ケテ青年訓練ヲ為スノ案ヲ立テシモ…」→アジア歴史資料センター:C01001106400(大日記甲輯昭和04年)
Mar 28, 2005
-
韓国併合正当化のレトリック
韓国併合正当化のレトリックについて、以下の論文は、実に的確にまとめていると思います。○山中速人「日韓併合時の新聞報道と在日朝鮮人像」『在日朝鮮人史研究』4、1979.6「日韓併合の正当化のレトリックを注意深く探れば、その中に二つの相反する軸が存在することが読みとれる。一つの軸は、帝国主義的な侵略、植民地分割それ自体を肯定し正当化するという欧米的帝国主義の立場からの論理であり、他の一つの軸は、列強の植民地政策を批判しながらも『日韓併合』の特殊性を強調することで『合併』を侵略と切り離して正当化するというアジア・ナショナリズムの立場からの論理である」60頁前者の「欧米的帝国主義の立場からの論理」にあたるものとして、次のものが挙げられています。1.「朝鮮停滞論的レトリック」2.「例証的レトリック」→他の帝国主義国の植民地化を例示し、それを「世界の趨勢」として一般化する3.「進化論的レトリック」→強国による弱国の支配を普遍の原理とするまた後者の「アジア・ナショナリズムの立場からの論理」としては、次のものが挙げられています。4.「日鮮同祖論的レトリック」5.「形式論的レトリック」→条約の形式をもって、併合が韓国の意思だったとする以上は、併合当時の新聞の論調を分類したものですが、100年近くたった現在においても、ネット上では、同じレトリックが、往々にして、前者と後者のレトリックの整合性に思い至ることなく、再生産されているわけです。
Mar 16, 2005
-
主権線と利益線
山県有朋の外交理論、「主権線」「利益線」論はよく知られるところである。(山県有朋「外交政略論」1890.3、歴史学研究会編『日本史史料 4近代』岩波書店、1997、193頁)「国家独立自衛ノ道二ツアリ。一ニ曰、主権線ヲ守禦シ他人ノ侵害ヲ容レズ。二ニ曰、利益線ヲ防護シ自己ノ形勝ヲ失ハズ」では「主権線」、「利益線」とは何か。「何ヲカ主権線ト謂フ。疆土是レナリ。何ヲカ利益線ト謂フ、隣国接触ノ勢我ガ主権線ノ安危ト緊ク相関係スルノ区域是レナリ」「主権線」とは領土であり、「利益線」とは具体的に朝鮮であった。「我ガ国、利益線ノ焦点ハ実ニ朝鮮ニ在リ」山県の認識では、日本の領土を窺うような国はなく、「主権線」は安泰とみていたが、「利益線」に関しては、そうみてはいなかった。「今夫レ我ガ国ノ現況ハ、屹然自ラ守ルニ足リ、何レノ報国モ敢テ我ガ疆土ヲ窺覦スルノ念ナカルベキハ、何人モ疑ヲ容レザル所ナリト雖、進ンデ利益線ヲ防護シテ以テ自衛ノ計ゴトヲ固クスルニ至リテハ、不幸ニモ全ク前ニ異ナル者トシテ観ザルコトヲ得ズ」では、「利益線」を失うとどうなるのか。「利益線ヲ防護スルコト能ハザルノ国ハ、其ノ主権線ヲ退守セントスルモ、亦他国ノ援助ニ倚リ纔ニ侵害ヲ免ルヽ者ニシテ、仍完全ナル独立ノ邦国タルコトヲ望ムベカラザルナリ」他国の援助によって辛うじて独立を維持しているような国になるという。しかしこのような外交論の下では、「利益線」は際限なく、拡大し続ける。○石原莞爾「満蒙問題私見」1931.5「朝鮮ノ統治ハ満蒙ヲ我勢力下ニ置クコトニヨリ初メテ安定スヘシ」(歴史科学協議会ほか編『史料日本近現代史2』三省堂、1985、122頁)○関東軍司令部「北支問題に就て」1935.12「北支ノ満洲国ニ対スル地位ハ満洲国ノ治安ニ重大ナル影響ヲ有スル外経済的ニハ更ニ密接不離ナル関係ニ在リ」(同上、197頁)そして「利益線」維持に伴う犠牲者の存在、「英霊の犠牲の上に獲得した権益」という感情論は、撤退することを許さなくしていく。○香川県川島町民の声、1938.3「命を投げ出して占拠したところを意味なく返すのは勿体ない」(吉見義明『草の根ファシズム』東京大学出版会、1987、9頁)
Mar 1, 2005
-
ある会社員の出征
住友本社『戦没者書簡集』第一輯(1939年)より。1937年9月、応召された住友アルミニウム製錬株式会社のある会社員は、出動前夜、社に宛て次のように記している。「武器トシテハ参八式歩兵銃ノ他竹槍ノ用意アリ、匪賊ヤ便衣隊相手ニ颯爽ト竹槍ヲシゴクコトモアリナン、其ノ勇姿御想像アリタシ。 終ニ臨ミ皆々様ノ御健康ト社運ノ彌栄ンコトヲ祈念仕候」この会社員は、輜重兵であったが、竹槍は、万一の際、役に立ったのだろうか。所属の部隊は朝鮮を通過する。9月12日の手紙には次のようにある。「○○ノ街ハ全ク日本化シテ一寸朝鮮ダト云フ感ジハシマセン、十九日ハ丁度朝鮮ノオ盆ダ相デ小サイ子供ガハデヤカナ色彩ノ朝鮮服デ美々シク町ヲ歩イテヰルノガ目ニ着クダケデス」同月23日には、奉天に着いている。「奉天ノ街ハ人力車ト馬車ガ実ニ多イデス。街路樹モ実ニ豊富デスガ街ノ感ジハ何トナク穢イデス」「朝鮮デハ朝鮮人老若男女ノ熱烈ナ歓送迎振リニ全ク感激致シマシタ、奉天デハ日本人モ随分居ルノニ万歳一ツ聞キマセン、満鮮ノ相異ヲヨク表ハシテヰルト思ヒマス」10月定縣にて。「車馬ヲヒツパツテ支那ノ田舎道ヲ歩クノモ余リ楽デハアリマセン、第一塵ガ大変デス。村村ニハ華北乃華北人之華北、謀華北之永久和平福祉是因為千載一遇之機会等ノビラガ至ル処ハリツケテアリマス。支那人ガ日章旗ヲ立テテ湯茶ノ接待ヲシテクレマス」38年1月29日、邯鄲にて。「京都ニ居タ時ヨリ大分肥エタト戦友ガ申シマス、事実一寸肥エタ様デス。足ガ象ノ足ノ様ニ見エルノハ何シロ下ニ冬ノズボン下ヲ三枚(其ノ中ノ一枚ハ御恵送ノモノ)モ穿イテヰルノデスカラ蓋シ已ムヲ得マセン。特ニ釈明シテオキマス。呵々」「写真ノ防寒帽ハ仲々暖クテ宜敷イ。コノ事変デ日本ノ兎界ハ大恐慌ヲ来タシタ事デセウ」2月5日、食堂のおばさん(?)に宛てて「僕モオ蔭デ相変ラズ元気デスカラ御安心下サイ。貴女モ御元気デ何ヨリデスネ。朝晩遠イ所ヲ自転車ニランプヲツケテ通フノハ随分寒イコトデセウ。アノ寒サハ戦地ノ寒サニ劣ラナイデセウ」「我々ノ方ハ待機中ハ朝七時起床デス、ソノ点ハ会社ヨリ楽デス。待機モ随分永ク続キマシタガ愈々近日出動ノコトヽナリマシタ。当分ノ間ハ朝顔ヲ洗フコトモ出来ナケレバ夜モ寝レナイ夜ガ続キマス」
Feb 19, 2005
-
軍人すごろく
大濱徹也『天皇の軍隊』(教育社、1978)は、「兵士の心情と生活実感の場から軍隊」(4頁)をとらえた先駆的業績である。42~44頁では、『尚武須護陸』(1893年)が紹介されている。子どもたちにとっては、軍人は憧れの職業であり、このようなすごろくで遊んだのだろう。「大将」に加え、「靖国神社」も一種のゴールと見なされているようだ。なお書いていない目は、振り直しだろうか。【振出志】(小学校)123…軍人志願456…徴兵【軍人志願】16…幼年生徒トナル3…士官候補生トナル4…志願ナラズ兵卒トナル5…病気ノ為一年休学ス(一回休)→引用元には6とあるが、5と判断した【徴兵】135…合格シテ兵卒トナル46…不合格振出志ニ還ル【兵卒】13…士官候補生トナル25…軍曹ニ抜擢セラル4…軍律ニ触レ銃殺(退局)6…一年志願兵満期ノ後予備少尉トナル(少尉トナリ退局)【軍曹】1…曹長トナル4…軍律ニ触レ兵卒トナル5…曹長トナル6…士官候補生トナル【曹長】1…抜群ノ戦功ヲ以テ少尉ニ任ズ3…士官候補生トナル6…戦死、靖国神社ニ祭ラル【幼年生徒】125…士官候補生トナル3…病気一年間休学(一回休)6…学術劣等ニ付キ兵卒トナル【士官候補生】14…見習士官トナル3…一年後シテ見習士官トナル(一回休)6…学術劣等ニ付キ兵卒トナル【見習士官】1…貶セラレテ曹長トナル235…少尉ニ任ズ【少尉】156…中尉ニ進ム2…一年後中尉ニ進ム(一回休)3…戦死、靖国神社ニ祭ラル【中尉】2…一年後大尉ニ進ム(一回休)34…大尉ニ進ム5…一年間休職(一回休)【大尉】1…少佐ニ進ム4…一年間停職セラル6…予備トナル【少佐】1…戦時功ヲ以テ中佐ニ任ジ一年ノ後大佐ニ特進ス2…一年間休職3…中佐ニ進ム4…戦死、靖国神社ニ祭ラル【中佐】13…大佐ニ進ム2…一年間病気【大佐】2…戦功ヲ以テ少将ニ進ム3…一年間休職4…名誉進級少将トナル(賞品ヲ受ケ退局)6…年齢満限後備トナル(退局)【少将】1…中将ニ進ム2…願ヲ以テ一年間各国ヲ巡遊ス3…予備トナル【中将】1…予備トナリテ貴族院議員トナル3…歴戦ノ功ヲ以テ大将トナル【大将】【靖国神社】
Jan 26, 2005
-
南京事件へのアプローチについて
南京事件に関心を持つ際のアプローチに関して、南京事件をめぐる議論に関する本ではなくて、事件そのもの、事実として何が起きたのかという点から入ってほしいと思います。被害者数に関しても同様です。南京事件をめぐる議論に関する本を読んで、議論のされ方に疑問を感じたからといって、事件そのものの存在の否定に向うのではなく、何が起こったのか→では被害者数は?という順番が普通のアプローチではないでしょうか。そして何が起こったのかという史実を確定する作業に関しては、これまでの歴史学研究の蓄積を無視することは、できないでしょう。歴史学者以外が書いたものには、これまでの研究を全く無視していたり、漠然と歴史学者に否定的だったりしますが、歴史学者が一般向けに書いたものもありますから、それからスタートしても、全然遅くはない、何も不都合なことはないと思います。笠原十九司『南京事件』(岩波新書530、1997)がオススメです。南京事件に関しては、何か漠然と、おどろおどろしいイメージがあるかと思いますが、事実はどうだったのかということについて、一定のイメージ、事件の全体像がつかめると思います。
Jan 23, 2005
-
陸軍省年報
『陸軍省年報』(龍渓書舎、1990年復刻)を購入する。国立公文書館に所蔵されているもので、明治8年~19年の統計を中心に纏められている。明治20年以後は、『陸軍省統計年報』があるが、それより前の時期の人員・経費・衛生・徴兵などのデータがしっかり揃っている。ただ縮刷しているので見づらいところもある。興味深いのは、数値だけではなく、陸軍自身の現状に対する認識が記されていることである。例えば、明治九年の徴兵事務に関して、「九年各軍管徴兵名簿人員ヲ以テ之ヲ八年ニ比ルニ稍多キヲ加ヘタレレハ定額ノ常備徴員ハ已ニ充足シ補充兵モ亦其定員ニ充ツルヲ得タリ」(第一年報、41頁)とある。この時期は、徴兵忌避の横行が強調されるが、定員を満たせないほど、徴兵事務が滞っていたわけではないことがわかる。
Jan 22, 2005
-
畑俊六日誌
『畑俊六日誌』を購入する。元帥陸軍大将畑俊六の、1929年10月~45年3月までの日記と巣鴨刑務所在監中の「獄中手記」が収録されている。1月17日付の記述をあげてみよう。1938/1/17「蒋より回答なく十五日閣議及連絡会議となり、参謀本部側は未だ脈が切れたるものと認めあらず、内閣側は既に脈なきものとし、其間内閣と参謀本部側とは意見の相違を来したることゝなりたる…」蒋介石との和平工作に関して、内閣側がそれに見切りをつけようと強硬的なのに対し、それまで戦争をリードしてきた参謀本部側が、反対に、和平工作継続を主張するという興味深い局面である。1944/1/17「東南太平洋方面の敵機依然優勢にして二〇〇〇機を算するものゝ如く、我は之に対しラバウル方面に海軍一五〇機、ニューギニア方面に陸軍八〇機に過ぎず」「絶対国防圏」設定から三ヶ月半で、圧倒的な戦力差が出来てしまっている。
Jan 17, 2005
-

修論提出おめでとう
修論提出の打ち上げと新年会とをかねて、行った。大学院拡充に伴い、院への進学が増えている。また“生涯学習”に相応しく、仕事をしながら、もしくは休職して、また定年してから、大学院に入学する人も多くなっている。こっちも、そのバイタリティーに負けないように、“若者”らしく、活動していきたいところだが、近頃、深酒は体力的にきつくなってしまった…。
Jan 16, 2005
-

拾骨
市唯一の火葬場で、祖父のお骨を拾う。お骨を拾うのは二度目である。曾祖母の時は、独特の臭いが印象に残っていた。しかし、今回はそれほど臭いを感じなかった。柩に入れた十円玉も形を保たないほど、熔けてしまい、小石のようだ。昔より高温になっているらしい。立派な体格で、軍隊でも優秀であった祖父の骨。脆く崩れ、箸でしっかり持つことができない。骨壷に入れたそばから、係りの者が擂り棒のようなもので、ザクザクと砕いていったのには、少し驚く。最後に頭とあごの骨が、そのままの形で納められた。骨壷の入った箱を両手でもつ。3kgか4kgくらいか。これだけになってしまった。しかしその重みが体の芯に響く。
Jan 9, 2005
-

卒論提出おめでとう
12月末は、卒論提出の時期。卒論の校正・製本、提出後の打ち上げが研究室の年中行事となっている。ほかの研究室ではやっていないところもあるらしい。大学の制度的にも、研究室としてのまとまりは、緩くなって来ている。学部生は、必ずしも特定の研究室に所属しなくてもよくなった。当初は煩わしいと思うこともあったが、全部個人で、というのはやはり寂しい。これまで所属した研究室やクラスが偶々まとまりがあって本当にラッキーだった。自分は率先してリーダーシップを執れるタイプではないが、自分のようなタイプばっかりのクラスだったら、つまらない生活だっただろう。時々そういうタイプばっかりの、煮え切らないグループで行動する場面に遭遇することもあるが、リーダーシップを執ろうと、キャラにないことをすると、上手く行かないことが多いんだよね。何はともあれ、卒論提出おめでとう~
Jan 2, 2005
-
在京軍人の三が日
在京の軍人は、官位・勲等に応じて、年始の儀式に参加した。(海軍省人事局『在郷士官参考事項便覧』1942年)1月1日〇拝賀大将(親任官):午前9時40分参内中少将(高等官1・2等):午前10時30分参内1月2日〇参賀大佐以下:午前9時~午後4時1月3日〇元始祭大将:午前9時30分賢所に参集中少将:総代一人同上〇賢所参拝大佐以下(勅任官同待遇?):午後0時30分~1時30分・また1~2日のうちに、 大宮御所、高松宮、伏見宮、山階宮、久邇宮邸参賀があった。・服装は軍装で勲章記章すべて。・拝賀、参賀は夫人同伴。・地方在住者は、賀表を「奉呈」した。
Jan 1, 2005
-
石橋湛山の靖国神社廃止論
石橋湛山は、「靖国神社廃止の議」1945.10.13「社論」において、靖国神社の廃止を主張した。(『石橋湛山評論選集』東洋経済新報社、1990、391-392頁)湛山は、第一に「国際的立場」に関して指摘する。大東亜戦争の戦没将兵を永く護国の英雄として崇敬し、その武功を讃える事は我が国の国際的立場において許さるべきや否や。…ただに有形的のみではなく、また精神的武装解除をなすべしと要求する連合国が、何とこれを見るであろうか。第二に、同神社が「怨恨の記念物」となることを懸念した。靖国神社の主なる祭神は明治維新以来の戦没者にて、殊にその大多数は日清、日露両戦役および今回の大東亜戦争の従軍者である。しかるに今、その大東亜戦争は万代に拭う能わざる汚辱の戦争として、国家をほとんど亡国の危機に導き、日清、日露両戦役の戦果もまた全く一物も残さず滅失したのである。遺憾ながらそれらの戦争に身命を捧げた人々に対しても、これを祭ってもはや「靖国」とは称し難きに至った。とすれば、今後この神社が存続する場合、後代の我が国民はいかなる感想を抱いて、その前に立つであろう。ただ屈辱と怨恨との記念として永く陰惨の跡を留むるのではないか。もしそうとすれば、これは我が国家の将来のために計りて、断じて歓迎すべき事でない。第三に、「怨恨の記念物」となることは、敗因解明の障害となり、戦没者遺族にとっても望むところではないとする。言うまでもなく我が国民は、今回の戦争がどうしてかかる悲惨の結果をもたらせるかをあくまで深く掘り下げて検討し、その経験を生かさなければならない。しかしそれにはいつまでも怨みをこの戦争に抱くが如き心懸けでは駄目だ。そんな狭い考えでは、おそらくこの戦争に敗けた真因をも明らかにするを得ず、更生日本を建設することはむずかしい。…記者は戦没者の遺族の心情を察し、あるいは戦没者自信の立場において考えても、かかる怨みを蔵する神として祭られることは決して望む所でないと判断する。
Dec 31, 2004
-
ドイツ人捕虜収容所のクリスマス
以下は、第一次大戦の際、習志野に収容されたドイツ人捕虜の日記から、クリスマスの時期のものを引用してみる。(習志野教育委員会編『ドイツ兵士の見たニッポン』丸善株式会社、2001)一九一五年一二月二三日~二六日聖なる夕べ、クリスマスのお祝いが始まった。たくさんのクリスマス・ツリーや緑の葉が、居室を彩った。午後五時に、シュポーア宣教師によってクリスマスの礼拝が行われた。…六時には我々の居室で、クリスマスプレゼントが分配された。ある日本の石鹸工場が、一人一人に石鹸一箱と歯磨粉を寄付してくれた。一本のビールの他に、それぞれ胡桃や果物をたっぷりもらった。私は、おまけに財布と、くじ引きで煙草二〇本にテニスボール一個をもらった。夜にはポンチと豚の焼肉、ソーセージ・スープが出された。将校は、将校だけで集まって祝っていた。二四日には朝食に、クリスマスのシュトーレン(引用者注―パウンドケーキの一種)が出された。引き続き水の汲み上げ、誰もが二〇〇回押さなければならなかった。一〇時に、フィッシャー宣教師による礼拝。午後は大音楽会。夜は再び、夜中の一二時まで大騒ぎとなった。…酒保ではビールが、一本残らず売り切れとなった。このお祝いの三日間で、ほぼ三〇〇〇リットルが販売された。収容所では日本側から寄付があるなど、物資が豊富であり、それなりに充実したクリスマスを過ごしたようだ。一九一六年一二月二四日クリスマス。温かい風呂のあと、お祝いの服を身に着ける。短い礼拝と、いつもよりかなりうまい昼食の後、五時頃から本来の祝祭が始まった。…クリスマスの二日目は、ミリエス楽長の音楽と、必要な飲み物で過ぎていった。なぜならば、大きな金額の義捐金が届いたのだ。新しい歌を歌う。「ビールがほとばしる、ビールを持って来い! 俺たちが死ぬとき、はした金なんぞ約にはたたぬ」。いろいろ不愉快な事件が起こったせいで、日本人はビール禁止令を出した。酒保は、これ以上ビールを出すことが出来なくなった。「お祝いの服」とはどんなものだろうか。また俘虜たちは少々ビールを飲みすぎたようだ。日本のビールを気に入ったのだろうか。ビール禁止令も大晦日には解けており、その際にはまた祝宴がおこなわれている。一九一九年のクリスマスイブは静かなものとなった。翌日には故郷への帰路に着くことになっていたのだ。クリスマスの聖なる夜だった。誰も、祭のこと考えていなかった。まだ何を、うわべだけ祝おうというのだ! 実に静かに、我々は並んで座った。日本人からの贈り物が配られた。東京にある日本の赤十字の婦人会が、捕虜一人一人に、日本の文字で献辞のついた二枚の格調高い版画を提供してくれたのだ。日本の政府からは捕虜全員に、繊細な磁器のティーセットをくれた。以前述べたように第二次大戦時に日本は、宣戦の際、国際法遵守を明文化しなかった。第一次大戦期には、後の戦陣訓につながるような捕虜蔑視感が現われはじめていた。しかしドイツ人捕虜に対しては、丁重な扱いがなされていたようだ。日本人とドイツ人の交流もなされた。ドイツ人捕虜から、クリスマス用菓子作りの願出があった際、それは「邦人ノ練習」にも供されている。(「菓子製造販売ニ関スル件照会」板東俘虜収容所長より軍務局長宛、1917.12.7、アジア歴史資料センター:C03024851400)
Dec 26, 2004
-
近代思想の教科書 3.マルクス主義-C.経済学説
綾川武治『近代思想と軍隊』(兵書出版社、1929)より、マルクス主義の骨組みの三つ目、余剰価値説について(57-62頁)。商品が生産者の手から出て消費者の手に移り行く道程を商品の流通といふ。マルクスは上述の如き流通の形(引用者注…商品―貨幣―商品)を「単純なる商品流通形態」と名づける。 然るに、右の「買うために売る」といふ単純なる商品流通形態から、次第に「売るために買う」といふ新しい流通形態が発達して来て、両者が並行的に行はれるやうになる。(中略)売るために買ふことの唯一の動機となるものは、かゝる売買の結果として一の余分な貨幣を得んとするに在る。そこで、この交換の行程が完全に意義を現はすためには、貨幣―商品―(貨幣+△貨幣)とならねばならぬ。△貨幣は交換の結果として新たに付け加へられた所の貨幣である。この新たに付け加へられる貨幣の部分が、即ち「余剰価値」と称するものである。商品―貨幣―商品といふ流通形態に於いては、最後の商品が手に入つて消費に帰したとき、流通は終りを告げる。然るに、貨幣―商品―貨幣といふ流通形態に於いては、最後の貨幣が更に第二の流通の出発点となるのであつて、この関係は無限に連続して行く。(中略)商品―貨幣―商品に於ける貨幣は、使用価値獲得の手段に過ぎないが、資本家の行ふところの貨幣―商品―貨幣なる流通行程に於いては、使用価値は手段であつて、反対に貨幣が目的となる。資本家はこの様に、その所有する所の貨幣価値に絶へず新しき価値を付け加へることを目的として、貨幣を利用する。かく利用される貨幣を資本といふのである。(中略)かくてマルクスによれば、「資本家的生産とは単に商品の生産のみに非ずして、本質的には余剰価値の生産である」従つて資本家的生産の目的は生産の結果たる商品の価値を其の生産に要したる労働力及び生産手段の価値より大ならしむる事にある。而してこの生産物たる商品の価値が其の生産に要したる労働力及び生産手段の価値に超過する部分が余剰価値なのである。此の場合に於て生産の道具となるものは其の性質上夫れ自体に於いては価値を増減し得ないものであるから、それの価値は商品の価値を形成するところの生産の道程に於いても毫も増減する事はない。従つて生産物たる商品の価値をしてそれに要したる労働力及び生産手段の価値より大ならしむるもの、即ち余剰価値を創るものは、労働力にありと云はなければならない。斯くの如く労働力が余剰価値を創造し得る所以は労働力が其の価値以上の価値を創造し得る特殊の使用価値を有するに依り、而して又労働力の売手は他の一般商品の売手と同じく其の交換価値を手に入れて其の使用価値を提供するからである。即ち後者を与へることなしに前者を取る事は出来ないのである。かくて労働者は彼の一日の生命を支ふるに六時間の労働にて足るに拘らず、他面に於いてその労働者は、生活に必要なるより以上の労働力、例へば十二時間も働き得るのみならず、資本家の方でもその労働力を六時間分の価値で買取つて(即六時間分の労働に相当する価値の賃金を支払つて)労働者に十二時間以上もの労働を要求する。従つて其の労働力の価値(労働力の生産に必要なる生活資料の原費)と労働力の使用価値(労働力が生産の道程に於いて実現し得る価値)との間には必然に差額を生ずる。此の差額こそ余剰価値に相当するのである。かくの如くにして余剰価値は労働者の労働力より生じたものであるから、当然彼等労働者に帰すべきに拘らず現代の資本家的生産社会に於いては、之を資本家に掠奪せられてゐるのである、と。◎余剰価値説労働(元々の価値+余剰価値)>賃金(元々の価値に相当する分のみ)→余剰価値は資本家の手元に。労働者に帰すべき。六時間、十二時間の話と労働力の価値、使用価値の話は次元が違うように思えるが…。綾川でもマルクス主義を簡単に要約するのは難しい。
Dec 23, 2004
-
近代思想の教科書 3.マルクス主義-B.社会学説
綾川武治『近代思想と軍隊』(兵書出版社、1929)より、唯物史観について(45-48頁)。B.社会学説―唯物史観唯物史観は、社会の構成―即ち成り立ちとその変遷の法則を説明したものであつて、その根本の考を経済の関係、特に「生産力」といふものに置くのである。…マルクスに従へば、社会の実際上の土台をなすものは経済であつて、社会の制度や思想は、その社会に於てどういふ物がどういふやうにして生産せられ、又その生産物がどのやうにして分配せられるかによつて、決定せられるものである。(中略)建物に比べて見れば、経済の構造が此の建物の土台であつて、法律や政治の制度組織は此の土台の上にのつかる「上部構造」である、さうして此の土台であるところの経済の関係を作り上げる最根本のものは、生産力だといふのである。(中略)唯物史観に従へば、生産力は社会の構成並に変遷の動力であつて、生産力が変化すれば、それに伴つて全社会が変遷されるのである。即ち、社会の物質的生産力がある程度の発達の段階に達するとその段階に相応した生産関係を生じ、此の生産関係が法律化されて諸種の制度を生む。此の法律上の制度がその内部にはたらく生産力とうまく調和して居る間は制度と生産力との相互作用が円滑に行はれて生産力の発達が促される。ところが、法律や政治の制度が固定的な動かないものであるに反して、生産力は絶えず進歩してやまないものであるから、時が経つに従つて此の両者の間にへだたりが出て来る。さうして両者の間の不調和が著しい程度に達したとき、制度が邪魔になつて生産力の発達が阻害せられるやうになる。……斯うして、生産力と制度との衝突が現はれ、社会革命の時代が開始せられる。(中略)而して物質的生産力と現在の経済組織との矛盾衝突が、人間の意識に反映するときに、此処に階級間の利害の衝突となり、階級闘争となつて現はれる。物質上経済上の矛盾が人間の意識に反映して階級闘争を惹起し、階級闘争の歴史が社会発達の歴史を織りなして行くのだといふ道程を書き示したのは共産党宣言である。マルクスの学説の中では、経済上の変動から来る社会変革の原則を唯物史観が説明し、経済上の矛盾が人類の意識に反映して決戦するに至るところの関係は、階級闘争説が説明することになつて居る。◎唯物史観生産力と法律・政治制度の不調和↓階級間の衝突↓社会変革
Dec 21, 2004
-
近代思想の教科書 3.マルクス主義-A.哲学説
綾川武治『近代思想と軍隊』(兵書出版社、1929)より、マルクス主義について(37-41頁)。彼の所謂マルクス主義とは、生産機関の共有、階級の廃絶、国家の死滅を主たる内容とする社会主義の社会が、現在の資本主義の社会の次に、階級闘争による社会革命の結果、必ず到来するものであるといふことを説明するところの一つの学説であり、同時にそれを企て求めるところの一の主張である。(中略)マルクス主義は、今日学問の分類の上から之を見るときには哲学と、社会学と経済学の三方面に跨つて居る次第なのである。マルクスの哲学としては所謂唯物論的弁証法(唯物弁証法)があり、社会学説としては、所謂唯物史観があり、経済学説としては所謂余剰価値説がある。マルクス主義は此の三つの骨組みから成り立つて居るのである。A哲学説―唯物論的弁証法ヘーゲルに従へば世界は一つの絶対なる観念又は精神の現はれであつて、此の絶対精神は次のような三つの段階をとつて発展するものである。(中略)此の三つの段階は普通「正」「反」「合」といふ言葉によりて云ひ表はされて居る。さうしてこの三つの段階をとつて進む発展の理法を称して弁証法といふのである。(中略)マルクスは右のヘーゲルの弁証法とフオイエルバツハの唯物論とを結びつけて彼独特の唯物論的弁証法、簡約して唯物弁証法といふものを作り上げたのである。(中略)要するに、ヘーゲルは絶対的な精神を以て世界の本体となし、万物は此の絶対精神の弁証法的発展であると観たのに反して、マルクスは物質を以て世界の本源と観、此の物質が宇宙の弁証法的活動の主体であるとしたのである。◎マルクス主義の骨組みA.哲学説…唯物論的弁証法B.社会学説…唯物史観C.経済学説…余剰価値説
Dec 20, 2004
-
近代思想の教科書 2.社会主義
綾川武治『近代思想と軍隊』(兵書出版社、1929)より、今回は、社会主義について(11-12頁)。社会主義は、右に述べた自由主義特に経済上の自由主義、その現はれとしての資本主義に対する反動として生れて来た思想であつて、資本主義的経済組織の土台をなすところの個人的営利主義の弊害を矯めやうといふ考へから出発して、その反対の極端を主張するに至つたものである即ち、資本主義の社会では、財産の私有を許すから財産を余計に持つたものと殆ど之を持たないものと区別、金持と貧乏人との区別、大地主と小作人との区別が出来、かういふかけへだたりが出来るところからいろいろな社会の不幸が生れて来る。それで此の私有財産といふものはやめなければならぬ、土地や、資本の生産手段(工場とか機械とか)を個人の私有とすることをやめて之を国家なり社会なりの公有若くは共有に帰してしまはなければならぬ。又今までの社会では、個人の自由は競争に放任したから、資本のあるものは資本の力で益々金持になり、貧乏人は一層貧乏人になる。即ち金持ちと貧乏人とのへだたりが益々大きくなつて来る。政府が個人の競争を制限しないで自由に放任して置けば資本の無いものは資本を豊富に持つて居るものにかなひつこない。であるから、国家なり社会なりの力で自由競争を制限するばかりぢやない、一そこんな自由競争といふものを絶対に禁止してしまつた方がよい、そして生産も分配も、国家や社会の公けの力で行つて、今までのやうに個人の自由にまかせ置いてはならない、とかう主張するのである。即ち社会主義は、今日の資本主義制度の根本をなして居るところの、私有財産を廃止し、自由競争を禁止し、土地や生産手段の公有を実現して、この基礎の上に新しい社会を打ち建てやうとする思想である。◎社会主義私有財産の廃止自由競争の禁止→土地や生産手段の公有へ
Dec 19, 2004
-
近代思想の教科書 1.自由主義
綾川武治『近代思想と軍隊』(兵書出版社、1929)では、近代思想について、シンプルに判りやすく纏められている。この本には幾人かの将校から序文が寄せられており、この本で近代思想について学んだ軍人もいたかもしれない。後学のため、重要な箇所を保存しておく。今回は、自由主義に関する箇所(5-8頁)。(読みやすくするため、適宜改行した)すべて社会とか国家とかいふものは一人一人の人間が集つて形作くつたものであつて、結局は個人の利益幸福が駄目(引用者注―為)である。個人が国家に対して服従するといふことも、それぞれの個人の自由な意思に基いてさうするのであるから、国家の権力も絶対のものではない。社会の諸の制度はいづれも悉く個人の自由を保護するための手段であり、政府は個人の福利のための機関である。個人の生命財産の安固をはかる範囲内でだけ、個人の自由を制限することが出来る。社会国家が主ではなくて、個人の安寧幸福が主である。而してなるべく個人の自由に放任して置いた方が社会の進歩も容易であり速かである。理想の社会は各人が自然に自由を享け楽しむことが出来るやうな社会である。かういう考え方が自由主義の思想である。即ち自由主義の核心は個人主義、個人本位主義である。(中略)右に述べた自由平等天賦人権の説は政治上の自由主義であるが、十八世紀の末頃に及んで経済上の自由主義が大に盛んとなるに至つた。(中略)即ち経済上の自由主義は個人の利己心の働きを是認し、個人同志の経済競争を自由に放任しなければならぬとする主張を中軸とする思想である。であるから、個人の財産、私有財産といふものは絶対的なものであると承認すると共に、富める者益々富み、資本を持つた者は益々その資本を増やして行くことが出来る結果となるのである。恰度政治上の自由主義が、議会主義代議政体となつて現はれたやうに経済上の自由主義は実際上の制度としては資本主義という制度をつくり上げたのである。資本主義といふ制度は、経済上の自由主義の現はれであり、個人の自由競争と私有財産制度の絶対といふ考えとを基礎とするものである。(中略)資本主義といふと、社会主義や自由主義や国家主義といふやうに一つの思想又は理論を現はすものであると考えるかも知れぬが、此の言葉は決して社会思想とか経済理論とかを意味するものではなく、一つの社会組織、或る経済制度をいひ表はす言葉なのである。(中略)議会主義と資本主義は自由主義の双児なのである。◎自由主義政治上…議会主義経済上…資本主義 →思想や理論ではなく制度
Dec 18, 2004
-
戦争の終わらせ方
〇「対米英蘭蒋戦争終末促進ニ関スル腹案」41.11.151941年11月、大本営政府連絡会議が決定した戦争終結の見通しは、次のように計画されていた。(歴史科学協議会『史料日本近現代史2』三省堂、1985、268-269頁)「速ニ極東ニ於ル米英蘭ノ根拠ヲ覆滅シテ自存自衛ヲ確立スルト共ニ更ニ積極的措置ニ依リ蒋政権ノ屈服ヲ促進シ独伊ト提携シテ先ツ英ノ屈服ヲ図リ米ノ継戦意思ヲ喪失セシムルニ勉ム」「日独伊三国ハ単独不媾和ヲ取極ムルト共ニ英ノ屈服ニ際シ之ト直ニ媾和スルコトナク英ヲシテ米ヲ誘導セシムル如ク施策スルニ勉ム」英国を「屈服」させることによって、米国の「継戦意思ヲ喪失」させようというのである。米国に決定的打撃を与え、「屈服」させられるとは、考えていなかったようだ。これでは、独伊の戦いぶりに大きく制約されてしまう。しかも、国力で劣るにも拘らず、長期戦となる公算が高い計画であった。
Dec 15, 2004
-
満州は「生命線」か
1906年、参謀本部作戦課高級課員であった田中義一は、守勢作戦計画を立案し、そのなかで、「本国及韓国々境ノ防禦ニ全力ヲ傾注シ関東州ハ之ヲ放棄ス」としている。田中は、「関東半島ハ我ガ租借地ニシテ官民ノ財産亦尠カラズ、且ツ曩キニ多大ノ犠牲ヲ供シテ得タル所ニシテ我歴史上ニ一光彩ヲ放テシ土地ニアラズヤ、故ニ之ヲ放棄スルハ国家ノ体面ヲ損シ且ツ情ニ於テ忍ヒサル所」といった議論に関して、「国運ヲ賭シテ強敵ト交戦スル場合ニ於テ殆ンド何等ノ価値ヲモ有スルモノニアラズ、且情ニ熱キハ戦略家ノ最モ忌避セザルベカラザルモノ」と主張する(以上「随感雑録」)。すなわち田中は、戦略面から冷静に判断し、日露戦争により、多大な犠牲を出して勝ち取った、満州権益を放棄することも想定していたのだ。(小林道彦『日本の大陸政策 1895-1914』南窓社、1996年、161-162頁参照)後代の指導者は、田中のような冷徹な判断を下せただろうか。多くは、「英霊の犠牲の上に獲得した権益」という感情論に縛られ、抜き差しならない状況に突き進んでいったのではないだろうか。【関連書籍】黒野耐『日本を滅ぼした国防方針』文春新書、2002⇒「敗戦の原因はどこにあったのか」 「大正期以降の日本軍の弱点は、まさに日本近代社会の弱点そのものだった」→楽天フリマで購入する(300 円)→楽天ブックスで購入する(767 円)
Dec 12, 2004
-
戦争のやり方
1941年11月3日、参謀総長と軍令部総長が天皇に上奏した初期作戦計画は、次のようであった。(歴史科学協議会『史料日本近現代史2』三省堂、1985、266-278頁)まず陸軍について。「南方作戦ノ目的ハ東亜ニ於ケル米国、英国及蘭国ノ主要ナル根拠ヲ覆滅シ南方ノ要域ヲ占領確保スルニ在リ」「占領スヘキ範域ハ比律賓、瓦無島、香港、英領馬来、緬甸、『ビスマルク』諸島、爪哇、『スマトラ』、『ボルネオ』、『セレベス』、『チモール』島等トス」「支那ニ対シテハ帝国海軍ト協同シ概ネ現在ノ態勢ヲ保持スルト共ニ支那ニ於ケル米英等敵側諸勢力ヲ掃滅シテ政謀略ト相俟チ対敵圧迫ニ努メ蒋政権ノ屈服ヲ期スルニ在リ」「北方ニ於テ米露カ提携シ或ハ露軍単独ニテ我ニ挑戦シ来ル場合ニ於テハ機ヲ失セス支那及内地方面ヨリ所要ノ兵団ヲ転用シ速ニ極東露領ノ敵航空勢力ヲ撃破スルト共ニ爾後ノ攻撃ヲ準備シ次テ成ルヘク速ニ烏蘇里方面ノ敵ヲ撃破シテ同地方ノ要域ヲ占領ス」作戦の対象となっている中国、和蘭に対して宣戦布告を行っていないのは、すでにみた通りである。資源・工業力で劣る日本が、英米蘭と戦い、中国と戦い、さらにロシアにも備えるという多方面作戦が、本当に可能だと考えていたのだろうか。つぎに海軍について。陸海軍協同を除き、海軍単独の作戦は次のようであった。「開戦劈頭比島及馬来ニ対スル先制空襲ト成ルベク時ヲ同ジク致シマシテ第一航空艦隊司令長官ノ率ヰル航空母艦六隻ヲ基幹トスル機動部隊ヲ以チマシテ布哇在泊中ノ敵主力艦隊ヲ空襲致シマス」「攻略作戦ガ終リマスレバ第一、第二艦隊ハ成ルベク速ニ内地ニ帰還致致シマシテ補給修理ヲ行ヒ敵艦隊ノ出撃ニ備ヘ 第三艦隊ハ菲律賓及蘭印方面ノ防備ニ 南遣艦隊ハ新嘉坡及『スマトラ』方面ノ防備ニ任ジマス」「長期戦トナリマスレバ海上交通線ノ保護竝ニ通商破壊戦ガ其ノ主体ヲ為シマスノデ内戦部隊ノ外第三艦隊、南遣艦隊及聯合艦隊ノ水雷部隊ノ大部ヲ以チマシテ内地沿岸、日本海、黄海、東支那海等ノ海上交通路ヲ確保致シマスル外 南方地域ト帝国トノ間ノ海上交通線ノ確保ニ任ジマス」「又敵ノ企図スル通商破壊戦ヲ困難ナラシメマス為敵ガ潜水艦基地トシテ利用スルコトアルベキ濠州北部、『ニューギニヤ』其ノ他南太平洋諸島ニ在ル敵前進基地ノ奇襲破壊ニ努メマス」海軍も敵主力艦隊を警戒しつつ、南方占領作戦を実施し、日本と南方の海上路を警護するという八面六臂の活躍が求められた。このような計画を立てたものの、軍令部総長永野修身は、「開戦二ヶ年の間必勝の確信を有するも……将来の長期に亘る戦局につきては予見し得ず」と言い、東条首相兼陸相も、「戦争の短期終結は希望する所にして種々考慮する所あるも名案なし。敵の死命を制する手段なきを遺憾とす」と述べたように、勝利への自信のなさを表明していたのも事実であった。(参照:木坂順一郎『昭和の歴史7 太平洋戦争』小学館、1982年、32-33頁)【昭和の歴史(11冊揃)】
Dec 10, 2004
-

LOMOを購入
今回は、日記です。急に欲しくなったLOMOをヤフオクで買った。思っていたよりコンパクト。元来、三日坊主で飽きやすい性格だが、今度の趣味は…。おすすめLOMOサイト・CMEHAPPY・LOMO Chips
Dec 9, 2004
-
対英米宣戦の詔書を発す
1941年12月8日、午前11時37分、宣戦の詔書が天皇によって裁可され、正午にラジオで放送された。詔書の構成は、次のようになっている。1.序文2.宣戦相手国の明示・臣下への呼びかけ・国際法の遵守3.宣戦理由の具体的説明1に関して、次のようにある。「天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚ヲ践メル大日本帝国天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス」日清、日露、第一次大戦と文面はほぼ同じであるが、太平洋戦争の際の詔書では、それまで「大日本帝国皇帝」とされてきた箇所が「大日本帝国天皇」となっている。2の宣戦相手国に関して、「朕茲に米国及英国ニ対シテ戦ヲ宣ス」とのように、オランダ、中国の重慶政権については明記されていない。次に臣下への呼びかけについては、「朕カ陸海将兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ励精職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ尽シ億兆一心国家ノ総力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ」とある。呼びかけの対象に、第一次大戦までの「陸海軍」、「百僚有司」だけでなく、総力戦にふさわしく、「衆庶」が加えられている。また国際法の遵守については、「凡ソ国際条規ノ範囲ニ於テ一切ノ手段ヲ尽シ必ス遺算ナカラムコトヲ期セヨ」(第一次大戦)とのように第一次大戦までみられた同該当箇所が、抜け落ちてしまっている。3の宣戦理由に関しては、長くなるので全文の引用は控えるが、中国政府は長年、「帝国ノ真意ヲ解セス」、「東亜ノ平和ヲ撹乱」してきた↓国民政府は「更新」したが、「重慶ニ残存スル政権」は、「米英ノ庇護」を恃み、米英はそれを支援し、「東亜ノ禍乱ヲ助長」した↓さらに米英は「平和的通商」を妨害し、「経済断交」を実行した↓日本は、「自存自衛ノ為」、起ち上がるほかはないという論旨になっている。中国との戦争を処理できないうちに、戦線が拡大し、状況の困難化を招いていったのがよくわかる。日中戦争を終結できないフラストレーションが、対英米宣戦により、戦争終結への期待感、ある種の爽快感をもたらしたかも知れないが、実際にはより悪い結末が待っていた。以上のように宣戦の詔書からも、太平洋戦争がそれまでの戦争とは一線を画すものであったことが、窺える。(参照:木坂順一郎『昭和の歴史7 太平洋戦争』小学館、1982年)【昭和の歴史(11冊揃)】
Dec 8, 2004
-
ハル・ノートの内容
日米の決裂を決定づけた「ハル・ノート」は、アジア歴史資料センターで、オンライン上から閲覧できる(レファレンスコード:B02030747200、38枚目)。以下、要点を引用してみる。第二項 合衆国政府及日本国政府ノ採ルヘキ措置一、合衆国政府及日本国政府ハ英帝国支那日本国和蘭蘇聯邦泰国及合衆国間多辺的不可侵条約ノ締結ニ努ムヘシ三、日本国政府ハ支那及印度支那ヨリ一切ノ陸、海、空軍兵力及警察力ヲ撤収スヘシ四、合衆国政府及日本国政府ハ臨時ニ首都ヲ重慶ニ置ケル中華民国国民政府以外ノ支那ニ於ケル如何ナル政府若クハ政権ヲモ軍事的、経済的ニ支持セサルへシ九、両国政府ハ其ノ何レカノ一方カ第三国ト締結シオル如何ナル協定モ同国ニ依リ本協定ノ根本目的即チ太平洋地域全般ノ平和確立及保持ニ矛盾スルカ如ク解釈セラレサルヘキコトヲ同意スヘシすなわち、日本の軍隊の中国・仏印から一切撤退すること、重慶政権のみを中国の正統政府と認めること、三国同盟を否定し、日・米・英・ソ・中・蘭・タイ間の多辺的不可侵条約締結を含むもので、日本がこれまで採ってきた方針を全部否定するものであった。よく、日本が満州事変以前に戻ることを要求したものである、と言われる。しかし、今回「ハル・ノート」を読み直してみて、驚いたのは、次の条項(第二項の五)であった。五、両国政府ハ外国租界及居留地内及之ニ関連セル諸権益並ニ一九〇一年ノ団匪事件議定書ニ依ル諸権利ヲモ含ム支那ニ在ル一切ノ治外法権ヲ抛棄スヘシ義和団事変によって列強各国が得た軍隊を駐屯させる権利の放棄も含んでいたのだ。満州事変からさらに義和団事変まで遡ることになる。米国は、1938年にすでに、京津地方から駐屯軍を撤退させ、1941年11月には上海駐屯軍を引き揚げている。【太平洋戦争開戦経緯に関する本】
Dec 7, 2004
-
公開された小津安二郎の陣中日誌
『諸君』2005年1月号では、小津安二郎の陣中日誌が65年間の封印を解かれ、公開されている。小津は、1937年9月召集、近衛歩兵第2連隊に所属し、39年7月除隊となるまで、軍曹として華南方面の作戦に従事した。小津は、映画のことが頭から離れず、戦闘のさなかにおいても映画のことを考えていた。「戦地にライカを持つて行つてゐたので、何かにつけて帰るまでに千枚程無暗と撮つた。長い間の身についた意欲はある程度みたすことが出来たわけだが、いい場面でも音と切離せない複雑な場合に出会ふと、頭の中や、手帳にとめておくだけで、残念だつた時も数多くあつた」「(砲弾の―引用者注)金属の羽が空気を截るあの特別な音が近づくと黒い一抹の煙のやうに花の上を通るのが見えた。と思ふとばらば沢山の杏の花が散つた。これが何度も起るのを見てゐて、これは使える、兵隊を一人も画面へ出さないで、迫撃砲の音と、光りながらこぼれる杏の花とだけで出せば面白いと思つた」「機関銃が私達を狙つた時は、まづ前面の土をぱつぱつとはねかして小さい土煙りがまたたくうちに近づいて来る。これが映画にどうすれば出るだらうか」(以上、小津安二郎「戦争と映画雑筆」『中央公論』54-13、1939年12月)もし小津が戦争映画を撮っていたら、どのようなものになっただろうか。それに関して、小津は次のように述べている。「山中君(山中貞雄―引用者注)が生きてゐればどんな戦争映画を撮つたであらうか。実際上の困難な条件や制約を顧慮して、田坂具隆君の作品に例をとれば『土と兵隊』より『五人の斥候兵』により近く、大部隊の行動を追はず、小部隊を何処迄も追求してその全貌を示したに相違ない。 私が戦争映画をもし作るにしても同様であらう」(同上)公開された陣中日誌には、映画作りのためのネタ帳(「撮影に就ての≪ノオト≫」)が含まれており、「小部隊」での兵隊たちの日常が切り取られている。小津映画の登場人物のセリフが聞こえてきそうだ。いくつか面白いものを引用したい。▲映画館(南京)上映中皆笑ふ。半畳が入る。 返事がない。場内静になる。男出て行く。また元の騒然となる。▲出発。坊さんの兵隊に云ふ。 ▲クリークの水で飯を焚く。釜に水を張つて▲▲犬をつかまえてくる。後日。小津の戦争体験については、以下の本でも述べられているようだから、今度、調べてみよう。【楽天ブックス】完本小津安二郎の芸術今日は、久しぶりに『東京物語』を観てしんみりしよう。小津安二郎 DVD-BOX Vol.1【楽天野球団】
Dec 6, 2004
-
韓国併合と韓国民の希望
韓国併合に関して、韓国の国民が望んだので、日本は併合に踏み切ったとの主張があるが、その説は成り立たないであろう。1909年12月、一進会が合邦の請願を発表したが、国民にも韓国政府にも支持されていない。〇憲兵隊による報告 1909.12.8「今回一進会ノ発表シタル声明書ノ首謀者ハ内田良平ニシテ、仝人ガ該書ヲ齎ラシタルコトハ蔽フ可カラザルモノニシテ、発表後、以外ニモ国民及政府ノ反対激烈ナルタメ、殆ンド今日ニテハ其成算ニ苦ミ居レリト」(海野福寿編『外交史料 韓国併合 下』不二出版、2003年、657頁)しかもその請願書は、日本人策士の手によるものであった。さらに日本は、韓国側の意向を尊重する気は更々なかったのである。〇桂首相より一進会顧問・杉山茂丸宛内訓 1910.2.2「合邦論ニ耳ヲ傾クルト然ラサルトハ日本政府ノ方針活動ノ如何ニアル事故、寸毫モ韓国民ノ容喙ヲ許サス」(同上、666頁)〇山田三良「併合後ニ於ケル韓国人ノ国籍問題」1910.7.15「一国カ他国ヲ併合スルニ際シ、其住民多数ノ希望ニ従フコトヲ表示センカ為メ、所謂国民投票(Prehiscife)ヲ行ハシメタル二三ノ先例無キニシモアラスト雖モ、国際法上一定ノ慣例ト為スニ足ラサルノミナラス国際法上ニ於テモ亦之ヲ認ムヘキ理由存セサルカ故ニ、韓国人民カ併合ヲ希望スルヤ否ヤヲ顧慮スルノ必要無キコト明白ナリ」(『寺内正毅関係文書』首相以前、京都女子大学、1984、61-62頁)
Dec 5, 2004
-
大東亜共栄圏の実態
南方軍総司令部に配属され、サイゴンで軍政に携わった榊原政春の日記には、次のように記されている。(榊原政春『一中尉の東南アジア軍政日記』草思社、1998年)「南方各民族は突然欧米との紐帯を切断され、今日は生活上に於てすこぶる苦しい状態になるであろう。しかし、この苦痛を通り抜いてこそ初めて彼等本然の生活が存する事を考えて貰いたい。我々は今日、彼等の反抗的態度を何等恐れない。また彼等の御機嫌をとる如き従来の政治家風の政策を実行しようとは思わない。もし彼等にして反抗するならば、容赦なき手段をとる。我々としてはかくして清浄化され真の大東亜が建設されるのを、むしろ喜び期待している位だ」(1942年5月11日)「各軍の軍政部員より色々の要求がある。バター、煉乳、小麦、ゴム靴等。なるほど従来の彼等の生活を考えれば、それらの物質は不可欠の物だったろう。しかし、現在内地の日本人でさえそれらの物質は食べられずにいるのだ。日本人が大切なのか、土人が大切なのか。民生を考える時、それは日本を外にしては考え得ないのだ」(同上)すなわち、東南アジアを占領した日本は、英仏蘭の役割を肩代わりして日用品等を供給することはなかった。東南アジアの人々の生活を考慮するのではなく、日本本位に、搾取方針をとっていく。では、東南アジアがその痛みに耐えた後、独立が認められる余地はあったのか。日本の支配下から脱することは許されず、自決権が認められる余地はなかったのである。「大東亜共栄圏の目標は日本を中心とした大東亜共栄圏を建設する事にして、このためには各民族が従来の英米蘭の桎梏より完全に脱却し、自己本来の姿に目覚め、自己の犠牲に於て大東亜共栄圏建設に参画せんとするに非ざれば到底不可能である。ここに日本の強き政治を必要とする所以である。 従って在来の行きがかり的民族、独立、自決運動の如きは認める余地なく、各民族にして真に自己の地位を認識するに非ざれば、民族としての真の政治性を把握する事は不可能である」(1942年6月2日)※同日記の解説で倉沢愛子氏は、日記の記述について、南方軍総司令官寺内寿一に近いところにいた榊原の立場からみて、「単なる一個人の恣意的な意見ではなく、南方軍の中枢部の意見をかなり反映したものではないか」としている。
Dec 4, 2004
-

超整理法は改良しないと
最近、モノが多くなり、部屋の中は片付かなくなってきた。ただ論文だけはすぐ取り出せる体制が整っている。以前は、論文のコピーをリングファイルに入れて分類していたが、見たい論文が探せないことが多々あった。そして検索の困難さもさることながら、分類する際にどれに入れようか迷うものが出てくるなど、結局作業があと回しになって、机や床に山積みになっていた。またファイル一個の割高感も、作業を遅らせるブレーキになった。そこで野口悠紀雄の超整理法の押し出しファイリング方式である。押し出しファイリングでは、安く大量に買える、角形2号の封筒を使う。論文を入れ、封筒裏の右端に著者、論文名と作成日を書く。野口氏の本では、封部分を切り取るように言っているが、いちいち面倒なので切らない。出来たらこんな感じで本棚に並べていく。読むために取り出したものは、一番左に並べる。こうして最近使用したものほど、左側に来る。そして検索の際には、その記憶を頼りするという仕組み。しか~し、これで万事OK,めでたしめでたし、ではなかった。野口先生は、左のほうから順番にさがして行けば、見つかるっていうけど、全然、見つからない。論文を読む前に、探すのにエネルギーがとられてしまった。何百もあるものを手作業で探すのは無理があった。そこでラベリングして、パソコンで検索できるようにした。データベースは、フリーソフトの「MCardDB」でつくった。これで検索がラクにできる。入力が済んだものだけは…ね。
Nov 30, 2004
-
歴史家はそんなにバカじゃない
近代史の領域には、政治性が問われる問題を多く含んでいる。メディアで扱われるのは、主にそのような問題である。その一方で、学校においては、近代史は、日程的に、しっかり教えられていないものと思われる。多くの人は、その間のギャップをどう処理し、日々、メディアの情報に接するのだろうか。歴史家以外が書いた歴史に関する記述は、根拠が明確ではないものも多い。大事なのは、主張の根拠である。そしてその根拠は、史料によって支えられる。史料的に本当に裏付けられるのか、反対の状況を示す史料はないのか、と問えば、その主張の質がみえてくる。
Nov 25, 2004
-
MMORPGとクワガタ採り
一時期、MMORPGにはまった時期があった。純粋に遊ぶためだけに集まり、その場の流れで誰かがリーダーシップをとり、知り合いの知り合いが仲間に入ってきたりして、幼少のころを思い出させ、童心に帰って遊んだ。小学生のころ、市のはずれの団地に住んでいた。小二のある日、同級生の友だちと遊んでいて、ひょんなことから、その友だちの知り合いの上級生とクワガタ採りに行くことになった。クワガタ採りというと、雑木林が一般的だと思うが、われわれの間では、スイカ畑だった。団地の北側には、交通量の多い大きな道路が東西に走り、東側には大きな川が流れていた。西と南には、一軒家の住宅地が拡がっている。スイカ畑は、北側の道路を越えて、拡がる砂地にあった。そこに行くには、北東に向い、道路と川が交差する橋の下をくぐって、北にぬけなければならなった。漆黒の川を右手に見ながら、交通量の多い橋の下をくぐることは、少し勇気がいることだった。何とかそこをクリアすると、今度は、スイカ畑に不法侵入である。畑の主人に見つからないように、体勢を低くしながら、一列になって、砂地を進んだ。手ごろなところで、クワガタを探しにかかる。当時、「スイギュウ」と呼ばれた極大なオスのクワガタをもっているやつは、ヒーローになれた。しばらくして、俺は一匹のクワガタをみつけた。メスだった(種類は憶えていない)。結局、グループで収獲したのは、俺の一匹だけだった。今だったら、申告しないでこっそり持ち帰っていたかもしれないが、純粋だった俺は見つけたことを申告し、そのクワガタは、リーダー格の上級生がもっていった。MMORPGでも、ドロップしたアイテムをめぐり、各人の欲や思惑が働いたりして、クワガタ採りのことが思い出されて、それもまた面白かった。
Nov 23, 2004
-
中学の時の同級生
近所のスーパーで、中学の時の同級生を見かけた。2、3歳の男の子を連れていた。たぶん、彼の子供だろう。まだこの街に住んでいたのか。それとも、実家に子供を連れて遊びに来たのだろうか。彼は「不良」だった。ただ「不良」とは言っても、そんなに悪くはない。中学に入学したころの三年生にくらべれば、そうでもない。二年生、一年生と、学年が下がるにつれて、ワル度は低くなっていた。彼は、うちの学年のプチ「不良」のなかでの中心格だった。中学に入ったばっかりの時の、三年生は凄かった。「ボンタン」を履いて、茶髪で、自転車で遅くに登校し(自転車通学はご法度なのだ)、授業中に抜け出して、学校の裏山に煙草を吸いに行く輩が何人もいた。入学して初日か二日目くらいのころ、休み時間にそんな連中がうちのクラスに現れた。うちのクラスの窓から、「バカ」と罵ったやつがいると言うのだ。ちょうど、窓側の席にいた俺は疑われた。こんな善良な俺が、そんなこと言うか~。入学当初からこんな災難に遭う運命を俺は呪った。確たる証拠はないが、犯人はたぶん、うちのクラスで一番のワルのあいつだと思う。俺は、その不良らにマークされることになった。その連中が現れると、同級生は俺の周りから退いていった。(心の広い俺は、トバッチリを受けたくないという同級生の気持ちがよく判るぞ)ただ、しばらくすると、その連中が現れることもなくなった。こんなスタートからして、中学時代は全然、いいことがない。不良は嫌いだ。当然、彼も嫌いだ。不良はモテる。だから嫌いだ。知ってる。嫉妬だ。彼を見たとき、卒業してからすでに10年以上経っているのに、「嫌い」という感情が蘇ってきたことに、驚いた。よほど強い感情らしい。ちゃんと家庭を築いている彼へのジェラシーか。しかし、こっちには結婚の予定は今のところ、全くない。ああ、子供ほしいな~。
Nov 20, 2004
-
思いがけず…
大学においていない本を、図書館を通じて、よその大学から借りたのですが、なかを見ると、題名に全然沿っておらず、期待していたものとちがった内容でした。郵送料が自分もちで、すぐ返却するのは癪なので、仕方なく読みはじめましたが、これが意外に面白い。自分の関心からちょっと外れていても、しばらく読んでみることが大切。本との出会いってそういうものなんでしょうね。そう言えば、卒論のテーマも、偶然、手にとって見た本がきっかけだったことを思い出しました。
Nov 18, 2004
-
じょうずな勉強法
「日常」とは恐ろしいものですね。学ぶことに対する素朴な喜びを、最初はもっていたはずなのに、気がつけば、日課をこなすだけの毎日に変わってしまっています。麻柄啓一『じょうずな勉強法』は、中学生・高校生向けで、学ぶことの素朴な喜び、楽しさを思い出させてくれます。中学生・高校生では、何かを覚えるという作業は欠かせません。しかし、学ぶということを、「百科事典」を頭の中につくるように、考えるのは、好ましくないと筆者は言います。例えば、日本史で、徳川家康に関する事項として、関ケ原の戦い、親藩・譜代・外様大名、武家諸法度、参勤交代などがあります。これらの内容をそのまま、頭にいれるのではなく、「家康はいいやつなのか、悪いやつなのか」、自分なりに考える。そうやって、さきほどの客観的な各事項を「自分の世界」にひきこんで考えるという、作業を経ると、非常に忘れにくいものになります。これを筆者は、「百科事典」をつくることに対して、自分なりに考える=「日記」をつくることであると、呼んでいます。大学の歴史学では、先ほどの「家康はいいやつなのか、悪いやつなのか」、というような問いを自分で立てて、考察することが存分にできます。史料を探してきて、新しい歴史的事実を見つけたり、その歴史的事実を繋ぎ合わせることにより、今までの解釈は違うんじゃないかと主張したりします。解釈することに歴史の面白さがあります。「日記をつくる」ようにという勉強法は、その面白さを生かしたやり方なわけです。
Nov 17, 2004
-

楽天公認ガイド本
猫も杓子もアフィリエイトの時代。この「楽天アフィリエイト&楽天広場」公認ガイドの監修者は、月収30万円以上を稼ぎ、アフィリエイト界をリードする藍玉さん。本の内容は、藍玉さんが、アフィリエイト初心者の「ミホコ」、「タケシ」に一からレクチャーしていくという形式になっています。多くの人にとって、一番の関心は、成功の秘訣。売れるサイトになるための、テーマ選びからページのデザインまでの細かな基本テクニック、そしてレポートの分析術が伝授されます。参考になるのが、「先輩のホームページを拝見」のコラムと、具体的なページの事例を出して、アドバイスをしているところです。また儲けることだけではなく、コミュニケーションを大切にしているということが、伝わってきて、初心の大切さを見つめ直すことができます。これからアフィリエイトを始める人はもちろん、始めたがあまり上手く行かず、もう一度、基本から見直したい、という方に、ピッタリではないでしょうか。「楽天アフィリエイト&楽天広場」公認ガイド
Nov 15, 2004
-
各社ブログ雑感
まだ何も書いていない状態で、訪問者があることに驚く。楽天ブログは、本当にコミュニケーション機能がすぐれていると思う。最初につくったBIGLOBEのブログに慣れているためか、ここの管理ページはなかなか馴染まない。また日記を1日1回しか書けないのが残念。はてなダイアリーは、管理ページが使いづらい。FC2のブログは、サービスが始まったばかりで、まだこれから。
Nov 14, 2004
全45件 (45件中 1-45件目)
1