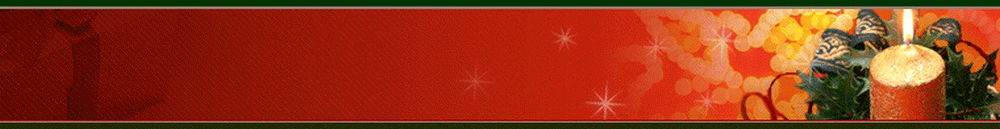2011年01月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
洋服の選び方
僕の洋服を見た目とか他人からどう思われるか?でなく「着ると元気が出る」かどうかで選ぶようにしている。値段が高い洋服を着ると元気が出るというわけではない。だから、時としてアンバランスなことが起こる。上下合わせた洋服の値段の総額とネクタイ1本の値段が同じだったりする。お母さん方に提案なのですが、「塾選びの基準」を「お子さんがその塾に通ったことで元気になるか?」にされてみてはいかかでしょうか?元気になる塾に通っていると成績は上がるものです。
January 31, 2011
-
反省と計画
毎週日曜日の午前中にやることを決めている。自習に来た子どもたちの監督をしながら反省と計画を行う。まず、1週間分の日記と手帳を読み返し、この1週間の反省をする。つぎに昨年の日記と手帳を読み返し、これから1週間の予定をたてる。月末には同じように日記と手帳を使い、この1か月の反省と次の1か月の計画をたてる。日記や手帳は何度も繰り返し読むのでボロボロになってくる。僕は日記や手帳は書くものでなく「読むものだ」と思っている。多くの子どもたちは、テスト前になると計画をたてる。しかし、その計画が前回のテストの反省に基づいていないことが多い。「前回のテストで足らなかったのは何か?」をよく自己反省しないまま、今回のテスト勉強の計画を立てようとする。当然のごとく反省なき計画は、同じミスの繰り返しにつながる。人間だれしもミスはする。むしろミスがあるところが人間らしいといってもいい。しかし、何度も同じミスを繰り返す人間を僕は愚かだと思う。愚か者にならないように計画をたてる前に反省が大事だ。
January 30, 2011
-
やりたくない!
僕の子育ての基本は「やりたくない」ことはやらせない。「ご飯を食べたくない」という子には「じゃ食べなくてもいい」という。でも、出された食事以外のお菓子など絶対に口にさせない。そして、お腹がすいて「食べたい」と本人が言いだすまで完全に無視する。「勉強したくない」といい子には無理に勉強をさせない。食事欲も知識欲も本来人間の持つ本能的欲求だ。食事も食べれば楽しくなるし勉強もやれば楽しい。その楽しさを子育ての初期に教えることが大事だ。人間は楽しいと感じることは、無理やりやらせずとも自分からやるようになる。勉強は「やりたくなければ今はやらなくていい」でも、勉強は楽しいものだという姿を大人が見せていれば子どもは自然と勉強を始めるものだ。しかし、「他人に迷惑をかけない」とか「他人を不愉快にさせない。」とかいう生活のマナーの「しつけ」は別だ。「しつけ」は厳しく行う。できていなければできるまで繰り返しさせる。泣こうが喚こうが関係ない。勉強と「しつけ」を混同してはいけない。昨日、娘が問題集の答えを失くした。「お前は塾で勉強する資格がない。もう、塾に入ってきてはいけない。」と厳しく30分ほど泣いている娘を注意した。問題集の答えを失くすなどということは勉強以前の「しつけ」の問題だ。毎日、僕は昼の時間帯、年少さんから年長さんの幼児教室をやっている。桑原塾の教室のUSP(ユニークセールスポイント)は毎回10分から30分の「お母さんの子育て勉強会」です。
January 27, 2011
-
勇気を与える言葉
僕の顔はブラマヨの吉田さんと同じようにニキビ跡で汚い。学生時代からずっと気になっている。高校生のころ母から「大人になればそんなものきれいになるよ。私もそうだったもの。」と言われたが信用しなかった。先日、テレビを見ていると名前は忘れたが女性の心理学者の大学教授が、「男性は肌がつるつるしているよりもブツブツ顔の方が女性から見た印象がいい。」というような発言をしていた。長年のコンプレックスが軽くなった。とても勇気を与えてくれる言葉だった。次のような言葉を昨年の手帳のメモ書きから発見した。もっとも適切なアドバイスとは、相手が困難を乗り越えていく「勇気を与えること」である。相手を動かすとせず、相手のために自分ができることを考え続けようとする姿勢が大切。ウソやごまかしの多いテレビの情報でも、時にはためになることもあるものだ。
January 26, 2011
-
野口英世
今朝から本人の希望により、小学2年生の娘の小雪にそろばんを教え始めました。僕自身は小学3年生から5年生までの3年間、週2回そろばん塾に通って1級まで取りました。僕自身がそろばんで身に付けた力、「集中力」「忍耐力」「継続力」を娘にも身につけてほしい。そのために朝の30分をそろばんの練習に使います。目標は5年生までに1級取得です。その娘にそろばんを始める前に次の文章を読ませました。石井邦男(著)続 中学生の勉強法より野口英世に学ぶ1900年、野口英世(1878~1928)は渡米(アメリカに行くこと)しました。ニューヨークの数十キロメートル南のフイデルフィア市にあるペンシルバニア大学のサイモン博士を頼っての渡米です。初めは、博士の個人助手で、月にわずか8ドル、パンと水でようやく生きていけるだけの収入です。まもなく、博士から蛇毒(へびの毒)のことを調べるようにいわれました。英世は大学の図書館に閉じこもり、蛇毒について書いてある英語・ドイツ語・フランス語の原書(もとになっている本)を読み、その要点をノートに書きうつしていきました。こうして三カ月たったとき、かれのノートは、二百五十ページの分量になっていました。サイモン博士は、この野口英世の熱心さに感激し、大学から三十ドルの月給が出るようにしてくれました。この蛇毒研究が、野口英世のその後の大活躍の出発点だったのです。ひとつのことを徹底的に調べれば、そこにおのずから輝かしい未来が開けてくるのです。二百五十ページとおどろいてはいけません。三か月、つまり九十日でいわば、一日わずか3ページずつです。1日にノート3ページ書くことは、中学生にもできることです。ただ問題は、それを90日間こつこつと、うまずたゆまずつづけていく根気があるかどうかです。時間をめぐって大切なことは、短期決戦ではありません。ねばりなのです。いかに長期間、ひとつのことにこだわりつづけるかです。<継続は力なり>これが大原則です。いましなければならないことを、じみちにこつこつとつづけてほしいと思います。
January 25, 2011
-
進研ゼミのCM
最近、気になるCMがある。進研ゼミ中学講座のCMなのだが、「一人でやるから進研ゼミは受験に強い。」という内容のもの。確かに受験本番は「ひとり」。自分自身の力しか頼ることができない。受験はひとりボッチの孤独に耐えなければいけない。「先生が横にいないと勉強できなーーーーい。」なんて甘えているようではだめだ。受験本番に強くなるには、勉強は自分ひとりで頑張ることは大事だ。しかし、本当に受験本番に強い子は「説明力」を持つ子。解っていない友人にきちんと説明できる学力と心の優しさをもつ子こそが本当に受験に強い。
January 22, 2011
-
自信を回復させる
この時期の受験生は自信を失いやすい。「どうせ自分はやっても無駄。」とマイナス思考にどっぷりと陥りやすい。僕は自信を失いそうになると、「車の中」や「トイレの中」に駆け込む。そして、3回叫ぶ。「俺はできる!俺はできる!俺はできる!」すると、不思議なことに体の中から「元気」が湧きだしてくる。だまされたと思ってやってみてほしい。受験のこの時期の僕の朝は、塾のトイレを掃除しながら大声で「俺はできる」の連呼から始まる。受験前、朝から勉強できる塾は多いと思うが、朝から塾長が叫んでいる塾は少ないだろう。
January 21, 2011
-
1.01倍の努力
がんばっているのに成果が出せないあなたへ今までの2倍の成果が出せる簡単な方法を教えます!それは今日から70日だけでいいから、今までの1.01倍の努力をしてみよう。今まで腹筋を100回やっていた人は101回にする、今まで5時間勉強していた人は5時間3分勉強する。たったの1パーセントの努力で2倍の成果が出せる。なぜなら、1.01を70回を掛け算すると2を超える。もうこれで十分100パーセントやりきったと思ったところからあと1パーセントの努力する。それを70日続ければ成果は2倍になる。でも、今までどおり100パーセントのがんばりでは、1は何回かけても1。もっと残念な人は「がんばっているけど成績が下がる人」。その人は99パーセントの努力をしている。0.99を70回かけると0.5より小さくなる。実にたった2パーセントの努力の差が4倍以上の結果の差となる。しかし、この2パーセントの努力の差は周りからは見えにくい。わかりやすいようにコピー用紙を三束準備する。500枚のコピー用紙の束、505枚のコピー用紙の束、495枚のコピー用紙の束。机の前に載せて見比べても違いには気づかない。でも505枚と495枚を合わせて1000枚の大きな束にして、残りの500枚と比べてみよう。だれでも大きな違い気付く。人は1パーセントの差には気付かないが、2倍の差には気付く。だから、「同じようにやっているのに・・・・・・」とぼやく人が出てくる。でも、成果を出す人はほんの少しだけあなたよりがんばっている。1.01倍の努力。それが僕の今年の目標値です。24時間の1パーセントは15分。毎日15分だけ苦手なことに挑戦している。きっと春までには大きな差が出せる。
January 16, 2011
-
長崎大学附属小入試
昨日は長崎大学附属小の入試日でした。男子は9時、女子は12時30分の受付開始。塾に通ってくれた10名の年長さんの激励に行ってきました。気温4℃の中、寒さと初めての受験への緊張から小さな手はキューピー人形ようになっていた。一人ひとりに小さなカイロを手渡し、「右手、左手」の確認。最後に「お名前は?」大きな声で「●●●●です!!」みんな元気にいつもの笑顔に戻っていました!しかし、うちの塾以外の幼児教室の先生方は応援に来ないのだろうか?朝と昼、合計2時間近く校門の前に立っていたが、僕と守衛さんの2人だった。
January 13, 2011
-
肩に力が入る
小学生のころ人前に出ると極度に緊張して、「桑原は肩に力が入りすぎている」と先生に言われてものだ。その癖は今も抜けない。でも、その肩に力が入ることが今では「塾長の威厳」に見られるようになった。自分自身は大きく変わっていなくても人の見方は変わっていくものだ。
January 10, 2011
-
仕事
どんな些細な仕事であれ、雑務であれ仕事を頼まれることに感謝する気持ちが薄い人間は仕事を頼まれなくなる。仕事を増やしたければ自分の都合を考える前にこんな自分を信頼して仕事を頼んでくれて「ありがとうございます」という気持ちをもち2つ返事で引き受けべきだ。今の自分の実力では無理でも引き受けてがんばっているうちに力がついて突破口が見えてくることが多い。がんばって、がんばって人の3倍がんばっても無理だったら素直に謝ればいい。でも、がんばっても無理なことなど今まで頼まれた経験はない。きっとやればできる。
January 8, 2011
-
終電前
最終電車の出発まであと10分。5名の高校生が塾の玄関から駈け出している。ギリギリまで頑張る彼らを見ていると、「これが受験なんだ!」という実感が湧いて出てくる。ギリギリかもしれない。駆け込み乗車になるかもしれない。でも間に合うだろう。きっと彼らなら。電車にも。そして受験にも。
January 5, 2011
-
趣味の時間
予定表を書くときには、まず趣味の時間を確保するようにしている。僕の趣味は読書と運動です。1日1時間は読書、1時間はジョギングと筋トレかボクシングです。読書で心と頭を鍛え、運動で体を鍛えることで仕事の効率が上がります。もちろん、趣味の時間のときも頭の中の20パーセントは仕事のことを考えています。「よりよい塾にするには?」これだけは、寝ていても頭から離れません。
January 3, 2011
-
明日に備えて
明日やるべきことを手帳に書き出してみると、なんとハードな一日だろうと不安がよぎる。今日のうちに1つでも終わらせておくことで明日が少しだけ楽になりそうだ。今できることは今やってみる。だめなら明日また挑戦です。忙しくて自分を見失いそうになるときは、自分自身に問いかけるようにしています。「いったいどうしたいの?」「信念はあるの?」がんばっている受験生に負けない信念を持たなければ生徒に申し訳ない。
January 2, 2011
-
負ける喜び
元旦から元気に仕事ができる幸せを感じています。今年の目標は、自分より優れたスタッフを数多く育てることです。授業では「塾の先生はすごい!」と子どもたちに感動を与え、授業以外では子どもたちのコーチとして接し「やる気が出た!」と言わせ、保護者面談では「安心しました!お任せします!!」と言われる。塾バスの送迎では安全に快適に子どもたちを送り届け、掃除は隅々まで毎日磨きあげる。1人ではすべてそろったスタッフはいないかもしれない。でも、自分が得意な分野なら僕を超えることはできるはずだ。「負けることの喜び」を感じる1年でありたい。
January 1, 2011
全15件 (15件中 1-15件目)
1