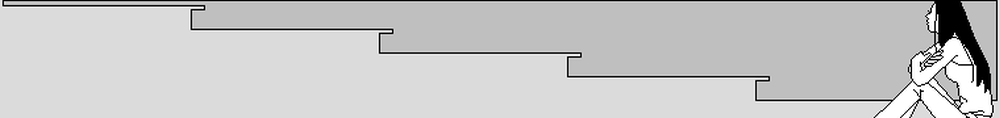PR
X
Freepage List
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Words
Тоsйiуаさん
A LITTLE DREAM winthemixさん
アンバーグリースの… アンバーグリースさん
手作り日記 junjun0306さん
わたしのブログ ちるちる9428さん
A LITTLE DREAM winthemixさん
アンバーグリースの… アンバーグリースさん
手作り日記 junjun0306さん
わたしのブログ ちるちる9428さん
Comments
カテゴリ: 普通の日記
昔から私は本を読むのが好きな人間だった。今となってはそれなりの本を読んでいるわけだが、勿論子どもの頃は絵本を毎日のように読んでいるような感じだった。もともと両親がそのような本が好きで家にたくさんあったということも関係しているのかもしれないが…本棚に膨大に積まれている本を片っ端から読んでいたものだった。
そのせいか…保育園の頃にはお昼寝の時間を無視してでも絵本に齧りついていたので先生にいつも寝なさい寝なさいと怒られていたこともあった。子どもにとってお昼寝の時間は楽しい(とは言っても無意識なのだが)時間のはずなのに、私にはお昼寝の部屋の本棚にある絵本を読み漁る方がよっぽど魅力的に見えた。家の本棚の数倍の本、しかも全部が読んだことがない本なのだ、それはそれは目をキラキラさせながら寝ることもしないで先生の目を盗んでは絵本を布団の中に持ち込んで読み耽っていた。
小学校にあがった頃には絵本よりももう少し発展した本を読むようになった。所謂伝記と呼ばれるもので、歴史上の人物の偉大さを書き綴ったような本に嵌った。リンカーンにはじまりエジソン、ナイチンゲール…日本では豊臣秀吉、織田信長、徳川家康…そのような本を好んで読んでいた。
私は特にエジソンの話が好きだった。特に勉強をしているという意識はなかったのだが、現代のように便利なものがない時代に生活に根ざした発明をしているという意識が存在しているということが面白かった。人が目をつけないところにこそ文化の種はあるものだと感じた。
中学・高校になると、推理小説に嵌った。綿密に考え込まれたシナリオ、張り巡らされた伏線、数ページでも気を抜いて読めない展開にわくわくしていたものだった。
しかし、私の中で一番衝撃に残った本というのは、7歳か8歳で読んだ「はじめてであう数学」(だったかどうかはわからないが…確かそんなようなタイトルだった)だった。これは一応小学校低学年からの本とされていたのだが…書かれている内容はとてもそんな風には見えなかった。確かに可愛らしいキャラクターや綺麗な絵が出てくるので絵本と言ってしまえばそれまでなのだが、私にはただの絵本とは思えなかった。
その3巻くらい(この辺りは本当に曖昧)に出てくる話が衝撃的だった。
話の命題というのは「川で囲まれた土地があって、周りには川を挟んで7つの橋をかける。合計7本の橋を須らく一回ずつだけ渡って歩けるかどうか?」という本だった。つまり7本の橋を渡るように一筆書きできるかどうかということだ。
これだけでは全く図が想像できないかもしれないが、簡単に言えば8のすぐ横に3をくっつけるような図形だと思ってもらえればいい。それを一筆書きできるかどうか?という命題なのだ。
数学の歴史のようなものを勉強している時に「ケーニヒスベルクの橋渡り」というページがあって、そこに描かれている図を見て驚いた。それは私が遠い昔に頭を悩ませた問題だったからだ。興味があって読んでみるとこれはオイラーによって不可能定理とされているものだということがわかった。
少し話は逸れるが…世の中に多くある数学的な定理を証明した人は数式の数と同じだけ多くいるが、その定理が可能か不可能かを判断するという視点で言えば圧倒的に不可能定理を証明する方が勇気のいることだ。
数式を定理として持ち上げるということは、そこに至るプロセスというものは必ず介在する。しかし不可能定理を認めるということは数式には綺麗になる最終形があるという前提で言えば、その今までのプロセスを否定することになってしまうからだ。しかも物事をわからない人から見れば放棄しただけに見られるかもしれない。つまり定理として安定しているものよりも認められるのに時間がかかる可能性もあるのだ。
話を戻して……オイラーと言えば虚数単位のiを作り出した人で、文系の私でも知っている人くらい有名な人だ。そう考えると私は小学校の頃からオイラーの不可能定理に挑んでいたということで…少しだけ自慢気になったものだった。笑
そのせいか…保育園の頃にはお昼寝の時間を無視してでも絵本に齧りついていたので先生にいつも寝なさい寝なさいと怒られていたこともあった。子どもにとってお昼寝の時間は楽しい(とは言っても無意識なのだが)時間のはずなのに、私にはお昼寝の部屋の本棚にある絵本を読み漁る方がよっぽど魅力的に見えた。家の本棚の数倍の本、しかも全部が読んだことがない本なのだ、それはそれは目をキラキラさせながら寝ることもしないで先生の目を盗んでは絵本を布団の中に持ち込んで読み耽っていた。
小学校にあがった頃には絵本よりももう少し発展した本を読むようになった。所謂伝記と呼ばれるもので、歴史上の人物の偉大さを書き綴ったような本に嵌った。リンカーンにはじまりエジソン、ナイチンゲール…日本では豊臣秀吉、織田信長、徳川家康…そのような本を好んで読んでいた。
私は特にエジソンの話が好きだった。特に勉強をしているという意識はなかったのだが、現代のように便利なものがない時代に生活に根ざした発明をしているという意識が存在しているということが面白かった。人が目をつけないところにこそ文化の種はあるものだと感じた。
中学・高校になると、推理小説に嵌った。綿密に考え込まれたシナリオ、張り巡らされた伏線、数ページでも気を抜いて読めない展開にわくわくしていたものだった。
しかし、私の中で一番衝撃に残った本というのは、7歳か8歳で読んだ「はじめてであう数学」(だったかどうかはわからないが…確かそんなようなタイトルだった)だった。これは一応小学校低学年からの本とされていたのだが…書かれている内容はとてもそんな風には見えなかった。確かに可愛らしいキャラクターや綺麗な絵が出てくるので絵本と言ってしまえばそれまでなのだが、私にはただの絵本とは思えなかった。
その3巻くらい(この辺りは本当に曖昧)に出てくる話が衝撃的だった。
話の命題というのは「川で囲まれた土地があって、周りには川を挟んで7つの橋をかける。合計7本の橋を須らく一回ずつだけ渡って歩けるかどうか?」という本だった。つまり7本の橋を渡るように一筆書きできるかどうかということだ。
これだけでは全く図が想像できないかもしれないが、簡単に言えば8のすぐ横に3をくっつけるような図形だと思ってもらえればいい。それを一筆書きできるかどうか?という命題なのだ。
数学の歴史のようなものを勉強している時に「ケーニヒスベルクの橋渡り」というページがあって、そこに描かれている図を見て驚いた。それは私が遠い昔に頭を悩ませた問題だったからだ。興味があって読んでみるとこれはオイラーによって不可能定理とされているものだということがわかった。
少し話は逸れるが…世の中に多くある数学的な定理を証明した人は数式の数と同じだけ多くいるが、その定理が可能か不可能かを判断するという視点で言えば圧倒的に不可能定理を証明する方が勇気のいることだ。
数式を定理として持ち上げるということは、そこに至るプロセスというものは必ず介在する。しかし不可能定理を認めるということは数式には綺麗になる最終形があるという前提で言えば、その今までのプロセスを否定することになってしまうからだ。しかも物事をわからない人から見れば放棄しただけに見られるかもしれない。つまり定理として安定しているものよりも認められるのに時間がかかる可能性もあるのだ。
話を戻して……オイラーと言えば虚数単位のiを作り出した人で、文系の私でも知っている人くらい有名な人だ。そう考えると私は小学校の頃からオイラーの不可能定理に挑んでいたということで…少しだけ自慢気になったものだった。笑
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.