2010年05月の記事
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-
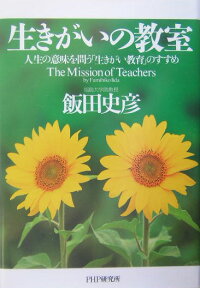
飯田史彦『生きがいの教室』1 ~「そで擦り合うも、他生の縁」
飯田先生の『生きがいの創造』は、かなり前に読んでいて、非常に衝撃を受けました。それ以来、「生きがい」シリーズの情報は、かなり気にしていました。あるときから、『生きがいの教室』という本も出されていることを知りました。教師という職業柄、『生きがいの教室』という題名には非常に惹かれました。存在を知って以来、ずっと気になっていた本です。その本を、このあいだ、ようやく読みました。ブログをちょくちょく見させていただいている原田誉一先生のお名前も出てきて、びっくりしました。(^。^)『生きがいの教室 ~人生の意味を問う「生きがい教育」のすすめ』 (飯田史彦、PHP研究所、2004、1400円)============================【内容情報】(「BOOK」データベースより)ベストセラー「生きがい論」シリーズの、新たなる挑戦!「心の真ん中が空っぽの子どもたち」を救う、画期的な「生きがい教育」の手法と実践レポート。日本の将来を憂いて立ち上がった、全国各地の教師たちの試みとは。【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 「生きがい教育」とは何か(心の真ん中が空っぽの子どもたち/「生きがい」を創造する人生観/「生きがい論」の七つの特徴/「生きがい教師」の心がけ)/第2章 「生きがい教育」の実践レポート(大学での試み/高等専門学校での試み/高等学校での試み/看護学校での試み/中学校での試み/小学校での試み)============================この本ではまず最初に、これまでの著作での著者の主張(仮説)がかいつまんで紹介されています。事前に『生きがいの創造』などの本を読んでおいたほうが詳しく理解できるとは思いますが、なかなか分厚い本ですので、人によっては『生きがいの教室』などでまずかいつまんで著者の仮説に触れてみるのもいいのかもしれません。『生きがいの創造 ~"生まれ変わりの科学"が人生を変える』 (飯田史彦、PHP文庫、1999、720円) 本来は著者の仮説・論点を整理して紹介するべきなのでしょうが、ここでは私スタイルで、いつも通り「特にここ!」と個人的に思ったところを部分抜粋で紹介していきます。(^_^)興味をもたれた方は、ぜひ同書または『生きがいの創造』をお読みください。(↑これは、本当に、人生観が変わる本です。)==============================『生きがいの教室』読書メモ1(p157~ #の緑文字は僕のコメントです。)・意味が現象に優先する・意味のない現象は生じない・宇宙とは「意味空間」であり、 宇宙の本質は、「物質」ではなく、 その意味を生みだしている「精神」である。・『そで擦り合うも、他生の縁』 家族や親友や恋人など、今回の人生で身近な人々は、 過去や未来の人生でも身近に生きる縁の深い人々。 愛し合い、助け合い、切磋琢磨し合いましょう。 『多少の縁』ではありません。#今まで勘違いしてました。(^^;) なるほど、『他生の縁』ですか。 そんな意味があったとは! なお、ネットでちょっと調べると、 『多生の縁』という漢字でも出てきました。 本当はこちらが正しいのかもしれません。 どちらにしろ、前世や来世があることをふまえたことわざだったのですね。(p42まで)==============================次回以降も、続けて読書メモを公開していきます。自分用のメモですが、もしご参考になるところがあれば幸いです。(^^) ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ブログ継続の力となります。 (「おすすめ本」のブログランキングに新しくジャンル登録しました。 まだ登録したてで実績がないので、ぜひ、クリックしてください!(^0^))
2010.05.31
コメント(0)
-

『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』5 「清掃時間」と呼ばないで。
この本に書いてあることが、今の教育には必要だと思います。 『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』(平田治、三五館、2005、1400円)今日は、第7章「『道徳』で深める」から、最後までを部分引用・紹介します。===========================『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』 読書メモ5(p157~ #の緑文字は僕のコメントです。)・道徳の授業で、 子どもが書いた掃除についての作文を、主な資料として考え合い、 各自考えたことを、その日の清掃活動の中で試してまた振り返る。・皆さんが働くのは、 皆さん1人1人が、よい人間に高まるためという意味の方が 本当なのです。・もっと言えば、これからは、学校はそれほどきれいにならなくていいから、 よい人間になるための時間なのだ、と考え直すことにします。#このへん、「逆転発想」の部分です。 つまり、学校がきれいになることを目指すのか、 心の成長を目指すのか、ということです。 学校教育はその全時間をかけて、 子どもたちの成長を目指しています。 もちろん、掃除の時間も例外ではありません。 私たちは、その目的を、もっと意識していいかもしれません。・「清掃時間」と呼ばないで、「成長の時間」と呼びたい。#韻を踏んでいて(?)いい感じです。 思わず言いたくなるフレーズです。(^。^)・そういう掃除をしている学校では、今、「自問の時間」と呼んでいます。 それは「よい人間になれるかな」と、自分で自分に質問する、 つまり自問しながら働くからです。・子どもに掃除の義務はあるのか?・いちばん「頭を切りかえてもらう」のは、教師です。・分担があるからといって、分担された仕事しかしないようになったら 最低です。・分担は入り口ではあるが、出口ではない。・その子が自分で決めればいい。 ・ゆったりと構え、相手のレベルに完全に合わせます。 同調、共鳴というほうが当たっているかもしれません。・身近にいる友だちを目標にすることです。・ごく身近にいる、 自分より少しだけ先を行っている友だちを目標に頑張ります。#子どもたちに望んでいることは、 そのまま、教師が教職員の中で自ら望んでいる行動につながります。 様々な分野で、目標にしたい先生方がおられます。 お互いがお互いを目標に、取組を続けている教職員集団って、 すてきです。 子どもたちも、教職員も、そういう集団になっていきたい。 福島正伸さんが言うところの「相互支援社会」という意味と、 同じだと思います。 僕は、そういう考え方に賛同し、それを目指していきたいと考えています。 まだまだ実践ができていないところですが・・・。・今こそ、「自問」の心が求められています。 「自問」、それは「自ら問う」こと。・物事を前のほうへと進める「心のアクセル」です。・自分をコントロールする「心のブレーキ」です。・自分が自分を正しく操縦できる 「心のハンドル」 「心のナビゲーション・システム」です。・「自問」、それは、自己の生き方を問うこと。 自問教育は、21世紀の人間教育です。#この、最後の方の部分、 まとめとして、非常にシンプルに、 象徴的に表現されているなあと感じます。 子どもの成長と、自分の成長を信じて、 「生き方を問う」ということを、やっていきたいです。=========================== これで、『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』の読書メモを終わります。読後に、行動意欲を奮い起こされる、心に残る本でした。↓続編のこの本も、読んでみたいです。『「魔法の掃除」13カ月~「Iメッセージ」を語れる教師』(平田治、三五館、2007、1400円) ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.30
コメント(0)
-

『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』4 ほめようとせずに感動を伝えよう。
さきほど、PCを再起動したら、デスクトップからアイコンが消えて真っ黒な画面に・・・!「システムの復元」を実行し、長時間待った挙句、何とか復元できました。元に戻ってよかった!そういうわけで、昨日の続きを無事に書き込むことができます。ありがたいことです。(^^)『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』(平田治、三五館、2005、1400円)===========================『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』 読書メモ4(第5章「魔法の『水をやる』」および第6章「『出た芽』を育てる」より。 #の緑文字は僕のコメントです。)(5章「魔法の『水をやる』」)・ただ闇雲に信じて待っているだけでは、自発性は引き出されません。・よい種を蒔かずに、そして水もやらないまま、 ただ待っていても芽は出ません。・水が沁み込んで膨らんで、芽が出そうになるまで毎日水をやり、 目を離さないことです。 水加減が大切なのです。#そのときどきだけでなく、長期的視野に立って、 水やり(声かけ)を継続しながら待ち続ける、 ということが、必要なんですね。 「毎日の水やり」 簡単そうですが、これが僕にはなかなか難しいのです。(>。<;)↓「水をやる」ことの具体例・神さまからもらった「3つの玉」の話・「狼から育てられた子」の話#話の詳細は割愛します。 (6章「『出た芽』を育てる」)・子ども同士も指示・命令・注意し合わないように。・「信じて待つ」ことが、「自問清掃」の核心。・感動が口を衝いて出た言葉は、 相手が主語であるYOUメッセージではなく、 自分が主語であるIメッセージになっている。・Iメッセージこそ、人の心を動かす力を持っている。・ほめようとせずに感動を伝えよう。#なるほど。 たしかに、すぐ「あなたはえらい」とか「あかん」とか 言ってしまう、自分がいます。 ほめることよりも、自分の感動を伝える。 そのためにも、 「思わずIメッセージが口を衝いて出たか」という検証をする。 おもしろい視点です。意識してみます。 ・心身障害児の療育でよく言われるように、 「叱らないけれど、決して譲らない」#僕も障害児教育に数年間関わってきましたので、 この言い方は、大変腑に落ちるところです。 「叱らない」ということを自分としての、教師のポリシーとするなら、 この「叱らないけれど、決して譲らない」は、 大きな、教師としての行動哲学になります。 自分としては、割と意識してそうするようにしているのですが・・・。・やたらに感情的に叱らないけれど、 必ず成長する可能性があるのだという確信があるからこそ、 譲らないのです。 信じて待っているのです。・「比べる」ことはしない。・「比べないけれど学び合おう」とする時間。#「学び合い」も、教師として意識して勉強していこうとしている キーワードです。 授業時間だけでなく、掃除の時間にも、 「学び合い」の視点が持ち込めるんですね。 いえ、本書によれば、掃除だからこそ、最も「学び合い」が成立しやすいと 言えるのかもしれません。・日記や作文を紹介したり、 「道徳」の授業でじっくりと読み深めたりして、 子ども同士の関係をつないでいきます。 比べないけれど関係をつなぐ。・作業という労働行為を通して認識に至る、 儒教的意味を超越した知行合一の人間像を形成したということは、 世の授業論の到達点をはるかに超えている。#上の記述、難しかったです。 調べてみると、知行合一(ちこうごういつ)というのは、 「知っていることと行動が一致している」といったことを 表しているようです。(以上、p156まで)=========================== 次回は、第7章「『道徳』で深める」を参照します。それでは、また! ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.29
コメント(0)
-

『斎藤孝の勉強のチカラ!』
『齋藤孝の勉強のチカラ!』(斎藤孝、宝島社、2005、1200円)「勉強する」ことの意義やメリットがとても詳しく書いてある本です。勉強への意欲がアップします。勉強を教えることへの意欲もアップするので、教師や塾の先生にもおすすめ。==============================「勉強なんてしなくていい」という今の社会にだまされてはいけない。勉強することが人の能力を磨き、社会で活躍できる人材を作る。勉強が嫌い、社会に出たら役に立たない、暗記はつまらない という人への処方箋。【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 「学ぶ」ということ/第2章 強勉の喜び/第3章 勉強で培われる力/第4章 「教科」の楽しみと学び方/第5章 勉強の技とコツ/第6章 教養の楽しみを広げる==============================以下、僕の読書メモです。かなり気に入ったOR気になった部分の抜粋です。==============================『齋藤孝の勉強のチカラ!』読書メモ・勉強はストレスを快感にします。・勉強が持つ意味のひとつに、 ストレスを快感に換える回路を作るということがある。・収穫の喜びを味わうには、そのために準備する時期が必要だ。・教養のおもしろさに目覚めると、勉強をする気がガンと出る。・「感動」と「習熟」が人生を広げる・「感動の喜び」、「習熟の喜び」、 この2つの軸は、すべての教科について満たすことができる。 この2つの喜びを両軸にして回転させていけば、 勉強は大きく変わってきます。・先生のパワーってすごいもので、 いい先生と出会ったら一発でその教科が好きになります。 大嫌いだった英語を突然やり出すなんてことが起こる。・予習をすると、すごく勉強の効率がアップする。・予習の一番のポイントは春先。 次の学年の教科書をもらったら、 1年分の勉強を終わらせるくらいの気持ちで ザーッと教科書を読んでみてはどうでしょうか。 ここで予習をしておくと、春先からトップスピードで走れて、 1年間がすごくスムーズに流れます。==============================さて、この本の中で紹介されていた本で、その紹介文に衝撃を受けた本があります。『トットちゃんとトットちゃんたち』(黒柳徹子、講談社青い鳥文庫、2001、720円)==============================ユニセフ親善大使として発展途上国を回った黒柳さんが見た、子供たちの切ない状況。失業率80%のハイチでは、少女がわずか42円で売春していたりする。彼女は自分がエイズにかかっても何年かは生きられるが、自分の家族は明日、食べる物がないからと話す。世界で年間1000万人以上の子供が餓死しているといった統計的な数字と、人々の暮らしの関係がわかる実に地理的な本。世界の真実を理解するために、ぜひ読んでほしい。(『齋藤孝の勉強のチカラ!』p167より)==============================紹介文を読んだだけで、切なくなりました。そして、こういったことは本当に知らなければならないことだと感じました。ぜひ、読んでみたいと思います。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.28
コメント(0)
-

『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』3 5段階の清掃プラン
この本に書いてあることが、今の教育には必要だと思います。『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』今日は、5段階のプランの具体的内容を紹介します。===========================『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』 読書メモ3(第4章のp92~p117まで。)・5段階の清掃プラン 1) がまんとやる気という意志力を目標にする段階 =「がまん玉」を磨く「がまん清掃」 2) 黙っていてもどれほど人の心を汲む気働きができるか を目標にする段階 =「しんせつ玉」を磨く「しんせつ清掃」 ・「言葉でなく行為で協力する」ことを目指す。 (目配せや手招きなどによる連絡の仕合も×) ・言葉で連絡をとらないという不便さに、わざと身を置いてみる。 3) 最後の一分まで仕事を見つけとおすことを課題とする段階 =「みつけ玉」を磨く「みつけ清掃」 4) 目を内に向けて感謝の気持ちで働けるかを自問する段階 「感謝清掃」 ・「やだなあ」と思って机を拭くんではなくて、 ありがとうという気持ち、感謝の気持ちを込めて、 雑巾や箒を使う。 ・廊下を歩いているとき、 「ああ、あの隅はだれも知らないが、 昨日この僕がきれいにしたのだ」 と思える。それは、学校の中での自己の存在感を持つことであり、 学校を愛する心の具体的な現れだ。 5) いっさい自分自身の心を尺度にして正直に過ごす時間とする段階 「正直清掃」・自分が黙ってやれるようになって初めて、 平気で人に話しかけることがいかにいけないか、 迷惑をかけることになるかが、徐々にわかってきます。 わかってからできるのではなくて、できてから初めてわかるのです。・「がまん清掃」が実現するまでには、相当に個人差がある。・5段階の発想は、ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」という概念に一致。 (他の子どもや教師の援助によって達成できる可能性の領域)・「自問清掃」では、子ども達にまず到達すべき地点を示し、 そこに至るための手順と方法とを、5つの段階と条件という形で モデル化して提起します。(以上、第4章の終わりまで)=========================== 次回は、第5章「魔法の『水をやる』」を参照します。それでは、また! ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.28
コメント(0)
-

『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』2 「3つの玉」を磨くこと
この本に書いてあることが、今の教育には必要だと思います。『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』===========================『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』 読書メモ2(第3章~第4章のp91まで。 #の緑文字は僕のコメントです。))・心磨きとは、大脳の前頭葉にある「3つの玉」を磨くこと。・3つの玉: ○がまん玉 ○みつけ玉 ○しんせつ玉 =人間が他の動物に比べて著しく発達している前頭葉のはたらき#この3つの玉の話、 わりと子どもの心にスッと入りやすいようです。 3つにしぼっているので、おぼえやすいし、分かりやすいですね。・「3つの玉」に対応する掃除の様相: ○がまん清掃: 何分くらい黙って(友だちと離れて1人で) 掃除に取り組むことができるか挑戦する掃除#人と比べるのではなく、 前の自分との比較で、 どれだけ黙ってできるようになったかに挑戦するのが大事、らしいです。 僕は「百マス計算」などの指導で、 「人と比べるではなく、自分の記録と比べる」といった指導をしてきましたが、 そういったこととちょっと似ている気がします。 しかも、計算よりも掃除の方が、 より自分の心というものがはっきりあらわれます。 これは非常にシビアな自分磨きではないかと思います。 ○しんせつ清掃: 友だちのよいところを見つけたり、 お互いに気働きをして助け合ったりしながらする掃除#これも黙って行うのです。 手話などのハンドサインもダメです。 「気働き」ということをここまではっきりと子どもに教えようとした実践を 僕は初めて知りました。 ○みつけ清掃: 人が見つけられないような仕事を見つけたり、 人が考えられないような方法で掃除したり、 大体きれいになったと思う状態からさらに時間いっぱい 仕事を見つけとおすことができるような掃除・5段階の清掃プラン#5つの中身は、明日、明かします。(^。^) (うち3つは、上の「○○清掃」が当てはまるのですが。)・まるで大切な花を咲かせていく過程のように、 畑の土を耕して、種を蒔き、水をやってじっと待ち、 芽が出たら育てる。 そして、機を見ては間引きをするように単純化して方向性をはっきりさせ、 「道徳」の授業で深めていく。#「道徳」の授業という言葉が出てきたことにも、僕は好感を覚えました。 「道徳」の授業は、国語や算数のようにカリキュラムがはっきりしていませんが、 それだけに、学級担任の思いをクラス全体につなげていく、 非常に大事な時間だと思っています。 この時間を1番大事にするということが、 もっとも、クラスを育てるということにつながるのでは、と思っています。(以上、p91まで)===========================5段階の清掃プランの詳細については明日!(^0^)それでは、また! ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.27
コメント(0)
-

『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』1 心を磨こう
またまたすごい本を読んでしまいました。前から気になっていたこの本、図書館で借りられたので、読破しました。この本に書いてあることが、今の教育には必要だと思います。『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』(平田治、三五館、2005、1400円)============================【内容情報】(「BOOK」データベースより)心を磨く魔法の掃除「自問清掃」を知っていますか。子どもから「自発性」を引き出す、二十一世紀の人間教育のことです。この本では、感動的な子ども達の姿を示しながら、「自問清掃」での魔法のかけ方、自発性の引き出し方をたどっていきます。 【目次】(「BOOK」データベースより)1 私の奮闘記/2 「自問清掃」参観/3 「自問清掃」で育つ/4 魔法の「種を蒔く」/5 魔法の「水をやる」/6 「出た芽」を育てる/7 「道徳」で深める/8 「自問」を活かして/9 「自問清掃」を深めるQ&A============================図書館の本ですので線は引けませんでしたが線を引きたいところが山ほどありました。代わりに付箋を貼ったら、付箋が山ほどついてしまいました。その、付箋をつけたところを、今から読み返していき、読書メモとして記録しておきます。===========================『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』 読書メモ1(第2章まで。 #の緑文字は僕のコメントです。))・「自問清掃」・私たち大人が、子どもに何かやらせようとする姿勢から、 自ら何かをやろうとする姿勢に、自分の生き方を転換できますか、 というメッセージが含まれている。・子どもを変えよう変えようなどと考えずに、 「自問」の場に共に立つことです。 掃除の時間では、自分もまっさらな一人の人間になって、 自分の心磨きに専心すればよい。#ここにおいて、自分の課題と、昨今の「教育」の課題は一致します。 こういった読書メモを書いて、自分が成長しようとすることと、 子どもたちの教育に生かそうということも、 同じ発想によるものです。 つまり、「させようとする前に、自分からする」 子どもと共に、大人も同じ成長の舞台に立つということです。 ただ、惜しむらくは、自分の場合、 「実践」が足りないのです。(>。<) 「掃除」は、「実践」の最も端的で、日常的に、身近なものです。・床を磨けば、心も磨かれるなどとは考えない。 むしろ逆に、心を磨こう磨こうとしていると、 結果として校舎もきれいになってしまうと、発想を逆転するわけです。 逆転発想の掃除です。#こういう、「逆転発想」という考え方、大好きです。 発想の面白さ、意外な解決は、「逆転発想」から生まれます。・「自問清掃」の核心は、「信じて待つ」・「自問清掃」では、掃除を堂々と休んでよいことになっている。 全員の子どもが一人残らず働いていることの方が 異常だと考えるからです。・座って休んでいることを、サボっているとは見ない。 一心に掃除している子どももいる、 黙って座って休んでいる子どももいる。 それが、なんの違和感もなく共存しているのは、 たいへん素敵なことです。 ・掃除は嫌なものか?・「指導者は始導者」・その発想の根本には禅(行)の思想もある。(p61まで)===========================長くなるので、次回に続きます。 この本には続編もあります。こちらもぜひ読んでみたいです。↓『「魔法の掃除」13カ月~「Iメッセージ」を語れる教師』(平田治、三五館、2007、1400円)============================【内容情報】(「BOOK」データベースより)ほめない、叱らない、比べないから子どもが伸びる。そんな先生いていいの?【目次】(「BOOK」データベースより)授業開き 「自問清掃」とは何か?/四月 自発性を信じて/五月 自発性を引き出す/六月 輝き出す子どもたち/七月 波を広げる/八月 「信じて待つ」/九月 生活への広がり/十月 熟成される心/十一月 確実な歩みのために/十二月 成長を確かめる/新たな段階への挑戦/休むことと自律の意味/理念と実践と/反「自問」の清掃方式============================ ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.26
コメント(2)
-

『おとうさんはウルトラマン/おとうさんの育自書』
読んでいて元気になる、おとうさんのための本を見つけました。『おとうさんはウルトラマン/おとうさんの育自書』(宮西達也、学研、2005、1500円)=========================【内容情報】(「BOOK」データベースより)子育ては自分育て!親子に人気の絵本「おとうさんはウルトラマン」の作者であり、4人の子どものおとうさんである絵本作家宮西達也が贈る、おとうさんに読んでほしい育自書。===========================自分が「おとうさん」になってまだ6か月半。(^^;)まだまだ実感の湧かない自分ですが、自ら成長していく姿、成長していこうとする姿を子どもに見せていきたい、と思います。では、同書から1つ、元気をもらった部分を引用します。=========================子どもは おとうさんのいっしょうけんめい・力のかぎりやっている姿を見てがんばろうと思う。おとうさんのいっしょうけんめいやっている姿が、おとうさんの力のかぎりやっている姿が、子どもに力を与える。そして、いっしょうけんめい・力のかぎりやっての失敗は 負けじゃない。本当の負けは、なにもしないことだ。(『おとうさんの育自書』p11より)========================= ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.25
コメント(2)
-

自然学校からの帰りに防災学習
自然学校の引率で、土・日・月と、淡路島に行ってきました。玉ねぎがおいしかったです。(^。^)今日は帰り道で北淡(ほくだん)震災記念公園に寄りました。警報が出ていましたが震災記念公園やたこフェリー乗船時にはほとんど雨が降っておらず、よかったです。西脇市まで帰ってきたら、かなり河川が増水していました。ニュースでも流れていたとか。今年は防災担当になり、現在「水害」に関する学習への取組をすすめているところです。自宅への帰り道を少し変更して、河川の増水状況を確認。ケイタイで資料写真やビデオを撮影。もしかすると今度の「総合防災学習」の日に使用するかもしれません。地震の様子も河川の氾濫も、実際に目の当たりにすると、身が引き締まる思いです。防災学習での視覚的提示資料は必須だな、と思いました。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.24
コメント(0)
-

玄侑宗久『観音力』2~からだは空だ
『観音力』(玄侑宗久 ,PHP,2009,1100円)ウイルスにかかっていました。(>。<)なので、ちょっと空いての更新です。前回の続きです。===============================玄侑宗久『観音力』読書メモ2(#の緑文字は僕のコメントです。)・多重人格なら、別人格のときに 老眼が治ったり、右利きが左利きになったりする。・「からだ」は「空(から)だ」 それを使う人によって、いろんなふうに使える。#多重人格の勉強は大学のときにしました。 非常に不思議な現象です。 こういう現象がもし本当だとするなら、 「体は器にすぎなくて、たましいが体に入っているんだ」といったことが うなづけます。・原因を一つに絞ろうとする「単因論」。 仏教が最も嫌うところ。 ・コオロギは完全に鳴くタイミングを(集団で)一致させている。 =「同期」:なぜピタッと合うのか。・人間の体にも「同期」がある。・ベースの部分では、われわれは他の命に合わせようとしている。・仏教が世界の宗教の中で珍しいのは、 大切な徳目として「智慧」というものを置いている。 智慧――「般若」・智慧が持てなければ、慈悲は発現しない。 ・観自在とは「私」から離れて見ること・「不垢不浄」・五木寛之は風呂へ入っても、石けんで体を洗わない。 遠藤周作に教えられた。・汚いというのは、子どもの頃から身につけてきた錯覚の最たるもの。・「不増不減」・増えないし、減らない。・私の財布から1万円が減ったんだけど、誰かのところには、ある。・移動して、元気でやれよと見送れるようなら、大したもの。#「般若心経」の本はいくつか読みましたが、 「不垢不浄」や「不増不減」のこの本の解説は一番分かりやすかったです。・庭を掃くという行為: きれいにするためというより、自分にとっての手入れ。 キリがなければないほどいい。#「キリがない」というのは、今までマイナスにとらえることばかりでした。 「キリがない」ことに「"私"から離れる」というメリットがあるとは、 大きな気づきです。・「真言」を21回唱える。・何回も何回も同じ真言を唱えることで 「私」の状態が変わる。・お釈迦様の教え 「一切、あれを食べないとか、これを食べるとかいう、 そういうことは考えるな。 頂いたものを、何でもありがたくいただく」・一番効率のいいネットワークは、 ご近所をまず知っていることが第一。・これが全体に情報を速やかに伝えるための理想的な形。・うちのお母ちゃんを救いたいときに、 お母ちゃんに直接お供えしたんじゃダメなんです。 「ネットワークの全体に供養しろ」 仏教は、みんながつながっていると考える。===============================これで、この本の紹介を終わります。明日から自然学校に行ってきます。お天気に恵まれるといいな。それでは、また! ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.21
コメント(2)
-

玄侑宗久『観音力』1~相手に応じて自分を無限に変化させること
『観音力』(玄侑宗久 ,PHP,2009,1100円)玄侑宗久『観音力』を読みました。仏教に関することや、心に関することが分かりやすく述べられています。「へえ!」と思うことが多くありました。===============================玄侑宗久『観音力』読書メモ1(「第1章 観音力ということ」より)・やめてもらいたいときに「もうやめなさいよ」と云う = はたしていちばん効果的なのか? ひねりが足りない・正しいことが好きな人というのは、 「はた迷惑かもしれないけど」という思いがない。・正面から説教しても絶対無理。 まずその人が食いつくようなエサを前に出さなきゃいけない。・観音というのは、相手に応じて自分を無限に変化させること。・観音さまは正しさを主張したりはしない。 応じて変化する力、これが観音さまの場合、とてつもなく大きい。・日本記録は数えで243歳。 江戸の天保年間 三河の国の百姓である満平さん夫妻が日本一だった。===============================↑最後の、長い聞記録の話、びっくりしました。 本当かな? いちおう理論上は、100歳を超えてもまだまだ長生きできると 聞いたことはありますが、それにしても243歳・・・! 第2章以降は、また次回。(^^)それでは! ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.18
コメント(0)
-

指導技術を磨く
昨日、家の倉庫にしまっていた本を全部整理・整頓しました。しまったまま忘れていた授業づくりや指導技術の本がたくさん出てきました。もう1回読もう、と引っぱり出して並べた本だけでも20冊ぐらいあります。 現在、4年生算数の少人数授業を担当していますが、まだまだ教材研究も子どもを見る力も、指導技術も足りない、と感じています。あんなにたくさんの本を買って懸命に読んでいた頃に比べて教師としての力量が上がっているのか疑問です。特別支援学級担任としての個別指導的な関わりをすることが続いていたので、集団指導についてはかえって力量が落ちているかもしれません。校務分掌上の仕事も急に入ってきて立てこんでいるのですが、授業準備や「教師修行」も身を入れてやろうと思います。さきほどは参考にするために超久しぶりに◆TOSSオリジナル教材http://www.tiotoss.jp/のサイトを利用しました。実際の授業を記録した音声CDを買いました。価格が2万円もします。高いので、1か月前には購入を見送ったものです。▼向山洋一算数授業CD4年「大きな数」 http://www.tiotoss.jp/products/detail.php?product_id=122「教師の言葉を削る」ことを実践されている向山洋一先生の録音です。自分の今の反省として、教師の言葉が多く、教師の説明が多くなっていると感じているので、こういったCDを聴いてみたいと思いました。あと、今年度はTTとしての動きも多い自分にとって、TT授業の目指すものをはっきり感じたい、と思ったのも購入動機です。自分としてはかなり思い切った買い物です。(^^;)ほかにも、授業の実際が感じられる録音や録画を手当たりしだい探しています。「算数」で、という条件をつけると、これがなかなかないのです。もしご存知の方は、ぜひお知らせください。(^0^) ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.17
コメント(0)
-

藤原和博『つなげる力』5~修正主義でやってみる!
『つなげる力』(藤原和博、文藝春秋、1500円)この本の読書メモ。今回が第5回。最終回です。参照個所は、「第6章 人を動かす」の続きから。============================『つなげる力』読書メモ5 (p194~)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・「正解」ではなく「納得解」の時代 = 修正主義の時代・走りながら考えるのが基本・だから、リズムとテンポが大事になる。 スピーディーに修正をかけながら、間違ったなと思ったら すぐに引っ込める。 こっちかなという方向に小さく打ち出して、 当たりがあれば、さらに掘り進む。・小さなアプローチをリズムとテンポよくしている人には、 自ら機会を創り出すチャンスがたくさん訪れる。(企画の起案者側の話法例:「ドテラ」の場合)・「とにかく、一人でもやりたいという生徒がいれば、 1人の学生ボランティアからでも募集を始めてみようと思います。」 「もっと有効な手があればぜひ"代案"を出してください。 来週の会議までに代案が出なければ、原案でスタートしてみて、 どんどん修正していきましょう!」#こういう積極的な提案、 失敗しても修正すればいいと思ってとにかくスタートする勇気、大事ですね。 僕も職員会議でそういう提案をしたいと思います。 (さっそく水曜に防災学習の提案をします。 例年にない内容なので反対もあるかもしれませんが、 勇気を持って具体的に提案し、修正主義でスタートさせたいです。)・現場からのフィードバックと、 それにともなう修正のリズムとテンポを上げる。・同時多発的な「修正」を可能にする 「情報の共有」がなにより大事。 ・学校現場などのなかには、 「いくらかかっているか」という意識がまるでないところがある。・公立中の授業は、生徒一人当たり1コマが1000円という勘定になる。・「あなたが今やった授業は、生徒一人から1000円の授業料をとるのに ふさわしい授業でしたか?」============================最後の「コスト意識」の話、耳の痛い話です。自分の授業実践を振り返れば、そのほとんどが、授業料1000円を1人ずつからとるのに値するかといえば、疑問です。1コマ1000円という計算は、塾から比べれば安いかもしれません。しかし、1000円分、きちんと学力をつけたか、成果があるのかと問われたとき、それが感じられるのかどうか。前回の日記でも書きましたが、授業前と授業後のビフォーアフターですね。ビフォーアフターで、成果が、1人1000円分、あったのか?長い目で見る教育も必要なので、1時間で成果が見られることだけ考えろというわけではないですが、やっぱりこういうコスト意識は、自分たちになかなか足りないところだと思います。民間と違ってコスト意識を感じにくい分、個人的に意識して仕事に臨むことは、必要だと思います。 以上で、藤原和博『つなげる力』の読書メモを終わります。藤原和博さんの本は他にも読みました。どれも読みやすく、役に立つことが書いてありました。他の本もぜひ紹介したいです。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.16
コメント(0)
-

中谷彰宏『あなたが動けば、人は動く』
『あなたが動けば人は動く ~"この人のために"と思わせる50の方法』(中谷彰宏、PHP、1998)図書館で借りた本。今日が返す日なので、付箋を貼ったところを読書メモにしてWeb入力しておきます。中谷さんの本、4冊借りましたが、これが一番よかったです。===========================『あなたが動けば人は動く』読書メモ・命令ではなく、具体的にどうすればいいか質問すること。 部下に「こうしろ」というのではなく、 「○○はどうなんだ?」と聞いていく。(例)ヤクルトの野村監督は古田捕手に 「こういうふうに配球しろ」と言うのではなく、 「今、なぜこういう配球をしたんだ?」と聞く。・人を動かすのは、お金や数字ではなく、人間の魅力です。・魅力を引き出すために ほめたり、感謝することがあるのです。・人間はお金や数字のためには働きません。 人間はもっと賢いです。 人間はバカではない。・ちゃんとした目的があれば、数字やお金など掲げなくても、 いくらでも働いてくれる。 それだけ賢い存在です。 相手のほうが自分よりも賢いと思えて初めて その人は相手を動かすことができる。・人を動かす力を持っている人は、 大問題をニコニコ語れます。 「いやあ、参ったよ」と笑いながら言えます。 「いやあ、売れないねえ」とニコニコ笑いながら、売れない状況を話せる。 「どうするかねえ、この売れないのを」とニコニコしながら言われると、 悲惨な状況であるにもかかわらず、 その悲惨な状態を明るく受けとめることができます。・同報メールで一瞬にして1000人にメッセージを送ることができても、 それだけでは人間は動きません。 やはり面と向かって直接会ったときに初めて 「この人はこういう人なんだ。 この人から買おう」という気持ちになります。===========================僕はメールなどお手軽な手段で何でもすまそうとしてしまいます。肉声、手紙、大事ですね。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.15
コメント(0)
-

藤原和博『つなげる力』4~貢献が先、自立が後!
『つなげる力』(藤原和博、文藝春秋、1500円)この本の読書メモ。今回が第4回。「第5章 子どもたちと世界をつなげる」の続きからです。============================『つなげる力』読書メモ4 (p165~193)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)(「よのなか」科検定試験における、中学3年生の回答より) ・1人では、自立できない。・貢献することで自立できる。・誰かのために一生懸命になれたら、自立したことになるのだ。・「貢献が先、自立が後」という藤原校長のメッセージ#なるほど。 「言い得て妙」だと思います。 (第6章「人を動かす」)・誰だって目に見える成果がほしい・「目に見える成果」を共有し続けられる限り、 みなお互いエネルギー交換をしながら動機づけられる。 つながりながら、高め合っていることを確信できる。・自分の成長実感のないものを続ける行為に、 どうして子どもが耐えられるだろう。#学校の授業1時間で、 授業前と授業後でどんな成果を実感できているだろうか。 TV番組ではないが、 ビフォーアフターではっきりと成長・変化を実感できることは大事なこと。 それがない。 あまりにも、ない。 ただ、1時間が過ぎただけ。 そんな授業では・・・まったく、申し訳ない限りです。(>。<;) 「ビフォーアフター」で、1ポイントでも、成果が見られること。 それを、「授業」を考える基本的な合い言葉にしていきたいです。 ↑ ↓(「成長実感」を感じさせる具体例)・計算の不得意な子を集めた「ドテラ」の「らくだコース」では DS「計算DSトレーニング」を使って、 個人別に細かく成果を出させ、動機づけエンジンが切れないようにした。【DS】「計算DSトレーニング」(IEインスティテュート、2007、3990円 ↑リンク先なら新品最安値1480円。)#DSソフト学習のいいところは、 学習したら、その記録が自動的につくところですね。 紙の上での勉強なら、別紙の「がんばりカード」などに また別に記録しないといけない。 DSなら自動的。勝手に記録がされて、いままでの履歴が分かる。 この差は、大きいです。 ちなみに僕は個人的にDSの「もっと英語漬け」を続けています。・「お願い」場面でも、 自分に現れた「目に見える成果」を相手にフィードバックし続け、 「あなたがやってくれているおかげで、 私はこんなによくなっていますよ」という実感を与え続けること。#「おかげさま」という感謝の気持ちを、 具体的に見せていくということですね。 相手の「貢献」を、はっきりと「成果」として実感させていく。 こういうことも、大事です。・どういうときに「子どもの目が輝く」のか 具体的に述べるべきだ。・「心豊かに」というのは具体的にどんな状態をいうのか・「社会」という言葉をブレークダウン(細分化)して、 具体的に、誰と誰なら学校に協力することが可能なのかを洗い出す・どこに集中すべきなのかを明確に指示する・リーダーは、言葉づかいが具体的でなければならない。・たとえ話:抽象的なコンセプトを、具体的なお話で語る技術・具体的な行動に結びつけたいなら、 抽象的な美徳を具体的な事例で語る 「物語」的な手法を身につける・自分の知っているヒトやモノや事につながれば、 子どもでも、その美徳について腑に落ちる・「ほら、あのヒト、知ってるでしょ。 あんなふうになるといいよね」という話法 (具体的なモデルを示す)#身につけたいです。こういう話し方。 子どもが話を聞いて、「そういうふうになりたい」と思えるかどうか。 具体的なモデルを示されると、俄然にやる気になります。 少なくとも、僕はそういうタイプです。 自分が聞いて感動したり、やる気に火がひいた話を 子どもに聞かせてやるのもいいと思います。 購読しているメルマガ「夢エール」の話などは、 やる気に火がつく具体的なモデル事例が示されていることが多いです。 そういう話も、自分もしていきたいな。(以上、p193まで)============================このあたり、触発される内容が続いており、読書メモにも熱が入ります。 第6章をまだ残しています。次回は「リズムとテンポ」の話から。そろそろ終わりが見えてきました。ではまた、次回! ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.15
コメント(1)
-

藤原和博『つなげる力』3~子どもたちと世界をつなげる
『つなげる力』(藤原和博、文藝春秋、1500円)この本の読書メモ。今回が第3回。今日は「第5章 子どもたちと世界をつなげる」 の途中までを参照しています。============================『つなげる力』読書メモ3 (p139~p164)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・「学校で習うことがどう世の中とつながっているのか、 さっぱりイメージできないんだよね。」・なにか、社会問題の根っこのところを全部目隠しされて、 耳だけで教えられてる気がする。#教えている方も、 耳だけで教えている気がします。 (教え手が使うのは、「口だけ」かな?) そこからの脱皮を目指したいところですが、 結局また「口だけ」で教えているような気がして、 毎日が反省です(>。<;)。・「よのなか科」 :「学校の授業」と「よのなか」をつなげた。 世の中で起こっている現実と学校の授業とのリンク・子どもたちに馴染みのあるロールプレイやシミュレーションという ゲーム的な学習法を多用し、授業で取り上げる課題を 自分のこととして考えるよう導いている。#「よのなか科」は画期的な授業です。 本当に、世の中のことがよくわかります。 読み物として本で読むだけでも、かなりおもしろいです。(^^) ウェブサイトに、詳細な実践情報が集積しています。▼全国[よのなか]科ネットワーク・本当にそうだろうかといったん疑ってみる。 = 批判的洞察力(クリティカル・シンキング)・つながっていないものをつなげることで 解決にいたる問題は世界中に広がっている。・「いま、塾を出ました」と塾側が親のケータイメールに配信するサービス => ちょっとした情報をつなげるだけで、 サービスレベルが格段に上がる!・Wii:ゲーム上の対戦を「家族のコミュニケーション」に結びつけた。・世界が「つながっている」と意識することだ。#森源太さんの曲で、『ちゃんと繋がってる』という曲があります。 いい曲です。(^^) ・『親と子の[よのなか科]』 「ある親子の食卓での会話を例にして、日常の身近な話題から入り、 物事を論理的に考えるクセをつけるための具体的な方法を提示しながら、 「学力」や「生きる力」の本質に迫る。 」(「BOOK」データベースより)・「1枚の新聞紙をもし100回折ったら、 どれだけの厚さになるだろうか」 計算してみるとどうなるか。 じつは、宇宙の果てまで行ってしまうのだ。 新聞紙は、こうして宇宙論にまで「つながる」。#こういう発想、大好きです。 予想もつかない結果が「なるほど、たしかに!」と納得できたとき、 勉強が自分のものになり、勉強が楽しくなります。(以上、p164まで)============================長くなったので、第5章をまだ少し残したまま、次回へ続きます。ではまた! ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.14
コメント(0)
-

自分の授業の反省~録音を聞いて~
今日、久しぶりに、自分の授業の録音を聞きました。ボイスレコーダーに録音した、1週間前の授業録音。(4年生「1億を超える数」単元初回授業。 電子黒板を初めて使用した授業です。)途中で電池が切れたので、録音されていたのは、授業の前半だけでしたが・・・。FMトランスミッターで電波を飛ばして、車内で帰宅途中に聞きました。聞いてみての感想。・子どもの声はかわいい。こうやって後できくのもいいものです。・自分の声は、はっきりは言っているけれど、 メリハリ・変化がない。もっと「声に表情」をつけて、驚いたり、怒ったり、笑ったり、といった感情の表出、「先生の声の分かりやすさ」があるともっといい、と思いました。せっかく演劇の経験があるので、それを生かして、表現力を鍛えていきたいです。特別支援教育の観点の中に、「分かりやすさ」というものがありますが、教材・教具や視覚提示の分かりやすさといったもののほかに、先生の話し方、表情、動作、声の調子の分かりやすさといったものがあると思います。自分で自分の授業中の声を聞いてみたところ、まじめで平坦な感じで、そういった「分かりやすさ」に乏しいと思いました。きっと、もっと変化をつけていっていいはずです。その方が、「先生が驚いた/ほめた/笑った/悲しんだ/叱った/怒った/うれしい/・・・」といったこちらの行動(気持ち)がはっきりと子どもに伝わり、やり取りが円滑に進んでいくような気がします。そういったところを、鍛えていきたいです。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.13
コメント(0)
-

藤原和博『つなげる力』2~「正解主義」から「修正主義」へ!
『つなげる力』(藤原和博、文藝春秋、1500円)この本の読書メモを続けます。今回が第2回。今日は「第3章 正解のない問題に取り組む」 「第4章 情報編集力のテクニック」を参照します。============================『つなげる力』読書メモ2 (p85~137)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・自分の経験した世の中の現実との関係で答えなければ説得力は生まれない。・日本の子どもたちは、こうした「正解が1つではない」記述問題に対して 約4割が「無答」。#この「無回答」、毎年行っている学力テストでも 記述式になるととたんに多くなります。 今の日本の子どもたちの課題ですね。・正解ではなく納得できる解を見つける・現実の世の中を数学的に思考してみる視点 (視点の移動)・「正解主義」→「修正主義」へ! まず、やってみて、それから無限に修正していくやり方・失敗してもいいと教える・成功を語るより、失敗を語るほうがいい作文が書けることを教える。・失敗談のほうがはるかに印象的・「負」の体験をおそれるな!・「学校というところは、正解を教えるところである」 という呪縛からの解放・家庭ではよく遊ぶこと。・「遊び」は、「予定調和」とはほど遠く、 したがって「修正主義」にならざるを得ない。 だから、いい。・「事なかれ主義」ではなく、 むしろ「事あれ主義」で生きること。・失敗とそのリカバリーを評価し、 試行錯誤しながら生きる子どもたちのドラマを、 覚悟を持って見守っていただきたい。#自分自身が、失敗に打たれ弱いので、 自分への激励と取りました。(^^) 教室で、失敗をオープンにできる空気を作るには、 まず、先生が、失敗を恐れずに、むしろそれを楽しむくらいの姿勢を 見せることですね。 こういう本を読んでいると、 「失敗してもいいんだ」ということに自信を持つことができます。 ・「情報編集力」・「本来は複雑でむずかしいことを、こんなふうに、 やさしく図に描いて説明できる力のことを 『情報編集力』と呼びます。」 「他人に知ってほしい自分の考えや思いを 絵やマンガや図に描いて、やさしく伝えられたら、うれしいでしょう。」・「情報編集力」は「つなげる力」なのだから 「引き寄せる魅力」にもなり、したがって「味方をふやす技術」に通じる。(以上、p137まで)============================前回と今回で紹介し終わろうと思っていたのですが、長くなったので、次回へ続きます。ではまた次回! ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.09
コメント(0)
-

藤原和博『つなげる力』1
『つなげる力』(藤原和博、文藝春秋、1500円)============================【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 つなげることで世界は変わる第2章 学校と塾をつなげる第3章 正解のない問題に取り組む第4章 情報編集力のテクニック第5章 子どもたちと世界をつなげる第6章 人を動かす第7章 偶然をつなげる============================ちょっと前に読んだ本ですが、よかったです。著者の藤原和博先生は、民間校長として有名な方で、かなり多数の著書を書かれています。具体的で胸のすく実践事例が多くあり、全校的な取組や、地域を巻き込む取組をしようとしたときには非常に参考になります。以前線を引いたところを読み返しながら、具体的に本書の中の言葉を抜粋して紹介します。============================『つなげる力』読書メモ1 (p83まで)・教育現場の正解主義を払しょくせよ・正解のない問題にどのように取り組んでいくか・現代社会のさまざまな問題は、 「つなげる」ことでドラマチックに解決していく。・三方一両得(トライアングル・ハッピー)・「学校支援地域本部」↑藤原校長の取組をモデルとして文科省が全国普及に乗り出したものです。・コミュニケーションの渦の中で 「ナナメの関係」をはぐくみながら成長する。・宿題を中心に自学自習する土曜寺子屋「ドテラ」・非常に厚い落ちこぼれ対策 + できる子、もっと先に進みたい子のためのプロジェクト ・英語アドベンチャーコース 大学の先生や塾の講師の力も借りて、文字どおり総力戦を試みた。・英語リーダーたちが授業でもほかの子を教えるという好循環を生んだ・生徒同士で学び合う ・「塾」 と 「学校」 同じ一人の生徒を両側から支え合って、対峙するのではなく、 同じ方向を向いて歩けないのか ↓ 「夜スペ」 (サピックスという、塾の中の塾が、学校の校舎で、 公立中学の生徒の指導をする。)・それがどこに帰属する人であれ、 同志としてパートナーシップを組めるはずだ。・そもそも、多様化する子どもたちに公立学校がどう対応できるのか・英数国ともじっさいの世の中での現象と知識との 「つながり」を重視して教えてほしい・私は「不健全な理想主義」よりも、 目の前の子どもたちに対応する「健全な現実主義」をとりたい(p83まで)============================僕は本書の題名の「つなげる力」というのは、これからの学校や授業を改善するキーワードだと思っています。個人的にすごく注目している言葉です。 また次回も、後半を紹介します。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.06
コメント(2)
-

(英語)(研究会)日本児童英語教育学会 関西大会 5月30日(日) 大阪
日本児童英語教育学会(JASTEC)関西支部 春季研究大会 の案内が届きました。これの全国大会に昨年度参加したのですが、大変よかったです。(そのときの報告はブログに載せています。 ▼英語へ取り組む学校としてのゴールイメージがはっきりしてきたぞ!! 掲載画像は別名保存でダウンロードすると拡大して見られます。)校長と相談し、出張で行けることになりました。僕と同期の先生も発表されます。大変楽しみにしています。以下、研究大会の案内の転載です。(データ転載元: http://ace1.yasuda-u.ac.jp/~jastec/2010/kansai-spring.pdf)==============================日本児童英語教育学会(JASTEC)関西支部 春季研究大会日 時: 2010年5月30日(日) 10:00~17:00(受付9:30~)(予約の必要はございません。会場に直接お越しください。)場 所: 大阪成蹊大学(大阪市東淀川区相川3丁目10-62)阪急相川駅より東へ200m、地下鉄今里筋線井高野駅から西へ850m参加費: 一般1000円、学部学生500円*JASTEC会員は無料。賛助会員は所属の3名まで無料。内 容: 1.ワークショップ:10:00~11:00(1)「歌とチャンツの効果的な使い方」発表者:箱崎 雄子(追手門学院大学)(2)「国際理解教育を目指した教材と指導の進め方」発表者:別府 邦子(池田市立細河中学校他)2.ビデオによる研究授業と協議:11:10~12:20「はじめての英語との出会いを大切にした5年生の英語活動」授業者:菅原 淳也(芦屋市立潮見小学校)多田 玲子(Group of English Teachers、親和女子大学(非))コメンテーター:樋口 忠彦(元近畿大学)3.総会:12:20~12:30 司会:高田 悦子(大阪キリスト教短期大学(非))4.研究・実践発表:13:40~15:35第1会場(1)「外国語活動を核としたコミュニケーション能力の育成」角崎 洋人(枚方市立春日小学校)、吉田 直美(枚方市英語教育指導助手)(2)「発達段階に合った教材と指導法-外国語活動授業展開のプロトタイプに焦点を当てて-」辻 伸幸(和歌山大学附属小学校)(3)「英語活動35時間を支える校内体制をどう作り上げるか」村上 力磨(神戸市教育委員会)第2会場 (1)「日本人児童が英語を学習する際のリキャストの有効性-ケース・スタディーを通して-」川口 薫(元光泉高等学校他)(2)「日本人小学校英語指導者の資質診断テストの結果が示唆するもの」松永 舞(近畿大学)(3)「大学の授業だけが学びの場では物足りない-大学演習科目の公立小学校スクール・インターンシップ実践-」5.講演:15:45~16:55「歴史の教訓と異言語教育」講演者:大谷 泰照(大阪大学名誉教授)司 会:加賀田 哲也(大阪教育大学)============================== ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.06
コメント(0)
-

『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』9~「あんなに見事に子どもたち全員が納得するものだろうか?」
『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』(正木孝昌、黎明書房 、2009、2000円)子どもの「たい」を大事にする、この本の読書メモ、今回が最終回。第0回~第1回のブログ記事は、「読書メモ一覧サイト」に追記したのでそちらからご覧ください。======================正木孝昌『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』読書メモ9(p171~より) (・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)(「第5章 資料集めを教える」より)・棒グラフの学習で大切なのは、 自分の身の回りの出来事の中から、 調べてみたいものを見つけ、調べていく子どもたちの姿です。・誰が調査したのかわからない架空の結果ではありません。 自分たちで調べた結果です。 整理したいという鯛はこの上なく元気です。#本書では、学校の前を通った自動車を調べる 「自動車調べ」の実際の様子が描かれていますが、 割愛します。・グラフのかき方を教えることも大切かもしれません。 しかし、もっと大切なことがあります。 自分の観点を持って、身の回りのことを見る目を持つことです。 (あとがき「授業で大切にしたいこと」より)・よく見かけるのは、一人の子どもが発表すると間髪を入れず、 全員が「いいです」と声を揃えて言う風景。・1人の子どもの発表をあんなに見事に子どもたち全員が 納得するものだろうか。 よく分からない子どもたちもいるはずである。・子どもたちの疑問や思いが、 あの「いいです」という掛け声に押し潰されていく。#僕の勤務校でも、誰かが発表した時によく見られる光景です。 このこと自体は、また別の意味も持っていると思うので 一概にやめるべきとかいうことは思いませんが、 正木先生の文章を読んでからは、 そんなにこのことにこだわらなくなりました。・どうすればいいか。 ただ、一つひとつの授業で七転八倒するだけである。#「七転八倒して、いいんだ」と安心しました。 いや、むしろするべきだと。(^。^) ・まず、必要なことは、学級全体が1点を見つめることである。 見つめるものは、短い子どもらしい言葉がいい。#子どもから出てきた言葉をつなぐ、共有していくという授業の意味が、 ここに凝縮されています。 教師の言葉で「教える」授業とは別に、 子どもが子どもの言葉で分かっていく授業が、ここにあります。 ======================長くなりましたが、これで正木先生の『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』の読書メモを終わります。ここまで読んでくださって、ありがとうございました!また一緒に授業について考えましょうね♪(^0^)正木先生の本、この本に続いて他の本も注文して購読しています。今日届いたのは以下の本です。『活動する子どもたちと算数の授業』(正木孝昌、東洋館出版社、1999、2400円)========================【内容情報】(「BOOK」データベースより)授業の本質を徹底して授業の実際そのものに基づいて凝視する。子どもたちが活動している姿を根拠にしながら、授業にかかわる様々な問題を提示し、1万数千時間におよぶ授業に裏打ちされた子どものいっぱいいる授業論を展開する。授業の技術とそれを支えるきめ細かな目は重厚にしてわかりやすい。正木孝昌の算数授業34年の集大成。【目次】(「BOOK」データベースより)序章 それぞれの現実-私の授業論の根底にあるもの/第1章 算数の授業と子どもたち-算数の授業で何をねらうか(授業とは/しなやかな子どもたちと授業 ほか)/第2章 授業における教師の役割(授業における教師の役割/子どもたちの言葉を大切にすること ほか)/第3章 基礎、基本と授業(基礎、基本と授業/授業の条件と基礎、基本 ほか)/第4章 授業の技術とそれを支えるもの(授業の技術を考える/問題文の中に□を効果的に使う ほか)========================それから、読みたいと思っている本はこれです。『受動から能動へ 算数科二段階授業をもとめて』(正木孝昌、東洋館出版社、2007、2500円)==========================【内容情報】(「BOOK」データベースより)授業の技術とそれを支えるものを実践に基づいて凝視する子どものいっぱいいる算数の授業論。【目次】(「BOOK」データベースより)1 受動から能動へ(鯛のいる授業を目指して/二段階授業のすすめ ほか)/2 たくましい学力(貧しい学力と逞しい学力/力ずくの力 ほか)/3 授業の技術を支えるもの(授業の二つの目標/算数の楽しさ ほか)/4 すばらしい子どもたちと(気流/愛言葉 ほか)==========================それでは、また! ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.05
コメント(0)
-

『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』8~「どちらが長い?」の授業
『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』(正木孝昌、黎明書房 、2009、2000円)子どもの「たい」を大事にする、この本の読書メモを続けます。今回が第8回。「第4章 量と測定を教える」から。======================正木孝昌『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』読書メモ8(p145~170より) (・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・自分から対象に働きかけていくという 子どもたちの能動性を伸ばすこと。・「分かる」「できる」だけに力を入れすぎると、 一方、能動性、活動力は減衰してくる。#塾の授業とかは基本的にかなり「分かる」「できる」のみにシフトした授業 のように思います。そういった授業の教授技術から学ぶこともかなりありますが、 特に公立小学校の授業では、「分かる」「できる」だけをめざさない、という バランス感覚が大事だと考えています。 そこを重視するのが「楽しい授業」「子どもの『たい』を生みだす授業」 といったものではないかと思います。 僕は「分かる」「できる」だけでなく、そういったバランスを大事にしたいです。・「長さを比べたい」という「たい」の目を覚ますには?・横向きの線は黒板いっぱいになるほど長くしてある。 「さあ、どちらが長いでしょう」 見ただけで分かります。 しかし、私は大真面目です。 それぞれの線の横にじゃんけんのグーとパーの絵を描きました。#以前も紹介した「じゃんけん発表」です。(p148より)・どちらが長いかは見ただけで分かります。 だから安心して反応できます。 それでも、自分の判断を一人ひとりが手で示すとなると、 ちょっと緊張します。・子どもが30人もいれば、必ず2,3人は 温かいお風呂に入っているような気分の子どもがいます。 その子どもたちの目をしっかり開けさせなくてはならない。 だから、このじゃんけん発表をするのです。#そういう意図があったのですね。 確かに、全員が発表するという機会を授業のはじめのほうで持つことで、 ふわふわしていて気持ちが入っていない子どもの、 授業内容への意識・集中を促す効果があるように思います。 「じゃんけん発表」以外にも「全員起立」などで行うこともあります。 そういう意図的な仕組みを授業の中に入れていくのは大事ですね。・長い線の方を端から少しずつ消していきます。 「さあ、今度はどちらが長いでしょう」(p149より)#2回目のじゃんけん発表では真剣さが変わります。 そして、「答えを知りたい、はっきりさせたい」という「たい」も 生まれました。 このあたりの持っていきかたが、さすがだと思います。・分かってしまっては、みんなの「たい」が消えてしまいます。 だから、つよし君のアイデアだけ認めて、実際に比べるのは止めた。#比べる方法を発表しようとする子どもを途中でストップさせるのが 学級全体へのすばらしい配慮だと思います。 正木先生は、「みんなの『たい』が消える」ことに対して、 非常に大きな警戒感を感じておられます。 この授業(模擬授業)では、実際には 発表の1人目はみんなにヒントを促す役割としてとどめておいて、 みんなの様子をうかがいながら、その次の人が自分のやり方を見せる、 という流れでした。 この、「答えを出すまでに、ヒントだけ出す」という授業の流れ、 そして、そのヒントは「子どもから子どもに出す」という授業の経営法、 どちらも素晴らしいと思います。 そして、最後に正木先生は 発表した子の発表内容の「いいところはどこですか」と 全体に問いかけることもされています。 「ひとりひとりが考える」という授業の具体的内容を見た思いです。・この『芳子さんのいいところはどこですか』という問いかけが とても大切なのです。・これがなかったら、芳子さんの手柄だけで終わってしまいます。 芳子さんはすばらしい。 その彼女のすばらしさをみんなで共有する。 みんなのものにしていく。 そこが授業者の腕です。・芳子さんは、黒板消しを使って長さを比べた。 では、他に使えるものはないだろうか。 子どもたちに聞くと、たくさん単位として使えるものを見つけます。(以上、p170まで)======================上で紹介したのは「長さの測定」に関わる授業内容でしたが、章の後半では「速さを教える」という例も出てきます。そこでは、「電卓の速押し競争」など、いかにも楽しそうな活動をはさみながら、時間や速さについてきまりを見つけ出していく様子が描かれています。「第5章 資料集めを教える」と最後の「授業で大切にしたいこと」については次回にまわしたいと思います。いよいよ次で最終回。では、また次回!お楽しみに。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.04
コメント(0)
-

581アクセス。ありがとうございました!
おかげさまで、5月3日のアクセス数として、このブログでは過去最高の 581をいただきました。 やはり毎日書いていると、見て下さる方も増えるようで、うれしいです。これからも、みなさんのお役にたてるような情報を書いていけたらと思います。よろしくお願いします。(^0^) このGWは特別支援などの研修に全く行かないために近年まれにみる休日を満喫 しています。赤ちゃん連れだと遠出ができないので近場の名所をまわっていますが、毎日がかなり充実しています。今日は藁ぶき屋根のお店で本格的な手打ち十割そばを食べました。夜は地元の牛肉を家で焼いて焼き肉です。(^0^)昨日、牧場で直接買ったお肉です。おいしかったですよ♪食べることばっかり書いていますが、神社やお寺、山や川などの自然もたくさん見て楽しんでいます。神戸に住んでいた時は屋久島・北海道まで出かけないと見られないと思ってい た大自然の美しさが、同じ兵庫県内で十分堪能できています。 休日もあと1日。明日はどう過ごすかな? ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.04
コメント(0)
-

『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』7~スクールプレゼンターでICT授業
『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』(正木孝昌、黎明書房 、2009、2000円)子どもの「たい」を大事にする、この本の読書メモを続けます。今回が第7回。電子黒板での授業で具体的に使える「スクールプレゼンター」という専用ソフトをとりあげます。======================正木孝昌『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』読書メモ7(p135~144 「第3章 図形を教える」より) (・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)4 長方形の性質を調べる(算数授業ICT研究会 全国大会での授業) ・スクールプレゼンターを使えば、 図形を切る、移動する、変形する、動かすなどの操作が容易にできる。#参考リンク、貼っときます。 体験版のダウンロードができます!▼スクールプレゼンター▲上の画像は、スクールプレゼンター体験版の画面をとりこんだものです。 ハサミツールを使うことにより、任意の場所で線を引き、 実際に画面上でまっぷたつに図形を切ることができます。・しかし、一方、図形の学習では、 自分の手で作り、自分の手で操作することがなによりも大切。#ICT授業の目的は、ICTを使うことにあるのではありません。 やはり、子どもが実際に身近なものを操作する活動は大事ですね!・課題は 「1本の直線で2つのぴったり重なる形に分けてみよう」・まず、一斉に空中に、その線の方向を描かせてみる。 子どもたちの1人ひとりが、自分の考えた線を持つ。(以上、p144まで)======================この授業の実際が、授業見学をされた一人の先生のブログで詳細報告されています。先ほど見させていただき、大変勉強になりました。▼第11回 研修報告 「算数授業ICT研究会全国大会で伝説正木先生の授業を観た!」 (ブログ「とげとげ★先生の教育本フォトリー日誌」より)電子黒板を使った授業は、5月上旬に実際におこなっていきますので現在その準備中です。以下の書籍も役立ちそうなので、ネットで取り寄せました。『スクールプレゼンターで変わる算数の授業~IT時代の黒板革命』(算数授業IT研究会 、東洋館出版社、2006、2500円) =============================【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 スクールプレゼンターの可能性を探る(スクールプレゼンターってなあに/現場の教師とともに成長するオーサリングツール ほか)/第2章 スクールプレゼンター活用例(1年『たし算』-アクション機能で、子どもの声を引き出す コピー機能で、同じものを繰り返しみせる-イメージづくりと計算の習熟/1年『いくつといくつ』-問題場面をゲーム化して-5の構成を理解する ほか)/第3章 スクールプレゼンターを使った授業の実際-第1回算数授業IT研究大会より(5年「三角形の面積」-スクプレで、考える楽しさを共有する/6年『単位量あたりの大きさ(速さ)』-アニメーションで動かし、速さを数値化する必要性を感じ取らせる)/第4章 スクールプレゼンターの使い方-操作マニュアル(基本的な操作と2つの画面/授業でのイメージ-実行画面での操作 ほか)=============================正木先生の本の読書メモは、まだ続きます。次回は「第4章 量と測定を教える」に入ります。では、また次回!お楽しみに。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.03
コメント(0)
-

算数授業名人の授業に感激!
昨日、算数の授業の参考のために、以前録画していた動画ファイルを見てみました。5年ぐらい前?にPCに録画した動画ファイル。外付けハードディスクに保存してあったのをひさびさにリーディング!見てみたのは、NHK教育で放送された番組の録画。「わくわく授業~わたしの教え方」や、3年生向け「かんじるさんすう 1、2、3!」4年生向け「小学校4年 算数」。見て思ったのは・・・さすがNHK!番組がとてもしっかりできており、特に現場の第一人者的先生方の実際の授業場面も多く取り入れられていたのでめちゃめちゃ参考になりました!特に、「授業の進め方」「子どもとのやりとり」では勉強になりました。子どもがとても楽しそうにしている授業風景を見ながら、「僕もこんな授業がしたい! こんなふうに子どもたちみんなの笑顔を引き出したい!」と強く思いました。「かんじるさんすう 1、2、3!」では、放送回によって、2人の先生のうちどちらかが登場されます。こうぞう先生(坪田耕三先生)もいいのですが、今回「おおっ」と思ったのは、もう一人の先生。その名もひろし先生。本名を調べてみたら、田中博史先生でした。この先生のときの授業は、今読んでいる正木先生の授業の進め方そっくり!「分かった子」に発表させる前にストップをかけて周りの子に予想させたりして、「分かる子」だけでなくて、みんなを巻き込んでいく、楽しい授業でした。授業内容も、正木先生の本に出てきた「きまりを見つける」系の内容がそのまま出てきて、「おっ、これ、本に出てきたやつ!」とびっくりしました。坪田先生、田中先生、正木先生は、みなさん筑波大附属小学校の先生をされていた方々ですが、特に正木先生のスタイルを田中先生はかなり受け継いでおられるように思いました。筑波大学附属小学校は、算数の授業の名人が多数おられます。今年はぜひ「算数の授業研究会」に筑波大学附属まで行きたいと思っています。7月の土日にあるようです。特別支援のSENS講義も同じ日程であるのですが、土曜は大阪で特別支援,日曜は東京で算数とはしごで参加してこようかと思っています。(^。^)▼オール筑波算数フェスティバル(7月16日、17日) ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.02
コメント(4)
-

『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』6~「ちょっと待て。まだ早い」
『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』(正木孝昌、黎明書房 、2009、2000円)子どもの「たい」を大事にする、この本の読書メモを続けます。今回が第6回。第3章「図形を教える」の章からです。======================正木孝昌『算数の授業で教えてはいけないこと,教えなくてはいけないこと』読書メモ6(p100~ 「第3章 図形を教える」より) (・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)1 直角を教える ・1人の子どもが、こちらの思い通りの発想をしていたときに、 それに飛び付き、それに乗っかって全体に教えてしまってはいけない。#以下のエピソードは著者の失敗談として語られます。 でも、これを失敗と呼ぶのなら、僕なんかはこんなことばっかりしています。 「できる子」「分かっている子」の発表を受けて、全体に教えて次へ進む・・・ これでは落ちこぼれを作る授業になってしまうのではと心配しつつ、 ではどうしたらいいのか、と代案が思いつかずに結局また 授業の進度も気になって、同じことをしてしまうのです。 ここでは、その代案も示されます。 「なるほど」と思いました。 少しでも真似できたなら、「みんなで分かる授業」に近づけると思います。・直角という言葉が分かるということは、 直角でないものとの区別がつくということ。(黒板の隅に「直角でない紙」を持って行って、 貼り付けて見せることで「直角でない」ことを言おうとした女の子に対して・・・)△「ああ、いいなあ。黒板の角に気づいたのはすばらしい。 それを直角と言うんだよ」とほめた。 →後の協議会で 「あの場面で直角と言う言葉を教えるのはまだ早い」 と批判された。○「黒板の角を使った詩織の目はすばらしいけど、 もし、黒板がなかったらどうするかな」 と聞けば、子どもたちは、 身の回りにある、たくさんの「黒板の角」を見つけるでしょう。 窓枠の隅、ノートの角、床のタイルの角。 見回してみると数え切れないほどある「黒板の角」と同じ角が 子どもたちに見えてきたはずです。(今の著者がこの授業場面に出くわしたなら・・・)○瞬間「ちょっと待て」と、そのままの姿勢で詩織を止めます。 そして、「詩織は何をしようとしているのかな」と全体に聞きます。#続きもありますが、長くなりますのでカットします。 このあたり、本当に読んでいて面白かったです。 「ほうほう、なるほど」と思える個所が連続的に目白押しでした。 2 平行を教える (1) あるなしクイズ ・黒板の真ん中に1本線を引いて、その右と左に四角形を置いていく。 5つめの四角形オを子どもたちに見せたとき、 「これは右かな、左かな」と聞きます。 (2) じゃんけん発表 ・全員を起立させます。 そして、右か左か決めたら座るように言います。 子どもたちが全員座ったところで、自分の判断を発表させます。 「右だと思う人はジャンケンのグー、 左だと思う人はパーで挙げなさい」 「3,2,1ドン」で一斉に手を挙げさせます。 (3) それを言ってはおしまい ・正解を解説し、これを「平行」と言いますと教えたとしたら、 この授業でいちばんの山場を損なってしまいます。 ・見えたものを子どもたちに表現させる。 「なぜ、この四角形カが左の仲間に入ると考えたのかな。 自分の言葉で言ってごらん」 と問いかけます。 (5) 働きかける子どもたち ・子どもたちは黒板に貼ってある、キの四角形を手に取ってみたい と思っているはずです。 自分の手元に持ってきて、折ったり、切ったり、測ったり いろいろと働きかけてみたくなっているはずです。#「あるなしクイズ」も「じゃんけん発表」も、 非常に面白いやり方だと思いました。 自分の授業にも応用してみたいです。 「あるなしクイズ」のところの本のコピーは、読んだその日の翌日に 5年生の先生方に渡して 「英語の初回の授業で、こういうやり方、使えるかも?」 とお知らせしました。 図形だけでなく、いろいろなカードを子どもたちに提示するときに 使えるひとつのやり方だと思います。(以上、p134まで)======================「第3章 図形を教える」の途中まで参照しました。 「図形を教える」で取り上げられたエピソードのうち、最後は「スクールプレゼンター」というのを使ったICT活用授業です。少し毛色が違うので、次回に単独で取り上げます。そういうわけで、また続きます。では、また次回!お楽しみに。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.05.01
コメント(0)
全26件 (26件中 1-26件目)
1





