全108件 (108件中 1-50件目)
-
税の作文 書き方のヒント その4
最後に、ぼくが例として書いてみた税の作文をいくつかのせます。 盗作してパクってもらってかまわないので、どうぞご自由におつかいください。 私は、この作文を書くにあたり税金について少し調べてみました。 調べてみて初めて知ったことは、税金には所得税、酒税など、私が予想していたよりも多くの種類があるということです。そして、これらは、国に納める国税と都道府県などに納める地方税に分けられています。国税には、所得税や法人税など、地方税には、都道府県民税や市町村民税などがあります。 また、所得税や住民税は、納める人の収入によって税率を決めており、公平に課税されています。 このようなことを調べていくうちに、これらの税金はどのように使われているのか興味を持ったので、調べてみました。 まず、私たちに今、一番身近なのは教育です。国はこれに歳出全体の約八%、地方財政では約二十%も使っているそうです。中学生一人にすると、年間約九十万円にもなります。私は今まで、税金を身近に感じたことはなかったけれど、こういうところで、私たちを支えてくれていたことに驚きました。 次に、歳出全体の約十%を占めているのが公共事業関係費です。道路をはじめ、上下水道や公園などの公共施設は、これによってできています。そして、歳出の中で二十五%と大きな割合を占めているのが、社会保障費です。 今、日本は、高齢化が進んでいます。 その問題の一つに、社会保障の費用が増えていくということ、費用を負担する働き手が減っているということがあります。二〇〇〇年には、六十五歳以上の高齢者一人を三・六人で支えていたのに対し、二〇四〇年には一・六人で支えることになるそうです。 福祉先進国のスウェーデンでは毎年、福祉関係の予算が、政治予算の五十%を超えているそうです。 そのかわり、労働者は給料の約半分を税金として納め、国民負担率は約七十%にもなるそうです。しかし、日本では税金を払っても将来の心配をしなければならないのに対し、スウェーデンでは、これらを払えば将来は安心できるのです。 どちらとも税金の使い方はちがって、どちらがいいとは分からないけれど、私はやっぱり、税金はより良い使い方をされるのが一番だと思います。この作文を書く中で、私の身近にも税金にかかわるものがたくさんあること、私たちが豊かに生活していくには、税金は欠かせないことが分かりました。 また、私もいつかは納めなくてはいけない、まだ関係ないのではなくて、これから税金はどうなるのか、どのような使い方が一番良いのか、などきちんと考えてみよう、と思う良いきっかけになりました。 そして、税金は、みんなに平等で、みんなの生活をより豊かにしてくれるものであつてほしいと思います。 私は、この作文を書くにあたり税金について少し調べてみました。調べてみて初めて知ったことは、税金には所得税、酒税など、私が予想していたよりも多くの種類があるということです。そして、これらは、国に納める国税と都道府県などに納める地方税に分けられています。国税には、所得税や法人税など、地方税には、都道府県民税や市町村民税などがあります。 また、所得税や住民税は、納める人の収入によって税金を決めており、公平に課税されています。 このようなことを調べていくうちに、これらの税金はどのように使われているのか興味を持ったので調べてみました。まず、私たちに今、一番身近なのは教育です。国はこれに歳出全体の約八%、地方財政では約二十%も使っているそうです。中学生一人にすると、年間約九十万円にもなります。私は今まで、税金を身近に感じたことはなかったのですが、こういうところで私たちを支えてくれていたことに驚きました。次に、歳出全体の約十%を占めているのが公共事業関係費です。道路をはじめ、上下水道や公園などの公共施設は、これによってできています。そして、歳出の中で二十五%と大きな割合を占めているのが、社会保障費です。 今、日本は、高齢化が進んでいます。 その問題の一つに、社会保障の費用が増えていくということ、費用を負担する働き手が減っているということがあります。二〇〇〇年には、六十五歳以上の高齢者一人を三・六人で支えていたのに対し、二〇四〇年には一・六人で支えることになるそうです。福祉先進国のスウェーデンでは毎年、福祉関係の予算が、政治予算の五十%を超えているそうです。 そのかわり、労働者は給料の約半分を税金として納め、国民負担率は約七十%にもなるそうです。しかし、日本では税金を払っても将来の心配をしなければならないのに対し、スウェーデンでは、これらを払えば将来は安心できるのです。 どちらとも税金の使い方はちがって、どちらがいいとは分からないけれど、私はやっぱり、税金はより良い使い方をされるのが一番だと思います。この作文を書く中で、私の身近にも税金にかかわるものがたくさんあること、私たちが豊かに生活していくには、税金は欠かせないことが分かりました。 また、私もいつかは納めなくてはいけない、まだ関係ないのではなくて、これから税金はどうなるのか、どのような使い方が一番良いのか、などきちんと考えてみよう、と思う良いきっかけになりました。 そして、税金は、みんなに平等で、みんなの生活をより豊かにしてくれるものであつてほしいと思います。 我々中学生にとって最も身近な税金、それは消費税であろう。今回、税金についての作文を書くにあたり、私がまっさきに思いついたのも、消費税についてだった。 お店でもコンビニでも、我々が買い物をするときには消費税を払う。以前は百円のものを買うときには、百円を払えばよかったという。日本に消費税が導入されたのは平成元年からである。私は生まれてもいない。 私にとっての転換期は、平成九年の消費税5%引き上げであった。これは困った。 当時小学生だった私は、遠足のときに先生が「おやつは315円まで」というのを聞いて「何だと! 309円じゃないのか。6円得したよ」と喜んだものである。しかしそれは空しい喜びだった。消費税が上がったため、遠足のおやつの上限も上がっただけで、我々が手に出来るお菓子はやはり三百円分。その現実は変わらなかった。 消費税は、たったの5%である。百円のおかしを買って、わずかに五円だ。少ないお小遣いをやりくりする小学生の財布から五円を持っていって、いったい意味があるのだろうか、と小学生の私は思った。 しかし、ちりも積もれば山となるということを、私は最近身をもって知ったのである。先日、総合学習の時間にボランティアで募金活動をした。駅前で懸命に声を張り上げ、道行く人に募金をつのったが、なかなか集まらない。渡る世間に鬼はなしというのは間違いが、やっぱり本当は、渡る世間は鬼ばかりじゃないかとため息をついていると、小学生の子私の前で足を止めた。 その子は募金箱に、ちいさな財布から十円玉を入れてくれた。「ありがとうございます」とっさに笑顔を返した私は、しかし心の中で、「十円じゃなぁ……」と思ってしまった。朝からがんばって、若い人や老人、子供などさまざまな人が募金をしてくれたが、どれも同じようにわずかなお金でしかない。これではあまり集まらないな、と落胆していたのだ。 しかしボランティア活動が終わり、募金箱の中のお金を数えてみると、思ったよりもたくさんのお金になっていた。私は、十円玉を入れてくれた小学生にはずかしく思った。ひとりひとりの持っているものは小さくても、それが集まれば大きなものになるのだ。 消費税もすこしのものに思えるが、全体としてみれば大きなものになる。日本全体では一年間で十兆円ほどにもなるという。そして、そのお金がわたしたちの生活を支えるためにつかわれているのだ。 私も、これからは、誇りを持って税金を納めようと思う。 今回、税の作文を書くにあたり私は自分の知っていることで税金と関係のありそうなものを思い浮かべてみた。 たとえば、年貢だ。 江戸時代、日本の農民は年貢を納めていた。 それは過酷なものである。五公五民、つまり五割が幕府にとられ、残りの五割が自分の手元に残るのだ。しかしそれはまだいいほうで、中には七公三民という、自分の稼ぎの七割が持っていかれてしまうという地方もあったそうだ。 これが税金だったらと考えると、ぞっとしてしまう。 もしも、自分が働いて一万円の収入を得て、その内の七千円が税金として持っていかれてしまうとしたら、私はとても耐えられないだろう。 しかも、年貢は自分に返ってくることはない。払った年貢はすべて幕府が自分とは関係のないことにつかってしまうのである。 テレビの時代劇でみる悪代官の手に自分の税金が渡るのだとしたら、私は税金を払うことをためらってしまう。何に使われているか、わかったものではないからである。 今と昔がちがうのは、税金の使い道がわかっている点だ。私たちの払う税金は、道路や図書館、そして私たちが学ぶ学校などを作るために使われている。 しかも、かつての七公三民などという重税ではなく、今の税制はじつによく考えられた、納得のできるものである。 所得税は累進課税制度がとられ、収入の多い人はたくさん税金をおさめるようになっている。去年の長者番付を見ると、東京都の橋本さんが四十六億円の年収で十七億円とあった。お小遣い三千円の私は、年収の三万六千円で買い物をしてすべて消費税を払ったとしても、払う税金は二千円ほどである。 橋本さんとのことを思えば、二千円がなんだというのか。 税金は、年貢とちがって払ったぶんだけ自分に返ってくるものだ。 今でも、かつての悪代官のように税金を無駄に使う警察官や官僚のニュースをたまに見る。もちろん、それはごく一部の例であり、私たちの払った税金はみんなの暮らしを豊かにするためにつかわれている。 私たちは、自分の払った税金が何につかわれているのかを正しく知り、その上でしっかりと税金を納める必要がある。 それは、一方的に奪われる年貢ではなく、やがては自分に返ってくるものである。 自分の暮らす社会を豊かにするために、税金についてもっと知ることが、これからの未来をになっていく私たちの義務だと思う。 税金は、私たちの暮らしに密接に関わってゆく問題だと思う。
2007/08/03
コメント(20)
-
税の作文 書き方のヒント その3
ホームページのほうに質問をもらいました。回答とあわせてのせておきます。☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆Q:ジョースター『作文を書こうと思うのですが、「~だ」と書くか、「~です」と書くか、どちらかで統一しろと言われました。どっちがいいですか?A:基本的には、どっちでもいいです。論文としては、「~だ」と書くのがちゃんとしてるのですが、中学生の作文なのでどっちでもいい。しかし、ぼくは「~です」のほうをすすめます。なぜなら、そっちのほうが文字数をかせげるからです。ほんの少しのちがいですが、「~です、~ます」のほうが、おトクです。☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆Q:ichigo 『すいませんッ!!国民の義務といえば、勤労、教育、納税である。それらはどのように結びついているのだろうか。(たぶんこれ書きやすい)って、あるんですけど、どういう風に、書きやすいんですか??書こうと思っても、ペンが動かないんです。どうやって、つずければいいですか?』A:『国民の義務といえば、勤労、教育、納税である。それらはどのように結びついているのだろうか。(たぶんこれ書きやすい)』というのは、国民の三つの義務ってのは、中三の社会でやってる公民の範囲なので、そことからめたら書きやすいなぁと思ったのでした。あと、「勤労」、「教育」という自分の身近にあって内容を想像しやすいものと比べることで、文字数をかせげるし。たとえば、「学校の社会科の授業で国民の義務を習った。勤労や教育が大切だというのはよくわかる。もし誰も仕事をしなかったら、もし学校で学ぶことができなかったら、社会がだめになってしまう。では、もし税金がなかったらどうなってしまうのだろうか。」とか、「勤労、教育は義務だけれども、自分からしたいことでもある。私は将来○○の仕事をしたいと思うし、高校・大学に行って○○を学びたいと思う。それに比べて、納税というのはただ強制されるだけのもので、今まで払わないでいいのなら払わないですませたいと思っていた。しかし、税金について調べているうちに、税金は私たちの暮らしの大事な部分を支えているのだと知り、強制されるから払うのではなく、自分たちのためにすすんで払っていくべきだと思った。」とか、こんな感じかな。何を書けばいいのかわからないというのは、はっきり言って税金に興味ないんだから仕方ない。自分の興味のあることだったらずっとしゃべっていられるけど、興味ないことについて書けって言われても、書けないからね。だから、何かほかのものと比べてみたり、もしそれがなかったらと仮定してみたり、そんな書き方をしたらいいと思います。あと、宿題の作文については、「自分の書きたいことを書く」ってのとはだいぶちがって、「向こうが(学校の先生とかお役所の人とかが)書いて欲しいと思っている内容に合わせて書く」くらいのつもりで、割り切って書いたほうが気がラクです。☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆Q:rei 『こんにちは^^私は、今税について書こうと思っています。だけど、3600字以上で書かなきゃいけないんです・・。↑のを参考にしようとおもってるんですが、どうやって3600字にしたらいいですか??』A:『3600字ということは、原稿用紙9枚ですか。長いですね。話題ふたつ、それぞれに賛成の例と反対の例で、基本的には、4枚の作文をふたつつなげるようにするのがいいと思います。9枚だったら、ひとつの話題では足りません。』☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆Q:rei 『わかりました^^あと1ついいですか??「二〇〇〇年には、六十五歳以上の高齢者一人を三・六人で支えていたのに対し、二〇四〇年には一・六人で支えることになるそうです。」の三・六人って??どういう意味ですか??あと一・六人・・・・』A:●二〇〇〇年には、六十五歳以上の高齢者一人を三・六人で支えていたのに対し、二〇四〇年には一・六人で支えることになるそうです。というのは、2000年には高齢者ひとりにかかる介護とか年金とか、そういったいろんなお金を、いま働いている世代の数で割ったら、老人ひとりぶんのお金を3.6人で負担していることになる。しかし、2040年には高齢化が進み老人が増えて、少子化の影響で働く世代は今よりも減って、老人ひとりにかかる費用を、1.6人で負担しなくてはならない計算になる。☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆Q:rei 『また?質問ですっ☆★「日本では税金を払っても将来の心配をしなければならないのに対し、」ってあるじゃないですか・・・。でも、「 税金は、年貢とちがって払ったぶんだけ自分に返ってくるものだ。」とも書いてあります。あと、「かつての七公三民などという重税ではなく、今の税制はじつによく考えられた、納得のできるものである。」とかも・・・。どっちですか??心配しなくてもいいの?しなくちゃいけないの??』A: 『簡単にいうと、スウェーデン > 今の日本 > 昔の日本スウェーデンと比べると、今の日本はまだまだ。スウェーデンは消費税が25%で、税金大変だけど、そのぶん老後の保障がしっかりしてる。税金はしっかり払わなくちゃならないけど、そのぶんあとでちゃんと面倒みてくれる。それにくらべたら、今の日本は税金を払ってもそれが自分に返ってくるか、あやしい。自分の老後を保障したり、道路を造ったりといったことにちゃんと使われているのか不安。でも、江戸時代の年貢と比べたらぜんぜん安心。江戸時代の年貢は一般のひとたちにかえってくるものなんて、ほtんどなかった。だから、スウェーデンやイギリスといった國と比べたらまだまだ税金が国民のために機能しているとはいえないけれど、江戸時代と比べたら納得できる。という意味です。』☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆Q:みりぃ 『税の作文で国民の三大義務についてかいていて調べたことを書きたいんですがどんなことを調べて書けばいいですか?教えてください!!A:『●教育を受けさせる義務 ・自分たちが学校に行けるのは税金のおかげ ・東京都公立中学校の生徒1人あたりの3年間公費負担額は約381万6000円。●勤労の義務 ・勤労は権利であり、義務である。 ・働いて税金を納めることは、結局は自分自身を助けることだ。 ・学生は直接に税金を納めることはない。税金をつかう立場だからこそ、税金についてよく知り、無駄につかうことのないようにしたい。●納税の義務 ・税金は義務で納めなければならないものだが、それは無駄ではない。 ・自分たちの住む地域、社会のために納める。 ・税金は貯金箱だ。「盗られる」のではなく、「一回集められて、私たちに返ってくるもの」☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆Q:かずは 『「私の父は公務員」ネタで書こうと思ったのですが、どうつなげてまとめたらよいのか分かりません。ほかの書き方にしたほうが書きやすいですかねぇ?』A:「私の父は公務員」のネタでいくのなら、たとえば[1]作文を書くために税金についてしらべました。消費税、自動車税、相続税、住民税、いろいろと税金を集めています。いったい、税金は何につかわれているのでしょうか。[2]夏休みに税金のことをしらべるために友人と図書館に行きました。帰りに友人と食事をして、コンビニで買い物をして、好きなアーティストのCDを買いました。すると友人が「かずはのお父さん、公務員だったよね。お給料は税金から支払われているんだね」と言いました。私は今まで意識したことはありませんでしたが、私たち家族が暮らすためのお金は、みんなが払った税金から出ているのです。さっき友人が払った10円、20円という消費税や、みんなの払うさまざまな税金が集まって、公務員の給料が支払われたり、私たちが利用した図書館を建てたりしているのです。[3]2005年度予算でみると、国家公務員約61万5000人の人件費は5兆4410億円に上るそうです。病院や水道事業など地方公営企業を除く地方公務員約246万人の給与関係経費は、22兆7240億円にもなるそうです。公務員の仕事は警察官や消防官、役所の職員、学校の先生など、どれも大切な仕事です。しかし、警察官に道を聞いてお金をとられたり、学校に通うのに授業料や教科書代は払わなくてもよかったり、私たちは公務員の仕事にお金を払っていません。もしそういったことがすべて有料のサービスだったら、私たちはみんな困ってしまうと思います。だから、税金でみんなにとって必要な仕事をしている人たちの給料を払う仕組みになっているのだと思います。[4]今までは税金についてあまり関心がありませんでしたが、これからは自分に身近な問題として考えていきたいと思います。みんなが払った税金を有効に活用していけるよう、全員が意識していかなければならないと思います。☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆Q:あさみ 『私は税の作文で、少子・高齢化について書いていきたいと思ってるんですけど、はじめはどんなふうに書き始めていいかわかんなくて・・・。どんな感じで書いていくかがおもいつかなくて・・・。良かったら教えて下さい★★』A:少子高齢化、でいくと、[1]ニュースで増税について話していました。消費税も今の5%よりもっと上がるとのことです。なぜ増税する必要があるのか、本当に必要なのか、考えてみました。[2]私は一人っ子で、両親と七十才になる祖父母と暮らしています。少子・高齢化という言葉がそのまま当てはまる家族です。私は両親と祖父母には元気で長生きしてほしいと思いますし、これからも充実した生活を送って貰いたいと願っています。でもやがて両親が高齢者になったら、私一人の力で両親と祖父母の生活を支えることは難しいと思います。そんな私の不安と、今の日本の状況は似ていると思います。[3]現在、日本は少子・高齢化という大きな問題を抱えています。日本人の平均寿命はここ30年間で約10歳も延び、今では世界一の長寿国となりました。その一方、将来の働き手となる子どもの出生率は急激に低下しています。このままでは10年後には国民の4人に1人が65歳以上の高齢者となり、いままでは5人で1人の高齢者を支えていたのが、これからは3人で1人の高齢者を支えていかなければならなくなる計算になります。少子・高齢化はますます深刻な問題に進展していってしまいます。[4]より豊かな未来に希望を託す為にも国民一人ひとりが正しい税金の理解を深め、お年寄りや弱者が税金の恩恵を身を持って感じる事が出来る税金が生かされた社会になればと思います。そして、それが実現される様に私も、もっともっと勉強して国を支える力になりたいと思います。 とか。☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆…☆Q:ひな 『募金の体験談以外で作文に使えそうな体験談ってないですかねぇ?あたしには税に関係する体験談がなくて。。。』A:体験談なんて、ぼくもありません。体験なんてする必要ないんです。書くことが決まったら、それにふさわしいお話をでっち上げればいいんです。上に書いた「父は公務員」も「少子高齢化」も、数字以外は全部テキトーです。体験なんて何もないです。作り話で、もっともらしい話を考えてみてください。本当のことかウソか、なんてのは作文を書く上では大事なことではありません。自分の主張を伝えるために都合のいいお話を考えることが、作文だと思ってください。』
2007/08/03
コメント(0)
-
税の作文 書き方のヒント その2
原稿用紙に書き出す前に、書く内容をメモしてみましょう。 [1]話題、[2]体験、[3]意見、[4]結論、というように分けて書き出してみると、全体の構成がわかりやすい。 たとえば、こんな感じ。[1] もしも税金がなかったら、どうなってしまうのだろうか。[2] 税金がなくても、自分のことは自分でするという人がいる。たしかに、自分で働いて住むところや食べるものを買えばよい。しかし、それではさまざまな公共サービスが成り立たなくなってしまう。[3] たとえば、郵便局や警察、消防署などの公共サービスは税金がなければなくなってしまう。わたしたちの暮らしをささえるものは、税金で成り立っている。[4] 社会全体のためにも、またわたしたち自身のためにも、税金は必要だ。[1] 消費税が10パーセントに引き上げられるという。本当に必要か。[2] テレビで脱税する政治家や、公費で豪遊する公務員の姿を知った。税金がそんなことにつかわれるのなら、納めたくない。[3] たしかにニュースでそんな場面を見ることもあるが、自分の身の回りのも学校や図書館、道路など、税金が有益につかわれている例はある。それらのことにも目を向けなければならない。[4] 税金を納め、またそれが何につかわれているのか、社会に関心を持つことが大事だ。[1] 消費税は、たったの5%である。それが意味あるのか。[2] 先日、ボランティアで募金活動をした。なかなか集まらず、小学生の子が10円玉を入れてくれても、「10円じゃなぁ・・・」と思ってしまった。しかしお金を数えてみると、思ったよりもたくさんのお金になった。[3] 消費税もすこしに思えるが、全体としてみれば大きなものになる。一年間で10兆円ほどにもなるという。そして、そのお金がわたしたちの生活を支えるためにつかわれているのだ。[4] これからは、誇りを持って税金を納めようと思う。 どうでしょうか。 こんな感じに構成すれば、論点のまとまった作文が書けます。 まず、書き出してしまうことが大事です。 書く前にあれこれ考えてしまうと、手も止まってしまいます。 トライ&エラーでいいのです。やってみて、だめだったら直せばいい。初めから完璧なものを目指さずに、初めは40点の出来でも、手直しをして60点、80点の作文が出来ればそれでいい。 試しに書いてみて、そしたら益田まで見せにきてください。 どこを直したらいいか、何を加えたらいいか、アドバイスします。 とりあえず三千冊くらい本読んで、文章書いて十五年の無駄な経歴を持っていますので、多少はアドバイスできると思います。 (。-_-)ノ☆・゜::゜ヨロシク♪
2007/08/03
コメント(0)
-
税の作文 書き方のヒント その1
中学三年生は、夏休みの宿題に「税の作文」というのがあります。 東京だけでなく、各地で税金の作文書かされてます。 去年の夏期講習のときに「税の作文はこう書け!」というのを作って配ったのですが、今年もその改訂版を掲載しておきます。【 夏期講習 「税の作文」はこう書け! 】 まず、作文を書く上で大切なのは「1.何について 2.どう思うか」をはっきりさせることです。1. 「何について」とは、内容のこと。 内容は、「税について」に決まっている。それ以外にないです。2. 「どう思うか」はつまり、自分の意見。 しかし実は、これも決まってしまっているのです。 本来ならば、文章とは自由に何でも書いていいものなのだけれども、 今回は「東京都主税局」が募集している作文です。 「税金は、大切だ」という、税に対して賛成の立場で書く以外には、ないのです。 税金なんて必要ない、という立場は、ありえない。 つまり、「こんなことがあった、だから税金は大切だと思う」「こういうことがある、だから税金は大事につかうべきだ」 という結論になるしかない、ということです。 具体的な流れとして、以下のパターンをすすめます。[1] 話題 税の、どんな面についてのことを作文に書くのかを書く。 この段落をわかりやすくまとめるためには、「税は必要なのだろうか」「税金は本当に役立っているのだろうか」 などと、疑問の形で問題を提起すること。 疑問の形にすることによって、何を問題として作文を書くのかが明確になるし、 その質問に対する自分の結論を書くことによって自分の意見をはっきりすることができる。 ただ思ったことを書いただけでは、まとまりのない文章になってしまう。 たとえば、「税は必要なのだろうか」と疑問を示して、 最後に、「やはり税は必要だ」と答えを書くことで、 主張の通ったすっきりした流れの作文になります。「~~だろうか?」という疑問に「~~である」という答え。 これが論文の型です。 [2] 体験 話題をうけて、自分の体験や調べたことなどを書く。「こんなことがあって、税に興味を持った」「税金について調べてみると、こんなことがわかった」 なんとなく書き始めて、とりあえず書き終えました、というのではなく、 ゴールを設定してそれに合ったネタを並べるのがコツです。 自分の体験やニュースで見たことなど具体例を書いて、「だから~~だと思う」というように書く。 もちろん、体験とはいっても事実そのままである必要はない。 ウソもオッケー、誇張も歓迎。 自分の都合もいいようにでっちあげましょう。[3] 意見 話題をうけて、自分の意見を書く。 基本的な形としては、「~~だという人がいる。たしかにそれは~~だ。しかし、……だ」という形。 重要なことは、 はじめに「~~だという人がいる」と一般的な意見を書く。 自分の結論とはちがう意見も書いて、あとから「それではいけない」と否定する形にする。 まず反対意見を書いて、「そう言う人もいるが、本当は……だ」と書くことで、「はばひろい物の見方をして、こういう結論になったのだね」 という気になる。 いかにも深い意見という気がしてくる。 だから、前に書くのはちょっと駄目な発想であるほうがよい。 そして、「実はこうなのだ」とあとから書く。[4] 結論 最後に自分の結論を書いて、作文をまとめる。 結論は短く、三行くらいにまとめるのがよい。 次に、各部でよく使われる表現や、こんなことを書いたらいいんじゃないかな というネタを書きます。 参考にしながら、自分が書くことを考えてみてください。[1] 話題 … いちばんはじめに、とっかかりをつくる。 自分と税というのは関係のうすいものなので、 自分と税金を結びつけるような書き出しがいい。 この導入部は、いろんなバリエーションがあって、頭をひねるところです。 作文を書く上でいちばん大切なのはここで、「ほうほう、ふむふむ」「なにそれ?」「で、何の話?」 と読む人の興味をひくことができたらしめたもん。 作文に書きやすそうな例を書いてみます。 この中で、ちょっとでも心にひっかかるものがあれば、 それをきっかけにして内容を考えてみてください。○ 消費税をいつも払っている。いったい何につかわれているのだろうか。○ 消費税が今度増税されるらしい。(それでは困ると書いて、あとから「それも仕方ない」と書く)○ 社会の授業で、さまざまな税金があることをしった。○ 財布を落としたら、交番に届けられていた。(ほかにゴミ処理、郵便、災害救助などの公共サービス。すべて税で成り立っている)○ 「税金は万人に公平でなければならない」という。 しかし累進課税制度というのは公平ではない。(納めるときには不公平、つかうときには公平に)○ 新潟・福井の水害のときに救助隊が出動。○ 税について図書館で調べた。その図書館も税で成り立っている。○ ニュースで税金が無駄につかわれているときいた。○ なぜ5%もの消費税を納めなければならないのか。○ 現在の消費税5%は、外国に比べれば低い。(高齢者の環境が充実しているスウェーデンでは、25パーセントもある)○ 学校にクーラーがはいった。(それも税金)○ 「この施設は~税によって建てられました」という看板があった。○ 先日、お祭りにいった。その公園も税金でまもられている。○ 私の父は公務員。○ 私の祖父は年金で暮らしている。○ 税金といえば、消費税しか思いつかない。 そこで私はほかにどんな税があるのか調べてみた。(と、以下いろんな税のことを書いて字数稼ぐ)○ 国民の義務といえば、勤労、教育、納税である。 それらはどのように結びついているのだろうか。(たぶんこれ書きやすい)○ 無駄な公共事業(長良川、川辺川の河口堰など)がある。○ 安倍首相が貰える年金は月に50万円。○ 学校に行くのに、教科書のお金も税金で払われている。(教育を受けるために税金がつかわれている)○ 現在、日本には700兆円ほどの借金がある。○ 国の収入の半分は税金だ。○ 東京都公立中学校の生徒1人あたりの3年間公費負担額は約381万6000円。○ 税が何につかわれるのかよく知らなかった。知ろうと思う。(なんて反省してみるのも有効)○ たかだか5%で意味があるのか。(現在消費税の税収は約10兆円。1%増えれば単純計算で1兆円の増収になる)○ 日本は、高齢化が進んで、社会保障の費用が増えていく。二〇〇〇年には、六十五歳以上の高齢者一人を三・六人で支えていたのに対し、二〇四〇年には一・六人で支えることになる。○ 江戸時代の年貢は、とられるだけだったが、税金は結局自分のためにもなる。 基本的な流れは、「税について、~~を知った(考えた)。 そしてわたしはこう思った」という形になります。 そして、「なぜ~~だろうか」「どのようにして~~するべきだろうか」「本当に~~だろうか」 というように、疑問の形にする。[2] 体験 … [1]話題の段落で書いた話題を、さらにくわしく書く。 この段落は具体例を書く段落なので、[1]で書いたことを自分の体験や見聞きしたことを通してわかりやすく説明して、伝えることが大事です。 実感が持てるような、自分の身の周りの出来事を探して、それを書く。 自分が経験したこと、自分が新聞やニュースで見たこと、 どうしてもなければ、創作でもかまいません。 うそでも、「こんなことがあった」という実体験の形で書くこと。 基本的には、あとで書く自分の意見につながるような例を考えて書く。 最後に「だから、~~だ」とつなげます。 ここでしっかり材料が集まったかどうかで、 作文のデキが違ってくるので、気合入れましょう。[3] 意見 … 「わたしはこう思う」 自分の意見を書くときに注意するのは、税金には「払うもの」と「つかうもの」という二つの面があることに着目すること。 ふつうに暮らしていると、消費税などで税金を払うことだけに注意がいってしまうが、じつはその税金は身の回りのさまざまなことにつかわれているのだということに気を向けてやると、主張に厚みが出てきて、ちょっとがんばった作文になる。 この[3]意見 の部分は、あまりバリエーションないです。 なぜなら、「税金は大事だ」という結論にもっていくしかないので、意見もその方向でしか展開できないから。○ 税金を払うことは大事だが、それをどうつかうかも大事だ。○ 税金は、国に納めているのではなく、自分自身に納めている。○ 税金は納めるだけでなく、わたしたちを助けてくれる。○ 消費税増税に反対する人がいるが、やはり必要だ。○ 健康なものには実感できないが、老人や障害者のためにも、税金は必要だ。○ 少子・高齢化社会では助け合いの精神が必要。○ 自分にはできない公共サービスをするためにも税は必要。○ 汚職などのニュースをきくと否定的になるが、よいことにつかわれている税もある。○ 高くても税金を払わなければならない。○ 税にはちゃんと意味があるのだ。○ 税とどうつきあっていくかを考える必要がある。○ 税が何につかわれているのか、理解して税を納めることが大事だ。○ 税金を払うとは、社会に貢献することである。○ 親の払った税金がわたしを支えている、私の払う税金はわたしの子を支えることになるのだ。○ わたしたちが思う普通の暮らしは、実は普通ではない。○ 税金は貯金箱だ。「盗られる」のではなく、「一回集められて、私たちに返ってくるもの」だと私は思いました。 税は身近にあるべきものです。○ 消費税の引き上げはやむをえない。○ 今までは消費税を払うのが嫌だったが、これからは誇りに思いたい。○ 国民の三大義務を果たすことは、わたしたちの権利を守ることにつながる。 ここでよくつかわれるのは「なたもだ」というやつで、 自分の意見を述べたあとに、【な:なぜなら、た:たとえば、も:もしも、だ:だから】 という四つの接続詞をつかってみるといいです。 困ったら、「なぜなら~~」「たとえば~~」「だから~~」「だから~~」 とつなげてみて、そのあとを考える。 こう書いて文をつなぐことによって、説得力のある作文になるし、 無理なく字数を稼げます。 困ったら「なたもだ」で字数を稼いどけ。[4] 結論 ここは、基本的には、「だから、税金は必要だと思う」という方向以外の結論はありません。 具体的にまとめの例を書くと、こんな感じに。○ 私達もいずれ大人になり、働き手となる。 明日の良き納税者となるためにも、今から税への正しい認識を深めていこう。○ 一人一人が納めた税金は形を変え、ゆとりのある豊かな社会を支え、 またそれに自分自身も支えられている。 私も将来納税者になりますが、このことを忘れないでいたい。○ 税は決して他人事ではない。 未来を支えていく私達は、これからはしっかりと税の使われ方も見守りながら、 未来を考えていかなければならない。○ 国民一人一人が、税についての理解をより深め、正しく理解し、きちんと納税の義務を果す。 その一方で、自分たちが支払った税金がどのように使われたのかを知ることが重要になってくる。○ 私たちはいつでも、税にささえられています。 警察や消防に守られ、道路や街灯の整備によって更に快適な環境となります。 学校で勉強ができることも税がなくてはできません。 税に感謝して、私達もやがて子供のために納税をするのだ。 とかね。(^ー゜)b
2007/08/03
コメント(1)
-
ワキ文具のこと
ぼくが最もよく利用する文具屋で、またぼくに最初に文具の世界の広さ、深さ、面白さを教えてくれたお店、 それは「ワキ文具」文房具通販、輸入文具のお店 - ワキ文具 (↑ このお店) そんなワキ文具の店長・キッシーこと岸井祥司さんのことを書いている記事がありました。浪速のあきんど ワキ文具のキッシーのこと なんつーか、あれですわ。 コンビニで買うコクヨのボールペンは、ただの筆記用具です。 ヨーカドーで買うドクターグリップは、ただのシャーペンです。 コクヨもパイロットもゼブラも、ドクターグリップも無印良品もHI-TECも、いい商品ですよ。 でも、その先がある。 機能性とか、書きやすさとか、安さとか、それだけじゃなくて、 楽しい文房具ってものもあるんだと。 自慢したくなるような文房具、ポケットから取り出したくなっちゃう文房具。 ぼくが「ワキ文具」のことを知ったのは、あるシャーペンを探していたときでした。 ロットリングというドイツのメーカーのロットリング-ROTRING ラピッドシャープペンシルです。 その頃ぼくはまだそんなに文房具のこともよく知らなくて、「ちょっとだけこだわりがあるぜ」くらいのもんだったのですが、何かのサイトで読んだ「ロットリングのラピッドってのが書きやすい」という記事をみて、「どこかネットで扱ってるところないかなぁ」と探していたら、ワキ文具にたどりつきました。 しかし、今でこそラピッドは注文すれば手に入る商品ですが、その頃は製造がストップしているだか輸入がストップしているだかで、廃盤扱い。どこに行ってもSOLDOUT。 きいてみても、「もう入荷することもないと思います」とつれない返事。 ところが、ワキ文具を見ると、売り切れ、と書いてある下に「購入を希望されるお客様は、次回入荷がありましたらお知らせいたします」とある。 ダメもとで、「どうしてもこのシャーペンが欲しいので、次回に入荷がありましたらお知らせください」と書いてメールしました。 そうしたら、店長の岸井さんからメールが来た。「ラピッドはドイツでも製造が中止されている状況で、次にいつ入荷するか、入荷があるのかもわからない状況です。しかし、ぼくが個人的にコレクションとして何本か持っているものがありますので、その中の一本だけでしたらお譲りいたしますよ。」 とのこと。 感謝感激して、一本お願いしました。 それ以来、ワキ文具とラピッドはぼくにとって特別なお店、特別な文具になったのです。 それから、ワキ文具でさまざまな商品を見るたびに「お、こんなのもあるのか!」「なんだこれは! これボールペンかよ!」「電卓でけえ!」「消しゴムでけっ!」 と、はまっていきました。 文房具ひとつとっても、自分がそれまで知っていたものはほんの一部で、飛び込んでみればまだまだ奥が深く、見ているだけで楽しくなるようなモノがたくさんあるのだと知ったのですよ。 もちろん、コンビニや100円ショップで売っているものにもいいものはたくさんあって、別にそれだけでも充分に用は足りるのですが、自分のお気に入りの一品を探し出したときの喜び、自分にジャストフィットする一本を見つけたときの嬉しさは、ついニマニマしてしまうものがあるのです。 友達から借りたグローブで野球はじめて、ついに自分のグローブを初めて買って試合に出るときの気持ち。 CDショップで視聴してて、聞いたこともないバンドの曲が最高によかったときの気持ち。 友達に連れられて行った居酒屋が居心地よくて、次もまた来ようってときの気持ち。 そんな気持ち。「これだ!」 ってものを発見する嬉しさは、格別。 そして、それを毎日つかうときの嬉しさも、また格別。 ワキ文具は、ぼくにそんな嬉しさを教えてくれた店なのです。
2007/04/20
コメント(0)
-

本屋大賞2006は「一瞬の風になれ」が受賞!
「一瞬の風になれ」佐藤多佳子「好きな作家は?」ときかれると、「佐藤多佳子」とこたえてきた。 そう答えてもなかなか反応はなく、「どんなの書いてるひと?」「しゃべれどもしゃべれども、とか」「どんな話?」「落語家ががんばる話」 聞いてるほうも話してるほうも、ふーん以外の何物でもない会話なのだが、まぁそんな感じ。 でも、これからは変わるんだろう。「どんなの書いてるひと?」「一瞬の風になれ、とか」「あー、あの陸上の、」と。 もしかしたら、さらに、「あー、あの映画になったアレ」「あー、いまドラマやってるやつね」「あー、あれ読んだよ」 っていうような反応が返ってくるようになるのでしょう。 ついにとったよ、本屋大賞。「しゃべれども しゃべれども」から10年、やっと佐藤多佳子が世間に届くときがきた。 この作家はいいよー、と言い続けて10年、うれしいかぎりです。 まことにもって、おめでとうございます。 まだ読んでいない人は、ぜひ読んでみてください。 何を書かせてもうまい佐藤多佳子の作品の中でも、この「一瞬の風になれ」のストーリーの躍動感ったらない。 高校の陸上部を舞台にしたさわやかな青春小説で、楽しい気持ちとか悔しい気持ちとか、いっぱい詰まった素晴らしい小説。にぎやかでさわやかな青春小説です。 春野台高校陸上部。さして強くもない公立高校に入部してきた期待のふたり。 中学のころか注目されながらも練習嫌いでおまけにブランクのある天才スプリンター連と、中学まではサッカー少年でありながら限界を感じ、陸上に何かを見出そうとする幼馴染の新二。サボり癖のある連をやきもきしながら見守るチームメイトたち。 やる気のない天才と、努力してる主人公。 そんなありふれた構図で、しかも陸上競技のスプリントなんていう小細工のきかない設定で、 でも読み出したら面白さ。 たまらない面白さなのである。 新二が走る、連が走る、物語が疾走する。 佐藤多佳子の描く最高の物語を、ぜひ味わって欲しい。 スポーツ小説の王道ど真ん中を突っ走って、文句なしのストライク。 奇をてらった設定はなく、すいすい読めて、ぐんぐん引き込まれる。 おそるべし佐藤多佳子。 これはもう、今年のベストは確実なんですが、オールタイムベストにも入る大傑作ですよ。 本好きなら、何が何でも読め。 現在の日本の作家で、最高の物語作家だと私は思っている。 マンガ界に、映画界に、ゲーム界に、「どうだ、文学には佐藤多佳子がいる」と誇れる作家なのだ。 本屋大賞2006を獲ったことも、当たり前。 2006年のベストにして、この10年のベストかもしれないのですよ。一瞬の風になれ 第一部 --イチニツイテ--作者: 佐藤多佳子 出版社/メーカー: 講談社 発売日: 2006/08/26 一瞬の風になれ 第二部 --ヨウイ--作者: 佐藤多佳子 出版社/メーカー: 講談社 発売日: 2006/09 一瞬の風になれ 第三部 -ドン-作者: 佐藤多佳子 出版社/メーカー: 講談社 発売日: 2006/10/25
2007/04/15
コメント(3)
-
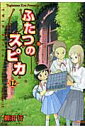
ふたつのスピカ
土曜日に新刊が発売されてました。「ふたつのスピカ」12巻です。 夏休みも近づき、アスミたちはいつもの5人で毎年恒例の旅行先を考える。くじ引きの結果、行き先はアスミと府中野の故郷であり、去年も訪れた唯ヶ浜に決定する。実は皆、唯ヶ浜行きを希望していたのだ。 唯ヶ浜に着いた5人は、獅子号事故の慰霊碑を訪れ、ケイとマリカはアスミの実家に向かう。3人が実家にいるところへ、アスミの父・トモロウが帰ってくる。トモロウとともに、彼のロケット技師時代の話も聞きながら楽しく過ごす3人。翌朝、再び遠方へ仕事に出かけるトモロウは、顔を合わせたマリカにアスミのことを話す。 一方、秋は花火大会の準備で忙しい府中野を手伝っていた。その秋は電話である知らせを受ける。 最後かもしれない5人の夏が始まった。 10巻くらいからずっと、泣かせるいい話がつづいていて、でもそれは悲しい出来事を予感させるものだったのです。 11巻でなんもなかったから、とりあえず何もないんかなと思ってたら、12巻の最後でいきなり来ました。 前から病気のサインは送られていたのですが、「まさか、ね」と甘く考えていました。 現実に友人が出血していて、それを自分がそのサインを見逃していたとしたら、後悔することだと思いますが、マンガでそんな後悔を味わうとは思わなかった。 喪失感でいっぱいです。 これから彼らが、どう向き合っていくのか、どう背負っていくのか、見守りたいと思います。 いやもう、このマンガはもっとたくさんの人が読んで欲しいな。 今の時代にこれだけむやみやたらとノスタルジーで、 まっすぐなマンガもめずらしい。 印象深い言葉があちこちにあって、懐かしい風景がたくさんあって、 かなしい想い出、やさしい友達、ハードな現実。 柳沼行という作家が身銭切ってる感じがします。 自腹で描いてるマンガだなぁって思いますよ。「こうしたら売れる」「こういう話がうける」とかの方法論ではなく、この話が描きたい、この人物が好きだ、っていう思いが伝わってくる。 もちろん、プロのマンガ家なんで物語の展開とかキャラの配置とかの計算は立ってるんだけど、それだけじゃなくて、それ以上にあふれる思いがある。こんなマンガが、少なくなった現在だからこそ、胸に迫ってくるのです。 たくさんの人に読んで欲しい作品です。
2007/03/26
コメント(1)
-
東京都立高校 200字作文 書き方のコツ その2
【楽天ブログでは文字数が制限されているため、二回にまたがってしまいました。 前回のつづきです。 】 その3 実用的方法 ~この通りにやれば「とりあえず書けちゃう」 私のやり方は、・作文が苦手で、何をどうしたらいいのかわからない・どんなことを書いたらいいのかわからない・何がわからないのかもわからない・とにかくわからないんだコノヤロー という人を対象にしてます。 だから、文章の作り方としては素晴らしくないし、すごくもない。 10点満点のうち、10点は目指してない。 でも、6点から8点は取れる。 目標は、「読んでも文章の意味分からなかったけど、言うとおりにしたら作文書けた」です。 さらに、「そんでもって、よくわかんないままに点取れた」です。 たぶん、学校の先生は一生教えてくれない方法だと思います。 かなりセコくて、卑怯な方法ですが、かんべんしてください。【 都立高校 二百字作文 基本の作成例 】◎作成例 その11 「私も(本文から筆者の意見を抜き出す)~~と思う。」と自分の立場を明らかにする。2 「なぜなら(本文から理由の部分を抜き出す)だからだ。」と理由を書く。3-1 賛成例を書いて、「私の周りにも~~という人がいるが、そうあるべきだ」と書く。3-2 反対例を書いて、「私の周りにも~~という人がいるが、それではいけない」と書く。4 「やはり(本文から筆者の意見を抜き出す)ことが必要である。」と結論を書く。【賛成反対、理由、具体例】すべてを書いて完答の10点を狙う方法。 具体例は自分で考えなければならない。本文の内容に合う状況で、身近な例を考える。◎作成例 その21 本文から文を抜き出す。最初の段落、最後の段落の文、何度も出てくる言葉、など。(都立の問題は、だいたい一行が三十四字なので、それを目安にする。)2 最初の文に「~と私も思う」、最後の文に「~という筆者の意見に私も賛成だ。」と付け加える。3 具体例が必要な場合は、本文にある具体例を少し変えて(自分の体験だということにして)書く。 具体例を自分で考えない。本文の例をそのまま頂戴して、「私にも~~ということがあった」とする。 うまくすれば10点も狙える。 以上のふたつはなんだかんだ言って「作文」になっているが、これから述べる3つの方法は「作文」ともいえない、単なる「解答の作り方」である。しかし、それなりに使えるものなので作文の苦手な生徒には充分に有効。◎作成例 その31 本文の最初の段落の一文目(または最後の文)を抜き出して 「と私も思う。」 とつなげる。2 本文にある具体例を書く。(私も以前~~があった。と自分の体験として)3 本文の最後の段落の一文目(または最後の文)に「という筆者の意見に私も賛成だ。」とつなげる。 本文を読んでも内容がよくわからなかったときのためのもの。 本文の最初の段落と最後の段落で勝負を賭ける。 本文の具体例を変えずにそのまま書いちゃう。具体例がなければ、あきらめて書かない。(2点の減点)◎作成例 その41 本文の最後の段落から五行程度をまるまる抜き出して、「と私も思う。」とつなげる。2 「筆者の意見に私も賛成だ。」とつなげる。 本文を読んでも内容がよくわからなかったときのためのもの。 本文の最後の段落で勝負を賭ける。5行ごっそり抜き出すので、作業はかなりラク。手数と効率の点からいうと、この方法がいちばんいい。 もし具体例が見つかれば、書く。しかし基本的には具体例はあきらめて書かない。(2点の減点)◎作成例 その5(これは平成18年度にしか通用しないかもしれない)1 本文の中で、問題用に傍線がひいてある文をつなげて、「と私も思う」「と思う」とつなげる。2 1を繰り返し、最後は、「という筆者の意見に私も賛成だ」でしめる。本文を読んでも内容がよくわからなくて、しかも基本の1~4が使えないときのためのもの。これはかなりの裏技であり、最終手段。でも平成18年度はこれで8点は取れた。 作文の苦手な生徒は、1と2でダメだと思ったら、3と4の方法で勝負しても良い。 ここ10年の都立入試では、345のどれかの方法で、6点から10点の作文が書けた。 へたにがんばるより、そのほうが効率よく得点できる。 都立入試の作文は、「すばらしい文章を書くこと」や「独創性のある文章を書くこと」が目的ではない。 ただ単に、「原稿用紙のルールが守れているか」「主語、述語が合っているか」「理由がちゃんと書けているか」といったものを見るだけだ。 こんなもん、読むほうもたいして時間書けて読まないんだから、書く方も時間かけないで、テキトーでいいんである。「なんだこのバカみたいな方法は」という感想を持つ方もいると思いますが、これでいいんです。 なぜなら、作文なんかに点数つけられるわけないし、それが不可能だとわかって作文書かせてくるんですから。 こっちも、テキトーに対処しとけばいい。 作文なんかは5分でかたずけちゃって、他の問題にもっと時間をかけるべきです。「とりあえず、書くだけ書いた」 それで充分なのです。 作文を書いても、それを直してもらわないでは効果がありません。 もし身近に作文の指導をしてくれる人がいないのなら、メールでもコメント欄でも、作文を見せてください。 添削・直しを入れて採点します。 トライ&エラーが、レベルアップへの近道です。 まずはやってみてください。
2006/12/13
コメント(1)
-
東京都立高校 200字作文 書き方のコツ その1
都立入試 国語 二百字作文の書き方について 東京都立高校入試の国語にある「二百字以内にまとめて書け」の問題。 200字作文を書くためのヒントを、考えてみる。その1 書くための準備 ~知っておいたほうがいいこと~ 1、都立高校 国語科問題の例年の構成 まずは、戦うには敵を知らなければならない。 都立高校入試の国語問題の例年の構成と配点は、こんな感じです。 [1] 漢字 読み 2×5=10点 [2] 漢字 書き 2×5=10点 [3] 物語 5×5=25点 (心情と表現についての選択問題がメイン) [4] 説明文 5×4+10=30点 (問題文と本文の対応をみれば解ける) [5] 古文 5×5=25点 (必ず現代語訳がついているので、それを参考にする) [4]の説明文のうち、10点というのが作文です。 百点のうち10点の配点は大きい。例年「結局何も書かなかった」という生徒がいるが、それではみすみす損をしてしまう。10点とはいかなくても、6点から8点は狙っていきたい。そして、できるのである。 しかし10点は大きいといっても点数で言えば選択問題の2問相当にすぎない。これに15分も20分もかけていてはならない。では、何分くらい時間をかけるべきか、かけることができるのか、時間配分が必要になる。2、試験時間と時間配分 試験時間50分から逆算して、各問にどれくらいの時間が割けるか? たとえば、「漢字10問解くのに何分かかるか?」と考えて見てほしい。 平均して、[1][2]で5分、[3]で15分、[4]で15分、[5]で15分といったところがおおざっぱな時間配分となる。「時間が足りなくてぜんぶ解けませんでした」ということのないように、一問にかけてもいい時間をあらかじめ知っておくことは、大事。 わからない問題があっても考え込まずに、一問につき3分程度で見切りをつけて、次の問題に移る。 その際わからないからといって空欄のまま次の問題に移るのではなく、その段階での答えを出して次の問題に移ることが大事。後から見直すとして、またゼロから始めていては時間がかかるので、その段階での見当をつけて答えを選んでおく。 50分の試験時間を、それぞれの問題ごとに区切っていくと、必然的に作文に割ける時間は5分から10分しかないことになる。それゆえ、短い時間で二百字の文章を作ることが必要になる。 では、そのためにどうしたらいいか?3、二百字作文を5分で書くには? 本文を読んで自分でゼロから二百字を書くよりも、パターンにはめて書いたほうがラク。 あらかじめ、「こんなことを書いたらいい」というパターンを用意して、当日はそのパターンに本文から言葉を抜き出して、パターンの中にその言葉をちりばめて作文つくったら終わり、というようにする。「こんなことを書いたらいい」というのは、ひるがえって言えば「こういったことを書かないと点をもらえない」ということでもある。 これが書いてあったら点数を加える、これがなかったら減点する、という基準をしること。 つまり、採点基準を知ること。 作文で点を取るには作文の採点基準を知り、それをクリアーしながら200文字書いてゴールしなければならない。 ただ書けばいいというものではないし、すばらしい文章をかくべきだということもない。 目的が点数である以上、採点基準を知らずに突撃するのは野蛮人なのである。 だいたい、採点基準はこんな感じであると予想されます。【採点基準】1.課題としてあたえられたテーマに、きちんと答えているかどうか、キーワードが入っているか。2.課題に対する意見・感想について、賛成・反対の立場が示されているか。3.主張の根拠・理由付けが課題のテーマと関連がある内容でなされているか。 この「2」がポイント。 作文といえども小論文みたいなもんなので、その話題に対して賛成か反対かという自分の立場を明確に示してやらねばならない。 で、私からのアドバイスとして『私は筆者の意見に賛成である』 これでいけ。 どんなテーマでも賛成。 とりあえず賛成。 作文の最初に「~と私も思います」と書き、最後にも「~という筆者の意見に賛成です」と書く。 反対意見は、書かないほうが無難。 なぜなら筆者の主張をくつがえす理由付けをするのが大変なので。 短い時間しかないのである。「私は反対だ、なぜなら~~だからだ」と自分独自の意見を考えて、書いて、なんてやってる時間があったら、ほかの問題を解いたほうがいい。「私は賛成だ、なぜなら、いやぁ意見はぜんぶ筆者に言われちゃったから、私から付け足すことなんて何もありませんよ」 これです。 このセコさが、ぼくのやり方です。 もちろん大学入試の小論文ではそんなセコい手は通用しない。またもっと本格的にやりたいの、おれは! という人は別にきいてください。とりあえず「短時間で、最低限の答案を作る」というテーマでこの文章は書かれています。 文筆家・益田としてはこんな方法はオナラ程度にしか思っていませんが、塾講師・益田としてはこの方法がベストとは言わないがベターなものではあると思っています。 参考までに、減点の対象となるものも述べておきます。【減点対象】1.原稿用紙の枠を無視(はみったらあかんで!)2.誤字・脱字3.文末の不統一(常体「だ・である」か敬体「です・ます」のどちらかに統一しないとダメ)4.賛成・反対が書いていない5.字数制限の80%に満たない(できれば170字以上! さらにいうと180字以上!)6.字数制限を1文字でも越えている7.「~しちゃって」「超すごい」などの若者言葉8.原稿用紙のルールを無視 で、この8.原稿用紙のルール が問題なのです。 なぜなら、200字作文の原稿用紙のルールは一般の原稿用紙のルールとはちがうから。4、原稿用紙の基本ルールを説明 字数制限のある入試の作文は一般の原稿用紙のルールとは少し異なる点がある。 これについては、一応私はとある学習塾に所属している身なので、あえて秘密とさせてもらおう。 知りたかったら、うちの塾においで。 私は意地悪なのである。(本当はだんだん書くのめんどくさくなってきただけ)その2 実践編 ~実際に書き出すための方法~ 作文は、書き出すまでがむずかしい。 一行目でいきなり詰まってしまう、という人のために、手取り足取り「こうすればいい、こう書けばいい」と教えていきます。1、本文の主張を自分の作文に引用する作文を書くには、本文のテーマ・主張を読み取って、それを抜き出して作文にあてはめるとラクだ。自分で意見を出して、自力で文章が書ければいいんだけれど、それは大変だし、そんな時間もない。ではどうするのかというと、学級会で「意見を言ってください」と言われて、「ぼくも~~君の意見に賛成です」と言うせこいやり方をつかって、あれを作文でやればいい。前回に言った「必ず書かなければならないこと」のうち、「1.テーマについて書いている」「2.賛成か反対か書いている」(「3.理由付けがされている」 というのは出来たらでいいです)のふたつだけは最低でも書いておいて、あとは本文の主張を引用して、「~~と私も思う」とつなげれば、それで作文ができる。そのために必要なことは、文章を読んで「この文章は何について言っているのか」「筆者のもっとも言いたいことは何か」を読み取ること。これができれば作文はできたも同然。そこで、文章のパターンを知り、「だいたいここらへんに主張がある」というパターンを学ぶのです。2、日本語の文章の構成について日本語の文章には、だいたいのパターンがある。[1] 結論は最後の段落にある◎ 基本的には、このパターンです。最初の段落 → 文章の話題を出す途中の段落 → 主張の根拠や具体例最後の段落 → 文章の結論を書く とくに論文のようなきっちりとした文章であれば、ほとんどがこの形をとっている。 最後の段落の、最後の行から2、3行のところに結論があるパターンがほとんど。(どうしてもわからない場合は、最後の段落から5行くらい抜き出して「と私も思います」と書くだけでもそこそこの点数が取れる。問題の文章によって差はあるが、6点~8点は取れる。平成16年度の問題はこれだけで8点取れた)[2] それぞれの段落の内容は、その段落の最初の行にある 各段落の先頭には、「その段落でどんなことを言おうとしているか」、という段落の内容がまとめて書いてある場合が多い。つまり、各段落の1行目を拾っていけば、本文の主張をつかんだと同じことになる。(どうしてもわからない場合は、各段落の1行目の文を拾っていって、「と私も思います」とつなげる作戦もある。文章によって差はあるが、6点~8点は取れる。平成17年度の問題はこれだけで8点取れた)以上のことをふまえ、まずは筆者の主張を抜き出す訓練からしても良い。3、実際に書いてみる 抜き出した作者の主張を作成例にあてはめて、作文をつくる作業をする。 まずは慣れることと、「なんとなくできちゃった」という成功体験をつかむことを目的とし、・まずは書いてみる・とりあえず書き終える・直すべきところだけ直す(誤字・脱字・字数制限・原稿用紙のルールなど) はじめの目標としては、数をこなすことを目標として、次々と書くのがいい。 でも書いて終わりじゃあ、いいのか悪いのかわからないので、身近な人に(文章を書いてる人に)判断してもらう。 おれに見せてくれたら、その場で評価・訂正・採点します。 メールでも掲示板でもいいっすよ。
2006/12/13
コメント(0)
-
七色のハイ
学生時代は体育会系のクラブに所属していたので、大変だったのである。 なにしろ、先輩には絶対服従だ。 どんな理不尽な要求にも、「はい」の一言で従わなければならない。 我々下級生は「京都駅つくまでに弁当6つ食え」とか「ビールと日本酒シェイクして一気のみ」とか「明日までに新人ふたり入部させろ」とか「柔道部の藤本に勝ってこい」とか「今からおれんち来い。電車ないけど」とか「腕立て伏せ、四時間」とか、無茶無体な要求を日々つきつけられる。しかし、すべての状況において返事は「はい」しか許されていない。「ジュース買ってきて、ファンタササニシキ」「はい!」「お前ホッチキスおでこにさせるよな?」「はい!」「明日までにショートコント考えとけ。下級生対抗」「はい!」 合宿の夜は詩吟に合格してからコントで上級生を笑わせて、それからクイズに全問正解しないと眠りにつくことは許されなかったのだった。 なんでもかんでも、とりあえず「はい」 中には「それは無理だ」という要求や、「いったいなぜ?」という要求もあるのだが、すべて「はい」 そんな暮らしの中で私は、「七色のはい」という高等テクニックをマスターした。1.賛成のはい はい、と元気よく発声する。声は大きすぎず、小さすぎず適切な音量で。この場合の適切な音量とは、50メートル先の相手に聞こえるくらいの声を意味する。 先輩の出した要求がまっとうなものであり、それを進んで実行するときに用いる。2.大賛成のはい はい! と声を張り上げて発声する。目を輝かせて、ときに大きくうなづきながら。 先輩の出した要求が飯をおごるとか酒をおごるとか自分の利益に結びつくときに用いる。3.否定のはい はい…… と腹痛か十二指腸潰瘍か自分の体をむしばむ病魔に負けそうになりつつ、絞り出すように発声する。ひたいには自然と脂汗がにじみ出る。 先輩の出した要求が実現不可能なものであったり、法に触れるんじゃねーのかというときに用いる。4.疑問のはい はい? と疑問を投げかけながら、言葉の底にはかない否定の色を見せる。しかしその思惑が達成されることはないことを知りつつ、諦めの表情を浮かばせて哀れみを誘いながら発声する。 先輩の出した要求がありえないものであったり意図のわからないものであったときに用いる。5.とまどいのはい はい? 疑問形だがそこに否定の色合いはない。「おっしゃっている言葉の意味がよくわかりません」とはじめてテレビを見たマサイ族の顔で発声する。 先輩の要求に対して、とりあえず時間を引き延ばしたいときなどに用いる。6.驚愕のはい は、は、はいぃぃぃ と顔面をひきつらせながら、陸揚げされたマグロのように全身を痙攣させつつ発声する。 先輩の怒りをかったときなど、謝ればますます相手は怒りをつのらせるので、謝罪の言葉を驚きにかえて説教と罰練習は必至の状況を、別のステージに移行させる効果がある。7.逆ギレのはい はいぃぃ! 憮然として、全身に気魄をみなぎらせながら発声する。 先輩の怒りがMAXに達し罰練習が決行されるときに、自分は気合に満ちていてどんな練習でもやりきってみせます、とアピールするために用いる。練習の終盤に、限界を迎えて精神がぶち切れたふりを装い、「今日はここらへんにしとくか」という雰囲気をもたらすためにも有効。 体育会で下級生生活を送る方に、ぜひ活用して欲しいテクニックなのであった。
2006/10/31
コメント(0)
-
友と会う
大学時代の友人に会った。 そいつは、同じ部に入って、でもすぐにやめてしまった奴で、その頃からどこか変わったところのある奴だった。 そいつは松本という。おれと松本は、そんなに頻繁に会うわけでもないが、会っては一昔前の若者みたいに、日本がどうだとか、世界がどうだとか、そんな青臭い議論をする仲だった。 松本が部を辞めたのは、大学を辞めるからという理由だった。大学を辞めて何をするのかというと、青年海外協力隊としてアフリカだかアフガンだかに行くという話だった。 変わった奴、と言ったのは正確ではないかもしれない。「おれは自分にはやることがあると思うんだ」「おれは誰かの役に立ちたい」「おれは人のためになってる、っていう実感が欲しい」 松本はいつもそう言っていた。 それはあまりに正しくて、おれたちにはちょっとまぶしすぎただけのことだ。 久しぶりに会おうと連絡を受けて、それは久しぶりという言葉では言い足りないくらいの久しぶりで、数えてみれば十年ぶりくらいの久しぶりなのだ。「東京に来てるんだ。こっちにいる仲間で、誰かいるかなって考えたら、お前がいたから」 そう言われておれは嬉しくて、とまどってしまった。 久しぶりは嬉しいけれど、会ってどんな話をしよう。 学生時代、そいつの正しすぎる言葉と行動に対して周りの奴は理解できないって態度をとるか、または納得できないって態度だった。「松本くんの言ってることはわかるけど、なんかよくわからない」「もっと大事なことあるんじゃないのか、自分の周りのことでも」 なんというか、彼の言うことは立派すぎて、本や映画の中ではよくあることでも、それが自分の周りにあると、とたんに遠ざかってしまう。どうにも現実感がなくて、そんな話をしっかりとした目で語る存在におれらは慣れていない。「あいつにはがんばってほしいけど、正直よくわからん」 そんなことをいう声が、あった。 おれは、そんな松本をわかってやりたかった。おれにとって世界は自分の中にある小さな宇宙でしかなく、松本にとって世界は自分の外にある未知なる広がりだ。おれは松本の思う世界を感じることはできないと分かってはいたが、分かりたいと思った。話を聞いて、言葉を返した。どこまでも交わらない議論をしながら、こいつは世界の不幸とか貧しさをダイレクトに感じる心を持っていて、他人の痛みをきっちりと実感できる強い心を持っているのだと思った。それはおれにはない性質で、おれはそのことにただ感心して、うなづくことを繰り返した。 同意して、誰よりも松本を認めてやりたかった。自分にできることはそれくらいだと思ったからだ。 出発の日は関空に仲間と見送りにいって、いそがしいままたいして話もできないまま別れた。 ただ、最後に松本が言った言葉はずっと忘れられなかった。 最後に、松本はおれの前に立って、おれの目を見て、いかにもあいつらしく全身でおれの方を向いて、言った。「おれは、お前に感謝してるよ。 お前といろいろ話せてよかった。 お前に言われた言葉を、ずっと考えてた。 お前に言われた言葉に、支えられてる」 そう松本は言って、おれは「おう」と答えた。 そのときおれは、「おう」としか言えなかった。 自分が言ったどんな言葉が彼の支えとなったのか、そんな力のある言葉をおれが言ったのか、何かの勘違いじゃないのか。 他の奴が言った言葉とか、何かの本で読んだ言葉を勘違いしてるんじゃないのか。 そんなたいした言葉を吐いた記憶もない。 おれにはわからなかった。 その言葉を確認しようと思う間もなく松本は旅立っていって、結局のところはわからないままだ。 それから、十年も経つ。 それから、一回だけ松本から連絡があったことがあった。 おれの三十歳の誕生日にメールが来て、「Don't trust over 30!」 それだけ書いてあった。 ともかくも、十年だ。 新宿の町で、おれはすぐに松本を発見することができた。 昔と変わらない人懐っこい笑顔で、松本はおれを見つけた。 おれは、昔とどれくらい変わったんだろう、どれくらい変わらないんだろう。 そんなことが気になった。 とりあえず飯を食おう、酒も飲もう、と店に入って、松本は前置きなしに話を始める。 松本の話には世間話が存在せずに、いきなり本題なのだ。 自分の仕事の話。学生の頃から今に至る話。付き合っている女性の話。そんな近況報告から、最近の政治や世界情勢の話まで。 意外なことに松本はコンピュータのプログラミングの仕事をしていた。学生時代に行ったアフリカでは灌漑施設とか農場作りとかをしていたらしい。今はふたつ年上の女性と付き合っていて、結婚も考えているらしい。 そんな話を一通りしてから、松本はおれに訊いた。「で、お前はどうなんだ。どうしてる?」 きかれて、改めておれは詰まってしまった。 かつての根無し草から、今はしっかり根を張って生活しているらしい松本に対して、おれには語るべき生活があるのか。 吹けば飛ぶような塾講師で、学生の頃から今に至るまで完結しない小説をいくつも書いて、付き合っていた女性とは縁も切れて何も残らない。 語るほどのものが自分にはあるのか、と自問自答して、その答えは「なんもないなぁ」でしかない。 それでもおれは、自分のことを語るしかない。 大学時代から千枚くらいのボツ原稿を書いて、その間バイトに明け暮れて、六年前から塾講師をしているがこの先どうなるかはわからない。好きな女とは別れたが、いまだに壁から写真をはがせずにいる。その写真の隣にはマチュピチュの写真があって、いつか行きたいと思っている。その隣にはヒクソン・グレイシーの写真が貼ってあって、いつか倒したいと思っている。 話しながら、自分に成長のないことが恥ずかしいような目になってしまう。 おれはこいつにどう写っているんだろう。あきれてはいないか。情けなくはないか。 自分が他人と同じフィールドに立っていないような引け目がある。 自分が何かひどいミスキャストをしてしまったような感情。 松本は言った。「おれは、もうそこにはいられない。お前はすげえな。 あの頃と同じように悩んで、同じように引っかかって、立ち止まってる。 おれは立ち止まってるのが怖くて、不安で、荷物下ろして先に進んじゃったけど、お前はまだあそこにいるんだな。 おれはそこにはいられないけど、お前はまだそんなところにいたのか。 なんていうか、忘れ物をずっと忘れ続けて、まだ宿題やってんのか。 まぁ益田。 無責任だけど、そこにおってくれよ。おれはもうおれんけど、お前はおっといてくれ。 お前がまだそこにおっといてくれて、嬉しかった。みんなもう悩むのやめて、ええことやってる。 でもお前がそこにいると思ったら、がんばれるわ」 すごいも何も、おれはこうしているより他にやりようがなくて、抜け出せるものなら抜け出したいと思ってやってきただけだ。 もちろんすごくなんかなくて、おれには充分な助走がなくて、充分な貯えがなくて、飛び立つことができなかっただけだ。 ペンギンみたいに、空を飛べずに水の中をもがいていただけだ。 そう言う松本を前に、おれはまた「おう」と答えるしかなかった。 お前のほうが、よっぽどすごい。「お前に言われた言葉が支えになってた」という言葉を、きいてみた。 それは、おれの小説の中の言葉だった。 おれが大学二年の頃に書いた小説の中のセリフだった。 こんな小説を書いているんだ、と話していた中の言葉を、彼はずっと覚えていてくれた。「主人公は、十年前に戻りたい、二十年前に戻りたいって、ずっと思い続けてるんだよ。 今の自分に後悔があって、十年前に戻りたいって思ってるんだ。 今の生活はあるんだけど、やり直したいという気持ちは消せない。『あの頃に帰ったら……』そう思ってる。 でも、あるとき気付くんだ。 どうせそんなだったら、そう思うくらいだったら、 いまの自分を、十年後から来たんだと思って、 今をやり直せばいい。 三十歳の自分が、二十歳に戻りたいと思うんじゃなくて、 三十歳の自分を、四十歳の自分が満足できるように。 どうせそんなだったら、そう思うくらいだったら、 いまの自分を、十年後から来たんだと思って、 今をやり直せばいい。」 こう書いたのは、二十歳のおれだ。 三十二歳のおれは、今をしっかり生きているだろうか、 そんなことを考えた夜だった。
2006/09/26
コメント(0)
-
予シリ6年下 第1回 ・ 説明文・論説文の読み方(2
【 予シリ6年下 第1回 ・ 説明文・論説文の読み方(2) 】記述式の問題を中心に、解答の作り方を考えてみます。[基本問題]問2 「これら」とは何のことですか。【指示語の問題】1. 基本的には前を見る ↓ これ この → 近く ↓ あれ あの → 遠く ↓ それ その → まず近くを見て、なかったら遠くへ もし前になかったら、後ろをさがす2. 指示語の部分が主語のとき、まず述語をみてその内容を踏まえたうえで指示語よりも前を探す。 ↓ 指示語が含まれる一文はじっくり読むこと。――部分以外のところにヒントがあることが多い。 傍線部分は、「これら」だけだが、問題を考えるときはその一文全体をちゃんと読むこと。「初めて渡る鳥たちは、これらを利用するだけで最初から十分に飛んでいけるのでしょうか?」 指示語の問題は、指示語の部分を空欄にして、そこに当てはまる言葉が正解。つまり、「初めて渡る鳥たちは、 を利用するだけで最初から十分に飛んでいけるのでしょうか?」 としたときに、自分で書いた答えがちゃんと当てはまるか、確認することを忘れない。 に当てはまる「これら」は、「名詞」なので、答えも名詞となる。 指示語の内容は、それより前にあることが多い(「これ」の場合は直前の文)ので、直前の文から名詞を探す。 また、「これらを」とある、「~を」という形もかなりヒントになる。 直前の文から「~を」となっているものを探すと、「体内時計を」「コンパスを」とあるので、この二つが正解。問3 中学入試の国語では、ふたつのことを対比して考えている文章が多い。 この部分では、「一度でも渡りを経験したことのある鳥」と「未経験な若鳥」を比べている。1. 問題文 「一度でも渡りを経験したことのある鳥たちは、 何を 頼りに 軌道修正するのですか」 ↓ ↓ ↓ ↓ 鳥は を つかって 修正する( 問題文の言葉を、簡単な言葉に直して、それと対応するものを本文から探す ) 問題文の中から、「軌道修正」という言葉を得て、それを本文から探すと、L15「軌道修正」L30「修正」とある。 しかし、L15の部分は、参考にならない。国語の答えで、『抜き出して』などとあった場合は、傍線部分から抜き出すことはないというルールがある。 それゆえにL30「修正」にしぼって探すと、彼らが、A体内に遺伝的に備わったプログラムだけでなく、Bあとで学習したさまざまな地上の目印も 利用して ↓ ↓ ↓鳥が を つかって というように対応している。よって、1.一度でも渡りを経験したことのある鳥たち 2.未経験な若鶏たち の答えは、ここからもってくればいい。問4 1「何のために渡りなどするのでしょう?」 傍線部の問題は、「傍線部の前にヒントがある」という問題が多いのですが、この問題は[6]段落の最初が「では」とい話題を転換する接続詞で始まっているので、ここから前は別の話になっていて、ここから前にヒントがあることはない。[7]段落を見て、渡りをする利益とコストという二つのことを対比しながら、本文を読む。渡りの利益 もっと食べ物の豊富な場所があるのであれば、~~、そこで過ごしたほうが生存率があがる渡りのコスト 死んでしまう エネルギーを消耗し、次の繁殖での繁殖率が下がる こういったところを○や□で囲みながら、本文を読む。 これで問5も同時に解けます。 また、「一方」という表現は、「Aだが、一方Bでもある」とふたつのことを並べていう表現であるが、この場合Bに大事なことがきている場合が多い。問7 文章を二つや三つに分ける問題では、いくつかヒントがある。【段落分け問題】 1. 「さて」「ところで」「では」の話題転換語に注意 2. 文中の繰り返し語句や内容が、急に変わる。 (1.は邪道、2.は王道。しかし1.2ともにほぼ100%の確率で分かれる場所) 3. 時間、場面が変わる 4. 1から3がすべて駄目でピンチなとき → 逆接で始まる段落 (ただし信頼度はかなり落ちる) 5 結論の段落は、それだけ独立している。 たとえば、 12 - 345 - 67 - 8 (8が結論だとして、78とくっつくのはあまりない) この問題の場合、「では」「それでは」とあるので何も考えなくても正解が出る。 [発展問題]問4 を埋める問題は、 のうしろの言葉を見て、それに対応する部分を本文から探すと良い場合が多い。1 □をする 鋭い、よい言葉づかい をしたい2 □こと 文脈ごと言葉を覚える のがよい3 □文章を熟読して 自分を引きつける ものを熟読して4 □ようにし、 いっそう鋭く深く受け取る ようにする5 □ことが必要だ 自分の目で判断する こと 問題文と本文との対応を探す、これは国語の問題を解く上でよくあるパターンです。問5 文章を書くときに、同じことを表現をかえて何度も繰り返すことがあります。 自分の言いたいことを相手に伝えるために、主張を形を変えて繰り返すのです。「社会で存在を認められる単語」とあるので、「社会」「存在」「認める」といった言葉をキーワードにして本文を探します。ふたつ前の文に「人間社会にある一つの事実を的確にとらえ言語化したから、社会に存在を認められたのです」とあるので、その部分をつかいます。 問題は「どのような言葉」なので、答えの型は「~~言葉」となります。問6 「彼は二十万語の日本語を消化しようとした」とあります。彼は 二十万語の 日本語を 消化しようとした ↓ ↓ ↓ ↓大江さんは たくさんの 日本語を つかう(問題文の 指示語は言い換えて、ややこしい言葉やあいまいな言葉は簡単な言葉に言い換えて、考える)理由・原因の問題のヒントの探し方で、文の前後が「ヒント=答え」、「答え=ヒント」となっているパターンがある。 ヒント 答え 文 A ならば 文 B である 答え ヒント それと同時によくあるのが、 ヒント 答え 文 A でなければ 文 B ではない 答え ヒント と、逆のことを言っているパターン。 自分が区別して 使える 言葉の 数が多くなくては、ぴったりした表現ができない。 ↓ ↓ ↓ ↓ (こっちがヒント) つかう 言葉 たくさん (こっちが答え)問6 傍線部と、ひとつ前の文を比べてみます(6)それは その人 その人なのです。 ↓ ↓ 言葉をどう使うかは、 その人が保守的な態度をとるのか、 新しい態度をとるのかによって違う。 指示語の部分が主語であったら、その意味内容も別の文で主語の働きをするものである場合が多い。問12 「筆者は言葉を的確に使うにはどうすることが大切だと述べていますか?」 本文から、「言葉」「的確」「つかう」のキーワードを探すと、最終段落に「言葉を的確に運用できない」とある。 「筆者は 言葉を 的確に 使う にはどうすることが大切だと述べていますか?」 ↓ ↓ ↓(~がなくては) 言葉を 的確に 運用できないのですね「Aでなければ、Bではない」 → 「Aであれば、Bである」「単に言葉に敏感になるだけでなく、事実そのものをよく見る眼と心とを持つこと」 (36字)「はっきり見て、それをきちっと表現する心がまえ」 (22字) 以上のことから解答を作って、文末の「~すること」をつければ、解答はできあがります。解答例1 [言葉に敏感になるだけでなく、事実そのものをよく見る眼と心を持ち、それをきちっと表現する心がまえを持つこと](52字)ただし、これは正解になるには不充分で、満点の解答になるためには、これ以外に前半部分に書いてある、「自分が区別して使える言葉の数を多くする」 (19字) というのも入れてやらなくては満点にならない。解答例2 [自分が区別して使える言葉の数を多くして、事実そのものをよく見る眼と心とを持ち、それを表現する心がまえを持つこと] (55字) 重複する部分は削り、文字数を揃えました。また「きちっと」といった擬音は国語の解答に書いてはならない言葉なので、けして書かないように注意します。(この場合は文中の言葉なのであっても許されると思うが)
2006/09/11
コメント(0)
-
国語読解の解答公式
●はじめに ~国語の学習で大切なこと~国語の勉強をするといっても、何をしたらいいかわからない人もいるでしょう。漢字やことわざを覚えたり、四字熟語を覚えたりすること、それはできます。しかし、物語文や説明文を読んで「このときの主人公の気持ちを四十字以内で答えよ」と言われると、何をどう書いていいかわからない、そんな声をよく聞きます。授業やテストの復習で、解説を読んだり模範解答を書き写したりしても、自分で同じような解答が書けるかといえば自信がない、という生徒が多いと思います。解説を読んでも、「なんでその解答になるのか」は書いてあっても、「どうやってその解答を書くのか」は書いてありません。「国語の問題を読んでも、問題に書いてあることがわからない」「問題が解けないのは、問題の文章が理解できないからだ」そう考えて、必死で本文を理解しようと、本文を丁寧に読んでいる生徒を見かけます。算数の問題で言えば「太郎くんは家を8:30に出発して、学校に9:00に着きました。太郎くんの家と学校は800メートル離れています。太郎くんの歩く速さは分速何メートルですか」という問題を解くときに重要なのは、速さの公式を覚えているかどうかであって、それが太郎くんであろうが花子さんであろうが、重要ではありません。もちろん、算数とちがって、国語の解答を書くためには課題文の意味を理解する必要があります。しかし、国語の学習とは、「課題文の意味を理解すること」ではなく、「問題を解くこと」です。課題文の意味を理解することよりも、問題の種類をみて、その問題を解くための方法を知ることが大切です。●国語の問題を解く手順1. 問題文の種類を見分ける。 1 物語文 読者に感動を伝えるために書かれた文(小説、随筆、詩歌など) 2 説明文 読者に知識を伝えるために書かれた文(説明文、記録、随筆、解説など)2. 知識問題と文章読解問題を区別する。 1 知識問題 知っているかどうかだけなので、先にさっさと済ませる。 先に漢字や文法、文学史などの知識問題を先に片付けてしまいましょう。 こういった問題は、知っているか知らないかというだけだから、うーんと考え込んで時間を使わないこと。 間違っても、あとまわしにして知識問題やる時間がなかったなんてことはないように。 知っていれば解ける、知らなかったら解けない問題は、さらっと解いて、次に進む。 2 文章読解問題 問題の種類によって、解く。3. それぞれの問題の種類を見分ける。 1 理由問題 「なぜ~?」「どうして~?」「~の理由を書け」 2 気持ち問題 「~の気持ちを説明せよ」「どういった気持ちか」 3 表現問題 「この表現はどういった意味があるか」 4 言い換え問題(~~こと問題) 「~とはどういうことか?」 ほかに、「~様子」「状態など」多数 5 テーマ問題 「文章全体を通して作者が言いたいことは何か」 6 指示語内容問題 「その考え、とはどのような考えですか」 7 部分・場面わけ問題 「この文章を三つにわけるとするとどこで別れるか」4. 答案メモを作る。 1 理由問題 答案フォームを作る。 2 気持ち問題 答案フォームを作る。 3 表現問題 答案フォームを作る。 4 言い換え問題(~~こと問題) 本文のキーワードをチェックする。 5 テーマ問題 最終段落、最初段落、各段落の第一文からテーマを探す。 6 指示語問題 指示語が含まれる文と対応する部分を探す。 7 部分・場面わけ問題 接続語、場所・時間・人物の変化をみる。5. 清書する。 問題にあった形に答案メモをまとめる。理由問題の解答公式 (物語文の場合) 理由問題の基本フォームは、こうなります。1 理由 2 相手 3 気持ち 4 文末( )( )( )( から ) ( 考える順番 4→3→2→1 )これは、「~の理由を答えろ」の問題では解答に1から4の四つの部品がなくては満点にならないということです。 それでは、実際に例題を通して、理由問題の解き方をかんがえていきます。例題『自分の順番が近づいてくるにつれて、洋はゆううつな気持ちになった。今日の体育の授業はとび箱の授業で、洋はとび箱がにがてだったのだ。クラスのみんなは軽々ととび箱をとんでいて、洋は逃げ出したいような気持ちになった。そして、洋の番が来た。もうどうにでもなれと、とび箱にぶつかるくらいに全速力で走って、夢中でとびはねた。「とおっ」気がつけば、自分の後ろにとび箱があった。はじめて22段のとび箱をとべたのだ。「すごいな、洋。よく飛べたぞ」先生がほめてくれた。洋の心は、はずんだ。』 問題 上の文章に「洋の心は、はずんだ。」とありますが、それはなぜですか。この問題を読んで、答え → 「とび箱がじょうずにとべたから」という答えを書く人が多いですが、これではサンカクです。なぜこれではいけないのかというと、この答案には【気持ち】がないからです。それでは、この問題を解答公式に当てはめて考えてみます。まず、問題を解く準備として、基本のフォームをメモ用紙に書いてください。 1 理由 2 相手 3 気持ち 4 文末( )( )( )( )1.【文末】を決める考える順番は、4→3→2→1です。この場合、理由問題なので文末は「から」で決定です。4文末 のところに「から」と書きます。1 理由 2 相手 3 気持ち 4 文末( )( )( )( から )2.【気持ち】を考えるここで注意するのは、国語の問題では必ず【気持ち】が解答にないとマルにならないということです。ふつう、「どうして教科書を忘れたんだ?」ときかれたら、「学校から帰るのが遅れて、急いで家を出たからです」 と答えれば意味は通じるのですが、もしこれが国語の問題であれば、「学校から帰るのが遅れて、急いで家を出て、あわてていたからです」 と気持ちの表現を入れないとマルになりません。 これは問題には書いていないし、解説にものっていませんが、国語の問題のルールなので覚えてください。 ここでは「先生にほめられた」→「うれしい」という気持ちが考えられます。「洋の心は、はずんだ」という表現から、「心がはずむ」 → うれしい。喜んだ。おもしろい。 などの気持ち言葉を考えます。3気持ち のところに「うれしい」と書きます。1 理由 2 相手 3 気持ち 4 文末( )( )( うれしい )( から )うまい気持ち言葉が思いつかないときは、まずそのときの感情が「プラスの感情」か「マイナスの感情」か考えます。良いことなのか、悪いことなのか、どちらかあてはまりそうな気持ち言葉を考えます。◎ プラスの気持ち言葉 → うれしい。安心する。決心する。賛成する。期待する。あこがれる。 夢中になる。自信を持つ。感動する。許す。ほめる など◎ マイナスの気持ち言葉 → 悲しい。つらい。怒る。不安になる。緊張する。おびえる。恥ずかしい。 反省する。驚く。迷う。悩む。うらやましい。落ち込む。 など3.【相手】を決める これも、問題には書いていませんが国語の解答になくてはならないものです。「相手」は必ず本文に書いてありますので、本文にある登場人物をそのまま書けばよいです。1 理由 2 相手 3 気持ち 4 文末( )( 先生にほめられて )( うれしい )( から )4.【理由】を決める 3【気持ち】 で書いた感情がおこった原因となる出来事を考えます。 ここで書くのは具体的事実です。しかも、それは必ず本文に書いてあります。 本文に書いてあること以外を書くのは国語の解答では許されません。ここでは、「なぜうれしいのか」、「なぜ先生にほめられたのか」と考えて、1 理由 2 相手 3 気持ち 4 文末( とび箱がじょうずにとべて、)( 先生にほめられて )( うれしい )( から ) 本文の中にあった出来事をみて、「なんでうれしいのか」「どうしてつらいのか」に関係のあるものを抜き出します。5.清書する 答案フォームにメモを書いたら、それをまとめます。 ここで注意するのは、「じょうずな文章を書こう」とか「立派な文章を書こう」ということはまったく考えなくてもいいということです。「清書」するというのは、「日本語としておかしくないように文をつなげる」というだけです。 国語の答案を採点する人がチェックするのは、「必要な部品がそろっているか」「誤字・脱字はないか」「文末表現はあっているか」といったことです。それ以外のことは見ません。 国語の答案に求められているのは、「じょうずな文章」ではありません。1 理由 2 相手 3 気持ち 4 文末( とび箱がじょうずにとべて、 )( 先生にほめられて )( うれしい )( から ) このメモから答案を作ると、【答案】 とび箱がじょうずにとべて、先生にほめられてうれしかったから。 これで満点の解答になります。 物語文の理由問題を解くときの方法は、だいたいこのような感じになります。 今回の講義は、とりあえずここまでとします。 ネジネジ ゛"8-( ・Θ・)ノ~'' ピヨピヨ バイバーイ
2006/08/31
コメント(0)
-
読書感想文の書き方
【 夏期講習特別ふろく 読書感想文の書き方 】1 はじめに 夏休みや冬休みになると、たいてい「読書感想文」が宿題で出されます。でも、何をどう書いて良いか分からないという生徒が多いのです。塾の生徒でも、毎年夏休みの終わり頃になると「先生、読書感想文どう書いたらいいんですか?」といって持ってくる生徒が何人もいます。 どうやら、学校では宿題は出すけど、その書き方までは教えてくれないらしい。ぼく自身も、読書感想文の書き方を学校で習った記憶はない。国語の授業といっても、授業で文章の書き方を教わった覚えはない。 そこで、ここでは読書感想文の書き方のひとつの方法を示します。 これが「唯一の方法」だとも、「最善の方法」だとも思わないけれど、「簡単な方法」ではあるとは思います。 小説を書くときの基本となる方法を、読書感想文に応用してみました。他のどんな文章でも使える方法なので、知っておいて損はないと思います。また、こんなせこいのじゃなくて、もっとちゃんとした文章の技術を知りたい人は、益田まで相談しにきてください。2 読書感想文に本の感想なんて書いてちゃダメ 読書感想文を書けと言われて、まず思いつく駄目なパターンは「おもしろかった」「感動した」と読んだ感想を書いただけの作文です。「読書感想文なんだから、本を読んだ感想を書けばいいんじゃないの?」と思った人は、ぼくからしたら読書感想文が何であるか、まったく理解していないということになります。 結論から言うと、 読書感想文とは、「本を読んで、自分の生活を反省する作文である」 ということになります。 まず、登場人物の体験と自分の生活を比べる、そして、「自分にはこんなことはできない」「自分にはこんなところはないか」と反省して、最後に、「これからは自分もこうしよう」と前向きになる。 これが基本です。 つまり、読書感想文とは本の内容や感想を書く作文ではなく、自分の生活や体験を書く作文であるということです。 例えば、読んだ本の登場人物が「自然をとても大事にする人」だったとしましょう。 あなたはそこで、自分をふり返るのです。「自分は環境のことを考えているか?」「ゴミの分別や水道の無駄づかいなどに気をつけているか?」そして、登場人物と自分を比べながら 自分はどういう人間なのか、自分の身の回りにどんなことがあったかを書いて、「これからは自然を大切にしたい」と書くのです。 あるいは、本の登場人物が「友情は大事だ」と言ったとしましょう。 そこで自分自身をふり返ります。「自分には大事な友人がいるか?」 「友人を裏切ったことはないか?」 また逆に「友人に助けられたことはないか?」「ケンカした友人と仲直りするにはどうしたらいいか?」 など、読んだ本を通して、自分の生活や体験、そして自分の気持ちをふり返って下さい。 読んだ本のことを書けと言われても「おもしろかった」「感動した」くらいしか書けなくても、自分のことなら少しは書けるような気がするでしょう。本を読んで、自分の生活や体験を反省し、今後の希望を書く、それが読書感想文の書き方です。 なぜそう言い切れるかというと、少なくとも学校の求める読書感想文とはこういうものだからです。それは、コンクールで賞を取っている作品を眺めてみればわかります。ほとんどこんな作品ばかりですから。 3 下書きメモを作ろう 文章を書くときは、まずメモを作ります。いきなり原稿用紙に書き出してはいけません。 あらかじめ、どんなことを書くかというメモを作って、だいたいの内容が決まってからはじめて原稿用紙に向かいます。 小説では「プロット」とか「箱書き」とかいうのですが、全体の構成を考えたメモを作ります。 ○何を書くのか (必ず入れる言葉、体験した出来事、など思いついたことはメモに書く) ○字数配分 (この内容で何行というおおまかな配分を決めておかないと、全体の字数に合わせる) とりあえず全体のプランを立てるために必要なのはこの二つくらいです。 次に、1.何を書くのか について、を書くために考えるべきことを具体的に述べていきます。 ●メモ作り・文章を書くための材料を集めます。 読んで印象に残った場面、ポイントになりそうな場面をいくつか選びます。(いくつあってもよい)・材料をふくらませていきます … 各場面ごとに次の1.から~4.のことをノートに書いていきます。1. 印象に残った場面の登場人物の行動や体験2. 「1」に対する自分の考え3. 「2」からわかる自分の性格、生活、考え方4. 「3」の具体例、成功例、失敗例(実際にあったことでなくても良い) これらのメモを組み合わせて、読書感想文を書くわけです。 場面はいくつあってもかまいませんが、テーマはひとつにしぼるべきです。たとえば「友情」というテーマで書こうと思ったら、友情に関係のない場面は捨てて、テーマにあった場面だけを書くようにします。 このメモを元にして、全体の構成を決めます。例として、原稿用紙三枚(60行)の読書感想文を書くとしてハコ書きを書いてみます。1. はじめ … この本はこんな本だと、簡単に説明 5行2. 1 印象に残った場面の登場人物の行動や体験 15行 2 「1」に対する自分の考え 5行 3 「2」からわかる自分の性格、生活、考え方 10行 4 「3」の具体例、成功例、失敗例(実際にあったことでなくても良い) 15行3. まとめ … これからは自分はこうありたい 5行 これで55行です。 ひとつのネタで15行はちょっと長くて、書くのがつらいかも知れないので、そんなときは、1. はじめ … この本はこんな本だと、簡単に説明 5行2. 1 印象に残った場面の登場人物の行動や体験 10行 2 「1」に対する自分の考え 5行 3 「2」からわかる自分の性格、生活、考え方 5行3. 1 印象に残った場面の登場人物の行動や体験 10行 2 「1」に対する自分の考え 5行 3 「2」からわかる自分の性格、生活、考え方 5行 4 「3」の具体例、成功例、失敗例(実際にあったことでなくても良い) 10行4. まとめ … これからは自分はこうありたい 5行 と、場面をふたつ持ってきて調整すれば、60行くらいはすぐにいってしまいます。 この段階で、書き始めるための準備は整っています。 あとは実際に書き出してみて、細かいところを直して清書したら完成です。
2006/08/06
コメント(0)
-

東京タワー、放送延期…
ショック! ショック☆☆ショック 山本さんの事件のあおりを受けて、ドラマ「東京タワー ~オカンとボクと、時々、オトン~」の放送が延期される見通し。 7月29日の放送を楽しみに待っていたのに、山本さんがけっこう出演してたので出番なくなるか別キャストで撮り直しになるかして放送延期だ。 ひとまずのところ放送取りやめではないのでひと安心だが、それでも場合によってはお蔵入りもあるかもしれない。●ドラマ「東京タワー ~オカンとボクと、時々、オトン~」 なぜ私がこんなにもあせってびびってショッキングなのかというと、このドラマは大泉洋の全国ゴールデンドラマ初主演作品となるべきものだったからなのである。 大泉さんは、2006年現在私の心のアイドルとして離れることのないタレントさんなの。 大泉さんのことを知らない方のためにいっておくと、 大泉洋は北海道を中心に活動するローカルタレントで、北海道テレビの深夜バラエティ「水曜どうでしょう」での活躍により今や全国区の人気を博するようになった俳優さんであります。「水曜どうでしょう」は、北海道限定の深夜放送にも関わらず、口コミやインターネットでファンを拡大させていき、2002年に放送が終了したあとも全国各地のテレビ局で再放送が相継ぎ、今や32の地方局で放送されているという非常に珍しい番組であります。 「水曜どうでしょう」がどんな番組かを、どうでしょうリミックスの文章を借りて紹介いたしますと、▼『水曜どうでしょう』とは 『水曜どうでしょう』とは、テレビ朝日系列のローカル局、北海道テレビ(HTB)が制作している、ローカルバラエティー番組です。 企画担当であり、出演者でもある、鈴井 貴之(通称:ミスター)、大泉 洋、そしてディレクターである、藤村 忠寿ディレクター、嬉野 雅道ディレクターの男4人が、日本中、世界中を気まま、わがままに旅する、旅番組(一部料理番組、教養番組、クイズ番組、つり番組)です。 旅番組とはいえ、一般的な旅番組と侮ること無かれ。基本的に「おいしいもの」や「名所」なんてこれっぽっちもフィーチャーしません。 基本的に「移動がメイン」。 いろんな場所を無鉄砲に移動しまくり、その移動最中に起こる様々なハプニングや罵り合いなどなど、自由気ままなその姿を映し出す。それがこの番組の魅力なのです。 1996年10月09日(水)に放送が始まり、2002年09月25日(水)までの約6年間、北海道で放送され、出演者とディレクター人の掛け合いが人気となり、その人気が口コミや個人のホームページやファンサイト、インターネットテレビ(インプレスTV)などによって広がり、2003年04月当時では、北は北海道、南は四国まで、合計16局で再放送版の『どうでしょうリターンズ』が放送されておりましたが、2年1ヵ月後の2005年05月現在では、北は北海道から南は沖縄まで、全国32放送局で再放送版の『どうでしょうリターンズ』、再編集版の『水曜どうでしょうClassic』が放送されています。 2002年09月25日(水)に一旦最終回を迎えましたが、年に2~3回程度の特番という形で今後も放送される予定です。 また、過去に放送した企画を再編集したDVDを年に2~3枚程度発売する予定です。 私はネットで目にした「水曜どうでしょう」の内容にバカ受けして以来、マニアとして放送を2度3度と繰り返して見るくらいのファンなのですが、この番組のカギは何と言っても大泉洋という人間の発散する田舎臭い魅力、うさんくさい話術、はんかくさい存在感にかかっている。 どんな内容の番組か、実際に見てみたいという人はインプレスTVで無料視聴のコーナーがあるので、そちらをゼヒご覧ください。●「水曜どうでしょう」ユーコン川160キロ 全7回 でもって、そんな大泉洋(別名よういずみおう、またの名を尿泉尿)の本業である役者の仕事で、ついに全国キー局の午後九時放送という時間帯で、しかも原作は130万部の「東京タワー ~オカンとボクと、時々、オトン~」 こんな大役に大泉さんが挑むとは。北海道では「ビビリ王子」の異名をとる小動物のようにビビリ屋の大泉さんが、果たして逃げ出さずに主役を最後まで全うできるのか。 道民は注目していたのですよ、たぶん。 それがなぁ。 山本さん出てたもんだから、放送は中止。 延期の日程は決まっていない。 ついてないなぁ、大泉さん。 それでもこのドラマは、やがて必ず放送されると思っていますので、放送が決まったときには皆様ゼヒ、ご覧ください。
2006/07/19
コメント(0)
-

山本さんがやってもた
やってしまった。 極楽の山本さんが、やってしまった。「極楽とんぼ」の山本圭壱、函館で17歳少女への飲酒、淫行!! 芸能界から永久追放!>>「山本だったらありそうな話だよね」。ある大手プロダクションの妙齢の女性社員は苦笑いした。吉本興業は18日、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱との専属タレント契約を解除した。17歳の未成年者との飲酒や淫行行為で北海道の函館西署に訴えられたのだ。それにしても、吉本興業は実に素早い行動をした。契約を解除し、報道各社にファックスを送ってきたのだ。 山本は、先週末に、欽ちゃんの野球チームの試合のために函館に入った。事件は、その時に…。これはあくまで未確認情報である。山本は、函館のホテルでデルヘルを呼び出した。呼ばれて来た女の子は17歳の未成年だったようだ。山本は、どうやら、その子が17歳と知りながら酒を飲ませ、その後、仲間と一緒に回してしまったというのだ。女性は、未成年でありながらも、山本のとった行動に納得できなかったのだろう。函館西署に被害届けを出したことから、事件が発覚したというのである。っていうことは輪姦ということになる。しかも、犯行は山本1人ではなかったということにもなるわけで、今後の成り行きが注目されるところだ。だが、これは未確認情報なので事実は分からない。だけど、もし、これが事実だとしたら、あの早稲田大学の「スーフリ」と同じ。いや、それ以上に重い犯罪行為になる可能性もあるってことだ。しかも、吉本から解雇された今、もはや山本にはバックがない。裁判でも何でも1人で戦うしかない。これは大変なことだ。因みに、事件に関して吉本興業では「関係者のプライバシーを侵害する」との理由で明らかにしていない。ただ、今回の山本のとった行動については「許されざる反社会的行為に該当するものとして処分した」と強い表現をしている。山本圭壱は、本名が山本圭一。1968年(昭和43年)2月23日、広島県広島市生まれ。89年に加藤浩次とお笑いコンビ「極楽とんぼ」を結成した。バラエティー番組「とぶくすり」「殿様のフェロモン」やラジオ「THE LAST 笑」「笑っていいとも!」にレギュラー出演し、全国的人気に。以降「めちゃめちゃイケてるッ!」や「とび蹴りゴッデス」での2人の本気プロレス対決が話題となった。また、映画「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」に水道局員役で、相方とともにスクリーンデビューも果たしている。ソロとしても「ラブ・レボリューション」「ナースマン」などのドラマに出演。学園祭で下半身を露出し、公然わいせつ容疑で書類送検されたこともあった。今後の活動に関しては、加藤が単独で活動していく。山本は、芸能界から完全に追放され、ニートになるのか? まさにやってもうたの極致で、悲しい限りです。 今年は「めちゃイケ」が1996年に放送を開始してから10周年の年で、メンバー気合はいってたと思うんだが、山本さんやってもた。 残念ですわ。 ぼくは、めちゃイケという番組には特別な思い入れがあって、それはこの番組がテレビ局の企画によるものではなく、メンバーの意志によって作られてきた番組だと思うからだ。「新しい波」にはじまり「とぶくすり」「とぶくすりZ」から「殿様のフェロモン」を経て「めちゃ²モテたいッ!」、そして「めちゃ²イケてるッ!」としてゴールデンに進出する姿をぼくは目撃してきた。 無名の若手芸人を紹介する番組である「新しい波」で共演したナインティナイン・極楽とんぼ・よゐこ・オアシズが集まってできた「とぶくすり」が終了して、次は23時台でバラエティを作るというときに、すでに名前の売れていたナイナイだけを残してあとは切ろうとしたテレビ局側に対して、このメンバーで再び番組を作ろうとする彼らのじわじわした熱意が嬉しかった。「めちゃモテ」放送開始時にはまだナイナイの評価も高くはなく、武田真治、雛形あき子らのアイドルを絡ませることでようやく放送の許可がおりた。当時のナイナイには極楽とんぼ・よゐこ・オアシズをレギュラーとしてのませるほどの力はなく、なんとか極楽とんぼからは山本圭壱だけがレギュラー出演。しかし山本はナイナイらが集まるバーのバーテン役での出演で『バーテン:山本』と極楽とんぼの名前を出さずにひっそりとクレジットされていた。 それが番組途中から加藤、光浦がレギュラーとして参加して、「とぶくすり」のメンバーが再び結集してきた。よゐこは結局レギュラーにはなれなくて、でも番組の最後らへんは頻繁にゲストとして呼ばれてた。 本田みずほは濱口とのいきさつで番組を離れたが、その代わりにオアシズの大久保が参加した。かつて、光浦は、フジの片岡飛鳥に「二人で番組に出して欲しい」と直訴するも、「ブスは二人もいらない。光浦は笑えるブスだが、大久保は笑えないブスだ」と返され、仕方なく一人での番組出演を決意した過去がある。 そうしてバラバラになっていたメンバーがだんだんとそろっていく過程は、それがテレビ局の演出によるものではなく、彼らの熱意によるものであるだけに、ちょっとじーんとした。 テレビ番組においては、テレビ局の意向によってキャスティングがなされ、売れている芸人や売れそうな芸人、売り出したい芸人を組み合わせて番組を作るのがほとんどの場合だろうと思う。出演者の意志でひとつの番組が終わった後にまたそのメンバーが結集して新しい番組を立ち上げるというのは、これまでにはなかったことだと思う。 ナインティナイン・極楽とんぼ・よゐこ・オアシズの8人を中心とする芸人の横のつながりは見ていて快く、気持ちのあたたまるものだったのだ。 今回の事件は、そんな彼らの「平成のひょうきん族を目指す」という夢への過程での、大きな挫折である。 もしかしたら山本の復帰は可能かもしれないが、それは相当の期間が空かないと難しいだろう。(過去に板尾創路が事件を起こしたときは、松本人志らの取りなしによって長期謹慎という形になった。結果、一年間の謹慎だったと思う)しかし山本の場合は事件の内容がちょっとひどすぎるので、復帰できるとは決して断言はできないのが現実だ。そうなるとメンバーを欠いた「めちゃイケ」はそのまま放送を終えることになるだろう。ぼくがそう予想するくらいに、この番組にはメンバーの絆があった。 ぼくは周りの迷惑をかけるなとかいうことを声高に言うタイプではないけれど、さすがにこれはあかんやろ。●動画 極楽とんぼ加藤 山本の不祥事を号泣で謝罪。YouTube - 極楽とんぼ加藤 山本の不祥事を号泣で謝罪。 朝のスッキリ見てたんだが、加藤さん泣いてたよ。 加藤は相方の山本大好きで、矢部から「加藤さん相方好き過ぎやわ」とか言われちゃうくらい仲のいいコンビだった。嘘泣きじゃねーかという人もいるが、おれは信じるよ。 加藤の涙は、岡村や矢部も同じ思いだろう。とくに岡村がどれだけ落ち込んでるか、想像するに悲しいものがある。 過去に吉本興業では板尾創路が同じような少女に対する事件を起こして、そのときは、松本人志らの取りなしによって長期謹慎という形になった。松本が島田紳助に泣きついて、副社長に土下座して処分を勘考してもらった、といったような経緯があったと思う。結果、板尾は一年間の謹慎で済んだわけだ。 今回の山本の件でも、おそらくナインティナインの岡村、矢部は事件の収拾に動いたのだろうと思うが、これは彼らでは収めきれないほどの事件だったのだろう。岡村の悔し泣きを、ぼくは容易に想像できる。 実に悲しい、悲しいニュースだった。 なお、報道の当初においては被害者女性が「17歳」と「中1(12歳)と中3(15歳)」と二種類の報道があったのが、途中から「被害者は17歳女性」で統一されたということだけ、ここに記しておきます。
2006/07/19
コメント(0)
-
夏はもうすぐ
夏の準備をいろいろと。 国語の読解講座をやることになりそう。 どんな形にするか、考えております。 正統的な方法と邪道な方法のさじ加減など。 あとは作文。 先輩にお願いしたので、どんなものを用意してくれるか楽しみだ。 以前おれが「税の作文の書き方はこんなかんじ」ってのを作ったんだが、 それに対して駄目出しをされたのである。「じゃあ今年はお願いします」「あぁ」 ということだったので、お手並み拝見と参ります。 まさかまた「忘れた」とか言うことは、ないよなぁ。 音沙汰ないのがちと不安だが。「負けない」「逃げない」という言葉のとおり、負けずに逃げずに有言実行して欲しい。【今日の小ネタ】●涼しげな壁紙よこせ●熱帯夜に快眠する7つの方法●扇風機をつけたまま寝ると?●関東大地震写真●盲目の女の子と付き合うことになった●痴漢男●松本人志が写真週刊誌を訴えた「本当の理由」●【現代科学でも】これ聞いてみて。マジありえない【解明不可能】
2006/07/18
コメント(1)
-
目標の設定について
大学では哲学を学んだ。 アメリカのプラグマティズムと、中国の陽明学というのを学んだ。ともに実践をむねとする哲学で、机上の考えよりも実際の行動を重んじる考え方だ。 プラグマティズムの創始者チャールズ・サンダース・パースの言葉によると、「ある思想の意味をはっきりつかむには、その思想が真であるとすればどんな実際的結果が必然的に起こるか、と考えてみればよい」 プラグマティズムの根底にあるのはこういった考え方だ。イギリスの経験主義、アメリカの実証主義を発展させた考えとして、プラグマティズムは存在する。 言葉は、口からセリフとして出ただけで完成するものではなく、その結果どんな行動に結びつくか、どんな影響を及ぼすか、そこまでを含んだものがその言葉の意味であるとする考えだ。 またアレグザンダー・ベインズにはこんな言葉もある。「信念とは、ある人がそれにのっとって行動する用意のある考えである」 つまり、実現不可能な理想をいくら述べても、それは現実の生活とは無縁のものであり、本当にひとが生きる上での信念とはならない。言葉は実現性のある予定であるべきで、またその言葉が実際に行動されたときにはじめて意味が生まれるとする考えである。 ぼくは何かというと「具体的にはどういうこと?」とか言って周囲から煙たがられているけれど、それはつまりこういうことだ。ぼくにとっては「おれはぜったいに逃げない」とか「日本一になる」とかいった実効性のうすい言葉は馴染みのないもので、不特定な状況や対象しか見ない言葉に意味があるのかと思ってしまう。 生活の中のどの状況で、誰に対して、どのように行動するのかという裏付けのない言葉は言うだけ自由で、言うだけ勝手だ。しかしその言葉が実現されることがないのだったら、何の意味があるだろう。ましてや、その言葉が実現する手段のないことだったら、何の価値があるだろう。さらには、その言葉が言っている本人も信じていないようなうわべだけのものだったら、何の意義があるだろう。 綺麗事であってもいい。ただしぼくは綺麗事を信じている。自分が信じることのできることなら、ぼくは言うことができる。信じてもいないのなら、綺麗事ですら言べきではない。「今週は二次方程式の教え方を研究して、生徒に伝えるべきことを整理する」 これくらいなら実感が持てるが、「いつか必ず日本一の塾講師になる」 この目標では漠然としすぎていて、努力目標としてふさわしくない。第一、何をどう努力していいのかすらわからない。 受験をひかえた生徒たちも、目標を立てるときは具体的なものでなくてはならない。「とにかくがんばる」「かならず勝つ」「絶対に諦めない」そんな曖昧なものではなく、具体的なものにするべきだ。ならなら、抽象的な目標では、その目標を達成したかどうかを見ることができないので、「おれはがんばった」とか自己満足に終わる可能性が高いからだ。「一日十個単語を覚える」「今週中に江戸時代の年表を覚える」「この問題をやる」「三ページ進む」といった、具体的な行動に密着した目標を設定して、それを実現することに精力を傾けるべきだ。 目標として設定することの条件を具体的にいうと、1.終えるまでの期日が定まっている2.するべきことが現実に手元に存在する3.するべきことが自分に実行可能なことである4.それが実行できたかどうか、客観的に判断することができる と、これくらいしっかりしていれば、目標として機能するだろうと思う。 言葉は実現されるためにあって、それにのっとって行動したときはじめて意味が生まれる。 ぼくはそう思っている。
2006/07/12
コメント(0)
-
一度は行きたい世界遺産
一生に一度は行きたい世界遺産ベスト10! - [世界遺産]All About 第1位は! ぼくも全面的に同意! ぼくの机の横にも、写真が貼ってあります。 自然の美、人間の技、地球でもっとも神秘的な場所ではないでしょうか。 写真を見ただけで、「すごい!」と思える場所。 さぁ、どこだと思いますか?
2006/06/29
コメント(0)
-

ジゴロウソング
誰がアップしたか知らないけど、you tubeにsakusakuの「みんなでうたおうZ」のジゴロウソングがアップされてた。 ひさしぶりに「藤沢のうた」とか「国分寺のうた」とか聞いちまったよ。 ブンジ! ブンジ! コクブンジ! hey! はじめにのってる「武田信玄のうた」をきいて、気に入ったらほかのもきいてみてください。おもしろまにあっくす 武田信玄のうた とか
2006/06/29
コメント(0)
-
15年前の基本方針
はいはいどーも。 私の部屋には段ボールに入って「過去原稿」と名付けられた大量の原稿用紙が存在するのですが、それはそれは見るも恥ずかしいような代物なんでございますよ。 今日はその中から、「基本方針」と題した文章をご紹介。 高校生の私が、かくあるべきと思った考えを記した一文ですよ。1.面白がる精神。どんなにつまらなく、くだらなく思えるものでも、まずは面白いと信じて接する。そしてそのまま面白いのだと思い込んで、とにかく楽しむことを心がけるものには何かしら取得というものあるので、おこを面白がり、他は見ない。2.怒っても腹が減るだけ。人の怒る感情は我も気分悪く、彼もむかつく。なるたけ怒りの気持つな。許せないことがあっても、三日待つ。それでも怒りおさまらなければ、三週をさらに待て。なお怒り残るならば、三ヶ月を。三ヶ月継続したなら、その怒りに真価ある。闊歩して捩じ込み、彼に怒りをもって理非を問うのがいい。3.パースペクティブの考え。いくらかの知識を持っても、自分こそは主観のカタマリだ。自分のものの味方は極私的であり、独断を含む。意志によって、他のものの味方をとりいれ、より普遍的なパースペクティブに向かう。しかしいくらがんばっても最終的なところに到達するということはない。4.道を曲がるまでは直進する。しばらくの後に右に曲がる道があっても、ゆるやかなカーブは描かない。曲がり角まで直進し、曲がり角にてカカトを鳴らして90度ターンすべし。昨日には赤くなる今日の自分を、明日また赤くなるようなことでも、どうせ赤くなるのだと言って力を抜くのではなく、明日の反省点を増やすためにも、今日は力のかぎり猛進する。 o(-_-;*) ウゥム… おれって高校の頃から成長してないのね。 この文章で現在の自分もほとんど表現できてしまっている。 まぁそれもいいか。
2006/06/28
コメント(0)
-
一番わるいのはジーコではなく、
昨日は後半すぐで柳沢がシュートはずしたところで見るのやめてしまいました。 あれは入れて欲しかった。 そんな柳沢がだめだとか、小笠原はこけすぎとか、 中村はきしょいとか、そんなことは他の人が書くと思うので、 私はちがうことを書きます。 予選リーグは三試合。 日本代表はそのうち二試合が午後三時からの試合でした。 今回のワールドカップは、だいたい三時、六時、九時の三回試合が組まれます。 この時期のドイツは夏を迎えて気温は30℃を超え、かなりの暑さになります。 試合の時間が早いほど暑さにやられてしまうことになるので、夜の試合に当たりたいと思うのが当然だろう。暑いとミスが増える。技術で勝負したい日本にとって、できれば昼の試合は避けたいところ。 でもって、日本が入ったF組の試合日程を見てみると、6月12日(月) 15:00 オーストラリア - 日本 6月13日(火) 21:00 ブラジル - クロアチア 6月18日(日) 15:00 日本 - クロアチア 6月18日(日) 18:00 ブラジル - オーストラリア 6月22日(木) 21:00 日本 - ブラジル 6月22日(木) 21:00 クロアチア - オーストラリア 日本の試合以外で午後三時の試合ないじゃん。 ほかのチームみんな涼しい時間帯に試合してんじゃん。 日本だけ暑い昼間の試合じゃなくて、夜にできなかったのか。 なんとかならなかったのか。 なんつー声もあるかもしれませんが、なんとかならないわけがない。 なんとかなっちゃった結果、こんなひどい日程になったんでしょう。 ワールドカップといえば権威ある大会ですので、対戦相手をカネで買うこともできないし、審判をカネで買うこともできないでしょう(たぶん) でも、試合時間をカネで買うことはできる。 そう思ったバカが、カネでなんとかしちゃったんでしょう。 日本とドイツの時差は7時間。 午後3時開始なら、日本時間は午後10時。 午後6時開始なら、日本時間は翌日の午前1時。 午後9時開始なら、日本時間は翌日の午前4時。「せっかくのワールドカップなのに、朝の4時なんて困るよ。 それじゃ視聴率とれない、誰も見ないだろそんな早朝」 つーことで今回のワールドカップ、一番悪いのはジーコではなく、 中村でも柳沢でも玉田でもキング加地でなく、 電通のバカ社員だということだ。追記 : ジーコ監督のコメントとして、BBSのサイトの中に"It's a crime that we had to play in this heat again," というものを見かけました。 犯罪ということばをつかってまでジーコが訴えたかったものが、たしかにあるのだろうと思います。http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/world_cup_2006/teams/japan/5044540.stm
2006/06/19
コメント(0)
-

カズを知ってるかい
昨日カズのことをちょっと書いたら、もっと書けと言われた。 カズについて、すごいと思うのはその純粋な情熱だ。「十年後は、どうしていると思いますか?」 と記者にきかれ、「十年後……、48かぁ、わかんないなぁ」 と苦笑いしつつ、「現役でいられたら一番いいけどねぇ」 と言ってのける強さ。 キング、というニックネームで呼ばれるカズが尊敬をあつめるのは、そのバカバカしいまでの強い思いからなのだろうと思う。 人は多く、夢を持つ。 人はときに、自分の限界を思ってしまう。 人はえてして、思いをあきらめてしまう。 そして人は、夢を持ちつづける男にまぶしさを見るのだ。 48才だったら、指導者としての自分をイメージしてもおかしくはない。 選手として泥にまみれ、かつてのイメージ通りには動かない体をひきずって、かつての栄光をひきずりながらもがきつづけるよりは、その場所から撤退して、次の場所で勝負することを選ぶのがほとんどだろう。 もちろん、現役選手として活躍できたら、それにまさることはない。 背広よりはユニホームを着ていたいに決まっている。 ユニホームを着るのなら、ベンチから指示をするのではなく、フィールドで走っていたいと思うのがサッカー選手だろう。 しかし、その夢を許される時間は短い。 サッカー選手で、しかもフォワードという位置にあっては、三十代の半ばでユニホームを脱ぐ選手が多い。カズが今居る横浜FCの監督も、かつてカズと一緒にプレイした高木琢也だ。高木はカズの後輩になる。 いつまでも、プレイしていたい。 いつまでも、フィールドに立っていたい。 そう思うことを許された、思い続けるだけの意志を与えられ、その力をかちとった存在が、三浦知良という選手なのだろう。 とはいっても、おれはカズのこともサッカーのこともたいして知りはしないので、ネットで流れているカズの伝説を紹介しようと思う。
2006/06/16
コメント(1)
-
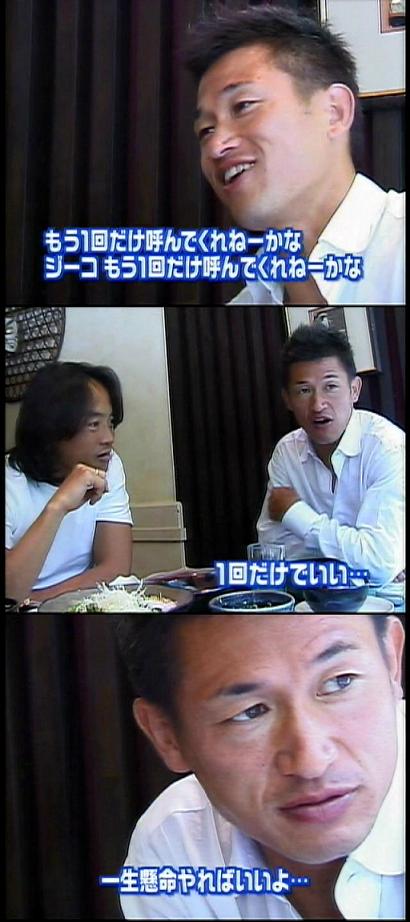
カズ伝説
昨日カズのことをちょっと書いたら、もっと書けと言われた。 でもおれはカズのこともサッカーのこともたいして知りはしないので、ネットで流れているカズの伝説を紹介しようと思う。◆カズのボール ブラジルのサッカー選手を夢見る孤児たちを育てる団体に、カズがサッカーボールを送ったことがあった。それも、200個ものボールを。子供たちは、とても喜んだ。 しばらくして、やはりJリーグが同団体にボールを寄付することになった。エージェントが現地へ赴き、少年たちにボールを渡す。少年たちはやはり喜んだが、渡されたアディダスのボールを見て「アディダスではなくて、メーカーは『カズ』が良かった。」「『カズ』のボールはとても使いやすかった」と口々に言う。 Jリーグのエージェントは首をひねった。カズ?そんなメーカーがあっただろうか。「これだ」と、手渡されたボロボロのボールを見てエージェントは驚いた。すでにかすれてしまっているものの、ボールにははっきりとサインペンで「夢をあきらめるな カズ」 と、現地の言葉で記した跡があった。200個ものボール全てにカズは自筆のメッセージとサインを入れ、それを子供たちは「カズ」というメーカーのボールであると思い込んでいたのだ。◆もんじゃ屋 キングカズは神だと思っている。 7年ほど前の正月休みに両親と静岡市のカズ実家(もんじゃ焼き屋)に 食べに行った時の話。 両親と3人で鉄板を囲んで食事をしているといきなりキングカズが玄関から入ってきた。もんじゃ焼き屋に似合わないイタリアンないでたちで。 カズが「俺いつもの~」と言って二階へ上がろうとすると、 店内にいた高校生集団が「カズさん!」「カズさんかっけー!」などと騒ぎ出し、カズが戻ってきてくれて即席サイン会になった。 店内に13、4人ほど居合わせた客全員に店内にあった色紙を使い サインをしてくれた。 高校生達がカズの母校静岡学園のサッカー部だとわかったカズは いい笑顔で会話を交わしていた。 そしてカズは「またな~」と二階に上がっていき、店内は静かになった。 私と両親はカズの気さくさとかっこよさに興奮しつつ食事を終え、会計を済ませようとレジに向かうと、店員さんが階段の上を指差しながら 「今日のお客さんの分は出してくれましたから。また来てくださいね」と。 あれには本当にびっくりした。 ◆大黒「カズさんは生きている!」昨夜コンフェデ杯ブラジル戦でゴールを決めた大黒は胸を張った。「僕の後ろにはいつもカズさんがいてクロいけー!ここでシュートだ!ってアドバイスしてくれるんだ…ほらね?」と大黒はユニフォームをぬいで中に着込んだTシャツの背中を見せてくれた。そこには汗でにじんだカズのサインがあった。「これはカズさんがキングって呼ばれていた時に貰ったサインなんだ…いや、僕の中ではいつまでもカズさんがキングなんだけどね…」◆サインその1 カズが、読売ヴェルディ時代に、甥っ子連れてサッカー場行った時の事。 カズは当時、絶大な人気だった(その試合では2得点ゴール)。 あれだけ人気なんだからきっと天狗になって調子こんだヤローなんだろうな。と思っていた。 試合が終わり、甥っ子が、どうしてもカズのサイン欲しいと、言うこと聞かず、 近くに居たヴェルディファンに「どうしたらもらえますか?」と聞いたらチームバスで来ていたら、 それに乗り込む時にもらえるかもしれませんよと教えてもらい、そこに連れて行ってもらった。 するとカズが現れた。前の方にいた甥っ子と自分は、周りの黄色い声に、圧倒されてたじろいでいた。 そして甥っ子は、怖くなって色紙とサインペンを持ちながら泣いていた。 そしてカズが、前を通り過ぎようとしていた。 勇気を振り絞って甥っ子が、色紙とサインペンを一生懸命差し出すも、 近くに居た、 ギャルっぽい女の子が甥っ子を押しのけて、サインをもらおうとしたその時、 「小さい子供いるのが見えないのか?」 と女の子に言い放ち自分の甥っ子の頭をなでて、 満面の笑顔で「大きいサインあげるから泣かないで」と、色紙いっぱいにサインしてくれた。 そしてさっきの女の子がサインもらおうと、カズに差し出すも、 カズは無視。 バスに乗り込んでいったまさにKINGこそ漢。私は、それ以来熱狂的なカズ崇拝者です。 その後甥っ子は中学生になり、サッカー部に入部 。背番号11FWとして、活躍している。 ◆サインその2 俺が小学生の頃、どうしても武田のサインが欲しくて、等々力競技場で色紙とマジックを持って、選手の出待ちをしていた。武田が出てきて俺は「武田選手サインおねがいします」と叫んだがササッと車に乗ってしまった。 がっくりしてると、カズが俺に「僕のサインでもいいかな?」とニッコリしながら声をかけてくれた。俺はびっくりしたが「もちろんです、お願いします!」と言うとスラスラとサインをしてくれた。その後「これからも武田選手とヴェルディの応援よろしくね」と声をかけてくれた。 あのカズの笑顔は、今でも忘れられない。◆サインその3 俺は代表合宿に参加するモリシとアキを激励しようと、選手達の到着を待ちわびていたんだ。 そうこうするうちに選手達を乗せたバスが駐車場に到着して、選手達がグラウンドへ向けて歩いてきたんだ。 そうこうするうちに、黒崎や前川なんかの今となっては地味な選手達(ファンの人、ゴメンねw)に混じって、 明らかにオーラが出てる選手が二人、こっちへ歩いてきたんだ。 それがカズと前園だった。二人で並んで歩いて来た。仲良かったんだろうな。 俺、ミーハーみたいに凄ぇって思ったよw 俺は目の前まで歩いて来たカズと前園に 「サイン頂けますか?」と訊ねたんだ。 するとカズはにっこり微笑んで 「もちろん」 と答えてくれた。 そうしたら前園は俺を無視してスタスタ歩いて行こうとしたんだ。 そうしたら今までニコニコ微笑んでいたカズが急に険しい顔になって「おい!ゾノ!!」 って前園を呼び止めたんだ。 びっくりして振り返る前園にカズは 「おめぇ、プロだろ?」 って語りかけたんだ。 そうしたら、前園、こっちへ戻ってきてサインしてくれたよ。 そん時のカズ、おしっこちびるくらい格好良かったよ。◆エンジン停止 去年の暮れぐらいなんだけど、郊外で車故障して、立ち往生してたんだよ。 俺、全然車とか詳しくないんで、ボンネット開けて中見ててもなにが悪いのかさっぱり意味不明 。 で、あたりも暗くなってきてたし車通りも全然ないところでヤベー、とか思ってたら 俺の車 の後ろに一台の車が停車した。 その車から降りてきた男を見て、俺は息を飲んだ。 それは見間違うはずも無い、日本代表の、あのカズ選手だった。「なぜこんな田舎にベージュの スーツで!?」と思うまもなく、カズは 「どうしたの~?」ときさくに俺に声をかけつつ上着を脱ぐと、ボンネットをのぞきこみ、 そし て、いろいろエンジンのまわりをごそごそやりだした。 高そうな白いシャツの袖が、どんどん汚れていく・・・ 結果、俺の車は見事エンジンスタ ートに成功。 カズは「車は普段から可愛がってやらないと、すぐ壊れるよ。じゃあな!」 と言うと、颯爽と自分の車に乗り込み去っていった。 そしてついに今日、カズが日本代表から外れた。それでも俺は一生、あの日のカズを忘れない。 ◆同じ数だけ カズは里帰りするたびに、実家の近所の老夫婦がやっ てる紳士服店でスーツを仕立ててるらしい。 どんなイタリア製のスーツよりもいい着心地だとか。 子供のころよく、老夫婦に飴玉をもらっていたカズいわく、「もらった飴玉と同じだけの数、同じだけの色のスーツを仕立てるつもり。俺がサッカーを続ける限りね。」 ◆ファンレターその1 昔弟とファンレター書いたとき、弟には「夢諦めずにサッカー選手になれ」って返事がきた。 ああみんな同じようなこと書いてんだろな、って思ったら、俺のには「好きな子にアタックしろよ、ウジウジしても何も始まらないぞ」って書いてあった。 ちゃんとファンレター読んでくれてたんだって嬉しかった。◆ファンレターその2 今から6年前、僕が国体の強化選手に選ばれていて、もちろん将来はプロサッカー選手にと思っていた時、練習中に大腿骨窩と大転子の骨折によりもうサッカーは将来できないと医師に言われ落ち込んでいた。 2~3ヶ月後に手紙がきた。カズさんからだった。部活の顧問がたのんだらしい。「君はサッカーができなくなってしまったけど、プレーする事だけがサッカーじゃないんだよ。応援する事はフィールドに立っていると同じ事なんだ。サッカーは選手と応援があってサッカーと言えるんだ。サッカーを嫌いにならないでほしい、そして愛してほしい。 三浦知良」◆カルチョの国で 94年9月4日ミラノのサン・シーロ・スタジアムでのセリエA開幕戦。相手は3連覇を成し遂げ、4連覇を目指す王者ACミラン。カズのイタリアデビューである。しかし、それが一瞬にして悪夢に変わるとは誰も予想していなかった。前半28分、セリエAを代表するDFのバレージと激しく接触。前半は気合で乗り切ろうとするが、もはや目も腫れて塞がっていて満足に物が見えてない状態だった。 前半終了後すぐに近くの病院へと足を運んだ。鼻骨骨折…全治2ヶ月…。恰幅のいいイタリア人の医者は笑顔でこう言った。「いいかい、ジャポネーゼ…。君の長いサッカー人生を考えれば、これはちょっとの休息だと思えばいいんだよ。」カズは医者の顔をまっすぐに見据えながら、流暢なイタリア語で答えた。 先生の言いたいことはすごくわかるよ。僕もこれまでもっと厳しいケガを克服してきた。でもね、僕には時間がないんだ。僕はここでは招かざるゲストなんだ。みんな周りは色眼鏡で僕を見ている。なんだ、こいつは?ってな具合でね。試合中や練習中に僕にボールが回ってこないこともある。でも、それは僕にとって些細なことなんだよ。僕は自分にボールが転がってきたら、それを決めるだけの自信があるからね。でも、僕が我慢できないのは、日本人がサッカーできないと思われることなんだ。僕は証明したい。僕の力だけじゃなくて、日本人の力を証明したい。結果を出す時間は10ヶ月しかない。その中の1ヶ月を失うというのはあまりにも大きいんだ。先生、別に鼻なんかなくてもいいんだ、目さえ見えればいいんだ僕がすぐにプレーできるって診断書書いてくれないかな…。 カズはそこまで言ってから下を向いた。恰幅のいいイタリア人の医者はこれほどまでの熱意を目の当たりにして言葉を失っていた。 そして、翌日チームに届けられた診断書には全治3週間と書かれていた。カズは今でもちょくちょくその病院の先生に挨拶に行くという。 ◆誰かを貶めるのではなく カズはJリーグ開幕の頃、バカなマスコミが「野球は時代遅れ」と言ってた頃、「僕は野球好きですよ。」とテレビカメラの前でヴェルディの選手達とキャッチボールしてた。 ◆もう1回だけ、1回だけでいい…。「よく励ましの言葉とかエールとかっていわれるんですけど、僕の方が皆さんの言葉や励ましから、勇気を貰ったりしているんです。僕からのエールと言うよりも本当にみんなと頑張っていきたいなとおもっているんですけどね。 同世代の人も含めてみんな頑張って目標に向かって進んで行きましょうってことですかね。」 「練習も含めて試合全てが、一つ一つに想いを込められる。やっぱりこれは年齢でしょうね…。もう確実に先は短くなってきている…。昔も絶対に一つ一つに対して、プライドを持ってきてやってきたつもりなんですけど、今の思い入れとは全然…サッカーを愛する気持ちは全然変わりました。」「ジーコもう1回だけ呼んでくれないかな…1回だけでいい… 一生懸命やればいいよ…。」
2006/06/15
コメント(2)
-
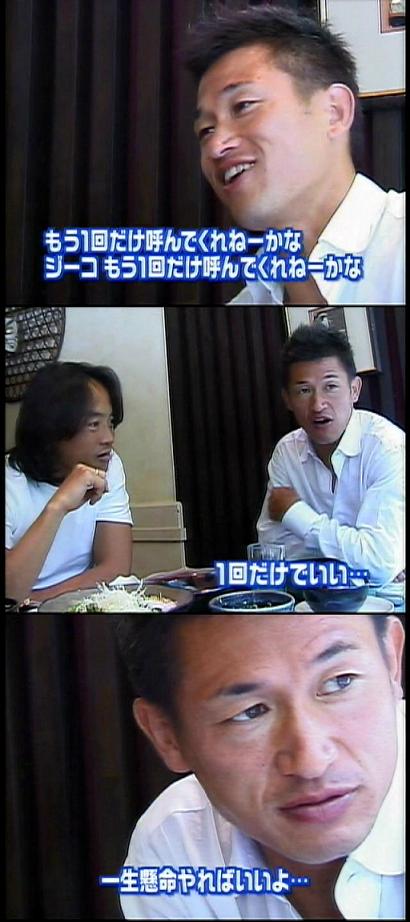
カズを出せ
ワールドカップで、ゴール前で横パスしちゃうようなFWを並べてしょんぼりするくらいなら、今こそカズを招聘しろ。 苦境を救えるのは、ヒーローしかないだろう。 YouTube - KING KAZU STORY そして、4年後はぜひとも、 YouTube - Fantasista DAISUKE MATSUI
2006/06/14
コメント(0)
-

こうの史代「夕凪の街桜の国」
こうの史代「夕凪の街桜の国」昭和30年、灼熱の閃光が放たれた時から10年。ヒロシマを舞台に、一人の女性の小さな魂が大きく揺れる。最もか弱き者たちにとって、戦争とは何だったのか……、原爆とは何だったのか……。漫画アクション掲載時に大反響を呼んだ気鋭、こうの史代が描く渾身の問題作。 おすすめです。 絶対のおすすめ。「お前読んでる本いつもいつもおすすめしてんじゃないかよ」、と言われましたが、バカいってんじゃないぜ松本裕。 おすすめの陰には何十冊のダメ本があるのです。 と言ったら、「でもお前マンガばっかり読んでるのか?」と言われました。 そういうわけではないんだが、マンガの方に名作が多いんだから、仕方ない。 活字のものもおすすめしたいと思っているんだけど、こっちの方はヒットに巡り会わないのです。 さて、「夕凪の街 桜の国」 これは一生モンの作品ではないかと思う。 戦争もの、原爆ものというと声高に反対を叫んだり、感情的に悲惨を訴えたり、グロな描写で肝を抜いたり、ドロドロした怒りを叫んだり、読むと精神的につらくなり、疲れてしまうものがほとんどであり(それは性質上当然なのですが)、この作品はそういったものとは違っている。 この人は、うまいのです。 たいした物語の展開があるわけでもなく、ショッキングなシーンがあるわけでもなく、オチもクスグリもなく、100ページで800円はへたな同人誌より高いのです。 それでも、いっぺん読んだあともう一回読もうと思った。さらに、何度も読もうと思った。それは、この作品が表現としてすぐれているからだ。 マンガという表現ならではのすばらしさがある。 人物の目線でや、空白、コマ割り、線の強弱など、マンガの持っている武器を存分につかって表現している。絵もうまいけど、それ以上にマンガのうまい人だと思った。 マンガでしかできないやり方で、悲惨になりすぎることなくユーモラスに物語は描かれている。 伝えたいことは、ことばにはできないようなことで、ことばにしてしまったら逃げていってしまうような、あやういものだ。 それを、静かに、あくまでも静かに語る。 読んでのち、グラグラ沸騰する激しい怒りではなく、沈殿物のように自分の心の底に怒りが存在することに気付く。 いや、怒りではないな。 しょぼーんとした感情。 しょんぼり悲しくて、 悲しいんだけど、心があたたまって、 灯りがともるような物語。 本の帯には、こう書いてあった。「読後、まだ名前のついていない感情が、あなたの心の深い所を突き刺します。」 泣くために読む本ではない、考えるために読む本だと思った。 戦争について、広島について、人生について、幸福について。 考えて、生きるための本なのだろう。 ゼヒ。 嬉しい?原爆を落とした人はわたしを見て「やった!またひとり殺した」ってちゃんと思うてくれとる?ひどいなぁ…わたしは死なずに済んだ人やと思ってたのに 第8回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞、第9回手塚治虫文化賞新生賞を受賞する。その他にも、朝日新聞で2週にわたって絶賛され、月刊誌ダ・ヴィンチで編集者総出で勧める「絶対はずさないプラチナ本」として掲載、フリースタイル刊「このマンガを読め!2005」で第3位になるなど、各方面から絶賛され、著者にとって最大のヒット作となっている。海外でも高い評価を得ており、韓国で翻訳版が出版され、米国、ドイツ、フランス、台湾でも出版が検討されている。映画化の予定あり。夕凪の街は、1955年(昭和30年)の広島市の基町にあった原爆スラム("夕凪の街")を舞台にして、被爆して生き延びた女性の10年後の心の移ろう姿を描く。桜の国は、第一部と第二部に分かれている。主人公は被爆二世の女性。第一部は1987年(昭和62年)の春、舞台は東京都中野区および当時の田無市。第二部は2004年(平成16年)の夏、舞台は西東京市および広島市など。夕凪の街、桜の国の第一部と第二部、すべて合わせても120ページ弱しかないこの三つの話を順序通りに読み通して、初めて三世代にわたる家族の物語がつながるという巧みな構成になっている。両作とも、主人公に思い出したくない記憶があり、それがふとしたきっかけで蘇ることも、その記憶の内容は違うとはいえ、後々まで後遺症の残る原爆の恐ろしさと悲しさを伝えてくれる。とはいえ、単行本の表紙の絵の通り、絵のタッチは生々しくはなくむしろ穏やかである(原爆当日の描写はわずか数ページしかない)。何気ない生活の描写に、他の作品にも共通するこうの史代の最大の魅力がある。(夕凪の街 桜の国 - Wikipedia)
2006/06/09
コメント(0)
-

フジが「PRIDE」中継の契約を解除
フジが「PRIDE」中継の契約を解除 フジテレビは5日、ドリームステージエンターテインメント(DSE)との契約を解除したと発表した。同局で中継されるPRIDEやPRIDE武士道の放送がなくなることになり、予定されていた10日の「PRIDE武士道-其の十一-」と、18日の「ハッスル・エイド」の放送も中止する。 フジテレビ広報部は「契約違反が判明したので本日(5日)をもって契約を解除した」としている。一方、DSEは「現在、状況を確認中でコメントできない」とした。 [ スポーツナビ 2006年6月5日 21:37 ] フジテレビの放映がなくなったら、放映権料が欲しいだけのDSEはPRIDEなんか速攻で閉じるだろうし、格闘技界の市場は縮小するだろうね。 かといって、格闘技に流れたファンがプロレスに戻ってくることもないだろうし、いいことなんて何もない。 この件について何か書けといわれたが、 おれはこの写真を紹介するだけにとどめておくよ。 今回のフジ撤退は暴力団がらみのことが直接の原因ではなく、TBSに対して武士道の放送を交渉して、フジとTBSを天秤にかけたのが原因だとのことです。 TBSに天秤かけた云々ってのは、無理矢理のこじつけみたいな感じがする。 それならK-1のMAX、JAPANでTBS、日テレとの関係なんかは何で問題ないのかと思ってしまうし。 まぁ、多くは語るまい。
2006/06/05
コメント(2)
-

柳沼行「ふたつのスピカ」
西暦2010年、日本初の有人宇宙探査ロケット「獅子号」が市街地に墜落し、主人公アスミの母を含め多くの人がその事故の巻き添えで後遺症に苦しんだり死亡するという大惨事となった。そんなある日、事故で母親を失った幼いアスミは、墜落したロケット獅子号のパイロットの幽霊「ライオンさん」と出会う。アスミはロケットの運転手になる夢を抱き、その目標に向かって物語が動き始める。 ひさしぶりに、いい作品に出会いました。 とにかくまっすぐで、くもりがない。 夢とか、ロマンとか、そんなことを疲れることも疑うことも知らない少年のように語れるなんて、この作家はどんな人なんだろう。 絵が優しくて、まるで子どもの頃にチラシの裏に書きためたマンガを読んだみたいに、懐かしい気持ちになる。 登場人物たちのセリフが切なくて、会えなくなってしまった友人と再会したみたいに、くすぐったい気持ちになる。 単行本には連載する前に読み切りで描かれていた話も載っていて、それがいい。いいのよ。 宇宙飛行士になるお話なので、訓練の場面とかもあるんだが、そういった要素は物語をまわすためではなく主人公の性格を語るための、主人公の夢を乗せるための道具としてしか描かれない。苦労したり努力したり、友情とか淡い恋とか、マンガを構成するそんな要素はこの作品では主人公の意志を描くための舞台に過ぎない。「ロケットの運転手になるんだ」という夢が、既定の事実としてあり、それだけに向けて走っていく主人公。 ゆるぎなくて、まっすぐで、力強い。 じんわりしたかったら、ぜひ読んでください。 人はけっしてひとりじゃないと教えてくれる。 生きるってのは目的のためじゃなくて夢のためなんだと教えてくれる。 空は、星は、いつまでもそこにあるのだと教えてくれる。 抜群です。 私の一番好きな漫画家でありますよしもとよしともさんが「オモロすぎ。泣いた泣いた」と言っていたそうです。小3の娘さんもハマって「父ちゃんあたし宇宙飛行士になるよ」と言っていたそうです。 よしもとよしともが手放しでほめるなんてあんまりないんではないだろうか。
2006/06/03
コメント(0)
-
ナイトスクープを知ってるかい?
たとえば、日曜日に友人と電話ではなしていて、こんな会話をしたのですよ。園本「あ、もうすぐ笑点始まる、あれ何チャンネルやったっけ?」おれ「笑点は10チャンネルやろ」 笑点は10チャンネルですよ。 筑紫哲也ニュース23は4チャンで、報道ステーションは6チャンで、きょうの出来事は10チャンだ。ニュースジャパンは8チャンです。 関東の人は思いもしないことだろうが、関東と関西はチャンネルがちがうの。 以上、ちょっとした豆知識。 で、6チャンネルの朝日放送(関東地方ならテレビ朝日は10だけど)の看板番組といえば「探偵ナイトスクープ」 もう18年くらいやってる人気番組です。ちょっと前までテレビ朝日でも放送していたけど、今はやっていません。ちばテレビならやってます。ぼくが高校生のときから見てる番組で、視聴者から寄せられた数々のくだらない依頼を石田靖や桂小枝、北野誠、間寛平といった探偵たちが依頼のくだらなさに輪をかけて難問を解決したりしなかったり苦労する番組なのです。 この番組の企画を紹介しているサイトを見つけたので、ご紹介。 おもろいので、ぜひ見てね。 数々のアホ企画をまとめたサイト●おもしろまにあっくす ナイトスクープ・アホ企画特集 名作の呼び声高い企画●タケモトピアノCMの謎 その他の動画はこちらから●YouTubeで「ナイトスクープ」と検索 恐るべしナイトスクープ。
2006/05/31
コメント(0)
-
亀田興毅の世界戦
>∩( ・ω・)∩ ばんぢゃーい 亀田興毅の世界戦が決まったよ。 なんてこった。一部で噂されていた最低のシナリオが、本当に実行されるみたいだね。 何が最低なのかって、今まで繰り広げられてきた亀田リサイタルが世界戦の舞台でも続行されるらしいってこと。 ほとんど引退してる選手を引っ張り出してきたり、対戦相手が試合が発表になる数日前にいきなり世界ランクにランク入りしてたり、そんなアメージングな亀田ワールドが今度も炸裂ってことだ。 それも今までは、「まぁそのうちイタイ目にあうだろ、それまで楽しんどけや」と思ってガマンしてたんだが、どうやらイタイ目にはあわせない方針らしい。かつて、これほどまでに負けるかも知れない試合をしてこなかったタイトルコンテンダーがいたか。これほどまでに緊張感のない世界前哨戦があったか。 しかし、どんなに弱い相手選んでやってても、世界戦になったらチャンピオンとやるしかないんだから、そこで叩きのめされてくれ、と思っていたのだよ、おれは。そしておそらくは多くの善良なボクシングファンもそう思っていたはずだ。 それが、亀田親父と金平会長は、そんな我々の思いを華麗にかっとばすチカラワザで、世界戦の舞台をつくってきた。 日刊スポーツの記事によると、>亀田興毅が8・2ランダエタと王座決定戦 WBA世界ライトフライ級2位の亀田興毅(19=協栄)が、8月2日に横浜アリーナで同級1位ファン・ランダエタ(27=ベネズエラ)との同王座決定戦で世界王座を狙うことが24日、内定した。既に協栄ジムが試合中継するTBS側と放送枠の最終調整に入っており、来週にも発表される見通しだ。20日に3度目の防衛に成功した同級王者ロベルト・バスケス(22=パナマ)陣営がフライ級転向による王座返上を表明。王座が空位となったため、WBAによる裁定でランキング1位ランダエタ、2位亀田による王座決定戦が決まった。 前WBA世界ミニマム級暫定王者ランダエタは、バスケスと同じサウスポー。04年10月にはWBA同級王者の新井田豊(横浜光)との王座統一戦に敗れた。以後も同級1位を維持していたが、今月からライトフライ級に転向していた。協栄ジムの金平会長は「近日中に何らかの発表をするつもり」と説明していた。< どうでしょうか。 これを読んで何の疑問も不思議も抱かずに、何もひっかかるものなしに、「('-'*)キャー 亀田兄弟サイコー」なんてのんきなことを言っているわけじゃあ、ないだろう? 亀田がそれまで11戦を戦ってきたフライ級からライトフライに階級を移したのは世界を獲る確率の高いところに移るという意味では正統な判断だが、それでもポンサクレックとのデビュー当時からの因縁はどうなるのかとか、かつて亀田が言ってた「ポンサクはライトフライの選手とやってるからな」とかいう発言は、自分がライトフライに階級落としたらかっこわるくないのかとか、いろいろつっこみたい。 そして、あまりにもタイミング良すぎじゃないですか。あからさまに。 金平会長は以前から「バスケスは王座を返上するらしいし」とか言ってたから、王者との試合よりも王座決定戦を選ぶっていう選択肢はありなんだけど、その対戦相手もライトフライの選手ではなくてミニマム級から上がってきたランダエタってのも、どうなんだこれ。それまでライトフライで一戦もしてない選手同士の王座決定戦です。 二人のそれまでの階級だったら、二階級下の選手との対戦ってことになるでしょ。もしかしたら、亀田の言ってる「3階級制覇や」ってのは、この一戦だけでもう3つとも達成するつもりなのか。「フライ級で敵おらんかったやろ、ライトフライ獲ったやろ、ミニマムのやつも倒したやろ。これで3階級制覇じゃ!」 とか、そんな素敵なストーリーなのか。 本当にこれはボクシングなのかいな。 なんかこう、すっきりしね~。
2006/05/29
コメント(1)
-
噂は実現するのか? 桜庭vsヒクソン
まだ噂の段階で何とも言えないのだが、それでも気になる噂なのだ。 その噂は日本のサイトではまだ出回っていなくて、海外の格闘技サイトで流れている。 ・ ヒクソン・グレイシー vs 桜庭和志 戦が現実味を帯びてきた?(ROCK'N'ROLL、格闘技、時事、E.R.Oその他)・ Rickson Gracie vs. Sakuraba In K-1 HERO's?(MMANEWS.COM)## いくつかのブラジルの情報筋、メディアによると、ヒクソン・グレイシーは日本の伝説的ファイターでグレイシー一族がいまだに乗り越えられない相手、桜庭和志選手との対戦を受け入れたとのこと。これは百万ドルより価値のあるオファーだ。 複数の情報筋は、桜庭がPRIDEからHERO'Sに移ったのは、このヒクソン戦が唯一の理由ではないが、魅力的な要素であり移籍につながったと話している。 本当なら、交渉は確実に完了はしていないし、これは団体側(FEG)が組みたい試合の1つでしかない。これが実現するかどうかは、まったく別の話である。しかしヒクソンは明らかに興味を示してきており、またいくつかの条件(少なくとも金額面では)に同意したとも噂されている。この噂が本当なら、実現への最も大きな障害は取り除かれたと言えよう。## こちらにも情報。・ 格闘技噂のカード(ヒクソン・ニュートン・エドワーズ)(GAME AND MMA)・ Rickson To Face Sakuraba For Three Million Dollars? (Complete Vale Tudo Access)##Complete Vale Tudo Accessから桜庭vsヒクソン戦の続報。噂の出所はグレイシー・ウマイタ所属でホイラーの弟子Mario Aieloで、ギャラはなんと300万米ドル近く・大晦日のダイナマイトか早ければ10月のHERO’Sで行われるそうです。##(カクトウログ: 桜庭和志vsヒクソン・グレイシー、高まる噂より) 誰もが驚いた桜庭のHERO'S移籍も、ヒクソン戦の実現という珠玉のニンジンをぶら下げられたのなら納得がいく。 これが本当に実現するのなら、桜庭のことを非難した者もその姿勢を改めなければならないのではないだろうか。このカードは、PRIDEに対する忠誠とか、高田に対する恩義とか、ファンに対する信義とか、桜庭の移籍について語られたそういったマイナスの声を昇華して、炎上気分にさせるカードなのだ。 ヒクソンは2000年5月26日、船木誠勝とコロシアム2000(東京ドーム)で闘って以来試合をしていない。しかし、その間もPRIDEやK-1のリングに上がるという噂は何度もあった。それはすべて噂で終わって(とはいえそのうちのいくつかはただの噂ではなかったのだろうと思うが)、現在のところ実戦からは6年ほど離れている状態。これが普通の選手であれば、6年のブランクは問題ともなるのだろうが、ヒクソンについてはやはり別格と見るべきだろう。試合がなくてもトレーニングは欠かしていないだろうし、桜庭の対策もホイラーが敗れたときからしているはずだ。 そしてひとつ、ぼくが思うことは、「ヒクソンが試合を受けることがあれば、それはヒクソン陣営が桜庭に100%勝てると判断したとき」 ということだ。ああ見えてどこの相場師よりも経営者よりも計算高いヒクソンさん、負ける戦はしない男である。あらゆる要素を分析して、「勝てる」と判断したカードしか受けない男だ。(だから無敗) この一戦、できれば5年前くらいに実現して欲しかったカードではある。だが、もし実現すればこれほどのビッグカードはふたつとない。作ろうと思っても作れないほどのストーリーを抱えて、ふくらまそうと思ってもふくらましようのないほどの幻想をふくらまして、見る側の心を扇情的に打ち鳴らす。 アコースティックなものになるのか、懐メロになるのか、どんな試合になるのかわからない。スイングするのか、ロックするのか、試合展開は幾通りにも予想される。 この試合は、PRIDEが追いかける「60億人の中の最強」というテーマともはずれているし、K-1・HERO’Sが作りたがっている「渋谷にいる若者が見たがる格闘技」とも違う。この試合にテーマを見つけようとすれば、どうしてもテーマは90年代の「打倒グレイシー」とか「UWF最後の戦い」とか、そんな懐古的なテーマを考えてしまう。それは、すでに過ぎ去ったテーマであり、今さら語るべきものではないのかもしれない。しかし、過ぎたことは過ぎたが、クリアーされたわけではないのだ。 やり残した宿題。しまいこんだ課題。解けなかった問題。 ラスボスを倒す手前でうち捨てられたRPG。 意志ではなく、雪崩によってかき消された物語。 打倒グレイシーも、UWFの行方も、途中のまま瓦解している。最後のピースを残して放置されたジグソーパズルのように、気持ちはぶらさがったままだ。それは消化不良のまま無理矢理のみこんだだけの話で、まだクリアーされたわけではないのだ。 この一戦は、ぜひとも実現して欲しいと思う。 ずっとひっかかっていた物語の結末を、見たいと思う。 しまい込んではいたが忘れてなどいなかった物語を、完結させて欲しい。 その物語とは、UFCの出現やパンクラス旗揚げ、第一回K-1グランプリなどのあった93年をから始まった日本の総合格闘技15年の歴史の分水嶺でもあるし、桜庭和志というプロレスラーの15年の到達点でもある。(桜庭は93年デビュー) この山を、登りたかったのだ。 横目にながめて諦めて、でもずっと登りたかった山。 夢が思い出にかわる前に、実際に踏みしめて欲しい。 それができるのは、桜庭しかいないのだから。 桜庭は、ぼくのアイドルだし、ヒーローだった。 桜庭と一緒に味わってみたい。桜庭に、連れて行って欲しい。 願わくは、ヒクソン試合受けろ。 そのために、谷川はカネ集めろ。 もう一度、爆発炎上させてくれ。 すべては、桜庭のもとに。 すべてを、桜庭のものに。 夢よ実現してくれ。
2006/05/25
コメント(0)
-

山田芳裕「へうげもの」
へうげもの 1 (1)作者: 山田芳裕 出版社/メーカー: 講談社 発売日: 2005/12/22 メディア: コミック ISBN:4063724875:detail信長、秀吉、家康、光秀、宗易(利休)・・・いろいろいるけど、主人公は!!古田左介だ。群雄割拠、下剋上の戦国時代。立身出世を目指しながら、茶の湯と物欲に魂を奪われた男がいた。織田信長の家臣・古田左介。天才・信長から壮大な世界性を、茶聖・千宗易(利休)から深遠な精神性を学び、「へうげもの」への道をひた走る。生か死か。武か数奇か。それが問題だ! 山田芳裕といえば、出世作の「デカスロン」や好事家に人気の「度胸星」などのダイナミックで強引な展開とデフォルメ効き過ぎの画風で知られる奇特な漫画家ですが、この人は初期には「考える侍」「大正野郎」といった『粋』をテーマにしたマンガもあり、売れセンではないのですがこちらのほうも魅力的なのですよ。 この「へうげもの」は、商業ベースにのることを考えながら初期の作風にも似た『粋』への追求がうかがえる、かなり期待をさせる作品ですよ。 戦国時代もので主人公が古田佐介(のちの古田織部)って段階ですでにものすごいんだが、それが地味な話にならずにスピードのある展開になってるのもすごい。 武人として生まれたからには、主君・織田信長のような大大名に、と思いつつも、ついつい「信長様が帝から譲り受けた香木」や「信長様がお召しの"びろうど"」「天下に知られた平蜘蛛の茶釜」といった「物」のほうに欲望が向いてしまう古田左介。名物に対する執着と数寄であることへの憧れが、山田芳裕のデデーンとした絵によっておもしろ切実に描かれています。 信長もなぜかピアスしてるし、鎧はあり得なさ過ぎるし、見開きページ多いし、本能寺の変の解釈も独特で斬新な描き方で、畏れ入る。 戦国ものなのに戦がメインではなくて、茶入や茶釜などの名器が主役。 これからのこの物語のテーマになってくることなんでしょうが、戦国時代ってのは国盗り合戦でワーワーやってたのはもちろんですが、その一方で日本の歴史上ほかにないくらいの、価値観の転換が行われた時期なのです。もっといえば、新しい価値観が生まれた時期。 今に通ずる「侘び・寂び」の文化というのはこの時代に生まれたもので、そのために千利休などは文字通り命をかけて戦っていた。 この「へうげもの」はそんな文化革命をなしとげた(なしとげようとしている)男たちを描いています。 前田慶次を描いた「花の慶次」が「傾奇者」という概念を知らしめたように、今度はこの作品が「数寄者」という在り方を再び世に出すのかもしれません。
2006/05/21
コメント(0)
-

野球盤と遊び
かつて、野球盤というゲームがあった。 野球場の形をした板で、家にいながらにして野球の試合ができるというスグレモノ。 ふと、この野球盤を見かけて、「懐かしいなぁ」と思ったのです。 バネではじかれたボールがびゅーっと出てきて、それをバットで打ち返す。ヒットとかアウトとか、あるいはホームランとか書かれたところにボールが入ったら、それに従ってランナーを進める。 ぼくくらいの年代なら、一度はやったことのあるポピュラーなものだと思います。 で、この野球盤に「消える魔球」という機能がついていました。 バットに向かって転がってくるボールを打とうと、「おりゃ!」 とバットを振ると、その目前で地面がべこっと開いて、ボールが下に消えてしまう。 当然地面に潜ったボールなんか打てるわけもなく、空振り三振。 ボールが地下に消えてしまうなんてのは、どう考えても無茶なシステムで、実際にそんなことがあったら「ふざけんな!」と抗議がおこると思うんだが、この消える魔球というものについて我々はたいして疑問に思うこともなく受け入れて、「消える魔球は一試合で三回までね」とか、「じゃあハンデに消える魔球使っていいよ」とか、 そんなルールを各自つくってゲームしていました。 ぼくが懐かしいと思ったのは、野球盤そのものではありません。 消える魔球についてでもない。 このルールのことを、懐かしいと思ったのです。 むかしのおもちゃというものは細かいルールや設定なんてものはなくて、遊ぶ側がさまざまに補足して遊んでいました。 実際、消える魔球があるからといって、ぜんぶ消える魔球にしてたらゲームにならないのです。 お互いに譲り合ったり、相手を思って、「ここはこうしておこう」「これはやっちゃだめだ」と自分で加減をして、遊びを成立させていた。 こういった、遊びに対する姿勢を、「懐かしい」と思ったのです。 いまは、ゲームといえばプレステやらDSやらになると思うのですが、そこにあるのは細かく設定されたストーリーと、次々と襲ってくる敵や謎。 プレイヤーは、用意されたものを順番にこなすだけで、自分から何かするということはない。 与えられたものを、与えられたようにこなすだけ。 遊びというものは、もっと自由で主体的なものだったのではないでしょうか。
2006/05/14
コメント(4)
-
桜庭和志がHERO'S移籍!
おい仰天だ。 びっくりしてしまったよおれは。 桜庭和志が、PRIDEからHERO'Sに移籍だ。 高田道場をやめたのはしってたけど、まさか戦場を移すとは。 これは前田日明のいう「PRIDE、K-1、UWFによる天下三分の計」のための一手なのか。 ↓ HERO'Sでの桜庭マスクのあいさつhttp://www.youtube.com/watch?v=ijsQ_1qLlI0 あと、昨日の山本KID徳郁の試合。「だましうちじゃん」とか「あれでいい気になってるようじゃ」とか「勝ったには勝ったけど内容がどうも」とか言っている意見を見かけたので言っておきますが、あれは素晴らしい勝利でした。 おれは基本的には山本KID徳郁は嫌いなんだが(対戦相手やドクターに暴行をするなどマナー悪いし、なおかつ反省の色もない)、試合は別。 4秒という短い時間の中にも、作戦とそれを実行する身体能力、勇気が見て取れる一撃だった。 飛びヒザ蹴りをしながら、右飛びヒザでフェイントかけて左跳びヒザでカウンターとるなんて、並の選手に出来る芸当じゃない。 すごいっすね。 http://www.youtube.com/watch?v=isIQJcsICQ8
2006/05/04
コメント(0)
-
カネヨシの「そんなにくえねえよ」
話すことが何もないときは、我が友人のカネヨシの話をしましょう。 私が知っている限りでは地上最高のバカ・カネヨシ(略してバカネヨシ) どのくらいバカかっていうと、プレステの何かのゲームで、中ボスを必死の思いで倒して、残りヒットポイント3とかのギリギリの戦いを制して、「あぶなかったぜ」とニヤついた次の瞬間開けた宝箱が毒で、それで死んでしまったくらいのバカです。 ある日のこと。 おれが高級中華料理をごちそうになって、その自慢話をカネヨシにしていると、「お前、すごかったぞ。おれはフカヒレとか初めて食った」「なんだそれ、しらねーよ」「フカのヒレなんだよ」「フカってなんだよ」 ヤツはものをしらない。「サカナだろ、たぶん」 おれも、そんなもん食いなれてないからよくわかっていないのである。「エイヒレみたいなもんか?」「そうだな、あれがでかいギョーザみたいになってんだ」「そうか、でかいのか。それはいいな」 でかいとかそういうところにしか反応しないバカネヨシ。「でもよお、よくわかんねえんだよなお前さんの話はよっ」「なんだよ」「わかりやすく、具体的にいえよ」「だって海老のボールみたいになってるのがうまかったとか、具体的に言いようがねえだろが」「どんくらいの大きさだよ?」「5センチくらいかな」「なんだよ、ちっちぇえな」 具体的に言えだの何だのと、カネヨシがうるさいので、おれは数字を告げた。「お前聞いて驚くなよ、会計してる時に見たらな」「おう、いくらだったよ」「四人で二万五千円くらいいってたぞ」「なに!」「ひとりあたり、六千円だぞコラ」「六千円……」 さすがのカネヨシも、絶句したのだった。 日頃、A定食とかサービスランチとかしか食べていないカネヨシにとって、六千円というのはまさに未知の世界。その高級さ加減にヤツもびびってたじろいでるんだろうと思ったおれに、ヤツは言った。「六千円って、そんなに食えねえよ、おれ……」「あ?」「だって六千円っていったら、それすげえ量だろ。テーブルにのりきらないくらいの……」 量じゃねえんだよ! バカ! ヤツの脳内は、物事を大きいとか小さいとかでしか判断できないのだった。「そんなに食えねえよ、おれ……」 ショック受けてんじゃねーよバカネヨシ。 おれは何だか悲しくなってしまったのであった。
2006/05/01
コメント(0)
-
国語の問題を解くために 3
11月28日に書いた「国語の答えはひとつだけ」という文章の続きを書きます。 大学で文学をやった人ならはじめの頃に教わる「物語論」の最初のところですが、物語というのは基本的に成長する方向で作られます。 少年なら青年へ、田舎から都会へ、ひとりからふたりへ、過去から未来へ、何かが成長する過程を書くのが物語です。 たとえば有名な作品で漱石先生の「坊っちやん」という小説がありますが、あれも無鉄砲でケンカばかりしていた青年が、最後にはケンカには勝ったが社会的には負けて、辞表を出して東京へ帰り、その過程でもうケンカも終わりだな、と思う青年期の終わりを書いている(たぶん)のです。 入試の問題文としてよく出される重松清や椎名誠などの作品も、登場人物が事件にでくわして、それを乗り越えたりやり過ごしたりして、今までの自分から少し変わって、成長する姿を書いているものが多い。 日本には私小説という世界でも類を見ない伝統があり、梶井基次郎とか幸田文とか、車谷長吉とか佐伯一麦とか、そこらへんの作家の成長も何もなくて作者の身の回りのことを題材に書くスタイルがあるのですが、これは小説の形としては独特すぎるもので、だから入試にはほとんど出ない。 国語の問題といえども、教育の一環として出題されるので、そんなダラダラした小説は出ない。 だから、国語の問題に出てくる小説は、かなり限定したパターンで語ることができるのです。 ここで、ぼくの実際の授業の進め方を例にとって話をしてみます。 ぼくは授業のときは、○印と□印で文章を囲ませる、ということをよくやります。 黒板には、横に一本線をひいて、上半分が、「つらい」、下半分が、「がんばった」 小説の内容によってこれはいろいろと変わり、「さびしい」「仲間」とか「くるしい」「負けない」とか、いろいろです。 本文を読みながら、生徒に手を挙げさせます。「登場人物の気持ちに関する表現があったら、手を挙げろ。そして「つらい」気持ちなのか、「がんばる」気持ちなのか、どっちなのか教えてね」というわけ。 すると、「首をすくめて、手で顔をおおった」なんていう文になると生徒の手が上がる。「はーい、つらい気持ち」「じゃあ手で顔をおおうってのは、どんな気持ち?」「うーん」「喜び?」「ちがう」「怒り?」「ちがう」「じゃあ何?」「恐い」 そこで、黒板に「手で顔をおおう」と書いて、そこに「恐怖」と書きます。生徒にはテキストに○で囲ませて、「恐怖」と書き込ませる。 また本文を読んでいくと、「じいちゃんはあすかにほほえんだ」なんて文がある。「はーい」「ほほえむってのは、どんな気持ち?」「嬉しい」「うーん、ちょっとちがうかもしれない」「うーん」「これはね、あすかが弱ってるからじいちゃんがはげましてあげてるんだよ」「そうか、じゃあ、はげます」「誰がハゲやねん!」「いやいや」「ハゲ益とかいうから……(ノへT*) シクシク..」 とかそんなことをやりつつ本文を読んでいくと、黒板にはつらい気持ち、がんばる気持ちで上下に別れて気持ち言葉がずらっと並ぶ。生徒のテキストには、○と□で印がつけられて、感情が書き込まれた状態になる。 実は、この段階で記述の解答に必要な要素はほとんどピックアップできているのです。「50字以内で答えなさい」なんて問題があったとしても、その問題の傍線部の前後の○や□で印をつけたところの言葉を組み合わせて、文字数におさめてやれば、ほぼ満点の解答になる。 ぼくは、国語の授業でも「なんとなくここらへんが答えだってのはわかるだろ」なんていう言葉は言いません。 国語の答えはデジタルで、法則さえ知っていれば迷わず正解にたどり着ける、というのがぼくの考えなので、「なんとなく」だとか「勘で」とか「本をたくさん読んでればわかる」だとかいう言葉は一切言いません。 前に書いたことですが、小説で人物の気持ちを表現するパターンは五つしかありません。(ほんとはもっとあるけど、とりあえず5つで充分) だからそのパターンを知っていれば、「ここに気持ちが書いてあるから、それをつなぎあわせれば答えになるんだな」ってのは簡単にわかります。 もう一度いいますが、「国語の読解力は、パターン認識のチカラ」なのです。 これは、文学的な読解力とは別の話です。 国語で求められている正解を導き出すのには、という話。 国語の解答を見つけ出すには、単にパターンを知って、それを見分けて、当てはめるだけです。 そんな簡単なものじゃないだろう、馬鹿いってんじゃないよ、という人もいると思いますが、実際そうなんです。 今までの小説の枠を破壊したまったく新しい小説を書こう、なんて決意して書き始めても、それはむずかしい。知らず知らずのうちに、今まで読んだ何かの物語に似てきてしまうものです。そしてそれは、正しいことなのです。物語にはパターンがあり、それが約束事がからです。 もちろん、ピンチョンとかバースとかバーセルミとか高橋源一郎とか、物語のパターンを壊して書く人もいるけど、そんな小説は国語の問題には出ない。高橋源一郎の「さようなら、ギャングたち」は名作ですが、国語の問題には出ない。誓って出ない。 今度の日曜にテストがあるので、勉強をするとしよう。 算数だったら、今までにやった問題の解き方を繰り返して、式の立て方を学ぶのは良い学習法でしょう。 理科、社会だったら、用語を覚えて、すらすら出てくるまで繰り返すのが良いかもしれない。 じゃあ、国語はどうなのか。 たとえば、学校で「走れメロス」をやっているとしよう。 テストのために「走れメロス」を読んで、メロスの心情を理解したり、比喩表現の対応をみたり、そんなことをやっても、不安になる。 だって、テストで出るのは「走れメロス」じゃないかもしれないし、おそらくは別のお話なのだから。 それで、とりあえず漢字の練習とかことわざの復習とかをして、テストを迎える。 テストでは重松清「エビスくん」なんかが出てきて、「メロスの気持ちしか、おれはわからーん!」 なんてことを思うのである。 小説の授業でも、「登場人物の気持ちになって考えよう」とか「このとき主人公はどう思ったか考えよう」とか、そんな指導はいらない。「走れメロス」はどういう話かというと、『つらかったけど、がんばった』話なのだ。 走れメロスだろうと何だろうと、作者は『つらかったけど、がんばった』話を書きたいだけなのだ。 そのためにつらい状況を作り出して、がんばる状況を作り出す。 だから、「何がつらいのか」「何をがんばったのか」ということをパターンにはめて考えるだけだ。「走れメロス」なら、『つらい』 → 王様わがまま 友人が人質 走るのつかれた『がんばった』 → 王様悔い改めた 友人救った つかれたけど負けなかった という、これだけの話であり、「エビスくん」でも、『つらい』 → エビスくんいじめる うそついた 妹病気 『がんばった』 → エビスくんありがとう 母ちゃんごめん 妹がんばれ だいたいこんな話です。 しかも記述の問題でも、ここに書いたことをちゃんと押さえていれば問題なく書ける。 50字だったら50字の中に、「つらいけど、がんばった」というニュアンスをちゃんと出してやれば、マルもらえるんです。少なくともバツってことはない。 もちろん、こんな断言口調でバリバリ言ってますが、そこにはあてはまらない問題があるのも事実。 でも、国語の問題を解くのにこの考え方を知っておいたほうがいいというのは、これは自信を持って言い切ります。 これはつまりは、 読者の立場ではなく、作者の立場から読む、ということでもあります。 ぼくは二千册くらい小説を読んで、二十くらい小説を書いた立場なので、そういうふうに小説を見ますが、小説を書かないとしても、その視点を技術として手にすることは、益こそあれ害ではないと思います。 まだ自分の考えを整然とはまとめられていないのですが、また今度書いてみたいと思います。
2006/04/18
コメント(0)
-
夢日記
【夢日記】4/12 義経を包囲する頼朝軍の中にいる。 皇居のような五稜郭のような、堀に囲まれたところが本陣で、そこにおれの屋敷。 義経を救おうと、総攻撃の日を先延ばしにする。 頼朝軍に気にくわないいけすかないヤツがいて、そいつはおれを陥れて総攻撃をかけて、義経を殺したい。 おれの言動を逐一チェックして、何かミスがあればそこをつついておれを失脚させようと、いつも見張られている。 おれは実は未来から来た人間で、そのことがばれないように隠しているのだが、やがてそいつにその秘密を知られてしまう。 おれの家にいる従者の少年は、アイヌだかインディアンだかの少年で、自分の破滅を知ったおれはその少年に話しかける。少年はおれに大事にしている刀を渡してくれる。それはガラスを削って研いで作った鋭利な刃物で、触れたものすべてを切り裂くほどの切れ味だ。 なかなか尻尾を出さないおれにしびれを切らしたヤツは、おれを捕らえて拷問をかける。 それでも口を割らないおれを前に、今度はヤツは少年を捕らえる。 少年が地下牢に運ばれてくるが、その頃にはおれは絶命している。 死んだおれを見て、少年は「こいつは簡単に死んだけど、おれはそう簡単にはいかないぞ」という。4/13 園本と風間とキャンプに来ている。途中の電車で永山に会い、彼女はギャル風だ。 おれはひたすら携帯で短歌を詠んでいて、海山川を詠んでいる。 永山が「誰にメールしてんの? えらい勢いで」と訊くが、無視。 正月で、帰りの電車は筑紫哲也と一緒になる。「この400系とか500系とかっていうの、400とか500って何の数字だか知ってる?」と訊かれて、「皇紀2400年とかそういうことですか?」と答えた。4/16 緒方が敵のヤクザを三人やっちまって、こっちからも三人死者を出さないとバランスがおさまらない。 緒方は池田とかに「なぁ、手をかしてくれんか?」と誘っているが、そんな理不尽なゲームには誰も参加しない。 緒方には取り巻きがいるのだが、死に役となるのはあとひとり足りない。 古いつきあいがあるので、命をあげることにする。 とはいっても、途中からやっぱり後悔していて、「なんとか逃げらんないかなぁ」と考えている。 相撲取りみたいなヤツが、おれが根性つけたるわいとか言い出して、おれをしごきだす。 ぶつかましガツンガツンやられて、血だらけになりながら「がーんばりまーす」とか言っている。 電車の中で演歌歌手に会ったが、それはニセ者だった。
2006/04/16
コメント(0)
-
小ネタでドン
(・_・)/ ハーイ それでは今日も小ネタ、どーんといってみましょー。●十三年後のクレヨンしんちゃん僕はシロ、しんちゃんのともだち。十三年前に拾われた、一匹の犬。まっ白な僕は、ふわふわのわたあめみたいだと言われて。おいしそうだから、抱きしめられた。あの日から、ずっといっしょ。 なにこの泣ける展開・・・ ドラえもん最終回に次ぐ涙。 なんでこの人こんなにたくさん泣かせるの? 。・゜゜ '゜(*/□\*) '゜゜゜・。 ウワァーン!! 泣けるぜ・・・ ゚・*:.。. .。.:*・゜゚*・゜゚・*:.。..。・゜・(ノД`)・゜・。. .。.:*・゜゚・*:.。. .。.●日本全国夜桜の名所●私は毎日自動販売機の写真を撮っています。ごめんなさい。●おもしろまにあっくす 漫画家の顔&プロフィール特集●スピードネーター : DJラオウのニコニコラジオ●ワロスニッキ:iPodつくったww●ワロスニッキ:ご は ん か け ご は ん●ワラタ2ッキ:7+8=15っておかしくね?●にこにこブーン:家でゲーム中にありがちなこと●ニャー速。 - 2ちゃんねるスレッド紹介ブログ -:合唱曲って何気にいい曲多くね?●日刊良スレガイド:◇幼かりし日、好きだった光景◆●ドラクエからガンダムまで。ネットに転がる相関図・家系図まとめ●pya! (nya)魔法を掛けられた少年●ワラタ2ッキ:偶然出会ったクラスメイト (T△T)あ~ あんたみじめすぎるよ・・・◇ダウンタウンの懐かしい動画 ●うわぁ~やってもうた!スペシャル●お勘定●たとえ警視●ごっつの車窓から●西日本番長地図
2006/04/09
コメント(0)
-
読書感想文と短歌
読書感想文。 例によって、夏休みだ春休みだと言っては生徒に頼まれて読書感想文だの自由作文だのを書く。 今回は「博士の愛した数式」の読書感想文を書きましたので、それを掲載。「博士の愛した数式」は80分しか記憶を維持できぬ数学者と、ある母子の交流の話だ。この物語を読んで博士が語る数の世界に耳を傾けるうちに、数というものがこの世界の秩序にかかわっており、それは世界の美しさにつながっているのだと思った。 この物語の主要な登場人物は3人。まず「わたし」。「わたし」は母子家庭に育ち、現在も子と二人で暮らしている。職業は家政婦。紹介所からの斡旋で瀬戸内海に面した小さな町の「博士」のもとで働き出す。 その息子「ルート」。つまり「√」。本名ではなく、彼の平らな頭頂部を撫でながら博士がつけた名前が最後まで使われる。そしてこの作品の主人公である「博士」。初老の元数学学者。ケンブリッジにも学び、前途洋々たる未来を約束された明晰な頭脳の持ち主であったが、交通事故により脳に重い障害を残す。それは1975年で記憶が止まり、それ以降のことがらは80分しか記憶が残らないというもの。 互いに心を開き、思い出を積み重ね(博士は80分ごとに更新してしまうのだが)、生きていく三人。途中語られる数学のエピソードはすばらしく、読んでいて飽きなかった。<物質にも自然現象にも感情にも左右されない、永遠の真実は、目には見えないのだ。数学はその姿を解明し、表現することができる。なにものもそれを邪魔できない>たとえば博士は「完全数」について説く。自分以外の全ての約数の和がそれ自身に等しい数である完全数について、博士は「完全の意味を真に体現する数字」だとのべ、100億以下に存在するたった5つの完全数をあげ、数が大きくなるほど見つけるのは困難であることや、過剰数と不足数など、この数字をめぐる特徴を話す。 この博士の言葉を聞いて、実は世界には人間が知らない秩序があり、まだ人間が知らない調和や美しさが隠されている、と思えてきた。無味乾燥な数字も、説明を聞いた後は表情を持ち始める。博士の話を聞いた「わたし」も、「博士の説明を聞いたあとでは、それらは最早ただの数字ではなかった。人知れず18は過剰な荷物の重みに耐え、14は欠落した空白の前に、無言でたたずんでいた」と思うのだ。 最もそれを私が感じたのは、この主人公と同様に、素数の説明を聞いたときだ。 私は中学で素数を習ったとき妙な感じがした。方程式を解くのにも図形の面積にも関係のないこんな数字をなぜ習うのか不思議な気持ちがした。しかし、素数は不思議とその意味を考えてしまう数字なのだ。そのときはその妙な気持ちの正体がはっきりとはわからなかったが、その私のぼんやりとした気持ちは、主人公の次の言葉ではっきりした。「私が推察するに、素数の魅力は、それがどういう秩序で出現するか、説明できないところにあるのではないかと思われた。……この悩ましい気紛れさ加減が、完璧な美人を追い求める博士を、虜にしてしまっているのだ」 私たちが日常使う数字は整数、あとはせいぜい小数と分数くらいだ。その間にどんな関係があり、いかなる秩序が潜んでいるのか、などとは考えもしない。ところが、たとえ28という何の変哲もない数字でさえ、それは完全数として、世界の秩序の中にハッキリとした位置を占めており、しかもそれは100億以内にたった5つしかない貴重なものなのだ。 それは、私たちがいかに世界のことを何も知らず、何も気づかずにいるかということの証拠だ。何も気づかない私たちの意識とは別に世界そのものはいかに豊かで美しく広がっているのか、ということの証拠なのだ。私たちが世界に気づかないだけなのだ。 それは数だけの話ではない。 世界はすべて、そのようにできているのだ。 博士は、主人公にこう語る。「自分が生まれるずっと以前から、誰にも気づかれずにそこに存在している定理を、掘り起こすんだ。神の手帳にだけ記されている真理を、一行ずつ、書き写してゆくようなものだ。その手帳がどこにあって、いつ開かれているのか、誰にも分からない」 主人公が、博士の記憶をまさに「掘り起こす」ように探っていた時、その奥には美しい恋の物語が秘められていた。また、最初は近寄り難くみえた博士も、主人公の息子との交流の中で別人のような側面を見せる。 それは、「発明」された美しさやあたたかさではない。すでに世界に存在していて、私たちはそれを見つけたに過ぎないのだ。ぼんやりと見ていれば気づかない世界の美しさは、分け入ってみて初めて見えてくる。そして、私たちに素晴らしいことを教えてくれる。 あと、 課題で「短歌」というもあったので、それもつくった。 冬枯れの花も葉もなき弱き枝 月光浴びて白に輝く嵐来る曇天裂いて横切る烏かすかに聞こゆ涙雨かな涙ただ もはや帰らぬ姿より忘れかけたる声聞けぬこと天に伸ぶ不思議な目して樹を見ればぽぷらと教わる秋近し夕君にあげるものが僕には何もないだから心をあげようと思った(最後のは「ハチミツとクローバー」のセリフからパクった) じるりん先生、講評よろしく。
2006/04/06
コメント(3)
-

ハチミツとクローバー
マンガは全般的に読みます。 少女マンガも読みます。 とはいっても、少女マンガ雑誌を読むのはどうかと思うので、女友達におすすめのを教えてもらって、それを読むくらいです。 最近は、「ハチミツとクローバー」にはまってました。 いいマンガです。 笑って泣いて、読むのが忙しい。 学生時代ならではのバカ話かと思ったらセンチメンタルな恋模様で泣かせる。 ギャグマンガそのものみたいな回もあれば、心に染みるラブストーリーもある。「三角関係」とか「片思い」なんていう言葉では片付けられないような、切ない切ない思い出。 泣いていいのかと思ったら奇人変人森田先輩が笑いをぶっとばして登場して、笑っていいのかと思ったらやっぱり胸がしめつけられるような、憎いほどバランスの取れた作品。 時折さしこまれるモノローグが、これがまたいい。(でも松本大洋の影響か、とも思う) 少女マンガというくくりにはなるが、万人に読んで欲しい作品です。
2006/04/05
コメント(3)
-
エイプリルフール
明日はテストで忙しいので、寝ます。■エイプリルフールで変なことやってるよリンク集 ■しーぶろ | 2006年 エイプリルフール特集! ■NOKUTEE増刊号 エイプリルフールサイトメモ ■2006エイプリルフール リンク集 ■日本インターネット エイプリル・フール協会(JIAFA)
2006/04/01
コメント(0)
-
もうすぐ糸冬 了
明日で春期講習は終わり。 短い間の勝負でしたが、一学期のスタートを切るためのアドバンテージを持たせてやることができたのではないかと思います。 といっても、それは公立中学に通う高校受験をめざす生徒の話で、中学受験をめざす小学生はもっと切実、真剣です。 とくに小学六年生については、今からやることがぜんぶ受験に直結しているくらいの意識で、きりきりと向かっていかなくてはならない。でもまだ勉強することに慣れていない、勉強との向き合い方が分からない生徒も多いので、深刻にならずに、真剣に取り組んでいくようにしたいと思います。 ぼくは、教えるに際しては、「学ぶことの楽しみ」を知って欲しいと思います。 世の中に楽しいことはいろいろあって、おいしいものを食べたり、本を読んだり、旅をしたり、ゲームをしたり、人と話をしたり、すべて楽しい。 人間はうまくできているもので、生きるのに必要なことは、楽しみと結びつくようにできているそうです。 たとえば、食欲。もし食べるのが苦痛だったら、生きてるのがつらくなるじゃないですか。食べるということは人間が生きるのに必要不可欠なもので、だから楽しく設計されている。ほかにも睡眠とか排泄とか、ぜんぶ気持ちいいように設計されていると、本で読みました。「知る」ということも、それに準ずる行為だと思います。 生きていくには、さまざまな知識を身につけることが必要です。「いま勉強しておけば、あとから役立つんだから!」なんてことを言う人もいますが、ぼくはそうではなくて、「知る」ことは、それ自体が楽しいものだと思っています。 自分が今まで知らなかったことを知る、それまでできなかったことができるようになる、どうしても解けなかった問題が解けるようになる、それらはすべて、「受験に役立つから」でも「大人になってから必要だから」でもなく、そのこと自体が素晴らしい経験で、そのこと自体がうれしさにあふれた達成なのです。 知識欲、というものは生物としてのヒトにはない本能ですが、ヒトが人間になるにつれて獲得した新しい本能なのではないでしょうか。 教えるということについて、さらに。 ぼくがはじめて勉強を教えたのは京都での学生時代でのことでした。 高校三年生の男子で、偏差値でいえば40そこそこの、まぁ成績の悪い生徒でした。 家庭教師紹介の会社に申し込んで、その二日後には「すぐにでも入ってもらいたいんですが」との連絡がきて、そのまま何の講習もなく授業に入りました。 まだ大学受験の受験勉強の貯金が充分に残っている頃で、しかも英語と国語という、ぼくが得意とする科目だったので問題を見ても内容がわからないという心配はなかったのですが、それでも何の準備もなしに向かうというのは不安で、とりあえず英語やろうかなぁ、とぼくの英語の師匠の安河内哲也氏の書いた参考書を丸善で買って、「このページやろうかな」と拡大コピーしてその家庭に向かいました。 生徒の男の子と会って、あいさつしていざ開始。 学校の宿題を見て欲しいというので、英語の教科書を開いて、英文を読んでいくことにしたのですが、まず単語を知らない。 本文を読もうにも、たとえば一行目の「teach」という単語の意味がわからない。 teach=教える、なんてのは中学の一年で習うような単語で、それが分からない高校三年生ってのは、これは大変だぞ、とぼくは気合を入れ直しました。「いいか、ヒント出すぞ。teachが分からなくても、この単語なら知っているか?」 と、ノートに「teacher」という単語を書きました。「知ってる、先生って意味です」「teachは、teacherと関係があるんだよ、teachする人がteacher=先生なんだ。だったら、teachってのはどういう意味だと思う? 想像してみてくれ」 そして、彼は三分ほど考えて、「teacher …… 先生」「そうだ、じゃあ、teachは?」「teach …… 先!」 セン! と彼は元気よく答えてくれました。 勢いとしては、スーパーひとしくん出しそうなくらいの勢いで。 その後、英語は単語の意味を書かせて、本文を音読して、という繰り返しを淡々とするようになったのですが、国語もやばかった。 国語の問題文を読んでも、意味がわからない。 評論文を読む訓練なんてまったくされていないわけで、「物事の真理を実際の経験の結果により判断し、効果のあるものは真理であるとする」とか言われても、何を言っているのかまったく理解できない。 国語については方針をがらっと変えて、邪道なことしかやらないことにしました。 まず、本文を読まない。 本文を先に読まないで問題を先に読む、とか甘っちょろいことじゃなく、一切読まない。 選択肢を部分分けして見比べて、共通を探す訓練。 言い過ぎているもの、行間を読んでいるもの、論外のもの、抽象的な正論を言っているもの、など誤答のパターンを教えて、それを除外する訓練。 小説の選択肢も、メルヘン入ってるものや電波入ってるものは違う、とかそんなことばかり教えた。 あとは、この日記にも以前書いたような、「物語の型を知る」ということ。 少年なら青年へ、田舎から都会へ、ひとりからふたりへ、過去から未来へ、何かが成長する過程を書くのが物語だという話をして、その方向に沿った形でしか、国語の解答はありえないのだと話した。 途中から、向こうがポカーンという顔をしているのはわかっていたが、構うものかとしゃべり続けた。 ぼくは高校の頃からバカみたいに本を読んでいたので、物語を読むことと国語の問題を解くことは別物で、国語の問題を解くのには、読解力よりもパターン認識力を鍛えればいいということはわかっていたので、それだけ教えることにした。「いいか、国語の問題を解くコツは優等生ぶることだよ。よく学校で作文書けというと、先生に気に入られるような作文書いてくるやついるだろ。『日曜日に公園のゴミを拾いました』とか、そんなウソつけってやつ。ああいうカッコつけて優等生ぶったやつの言いそうなことが正解なんだよ」 そんなことを、ただひたすらしゃべった。 彼は、黙って話を聞いていた。 途中、笑わそうとしたり驚かそうとしたりしたが、笑いも驚きもせず、ただ話を聞いていた。 いきなりわけわかんない話しないで、もっとオーソドックスに始めればよかったなと思いつつも、初めてしまったものはどうしようもなく、ぼくはそこにあった国語の問題を分解し、再構成することに終始した。 二時間が過ぎ帰り際に、「いきなしわけわからんくてごめんな。まぁぼちぼちやってくし、ジブンもぼちぼちやっといたらいいで」と言うと、 「はぁ」と気のない返事をしてみせたのち、彼は言った。「でもおもしろかったですよ。よくわからんことばっかしやったけど、学校の先生が言うてることとちがって、そんなんのもあんねやなぁって思たし。自分の知らんことたくさん聞いて、おもしろかったですよ」 そうかそんならよかったら、こたえながらぼくは、申し訳ないような気持ちになりながらその家を辞した。 たぶん、偏差値40というのは知らないことがいっぱいあって、しかも多くの未知に接する機会も与えられることなく過ごしてきた結果なんだと思います。 それは、伝える努力をしてこなかったり、知識や興味を広げる機会を与えなかった周囲にも責任はある。 ぼくが彼に伝えた邪道の国語は、実生活では役に立たない技術ですが、そんなものでも知識欲を刺激する何物かにはなり得たらしい。 彼は、その後国語だけは偏差値55くらいいくようになった。 しかし、文章に何が書いてあるのかは、ついにわからないままだったけど。
2006/03/31
コメント(2)
-

少年マンガでもありえないストーリー
WBC695 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2006/03/20(月) 05:00:06 ID:zKmj8PBPあり得ないほど少年マンガっぽい展開なので、あらすじをまとめてみた。Ver1.6・ナショナルチーム結成前に、監督に内定していた国民的元人気選手が病に倒れる。・かつて戦友でありライバルであった、偉大な世界記録保持者が代わって監督となる。・2人の世界的選手のうち、気さくでオープンだと思われていたスラッガーが、まさかの出場辞退・しかし、今まで無愛想で個人主義だと思われていた男が参加。チームリーダー役となる。・順調な一次予選リーグ。無難に突破するも、因縁の相手には競り負けてしまう。・監督、アメリカ出陣前に、療養中の元戦友から、「私も一緒に戦う」と国旗をかたどった宝石バッヂを託される。・アメリカに渡って二次予選開始。誰もがその強さを認めるアメリカ戦。日本は善戦するも、ありえない誤審でペースを狂わされ敗れてしまう。・その後一勝し、因縁の相手と再び対決。まるで敵地のような右翼的民族主義的応援団に囲まれる中、またも競り負ける。 試合後にはマウンドに相手国旗を立てられ、日本リーダーに嘲笑のコールを浴びせられ、決勝トーナメント進出は絶望的となる。・リーダー「生涯最高の屈辱」と、キャラ的に考えられなかったように感情をあらわにして荒れる。やけ食いやけ酒の後、歯も磨かずに寝てしまうほど。696 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2006/03/20(月) 05:01:28 ID:zKmj8PBP・しかしリーグ最弱と思われていたメキシコが「俺達ゃもう決勝にゃいけそうもねぇ。 だが、あんな判定するアメリカを決勝に行かせるわけにゃいかねぇぜアミーゴ。行くならお前ら日本だぜセニョール」とアメリカ戦に挑む。 またもあり得ない誤審の不利を跳ね返し、なんと勝利。日本決勝進出。・中華料理店で「怖くてテレビから離れた席に座っていた」日本監督、店内のメキシコ人客がハイタッチを求めてきたことでそれを知る。・決勝トーナメントで三度の因縁の対決。中盤まで息も詰まる均衡が続くが、国際試合にはめっぽう強いピッチャーがしのぐ。・後半、不振だったスラッガーが、まさかの代打ホームラン。これを皮切りに打線が爆発して完封大勝。・決勝の相手は、「世界最強のアマチュアチーム」キューバ。 実力は折り紙つきの上、カストロ議長が直々に選手にメッセージを送るほどの入れ込みようの強敵。・果たして決勝の行方は?・俺達のほんとうの戦いはこれから始まる!先生の次回作にご期待ください。(-_-)ウームわかりやすい。
2006/03/23
コメント(0)
-

WBC 日本優勝!
最後の一球、大塚は明らかに三振狙いだ。キ・キ・キ・キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!王ジャパン、世界一!キチャッタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!日の丸が翻った!王監督、胴上げ!文句なし! ワールドベースボールクラシック、開催前にも制度の不備や偏りが指摘され、開催中にも誤審やひいきが水を差し、韓国の火病が炸裂して、アメリカのふがいなさ、ファンのマナーの悪さなど、問題点もあったWBC。 しかし、そんなすべてをはねとばして日本代表は勝った! ∩( ・ω・)∩ ばんぢゃーい 終わってみれば、見事なドラマ。 少年マンガのストーリーのような、敗北、落胆、幸運、勝利、歓喜。 野球の世界一を決めるべく開かれた大会で、その第一回の大会の優勝者が日本であるという誇り。 これからこのWBCという大会がどんな歴史を刻んでいくのか、サッカーのワールドカップのような世界規模の大会になるのか、尻すぼみに終わるのか、わからないけれど、少なくともこの瞬間、この今は日本が世界最高だ。 今まで見たどのチームよりもいいチームだった。 また続きを見たい、そう思わせてくれるチームだった。 野球のすばらしさを伝えるのに、選手のファンサービスも大事だし、球団のファン獲得への努力も大事だし、テレビ局の番組作りへの工夫も大事だ。 しかし、本当に野球のすばらしさを伝えるのは、野球なのだということ。 結局、それがまずはじめにあって、最後にあるのもそれだけだ。 野球それ自体がすばらしく、面白いのだと、そう思えた一ヶ月だった。 ●ニュースまとめ●CNN.co.jp : 日本が初代王者に、決勝でキューバ破る WBC ? - スポーツ●日本、キューバ破りWBC初代王者に…MVPに松坂 : WBC : スポーツ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)●asahi.com:日本、キューバ破りWBC初代世界一 MVPは松坂?-?スポーツ●SANSPO.COM王ジャパン、キューバ倒し世界一!松坂がMVP●スポニチ Sponichi Annex 速報キューバ破った!王ジャパン世界一●Sankei Web スポーツ 王ジャパン、初代王者に 松坂がMVP WBC(03/21 18:15)●日本、キューバ破りWBC初代王者に…MVPに松坂 : WBC : スポーツ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)●asahi.com:王監督、世界一の胴上げ イチロー、松坂ら活躍 WBC?-?スポーツ●asahi.com:日本、キューバ破りWBC初代世界一 MVPは松坂?-?スポーツ●MLB Baseball - CBS SportsLine.com Bonsai! Bonsai! ↑ Bonsai! ッテ何だよ。(・。・)ぷっ♪ そして、WBCの名場面を見逃したという人のために動画を集めてみました。●まずは、日本中に物議をかもしたあの誤審。西岡のタッチアップがアウトと宣告されたあれ。●同じボブ・デイビットソンのアメリカvsメキシコでのホームラン取り消し宣言。●韓国の投手、福留のホームランのやつあたりに小笠原にデッドボールする。●韓国の三塁手、イチローむかつくから、ボールでこけちまえ作戦。●日本、優勝の瞬間●イチロー、松坂、王監督インタビュー●シャンパンバトルの様子、上原がはじけてる。 WBC 日本チーム登録選手監督王 貞治 ソフトバンクホークス監督投手コーチ鹿取義隆 元読売ジャイアンツコーチ 武田一浩 元読売ジャイアンツ打撃コーチ大島康徳 元日本ハムファイターズ監督 内野守備走塁コーチ辻発彦 元横浜ベイスターズコーチ 外野守備走塁コーチ弘田澄男 元読売ジャイアンツコーチ 投手清水直行(11) 千葉ロッテマリーンズ 右右 藤田宗一(12) 千葉ロッテマリーンズ 左左 久保田智之(15) 阪神タイガース 右右 松坂大輔(18) 西武ライオンズ 右右 上原浩治(19) 読売ジャイアンツ 右右 薮田安彦(20) 千葉ロッテマリーンズ 右右 和田毅(21) 福岡ソフトバンクホークス 左左 藤川球児(24) 阪神タイガース 右左 渡辺俊介(31) 千葉ロッテマリーンズ 右右 大塚晶則(40) テキサス・レンジャーズ 右右 小林宏之(41) 千葉ロッテマリーンズ 右右 杉内俊哉(47) 福岡ソフトバンクホークス 左左 馬原孝浩(61) 福岡ソフトバンクホークス 右右 捕手里崎智也(22) 千葉ロッテマリーンズ 右右 谷繁元信(27) 中日ドラゴンズ 右右 相川亮二(59) 横浜ベイスターズ 右右 内野手岩村明憲(1) 東京ヤクルトスワローズ 右左 小笠原道大(2) 北海道日本ハムファイターズ 右左 松中信彦(3) 福岡ソフトバンクホークス 左左 西岡剛(7) 千葉ロッテマリーンズ 右左 今江敏晃(8) 千葉ロッテマリーンズ 右右 宮本慎也(10) 東京ヤクルトスワローズ 右右 新井貴浩(25) 広島東洋カープ 右右 川崎宗則(52) 福岡ソフトバンクホークス 右左 外野手和田一浩(5) 西武ライオンズ 右右 多村仁(6) 横浜ベイスターズ 右右 金城龍彦(9) 横浜ベイスターズ 右両 福留孝介(17) 中日ドラゴンズ 右左 青木宣親(23) 東京ヤクルトスワローズ 右左 イチロー(51) シアトル・マリナーズ 右左 (。TωT)/゚・:*【祝】*:・゚\(TωT。)
2006/03/21
コメント(0)
-
WBCについて
さぁワールドベースボールクラシック、決勝トーナメントです。 今日、日本対韓国。 この試合、やる前から日本の勝ちと決まったようなもんでしょう。 だって、 アテネの予選で負けた台湾に勝って雪辱を果たした。 イチローの「今後30年は日本にはかなわないと思わせる」発言にバーニングして、その日本に二連勝し、韓国の優位を示した。 野球発祥の国、米国にも勝った。 韓国政府が発表した「ベスト4進出で兵役免除」の権利も得た。 そしてマウンドに旗立てた。 このマウンドに旗を立てるという行為にも賛否両論あるのだが、(っていっても「賛」は韓国人だけしかいない) 朝鮮日報では「人間の限界を克服した登山家が頂上に旗を立てるように誇らしい2つの太極旗が立てられた…」 ということらしい。 そうですか、「頂上」ですか。 ここが韓国の頂上ってことか。 頂上をきわめたのなら、あとは山を下りるしかない。 一方、日本はというと。 WBCに向けて最高のチームを結成した。(ぼくは今回のチームは大好きなチームです。黒田がいないのが残念だけど) 松井、井口が辞退も、福留、宮本が参加。 予選リーグで強さを示すも韓国に敗れる。 米国戦では審判の誤審で悔しい敗戦。 しかしこの誤審により国内の関心は高まる。応援ムードも高まる。 仕切り直しの韓国戦で再び韓国に負ける。イチロー「野球人生最大の屈辱」。 ところがやる気無かったはずのメキシコが再度起こった誤審で発奮してアメリカを倒す。 わずかな希望だった決勝トーナメント進出を勝ち取る。 再び韓国とのリベンジの機会を得る。 そして迎えたこの試合。 こんなもん、物語の展開でいったら日本が勝つしかない。 良くできたストーリーだったね、ということで、日本の勝ちを祈りましょう。日本チーム、勝ちました!しかも松井・井口の代役の福留・宮本が活躍しての勝利。次はキューバだ。勝って世界一!
2006/03/19
コメント(0)
-

亀田興毅について
今日、テレビを見ていて気持ち悪くてしょうがないことがあった。 一週間のニュースを振り返ってざっと放送するような番組を見ていて、スポーツの話題では浅田真央やらWBCやらの話題をやっていた。 ぼくが興味あるのはひとつだけ、亀田興毅の試合を映像で見たかったからその番組を見ていて、いつ問題のシーンが流れるかと待っていた。 問題というのは、相手を倒したのがボディなのかローブローなのかということ。 その場面を、ぼくは写真では見たけれども動画としては見ていないのである。 格闘技のマニア間では「まぁローブローだわな」という意見が多数を占めているのだが、マスコミでは触れていない。 実際のところはどうなんだろう、という興味があった。 また、それをテレビはどう扱っていくのか、と。 それまで見た新聞やネットの反応は「ボディへの強打」であり、せいぜいが「ローブロー気味」というもの。 テレビはこれを、どう扱うのか。 このニュースを扱う以上、問題のシーンも放送しなければならない。 さあどうだ、と関口宏の番組見てたんだが、これがせこかった。 問題の場面になると急に亀田の背中から撮ったカメラアングルになって、肝心のパンチが当たっている部分は見えない。 そして関口宏がバカみたいに「これはあっぱれですよ!」などとおっしゃって、ローブローであるか否かという話題にすらならなかった。 しかし、ぼくが見た写真では明らかに金的入ってる。 これがローブローでないというのか。 タイムに02:01とあるので、これはKOショットではなくその前の攻防なのだろうが、レフェリーはこれを反則と取ることをしていない。流しているのである。 亀田の攻勢で進んでいた試合なので、故意にローブローを打つような場面でもなかったのだろうから、「狙った」ショットではなく、「当たってしまった」ショットなのかも知れない。 しかし、これだけはっきりと金的に入っているのだから、相手ボクサーに回復の時間が与えられるなど、何らかの処置はとられて然るべきだろう。 亀田興毅は、日本ボクシング界が手にした久しぶりのスターである。 現在、日本には世界チャンピオンが四人もいるが、その名前をすべて言えるなんて人は、ボクシングのことを相当好きな人でもなければいない。 以前の辰吉丈一郎や畑山隆則のように、ボクシングファンの枠を越えて一般にまでその存在が届くようなボクサーが久しぶりに現れたことで、JBCが大事に育てたいのはわかる。 マスコミも、ケチつけて出入り禁止になったら困るから、誉め称えるのはわかる。 安直なマッチメークをするJBCにも、ジャーナリズムの精神に欠けたマスコミにも、いずれにも問題はあるが、苦しい事情というものがあるのはわかる。 わかるが、賛同はできない。 亀田が強いのは知っているが、どこまで強いのかというと、疑問だ。 今までの相手は峠を越えたタイ人が多く、タイ人が実力査定の対象にならないというのはキックボクシングでもボクシングでも、常識である。 現役のランカーならともかく、元○○なんていう選手のほとんどは実質引退した選手であり、単にカネになるから日本まで来て試合をしているだけだ。彼らに共通するのは、見事なまでのやられっぷり、倒されっぷりであり、それはチャンバラの斬られ役のように見事なのですよ。 JBCは、本気で亀田を世界王者にしたいのなら、そろそろ日本タイトルへの流れを作って、対戦相手として日本人をマッチメークするべきだろう。 マスコミには、亀田のマスコミ受けする言動に飛びついて、提灯記事を書くだけでなく、そこで起こったことを報道する姿勢を持って欲しい。 都合の悪いことは隠して、ただただ誉め称えるというのでは、ジャーナリズムの精神の欠片もない。 亀田が勝っているうちは称賛して、そして亀田にボロが出たら一斉に叩き出すというのがマスコミの基本姿勢なのだろうが、それはライブドアの堀江貴文前社長に対する扱いと相似している。 今までさんざん持ち上げておいて、何かあったら地の底まで突き落とす。 そんなくだらないマスコミに踊らされることなく、亀田には勝手に強くなってもらいたいものである。 本当はあんまり興味ないんだけどね。
2006/03/12
コメント(1)
-

身長と体重
塾の先生をしていて、もうなんつーか。 いろいろ生徒がいったい何考えてんのかわからないときもある。 いきなり「もじょぱーん!」とか言ってなぐってくる小学生。 とつぜん「先生、マーガリンとカタツムリどっちがいい?」とかわけのわからないことをきいてくる女子。 なんの心理テストだ、と思っても、その結果は決して教えてくれないのである。 部活やらテレビやらマンガやらに忙しい彼らだが、共通して興味があるもの。 それは、身長。 ためしに、小学生のO君にインタビューをしてみると・・・益「いま何センチ?」O「うーん、140センチ」益「まじで!」O「えっとね、136センチ」益「一気にかわったな」O「だって、それくらい欲しいじゃん」益「やっぱり身長高いほうがいい?」O「そうだよ」益「何センチくらい欲しいの?」O「170は欲しい」益「180はいらないの?」O「もらっとく」益「190は?」O「びみょー」益「でかいのは、いや?」O「それよりデブがいや。先生やせなよ」益「益ちゃんぱーんち!」o( ̄ー ̄)○☆パンチ! 一方、女子。 中学生のMさんにインタビューしてみると、益「身長何センチ?」M「152かな」益「何センチが理想なの?」M「165かなぁ、でも163くらいでもいいかも」益「その2センチはなんなのさ」M「だって、かわいいじゃん」益「かわいいんかい」M「170だと、でかいってかんじだし、165でも、ちょっとでかいじゃん」益「ちょうどいいのがいいのか」M「だから、163だよ」益「あんまり大きいのはいやなのね」M「うん、ぜったいいや」益「2センチとか、あんま変わんないだろ」M「それがかわいいの」益「わっけわからん」M「先生はさー、やせないと彼女できないよ」益「益ちゃんきーっく!」トリャア≡(:D)┿━
2006/03/09
コメント(0)
-
過去について
タイムマシンの話をしよう。 ドラマ「白夜行」を見ているとふたりが、「もしタイムマシンがあったら、過去に行く? 未来に行く?」 なんて話をしておりました。 もちろんそんな会話はSFファンの間では日常挨拶として、「こんにちは」という言葉よりも頻繁にかわされている話題なわけですが、さぁどうでしょう。 さて、ぼくは、過去に行きたいです。 過去と行っても、「江戸時代に行って平賀源内に会いたい」とか「幕末に行って海援隊に入りたい」とかそんなビッグな過去ではなく、せいぜい「5年前に行って、あのときの自分に『ヤメトケ』と言いたい」とかのスモール極まりない過去に行きたい。 さてさて、ジャニス・ジョップリンの歌に「Me And Bobby McGee」というのがあって、名曲です。 その歌詞に、こんなのがある。 I'd trade all my tomorrowsFor one single yesterdayFreedom's just another wordFor nothing left to lose 私は自分のすべての明日を ただ一日の昨日と取り替えたい 自由という言葉は 失うものが何もないということの もう一つの言い方に過ぎない なんて豊かな思い出。 なんてぜいたくな過去。 なんて、幸せだろう。 過去というと、「もう過去のことなんて忘れろよ」とか「いつまでも過去のことにこだわってるんだよ」とか、そんな忘れて次に行くためだけのものみたいに言われがちです。 未来に進め、過去を振り返るな。 宇宙刑事ギャバンの歌詞にも「 若さ 若さってなんだ? 振り向かないことさ ギャバン あばよ昨日 ギャバン よろしく未来 宇宙刑事 ギャバン 」 なんてのがあった。 しかし、すべての過去が忘れ去るための存在してるなんて、そんなわけがない。 過去を大切に思うことをネガティブだと切り捨てる前に、考えて欲しい。 だって、我々が今日を生きているのは、すべての明日と取り替えてもいいくらいのただ一日の過去を手に入れるために生きているのに違いないから。 ぼくは、そんな過去を自分の中に持ち続ける人生というのは、決して不幸でも後ろ向きでもなく、幸せだと思う。 そんな過去を、そんな一日を、ぼくも持ちたいと思う。 自分が生きてきたことの答えは過去にあるのだから。 だから、明日よりも昨日を味わって、確かめて、信じていたいと思う。
2006/03/09
コメント(0)
-
ちびまる子ちゃんのキャスト
●フジテレビ ドラマ ちびまる子ちゃん3年4組のみなさん 似てる。 これはかなりがんばったな、フジテレビ。 これならおれの友人のちびまる子マニアの皆川さんも文句言わないんじゃないだろうか。 ___ _l≡_、_ |_ (≡,_ノ` ) GoodJob・・・
2006/03/06
コメント(1)
-
中三の社会は
明日から久しぶりに中三生の社会に復帰するもので、その進め方について。 いきなり結論からいうと、ぼくは中三の社会はおさらいに徹するのがいいと思う。 大事なことだけ、教科書でいったら太字のところだけやる。「だけ」と言っても、実際はその周辺にも触れることになるのだろうけど、気持ちとしては重要事項だけ。 具体的には、一学期は地理・歴史の復習で、二学期は公民、三学期は入試問題。 塾では入試のことだけではなく、定期テストの点数も上げて内申の対策もしなくてはならないという前提もあるが、それでもやはりゴールは入試に設定するべきだと思う。 定期テストの対策は、テスト前の二週間くらいの対策の期間をつかって、あとは年間で考えたほうがいいのではないかと思います。 地理の勉強は、地図をつかう。 歴史の勉強は、年表をつかう。 それぞれの要点だけまとめたプリントを用意して、それをひたすら暗記させる。 入試の対策には、図表を読み取る問題で確実に点が取れるように、それだけまとめたものを用意して、やらせる。 授業では要点の暗記につとめて、問題集は暗記の確認につかう。 とにかく暗記するしかないのは明白。 あとはこちらで、いかにして情報を選別するか、いかにして手を動かさせるか。 入試を前にして困らないように、三年で公民だけやっていればいいなんてことはないと思う。 さあ、どうでしょうか。 ご意見、お聞かせください。
2006/03/06
コメント(1)
全108件 (108件中 1-50件目)











