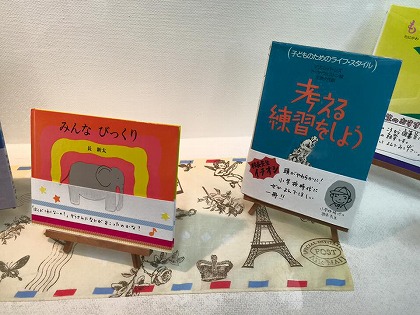PR
X
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年06月
2025年05月
2025年06月
2025年05月
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
コメント新着
テーマ: 塾の先生のページ(8375)
カテゴリ: カテゴリ未分類
高校生のお姉さんが小学生の妹さんのことを思って
そんな風に聞いてきました。
「じゃぁ、2つだけあるんだけど。。。
お父さんやお母さんに協力してもらって
次の連休とか10月のお休みとかに
京都か奈良の寺院に連れてってあげてほしいんだ。
法隆寺とか金閣寺とか
たくさんじゃなくて1か所でいいから。
大阪城でもいいし、姫路城でもいいし
近場なら、大仙古墳でもいいんだけど
これから歴史で習うであろう場所とか
地理でする淀川の河川敷でもいいから
行ったことある場所を習えば
そこから、興味って湧いてくるものだから。」
「もう一つは?」
「もう一つは、月に一回でいいから
一緒に図書館に行って
○○ちゃんが、本を借りてきてほしいんだ。
何か借りなさいとか本を読みなさいではなく
『図書館行くからついてきてくれる?』って。
で、『何か、一冊借りてみる?』
って、誘ってあげてほしい。
中学でも高校でも、そして大学でも
勉強って、話を聞いたり実習するけど
実はその大半は、本や文章から読み取ったり
そこからレポートや論文にまとめることだから
簡単な本から始めて、
本に親しんでることは大きな財産になるんだよ」
そんな話をすることができました。
学年によってもその状況によっても
違ってきたりはするんですが
「だって、本読まんもん。」 というお子さん
年々増えてるなぁと感じますし
応用力が育ってこないため
頑張ってるのに、なかなか伸びてこない
という現象も見かけたりもします。
下のコラムの
『ポイントになるのは小さいころから本に触れさせること』
その言葉を見つけて
昨日のやりとりの背中を押してもらったようでした。
写真は、先日行った区民図書館の玄関にあった展示です。
いい本をチョイスしてますよね。。。
(コラムの抜粋です)
■ユダヤ人の家庭は本が溢れている
ユダヤ人の国際弁護士アンドリュー・J・サターさんの
『「与える」より「引き出す」!
ユダヤ式「天才」教育のレシピ』 という本を読んで
かなり以前から意識的に多くやっていました。
ユダヤ人は世界で1300万人とむちゃくちゃ少ないのに、
なぜ世界的に起業家やノーベル賞受賞者が多く、
世界の金融界やビジネス界を牛耳っていると
言われているほどに、天才が多いのか?
といったことがこの本には書かれています。
ポイントとなるのは、小さい頃から本に触れさせる環境だというのです。
とはいえ、本を強制的に読ませる必要や、
読むことを働きかける必要は全くなく、
とにかく家中に本を溢れさせておくだけ。
ただし、親自身も読書を楽しむことが大切だと書かれています。
■ユダヤ人は「頭」に投資する
歴史的に迫害を受けてきたユダヤ人は、
自分の頭こそが最も頼れるものだと信じており、そこに最も投資をする、
つまり教育への投資を非常に重視しています。
ただし、ここで面白いのは、それが決して詰め込み教育ではない、ということです。
日本で、「教育に投資をする」というと、
つい詰め込み教育を連想してしまいがちですが、彼らは違います。
彼らの教育は、「子どもの持っているものを引き出す」
ということに重きが置かれており、
Education(教育)の語源となったラテン語の「エデュカーレ」(引き出す)
ということを重視しているのです。
元来、Educationは「引き出す」という意味だったというのです。
一般的な教育は「与える・強制する・教える」ものだが、
ユダヤ式家庭教育は「子供の力を引き出す」ものである、ということです。
その「引き出す」方法として、家中に本を溢れさせておいて、
興味をもったことを、いつでもどこでも勝手に読めるようにしておく
あるいは何かあった時に、すぐに調べられるようにしておく。
家が図書館状態になっていることが、ユダヤ人に共通する家庭環境のようです。
また親が本を読む姿を見せる、というのも大きなポイントになるというのです。
■教えるのは「学ぶことは楽しい」ということだけ
ただし、こうした「引き出す」ことに重きを置いている教育方針の中で、
唯一教えることがある、と言います。
それは、 「一番大事なのは、学ぶのは楽しいことだと教えること」
だというのです。
一度、学ぶことは楽しい、と感じた子どもは
放っておいても好きなことを見つけて、
どんどんそこにのめり込むようになるのだ、ということです。
そうした世界に、一番手っ取り早く
身近に触れることができるのが本の世界なのです。
だからありとあらゆる本を、氾濫させておくのでしょう。
これがユダヤ人が歴史的に成功者が多い秘訣だというのです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.