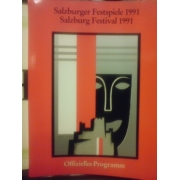PR
キーワードサーチ
フリーページ
Concert Review since1986

★2001-2010

★1996-2000

★1991-1995

★1986-1990

★2011-
PianoLesson

Playing the piano

Lesson Archives
Omikuji-Words

2005 大御心

2006-2008 大御心

2009 大御心

2010 大御心

2014 大御心
Favorite Words

YOKO ONO

Eihei-ji

座右の銘ファイル
Favorite CD(曲目別)

Brahms op.118-3

Mendelssohn 無言歌集

Schumann Arabeske
Favorite CD (ピアニスト別)

マリア・ジョアン・ピリス

内田光子

ブレンデル
CD Present MEMO
名古屋 ピアノ練習スタジオ
October , 2025
September , 2025
August , 2025
July , 2025
May , 2025
April , 2025
March , 2025
February , 2025
このあいだの休日、本屋さんの新書コーナーで
「新書大賞1位」という本の帯が目につき、気になりました。
また、複数の方が推薦している新書でもあったりして、中身も気になりました。
時間があまりないので、書評を見てから気になるところを読もうと思うと
書評もつぎからつぎへとネットでも出てきました。
新潮社
朝日新聞1
朝日新聞2
読売新聞
チーフコンサルタント
はてな
yougetuhiwaというブログ
bookjapan
booklog
一番下のリンク先のものがわかりやすかった感じがします。
「日本人ほど日本人論が好きな民族はいないと良く言われる。
常に外からの目を気にして、遅れていないか心配している。なぜそんなメンタリティが生成されたのか。
著者は日本は古代から辺境国家であった事に着目する。
・他国との比較を通じてしか自国の目指す国家像を描けない。
・アメリカのように「我々はこういう国家である」というアイデンティティが持てない。
・私たちは(開戦のような)きわめて重大な決定でさえその採否を空気に委ねる。
・辺境である事を逆手に取り、政治的、文化的にフリーな立場を得て自分たちに都合のいいようにする?面従腹背に辺境民としてのメンタリティがある。
・後発者の立場から効率よく先行の成功例を模倣するときには卓越した能力を発揮するが、先行者の立場から他国を領導する事になるとほとんど脊椎反射的に思考が停止する。
・辺境民の特質として「学び」の効率に優れ、「学ぶ」力こそが最大の国力である。
・辺境民の特質は、日本語という言語の影響が大きい。
説得力がある民族論。著者は決してこれを悲観的に捉えている訳でなく、逆に辺境であることを受け入れて、独自の文化を世界に示していく方がいいと語る。大いに納得させられた。 」
●
辺境ということばが、気になりました。
政治的なことはさておいて、文化的な面ということについて、なんとなく考えたくなりました。
ぜんぜん話題がかわってしまうかもしれませんが、
クラシック音楽やっているものにとっても、ヨーロッパからみれば、とてつもなく辺境の地なのかもしれませんし、受け入れ方も向こうの人から見れば異質かもしれませんので。
過去のブログをひっくりかえしてみると、西洋音楽と日本の音楽のかかわり方みたいな講演を聴いたり、書物で知ることとなったりしました。
世界のレッスンを紹介して、日本人で学ぶ人に対して警鐘めいた感じをするものもありました。ここ最近の公開レッスンに対してもそういうことなのかもしれないと思うようになりました。
●
http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200809270001/
日仏音楽協会から、
「日本におけるフランス音楽の現在について」ということで、
野平一郎さんからレクチャーがありました。(2008/9/27ブログより)
(主な内容)
150年の歴史のなか、パリ音楽院に日本人が最初に学んだのは、明治時代に陸軍の軍楽隊が、明治時代(125年前)に行ったのが最初。 作曲家の池内友次郎が1927-、ピアニストの安川加寿子が1934-から留学したのが本格的なはじまりで、80年ほどしかまだたっていない。
http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200809280000/
青柳いづみこ著「翼のはえた指」評伝 安川加寿子 (1999年)
「1975年に安川加寿子氏が、エリザベート国際コンクールの審査をされたとき、日本が世界レベルになるのにあと50年かかるといったこと、何が足りないのかをある意味問題提起しています。」
http://mixi.jp/view_item.pl?id=1216273&reviewer_id=532391
ピアノレッスン-世界のレッスンとレパートリー
(和書)
中村 菊子
ヤマハミュージックメディア (1996年12月出版)
あらためて読み直してみて、気になった箇所はレッスンのことに関してのこと。(以下は引用した内容)
「音楽とは、自分が「思うこと、感じること」を表現する芸術であるから、「指づくり」より「歌ごころ」が先、初期のレッスンから自分の心と曲の内容を結びつけて弾くことが大切」
「ピアノレッスンは楽しみのためのレッスンも情報教育のレッスンもピアニストを目指すレッスンもやることは同じ」
「指づくりを強いたレッスンをしていた場合、聴くことが留守になり、音色が固いモノトーン(一色)になり、形からはいった指に「歌ごころ」をつけようとしてもほとんど困難」
(上記の青柳さんの著書でも似たような指摘は他の著書やコラムでも)
http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200905040000/
マスタークラスを聴講 (講師のブリジット・エンゲラーさん 2009年5月)
「曲に対するイメージ、感情、何を表現したいかを語る口調を大切に、
色彩感を持つように、(同じフレーズでも)ちがう表現になることをためすように、
学者のように探究することを強調されました。
どう聴かせたいかわからず、モノトーンのような色彩感になるのは最悪だとも。
オーケストラ、室内楽、オペラなど、多彩な音色の楽器の演奏をたくさん聴いて耳を育てること、ピアニストという範囲に閉じこもってはいけない。
鍵盤の上でただ速く弾ければいい、暗譜で弾ければいいという単次元的のものではない。」
上に書いたことで、「あと50年」といっていたことは、こういうところでも指摘されているのではと思ってしまいました。
●
最近でこそ変わってきたのかもしれませんが、
そろばんや書道とかのように、何級とか何段とかそういうものと置き換えて、
体系的なものを重視しすぎて、何か肝心なものをなくしてしまうような練習の仕方を
してきたのではないのかなあと、自分の年代以上の人を見ていたらそう思ってしまうこともあります。
いろいろなところを旅して、見て感じたりしたことを素直に表現するようになればと思っています。過渡期のような時代をいろいろ見ていければと思うようになりました。
あしたは旧奏楽堂に行くことがあるので、また歴史のある場所で格調高い音楽聴きたいです。
シューマンのピアノカルテット 聴いています。
カレンダー
11月17日同仁キリス…
 ひっぷはーぷさん
ひっぷはーぷさんLIVEやります!
 SEAL OF CAINさん
SEAL OF CAINさんパニック障害と共に… kanayuineさん
Tyees_Cafe tyeesさん
ほしあかりのノクタ… ふゆのほしさん
nyantasistaのピアノ… nyantasistaさん
MY FAVORITE THINGS リタ0826さん
「のり2・クラシカ… のり2さん
☆MyuのどきどきMぶろ… myu20054000さん
コメント新着