-
1

TVドラマ「ふくまる旅館」
「閑話休題」 TVドラマ「ふくまる旅館」が訴えるもの最近は新聞を広げると殺人・放火・死体遺棄が連日のように報じられており、マスコミも被害者家族や加害者家族の人間模様を暴き立てるかのように彼らの自宅の前にカメラの方列を組んでいる。一方では食品会社の製造・賞味期限の食材の偽装発覚。 また国家公務員・地方公務員による不正発覚事件と、明るい話題がほとんどない今の日本。 家庭での唯一団欒時間では低級なスタジオトーク(若いタレントや漫才師による意味不明の日本語が飛び交う低俗番組)が多いですね)。そんな時代の風潮に逆行するかのような、観ている者をほのぼのと包んでくれる貴重な1時間番組があります。 TBS系列の月曜日8時からの放送「浅草 ふくまる旅館」。東京・浅草で60年以上続く老舗旅館「ふくまる旅館」が舞台のドラマ。主人公の福丸大吉(西田敏行)は三代目主人としてふくまる旅館を継いで30年になる男やもめ。大吉は義理と人情に篤い人柄ですが、ふくまる旅館は近年、近辺のホテルなどに客を取られ、経営が芳しくない状態が続き、旅館を切り盛りする大吉の義姉・福丸はな(木野花)はインターネットでの客の呼び込みに必死です。毎回、旅館周辺で巻き起こる身近な問題に、大吉が首を突っ込み、奔走すします。物語は、旅館の客と従業員との触れ合いを描いた、笑いあり、涙ありの人情コメディーです。ふくまる旅館のモットーは「お客は家族、従業員も家族」。このドラマは、台東区をはじめ、浅草寺、浅草花屋敷や浅草観光連盟も製作に協力しており、下町情緒が堪能できる内容となっています。この作品で「男はつらいよ」を彷彿とさせる"人情"路線をとっています。「男はつらいよ」とは違った味なんですが、どこか似ているドラマです。 福丸大吉は大のおせっかい焼き。 飛び込んでお客の悩みをおせっかいのように仲介して丸く収めるお話。毎回観るたびに心が洗われるような想いになるドラマ。 騒動はあっても観終わった後に嫌なものがのこりません。 鑑賞後はとてもさわやか。「男はつらいよ」と同じパターンで他人の悪口や他人を傷つけない人たちの集まり、日本人がいつか忘れてきた「温かさ」が蘇ってくるドラマです。鑑賞後は胸がす~として下町人情の幸せにひたれる稀有な番組です。お薦め番組です。
2007年11月13日
閲覧総数 592
-
2

ヴァイオリン協奏曲
「名曲100選」 シベリウス作曲 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調ヴィヴァルディなどのバロック音楽時代を経て、バッハ、モーツアルトに受け継がれてきたヴァイオリン協奏曲が、「サロン風」音楽から劇場型音楽に変えたのがベートーベンでした。 音楽は優美さと雄渾さ・雄大さが備わった協奏曲が、やがて交響楽的な響きのブラームスの協奏曲が生まれてきました。その後ロマン派作曲家の、ヴァイオリンという楽器の特性をフルに生かした個性ある美しい曲の数々が生まれてきました。 メンデルスゾーン、ブルッフ、ラロ、チャイコフスキー、ドヴォルザークなどを経て、20世紀にはバルトーク、プロコフィエフ、グラズノフ、ストラビンスキー、ハチャトリアン、ショスタコービチなどに受け継がれてきました。その中でもシベリウスの協奏曲は人気があり、ヴァイオリニストたちの心をかきたてる曲の一つとして演奏会や録音でよく採り上げられています。シベリウスの祖国フィンランドは「湖沼の国」と呼ばれるくらいで千の湖と深い森林に覆われた国です。国土の70%が原始林に占められており、ごつごつとした岩だらけの風土に、暗い厳しい寒さという、過酷な自然環境に包まれています。シベリウスの作曲した交響曲や交響詩などは、こうしたフィンランドの森、湖を想像させるような情緒を醸し出した音楽で、清冽な美しさに満ちています。 私も仕事の出張で訪れたことがありますが、あの深い森とそこに点在する湖に立ってみて、初めてシベリウスの音楽が心に染み渡るようになりました。霧に覆われた神秘的な湖や、奥深い森の情景がまざまざと目に浮かんできます。 ある音楽評論家が「シベリウスの音楽世界には人が誰もいない」と表現していますが、そういう情緒を湛えていることは確かです。このヴァイオリン協奏曲もこうしたフィンランドの情景を彷彿とさせており、幻想的な美しい旋律が散りばめられた傑作です。 フィンランドの風が吹き渡るかのような清冽さにみちた美しい音楽が全楽章を包み込んでいます。シベリウスは謎の隠遁生活を送っていた1957年の9月20日に、脳出血のために91歳の生涯を閉じています。彼の訃報は全国に伝えられて、フィンランド放送番組は中断されて、シベリウスの名作「トゥネラの白鳥」が流されて哀悼の意を表したほど国民から愛された作曲家でした。シベリウスは、ヴァイオリン演奏でも優れた演奏家で音楽院で勉強中には、すでにメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を弾きこなしていたそうです。ただ彼はヴァイオリニストの道を歩まなかったのは、ステージに立つとあがってしまう性格だったので、ヴァイオリン演奏の道を断念したというエピソードが残っています。彼がヴァイオリニストとして研鑽を積んでステージに立つ道を選んでいれば、今私たちが聴いている素晴らしい音楽が生まれていなかったかも知れません。愛聴盤 (1) キョン・チョン・ファ(Vn) アンドレ・プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7007 1970年録音)有名なキョン・チョン・ファの1970年の録音盤で、第1楽章の清冽なリリシズムとフィンランドの清澄な空気、そこはかとなく秘めた寂寥感がたまらない魅力です。LPからCDに変わっても何度も再発売を繰り返されてきた名盤です。(2) 五嶋みどり(Vn) ズービン・メータ指揮 イスラエル・フィルハーモニー(SONYクラシカル SRCR9651 1993年録音)キョン・チョン・ファの演奏に力強さが加わったような、たくましいシベリウスとなった名演だと感じています。
2010年09月05日
閲覧総数 40
-
3
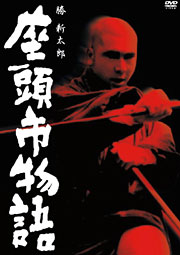
いいなあ~、時代劇!
股旅もの礼賛私は小学生の頃から映画が好きでした。 私の家から徒歩2分のところに映画館があって、3本立てで50円くらいだったと記憶しています。 母が美容院を経営していたので、店にはいつも映画雑誌や芸能雑誌が置いてあり、それを見て育ちました。 またその近所の映画館には比較的時代劇映画をかけることが多かったので、子供のころから時代劇ファンでした。時代劇といっても様々なジャンルの映画があります。剣豪・剣客物、平次・半七などの捕り物帳、仇討物、お家騒動、股旅・任侠物等があります。そうした中でも一番好きな時代劇は「股旅物」です。股旅は長谷川 伸によって始まったのだそうです。 長谷川 伸は昭和初期の作家で、今でも映画・ドラマ・流行歌などで目にする・耳にする「瞼の母」(番場の忠太郎)の作家です。股たびの何が私を惹きつけるのか? 一言で表現するなら「追われやくざの悲しき性」でしょうか? 「座頭市物語」を例にして話しましょう。 座頭市は「やくざ」ではありませんが、ほぼ同じような境遇を生きている「やくざ・按摩」とでも呼べるでしょうか。原作は子母澤 寛(新撰組始末記や勝 海舟などを書いた作家)。 彼の随筆「座頭市物語」(中央公論社の「ふところ手帳」に収録された短かい随筆集)で、子母澤は述べている。「な、やくざあな、御法度の裏街道を行く渡世だ、いわば天下の悪党だ。こ奴がお役人と結託するようになっては、もう渡世人の筋目は通らねえものだ。 俺達あ、いつも御法というものに追われ続け、堅気さんのお情けでお袖のうち隠して貰ってやっと生きていく。それが本当だ」これこそ股旅ものの真骨頂。 汚れて、追われて、堅気(世間)さまから蔑まれ、最低の場所にまで身を落として、破れ三度笠に薄汚れた道中合羽を羽織ったやくざ一匹。 法の世界の悪を斬る。正義だ、格だ、道徳だなんてご大層なイデオロギーを振りかざすこともない。 武士のようにお家のため、主君のため、なんて大義名分もない。 幕末志士のようにお国のためなんてこともない。 あるのは裏街道しか生きられない日陰者の意地か。この「汚れてしまった最後の意地」がやくざ一匹を支えている。 それが股たび物の良さだと思います。明日からこれまでに心に残った「股旅」映画について紹介していきましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・白梅
2010年02月10日
閲覧総数 40
-
4
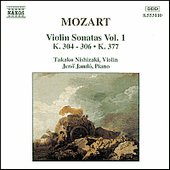
名曲100選~モーツアルト/花菖蒲
「名曲100選 モーツアルト作曲 ヴァイオリン・ソナタ第28番 ホ短調」今日もモーツアルトの作品から。私はあまりモーツアルト(1756-1791)の音楽を好んで聴きません。 あまりに明るく過ぎて華麗でロココ調そのままという音楽が私に合わないのだと思います。 同じ古典派ではハイドンの音楽は素直に心に入ってきますが、モーツアルトはそういう訳にいきません。感動はしますが心に入り込んできて琴線を震わせることがあまりないのです。これはクラシック音楽を聴き始めてから54年来続いており、今でもその理由はわかりません。 ピアノ・ソナタ、弦楽四重奏曲、その他の室内楽作品、協奏曲、交響曲など心に入り込んでくるのはごくわずかの曲です。モーツアルトのほんとに感動する作品は短調の曲が多いのです。ほとんどの作品が愉悦感にあふれ華麗で明るく、典雅な調べに対して、終世貧乏で過ごしたモーツアルトが本音で書いた「悲しみ」を表したのが短調の音楽のように思えます。故小林秀雄氏(評論家・随筆家)が「疾走する悲しみ」と名言を残していますが、モーツアルトの悲しみは後のチャイコフスキーなどのようなアダージョで書かれた直截的な悲しみ表現ではありません。アレグロで書かれた悲しみはいっそう人の心に入り込んでくるのでしょう。 代表的なのが交響曲第40番のト短調であり、25番のト短調交響曲です。アレグロで書かれた悲しみは聴く者の胸をえぐるような悲哀感があります。 ト短調で書かれた弦楽五重奏曲もそうです。こうした短調の曲に感動を覚えるのは、どれも劇的な感じがして、モーツアルトの本心を吐露した音楽・作品だからだと思います。今日の話題曲ヴァイオリン・ソナタ第28番もホ短調で書かれており、40曲以上にのぼる彼のヴァイオリン・ソナタの中でも唯一の短調の作品です。他のヴァイオリン・ソナタに比べて劇的緊張感が2楽章の音楽全体を覆っており、ハッと耳を澄ませて聴いてしまう音楽です。モーツアルト特有の伸びやかな旋律が少し暗い雰囲気を醸し出して、彼の悲しみをひたひたと訴えてくるような感じがします。 「何故、そんなに悲しいの?」と問いかけたくなるほどです。彼の時代は室内楽はまだ「ハウス・ムジーク」(家庭内音楽)として定着していたころですから、華美に華麗に典雅に書かれた音楽が王侯貴族に好まれる時代でしたから、他のヴァイオリン・ソナタもほぼその傾向にあり、この第28番だけは異色です。音楽にも深さがあり彫刻的な美しさにあふれた音楽が、わずか15分足らずの間にモーツアルトの別の世界に引きずり込まれるような感じがしてなりません。愛聴盤 西崎崇子(Vn) イェネー・ヤンドー(P)(Naxosレーベル 8.553110 1994年録音)Naxos社長夫人でもあり、ヴァイオリン教授の鈴木メソッドの最初の生徒であり、世界でも一番数多く録音を遺している西崎の美音はとても素直で、個性のない個性とでも呼べる心を預けて聴ける数少ないヴァイオリニストの一人です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 花菖蒲大阪府堺市大仙公園内 日本庭園にてカメラ Pentax K-10Dレンズ Tamron 28-300mm XR Di
2010年06月29日
閲覧総数 13
-
5
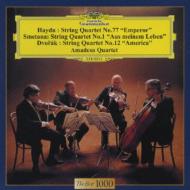
ハイドン「皇帝」
「名曲100選」 ハイドン作曲 弦楽四重奏曲第77番 「皇帝」ヨゼフ・ハイドン(1732-1809)が作曲したこの「皇帝」四重奏曲は、ナポレオン戦争と呼ばれる19世紀初頭のヨーロッパを巻き込んだナポレオンが引き起こした大混乱と関係しています。フランス革命が起こったのが1789年。 この革命が野火のようにオーストリア、プロシャ(ドイツ)などを戦争状態に巻き込み、それに乗じてフランスのナポレオンが全ヨーロッパを征服すべく戦争を仕掛けていきました。 約20年間ヨーロッパは戦争状態となります。それが19世紀の幕開けでした。オーストリアも1809年、ウイーンに怒涛のようになだれ込んだナポレオン軍から激しい砲撃を浴びせられました。 この砲撃でハイドンの大邸宅地も砲撃のために地震のように揺れ、邸内の人たちは悲鳴を上げて逃げ惑ったと言われています。大作曲家ハイドンは少しも騒がず、「皆の者、怖くはない、怖がることはない。 このハイドンがいる限り、何にも起こることはないのだ」と邸内の人たちを励まし、砲撃される中を自らピアノに向かい、自身が作曲した「皇帝賛歌」を演奏したと伝えられています。この時から3週間後の5月31日にハイドンは亡くなりました。 葬儀はウイーンで行われましたが、すでにナポレオン軍の占領下でした。 それでもフランス軍からも葬儀に列席してこの大作曲家を追悼したそうです。ハイドン最晩年の最高傑作である弦楽四重奏曲第77番ハ長調「皇帝」の第2楽章に使われている主題と変奏曲が、彼の死の3週間前にフランス軍の砲撃中に演奏した「皇帝賛歌」です。この弦楽四重奏曲第77番は、この「皇帝賛歌」が第2楽章で使われているために「皇帝」という副題がつけられています。 「皇帝賛歌」とはハイドンがオーストリア国家として書いた作品です。それが何故現在ドイツ国家になっているのでしょうか?その前にハイドンがオーストリア国家として書いた経緯は、イギリス国家にあります。 ロンドンのザロモンという興行師から再三招かれてイギリスにわたって、「ザロモンセット」と呼ばれる12曲の交響曲を書いたハイドンは、イギリス滞在中に聴いた熱狂的なイギリス国民の国歌への愛着と祖国への熱い想いが、人一倍愛国心の強かったハイドンを刺激して、オーストリアのためにと書いたのが「皇帝賛歌」と言われています。その後長くオーストリア国歌として親しまれてきましたが、ヒットラー率いるナチス・ドイツに占領され、この国歌も歌詞を替えられてドイツ国歌となり、終戦後もそのまま西ドイツ国の国歌となってしまい、東西ドイツ統一後もそのままとなって現在に至っているそうです。ナポレオンのオーストリア砲撃から人々を鼓舞してきた「皇帝賛歌」、第2次世界大戦後も国を違えて国歌となった「皇帝賛歌」。ハイドンの思いはこんな結果になって今なおも世界の人々の心を癒してくれています。愛聴盤アマデウス弦楽四重奏団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5091 1963年録音)ハイドン「ひばり」「皇帝」、モーツアルト「狩り」の3曲が収録された1000円廉価再発売盤。 愛聴盤と言ってもこの紹介盤を持っているわけではありません。 同じ音源の「皇帝」と「狩り」だけが収録されたCDで聴いています。現在求めうる盤として上記を紹介しました。
2010年09月25日
閲覧総数 616
-
6
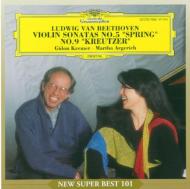
ベートーベン 「クロイツェル・ソナタ」
『室内楽の楽しみ』 ベートーヴェン作曲 ヴァイオリンソナタ第9番イ長調 ベートーヴェン(1770-1827)はヴァイオリンソナタ第5番「春」を書いた後、6番ー8番を作品30として一括して出版したあとに、1803年5月にイ長調の第9番「クロイツェル」を書き上げています。 ベートーヴェン32歳の春でした。 交響曲では3番「英雄」が完成間近の頃にあたります。 彼はヴァイオリン・ソナタを全部で10曲書いていますから、「傑作の森」と呼ばれる中期以前の第1期にすでに9割のソナタを書き上げてしまったことになり、最後の10番の完成はほぼ10年経った1812年まで待たねばならないのです。そして1812年以降、亡くなるまでの15年間はとうとうヴァイオリンソナタを書くことがありませんでした。さて、この第9番の「クロイツェル」ですが、様々なエピソードが残されています。第一に、ベートーヴェン自身が副題をスコアに書いているのが「ヴァイオリンの助奏を伴うきわめて協奏的なピアノのためのソナタ」と指示していますが、とんでもない、この曲は「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」と呼ぶべきで、ヴァイオリンは助奏どころかきわめて二重奏的な色合いの濃い曲となっています。 これは前作の第5番「春」についても言えることですが、ヴァイオリンとピアノのパートが独立性が高く、まるで2つの楽器による二重奏といった趣きで、決してヴァイオリンパートは「助奏」ではありません。 もっとも曲を聴けばそんなことはすぐにわかるくらいにきわめて優れた二重奏曲であると理解はできますが。演奏時間は30分を超す雄大・壮大な規模で書かれており、3楽章形式です。第1楽章は、二つの楽器の対話で進む緊張感にあふれたアダージョ・ソステヌートで始まり、大規模な主部へと進んでヴァイオリンとピアノの掛け合いによる張り詰めた緊張を伴う音楽に耳を奪われます。 ベートーベンのほとんどの音楽がそうであるように、とても腰が据わった安定感のある旋律・リズム・和声で貫かれた堂々とした音楽です。第2楽章は、アンダンテでしかも変奏曲風にと書かれていて、変奏曲スタイルによる緩やかなテンポの楽章で、風格ある主題が提示されたあとに4つの変奏が行われ、しかもカデンツァとコーダ付きという重厚なアンダンテ楽章です。 雄大・壮大な規模の音楽と打って変わって、ベートーベンはこれほどに優しいのかと思うぐらいに優美な旋律の楽章です。終楽章は、プレストでまるでイタリアの「タランテラ舞曲」を想起させるようなリズミックな躍動感にあふれ、華麗で、力強い音楽で締めくくられています。まさにヴァイオリンソナタの音楽史上でも稀な大傑作です。ベートーヴェンは、この曲をイギリス国籍のブリッジタワーというヴァイオリニストに献呈するために書いたと言われています。 ですから初演はこのブリッジタワーとベートーヴェンによって行われたのですが、完成が遅れたために初演のステージでは、楽譜の清書が間に合わず、第2楽章はヴァイオリンは草稿のまま、ピアノはスケッチで演奏されたというエピソードが残っています。ブリッジタワーに献呈するために書かれたこの曲が、何故「クロイツェル」なのか? それは初演のあとベートーヴェンとブリッジタワーが不仲となり、フランスのヴァイオリニストのロドルフォ・クロイツェルに献呈されてこの副題がつけられたそうです。しかし、クロイツェル自身がベートーヴェンの激しい音楽を好んでいなかったので、彼によってこの曲は一度も演奏されなかったという後日談が残っています。この曲にまつわる話は、ロシアの文豪トルストイが書いた小説「クロイツェル・ソナタ」があります。 倦怠期のロシア貴族の一家庭の不倫事件を扱っており、貴族の妻が家庭に出入りするヴァイオリニストと恋に落ち、夫が嫉妬のあまり妻を殺すという物語ですが、その不倫の発端となったのがこの「クロイツェル・ソナタ」の合奏だったのです。 トルストイはこの小説の展開上、この曲を重要な予想として扱っています。またチェコの作曲家ヤナーチェックは、このトルストイの小説を読んで「トルストイのクロイツェル・ソナタに霊感をうけて」と題した弦楽四重奏曲第1番を作曲しています。愛聴盤(1)ギドン・クレーメル(VN) マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)(ドイツ・グラモフォン 447054-2 輸入盤)緊張感の漲った演奏で丁々発止と受け渡しをしながら演奏される名人芸に酔うのに格好のディスク(2)ダヴィッド・オイストラフ(VN)、レフ・オボーリン(ピアノ)(Philps原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1967年録音)風格がただよう、オイストラフの遅めのテンポが王者の足取りのように聴こえてきます。 しかも力強い気迫のこもった熱い演奏で、40年以上の前の録音というのを忘れてしますほどの堂々とした熱演で、これこそ名演奏と呼べる記録だと思います。LP時代から一体何度再発売を繰り返してきたことでしょう。 現在は1000円盤で第5番「春」とのカップリングもうれしいディスクです。(3)アルテュール・グリュミオー(Vn) クララ・ハスキル(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3438 1957年モノラル録音)私が14-5歳の頃に買って聴いた懐かしい録音で、しなやかで温かみのあるグリュミオーのヴァイオリンとハスキルの奏でるピアノは、至福の時空へ誘ってくるれような演奏です。 これも何度再発売されているかわからない程リリースを繰り返しています。 現在は「歴史的名演シリーズ」として1200円盤として再発売されています。(4)西崎崇子(Vn) イェネ・ヤンドー(ピアノ)(Naxos 8.550283 1989年録音)可もなし不可もなしと言ってしまえばそれまでですが、西崎の実に素直な音色が美しい演奏で、こういうのを「普遍的」と呼べる演奏ではないでしょうか。 知人のヴァィリオンの先生に聴いてもらったところ「こんなんやったら私でも弾けるわ」と言われたそうです。それほどに西崎の音色は素直そのものです。Naxos社長夫人という地位にありながら、さすが世界で最も録音の数が多いヴァイオリニストの演奏と肯ける模範的で万人に薦めたいディスクです。 価格も1000円。 ベートーベンの「スプリング・ソナタ」とのカップリングです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1876年 誕生 パブロ・カザルス(チェリスト)1893年 初演 ドビッシー 弦楽四重奏曲1906年 初演 シベリウス 交響詩「ポヒョラの娘」1965年 没 山田耕作(作曲家)2001年 没 朝比奈 隆(指揮者)
2007年12月29日
閲覧総数 266
-
7
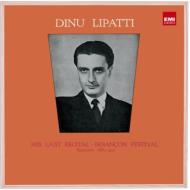
ジョルジュ・サンドとの終焉~小犬のワルツ
「今日のクラシック音楽」 ジョルジュ・サンドとの離別~子犬のワルツリストから紹介されたショパンへ傾いていくように愛を告白したサンド。 彼女の奔放な性格・生活を知りながら、ショパンもサンドに傾いていきます。1837年でした。二人は魅かれるように急速に接近していきました。当時サンドは交際をしていた愛人がいたので、パリでの噂から逃げるためにマジョルカ島へと自分の二人の子供を連れて逃避します。 ショパンもそれに従いていきました。 それから10年近い二人の生活が始まります。1838年10月のことでした。ここでショパンは「24の前奏曲」「ポロネーズ」「マズルカ」「スケルツオ」など作曲に専念しています。 しかし、マジョルカ島へ渡った時期はとても湿気の多い、雨がよく降る気候の時期で、病弱のショパンは次第に体を蝕まれていきます。この頃、ショパンはまだマリアとの恋が忘れらなく思い出にひたっていたようです。 サンドは友人にこのことについて、1通の手紙を書いています。 「ショパンを得るのは誰か」という趣旨の手紙です。サンドは友人に訴えます。 ショパンの心にはまだマリアがいる、彼は私を獲るのか、マリアを選ぶのかと問うています。 マリアから「さよなら」の手紙を受け取った大きな理由の一つはショパンの病気であり、彼女の忠告にも関わらず無理をしたために喀血したショパンに絶望的になって、別れを選択したマリアとの「愛の断絶」は、「愛の復活」を望むべくもなかったのに。サンドの奔放な性格は、マリアとは好対照でした。 ショパンにはまだマリアへの思慕があったのでしょう。 それを風化させるサンドの愛はショパンには異質のものだったのでしょう。それでもサンドはかいがいしくショパンを看護する生活を送っているのですが、自分の子供が成長していくことが、二人に大きな亀裂を生じさせていきます。やがてサンドの長男が自分がこの家の家長であり、ショパンは居候的存在と見下すような態度が顕著となり、ショパンはサンドの家庭内問題に巻き込まれていきます。 サンドの娘の結婚話が二人の間に亀裂を生じさせる原因になったと言われています。 しかし、この間もサンドは年下の男性との情事に溺れており、二人の別離は時間の問題だったのでしょう。もともと一人の男性に満足しないサンドの心はやがてショパンから離れていき、1847年7月にとうとう別れの手紙を書いています。 そうしてサンドとの恋も終焉を迎えたのです。その後ショパンは演奏旅行で英国に渡りますが、肺結核の病状は進んでいきます。 当時の医学では結核は伝染病として扱われていたために、病人が伏せたベッド・家具類は焼却されるという現代医学では考えられない扱いだったそうで、ショパンもますます劣悪な環境に生きていったことが、病気の進行を促したようです。サンドとの別離がショパンの心に重い影を落としたのも病気を進行させたのでしょう。 英国からパリに帰ったあとは病床について、1849年の今日(10月17日)39歳の生涯を閉じています。 葬儀にはジョルジョ・サンドの姿もなく、彼女からの花束もなかったそうです。ショパンの音楽は今でもピアニストや世界中の人々から愛され、「ノクターン」「エチュード」集は慰めを、「ポロネーズ」「マズルカ」「バラード」集などは勇気と情熱をもたらす音楽として聴き継がれています。今日がショパンの命日。 私も命日にちなんでショパン音楽を堪能したいと思っています。「小犬のワルツ」サンドが飼っていた小犬が、自分の尻尾を追いかけてくるくる回る様を描いた音楽というエピソードが残っています。 サンドとの愛の危機にあり、病状が悪化している頃に書かれた作品です。愛聴盤 (1) ディヌ・リパッティ 「最後の演奏会」 (EMI原盤 東芝EMI TOCE14051 1950年ライブ録音)(2) ウラジミール・アシュケナージ 「ワルツ全曲集」 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5084 1970-85年録音)チェロ・ソナタピアノ曲に数多くの名曲を残したショパンの作品でも異色の名作、チェロソナタがあります。ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)練木繁夫(ピアノ)(DENON CREST1000 COCO70552 1978年録音)
2007年10月17日
閲覧総数 957
-
8
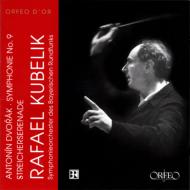
「新世界より」
「名曲100選」 ドヴォルザーク作曲 交響曲第9番「新世界より」アメリカ・ニューヨークのジャネット・サーバー夫人から、彼女が経営する「ナショナル音楽院」の院長という職への要請が、チェコのアントニン・ドヴォルザーク(1841-1901)に届いたのは1891年の春というエピソードは、先日のドヴォルザーク「チェロ協奏曲 ロ短調」の記事で書いています。 その頃のドヴォルザークは既に8つの交響曲、ピアノ曲、室内楽作品、オペラなどを発表しており、ヨーロッパでは大作曲家の一人でした。 その彼に当時のヨーロッパからすれば「新世界」の国の人々に音楽教育をして欲しいと要請されたのです。アメリカはまったくの異質の新しい人種が建国した国ではなく、すべてヨーロッパから移民した人種でした。クラシック音楽には素養もありました。新しい国に音楽教育が必要で、そのために立派な音楽家を必要と考えたサーバー夫人だったのでしょう。受託までは紆余曲折がありましたが、ドヴォルザークは1892年9月15日にニューヨークに向けて旅立ちました。 ニューヨークには9月26日に到着しました。 それから約2年半彼はアメリカに留まります。その頃のアメリカは、すでに大陸横断鉄道が完成しており、1793年に独立を果たして109年目を迎えていました。ドヴォルザークがアメリカについて驚いたのは、活気にあふれた街並みでした。 まだエンパイア・ステートビルは建っていませんが、大きな建物がブロードウエイに立ち並び、行き交う群衆の活気あふれる姿に驚いたそうです。 祖国の田舎町とは比較にならない活気ぶりでした。 もう一つは「黒人霊歌」や純朴なアメリカ民謡に大きな感動を受けたそうです。 アフリカから奴隷として売られてきた黒人たちの歌う「黒人霊歌」は、虐げられた人々の救済への祈りと願いを込めた歌ですが、ドヴォルザークはその歌にいたく感銘を受けて、自宅に黒人歌手を呼んで彼らの歌に耳を傾ける機会が非常に多かったそうです。ドヴォルザークは、それまでアメリカ人には不当に低く見られていた「黒人霊歌」の価値を高く認めた、最初の大作曲家であったそうです。 彼は美しく変化に富む黒人霊歌を「土の産物」として評価していました。「ナショナル音楽院」の忙しい職務のかたわら、1893年の約半年間新しい交響曲への構想をまとめて草稿を仕上げています。 その年(1893年)の夏に休暇を取ってニューヨークから遠く離れたアイオワ州の町へと旅立ちます。 この時にはドヴォルザークはかなりひどいホームシックに陥っており、音楽院の弟子の勧めでわざわざ遠いアイオワまで出かけたそうです。そこはスピルヴィルという小さな町ですが、そこにはボヘミアから移住してきた人々が数多く住んでいた所で、母国語を気兼ねなく話すことが出来、祖国の料理を楽しめる、祖国の雰囲気を味わえる土地でした。 アイオワの自然は祖国のそれと似ていたのかも知れません。 ボヘミア移住民と接することで彼の郷愁も少しずつ和らいでいったそうです。こうして新しい交響曲は短期間で書き上げられています。 それが交響曲第9番ホ短調「新世界より」なのです。 初演はその年(1893)の12月16日にニューヨークで行われており、大成功に終わったそうです。「新世界より」はドヴォルザーク自身が付けた副題で、当時ヨーロッパでは「新大陸」と呼んでいたアメリカを指す「新世界」ですが、音楽にはアメリカ・インディアンの民謡と思しき旋律や、黒人霊歌の旋律らしいものが使われていますが、彼が何故「新世界より」と「より」を付けたを考えると、決して「新大陸」を表現した音楽ではなくて、遠くアメリカからボヘミアを望郷の想いで書いたことは容易に想像できます。 この「新世界より」は、ドヴォルザークが故郷ボヘミアを想って書き綴った「手紙」のような音楽でしょう。 アメリカ的な匂いがすると感じれば、その「手紙」をアメリカで書いたからと思えばいいのではないでしょうか。この作品中、最も有名なのが第2楽章「ラルゴ」です。 イングリッシュ・ホルンによる郷愁を誘うような美しい旋律は一度聴けば忘れられない、ほのぼのとした哀愁を誘う旋律で、今では「家路」という名前で合唱曲にさえなっている有名な旋律です。 小学校の下校時の音楽もこの旋律を使っている学校が一体何校あるでしょう。 ほとんどの学校が使っているほど家路に着く旋律にぴったりです。1957年、私がクラシック音楽に興味を持って聴き始めた時に、小学校の恩師が貸してくれたLPがこの「新世界より」でトスカニーニ指揮 NBC交響楽団の演奏で、何度も何度も第2楽章「ラルゴ」を聴いていました。私がクラシック音楽を聴く原点の一つでもありました。 愛聴盤ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団(ORFEOレーベル ORFEO596031 1984年録音 海外盤) いまはこの1984年の演奏会ライブ録音での、クーベリックの緊張をはらんだ、しかもボヘミア色に塗りつぶされたような色彩感のある、一音一音をしっかりと奏でている演奏に魅かれて、このCDばかりを聴いています。その他の愛聴盤トスカニーニ指揮 NBC交響楽団ケルテス指揮 ウイーフィルハーモニー管弦楽団ゲオルグ・ショルティ指揮 シカゴ交響楽団ヴァツラフ・ノイマン指揮 チェコフィルハーモニー
2010年09月30日
閲覧総数 173
-
-
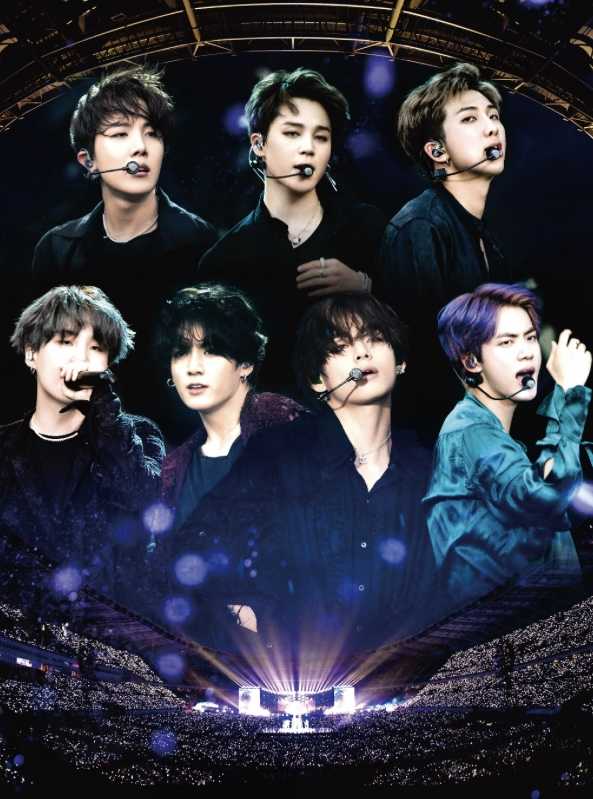
- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…
- (2025-11-21 18:37:01)
-
-
-

- 吹奏楽
- ちくたくミュージッククラブ7thコ…
- (2025-11-22 23:43:42)
-
-
-

- Jazz
- Jan Garbarek with the Federation o…
- (2025-11-25 22:32:33)
-







