-
1

帝都東京を感じる上野旅と、寒い朝にはミニタオルを持って・・・
こんにちは。今週は旦那の勤続40周年記念の旅行及び、休暇で先週末より今週末までお休みでした。が、鹿児島でまっ~たりしている時に実家や家から電話。何でも9月下旬にフォークの番組収録の観覧に姉と当選。出かける二日前に姉から施設にいる姑が入院したので、行けないとの連絡で私だけが東京に出かけて、NHKの番組収録の他に皇居付近や靖国、ここ東京国立博物館に出かけたのだが、その入院中だった姑さんが亡くなったとの連絡で、葬儀は鹿児島旅行から帰った次の日だったので参列をしてきたところだ。共働きだった親に代わって家で世話をしてくれたとの孫娘らの手紙を司会の女性が代読をしていた若い時は看護婦さん、助産婦さんもしていたそうでやめてからも近くの人が急病になると、医者が来るまで世話をしていたそうで、自分の事よりもまずは人の事を思いやる人であったそうだ。姉も認知気味の舅には悩まされたが、姑さんには恵まれていたと思う私の母親は長野五輪の頃に、70代前半で亡くなったが実家(長兄)義姉の母親は「元気、元気」らしくて、次兄と同居をしている義姉の母親もかなりのご高齢らしいが元気しかし認知症気味らしくって、ついさっきの自分の言動を忘れてしまうみたいだ。最近のネットニュースで読んだが10年程前に徘徊をする認知症の高齢の母親から目が離せず50代の息子が仕事をやめてその失業保険も給付停止で生活に行き詰まり、生活保護も受けられず、遂には心中を図ったそうだが自分だけが生き残ってしまったそうだ。その直前の母子の会話が子「もう生きられへん。ここで終わりやで」母「そうか、あかんか。一緒やで」子「すまんな」と自分の額を母の額にくっつけると母「わしの子や。わしがやったる」その言葉を合図に中年の息子は母の首を絞め、自分も自殺を図ったが生き残ってしまったという。裁判ではその過酷な境遇から温情判決が下され、執行猶予を受けながらも、事件から10年もたたず息子も命を絶ってしまったそうだ。所持金わずかに数百円と自分と母親のへその緒を一緒に焼いて欲しいとカバンに入れていた最近は認知症の高齢者の重大交通事故が多く、社会現象ともなっており、もはや本人や家族の力ではどうこう出来る状況でもないようにも思う。さて写真は何回も展示品を紹介してきた東京国立博物館、本館内部であるさすがに置かれた電話もレトロだったその本館は昭和7年に着工し昭和12年に竣工。翌年に開館をした。設計は公募で渡辺仁の案が採用されたそうで、日本伝統の木造建築の様式を踏まえた鉄筋コンクリートの和洋折衷な建築で、「旧東京帝室博物館本館」として国の重要文化財に指定されているこちらの建物は表慶館。ウィキペディアによると>1909年(明治42年)、東宮皇太子嘉仁親王(のちの>大正天皇)の成婚を祝う目的で開館した。設計は宮廷>建築家の片山東熊。建物は重要文化財に指定されている>石造及び煉瓦造2階建て、ネオ・バロック様式の建物で>中央と南北両端にドームがあり、中央のドームは吹き>抜け、南北のドームの下は階段室になっているといった感じで展示物同様に、その建物自体も価値がある東京国立博物館だった東京国立博物館の構外施設にあたる黒田記念館ウィキペディアによれば>博物館敷地から道路を隔てた西側にある。洋画家>黒田清輝の遺言により、黒田の遺産を活用して>1928年(昭和3年)建てられたもので、設計は岡田>信一郎である。黒田記念室と特別室があり、湖畔、智・>感・情をはじめとする黒田の作品が収蔵展示されているこちらは東京国立博物館の入館料を払わなくても開館時には、誰でも無料で拝観が出来るという嬉しい施設だ。という訳で私も見学をされて貰うことにした。ここも撮影がOKみたいだ。ネットでも内部や作品の写真を載せている人が多いので私も紹介します東京って近代的な建築や、江戸情緒なものも残されているけど私はやっぱ文明開化、和洋折衷を経ての帝都東京としての戦前のレトロな建物を見るのが、一番の楽しみだこちらは高村光太郎による黒田清輝胸像。なかなか恰幅の良い人物であったみたいだ。黒田は東京美術学校西洋画科で教鞭をとっており、光太郎は彫刻科を卒業後西洋画科に再入学をしていたとか、そんな縁から胸像ものちに頼まれたみたいだこちらは若かりし頃の黒田清輝の自画像。法律を学ぶ為にフランスに留学をするが、パリで洋画を学ぶ日本人の画家らに出会い自らも画家を志し、ラファエル・ラコンに師事するフランスの展覧会でも入選し、帰国後は美術教育者として活躍。塔虚位美術学校教授、帝国美術院院長などにもなり養父が亡くなるに至って子爵となり、貴族院議員ともなった黒田の遺言には、遺産を美術の奨励に役立てるようにとあり、その遺言に基づき黒田記念館が設けられたそうである。代表作である読書、舞妓、智・感・情湖畔の四作品を展示留守特別室は年3回のみの公開で見る事は叶わなかったそんな代表作まで寄贈するとは近代洋画家の父とも呼ばれた教育者でだけある。その素性は薩摩藩士の家柄で、伯父の子爵黒田清綱の養子になったそうで大河でも有名な黒田官兵衛の遠縁にもあたるらしいその向かいにあるのは、かつてあった京成電鉄の博物館動物園駅の建物。昭和8年の京成本線開通に合わせ、東京帝室博物館、東京科学博物館、恩賜上野動物園や、東京美術学校、東京音楽学校の最寄り駅として開業しかし利用者も減り、建物も老朽化していたので平成9年に営業停止。10年前に廃止となったが駅舎の他にホームなども現存しているらしいちょうどパラリンピックの期間であったのか、何やらイベントもしていたが時間がないので素通りこちらは「ル・コルビジェの建築作品、近代建築運動への顕著な貢献」の構成として、世界遺産にもなった国立西洋美術館上野公園からは遠くにスカイツリーも顔をのぞかせた新幹線の時間待ちで、東京駅のグルメスポットをうろうろしていたらこれは栗きんとん~。恵那の銀の森のものだった。まっこれを土産に買う訳にもいかないのでとりあえずは小岩井農場のソフトクリームを食べてみた東京では、このように日本全国の美味しいものを食べる事も出来るのがうらやましい夜遅くに家に戻ると、息子が食べたらしくってラーメンの残骸が。それを見て途端に現実に戻った 平成28年9月下旬に東京上野公園で撮影さて冬のような寒い朝も迎える11月。ついに初めての雪マーク登場。旦那は電源が入っていると思い込んで電源を消そうとしてるし、舅や姑も朝からボイラーの音がすると気がついたみたいで。電源が入っていようがなかろうが冷えた朝に、一定の温度を下回ると水道管が凍結をしないようボイラーが運転をするのだと教えた更にお風呂の方も、朝方に温度が下がるとお風呂の残り湯が撹拌され凍結しないようになっているので、こちらも残り湯を抜かないように頼んでおいた。なんでも綺麗好き(風水好き?)だかの奥さんが夜にお湯を抜いて掃除もして、窓も開けてたら朝には水道が凍結してしまったそうだし娘の部屋の☆3つと断熱が少し劣った小さな東向きのペアガラスの窓は隅の方が、寝室の北側の窓の次に結露しやすいんで、朝一で私がチェックし網戸が外しにくいので窓がふけないので、窓を少し開けてるんですけどその日の朝は、なんかちょっと違う。窓の下部の隅の方は内側に結露をしているが、窓の真ん中の方は外側からとWでくもっているし。もう、何が何だか。冬の間はミニのタオルを持って、あっちの窓こちらの窓と見回らなければならなそうだそんな訳で次回からは、久しぶりの飛行機で行く鹿児島の旅を紹介できたらと思うにほんブログ村
2016年11月19日
閲覧総数 402
-
2

艶やかな時代絵巻を、晩秋の馬籠宿で和宮御降嫁行列
正月(むつき)立つ 春の初めにかくしつつ 相(あひ)し笑(ゑ)みてば 時じけめやも令和の出典ともなった万葉集にある、大伴家持が天平勝宝2年(750)年に、宴で詠んだ歌ですその意は、お正月の春の初めなのだからこのように、皆で笑いあえるのは楽しいものですね。との事で、令和2年のスタートです。今年もよろしくお願い致します!今年最初の日記は、前回に続き地元の馬籠からご紹介します。昨年11月3日に開催をされた和宮降嫁行列です。皆さん、知ってらっしゃいますよね。幕末の孝明天皇の異母妹で仁孝天皇の第八皇女であった和宮親子内親王ですが公武合体(朝廷の権威と、幕府を結びつけて幕藩体制の再編強化を図る)の懸け橋として江戸幕府第14代将軍である徳川家茂の正室(御台所)になるべく、中山道をご降嫁されたという行列を再現したものです既に和宮には有栖川宮 熾仁親王という許嫁がいたのを反故にされて、東国に下ったのですが、皮肉な事に王政復古後の新政府によって、有栖川宮は東征大総督に任命されて東征に際しては、明治天皇から錦旗と節刀(天皇が出征する将軍や遣唐使の大使に持たせた任命の印である刀)を預かり、京都を出立し江戸開城を成し遂げたのであるさて和宮降嫁行列には、地元の有志や中津川の中京学院大学や、名古屋外国語大学の学生さんたちが当時の装束に身を包み、馬籠宿を下から上へ(東国へ)と練り歩いた和宮は、16才で降嫁をされたそうだがこの行列では、地元の中学3年生の女の子が和宮をやっているので、年齢的にもぴったり。こんな少女が、知らぬ世界に飛び込んでいくのは、さぞかし心細かった事だろうお付きの女官たち。中津川の中山道歴史資料館には、降嫁行列で和宮のお世話をした家に、礼の品物などが贈られたとして展示がされている文久元年10月20日に京都を出立した降嫁行列は京都方が一万人、江戸方が一万五千人京都からの通し人足が四千人というもので、その長さは50キロにも及んだそうである行列の先頭が通過してから、最後尾が通過し終わるまで4日間もかかったそうだ。和宮を奪還すべく過激な攘夷派が行列を襲撃するという噂があり、御輿の警護に12藩、沿道の警護に29藩を動員し、幕府の威信をかけての大行列となったのだ馬籠宿では行列の為に、街道沿いの石垣を2尺引っ込めて、道幅を2間(約3.6m)に拡幅する工事がされたそうだ迎える宿場、街道でも様々な約束事もあり伝馬役以外は一切の外出禁止前後3日間の遊興と売り物禁止女は姿を見せないこと通行を上から見下ろしてはいけない正座して迎えること看板を取り外し、2階の雨戸は閉めること寺の鐘などの鳴り物を鳴らしてはいけない犬猫・牛馬は、鳴き声が聞こえないよう遠くに繋いでおくことその降嫁の道中に、和宮が歌ったのが 落ちて行く身と知りながら、もみぢ葉の 人なつかしくこがれこそすれこのような経緯があったにも関わらず和宮と同じ年の若き将軍、家茂とは仲睦まじい夫婦であったそうだが、僅か4年後に、家茂は脚気衝心のため亡くなってしまうそんな中山道には欠かせない和宮ですが私が知ったのは、替え玉説の有吉佐和子「和宮様御留」の大ヒットからです。中学くらいでした。私にとって中山道を旅したといえば、西行法師で、その次は新選組といったところでした今回の御降嫁行列は100名程のもので地元有志や、大学生が美しい装束を身にまとって、再現をしているものだけど皆さん、なかなかお似合いですよね宿場の中ほどの藤村堂記念館で、お昼の休憩の前には、しばし写真撮影タイムちょっぴり現代人の表情にも、戻ります和宮を中心にハイ、ポーズ和宮そっちのけでハイ、ポーズ扇子使いも様になり現代人にまじっての休憩タイムお侍が小さく樹の奥に。この写真なかなか好きです。タイムスリップしたみたいさてさて、後半戦のスタートです幅が広くて、ここって奥まで行列が綺麗に観れて、なかなか良いですね歩くより、正座して輿に揺れるというのも大変そうな気もしますさてさて前回の燈籠やライトアップの準備もですが、今回の時代絵巻にも地域役員の旦那は参加をしておりますハリボテですが刀も持てて喜んでました図柄を決めるのも面倒なので、うちの今年の年賀状は、この行列での旦那の時代装束姿です。まっ、正月らしくていいんじゃないかとこれはないなと思った、くしゃくしゃの宝くじマークご祝儀も募ってました子供たちは後半だけ、行列に参加をしてました馬籠は左右に並行して脇道(車道)もありそれを使ったりして、行列の先回りも出来ます。このあたりまで来ると見物客も随分少なく、見やすいです緑も多くて、下の方より良い写真が撮れるかも今回は旦那も出るので、気合を入れてあちこちで、写真を撮りまくったので行くところ、行くところにお前がいるから恥ずかしいと旦那に言われましたが次は、上の方と展望台だけでいいな。あっ旦那の写真はたくさんあるけど、ここでは特に紹介しませんいよいよ行列も終盤。陣場の急坂ですキツイ勾配で、普通に歩いていてもふ~ふ~言います(ここと、最初の大きな水車のところ)草鞋なんでしょうね。歩き心地はどうなんだろうキツくても、顔には出しません宮様もあと、わずかゴールの展望台が見えてきました既に展望台にいた娘が、スマホで上から撮影した行列。私も次回は先に上に行っていようかな車の前を、御輿に揺られる和宮行列も無事に終え、表情が明るい和宮その背後には恵那山もよく見えます令和の世になっての、幕末の時代絵巻楽しませてもらいました。皆さんお疲れさまでした♪という事で、皆様。今年もよろしくお願いします 2019年11月3日に中津川市馬籠宿で撮影にほんブログ村
2020年01月01日
閲覧総数 649
-
3

無料で並んだ上海博物館は鼎のカタチ。中国四千年の歴史と言うけれど
1月末に娘と格安旅行で出かけた上海一日目の日記は、まだまだ終わってはいなかった。都合上で投稿が前後したが初日の午後に最初に出かけた観光先は「上海博物館」であった昼に上海の空港着→昼食→上海博物館→思南路→田子坊→夕食→ホテル→個人で外灘→南京東路→ホテルに午後10時着といったのが一日目の上海スケジュールであった。コメントで〇○は?とあったけどまだ初日なので、明日、明後日もあるのでお楽しみにそんな訳で初日の午後は、上海博物館にやってきました。土曜日は中国もお休みなのか? 子供も含めて地元の方も沢山みえていて、入り口には大行列ができて入館まで30分近くかかったと言うのも地下鉄同様に、ここでも入館時飛行機の搭乗時のような手荷物検査があり時間がかかったが、60歳以上は優先的に入館が出来、ツアーでも高齢の方達は長く見学出来て役得、役得と喜んでおられた北京の故宮博物院と南京博物院と並び、中国三大博物館に数えられ、その収蔵品であるが青銅器から仏教美術、陶磁器、民族衣装、書印章、貨幣など多岐にわたっており、なんと入場料は必要なく、無料で見学が出来るのだテーマ毎に所蔵品が展示されている中で、1階の「中国古代青銅館」に陳列をされている青銅器は常時、夏、商(殷)から漢代において製造された数百点程あまりと、世界屈指の規模を誇っており上海博物館自体が、青銅器の鼎(かなえ)の形をしている鼎について、ウィキペディアによると>鼎(かなえ、てい)は中国古代の器物の一種。>土器、あるいは青銅器であり、竜山文化期に>登場し、漢代まで用いられた。通常はなべ型の>胴体に中空の足が3つつき、青銅器の場合には>横木を通したり鉤で引っ掛けたりして運ぶ>ための耳が1対つくが、>殷代中期から西周代前期にかけて方鼎と>いって箱型の胴体に4本足がつくものが>出現した。蓋のついたものもあった。殷代、>周代の青銅器の鼎には通常は饕餮紋などの>細かい装飾の紋が刻まれており、しばしば>銘文が刻まれる。>鼎はもともとは肉、魚、穀物を煮炊きする>土器として出現したが、同時に宗廟において>祖先神を祀る際にいけにえの肉を煮るために>用いられたことから礼器の地位に高められ、>精巧に作られた青銅器の鼎は国家の君主や>大臣などの権力の象徴として用いられた。そんな訳で最初に入室した青銅器のコーナーがあまりに充実しており、フラッシュ禁止であれば写真撮影も出来たので思いのほか、時間がかかり所要時間は1時間もないというのに、あぁ他のは駆け足になってしまいそうだ中国の歴史は?と聞かれて戦後の数十年!なんて答える人もいると思うが、様々な王朝などによる歴史はかなり遡れる訳で。中国四千年の歴史と言われるのは、糸井重里による明星の中華三昧のCMのキャッチコピーなだけで、その少し前にはラーメンマン(キン肉マン)は中国三千年の歴史と言っているそうだしかし中国では五千年の歴史と言ってるそうで中には四千年とか、三千年といった意見もあり日本の127才で亡くなった神武天皇同様に伝説なんだか実在したんだかわからない王朝があったからハッキリとはしないのだそれだけに実際に出土する文物によって、歴史の真実を知る事は重要である。その歴史の始まりは長江文明、黄河文明、遼河文明で、五千年説での盤古、女媧、伏羲と、三皇五帝の神話時代となる更には・・・夏(紀元前2千年~紀元前17世紀頃)で四千年説殷(商)(紀元前17世紀頃~紀元前11世紀頃)周(紀元前12紀頃~紀元前256年)春秋時代(紀元前770年~紀元前403年)戦国時代(紀元前403年~紀元前221年)秦(紀元前221年~紀元前207年)始皇帝前漢(西漢、紀元前206年~8年)劉邦(高祖)新(8年~23年)後漢(東漢、25年~220年)三国時代(魏、蜀、呉。220年 ~280年)晋(265年~420年)西晋(265~316年)司馬炎(武帝)東晋(317年~420年)五胡十六国時代(304年~439年)南北朝時代(439年~589年)北魏、東魏、西魏、北斉、北周、宋、斉、梁、陳隋(589年~618年)唐(618年~907年)武周五代十国時代(907年~960年)後梁、後唐、後晋、後漢、後周の五代呉、南唐、閩、呉越、荊南、楚、南漢、前蜀、後蜀、北漢の十国宋北宋(960年~1127年)南宋(1127年 ~1279年)遼、西夏、金元(1271年 ~1368年)明(1368年 ~1644年)南明清(1616年~1912年)太平天国、満州国中華民国(1912年~1949年)中華人民共和国(1949~)といった感じで、↑ウィキペディアより国名をひろってみました。日本(倭国)は前漢の前2世紀頃あたりから登場し、後漢では委奴国王印、三国志の魏志倭人伝には卑弥呼、宋書には倭の五王が語られているそして遣隋使に持たせた書には、日出處天子日本との国名となっての遣唐使派遣によって多くの留学生や留学僧が唐の先進文化を吸収唐の開元通宝を元に和同開珎の鋳造が始まり平城京は唐の長安を手本に整備をされた遣唐使のような大々的な交流はなくなっても朝廷は大宰府で、私貿易(密貿易)は博多や敦賀で続き、平氏が台頭をすると日宋貿易を盛んに推進し、大量の宋銭が日本に流入して日本は貨幣経済の時代を迎え、栄西や道元らの禅宗や、茶もこの時期に日本に伝えられた室町時代には勘合符を遣明使船に所持させる勘合貿易が行われ、日本からは硫黄、銅などの鉱物や、扇子、刀剣、漆器、屏風。中国からは永楽通宝、生糸、織物、書物などが輸入され北山文化、東山文化に影響を与えたそうだ江戸幕府による鎖国で、朱印船貿易は終焉を迎えたが、清はオランダ、李氏朝鮮、琉球、蝦夷地と共に出島や対馬、琉球、松前を通し定高貿易を行った。そして幕末から明治へと日中は激動の時代を迎える日本に渡来して様々に工夫、応用はされても根底は同じなので、正倉院とか奈良京都の寺などで見る文化財と同じようなものが並んでいる。それは中国から伝来したものもあれば日本で作られたものも正倉院で保管をされている螺鈿紫檀五絃琵琶は制作をされた中国にも現存しておらず、世界で唯一、日本の正倉院だけに現存している超お宝だそうで、玄宗皇帝の頃のものらしいのですが天皇家の御物であるので、国宝などには指定をされていないそうです天皇家の御物は宮内庁の管轄で、国宝などの指定は文化庁で、そもそも所管が違う事もあるそうですよ。独身の頃には何度も正倉院展を観に秋の奈良まで出かけたが、最近はご無沙汰鳥毛立女屏風は、一度は観てみたいと思うがちなみに東大寺の正倉院は、聖武天皇の冥福を祈り、光明皇后が大仏に寄進した聖武天皇遺愛の御物や、大仏開眼会に使用された仏具や東大寺境内図等の地図、古文書類、生薬などが納められ大半が奈良時代もしくは、中国唐代の優れた文物ばかりである東大寺に奉納され、東大寺の正倉院に収められていたものが再び、天皇家の御物になったのはこのブログでも何度も紹介をした、明治幕府による廃仏毀釈。これで東大寺の財政も悪化、存続すら危ぶむ事態に、東南院という付属院家の宝物と共に、正倉院を天皇家に献納したからです江戸幕府に仕える立場だった寺院に反感を持った地方の神官や国学者などが扇動し、廃仏毀釈の運動は激しさを増し、江戸期に石高の高い奈良の八つの大寺院のうちの三寺院が完全に破壊され一寺院が神社になり、存続出来たのは東大寺と興福寺、法隆寺、吉野蔵王堂の四寺院となった聖徳太子所縁の法隆寺は、堂宇や仏像の破壊こそ免れたが、経済基盤である寺領を取り上げられて僧侶たちの日常生活もままならず、貴重な古文書をかまどの焚きつけに使うような有様だったそうで宝物の多くを売りに出す古寺もある中で、法隆寺は貴重な宝物類を皇室に献納する道を選んだその時に1万円札にも使われた有名な聖徳太子の肖像画も御物となった。献納によって1万円が下賜され、当面の維持基金となり法隆寺は存続出来たのだ。皇室に献納した宝物は300点を超えその殆どは「法隆寺献納宝物」として、東京国立博物館で見学ができるしかし、この廃仏毀釈でどれだけ沢山の宝物が破壊され、流失した事か。それ以前に戦乱とかに巻き込まれて、焼失したものもあるだろうし昨春の韓国旅行でも、李氏朝鮮によって儒教が尊ばれ、仏教は廃れ、多くの仏画や書物などが売られて日本に渡ってきたと紹介をしたが中国でも日本や李氏朝鮮のように、大規模な廃仏が行われ、各皇帝の廟号や諡号をとって三武一宗の法難と呼ばれている。北魏の太武帝(在位423年~452年)太平真君年間北周の武帝(在位560年~578年)建徳年間唐の武宗(在位840年~846年)会昌年間後周の世宗(在位954年~959年)顕徳年間ウィキペディアによれば>寺院の破壊(但し、必ずしも施設の破壊を>意味する訳ではない。一般施設や住居に>転用される場合が多い)と財産の没収、>僧の還俗であり、(中略)銅(貨幣の>材料)や鉄(武器の材料)という金属を>中心とした物資を仏寺中の仏像や梵鐘>などから得ることも、当時の情勢から>して、差し迫った問題であった。軍事面>でも、出家して軍籍から離脱する国民が>大量に出ることは、戦乱の時代にあっては>痛手であった。(中略)当時の割拠政権に>とって、そのような膨大な人口を再び国政に>戻すことは、必要に迫られた事情であった1960年代の文化大革命では、極端な弾圧と破壊が行われたが、現在は中国政府は文化大革命の非を認めて、再び保護政策に戻っているそうで、仏教寺院は荒れ果てていたが華僑などの援助によって沿海部を中心に復興を遂げているそうである中国仏教発祥の古刹の洛陽の白馬寺では後漢時代から残る仏像を壊し、千年以上前の仏典を焼かれ、明の万暦帝の墳墓やなんでも鑑定団でも、よく名の出てくる景徳鎮の窯が破壊をされたそうだ。ここにも景徳鎮の壺などが沢山、置かれていたそうそう中華民国の台北市にある国立故宮博物院に、中国の至宝がわんさか所蔵されているのは紫禁城にあった宝物を、蒋介石の国民政府(1948年からは中華民国政府)が戦火から守るべく重要文物を疎開させて大戦後も、国共内戦が激化し中華民国政府の形勢が不利となった為に、第一級の所蔵品を精選した文物、台湾へと運び出した為である白菜や肉片、一度は観に行きたいとは思うのだけど日本に来日した時ですら行けなかったこのあたりになると、もはや隅から隅といった見学などできず、重要そうだなぁと思われる中央部のものをさら~と流す感じで時間に追われる。もしもフリーで来てたら3時間はいたに違いないでも団体旅行なので1時間も見学時間がないのはキツイです。どこか重点的にでも観ればいいのに、来た限りはとりあえずは全分野を網羅したいといういつもの本能が働いてしまうので頑張りました。全室制覇コメントなどでも伺えるように、中国イコール中国人。今も昔も中国人のひとくくりに考えておいでになる方が多いようですが、今の中国は広いです長い年月の間には様々な王朝があって同時期に、幾つもの王朝があるというのは同じ民族が覇権を争っているという場合も中にはあるかもしれませんが、広い中国である故、様々な民族があり時には国を統一したり、国を追われたり今の中国は漢民族が主流ですが、清王朝を支配した愛新覚羅家は満州族ですし、ここ上海あたりを支配していた呉の呉人たちは国が滅亡した事で、沢山の人が日本に渡ったなんて説すらもある現在の中国が過去の中国全土(にあった国々歴史)を継承している訳でもなく、全く同じものでは無いという事だ。更に今の上海には中国にいるという、55の少数民族の全てが集まっているんだとか優れた美術品や、歴史的に価値のある文物なども見応えがありますが、こういった民俗学的なの好きなんですわ~。もう時間も残り少ないというのにワクワク♪ すごい細工の工芸品で見飽きない5分前になったので、後ろ髪を引かれる思いで集合場所の1階のロビーに戻ると、うちがたぶん最後だったと思ってたら、トイレから戻られたお父さん。人数が少ないので時間前にはみんな揃って、早めに移動もできる初日の上海の紹介は終わり、次回から次の日の無錫と蘇州ですが、上海市内の観光は最終日の三日目にもまだ残されている 旅は無錫へと 平成31年1月26日に上海博物館で撮影にほんブログ村
2019年02月19日
閲覧総数 433
-
4

宮さん宮さん♪ お馬の前でひらひらするのはなんじゃいな
あの猛暑は嘘のように、ここにきて一日、一日 日増しに秋らしくなってきて、今朝は部屋の中は 22度で、ハムスター(以前、飼っていた)の適温 ではないか。これくらいがちょうど良いのにな さて、京都の夏の旅の続き。午後にバスが横付けを したのは、享和3(1803)年に、京都西陣において 初代伊兵衛によって創業した、老舗「鶴屋吉信」だ バスガイドさんいわく老舗は、暖簾(のれん)が命 火事などでは、暖簾を抱えて逃げると言われており 四季折々に変えたりもして、まさに店の顔でもある 近代的なビルの上階で喫茶が出来て、茶室も誂えてあり ツアーの方の為に、特別に用意をされたという「菊華」を 頂戴をした 無論、お買いものタイムも用意されてあるので、お店自慢の 「京観世」「柚餅」など伝統のお菓子や、新作のお菓子も 試食も自由で、あれやこれやと一口ずつ食べ比べも出来た (観光バスで来店のみの、試食サービスかもしれません) 京都では「お配り饅頭」といって、花嫁を知人に紹介する 時に、腰高のお饅頭に花嫁の名を添えるそうで、純白の 饅頭はお嫁に来た家の家風に染まって、家を護る決意を 示しているといわれる 更に饅頭のようにまるく和やかで、円満な家庭の幸せを 築くという心構えを込めるとか。最近は紅白の饅頭も多い その始まりは、江戸時代の元禄享保の頃に大奥で鑑賞された 献上菓子であるそうで、明治になって、白砂糖が輸入されて 生砂糖(雲平生地)の細工菓子の製法がて、特に京都の 飾り菓子が有名になった と言うわけで、この大輪の菊はお菓子です 更に御所車をあでやかに飾る花も、菓子で出来てます 有職故実(朝廷や公家の礼式・年中行事などの先例や 典故による儀式典礼)や、有名社寺の伝統の祭礼や 儀式の為の供餞菓子、茶の湯に使う茶菓子などという ように、京都の和菓子は磨きぬかれてきたそうだ 明治8(1875)年に、米国聖公会から派遣をされた 米国人教師が大阪で始めた女学校がその始まりだそうで 明治28(1895)年に京都移転をして、平安女学院と して開校し、大正9(1920)年には日本で初めて 制服としてのセーラー服を採用したそうである 京都御苑の真横に、明治31(1898)年に平安女学院の チャペルとして建設された、レトロな聖アグネス教会があり 平安女学院の守護聖人で、ローマ皇帝ディオクレティアヌス 統治の時代にローマで殉教した聖アグネスにちなんだ名前だ 教会のある平安女学院京都キャンパスは、後期の室町幕府の 政庁が置かれ、第14代足利義輝、第15代足利義昭らが 旧二条城を築いて幕府を運営していたという そのお隣にあった古いお屋敷は、長らく裁判所の官庁宿舎で あったのを、平安女学院が買い取って「有栖(ありす)館」と 命名をされ、茶道など女学生の授業に利用をされている そのお屋敷も夏の旅で特別公開をされており、お邪魔をしたが なにゆえ「有栖(ありす)」であるかというと、そのお屋敷は 幕末のヒロインの和宮親子内親王の元の許嫁(いいなずけ)で 十五代将軍徳川慶喜の追討軍の総帥であった、有栖川宮 熾仁親王で有名な「有栖川(ありすがわ)宮」の邸宅だからだ 十五代将軍徳川慶喜の生母の登美宮吉子は、この有栖川宮家の 出身で、熾仁親王は吉子の甥にあたり熾仁親王と慶喜は従姉妹 同士でもあった 官軍の軍歌であるトコトンヤレ節で歌われた「宮さん宮さん お馬の前でひらひらするのはなんじゃいな」の宮さんとは この有栖川宮熾仁親王でもある。 前述の閑院宮や伏見宮、桂宮と並ぶ世襲親王家の一つである 有栖川宮は歴代、書道・歌道の師範を勤めて皇室の信任も 篤かったのだが、大正12(1923)年に後継ぎが無くて 廃絶となった。ところが近年になって有栖川宮の継承者と 勝手に名乗る人物が現れた、有栖川宮詐称事件で騒がれた 初代の好仁親王の時代から京都御所の北東部分にあたる 猿ヶ辻と呼ばれた場所に屋敷があったが、幟仁親王の頃 慶応元(1865)年に、御所の拡張で召し上げられて 今の京都御苑内で、直前まで松平容保が宿舎としてした 凝華洞(御花畑)跡に、明治2(1869)年に新御殿が 落成をした ところが明治5(1872)年に、明治天皇からのお呼び 寄せによって、幟仁親王も東京へ転住をされる事となって 宮邸の土地と家屋は、京都府に引き渡し裁判所として使用を され、この建物の一部を移築したのが「有栖(ありす)館」だ さすがに宮家のお屋敷。その造作は素晴らしく釘を隠す装飾の 「釘隠し」や、天井を高く見せる為の幅の狭い「蟻壁」とか 菊の紋が入った襖の引き手など見どころも多い 能舞台として使われた「板張りの間」があり、裁判所の所長が 住んでいた時代には、知り合いの歌舞伎役者や芸能人などと 板張りの間宴を催していた事も。能舞台の床下には音響効果を 上げる為に甕(かめ)が埋められているそうだ 平安女学院が購入した時には、庭の草木も荒れ果てていたので 平安女学院の客員教授で、江宝暦年間から250年もの間 平安神宮や円山公園などを作庭してきた造園業「植治」の 11代目当主の小川治兵衞氏によって、現代の名庭が出来た 烏丸通りに面した門は、明治45(1912)年に三井財閥の 総長の三井高保氏が邸宅の表門として築いたもので、後に 裁判所が購入し、昭和27(1952)年に裁判所所長宿舎の 表門として現在地に移築をされた。当時の所長と親交のある 歌人の吉井勇が、李白の詩から「青天門」と命名をしたそうだ その門の脇の見事なしだれ桜は、昭和27(1952)年に 画家の堂本印象のアイデアにより、豊臣秀吉が醍醐の宴をした 醍醐三宝院の「実生(みしょう)の桜」を分譲移植したもの そんな訳で京都のお土産には、京都駅で購入した「阿闍梨餅」 (満月)と、「嵯峨野若竹」(京菓匠鶴屋長生)と、もちろん お邪魔させていただいた鶴屋吉信の「御所氷室」もお土産に 平成22年9月5日に京都で撮影
2010年09月16日
閲覧総数 88
-
5

「国宝・源氏物語絵巻」
11月4日の夕焼け 千年もの昔、紫式部によって、光源氏の様々な女性との 恋愛遍歴と、サクセスストーリーが、美しくも哀しく 描かれたという源氏物語は、少女マンガや、幾多の 芝居にもなり、知らないという日本人は少ないと思う 与謝野晶子、谷崎 潤一郎、円地文子、瀬戸内寂聴と いった作家によって、現代語訳をされているので 読まれた方いると思う。私も通しで2度ほど読んだ この物語で、後朝(きぬぎぬ)の別れや、亥の子餅 物忌み、生霊、青海波などの様々な王朝アイテムに 触れるきっかけになり、殿上人日記といった気取った ブログタイトルも、この源氏物語、そして藤原道長らに より繰り広げられた、華やかで、おどろおどろしい 王朝絵巻に魅かれてのことだ 澪標(みおつくし)、初音(はつね)など、巻名がまた いい。巻名だけの、雲隠(くもがくれ)は効果的だなぁ 源氏物語がここまで有名な要因には、華麗な絵巻物が 現存をしている事も見逃せない。ぽっちゃりと下ぶくれを した顔に、ちっちゃな目、雛人形のような風合いの 「源氏物語絵巻」は、白河・鳥羽上皇の院政期 (12世紀前半)に、制作をされたものと思われる 原作の54帖から、1帖につき1~3場面を取り上げて いたと考えられ、現在は、 絵巻は、絵と詞書が1面ごとに 切断をされてしまい、絵15面・詞書28面が徳川美術館 絵4面・詞書9面を五島美術館で、所蔵をされている 徳川美術館では、例年ほんの少しを、この時期に公開を していますが、両館において、それぞれ10年に1度だけ 『国宝・源氏物語絵巻』 全巻・全面(絵・19面、詞書 ・37面≫を公開をしており、徳川美術館においては 平成7年以来10年ぶりの公開(五島美術館の公開以来 5年ぶり)の公開が、明日から始まる(12月4日まで) NHK総合放送では、全国ネットで、源氏物語の復元などの 特集「よみがえる源氏物語絵巻・浄土を夢見た女たち」が 23日(水・祝)午後9時15分から、放映予定だそうだ 詳しい内容は下記サイトで http://www.nhk.or.jp/nagoya/event/genjiemaki.html
2005年11月11日
閲覧総数 80
-
6

景福宮と、カチカラスと、骨付きカルビと、真央ちゃん!
さて、私は22日に韓国に行った訳ではなく 早朝出発は家族に迷惑をかけ、そそっかしい 姉がパスポートを家に忘れても、取りにいける ように、名古屋駅前で前泊をしました 美味しい夕食を食べ、名古屋駅のライトアップも 楽しみ、新幹線の改札前を通ると、すごい人ごみ カメラもきてるし、午前中に成田空港に着いた フィギュアスケートの新星、浅田真央ちゃんだぁ~! もう間近でお迎えできました。なんだか幸先がイイ 5ペアのところ、キャンセルをされた方がいた ようで、4ペアが現地で集合。当日は日本語の とっても上手な、現地ガイドさんに連れられて 昼食と、午後からの半日観光に向いました ソウル市内にある5大王宮の中で、最も規模が 大きく、李氏朝鮮時代の正宮だった「景福宮」での 観光がメインです 景福宮は、1394を年(太祖4年)に創建され 現在は国の史跡第117号に指定されている古宮で 勤政殿、慶会楼、慈慶殿、慈慶殿十長生煙突など 数多くの文化財(国宝7点、宝物11点)があります 「景福」とは、「詩経」に出てくる言葉であり 王とその子孫や、すべての百姓が、太平の御代の 大きな幸せを得ることを願うという意味だとか 景福宮は、秀吉による文禄・慶長の役で全焼し 1865年(高宗2年)、興宣大院君が再建に着手 3年後に創建当時の規模に復元をし、7月には 「昌徳宮」から、王宮を移転をされました 1910年、日韓併合によって、勤政殿など 10棟程を残し、そのほとんどの殿舎が破壊を されてしまい、日本帝国が、勤政殿の南側正面に 朝鮮総督府庁舎を建立をしました 1991年より「景福宮復元事業」が始まり 総督府の建物が完全に撤去をされ、復元工事が 今も続いています 「禁軍」という王宮の警備を管掌し、大殿を 護衛する軍隊の儀式を再現をした「王宮守門将 交代式」というイベントを、ちょうど見ることが 出来ました 韓国の国鳥であるカササギを、何度も見る機会が ありました。カササギは、珍しい人物やお客さんの 出現を知らせる鳥で、お正月の夜明けに一番先に カササギの声を聞けば、その年は「運数大通」の 吉鳥とされています 豊臣秀吉の朝鮮出兵をしていた時、佐賀藩祖の 鍋島直茂がこの鳥を気に入り持ち帰り、佐賀で 広く生息をするようになり、 その鳴き方が 「カチカチ」と聞こえるので「勝ち」とかけて 「カチカラス」と名づけたそうです 国立民族博物館では、庶民や、貴族などの生活や キムチのつけ方、子供の遊び、結婚式や葬儀など 様々なお勉強が出来ました その後は免税店ですが、行った事が無い所だった のでけっこう新鮮。でも、買う事は、今回も無し 見るだけでした お昼ごはんは、今回もビビンバ。お昼の団体の 定番ですね。ま、手早く、安く済ませられるから 夕食はホテルの近くで、やっぱりソウルフードの 代表「骨付きカルビ」を、清酒付きでいただき ましたよ~。日本酒に比べて甘口だなぁ こうして、一日目は終った!?・・・・いやいやホテルで 韓国ドラマを、0時40分過ぎまで観てましたよ お~、オールイン!のおやじだぁ~、宿敵のお兄ちゃんだ クラブのおばちゃんだ、おじちゃんだぁ(チャングムの 育ての父でもある) コッチの済州島のお姉ちゃんに、その意地悪姑は、また 目つき悪い~~!!なんて、見慣れた俳優さんに拍手!! いよいよ2日目、私は、なりゆきでイムジン河を 見に行く事になったのです ( 続く )
2005年11月26日
閲覧総数 49
-
7

ヨン様のソウルで、キムチ!
日が傾き始めてから、地下鉄を使い「南山ゴル韓屋村」に むかいました。ついた途端、韓国人のおやじ同士で すさまじい勢いで、口げんかをしてますよ。いゃ~ びっくりしました。迫力! 迫力! さて、ここはヨン様の映画「スキャンダル」では ロケが行われたところです。伝統的な韓国のお屋敷が 移築された上、無料公開をされています。団体もおり 外国人より、韓国の皆さんが多かったような 先ほどの南大門市場では、ヨン様&ビョン様の顔が プリントされた靴下や、マグカップ、手帳などを 「ファンなのに、ナゼ、買わないんですか~~!」と ガイドさんに山ほど言われたけど、そんなものを 買った日には、家族から総スカンですよ 映画やドラマの中では興味があっても、おっかけとか そうゆうのは興味は無いです。「スキャンダル」の 美しい衣装、怪しげな視線・・・思い出すなぁ~ 少し高台にあって、「美しき日々」でヨンスとセナが 再会を誓った「ソウルタワー」も間近にみえます 建物の話も無いし、話は変わりますが「キムチジャン」と いいまして、この時期の韓国は、キムチ作りの最盛期 らしいです。次の日に、人が行きかうような路上で 白菜を漬け込んでいた人を見ました。茶碗も路上で洗って いたし、路上は生活&商売の一部なのかと・・・・ ま、普通の家庭では、そんな事はされないと思いますが 大八車に、八百屋で買った山盛りの白菜を乗せた オバサンが、坂道を一生懸命に登っていましたが オモニ(お母さん)の号令のもと、娘や、嫁さんや 近所のおばちゃんらが集まって、キムチジャンに 精を出します ガイドさんも、姑さんから電話があって、週末は キムチジャンだぁ~と、話されていました 日本って、そうゆう家族での作業って、無くなって しまったから、なんだかうらやましいなぁ~ 地方によって様々なキムチがあり、南の方は イカなどの入ったキムチ。北の方は野菜だけの キムチなので、ガイドさんは南のキムチは苦手 だそうですよ ペチュキムチ 白菜キムチで、発酵が進んだキムチは 鍋などにも使われます ポッサムキムチ 白菜で、他の具を包むようにしたキムチ 王様のキムチとも呼ばれ、カキ、松の実など 豪華な食材を使用し、かつては上流階級 のみが、作ることを許されていた カクテキ 大根を角切りにして漬けたキムチ オイキムチ キュウリを半分に割って、唐辛子などで漬けたキムチ 水キムチ この後のお粥の写真にありますが、けっこう定食などで 出てきます。このお汁も美味しいですよ 歩いて「美しき日々」の明洞聖堂(教会)に、行く つもりが、あれぇ?、大きなビルの谷間を歩くうちに 気がつけば、ソウルの一番の繁華街「明洞」の 中心部に、迷い込んでいました 服や靴、雑貨、化粧品などファッションに関するお店が 低価格を売り物にする東大門市場とは異なり、韓国の 人気ブランドの他、世界的にも有名なショップが立ち 並んでいます 夕方ですから、会社や学校帰りの若い人たちで一杯です さて、おなかも空いてきたので、以前の旅行で使った 2003年版のガイドブックに紹介をしてあったお店に 行こうと思って、迷路のような路地を、左に曲がって 右に曲がって・・・・ あれ? 無い!? 小さなお店がゴミゴミと集まって いたような路地裏は、巨大ビルの建設予定地で 更地になっていましたよ~ 仕方が無いので、日本の雑誌の切抜きが貼ってある 小奇麗な「お粥」と「伝統茶」の店に入りました やっぱり、日本語が通じるとか、日本語メニューが あるのは安心が出来ます 地元の若い子達も何組も入っていて、繁盛をしてます 姉は「あわび粥」 一切れもらいましたが、いゃ~ 美味しいあわびです♪ 私は黒ゴマのお粥でしたが 白いお粥に、黒ゴマがぱらぱら~と思ったのに いやぁ、驚きました!「くどそう」と、心配でしたが 思いのほか、あっさりしてて美味しかったです ソウルも、町並みはクリスマスイルミネーションで 彩られていて、夕方になってからホテルを飛び出して ホント良かったですよ。こんなに美しいツリーを 見ることが出来たのですから そして、キラキラと輝く光のむこうには あの方の爽やかな笑顔が・・・ まだまだ、旅は続きます
2005年11月30日
閲覧総数 22
-
8

再びの桜島。鹿屋より飛び立ち零戦は空の彼方へ
永遠のゼロで宮部が、最後に飛び立ったのが大隅半島にある日本海軍航空隊の鹿屋特攻基地だった。この基地から南方へと飛び立った特攻隊員の数は908名にものぼり、数ある特攻基地の中で飛び抜けて多い人数であった飛行機による特攻隊は、前に紹介した薩摩半島の知覧のように日本陸軍のものと別に日本海軍のもあり神風特攻隊という。その名の由来は、蒙古襲来時に神風が吹いて追っ払ったという伝承に基づいてであるカミカゼ、もしくはシンプウとも言ったらしい日本海軍の神風特攻隊において一番使われたのが零戦。零式艦上戦闘機だ宮崎アニメでは設計者を主人公にした「風立ちぬ」もあれば、永遠のゼロなど様々なメディアでも取り扱われる機体だ開発者は三菱重工業であるが、日本海軍航空隊の主力となって、生産数が多いので中島飛行機も半分近くを作っていたそうだ生産数は1万機にものぼったそうだ。当時の軍用機は採用年の皇紀(神武天皇紀元)下二ケタを冠する決まりで、昭和15年は皇紀2600年なので00から零戦となった連合軍が付けたコードネームは、ジークだが将兵らはゼロとかゼロファイターと呼んでいた昭和14年に試作一号機が完成し、4月1日に岐阜県の陸軍各務原飛行場で初飛行に成功翌15年(皇紀2600年)に採用をされると、7月大陸戦線にて零戦11機が配備され、夏には実戦にも使われるようになった太平洋戦争の中期あたりまでは、零戦の卓越した性能が勝り、敵機を撃退し無敵とも言われるほどであった>アメリカ戦略空軍司令部作戦部長補佐代理>ジョン・N・ユーバンク准将は「ニューギニアや>ラバウルで我々が遭遇した日本軍は、本当に>熟練した操縦士だった>我々は最優秀の敵と戦っているのだという>ことを一時も疑ったことはなかった」と>回想している (中略)登場時こそ高性能を>誇った零戦であるが、後継機の開発が順調に>進んだ陸軍に比べ、海軍は後継機の開発が>うまくいかず、零戦は終戦まで主力機として>使用され、性能でもアメリカやイギリスの>新鋭機に敵わなくなった>戦争中盤以降アメリカ軍は2,000馬力級エンジンを>装備するF6FヘルキャットやF4Uコルセアなどの>新型戦闘機を投入するようになっていったが、>雷電や烈風など零戦の後継機の開発に遅れを>とった日本海軍は零戦の僅かな性能向上型で>これらに対抗せざるを得なかった。 ウィキペディアより転載しました そして飛行戦を行っていた零戦も、戦争末期には、熟練したベテランパイロットも戦死し、若い命を乗せて敵艦に突っ込む特攻兵器としての運命をたどる事となったこの零戦の機体は、1992年に引き揚げられた中島製ニ一型と五ニ型丙の二機の残骸から復元した機体で、機体の強度上の問題からエンジンは取り外して展示されている海上自衛隊鹿屋航空基地の敷地内にある鹿屋航空基地資料館(無料)には先程の零戦が展示され、これは撮影が出来るが、特攻隊員の遺品などは撮影禁止となっていた旅から帰ってから知ったのだが、更に屋外にも世界で唯一現存をするという二式飛行艇もあったのだが、遠くから見ただけだった。しまった、もっと近くにいって、じっくり見ればよかった。やはり旅の事前学習は必要だ旧日本海軍が九七式飛行艇の後続として昭和16年に初飛行、高い性能を持った傑作機で、空の戦艦とも呼ばれたそうだ通称は二式大艇、製造は川西飛行機だ戦争後に米国が残存機の性能試験をしてその高性能ぶりに驚き、飛行艇技術では日本は世界に勝利したと称賛した名機だ聞けば聞くほど、もっとしっかりと見て来ればよかったと思った。もう鹿屋に行く機会もないだろうに・・・。なんて事で、こちらは海上自衛隊の展示機US-1A(おおとり)緊急飛行艇。さっきの二式大艇の川西飛行機の後進である新明和工業製だT-6テキサンのSNJ-5練習機はノースアメリカン社のレシプロ高等練習機でその形からカラーリングを施し、零戦や九七式として映画で使用されていたビーチクラフトモデル18のSNB-4(米国のビーチクラフト社)ビーチクラフト社の設計で、富士重工(旧中島飛行機)がライセンス生産をしたT34Aメンター。メンターとはよき助言者、優れた指導者という意味だそうだロッキード社のP2V-7対潜哨戒機(後に川崎飛行機がライセンス生産も)米軍の愛称はネプチューン(海神)で海上自衛隊ではおおわしと呼んでいたグラマン社の艦上対潜哨戒機S-2。愛称はトラッカー(追跡者)。海上自衛隊にはMAP(軍事無償援助)として、S2F-1が数十機供与され、愛称はあおたかダグラスエアクラフト社のダグラスC-47は世界初の旅客機で愛称はスカイトレインノルマンディー上陸作戦など第二次世界大戦で輸送機として活躍をした。イギリス軍に供与された機体は、ダコタの名で運用されたアイゼンハワー大統領が「第2次世界大戦を勝利に導いた3つの兵器はジープ・バズーカ砲(対戦車用)そしてダコタ(C-47)輸送機である」と言ったらしい。海上自衛隊ではR4Dー6Qまなづるといって戦後に導入されたてな感じで、戦中から戦後にかけての軍用機をいろいろと見せて貰いましたが悔しいのはやっぱ二式大艇を近くまで行って、じっくりと見学をしなかった事先程、資料館内は零戦のみ撮影可能で遺品もあるので後は撮影禁止と言ったが海上自衛隊のブースは写真が撮れる鉄分一杯、気分もウキウキ。そうそう先週日曜日に、中津川へ買い物に出かけたら汽笛の音が。公園に屋外展示されているD51のイベントで汽笛を鳴らしたみたいだ郷愁を感じる良い音だ南極の石もあった。海上自衛隊の活動には、砕氷船「しらせ」による南極観測の協力もある昭和11年4月1日、日本海軍鹿屋海軍航空隊が創設され戦争末期は菊水作戦神風特攻隊の基地となり908名が出撃平成27年まで海軍航空隊本部時代の司令部庁舎も使われていたそうだ昨年1月27日には、パプアニューギニアで戦後に発見されアメリカ人コレクターが回収しロシアで修復した零戦が、日本人の所有となって里帰りプロジェクトを行い、この鹿屋の空を飛んだそうだ鹿屋を後にして錦江湾沿いに大隅半島を北上すると正面に大きく見えてきたのが桜島かつては名のごとく錦江湾に浮かぶ島であったのが、大正3(1914)年の噴火により陸続きになった今も頻繁に噴火活動をする活火山で展望所の入り口には注意書きもあったそして丈夫そうな避難所も、あちこちに今回は南岳の麓、有村地区の大正溶岩原に作られた展望所から桜島を眺めてみようと思う。一面に広がる溶岩原もまた見ものらしい東西約12キロ、南北約10キロ、周囲約55キロ面積約77kmの姶良カルデラの南縁に位置した火山で、このカルデラの2.9万年前の巨大噴火の3千年程後に誕生をした有史以来30回以上の噴火が記録に残されており特に文明、安永、大正の3回が大きな噴火だった文明3(1471)9月12日の噴火(VEI5)では北岳の北東山腹から、溶岩(北側の文明溶岩)が流出し多数の死者があった安永8(1779)年9月29日に大噴火が起き火砕流も流れ、火山灰は長崎や江戸でも降ったとか。一連の海底火山活動で燃島、硫黄島、猪ノ子島など6つの火山島が出来安永諸島と名付けられた大正3(1914)年1月12日午前10時5分桜島西側中腹から黒煙が上がり大音響とともに噴火が始まり、約1か月間にわたって頻繁に噴火が繰り返された。更に午後6時30分には噴火に伴いマグニチュード7.1の桜島地震が発生し大きな被害があった今もなお頻繁な噴火活動が続く桜島の御岳は筑紫富士と呼ばれているそうで筑紫は以前は九州を指していたそうだという訳で、本来なら鹿屋の屋外展示をした飛行機の写真の時に書こうと思ったけど、ついつい飛行機の説明に終始してしまったので桜島の写真をバックに、鹿屋基地から出撃した特攻隊の隊員の話を紹介したい。彼の名前は石丸進一。昭和20年5月11日に500キロの爆弾を抱えた零戦で、鹿屋基地を飛び立ち、沖縄へと向かって出撃消息を絶った佐賀市で理髪業を営む家の五男に生まれた石丸進一は、兄の藤吉の影響で野球を始め送球派エースとなった。兄に続いて名古屋軍(現在の中日ドラゴンズ)に昭和16年に入団し持ち前の速球と、針の穴を通すほどの抜群の制球力で大活躍をした昭和18年10月12日の対大和戦では戦前最後となるノーヒットノーランも達成をしたこの年は20勝12敗、防御率1.15と前年以上の好成績を収め、チームを2位まで躍進させた兵役を逃れる為に、大学に籍を置いていたが昭和19年春の学徒出陣で招集をされた石丸は海軍飛行科を希望し、筑波海軍航空隊に配属となり、昭和20年に神風特別攻撃隊に志願して特攻隊員となった。出撃前に同僚の本田耕一と、最後のキャッチボールを行って従軍記者だった山岡荘八(作家)が審判を務め「涙でよく見えなかった」という10球は全てストライクだったそうだ>藤吉が最後に会った時は「敵艦に体当たりして>轟沈(ごうちん)させる」と話す弟を、「そんなに>死に急いでどうする!」と諭したという。「兄さん、>そんなこと分かってるよ」――。それが石丸の答え>だった。出撃前、鹿屋基地では戦友に「死にたくない、>怖い」とも漏らした。兵舎の陰で泣いている姿も>あった。22歳。死の恐怖と必死に闘っていた。スポニチ記事 詳しくはこちらをお読み下さい↓戦前最後のノーヒッター神風に散った22歳・石丸進一の在りし日 平成28年11月16日に鹿児島県で撮影にほんブログ村
2017年08月09日
閲覧総数 915
-
9

イムジン河の向こうの北朝鮮と、南大門市場
共同警備区域(JSA)で有名な板門店は、なんだか 勇気が無くて、行く気持ちにはなれなかったので 臨津江(イムジン河)のすぐ向こう岸に、北朝鮮の村が 見れる「オドゥ山統一展望台 」は、規制やチェックも 無くって、簡単にいけるというので、オプションで 参加をすることにしました ソウルから、板門店に向う「自由路」は、将来は 韓半島が統一された暁は、板門店から開城、そして 平壌へつながる主要道になる事を、想定して いるそうです 韓国において、朝鮮という言葉は李氏朝鮮などを のぞいては使用はしないそうで、朝鮮半島ではなく 韓半島、北朝鮮ではなく北韓、朝鮮戦争でなく 韓国戦争と言うそうです 南北朝鮮戦争の休戦時に決められた、休戦ラインの 南北2km内のエリアであるDMZ(非武装地帯)は 一般人は立ち入りができない為、入るには厳重な チェックが行われています 臨津江(イムジン河)の手前側、韓国の人たちが 自由にいける「臨津閣」に最初に立ち寄りました 朝鮮戦争において、北から南に来た人たちが 帰ることが出来ない故郷を偲び、先祖を供養を する為に、大きな碑が建てられ、美しい故郷の レリーフが描かれていました 映画「JSA」の女将校の父親は、北の出身者 でしたが、ガイドさんの父方もまた、北からの 移住者だそうです。数え切れない人たちが北と 南に分かれることになり、故郷に訪れ墓参りも 親族に会うことも許されず、引き裂かれたままで あるという事を、ひしひしと感じるました 「自由の橋」は、朝鮮戦争当時に、戦時捕虜が 「自由万歳!」と叫びながら、この橋を渡って きたことから、名づけられたそうで、橋の北端は フェンスでさえぎられており、南北統一を願う 旗などが、数多く掲げられていました 臨津駅から、DMZ(非武装地帯)のすぐ手前の 都羅山(トラサン)駅へと向かう列車が走る橋が ありました。右側には、朝鮮戦争で破壊をされた 橋げたが、そのまま残されています 都羅山駅に、一日に3本運行をされているそうで 偶然、その列車が通りかかり、ガタンゴトン・・・と イムジン河の向こうから、どんどん大きくなる 列車の音は、暗く、重々しく感じました 漢江(ハンガン)と臨津江(イムジンガン)が 合流をする風光明媚なオドゥ山に、統一展望台が 作られ、川向こうに北朝鮮の開豊(ケプン)郡の 農村地帯を見ることができます 写真ではこの程度ですが、肉眼ではさらに近くに 見えて、有料の20倍の双眼鏡を使えば、もう 建物も大きく見えて、人間さえも見えました 井筒監督が映画「パッチギ!」で、京都の鴨川を このイムジン河に見立てて、在日朝鮮人の学生と 日本人の学生を通し、相手に近づき、相手の立場を 理解をする事の難しさを、語っていましたが この「イムジン河」は、北の人が作った歌だそうで 韓国では、あまり語るのは喜ばれません イムジン河 水清く とうとうと流る 水鳥 自由にむらがり 飛び交うよ 我が祖国 南の地 想いははるか イムジン河 水清く とうとうと流る 北の大地から 南の空へ 飛び行く鳥よ 自由の使者よ 誰が祖国を 二つに分けてしまったの 誰が祖国を 分けてしまったの イムジン河 空遠く 虹よかかっておくれ 河よ 想いを伝えておくれ ふるさとを いつまでも忘れはしない イムジン河 水清く とうとうと流る 南から故郷を思うように、北からもまた 故郷を思う人がいると思います。しかしながら 国家体制も、思想も違った、南と北が統一を する道は、長くて険しいものであるでしょう 南北の歴史や、北朝鮮の生活や、産業などが 様々な展示品によって勉強が出来るように なっています 売店では、北朝鮮の生産品を、韓国側が輸入を したというお酒を売っていたので、購入を したのですが、飲むのも勇気がいるなぁ~ そして、オプションのお昼ご飯は、プルコギでした 肉や野菜に味噌をつけて、葉っぱに包んで 食べるのは、カルビと同じ。肉汁は、ご飯にかけて 混ぜ混ぜして食べるのが地元風らしい 午後、ソウルに戻ってからは、南大門市場に 連れて行ってもらっての、お買い物タイム! 崇礼門(南大門)は、1398年に創建をされ 1448年に改築された、韓国で最も規模が 大きな城門であり、そして最も古い木造建築物で 国宝1号にも指定されたソウルのシンボルです 600年もの歴史を誇るソウル最古の市場である 南大門市場は、キムチや海苔、高麗人参などの 韓国食材、そしてメガネ、革製品、アクセサリー 時計、子供服、お土産・・・生活感のある市場です ガイドさんに連れられて、無事にひまわりチョコも 韓国のりも、ゆず茶もゲットできました♪ 姉は 帽子が素敵だといわれ、25000ウォンを ガイドさんが値切って20000ウォン。帰りの 飛行機の中でよくよく見たら日本製! そりゃ 品質が良いわけだ で、日本の量販店で買った2000円均一の カットソーは、やっぱ韓国製なのでした(笑) ホテルにもどったら、まだ4時前。こりゃ、まだ ホテルにしけこむ時間でもないし、南大門市場で 買い込んだ荷物を降ろし、街に繰り出すぞ~! 続 く ・・・
2005年11月28日
閲覧総数 234
-
10

年を越してもかっこええわぁ~、ニッキーに夢中♪
↑歩歩驚心(宮廷女官若曦)予告編(なぜか2つ入ってます)ご存じ日本人の父と台湾人の母との間に生まれ日本国籍を持つ金城武とか、林志穎(ジミー・リン)、蘇有朋(アレック・スー)と並んで「台湾四小天王」と呼ばれていた台湾の俳優「呉奇隆(ニッキー・ウー)」と、中国女優の「劉詩詩(リウ・シーシー)」が共演をして大ヒットしたのが「宮廷女官 若曦(じゃくぎ)」だがBSジャパンで昨年放映をされていたのを見て、メチャはまる ↑主題歌に合わせて、美しい場面カットの数々が見れます現代からタイムスリップをした女性と、清の康熙帝のイケメンな皇子たちと織りなす恋模様というか、血で血を争う後継争いが繰り広げられて否応なくそれに巻き込まれていってしまうので決して女性向きの恋愛ものではなく、歴史政争劇としても面白い↑宮廷女官若曦のNG集が、私としてはやっぱニヒルな第四皇子(ニッキー)もいいが優しい十三皇子もいいなぁ~♪と、やっぱ目当てはそっちかい!連続ドラマはタイムリーで見れるかわからないので、録画したものを後日見て削除をしてるのですが、これに限っては削除などとても出来ないしっ DVDに焼くか(やった事ないけど)↑歩歩驚情(続・宮廷女官 若曦~輪廻の恋)予告編そんな人気ドラマだけに、続編も出来てBSジャパンで見る事も出来たのだが、第四皇子が現代に生まれ変わり若曦(実は張暁)と出会い・・・っていうの話で、清朝同様に大企業で後継者争いを繰り広げるのだが、中国ドラマなのに韓国ドラマ並みのぐちゃぐちゃ復讐劇。交通事故あり~の、出生の秘密あり~の、記憶喪失~誘拐&監禁と、あまりにもどよどよ~泥沼過ぎて、閉口(汗)↑犀利仁師(トキメキ!弘文学院)予告編あぁ、やっぱオリジナルがいいわとか思っていた矢先に韓国ドラマトキメキ成均館スキャンダルみたいな日本語タイトルの時代劇で↑のリウ・シーシー(若曦)、ニッキー・ウー(第四皇子)が別の役でBSジャパンに降臨(現在放送中)。全く別作品なのに宮廷女官若曦を意識したセリフや、場面もあったりで面白い↑ニッキー・ウーの歌唱に合わせ、美しいカットの数々恋愛色もさほどなく泥沼もなく、痛快学園コメディものでの師範役ニッキー・ウーもおちゃめで、コメディがすんごい似合っているし髪型も今までの中で一番お似合いかも。ネットによるとここ半年で4回も日本に来日をする程、日本が好きだそうで更に好感度アップ!ユーチューブの動画リンクタグは、文字数が少なくて済むのでまだまだ日記もかけるので後半はお蕎麦の話題でも。昨年末に数回は松本付近で食べたお蕎麦で、↑の松本のお蕎麦屋さんも旦那と、娘と、私だけでと出かけたが年を越してお正月になっても初お蕎麦で、また同じ店へ。そば粉で200g麺になれば300gのお蕎麦、500円を旦那と各々に頼む300円の野菜天ぷらは、二人で分けた1月2日のランチだ次の日3日には国道19号沿いにある「親父のそば 息子のうどん」の看板が前々から気になっていた塩尻の「めん喰い処 宗月」に出かけたなんだか、そこかしこでにゃんこにこだわってもいるお店のようだブログもねこネタが多い模様さすがに蕎麦はいいやと、旦那は息子の打ったうどんを注文お袋の味の五平餅というのもあったので、それも頼んでみた私は親父の打ったそばを注文した。塩でも食べて下さいと塩もあった流石に私も最近の蕎麦三昧で、当分はもういいかなぁ~。ここの蕎麦の価格は一般的だったなんでも蕎麦の一大生産地の北海道が不作で、中国も蕎麦よりももっと儲かる作物に乗り換えたので、そば粉が不足しており価格も全般的にあがる可能性も年末に近くのスーパーで懸賞があったので、旦那が買い物をした姑に頼まれて応募券を書いて応募をしたら、千円以上もする郡上八幡の「明方ハム」があたったウィキペディアより>現在明宝(めいほう)ハムと明方(みょうがた)ハムの両方が存在>する。元々は同じ物であった。明方村(後の明宝村、現郡上市)が>中心となって展開しているのが明宝特産物加工株式会社が製造する>明宝ハムであり、めぐみの農協が中心となって展開しているのが>明方ハムである。明宝ハムは全国的に流通しているが、明方ハムは>その殆どが岐阜県内でしか流通しない年末に娘の車のお世話になっている車屋さんで、福袋を貰ったと紹介したが、旦那や私、息子の車がお世話になってる地元の車屋さんからも福袋を貰った。どちらにも偶然か大人のきのこの山と、たけのこの里旦那が軽トラを欲しがっているので昔、私の車を買った車屋さんに行ってパンフレットを貰ったらお菓子もくれた。10年も付き合いのなかった客だけど、ちゃんと店長さんが顔を覚えてたようだその日は久しぶりに、モヤシやスプラウト野菜生産をしている市内のサラダコスモの「ちこり村」へも寄ったちこりは、ウィキペディアによれば>葉や根には独特の苦味があり、肥培した株から出させた芽を>暗黒下で軟白栽培したものを、主にサラダとして賞味するほか、>根を炒ったものをコーヒーの風味づけや代用品にも使うちこりにはイヌリンとラクチュコピクリンという成分が含まれイヌリンは血糖値 の上昇を抑制するなど、整理作用が期待され欧米では糖尿病患者の食事に用いられているんだとか。生での試食もできるが ちこりから生まれた原酒を6年間貯蔵をした数千円もする高級焼酎「初垂(はなたれ)」を、ドイツのグラスで試飲させて貰いました冷凍庫で冷やしても凍らないという飲み方の試飲も♪海外からの農産物の輸入もしており、マカダミアの実もこの器具で割って、試食ができたお昼は王将へ、昨秋に円安などによる材料費の高騰で、メニューの大半を23年ぶりに値上げしてからの初来店となったが、やっぱり以前よりは高くなったイメージも 写真は平成27年1月初旬に中津川&松本、塩尻で撮影
2015年01月12日
閲覧総数 401
-
11
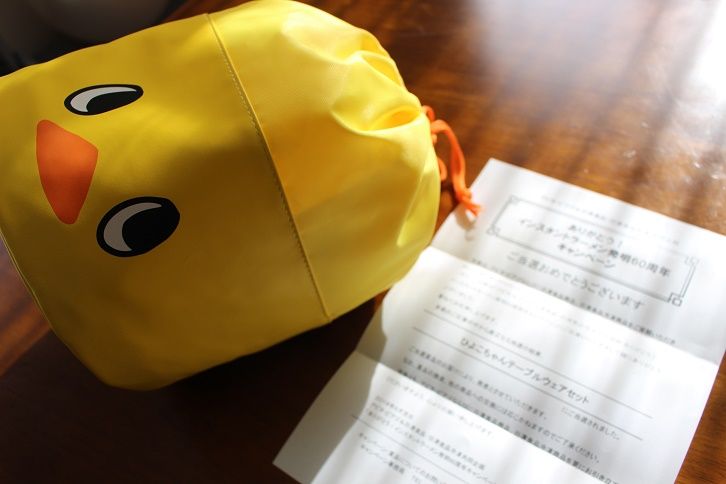
10年ぶりに懸賞復活。100日間での成果は如何に?
ふとテレビのチャンネルをかえて、偶然やっていたのが「10万円でできるかな」の、懸賞1万通応募スペシャル。はがき1万通ともなれば10万円どころか、ハガキ代だけで数十万円はするけど10万円程度のハガキじゃ、目ぼしい結果が出ない恐れがあるからだろうけど懐かしい~。20年前に日本テレビ系列で放映していた電波少年的懸賞生活をしていた、なすびなども参戦している。それまで雑誌のプレゼント位は応募していたが私だが、実はその番組を見た事で、本格的に懸賞を始めたという経緯がある時は1998年夏。もう20年前なのか番組で触発されて、お盆休みで家族で出かけたお伊勢さんの内宮のおかげ横丁にある郵便局でお伊勢さんのイラスト入りハガキを購入して東海テレビ(フジ系)と、CBC(TBS系)の情報番組の視聴者プレゼントに応募をしたらどちらもが当選それからは色んな懸賞に手も出して、僅か3ケ月程で、8月の伊勢旅行で立ち寄ったスペイン村の懸賞に、旅での思い出なども書いて応募をしたらスペイン旅行ペア招待という大物も当選をして約10年間にわたって、海外旅行ペア招待7回10万円旅行券、車購入費50万円引を始めとし自転車3台、マッサージチェア2台、DVDレコーダー2台、ANA5万円利用権、テーマパークパスポートやスポーツ&舞台のペア招待、ペア宿泊券などなど数知れずといった感じで、我が世の春を謳歌していたのだが、10年位前に娘が大学入学もして一人暮らしを始めた事で、私もよく出かけたりもしてどたばたやっているうちに、懸賞もめんどくさくなってやめてしまったそれに以前は懸賞の情報も興味のある人が、何かで調べたりしなきゃ手に入らなかったし、はがき代もかかるしって、限られた人たちのものだったけど最近はインターネットで簡単に懸賞の情報も手に入れられて、無料でネットから応募も出来るので沢山の人が気軽にできるので、簡単に当選も出来なくなったような気もしたしとは言っても例のバス旅行招待とか、ドラゴンズの観戦チケットとか年に数度は、よほど興味があるものには応募もしてはいたけど。。。そんなんで月日も流れた今夏。近所の奥さんが「○○ちゃん(私)に触発されて、懸賞に応募したら羽生君のフィギュアスケート当たったから行ってきた~♪」と言われて、えぇ? それって・・・羨ましいなんか沸々と私の懸賞魂に火がついて、今年の夏から、再び懸賞生活を始めました。専らスーパーでお買い物をしてレシートで応募をする「クローズド懸賞」が殆どなので、当選品もスーパーの商品券(3千円、2千円、千円)が大半だったりするこのメーカーと小売店のタイアップ懸賞だが色んな条件が混在しているので非常に面倒だAメーカーの商品を入れ千円以上のレシートというのも税込みと、税抜きというのもあるAメーカーのB商品を入れた上で、Aメーカー500円を入れた2千円以上のレシートとかAとBのメーカーそれぞれ1つずつを入れて更に野菜だか肉も購入した千円以上のとかもう何が何だか。更に会員5%オフ日では5%引かれてもいいように余分に購入をする必要もあるし。対象商品購入費と切手代を引いても、それなりに収穫もあるので旦那が、春から高齢者再雇用で収入が半減もしたので、こんな形でも実収入を増やすのは重要だけど、旦那自体は懸賞の為の買い物はすこぶる嫌がる。今も昔もいくら懸賞だろうと必要じゃないものは、購入をしないんだけど日持ちのするモノなど、ちょっと余分に購入をするのでストックが増えてたりすると、懸賞の為にまた買って!と叱られる。秋なので新米プレゼントも多いようだ。うち農家だけども古い保有米ばかりを食べて、新米を食べれるのはお正月と来年の早春から。しかも岐阜産こしひかりばかりだしスーパーなどで、ブランド米を購入する事も出来ないし、他の産地の新米を食べれるのはかなり嬉しかったりするのだ。この福井産の新米コシヒカリも美味しかった~!20年前に懸賞を始めた夏に、応募して初めて当たった、東海テレビ(フジ系)の番組。その後続の情報番組では名古屋のデパートで開催をされた北海道物産展の中継での食品の詰め合わせが当たった更には後日の番組内で、コメントが読まれて記念品も届いた。こういったテレビ番組でのプレゼントも最近は多いし、見ている人限定だったりするのでオススメだその中でも、全国区のフジ系のめざましテレビはよくローソンの商品が大量に当たるものをしてて最近はダメだけど、今夏のカフェオレが当たるという7月の週には2回当選そして8月に至っては、月曜日から水曜日まで3日連続で当選し、1日あけて金曜日朝もまた当たるという入れ食い状態だった毎日のようにアイスカフェオレを飲みにローソンへ・・・。あの後のスイーツや塩オニギリのはかすりもしない。あの夏なんだったんだろ。応募者も増えたのかなクイズで当たるといった「オープン懸賞」やメーカーが新製品の販促などの為に大量に当選させるといったものは、最近はネットを利用した懸賞が主流になってきたようだ私はスマホのラインで大手企業と、お友達登録をしていると、自社製品の懸賞の知らせなどが届くので、ぽちっとするだけで当選落選がわかり、コンビニなどで引き取るといった簡単な応募のものばかりただ私も小心者だから、コンビニに出かけ当選品だけをタダで貰ってくるのも、気がひけるので、100円位のものをあと1品お金を出して一緒に購入をしてたりも驚いた事に、これなどはツイッターでフォローした上で、リツイートしただけで大量の人に先着で商品が貰えるというものだ(1本ずつ引き換え時期がずれている)私も早速、近くのファミリーマートに出かけ最初の分のを無料で貰ってきた。あと1本は来週、貰えるみたいだが、これも商品の宣伝なんだろうな。ツイッターとかSNSで貰ったみたいに写真も拡散されるだろうし・・・ラインポイントが当たったり、ペットボトルを購入すると、もれなくポイントが貰えたりとコツコツと塵も積もれば山となる方式でもともとが気軽にどこかに遊びに行きたいという気持ちもあって、やってた懸賞でもありこういった行楽系のペア招待は一番、嬉しい休日の実施でもあるので、旦那と参加をする事もあり息子が駅まで送迎してくれるそうだ更にこちらは平日の日帰り旅行なので、姉と二人で出かける事になった。いつもは旦那の運転で、出かけるドライブ先の駒ヶ根だけど今回は高速でぴゅ~と行けるそう。お土産も期待できるかな?メーカーとスーパーなどのタイアップ懸賞が主流なので、応募はがきに貼るかわいい切手最近は、シールのシートが普通になっているみたいで絵柄もかわいい最初の2つ、3つは捨ててしまったけどもそれ以降は、当選通知をファイルにためるようにしている。ネットの懸賞を別にして再開して100日程で、24つ当選している応募はがきのファイルは種類別で、これは一番、当たりやすいと言われるタイアップ懸賞。レシートに加えてバーコードまで貼るタイプも出てきた。レシートを写真で撮ってネットで応募できるのは、切手代金が浮くのでありがたいこちらはメーカー独自のクローズド懸賞で商品のバーコードを貼るもの。全国展開をするので応募数も多いが、当選人数も多い定期的に行う商品は普段からバーコードを取っておく人もいるこちらはバーコードではなく商品についたキャンペーン中の応募券とか、ポイントなどで応募するタイプ。後者も普段からためておける。ビールとかの応募シールなんていうのが有名かも先程の応募券と、同じファイルに入れてあるのがメーカーのクローズド懸賞でもレシートで応募するタイプと種類も色々その日に行く予定のスーパーなどの店頭でどんな懸賞をしているのか内容がすぐ把握出来るように、応募はがきの必要条件等をスマホで撮影して、すぐに確認できるようにしているこの写真は20年前に、懸賞を始めたばかりで当選したをスペイン旅行ペア招待で、冬休みに小学生だった娘と行きました。↓最後は同じく小学生の息子と出かけたイタリア旅行ペア招待で旦那とはハワイ旅行ペア招待に行きました。あと海外はフィンランド、ベトナム、韓国ソウル2回 平成30年、夏から秋にかけて撮影にほんブログ村
2018年11月15日
閲覧総数 870
-
12

蘇州古典園林の藕園にて、李白、白楽天、杜甫と芭蕉
今、BS12トゥエルビで夕方に放映している「麗王別姫~花散る永遠の愛」を見ているが玄宗皇帝と楊貴妃の唐の時代蘇州にも近い呉興太守の娘の沈珍珠が、幼い頃に太湖で溺れ、助けてくれた少年(広平王・李俶)を思いを寄せつつも皆殺しにされた家族の仇を探すという歴史ドラマで、安禄山や楊国忠なども暗躍して・・・韓国夫人や皇太子妃など女のドロドロも見どころだ。その作中で沈珍珠の詩の師匠が、李白だったりするのだが、彼が蘇州に来訪した際の詩は「蘇台覧古」李白旧苑荒台 楊柳新たなり菱歌清唱 春に勝へず只今惟 西江の月のみ有って曾て照らす 呉王宮裏の人呉王の宮殿のあった姑蘇台は古びた庭園となり、荒れ果ててしまったが楊柳だけが新しい芽をふいている。ひしの実を採る乙女の歌声を聴けばやるせない気持にもなる今となれば月は西江の水面を照らしているだけであるが、かつては呉王の美女(西施)の姿を照らしていただろうにそんな李白は、遣唐使として渡海しながら日本に戻ることがなかった阿倍仲麻呂と仲が良かったそうだ仲麻呂は官吏登用試験である科挙に応じ最難関の進士に及第したとされ、中国名は晁卿(晁卿衡)という。年老いて仲麻呂は日本への帰国を許されるが、船が難破をし安南に流されて、翌年に長安に戻るのだが李白は、仲麻呂が亡くなったと誤報を受けそれを嘆いた「晁卿衡を哭す」 李白日本の晁卿帝都を辭し征帆一片蓬壺を繞る明月歸らず碧海に沈み白雲愁色蒼梧に滿つ日本の晁卿は長安を去って、船の帆をはためかせ日本へと向かった。しかし名月のように聡明な晁卿は、碧い海に沈んで、白雲が憂いを帯び蒼梧の海を覆ってしまった日本へ帰る事が叶わなかった仲麻呂を阿部寛が演じたのが、夢枕獏原作の映画「空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎」で物語は時系列が二つあって、仲麻呂や楊貴妃の部分と、後世の空海と白楽天の謎解きの部分だ李白701年~762年10月22日阿倍仲麻呂698年~770年(唐は717年~)楊貴妃 719年6月22日~756年7月15日杜甫 712年~770年(後で出てきます)白楽天(白居易)772年~846年空海774年~835年(唐は804年から2年)白居易が、蘇州の長官をしていた時に蘇州城と虎丘をつなぐ山塘河を作ったと前回の日記にも紹介をしたけど、彼は詩人でもあり白楽天として有名であり映画では、空海とコンビを組んでいたイケメンだ「小舫」 白楽天(蘇州にて)小さき舫一艘 新たに造り了り軽く梁柱を装いて 庳く篷を安んず深き坊 静かなる岸 遊應に遍く 浅き水 低き橋 去りて尽く通ず黄なる柳の影は 棹に随う 月を籠め白き蘋の香りは 頭を打つ 風を起こす慢く牽き櫻桃の傍らに 泊まらんと欲するが借問す誰が家ぞ 花最も紅なる小さな舟を一艘新しく造った。柱をたてた。屋根を低く葺いたものだが街の奥や静かな岸にだって何処へでも行く事が出来る。浅い水の上も低い橋の下にも何処だって通れる黄色く芽吹いた柳の影、棹にからまるようにして月が映って、白い浮草の香りが頬を打ち、風の中でただよう。ゆっくりと舟を牽いで、桜桃の花の下に行きたいのだが、どの家の花が最も紅く美しいのか教えてほしいものだこのように風流人にも愛された蘇州にはお金持ちが贅をつくした邸宅を建ててそれらは「蘇州古典園林」と呼ばれて世界遺産にも登録をされている。いつものようにウィキペディアによると>蘇州古典園林の庭園の多くは明や清の>時代に建設された。これらの多くは>地元の名士により作られたもので、>公共事業としてではなく、個人の趣味で>置かれたもので、皇帝所有の庭園で>ある皇家園林に対して私家園林という>庭園は豊かな水を利用し、池を配置した>素朴な美しさを特徴とする。蘇州以外の>江南の地にある名園(例えば上海の豫園)を>含めた江南私家園林が総称として中国>国内では一般的である。蘇州古典園林の>うち、拙政園と留園は中国四大名園の>二つに数えられる今回、出かけたのは「藕園(グエン)」で清代の光緒年間(1875年~1909年)に江蘇・安徽・江西省の総督であり蔵書家だった沈秉成という高級役人が退官後に夫人とともに蘇州に隠居をする事となりこの庭園を買い取ったものである藕園園東部の旧跡は、清の雍正年間の保寧府知事の陸錦が造営した「渉園」で、光緒初年湖州の沈秉成が、渉園の旧跡を買い取って画家の顧芸らを招聘し、設計をさせたもので山を主とし、池を従とし、亭、台、楼が池の周りに建てられている配置が独特な庭園で、邸宅が中央にあり東西に分けられて、各家屋の間は楼で繋がっている。西花園は書斎の「織簾老屋」を中心にして前後二つの庭があり前庭には太湖石の築山があり、後庭には太湖石の花壇があるなお、藕園の藕(ぐぅ)はレンコンのことで、その発音が配偶者の偶と同じことから、夫婦がここで仲良く余生を送るという意味を込めているだそうだ李白、白楽天と紹介したけど、ここはやっぱり杜甫も紹介せねば。幼少の頃から詩文の才能があり、李白と並ぶ中国文学史上最高の詩人で、李白の「詩仙」に対して「詩聖」と呼ばれる李白と杜甫は互いに認め合う仲であったそうだ。杜甫の「国破れて山河在り」は、多くの人が知っていると思う。かの松尾芭蕉も杜甫から思想的、文学的な影響を強く受けて「春望」を引用をしたのだ「春望」 杜甫国破れて山河在り 城春にして草木深し 時に感じては花にも涙を濺ぎ 別れを恨んでは鳥にも心を驚かす 烽火三月に連なり家書万金に抵る 白頭掻けば更に短く 渾べて簪に勝へざらんと欲す「奥の細道」より 松尾芭蕉さても義臣すぐってこの城にこもり功名一時のくさむらとなる「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、笠うち敷きて時の移るまで涙を落としはべりぬ夏草や兵(つはもの)どもが夢の跡杜甫の春望は、楊貴妃も命を落とした安禄山の反乱(安史の乱)で唐の都の長安が陥落をした時のもので、芭蕉の方は義経や藤原三代らが功名・栄華を夢見た平泉での事だ。今回紹介をした李白、白楽天、杜甫の漢詩は高校の頃全部習ったような気もまもなく平成の世が終わろうとしているが、天皇ごとの「元号」も中国が始まりで、古くより漢籍から元号が選ばれている。例えば「史記」第一巻の五帝本紀にある「内平外成」や「書経」大禹謨の「地平天成」から平成となったその前の昭和の出典は、同じく「書経」尭典の「百姓昭明、協和萬邦」からでこの「書経」から今までに多くの元号が作られたそうだが、今春に新しい天皇を迎えるにあたって現首相はそういった、日本古来からの慣例ではなく、漢文で書かれた日本の古典から、次の元号を採用して欲しいと言っているらしいが、これって果たして保守なのか革新なのだろうかウィキペディアによれば、元号とは>「日本書紀」によれば大化の改新(645年)の>時に「大化」が用いられたのが最初であると>される。以後、7世紀中後期には断続的に>元号が用いられたことが『日本書紀』には>書かれている>しかし、当時使われた木簡の分析によると>元号の使用は確認されていない。まだ7世紀>後半は、元号よりも干支の使用が主流だった>ようである。文武天皇5年(701年)に「大宝」と>建元し、以降、継続的に元号が用いられる>こととなった>広く庶民にも年号が伝わるようになった>のは、江戸時代になってからのことである>1950年(昭和25年)2月下旬になると、>参議院で「元号の廃止」が議題に上がった。>ここで東京大学教授の坂本太郎は、元号の>使用は「独立国の象徴」であり、>「西暦の何世紀というような機械的な時代の>区画などよりは、遙かに意義の深いものを>持って」いる上、更に「大化の改新である>とか建武中興であるとか明治維新」という>名称をなし、「日本歴史、日本文化と緊密に>結合し」ていることは今後も同様であるため>便利な元号を「廃止する必要は全然認められ>ない」一方で「存続しなければならん意義>が沢山に存在する」と熱弁をふるったちなみに1400年前の、一番最初の元号の大化であるが、その出典は「書経」(尚)大誥「肆予大化誘我友邦君」「漢書」巻56「古者修教訓之官務以徳善化民、 已大化之後天下常亡一人之獄矣」「宋書」巻20「神武鷹揚、大化咸煕」その次の白雉は、「漢書」巻12 平帝紀の「元始元年正月越裳氏、重訳献白雉」だとかちなみに中国では、ウィキペディアによれば>前漢の武帝の治世・紀元前115年頃に>統治の初年に遡って「建元」という元号が>創始されて以降、清まで用いられた。武帝>以前は王や皇帝の即位の年数によって、>単に元年・2年とだけ数えられ、新しい>王が即位すると改元されて再び元年から>数えられる在位紀年法が用いられていた。>治世途中での改元は文帝によるものが>最初で、改元後は後元年・後2年とされた>明の太祖(朱元璋)は、皇帝即位のたびに>改元する一世一元の制を制定した。これに>より実質的に在位紀年法に戻ったといえるが>紀年数に元号(漢字名)が付されることが>異なっている。また元号が皇帝の死後の>通称となった。そして蘇州・・いや呉の国で思い出されるのが、着物(和服)の事を「呉服」と言うこれは絹(シルク)などが、呉から日本に輸出をされ、平安時代あたりまで呉の布を使って着物を作っていたからだ。↑最初の「麗王別姫」の唐の衣装など、日本の着物に通じるものが多々あるそれ以前にネット検索なでをすると、倭には稲作文化を携えた呉の国の人たちが、戦争に負けたりで海を渡って、数多く移り住んだという説もあるそうで、 中国の史書に「倭人は太伯の後裔(こうえい)である」との記事があるんだとか太伯は周の古公亶父の子で、呉(句呉)の祖とされる人物である。吉野ヶ里などの弥生時代の墳丘墓が、中国江南地方で呉や越の限られた時代に行われた土墓の影響を受けた可能性があり、養蚕が盛んに行われていたようで、この時代の人々が呉から日本列島に渡来したという説もある現在の中国の国家体制は、100年にも満たず私が見てきたものは、かつて中国大陸にあった大昔の王朝や国であって、民族も違っていたりするのだから、今がこうだから昔もというのは論点が違うと思う 旅は続く。 平成31年1月27日に蘇州で撮影にほんブログ村
2019年03月06日
閲覧総数 675
-
13

徳寿宮の紅葉と、祈りの姿に、韓定食!
さてソウルの最後の朝、姉と二人で地下鉄を使って 宮殿めぐりなどしようと思っていたのだが、前日の 統一展望台のオプションなどで、ご一緒した姉妹も 同行することになった。ま、姉一人でも、3人も同じ ようなものである 静岡からお越しの、姉よりも一回りは、年上の 日本舞踊のお師匠さんと、義理の妹さんなのだが なんだか森の石松っぽく、きっぷの良い話し方が 格好が良い。にわかガイドに変身をして、後ろを 振り返えつつ、3名を引き連れて、最初の訪問地の 「徳寿宮」(旧・慶運宮)を訪れた 李朝第9代王にあたる成宗の兄、月山大君が 住んでいた邸宅だったが、豊臣秀吉による 文禄・慶長の役で、避難先からソウルに戻った 李朝第14代王の宣祖が、臨時の王宮として 昌徳宮へ居場所を移すまでの一時期、ここが 王宮として使われたそうだ 1897年、李朝第26代王の高宗が修理をし 明成皇后の暗殺に、身の危険を感じた高宗が 慶運宮へ移ったことで、再び王宮として使用を されるようになった 高宗が皇帝として在位した、1907年までの 李氏朝鮮王朝の、波乱万丈な歴史の中心舞台となり 1905年には重明殿で、日韓保護条約(乙巳条約)が 締結をされた この建物は、ロシア建築技師サバティンの設計で 1900年に建てられた、王宮の中に建立された 最初の西洋式(中国風)建物。高宗皇帝が茶菓会を 開催したり音楽を鑑賞したりした休息の場所だ この宮殿は、ソウルの繁華街のど真ん中に位置し 目の前は「パリの恋人」でテヨンとハン・ギジュが 待ち合わせをしたソウル市庁・・・いや、一般的に ワールドカップサッカーで、真っ赤になった所だ 現庁舎の裏庭に新庁舎が建てられて、 日帝時代の 建物である、旧・京城府庁だったソウル市庁舎は 博物館として、保存をする計画があるそうだ ソウル初日に「美しき日々」のソンジェが通った 医大のロケを行った、延世大学のキャンパスの前を 通り、中の様子を垣間見る事ができた 学歴社会の韓国は受験戦争が激しく、小学生の 頃から、母親と海外留学にいくくらい加熱をしている ちょうど、私の到着した日は、韓国大学修学能力試験の 当日にあたっていた。チェ・ジウの「真実」では 替え玉受験を行ったり、実際に、昨年は、携帯電話に よる集団カンニング事件もあったほどだ 社会みんなが受験生に協力的で、パトカーに乗って 受験会場に向うなんて話を聞いてたら、ガイドさんが 実際に体験をされたそうで・・・本当だったんだ(笑) 受験生が、机に向って試験に取り組んでいる間 そして試験結果がわかるまで、父や母は、神さま 仏さまと言うわけで、韓国で一番大きな宗派である 曹渓宗の総本山である「曹渓寺」にも、私と同じ くらいの女性の姿が目立っていたのは、そのせいかも 韓国のお寺も、宮殿のようにきらびやかであった 陶磁器や工芸品の店が軒を連ねる「仁寺洞」は 裏通りに、庶民的な安いお店や、古い韓国の家が 点在し、本格的な韓定食や、伝統茶を味わうことが できます♪ 事前にガイドブックを調べて、韓定食のお店を 物色をしていたので、路地裏をすすんで、無事に 目的のお店「智異山」に到着をした 大きなテーブルいっぱいに、韓国のお袋の味が 並ぶ、並ぶ。姉の好きなお豆腐の料理もある サラダのドレッシングが甘い~? 梨をすった ものを使っているようだった。へぇ~~ 「チャングムの誓い」を見れば、おわかりのように 「医食同源」のお国柄だけに、朝鮮人参なども 料理に使われているよ 食後には、様々な効能のある「伝統茶」が出てきました これは、ご飯粒と麦芽の粉を、水に浸した上澄みで ねかしてつくる「シッケ」 いよいよ、ソウルの旅も、あとわずか。お二人の 同行者のために、世界遺産でも見物をしますか
2005年12月08日
閲覧総数 29
-
14

伊香保姫の水澤観音でガンダムと、アンパンマンと、うどん!
たのみくる心も清き水沢の 深き願いをうるぞうれしき 仏教の教えを、五・七・五・七・七の和歌と成して 旋律に乗せて唱える「ご詠歌(ごえいか)」は平安 時代より伝わるもので、これは通称を「水澤観音」 「五徳山水澤寺(ごとくさん みずさわでら)」の歌 日記の構成上、最後の紹介になってしまったが 二日目のお昼頃には、伊香保温泉の間近にある 「水澤観音」にも立ち寄っていた。その目的は 別にあるのだが(後述) 寺の創建は飛鳥時代にさかのぼり「伊香保姫」が 深くかかわっているという 推古天皇の御代(592~629年)に、高野辺左大将 家成が上野国に左遷をされて、妻と子らと深須郷に 蟄居をしていたが、そのうち若君の家定は母方の 祖父を頼って都に戻って中納言となった 淵名の姫、赤城の御前、伊香保姫の三人の姫君を 残し北の方が病死したので、家成は更科大夫宗行の 娘を後妻に迎えて、一女を授かったそうだ ところが家成は宣旨を受けて単身で上洛し、残された 継母は先妻の産んだ三人の姫君を疎んで、殺して しまおうと、弟の更科次郎兼光と図り赤城山麓で 牧狩りの最中に、姉二人を吾妻川に沈めて殺した 伊香保姫も川に沈めようとした時に、赤城山から 黒雲が起きて、俄かに風雨激しく雷鳴が轟くのを 驚いて兼光ら逃げ帰った為、伊香保姫は伊香保の 郷に逃れて隠れ住んだそうだ 伊香保姫は都の父に事情を知らせたのだが、既に 没していたので、兄の家定が上野国の国司として 五万余騎の軍勢を率いて、更科次郎と継母を捕らえ 更科次郎は倍屋ヶ淵に沈められて殺され、継母は 信濃国に追放をされて更科山で死んだそうである その後、伊香保姫は中将高光に嫁ぎ(たぶん)幸せに 暮らしたとさ。その上野の国司の高光中将が開基となり 高麗来朝の僧恵灌僧正を南部から招いて、伊香保御前の 御守持仏の「千手観世音菩薩」を本尊と建立されたのが 水澤観音である。伊香保姫の観音様は秘仏とされ、参拝 する為の前立ち御本尊は、江戸時代のものであるそうだ 「六角堂」の内部には、六道界を守る地蔵尊を祀り 六道輪廻の相を表して、二階には大日如来が安置を されている。天明七年に竣工をされた「六角堂」は 六地蔵尊自体が回転する、全国的にも珍しい構造で この地蔵尊を左に3回廻して、供養をするものだ 地獄道 金剛願地蔵尊 餓鬼道 金剛寶地蔵尊 畜生道 金剛悲地蔵尊 修羅道 金剛憧地蔵尊 人間界 放光王地蔵尊 天人界 預天賀地蔵尊 池があり、龍王弁財天が祀られている ご神木の前にはなにやら碑 こっちはガンダム像。撮影禁止で貴重な仏像などが 無料で公開されている資料館の売店付近に「これは 撮影できます」とわざわざ貼り紙がしてあった 境内にはアンパンマン像も 門前の売店には、一所懸命巻き上げてくれるらしい ソフトクリームがあったのだが、これからお昼だし~ さて坂東三十三箇所の十六番目の札所で、由緒があり 古くから参詣客が多った水澤観音の門前で、天正年間 (16世紀後半・安土桃山時代)の頃より、振舞われて いたのが名物の「水沢うどん」で、今でも沢山の店が 道沿いに建ち並んでいた 上州(群馬県)は古くから、小麦の栽培が盛んだそうで 今でも群馬県は小麦の生産量の全国第2位を誇っており 香川県の讃岐うどんや、秋田県の稲庭うどんと並んで 「日本三大うどん」にも数えられているそうだ やや太めでコシのあるうどんは、一般的には冷たいざる うどんで食べられ、つけ汁は店ごとで違い醤油だれや ゴマだれなどで。これで735円で湯の花まんじゅうも お茶受けにいただけた 高崎駅(営業上は東京駅)より、長野駅までを結んでいる JR東日本の「長野新幹線」は通称であって、正式には 「北陸新幹線」の一部である。群馬県安中市東上秋間に ある「安中榛名駅」には峠の釜めしの売店や待合室がある らしいが、一日の利用者は200人台で、駅前があぁ~ 寂しすぎる・・・ぽつんとコンビニ 亡き母親が「妙義山」は面白い形をしているぞ」と生前に 話していたのが忘れられず、榛名山の帰りに通ってみたら ほんとダイダラボッチが土をぶちまけたようなヘンな山 上毛三山の一つに数えられ、急勾配の斜面と尖った姿が 特徴的な事から日本三大奇勝(他に大分県中津市の 耶馬溪、香川県の小豆島にある寒霞渓)の一つでもある 「妙義山」は、白雲山・金洞山・金鶏山・相馬岳・御岳・ 丁須ノ頭などを合わせた総称であり、南側の「表妙義」と 北側の「裏妙義」に分かれている 帰りに、軽井沢でこの前食べたちゃたまやの本店で食べた ダブルのジェラード。これで240円。盛り方が軽井沢と 違っているが、価格もお得だ(これが本当は最後の写真) ジェラード食べたさに高速道路ではなく、「碓氷(うすい) 峠」を越えて軽井沢に抜けた。妙義山方向のおかしな山の 前にある美しい橋は高速道路のものだろう。信濃川水系と 利根川水系とを分ける中央分水嶺で、峠の長野県側に 降った雨は日本海へ、群馬県側に降った雨は太平洋へと 流れるそうだ 寄り道しすぎて峠の釜めし店素通り!。ま、諏訪にも 支店があるけどね。今度、諏訪湖の花火の時に立寄るし 平成22年7月24日に榛名山などで撮影
2010年08月07日
閲覧総数 1274
-
15

横浜の恩人も生まれた小野宿は、小粒ながらきらりと光る
2009年01月28日
閲覧総数 132
-
16
最初の一歩は業者選び。これさえ成功すれば殆ど成功したようなもの
住宅を既に建てた方のお話も伺いたいし、これからの方には参考に少しでもなればと思い、今回も建物ネタ。まだ初期の私の場合は業者とお見合い編みたいな段階だ。勿論、いつもの日記(行楽とかグルメ、買い物他)も書きますのでご安心を前にハウスメーカーはちょっと・・・というのは、あくまでも個人的な思い込みだけかもしれないが、何か営業さんからのプッシュがすごそうで、そのペースに乗せられてしまうのかもって気持ちもあったりして。やっぱ、あくまでもイニシアチブはこちらで握っていたいしまっ展示場も遠いし、あくまでも個人的な見解であるがモデルルームは実際建てる家よりもゴージャスそうだし、建築代金も高そうな気もするし、自分の住んでいる地域に適した家は地元業者の方が良いような気もしてそんな訳で地元工務店などの新築完成見学会などにせっせと出かけているのだが、これって施主(家を建てる人)の好意で週末の2日間位を業者が借りて行うものが主流である。でも誰でも来れるのでは治安もどうかという事で、必ず見学者は入り口で住所氏名などを記入しなければならない中には業者の資料にしたいのか、家族の年齢とか細かい事も書かせる業者もあるが、まっ家作りに興味のある人が来るので当然の事だろう。おしゃれなお宅が続いた上、農作業も忙しくなったので、旦那は「忙しいし、(30代の夫婦の今時の家は)もう見なくてもいいや」と私一人で行く事もあって、時には冷やかしに思われる事も前夜に旦那が飲み会があったので、旦那の車を会社の駐車場まで取りに行くというので、週末に私の車で久しぶりに旦那と出かけ、途中でローコスト住宅の完成見学会に立ち寄ったが家のアンケートもあるのに「住所と名前だけでいですよ~」とか言われ、間違って私の名前を書いたら「奥さんの名前でいいですよ~」って・・・適当すぎる営業マンがくっつく事もなくて自由見学となって、旦那はこの手の家は興味もなさそうでペース早っ! こちらから営業さんに質問するも、それに答えたらさっさとどこかに行ってしまうし。礼状は私宛に届いたけど完全に冷やかしと思われたのかな。ネットではアフターサービスがちょっととあったし、なるほど~~と思いもして完全に候補から外れた。内装はおしゃれなんだけどもね~完成見学会でついてくれた営業マンが担当になる事が多いようでその人との相性(好感度が持てるか)とかって、業者の選択でも大きなポイントになったりもする。一応はついてはくれて説明もしてくれても何だかヤル気が無い対応だと、いくら良い家でもここでは作れそうにもないなぁ~という気持ちにもなってしまう田舎なので都会程は業者がないので、ネット検索でホームページを持ってるような地元のめぼしい業者の半分くらいは接触できたけど見学会をしてたけど行く機会がなかったのは2社で、実際に行ったのは10社。そのうちイベントや勉強会など再び接触した ABE旦那の知り合いや、知り合いの知り合がいた CD見学会や勉強会などの紹介、会報などの送付 ABCDE冷やかしと思われた HIJ名刺を貰えなかった J礼状の封筒がからっぽのままで送ってきた G私だけしか接触出来ていない DEHって感じでFGHIJの5社は今後、完成見学会とかこちらからの接触が出来ない時はサヨナラ・・・って事になりかねない。近所の家を建てた業者なんかもあるのに詰めが甘いなぁ。こっちも本気度出てなかったのかなぁ。なんでも良い服を着て良い客になりそうなオーラを出さないと相手にされないとネットにあったこんなんじゃ、我が家の場合はハウスメーカーなど寄りつけそうもないじゃなのぉ~。なんだか、そうゆうのも寂しいなぁ。金のある客だと勘違いされてぼられるより、貧乏そうな客でも親身に話を聞いてくれる業者さんの方がなんだか好感が持てそうだ相見積もりとかで、複数の業者から安い予算&良い間取りで業者を決める人もいるようだが、やっぱ先に業者はある程度は絞っておく必要があるような。だって施主の事情や、好み、希望を知らなきゃ自分の家族の望む間取っておいそれと出来ない。その為には何度も直接に打ち合わせもした方が良いと思うし予算なんてのも外壁一つでもいろんな仕様があるし、どこまでが基本料金で、どこからがオプション料金がかかるのか。その業者の基本にあたる仕様がどのレベルであるのかも千差万別なので、安いからココと決めれるはずもない。高い方は断熱材を入れて、ペアガラスが基本だけど、安い業者はそれらが全部オプションなのかもだから営業マンがどうのとか言わず業者がどんなレベルの家を建ててくれるのかって見極める為にも実際に建てた家を見ながら、さぐりを入れたりしたのだが、なかなか難しい。坪60万とかいうのだって大きな家になれば坪単価は安くなるし、ソーラーのせたり、床暖房いれたり家の仕様も施主の希望で千差万別。まずオプション入れてて基本のままの家も皆無だただ宝塚でも歌がうまい、演技が良い、ダンスが下手みたいな特徴があるように、業者でも何を得意としているのか、これをこだわりにしているというポイントがあるので、これについては見学会とかネットでホームページを見たら一目瞭然うちのあたりは、東濃ヒノキや木曽ヒノキの地域なので、ふんだんに天然木を使った本格的和風住宅や、東海地震の地震防災対策強化地域なので、耐震性に優れた工法を持つとか、寒天干しをするような極寒地域なので高気密断熱に力を入れているとか、更にはローコストとか建物の収支を明快にしているとか、アフターサービスなどなど・・・抜本的に倒産の危険がなく、欠陥住宅を建てず、極端に高い料金を請求するような業者でなければそれで良いだけだが。電気店でも何か選ぶときには数ある商品の中から、あれがいいとかこれにしようかと迷うけど、いざ買ってくれば1つしかないので比べようもなく、何かトラブルがなければ、それが1番みたいに納得もできるしそんな訳で、家づくりの第一歩、そして一番重要なのが業者選びでそれさえ成功すれば、そこそこ良い家はおのずと出来るように思えるただ見学会など業者イベントもいつもある訳でもないので、1度だけ接触して話が出来たとしても、その次はこちらから営業所とか行って話でも聞かない限りは先に進めないそうもないけど下手に出かけたらずんずん話がすすんでしまいそうで、その業者でもいいの~?となかなか先へすすむ気持ちにならず。このまんまじゃ先に進めないじゃん~ってジレンマ。旦那とか建てているときの舅姑の住まいをどうしよう!というのしか頭になくて。さてどうなる事やら家づくりの業者を大まかに分類すると(ど素人の個人的見解) ハウスメーカー テレビCMなどで名の知れた有名な大手メーカー ローコスト住宅ハウスメーカー 建物料金が名前のように安いらしい? 建築家 設計&管理料を支払う事で、大工の手配とかだんどりをしてくれる ビルダー 広範囲に大工って事らしく、見解もいろいろだけど地域に 根差した土建業や、不動産などもされているような中堅の 工務店。営業さんや設計士、大工などの専門職の社員も多い 工務店 ビルダーに比べて少人数の社員の経営で家作りをされている 大工さん 個人で経営をされており、すべての段取りなどをしてくれる あとゼネコンは個人宅ではなく、公共工事やビル建設などさてさて最後に。少し前にV6のメンバーが「オチャダ、オチャダー、俺○○ね~」とかブレンディを飲むTVコマーシャルがあったけど、商品のバーコードで、V6コラボのカラフルなマグカップが当たる懸賞があって普段から購入しているので家にも商品があるしと、2口応募したら当たりました。アウトドアで有名なロゴスだし♪ このまましまっておいて新居が出来たら普段使いにしようかなやっぱブレンディは手軽で美味しいし、30本入りのがぬぁんとスーパーで税抜250円で特売をしていたので購入。また品切れ販売中止となったらしいサントリー天然水のヨーグリーナも安かったので試しに購入。個人的な感想だけど、ネットでも言われるようにやっぱカルピスの薄いような味・・・ 平成27年春に
2015年04月27日
閲覧総数 148
-
17

キャンセル拾いで、日立に、長久手日本館♪
それは、数日前のことだった・・・・ 1ケ月前の9時からの「ネット予約」開始後 日立館は、9時1分に、既にある時間は ×がついていて、アクセスできないまま 呆然としたまま、全て×になっていた 昨日、愛地球博は21万人を超え、日立は 7時間待ちになった時間帯も、あったそうだ 熱中症の配慮か、夏休みに入る7月21日から 日立館は行列ではなく、トヨタ館のように 「整理券方式」になるという すでにゴールデンウィークの頃に、5時間待ちの 行列が珍しくなかった日立館。グローバルハウスが 行列解消の為に、マンモスの単独コースを作って スムーズな人の流れを、早々に作ったのと対照的に あまりにも後手後手に、まわってしまったのでは ないのだろうか この三連休の中日(なかび)の人出の多さは 素人ですら予想が出来たのだが、なぜ、この 3連休から「整理券配布」が出来なかったのか 理解に苦しむ とにかく、真夏の炎天下での「幼い子供が長時間の 行列」の解消を望むのだが、今度は整理券配布の 為の行列が出来るんだろうなぁ、きっと そんな訳で、夏休みのお盆は、更なる人出も予想 されるそうで、当日券の販売中止など、場合に よっては「入場制限」も、考えるそうだ その昨日の報道が影響をしたのか、しなかったのか 今日は朝からキャンセルが続出! おかげさまで 念願の「日立」が拾えました。これで、娘と二人で 夏休みバージョンの「長久手日本館」を見てから 娘だけで、自分のと私の予約で、「日立」と「大地の塔」 (娘が一番楽しみにしてるらしい)に、入れます♪ キャンセル拾いなんですが、万博のトップページの 「基本情報」での「予約情報」>パビリオン予約の 「2・予約方法を選ぶ」の「今すぐ申し込む」> 事前予約の空き状況を見るで・・・・ 「すでに目的のパビリオンや、日付が決定して いる方 」の、日付とパビリオンを選んでくださいで 日時、パビリオンの設定をして、表示をして下さい 全体の空き状況を見たい方の「週表示一覧」では ×がついていても、そちらの方は、三角があり ますので。今のところは、毎時20分にキャンセルが まとめて放出をされます(深夜はオヤスミのようです) 私の場合、日立、長久手日本館、ガスパビリオン 大地の塔などなどの、ネット予約が出来ました (最初は日立ではなく、色々と予約をしてみたけど やっぱ、日立に楽に入りたかった。朝の整理券は トヨタ狙いなんで・・・) あと3日といった場合でも、何かしら拾える チャンスはあるので、あきらめずにキャンセルを 拾ってみて下さい それにしても、今回の万博は、情報を持つものと 持たないものでは、あまりにも不公平感があります 中部地方のように、毎日のようにいくつもある 万博番組や、新聞、ニュースなどで、外国館や グルメ情報を、熟知をして、全期入場券を使い 何度も足を運び、現地慣れしているのと違って 高い交通費を払って、ホテルも探し、コミコミの 万博で、数時間も並んで「日立館」ですか・・・ 「何時間も並んでまで、そんなに見たいのか?」 なんて、とても言えないですよ 遠方の人には、たった一度だけの万博。日立館に 入るチャンスもたった1回しかないから、数時間でも 並ぶしか無いんです。ですから、お盆とか、連休の ように、帰省者や、遠方の来場者が多い時は、比較的 簡単に来場が出来る全期利用者の人は、来場を遠慮を してあげるだけの配慮も、してあげたらいいのになぁ~ なんて思うけど・・・・ そういった時には、イベントもあるから、そうもいかない のだろうね。とにかく、誰にとっても、サイアクの万博の 思い出だけになってしまっては、残念ですよ 4月の万博は散々だった娘に、見たかった大地の塔 日立館、長久手日本館・・・・。リベンジは出来そうな 予感です あなたも「リベンジを誓ってる事」、ありますか?
2005年07月18日
閲覧総数 22
-
18

京都宇治でのお昼休憩には、足早に赤い橋を渡って
さてさて前回の懸賞当選報告でも、少し紹介しました、いつもの日帰りバス旅行無料招待いつものように一人で出かけたけど、今回もとても良い方がお隣で、楽しい一日でしたよまずは、お決まりの宝石屋さんで90分間のショッピングタイム。誕生石クイズで当たりパックのシートを今度も貰いましたが、お隣の奥さんも当たった♪と、ニコニコされてましたこの宝石は、コンクールとかに出すやつらしく撮影が出来る入口の部屋で今回はお買い上げになった方がいるらしくその手続きなのか、バスの発車が遅れたので先程のパックのシートをバス全員にも配ってくれました。バスは木曽川を超え名神高速を西へと向かい昼頃には、昼食場所の京都の宇治に到着!家族旅行などを含めて、宇治は今までに数度は来ているが、嵐山同様に風光明媚でいいところだなぁ~川の畔の喜撰茶屋で、団体料理をいただきますが、今までは早くに食べても、土産物屋を見物する位でしたが、ここならお散歩に行けそうだし!お店のホームページを見たところ、たぶん1500円位のお料理かな。冷たくなった天ぷらは湯豆腐に投入し、温かで美味しくなりました。お散歩時間確保の為に早食いしちゃいまして集合時間までの時間はありますし、早足ではありますが、宇治の散歩に行くぞ~宇治に来ると、平等院が満足度が高いし抹茶パフェとか食べに行くので、実の話川の向う(東側)は行った事が無いのだまずは朱色の喜撰橋を渡る鵜飼いと言えば、岐阜市の長良川が有名だけど、ここ宇治でも鵜飼をやっているようだ。私は岸からだけど以前に嵐山で泊まった時に、遠くから鵜飼を見た事があるお~~、鵜がいるよ♪ 鵜飼についてウィキペディアで、紹介させて貰うと>鵜飼い・鵜飼・鵜養(うかい)は、鵜(ウ)を>使ってアユなどを獲る、漁法のひとつ。中国、>日本などで行われていた。現在では漁業という>より、観光業(ショー)として行われている>場合が多い。 また、ヨーロッパでは16世紀>から17世紀の間、スポーツとして行われた。>鵜飼いの歴史は古く、『日本書紀』神武天皇の>条に「梁を作つて魚を取る者有り、天皇これを>問ふ。対へて曰く、臣はこれ苞苴擔の子と、>此れ即ち阿太の養鵜部の始祖なり」と、鵜養部の>ことが見え、『古事記』にも鵜養のことを歌った>歌謡が載っている。>天皇の歌に「しまつとりうかひかとも」とある。>また中国の史書『隋書』開皇二十年(600年)の>条には、日本を訪れた隋使が見た変わった漁法と>して『以小環挂鸕鷀項、令入水捕魚、日得百餘頭』>(小さな輪を鳥にかけ日に100匹は魚を捕る』と>記されている。>延喜年間(901年 - 923年)には長良川河畔に>7戸の鵜飼があり、国司藤原利仁により鮎が献上>された。そして、それを時の天皇が気に入り、>方県郡七郷の地を鵜飼に要する篝松の料として>賜り、鵜飼七郷と読んだ>『和名抄』には美濃国方県郡の鵜飼が掲げられ、>『集解釈別記』には鵜飼37戸とあり、『新撰>美濃誌』には方県郡鵜飼の郷9箇村とある。>文明年間(1469年 - 1486年)、一条兼良が>美濃の正保寺に滞在し鵜飼を見物した記録が>ある。>永禄7年(1564年)、織田信長は長良川の>鵜飼を見物し、鵜飼それぞれに鵜匠の名称を>授け鷹匠と同様に遇し、1戸に禄米10俵を>当て、給与した。う~む、古くから鵜飼されていたんだ。しかも美濃国の長良川河畔でされていたとは。岐阜県民だというのに見物したことが無い「浮島」「浮舟ノ島」などの人工島の一つである「塔の島」には、現存をする近世以前の石塔では日本最大(約15.2メートル)の十三重石塔が建つこれは鎌倉時代に、宇治橋の大掛かりな修造がされ宇治川の川中島として、大橋の南方に舟を模した人工島を築き、放生会を修する祈祷道場とした宇治川で漁撈される魚霊の供養と、橋の安全の祈念を旨にして島の中央に大塔婆が造立されたそうである島は宇治川の氾濫にも耐えて、激流に浚われる事が無く「浮島」「浮舟ノ島」と呼ばれるようになったが大塔は氾濫の被害を受けて、倒伏と修復を繰り返し江戸時代に起きた氾濫で倒伏し、川底の泥砂に埋もれ明治末に発掘されて再建をした。国の重要文化財だ近江より奈良へ帰る途中、宇治川付近で歌われた柿本人麻呂の歌碑があった。「宇治川の網代木で一時停滞し、やがて行方知らずとなる波のように滅びさった近江の都に仕えていた人々はいったいどうなったのであろうか」との意で、もののふの八十氏河(やそうじがわ)の網代木(あじろき)にいざよふ波の行く方しらずもこちらは橘橋と言うらしい。時間がないので渡らず遠くから、眺めて拝観終了宇治川の向こう岸には、道元が興聖宝林寺を建立した事に始まる、日本の曹洞宗としては最初の寺院となった興聖寺。宇治川に面した総門より本堂に通じるまでの緩やかな参道は「琴坂」と呼ばれ、宇治十二景の1つにも数えられている更に、源氏物語の宇治十帖に縁があるという「手習観音(聖観音)」が安置されているというので、いつかは参拝に出かけたいけど今回も時間的に無理のようだそして宇治川と言えば、源義仲と鎌倉の源頼朝から派遣をされた源範頼、源義経との宇治川の戦いとしても有名で、佐々木高綱と梶原景季の宇治川の先陣争いなどもそれに先んじて、以仁王(高倉天皇の兄宮)と源頼政が平氏打倒のための挙兵を計画し、諸国の源氏や大寺社に蜂起を促す令旨を発したが、準備不足の雨に露見し追討を受けて、以仁王と頼政は宇治平等院の戦い(橘合戦)で敗死をしてしまった単に風光明媚な土地と言うわけではなく、交通の要所がゆえに、歴史に幾たびか登場する宇治だがやっぱり、その名が一番知れ渡ったのは紫式部が執筆した「源氏物語」の存在が大きいと思われる私も子供の頃に、これで宇治の名を知ったとは言っても現代語訳のものだし、光源氏の物語は真剣に読んだけど、亡くなったのちの宇治十帖とか流し読み状態だったが。ここでの主人公は薫の君で光源氏(本当は柏木)と女三宮の息子で、生まれつき体から良い薫がするので、そう呼ばれているこちらは匂宮と浮舟が、小舟の上で愛を語らう場面らしい。匂宮は今上帝の三の宮(第三皇子)で、母は光源氏の娘である明石の中宮で、光源氏の孫となる薫の君に対抗し、薫物(たきもの)に心を砕いており二人は世間から「薫る中将、匂ふ兵部卿」と呼ばれ世間の評判はこの二人に集中していたそうだイケメンでイケイケな匂宮は、薫の君から宇治八の宮の姫君たちの噂を聞き、薫の手引きによって中君と結婚するが、夕霧の娘六の君を北の方に迎えると、中君をないがしろにしてしていた。しかも中君の異母妹である浮舟が、薫君の恋人と知りながらも薫になりすまして契りを結んだ為、浮舟は苦悩のあまり入水を図ったのだもともとが昼食タイムなので、あまり時間がないけどこの神社位なら参拝が出来そうだ。このすぐ近くには世界遺産にも登録されている、宇治上神社もあるが時間のある時にゆっくりと参拝をさせて貰おうかと思う。先程の曹洞宗のお寺や源氏物語ミュージアムなども行きたいしといった訳で今回お邪魔をしたのは、かわいらしい「宇治神社」である。普通であれば龍の口からだがここではウサギだし。中世に宇治茶の象徴としての宇治七名園が作られて、お茶には不可欠な水として「宇治七名水」も定められ、現存する唯一のものがこの「桐原水」で、宇治上神社の境内に沸いているこの樹は「兎楽の樹(うらくのき)」といい、簡単な説明は下の写真をご覧下さい。宇治神社と宇治上神社の御祭神は、ウサギに導かれた菟道稚郎子命である彼は第15代応神天皇の皇子(日本書紀では皇太子)で16代仁徳天皇の異母弟であるそうだ。宇治の地名は古くは宇遅、莵道、兎道などとも表記されており菟道稚郎子の宮があったウィキペディアによると>『日本書紀』によれば、百済から来朝した阿直岐と>王仁を師に典籍を学び、父天皇から寵愛された。>応神天皇28年には、高句麗からの上表文に「高麗王、>日本国に教ふ」とある非礼を指摘し、これを破り>捨てている。応神天皇40年1月に皇太子となった。>翌年に天皇が崩じたが、郎子は即位せず、大鷦鷯尊と>互いに皇位を譲り合った。>そのような中、異母兄の大山守皇子は自らが>太子に立てなかったことを恨み、郎子を殺そうと>挙兵した。大鷦鷯尊はこれをいち早く察知して>郎子に伝え、大山守皇子はかえって郎子の謀略に>遭って殺された。>この後、郎子は菟道宮に住まい、大鷦鷯尊と皇位を>譲り合うこと3年に及んだ。永らくの空位が天下の>煩いになると思い悩んだ郎子は互譲に決着を期す>べく、自ら果てた。>尊は驚き悲しんで、難波から菟道宮に至り、遺体に>招魂の術を施したところ、郎子は蘇生して妹の八田>皇女を後宮に納れるよう遺言をし、再び薨じたという>『播磨国風土記』には「宇治天皇の世」という記載が>あり、事績は見えないがこの「宇治天皇」は菟道稚>郎子を指すと見られている壬申の乱を前にして大海人皇子(天武天皇)も近江を後に吉野へ向かう途中で、ここ宇治にも立ち寄っていたという。宇治川のあたりでの別れ際に、舎人たちは大海人皇子の吉野行きを「翼をつけた虎を野に放したようなものだ」と言ったそうだそんなこんなの歴史の端々に登場する宇治、歴史ファンならば妄想モード最強になれるのは間違いなし。宇治川の東側のこの道をさわらびの道といい川の西側はあじろぎの道で、良い散策路になっている万葉集にある詠み人知らずの歌宇治川は淀瀬無(よどせな)からし網代人(あじろひと)舟呼ばふ声をちこち聞ゆ現代においては宇治と言えば、やっぱお茶という事で、さわらびの道沿いに「福寿園 宇治茶工房」があったので、次に来た時には立ち寄りたいが時間もないので、そろそろ戻るとするかお昼をいただいた喜撰茶屋で、50円の割引券を貰っていたので、喜撰ソフトをぱくり。八つ橋がささっているよ自分が喜撰ソフトになる事も出来るし♪ と言った訳で集合時間になったので、バスに乗車して、今回のメインの伏見稲荷大社へと向かう事にするバスの車窓からは宇治の縣神社。大和政権下における県(あがた)に関係をする神社と見られ1052(永承7)年に、藤原道長が別業(別荘)を寺院である平等院とする際、鎮守としたそうだ「宇治橋」は「瀬田の唐橋」と「山崎橋」と共に日本三古橋の一つに数えられ、日本霊異記に道登が宇治橋を架けたのは、646(大化2)年と伝えられている。古今和歌集や紫式部の源氏物語に登場し、能の「鉄輪」で登場する橋姫伝説でも有名である現在の橋は、1996(平成8)年に架け替えられ長さは155.4m、幅25m。橋の姿が宇治川の自然や橋周辺の歴史遺産と調和するよう、擬宝珠を冠する木製高覧という伝統的な形状を使用している宇治へは京都から京阪宇治線と、JR奈良線があり京阪は宇治が終着となるが、JRは宇治川を渡って奈良へと。この電車はJRの「みやこ路快速」だ昨日あたり、娘が最近は奈良に行っていないし、久しぶりに京都や奈良とかに行きたいなぁ♪なんて嬉しい事を言っていたので、この夏は関西地方に出かける事が出来るかも♪秀吉が隠居の為に建てた伏見城は、戦いも経て、関ヶ原の戦いで勝利した家康が再建をしたが、一国一城令で二条城を残し伏見城は廃城となり、一帯には桃が植えられ桃山と呼ばれたそうだ。戦後になって遊園地が出来模擬天守も作られた 令和1年5月24日に京都で撮影にほんブログ村
2019年07月02日
閲覧総数 471
-
19

2005年の旅。 ベスト5
さて、2005年もあと3日。今年もまた 2005年を、振り返ってみようと思う 旅行がメインのブログであるので、今日は 旅行&行楽ベスト5!をお届けします 1 韓国(11月)姉と 1位は、懸賞で当たった韓国旅行。イムジン河の 向こうに北朝鮮を眺めたり、美味しい料理に 観光、買い物と紅葉のシーズンだったのが ラッキーでした 2 京都、有馬温泉、神戸異人街、姫路城(7月)姉と 岐阜、近江八幡、京都(11月)姉と 7月は、息子の合格祈願した北野天満宮への お礼参りが、有馬温泉で泊まり、姉の行き たかった神戸異人館。果ては、姫路城へと 盛り沢山の旅だった 11月は、岐阜県の国宝展と、懸賞で当たった 近江八幡の水郷めぐり、そして非公開文化財 特別公開の冷泉家を見学に、京都まで 3 山梨、箱根、富士(8月)姉&甥と、途中、次兄も 東海道、箱根、富士(9月)旦那と 8月は、次兄が、箱根の会社の保養所に招待を してくれたので、甥の運転する車で、姉と 山梨のひまわり畑から、富士、箱根を満喫 9月は、箱根の温泉旅館の招待が当たって 旦那の運転で、今度は東名を使い、東海道の 宿場町や、富士の自然を楽しんだ 4 関宿、奈良(5月)旦那と 吉野の金峯山寺で、特別公開をされた日本 最大の秘仏である御本尊の「金剛蔵王大権現 立像3体」を見るために、途中、関宿などで 寄り道をしながら、奈良に行った 5 飛騨古川、高山(6月)旦那と 選べる昼食付き日帰り温泉の招待で、高山に 行ったついでに、飛騨古川に足を伸ばした 番外 愛・地球博(4~8月来場)姉と。娘&旦那と。姉と。娘と やはり、これを忘れてはいけない。人気の 企業館も忘れがたいし、世界中の外国館で 楽しい体験をさせていただいた。名古屋で 前泊をすることで、前田利家の荒子などの 観光スポットも、まわることが出来た 日本グランプリに行くのを、楽しみにしていた 息子は、部活が入って、今年は、家族との 行楽は無かったが、学校から愛・地球博に 出かけ、12月には友達とスケートに行って 楽しんだようだ さて、皆さんの2005年の「旅行&行楽& イベントなどのベスト5」はありますか?
2005年12月28日
閲覧総数 3










