2018年08月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

ペリカンの家のキジバト
今日は、喫茶店・ペリカンの家のキジバトの記事です。 来月16日に予定しているペリカンの家主催の明日香サイクリングについて、友人の偐山頭火氏が、地図に目的地(立ち寄り先)を落とし込んだコース地図を作成し、Eメールで送ってくれました。小生は、立ち寄り先にある万葉歌碑の歌とその現代語訳を付したものを作成しましたので、これらをPCから参加予定人数分印刷し、ペリカンの家にお届けしました。可能な場合は、参加希望者にそれらを配布して頂こうという訳です。 ペリカンの家に入ると、店主のももの郎女さんが鳩が巣を作っていると仰る。店の入口の左側、喫煙用のベンチの隣にあるシマトネリコの木に鳩らしき鳥が巣を掛けていました。よく見ると鳩は鳩でも、普通の鳩ではなく、キジバトでした。ヤマバトとも呼ぶ野鳥である。 ももの郎女さんによると、先日から店の前の電線にとまっていて何度も目が合ったと仰っていましたが、それは既に巣作りをしていて、警戒して様子を見ていたということであったのかも知れない。 彼女は、鳥の羽毛が苦手らしいので、店先の木に巣を作られて、そこから親鳥やヒナの羽毛が落下して来るのはノーサンキューとのことでありました。しかし、山の鳥がやって来て巣を掛けてしまった以上、我慢するしかないのでしょうな。 ペリカンの家とあるので、キジバトさんも親近感を覚えて、「此処に巣を作ろう。」と考えたのかも知れない(笑)。(キジバト) この角度では、普通の鳩にも見えるが、下の写真のように、少し動いた時に見えた、羽根の模様からヤマバト、キジバトであるということが見てとれました。(同上)(同上) いよいよ、ペリカンの家も「キジバトの家」或は「ヤマバトの家」に改名しなくては、いけないかも(笑)。 もう、卵を産んでいるのかどうかは、下からでは分からないが、ちょこんと巣におさまっている姿などからは、卵を抱いているようにも見える。<後日談> その後ヒナがかえったものの、9月4日の台風21号の直撃を受け、巣が崩壊。ヒナが2羽落下し、命を落としてしまったようです。是非に及ばず、であります。〇キジ鳩さ~ん頑張れ~(T-T)〇朝電線に
2018.08.29
コメント(6)
-

ペリカンの家サイクリング下見
(承前) ペリカンの家主催の明日香サイクリングの下見です。 本番は午前11時橿原神宮前駅東口集合・出発なので、下見もなるべくそれに近い時間帯でと、午前9時半頃近鉄枚岡発の電車に乗車、大和西大寺駅で乗り換えすべくホームに降り立ったところで、ポケットに財布が入っていないことに気がつく。自転車のキーも入っていない。 自宅の妻に電話するとテーブルにそれらは置かれたままになっているとのこと。出掛ける前にズボンを新しいものに穿き替えた時に入れ忘れたよう。どうやら途中で失くしたのではないことにひと安心。「何処かでカードで現金を引き出すからそのままにして置いてくれ」と言いかけて、キャッシュカードもその財布の中にあることに気が付き、ひとまず自宅へUターン。出直しとなりました。 ポケットには千円札1枚とコインが何枚かのバラ銭が入っていました。乗車券はICカードで乗降しているので、切符を買うということはない。チャージ残高は3千円余ある。自転車のキーがないので、駐輪・ロックして自転車の前を遠く離れるということはできないが、トレンクルは肩に担いだまま山道も登れるほどに軽いから、引き返さずにそのまま行ってしまっても良かったのであった。だが、何か突発事が生じてお金が必要となった場合にお手上げとなるので、引き返したという次第。結果から言えば、何事も起こらなかったので、引き返さずに続行しても問題はなかったのであった。念のため、用心したという次第。 そんなことで、橿原神宮前駅に到着したら午前11時35分前後になっていました。駅構内のお店で、お弁当と飲み物を購入して、東口駅前からトレンクルで出発。当日もお弁当持参の計画になっているので、同じパターンで廻ることとした。(橿原神宮前駅東口付近) 先ず、神武天皇陵へと向かう。およそ8分で到着。(神武天皇陵遥拝所)<参考>神武天皇陵の写真掲載のブログ過去記事 2011年1月11日 大和新庄・畝傍山周辺銀輪散歩(その2) 2014年3月20日 明日香・橿原銀輪散歩(その2) 神武陵の片隅の木陰でお弁当タイム。昼食休憩の後、大久保公民館裏手の大窪寺跡の万葉歌碑へ向かう。 12時22分到着。(大久保児童公園の万葉歌碑)春さらばかざしにせむと我が思ひし桜の花は散り行けるかも(万葉集巻16-3786)(春になったら髪に挿そうと思っていた桜の花は散って行ってしまたよ。)妹が名にかけたる桜花咲かば常にや恋ひむいや毎年に(万葉集巻16-3787)(あの娘と同じ名の桜の花が咲いたら、いつも恋しく思うことだろう。来る年ごとに。)(桜児伝説の桜児の墓と言われる娘子塚)<参考>大久保児童公園の万葉歌碑の写真掲載の過去記事 2014年9月23日 桜児伝説(畝傍御陵前駅) 畝傍御陵前駅北側踏切を渡り、東へ。国道169号を渡り、更に東へ。本薬師寺跡到着が12時37分。昨日の日記に記載の通り、ホテイアオイが咲き群れていて、黒豚のブーイに此処で遭遇。<参考>本薬師寺跡に関する過去記事 2012年10月16日 磐余銀輪散歩別巻(2)・本薬師寺趾 12時40分に本薬師寺跡を出発。飛鳥川に出て、川沿いの自転車道を北へ。さなぶり餅を買うために是非ともというももの郎女さんのご要望で急遽組み入れた寄り道先「さなぶりや」であるが、飛鳥川自転車道を走るので、サイクリングとしては丁度よいのかも知れない。 12時50分さなぶりや前到着。(さなぶりや) わが名はヤカ餅なるもさなぶり餅は興味なく、本番でも購入する気は更にもない。まして下見の今回、買う筈もこれなく店の前を素通り。再び飛鳥川自転車道に戻り、来た道を引き返す。 途中、飛騨町交差点で飛鳥川とお別れし、香具山方向へと東に向かう。(飛騨町交差点) その途中にあるのが、藤原京朱雀大路跡。道路を挟んで向かい側には万葉歌碑もあるので、これも見て行くこととしよう。藤原の古りにし里の秋萩は咲きて散りにき君待ちかねて(万葉集巻10-2289)(藤原の古い都の秋萩は咲いて散ってしまいました。あなたを待ちかねて。)<参考>藤原京朱雀大路跡向かいの万葉歌碑写真掲載の過去記事 2014年3月19日 明日香・橿原銀輪散歩(その1)(藤原京朱雀大路跡)(同上・説明碑) 道を東へ。香具山が目前に迫って来る。突き当りで左折すると、登山口へとつながる脇道へと入る角に休憩所がある。昼食場所の候補地である。13時16分到着である。(本番の時間帯に焼き直し、本薬師寺跡での休憩時間やさなぶりやでの買い物時間などを計算して当てはめてみると、13時15分頃となる。少し遅い昼食時間となるが、何とか許容範囲内の時刻であろう。)(香具山西麓の休憩所) 問題は、先客によって占領されている場合の措置であるが、その時はその時で、臨機に代替案を考えることとしよう。 此処に自転車を駐輪し、香具山登山組は徒歩で天香久山神社と香具山山頂へと向かい、残留組は、北側100mほど先の奈良文化財研究所展示館を見学していただくこととしましょう。<参考>奈良文化財研究所関連過去記事 2012年10月2日 万葉ウオーク下見(3)・古池から奈良文化財研究所まで(香具山西側旧登山口の万葉歌碑)大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙り立ち立つ 海原は かまめ立ち立つ うまし国そ あきづしま 大和の国は(万葉集巻1-2)(大和の国には多くの山々があるが、中でも近い天の香具山に登り立って国見をすると、平野にはかまどの煙があちこちから立ち昇っている。水面にはカモメの群れが飛び立っている。素晴らしい国であることだ。<あきづしま>大和の国は。)(同上・もう一つの万葉歌碑)久方の天の香具山この夕べ霞たなびく春立つらしも(柿本人麻呂 万葉集巻10-1812)(<ひさかたの>天の香具山は、この夕べ、霞がたなびいている。春が立つらしいなあ。)(香具山説明碑) 旧登山口から北に回り込んだところにあるのが、天香久山神社。山頂へはこの神社の参道脇から登る。(天香久山神社境内の万葉歌碑)<参考>天香久山神社境内の万葉歌碑の過去記事 2014年3月19日 明日香・橿原銀輪散歩(その1) 境内から香具山山頂までは上り9分、下り5分、往復で14分でしたから、山頂で5分程度時間を過ごすとして、20分を見て置けばいいか。(香具山山頂から畝傍山、二上山などを望む。)(香具山山頂・国常立神社)<参考>天香久山神社、国常立神社の写真掲載の過去記事 2013年3月23日 大和三山銀輪散歩 下の休憩所と山頂との往復時間は40分もあればいいだろう。 天香久山神社を13時47分に出発して、雷丘万葉歌碑前到着が13時59分。(本番の時間に焼き直すと、14時30分休憩所発で14時45分雷丘万葉歌碑到着、14時55分甘樫丘到着だろう。この分では、橿原神宮前駅に帰り着くのは17時を過ぎてしまう可能性もある。)何処かで立ち寄り先をカットするなどする必要があるかも。 そもそも、参加者の走行速度・ペースがよく分からないので、計画の立てようもないから、コースや立ち寄り先は成り行きで柔軟に変更するしかないでしょうな。(雷丘万葉歌碑 後方の小丘が雷丘)大君は神にしませば天雲の雷の上にいほらせるかも(柿本人麻呂 万葉集巻3-235)(わが大君は神でいらっしゃるので、天雲の雷の上に仮の庵を作り宮として居られる。)<参考>雷丘万葉歌碑の過去記事 2014年5月31日 飛鳥川銀輪散歩 甘樫丘の茶屋前到着が14時06分(本番での見込み時刻14時55分)。ここで氷菓子を食べて暫し休憩。本番ではここで丘に登り、ぐるりめぐって犬養万葉歌碑第1号を見ていただこうと思っているので、20分滞在の予定。(甘樫丘麓の休憩所)采女の袖吹き返す明日香風都を遠みいたづらに吹く (志貴皇子 万葉集巻1-51)(采女の袖を吹き返した明日香風は、都が遠くなったので、ただ空しく吹いている。)<参考>甘樫丘犬養万葉歌碑の写真掲載過去記事 2009年11月26日 明日香小旅行下見・番外篇 上の写真のように、広い休憩所があるので、昼食場所としては最適であるが、今回のコース取りでは午後3時に近い到着となるから、いくら何でも遅すぎる。 14時33分甘樫丘出発(本番見込み時刻15時15分)。 14時44分飛鳥坐神社到着(本番見込み時刻15時22分)。(飛鳥坐神社)みもろは 人の守る山 もとへは あしび花さき すゑへは 椿花さく うらぐはし 山そ 泣く子守る山 (万葉集巻13-3222)(三諸の山は、人が大切に守っている山。ふもとの方には馬酔木の花が咲き、上の方では椿の花が咲く。美しい山だ。泣く子の守をするように人が大切に守っている山である。)大君は神にしませば赤駒の腹這ふ田居を都と成しつ(大伴御行 万葉集巻19-4260) (大君は神でいらっしゃるので、赤駒が腹這う田んぼを都になさった)斎串立て神酒すゑ奉る神主部のうずの玉蔭見ればともしも (万葉集巻13-3229) (斎串を立てて、神酒を据えて奉る神主の髪飾りのカズラを見ると心惹かれる。)<参考>飛鳥坐神社及び境内万葉歌碑の過去記事 2017年1月24日 明日香銀輪散歩(その2) この神社にも3基の万葉歌碑があるので、本殿参拝のついでにざっと見ていただくべく、13分程度の滞在時間を考えているが、これも状況次第です。下見のこの日は鳥居前で失礼申し上げました。かたわらでは、小学生の姉弟と見られる二人が若いお父さんに付き添われて写生をしていました。夏休みの宿題なんだろう。お父さんの方は、隣でスマホに熱中されていましたが(笑)。いい絵が描けますように。 飛鳥寺の前を通って田中の道を西へ回り込み蘇我入鹿のものという首塚へ。首塚到着は14時45分(本番見込み時刻15時40分)。(首塚)<参考>首塚、飛鳥寺の過去記事 2009年11月30日 (続)明日香小旅行・読書会の仲間と 2017年1月24日 明日香銀輪散歩(その2)(飛鳥寺 西側から) 飛鳥民俗資料館前の万葉歌碑へまわるのを省略して、板蓋宮跡へ。 板蓋宮跡到着14時51分(本番見込み時刻15時45分)。(伝飛鳥板蓋宮跡)<参考>板蓋宮跡の写真掲載の過去記事 2017年1月24日 明日香銀輪散歩(その2) 14時55分(本番見込み時刻15時55分)犬養万葉記念館前到着。(犬養万葉記念館)山吹の 立ちよそひたる 山清水 汲みに行かめど 道の知らなく (高市皇子 万葉集巻2-158)(山吹が咲いている山の清水を汲みに行きたいけれど、そこへの道が分らない。)<参考>犬養万葉記念館及び前庭の万葉歌碑関連過去記事 2009年11月30日 (続)明日香小旅行・読書会の仲間と 2017年1月24日 明日香銀輪散歩(その2) この前庭にも万葉歌碑があるので、入館時間の余裕は無さそうであるが、歌碑だけは見学させていただこうと思っている。 15時02分(本番見込み時刻16時10分)石舞台前に到着。 石舞台への入場は割愛せざるを得ないでしょう。(石舞台 正面の生垣の向こう側が石舞台) 石舞台前から飛鳥川畔の道までは5分程度。 15時07分(本番見込み時間16時20分)犬養万葉歌碑前に到着。(飛鳥川畔の犬養万葉歌碑)明日香川 瀬瀬の玉藻の うちなびき 心は妹に 寄りにけるかも (万葉集巻13-3267)(飛鳥川の瀬々の玉藻のようにうちなびいて、心はあなたに寄ってしまったよ。)<参考>上記犬養万葉歌碑の写真掲載の過去記事 2014年3月20日 明日香・橿原銀輪散歩(その2) 橘寺を左手奥に見つつ、飛鳥川自転車道を辿り、帰途へとつく。(橘寺遠望) 飛鳥川左岸の自転車道を走り、甘樫丘の前で広い道路を渡った処で右岸の道に入る。どちらを走ってもいいのだが、右岸を行けば、万葉歌碑が更に2基あるので、これをついでに見てみようというコース取りである。(万葉歌碑)飛ぶ鳥の 明日香の里を 置きて去なば 君があたりは 見えずかもあらむ (元明天皇 万葉集巻1-78)(<飛ぶ鳥の>明日香の故郷を後にして行ってしまったなら、あなたの辺りは見えないことであろうか。)(同上)<参考>2014年3月20日 明日香・橿原銀輪散歩(その2)わが屋外やどに 蒔きしなでしこ いつしかも 花に咲きなむ 比なぞへつつ見む (大伴家持 万葉集巻8-1448)(わが家の庭に種を蒔いたナデシコはいつになったら花が咲くのだろうか。それをあなただと思って眺めることとしよう。) この歌碑の北側で橋を渡って左岸の道に移り、少し戻った三叉路を右(西)へ。橿原神宮前駅へと走る。途中の剣池(石川池)畔にも万葉歌碑がある。(剣池の万葉歌碑)輕の池の汭廻うらみ行き廻みる鴨すらに玉藻のうへに独ひとり宿ねなくに (紀皇女 万葉集巻3-390)(軽の池の浦のめぐりに沿って泳ぎ回る鴨でさえも、玉藻の上には一人で寝ないものを。)みはかしを 劒つるぎの池の はちす葉に たまれる水の 行方ゆくへなみ わがせし時に あふべしと あひたる君を な寝そと 母聞きこせども わが心 清隅きよすみの池の 池の底 吾は忘れじ ただに逢ふまでに (万葉集巻13-3289)(<みはかしを>剣の池の蓮の葉にたまっている水のように、行くへもなく思い悩んでいた時に、逢おうと言ってくれたあなたのことを、共寝してはいけないと母は言うけれど、<わが心>清澄の池の、池の底のように深く思って、私は忘れまい。じかにお逢いするまで。)<参考>剣池万葉歌碑と孝元天皇陵関連過去記事 2013年3月23日 大和三山銀輪散歩(剣池と孝元天皇陵) 剣池(石川池)の堤に上がって、木陰の風に暫し吹かれて休憩。 橿原神宮前駅到着15時45分頃でした。本番での見込み時刻は17時頃になるかと思われるので、もう少し早くに帰って来る必要があるのであれば、立ち寄り先をカットして、コースの短縮を図らなければならないかも。<参考>〇本番の記事はコチラ〇銀輪万葉・奈良県篇
2018.08.27
コメント(6)
-

ホテイアオイと黒豚
喫茶・ペリカンの家の店主、ももの郎女さんがその友人や店のお客様らと明日香をサイクリングすることを計画して居られ、そのコース設定と案内役を仰せつかった。サイクリングの主目的は本薬師寺跡のホテイアオイの花を見ることということで、これは外せない。 ということで、小生の設定したコース案は下記の通りとなりました。実施予定日は9月16日(日)で、当日雨天の場合は同23日(日)に順延するというもの。橿原神宮前駅東口集合・駅前のレンタルサイクルで出発→神武天皇陵→大窪寺跡万葉歌碑→本薬師寺跡(万葉歌碑)→飛鳥川自転車道→さなぶり屋(さなぶり餅)→飛騨町交差点→藤原京朱雀大路跡(万葉歌碑)→香具山西麓休憩所(昼食)→天香久山神社(万葉歌碑)→香具山山頂→雷丘万葉歌碑→甘樫丘(万葉歌碑)→飛鳥坐神社(万葉歌碑)→飛鳥寺・首塚→板蓋宮跡(万葉歌碑)→犬養万葉記念館(万葉歌碑)→石舞台古墳地区→飛鳥川自転車道(万葉歌碑3基)→剣池(石川池)万葉歌碑・孝元天皇陵→橿原神宮前駅東口 ということで、昨日(25日)、折りたたみ自転車・トレンクルを持って、橿原神宮前駅まで出向き、コース下見をして来ました。なお、さなぶり屋はももの郎女さんのご要望で無理に押し込んだ寄り道である。 ももの郎女さんは本薬師寺跡を昼食場所としたいと仰っていたが、お手洗いが無いので適地ではない。甘樫丘がいいのだが、時間的に遅くなってしまって不適。ということで、香具山西麓・奈良文化財研究所南側にある休憩所を昼食場所にする予定。自販機もあり、隣にはトイレもあるので、景色は別として悪くはない立地である。 此処で昼食をとった後、自転車は此処に置いて、徒歩で香具山に登ることとする。足に不安があって、香具山に登らない人も居るので、その人達は、登山組が帰って来る30分~40分程度の待ち時間を利用して、奈良文化財研究所の展示室を見学していただいてもいいだろう。 わが友人の偐山頭火氏も参加されるとももの郎女さんからお聞きしているので、こちらの案内、誘導は同氏と越郎女さんにお願いしますかな。 さて、問題のホテイアオイであるがもう満開と言ってよい状況で、多くの見学者が来られていました。(本薬師寺跡のホテイアオイ 後方右は畝傍山)(同上)(同上) そこで、思わぬものに遭遇。(ブーブー)(同上) ブタの品種のことなどはトンと存じ上げぬが、黒いから黒豚だろうという次第。赤いタスキと尻尾のリボン。多分、メス豚なのだろう。これは食品ではなくペット。飼主の女性が「ブーイ」とか呼んで居られましたから、名は「ブーイ」である。つい、「部位」などという漢字が思い浮かぶのは「食品」としての「豚」というものに馴染んでしまっているわが脳みその品格の欠如である。流石に「美味しそう」などとは思わなかったのではあるが。 コース下見のことは、明日の記事でご紹介することとし、本日はこれまで。
2018.08.26
コメント(12)
-

和麻呂逝く
高校時代からの友人、和麻呂君こと大嶽和久君が亡くなられた。 何んと悲しいことか。 高校一年生から二年生になる春休みに、初めて訪ねた日本基督教団小阪教会で、小生は彼と出会った。教会の高校生会でのことである。その当時の高校生会の同学年の仲間には、彼の他に槇麻呂君、邦麻呂君、リチ女さん、和郎女さん、寿郎女さんなどがいた(読書会のメンバーではないが、高校生会の同学年には、他にも伊〇君や石〇君などがいたのを記憶している。女生徒も他に居たような気もするが今は記憶の外である。)。青年会のメンバーが教会学校の各クラスの指導をするという仕組みになっていて、我々のクラスを担任されたのが凡鬼さんでありました。皆さん、現在の若草読書会のメンバーですから、そのままのお付き合いが今も続いているという次第。尤も、寿郎女さんは既に故人ではある。<参考>山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど・・2008.10.29. 和麻呂君との思い出は色々あるが、その第一のものは、2007年6月に槇麻呂君の企画で、和麻呂、槇麻呂、偐家持の男3人と寿郎女、和郎女、リチ女の女3人とで2泊3日の熊野旅行をしたことであろうか。 また、同じく2007年の4月であったか、彼が「万葉孤悲歌」という筝曲を作曲するに当たり、万葉の恋歌や犬養節の万葉歌をイメージして曲作りをしたいと言って来たので、たまたま、犬養先生生誕100年記念事業の一つとして、甘橿丘の第1号犬養万葉歌碑の副碑(解説板)建立の除幕式があり、彼と二人でこれに参加し、その後の橿原神宮の会館でのパーテイーにも参加したことが第二の思い出だろうか。 これらの懐かしい思い出の日々から11年、寿郎女さんが亡くなられてから10年、彼が旅立ってしまうとは・・。 もう一つ、もっと古い思い出と言うか、こんなエピソードもありました。 会社の仕事での出張であったかと思うが、新潟へと北陸線で向かっていた時に、高岡から乗車されたご婦人と席が隣り合わせたことがあった。言葉を交わすうちに、そのご婦人から名刺を頂いた。それには、高岡商業高校の筝曲部「かたかごの会」というようなことが書かれていて、お琴の指導をされている先生であったようで、「私の友人にも、琴の先生をしているのがいる。〇〇という奴ですが。」と申し上げると、彼女が「ああ、その方なら存じ上げています。有名な方です。」と仰ったのには驚いたのであった。同時に和麻呂君のことを改めて見直したということでもありました(笑)。 いつも優しい眼差し、穏やかな語り口と声、もうそれらを目にし、耳にすることもないのだと思うと、無性に悲しく、寂しく、無念である。 旅先で同じ部屋になって、彼の高鼾に悩まされて眠れなかったことなども今は無性に懐かしい。 どうぞ、やすらかにお眠り下さい。あなたのことは忘れません。 昨日の夕刻は、凡鬼さん、景郎女さん、小万知さん、和郎女さん、槇麻呂さん達と、ご遺体にお別れをして来ましたが、本日が告別式。若草読書会の仲間では、槇麻呂君、偐山頭火君らと共に参列。斎場までお見送りをし、そこで失礼して、帰って参りました。(ご遺影) 台風20号が近づいていますが、空はまだ晴れていて、八戸ノ里駅までの道を汗だくになりながら歩きました。青い空と白い雲、くっきりと見える生駒の山並み、明るすぎる景色は却って悲しみを誘う。(今日の空)わが背子は いづち行かめや 生駒嶺に 問ふもむなしき 横雲の空さ夜更けて すだく虫の音 ころころと ひとりし泣かゆ 背子は逝きにし君逝けば いたもすべ無み 秋の夜の 虫にもあれや 哭のみし泣かゆ箏の音は 途絶えたりける 面影の ここだも立ちて 心ぞ痛き 当ブログでも和麻呂君は度々登場しているが、それらの記事を以下に列記して、在りし日を偲ばん。2007年6月18日 一座面々面見世之歌2007年9月26日 「万葉孤悲歌」2007年12月1日 万葉孤悲歌・高校同窓会2008年5月31日 舞洲・若草読書会2009年2月13日 花月2009年11月29日 明日香小旅行・若草読書会の仲間と2009年11月30日 (続)明日香小旅行・読書会の仲間と2011年1月30日 若草読書会2011年6月28日 しあわせの村小旅行2011年9月25日 俳句の話・若草読書会2012年8月5日 若草読書会2012.8.5.2013年4月7日 桜花散りぬる風のなごりにはたこ焼きしつつ2013年12月7日 布留の里2014年5月3日 大坂夏の陣・小松山合戦まつり2014年8月21日 若草読書会夏之陣(上)2014年12月6日 誓いのとき2015年2月1日 若草読書会・あは雪のほどろほどろに降りしけば2015年10月20日 風の音秋は葉ぞ匂ふ2016年2月7日 2016新春若草読書会2016年4月3日 若草読書会のお花見2017年12月2日 山里の歌・関西邦楽作曲家協会第39回作品発表会2018年3月22日 第50回記念大嶽筝曲学院春期演奏会偐万葉・若草篇(その1)偐万葉・若草篇(その10)
2018.08.23
コメント(12)
-

偐万葉・あすかのそら篇(その5)
偐万葉・あすかのそら篇(その5) 本日は久々に偐万葉シリーズ記事とします。 このところ、コメントに付す歌も少なくなているのか、そもそもコメント書き込みそのものが少なくなっているのか、偐万葉シリーズに掲載すべき歌の数がなかなか増えない。 そんな中で、あすかのそらさん関連の歌が本日で20首となりましたので、偐万葉・あすかのそら篇(その5)を記事アップです。 偐万葉シリーズとしては第295弾。本年5月30日の閑人篇(その12)以来ですから3ヶ月ぶりとなり、あすかのそら篇としては、昨年の3月27日以来ですから、1年5ヶ月ぶりの記事となります。<参考>過去の偐万葉・あすかのそら篇はコチラから。 あすかのそら氏のブログはコチラから。 偐家持が明日香郎女に贈りて詠める歌20首沖の島にあの手この手や亀の手を 採らむと妹は船出すらむか (海辺の可不可)(20170518カメノテ採り)モクレンのつぼみたるらしカメノテは 人こそ知らね月の夜に咲く (亀家持)(20170518カメノテ)花の名は 紫式部に 及ばねど 墓でまさるか 和泉の式部 (清少納豆)(注)第5句は初案「和泉式部は」を「和泉の式部」に修正した。もみぢ葉の 下照る道を いざ行かな 熊野の奥の 犬落(いぬおち)の滝(20171122紅葉の下照る道)犬落の 滝にし添へる もみつ葉を われ見が欲(ほ)しと ひとりぞ来しか(20171122百間山渓谷の紅葉)犬落の 滝のかへるで つれなきや 来(こ)よとはあすか まだもみたはず(注)かへるで=蛙手。楓のこと。もみたはず=「もみたふ」は紅葉すること。(20171122犬落の滝)百間(ひゃっけん)の 渓(たに)のもみぢ葉 わが行けば 見る人なけれ ここだ匂へり(注)ここだ匂へり=ここぞとばかり照り映えている。初日の出 空かぎろひて 待つほどに 今ぞ昇り来(く) 雲の嶺より(20180103初日の出)あらたまの 年の始めの 初日の出 おろがむ人の きらきらし顔(注)第5句の初案「顔きらきらし」を偐万葉掲載にあたり「きらきらし顔」に修正。山川(やまかはを 隔(へ)なりてわれも 我妹子と 同じき時に 月をぞ見しか (月見家持)(20180201月食)この月はあすかのそらの月なれど きのふのそらの月にもあれり (あさってのそらまめ)真熊野の 浦の浜辺に 寄す波に 八十伴(やそとも)の男(を)は 禊(みそぎ)立ちける(本歌)婦負川(めひがは)の 早き瀬ごとに 篝(かがり)さし 八十伴(やそとも)の男(を)は 鵜川(うかは)立ちけり (大伴家持 万葉集巻17-4023)(注)婦負川=富山市婦中町辺りの神通川の古名。鵜坂川とも呼ばれた。 八十伴の男=多くの官人たち。 鵜川立ち=鵜飼いをすること。(20180207禊)入り組める 線路に見ゆる 転轍の わざの妙あり 見れど飽かなく (あすかの西大寺)(20180330近鉄西大寺駅)ニャンにゃるも ニャーといふのみ ニャといふを ニャとて返すは ニャンたることニャ (ニャの郎女)(本歌)来むといふも 来ぬ時あるを 来じといふを 来むとは待たじ 来じといふものを (大伴坂上郎女 万葉集巻4-527)(20180402ニャン?)くのいちの あすかのそらや 伊賀の春 (忍々)(元句)旧里(ふるさと)や臍の緒に泣(なく)としの暮 (芭蕉)石垣に 見惚(みと)れあすかは 伊賀のそら ひとり行く子に 声かけましを (伊賀虫麻呂)(20180424伊賀上野城石垣)外(と)つ国の 人も忍者に 伊賀の春 一人(ひとり)が二人(ににん) 二人(ににん)が八人(はちにん) (忍々家持)(20180424忍者一人)(20180424忍者二人)(20180424忍者八人)何となし陰ある如がよかりけり をのこをみなの一人し飲める (一人家持)山中湖 めぐり行けども 寄らざりき 花の都は 知らず悔しも (田舎家持)(20180627山中湖花の都公園)いのししは 夕餉(ゆふげ)求むと 飛ぶ鳥の あすかのそらに あひにけるかも (徒歩皇女(とほのひめみこ))(本歌)むささびは 木末(こぬれ)求むと あしひきの 山の猟夫(さつを)に あひにけるかも (志貴皇子 万葉集巻3-267)愛(かな)しウリ坊 いづち行かめと わがカメラ 手許にあらなく 今し悔しも (逸機皇女(いっきのひめみこ))(本歌)愛(かな)し妹を いづち行かめと 山(やま)菅(すげ)の 背向(そがひ)に宿(ね)しく 今し悔しも (万葉集巻15-3577)(20180820イノシシ)<注>掲載の写真は全てあすかのそら氏のブログからの転載です。
2018.08.21
コメント(6)
-

2018年青雲会囲碁大会
本日は青雲会の囲碁大会でした。 青雲会囲碁の例会にはこの処ご無沙汰しているが、年1回の囲碁大会だけはここ数年毎回出席しているので、今年も参加することとしました。 会場は、昨年と同じく、マイドームおおさか。12時50分集合ということであったので、早めに家を出て、地下鉄谷町4丁目駅近くのレストランで昼食を済ませてから、会場に向かうこととしました。 昼食を済ませてレストランを出て時間を見ると、まだちょっと早過ぎる到着になりそうなので、途中の公園、中大江公園に立ち寄って、食後の紫煙一服。(中大江公園) 公園の一角に何やら石碑があるので、近寄ってみると、宇野浩二の文学碑でありました。この作家の作品は読んだことがないが、その名前だけは存じ上げている。(宇野浩二文学碑)<参考>宇野浩二・Wikipedia(同上・副碑) 会場はマイドームおおさかの8階。(マイドームおおさか) ここまでは昨年と同じであるが、昨年がサロン会議室であったのに対して、今年はその隣の和室が会場でありました。サロン会議室は先約があって、ふさがっていたよう。 12時20分頃にその和室に入ると、世話役の銭〇氏が既に来て居られました。今回の出席者は8名とのこと。例年になく少ない参加者である。銭〇氏と雑談しているうちに、五〇氏、金〇氏、田〇氏、下〇氏、山〇氏がお見えになり、最後に廣〇氏が到着で全員が揃いました。(会場風景)(同上) 早くも「ベスト8か。」というどなたかの冗談に笑いながら、抽選で決まったトーナメント形式による対戦相手との対局が始まりました。 小生の対戦相手は山〇氏。完敗。山〇氏は廣〇氏・下〇氏戦の勝者廣〇氏にも勝ち、決勝戦進出。もう一方のブロックから決勝戦に進出された金〇氏にも勝利され、優勝。 小生は、一局目敗戦後、これまた一局目敗戦された下〇氏と番外の練習対局。これは、終盤で上辺の黒の薄みをついた手が功を奏し、黒石5子を切断、取り込んだ上、先手で右辺に回ることを得て、右辺の黒石の手抜きを咎めてこれを殺したところで勝負あったとなって、中押し勝ち。まあ、大会の成績は別として、1勝1敗でありましたから、よしとしましょう(笑)。 終了後、1階のレストランに移動、表彰式兼懇親会で、皆さんと楽しく会食でした。午後7時散会。<参考>2017青雲会囲碁大会 2017.7.8. 囲碁関連の過去記事はコチラ。
2018.08.18
コメント(6)
-
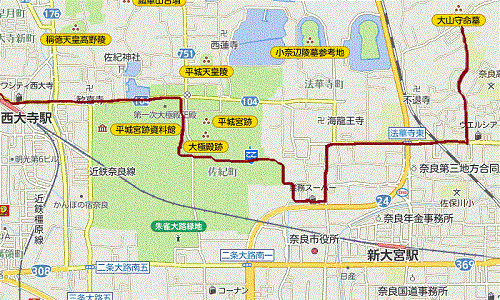
平城宮趾公園から伝・称徳天皇山荘跡へ
(承前) 昨日の記事の続きです。 大山守皇子墓から一条通りへ戻り、平城宮趾公園へと向かいます。思えば平城宮趾公園も久しぶりである。ブログ過去記事で調てみると、昨年の8月29日以来だからほぼ1年ぶりということになる。<参考>叡尊墓と北山十八間戸へ 2017.8.29. 例によって、裏口から入ることとする。東院庭園の裏にある法華寺旧境内阿弥陀浄土院跡から公園に入ることとする。(大山守皇子墓から平城宮趾公園への走行コース)(法華寺旧境内・阿弥陀浄土院跡)(同上・説明板) 説明板に記載されている「地上に見える花崗岩の大きな立石」というのはこれのことか。(田圃の中の大きな石) 白洲正子「十一面観音巡礼」(講談社文芸文庫)の第3章の「幻の寺」という項で「神社のそばの田圃の中に、動かすと祟りがあるという大きな石が遺っているが、もしかすると、お堂はそこにあったのではないか。」(50頁)と記載されている石も多分これであるのだろう。 同書によると、法華寺には本尊の十一面観音のほかにもう一体の十一面観音像があり、その光背裏面に、 桜梅天神十一面観音 延宝五年丁巳二月□日 御本地堂後光基座 願主 法華寺高慶という銘があり、御本地堂から法華寺本堂に引っ越して来られたものらしい。そして、この御本地堂は、宇奈多理神社の境内に明治の頃まで建っていたらしいが、この石のある辺りに建っていたのではないかと推理されている訳である。「十一面観音巡礼」単行本(新潮社)は昭和50年(1975年)12月刊行だから、2000年の発掘調査でそれが裏付けられる25年前のことである。 ということで、ついでにその宇奈多理神社にも立ち寄って行くこととする。その正式な名称は宇奈多理坐高御魂神社である。(宇奈多理坐高御魂神社)<参考>宇奈多理坐高御魂神社 この神社には何度か来ているが、門が閉まっていることが多く、中に入ったという記憶が余りない。この日は門が開いていました。(同上)(同上・由緒)(同上・境内)(同上・櫻梅神社の銘ある燈籠) この神社は江戸時代には桜梅天神、桜梅神社とも呼ばれたようだが、その名残が境内の燈籠の銘に見られる。これは「楊梅」の誤りだろうと考えられる。 平城天皇の陵を「楊梅陵(やまもものみささぎ)」と呼ぶことや、孝謙(称徳)天皇や光仁天皇の時代に「楊梅宮」と呼ばれたのは東院のことと解されているところ、その東院庭園がこの神社に隣接して存在していることなどを考えれば、「御所の神社」と言う意味で、これを「楊梅神社」と呼んだものと見るのが自然であろう。その「ようばい」が訛って「おうばい」となり、「楊梅」が「桜梅」と誤記されるに至ったという訳である。(同上・本殿) 宇奈多理神社と東院庭園との間の細道、即ち、楊梅神社と楊梅宮との間の細道から平城宮趾公園に進入であります。<参考>第一次大極殿跡付近から見た宇奈多理神社の杜の写真掲載記事 奈良銀輪逍遥 2010.4.9. 大極殿のあるブロックへと向かう途中、ナラガシワの木陰にベンチがあったので、其処でしばし休憩です。(楢柏の木陰で・・) 大極殿の方を見やると手前に工事仮設の構造物が高々と。 築地回廊や門の復元工事が行われているようですが、これは、南側の朝堂院ブロックとの間を隔てる閤門を築造するためのものであるのだろうか。(大極殿まわりの復元工事) 北側の県道104号から大極殿を撮影。これはうしろ姿ということになりますかな。(大極殿) 平城宮趾公園を出て、県道104号を西へ。 近鉄奈良線大和西大寺駅前を通り過ぎて駅西側の踏切を渡り、南へ。西大寺の北側の細道を西へと行きます。(史蹟・西大寺境内伝称徳天皇山荘跡●印) 上の地図では西大寺の表示がされていませんが、護国院とある場所の周囲全体が西大寺境内です。<参考>西大寺については下記記事をご覧下さい。 大和西大寺駅から矢田寺経由富雄駅まで 2010.3.5. 西大寺の北側の細道を西へ入って行くと、西大寺奥之院たる体性院がある。ここは、西大寺中興の祖、叡尊の墓があるというので、昨年の8月29日に訪れていることでもあり、今回はスルーして、その北側にある飛び地の境内地へと向かう。<参考>叡尊と北山十八間戸へ 2018.8.29. 伝称徳天皇山荘跡というのは、どのような典拠、根拠があってのものかは存じ上げないが、西大寺に関するウィキペディアの記述から知ったのである。しかし、場所が西大寺宝ヶ丘と表示されているだけで、正確な位置が不明。自衛隊官舎のある付近ではないかと見当をつけて行ったら、ドンピシャ正解でした。(史跡 西大寺境内、伝称徳天皇山荘跡) されど、其処はご覧のように何もない草地と言うか雑木林と言うか、陰気な空き地なのでありました。あるのはこの石碑のみ。 称徳天皇山荘跡という表示も関連の説明表示もないので、此処がそうだという確証はないのであるが、宝ヶ丘という地名からして此処であることは先ず間違いないものと思う。それ此処はまことみかどの跡なるや わが見る限り何とてもなし(偐家持)夏草の継ぎて生ひ敷くこの原に 置きしわぎへを如何にか偲ばむ(孝偐天皇) (本歌)この里は継ぎて霜や置く夏の野にわが見し草はもみちたりけり (孝謙天皇 万葉集巻19-4268) 以上で、15日午後の銀輪散歩完結です。 何んとも尻切れトンボの結末でしたが、戯れ歌で誤魔化して置きます。 これより西大寺駅前に戻り、近鉄線で帰途につきます。 お付き合いどうもありがとうございました。(完)<参考>銀輪万葉・奈良県篇はコチラ
2018.08.17
コメント(6)
-

狭岡神社
(承前) 大山守皇子の墓を訪ねる前に立ち寄った狭岡(さおか)神社です。(狭岡神社) 狭岡神社の位置は下掲地図の通りです。(同上・位置図●印) 鳥居前に設置されている祭神八神の表示板では、この神社の開基は仁寿2年(852年)となっているが、霊亀2年(715年)に国家鎮護と藤原氏の繁栄を願って、藤原不比等が自宅である「佐保殿」に創祀したことに始まるとも伝えられる神社である。 祭神八神は以下の通り。なお、各神の説明文は、手許の「日本思想体系・古事記」(岩波書店)80~81頁の注記を参考に記載しました。若山咋神:山の境界の杙の若い神。大山咋神の対。若年神:若い稲殻の神妹若沙那賣神:沙那賣は早苗の女の意で、田植えの女神彌豆麻岐神:田に水を引く神夏高津日神:夏に高く照る太陽の神秋毘賣神:秋に収穫を掌る女神久久年神:ククは茎。稲の茎の成長を掌る神久久紀若室葛根神:葛根で結び固めた新嘗の祭のための新室の神(祭神系統図) 上は神社に掲示されていた祭神系統図です。(同上・参道) この参道の脇に、万葉歌碑があったらしいのだが、気付かずに通り過ぎてしまったようで、残念なことをしました。 それも、笠郎女が大伴家持に贈った歌の歌碑であると言うから、尚更に残念である(笑)。再訪の折に撮影することとしましょう。 因みに、その歌というのはこれです。君に恋ひ いたもすべなみ 奈良山の 小松が下に 立ち嘆くかも (笠女郎 万葉集巻4-593)(あなたが恋しくてどうしようもなく、奈良山の松の下に立って嘆いています。)(同上・舞殿と本殿)(同上・本殿) 本殿前と参道左側の鏡池の脇とに、遷都1300年祭に際して太宰府市の大宰府万葉会から贈られたという梅の木が植樹されていて、大伴旅人の歌が併記された説明板が立っていました。(同上・本殿前の梅の木)(同上・鏡池脇の梅の木)雪の色を 奪ひて咲ける 梅の花 今盛りなり 見む人もがも (大伴旅人 万葉集巻5-850)(雪の色を奪って真っ白に咲いている梅の花は、今が盛りだ。見てくれる人がいたらなあ。)(同上・天満宮標石) こんな写真も掲示されていました。(同上・今は昔)(同上) 鳥居を潜ってスグの参道左にあるのが、佐穂姫伝承地の碑と鏡池。(佐穂姫伝承地の碑)(同上・鏡池) 佐穂姫は垂仁天皇の皇后であった女性。同母兄が佐穂彦。 佐穂彦が謀反を計画。佐穂姫に「兄である俺と夫である天皇とどちらをより愛しているか。」と問い、佐穂姫が「それはお兄様の方です。」と答えると短剣を彼女に授けて「ならば、これで眠っている隙を狙って天皇を殺せ。俺が天下をとったら生涯お前は安楽である。容色が衰えたら天皇の寵愛も無くなり、他の女に取って代わられ惨めなことにもなるのだから、そうしろ。」とそそのかす。 兄の言いつけに従い、天皇を殺そうとするが、天皇への愛情から、それを果たし得ず、全てを打ち明けてしまう。天皇は「お前が悪いのではない。」と言い、直ちに佐穂彦を討つよう命令を発する。 兄の罪が赦されることもあるやと、佐穂姫は天皇との間の子・誉津別命を抱いて兄の立てこもる稲城に入るが、兄の罪が赦されぬことが明らかとなるに及び燃え落ちる稲城の中で兄と運命を共にする。その死に臨んで、彼女が自分の後釜にと推薦した5人姉妹(丹波道主王の娘)を、天皇は後宮に迎え入れ、その長女の日葉酢媛を皇后とする。日葉酢媛の生んだ3人の男子のうちの次男・大足彦が次の景行天皇である。 以上は日本書紀・垂仁紀の記述によった。古事記・垂仁記の記述は細部で少し異なる。<参考>佐穂姫命・Wikipedia 鏡池(姿見池)が佐穂姫伝説とどのようにつながるのか知らぬが、この泉の畔で若き垂仁と佐穂姫が出逢い、恋のロマンスが生まれたというような伝説もあるらしい。しかし、古事記にも日本書紀にもそのような記述は見当たらない。(神社に掲示されていた由緒書その1)(同上・その2)(同上・その3) この後、大山守皇子墓を訪ね(昨日記事)た後、平城宮趾公園に立ち寄り、西大寺奥之院の体性院北側にあるという「伝・称徳天皇山荘跡」を訪ねますが、これは明日のこととします。(つづく)
2018.08.16
コメント(2)
-

大山守皇子の墓
本日は大山守皇子の墓に墓参でありました。 お盆には両親や祖父母など先祖のお墓にお参りするのが普通であるが、先のブログ記事(8月11日)でも記したように、お盆前に我が家の墓にはお参りを済ませていますので、他人様のお墓を訪ねたという次第。 たまたま、奈良の地図を見ていて、大山守皇子の墓が奈良高校の近くにあることを発見、訪ねてみようと思い立ったのでありました。(大山守皇子の墓付近地図) 昼食を済ませてから、トレンクルを持って出かけました。 近鉄奈良線・新大宮駅到着が午後1時半頃。駅前でトレンクルを組立て、出発。法華寺東交差点で右折、一条通りを右(東)へ。コンビニ・セブンイレブンの手前で左折して北へ。突き当りが大山守皇子(大山守命)の墓である。坂の登り口に狭岡神社があり、これに立ち寄ってから大山守皇子の墓へと向かったのでありますが、狭岡神社のことは明日にでもご紹介することとし、大山守皇子の墓を先にご紹介します。 狭岡神社の鳥居前で道は二股に分れていて、右の道を行くと奈良高校。左の道が大山守皇子の墓への道である。かなりの急坂である。ギアチェンジできるMTBなら難なく上れる坂であるが、変速機の付いていないトレンクルでは、かなりキツイ。坂を上り切る少し手前に、道標がありました。(大山守命墓の道標) 道標に記載されている通り、大山守皇子(おほやまもりのみこ)は応神天皇の息子である。 応神天皇には、10人の息子がいたようだが、皇位継承で有力であったのが、大鷦鷯皇子(おほさざきのみこ)(母:皇后・仲姫)、大山守皇子(母:妃・高城入姫)、菟道稚郎子皇子(うぢのわきいらつこのみこ)(母:妃・宮主宅媛)の3人であった。応神天皇は末っ子の菟道稚郎子皇子を可愛がり、これを皇太子とする。 応神が崩御。皇太子である菟道稚郎子皇子が天皇に即位するのが順当であるが、菟道稚郎子は「私は弟。兄を差し置いて皇位にはつけない。天皇に相応しいのは大鷦鷯である。」として即位しようとしない。 ここに於いて、大山守皇子は、皇太子を殺し、自分が皇位につこうと謀反をたくらむが、大鷦鷯がこれを知り、皇太子に通報。皇太子・菟道稚郎子は戦備えをして待つ。それと知らぬ大山守は夜半に発ち数百の兵を率いてやって来る。明け方に宇治に到り、木津川を渡ろうとするが、渡し守に変装した菟道稚郎子は大山守を船に乗せ、川の中ほどで、船を大きく揺らせて傾け、大山守を川に落とす。また伏兵を岸に潜ませ、大山守が川から岸に上がるのを妨害し、これを溺死させる。その死体が考羅(かはら)の渡り(山城国綴喜郡河原村<現、京田辺市河原>)に浮かぶ。これを那羅山に葬る。(注)古事記では、宇治川でのこととし、「訶和羅」は宇治市槇島町の地と解するのが通説のよう。 その後も菟道稚郎子と大鷦鷯との間で皇位の譲り合いが続き、菟道稚郎子は、このままでは天下が乱れると、自殺してしまう。かくて大鷦鷯が天皇に即位し、仁徳天皇となる。(以上、日本書紀・仁徳天皇即位前紀より) まあ、大山守皇子からすれば、「そんなことなら、俺に皇位を譲ってくれたらよかったのに。」であったろうが、大山守皇子は他者の心が読めない単純な人物であったようで、所詮、天皇の器ではなかったのであろう。 実際は、このような譲り合いはなく、三つ巴の皇位をめぐる争いがあり、大鷦鷯がこれに勝利したということであるのだろうとは思うけれど。 坂を上り切ると右手に奈良教育大附属中学校。そこから少し下りになり、更に200mほど先、住宅団地に入って突き当りに、民家に挟まれて大山守皇子那羅山墓の参道入口がある。(大山守皇子の墓・参道) 菟道稚郎子の墓、仁徳天皇陵はこれまでに銀輪散歩で訪ねているが、大山守皇子の墓が何処にあるのか知らなかったこともあって、未訪問でありました。これで、仁徳天皇即位前紀の主人公3人の墓を全て訪問できたことになります。(同上・遥拝所) 今日は、ここまで。続きは明日にします。(つづく)
2018.08.15
コメント(0)
-

墓参・花散歩
今日はお盆を控えての墓参。3日に続いて今月2回目の墓参。 3日に撮った写真と今日撮影の写真とを織り交ぜての記事となります。 道端の畑ではトマトが熟れている。(トマトが熟れて) 墓参恒例の門前の言葉はこれ。 この門前の言葉は月ごとに新しいものに切り替えられるようですから、3日も今日も同じものになります。(門前の言葉)つらくてもおもくても 自分の荷は自分で背負って 生きさせてもらう ー東井義雄ー 夏休みとあって、隣には子供向けの言葉も。都会の夜空にも数千億の星が輝く すべての光はぼくを照らす そう言えば、或る知り合いのメールアドレスに「テンノヒカリハスベテホシ」というのがあったことを思い出しました。(2018.8.3.墓地からの眺め)(2018.8.11.同上) 墓参の後は、花散歩。 今日も夾竹桃の花が咲いていましたが、この花は花期が長いようです。下掲の写真は、先月(7月)3日の墓参の折に撮影したものですが、今日も同じような状態でした。(夾竹桃・赤花)<参考>キョウチクトウ・Wikipedia 白花のものもありました。 わが家の庭にも、南隣地境界付近に夾竹桃の木がありましたが、何年か前に伐採してしまったので、今は存在しない。(同上・白花)(同上) 次は、ナツフジ。 既に、実もつけている。 ナツフジにまといつかれている背後の木はアキニレである。(夏藤)<参考>ナツフジ・Wikipedia 上の写真は8月3日撮影。下の写真は本日撮影のものですが、上の写真のそれとは別の場所の別の木です。こちらは実が見当たりませんでした。(同上) そして、クサギ。 臭い木と書いて、臭木。葉に触ると臭い匂いがするので、子どもの頃は触らないように注意していたものだが、最近は注意しなくてもこれに触ってしまうようなことがないのは、この木に出会う機会が少なくなっているということでもあるか。(クサギ)<参考>クサギ・Wikipedia この花は長い蕊が特長。(同上) 萩も咲いている。 そう言えば、夜になると何日か前から虫の声が聞かれるようになっている。暑い、暑いと言いつつも、既に暦の上では秋。 秋来ぬと目にはさやかに見えねども、そして風の音にも驚かないヤカモチに対して、花も虫もそれとなくそれを教えてくれているのかも。(萩) 次は、イヌビエ。 イヌビエにもノギ(芒)の長いタイプのものとそれが殆ど無いタイプのものがあるようだが、これは芒の無いタイプです。(イヌビエ)(同上)<参考>イヌビエ 次は、マキ。マキにもイヌマキというのがあるが、これは、マキなのかイヌマキなのかは小生には分からない。 と、ここまで書いて、調べてみたら、マキという種名はなく、マキ科の代表的植物であるイヌマキのことをマキとも言うとのことであるから、その違いが分からぬも何も、同じ木のことをイヌマキともマキとも呼ぶのでありました。 因みに、万葉でマキ(真木)と言えば、杉やヒノキなど建築用材として、役に立つ木のことを言いますから、特定の品種の木の呼び名ではないのであります。そう言えば、薪もマキでした。杉だろうと松だろうとクヌギだろうと、燃やすための木にするために、適切なサイズに裁断した木は、全てマキなのでした。同じような感覚で、古代人は建築用材になる木のことをマキと呼んだのでしょう。(槇)<参考>イヌマキ・Wikipedia マキ科・Wikipedia 以下は、墓参の折のものではなく、今月8日の囲碁例会の折に、梅田スカイビルの里山で撮影したものですが、花散歩ということなので、協賛で掲載して置きます。 ヒガンバナの仲間、リコリス(夏水仙)です。 ご本家のヒガンバナが咲くのは、来月後半まで待たなくてはならないが、ご本家が赤と白であるので、こちらは遠慮してピンクなのが、しおらしいと言うか、義理堅いと言うか、中途半端と言うか(笑)。(リコリス<夏水仙>)<参考>ナツズイセン・Wikipedia そして、よく目にはするが名前のわからなかったカヤツリグサの仲間のこの草。ネットでその名称を調べると「ヒメクグ」だそうな。 クグというのは、カヤツリグサの仲間の古名だそうな。(ヒメクグ)<参考>ヒメクグ・Wikipedia
2018.08.11
コメント(6)
-

茄子がやって来た
茄子がやって来た。 と言っても、茄子そのものではなく、茄子の絵がやって来たのである。 友人の画家・家近健二氏から送られて来た手紙の中に茄子の絵が入っていたのでした。 来年4月に銀座で個展を開くこととなったので、その準備やそのための新しい作品制作に取り組まれているのであろう同氏からの水彩画の「茄子」でありました。(茄子の絵)<参考> 家近健二氏関連の過去記事〇雪国 2018.7.26.〇家近健二展 2018.6.24. 〇玉子と気球 2016.10.6. 〇「生前葬」という名の個展--家近健二展 2016.9.22. 〇殉展そして近隣散歩 2012.9.26. 〇ガリラヤの風 2011.11.30. 〇中之島の後、心斎橋ー油絵個展 2009.5.25.
2018.08.09
コメント(2)
-
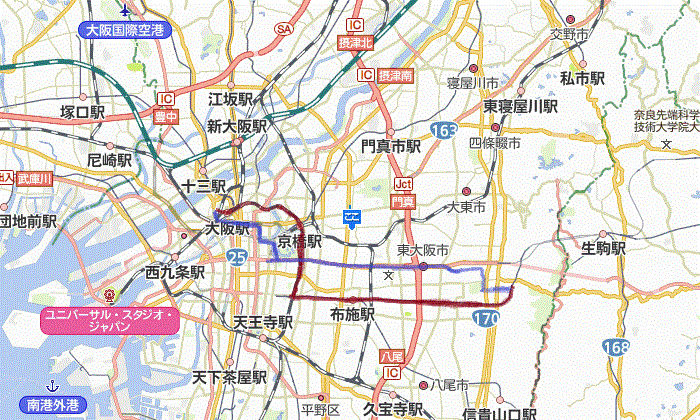
囲碁例会・水上バス
今日は、囲碁例会の日。 MTB(マウンテンバイク)で自宅を出発。 お天気に問題なければ自転車・MTBで梅田スカイビルまで行くのが通例。雨などの場合は、電車で行きます。下掲の地図で説明しますと、青い線で表示のコースがMTBの場合の走行コース(寄り道などがある場合は、これとは別のルートを走ることもあります。)、赤い線で表示のコースが電車で行く場合のコースです。 ドアtoドアで、電車だと1時間余、自転車だと1時間20分程度(寄り道したり、途中で写真を撮影したりするとその分のロスタイムが加わるので1時間30分とか40分或はそれ以上ということもあります。)で、左程の違いがありません。(囲碁例会走行基本コースー線、電車でのルートー線) で、本日は概ねこの青線コースを往復走ったという次第。 ここ数日の猛暑、酷暑に比べれば、今日は幾分ましな暑さ。勿論、それでも汗だくで、スポーツドリンクをペットボトルで2本、空にしましたので、それなりの暑さではありました。 途中、天満橋を渡りながら右手の水上バス乗り場を見ると珍しく3台が停泊していました。 それで、大川の対岸に降りて、これを撮影。(水上バス)(同上) 撮影していたら、上流から別の1台がやって来ました。(同上) こちらへやって来るかと思いきや、船首を旋回、寝屋川の方へと入って行くではないか。大阪城公園の船着き場へと向かうようです。(同上) ズームして、行ってらっしゃい、と見送る。 天満橋の下を潜って、橋の西側に出て見ると、今度は下流から黄色い水上バス。これは天満橋の手前でUターンして中之島の方へと戻るようです。外人観光客の増加で、水上バスも大はやり、商売繁盛なのかも。 尤も、ヤカモチはこれに乗ったことはまだない。(天満橋、こちらは黄色の水上バス。) 囲碁会場の梅田スカイビル到着は午前11時15分頃だったかと。先ず、里山にあるカフェテリアで、少し早い昼食とする。(WILLER EXPRESS Cafe) ゆっくり食後の珈琲を飲んで、煙草を喫って、里山の風に吹かれて、然る後に、里山散策です。(梅田の里山)(同上) 会場に入るも、小生が一番乗り。 美術部の方達が数名居られたので、ご挨拶。彼らの話を聞くともなく聞きながら、碁盤を並べたり碁石を揃えたりの準備。彼らが去ってしまって、小生一人に。ザックから本を取り出して読んでいると、竹〇氏と福麻呂氏が来られました。続いて、村〇氏、少し遅れて平〇氏。小生を含め今日は5名の出席でした。利麻呂氏は宇治に所用で出かけて居られ、午後には会社の方に戻らなくてはならない急用が生じたとかで、欠席する旨のメールがあって、ご欠席でした。 さて、本日の小生の戦績であるが、筋の悪い手や見落とし、勘違いなどミスの連発で、竹〇氏、福麻呂氏、平〇氏いずれにも大敗。3戦全敗。これで今年に入っての通算成績は10勝16敗。借金がまたまた6コにもなってしまいました。
2018.08.08
コメント(6)
-

銀輪散歩・マンホール(その11)
銀輪散歩で見掛けたマンホール蓋の写真もそこそこに溜りましたので、本日は「銀輪散歩・マンホール(その11)」とします。<参考>過去の「銀輪散歩・マンホール」の写真はコチラ 今回は、殆どが大阪府内で撮影のものですが、府内の市町村のそれも未撮影のものが多くあるようです。 先ずは、高槻市から。1.高槻市(カラー版) 高槻市の市の木はケヤキ。「槻」はケヤキのことですから、当然です。一方、市の花はウノハナだそうな。 マンホールのデザインはこの市の木と市の花を左右にあしらい、中央に摂津峡でしょうか、川が描かれている。 (モノクロ版)2.門真市 市の花はサツキであるが、これは桜ですな。 大阪みどり百選にも選ばれている、当市南部にある砂子水路の景観をデザインしたものだそうな。桜並木があって、ボランティアの手によって、このように遊覧のための舟の運行もされているとのことであります。(注)門真市のマンホールは(その1)にも掲載されています。3.東大阪市 これは1990年鶴見緑地(大阪市鶴見区)で開催された花の万国博覧会を記念してのものでしょうが、鶴見緑地やその周辺路上ではなく、何故か、東大阪市の石切近くの道端で見掛けました。(90年の花博図柄のもの)(注)東大阪市のマンホールは、 (その1)(その3)(その4)(その8)にも掲載されています。4.豊中市 (モノクロ版) (カラー版) 豊中市の市の花であるバラをあしらった中央にワニを配したデザイン。 このワニは「マチカネくん」という豊中市のシンボルキャラクターとのことです。 大阪大学正門脇の緑地に設置された碑には、このマンホール蓋が展示されていて、詳しい解説がされている。〇豊中市のシンボルキャラクター「マチカネくん」は大阪大学豊中キャンパスで発見されたマチカネワニをもとに「市民が誇りに思えるもの」として、市制施行50周年の昭和61(1986)年に誕生しました。ここでは豊中市と大阪大学の連携の象徴として、平成2(1990)年から市内の商店街などに設置された「マチカネくん」を描いた下水道マンホール蓋を展示しています。マチカネワニ(学名 Toyotamaphimeia machikanensis)1981年5月大阪大学理学部校舎用地(豊中市待兼山町)の更新世(30~50万年前)の地層から発掘。体長は推定7m前後、化石は大阪大学博物館待兼山修学館にて展示中。(解説板)(注)豊中市のマンホールは(その8)にも掲載されています。5.和泉市 (水仙図柄) (カワセミ図柄) 左は市の花であるスイセンの図柄。 右は「いずみ」から連想される清流にカワセミを配した図柄。6.忠岡町 忠岡町の町の花はサツキであるから、下掲の図柄もサツキの花であるのでしょう。(モノクロ版)(カラー版)7.岸和田市(カラー版) 中央に市の花であるバラを置き、岸和田城と市の木であるクスノキの葉を、バラの花を取り巻くように交互に配したデザイン。(カラー版・色違い)(モノクロ版) 岸和田城の二の丸敷地内には、こんな図柄のものがありました。岸和田城の天守閣のシャチホコを図案化したものなんでしょう。(岸和田城版)8.貝塚市 (非デザイン型) (デザイン型) 右は市の花であるコスモスがあしらわれています。 下は、二色の浜公園内で見たものですが、マークが大阪府のそれですから、貝塚市のマンホールではなく、大阪府の管理するマンホールのようです。(二色の浜公園版)9.田尻町 これは、泉州タマネギということで、タマネギを描いたもの。泉州と言えば、もう一つは、水茄子が有名であるが、茄子はお呼びがかからなかったようです。10.泉佐野市 これはイチョウの葉。泉佐野市の市の木はイチョウ。葉と葉の間にあるのはその実、ギンナンですね。11.甲賀市(旧水口町) 旧水口町の、町の木はヒノキ、町の花はサツキ、町の鳥はキジ。 そのどれとも関係ない図柄。12.新発田市(親子型タイプ) これは、親子型のマンホール蓋。調べてみると(その5)に既に掲載している図柄、タイプのものでした。(注)新発田市のマンホールは(その5)(その8)にも掲載しています。
2018.08.05
コメント(5)
-

千葉から知人
本日は千葉にご在住の知人K氏が奈良に所用があってやって来られました。 先月27日にスマホにメールが入り、西大寺でお会いすることになりました。同氏とは、小生がまだ現役で仕事をしていた時期に、或る問題で知り合いとなったのであるが、その問題が解決した後も交流が継続することとなり、同氏が関西に来られた折などにお顔合わせをしているのである。今回も所用で奈良に行くので、西大寺で会えないか、というメールを頂戴したのでした。 同氏とのお付き合いは10数年か或はそれ以上になるかと思うが、直近に同氏とお会いしたのは一昨年のことである。一昨年のいつ頃であったかは記憶が定かではない。大阪の新阪急ホテルのロビーで待ち合わせをしてお会いしたことはよく覚えている。今回はそれ以来だから、2年振りの再会ということになる。 同氏は、小生と同年齢。何ヶ月かは同氏の方が年長になるが、同じ時代を生きた同世代であれば、共通の話題や通じる話も多い。今回は、自身がかかわって居られる或る取引について、些かの齟齬やトラブルがあって、そのことの法的な面での小生の意見というか感想を聞きたいということでもあったか、関連の資料も持参されていて、話の多くはそれに関連したものでありました。 ヤカモチは長く企業法務に係る仕事をしていた関係で時々そのような相談を今でも受けることがあるのだが、今や「世捨て人」然のヤカモチですから、その種の話は、どちらかと言うとノーサンキューなのではある(笑)。 喫茶店での話が一段落したところで、西大寺駅向かいのビルにある月日亭で少し早い昼食にお誘いする。同氏は12時半だか1時だかに、当該所用でのお約束があるということであったので、少し早めの昼食とした次第。 昼食後、駅前で別れ、同氏は所用の待ち合わせ場所へ、小生は駅に向かい帰宅の途に。それだけのことでした。 さて、西大寺駅には待ち合わせの時刻よりもかなり早くに到着したので、同駅展望デッキに出て、写真を撮るなどして時間潰しをすることにしました。 このデッキに出るのは初めて。ブロ友のひろみの郎女さんのブログ記事にこのデッキのことが書かれているのを以前見た記憶がぼんやりあって、それを思い出したので、デッキに出てみた次第。 何と言うほどのこともないが、他に写真もないので、その写真を掲載して置きます。特急電車が行き交いました。(近鉄・西大寺駅2階デッキから・その1)これやこの往(ゆ)き来(く)電車の西大寺 上(のぼ)るしまかぜ下るビスターカー (似非丸)(同上・その2)(同上・その3)
2018.08.01
コメント(4)
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 【ライトオン(7445)】優待到着!
- (2025-11-15 09:50:04)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 🌿 My Aqua Terrarium! Part2【アク…
- (2025-11-15 14:42:21)
-








