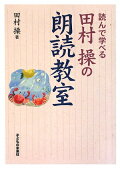PR
Keyword Search
Calendar
Comments
Freepage List
話し合いだけでは中身が、理解できない事例について
I先生へ
についてです。
・音読・・・・・・・・一般的には、十分な読解がないままの音声化で、
したがって、初歩的な音声化をさしています。
・朗読・・・・・・・読解を深めて、そのもとに音声化・表現することを目指しています。
これは、表現よみと同じです。
・表現よみ・・・・読解を基にその読み手の力量に基づく音声化です。
これは、朗読と同じです。
したがって、人間の音声化は、最初から表現よみです。
* 教室で子供たちに音声化させるときには、
「 朗読しよう
」と呼びかけるより「 表現よみしよう
」と
言う方が理解されやすいので、
この研究会では「表現よみ」と言っています。
ただ、このこと<音読・朗読・表現よみの違いを教えてください>という
声の扱いは、
注意が重要です。
このことで、10年近く、失敗を繰り返してきました。
と、言うことは、このことを説明し、話し合っていると、
論争になることが、かなりありました。
この論争は、後味の悪いものでした。
これは、後でわかることなのですが。
ですから、時間の無駄遣いという感じでした。
ある時は、研究会のすべてをこのことに使い、
実際の音声化をせず、
表現よみはいいが、朗読はよくない、
反対に、表現よみより朗読だなどの
意見げ出て、まとまらず、
参加者があきれて、次回から参加しなくなったこともあります。
これは 違いを強調するため
に起こることなのですが、
表現よみと朗読の 共通点
の着目こそ大切なのです。
それは、どちらも読解に基づく音声化ということです。
しかし、参加者は、それ論争・話し合いだけでは、
朗読・表現よみの良さが分からず、
力量も高めてないのです。
実際、
音声化してみる
聞いてみる
を通してのみその良さが分かり・力が着くのです。
話し合いだけでは、力はつかないのです。
中には、論争だけに力を注いてくる方もいます。
その苦い経験から、このような質問には、
重点を置いた運営をしないでようにしています。
実際、音声化に重点を置いていると
その時間は、あまり取れなくなてしまいます。
最近では、このような手の質問は
例会・研究会・アカデミーでは出なくなっており、
その話し合いの時間をとったことがありません。
如何でしょうか? T T
この記事に対するコメントなどお寄せください。
(ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)
また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。
下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、
上記のことが具体的に記述されています
(1年~6年・ルック刊)-
子どもにやさしい学校を 2012/12/10 コメント(5)
-
まともな教育ができる東京を 2012/12/08 コメント(4)
-
TPPは、原発問題と同じぐらい重大 2012/12/04 コメント(6)