PR
Category
Keyword Search
Freepage List
Calendar
Comments
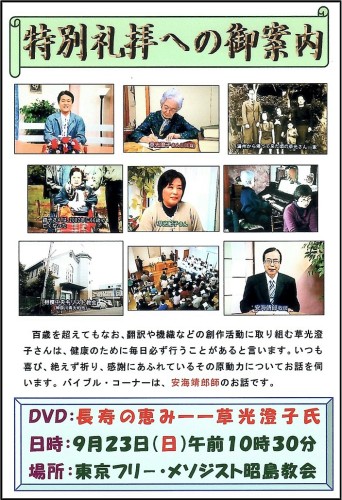
「情報学の視点から見た生命の起源(1)」
甲斐慎一郎
ローマ人への手紙、1章20節
「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世
界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきり
と認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです」(20節)。
一、科学には二種類ある
1.観察科学・実験科学(Observational/ Operational Science)
繰り返し実験することによって検証が可能です。飛行機や車は、
この種の科学に則って作られます。この種の科学の法則については、
創造論者と進化論者は合意できます。
2.歴史科学・起源科学(Historical / Origins Science)
過去の出来事に関する仮説を立てる科学で、実験して検証するこ
とはできません。この種の科学の仮説において、創造論者と進化論
者は合意できません。
▽研究の対象と方法が異なる二つの「科学」があるにもかかわら
ず、多くの人々は、「進化論は、観察科学であり、科学的事実」で
あると考えてしまっています。実際には、進化論も創造論も、歴史
科学の範疇にあって、観察科学のように検証し、証明することはで
きないことを理解する必要があります。
▽「観察できるものの仕組みを調べ、その仕組みを用いて技術を
発展させよう」とする営みは、観察科学の分野ですが、「観察でき
るものがどうして存在するようになったか」という起源を知ろうと
する営みは、歴史科学の分野であることを、しっかりと見分けなけ
ればなりません。
二、証拠は一つ、証拠の解釈は二つ
どちらの証拠が多いかが問題なのではありません。証拠は一つ
(同じ地球・同じ化石・同じ地層・同じ生物)であって、その起源
をどう解釈するかが異なることが問題です。解釈が異なるのは前提
(創造主が存在すると考察するか、創造主は存在しないと考察する
か)が異なるからです。
三、どちらの「解釈」が正しいのか
進化論者が言うように科学は、進化論を証明しているのでしょう
か。科学は、どちらの説も証明しておらず、最終的にどちらも「信
仰」です。しかし「どちらの説に基づいて考えることが、より観察
結果と一致するか」を検証することは可能です。その例としてDN
Aを考えてみましょう。
四、生物を形造る情報、DNA
進化論では、DNAは確率の問題であって、偶然にできると教え
ています。
創造論では、DNAは情報であって、情報という仕組みを用いる
ことができる知性のある存在がこの情報を作らなければ、情報とし
て存在しえないと考えます。
1.背後に知性の存在を指し示すものの例
建物、ラシュモア山の彫刻、車→これらは決して自然にはできま
せん。知性のある誰かが計画して作ったから存在するのです。
2.DNAを発見した科学者たちは、生命はただの化学現象だと
言おうとしました。
3.モールス信号や言語から分かるように、記号はただ並んでい
るだけでは機能しません。
それに意味を持たせ、その意味を読み解く仕組みが最初から整って
いる必要があります。
4.物質は、情報を生み出しません。
情報は、知性が生み出すも
ので、DNAは情報です。それゆえDNAは、知性のある存在(創
造主)が創造したものであると言うことができます。
「創造か進化か」は、「創造主なる神のことばである聖書を信じ
るか、創造主を否定して考える人間の知性による説を信じるか」と
いう信仰の問題です。どちらも過去を取り扱う歴史科学の仮説であ
るならば、創造主を否定し、かつ観察科学とも合致しない進化論で
はなく、創造主を認め、さらに観察科学も裏付ける創造論を信じよ
うではありませんか。
甲斐慎一郎の著書 → 説教集










