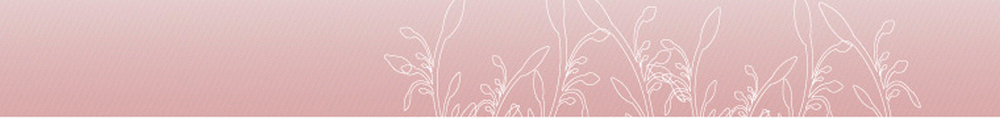PR
Calendar
Freepage List
Keyword Search
最愛の人に「死にたい」と言われたら? 絶望を経験した親子の“奇跡”
SNSなどでも活躍している作家・岸田奈美さんは、
中学生のときに父親を亡くし、弟には知的障害があります。
また、岸田さんが高校生のときに母親が 大動脈解離
の手術の末、
下半身が不自由となり車いす生活に。
そんな状況でも、ずっと笑顔でいたお母さんでしたが、
ある日、絶望に耐えられなくなり、
「死にたい」と娘である岸田さんに告白します。
岸田さんが答えた言葉は「ママ、死んでもいいよ」でした。
絶望の中にある人とどう向き合うのか、ある家族のストーリーです。
※本稿は、岸田奈美著
『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』
(小学館)
から一部抜粋・編集したものです。
母に「死んでもいいよ」といった日
大阪にある、落ち着いたとは口がさけてもいえない喫茶店、
新聞社の記者さんの取材を受けていたときのことだ。
両どなりでは、4人組の オバチャン
たちが、怒濤のおしゃべりをくり広げていた。
会話の8割が「ちゃうねん」「そんでな」「聞いた話なんやけど」からはじまっていた。
こっちの記者のおしゃべりも、負けていなかった。
「岸田さん、 ヤフーニュース
見ましたよ」
その日、わたしと母にまつわる話が、ネットニュースでとり上げられていたのだ。
「お母さんに『死んでもいいよ』っていうなんて、すごいですね」 ぴたり。
急にオバチャンたちが、静まり返った。
待て待て待て。
「しかもパスタ食べながらいったんでしょ。しっかりしてるなあ」
わたしをほめる記者に、悪気がないことはわかっていた。
しかし情報の切りとり方がやばいので、風評被害がやばい。
わたしの視界で認識できる限りのオバチャンは、
口元に手を当てて、わたしを凝視していた。
いやちょっとは遠慮してくれ。
わたしは決して、パスタを食べながら、母親に死ねといった娘ではない。
母が倒れる。生存率20%の手術
わたしは、母と弟の3人家族だ。
中学生のころに父が心筋梗塞で急逝した。
4歳下の弟は、生まれつきダウン症で知的障害があった。
母と弟は性格がとても似ている。
いつも穏やかで、優しい。
わたしの役割は、そんなふたりを父に代わって、
アホな言葉とバカな行動で、とにかく笑わせることだった。
わたしたち家族はそうやって、明るく楽しくまわっていた。
わたしが高校1年生のとき、自宅で母が倒れた。
「ご家族の責任者は、どなたでしょうか」
救急車で運ばれた先の医師がいった。
かけつけてくれた祖母は高齢で、わたし以上に呆然としていた。
弟は、むずかしいコミュニケーションをとることができない。
母はすでに、意識不明だった。
「わたしです」反射的にいった。
責任とは程遠いほど、震えた声だった。
「お母さまは極めて重症です。
このまま手術をしても、
手術中に亡くなる確率は80%を超えます」
「……手術をしなかったらどうなるんですか」
「数時間後にかならず亡くなります」
手術をするならば、同意書にサインを、と求められた。
わたしは、迷ってしまった。
父と最期の会話が叶かなわなかったことを、
わたしはずっと後悔していた。
このまま手術室に入って死んでしまうくらいなら、
一時的だったとしても、
最期にゆっくり話す時間をつくってもらった方がよいのかもしれない。
そんなことを、思ってしまったのだ。
でも、結局、母の命をあきらめることなんてできなかった。
わたしは祖母と一緒に、同意書へサインした。
本来なら、未成年のわたしではなく、
判断は祖母にゆだねられるべきだったのだと思う。
でも、この先、
母とともに生きていく時間が長いのは、子どものわたしだ。
わたしが後悔しないように決めた方がよいという医師の思いやりが、
本当にありがたかった。
もし、祖母がひとりでサインしていたとしたら、
わたしは祖母にすべてを背負わせることになっていたかもしれない。
6時間もの大手術のあと、母は一命をとりとめた。
集中治療室で、眼を覚ました母と話した。
安心やら疲労やらなんやらで、腰が抜けそうになった。
「死んだ方がマシだった」?
でも、命と引きかえになったものもある。
母は下半身の感覚をすべて失った。
一生歩けなくなったのだ。
「車いす生活になるけど、命が助かってよかったわ」
母は笑っていた。
あのときホッとしたわたしを、
わたしはなぐってやりたいといまでも思う。
母はそれから2年間、入院した。
それまで歩けていた人が、急に歩けなくなるというのは、
想像を絶する苦しみだ。
ベッドから起き上がるどころか、寝返りすらも打てない日々が続いた。
毎日、毎日、母は車いすに乗り移る練習をくり返していた。
「大丈夫やで」という母は、大丈夫ではなかった。
ある日、高校からの帰り道、病院へお見舞いに行ったときのことだ。
その日も母はめちゃくちゃ元気だった。
「じゃあまた来るから」と病室を後にして、
携帯電話を忘れたことに気がついた。
引き返すと、病室でだれかがわんわん泣いていた。
まさか母なわけないよな、と思った。
そのまさかだった。
「もう死にたい」母の声が聞こえた。
聞いているのは、看護師さんのようだった。
「歩けないわたしなんて、ヒトじゃなくて、モノになったのと同じ。
子どもたちにしてあげられることもない。生きてても仕方ない」
ああ、母は本当は、とっくに限界を越えていたのだ。
早くかけ寄って、なぐさめないと。でもわたしは一歩も、動けなかった。
「死んだ方がマシだった」
母の本音を聞いて、息ができなくなった。
わたしのせいだ。
わたしが手術の同意書にサインをしなければよかった。
生き地獄に、母を突き落とすこともなかった。
どうしよう、とり返しのつかないことをしてしまった。
「死にたい」気持を肯定すること
母にようやく、外出許可が降りるようになった。
母は、わたしが病室の外で聞いていたことを知らなかった。
わたしばかりが焦っていた。
だから、ふたりで街へ出かけようといった。
母が好きなお店に行けば、きっと元気になってくれる。
そう思った。
母はとても喜んでくれた。
でもそれも、最初のうちだけだった。
駅に到着したまではよくても、
地上へ出るためのエレベーターが見つからなかった。
ようやく見つけても、故障や節電で動いておらず、
駅員さんを探して30分もさまよった。
人ごみで、車いすが何度も歩いている人にぶつかった。
「すみません」「ごめんなさい」「通してください」
わたしたちは、何度もくり返した。
楽しみにしていたお店は、ぜんぶ階段があったり、
通路がせまかったりして、車いすでは入ることができなかった。
歩いていたときは、こんなの気づかなかったのに。
さんざん歩きまわったら、身も心もヘトヘトになった。
ようやく入れるカフェを見つけ、
席についてパスタとジュースを注文すると、
途端に母は泣き出してしまった。
「ママと一緒にいたら大変やんね。迷惑かけてごめん」
「そんなことないで」
「あのね、ママね、ずっと奈美ちゃんにいえなかったことがあるねん」
なんとなく、いいたいことはわかっていた。
「ほんまは生きてることがつらい。ずっと死にたいって思ってた」
あんなに優しくて明るかった母が、わたしの前で泣いた。
母の涙を最後に見たのは、父の お葬式
だ。
知人から
「つらいと思うけど、
母親のあなたが泣いたら子どもたちが不安になるから、
見えるところでは泣かないで」
といわれたことを、律儀に守っていた母だ。
「そんなこといわないで」「死なないで」
そういう言葉は、ひとつも口をついて出てこなかった。
わかっていた。
そんな言葉がなんの力にもならないほど、母が絶望していることを。
わたしは、運ばれてきたパスタをパクパク食べながらいった。
なにかしていないと、わたしの方が泣いてしまいそうだった。
「ママ、死にたいなら、死んでもいいよ」
母はびっくりしたように、わたしを見る。
「死ぬよりつらい思いしてるん、わたしは知ってる」
母を追いつめたのは、手術同意書にサインしたのはわたしだ。
わたしが母の死にたいという気持ちを、否定してはだめだ。
そう思って、いった。
でも情けないことに、母の顔を見ていると
「やっぱり死んでほしくない」
というわたしの本音もわき上がってくる。
パスタを食べながら、続けた。
「もう少しだけわたしに時間をちょうだい。
ママが、生きててよかったって思えるように、
なんとかするから」
「なんとかって……」
「大丈夫」
でまかせだった。
不安そうな母に、わたしは笑っていった。
「2億パーセント、大丈夫!」
でまかせが“ドリームジャンボ級”の奇跡に
でまかせは少しずつ、本当に少しずつ、現実になっていった。
わたしは母が生きていてよかったと思える社会をつくるため、
福祉と経営を一緒に学べる日本にひとつしかない大学へ進学した。
そこで、ふたりの学生と出会い、株式会社ミライロの創業メンバーになった。
3年後、母を雇用した。
母は見違えるほど、明るくなった。
「歩けないなら死んだ方がマシ」ではなく
「歩けなくてもできることはなんだろう」と、
わたしと母は考えるようになった。
絶世の聞き上手だった母は、入院していたとき、
病室に見舞客がたえなかった。
最初は友人や親戚ばかりだったのだが、いつの間にか、
看護師や 理学療法士
なども集まってくるようになった。
みんな母に話を聞いてもらいたいのだ。
予約表なるものがベッドサイドに登場したとき、わたしは度肝を抜かれた。
それは絶対に仕事にした方がいい、というわたしの説得により、
母は猛勉強の末、心理セラピストになった。
いまでは聞き上手どころか話上手にすらなってしまい、
年間180回以上の講演をしている。
さらに手動装置を使い、手だけで車を運転する免許まで手に入れ、
車をひとりでブイブイ運転するようになった。
「死んでもいいよっていわれたら、生きたくなった」母は笑う。
この一連の話が、ネットニュースでとり上げられたというわけだ。
「2億パーセント大丈夫。死にたい母に娘が放った言葉とは」
こんなタイトルだったと記憶している。
よく聞かれるのは、2億パーセントという数字がどこからやってきたのか、だ。
母に本音を打ち明けられた、あの日。
わたしは母の肩越しに、壁にはられたポスターを見ていた。
宝くじ ドリームジャンボ2億円。
人はパニックになったとき、
視界に入った一番大きな数字にすがりつくのかもしれない。
最大限の大丈夫を伝えたかったわたしが選んだ数字が、2億だった。
ただそれだけ。
ドリームジャンボ級の奇跡が、ここで起こったというわけなのだ。
PHPオンライン衆知
[YAHOO ニュース]

家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった [ 岸田 奈美 ]
生きている以上、修業が続きますね。
その時々でまた器を大きくして受け入れることなんでしょうね。
452万アクセス逹成しております。
いつもありがとうございます。☄
にほんブログ村
にほんブログ村
-
障害ある母と子が過ごせる場を 看護師が… 2024.11.18 コメント(9)
-
「どうせ家で話せるわけない」知的障害者… 2024.11.17 コメント(10)
-
障害者グループホーム「恵」事業所を神戸… 2024.11.07 コメント(11)