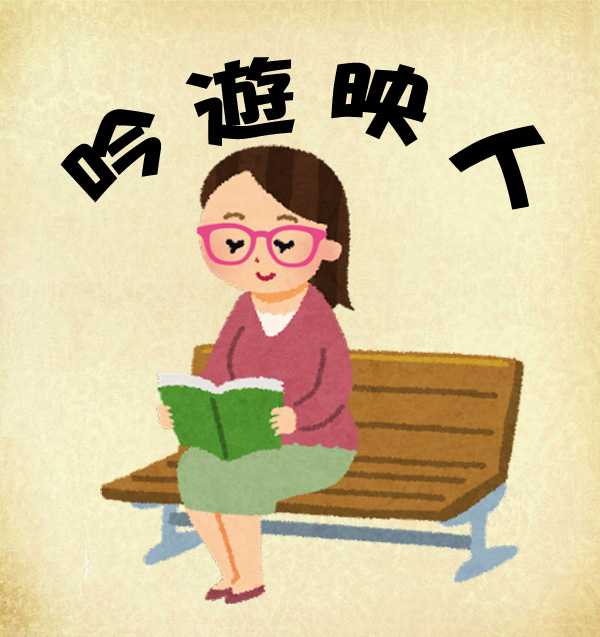PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ
その他
(7)映画/アクション
(77)映画/ヒューマン
(97)映画/ホラー
(35)映画/パニック
(25)映画/歴史・伝記
(32)映画/冒険&ファンタジー
(41)映画/ラブ
(47)映画/戦争・史実
(41)映画/SF
(55)映画/青春
(23)映画/アニメ
(24)映画/サスペンス&スリラー
(143)映画/時代劇
(21)映画/西部劇
(4)映画/TVドラマ
(29)映画/コメディ
(15)映画/ミュージカル
(1)映画/ドキュメンタリー
(3)映画/犯罪
(12)映画/バイオレンス
(9)映画/ヒッチコック作品
(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』
(8)読書案内
(217)仏レポ
(2)コラム紹介
(120)竜馬とゆく
(9)名歌と遊ぶ
(70)名句と遊ぶ
(288)風天俳句
(5)名文に酔う
(16)ほめ言葉
(3)教え
(42)吟遊映人ア・ラ・カルト
(13)江畔翁を偲ぶ
(12)ガンバレ受験生!
(5)オススメの本
(3)月下書人(小説)
(6)写伝人(写真)
(6)写真
(18)名曲に酔う
(1)名画と遊ぶ
(2)訃報
(11)舞台
(1)神社・寺院・史跡
(12)テーマパーク
(2)カフェ&スイーツ
(21)要約
(23)聖地巡礼
(1)発見
(8)体験談
(1)お気に入り
(1)ヘルス&ビューティー
(3)読書初心者
(5)カテゴリ: 竜馬とゆく
【竜馬とゆく(竜馬がゆく/門出の花)2】

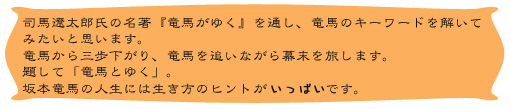
『座禅を軽蔑し「座るより歩けばよいでないか」とひそかに考えた。
座禅に行って、半刻、一刻の座禅をするよりも、むしろそのつもりになって歩けばよい。
いつ頭上から岩石がふってきても、平然と死ねる工夫をしながら、ひたすらにそのつもりで歩く。
岩石を避けず、受けとめず、頭上に来れば平然と迎え、無に帰することができる工夫である。』
江戸へむかう街道にて。
竜馬にとって歩くことはすなわち訓練であり、「無」の境地は歩いて体得した。
維新回天前、新選組を中心とした刺客に襲われた折りに、竜馬はその「心胆(境地)」と剣術修行から得た「間」で難を逃れることになる。
江戸への途上、岡田以蔵にからまれる。
「竜馬は、男のなかでも一番手におえないのはこういう男だとおもった。
小心な男だけに、せっぱつまると、何を仕出かすかわからない。」
~江戸へ~
そこで竜馬は『岩石』のような岡田以蔵に『避けず、受けとめず』そして『平然と迎え』えるのである。
竜馬の対応はこうだ。
「俺は幸い、金に不自由のない家に育った。それは天の運だ。天運は人に返さねばならぬという。」
~江戸へ~
そういって懐中の五十金を岡田以蔵にくれてやるのである。
机上の勉強に合理性を認めなかった竜馬は、ひたすら歩きながら勉強したわけだ。
「あの桂浜の月を追って果てしもなく船出してゆくと、どこへゆくンじゃろ。」
~お田鶴さま~
アレコレ思考をめぐらす竜馬である。
経験や知識と、世間の整合するところから仮説を導き出し、それを検証するためにまた歩くのが竜馬流の勉強である。
勉強が積み重なり、竜馬の知恵となり、そして叡智となった。
竜馬の勉強は現代風にいうと、安岡正篤先生の言われた「活学」の実践であり、また中村元先生の「学問が身についてきた」と評するところだ。
そして、考えるより先に実際に自分でやってみるのも竜馬流である。
「それよりも、おれにやらせてくれ。お前はそこについていて、いちいち手直ししてくれればいい。」
~お田鶴さま~
船中で船頭に梶を教わる竜馬は、「旦那、ひとつ梶を教えましょうか」という船頭の申し出に対しそう答えたのだ。
何事も実際に自分でやってみる、という竜馬のスタンスまた、竜馬の情報収集(取材)の基本姿勢にもなった。
つまり三次情報より二次情報、確かなのは一次情報というわけだ。
1.自分で
2.直接やる(見る)
3.そこから判断(行動)した
のである。


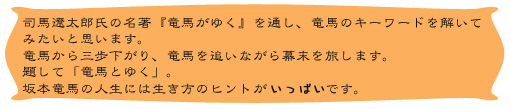
『座禅を軽蔑し「座るより歩けばよいでないか」とひそかに考えた。
座禅に行って、半刻、一刻の座禅をするよりも、むしろそのつもりになって歩けばよい。
いつ頭上から岩石がふってきても、平然と死ねる工夫をしながら、ひたすらにそのつもりで歩く。
岩石を避けず、受けとめず、頭上に来れば平然と迎え、無に帰することができる工夫である。』
江戸へむかう街道にて。
竜馬にとって歩くことはすなわち訓練であり、「無」の境地は歩いて体得した。
維新回天前、新選組を中心とした刺客に襲われた折りに、竜馬はその「心胆(境地)」と剣術修行から得た「間」で難を逃れることになる。
江戸への途上、岡田以蔵にからまれる。
「竜馬は、男のなかでも一番手におえないのはこういう男だとおもった。
小心な男だけに、せっぱつまると、何を仕出かすかわからない。」
~江戸へ~
そこで竜馬は『岩石』のような岡田以蔵に『避けず、受けとめず』そして『平然と迎え』えるのである。
竜馬の対応はこうだ。
「俺は幸い、金に不自由のない家に育った。それは天の運だ。天運は人に返さねばならぬという。」
~江戸へ~
そういって懐中の五十金を岡田以蔵にくれてやるのである。
机上の勉強に合理性を認めなかった竜馬は、ひたすら歩きながら勉強したわけだ。
「あの桂浜の月を追って果てしもなく船出してゆくと、どこへゆくンじゃろ。」
~お田鶴さま~
アレコレ思考をめぐらす竜馬である。
経験や知識と、世間の整合するところから仮説を導き出し、それを検証するためにまた歩くのが竜馬流の勉強である。
勉強が積み重なり、竜馬の知恵となり、そして叡智となった。
竜馬の勉強は現代風にいうと、安岡正篤先生の言われた「活学」の実践であり、また中村元先生の「学問が身についてきた」と評するところだ。
そして、考えるより先に実際に自分でやってみるのも竜馬流である。
「それよりも、おれにやらせてくれ。お前はそこについていて、いちいち手直ししてくれればいい。」
~お田鶴さま~
船中で船頭に梶を教わる竜馬は、「旦那、ひとつ梶を教えましょうか」という船頭の申し出に対しそう答えたのだ。
何事も実際に自分でやってみる、という竜馬のスタンスまた、竜馬の情報収集(取材)の基本姿勢にもなった。
つまり三次情報より二次情報、確かなのは一次情報というわけだ。
1.自分で
2.直接やる(見る)
3.そこから判断(行動)した
のである。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[竜馬とゆく] カテゴリの最新記事
-
『竜馬がゆく』より。竜馬とゆく9 2013.08.07
-
『竜馬がゆく』より。竜馬とゆく8 2013.07.23
-
『竜馬がゆく』より。竜馬とゆく7 2013.07.16
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.