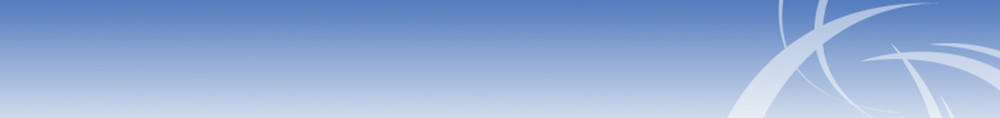PR
X
コメント新着
カテゴリ
カレンダー
テーマ: 政治について(21481)
カテゴリ: 日記
≪我々の食文化は”素材”を最大限に生かす食文化≫
たまにはこんなエントリーもいかがでしょうか。
ニセモノの日本食を他国の海外で広める中国人や韓国人。 ←映像をご覧ください。
日本料理といえば何を指すのか。
日本料理 とは(ウィキペによると)
との事であり、ラーメン・焼きそば・焼肉・牛丼・ステーキ・ハンバーグ・スパゲッティ・から揚げ・カレーなどなど多くの食べ物は日本料理では無いのは承知の通り。
食材を応用して日本風に仕上げたものとしては、肉じゃが・牛丼・すき焼き・しゃぶしゃぶなどが上げられ、おろしハンバーグなどのように日本風の食材と調理法を施したものを総じて「和風」という文字を頭につけられている。
日本料理を代表する食材として上げられるのは以上のようなものでなかろうか。
穀物、野菜、豆類(大豆など)、ソバ、果物、
芋類、山菜、キノコ、海藻・海草、鶏卵、魚介類
それらの自然の食材を生かす代表的な調味料は以下の通り。
塩・醤油・味噌・酢・ワサビ・山椒・生姜・ネギ・シソ
これら以外にもたくさん色々ありますが、ここで味噌・醤油に関して興味深いお話を。
日本食は調味料文化 から要約して引用
この熊倉功夫氏の講演の中で面白いエピソードとしては、「日本では”味噌汁”と御飯は一対である感覚に対して、西洋でいう”スープ”と言うのはそれそのもので食べるものとして捉えられている。ドイツの日本食レストランに入った時、まず最初に味噌汁が出てきたので、御飯が出てくるだろうと待っていたが、いつまで経っても御飯が出てきません。味噌汁を食べ終わらない限り御飯が出てこないという店に出会ったことがあります。」などという面白い話があった。
「日本ブランド戦略の推進」
独立した主権国家を保つ条件として我が日本の食文化の保護と食料安全の確保は欧米の農産物や中国からなどの農薬まみれ・何が混じっているのか分からない食料や農産物から日本国民を守る絶対条件となっている。
政治的や軍事戦力的に対抗するほどの完全自主防衛を行う事も現時点では至難であるが、まず、江戸時代の時のような食料自給率100%以上を達成しなければ「独立主権国家」となるのはまた遠い夢のような話になるのは間違いないようである。
「食」に関しましては、かむかむさんのブログを是非ご熟読ください。
(出来ればここまで徹底したいものですね・・・)
↓ ↓ ↓ ↓
「慈悲」で「健全な地球」を!
日本の食文化を見直し真の独立主権国家へ立ち返ろう!!応援クリックよろしくお願いいたします!!
↓ ↓ ↓ ↓
人気ブログランキングへ投票
こちらも参加しています、応援クリックお願いいたします!
⇒ 日本ブログ村・政治ブログへ投票
たまにはこんなエントリーもいかがでしょうか。
ニセモノの日本食を他国の海外で広める中国人や韓国人。 ←映像をご覧ください。
日本料理といえば何を指すのか。
日本料理 とは(ウィキペによると)
日本料理と「日本人が食べてきた食事」とは必ずしも一致しない。時代や社会階層や地域によって差があり、調理法も、古くから東アジア諸国、西洋などから伝来してきたものが多い。現在、日本人が食べている食事の中で、他国の料理としての度合いが強いものを除いた残りを「日本料理」と言うことが多い。
~(略)~
日常的な食事の構成としては、ご飯(白米やその他の穀物を炊いたもの)、汁物、おかず3品(主菜1品と副菜2品)という組み合わせを取り、一汁三菜と言う。これらを好みにより交互に食べる。一方、懐石料理・会席料理のように改まった席では一品(あるいは一膳)ずつ順番に料理が供されるのが普通である。
との事であり、ラーメン・焼きそば・焼肉・牛丼・ステーキ・ハンバーグ・スパゲッティ・から揚げ・カレーなどなど多くの食べ物は日本料理では無いのは承知の通り。
食材を応用して日本風に仕上げたものとしては、肉じゃが・牛丼・すき焼き・しゃぶしゃぶなどが上げられ、おろしハンバーグなどのように日本風の食材と調理法を施したものを総じて「和風」という文字を頭につけられている。
日本料理を代表する食材として上げられるのは以上のようなものでなかろうか。
穀物、野菜、豆類(大豆など)、ソバ、果物、
芋類、山菜、キノコ、海藻・海草、鶏卵、魚介類
それらの自然の食材を生かす代表的な調味料は以下の通り。
塩・醤油・味噌・酢・ワサビ・山椒・生姜・ネギ・シソ
これら以外にもたくさん色々ありますが、ここで味噌・醤油に関して興味深いお話を。
日本食は調味料文化 から要約して引用
『外国語になった日本語の辞典』という書籍によると、日本語がそのまま英語になった単語の代表的なものとして「カラオケ」「スシ」「テンプラ」などがあります。
その中の食品に関する言葉が沢山あって調べてみると、その約7%に当たる60か70語もあります。そのうち29語が(soy bean=醤油)に関する言葉です。ソイ・ソース(soy sauce=醤油)に関する言葉は余りにも古く入ってきているので、ソイ・ビーンの「ソイ」と言う言葉が「醤油」から来ていると言う事を知らないアメリカの人が増えています。事実、若い人たちに聞いたら知らないと言われました。初めから「ソイ・ビーン」を英語だと思っている若い人が居ます。
~(略)~
一方、味噌は調味料としてだけではなく、中に野菜を入れたりして、食品としての味噌、つまり舐めて酒を飲むとか、御飯につけて食べるという、舐め味噌というものも発達していきます。つまり16世紀までは日本の調味料の中心は味噌であったと言う事です。
味噌の中から液体を取って使うという方法が中世の終わりぐらいに出てきますが、その一つは、味噌の中に籠を入れて、その中に滲み出て来たエッセンスを溜めて使う「たまり」というものがあります。
同じように「たれ味噌」と言って、味噌を水に溶いて緩くしたものを袋に入れて吊るしておきますと、そこからドロップしてくる汁を使うようになります。
日本のお料理は刺身をすぐ思い浮かべますが、刺身を醤油で食べると言う事は江戸時代以降ののことで、江戸時代までの刺身の食べ方は、刺身を別のつけ汁を使って食べました。そのつけ汁で一番代表的な物は、煎り酒というものです。煎り酒の作り方は、たまり・塩・梅干・鰹節を加えて、3分の1ぐらいに煮詰めたものです。
そういうものが刺身のつけ汁だったのです。
~(略)~
味噌も醤油も生産するのに時間がかかります。かつては1年とか2年掛けて作ったものがありました。その長い熟成の間に蛋白質がアミノ酸にかわって、いわゆる”うまみ味”が生まれたのです。
これは非常に単純な比較なので、もっと詳しく考えなければならないのですが、西洋では塩とか香辛料とか比較的単純な自然の素材を使って、料理する過程で味わいを深くする、調理の間に味を十分付けていくのが基本的な作り方ですが、日本の場合には、予め長い時間を掛けて作られた味噌と醤油がありますので、食品に味を付けるスタイルは比較的浅い、場合によっては、それをつけて食べる、食品の中にしみこませずに使うことも非常に多いのです。
十分味付けされた料理が中国や西洋の料理の中心になってきますが、日本の場合は素材の味を助ける、素材の味を生かす調味料、つけ汁的な使い方が沢山あります。
この熊倉功夫氏の講演の中で面白いエピソードとしては、「日本では”味噌汁”と御飯は一対である感覚に対して、西洋でいう”スープ”と言うのはそれそのもので食べるものとして捉えられている。ドイツの日本食レストランに入った時、まず最初に味噌汁が出てきたので、御飯が出てくるだろうと待っていたが、いつまで経っても御飯が出てきません。味噌汁を食べ終わらない限り御飯が出てこないという店に出会ったことがあります。」などという面白い話があった。
「日本ブランド戦略の推進」
世界の人々は、味覚には、甘み、酸味、塩味、苦味、の4味があるというが、日本人だけこれにうま味が加わって5味を持っており、「UMAMI」はそのまま世界共通語になっている。小学校3年生から6年生までを対象にした味覚の授業をなどを行っているが、最近は家庭で子供たちに味覚を伝えられなくなっている。味覚が最も発達するのは8歳から12歳までであり、子供達への食育活動が重要。
独立した主権国家を保つ条件として我が日本の食文化の保護と食料安全の確保は欧米の農産物や中国からなどの農薬まみれ・何が混じっているのか分からない食料や農産物から日本国民を守る絶対条件となっている。
政治的や軍事戦力的に対抗するほどの完全自主防衛を行う事も現時点では至難であるが、まず、江戸時代の時のような食料自給率100%以上を達成しなければ「独立主権国家」となるのはまた遠い夢のような話になるのは間違いないようである。
「食」に関しましては、かむかむさんのブログを是非ご熟読ください。
(出来ればここまで徹底したいものですね・・・)
↓ ↓ ↓ ↓
「慈悲」で「健全な地球」を!
日本の食文化を見直し真の独立主権国家へ立ち返ろう!!応援クリックよろしくお願いいたします!!
↓ ↓ ↓ ↓
人気ブログランキングへ投票
こちらも参加しています、応援クリックお願いいたします!
⇒ 日本ブログ村・政治ブログへ投票
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.