PR
X
Comments
Freepage List
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 江戸時代を読む!(129)
カテゴリ: 江戸時代を知る
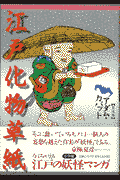
著者はアメリカ生まれの日本文学研究者。
15歳の時に英訳の『源氏物語』を読んで日本文学の虜になり、日本に留学、大学院の時から泉鏡花の幻想小説を専門に研究し、今では日本の大学の教授になっている。
江戸時代の、化け物を題材にした草双紙5種の紹介が中心。
草子の紙面を全部載せているので、全体のイメージがよく分かる。
取り上げられているのは、北尾政美(きたおまさよし)・画の『夭怪着到牒(ばけものちゃくとうちょう)』のほかはいずれも十返舎一九作の『妖怪一年草』(勝川春英・画)、『化物(ばけもの)の娵入(よめいり)』(勝川春英・画)、『信有奇怪会(たのみありばけもののまじわり)』(十返舎一九・画)、『化皮太鼓伝(わかのかわたいこでん)』(歌川国芳・画)。
どれも画が凝っていて面白い。『妖怪一年草』は人間界の年中行事のパロディになっていて、花見ならぬ「穴見」、お釈迦様の誕生を祝うのに対して「お逆さま」の誕生を祝い、月見をせずに「闇見」をするといった具合。十返舎一九の絵のうまいのにも驚く。
ほかに、山口昌男や小松和彦、京極夏彦らの考察もある。
ただ、京極夏彦は、「江戸化物草紙の妖怪画」で、柳田国男による、妖怪は零落した神の姿である、という定義を「現在でも妖怪を定義する条件として一般にも広く用いられている」と述べているが、これは小松和彦は否定しており、民俗学研究者に聞いても、現在でもそのまま通用しているわけではない、ということだった。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[江戸時代を知る] カテゴリの最新記事
-
森マリア卒業 2023.03.26
-
非人に賢者ある事 2022.07.27
-
『耳嚢』「義は命より重き事」 2022.07.26
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
Category
カテゴリ未分類
(527)江戸時代を知る
(137)時代小説・歴史小説
(111)岡本綺堂
(10)中国関係(漢字・中国文学)の本
(70)日本の古典
(59)近代文学
(50)民話(伝説・昔話)
(31)民俗学・社会風俗・地誌・歴史・博物学
(45)欧米露の本
(57)ミステリ
(20)その他の読書録
(272)気になる言葉・文字
(369)PC・IT関連
(251)目についたもの写真館
(234)旅行・観光・名所・レジャー・おでかけ
(683)プロレス
(271)特撮・アニメ・SF・マンガ
(340)時代劇(映画)
(179)時代劇(テレビ)
(259)その他の映画
(535)芸能・テレビ
(521)フォークソング
(49)野菜作り
(105)教育関連
(54)心・体・健康・病気・障害
(229)マス・メディアにつっこみ
(103)気になるニュース
(88)アウトドア
(63)飲食店
(77)Shopping List
1枚までネコポス発送可能【1枚までネコポス対応】【お買得】04804 ストレッチライトメッシュベスト S-5L シンメン ベスト ストレッチ メッシュ 軽い 3シーズン 作業服 作業 アウトドア 釣り
純正品よりお安く純正の機能が充実。パナソニック ブルーレイ レコーダー リモコンN2QAYB001171 N2QAYB001087パナソニック ディーガ リモコン ブルーレイ N2QAYB000994 N2QAYB000993 N2QAYB001056 N2QAYB001071 N2QAYB001172 N2QAYB001055 N2QAYB001142 N2QAYB001148 N2QAYB001044 N2QAYB001086 N2QAYB000995 Panasonic DIGA 代用リモコン REMOSTA
タテ型洗濯機 5KG 6KG 7KG 5.5KG 5キロ 6キロ 7キロ 5.5キロ ステンレス洗濯槽 手動水位設定 洗濯コース切替 予約洗濯機能 柔軟剤自動投入 糸くずフィルター 給水ホース 排水ホース【期間限定5%OFFクーポン 9/8 10:00まで】 洗濯機 6kg 全自動洗濯機 一人暮らし 1人暮らし コンパクト 引越し 縦型洗濯機 風乾燥 槽洗浄 凍結防止 小型洗濯機 残り湯洗濯可能 チャイルドロック マクスゼン MAXZEN JW60WP01WH PB00003 エクプラ特選
【送料無料】ウルトラマン青春記
南方熊楠
純正品よりお安く純正の機能が充実。パナソニック ブルーレイ レコーダー リモコンN2QAYB001171 N2QAYB001087パナソニック ディーガ リモコン ブルーレイ N2QAYB000994 N2QAYB000993 N2QAYB001056 N2QAYB001071 N2QAYB001172 N2QAYB001055 N2QAYB001142 N2QAYB001148 N2QAYB001044 N2QAYB001086 N2QAYB000995 Panasonic DIGA 代用リモコン REMOSTA
タテ型洗濯機 5KG 6KG 7KG 5.5KG 5キロ 6キロ 7キロ 5.5キロ ステンレス洗濯槽 手動水位設定 洗濯コース切替 予約洗濯機能 柔軟剤自動投入 糸くずフィルター 給水ホース 排水ホース【期間限定5%OFFクーポン 9/8 10:00まで】 洗濯機 6kg 全自動洗濯機 一人暮らし 1人暮らし コンパクト 引越し 縦型洗濯機 風乾燥 槽洗浄 凍結防止 小型洗濯機 残り湯洗濯可能 チャイルドロック マクスゼン MAXZEN JW60WP01WH PB00003 エクプラ特選
【送料無料】ウルトラマン青春記
南方熊楠
© Rakuten Group, Inc.










