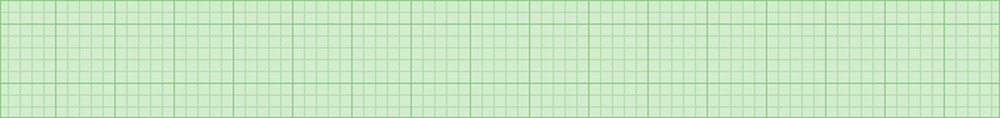2007年04月の記事
全45件 (45件中 1-45件目)
1
-

若干の筋
宮城音弥:著『夢 第二版』岩波新書たまたま、近所の図書館のリサイクル棚からタダで拾ってきて読んでいるんですが、数々の夢の実例を分析するところが謎解き推理クイズみたいで面白いですよ。『パプリカ』の第1部みたいだ。*ああ、そうか!オレが十数年前から「『パプリカ』は第1部だけがメチャクチャ面白い。第2部はダメダメ」とず~っと言っているのは、あの本をオレは「なぞなぞクイズの本」だと思って読んでいたからなんだ!「サイキック美少女アニメの原作」だと思って読んでいなかったんだ!最初から、『パプリカ』を読まずに、宮城音弥先生の本だけ読んでいれば良かったのである。そんなに、なぞなぞが好きなら。 筒井康隆:著『パプリカ』新潮文庫
2007.04.30
コメント(0)
-

日本人はジュニアが大好き
手塚治虫:著『マコとルミとチイ』秋田文庫オールド・ヤクルトファンとしては巨人の会田投手という人に注目しないわけにはいかない。だって、「ヤクルトの会田」の息子なんだもん。親父の会田照夫というピッチャーは、けっしてヤクルトのエースだったわけでも何でもなく、はっきり言うと2線級の投手だったんですが、ある理由から、ヤクルトのファンには非常に強い印象を残している人ですね。背番号が「12」だったんですよ。選手名鑑を見ると、監督→コーチ→投手→捕手→内野手→外野手の順に、しかも選手の場合は背番号が若い順番で載ってますよね。選手の名前と背番号を最初のほうから丸暗記していこうとすると、まず投手の背番号が若いところから。西井(11)会田(12)西岡三四郎(13)小林国男(14)巨人から来た倉田(15)…という順番で覚えることになるんですよ。年度末のトレードで、選手が入れ替わってもえ~と、神部(11)会田(12)、それから、え~と…。ロクにマウンドに立っている姿は思い出せなくても、「12番は会田」それだけは強烈に印象づけられている。載っているのが名鑑の最初のほうだから。『出る単』の「A」で始まる単語、みたいなものですね。*そういえば今は中日にも、堂上照の息子がいますよね。(「青エンピツ青山」に息子って、いないのか? もし青山にも息子がいるなら、ジュニアの世代でも、 堂上の息子と凸凹コンビを組ませてみたいところだ)オールド・プロ野球ファンには面白い時代になってきたけれど、でも、もうちょっと有名な親父の息子、というのはいないのだろうか。カズシゲやカツノリが派手に失敗してくれたせいなのかも知れないが、せっかく「プロ野球も2世の時代に!」と景気のいい話をしているのに、その題材が「会田の息子」や「堂上の息子」では、今イチ盛り上がりに欠けますよ。しかし、まあ、それは仕方のないことだ。もっと有名な選手の息子だったら、親父の名前を利用して、もっと楽な職業に就ける。テレビ局にも新聞社にも入り放題だ。わざわざ親父サン同様に、身体を張って危険な季節労働者の道なんかを目指さなくたっていい。言い換えれば、たまたま「会田の息子」や「堂上の息子」程度の境遇に生まれてしまった以上、親父のコネが通用する世界は、野球界ぐらいしかなかった、ということなんだなあ。
2007.04.30
コメント(0)
-
マンガというのは視覚的なものだから
小林信彦:著『唐獅子株式会社』新潮文庫「解説 ─ 原典探索による」筒井康隆(前略)しかしぼくはそれが読者諸兄の議論のとっかかりになりさえすればそれでいいと思う。以前ぼくはこの本の推薦文にこう書いた。「主人公の哲を高倉健、原田を松方弘樹、ダーク荒巻を菅原文太、金泉寺の和尚を若山富三郎という各社ごちゃまぜの配役で、それぞれ真面目に演じさせたら、どれだけ面白い映画ができることだろう」 驚くべし。たったこれだけのことで中島梓をはじめとする好き者があちこちの雑誌で火の手をあげ、侃々諤々の議論が湧き起ったのである。「いや。やはり主演は鶴田浩二であろう」「須磨の親分を金子信雄となぜ書かなかったか」「原田は成田三樹夫だ。筒井はやくざ映画をあんまりよく見とらんのではないか」しまいには「ぼくの好きな藤竜也はどこに出るんですか」という反論の手紙を書いてきたやつまでいた。ことほど左様に、好きな人はいっぱいいるのだ。いくら反論されても、怒りっぽいぼくが不思議に腹を立てなかったのは、それだけ活溌な論争になる面白さがこの作品に秘められていることを十二分に認めていたからである。(後略)*「主人公のカメちゃんを上戸彩、シゲさんを新垣結衣、ガキさんを加藤夏希、レイナを堀北真希という各局ごちゃまぜの配役で、それぞれ真面目に演じさせたら、どれだけ面白いドラマができることだろう」「いや。やはり主演は石原さとみであろう」「レイナの友だちの眼鏡ッ子を相武紗季となぜ書かなかったか」「シゲさんは栗山千明だ。石川はアイドルドラマをあんまりよく見とらんのではないか」「ぼくの好きな長澤まさみはどこに出るんですか」「マンガだけ北杜夫に選ばせろ」
2007.04.29
コメント(1)
-

グッピー
ちなみに、南長崎の古本屋で買ったのはこの本でした。250円。 倉橋由美子:著『老人のための残酷童話』講談社文庫*↓こっちは、元から持っていたから。倉橋由美子:著『倉橋由美子の怪奇掌篇』新潮文庫 倉橋由美子:著『大人のための残酷童話』新潮文庫
2007.04.28
コメント(0)
-

夏の恋人
昨日、豊島区南長崎の、黒岩よしひろ邸の近所にある古本屋で店内に流れていたラジオ番組で、ほぼ初めて、ちゃんと藤岡藤巻の曲というものを聴いたんですよ。1年前の『私は偉い』。 藤岡藤巻『よろけた拍子に立ち上がれ!』「息子よ」「よろけた拍子に立ち上がれ!」「私は偉い」「もうすぐ23歳」「娘よ(ショートバージョン)」なんだか、藤岡藤巻の曲って、「こんなことになっちゃう前の長渕剛」みたいですよね。さすがは「昔とったキネヅカ」というか。…違うか。「三つ子の魂百まで」?「年寄りの冷や水」? 長渕剛『BEST NOW 長渕剛/1978年~1981年』「夏の恋人」「涙のセレナーデ」「春待気流」「決心」「クレイジー・ボーイ」「恋のランデブー」「俺らの家まで」「乾杯」「順子」「ヒロイン」「素顔」「祈り」「Da!Da!Da!」「巡恋歌」「逆流」「さようならの唄」まりちゃんズっぽくは、全然ないですね。…というより、まりちゃんズというのはテイストをどうこう言うようなもんじゃなくて、ただ稚拙なだけのものだったんでしょうね。 まりちゃんズ『三巴狂歌』「まりちゃん」「くちづけ」「ひがみブルース」「まりちゃんが結婚してしまう」「僕等はドラ息子」「もう冬」「もうすぐ23才」「尾崎家の祖母 PART2」「君を食べちゃいたい」「オザキの逆上節」「続 まりちゃん」「編みかけのセーター」「男の世界」 まりちゃんズ『お買徳』「ツンツン音頭」「春だから」「売れてからでは遅すぎる」「君の手紙」「売れっ子ワルツ」「新 武道館でジョイントを」「月光仮面の正義について新カント学派に対するキルケゴールの実在主義的見地にたった一考察」「SM夜曲」「売れれば良いと言う訳でも無いがやっぱし売れなくては話になりはしない」「宛名のない手紙」「おちめタンゴ2」「君がいたらなあ」 まりちゃんズ『まりちゃんズの世界/まりちゃんズ ベスト』 「尾崎家の祖母」「ブスにもブスの生き方がある」「ひがみブルース」「まりちゃん」「男の世界」「まりちゃんが結婚してしまう」「オザキの逆上節」「笑って誤魔化せ」「続 まりちゃん」「SM夜曲」「もうすぐ23才」 まりちゃんズ『まりちゃんズ ワースト』「新 武道館でジョイントを(キャンディーズ VS まりちゃんズ)」「売れてからでは遅すぎる」「売れっ子ワルツ」「編みかけのセーター」「君がいたらなあ」「売れれば良いと言う訳でも無いがやっぱり売れなくては話になりはしない」「春だから」「もう冬」「僕等はドラ息子」「おちめタンゴ2」「ツンツン音頭」「君の手紙」「尾崎家の祖母」「尾崎家の祖母」オリジナル・カラオケ長渕剛本人は今では「こんなことになっちゃった」けど、そうなる前の頃の長渕剛の魅力というのは一緒に組んでいたフジオカ君の中に、しっかり真空パック状態で残っていたんでしょうね。二十何年間も。それこそが藤岡藤巻の真の実力だった。長渕剛あっての藤岡藤巻。…じゃあ、フジマキ君いらないじゃん。オザキ君が、いたっていなくたって構わなかったように…。 里田まい with 藤岡藤巻『オヤジの心に灯った小さな火 ~デュエットバージョン~』「オヤジの心に灯った小さな火 ~デュエットバージョン~」「オジサマって大好き」「オヤジの心に灯った小さな火 ~デュエットバージョン~」カラオケ「オジサマって大好き」カラオケあらためて3人目の誰かを連れてくるなら、里田を連れてくるより、山梨鐐平を連れてきたほうが良かったんじゃないでしょうか。
2007.04.27
コメント(0)
-
つっぱりブス
「幸之助と美由紀はデキてる、デキてる! 幸之助と美由紀はデキてる、デキてる!」「カンベンしてよ」「ワ-」結城昌治:著『不良少年』中公文庫佐々木譲:著『鉄騎兵、跳んだ』文藝春秋(徳間文庫版が見当たりません!)
2007.04.26
コメント(0)
-
森田、春子。父ちゃんゴメンネ
横溝正史が死んで、いろんな落ち穂拾いの未収録作品集みたいなものが出て、そのうちに「最初は短篇だったものが長篇化されて、 そのおかげで短篇のバージョンは未収録のまま忘れられている…というものが 横溝正史には多くある。 そういう作品だけを集めれば、未収録作品集みたいな本が作れるんじゃないか」ということに気がついた人がいて、90年代に、横溝正史「長篇の原型」短篇集というものが出版されました。ここで、ようやく、とうとう『金田一耕助の冒険』には含まれなかった、長篇化されてしまったがために未収録のままだった3篇が、世に出たわけです。横溝正史:著『金田一耕助の帰還』出版芸術社(1996.05) #横溝正史:著『金田一耕助の帰還』光文社文庫(2002.01) 「毒の矢」 「トランプ台上の首」 「貸しボート十三号」 「支那扇の女」 H「壺の中の女」(長篇『壺中美人』原型) I「渦の中の女」(長篇『白と黒』原型) J「扉の中の女」(長篇『扉の影の女』原型) 「迷路荘の怪人」*そこで結論を申し上げますと、シリーズ全14篇が全部、仲良く1冊にまとまっている文庫というものは、あ、り、ま、せ、ん!!!そういうものが必要なら、自分で企画書を書いて会議を通して、自分で編集して、どこかの会社から出版すればいいと思います。それが存在していないせいで、微妙に収録内容が違い、装幀が違う文庫本16冊をみんな集めて並べておかなくちゃいけない…というのも自分で選んだ道だと思います。*【追記】他にも、『金田一耕助の帰還』と、まったく同じ趣旨で、「後に長篇に改稿されてしまったために、忘れられていた原型の短篇」を集めた、未収録作品集の姉妹篇もあります。横溝正史:著『金田一耕助の新冒険』出版芸術社(1996.05) #横溝正史:著『金田一耕助の新冒険』光文社文庫(2002.02) 「悪魔の降誕祭」 「死神の矢」 「霧の別荘」 「百唇譜」 「青蜥蜴」 「魔女の暦」 「ハートのクイン」ただ、こっちは、タイトルがタイトルなのに『金田一耕助の冒険』のシリーズとは、何ら関係がない。何ら・アンド・ヒズ・アーケストラ。
2007.04.25
コメント(1)
-

私の名前は森田春子。
横溝正史の、『金田一耕助の冒険』のシリーズタイトルで知られている「●の中の女」といった短篇小説群には、以下のものがあります。(便宜上、アルファベットで順番を振っておきます)A「黒衣の女」 【読切小説集】1956.07B「霧の中の女」【週刊東京】1957.01.12~1957.01.19C「泥の中の顔」【週刊東京】1957.02.23~1957.03.02D「鞄の中の女」【週刊東京】1957.04.06~1957.04.13E「鏡の中の女」【週刊東京】1957.05.18~1957.05.25F「傘の中の女」【週刊東京】1957.06.29~1957.07.06G「檻の中の女」【週刊東京】1957.08.10~1957.08.17H「壺の中の女」【週刊東京】1957.09.21~1957.09.28I「渦の中の女」【週刊東京】1957.11.02~1957.11.09J「扉の中の女」【週刊東京】1957.12.14~1957.12.21~1957.12.28K「洞の中の女」【週刊東京】1958.02.08~1958.02.15L「柩の中の女」【週刊東京】1958.03.22~1958.03.29M「赤の中の女」【週刊東京】1958.05.03~1958.05.10N「瞳の中の女」【週刊東京】1958.06.14~1958.06.211篇を除いて、すべて【週刊東京】という雑誌に掲載されたもの。さらに、その中の大部分が前・後篇仕立ての、2話完結で発表されたもの。(1篇だけが、前・中・後篇の3話完結。)*このシリーズが最初に単行本になったのは、この形です。横溝正史:著『金田一耕助推理全集(6) 金田一耕助事件簿』東京文藝社(1959.05) B「霧の中の女」 K「洞の中の女」 E「鏡の中の女」 F「傘の中の女」 D「鞄の中の女」 A「夢の中の女」(A「黒衣の女」改題)全部で14篇あるうちの、6篇だけが1冊にまとめられていた。(もっと正確に言うと、 全部で13篇ある【週刊東京】掲載作品のうち、5篇だけを選び、 別の雑誌に載った短篇を改題して、同じシリーズの作品だ…ということにして、 その、もう1篇を加えて、6篇にした。)*次に、こういう本が出ます。横溝正史:著『壺中美人』東京文藝社(1960.09) 長篇「壺中美人」(H「壺の中の女」改題/改稿) C「泥の中の女」(C「泥の中の顔」改題/改稿)【週刊東京】掲載作品のうち、1篇を長篇に書き直して収録。もう1篇を、「●の中の女」シリーズに添ったタイトルに変更した上で、そのまま短篇として併録。この時点で、横溝正史には、【週刊東京】のシリーズ全篇を、掲載された形のままで単行本化する、というような意志はなかったわけですね。『壺の中の女』を長篇にしただけでなく、それを『壺中美人』と改題してしまっているんだから。それにしては、雑誌では『泥の中の顔』だったものを、ここで『泥の中の女』に改題して、わざわざ「●の中の女」の方向に揃えているのが分からない。そんなに「●の中の女」で統一することに、こだわりがあったのなら、たとえ長篇化されていたとしても『壺の中の女』は『壺の中の女』のままでも良かったのに。(ここにはオレの事実誤認があるのかも知れませんが。)長篇『壺中美人』は、後に長篇1本と、シリーズとは無関係な短篇を加えて1冊にして、文庫化されています。横溝正史:著『横溝正史長編全集(12) 壺中美人』春陽文庫(1975.04) #横溝正史:著『壺中美人』春陽文庫(1997.05)※新装版 長篇「壺中美人」 「黒蘭姫」横溝正史:著『壺中美人』角川文庫(1976.06) 長篇「壺中美人」 「廃園の鬼」(春陽文庫版と角川文庫版とでは、無関係なオマケ短篇が、それぞれ違う。)*その次に出たのは、この長篇。横溝正史:著『扉のかげの女』東京文藝社(1961.01) 長篇「扉のかげの女」(J「扉の中の女」改題/改稿)さらに、もう1篇「●の中の女」シリーズから短篇を長篇に書き直している。この長篇版の『扉のかげの女』というタイトルも、やっぱり気に入らなかったのか、あらためて改題して、新たな単行本にしています。横溝正史:著『扉の影の女』東京文藝社(1972.03)この『扉の影の女』のタイトルが最終的な決定版となったのでしょう。文庫は、これで出ていますからね。(角川文庫版には、シリーズと無関係なオマケ短篇アリ。)横溝正史:著『横溝正史長編全集(6) 扉の影の女』春陽文庫(1974.10) #横溝正史:著『扉の影の女』春陽文庫(1997.12)※新装版横溝正史:著『扉の影の女』角川文庫(1975.10) 長篇「扉の影の女」 「鏡が浦の殺人」*すでに、その頃の横溝正史は、もう1篇の「●の中の女」シリーズを長篇化していて、新聞連載小説として発表している最中だったんですね。長篇「白と黒」【日刊スポーツ】1960.11.06~1961.12.19(I「渦の中の女」改題/改稿)もちろん、この作品も単行本化され、文庫化されています。横溝正史:著『横溝正史傑作選集(5) 白と黒』東都書房(1965.04)横溝正史:著『白と黒』角川文庫(1974.05) #横溝正史:著『金田一耕助ファイル(18) 白と黒』角川文庫(1996.09)※新装版(『白と黒』の春陽文庫版というものは、出ていない)ここまでの経緯をまとめると、A~Nの全14篇のうち、単行本に収録された短篇が7篇。長篇に書き直されたものが3篇。未収録作品が4篇。こういう勘定になります。*このシリーズが『金田一耕助の冒険』という通しタイトルを持つ、短篇連作集である、ということに本格的に定まったのは70年代。長篇化された3篇を除く、残りの11篇すべてが文庫に収録されてからのことです。まず、どういう理由からかは分かりませんが、それまで単行本未収録だった短篇のうちの1篇が、他の関係ない作品と一緒に、中短篇集に収録されて刊行されました。横溝正史:著『横溝正史長編全集(18) 蝋美人』春陽文庫(1975.10) #横溝正史:著『蝋美人』春陽文庫(1997.04)※新装版 「蝋美人」 「トランプ台上の首」 「香水心中」 M「赤の中の女」そして、残りの10篇が、単行本収録作品・未収録作品もあわせて、短篇集として刊行されます。ここで初めて『金田一耕助の冒険』というタイトルがつきました。横溝正史:著『横溝正史長編全集(20) 金田一耕助の冒険』春陽文庫(1975.11) #横溝正史:著『金田一耕助の冒険』春陽文庫(1997.11)※新装版 B「霧の中の女」 K「洞の中の女」 E「鏡の中の女」 F「傘の中の女」 D「鞄の中の女」 A「夢の中の女」 C「泥の中の女」 L「柩の中の女」 N「瞳の中の女」 G「檻の中の女」1篇だけ、違う本にまぎれているのは、どう考えてもややこしいよなあ…と角川春樹が思ったのかどうか、角川文庫版『金田一耕助の冒険』では、『赤の中の女』も加えた全11篇になっています。横溝正史:著『金田一耕助の冒険』角川文庫(1976.09) B「霧の中の女」 K「洞の中の女」 E「鏡の中の女」 F「傘の中の女」 D「鞄の中の女」 A「夢の中の女」 C「泥の中の女」 L「柩の中の女」 N「瞳の中の女」 G「檻の中の女」 M「赤の中の女」春陽文庫が1篇だけ外したのも、たぶん同じ理由なのでしょうが、短篇が11本も入っている『金田一耕助の冒険』というのは、文庫本としては、ちょっと分厚すぎるんですね。その結果、後に角川文庫版『金田一耕助の冒険』は2分冊されます。大林宣彦:監督による角川映画『金田一耕助の冒険』が製作されたことが直接のキッカケです。横溝正史:著『金田一耕助の冒険(1)』角川文庫(1979.06) B「霧の中の女」 K「洞の中の女」 E「鏡の中の女」 F「傘の中の女」 N「瞳の中の女」 G「檻の中の女」横溝正史:著『金田一耕助の冒険(2)』角川文庫(1979.06) A「夢の中の女」 C「泥の中の女」 L「柩の中の女」 D「鞄の中の女」 M「赤の中の女」
2007.04.25
コメント(3)
-

【ん】じゃなかった
水木しげる:原案/沢村光彦:著『ゲゲゲの鬼太郎』角川文庫【み-18-50】だった。
2007.04.24
コメント(0)
-

投げやりなペンネームも、味わい
「泡江 剛」…。 馬場康夫:監督/君塚良一:脚本/泡江剛:ノベライズ『バブルへGO!! タイムマシンはドラム式』角川文庫ノベライズが角川文庫から出ていたとは知らなかった。てっきり扶桑社文庫か、さもなくば小学館文庫から出るものだと思っていた。
2007.04.23
コメント(2)
-
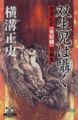
「おちぼ。かな。」(水谷豊)
横溝正史:著『双生児は囁く 横溝正史〈未収録〉短編集』角川書店:カドカワエンタテインメント #横溝正史:著『双生児は囁く』角川文庫横溝正史:著『喘ぎ泣く死美人 横溝正史〈未収録〉短編集 II』角川書店:カドカワエンタテインメント #横溝正史:著『喘ぎ泣く死美人』角川文庫その著者の、全作品を読み尽くしたわけでもないのに、落ち穂拾いの未収録ショートショート集みたいなものから先に読む…というのは、どうなんだろう。
2007.04.22
コメント(1)
-

原作病の女
BS放送が観られないので、この番組ごと知らなかったんだけど、こういうアンソロジーの作り方もあったんですね。 『この小説がすごい! BS-i「恋する日曜日・文学の歌」原作集』コアラブックス「水仙月の四日」宮沢賢治「晩菊」林芙美子「接吻を盗む女の話」佐々木俊郎「市井事」武田麟太郎「蒲団」田山花袋*似たような形での前例としては、かつて、↓こういうものも出ていた。 『幻想ミッドナイト 日常を破壊する恐怖の断片』角川書店:カドカワエンタテインメント「見果てぬ夢」赤川次郎「409号室の患者」綾辻行人「破壊する男」飯田譲治+梓河人「百鬼夜行・第三夜/目目連」京極夏彦「夢の島クルーズ」鈴木光司「ゆきどまり」高橋克彦「怪物たちの夜」筒井康隆「言わずにおいて」宮部みゆき「八千六百五十三円の女」夢枕獏『ミステリーゾーン』や『ヒッチコック劇場』なんかの、海外の例とは違って、国産TVドラマの短篇シリーズでは、原作に使われた既存の小説が、その著者それぞれの短編集単位で刊行されることはあっても、番組ごとの単位でアンソロジーになって出版されること…というのは、本当に珍しい。日本では、既存作品のアンソロジーというのは、まったく売れないんだろうなあ。たとえば『世にも奇妙な物語』でも、太田出版や角川ホラー文庫から出ている小説本は全部、オリジナル脚本のドラマを元にした、書下しのノベライズだけだ。既存作品を原作に使ったドラマは、ことごとく無視されている。海外の例のように、オリジナル脚本のノベライズと既存短篇が同居している、という本すらない。(たまに、漫画を原作にしたドラマに限って、ノベライズ小説が書下されることはあるけど。 その場合も、漫画そのものを「原作」として収録することはない。)
2007.04.21
コメント(0)
-

和製友近(キャサリン)
渡辺千穂:脚本/田中夏代:著『恋する日曜日 私。恋した』泰文堂:リンダブックス手足の短い女優さんは、「ポスト奥菜恵」の線を目指せばいいと思います。
2007.04.21
コメント(0)
-

愛 LOVE ナッキー
『生徒諸君!』と『生徒諸君! 教師編』は、もう全然違う、別の作品なんですよ。(『生徒諸君!』と『ナッキーはつむじ風』のほうが、まだ近いぐらい)『生徒諸君! 教師編』をドラマ化するのであれば、ちゃんとドラマのタイトルも『生徒諸君!(教師編)』としておいてほしいですね。「だったら観ない」とか「だったら観る」とかの判断ができるから。違うものが「違うもの」としてあれば、「オレにとっての『生徒諸君!』は 上田美恵の『生徒諸君!』だけがオンリーワンでナンバーワン。 映画もアニメも関係ない」だとか「飛島先輩役で出ていた北詰友樹という当時のイケメン俳優に、 高見知佳が喰われちゃって…」だとか「藤谷美和子は『俺はおまわり君』で日テレに残れたし、 上田美恵にはテレ朝で『生徒諸君!』の主演という新境地があったけど、 けっきょく北村優子と久我直子は『あさひが丘の大統領』を最後に消えちゃった。 やっぱり歌手クズレは生き残り難いのかなあ。 でも壇まゆみは、後から歌手になったんだよね?」だとか、いちいち古いことを言わなくても済む。 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(1)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(2)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(3)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(4)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(5)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(6)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(7)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(8)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(9)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(10)』講談社:ビーラブKC 庄司陽子:著『生徒諸君! 教師編(11)』講談社:ビーラブKC第12巻は5月発売だそうです。あと、 庄司陽子&BE-LOVE編集部:監修『生徒諸君! 教師編 オフィシャルファンBOOK』講談社:KCDXという本もありますが、これは2年前に出たもので、元祖『生徒諸君!』全巻と『教師編』第6巻あたりまでの内容でしかまとめられていません。
2007.04.20
コメント(2)
-

ビッグコミック譲ります
前田五郎:著『素晴らしき吉本芸人たち 前田五郎写真館』同文書院ドツル師匠も、朝日放送『漫才教室』の出身だったんですか?
2007.04.20
コメント(0)
-

代田くれたらいいのに
だいたひかるという人は、最近の吉本の若手芸人の中では非常に珍しい、「NSC出身ではなく、 TVオーディション(『R-1』のこと)を契機に吉本に入った人」であるんですよね。そのへんの境遇が、素人オーディション時代にステージガールズの二人と仲良くなった、万年落選組で、そのくせチャッカリ、いつの間にかヨシダマに所属を決めていた…という【笹塚さん】の造形に影響を与えている、と言えば言える。*あと、忘れてはいけないのは、だいたひかるは「他人のネタをパクることに躊躇しない人」であることだ。「ひょっとして私だけ…?」というフレーズがかつての「ぴあ」の『はみだし』投稿から生まれたものであることも含めて、そのネタ作りの姿勢からして、だいたひかるには有名な主婦ハガキ職人【長野県/私が湯本容子だっ!】からの影響が顕著である、等これまでにオレは何度も指摘してきました。『エンタの神様』だけ観ていても、それぐらいのことは読み取れる。でも、もっと露骨なパクリをやっていたことだってあるのだ。TBSの、桂邦彦さんプロデュースの深夜番組『笑林寺』に、だいたひかるがレギュラー出演していた頃。(あれは『笑林寺2』だったのかな?)『笑林寺』というのは月曜日深夜の放送で、真裏のフジテレビでは、その頃まだタモリ導入以前だった『トリビアの泉』をやっていたんですね。だいたひかるは、『笑林寺』の中で、ちょっと前に『トリビアの泉』で放送されたばかりのネタを堂々と言っていたんですよ。オレが観ていた限りでも、たしか3週ぐらい連続で。オンエアのタイミングから考えても、明らかに一視聴者として『トリビアの泉』を観て知った話を、そのまま喋っていた。「明日使えるネタ」を、本当に「明日」使っていた!しかも、真裏の他局で!!毎週『笑林寺』を観ているような視聴者は『トリビアの泉』のほうは観ていないはずだし、『笑林寺』の番組関係者にしたって、他局の真裏の番組(まだ深夜時代の『トリビアの泉』だから、それほど世間の評判にはなっていなかった)は観ていないだろう、観ていたとしても「観ている」とは表立って言えないだろう、だから「バレにくかろう」と判断して、そういうことをしていた。(自分は、しっかり観ておいて!)…そういう、あまりに馬鹿セコな判断が透けて感じられて、オレは、だいたひかるというのは、舞台で見せている朴訥な、素人っぽいイメージとは裏腹に、なかなか一筋縄ではいかない、相当のタマなのであるな、と思っていた。そのへんのドス黒さが、他人のカバンの中に平気で手を突っ込む【笹塚さん】の造形に影響を与えている、と言えば言える。(【笹塚さん】が、どんなドス黒さを見せるのか…というのは、今後のお楽しみで。)*もともと、当初の構想における【笹塚さん】は「ひょっとして私だけ?」というようなハガキ職人っぽいエッセイ漫談をやっている女ピン芸人だったんですね。それが、人形を抱えた腹話術師になってしまったのは、「モデルの誰かに似すぎてしまうから」という理由ではなくて、ぜひとも、ここで【マリーちゃん】を登場させたかったから、ということです。それについては、次回で御説明します。【笹塚さん】に人形を持たせたことで、↓かえって、このへんの別の芸人にも似てしまったのだが、 そっちと【笹塚さん】は、だいたひかると【笹塚さん】に関係がない以上に、 もっと関係がない。 いっこく堂『傷だらけの私鉄沿線』 パペットマペット:著『パペットマペットの4コマショートコント大作戦』竹書房
2007.04.19
コメント(1)
-

メイキング・オブ・『Stage Girls』第7話
ヘンリク・イプセン:著/矢崎源九郎:訳『人形の家(三幕)』新潮文庫ここから、しばらく連続物になるので全部の説明がしづらい。【ハーレムブギ】については、まだ今のところは、何も言わぬが華でしょう。ただ、オレが最初に、この「松園」と「原田」のコンビ名について提案したのは【ブギウギバンド】だった。宇崎竜童:著『ブギウギ脱どん底・ストリート』角川文庫それが、あまりにも露骨でイヤだ、というのならば、では、せめて【ファイティング・ブギ】ではどうか、と譲歩した。 ダウン・タウン・ブギウギ・バンド『ヴィンテージ・ベスト』「知らず知らずのうちに」「スモーキン・ブギ」「恋のかけら」「カッコマン・ブギ」「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」「商品に手を出すな!」「賣物ブギ」「裏切者の旅」「涙のシークレット・ラヴ」「沖縄ベイ・ブルース」「サクセス」「愛しのティナ」「身も心も」「トラック・ドライヴィング・ブギ」「欲望の街」「涙のヴァイア・コンディアス」「夜霧のブルース」「一番星ブルース」「網走番外地」「ちゅうちゅうタコかいな(LIVE VERSION)」 (↑このCDは【ファイティング】時代のものではないけれど。)そういう前段階を踏まえているので、あのコンビの名前が【ハーレムブギ】ということになったわけなんですが、【ハーレム】という言葉そのものも、今後の内容の展開に大きく関わってまいります。*小柄でツッコミのキツい「マリーちゃん」をパートナーに、ウケない腹話術をやっている、ブスな女ピン芸人【笹塚さん】。(黒岩先生には、「なるったけ、ブスに描いてください!」とお願いしました。 このキャラクターだけは、可愛らしく描いてもらっては困るから。)モデルは誰なんだろう?名前が「笹塚」?ブスな女ピン芸人が「笹塚」であることには意味があるのか?べつに「笹塚」でなくても、「幡ヶ谷」だって「初台」だっていいだろうに。初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋…。あっ!! だいたひかる:著『ほやほやの冗談』ワニブックス「だいた」ではなくて「ささづか」!そうか、そういうことだったのか…。…でも、なんとかブギウギバンドみたいな名前の、実在する大物コンビが、【ハーレムブギ】と深く関係があるほどには、ここには深いモデル関係はありません。【笹塚さん】だか【明大前さん】だか知らないけど、なんとなく京王線っぽい名前の、ブスな女ピン芸人。つながりと言えば、それだけですね。それだけだと思っていてください。(そういえば、ドラマの『下北サンデーズ』では、 下北沢を拠点とする劇団のテーマソングが 「梅が丘! 豪徳寺!」であって、世田谷代田が飛ばされてしまっていた。 小田急線を母体にしても京王線を母体にしても、 けっきょく常に「代田」は飛ばされてしまう宿命にあるのか?)*今回のサブタイトル『人形の家』で示唆されている、いわば今回の真の主役、人形の「マリーちゃん」の存在については、次回で御説明いたします。↓こっちの「マリちゃん」と関係があるのかどうかも含めて。 矢口真里:著『おいら』ワニブックス*【追記】そういえば、【ハーレムブギ】とは何の関係もないとは思いますが、一時期、本気で芸人を目指していたマグナム北斗の、組んでいた漫才コンビの名前が【ハーレム野郎】だった。 丸茂ジュン:著『マグナム伝説 モザイクの裏の真実』徳間文庫
2007.04.19
コメント(1)
-

この本の意義
『約三十の嘘』チーム with ゴンゾウ:編『約300の嘘』角川文庫オビを仕舞うケース。
2007.04.18
コメント(1)
-
マカロニ
何年か前にTBSで、古谷一行の『金田一耕助シリーズ』で『人面瘡』をやっていて、主演が斉藤由貴だから観ていたんですよ。原作は、まだ読んでいなかった。(調べたら2003年3月25日の放送。)そのドラマの中での斉藤由貴は、以前は東京の銀座で、宝石店のお嬢さまとして暮らしていたのに、ある日の夜中、とつぜん家が火事になって、全焼して、着のみ着のままハダシで逃げ出して、そのショックで記憶も失って、今は山奥の温泉旅館で住み込みの女中として働いている、という設定になっていた。「夜中とつぜん家が全焼」というのは、ずいぶん無茶な話だとは思ったけど、まあ、そういうことが実際に起きないわけでもないし、「絶対にありえない!」と言い張れるほどの無茶ではなかったから、とりあえず飲み込んで、ドラマを観ていた。観た後で、原作を読んでみた。横溝正史:著『不死蝶』角川文庫「不死蝶」「人面瘡」表題作の『不死蝶』がドラマ化された時の、竹下景子の写真がオビになっている古本の文庫を105円で買って、それで読んだ。読んだ後で、すでに新たに『人面瘡』を表題作にした再編集の角川文庫も出ていて、それには今回の「ドラマ化!」についてのオビもある、ということが分かり、あらためて、そっちも定価で買ってきた。(買ったら、その本のオビは古谷一行と谷啓の写真だった。由貴ちゃんがいなかった。)横溝正史:著『金田一耕助ファイル6 人面瘡』角川文庫「睡れる花嫁」「湖泥」「蜃気楼島の情熱」「蝙蝠と蛞蝓」「人面瘡」原作を読んでみて知りましたよ。原作にも、似たような「夜中とつぜん家が全焼」という設定は出てきた。でも、それは全然、無茶な話ではなかったのである。むしろ必然性のある設定だった。つまり「空襲」なんですよ。ドラマは設定を現代に置き換えてあったけど、原作は昭和20年代の話なんですね。(小説が発表されたのは昭和24年なんだから、それも「現代」の話ではあるのだが。)ドラマ版でいうところの斉藤由貴にあたる、『人面瘡』ヒロインの人は、昭和20年に大阪で空襲にあって…、以下は同じ。 夜中とつぜん家が全焼。 着のみ着のままハダシで逃げ出して、 そのショックで記憶も失って、 今は山奥の温泉旅館で…。いろんなことを考えましたね。※かつては「空襲にあう」ことが日常的だった時代があった。※空襲のおかげで、気の毒な境遇に陥ってしまった人物の設定にリアリティがあった。※その同じ気の毒な境遇を平和ニッポンの中で再現すると、ものすごく無茶になる。※そうまでして、現代の設定にする必要があったのか。※そもそも「空襲」という事態を「謎の火事で、夜中とつぜん家が全焼」と安易に置き換えてもいいのか。※しかし、現象面だけなら、それでも結果は同じになる。※さらに「謎の火事で、夜中とつぜん家が全焼」という話のほうが、圧倒的に、「怖い」。※それはオレに「空襲の恐怖」というものに対するリアリティが感じられないからだ。※「空襲」が来ると理解できてしまえば、それはそれで恐怖の日常かも知れないが、不条理ではない。※だいたい、それが日常と化しているわけなんだし。怖さの質が違うと思う。※戦争そのものが巨大な不条理で…みたいな話は、別。はっきり言うとオレは「謎の火事」には「謎の火事」のままでいてくれたほうが良かった。怖いから。原作を読んで「空襲だったのだ」と真相を知ってしまったのには、おお、それは面白い状況だ…ということに対する知的興奮はあったけれど、ちょっと失望もした。謎が謎でなくなってしまったから。「謎の火事」の謎を解こうとして原作を読んだ、という側面もあったから、それでいいんだけど、興味深い謎の、種明かしを知ってしまうと、たしかに夢は壊れますね。もっと言うと、ドラマ『人面瘡』の脚本家(石原武龍氏)の仕事は、ミゴトに成功しているんだと思いますね。よくやった。御立派。原作のままに「昭和20年の空襲」でドラマを作ってしまったら、そこにはオレにとっての「謎」や「恐怖」が、確実にひとつ減りますから。
2007.04.17
コメント(0)
-
鉄火あられ食べなきゃ女じゃないよ
気~づいちゃった気~づいちゃったワーイワーイ♪阿刀田高:著『ユーモア×ウイット=? 笑いの公式を解く本』KKベストセラーズ:ワニの本ボクみたいに頭の狂った人は、ミニスカのお姉さんが大好きだよね! (トントン!)←小太鼓しかもー、ミニスカのお姉さんは、たいがいドSだよね! (トントン!)←小太鼓しかもー、ミニスカでドSのお姉さんは、たいがい男前だよね! (トントン!)←小太鼓しかもー、ミニスカでドSで男前のお姉さんは、もっとどんどんエスカレートすると「鉄火」な人になっちゃうから気をつけないといけないよね! (パフー♪) (パフー♪) (パフー♪) (パフー♪)以上、テッカちゃんでした!!
2007.04.16
コメント(0)
-

女子アナ詩集
大橋未歩:著『大橋未歩のミホちゃんねる! 行け!行け! テレビ東京・女性アナウンサー』集英社女子アナを笑わせる笑っている女子アナはタレントの顔をしているそれは安いタレントの顔である女子アナを怒らせてみる怒っている女子アナはタレントの顔を忘れて怒っているOLの顔になる怒っているOL ほど エロいものは世の中にないしかも 元が女子アナだからそのOLは最高級に高いOLの顔をしている女子アナは 怒らせるに限る
2007.04.16
コメント(0)
-

原作のほうが面白そうだ
五味川純平:著『孤独の賭け(上)』幻冬舎文庫 五味川純平:著『孤独の賭け(中)』幻冬舎文庫 五味川純平:著『孤独の賭け(下)』幻冬舎文庫でも、ちょっと長いね。どこに連載されていたのだろう。週刊誌かな?
2007.04.15
コメント(0)
-

覚えたら忘れよう!
高野祥光:著『秋葉日和』新風舎 要するに「きこうでん」とは、「乞巧奠」という字を書いて、中国でいうところの「七夕祭り」のことなのだそうです。↓この本を読んでいて知りました。 丸谷才一:著『花火屋の大将』文春文庫
2007.04.14
コメント(0)
-
覚えて威張ろう!
玉井雪雄:著『IWAMAL 岩丸動物診療譚(9)』ビッグスピリッツコミックス化学兵器は、その性質から大別すると、以下の7種類に分類される。すなわち「神経剤」、 「血液剤」、 「窒息剤」、 「びらん剤」、 「無能力剤」、 「催涙剤」、 「枯れ葉剤」。し、け、ち、び、む、さ、か。「しけチビ六平」と覚えよう。
2007.04.14
コメント(0)
-
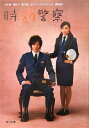
三日月サンがオシャレに!?
三木聡、岩松了、園子温、ケラリーノ・サンドロヴィッチ、塚本連平:脚本/進藤良彦:ノベライズ『時効警察』角川文庫「恋のライバル」役で投入された(?)とおぼしき新人キャラクターの婦警さんは、あの人は「ヤグチの偽物」なんですか?あの役が、ヤグチの本物では、いけなかったんですか?
2007.04.14
コメント(0)
-

みんな死んじゃうんだ
志賀真理子ってアイドルがいたじゃないですか。シガマリ。『どんなモンダイQテレビ』。『魔法のアイドル・パステルユーミ』。アメリカに留学していて、交通事故で死んじゃった人。出はじめの頃の「テレホンカード」高額プレミアムランキング第1位は、電々公社時代の斉藤由貴『卒業』だけど、それには劣るものの、NTT時代になってからの高額プレミアムランキング第1位は、志賀真理子『フリージアの少年』のテレホンカードだった。オレは、斉藤由貴のは持ってないけど、シガマリのは持ってましたよ。なんで持っていたかというと、くれたから。『フリージアの少年』をリリースしたばかりの頃のシガマリに、オレはインタビューしたことがあったから。「オリコンウィークリー」で。その時に、シガマリのスタッフさんがテレホンカードをくれた。プロモーション用グッズだったから、普通にくれた。まさか、後に高額プレミアムランキングの第1位だか第2位だかになる、激レアお宝グッズに化けるようなものになるとは、誰も思っていなかったから。(そんなことが予知できていたぐらいなら、 まずシガマリが死んじゃうことを予知しておくよ!)で、インタビューしていたら、シガマリは「読書が好き」だと言っていたんですね。SFが好きで、ブラッドベリが好きだ、と言う。そんな嬉しいことを言われちゃったらオレは、その部分にギュウギュウ押し込みますよ!「あ、そうなんですか~。 ブラッドベリ読んでるなら、その次はヴォネガット読んでくださいよ!」同行していた編集者も、一緒になって押し込みますよ!「ブラッドベリ読んで、ヴォネガット読んだら、その次はディック読んでくださいよ!」オレは、それには賛成できなかった。「ディックはないだろ、さすがに!」シガマリは、ただポカーンとして、ニコニコ笑っていた。…死ぬ前に、1冊でいいから、ヴォネガット読んでくれていたのかなあ。 『アニメージュ 魔法少女コレクション』「デリケートに好きして」太田貴子(『魔法の天使クリイミーマミ』オープニングテーマ)「パジャマのままで」太田貴子(『魔法の天使クリイミーマミ』エンディングテーマ)「囁いてジュテーム Je t'aime」太田貴子(『魔法の天使クリイミーマミ』挿入歌)「LOVEさりげなく」太田貴子(『魔法の天使クリイミーマミ』エンディングテーマ)「ハートのSEASON」太田貴子(OVA『魔法の天使クリイミーマミ/ロング・グッドバイ』オープニングテーマ)「ガールズ・トーク」太田貴子(OVA『魔法の天使クリイミーマミ/ロング・グッドバイ』エンディングテーマ)「見知らぬ国のトリッパー」岡本舞子(『魔法の妖精ペルシャ』オープニングテーマ)「ラブリードリーム」岡本舞子(『魔法の妖精ペルシャ』エンディングテーマ)「おしゃれめさるな」MIMA(『魔法の妖精ペルシャ』オープニングテーマ)「だいすきシンバ」富永みーな(『魔法の妖精ペルシャ』エンディングテーマ)「不思議色ハピネス」小幡洋子(『魔法のスターマジカルエミ』オープニングテーマ)「あなただけDreaming」小幡洋子(『魔法のスターマジカルエミ』エンディングテーマ)「不思議色ハピネス/アルバムバージョン」小幡洋子「金のリボンでRockして」志賀真理子(『魔法のアイドルパステルユーミ』オープニングテーマ)「フリージアの少年」志賀真理子(『魔法のアイドルパステルユーミ』エンディングテーマ)「DESTINY LIGHT(運命の光)」増田直美(OVA『魔法のデザイナーファッションララ/ハーバーライト物語』オープニングテーマ)「トワイライト★ドリーム」小森まなみ(OVA『魔法のデザイナーファッションララ/ハーバーライト物語』エンディングテーマ)「La La La ~くちびるに願いをこめて~」大森玲子(『魔法のステージファンシーララ』オープニングテーマ)「しあわせな き・ぶ・ん」大森玲子(『魔法のステージファンシーララ』エンディングテーマ)「デリケートに好きして」オリジナル・カラオケ死んじゃうんだ死んじゃうんだ。みんな死んじゃうんだ。 カート・ヴォネガット・ジュニア:著/浅倉久志:訳『プレイヤー・ピアノ』ハヤカワ文庫SF
2007.04.13
コメント(9)
-

恥言
最相葉月:著『星新一 一〇〇一話をつくった人』新潮社 ==================================== タモリさんにまで取材を敢行できている、というのが 何より立派だと思いました。 今日、番宣目的以外で タモリさんからのコメントを取ることが、いかに困難なものなのか。 それを考えると、 もちろん「他ならぬ星先生のことだから」という理由もあるんでしょうが、 「やっぱり、ベストセラー出している作家の人が来ると、違うんだなあ」と 最相さんには他意はないけど、思いましたね。 (それでも、やっぱり「番宣」的な一言は入れさせられていましたね) ====================================
2007.04.13
コメント(0)
-

ひっちゃんマン2号
石川ひとみも「捨て曲」はナシで、見るからに最強のラインナップが並んでいる。で、それに関しては倉田まり子のほうだって遜色はないのだ。ここまで大きく差が開くほどの、クォリティの違いはない。そして、ふたりの顔は区別がつかない!だとすると、石川ひとみが売れたのは、ひとえに「声」の力のおかげであった、ということになりますね。あんまり「声」が力を持ち過ぎていると、けっきょく「声優サン」になったり「アニソン歌手さん」になってしまったりするんだけど。 石川ひとみ『MYこれ!クション/石川ひとみ BEST』「右むけ右」「くるみ割り人形」「あざやかな微笑」「ひとりぼっちのサーカス」「プリンプリン物語」「ハート通信」「夢番地一丁目」「まちぶせ」「ひとりじめ」「君は輝いて天使にみえた」「冬のかもめ」「にわか雨」「メモリー」「アモーレ」「裸足でダンス」「秘密の森」…おいおいおいおい、↑ちょっと待て待て待て。そんなベスト盤があるかよ。石川ひとみのラインナップは最強、と言っているところなのに、どうして、その最強ラインナップから『ミス・ファイン』『オリーブの栞』『秋が燃える』『三枚の写真』を抜くの?そのへんを収録しないで、どうするの。何が最強だよ。何がベストだよ。どうしても収録曲数に限界があるのなら『メモリー』以降は、思い切って外そうよ。いっそ『プリンプリン物語』も外したっていいよ。(というか、『プリンプリン物語』を外しても 『ハッピー・アドベンチャー』を入れる、という選択肢だってあるけど 今は、そんな悠長なレベルで迷っていられるような段階ではない。)よしんば、最後の最後に、最前線0.5ミリのところまで譲歩するなら、もう、この際『ハート通信』を外したっていいから『ミス・ファイン』だけは残すべきなんじゃないのか。…『ハート通信』は「原曲を聴く」という手段がありますからね。でも、それを言ったら『まちぶせ』と『三枚の写真』も外れちゃうけど、それでもいいや。そういう選び方だってある。(そうなると『ひとりぼっちのサーカス』も外れちゃうなあ。)(なお、『オリーブの栞』の「原曲」というか「原典」については、不問!)『イブニング・スキャンダル』『JUNE浪漫』『DAY BY DAY』の3連弾があるからこそ倉田まり子のラインナップが最強であるように、石川ひとみのラインナップは、『ミス・ファイン』『オリーブの栞』『秋が燃える』のおかげで最強なんですよ。その最重要な3連弾が、なんで5枚組のBOXセットにしか入ってないんだよ!? 『石川ひとみ CD-BOX 78-86/ぼくらのベスト』【追記】『秋が燃える』と『三枚の写真』だけは、こっちに入ってました。 石川ひとみ『BEST SELECTION/まちぶせ』「まちぶせ」「くるみ割り人形」「三枚の写真」「夢番地一丁目」「右向け右」「君は輝いて天使にみえた」「秋が燃える」
2007.04.12
コメント(0)
-
グラジュエーーーションの眼鏡(楠美津香式発音)
倉田まり子に「捨て曲」ナシですよ! 倉田まり子『倉田まり子コレクション』「グラデュエイション」「いつかあなたの歌が」「HOWワンダフル!」「イブニング・スキャンダル」「JUNE浪漫」「DAY BY DAY」「さよならレイニーステーション」「恋はライ・ライ・ライ」「恋はAmi Ami」「哀しみのポエジー」「カナリヤ」「冷たい雨」「春の嵐」「避暑地の出来事」「真夏のランナー」「青いフォトグラフ」どうだ、この最強ラインナップ!曲はいい。歌唱力もある。ただ本人の「声」がダメダメなだけ。それは生まれつき、本人の育ちが良くないんだから自分の努力では如何ともできない。*倉田まり子の本名は「坪田真理子」であります。「真理子」が「まり子」になるのは、それは分かる。では、なぜ「坪田」が「倉田」になるのか?その「倉田」の「倉」というのは、どこから持ってきたのか?そうです。もちろん「都倉」の「倉」ですよ!…ということは、もしかしたら南野陽子も、「南都陽子」みたいな、南都雄二のような芸名でデビューしていた可能性があったかも知れないんですね。
2007.04.11
コメント(0)
-

「ヘアなし天使」か!
河合あすかじゃないんですから…。 森田征義:撮影『河合あすか写真集 ファム・ファタール』桜桃書房
2007.04.11
コメント(0)
-

誰にも優しいあなたのことだから
黒田研二:著『硝子細工のマトリョーシカ』講談社ノベルス事件の後年に、事件をモチーフにして書かれた小説の中では、↑コレがベリーベストですかね。(実際にオレが何も書かなかったからね。)*↑コレの、もうひとつのモチーフ(実際にオレも使っていた!)は、同じ著者の、↑コレの前作とも共通していて、 黒田研二:著『ペルソナ探偵』講談社ノベルスそれは、オレが同じモチーフを使っていた頃にも、とうとう手を出せなかった部分にまで到達しているのであった。別の著者の、↓コレは読んでいないので判断できないんですけど。 森雅裕:著『ビタミンCブルース』新潮社
2007.04.10
コメント(0)
-
ハセキョーの美脚
ポール・R・ロスワイラー:著/二宮磬:訳『スーパールーキー』集英社文庫『スーパールーキー』のタイトルで文庫化されている、ロスワイラー3作目の遺作長篇の、邦訳が最初に単行本で刊行された時のタイトルは『熱狂球場』。ポール・R・ロスワイラー:著/二宮磬:訳『熱狂球場』集英社『発狂球場』ではない。*アナタ、『発狂酒場』と間違えてやしませんか。矢野徹:編『矢野徹の狂乱酒場 1988』角川文庫
2007.04.10
コメント(0)
-

M男の特撮
『仮面ライダー電王』の、新しい「テレビ絵本」が出ていましたが…。 『仮面ライダー電王 デンライナーのひみつブック』徳間書店:徳間テレビえほん書店の店頭で確認したけど、これにはオネエサンの写真が全然載っていなかったので、買う必要がありませんでした。*こっちは、まだ現物を確認していない。 『仮面ライダー電王(2) デンオウ ロッドフォーム だいかつやく!!』小学館:小学館のテレビ絵本講談社の新刊は、どうなっているんだろう。*【追記】やっと中身を確認できた小学館の絵本では、あの、ミニスカ黒ストッキングのオネエサンの、立ちポーズでの、ほぼ全身写真(足首ぐらいまでで切れている)が大きく載っていたので、喜んで買ってきちゃいました。もっとも、そのページというのは、ウェイトレスのオネエサンと、石丸謙二郎を前面に大きく立てた見開きの合成写真で、ミニスカ黒ストッキングのオネエサンに関しては、かなりピン甘なんだけど、今までのテレビ絵本の中で、いちばんサイズが大きく載っているからそれだけでも満足です。なお、そのついでに、さらに新しい徳間のテレビ絵本も見つけました。 『仮面ライダー電王 さいきょうフォームデータファイル』徳間書店:徳間テレビえほんこれには、ミニスカ黒ストッキングのオネエサンの写真は、上半身までしか写っていないものが1点、載っているだけだったので、けっこう迷ったけど、けっきょく買いませんでした。
2007.04.09
コメント(0)
-

2006.07.22/スバルのCMソングに使ってください。
拙作『超合金歌集』(1987年4月8日発行)より再録。 * 死んじゃったってア~イド~ル 死んじゃったってア~イド~ル 高いサンミュージックから 声もあげずに飛び降りて 地味なスカート ヒラリで お弁当屋さんの視線を釘づけ 手首スッパリ切っても ガスの元栓 開いても ちょっとぐらいは近所に そうよ自殺だと気づかなくちゃイヤイヤ 事務所戻ったら泣くけど お説教ならノーサンキュー 窓ぎわが大切よ 弱く はかなく いさぎよく 死んじゃったってアイドル 私はアイドル(イマハ 死ンドル) 死んじゃったってアイドル 死んでもアイドル(イマハ 死ンドル) アイドルじゃ 生きられない Yeah! Yeah! Yeah! 死んじゃったってアイドル 死んじゃったってアイドル 死んじゃったってアイドル 死んじゃったってアイドル ちょっと疲れたタイプの 俳優さんと つきあっても 変な書き置き残して レポーターたちを煙に巻いちゃうわ ずっとこのままでいたい 成仏なんかはしたくない いつもみんなにメソメソ 泣かれ続けたい 騒がれればいい いい いつか幽霊になっても イタコ降ろしじゃノーコメント お母さんを通して 弱く はかなく いさぎよく 死んじゃったってアイドル 私はアイドル(イマハ 死ンドル) 死んじゃったってアイドル あの世のアイドル(イマハ 死ンドル) 死んでいちゃ 歌えない Yeah! Yeah! Yeah! 死んじゃったってアイドル 死んじゃったってアイドル 死んじゃったってアイドル 死んじゃったってアイドル * 限定版のコピー本『超合金歌集』は、 「アキモトヤスシ大特集!」と銘打ち、 この他には 『四谷のヒヤヤッコ』(『渚の「…」』) 『屋上』(菊池桃子の『卒業』) 『私は佳代ちゃん』(『私は里歌ちゃん』) 『嵐のユッコファン』(『嵐のマッチョマン』)と、 全部で5曲の歌詞が収録されていました。 他の歌詞は、多分に情緒的に流されている傾向があるので、 今ではチト厳しい。 岡田有希子:著『愛をください』朝日出版社『なんてったってアイドル』に『アナザー・バージョン』があるように、 もちろん『死んじゃったってアイドル』にも『アナザー・バージョン』がありますが、 * あの日『スター誕生!』で 河合奈保子さんの歌を お乳揺らして歌ったけど 審査員たちも誰もいなかった * この部分しか出来ていませんでした。 (最後のセリフは「また来世」で終わる。 それだけは決まっていた。)
2007.04.08
コメント(2)
-
オレは愚民だ
十七の頃に、橋本治:著『秘本世界生玉子』河出文庫この本を読んでいて(もちろん北宋社版で)さっぱり意味が分からなくて、難しくて難しくて、その合い間に息抜きで読んでいた『わッ毒ガスだ』が面白くて面白くて、そっちのほうしか理解できないオレは「ああ、愚民だなあ」と思い知った。ツービート:著『ツービートの わッ毒ガスだ ただ今、バカウケの本』KKベストセラーズ:ワニの本*その、ちょっと前に、糸井重里、橋本治:著『悔いあらためて』光文社文庫この本を読んでいて(もちろん北宋社版で。 北宋社版の『悔いあらためて』は著者名表記が「橋本治、糸井重里:著」で、 わずかの期間に両者のネームバリューが逆転していたことが窺える)この本ですら、さっぱり意味が分からなくて、難しくて難しくて、その合い間に息抜きで読んでいた『愛の傾向と対策』が面白くて面白くて、そっちのほうしか理解できないオレは「ああ、愚民だなあ」と思い知った。タモリ、松岡正剛:著『コトバ・インターフェース』大和文庫(↑もちろんオレが読んだのは工作舎版の『愛の傾向と対策』。 タモリのオールナイトニッポンで番組内プレゼントにハガキを出して、当選したもの。)
2007.04.08
コメント(0)
-

アフィれーグラス
次にアフィリエイトのポイントが貯まったら、【楽天ブックス】ではコレを買おうかな。 山前譲:編『文豪の探偵小説』集英社文庫「途上」谷崎潤一郎「オカアサン」佐藤春夫「外科室」泉鏡花「復讐」三島由紀夫「報恩記」芥川龍之介「死体紹介人」川端康成「犯人」太宰治「范の犯罪」志賀直哉「高瀬舟」森鴎外昨日、買いそびれたから。*2月度のアフィリエイト確定ポイントは、 2月20日【小名浜港市場食堂】 8ポイント 2月24日【楽天ブックス】 50ポイント合計で「58」ポイントでした。これが、今月に入ってくることになってしまいますね。*ちなみに、3月度の「未確定」ポイント。 3月4日【イージャパンアンドカンパニーズ】 13ポイント 3月7日【TENNIS 24】 78ポイント 3月25日【楽天ブックス】 18ポイントこっちは、まだここから無効になる数字などもあるのだろうし、最終的な総額がどうなるのかは分からない。5月に分かる。*【追記】泉鏡花の『外科室』は、吉永小百合の主演で映画化された時に、カバーに映画スチール写真が入った角川文庫版と、オビに映画スチール写真が入った岩波文庫版と、どっちの原作文庫を買えばいいのか迷わされたなあ。泉鏡花:著『高野聖』角川文庫「義血侠血」「夜行巡査」「外科室」「高野聖」「眉かくしの霊」 泉鏡花:著『外科室・海城発電 他五篇』岩波文庫「義血侠血」「夜行巡査」「外科室」「琵琶伝」「海城発電」「化銀杏」「凱旋祭」けっきょく、原作小説としては短篇1本なので、読むだけなら収録アンソロジーが1冊あれば、それで十分だったんですね。(映画化当時には、そんな便利なアンソロジーは文庫では出版されていなかったんだけど。 ↓コレが出たのも2004年だ。) 宮本輝:編『魂がふるえるとき/心に残る物語 日本文学秀作選』文春文庫「玉、砕ける」開高健「太市」水上勉「不意の出来事」吉行淳之介「片腕」川端康成「蜜柑」永井龍男「鶴のいた庭」堀田善衛「サアカスの馬」安岡章太郎「人妻」井上靖「もの喰う女」武田泰淳「虫のいろいろ」尾崎一雄「幻談」幸田露伴「ひかげの花」永井荷風「有難う」川端康成「忘れえぬ人々」国木田独歩「わかれ道」樋口一葉「外科室」泉鏡花*↑この、文春文庫の宮本輝アンソロジーには続篇で、浅田次郎アンソロジーが出ているんですが、そっちでは、川端康成の『死体紹介人』が入っていますね。 浅田次郎:編『見上げれば星は天に満ちて/心に残る物語 日本文学秀作選』文春文庫「百物語」森鴎外「秘密」谷崎潤一郎「疑惑」芥川龍之介「死体紹介人」川端康成「山月記」中島敦「狐憑」中島敦「ひとごろし」山本周五郎「青梅雨」永井龍男「補陀落渡海記」井上靖「西郷札」松本清張「赤い駱駝」梅崎春生「手」立原正秋「耳なし芳一のはなし」小泉八雲なんか、1篇ずつ、『文豪の探偵小説』とカブッている。「文豪」の「名作」というククリで選んでいる限り、ある程度カブるのは、しょうがないか。(宮本輝アンソロジー、浅田次郎アンソロジーに続く 「山田詠美アンソロジー」と「沢木耕太郎アンソロジー」って けっきょく出なかったんでしょうか? まだ出てないだけで、これから出るんでしょうか? 山田詠美アンソロジーはタイトルまで、 『古の香りに誘われて』だと決まっていたんですよね?)
2007.04.07
コメント(12)
-

2007.04.01/堤下気分でカフェめぐり
現在ただいま、最も話題になっている最新スポット、 渋谷のカフェ「SOMA」に行ってみました! 渋谷区桜丘。 ここ、昔の学研の編集部があった場所の、 すぐ近くじゃないですか! 学研の入っていたビルが、すぐ目の前に見える。 80~90年代までのオレが通い慣れていた、 自分の家の庭のような、あの御存知の坂道ですよ。 このあたりの場所は、今も昔も、 「アイドル大好きオヤジ」がウロチョロするのに 相応しい一帯なんですな。 この先の、学研のビルを越えて、 もう少し奥に入ったあたりに、 その昔の80年代には、別のオシャレなカフェがあったんですよね。 「フルハムロード」。 このあたりの場所は、今も昔も、 「女に汚い、犯罪者まがいの、胡散臭いカフェのオーナー」がウロチョロするのに 相応しい一帯なんですな。 * オレは「フルハムロード」の店内に入ったことは 一度もありませんでしたが、 (それは当時、学研の編集部内にタムロしていた他の皆さんも同様でしたが) 1985年9月の、ある日の深夜、 編集部でテレビを観ていたら突然、その近所の風景がニュースに映り、 「誰だかが逮捕されて、容疑者の夫人が店にいて、 記者会見のために店から出てくるところ」 という実況生中継が行なわれていたもんですから、 他の編集部の皆さんと一緒に、オレもホットな現場に駆けつけましたよ。 各局の中継スタッフが押し合いへし合いする中、 みんなで「不安を隠せない近所の住民」となって 騒動を見物していたんですが、 夫人の記者会見はテレビ朝日が独占放送することになっていたようで、 店からは、夫人の乗っているらしき車が出てきて、 そのまま一直線にテレ朝へ向かってしまった。 そんな状況では、 もうこれ以上「フルハムロード」前に詰めていてもしょうがないので、 各局の中継スタッフは撤収を始めた。 編集部の他の皆さんも、会社へ帰ってしまった。 オレだけが学研には戻らずに、まだ現場に残っていた。 店の前には、フジテレビの中継クルーだけが待機していて、 その周りにはオレを含む数人の野次馬。 その状況で、最後に一発、「フルハムロード前から」で、 レポーターが現場からシメのコメントを出す、 生中継の機会があったんですよ。 ここぞとばかり、オレはレポーターの真後ろにポジションを定めて、 レポーターの言葉に合わせてウンウン頷いたり、 顔をしかめてリアクションしたりする、 「不安を隠せない近所の住民」役を完璧に演じました。 その中継も終わり、 ようやくフジのスタッフも撤収を始めたのを見すまして、 オレは学研に戻ったんですが、そんなオレを、 全員でテレビのニュースにかじりついていた編集部の皆さんは 大爆笑で迎えてくださいました。 いま思えば、アレが、 オレの「タレント時代」にテレビに出た最後でしたね。 (タレント仕事では全然ないんですけどね。) その後もテレビには出ているけど、 それは「元タレントの、出版界の人間」としてしか出演はしていない。 * そんな想い出のある、渋谷区桜丘。 ここ「SOMA」のオーナー氏にも、 「フルハムロード」のオーナーと同じような運命は訪れるのでしょうか。 そして、オーナー氏と親しい美女の運命は。 オレは、やっぱり「SOMA」の店内にも入ることはなく、 店の外から遠巻きにして見守っているだけでした。 外で写真を撮っていたら、 お店のオネエサンが不審そうに出てきて睨んできたので、 あわてて逃げて来ちゃいました。 背の高い、キレイ系のオネエサンでした。 週刊誌の写真で見たような、小っちゃい女の子ではなかった。 (初音映莉子でもなかった。) あの小っちゃい美女は、 もうタレントではなくて、「元タレントの一般人」なのですから、 親しいオーナーのお店に出ていたって、何の不思議もないんですけどね。 彼女が店に出ているようなら、また行かなくちゃいけませんが、 どうも、オレが再び、あのお店を訪れるのは、 報道カメラマンが殺到しているような場合であるような気がしますね。*【追記】いやいや、チャチな後輩が起こした話題など、先輩の巻き返しにかかっては、ひとたまりもありませんなあ。役者が違います。 島田荘司:著『三浦和義事件』角川文庫
2007.04.06
コメント(0)
-

つまり、「ヨシダマ」というのは「全中裏」なのか
早見裕司:著『メイド刑事(4)』ソフトバンクGA文庫早見裕司センセイの『メイド刑事』シリーズは、明らかに『スケバン刑事』シリーズをモチーフにして作られている。それは、それでいい。それは尊重したい。いつの日か、オレも『スケバン刑事』をモチーフにして、何かの創作物を作るかも知れない。で、それはそれとして、『Stage Girls』というのは、もしかしたら↓コレがモチーフになっているのかも知れないのだった。高口里純:著『花のあすか組!(1)』角川文庫もっと厳密に言うなら、ドラマ版の『花のあすか組!』をモチーフにして、オレが「熱烈投稿」に連載(アレを連載というのか?)していた小説(アレを小説というのか?)の、『呂に似た女』が、『Stage Girls』の直系の御先祖様なのではないか、と最近いろいろと思いますね。(『呂に似た女』と『花のあすか組!』の距離よりも、 まだ『Stage Girls』のほうが、『花のあすか組!』との距離が近い。 「大人たちが泰平の天下を貪っている頃、少女たちは戦国時代に突入していた」。 お笑いの世界で!)もちろん『Stage Girls』は、オレが自分で原作のストーリーを書いているわけではないので、「カメちゃん」「シゲさん」「ガキさん」の、そのうちの誰が「栄村」で、誰が「ミコ」で、誰が「南牟礼はるみちゃん」で、いちいち正確に対応しているわけではないけれど、でも、「レイナ」の登場は「源五郎丸和歌子」っぽいよな~。どっちも「他人をムカつかせる喋り方」が身上。それまで「山下達郎みたいな喋り方」でヘラヘラしていたのに死んだ親父のことを言われると、急にマジになって、ブチギレる和歌子。キレる相手とキレさせる相手が逆だけど、それは『Stage Girls』第6話のシーンと、やっぱり似ている。『呂に似た女』の頃から、まだオレは、そんな言葉は知らなかったけれども「スピンオフ」というものの構想があって、本編の『呂に似た女』とは別に、外伝で『源五郎丸和歌子の事件簿』という少女探偵シリーズを考えていたのであった。実際、「女子高生年鑑」という増刊号に1本だけ、源五郎丸和歌子が主役の話を書いた。はなはだしくインチキだけれども、とりあえず「謎解きミステリー」の形はしていた。(学園の幽霊事件の謎を追うストーリーだから、本格的オカルトミステリーでもある)意図的に、今で言うところの「スピンオフ」を実行していたのである。1本しか書かなかったから、『源五郎丸和歌子の事件簿』は形成できなかったけれど、それは何のことはない、もっと書けば良かっただけのことなのだ。方向性としては、まったく間違っていなかったのだ。(『源五郎丸和歌子の事件簿』が完成したら、 その次には、和歌子の親父が生きていた、私立探偵だった頃の事件をまとめて 『源五郎丸源五郎の事件簿』も書いてみよう、とは思っていたけど、 それは、書けたらいいなあ、と思っていただけのレベルだった)いや、だから、レイナとレイナの親父をメインにして、『Stage Girls』のスピンオフは、ありえますよ!『日比木鈴菜の事件簿』ですよ!!カメちゃんとシゲさんの高校生時代の話、というのは、それは外伝ではないですね。本編の中に組み込まれる、ちゃんとしたメインストーリーの一部ですね。でも、レイナが主役のスピンオフは、完全に別の作品、ということにしたほうがいいんじゃないか。(極端な話、漫画家を黒岩先生以外の人に、替えてしまったっていいと思っている。)そんな外伝を発表できる、増刊号の機会なんて、あるんでしょうか、ないんでしょうか。…ええっ、実は!?
2007.04.05
コメント(0)
-
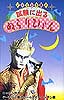
本棚探偵の冒険
そして『Stage Girls』第6話では、ついに初公開されました、シゲさんのプライベートルーム!シゲさんの本棚も初公開!気になりますねえ、他人の本棚というのは。ビデオテープやカセットテープらしきものが並んでいるあたりの、手書きラベルのようなものは、どうでもいいのですが、やっぱり本の形をしているもの、そのへんの書名が何なのか、これは気になってしょうがないところだ。(『すすめ!! パイレーツ』で、 一平の部屋の本棚に筒井康隆作品のタイトルがズラリと並び、 たった1冊だけ『シェクリイ選集』が置いてあったことなど懐かしく思い出される。)よ~~~く見てみよう。『かやく豆ゴハン』『ぬらり ひょん吉』『三国一の不幸者』『おろろんノート』『英国の『農『文化これらの本が、いったい何の本なのか?どういうジャンルに属する書物であるのか?まったく想像もつかない方も、おられることでしょう。はたして小説なのか、漫画なのか、詩集なのか…。ご説明します。これらは「ラジオのハガキ職人本」なんです!学生時代のシゲさんはラジオ番組にネタを送る投稿常連で名を馳せていて、つまり優秀な「ハガキ職人」だったんですよ。(第4話の『芸MEST』インタビュー記事で見出しに使われていた言葉 「毎日、図書室でネタばっかり考えてます。」というのは、そのことなんですね。)そんな、校内に一人も友達がいないようなシゲさんが、どうやってカメちゃんと仲良くなって、コンビを組むに至ったか…という話は、いずれ機会があれば発表しますが、とにかくシゲさんのアイデンティティは「自分は天才ハガキ職人だった」というところにある。だから、つつましく食堂の2階で、住み込みで暮らすシゲさんの部屋には、他には何もないけれど、ラジオ番組をエアチェックしたテープと、投稿のネタを集めて出版された「番組本」だけは、ビッシリと揃っているわけです。それぞれの「番組本」は、もちろん架空のものばかりですが、有名な元ネタがあります。*※『かやく豆ゴハン』 笑福亭鶴光:著『鶴光のかやくごはん 女はカオ、男はゼニで勝負』角川びっくり文庫 笑福亭鶴光:著『続・鶴光のかやくごはん ムチャクチャおもろいでェ~』角川びっくり文庫ドツル師匠の『かやくごはん』と題された書籍は、角川びっくり文庫版だけではなく、各社から何冊も刊行されていて、複数のシリーズ化が為されているのですが、わざわざモジッて『かやく豆ゴハン』というのであれば、むしろ直接の元ネタは、↓こっちなのでしょう。 笑福亭鶴光:著『鶴光の新かやくごはん第1集』KKベストセラーズ:ワニの豆本 笑福亭鶴光:著『鶴光の新かやくごはん第2集』KKベストセラーズ:ワニの豆本 笑福亭鶴光:著『鶴光の新かやくごはん第3集』KKベストセラーズ:ワニの豆本 笑福亭鶴光:著『鶴光の新かやくごはん第4集』KKベストセラーズ:ワニの豆本 笑福亭鶴光:著『鶴光の新かやくごはん第5集』KKベストセラーズ:ワニの豆本*※『ぬらり ひょん吉』 ニッポン放送「デーモン小暮のオールナイトニッポン」:編『デーモン小暮の試験に出るぬらりひょん』ニッポン放送出版/扶桑社*※『三国一の不幸者』 ビートたけし、高田文夫:編『伝説の幸せシリーズ VOL.1 ビートたけしの三国一の幸せ者』扶桑社文庫*※『おろろんノート』 大槻ケンヂ:著『のほほん雑記帳』角川文庫ただし、『のほほん雑記帳』はラジオ番組への投稿を集めた「番組本」ではない。オーケンは、ラジオ歴が長いわりには、そういう本は今まで出版していない。唯一あるのが、↓コレぐらいでしょうか。 ニッポン放送「デーモン・オーケンのラジオ巌流島」:編『デーモン・オーケンのハッスル巌流島』ニッポン放送出版/扶桑社コレだって、番組への投稿を集めた本…というよりは、対談集だもんなあ。*※『英国の※『農※『文化書名が隠れてしまっているので、このへんについては、サッパリ分からない。(もしかしたら黒岩先生のところのアシスタントさんが 勝手にタイトルを作って、書き込んだだけなのかも知れないし。 棚の下のほうにある『笑いの○と×』とかいう 何だか分からないBOXセットのような物なんかは、明らかにそうですね。)もしかしたら、『農…』というのは、タイトルが『農と言える日本』で、『UNと言える日本』に関係あるのかもしれない、とはちょっと思ったけど、いくら何でもシゲさんほどネタ作りの才能がある人が、あんな『UNと言える日本』なんかを面白がって、自分でも投稿したりしていた…なんて(藤井青銅さんには申し訳ないが!)そんなバカなことだけはありえない。それは絶対に考えられないことですよ。ただ、これは想像だけど、右端の『文化…』というのは、ひょっとして↓コレかも知れない。コレなら面白いからシゲさんも読んでいそう。 月刊タウン情報かがわ編集部:編『笑いの文化人講座』ホットカプセル以下、全25巻。『REMIX』版もあります。
2007.04.05
コメント(0)
-

メイキング・オブ・『Stage Girls』第6話
【Stage:6 友達】。「もう芝居の名前をサブタイトルに使うのは、やめたんですか」と質問されることがあります。やめてません。そこは、むしろ、こういう訊き方をしてほしかった。「『友達』なんてタイトルの芝居があるんですか?」あります。安部公房。安部公房:著『友達・棒になった男』新潮文庫谷崎潤一郎賞・受賞作。オレが最初に知ったのは、筒井康隆が『私説博物誌』の中で紹介していた「あらすじ」からだったんですが、「ある日、アパートで独り暮らしの男の部屋に、 友達だ友達だと言って、大家族が踏み込んでくる。 その家族たちは、友達ヅラをしながら、そのまま部屋に居座り、人数も増やし、 とうとう元からの住人だった男を追い出して、命まで奪ってしまう。 男が死ぬと、家族たちは、また新たな友達を求めて、 別の独り暮らしの男が住むアパートの部屋へ、押し掛ける」こういう話であると、そういうことですな。それで題名が『友達』。皮肉なタイトルじゃありませんか。レイナは、ヒビキプロの社長令嬢として、「お嬢」と呼ばれて、運転手つきのクライスラーに乗って、シゲさんが独りで住む部屋に押し掛けたわけですよね。そこでは、もちろん「家族」全体、ヒビキの家を丸ごと背負っている。シゲさんの行方を探すのだって、要は、レイナのしたことは「パパにお願いした」だけだ。レイナの親父にしても「天下のヒビキプロの二代目」経営者で、代々の家族を背負ってきているわけである。ダンスの先生に「日比木さんちのコーちゃん」と呼ばれている以上、先生が重要視しているのは「日比木さんの家」だ。「コーちゃん」個人の人格ではない。どうしてダンスの先生だけが、シゲさんの行方を知っていたのか。そして、「先生だけがシゲさんの行方を知っている」ことを、どうしてレイナの親父だけが知っていたのか。そのへんは、まだまだ謎は深まる一方ですが、この状況をシゲさんの立場になって受け止めてみると、まさに天下の「日比木家」という巨大な家族に、自分が完全に包囲されてしまっていることに気がつくわけですよ。実際に、独り暮らしの部屋に入り込んできたのは、レイナだけだけれども、そのレイナは、背後に巨大な権力を持つのであろう大家族を、背負って来ている。シゲさんには、そのように見えていたはずなのだ。きっと。たぶん。おそらく。大家族が全員で、ウチの部屋に侵入してきた!つまり『友達』の主人公と同じ、不条理な一幕だったわけである。*その、ダンスの先生。この人の存在が、どういう複雑な形で今後のストーリーに絡んでくるのか。お楽しみに…といったところですが、ときに、「スタジオ リョージ」の「中村先生」という名前。皆さん、聞き覚えはありませんか。そういうことになると、名前は「中村リョージ」なんでしょうね。で、この顔。この風貌。この筋肉質な身体。このゲイ術的な物腰。そっくりそのまま、名前までそのままなモデルが、現実にいないわけはない、そう思いませんかオ客サン! 東京パフォーマンスドール『That's the REVUE』(DVD)構成・振付・演出:中村龍史「カメちゃん」「シゲさん」「ガキさん」「レイナ」にヴィヴィッドに反応してくださっているヲタの皆さん、すいません!われわれの原点は、やっぱり、こっちです!こっちの時代のアイドルを忘れるわけにはまいりません!!というか、両方知っちゃってます!!!皆さんが「ヲタ」と呼ばれている現在も知ってるし、「外道」と呼ばれていた、あの頃も知っている。(さらに、それより前の「連合」と呼ばれていた頃も知っているし、 それより昔も知っている、オレは。 原作者は、そこから以前は、あまり詳しくはない)対象こそ違えど、その時々で、同じような活動を続けてきた、たぶん今後も、新たな対象をめぐって同じような活動をするのだろう、そういう【風の旅団】の一員であるわけなんですね、オレたちは。お世話になった「先生」が「中村先生」なのだとすれば、カメちゃんのモデルは「カメちゃん」でもあるんだろうけれど、穴井なのかも知れないし。シゲさんは篠原なのかも知れないし。じゃあガキさんは誰? レイナは誰?レイナの友だちの眼鏡っコは誰?というか、米光っちゃんは、どこ?さとみちゃんは? 知砂は? 麻衣ちゃんは?これから『Stage Girls』には、「コハル」であったり「ミッツィ~」であったりするのと同時に、「カナ」でもあったり「夏っちゃん」でもあったりするような、そんなややこしいキャラクターが出てくるの?…ひとつだけ鉄板で確実なのは、「市井」が「市井」であることだけです。*黒岩先生には、もちろん「中村龍史」という人物の説明なんかしていないし、写真も渡してはいなくて、ただ「オカマっぽいダンスの先生で、筋肉質で」と大雑把なキャラクター設定をお願いしただけなんですが、出来てきた絵が、描いた黒岩先生は知らないはずの、モデルの「本人」とあまりにもソックリで、これには仰天しました。一流の漫画家さんの底力、もっと言えば超能力、霊能力のようなものまでを見た思いがしました。
2007.04.04
コメント(1)
-

さがしものは何ですか?
「ピカ好きの人に悪い人はいないし、 むしろピュアすぎるような人ばっかりだ」という実例。【実例1】↓こんな日記を書いている、ジミーちゃん。 ジミー大西:著『天然色日記』朝日文庫【実例2】TVのドッキリ企画で、『あすなろ白書』に憧れて青学を受験していた、よゐこの濱口。 よゐこ:著『よゐこの芸能日記』学研*だから↓コイツが許せないのだ。 筧利夫:著『わしはおさるさん。』二見書房教訓:ピュアだと、マンコが舐められない。
2007.04.03
コメント(0)
-

なぞなぞ
「100%ピュアな人って、誰だ~?」 (こたえ=ピュアな正博) 桑名正博:著『不良親父のボランティア』講談社 (もちろん、「ピュアな晴子」でも正解。)
2007.04.03
コメント(0)
-
14年前のメモにあった言葉
サードステージ:編『役者の仕事 「演技」はどうやって作られるのか?』福武書店と、武藤起一:編『武藤起一インタヴュー集(1) 映画愛[俳優編]』大栄出版は、とてもまぎらわしいので混ぜて1冊にすればいいと思います。
2007.04.03
コメント(0)
-

ポワソン・ダヴリル
4月1日の夜、「SF乱学講座」というマニアックな催しに行ってきました。(オレが行ったのは、ジュニアSFの歴史について 大橋博之さんが講師を務めておられた、2004年12月の会に続いて2度目。) 北原尚彦:著『新刊!古本文庫』ちくま文庫 北原尚彦:著『奇天烈!古本漂流記』ちくま文庫 北原尚彦:著『発掘!子どもの古本』ちくま文庫 北原尚彦:著『本屋にはないマンガ』長崎出版今回の講師である、北原尚彦さんの (初めて御本人の御姿を拝見したのですが、今まではオレの勝手なイメージで、 もっと恰幅のいい、ブルドッグ系の顔をした人なのであろう、と思い込んでいた。 …どうしてだろう? それは、きっと「北原尚彦」と名前の似た「中原弓彦」のイメージのせいか。 たぶん「青木雨彦」も混ざっているだろう。)古本蒐集についてのお話は、非常に面白かったです。面白かったんだけど…。だけど…。でも…。どうして、この次の会の講師が、 急に、 オレ なんだ?????とんだエイプリル・フールなのだろう、とは今でも思っている。
2007.04.02
コメント(5)
-
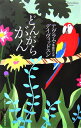
日曜の朝から
ところで、やっぱり最近は、『あるいは酒でいっぱいの海』というタイトルは『さもなくば海は酒でいっぱいに』と改題したほうが良くなってるのかな。 アヴラム・デイヴィッドスン:著/殊能将之:編『どんがらがん』河出書房新社:奇想コレクション「序文」グラニア・デイヴィス/浅倉久志:訳「ゴーレム」浅倉久志:訳「物は証言できない」浅倉久志:訳「さあ、みんなで眠ろう」浅倉久志:訳「さもなくば海は牡蠣でいっぱいに」若島正:訳「ラホール駐屯地での出来事」若島正:訳「クィーン・エステル、おうちはどこさ?」浅倉久志:訳「尾をつながれた王族」浅倉久志:訳「サシェヴラル」若島正:訳「眺めのいい静かな部屋」若島正:訳「グーバーども」浅倉久志:訳「パシャルーニー大尉」中村融:訳「そして赤い薔薇一輪を忘れずに」伊藤典夫:訳「ナポリ」浅倉久志:訳「すべての根っこに宿る力」深町眞理子:訳「ナイルの水源」浅倉久志:訳「どんがらがん」深町眞理子:訳「解説」殊能将之「著作リスト」
2007.04.01
コメント(0)
全45件 (45件中 1-45件目)
1
-
-

- 読書備忘録
- 馬上少年を過ぐ:司馬遼太郎短編集
- (2025-11-22 00:06:49)
-
-
-
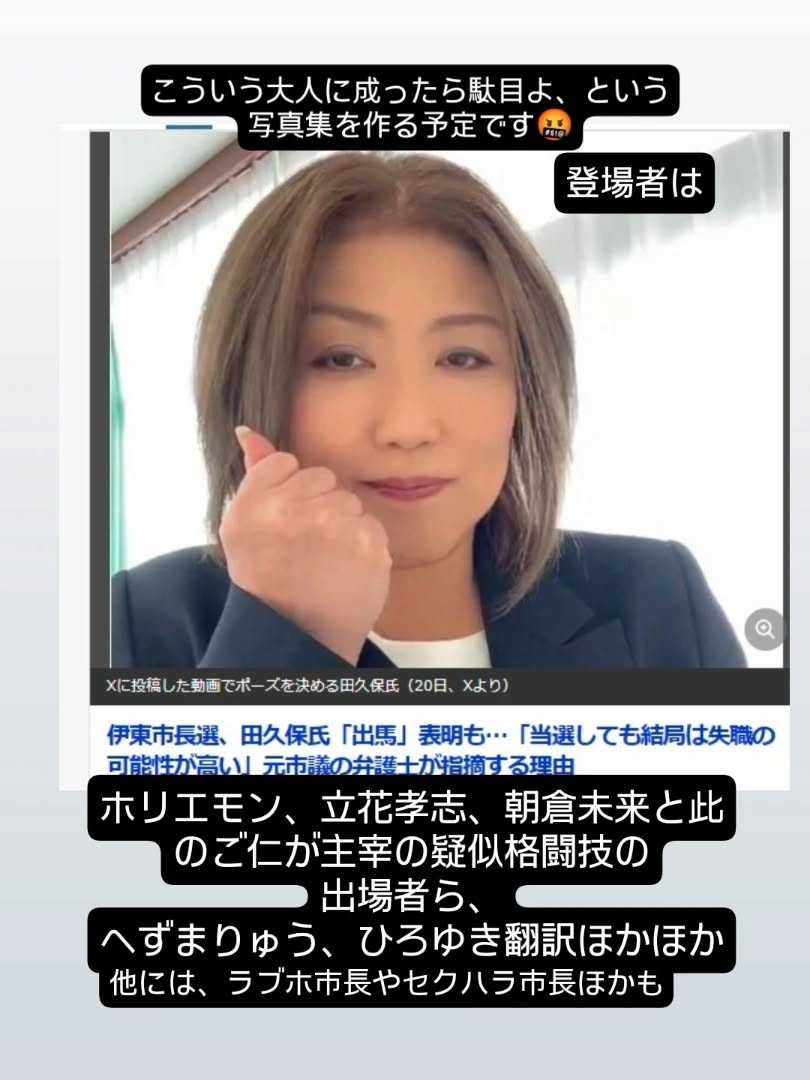
- 人生、生き方についてあれこれ
- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…
- (2025-11-23 19:32:35)
-
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ2025年52号感想その…
- (2025-11-25 13:59:33)
-