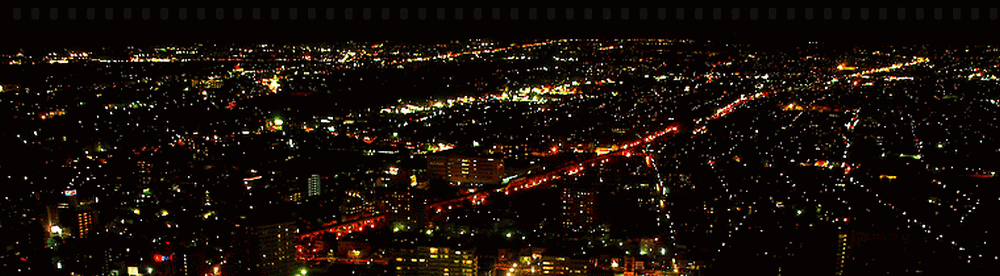PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
まだ登録されていません
Comments
コメントに書き込みはありません。
Freepage List
カテゴリ: 演出ノート(3)
川に落ちて灰が流れてしまい、彦市の姿が天狗の子にも見えます。
「や、姿ば現しよった。さあ、上がってけえ。ひでえ目にあわしてくるる」「わあ、灰がみんな流れてしもうた」「何、流れた? 蓑ば流してしもうたっか? すんなら、はよ取らにゃのうなってしまう。わーん」。「わーん」が可愛いです。隠れ蓑が川の中だと思って、天狗の子も飛び込みます。
これから彦市と天狗の子の、川の中での追いかけっこが始まります。取っ組み合いよりも、逃げ回るのを追いかけるのが、視覚的にも良いです。
能舞台で、狂言的に演じるなら、舞台がいきなり川の中の設定に変わっても、違和感はありません。劇場舞台なら、波幕でしょう。互いに、なるべく長い距離を動くこと、飛び込んで潜るとか、息継ぎのために上に顔を出すなど、上下の動きも入れます。
わたしはしませんでしたが、波幕を出す場合、二人の間に「河童」が現れると、観客は大いに喜ぶでしょう。
そこへ、殿さんがやって来ます。殿さんは彦市が、川の中に入って河童を捕まえようとしていると誤解して、頑張れ頑張れと、彦市を励まします。くたくたになった彦市を、天狗の子が殴りつけ、殿さんが扇を拡げてはやし立てているところで、幕が下ります。
なんとも可笑しく、のどかで、本音が通る世界でのびのびと生きている人たちのエネルギーを感じるお芝居です。演技者も観客も一緒に楽しめる作品です。
この芝居は、殿さんを演じる人によって、出來が変わります。いかにものどやかで、のほほんとした感じ、それでいて貫禄も感じさせたいですね。わたしの場合は、素晴らしい演技者に恵まれましたので、余計にそう感じています。狂言の場合は、先代の茂山千作師が、とても良い殿さんでした。
『彦市ばなし』は、その少し後に富山県の利賀村で行われた、アマチュア演劇祭にもってゆきました。そこでは能舞台を使って上演しました。冒頭を、出演者たちによる盆踊りで始めて、舞台に一人残った人物が彦市になるという演出をとりました。彦市は、多くの民衆の一人を代表しているのだという意図です。また、最後は彦市と天狗の子が客席に降りて行き、殿さんが舞台中央で、ご機嫌でいる、という終わり方にしました。ありがたいことに、評判が良かったです。
このときの音楽は、『二十二夜待ち』の「でんでらでん」の唄などと一緒に、PCを使って自分で作曲しました。
民話劇はやはり苦手です。もう演出するつもりはありません。ただし、『夕鶴』なら、演出したいです。あれは戦後の創作劇の大傑作ですから。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019.06.14 09:00:11
[演出ノート(3)] カテゴリの最新記事
-
『広くてすてきな宇宙じゃないか』(2) 2019.07.20
-
『広くてすてきな宇宙じゃないか』(1) 2019.07.19
-
『思い出を売る男』(10) 2019.07.18
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.