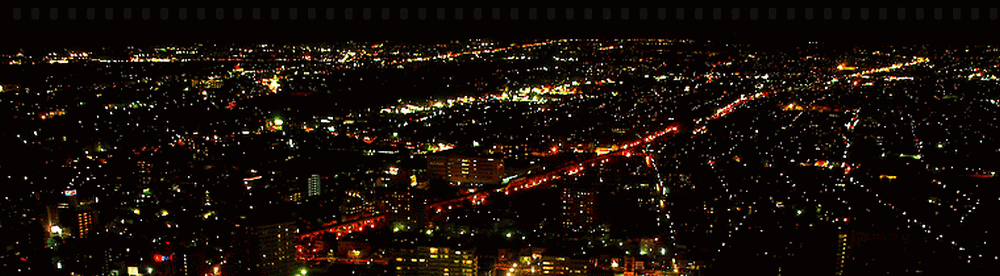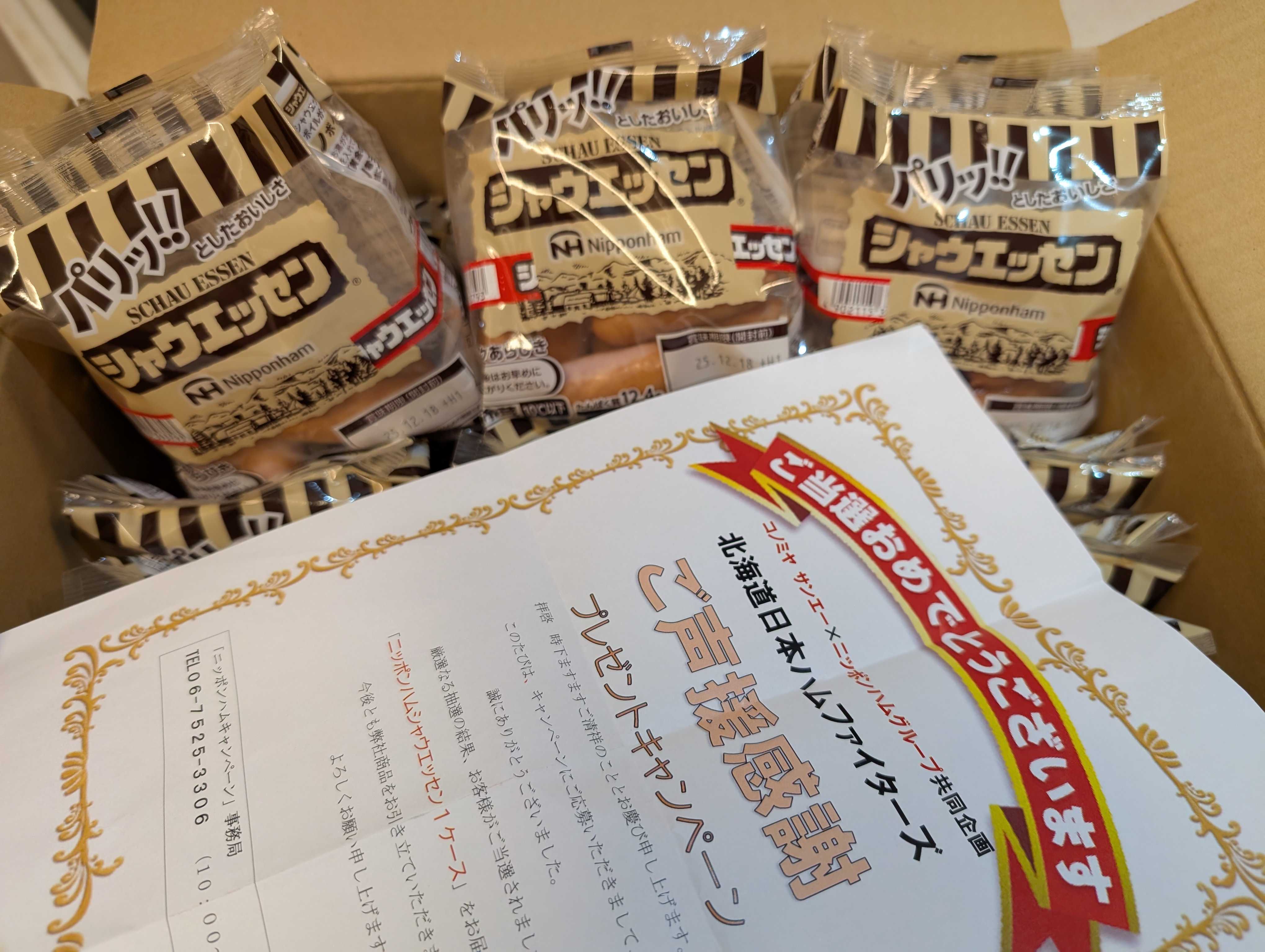全665件 (665件中 1-50件目)
-
大阪芸大 舞台芸術学科 演技演出コース1回生 第1週
大阪芸術大学舞台芸術学科演技園主tコース 新入生の皆さん「対面授業」ができるまで、とりあえず「通信教育」を行います。これまでブログに演技訓練や演劇論、演劇史などずっと書いてきました。それをもとにして、演技のための訓練の仕方を具体的に書きます。もちろん、「基礎訓練」は個々人が直接指導を受けて、体で身につけるものです。書かれたことを自分でおこない、疑問があればZoomでたずねてください。対面授業が始まれば、ちゃんとできているか、しっかり見てゆきます。○練習着のことから、細かく話してゆきます。稽古場に入るときの服装ですが、ルーティンの稽古と、上演のための芝居稽古とでは、当然違ってきます。演出家がいる芝居の稽古の場合、基礎訓練のときの稽古着でも良いですが、なるべく黒っぽい無地のウエアで、上下は統一感があるようにします。服装で、余計な性格を感じさせないためです。Tシャツにデニムでも良いですが、あまり肌が出ない方が望ましいと思います。足元は床の状態によりますが、バレーシューズや体育館シューズのようなものが良いです。カンフーシューズなども可でしょう。厚底のスニーカーはNGです。芝居が時代物であれば、足袋をはきましょう。靴下は、古典芸能分野では「裸足」と考えられますので、NGです。男女ともに、浴衣を着て稽古することも多いです。立ち座りするときのすその扱いなどがあるので、特に女性は着物で動くことに慣れておくべきです。ルーティンの稽古(基礎訓練)の場合は、薄物のウエアを着ます。これは動きやすいこともありますが、身体、筋肉の動きが指導者からよく見える必要があるからです。呼吸訓練のときに、腹筋が動いているか、肋骨の底部・腰のあたりが大きく動くか、胸呼吸をしたために肋骨が上がって、脇腹が狭まってゆかないか、また胸郭が全体に広がっているか、肩や背中が強張っていないか、見てすぐにわかるようにします。寒いときは、身体を動かさない間は何か羽織っておいて、訓練にかかるときは脱ぐ、というのはOKです。足元も冷えますが、こちらは我慢しましょう。上衣はだぶつかないもので、なるべく、かぶって着るものにします。ボタンやファスナーは無い方が良いです。身体の線が見えることを嫌がる人もいるでしょうが、上に述べたように、身体の各部分の動きが外から見えることは、指導する上でとても役立ちます。ウエストはゴムの入ったものにして、ベルトはしないほうが良いです。ただ、腰に圧迫感を与えて背筋を伸ばすとか、呼吸のときに腹筋を鍛えるために圧迫を加えるという目的で、幅広のベルトをすることは、考えられます。この場合、トラウザーズのずり落ちを防ぐというのではなく、腹筋運動の補助具と考えます。その場合は、幅の狭い堅い帯のようなものが良さそうです。浄瑠璃の太夫は、晒の布を腹巻きのように巻き付けると言います。「腹から声を出す」と言いますが、伝統芸能や古典劇の発声では、下腹部の腹筋に力を入れ、声を出すときにおなかを膨らませます。そのときに、この晒が切れるそうです。この呼吸法、発声法は高度ですので、始めのうちは練習しなくて良いです。指導者の目の届かないところでやってはいけません。足元は、床の状態によりますが、バレーシューズ、体育館シューズのように、底が平べったくて柔らかく、軽いものを履きます。わたしはモダンダンスを勉強していたために、よほどでなければ、裸足を好んでいます。足が最も自然な状態になりますし、床の状態を感じ取り、床を「噛んでいる」と実感できるからです。コンクリート床や、あまりに冷たい床の場合は、古い足袋を履くこともあります。靴下はいけません。滑りやすいからです。ダンスに適した木の床の上で、回転やジャンプをするなら、決して靴下ばきでしてはいけません。滑りやすくて危険ですし、ちゃんとした服装でレッスンしている舞踊科生に失礼ですから。スニーカーのように靴底が厚いもの、凹凸があるものは床を痛めます。あまり重い靴を履くと、動きづらくなります。ダメです。稽古場には汗ふきタオルと、メモするための小さな筆記具、そして水分補給の為の飲み物くらいを持って行きます。飲み物はきっちりと蓋が出来るものに入れます。それ以外は必要ないと思います。本来、稽古場で飲食するのは、言語道断の行為です。稽古場は修行の場で、リラックスする場ではありません。ICレコーダーなど記録用のものは、指導者・演出者に使用して良いかを確認します。携帯電話は電源を切るか、サイレントモードにします。劇場と同じです。○腹筋の鍛錬を考えます日常訓練として「鍛える」必要があるのは、いうまでもなく腹筋です。それも下腹部の腹筋が重要です。古武術や弓術で「臍下丹田」と呼んでいる箇所に、意識をおきます。お臍を基準にして、その上の腹筋は「おなか」が出っ張ってくるのを防いでくれます。スタイルのシェイプアップに重要な腹筋です。シットアップが一般的な運動です。仰向けに寝て、上半身を起こす運動を繰り返します。手は、頭の後ろで組んでも、胸の前で組んでも良いです。ヤッ、とばかりに勢いをつけて起きるのでは無く、おなかの部分にかかる加重を感じながら、急がずに上げます。呼吸とおなかの圧迫、状態の立ち上がりを連動させるように、一回毎に息を吐きます。そのとき、数を数えると、声と呼吸の関連づけにもなります。小さな動きで素早く何回も行う腹筋運動もあります。身体の引き締めにはあれが良いようです。声を出すには、良いとは思えません。あのやり方は、息を止めています。下腹部の腹筋は横隔膜が上下するのを助けます。空気を多く取り入れたり、多く送り出したりするために、重要な役割を持ちます。声を出すのに役立つ腹筋はこちらです。レッグアップが効果的なのですが、足を上げて保持する運動は腰に負担がかかります。両脚をそろえて上下に動かしたり、両脚を上げて「蟹挟み」のように開閉したり、足を上げて「自転車こぎ」をしたりすることで、鍛えることができます。他にも運動はありますから、運動の本を調べて、自分にあうものを見つけて下さい。わたしは、両足をそろえて伸ばし、床から少し(20センチくらい)上げたところを「下の位置」、そこから両足を90度に上げたところを「上の位置」とし、下から上、上から下を20回ほど繰り返します。「下」「上」の位置で、必ず一度静止し、流れないように運動します。なぜか学生諸君には、この程度できついらしい。やってみると、上の腹筋運動の方が楽です。腹筋運動をするときに、呼吸を止めず、動きに合わせて息を入れたり吐いたりしてください。アスリートではないのですから、トレイニングをするときも、台詞を言うつもりでするのが良いはずです。台詞を言いながら行う人もいます。ただ、長い音を伸ばすのは難しいので、歌うのはやめましょう。腹筋を鍛えるのは声を出す、呼吸調節を行うためです。時々テレビの番組などで、ジムに通って、バーコードのように筋が入った腹筋を作るとか、歌の練習のためにおなかを殴って腹筋が硬くなるように鍛える、とかの様子を見ます。あれは違うと思います。わたしたちは格闘技のために腹筋を鍛えるのではありません。そもそも、腹筋がコチコチに硬くなって動かなくなれば、空気を取り入れたり押し出したりが、うまくできなくなります。しっかりと力を感じ、大きく動く。その動きが、自由かつやわらかいことが、発声のために必要なのです。オペラ歌手や古典芸能の名優のおなかには、ボディビルダーのような筋は入っていません。相撲取りとボクサーを較べれば、歌がうまいのは相撲取りです。空手家やボクサーは、ロングトーンが苦手です。相撲取りやオペラ歌手の腹筋が弱い、と想う人はいないでしょう。ただひたすら腹筋を鍛えれば良い、というのは間違った考えです。頭を使わない(何故それをするのかを考えない)訓練はやめましょう。腹筋だけを鍛えずに、背筋も鍛えましょう。腹筋に対して「カウンターバランス」を考え、背筋の力を弱らせないことが、健康のためにも大切です。背筋そらしの運動が適切でしょう。背筋を伸ばすつもりでそらせます。腰のところで曲げるとは思わないことです。中には腰のところで「折る」ようにしている人もいますが、これでは腰を痛めます。背筋はまっすぐだけでなく、斜めに引っ張ったりして、しっかり伸ばしてゆくと良いです。足腰は基本ですから、声出しとは別に、普段から鍛えておきましょう。スクワットが良いようです。四股を踏むのも良いらしいです。時間がとれるならジョギングも良いですね。胸筋を鍛えて胸郭を拡げられるようにしておくと、共鳴が豊かになります。腕立て伏せは身体を痛める危険があるらしいので、エクスパンダー(バネでなく、ゴムのようなものが安全でしょう)のような運動具を、両手で引っ張るのが良いように思われます。○身体のリラックスを考えます 身体が硬く強張っていては、声がでません。自由な息の流れが遮られてしまうため、肩や胸に力を入れて、無理矢理息を押し出して声にしようとしてしまいます。首や喉の筋肉も硬直していますから、声帯がうまく動かず、むしろ閉じてしまい、息が出て行きません。具体的に言えば、巨大な校旗を支える応援団員のような声しかでません。それほどでなくても、身体が緊張していては、息がスムーズに流れないし、声帯も正しく合わさってくれないし、身体での共鳴も悪くなります。ですから、身体に無駄な、余計な力が入らない、リラックスした状態を作らねばなりません。力を入れるのは、腹筋だけで十分です。身体の強張りをとるためにストレッチをします。ゆっくり、なるべく大きく身体を伸ばします。両手を組んで、上に伸ばします。骨盤から背筋にかけて、伸ばします。わたしは骨盤から背筋が真っ直ぐになるようにして伸ばしますが、骨盤と背骨の接合状態に会わせて、少しそるようにして伸ばす人もあります。どちらも可のように思います。両手を胸の前で組んで、前に伸ばします。このとき引っ張られるのは、肩から背中の部分です。腕を長くする運動ではありません。背中の筋肉が後ろから前へ引っ張られる感じをつかみます。今度は、両手を後ろで組んで、後ろに伸ばします。引っ張られるのは胸の筋肉です。背中側は動きにくいので、腕は身体に直角でも、下に下がるようにしても、どちらでも良いように思います。まあ、前へ伸ばすのと同じ高さで後ろへ引っ張る方が良いかとは思いますが。腕の筋肉を伸ばすのでは無く、背中や胸を伸ばすと考えて行います。背中や肩は、すぐに強張ってきます。緊張すると肩がすくんだり、肩甲骨が互いに迫ってきます。ですから背中や肩を拡げておきます。両手を上に上げて、腰から前に身体を伸ばし曲げて行きます。背筋がたてに伸びます。背中を横に拡げるためには、両手を胸の前で交差させるのが良いでしょう。肘を横にはって、まず背中の広がりを感じ取ってから、腕を前に持ってきて交差させます。いきなり腕を前に持ってきて交差させると、背中が十分には広がりません。背筋を伸ばすときも、骨盤から上の身体を上に持ち上げるようにしてから前に倒してゆきます。ひたすら「伸ばす」ことです。首の筋肉はすぐに硬くなります。立っていると、上から頭の重さがかかってきますから、抑え付けられて縮んでいます。凝っています。首を前後と左右にゆっくり伸ばして、緊張をほぐします。曲げるのではなく、伸ばすのだということを、いつも意識します。最初に前に伸ばして行くとき、できるだけ伸ばして前に垂らしてやらないと、その後の伸びが十分になりません。伸ばした上に、反対側からまた伸ばして載せて行く、という感じで行います。首を回すのは、いろいろな角度で首の筋肉を引っ張るために、ひねっているのです。首の運動の後、上体を前に垂らして、野口体操で言う「ぶら上がり」をします。上体を倒してゆくときに、力の強張りが無いかを感じ、胸にたまっている息を吐き出します。そして無駄な力を降り出すつもりで、腰を支点にして上体を(前後左右に)スイング、(上下に)バウンスします。それから、無駄な力が入り込んでこないように注意しながら、身体を起こします。骨盤から上に向かって、持ち上げます。息は止めないで。まっすぐに上がっていることを心がけながらです。身体が立ち上がったら、口の中を大きく開けます。まず、口の上部を拡げるために、軟口蓋を持ち上げます。顔の前側、目の裏のあたりで、上あごを持ち上げるようなつもりで、あくびをするように上げます。正しく開けると、頭部共鳴が自然にできて、明るく大きな声が出ます。左右に拡げる時は、口角をあげ、斜め上に開ける感じが良いでしょう。スマイルを心がけると、この形になります。これも声を明るくします。顎を開けるときは、顔の前面で下げるのでは無く、顎のちょうつがいのところでガクッと外すような感覚で、下におろします。口の前の方で顎を下げると、後ろ側が上がってしまい、舌が持ち上がって、息の通り道を邪魔してしまうからです。口の開けは4回ずつくらいが適当でしょうか。あと、舌の運動をしておくと良いですね。舌の先を上下に動かす。舌の中央部を持ち上げて鼻に息を抜いて行く。舌の両側を持ち上げたり、舌先から巻いてくるというのもあります。得手不得手がありますから、できなくても気にしないで。舌を前に突き出すのも良いかな。左、右に動かすのは、発音に関係しませんが、舌の付け根の運動にはなります。声を出す前の身体の準備は、時間がかかってよいから、ゆっくり大きく行います。
2020.04.28
-
中原中也『サーカス』 「ゆあーん」(2)
その次は「ゆよーん」です。最初が「ゆあーん」なら、次も「ゆおーん」になりそうですが、「ゆよーん」です。なぜ「お」でなく「よ」なのか。「ゆあーん」で述べた考えが、ここでも応用されます。"yu yoh-n" で、"y" の音が入ることで、音にひっかかりが生まれます。そのままに流れずに、せきとめられる。そして「ゆ、や」と音が続くと、ひっかかる「や」の音に、力が入ります。するとどうなるか。「ゆ」でしっかりとブランコを抑えて、「よ」で力を入れてそれを押し出す感じです。情景を言うなら、「ゆあーん」と揺れてきたブランコを受け止めて、「ゆ」で、反動をつけるために軽く後ろにひき、「よ」で力をいれて前に押し出し、「よーん」で向こう側にブランコが揺れて行く。そんな情景を想像します。「ゆあーん」では動きは一つだけですが、「ゆよーん」では二つの動きが見られるのです。では「ゆやゆよん」は。「ゆあ」ではなく「ゆや」、「ゆよーん」ではなく「ゆよん」。これはどういう様子なのでしょう。「ゆ」「や」「ゆ」「よ」と半母音 "y" が?回続きます。それぞれに力が入る、動きがあると考えましょう。すると、こういう動きが想像されます。向こう側から戻って来たブランコを受け止めます。「ゆ」軽く後ろへ引いて、「や」前へ出すけれど、まだ反動は小さいので、飛び出しません。「ゆ」これでしっかり後ろへ引いて反動をつけます。「よん」で、力をこめて前に飛び出して行きます。こういう動きを表す音表現ではないでしょうか。向こう側へ飛んで行くのですから、「よーん」となるのが動きに対してふさわしい音でしょう。しかし「ゆよーん」と伸びた音にすると、連の終わりが間延びした感じになり、しまりがありません。それで、「ゆよん」と短くおさめて、しまりをつけたのだと思います。ですからわたしは、この「ゆよん」は、発する音は短いけれど、長く伸びる音の気持ちをもって、「ゆよん」とおさめています。詩を読むためには、音についても、このようによく考えなければなりません。より良く読むためには当然のことです。そのように学生には言うのですが、どうも勉強してくれません。カラオケで画面の歌詞を読むように、書かれた文字を自分のやりやすいように音として発するだけの者がほとんどです。勿体ない。by 神澤和明
2019.08.06
-
中原中也『サーカス』 「ゆあーん」(1)
詩のレッスンをする時に、中原中也の『サーカス』をよく使います。大変に音が面白く、リズムが楽しい作品です。中也の詩はその意味内容よりも、「音」を楽しむ要素が大きいです。『サーカス』という作品は小学生でも楽しめる作品です。詩の中では、冒頭の「幾時代かがありまして」というフレーズと、「ゆあーん、ゆよーん、ゆやゆよん」というフレーズが3回繰り返してでてきます。不注意な学生は、「ゆやーん、ゆよーん、ゆやゆよーん」と読んだりしますが、書かれた通りではないことに、気づきません。で、書かれた通りに読みなさいと、いつも注意をさせられます。「幾時代かがありまして」は、第一連で続けて出て来ます。導入の役割です。一方、「ゆあーん、ゆよーん、ゆやゆよん」は、2連目、3連目、4連目(最終連)の終わりに繰り返されて、それぞれの連の締めくくりをしています。 この音が、空中ブランコが振れているさまを表しているのは、間違いないでしょう。では、この描写が表しているブランコ、もしくはブランコ乗りの動きは、どんなものなのでしょうか。 テクストの言葉を考える時、その言葉が無ければどうであるかとか、他の言葉がおかれていたらどうであるか、と考えます。そこにみえてくる違いから、作者がその言葉を使った理由がうかがえてきます。今回も同じ事をしてみます。「ゆあーん」という音が暗示する動きはどんなものでしょうか。ここでは、学生がよく間違える「ゆやーん」という音との違いを考えます。「ゆあーん」の場合、"yu ah-n"、「ゆ」に含まれる口の開きが小さな「ウ」の母音から、すぐに「ア」という、口を大きく開ける母音に繋がって行きます。口の動きは滑らかで、引っかかる感じはありません。息が一つの流れの中で動きます。「ゆやーん」だと、どうでしょう。"yu yah-n" ですから、「ウ」の母音のあと、「ア」の母音になる前に、半母音の "y" の音が入ってきます。「ユ」と「ヤ」がそれぞれに音としてたってきて、ぶつかる感じがします。「ゆあーん」の場合にある「流れ」が、軽くせきとめられてしまう感じです。情景を思い描くなら、「ゆあーん」は、手から離れたブランコが、そのまま滑らかに向こう側に動いて行く。そんな絵面が見えてきます。サーカスのテントの高いところを、ゆったりとブランコが振れてゆく。伸びやかな動きです。by 神澤和明
2019.08.05
-
今、なぜ「名優」が生まれにくいか、(続2)
では、すべての演技者が持ってるべき「基礎」とは何でしょう。ここでもまた、わたしの勝手といわれるかも知れませんが。わたしは、コミュニケーションができる能力と、役の人物の心の動きについてゆける、精神の自由さだと思います。パフォーマーの行う表現が、鑑賞者に受け止められて初めて、パフォーミングアーツは成立します。それが受け入れられるか、受け入れられないかは別の話であって、ともかく相手まで演技者の表現が届かなければならない。それが演技者のコミュニケーション力です。コミュニケーションをとるためには、観客に台詞が聞こえる必要があります。だから、声を観客に届ける呼吸法を身につけていなければならない。それは腹筋式呼吸になります。肋骨を使う胸式呼吸では、ただ浅い呼吸、空気の量が少ない呼吸であるだけでなく、身体の深い部分、心に繋がる部分と斬り離れた、上辺だけの表現になるからです。声帯を的確に閉じて正しい音程の、きれいな声を出すこと、共鳴を巧く利用して、深水のある響きの豊かな声を出すことは、第二義です。観客に不愉快な感じを抱かせなければそれで良い。声が観客の側に向かって進んで行かねばなりません。演技者の口を出たらすぐに止まってしまう、あるいは演技者の中に留まってしまい、外に出て行かない声では、観客とコミュニケーションがとれません。観客のいる方向へ進まず、声が散らばってしまったり、観客のいない方向へ行ってしまう。つまり方向付けができていない声も、コミュニケーションを妨げます。ですから、観客の方向へ向かって声を進めて行く、プロジェクションがなければならない。これは、観客に話しかけるという意識をちゃんともっていればできるのですが、現代の若い人たちは、普段の生活から既にコミュニケーションを苦手としているせいか、巧く出来ない人が多いのです。役の人物と心をシンクロさせてゆく、共感し、その人の心の動きを自分の心で再現してゆく。つまり「役の人物になる」、正しくは「役の人物に近づく」ことも、すべての演劇ジャンルに共通して、認められることだと思います。その人物に入り込むことをせず、少し離れたところから役の人物を見てゆく、という演技法もあります。世阿弥の「離見の見」という言葉は、これに近いことを言うのかもしれません。しかしその人物の心を知らないで、人物を演じるということはおかしいです。その人が存在しなくなってしまいますから。だから、役の人物と、その芝居全体をしっかり理解することが必要なのは間違いないです。それができるために、読解力を高めなければなりません。自分が口にする台詞の意味や役割、役の人物の人となりを理解しないで行うのは、演技ではなく、ただ「ふりを踊っている」「音符を歌っている」ようなものだとわたしは思います。役の人物が感じている感情を自分も感じながら語ったり動いたりしているとき、正しい演技が出来ていると考えます。歌舞伎の演技でも、それは同じのようです。今回、発表したことに意見をもらって、いろいろと考えることがでてきました。わたしの演技に対する考えそものを変える事はさほどありませんが、若い人に指導するときに、これはいくつも考えられる演技法の一つであり、結局は自分が一番必要なものを見つけなければ鳴らないと言うことを、普段から言ってはいますが、もっと徹底して伝えておかないと、誤解されやすい状況になってきているなということを、考えさせられています。by 神澤和明週6で、2年書き続けました。しばらくペースを落として、とても書きたいことができたときに書くという、当たり前のペースにします。それでも毎週、何かは書きそうですが。
2019.08.03
-
今、なぜ「名優」が生まれにくいか。(続1)
このタイトルで、近現代戯曲研究会で口頭発表しました。発表の後、いろいろと賛成や反対の意見が出まして、なかなか活発な討論が行われました。わたしは「議論」が好きなこともあり、また曖昧だったり中途半端だったりする言い方を好まないので、かなり断定的な、極端な言い方をします。それによって反対意見や、またそれに対する反論を引っ張り出したいと思って、わざとそんな風に発言しています。 今回、反論が出て来たのは、簡単に言うと、わたしの考える「演技」は「新劇」のもので、それは古くなってしまっており、現代の若い演劇人にはあわないのではないか、ということでした。日常のままのような、自然な振る舞いが、現在の演劇においては重要とされているのではないか。映画やテレビの演技に対して否定的に語っているように感じられるが、そうした演技が今という時代に即しているのではないか、ということです。演技というものはジャンルにより、また作品により変化して良い、むしろ変化シテ行くものだとわたしも思っています。この場合の変化とは、"change" というよりむしろ "vary""variation" として現れてくるでしょう。芝居によって作り出される劇世界の気分は異なり、であれば、それが求める表現形式も変わらなければなりません。具体的に、能や狂言を演じるには、舞や謡を身につけ、リアルよりも象徴に近い表現を行わないと、あの世界は描けません。歌舞伎の時代物を演じるには、やはり大仰な台詞回しや仕草を伴わなくては、あの古風でエネルギッシュな気分は出せません。 同様に、現代の日常的で平凡な若者たち、自分の内にこもることが多く、外の人達に対して積極的に働きかけることのできない人達を表現するには、むしろ声は小さく、動きもなく、心の動きもほとんどないような人物表現をする方が適切かもしれません。 そういう芝居であれば、そうすれば良いのです。わたしはそれを否定していません。映画や映像の演技は舞台での演技とは異なると強調していますが、そしてわたしは舞台の演技を基礎的なものと考え、それを重視していますが、映画や映像における演技を否定したことはありません。学ぶ者が、自分でその違いを認識し、ちゃんと演じ分けられるようにと教えています。 ただ、わたしの言い方が断定的で、また舞台演技の重要性を強調しすぎるが故に、映像の世界に心を向けている人や、できるだけ自然に見える、現実での姿をそのまな表現しているように思われる演技を良しと考える人には、非常に反感を抱かせたのであろうと思っています。わたしは「演技の基礎」を教えています。それはおそらく、その人がどんな表現様式をもつ演劇ジャンルに進んだとしても、必要とされる事柄だと信じています。古典芸能も現代劇も、ミュージカルも台詞劇も、やはりそれを身につけていなければできないものを教えていると、自負しています。それが演技を教える教師の責任だからです。残念ながら日本には、演技の標準というものがありません。これができれば演技者としてどこでも通用する、出来なければ専門的な演技者としては認められない。そんなものがありません。そのために、自分で苦労して見つけようとしています。by 神澤和明
2019.08.02
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(10)
稽古場から外へ出てゆかせましょう。観察の練習をさせます。電車に乗って、その車両にいるすべての人を観察します。それぞれが違う人ですから、外見も、していることも違います。髪型、眼鏡のあるなし、ひげのあるなし、服装、座り方など、見るものはいっぱいあります。それぞれの人の、どこが違っているかを観察します。結構、面白いことです。 そしてその人がどんな人なのか、想像します。服装や持ち物が、ヒントになります。朝日新聞と競馬新聞を持っている人は当然違う生活様式をしています。単語帳を見ている学生と、漫画雑誌を見ている学生も違いますね。もっとも最近は、みんなスマホを見ています。観察をちゃんとしていると、人間をパターンで演じることがばからしくなります。頭で考えていた演じ方では、一人一人の違いが出せないことに気が付くはずです。 技術面の訓練です。腹式呼吸も滑舌も、それだけをやらせればたいていができます。一般の人でも腹式呼吸や早口言葉は言えるのですから、当たり前です。大切なのは、台詞を言う状況で、腹式呼吸ができているか、発音が明瞭になっているかです。ですから呼吸訓練も、基礎ができてからは、言葉を発しながら練習するのが良いでしょう。台詞を言える息でなければ、どんなに長く保とうと、意味はありません。 腹式呼吸がちゃんとできていて、声を出すポイント、つまりマスク共鳴をつけるのに最も適したところに声の「方向づけ」ができていれば、それだけで台詞は「何かある」ように聞こえます。ヴェテランの俳優が、初見でも台詞をそれらしくしゃべるのは、このためです。 しゃべりの基本が出来ていない人は、音を粒立てることができずに、つなげて発音してしまいます。「そうだろう」をちゃんと5つの音が聞こえるようにしゃべらず、「そーだろー」と1つか2つの音のようにしゃべってしまう。そうすると音が曖昧になるだけでなく、力もぬけ、息の支えもなくなります。最後の音までしっかり発音することで、台詞の最後まで気持ちを保持出来るのです。それをしないから、気持ちがすぐに抜けてしまう。役の人物で存在することができません。それは日常のしゃべり方を舞台にもってきてしまっているからです。俳優の仕事は、虚構の舞台の上で「実在」を生きることです。映画はカメラという現実を切り取る道具を使いますから、そこで現実そのままをやっていても良いです。しかし舞台ではそれをするのは正しくありません。 もう一つ、台詞や仕草を観客に向けてしっかり発信してゆくことを、身につけなければなりません。カメラやマイクを相手にするなら、何処に向けて行為をしようと、相手が寄ってきて受け止めてくれます。しかし舞台では、演技者は観客に向かって働きかけなければなりません。それができれば、映画では得られない、観客からの反応を受け取り、コミュニケーションが成立します。演劇はコミュニケーションの芸術です。自分がどう演じているかではなく、観客にどう受け止められているか。それを意識し、より良く受け止められるように努力を続けているのが優れた演技者です。それがいつも出来るようになっているのが、「名優」なのです。 現代の若者はコミュニケーション能力が落ちていると言われます。相手に面と向かって話すことを苦手とする、自分の意志や感情を表すことを照れる、相手の気持ちを推し量ることをせずに自分の思いや意見を一方的に押しつける。メールやラインの文章に慣れた人たちの悪い所です。舞台はアナログです。演技者を目指したのなら、真摯に努力を続けて、名優を目指してください。by 神澤和明
2019.08.01
-
9○「今、何故『名優』が生まれにくいか」(9)
わたしはそれで、彼ら一人一人に、みんなの前でテクストを演じてもらいます。そして見ていた人たちに、彼/彼女が語ったこと、やったことが理解出来たかをたずねます。このとき、見る人たちはテクストを見てはいけません。 多くの場合、何をしていたのか伝わっていません。わからないという答えが返ってきます。怒っているとか、悲しんでいるとかは分かった、と言う場合、では何故悲しんでいたのか、何を怒っていたのか、わかったかと尋ねます。たいてい、答えは返ってきません。理解の良い学生なら、これで自分は、自分が思っているようには「演じて」いなかったことに気づきます。 読解力を養成するには、脚本を繰り返し、じっくりと読むことなのですが、学生たちには難しいでしょう。というのは、彼らの台本の読み方は、台詞を覚えるために読んでいるので、意味や裏にあるその人の思いなどは、無視しているからです。台詞を覚えること、すらすら言えることが演技だと思っていますから、無理もない。そこで短いもの、詩が一番良いですね、それを勉強させます。朔太郎『竹』、中也『サーカス』、光太郎『レモン哀歌』をわたしはよく使います。まず、読ませます。ちゃんと読まない学生が多いです。自分の頭にある言葉、自分が言いやすい言葉にして読んでしまうからです。『サーカス』であれば、ブランコは「ゆあーん、ゆよーん、ゆやゆよん』と揺れるのに、「ゆやーん」と読む学生がよくいます。また、自分が普段口にしない言葉はうまくでてこないので、勝手に言葉を変えてしまう。それも意識をしてではなく、無意識に言葉を読み替えてしまうのです。この学生が、役の人物に溶け込んでゆけないのは当然です。 大切な事は、暗誦させることです。目で文字を追いかけると頭を使わないで済んでしまうので、覚えて自分の内から言葉が出てくるようにさせます。そして、一つ一つの言葉の意味、指示語は何をさしているか、なぜその言葉を使って、他の言葉を使わなかったのか、それが表しているイメージはどのようなものか、その言葉で作者は何を表現しようとしたのか。言葉で説明させます。言葉を読むのが下手な人は、自分の考えを言葉で表すことも下手です。だから、その訓練をさせます。 次に台本に進みます。一人台詞を言わせます。上手下手はどうでも良い。見るのは、声が前に出てきているか、観客に向かって発声しているかです。受け止める人がいてこそ、表現活動は成り立ちます。特に演劇は、コミュニケーションがなければ無意味です。それができるようになるまで。つまり声が聞こえるのではなく、内容が聞こえるまで、語らせます。次に二人台詞を試みさせます。この時、相手の台詞を聞いているか、それを理解しているかを確かめます。それができていなければ、そこには対話は存在しない。二人が独り言を言っているだけです。 台詞の働きがわかってきたら、台本全部を読ませます。そしてそれぞれの場面、それぞれの台詞について、それが表していること、演技者が表さなければならないことを、考えさせます。優れた演技者はすべからく、演出家の仕事ができなければいけません。すべての役の台詞や動きを理解してこそ、自分の台詞が言え、動くことができるのですから。by 神澤和明
2019.07.31
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」81)
俳優教育に携わるわたしとしましては、これからも「名優」がうまれてほしい。ですから、名優をめざすための、正しい演技ができるようになる勉強を、若い俳優志望者たちに行っています。それについて、少しだけお話をさせて下さい。 正しい演技者になるための修行は、精神面と技術面の両面を同時におこなってゆかなければなりません。ただし、技術面は外的なものであり、練習することによって伸びてゆきますし、その進歩が分かりやすい。対して精神面の方は、本人の性格及び知的潜在能力によりますので、伸び方に個人差が大きいですし、どれだけ伸びたかもわかりにくいです。精神、もしくは知力面からまず話します。 テレビドラマしか見ていない映像での演技と舞台での演技は異なるということを、しっかり理解させます。映像では、俳優の演技力よりも、その人の個性がより重視されます。ですから、映画やテレビの場合は、訓練していない人でも良いのです。その人らしさが画面から見えてくることが肝心です。観客も、その演技者が演じる役よりも、演技者その人を見たがっています。ささやくような小さな声しか出なくても、動きがガタガタしていても、マイクが拾い、カメラがうまく動くところだけを撮ってくれます。 アメリカの映画俳優が学んでいる「メソッド演技」は「スタニスラフスキーシステム」から派生したものです。作り物ではない、自然な感情表現を身につけるという点では同じですが、大きな違いがあります。「スタシス」ではその役の人物の自然な表現を目指しますが、メソッドではその演技者の自然を求めます。以前、メソッド演技について読んだとき、マリリン・モンローが泣く演技ができなくて、みんなが半日以上待った、そしてようやく泣くことができた、とありました。このとき泣いていたのはモンロー自身であって、彼女が演じる役ではなかったでしょう。テレビドラマやアニメで見ているものを「演技」だと思いこんでいる若い演技者は、かえって「作り物」の演技になってゆきます。 演技の経験がないとか、乏しいとか自分で言っている人ほど、型どおりの演技をしています。パターン演技です。テレビドラマによって、頭にすり込まれているようです。こんな場合、自分では自然にしていると信じているのでたちが悪い。彼らは記号として演技をします。老人であれば腰を曲げ、低い声でぼそぼそと話す。老人は本当にそうでしょうか。背が真っ直ぐに伸びてさっそうと歩く老人もいます。多くの老人が、硬くなった声帯で無理に声を出そうとするので、むしろ甲高く大きな声を出します。現実の人間を観察すれば分かることを、頭の中のイメージ、記号で、決めつけて表現しようとしています。だから、みんな同じような、嘘の演技をしています。 テレビで、外国人がしゃべっている場面に吹き替えの声をあてるとき、いつも同じしゃべり方をしているのが耳につきます。吹き替え口調とでもいいましょうか。声のトーンやしゃべり方が、決まり切ったものになっています。その人物になる必要がない、また練習する時間もないからでしょうけれど、それを見て、そうするものだと思いこむ若い人たちがいっぱいです。 難しいことですが、こうした既にもっている演技に対する間違ったバイアスを消去して行かねば、進歩することはできません。それも、自分でそれが良くないということに気づかさなければ、それを捨てさせることができません。by 神澤和明
2019.07.30
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(7)
俳優を目指す人間においては、「自己表現」が意味するものは、当然違ってこなければなりません。俳優は役を演じるのです。舞台におけるその人の言動は、その役の人物のものです。従って現れる反応・表現は、その役の人物から生まれるものでなくてはなりません。演技者本人のものではないのです。 たとえば「ハムレット」を演じているのであれば、劇中でハムレットが示す言動や感情の動きはハムレットとしてのものであるはずです。それを、演技者自身の「自己表現」が出てきては正しくありません。それであっても、演技者を通してハムレットが表現されている以上、当然、その演技者の「自己表現」がされないことはありえません。同じハムレットでも演じる人間によって別の人間像が舞台に現れるのは、このためです。 始めに言ったことの繰り返しになりますが、演技者の仕事は舞台の上に真実の世界を創り出すことであり、そこにおいて一人の人物として生きることです。 ただし、既に劇作家によってその世界のデザインは為されています。登場人物たちがどのような人達であるかも、示唆されています。ですから演技者はその「設計図」=台本を基にして世界と人間を創造して行かねばなりません。そのために台本を読み込み、理解し、自分の立場で研究して演技を構築して行きます。これが、今の若い演技者ができていないこと、或いは力をつくそうとしないことなのです。 自分が演じる人間がどんな人間であるのか。どんな性格で、どんな考えをもち、自分の周りの状況に対してどう対処して行くのか。そんなことを考えません。自分ならどうするか、自分はどう思っているか、それを基準にして書かれた台詞を言い、ト書きに指定された動作をしています。役を理解する、その人物に共感するということをしない。自分自身のままで、舞台に立っているのです。人物像の創造など、まったく考えていません。彼らは書いてあるから台詞を言うのであって、自分の心から言いたい、言わなければならないと思って口にしてはいません。ですから、演技者と台詞や仕草が、まったく乖離しています。彼らがしていることは演技ではなく、「ふり」や「真似」にすぎません。「悲しんでいるふり」「怒っている真似」をしています。それが演技だと信じているからです。しかし、自分の感情を「ふり」や「まね」で表して生きている人間はいません。ですから彼らは、けっして人間を描き出すことができないのです。 なぜそうなのか、と考えますと、彼らが「読解力」を養ってきていない、と言う結論がひとつでてきます。つまり、読んで考えるということをしていないのではなく、読めないのです。学生に詩や台詞といったテクストを読ませ、それについてたずねます。今の「それ」は何のことですか、「そんなことがあった」とはどんなことがあったのですか。これにちゃんと答えることができません。大学生なのに。「今言った台詞の内容はどういうことですか」。答えられません。「その言葉はどういう意味ですか」。わかりません、と平気で言います。意味がわからないで言葉を発するということは、わたしなどには信じられないことですが、今の俳優志望の学生は平気です。彼らは、言葉とは思考や感情を相手に伝えるもの、という意識がないのです。言葉とは記号であり、それをいかにももっともらしく、格好良く口にすることが台詞を言うことだ。いかにも悲しんでいるとか、うれしがっているとすぐわかるように、そのサインをだすことが演技だ。そんな風に考えているとしか思えません。ですから、名優など生まれっこないのです。by 神澤和明
2019.07.29
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(6)
しかし、名優が生まれにくくなっている理由の第一が、やはり演技者の側にあることは否定できません。舞台で上演されているのは現代劇ばかりではありません。古典劇や近代劇も同じく数多く上演されています。シェイクスピア劇などは、現代の劇場でも重要なレパートリーを為しています。それなのに名優が出にくくなった、舞台で確固たる人間を造型できなくなったのであれば、それはやはり演技者の問題が大きいと言わざるを得ません。そして、既に「名優」と呼ばれる演技者が少なくなっているだけでなく、将来に向けて「名優」が現れてくる可能性が非常に小さくなってきている。そのことを、俳優教育を行っている現場人として、危惧しています。演技者を志す人たちの「演技」についての考え・イメージがかなり奇妙なものになっており、従って演技訓練の仕方が間違ったものになってきているのです。 今、大学の演劇科にくる学生たちに、わたしはヴォイストレーニングのテクストとして「詩」や「一人台詞」をまず与えて、彼/彼女たちに語らせてみます。すると、彼らの思っている「演技」というものが見えてきます。 たいていの学生は、ボソボソとつぶやくような声を出します。自分の口を出たらすぐに進行を止めてしまう声です。抑揚のない、アクセントがつかない平板なしゃべりです。意識しているのか無意識かはわかりませんが、気取りがあります。言葉を少し強めては引き、変な節付けをします。ちょっと器用な学生は、言葉の表面の意味にあわせて、嬉しそうに言ったり悲しそうに言ったり、自分はこんな気持ちにあるんですよということを宣伝するようにしゃべります。ほとんどの学生が早口で、ペラペラと流ちょうにしゃべろうとします。これは、滑舌がとても重要なことだと思っているためでしょう。だから、つまったり、言い損なったりすると、必ずもう一度言い直さないと、先に進めません。日常の生活で、言葉につまったり、言い損なったりすることはありえないと思っているのでしょうか。 彼らは、演技とは書かれた台詞を格好良くしゃべること、だと思っているようです。その人物の感情を、単純な「記号」のように表すことが巧みであるのが、巧い演技だと思っています。そして、「自己表現」が演技の第一目標だと信じています。間違いです。 わたしは学校教師を長くやってきましたので、学校における「演劇教育」の目的を、それぞれの生徒の「自己表現」におくことは良しとします。特に日本の青少年は自己主張ができない、自己に対して肯定的になりにくいという問題を持っていますから、芸術活動によって「自己表現」の力をつけさせることは大切です。「自己表現」の訓練を通じて「自己認識」を行い、「自己発展」につなげてゆく。それは望ましい「人格発展」のための教育です。心の解放を行い、他者とのコミュニケーション力を向上させます。自閉気味のある若者には、効果のある治療法でもあります。しかしそれは、学校教育、あるいは生涯学習においてのことです。一般の青少年を対象にしてのことです。 イムプロビゼーションやシアターゲームの手法を使って、若い人たちに「自己表現」のレッスンがよく行われます。わたしも指導したことがあります。一つの刺激・状況設定に対して、自発的に反応させる。それがその人自身を表す、自己表現だというわけです。これは間違いではありません。最近ではこういうレッスンになれてしまって、こう反応すれば評価されるとわかっていて、ちっとも即興的に反応しない人が増えていますが。これに慣れてしまうと、いつもその人自身、自分自身として反応することが正しいと思いこんでしまいます。by 神澤和明
2019.07.27
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(5)
さらに、現在の若い劇作家たちは自分たちの世界に留まる傾向があり、広く人間を観察することを怠っています。ですから登場する人物たちはいつも同じように定型的な人間で、そうでなければ極端な変人たち、ということが多いようです。書く方も演じる方も苦労がいらなくて楽ですが、そこから印象に残る「演劇的人格」は生まれてきません。 演出家は劇作家と演技者の間にいて、劇作家が書いた青写真としての脚本を、立体的に舞台に構築してゆく手助けをする存在だと、わたしは考えています。舞台で現実化されるものを観客に受け止めやすい、理解し易い形で表現するために苦労するのが仕事だと考えています。作家と役者が中心で、演出家はその後ろに隠れるべき存在だと思っています。そもそも演出家にしろ指揮者にしろ、演劇の世界では最も後に生まれてきた役職なのですから。ところがいつからか、演出家が表に出てくる、いや出過ぎる傾向が生まれてきました。他の人が思いつかないような、奇抜なアイディアで観客を驚かせるのが、優れた演出であるという、誤解が生じました。そうなると、芝居の必然と関係なく、演出家の思いつきで舞台が飾られて行きます。装置や音響や照明が幅を利かし、演技者の演技を覆って行きます。下手な演技者にとってはありがたいですが、演技力で観客の心を動かそうとしても、努力は消されて行きます。 演出家が自分を見せようとして、俳優をそのための道具としている舞台では、演技者の力は十分に発揮できません。従って、名優も生まれません。 今の若手劇団の芝居ではたいてい、作者が演出者を兼ねています。そうなると、作者の頭の中にあるものを舞台に出すだけですから、人間性をもたない役の人物ばかりがうろうろしていても、誰も気にしません。若者に人気を得た多くの若手劇団が解散した後、劇団を主宰していた作家兼演出家だけが残り、役者たちは多くが消えていったのは、そうした芝居が演技者の力を伸ばさなかったことを示しています。 演技者のことは後にまわして、先に批評家の問題に触れます。わたし自身を含めての問題です。そもそも日本には、演劇批評というしっかりしたジャンルは根付いていないと思います。勿論、何人かの優れた演劇評論家はいらっしゃいましたが、ジャンルとして見れば非常に寒い状況です。 それは批評と現場とか乖離しているからです。欧米の演劇評論家には権威があります。彼らが褒めた舞台はロングラン、けなした舞台はすぐに公演打ちきりになります。劇場が中心となり、ロングランを基本とする上演形態を取っていますから、これは重要なことです。 日本の場合、商業演劇以外はロングランの上演方式を、ほとんどとっていません。たいてい2,3日で上演が終わります。ですから、批評がその公演に観客を呼ぶということは、期待できません。演劇評論家の多くは、新聞記者や演劇関係の雑誌の記者です。そして商業演劇はこうした人達を公演に「招待」し、普段から色々と繋がりを作っています。ですから、新聞に載るこうした公演についての批評は、観客に来てもらいたい興業会社の意向を汲んで、褒めるものばかりになります。新聞の歌舞伎評を見れば、おわかりになります。 そして小劇場関係の批評の場合は、批評家が自分の贔屓する劇団、作家をもっており、いつもその人や劇団について書きます。当然、良い様に書きます。そして他の劇団については、ほぼ書かない、というより、観に行きません。それでも新聞などは、そうした若手劇団について書いた記事が新しい、芸術的だと誤解して、喜んで載せます。新聞の劇評は若手劇団の小さな公演まで載せているのに、古くから活動を続けているいわゆる「新劇団」の公演にめったにふれていないことを、皆さんはどうお考えになりますか。by 神澤和明
2019.07.26
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(4)
その原因は、劇作家、演出家、演技者、そして批評家に、それぞれあると思います。 劇作家は、作品の中に存在官をもつ人物を描き出せなくなった。 演出家は、自分を目立たせようと突飛な技法を好むようになった。 演技者は、舞台演技の基礎を身につけず、映像演技を正しいと思い込み、またあやまった「自己表現」に走るようになった。 批評家は、正しい鑑賞眼をもたず、自分の好みの劇団ばかりをほめるようになった。 ということだと考えます。 名優がその力を発揮するためには、彼が創造するべき人間が戯曲に登場していなければなりません。古典劇の時代には、シェイクスピア劇に見るように、独特かつ強烈な主人公たちが登場し、各時代の名優たちがそれぞれに優れた人物造型をしてきました。近代劇においても、ノラで『人形の家』を、ラネースカヤ夫人で『桜の園』を、ウィリー・ローマンで『セールスマンの死』を、ブランチ・デュボアで『欲望という名の電車』を思い浮かべます。その登場人物たちによって芝居を語ることができました。 では、現在発表されている戯曲、特に日本の創作劇に、そのような登場人物が存在しているでしょうか。問いかけずにはいられません。わたしとしては、そうした人物たちは随分と数を減らした、舞台から姿を消しつつあるように思っています。 その理由は、現在に活躍している劇作家たち、若い(既に40代50代に入っている人達が大勢ですが)作家たちが人間を描くことにほとんど関心を示さないからではないでしょうか。生きている存在、個人としての存在官をもつ人間像を作り出す力が弱いのではないでしょうか。 特に若い世代の劇作家の作品において、人生を背景としてもたない、作者の頭の中だけでつくり上げられる世界のピースとして、決まり切った思考をし、当たり障りのない正論を語り、すべてを他人事のようにうけとめて行動している。こういう登場人物ばかりのように、わたしには思われます。 それはあるいは、社会の思潮が、個人よりも社会に、人間よりも思想や主義に重点を置くようになっているからでしょう。一個の人間は無力で、社会構造の中に組み込まれるしかないのです。古代ギリシア悲劇の場合、人間は神の定めた宿命の前に無力でした。しかしその中で、オイディプスやアンティゴネは確固たるものでした。人間復興を目指したルネサンス期には、シェイクスピア劇の主人公たちは、自分たちより大きな運命の力に対して、挑んで行きました。近代劇においては、主人公たちは社会の決まり事、保守的な思想に対して、それは変だと抗議し、改変しようとしました。今はどうでしょう。少なくとも日本の若い劇作家が描く登場人物たちはどうでしょう。日本社会全体の傾向に合わせて、どうせ変えることはできないのだ、現状を維持しているのが一番だ、それも自分が責任をもって行うのは真っ平で、仕事は誰かにおしつけて、それが巧く行かない場合、文句を言えば気が晴れる。そんなところではないでしょうか。 戯曲は社会を映し出します。であれば、戯曲が確固たる人間像を描き出さなくなってきた理由は、社会にそうした人間が出てこなくなったからだとも、言えるかも知れません。戯曲の世界から自覚的で強烈な意志をもつ、魅力的な登場人物が姿を見せなくなったのは、こうした社会的風潮を劇作家たちが受けているからではないかと思います。by 神澤和明
2019.07.25
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(3)
実際、技術の未熟な「下手な役者」を「名優」と呼ぶことはできません。この場合の「名」という修飾には、「他の者が目指すべき優れた」という意味が含まれていると思います。技量の乏しい演技者を名優と呼ぶことは、まずないでしょう。 では「良い役者」というのはどうでしょうか。技量が不足していても「良い役者」と呼んで良い演技者はかなりいます。しゃべりが滑らかでないとか、役の変化があまり見られない人でも、「良い役者」と呼ばれます。大滝秀治さんなんか、そうかなと思います。「うまい」とは言われないが、「良い」と言われる演技者は、映画やテレビの世界に多く登場しているように思います。典型は高倉健さんでしょうか。「スター」と呼ばれる人の多くは、この傾向がありそうです。舞台人には「スター」はあまりいませんね。おそらく「松井須磨子」が最初の舞台の大スターだと思いますが、彼女の演技がうまかった、という評は聞きません。 一方で、「あの人はうまいけれども、いやな演技をする」とか、「演技はうまいけれど、好きじゃない」と言われる演技者も多くいます。いわゆる「くさい芝居」をする人は、多くこんな風に言われます。こういう演技者を「名優」と呼ぶ事はためらわれます。 そうすると、「うまい役者」でなおかつ「良い役者」ということが、「名優」の条件といえるように思われてきます。つまり、高い演技の技術を持ち、かつ観客がその演技者(の演技)にすなおに共感できる役者が、「名優」と呼ばれて良いということでしょうか。 では「巧い役者」であり、かつ「良い役者」である、つまり技術と観客からの共感という、別の概念のものを同時にもつということはどういうことでしょう。ここで、「演技」とは何かを考える必要があると思います。 わたしの結論を先に述べますと、「演技」とは舞台の上で作り出される劇世界の中で、一人の確固たる人間像を、確かに描き出すことです。その人物を、人間として生きさせることです。 朗々と名調子を聞かせるとか、運動能力が高くて身のこなしがしなやかであるとか、そうしたことは望ましい技術ではありますが、それができるから名優であるとは決して言えません。 確かに、古典劇の時代には、こうした技術は名優の条件、というよりも俳優のスタンダードな技量でした。イギリスの俳優であれば、シェイクスピア劇の台詞がしゃべりこなせること、フランスの俳優であれば、詩をしっかりと語れることは、俳優と認められるための第一条件でした。今もそうでしょう。 しかし名優であるためには、そうした技術の上に、舞台の上で生きられること、明確な人間像を描き出す力をもっていなければなりません。それが英雄であろうと、普通の人間であろうと、演劇的存在として、人々が観るに足る人物としての内容を持っていなければなりません。舞台にただ出ているのではなく、存在していなければならない。その人物に現実性が伴わなければならないのです。頭の中で作られたとしか見えない抽象的な存在ではなく、具体的な人間です。 すると、「名優」がうまれなくなった理由は、舞台でそうした「人間」を描き出すことが難しくなった、その能力が無くなってきた、ということになりそうです。by 神澤和明
2019.07.24
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(2)
歌舞伎に、「菊吉じじい」という言葉があります。六代目菊五郎や初代吉右衛門を見ていた老人たちが、今の役者は下手だといって文句を言う。それを揶揄した言葉です。わたしが今こう感じているのも、そのたぐいなのかもしれません。でも、そうでないかもしれない。それを確かめようと思います。非情に個人的な見解になると思います。あとで、皆さんからご意見がいただけることを期待して、発言をさせていただきます。 そもそも「名優」とはどんな演技者をさすのでしょうか。「名優」の定義をしなければなりません。これは人によっていろいろと違ってくるかもしれません。実際、私が教えている若い人たちに、どんな演技者を尊敬しますか、目指しますかと尋ねますと、「ムロツヨシ」だとか「神谷明」だとか、テレビでよく顔を見る人とか、声優の方の名前ばかりがでてきます。関西芸術座の養成所ですらそうです。自分たちが目指しているはずの劇団の俳優の名前がでてきません。見ていないといえばそれまでですが、こうして名前の挙がる人たちの「演技」が、若い人たちには「良い演技」とみられていることがわかります。この人たちが「名優」でないと言うのではありませんが、悪いですが、わたしの定義には入ってきません。 演技者に対する誉め言葉として、「うまい役者」と「良い役者」というのがよく使われます。これについて、考えてみます。 「うまい役者」という表現は、「技術」についての評価です。反対語として「へたな役者」という言葉があります。古典芸能、たとえば能楽の場合は、舞や謡の技量に関してはっきりと差がでますので、うまい/へた、を言うのは容易です。技量がある段階まで来ないと、披くことが許されない曲があります。技声楽家や舞踊家の場合も、声域や声量、声の響き、音程やリズムの確かさで、またジャンプの高さ、脚の上りや手足の伸び具合、回転の速さや正確さなどで、その技術的な差ははっきりと見えてきます。これは素人にでもわかることが多いです。 演劇の場合は、セリフの明晰さやせりふ回しの快さ、動きに無駄がなく美しいこと、表現に感情がこもっていることなどが、うまいといわれる理由となります。言葉がたどたどしかったり、動きがぎくしゃくしていたり、台詞が棒読みだったりする役者は、うまいとは評価されません。うまくない役者がダメな役者だとは言っていませんので、ご注意を。 一方、「良い役者」という言い方は、技術と切り離されたものです。反対概念は「悪い役者」ではなく、「良い役者ではない」です。「良い/悪い」は何かの基準をもとにして判断されるものではありません。わたしたちが「良い役者」というとき、その役者は「見ていると何となくその人物が見えてくる」「演技にいやな感じがなく、何となく共感できる」役者だといえます。「うまい役者」の場合は技術での判断ですので、客観的な評価といえます。対して「良い役者」というのは見る人による判断になってきますので、主観的な評価であり、不安定なものだと考えられます。しかし不思議なもので、多くの人の「良い役者」という判断はかなり共通しているようです。「うまい役者」と「良い役者」が別の概念による評価であり、それぞれが演技者の価値を測る言葉としてあるするなら、「名優」は「うまい役者」と「良い役者」の二つの条件をそろえた演技者ということになるでしょうか。by 神澤和明
2019.07.23
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(1)
演劇学会の近現代戯曲部会で、何か発表することになりました。それで「今、何故『名優』が生まれにくいか」と題して、俳優教育の現場からの意見を述べることにしました。40分程、話す予定ですが、その下原稿として、半分ほどの長さで書いてみます。 わたしは今、演出家及び演劇評論家として活動を行っています。本来は演出家です。演出家としてのわたしは、舞台を演出する以上に、演技者を教育する仕事を熱心に行っています。それは若い人たちを対象とする、基礎的な「演技指導」です。特に、台詞術にこだわって指導しています。私自身は役者ではありません。狂言役者として40年ほど活動してきましたが、現代劇は演出がもっぱらです。ですからわたしの演技指導は、役者としての経験からではなく、芝居を研究し、舞台を見続け考え続けて考えだした理論や実践に基づいて行っています。 市民劇団のアマチュアから、大学の演劇科の学生や劇団の養成所、プロ劇団の若手まで教えています。指導をしていて大変に困るのが、若い人たちが、プロをのぞいて、舞台をほとんど観ていないということです。そのために舞台の演技というものを知らない、まったくイメージを持っていません。かわりにテレビドラマやアニメを見て、演技とはああいう風にするものだと思いこんでしまっています。他のものを知らないのだから、仕方ない。海を見たことがない人が、大きな湖を見れば海だと思う。星空を見たことがない人は、プラネタリウムの映像を、星空はこの通りでなければならないと信じ込む。それと同じです。舞台における表現、演劇という一つの芸術を作りあげてゆくための演技というものに、まったく触れたことがない、考えた事もないのです。 演劇に限らず、芸術の修行方法は基本的に「模倣」です。先人が培ってきたこと、発展させてきたことを学びながら、新しいものを生み出す努力をしてゆきます。音楽でも美術でも、文学でもそうです。それまでに作り出された作品を鑑賞し、研究して、自分の作品を作りだしてゆく。芸術を志す者が、先行する作品を全く知らなくて良いということはありえません。パフォーミングアーツでは特にそうです。演奏家も舞踊手も俳優も、優れた先人を見習って勉強してきます。 ですから当然、わたしは学生たちに、できるだけ舞台をみなさいと言います。わたし自身がそうして演技というものを考えてきました。ところが最近、学生から「誰の演技を見たら良いのですか」と尋ねられ、ハタと困りました。いないのです。誰の演技を見たら良いか、薦めることができません。舞台を見なさいと言っていながら、見るべき俳優を名指しできない。 わたしが芝居を勉強し始めたころは、そんなことはありませんでした。まず、民芸の滝沢修さんを見習いました。アクセント、発音が明晰で、引き付けられる台詞回し、役の人物を彷彿とさせる人物造形、演技の教科書としてみていました。千田是也さんはもう、演出家として印象づけられていましたが、小沢栄太郎さん、東野英次郎さん、三津田健さん、宮口精二さん、芥川比呂志さん、宇野重吉さん、女優では山本安英さん、杉村春子さん、長岡照子さん、岸輝子さん、若くなって仲代達矢さん、平幹二郎さんら、いくらでもあげられます。でも今、そうした人たちと比べて、この人たちを見習いなさい、演技を勉強するサンプルにしなさいと薦められる人たちが、いないといわないまでも、本当に少ないのです。 「名優」と呼ぶに値する演技者が、どんどん少なくなっている。これはなぜなのか、という疑問がわいたのです。by 神澤和明
2019.07.22
-
『広くてすてきな宇宙じゃないか』(2)
ブラッドベリ作品の「おばあちゃん」は、確かにおばあちゃんらしい性格付けになっています。3人の子どもたちそれぞれに合わせて、違う顔と対応の仕方を見せます。わざと間違って名前を呼んで、相手の意識を自分の方に引っ張ったり、優しく言い聞かせたりして、相手を納得させてゆきます。穏やかで経験を積んだ先達のようです。子ども達に、人生を教える存在とすら言えそうです。『広くて素敵な宇宙じゃないか』のおばあちゃんは、おばあちゃん然としていません。言葉より行動で、子どもたちを強引に、自分の方へひっぱってきます。行動は素早く、足は速く、力は強い。スーパーマン型のアンドロイドです。話し聞かせるおばあちゃんでは、若い人向けの舞台には向かないという判断があるでしょう。おばあちゃんの「威力」を、後半のSF活劇で見せるためにも、こういう設定が必要です。そうなるとこのおばあちゃんは、老人でなくても良さそうです。芝居の設定では「おばあちゃん」ですが、表現する上ではおばさんでも、おねえさんでも良いでしょう。わたしは「シアター生駒」では20代の女性に、「いかるが」では男性におばあちゃんを振りました。そして、老人で演じなくて良い、元気よく動いて欲しいと注文しました。おばあちゃんが登場するときに、傘と鞄を持っている。明らかに「メリー・ポピンズ」がイメージされています。おばあちゃんの「超能力」は、メリーがもっている「魔法」に近いものです。後半の活劇部分で、おばあちゃんの「敵」になるのは、やはりアンドロイドのヒジカタです。彼は介護の仕事をしていたときに、自分が担当する人物が死んでしまうのを阻止できず、それがトラウマになってしまった。アンドロイドは人間を救うことができない。アンドロイドは無力だ。だから自分が死んでも、それが人間を助けるためになるなら、かまわない。こう考えて彼は、末妹・クリコの願いをうけて、東京中の発電所を破壊して、太陽エネルギーで生きているおばあちゃんたちアンドロイドを停止させようとします。クリコの家庭内の問題を、アンドロイド全員に対する、東京全体に影響する事件にするのは、とてもおかしいのですが、そこは目をつぶります。ヒジカタの理屈は成り立たないのですが、彼の心情は受け止められる。ですから、彼を「悪人」にせず、悩める若者として演じるべきでしょう。この芝居のクライマックスは、発電機が爆発し、クリコをかばって倒れたおばあちゃんにクリコが近づく。おばあちゃんは、クリコのために自分は死なない、クリコをひとりぼっちにしないと約束して、いっぱいの星が輝く夜空をともに見上げる場面です。ここまでをとどこおりなく薦められれば、自然に感動が生まれてきます。ただ、まだ後に場面が続きますので、あまり盛り上げすぎるのもいけません。by 神澤和明
2019.07.20
-
『広くてすてきな宇宙じゃないか』(1)
わたしはいわゆる「小劇場系」「若手劇団系」の芝居は、肌合いが違う感じがして、演出しません。ですが、この作品はなぜか気に入って上演しています。「シアター生駒」のワークショップと、「劇団いかるが」の小公演、あわせて二回、上演しました。成井豊作のこの作品は、『銀河旋律』とともに、劇団の「ハーフタイムシアター」として企画されました。45分で上演できる芝居、という意味です。ともにSF仕立てで、『銀河旋律』はタイムスリップ『広くてすてきな宇宙じゃないか』はアンドロイドが登場します。『銀河旋律』は、国語教師であった作者らしく、和歌がプロットの中で重要な働きをしています。『広くてすてきな宇宙じゃないか』はその続編という形で、主要な登場人物に重なりがありますが、まったく別のプロットをもちます。『広くて素敵な宇宙じゃないか』は、アメリカのファンタジーSFの大作家である、レイ・ブラッドベリの短編、『歌おう、感電するほどの喜びを』(原題は"I sing the body electric!")を下敷きにしています。母親を亡くした子ども達の所に万能アンドロイドのおばあちゃんがやってくる。末の娘はおばあちゃんに反感をもつ、それは「いつまでも一緒にいる」と約束したのに、自分を残して母親は死んでしまった、おばあちゃんもやっぱり自分を残して居なくなってしまうのではないかと不安だから。やがて老人になった子どもたちは、孤独な生活の中で、もう一度「おばあちゃん」を必要として、来て欲しいと強く願う。原作から、こうした設定を借りています。しかし芝居の進行は、SFアクション活劇になっています。そして、アンドロイドは人間と本当に共感し合えるのかという問いかけが、なされます。非常に分かりやすく、夢があり、おかしく、テンポ良く運ばれるので、観客に喜ばれる芝居です。難しい演技もいりません。ただ、舞台を素早く動き回れる体力が必要です。アンドロイドのおばあちゃんというキャラクターが、なかなかに生きています。それ以外の登場人物たちも、演技次第でかなり魅力的になります。発展途上の演技者にとって、よい勉強になる芝居だと思い、取り上げました。「シアター生駒」での上演は、若い人たちを集めるという目的でした。思い入れをせずに、事件の展開を主に、どんどん芝居を進行してゆく、という演出をしました。発表場所が、大きな会議室のような場所で、装置や照明効果が使えないと分かっていましたので、主に無対称演技で場面を表し、出入りを素早くすることで、場面転換を印象づけました。移動式のパネルを何枚も使って背景とし、これを動かしてドアやエレベーターを表現しました。最後の場面でおばあちゃんが空に跳び上がります。しかし、会場の条件として、人間をつり上げることはできません。そこで、舞台奥にいるおばあちゃんが、跳び上がるタイミングで、すっとパネルを閉じておばあちゃんを隠し、彼女が持っている傘が上に上がる。その時に、舞台前で観客に向かっている末娘(クリコ)が、ずっと目を上げて行く、という表現をとってみました。by 神澤和明
2019.07.19
-
『思い出を売る男』(10)
ここから重要な情報が語られます。「戦争前のこたあ、俺は一切覚えてねえ」「どうしてです」「俺にも皆目わからねえのよ。気がついた時にゃあ、俺は病院のベッドの上に寝てたんだ」「シナだったんでしょ?」「シナだった。俺はそん時生まれたようなもんよ」ジョオは記憶喪失になっていたのです。男は、思いつきました。そして心を決めて、「ぼく、親分に是非お話したいことがあるんです」男の中で、街の女と黒マスクのジョオが結び来ました。花売娘はまだのようです。言いかけたところで、呼び子がけたたましく鳴ります。男は逃げ道を教え、ジョオはすばやく逃げ出します。警官が来て、「黒マスクをした顔のひん曲がって男を見かけなかったか」と訪ねます。男は、知りませんと答えます。警官は、ジョオが逃げていった方向へ追って行きます。男は壁を見つめながら、『巴里の屋根の下』を吹き始めます。灰色の壁に、待ちの女とジョオと花売娘の姿が次第に浮かび上がってきます。大事なところです。男の心の中で、三人が結びつきます。ここはシルエットで示しました。夫婦と女の子の幸せそうな姿。ホッとする情景です。と、突然、銃声が一発。続いて二発。男はギクリとして凍りつきます。灰色の壁に浮かんでいたシルエットが次第に消えて行きます。期待されたハッピーエンディングはきません。希望はこわされてしまいました。ここは、場面にオルゴールの淋しく優しい音をかぶせて、ゆっくりと照明を落とします。新劇人としては、この作品は非常にセンチメンタルで甘いです。ヴォードビルと名付けたのは納得できます。でも、心の琴線にしっかりと触れてきます。戦争に敗れ、人々が一様に絶望におちたとき。美しい過去はまったく消滅してしまい、将来に夢を持てないと思った時代。今日を生き、明日に希望をもつために、こんな「おとぎ話」が求められた、必要だったということが、分かる気がします。頭でなく心で作るお話です。幸せでない人達を慰め励ます作品です。励まされる火との中に、作者もいたでしょう。この作品は、今の目から古くさいですけれど、とても素敵な作品です。上演に向けての稽古中、わたしはとても快かったです。上演した劇団の人たちも、とても気に入っていました。時々で良いから、上演されてほしいと思います。劇団四季が、浅利慶太氏の縁で、時々上演しています。by 神澤和明
2019.07.18
-
『思い出を売る男』(9)
乞食は、今送っている、気楽な人生の話をします。そして、自分くらい幸福な人間はいないと思っていると言います。自由ですから。自分をみじめだと思うことはありません。「他人から恵んでもらうばかりで、気が引ける様なことはないかい」と問われ、「ないね。……初めはあったがね。考えてみりゃぁつまらんことさ。それが娑婆の人間のつまらん了見さ」世の中には金も食い物も有り余って、何の苦労もしないでいる奴もいる。同じその世の中に、金持ちを羨みながら、無理にいらないという顔をしている者たちがいる。金持ちと貧乏人がいがみ合ってる、憎しみあっている。だもので、金持ちは意地をはって肥え太り、貧乏人はやせ我慢して細くなって行く。これは世の中の大問題だ。乞食の老人は言います。「呉れ」って言えば良いのだ。素直に言えば、それで決着がつくのに。そこまで自分たちが落ちて仕舞っていることを、日本人はなかなか認めませんでした。ですから、終戦からの復興も、結局、いびつなものになったのでしょう。乞食もインテリではありません。世捨て人というのでもないでしょう。しかし、達観した人物、人生の実用哲学とでも言うものを、会得しています。突然、呼び子の声。けたたましい騒ぎが聞こえ、与太者たちが舞台を走りすぎます。「親方が野良犬のトムを殺したんだ! 手が回ってる! 逃げろ!」親方というのは黒マスクのジョオです。巻き添えをくってはいけません。乞食は男に逃げようと指しますが、男はその場に留まります。自分とは違う世界の出来事と、とらえているようです。そして『自由を我らに』のメロディを吹いています。そこへ外套に身をくるんだ黒マスクのジョオが、音もなく現れます。そして男に近づいて、ピストルを突きつけて言います。「おい、脱ぎな。……黒マスクのジョオよ。脱ぎな。俺に顔を立てる気があんなら、そいつを脱ぎなよ。上衣と帽子だ」警官が追ってくるので、変装してやり過ごそうというのです。警官が近づきます。ジョオは男からサクソフォンを取り上げると、自分で吹き始めます。男に歌えと命じます。曲は『巴里の屋根の下』です。人々の声が行き過ぎます。もう大丈夫なようです。黒マスクのジョオは礼を言って、はずしていたマスクをつけます。目立ちますという男に、(火傷した)顔があんまりみっともないんでな、と言って、マスクをつけます。「親分はサクソフォンが巧いんですねえ」「そうかい? 巧く吹いたかい」「前にやったことないですか?」「やった覚えないね」「不思議だなあ、あの吹き方はとても素人じゃ出来ませんよ」「命が惜しくて夢中でやったせいかな?」by 神澤和明
2019.07.17
-
『思い出を売る男』(8)
G.I.は男がサクソフォンを持っているのを見て、曲をリクエストします。フォスターの『金髪のジェニー』です。男はよくわからなくて、困ってしまいます。するとG.I.の青年は、朗々とした声で歌い出します。知っている曲なので、男もサクソフォンで伴奏します。 灰色の壁に、田舎の風景と、金髪のアメリカ娘が浮かび上がります。わたしは舞台両側に、アメリカの田舎の人々をイメージしたコーラスを出して、歌わせました。金髪の娘はG.I.が故郷に残してきた恋人なのでしょう。二人はむつまじく、幸せそうに言葉を交わします。「変わりはないかい?」「ないわ、あなたは?」「君に会えて幸せだ」「私もよ」「いつも君の事を思っている」「おやすみなさい」街の女と比べて、何と平和で幸せなカップルでしょう。恋なのでしょう。音楽が終わり、幻影も消えます。G.I.の青年は、うっとりとして、恋人の姿が消えていった灰色の壁を見つめて居ます。そして思い出を壊されたくないかのように、男の手に300円を握らせ、口笛を吹きながら去って行きます。男は、恥ずかしそうに、しかし感謝にみちた面持ちで見送ります。敵であった国の軍人に、多くの金を「恵まれた」ことへの抵抗と、同じ若者として共感した、恋する者の幸せをかみしめます。そしてサクソフォンで、『金髪のジェニー』を低く演奏します。陽気な中老の乞食が、よぼよぼの犬を連れて現れます。男の演奏に聴き惚れます。男は乞食(差別用語ですが)に気がつきます。「音楽好きかい?」「いいね。今度あ、別な奴をひとつ吹いてみねえ」「金を出さなきゃ駄目だよ。こっちだって商売だもの」「なんぼだい?」「百円」「お安いもんでねえか」乞食はボロの間から、10円札の札束を出して、百円を払います。男はあきれます。「随分もってるんだねえ」「もらう一方で、費うこたあ滅多にねえんでね」乞食は三日やったらやめられない、と言いますが、この時代でも、やはりそうだったらしい。恥を恐れる人は、食べられなくなっても、乞食だけはしたくないと、飢え死にすることもあったそうですが、広告屋が言ったように、恥をかけばいきてゆけたようです。この乞食もこの「仕事」で、一財産つくったようです。で、足を洗って、女房をもち、家を一軒借りて、勤めにも出た。ところが、一旦、束縛を離れた生活を送った彼には、娑婆の生活は不自由でした。こりごりしたのですが、妻はそれでも、乞食だけはしたくないとがんばって、挙げ句の果てにしんでしまいました。女房を殺したのは娑婆の生活だと、彼は恨んでいます。それで乞食に逆戻りして、今は犬と「二人」暮らしです。彼には、達観した明るさがあります。陽気な曲をリクエストされて、男は『自由を我らに』を演奏します。身体が軽くなるような曲調に、乞食は満足します。題名も気に入ったようです。by 神澤和明
2019.07.16
-
『思い出を売る男』(7)
男がサクソフォンを口にあてて、『巴里の屋根の下』を吹き始めます。「勝ち誇ったように」とト書きがされていますが、得意げにはならないようにしたいです。灰色の壁が透き通って、逆光線によるシルエットで、若い男女が踊る姿が浮かび上がります。紗膜で壁を作れば良いのですが、できなかったので、舞台の上をマスクをつけた男女が踊って通り過ぎる演出にしました。この間、男と街の女は不動のままたたずんでいます。ト書きだと、通行人が立ち止まって二人を見たりするとあります。思い出は二人にしか見えない、ということを示すのでしょう。わたしは通行人は省略しました。演奏の終わりで、幻影は消えます。女は涙をぬぐって、「よかったわ」と言います。幸せだった昔と比べて、今の自分が惨めなので、涙が浮かんだものです。女は恋人と結婚しました。しかし間もなく夫は、戦争に行ってしまいました。夫が出征してから、女の子が生まれました。でも、彼女が慰問で回っている間に、空襲で東京は焼け野原となり、子どもがどうなったか、わかりません。女は、多分死んだのだと思っています。男は女を励まします。「今のことを考えちゃいけない。どんなにみじめになっても、あの思い出だけはいつでも君の心に甦り、君を支えるただ一つの生きがいなんだ」これは、終戦後の時代を生きる日本人すべてに言える思いではないでしょうか。男は詩を書いて、女に贈ります。「何故かしら、あんなにも、遠い昔の歌が 今日はまた、こだまの様に、還って来る美しい、あの日々の幻が、瞼の裏に蘇る」「詩人なのね」と言われて、男は「自分は落ちぶれた詩人さ」と答えます。花売娘にも街の女にも、女性が相手だと、男は保護者のような態度をとっています。これは、作者の気分でしょうか。「また来るんだぜ」「また来るわ」女は去って行きます。「改めて生きる勇気を奮い起こすように」と、ト書きがされています。さて、街の女の場面で、一つの暗示がされました。行方がわからなくなった、街の女の子ども、それはひょっとしたら、花売娘ではないだろうか。そんな暗示が、この芝居が描いている社会の様子に、人々の生き方に、少しでも希望を持たせるように、書き込まれているのです。ダンスホールの音楽が、明るいジャズに変わります。グレン・ミラーの『真珠の首飾り』なんかが良いでしょう。その音楽を口ずさみながら、若いG.I.の青年が登場します。終戦後、日本が占領されていたということが、あらためて思わされます。G.I.は男に英語で話しかけます。男がどぎまぎしてしまうのは、英語がよく分からないだけでなく、占領軍に対する引け目、劣等感、何か文句を言われるのではないかという、謂われのない不安故です。by 神澤和明
2019.07.15
-
『思い出を売る男』(6)
第二パートは、「恋」に関っていると言って良いでしょうか。派手な服装の女が、建物の陰、階段が良いと思います、に現れて腰をかけ、男を見ています。人生に疲れた女性です。後の話で、夫は戦争にとられて消息知れず、子どもが一人いたが、別れ別れになって、今はどうなっているかわからない、という身の上であることが知れます。30歳になるくらいでしょうか。すさんだ生活のために、年齢より老けてみえるでしょう男が歌い終わると、声をかけます。「何してるのさ、其処で?」男は我に返って、女を見ます。声をかけたのが、いわゆる夜の女であることが、一目でわかります。派手な赤いドレスと濃い化粧で、一目でわかります。別に軽蔑するつもりはありません。でも、彼は少し、違うところにいる者を見ているような態度で始めているように思います。「思い出を売ってるのさ」「思い出?……そんなもの、どうやって売るのさ」「買ってみりゃ分るよ」男がサクソフォンを持っているのに目をつけて、女はたずねます。「あんた、サクソフォンを吹くの?」「吹くよ」「サクソフォンにゃ、あたし、思い出があるんだよ」「そうかい。百円出せば好きな歌を吹いてやるぜ」彼の女に対する態度は、先の二人と比べると、ちょっとまだ距離があります。でも、彼女はお客になるかもしれません。オルゴールに耳をすませて、女は「綺麗な音楽ね、それ」と言います。女は男が歌い終わるのを待っていた、というのも、彼女が音楽に思い入れがあるからかもしれないとも、思わせます。ここから、短い言葉をつらねた、男と女との対話が始まります。女がぽつりと語る一言に、男が頷くのですが、女の過去がひきだされてゆきます。「あたしはとっても不幸なのよ」「知ってる……」「あたしはとっても苦しいのよ」「知ってる……」「あたしは、とっても……醜いのよ」「知ってる。……だから、君の思い出は人一倍美しいのさ」「あたしには色んな思い出があるわ」花売り娘には思い出はなかった。広告屋は思い出したい思い出など一つもない。でも、街の女には、いろいろの思い出があるのです。男は女に、じっと灰色の壁をみつめているように言います。そうしていれば、音楽に導かれて、幸福の夢、美しい思い出しか見えなくなるのです。男に導かれて、女は今まで封印していた、楽しかった過去を思い出して行きます。「君はあの頃は、美しい少女だった……」「十年も前の話ね」「君はあの頃美しい恋をしてたね?」「……昔の夢よ」「あのひとは君の生きがいだった」「あたしの生命だったわ」昔、彼女はコーラスガールで、恋人は楽団のサクソフォン吹きでした。女が歌い出すと、男はいつも伴奏を始めました。女が低く『巴里の屋根の下』をくちづさみます。ふたりの思い出の歌なのです。by 神澤和明
2019.07.13
-
『思い出を売る男』(5)
うさんくさそうに男に対しますが、気の良い人物らしく、新参者に対して、親分である「黒マスクのジョオ」に仁義を通しておかねばいけないと、忠告してくれます。かなり怖い親分のようです。戦争で顔をひどくやられて、いつも黒マスクをつけているので、その名がつきました。何故こんな、裏町にいるのかたずねられて、男は、目の前の薄暗い街灯と灰色の壁が必要なんだと話します。そこに「思い出」が浮かび上がってくると言います。彼が音楽によって呼び起こす思い出は、画像となって視覚にも訴えかけてくるようです。思い出を試してみないかと薦められた広告屋は、はっきりと断ります。おれには美しい思い出なんかない、胸のむかつくことばかりだと言うのです。この芝居に出てくる人たちは孤独です。「失った人」ばかりだからでしょうか。彼の仕事の仕方は変わっています。人混みの中で警官に喧嘩をふっかけて騒ぎを起こし、ねばれるだけ粘って、人が大勢集まってきたところで、目に立つように、高々とプラカードをかかげる。そうして豚箱に放り込まれることになれば、「おやじ」が引き取りに来て、給料を倍くれる。彼の口によると、「恥をかく」のが仕事だということです。古来、日本人は「恥をかく」ことは最悪のこと、恥をかくくらいなら死んだほうが良い、という道徳で生きてきました。捕虜になるは玉砕を選ぶことが、正しいとされていました。その観念がひっくり返っています。慣れてしまえば、生きるために「恥をかく」なんてことは、なんでもないのです。彼は雇い主である「おやじ」とはうまくやっているようです。そして、かなり無茶な仕事も平気でこなす。三日三晩、数寄屋橋の下で水につかっていたこともあります。一日中、靴屋の店先にぶら下がっていたこともあります。そんな、人が見たら馬鹿だというような、プライドを捨て自分の身を粗末にし、みんなから笑われるような仕事を、全力でやっています。彼に、「うらやましい。君の生活は冒険に充ちている。君の様なひとには思い出なぞ用はないんだ」と男は言います。これは彼の本心でしょう。みんなが気力をなくし、後ろをみて生きている社会で、ともかく前向きに生きている広告屋には、ある意味で未来があります。こういう人物には、わたしたちもなんとなく好感をもってしまいます。広告屋は、ついでがあるから親分に口を利いておいてやろうと言って、去って行きます。花売娘と広告屋で、まず第一パートが構成されました。男はまた、オルゴールを鳴らして歌います。ブリッジです。「街角に、ただ一人……」第一パートでは、終戦後の貧しい状況の中で、それでも人が、真面目な方面で生活の方法を探して生きている、現在は大きな希望は持てないけれど、決して悲観するだけではないという情景があるようにみえます。そして二人の人物についてのエピソードは関連がなく、物語を作っても居ません。by 神澤和明
2019.07.12
-
『思い出を売る男』(4)
男は思い出を売ると言っていますが、彼が客に何かを与えるのではありません。その人がもっている記憶、苦しい生活の中で忘れてしまっているものを思い出させるのです。その人が大切にしてる思い出は、必ず美しく、幸福なものに違いありません。向こうから酔っ払いの二人連れがやって来ます。金回りの良さそうな連中です。冒頭に出た紳士達とは違うでしょうが、同じであってもかまいません。みんなが貧しい時代に、うまく立ち回って豊かに日を送っている階層を示しているのです。作者の気質でしょうか、悪い奴という描き方ではなく、普通の人達とは違った、自分たちの世界にいる、浮ついた連中という感じになっています。少女は二人に花を売るために近づきます。男は、危ないからお止しと言いますが、少女は大丈夫と言って、そばに寄ります。この二人連れは、ぐでんぐでんの酔っ払いという演技でかまいません。男女の噂話を大声でしています。少女から気前よく、花束を買いますが、少し歩くと花束を落っことして、そのまま言ってしまいます。少女はそれを拾って、得意そうに男に言います。「ほらね、みんなただもうけ」「(笑って)うまいね、はるみは」「(嬉しそうに)もうかっちゃった」。「(淋しげに)もうかったね」こんなに小さな子どもが、もう社会のずるいやり方を憶えて、それを嬉しそうに自慢している。そのことが、男には悲しく思われます。ダンスホールから、賑やかなダンス曲が聞こえて来ます。女の子は、客に花束を売ろうと思って立ち去ります。一つの小さな繋がりが出来て、終わりました。この少女は可哀想な境遇なのですが、本人はそうは思わず、明るく生きているように見えます。男の方は、彼女の行く末を考えて、少しつらくなります。でも、彼には何もしてあげられない。少女を見る彼の目は、あるいは保護者のように温かいのですが、同時に悲しさをたたえているのでしょう。広告屋がやって来ます。今は見かけなくなりましたが、以前はよく人通りの中を歩いていた、サンドイッチマン、当時の言葉では「マネキン」です。身体の前後に広告、この場合は映画の宣伝です、の大きな札をぶら下げています。口上を言う人も居ます。彼の場合は、西洋で普通の「ワンマンバンド」で、太鼓をぶら下げ、紐の操作でそれを鳴らす、そうして人の注意をひいて、宣伝をするやり方です。この男はインテリではないでしょうが、話しぶりなどなかなかに弁がたち、からっとした気性です。渥美清のような浅草出身コメディアンに似合いそうです。by 神澤和明
2019.07.11
-
『思い出を売る男』(3)
この芝居は前に進んでゆく筋を持つのではなく、幸せを売る若い男と様々な人々が出合い話を交わす、それの連なりの構成をとっています。若い男を狂言回しに、様々な人の人生と彼らの今の思いが、語られてゆきます。一種の「グランドホテル形式」と言えるでしょう。それぞれの人が、当時の人々の生き方や考え方を代表しています。シンボルとしての登場人物といえるかもしれません。彼らはそれぞれに孤立していて、人間関係はないのですが、観ているとある人物たちは関係をもっている、彼らはもとは家族だったのではないのか、と思われてきます。男が歌い終わると、花売り娘の女の子が近付いてきます。終戦当時、都会には自分で働かなければ鳴らない子どもたちが多かった。宮城まり子の歌『ガード下の靴磨き』や美空ひばりの『東京キッド』に歌われる子どもたちは、普通にあった姿でした。この女の子も、八歳ですが、親方に言われて花を売って歩いています。まず、子どもを登場させて、戦争の結果は、幸せであるべき子どもたちに、辛抱と無理を強いていることを見せます。また、その生活ぶりと裏腹なあどけなさが、芝居の始まりを優しいものにします。女の子は、おじさんはどこから来たの、と尋ねます。子どもと大人の優しい会話が、気分をほんわかとさせてくれます。「遠い、遠い幸福の国さ。そこでは誰も彼もみんな幸福だった。どんな人でも、とても不幸になった時、悲しくなった時、その国のことを思い出すんだよ」それは戦争のずっと前の日本だったかもしれません。「君はそんな風に悲しくなることはないかい?」「ないわ」「お父さんやお母さんはいるの?」「いないわ。二人とも戦争で死んじゃった」「憶えているかい、お父さんやお母さんの顔?」「憶えてないわ。だってあたし、まだとてもちっちゃな子どもだったんだもの」「ひとりぼっちで淋しくないかい?」「淋しくないわ。お姉ちゃん達が沢山いるから」お姉ちゃん達というのは、バーやキャバレエで男たちの相手をしている女性たちです。「早くおおきくなって、お姉ちゃん達みたいになりたいわ」男は淋しそうに、「そうなったら、おじさんとこへおいで」と言います。でも、その時に彼はどこにいるでしょうか。女の子は、男が何を売っているのかたずねます。男は、思い出だと答えます。「いくら?」「百円」「高いわ」「高くはないさ、涙の出る程有り難いものだもの」「あたしの花は一束80円よ」「三日もたてば枯れてしまうものね。おじさんのは枯れない」「思い出は枯れないの?」「枯れないとも。20年も30年も、そのひとが生きている間はね」少女は、自分にも思い出を頂戴と言いますが、男は駄目だと答えます。「君には思い出の種がないもの」。そして、このはるみという少女が10年経てば、きっと美しい幸せな思い出をもっていると言います。by 神澤和明
2019.07.10
-
『思い出を売る男』(2)
終戦直後の東京の裏町です。人通りは決して多くありません。灰色の壁に面し、街頭があります。その下に、肩に手回しオルゴールをかけ、古ぼけたサキソフォンを手にした一人の若い男が、たまに通りかかる、身なりの悪くない人たちに声をかけます。「いかがです、旦那。思い出をお買いになりませんか」「思い出?」「思い出です。美しい音楽によみがえる幸せな夢」「アプレゲール新商売か? 頭が悪いねえ」「アプレゲール」という言葉は、今の人にはわからないでしょうね。「戦後」という意味のフランス語で、元来は第一次世界大戦の後にヨーロッパで広がった新しい芸術運動をさしました。日本でも大正デモクラシーの時代に、芸術状況に現れた傾向です。第二次世界大戦後、それまでの社会通念や価値観が崩壊した時代に、既成の道徳観を無視した、無軌道な行動をとる若い人たちが増え、犯罪を犯す者も多かった。そういう人たちは「アプレゲール」略して「アプレ」と呼ばれました。あまり良い意味でつかわれた語ではありません。最初にこういう言葉が出てくることで、この作品の時代がわかります。男たちが行ってしまうと、若い男は肩をおとし、手回しオルゴールを奏しながら歌います。「街角に、唯ひとり、佇めば、蘇る遠き夢。喪われた幸福よ。過ぎし日の思い出よ。おお、マドレーヌ。永えの幻追いて、我が心こめし祈りに、そも汝は何時かこたえん。角笛に、聴き惚れて、佇めば、蘇る清き夢。遠き日の幸福よ。うるわしき思い出よ。おお、マドレーヌ。そも今は何処の空の、悲しみの星の光ぞ、何時の日か汝にまみえん」この歌が、『パリの屋根の下』とともに、この作品の「主題歌」になります。センチメンタルな気分とともに、何か懐かしい、昔の恋人へのあこがれが感じられます。PCでオルゴールの曲を作りました。歌詞のリズムにあわせ、前半を短調→長調→短調の進行の4拍子、後半を短調で通す3拍子のワルツで作曲しました。自分では気に入ったメロディなのですが、上演した町民劇団の人たちは歌に慣れていないので、歌いにくいと不評でした。残念です。若い男には名前はありません。彼だけでなく、登場する人の多くがそうです。名前を呼ばれるのは花売り娘のはるみと、ギャングの「黒マスクのジョオ」だけです。黒マスクのジョオというのも、あくまでもそう呼ばれているだけで、記憶を失っている彼の本名はわかりません。この作品に出てくる大人たちは、みんな戦争が終わったときに、その名前=アイデンティティを失っているのでしょう。by 神澤和明
2019.07.09
-
『思い出を売る男』(1)
観たことはないが、大変に気に入っている作品というものがあります。わたしの場合、岸田國士の『チロルの秋』と、加藤道夫の『思い出を売る男』がそれです。『思い出を売る男』は脚本をちゃんと読んだこともなかったのですが、素敵な作品というイメージがありました。加藤道夫という演劇人についての知識はありました。フランス演劇に詳しく、芥川比呂志の盟友、浅利慶太の師匠であり、矢代静一、三島由紀夫といった、文学座にあるフランス演劇の流れの劇作家たちに大きな影響を与えた人と覚えていました。『なよたけ』や『挿話』等の作品は読んでいました。『なよたけ』に感じられる若々しいロマンティシズム(センチメンタリズムと言ってもよいでしょうか)と、自分よりもはるかに強い力に対して、頭を上げて向かってゆくすがすがしい意志力、そして無力を知らされる切なさは、少年期のわたしに魅力的でした。新劇には珍しい「ヴォードビル」という呼び名がついていたことも、この作品を特別なものに感じさせました。この言葉が意味するものは、なかなかつかみにくいです。しゃれた気分をもち、音楽と笑いが織り込まれた、楽しい出し物とでもいえば良いのでしょうか。「演劇」というように本格的ではない、重い思想的テーマや社会批判があるのでもない、ひと時を楽しく過ごすための「娯楽」というニュアンスをもっています。いわゆる「新劇」が大切にしているものから離れた、むしろ逆の方向に向かっているものです。作者があえて「ヴォードビル」とつけたのは、「新劇」というものが既に身につけてしまっていた、「教条主義」や見かけだけの「深刻ぶり」を拒みたかったのでしょう。それでも、わたしたちが見れば、この作品はやはり「新劇」です。そこには終戦から近い時代の人々の生活に満ちていた貧しさや苦しさ、失ったものへの哀惜の気持ちが描かれます。親を失った孤児、戦地で夫を失った妻、妻と地位を失った男、そして生きる目的をなくした人たち。一方で犯罪に走り、ずるいことをして金持ちになった者たちもいます。そこには大きな貧富の格差があります。そんな社会への「ノーグッド」を投げかけていますから。「思い出を売る」という言葉には、とても感傷的な気分がつきまといます。かつて私たちが抱いたフランス、パリへのあこがれに満ちたイメージ、それにつながります。良く知られたシャンソンに『幸せを売る男』という曲がありますが、この題名はそれに連想されているのでしょうか。この作品では主題歌とともに、戦前から日本でもよく知られた『パリの屋根の下』や『自由を我等に』が流れます。ともにフランス映画の主題歌としてヒットしました。それらの音楽が、この出し物を、粋に、また切なく彩ってくれています。老婆心ながら、この作品を上演するときには、JASRACにご注意ください。楽曲使用料を、こまかく請求してきますので。by 神澤和明
2019.07.08
-
『西瓜と風鈴』(6) 7/6
洋子は事情を理解して、まやに真実を話すため、二階に駆け上がります。菊と花代、二人のお魂さんが残ります。菊「花代……」花代「……私は、福山の大下勇さんに恋してたんや」六十年も経って突然に、思いがけない事実を知らされました。長い間、守られてきた嘘だったのです。それを知って、強い衝撃を受けたには違いありません。でも、これは、裏切られた、のでしょうか。そうではないと、わたしは考えています。誰も青木昭一を責めないでしょう。花代が恋していた「福山の大下勇」。彼女は彼に会ったことも、話したこともありません。実際の彼を、花代は知らないのです。ですから、彼女が恋した「大下勇」は、六十年の間、毎年遠くから西瓜を持って、亡くなった彼女に会いに来る「大下勇」のはずです。たとえ彼が本当は「青木昭一」であったとしても、そこにいたのは「大下勇」です。それこそが、彼女が恋していた「大下勇」なのです。二人の心優しき人たちの大切な思いが、このようにこじれたものになってしまったのは、戦争のせいです。戦争は、本当にどんなところにでも悪い効果を残していきます。この幕切れで、つり下げられた多くの風鈴が一斉に鳴り響く、という演出をしたかったのですが、舞台機構と人手不足で、できませんでした。音響効果で風鈴の音は流せましたが、風鈴たちが揺れ動く、視覚に訴えかける効果を、是非使いたかったです。この上演は、二人のお魂さんの役に適役を得た事で、大変に良い舞台を作ることができました。演技力よりも、醸し出す雰囲気、真面目で素直で、明るい人物表現をしてもらえました。観客の反応も、期待通りでした。静かに、しんみりと、作品の言いたいことを受け止めていただけました。作者の和田さんも観に来て下さって、大変に喜んでくださいました。劇団未来での上演や、その前に行われた、関西のプロ俳優によるプロデュース公演よりも、良い出来映えの舞台だったと、自分では思っています。ただ、演出家としては、二階と玄関の位置設定といった、物理的な部分に混乱があったのが残念で、できればいつか再演したいと思ってはいるのですが、このときの上演を上回る適役の演技者を見つけられるように思えず、企てられずにいます。和田作品は、ごく普通の人が経験する日常的な出来事を、作家の目で事件として立ち上げ、それをあくまで暖かい感覚で描きだしています。大坂弁の巧みさと相まって、深みのある「人情劇」だと思っています。by 神澤和明
2019.07.06
-
『西瓜と風鈴』(5)
まやの母親、洋子が帰ってきました。知人の葬式に出ていたそうで、喪服姿です。彼女は葬式の会場で、変な詐欺師の話を聞いてきました。故人の戦友を名乗って訪れた男が、仏壇に手をあわせてゆく。ところが彼が帰った後、お供え物がなくなっていたり、仏壇にしまっていたへそくりがなくなったりしていることが続いていると言うのです。大下と言って訪ねてきた男は、間違いないのかなと言って、まやを怒らせてしまいます。まやが二階に上がると、洋子はビールや食器を片付けます。仏壇の引き出しを開けて、財布の中身を確かめます。一安心するでしょう。そしてふと、仏壇の白い封筒に気づきます。菊と花代ものぞき込みます。二階でオーボエの音がします。洋子は封筒の裏に書かれた名前を見ます。「青木昭一……? なんやろ、これ」。その不審は、菊と花代も同じです。洋子は中の紙を読みます。それは思いがけない内容でした。「花代さん、長いことだましてすみません。大下勇は、わしの戦友です。山口県の出身です。(略)西瓜作りの農家の出身でした。大下勇は、花代さんの写真を千人針の腹巻に入れて、『花代さんにわしの作った西瓜を食べてもらいたい。日本へ帰ったら、相島の西瓜を下げて行って、三谷花代さんをヨメにもらうんや』と言い続けておりましたが、宣昌のあたりで、敗戦になるちょっと前に病気で亡うなりました」ここから青木(大下勇と名乗っていた)の声に代わります。わたしは、ここは青木の姿が見えるべきだと思い、青木を舞台奥に出して、彼に客席に向けて語らせました。「大下の実家の人に遺品を届けるつもりでしたが、花代さんの写真と手紙以外のもんは、戦争の中でのうなってしまいました。あんたの写真を腹巻に入れとる間に、あろうことか、わしが花代さんの写真に恋をしてまいました。すんません、お許しください。大阪の花代さんのうちへ来たときは、大下勇のことをつたえるつもりで……福山の、というたあとするっと大下勇です、と続けてしまいました。それからずっとわしは大下勇でした。わしのほんまの名前は、青木昭一です。(略)大下君と花代さんの恋をわしがぶちこわしたようにずーっと思えて、それに、もし二人が結婚しておったら生まれたかもしれん子どもさんらも、その子どもらのこどもさんらも、未来永劫に葬ったのは、わしではないかと自分を責めてしもうたりします。ほんまに戦争いうもんは……わしは花代さんの写真と手紙を、大下に……」青木が取ってしまった行動。どこにも悪意はありません。彼が会ったこともない花代に恋をしてしまった、その気持ちはよく理解できます。最初につい、大下勇と名乗ってしまった。それはその名前が、花代に恋を告げる「資格」のようなものに、彼の中でなっていたからでしょう。一度名乗ってしまった以上、そして花代が死んでしまっている上は、彼はそう名乗り続けるしかなかったのです。この家に毎年訪れる以上は。その訪問は、彼の純情、恋心の証しであり、大下勇と花代に対する、真心であったと思われます。by 神澤和明
2019.07.05
-
『西瓜と風鈴』(4)
西瓜をさげて、花代さんを嫁にもらう、花代さんを嫁にもらう、と心の中で歌いながら、はるばる福山からやって来て、花代がもう居ないと知ったときの勇の心が、思いやられます。菊はまだ生きていました。それから十年ほどたって亡くなったそうです。見知らぬ若い兄ちゃんだった勇を見て、菊はなんと思ったことでしょう。花代はもう魂になっていましたが、「この人が家へ来てくれはったとき、びっくりして、ぼーっとしてた」。菊と花代は泣いています。まやも涙ぐんでいるようです。「おじさん……。おじさんはよっぽど……」「風鈴のお礼じゃけえ、西瓜は。(写真に向かって)花代さん、あんたはずーっとわしの心の奥に住んどります。顔も見ず、声もきかず、さわりもせんでも、花代さんは、わしの心の中で生きてきよりました」そして続きます。「まやさん。平和でないといけません。わしらが一番そう思うとる筈です。戦争に行ったわしが生きて帰って、内地にいた花代さんが戦争で殺された。こげなむごいことが忘れられますか。これから先、世の中がどぎゃぁに変わっていくんか、わしらは心配しとります」作者の言葉を役の言葉として、必然に語らせる。ここに正しい台詞の書き方があります。勇はまやに水を一杯所望します。まやが台所に立ったすきに、もう一度、仏壇に手を合わせ、ちょっと迷ってから、白い封筒を御綸の下に置きます。菊と花代は顔を見合わせます。この動作のト書きで、これまで勇と書いていたのが、大下になっています。これは後の進展を暗示しているようです。 戻ったまやから水をもらって飲み、勇は、それではと言って、帰って行きます。来年もきっと来てくれというまやに、勇は「わしはな、まやさん、もうぼつぼついけまいて……。もう覚悟しょぉるんよ」と言います。「花代さんはの、まやさんのこれから先の人生が、はさみで斬ったようにぷっつりのうなったようなことになったんよ」だから「じゃけえ、やりたいことを、思い切りやらにゃぁいけません」。勇は帰って行きます。まやとお魂さんたちが見送ります。まやが戻ってきます。あとから菊も戻ってきます。しばらくして、花代が戻ります。菊が「もう来年は……」と言うと、花代が「また会えるわ、きっと」と強く言います。まやが電話で友達と話します。お客さんからいい話を聞いて、とても感動したと言います。そして、慰霊碑を見たいから京橋へ行くと言います。彼も一緒に来ないか。いや? それならもうつきあわない。……どうやら、彼も一緒に行くことになったようです。by 神澤和明
2019.07.04
-
『西瓜と風鈴』(3)
なぜ風鈴が飾られるのか、勇が話してくれます。花代が戦場に送った慰問袋の中に風鈴が入っていた、夜にそれを振ってチロチロ音がすると、急にあたりが涼しくなったと、語ります。風鈴をよろこんでくれていたことを知って、花代は喜びます。慰問袋には花代の写真もはいっていました。勇は仏壇の遺影と見比べているのでしょう。その写真を勇は腹巻きの中に大事に仕舞っていたそうです。風鈴は終戦で捕虜になった時に取り上げられたと言いますが、写真はもっていたのだろうと思います。勇の話は続きます。南方の戦地で食べる物もなく、苦しんでいた。暑い盛りのとき、冷たい西瓜が食べられたら、どんなに馬力が出るだろうかと思った。その記憶が、西瓜を持ってくることに繋がっているのでしょうか。ちなみにこの西瓜はそのあたりの店で買ったものではなく、家で作ったものを、わざわざ運んできたものです。兵隊たちは食べる物がないために、現地の人々のものを根こそぎ奪って食べていたと、勇はつい口をすべらせて、まやに非難されます。食べ物を奪われた人たちは飢え死にしたかもしれない。あとから考えたら非道いことをしてしまったと、勇は後悔しています。彼が悪い人だったのではなく、状況がそうさせたのです。その原因を作ったのは戦争を始めた国家です。国家が国民に悪を働かせる。国が、庶民の一人一人に悪行を働いた記憶を残させてしまう。ここに作者の告発があります。今、心臓が悪くなって苦しんでいるのも、その罰があたったのかなと、勇は言います。国家に、国を動かしていた権力者、政治家、財閥に、罰は当たったのでしょうか。老人と高校生、ここには戦争について、深刻な議論はおこりません。それぞれが違うバックグラウンドに属しているのですから。理解しあうことも、難しいでしょう。しかし互いを認め合うことはできます。勇がトイレに立ち、まやはボーイフレンドに電話をかけます。一度、話を途切れさせて、あらためて続けて行く技法です。終戦の翌年、初めて西瓜を持って訪ねてきたとき、勇は花代を嫁にもらうつもりでした。しかしその時、花代はもう亡くなっていました。終戦の前日、8月14日の大阪砲兵工廠空襲の際に、学徒動員で働きに行っていて、焼け死んだのです。工廠は東洋一の規模だっただけに、この空襲は大変に大きな被害を出しました。JR環状線で、森ノ宮駅から京橋駅の間にかけて、以前は大きな空き地がありました(今は大阪城公園駅になっています)。工場から逃げてきたけれど、京橋駅で焼け死んでしまった人も数多く、京橋駅にはその時のことを記した碑が建っています。by 神澤和明
2019.07.03
-
『西瓜と風鈴』(2)
お客のための用意をしてくれた、菊の孫の嫁、洋子はちょっと外出していて、その娘のまやが留守番をしています。オーボエの練習をしています。そこにチャイムが鳴ります。声がします。「こんにちは。大下です。福山の」オーボエの音が止み、まやが二階から降りてきて、大下勇を迎えます。入ってきた勇は、もうかなりの年齢で、足も弱っています。「いかるが」ではそれほどの老齢者がいないので、老けでやりました。勇はまやに、下げてきた西瓜を手渡します。仏壇の前に坐り、線香に火をつけて、手を合わせます。御輪がチーンと鳴ると、菊と花代もピクリとして、勇に向かって手を合わせます。「感謝」です。まやは母が用意したビールを出します。西瓜のお礼を言います。勇は照れて、「同じもんばっかり何十年も」と言います。菊「もう六十年も、毎年毎年」花代「六十個の西瓜を、お盆になったら」菊「なあ、ほんまに」花代「私、アホなこと考えるとこやった」菊「そうやがな」勇「もう、ええ加減にせにゃぁいけんなあ」と言いますが、花代も菊も、まやも、いえいえと首を振ります。「あんたはひとつも変わっとられんが、わしゃぁこがぁなじいさんになってしまいました」と、仏壇の花代の写真に話しかける様子です。まやと勇の会話は、親戚のお爺さんとのそれのように、和やかです。花代の写真をさして、「どっか似とられますな。えっと、花代さんの……」「えっと……生きてたら大オバさん……かな」場面全体に、暖かい微笑みがほしいです。勇にビールを勧めるように菊がまやの背中を押したり、勇の立ち坐りを花代や菊が手伝ったりするト書きがあります。生きている人間は気づかない、そよ風のような力なのでしょう。まやのオーボエを、勇が吹いてみますが、鳴りません。ここで勇が「女の人向き」の楽器じゃないと言ってしまい、まやがちょっと反発します。「そんなこと言いませんよ、うちら。女の人向きとか男の人むきとか」「世の中、変わりましたけぇな、なにかにつけて」花代に背をおされて、まやが勇にビールを勧めます。まやが、もう一杯注ごうとしますが、菊が止めます。はしたない、という感じでしょう。すると勇は、「いやぁ、もういけん。心臓がバクバクしてきょぉりますけぇ」と断って、「若きゃあ時分に戦争で死に損のうて、久しぶりに今年の春にも死に損ないました」と続けます。心臓が悪いようです。まやが「戦争って……」と問います。まやの知っている戦争はテレビで見たもの、学校で習ったものです。記録の伝聞でしかありません。勇にとっては、それは体験であり記憶です。by 神澤和明
2019.07.02
-
『西瓜と風鈴』(1)
劇団「未来」の創立メンバーで座付き作者の和田澄子さんとは、斑鳩ホールが主催する「劇作家養成講座」(後に「シナリオ講座」と改称)の講師を依頼した際に知己を得ました。この講座の第一クールでは、関西芸術座の宮地仙(藤田千代美)さんに講師を依頼しました。講座参加者が多かったので、第二クールも行うことになり、講師をどなたに依頼しようかと考えて、和田さんを思いつきました。実を言うと、それまで和田さんとは面識がありません。そして、厳しい方、怖い方とばかり聞いておりました。ですが、未来で上演されてきた和田さんの作品は良いものでしたので、この方なら指導をお願いするのに良いと、直観しました。それで人を介して連絡を取らせていただき、お願いをしたのです。正直、わたしは人見知りが強く、知らない方にお願いにゆくということが滅多にできないのですが、講座を良くするという目的に励まされて、お話を進める事ができました。予期したように、和田さんは非常に厳しく、しかし丁寧かつ親切に、受講者の皆さんを指導し、未熟な原稿を添削して下さいました。お忙しい中を、十分に準備して、大阪から法隆寺まで通って下さり、献身的にご協力をいただきました。この『西瓜と風鈴』は、和田さんの一幕物で、原稿で読ませていただいて心を打たれ、劇団「いかるが」で上演させていただいた作品です。上演時間は一時間足らずです。和田さんは、大阪のごく普通の人たちを登場人物に、日常の中にありそうな出来事から芝居を紡ぎ出してゆかれます。人から聞いた体験などから作品を作られることもよくあります。そして、大阪の「新劇」劇作家らしく、社会や政治の問題点、正しくないことへの批判の目が、しっかりとあります。『西瓜と風鈴』は、戦争が終わって随分たつのに、まだ始末がついていない問題、戦争があったために生まれた小さなアクシデントと、それに関わる善意の嘘の話です。幕が上がると、季節は夏、お盆。仏壇のある日本間に、二人の女性が居ます。娘の花代は浴衣姿、母親の菊はブラウス、スカート姿です。上演のときは二人とも浴衣にしました。二人は、いつもこの時期に西瓜を手土産に持って訪れてくる、大下勇を待っています。彼は復員してから毎年、「福山の大下です」と言って、お盆になると此の家を訪れてくるのです。かなりの老人ですから、彼が今年も、遠くからやって来られるのかどうか、二人は心配しています。もう、今年は来ないかもしれない。暑い季節です。たくさんに吊られた風鈴が、涼しげになっています。二人の仲むつまじい、明るい会話を聞いているうち、実は二人はもう死んでいる、お魂さんであることがわかってきます。客席からは見えませんが、仏壇には花代の遺影と菊の遺影が飾ってあります。花代は戦時中、戦地の兵隊たちを励ます慰問袋を送っていました。その一つを受け取った大下は、戦地から花代に手紙を出しました。その縁で、ずっとこうして訪れてきているのです。by 神澤和明
2019.07.01
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(13)
子どもたちの声がして、手がつっこまれ、老ガエルが引っ張り出されます。ひとりだけ早く、実験に使われるようです。老ガエルは見苦しいことはせず、最後まであきらめるなと言い残して、消えて行きます。トビからは免れても、すぐそこまで忍び寄る死の手からは、免れられません。残ったカエルたちが飢え死にしないようにと、ご飯粒が放り込まれます。大きな飯粒を、食べる演技で消してゆけるように、コットンで作りました。腹ペコの子ガエルがすぐに食べようとしますが、考え深いカエルが、それをブンナひとりに食べさせようと提案します。そうすればブンナが元気になって、この瓶から外へ跳んで出られるかもしれない。そうして、このガラスを壊して、みんなを助けてくれるかもしれない。他のカエルたちも賛成します。ブンナは飯粒を食べます。一口毎に、コットンをむしりとって、飯粒は小さくなります。だんだん力がみなぎってくるのを、感じてきました。ブンナは手足をストレッチして、ジャンプの準備をします。子ガエルたちは四つん這いになって、踏み台になります。彼らを踏みつけるようにしてジャンプできると、動きの躍動感が増すのですが、上演の時は演技者にとって難しいと考え、穏やかに上に乗って跳び上がることにしました。ガラスの壁を飛び越えたブンナが姿を消します。残った子ガエルたちが、少し心配になってきます。しかし、ブンナが大きな石を抱えて、戻ってきます。この石でガラスを割るつもりです。危ないから、みんな離れて。ブンナが石を投げつけるタイミングで、照明がカットアウト。同時にガラスの砕ける音が大きく響きます。ゆっくり明かりが入って来ると、舞台全面にカエルたちがいて、最後の歌をコーラスします。スズメ、モズ、ネズミ、ヘビたちも出て来て、加わります。水ぬるむ五月。今日も新しい命が生まれる。手をつないでそろって歌おう。きょう一日を大切に生きて行く。その喜びを歌い上げて、芝居は終わります。『ブンナよ、木からおりてこい』は動物たちが登場人物の長い「寓話」ですが、子どものための物語ではありません。おとなが読んで、深く感動できる作品です。もちろん、子どもたちにも好きになって欲しい。実際、アニメーションにもなっていますし、朗読や語りのパフォーマンスも行われています。水上勉さんの経歴、素養から、仏教的思想が強く出ていますが、それは仏教に限定しない、世界の多くの人々に理解され、共有されうる思想でしょう。小松幹生さんの脚色も、ポイントを抑えた、解りやすく楽しい、優れたものです。これは観客も演技者も、ともに考えさせられることの多い作品だと思っています。by 神澤和明
2019.06.29
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(12)
ネズミはぐったりと横たわっています。ブンナが近づく。ネズミはもう自分が駄目なことを悟っています。そしてブンナに、この木の土の中で、冬をすごすように言います。トビはブンナがいることを知りません。だから、安全なはずです。でも、冬眠するためには、食べ物が要ります。それはどこにあるでしょう。ネズミは言います。自分が死んで腐ってゆけば、そこから羽虫が生まれてくるだろう。それを食べて、生きて行くのだ。遠慮してはいけない。自分が死ぬことを気の毒がってはいけない。自分が死んでも、それで君が生きて行くなら、それで良い。自分は君の中で生きて行くのだ。そしてネズミは死にます。やがてその身体から、無数の羽虫が飛び出してきます。この場面は、青年座で初演されたとき、演出の鈴木完一郎さんがとても素晴らしい工夫をされました。みんなでネズミを取り囲み、シャボン玉を吹いて、虫が飛び出してくるのを表したのです。舞台の進行にピッタリと添い、とても簡素であり、輝くシャボン玉が美しく。おそらくこれは、ベストの演出でしょう。それは解っていますが、やはり演出者の意地で、別の演出を考えました。「演劇ワークショップ」のときは人手もなかったので、竹ひごの先にチョウチョを切り抜いてつけたものを幾つも作って、ネズミの身体からヒラヒラと舞い立たせました。「シアター生駒」のときは、その前の場面で登場した踊り手たちをネズミの身体の上に覆い被さらせ、一人ずつひらりと漂って離れて行くようにさせてみました。ダンスのテクニックで考えるとうまく行くはずだったのですが、出演者がそうした動きに慣れていなかったせいで、わたしの意図したような場面は作れませんでした。いまだに残念です。この場面に、芝居のテーマがはっきり示されています。人はどのように生き、どのように死ぬのが良いのか。自分の死が、他者を生かすようになることはできないか。そして命は、個々で終わってしまうものではなく、後の世代へと引き継がれてゆく。サス明かりの場面に戻ります。冬眠からさめたブンナは、無事に木のてっぺんから降りてきたのですが、まだ十分に動けないところを、子どもたちに捕まえられたのです。木の上での出来事を聞いた子ガエルたちは、スズメは非道い奴だとか、モズは口ばかりだとか、いろいろ感想を述べますが、ブンナは何も言いません。死にたくないのは、誰もが抱く思いです。死がまだ自分の遠くにあるときは、何とでも言えますし、自分を立派なものに見せたいという態度もとれます。しかし、死が現実に目の前に迫ったとき、生死の境目で思わずとってしまう行動、それを彼は見てきました。それは決して非難すべきことではないと、知ったのです。by 神澤和明
2019.06.28
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(11)
ヘビは口が裂けています。だから、ネズミのような図体の大きなものは、食べられない。カエルなら別だが。ヘビの言葉にブンナはドキンとします。二重の上と下、それぞれの様子が客席から見えます。ヘビが問わず語りに話すことから、ブンナは恐ろしいヘビにも、かわいがる子どもたちがいるし、優しく気を遣う母親がいたことを知ります。冷血漢としか思っていなかったヘビも、やはり心があるし、生きるために苦労をしているのです。自分たちは嫌われ者だ、この体形と音もさせずに歩く習性が、気味が悪いといわれる、おれたちは遠慮して生きているのだ、とヘビは言います。なるほど、話を聞いているとそんな気もしてきますが、本当でしょうか。話しながら、時々ヘビは、お前、笑ったな、とネズミに鋭く言います。ネズミは別に笑っていません。そんな余裕はありません。ヘビの神経質な部分、周りから白眼視されているといつも意識しているから、過敏な反応を示すのでしょう。笑われるのは我慢がならない、そうつぶやくヘビと同じ気持ちを持っている人も、いるのではないでしょうか。原作ではここに、ウシガエルも連れてこられるのですが、この脚色では省略してあります。確かに、舞台ではもう、多すぎます。口をやられていると言いながら、ヘビは徐々にネズミに圧力をかけてきます。ネズミを呑もうしているのかもしれません。思わずネズミは、土の中にカエルがいることをほのめかしてしまいます。ヘビは土に顔をつけて、カエルのにおいをかぎつけます。よし、二人してカエルを追い出そう。そう言って、ヘビは片側から土の中に入って行きます。ブンナが飛び出します。ネズミと顔があいます。ヘビが出て来る。ブンナを見つけて、捕まえようとする。ネズミが立ちはだかります。やめろ、この子は助けてやるんだ。偽善者め。そこをどけ。ヘビとネズミの格闘が始まりました。舞台では多人数を出し、ネズミのグループとヘビのグループが対立するダンス場面にしました。雷鳴が鳴り、雨が降り注ぐ、その中での闘争です。ヘビの方が優勢です。ネズミは木から墜落したときの大けがと、疲れとで力がありません。ヘビはネズミを抑え付けて、締め殺そうとします。首に巻いたマフラーを、ネズミの首にかける。占めようとする。ブンナがヘビのしっぽにかじりつきます。強い痛みに、ヘビの力が緩む。ブンナの方に身体を向ける。そのとき、ネズミが渾身の力を振り絞って、ヘビを突き飛ばす。後ろによろけたヘビは、足元が滑って、木のヘリから落ちかけ、かろうじてしがみつきます。助けてくれ、と哀願するヘビ。しかしネズミもブンナも、力がなくて手を出せません。ついにヘビは、墜ちていってしまいます。by 神澤和明
2019.06.27
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(10)
ネズミは、トビが知らないでいる、従って安全な立場のカエルを巻き添えにするよりも、スズメを食った方が良いと言って、スズメに近づきます。スズメは恐ろしさに叫びます。と、トビの声と、羽ばたきの大きな音。スズメとネズミは同時に叫びます。おれはさっき来たんだ。スズメの方が古いんだ。順番にしてくれ。ぼくじゃない。ネズミの方が先だ。羽ばたきと悲鳴が重なり、トビはスズメを連れ去ってゆきました。ひとりになると、ネズミも泣き始めます。ネズミの心の孤独と寂寥感が、ブンナにも感じられます。生意気なスズメだったが、正直な奴だった。おれは、生きたくない、覚悟しているとスズメに言ったくせに、いざとなったらスズメを売っていた。おれは悪い奴だ。モズと同じく、口で偉そうなことを言っていても、その瞬間には本音が出てしまう。自分が生き延びるためには、他の者を犠牲にすることを厭わない。この、あまりに人間らしい行動が、二度繰り返され、観客に印象づけられます。それを肯定するかどうかは、それぞれでしょうが、あっさり否定することはできないでしょう。夜になって、ミミズクが天気予報を告げます。月は曇り、雨がふるでしょう。ブンナは土の中から現れて、ネズミに声をかけます。そして、月明かりをたよりに、木をおりてゆくように励まします。トビは夜は目が見えない。だから、逃げるなら今がチャンスだというわけです。ネズミは怪我をしているけれど、このままだと明日には食べられてしまう。一か八か降りて行こう。観客から見えない側で、ネズミはゆっくりと木をおりてゆきます。しかし、ふっと月が雲に隠れてしまう。明かりが弱くなります。すぐに、アーッという悲鳴とともに、ネズミは落下してゆきます。明るくなると、再びそこにネズミがいます。トビに見つかって、また連れ戻されたのです。情けない、情けない。残された希望を失って、ネズミはすすり泣きます。と、また羽ばたきがして、何かが落とされます。後ろ姿をまず見せてみました。ネズミが悲鳴を上げます。食べないでくれ。ネズミが恐怖を覚えた相手は、恐ろしいヘビでした。今までの獲物と比べて大きく、また「悪」のイメージが強いです。これが以前に出て来たヘビと同じかどうかはわかりませんが、ヘビという一つの存在として、同じ演技者で演じれば良いでしょう。元気なときはしなやかに動いていましたが、今は傷ついていますから、動きはギクシャクする感じがあります。衣装に破れや汚れをつけておきます。始めのうちはあまり動かず、顔を持ち上げて相手にむけることで、凄みを出します。by 神澤和明
2019.06.26
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(9)
スズメはひとまず助かって、ホッとします。そしてシクシクと泣き始めます。泣きじゃくりながら、土の中にいるブンナに呼びかけます。カエルさん、いるんだろう。ごめんね。さっき言ったことは許しておくれ。ぼくはそんなに悪い奴じゃない。ただ弱いだけなんだ。ブンナはスズメを憎む気持ちが薄らいできます。自分だって、死ぬまぎわには、誰かを身代わりにしようとするかもしれない。そう思うのです。ブンナがいるサス明かりの中に、老ガエルと他の子ガエルたちが投げ込まれます。明かりの後ろから飛び込ませます。彼らも子どもたちに捕まえられたのです。カエルたちは再会を喜び合いますが、死ぬ運命が近くに迫っています。トビに捕まえられた獲物たちと同じ運命です。子どもたち=トビです。子ガエルたちはなんとかして逃げだそうとしますが、瓶の壁は高いし、つるつるして、飛び越えることも登ることもできません。なすすべがないので、老ガエルはひとまず落ち着いて、ブンナに木のてっぺんでどんなことを見たのか、話すようにたのみます。木のてっぺんです。トビの羽ばたきが聞こえます。今度連れてこられたのは、ネズミでした。後の場面を考えると、この役は少し年長の人が演じるのが良いでしょう。服装は地味で、灰色っぽいものが良いです。少し足を引きずらせてみました。首をややうなだれるようにして、上目遣いにすると、感じがでます。スズメはネズミにも、食べないでと哀願します。どこまでも、弱い存在です。ネズミはスズメに、こうなった以上、お前さんを食ったって、自分が生き延びられるものじゃない、だから食べはしない。おれは悪い事ばかりしてきたから、罰が当たった気がすると、そんな述懐をします。ネズミはスズメを食べないと繰り返しますが、また、元気があればこの木の上からおりてゆけるかもしれないと、そんなことも言います。ひょっとすると、元気をつけるためにスズメを食べようと思うかもしれません。ネズミの態度には、そんな当てにならないところが感じられます。スズメはおどおどして、おなかがすいているなら、土の中にカエルがいる、それを食べてと言い出します。悪かったと言って泣いていたのに、またこんなことを言うのか。ネズミは鼻白み、ブンナも腹をたてますが、スズメを卑劣だというよりも、弱いやつだと見てやった方が良いと、わたしは思うのです。スズメは生きたいのです。生きて子どもを作り、なんでもない幸せを経験したい。それを知らないまま死にたくないのです。by 神澤和明
2019.06.25
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(8)
スズメはなんとかして命が助かりたい。自分の代わりに何かを提供すれば、トビが許してくれるのではないかと、虚しい希望をもちます。そして、昨日ここで、カエルに会ったことを思い出します。カエルを犠牲に差し出すことで、自分の命を助けてもらおう。スズメはブンナが姿を現すよう、優しい言葉で誘いだそうとします。出てこないので焦って、次には土を掘って見つけ出そうとしますが、折れた羽ではうまく掘れません。グーの手で床をたたくように演技します。他者を犠牲にして自分は助かろうと必死になるスズメの姿を見て、モズは嫌悪を感じます。スズメに、やめろと言います。スズメは、モズだって死ぬのはいやだろう、一緒にカエルを堀り出そうと頼みます。ですがモズは、そんな浅ましいことをしてまで死を免れたくはない、と言い放ちます。スズメもモズも、どちらの行動も、もっともなことだと思います。どんなに無様でも、卑怯なことをしてでも、生にしがみついていたいというのは、生物の本能です。また、死は免れないことだから、死に際は潔くありたいというのは、人間のプライドです。本音と建て前の対立、と言えないこともありません。モズはスズメを浅ましいと軽蔑し、スズメはモズを、やせ我慢の格好づけ、嘘つきだと言い返します。険悪な雰囲気になり始めたとき、トビの声が聞こえます。餌食を取りに来たのです。この音響効果は不意に、そして緊迫感をもって聞こえなければなりません。バサバサと、羽ばたきの音が大きくなる。スズメは恐怖にかられ泣き叫びます。強いことを言っていたモズも、すぐそこに死が迫ってくると、恐ろしさにすっかり我を忘れて、わめきます。おれじゃない、おれは来たばかりだ。スズメが先に来たんだ。スズメを連れて行ってくれ。ぼくじゃない。モズの方が先に来たんだ。助けて。スズメもモズも、相手を連れて行ってもらおうと必死です。トビは上から来ますから、互いの後ろに隠れるのでなく、あちこちに逃げ回ることになります。腰を抜かして立てなかったり、転がったりしても良いです。襲いかかるトビの手がシルエットで下がってくる、ということもできます。さらわれた者は、奥に消えてしまいます。暗転にしてはける手もあります。黒子が複数で持ち上げて運び去る方法もあります。わたしはあっさりと、奥に飛びおりるやり方にしました。トビが連れて行ったのはモズでした。by 神澤和明
2019.06.24
-
7月いっぱいでブログをしばらく休みます
一昨年の8月から、思い立って、ブログを使って自分の演劇論、演技論、演出論、大学や劇団での演技史郎の実際、演技の練習の実践法、自分が演出した作品のノート・記録、さらにいろいろな戯曲についてや劇作家についての解説や、演劇史に類することを書いてきました。1000字程度で書いてゆくつもりだったのですが、実際には1200字を超えてばかりで、読んでくださる方にご迷惑をかけてきました。月曜から土曜の週6日掲載すると決めて書いてきました。一人の人間の考えや知識は知れていますから、2年になりますと、同じことの反復が増えてきていると反省しています。このままでは「惰性」に陥るといやですので、2年たったところで、しばらく休みを入れることにします。その間に、気力と知力を回復させるつもりです。まことに自分勝手ですみません。3か月ほどで復帰するつもりです。by 神澤和明
2019.06.23
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(7)
夜が明けると、トビの鳴き声が聞こえます。食べられてはいけない。ブンナは土の中に身を隠します。鉄骨を組んだ二重の、下の部分におります。前面はネットにして、透けて見えるように考えました。これは最後にヘビが墜ちるとき、このネットに片足を掛けて逆さまにぶら下がると面白いと思ったからです。ですが、考えると危険ですし、うまくその動きは出来そうにないので、やめました。ですから、紗幕でも良かったと思います。大きな羽音が近づいてきて、木のてっぺんに何かを落とします。一度、飛び去って、また別のものを運んできて、落として行きます。舞台では、二重の上にそっと上がることになります。照明は少し暗くして、何が落とされたのか、よくわからないようにしておきます。それからゆっくり明かりを入れて、それが何であるかが見えるようにします。最初に落とされたのは、羽を折られたスズメです。これは、前の場面で出て来たスズメのうちの一羽です。もうひとつの姿は、大けがを負って嘴が裂けてしまったモズでした。モスは乱暴というよりも、キリッとした感じが欲しいので、スタイリッシュにしました。公民館でやったときには、ナチス風の軍帽を被らせてみました。ここはトビが、獲物を一時、生きたまま保管しておく場所だったのです。スズメはモズを恐れ、食べないでと頼みます。モズは傷ついた嘴を示し、食べたくても食べられないのだと言います。彼らは静かに話し合います。モズは「スズメくん」と呼びかけ、スズメは「モズさん」と呼びます。お互いに同じ境遇にいる、一種の連帯感情が生まれています。スズメは自分が死ぬことを受け入れられません。ついさっきまで、楽しく暮らしていたのに、自分は何も悪い事なんかしていないのに、何故、急に死ななければならないのか。スズメの感じ方は、死を遠くのものと考え、毎日をうかうか生きている人間と同じです。一方、モズは覚悟ができているように見えます。肉食のモズは普段から小さなカエルや小鳥を食べています。他の生き物の命をとってきた自分が、今度はトビに殺される。それも仕方のないことだと考えているようです。スズメにはそれが理解できません。自分たちも虫を食べてますが、虫は「食べ物」だと思いこんでいる。極めて自分勝手なのですが、そのことに気づくことができません。モズは母親から、ひとりぼっちになることを教えられたと語ります。みんなと群がっているようでは、餌にありつけずに飢え死にするしかない。生まれたときも、死ぬ時もひとりきりなのだから、ひとりで生きることを心がけろと習ったのです。それだから、いつも仲間と一緒にいるスズメよりも、自分の状況をより正しく把握し、あきらめがつくのでしょうか。by 神澤和明
2019.06.22
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(6)
椎の木のてっぺんに上がってみると、そこには土がありました。そこから見おろすと、ずっと遠くの方まで見えます。太陽にずいぶん近くなった気分がして、気分が高揚したブンナは、てっぺんに上がったぞと、夢がかなった喜びを、高らかに歌います。このソロは、とても元気よく明るい歌にしました。木から下りてきたブンナは、仲間の子ガエルたちに、木の上から見た景色の素晴らしさを大げさに語って、彼らをうらやましがらせます。そして、一緒に木の上に登ろうと誘います。それはカエルには、かなり困難な仕事です。ブンナの他には、昇って行くことができません。ブンナは仲間を励ましますが、そこには自分の優位性を意識させたいという気持ちもあると思います。ブンナは自分だけが木の上に登れる方が良いんだろう。一人の子ガエルが言った言葉は、悔し紛れではありますが、真実をついてもいます。結局、他の子ガエルたちはあきらめて帰って行きます。ブンナは一人きりで、再び木のてっぺんに昇って行きます。いまさら、木登りをやめて、他のカエルと一緒にいるなんて、なんだか、負けたような気がします。ですからブンナは、一人きりで木の上にいることを選びます。木のてっぺんには、スズメが二羽やって来て、のんきに遊んでいます。チュンチュンと音響効果で鳴き声を聞かせます。無理にスズメを真似ることはしません。カジュアルな若者の服装にしました。両足をそろえてぴょんぴょん跳ぶようにして動くと、小鳥らしく見えますが、大変疲れるので、普通の人間の動きにしました。若いスズメたちは、自分たちがいつか死ぬ、なんてまったく思いもよらず、ただ今日をうかうかと暮らしている。これはわたしたちの姿です。遊んでいる気分を出すためにブランコをさせてみたのですが、もっと良い方法があったように、今は思います。ブンナが顔を出します。スズメたちは、カエルがこんな高い所まで上がってきたことに驚きます。空を飛べるスズメをうらやましがるブンナに、空を飛ぶのも楽じゃないんだとスズメは反論します。相手のことを知りもしないで、自分勝手にものを考えるのは馬鹿だね。スズメたちは飛び去って行きます。それでもブンナは、空を飛べることを夢見ます。おそらく、カエル仲間とうまく協調してゆけないブンナは、自分一人で大空を飛び回る、他者を気にしない環境に憧れているのでしょう。夜になって、ミミズクの爺さんが、天気予報を告げに出て来ます。「のりつけほーせ」と穏やかに、「洗濯指数」を知らせます。茶色のガウンを着せました。彼の登場は一つの息抜きになります。ここまでは、明日も今日と同じと期待して生きている者たちの、明るさのある世界です。これから、死がすぐそこにある、厳しい世界が始まります。by 神澤和明
2019.06.21
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(5)
なぜパンを食べないのかと訊かれて、生きたジョロウグモを食べたのでおなかがいっぱいだと答えます。ジョロウグモを捕まえるにはすばしこさと度胸がいると歌って、みんなをうらやましがらせます。彼の運動能力の高さを示していますが、ちょっと嫌みな感じがあります。ブンナがジョロウグモを食べる、ということは、彼らカエルもまたヘビなどに食べられるのだということで、これは後の内容につながりをもっています。のどかな気分が突然、緊張で凍り付きます。ヘビが迫ってきたのです。這いずる音を聞き止めて、ブンナが危険を知らせる。カエルたちは身を隠します。シューッと、息使いを音響効果で聞かせて、ヘビが登場します。しなやかな動きが欲しいこともあり、女性に振りました。衣装にも、光るものがほしいです。手は身体にそえて動かさず、頭を前に突き出して、蛇行するように進みます。立ち止まって、上体を動かして辺りをうかがう。しかし、カエルたちの姿はみえません。結局、ヘビは獲物を捕まえ損ない、空腹で文句を言いながら退場します。ホッとした気分が戻る。と、鋭い悲鳴と鳴き声が。ヘビが一匹の母ガエルを餌食にしたのです。カエルたちは悲しみよりもあきらめの気分に満たされます。「おれたちゃ、けっして弱虫じゃない。でも、この世はおとぎ話じゃない」弱いものは強いものの餌食になる。残念だけど、仕方がない。それが運命なのだ。わたしはこれを歌でなく、少し節をつけたシュプレッヒコールで語らせます。カエルたちを二つのグループに分け、マスゲームのように交差し入れ替わるように、動かしました。サス明かりの中のブンナの場面がはさまります。そして別の時間にゆきます。次の場面で、ブンナと他の子ガエルたちは赤トンボを捕まえようとしますが、トンボは飛んで逃げてしまいます。「秋の夕陽に」と歌っているのんきなトンボですが、空を飛べる相手を捕まえるのは難しい。ブンナは、自分も羽があって飛べたらいいのに、と思います。大体、彼は他のカエルたちよりも高い場所にいるのが好きです。上から見下ろすということに、快感があるのでしょう。それは高慢さでもあり、またより広い視野を持ちたい、つまり広い世界を見たいという願望でもあります。近くに、高く伸びた椎の木があります。ブンナはその木のてっぺんに上ることにします。慎重に木をよじ登り、ついにてっぺんにのぼりつきます。木登りの様子はマイムにしました。一足ずつ、歌いながら手と上に差し伸べて、引き下ろす。と同時に、足を上げ下げします。上るタイミングのときに、手に体を引き上げる力、足に踏みしめる力を感じさせることが必要です。by 神澤和明
2019.06.20
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(4)
ブンナとその他のカエルたちは、若い人たちにふりました。「さざんか」から参加した人たちもここに入ってもらいました。彼らの技量と持ち味は把握してあります。個々で登場する動物たちは、シアター生駒で続けて舞台に出ている人たち中心にふりました。スズメは若い役なので、シアター若手の少女二人に。モズやネズミ、ヘビは、難しい演技になってくるので、経験が多い人にふりました。男性が少ないので、多くの役を女性が演じますが、さいわいに動物という設定なので、違和感がありません。幕開き。舞台前中央に、広めのエリアでサススポットが落ちます。その中に、ブンナがうずくまっています。子どもたちの声がマイクで入ります。カエルがガラスの中に閉じ込められている。そして、学校の理科の実験で解剖される運命であることがわかります。子どもたちはカエルは何も考えていない、のんきなものだと言って立ち去ります。子ガエルは立ち上がって、自分の名前はブンナだ、カエルだってものを考えるし、悩みだってある、と言います。そして、自分が住んでいた池の、のどかな日常を思い出します。これで明かりが舞台全体に広がり、平和な池の場面になります。ブンナが子どもに捕まえられるという設定は原作にはありません。脚色者の工夫です。先に述べたように、死が近くにあることを示すため、また彼が生きるために精一杯の努力をする様を描こうとしたのでしょう。読経の声がするので、ここが寺の庭だとわかります。のどかなコーラスに合わせて、カエルたちが動き回っています。平泳ぎで泳がしたり、ピョコピョコ跳ねたりです。和尚さんの声がして、パンのかけらが投げ込まれます。カエルたちは一度散らばって、それから寄ってきます。仲良く食べるんだよ、と和尚さんは説教めいたことを言います。親切な人のようですが、カエルたちは、人間は自分の都合の良いときだけ慈悲を示すんだと、人間の勝手を笑います。ブンナはパンに群がるみんなを尻目に、石の上で横になっています。箱の上や、脚立の上に上がらせました。それを見て、生意気な子だという年寄りカエルもいます。両親をヘビに殺された、かわいそうな孤児だという者もいます。これで、ブンナの身の上と、周りからの見られ方がわかります。ブンナはいつもひとり離れて行動しがちです。声を掛けてくれる子ガエルに対しても、ちょっと冷ややかです。彼は気取った感じで生意気な物言いをしますが、これは親を無くした寂しさと頼りなさの裏返しとして、でてくるのでしょう。by 神澤和明
2019.06.19
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(3)
ただ、「演劇ワークショップ」での上演は、予算も協力してくれるスタッフもほとんど無かったので、非常に簡略なつくりにしました。一辺が二尺ほどの立方体の箱を幾つも並べて場面を作りました。みんなが、カエルの色である緑のTシャツをそろえて、衣装にしました。歌もダンスもわたしが作りました。照明は、演劇祭にしたおかげで、経験のあるプロの方に手伝ってもらえました。公民館講座として行ったので、演劇経験が乏しい人が多いので、台詞も刈り込みました。また、ほぼ全員が女性です。良い舞台よりも、楽しい舞台を作ることを、このときは目指しました。ブンナは女子中学生にやってもらいました。よく頑張って、元気な少年を演じきりました。困ったことに、当日、モズ役の方の親戚にご不幸があり、残念ですが出演不能になってしまいました。仕方ありませんので、わたしが急遽、代役で舞台に出ました。裏の人間が舞台に出るとは、なんとも恥ずかしいことでした。「シアター生駒」の上演は、予算もスタッフもつけられたので、装置を組み、作曲は知人のプロに、振付は地元の舞踊家に、衣装も専門家に依頼しました。装置は、鉄骨で土台を組んで二重舞台を作りました。学校の文化祭で、野外ステージを学生たちが組んでいるのを見ていて、割合と簡単に組めると踏んでいたのですが、実際には大変な作業となり、スタッフに迷惑をかけました。作曲は、「創作歌曲」の活動(わたしは作詞と台本構成・演出を担当)をしていたときに、組んで作品作りをして下さっていた、すぐれたピアニスト兼作曲家に依頼しました。彼はPCを駆使して、楽しく歌い易いだけでなく、芝居にあった構成の曲を、何曲も書いてくれました。「シアター生駒」の『ブンナ』には、『頭痛肩こり』に出演していた劇団員に加えて、第一回公演に参加していた人たちも何人か戻ってきてくれました。また募集に応じた新人の人たちと、『真夏の夜の夢』でわたしの演出に触れた、大和高田市民劇団「さざんか」の若手たちも、参加してくれました。主要人物以外にも、多くのカエルたちが登場します。コーラスが必要な舞台ですから、多くの人の参加が必要です。また、劇団員を増やすという趣旨も、うまく達せられました。わたしの方針なのですが、主役をする人をなるべく固定しない、可能性をみるために新しい人に大きな役をふる、というキャスティングをしています。もちろん、稽古に積極的に参加出来るというのが必須条件ですが。このときも、新しく参加した、演技経験のほとんどない女性に、ブンナの役をふりました。わたしにとって、演技経験が乏しいことは、まったく気になりません。演技指導はわたしが得意とすることです。by 神澤和明
2019.06.18
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(2)
この作品は仏教思想が底に流れています。特に「死生観」です。「死」は恐ろしいことです。しかし、誰も逃れることができない宿命です。この作品は死がそばにあり、免れられないこと、そしてだから、死ぬまでは精一杯生きてゆくべきこと、自分の死が他の者の助けとなるなら、それは意味のある死であること、更に死は個の終わりであっても、全体として、命は続いてゆくこと。こうした考えが見えてきます。始まりの場面で、子どものトノサマガエルであるブンナは、ガラスの瓶の中に閉じ込められています。子どもたちは、明日の授業で「カエルの解剖」をするので、その実験材料にするために、彼を捕まえました。ブンナにとって既に、死はすぐ近くの現実的なものとして存在します。わたしたちにしても、死は確実にやって来ますし、案外と近くにあるのかもしれません。しかしそれに気づかず、或いは考えないようにして、死から遠いところにいると信じて暮らしています。閉じ込められたブンナの姿は、そんなわたしたちの「楽観」に、そうではないと言っているようです。芝居の中では、死は「トビ」の姿を借りて、常に存在を誇示しています。いや、姿は現しませんが、羽ばたきと鳴き声が迫ってきます。私的なことですが、わたしは十歳以前から、死をとても怖がっています。夜、寝床に入って、自分がやがて死ななければならないと考えると、とても怖く辛くなって、子どもの頃は、よく泣きそうになりました。こういう「死ぬのが怖い病」を患っている人は、結構いるようです。落語家の桂枝雀さんも、そうだったと聞きました。「死ぬのが怖い病」は、治しようがありません。死なずにすむことはできませんから。この病のポイントは、死そのものが怖いというよりも、死ぬと考えることが怖いのです。ですから、この病から逃れる方法は、死ぬと考えないことです。しかし、どうしてもすぐに、死を考えてしまう。そうであれば、この病から完全に逃れる方法は一つです。それは、逆説的ですが、死ぬことなのです。実際、そういう理由で自死する人もいるそうです。わたしの場合、今でも死を考えるととても怖くなりますが、子どもが生まれてから、少しましになりました。自分にかかわる新しい命が続いてゆくと考えることは、大きな慰めになります。また、宇宙のエネルギーの総量が一定だとして、新しい命が生まれるために古い命が消えなければならないのなら、自分の命がなくなるのも意義あることだと、考える様にもなりました。そうした考え方は、『ブンナ』に表されるものに共通しているように思います。この死生観を土台に、登場するそれぞれの動物たちの、死との向かい合い方の違いをはっきりさせて、どのように生きて死ぬかを観客に考えてもらいたい、そして生きていることのうれしさを歌やダンスにこめるということを、演出のコンセプトにしました。それは第一回も第二回も同じです。by 神澤和明
2019.06.17
-
『ブンナよ、木からおりてこい』(1)
水上勉原作の『ブンナよ、木から下りてこい』は音楽劇として二度、演出しています。いずれも小松幹生さんの脚色を使わせていただきました。わたしは演劇誌「テアトロ」によく書かせていただいていますが、書き始めたころに、小松さんが編集長をされていましたので、その縁でお願いしたら、すぐ許可をくださいました。一回目はアマチュアでの上演でしたので、無料で良いと言っていただきました。ありがたかったです。一回目の演出は、生駒市の生涯学習グループでの上演です。生駒市中央公民館から依頼されて、「演劇講座」を開講しました。名称を「演劇ワークショップ」としました。参加してきた人たちに、簡単な基礎訓練を指導した上で、『ブンナよ、木からおりてこい』をテクストとして実践的な勉強をしてゆきました。折角、練習をしてきたのだから、発表をしようと思って公民館長に相談したところ、大ホールを2日間自由に使ってくれて良い、と返事をもらいました。今は指定管理者によって監督されるホールになっています(名称たけまるホール)ので、こんなことは絶対にできませんが、当時は融通がきいたのです。自分たちのグループ発表だけに、大ホールを2日間使うのは、あまりにもったいない。折角のこの機会を利用して、奈良県下の他のグループに呼びかけて、「演劇祭」を開けないかと考え、4劇団が出演する「奈良アマチュア演劇祭」実現させました。二回目の演出は、「シアター生駒」の第三回公演です。『二十二夜待ち』と『彦市ばなし』で旗挙げ公演を行いましたが、第二回公演は熊本一演出で『頭痛肩こり樋口一葉』を上演しました。舞台は大変に良い出來でしたが、女性六人しかでない芝居です。旗挙げに参加した人たちの多くが劇団から抜けてしまいました。それで第三回公演は、大勢が出演できる芝居をすることにし、新たに劇団参加者を募集しました。それで、演出を担当するわたしが選んだのが、『ブンナよ、木からおりてこい』です。市民参加型公演の多くが「ミュージカル」風に歌やダンスをいれています。これは部分練習がしやすいし、また演技者に「楽しい」実感が得られやすいからだと思われます。芝居をして「楽しい」と感じるには、ある程度の技量が必要になります。しかし歌や、簡単なマスのダンスならそれほどの技量がなくてもすみます。カラオケや盆踊りを見れば、わかりますね。もちろんわたしが演出する以上、それなりのレベルの歌とダンスを求めます。ダンスには、演出家として口をだしました。緊迫感が不足していたので、倍テンポで踊らせました。そして、芝居をきっちりと。歌やダンスは「追加要素」であって、芝居ができていなければ話になりません。by 神澤和明
2019.06.15
-
『彦市ばなし』(9) 6/14
川に落ちて灰が流れてしまい、彦市の姿が天狗の子にも見えます。「や、姿ば現しよった。さあ、上がってけえ。ひでえ目にあわしてくるる」「わあ、灰がみんな流れてしもうた」「何、流れた? 蓑ば流してしもうたっか? すんなら、はよ取らにゃのうなってしまう。わーん」。「わーん」が可愛いです。隠れ蓑が川の中だと思って、天狗の子も飛び込みます。これから彦市と天狗の子の、川の中での追いかけっこが始まります。取っ組み合いよりも、逃げ回るのを追いかけるのが、視覚的にも良いです。能舞台で、狂言的に演じるなら、舞台がいきなり川の中の設定に変わっても、違和感はありません。劇場舞台なら、波幕でしょう。互いに、なるべく長い距離を動くこと、飛び込んで潜るとか、息継ぎのために上に顔を出すなど、上下の動きも入れます。わたしはしませんでしたが、波幕を出す場合、二人の間に「河童」が現れると、観客は大いに喜ぶでしょう。そこへ、殿さんがやって来ます。殿さんは彦市が、川の中に入って河童を捕まえようとしていると誤解して、頑張れ頑張れと、彦市を励まします。くたくたになった彦市を、天狗の子が殴りつけ、殿さんが扇を拡げてはやし立てているところで、幕が下ります。なんとも可笑しく、のどかで、本音が通る世界でのびのびと生きている人たちのエネルギーを感じるお芝居です。演技者も観客も一緒に楽しめる作品です。この芝居は、殿さんを演じる人によって、出來が変わります。いかにものどやかで、のほほんとした感じ、それでいて貫禄も感じさせたいですね。わたしの場合は、素晴らしい演技者に恵まれましたので、余計にそう感じています。狂言の場合は、先代の茂山千作師が、とても良い殿さんでした。『彦市ばなし』は、その少し後に富山県の利賀村で行われた、アマチュア演劇祭にもってゆきました。そこでは能舞台を使って上演しました。冒頭を、出演者たちによる盆踊りで始めて、舞台に一人残った人物が彦市になるという演出をとりました。彦市は、多くの民衆の一人を代表しているのだという意図です。また、最後は彦市と天狗の子が客席に降りて行き、殿さんが舞台中央で、ご機嫌でいる、という終わり方にしました。ありがたいことに、評判が良かったです。このときの音楽は、『二十二夜待ち』の「でんでらでん」の唄などと一緒に、PCを使って自分で作曲しました。民話劇はやはり苦手です。もう演出するつもりはありません。ただし、『夕鶴』なら、演出したいです。あれは戦後の創作劇の大傑作ですから。by 神澤和明
2019.06.14
-
『彦市ばなし』(8)
彦市は、隠れ蓑を焼いた灰を身体に塗って、見えなくなって登場します。「はあこらよかった。灰になっても神通力はいっちょん変わっとらん。……どうです、声はすれども姿へ見えずでっしゅうが?」。これは声だけ聞こえるというト書きになっていますが、どうもそれでは寂しい。それで、姿を出すことにしました。カッパのような、ビニールの薄い上着を着て、隠れ蓑の灰を塗ったつもりにしました。これで、観客に話しかけることが、素直に出来ます。姿が見えなくなった彦市は飲んだり食ったり、散々に悪さをします。脚本にはその場面はありませんが、舞台では演じました。何人かがご馳走やお酒をもって、舞台を横切る。そのご馳走やお酒を、彦市が盗んでしまいます。彦市よりも、盗まれる人たちの慌てぶりや、キョロキョロする演技が、彦市の姿が見えないことを示してくれます。散々に飲み食いして満腹した彦市は、そのまま木の下に寝転んで、いびきをかいて寝てしまいます。そこへ天狗の子がやってきます。今回は、起源が良いです。親天狗に褒められたからです。「あの天狗の面は、うちの死んだ爺さんに生き写しげな。その上大好物の鯨の肉ば取ってきたとは大手柄。隠れ蓑はまた替えのあるけんゆるしてやる」ということで、一件落着です。しかし天狗の子は急に怒り出します。「ばってん、ああ腹ん立つ。どうもこうもわたいは、彦市んやつが癇癪ぃ障ってたまらん」。自分をこどもだと思って、だまして馬鹿にした。そんな彦市に対して、プライドが許さないのです。子ども同士の意地のはりっこのようなものです。このままにしておいては、将来も彦市に軽んじられるかもしれません。どうあっても、彼を徹底的にやっつけてやらねば、天狗のメンツがたたないのです。彦市を捜し回っていると、いびきが聞こえます。でも、姿は見えません。ははあ、これは隠れ蓑を着て眠っているに違いない。天狗の子はいびきのするあたりに、ちかづいてゆきます。ここは手探りをする方が、観客に解りやすいでしょう。そして、彦市につまづきます。「やいやい誰か、人の寝とるところをば。……や、天狗の来た」。「やい彦市! 大ぬすど! どけぇおるか。蓑ば脱げ」。天狗の子は彦市を捕まえようとしますが、姿は見えない。彦市は酒が抜けていないから、動きが悪い。滑稽な取っ組み合いになります。そして追い詰められた彦市は、転がって、川の中にザンブリ。二重を組んでいるなら、川へはまるのは簡単です。そうで無ければ、一つは観客席におりる方法があります。ただ、これは観客から見えにくくなります。或いは、ここで舞台の前に波幕を拡げ、その中で動いて、川の中の様子を示す方法があります。by 神澤和明
2019.06.13
-
『彦市ばなし』(7)
こんなことを繰り返しているうちに、天狗の子がやって来ます。そして、鯨の肉を包んだ竹の皮が、隠れ蓑だと思って取り返そうと、こっそりと近づきます。すると、殿さんの腰に天狗の面がついているので、父親だと思ってびっくり。でも、よく見るとただのお面です。胸をなでおろし、天狗の子は竹の皮包みを狙います。この辺りは、天狗の子の動きの演技がポイントです。前の二人は釣に集中しているという感じで、少し動きを大きくして、滑稽みを出します。河童はいつまでも釣れません。おまけにそれが、自分が声を出したせいにされてしまう。殿さんはしびれをきらして、お城に帰ることにします。お前が一人で釣って、お城へもってこいと命令します。彦市は餌の鯨の肉をもらいます。更に、河童を釣ったご褒美に天狗の面を下さいとお願いし、まんまと両方をせしめます。殿さんが立ち去り、それを見送った彦市が、自分の智恵を自画自賛している間に、天狗の子はこっそりと近づき、竹の皮包みを取って、逃げようとします。それに気づいた彦市は、天狗の面を被って天狗の子を脅かします。天狗の子は、彦市が面を被っていることを知って居ます。それで、騙されたふりをして彦市に近づき、いきなりその面をつかんでもぎ取ると、「ぬしなんかに負くるもんか。さあ、蓑ば取り返した」と言って、風のように逃げて行きます。ト書きでは鼻をつかんでもぎとる、とありますが、こんな風にすると面を壊しやすいので、顎のところからすくいあげるようにして、ぬがせます。面は、紐で結んで固定するか、ゴム紐をつけておくと仕事が早いです。片手で持つやり方もあります。このときは、天狗の子が取る邪魔にならないところを持ちます。「やあ、やられた」と彦市は地団駄を踏みます。彼の自慢の智恵が、裏をかかれました。大きなショックです。昨夜の河童釣りからして、彼が自分で考えたことではなく、降りかかってきた難儀を、なんとか収拾してゆく、後手後手の成り行きになっている。どうも調子が良くないです。次の登場場面になるまでに、更に想定外がおきています。この場面の終わりも、彼は困りながら退場します。先の場面と違えるために、家に帰って早く思案をしようという気持ちで、足早に退場させます。少しあって、彦市がしおれて出て来ます。家に帰ったら、かかあが隠れ蓑を、汚い蓑があると思って、燃やしてしまっていたのです。この場面、前の場面の後に黒幕を下ろして、そこに彦市が出てくる場合は良いのですが、そうせずに、退場した彦市がすぐに出てくると、観客の感じとして、ちょっと変な感じがするかもしれません。短い音楽を入れて時間経過を感じさせるか、後の天狗の子の場面をここに持ってくると、うまく流れるでしょう。その場合、天狗の子はここで親天狗に褒められたことを話して、彦市に仕返しするために一度退場する、ということをします。by 神澤和明
2019.06.12
全665件 (665件中 1-50件目)