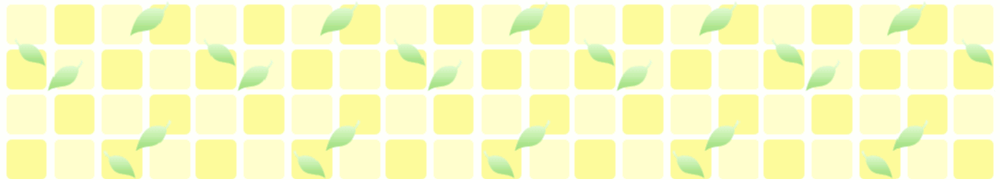[仕事] カテゴリの記事
全51件 (51件中 1-50件目)
-
社会福祉協議会の仕事で出会ったEさんと、ノーマライゼーション啓発事業のこと
もう、社会福祉協議会(通称「社協」)を退職して30年以上も経っている。当時の職場の人達も現職で働く人はいなくなったし、ここで少し具体的に書いても、個人情報に触れたり個人を特定しようとする人もいないだろうから、当時のことの思い出も書いてもいいかと思う。先日、一緒に息子のブドウ畑に行ってランチをしたのは、その頃の仲間である。彼女は先天性の二分脊椎症として生まれたため、幼い頃から手術などを繰り返し、入退院を繰り返しながら育ったようだ。「長生きはできない」と言われたらしいが、私が出会った頃の20代の彼女は、松葉杖を使いながら小中高とも一般の学校で学び、中学時代から習い始めたピアノをもっと学びたいと、本州の音楽系短大を卒業し、ピアノ教室を開こうとしている頃だった。その頃の私の仕事は、『ノーマライゼーション及びソーシャル・インクルージョン』の普及啓発と、障がい者の社会参加や福祉に関わるボランティアや青少年の育成を目指す事業としての「ふれあい広場」に取り組んでいた。まあ、現在でもこんな風に書いても何のことやらわからない人が多いだろうが、わけがわからない私が事業の企画や実行をしなくてはならない。何でこんなカタカナ言葉を羅列して「啓発事業」をしなくてはならないのかと頭を抱えてしまった。それでも、私の前職は「障害幼児の機能訓練」の指導員だった。だから、この様々なハンディを持つ子ども達と家族の取り巻く環境が、どれほど偏見に満ちていて生きづらい社会であるかということは身に染みていた。この子たちが将来、少しでも多くの人達に支えられ守られて生きてゆく社会をつくるためには、障害者への偏見や不都合な社会を変えていかなくてはならないことはわかっていた。だから、この仕事が「老若男女、障害の有無にかかわらず生きてゆける社会づくり運動」なのだと思うと、これこそが私のやりたいことだと思えたのだ。しかし、当時の当市の社会福祉協議会の活動に関わる人たちの中に、障碍当事者は勿論のこと、若者たちもほとんどいなかった。民生児童委員、老人クラブ、日赤奉仕団、遺族会、障害者団体はあったけれどそれは傷痍軍人の人達が主要メンバーだった。当時の全国社協は、ノーマライゼーションの理念の啓発普及に力を入れていたので、道社協の指定を受けて道内各市で「ふれあい広場事業」を開いていたのだが、私達の社協はそれを担当する職員が少ないということで、私が社協で仕事をすることになって1年も経たずにそれを引き受けなくてはならないことになっていた。つまり、とにかく職員が少ないのに事務仕事が沢山あって、障がい者についてもほとんど知識のない職員ばかりだったのだ。その中に、多少は障がい者の知識があると思われる私が入ったので、当然その担当は私になった。「みらいさん、この事業もう断れなくてやらなくちゃならないんだよ。何とかやってくれ」と、当時の事務局長に言われたのは、多分1月か2月。事業は次の年度に完了しなくてはならないという。事業の企画や実行は私は経験がないので、本当にどうなることかと不安だったけれど、それを断っては自分がここに勤めた意味がない。ということで、道内各地で開催された「ふれあい事業」の報告書などを読み比べ、予算がつく一年だけではなく次の活動につながるための取り組みを考えた。必須なのは、若い人たちが主役になるような取り組みだ。ということで、各福祉課系団体、ボランティア団体、福祉施設の職員などへ、「ふれあい広場事業」の実行委員として、若い人を推薦してもらうことが最初の仕事だった。その後、まあ色々とあったけれど、障害当事者、障害児親の会、福祉施設、障害者団体から、会長などの年長者ではなく、若い人に集まってもらえたのは本当にありがたかった。同時に、市内にある二つの高校に、「ふれあい広場のボランティアとして参加してほしい」と依頼した。実行委員会を発足する前に、その準備委員会としてこれらの若い人たちに集まってもらい、ノーマライゼーションのことや、この事業でやりたいことを理解してもらうことにした。コアになる人が、その願いをちゃんと理解していなくては、やはり単年度限りのものになりそうだったからだ。その会議の中で、私は何度も特に福祉施設の職員に話した。「この町で、障害を持つ人達への偏見が少しでも無くなり、障害者施設が地域に根差したものになるために、自分がやりたいと思う企画を考えてほしい」と。しかし、そのたびに私は彼らから言われた。「みらいさんは、どのような企画ならいいと思うのですか? 道社協の指定事業なら、マニュアルもあるでしょう?」「私は、マニュアルではなくて、皆さんがこの町で今やりたいことがやりたいのです。できれば、今年だけではなくて、来年も続けていける活動に取り組みたい」。もちろん、ヒントとしては各地のふれあい広場での取り組みの内容も伝えたはずだ。このやりとりは何度も続いたけれど、それでもやっとそれぞれからやってみたいことが出てきて、ふれあい事業の骨格ができた時に、やっと実行委員会を開くことができた。実行委員会にはできるだけ幅広い市民に参加してほしいと思ったので、市内の考えられるすべての団体に案内を送った。日赤奉仕団関係、女性団体、老人クラブや遺族会、商工会や学校やPTAなど、当時社協が把握している団体全てである。やっと実行委員会が発足したのは、多分秋になろうとする頃だった。それまでの間、道社協からは何度も電話があり、「説明に行きましょうか?」「年内に開催できますか?」などと心配されたが、私は「絶対に道社協のお仕着せ事業にはしたくない」と考えていたので、「大丈夫です。自分たちでやることが大事だと思うので、メインイベントには見に来て下さい」などと、失礼を承知で助っ人を断り続けていた。長くなってしまったが、その時に出会ったのが今回久しぶりに再会したEさんだった。Eさんについては、また別の日にもう少し書くことにする。
2024年09月30日
コメント(0)
-
西埜馬搬の仕事の紹介動画
先日のブログでご紹介した、西埜馬搬の仕事の紹介動画です。 【探訪】「イオルの森」優しく守る馬搬の力 凍てつく森のなか。チェーンソーの音が鳴りやみ、ナラの木が倒れると地響きと同時に雪煙が舞った。すぐ近くで草を食む馬はびくともしない。 「うちの馬たちは皆、素直で優しいですよ」と、北海道厚真町で馬を使って木材や荷物を運ぶ「馬搬」を営む西埜将世さん(43)は語る。 広葉樹が群生する「イオルの森」(北海道平取町二風谷地区)。「ゴー!」。西埜さんの声で馬が動き始めた。運搬する間伐材は、重さ約300~500㌔もあるが、雪道をものともせず仮置き場まで力強く運ぶ。 昭和40年代以降衰退していた馬搬が北の大地で息を吹き返している。重機と比べスピードでは圧倒的に劣るが、山の土壌を荒らすことなく、狭い木々の中もすり抜けることができるため環境に優しい。積雪時の方が木材が滑りやすく、馬に負担が掛かりにくいという。 「馬搬は森を傷つけず優れた木を成長させることができる」と、森の再生事業に携わる北海道科学大の岡村俊邦名誉教授(72)は話す。 「イオルの森」の「イオル」とはアイヌ語で「狩り場」の意。かつて森にはアイヌの人々の生活に欠かせないオヒョウの木が生い茂っていた。オヒョウからは樹皮の繊維を利用し、伝統ある「アットゥシ」(着物)が作られてきた。 現在、その木も開拓や開墾のため伐採され、わずかとなった。平成20年、平取町は、アイヌ文化の伝承と普及のため「イオル再生事業」を始めた。その一環として4年前から冬の間伐作業で馬搬が導入され、夏には植樹も行われる。未来に向けた森の保全に生かされている。 夏はブドウ畑で馬耕も行う西埜さん。「馬の力は侮れない。まだまだ活躍する現場はある」。寒い日も暑い日も、愛馬たちとともに自然との共生を目指していく。 (写真報道局 納冨康) 自然と動物と人間の優しく力強い関係と共生が、今の時代にこそ見直さなくてはいけないのではないでしょうか。自然や動物と触れ合う中で、子ども達は生き物として健全に育つような気がします。もちろん、様々な動植物との共生と相互作用がなくては、人間は生きることができないのです。
2024年02月12日
コメント(0)
-
旅立った布の絵本はカンボジアで活躍中
「旅立った布の絵本の今後が楽しみ」だったのだが、エファジャパンから下記の報告が動画とともに届いた。Facebookが見れる方は見てください。文章だけコピーしておきます。みなさん、こんにちは!事務局長の関です。13日夜にプノンペン入りし、乱立する高層ビルに見下ろされながら宿まで。15年前と比べ中間所得層(世帯所得5,000~34,999US$)は13%増、国民の半数弱を占めるようになったカンボジア。エファでとり組み始めた「障害児のためのライフスキルプロジェクト」の活動地は、首都から3時間ほど南下した南部カンポット州。30年前とさほど変わらぬ当時の農村の風景が広がっています。健康、教育、生活水準面で貧困程度と発生頻度を示した多次元貧困率は、国全体で35%、地方では40%以上。地方に暮らす人々の半数近くが、いまだ厳しい貧困状態の中に。今回は次年度のとり組みのためにパートナー団体と詰めた話を行うことが目的でしたが(対面はやはり違う!)、日に日に変化していく子どもたちと再会できたのが何よりでした。この間お世話になっている木村さん、ご友人の方々に託していただいた布絵本、大喜びです!これから広げていくデイジー図書は、デジタルによる情報アクセスを目指しますが、ぬくもりを通して伝えていくことができる世界も届けていきたい。貧しさの中にあっても、障害がある中でも自分の力で生き抜く力を身に着けていける社会を目指していきます。動画は、これとこれ。(これでちゃんと見られるのかちょっと不安…)Kさんが「簡単なものだけど…」と一か月足らずで作ってくれた「いないいないばあ」の布の絵本である。カンボジアで読み聞かせしてくれた人も子ども達も、布の絵本は初めてのようだったけれど、特に女性の方は子ども達の反応に合わせてのパフォーマンスがとても上手で、布の絵本を大人も子どももとても喜んで楽しんでくれていることが伝わってきた。カンボジアに届けてくれたエファジャパンの関さんが撮影してくれたのだと思うが、子ども達の様子に撮影者もを喜んでだろう、思わず漏れた笑い声が嬉しかった。私達はブックスタート会場でこのような絵本を赤ちゃんに読み聞かせてはいたが、学齢期の子ども達に見せたことはなかった。こんなに楽しんでくれるのだと思うと同時に、この反応は本当に障害を持つ子なのかと思い、エファジャパンの鎌倉さんに問い合わせると、「ポリオなどの障害や、発達障がい、知的障がいの子もいます」とのこと。あらためて、布の絵本の力を感じることが出来た。仲介してくれた人も鎌倉さんも「とても貴重なものをありがとう」と言ってくれている。私もKさんも、サンプルとしての布の絵本を送ったつもりなので、貴重品にはしてほしくない。布の絵本は、子ども達が触れてひっぱってほおずりして、使い方をその子なりに創造して楽しむことに意味があると思っている。だから私たちは、布の絵本は消耗品であってほしい。あの絵本をサンプルにして、カンボジアの人達がカンボジアの子ども達に合った絵本をどんどん作ってほしい。たとえば、動物にしてもカンボジアと日本ではなじみのものが違うだろう。描かれる花にしても、北海道とカンボジアでは違うことだろう。大切なのは、手に取る子どもが興味を持ち、それと本物をマッチングし、名前を知り、言葉を覚え、それによってコミュニケーションの枝葉を広げ、新しい世界への興味を広げていくことなのだ。私は布の絵本の活用については詳しいわけではない。しかし、障碍をもつ乳幼児たちが圧倒的に体験不足になるということはよく知っている。障がいにより動きが少なく、言葉も遅く、結果的にコミュニケーション不足になることにより、二次的な発達の遅れが必ず生じるのだ。その二次的障害を防ぐためにも、布の絵本はとても役に立つツールではないかとあらためて考えさせられた。エファジャパンの関係者の皆さん、そしてカンボジアの皆さん、頑張ってくださいね。北海道から心から応援しています。
2023年02月19日
コメント(0)
-
旅立った布の絵本の今後が楽しみ
先月「すべての子ども達に絵本を…エファジャパンと布の絵本のご紹介」のブログを書いたが、その後の話。そのブログではKさんに簡単な布絵本の制作依頼をしたと書いたが、その後Kさんから「体調が思わしくないし、手の調子が悪くて自信がない」との連絡があった。私よりも高齢の人なので、「それならば無理はしないでね。今まで作ってもらった絵本で提供してもらえないかどうか探してみますから」と伝えてあった。その後、やはり以前私が関わっていたブックスタートのサポート団体の代表に電話をして、一冊でも二冊でも提供してもらえないかとお願いした。実はこのブックスタートも、コロナ禍のために活動休止中で、二か月に一度の例会しか集まらないという。ということで、一月の例会に参加して事情を話して提供をお願いすることにした。今年に入り、Kさんから電話が来て、「少しでも作ってみようかと思い作り始めたら楽しくて、なんだか体調も良くなった。もう少しで簡単なものが作れそう」とのこと。ヤッター!の気持ちで、ボランティアグループの例会に出席して、布の絵本がカンボジアの障害児の教育支援に役立てるかもしれないと話すと、みなさん賛同してくれて、Kさんのグループが最後に提供してくれた布絵本がまだ会のロッカーに残っているので、それを寄付しようということになった。早速探してみると、四冊のうちの二冊が、障害児のために活用できそうだといただいてくる。次の日にはkさんから、「簡単なものだけど、できたよ」との連絡で、早速受け取りに行った。そのほかに、以前Kさんのお母さんが施設に入所していた頃に、施設で使ってもらっていた絵本をいただいた。Kさんは何冊も布の絵本を作り続けてきたが、全部様々な場所に旅立っていて手元にないので、自分自身の思い出として取っておくつもりだったそうだが、「私がしまっておいても、死んだときにはどうなるかわからない。それよりも、カンボジアの人達のお役に立てた方が嬉しい」とのことだった。ということで、五冊の布の絵本を早速エファジャパンに送った。Kさんの思いが、カンボジアの人達に届いて喜ばれますように。布の絵本と私の関りについては、下記のブログ参照。「布の絵本」なんだか、久しぶりに仕事をした気分である。
2023年01月22日
コメント(0)
-
すべての子ども達に絵本を…エファジャパンと布の絵本のご紹介
2022年04月05日に「布の絵本」というブログを書いた。その時に「カンボジアの障害児の図書館教育支援プロジェクト」がスタートするということを紹介したのだが、いよいよそれがエファジャパンという組織とカンボジアの教育省との連携で具体化されるようになってきたらしい。カンボジアでは内戦が続いて、国内の先生や文化活動をしている人たちの多くが虐殺され、戦後は残された子ども達の教育支援が課題だった。なにせ、学校はもとより先生も教材も何もないところからのスタートだったのだから、そん状況下では、障害を持つ子ども達のことは見向きもされなかっただろう。カンボジアの内戦が終わって約30年、やっと国内の教育体制も整いつつあり、障害児への教育にも目を向けることが出来るようになったようだ。 それで、また旧友からの情報で、障害を持つ子たちが使える「布の絵本」の現物がほしいとのことで、かつて市内で活動していた布の絵本作りのグループ代表だったKさんに電話をした。このグループは、約35年ほど活動を続けていたのだが、メンバーの高齢化で二年前に解散している。さらに、布の絵本は出来上がり次第に地域のニーズに応じて養護学級や図書館などに旅立つので、制作した人の手元には残ってはいない。だから、もしKさんがお元気でまだ製作ができるようなら、簡単な布の絵本を作ってもらえないかと思ったのだ。幸いにKさんはお元気だったので、私は勢い込んでお願いした。「今までは市内の子ども達のための絵本だったけれど、今度はカンボジアの子ども達のところに行くよ!これは国際ボランティア活動だよ! できれば作ってほしいのだけど」彼女もそれなりに高齢化し、若い頃のように手早く上手に作れないと迷っていたが、多少でもお役に立てるのならと引き受けて下さった。今まで、縁の下の力持ちのように、目立つことなくコツコツと活動を続けてきた経験が、カンボジアの障害を持つ子ども達やお母さん達、そして先生たちの参考になればとても嬉しい。
2022年12月09日
コメント(0)
-
布の絵本
カンボジアの教育支援を、絵本を通して行ってきた旧友からメールが届いた。「カンボジアの障害児の図書館教育支援プロジェクト」をスタートすることになり、日本にある教材となりそうな図書(子どもの本・絵本)を参考にしようとしているので、何かあったら教えてほしいとのことだった。カンボジアでも、障害児の図書館教育支援に取り組める段階に入ったのだなと嬉しく思った。現在のウクライナ問題でもわかるように、戦争状態になった時に一番先に切り捨てられるのは弱者だ。ハンディを持つ人や子ども達は、どの国でもなかなか目を止めてもらえない。この日本でだって、私の20代の頃は、重度の障害児は就学免除や猶予が当たり前であり、かれらにも教育を受ける権利があるのだとは、親でも思っていなかった。さらに、障害を持つ子への偏見や世間体を恐れて、障害を持つ子がいることを隠す傾向も強かった。今でもその傾向は残っているとは思うが、かつての頃よりは随分開かれてきたと思っている。話を戻すが、私の一番最初の仕事は障害幼児の療育指導で、その仕事を辞めてから次についた仕事は「社会福祉協議会職員」だった。その仕事の中で、ハンディを持つ人達や子どもたち、その保護者とも関わるようになり、市民ボランティアと一緒になって色々な仕事をすることになった。「布の絵本作り」のボランティアグループの発足に関わったことや、絵本に点字の翻訳シールを貼るボランティア達と関わったことなど、考えてみれば随分先駆的なことだったのかもしれないと思う。彼女とのメールのやりとりで色々と芋づる式に思い出すことがあり、その内容をブログにまとめておくことにした。最初の仕事が様々な障碍を持つ学齢前の乳幼児との関わりだったため、社協職員となってからも前職の時に出会ったお母さんたちと関わる機会があった。その頃には、身体障害や精神障害・知的障害の親の会のメンバーと、福祉活動のお世話係のような社協職員としてのお付き合いになった。その頃、一人の自閉症の子を持つお母さんが日常生活の大変さの中でこんな話をしてくれた。「うちの子はね、少しもじっとしていないでしょ。絵本を読んだって聞いているんだかどうかわからないんだけれど、とにかく絵本をすぐに破いちゃうの。かじったり投げたりして絵本がすぐにダメになっちゃう。でも、うちの子は興味のないことには見向きもしないから、きっと興味はあるんだと思う。どんなに乱暴に扱っても破れない絵本があったらいいんだけど」それを聞いた時に、私の脳裏に「ふきのとう文庫」の布の絵本が浮かんだ。札幌で、障害を持つ子ども達のために布の絵本を作っているというボランティア団体のことを聞いていたのだ。しかし、実際に手に取って見たこともないし、簡単に地方の人が借りられるとも思わなかったので、そんな絵本が気軽に利用できればいいけどと思っただけであった。その後、先輩職員にそんな話をすると、「共同募金の配分申請をしたら材料費などは確保できると思う。制作できるボランティアがいればいいんだけど」という。それで二人で色々相談して、ふきのとう文庫の人に講師になってもらって「布の絵本作り講習会」を企画することにした。その時に参加してくれた人に趣旨を説明して、ボランティアグループを立ち上げたらいいのではないかということになった。しかし、「これは、貴女が言い出しっぺだから、企画や申請手続き、講習会の手配などもあなたがやってね」と言われてしまった。私はそれまで事務仕事はほとんどしたことがない。しかし、社協職員となったからには、今後このような仕事をこなさなくてはならないということはわかりつつあったので、不安ではあったが頑張ることにした。結果的にはこの講習会から布の絵本作りグループが誕生し、その後30年以上も市内のハンディのある子ども達のために、絵本だけではなく小中学校の養護学級の教材的なものを作り続けてくれた。私自身は講習会で簡単な布のサイコロに挑戦したのだが、あまりに自分が不器用なことにガックリして、早々に制作は諦めてボランティア活動の支援の仕事に徹することにしたのだ。私が社協職員になって一番驚いたことは、地域が様々な人が助け合って成り立っているということであった。何をいまさらという感じではあるが、当時はまだボランティアという言葉も定着しておらず「奉仕活動」と言われていた。日本赤十字奉仕団をはじめとして、その関連団体として点訳奉仕団やスキーパトロール奉仕団、やがて朗読奉仕団や救急奉仕団なども当市でも活動をするようになったと思う。【参考】特殊赤十字奉仕団そのほかにも、町内会、婦人団体、老人クラブ、ボーイスカウト、衛生団体、防犯協会、消防団等々、市民が自治活動に参加していることのいかに多いことか。恥ずかしながら私はそれまでどの活動にも参加したことはなく、こんなにたくさんの組織があることにまず驚いたのだが、気付けばそのメンバーのほとんどは中高年である。若い人が社協活動に関わっているグループはほとんどいなかった。だから、事務所に来る人はほとんど高齢者であり、たとえば「福祉大会」などを開催しても、準備をするのはみんなお年寄りだし、何より私は同世代の仲間と言える人がいないことがとても寂しかった。そんな状況の中でスタートした布の絵本作りのグループは、私と同世代の人も何人もいた。皆さん手先が器用で、毎週一回みんなとおしゃべりしながら布絵本を作るのを楽しみに参加してくれたし、私もその人たちとお話しするのは楽しかった。前職で出会った障害を持つ子のお母さん達とのつなぎ役をできることも嬉しかった。以前にもブログで書いたが、障害幼児の療育指導員を逃げるようにやめたことが、私の罪悪感にもなっていて、このような形でお母さんや子ども達の役に立てるのが嬉しかったのだ。この時の経験が、その後にノーマライゼーション啓発事業に取り組む大きなヒントをくれた。それは、どんな福祉活動やボランティア活動も、それがスムーズに動き出すためには、明確なニーズがあって、それを手助けしたいという協力者の強い気持ちがとても大切だということだ。社協で働き始めて知ったことだが、当時の社協活動は従来の「奉仕活動的」な継続事業を、毎年滞りなく続けることがメインだった。その頃は高度成長期でもあり、毎年の赤い羽根募金や歳末助け合い募金も順調すぎるほどに集まる時代であった。しかし、赤い羽根募金の配分金は、地元の社協を通して基本的な配分がされて事業に活用はされるけれど、新しい福祉活動に取り組まない限り、ほとんどは全道・全国的な広域活動に使われることになっている。はっきりした割合は覚えていないが、例えば1000万円集めても、地元には4割程度しか使われないという感じだ。私は、せっかく沢山の市民が街頭募金に立ったり、企業や商店を回って寄付を集めてくださるのに、地元で使われる割合が少ないことに驚いた。布の絵本作りは、新しいボランティア活動の推進ということで、金額は忘れたが講演会の開催費や布の絵本の材料費などを赤い羽根募金から配分してもらってスタートした。その後も継続的な活動の定着のために何年も共同募金配分金を財源にして続けることが出来たのだ。それに味をしめた私は、その後も色々な事業を企画したりした。その中で中心を占めていたのが、若いボランティアの育成とノーマライゼーションの啓発事業を道の社協も力を入れていたので、それに関する事業は助成金を獲得しやすく、毎年、北海道の助成事業や、共同募金の配分金要綱などを真剣に検討して、地元で活用できそうな事業を考え続けることになった。もちろん、私一人の知恵ではどうしようもないので、近隣の社協活動を参考にしたり、道社協や他市の社協職員に相談したり、少しずつつながりが出来てきた市内の福祉施設の職員に意見を聞きながらのことだった。その経緯や苦労話は布の絵本と少し離れてしまうので割愛するが、とにかく「布の絵本作りボランティア」の育成が私にとって社協職員としてのスタートのきっかけになったことだけは確かである。ちなみに、布の絵本は障害を持つ子も絵本を楽しめるようにと、親やボランティアが造り始めたのがスタートだと思う。障害と言ってもその子によって様々で、大きく分けると身体障害、知的障害、視覚障害、聴覚障害、自閉症的な障害などがあり、紙媒体の絵本ではなかなかその子の意志で楽しめないということがある。今は、「バリアフリー絵本」と呼ばれていることを、最初にメールをくれた彼女とのやりとりで知った。興味のある方はご覧になってください。
2022年04月05日
コメント(2)
-
パラリンピック
障害を持つ人達のスポーツに出会ったのは、30代後半の頃だった。当時はまだ、スポーツ用の車椅子も日本国内では手に入れることが出来ない状態で、ノーマライゼーション運動に仕事で関わった頃に障碍者スポーツにも関心を持つようになり、日本の現実も知った。具体的には、車いすマラソン、車いすアーチェリーをやっている人が市内にいたので、その人たちを通して色々な出会いや学びがあったのだ。2002年に「第6回DPI(障害者インターナショナル)世界会議札幌大会」が開催された時は、個人的にではあるが、車いすを使用している人のボランティアとして大会に参加し、世界中の障害を持つ人達と出会う機会もあった。初めて車椅子マラソンのパイオニアであるMさんと出会ってから、すでに35年は経っている。そんな経験を持つ私は、パラリンピックには色々な思いがあるし、日本で開催される今回の大会にはとても期待していた。なのに、このコロナ禍の拡大である。本音としては、オリンピックは中止してパラリンピックの時には「安心・安全な大会」にしてほしいと願うくらいだった。最悪は、オリンピックは開催しても、パラリンピックは中止となることだった。本当に本当に残念な思いがあるのだが、それでもパラリンピックは何とか開催された。開会式は、オリンピックよりはメッセージ性には雲泥の差があるように感じた。もちろん、パラリンピック開会式が良かったということだ。昨日から競技が始まったが、それぞれの競技を見ながら感動している。人間の可能性や底力を、心から感じることが出来る。開催期間中、多分私は常にアンビバレンツな思いを抱き続けるだろう。しかしそもそも、人間はそのような存在であり、運・不運や様々な理不尽の中で生きなくてはならないものだ。その中でも、自分自身の可能性や願いを追い求めることが出来るし、周囲の人たちと上手につながり、必要な助けを求めることが出来れば、必ず道は開けるものだということを、パラアスリートたちはその笑顔で教えてくれるような気がしている。かつて出会ったハンディを持つ人の中には、すでにあちらの世界に旅立った人も何人もいる。でも、かれらの拓いた道を歩み続けている後輩たちが沢山いて、それを支える人たちも確実に増えているはずだ。残念だけれど、あの頃願った「障害の有無にかかわらず、差別なく同じ権利を持ち、対等に支えあえる社会」にはまだまだだけど、その願いを持つ人達が増えることで良い方向に向かっていると信じたい。このパラリンピックが、その推進力になることを心から願っている。
2021年08月26日
コメント(0)
-
こんな生き方もあります「馬搬(ばはん)日和」
こんな仕事をしている人がいます。「仕事はゼロ。これから増えていくしかない」――昭和に消えた「馬搬」で起業した夫、生活が不安な妻山田裕一郎(フィルムメーカー)「馬搬(ばはん)の仕事は、今はゼロだから、これから増えていくしかない。もし増えなかったら、他の仕事をしてでも稼いでいく」。北海道で、「馬搬」という仕事を始めた男性がいる。「馬搬」とは、馬の力を利用して、山中で伐採した木を運び出す作業だ。かつては日本全国で行われていたが、トラクターやブルドーザーなど大型機械が使われるようになり、その姿は消えていった。なぜ今、馬搬で起業することを決心したのだろうか。「森に優しい。こんな林業もありなんだ」。背景には、山林の自然環境や生態系の保全への思いがあった。●「自然に優しい」馬搬にひかれて「馬は一度に300〜500キロの丸太を運ぶことができます。移動する距離は短い時は数十メートル、長い時には300メートルくらい。山の傾斜や地面の状態、移動する距離に応じて、丸太の重さを変えていきます」そう話すのは、西埜将世さん(40歳)。2017年から妻と2人の娘とともに北海道厚真町で暮らし、「西埜馬搬」を営んでいる。馬搬は、馬の力を利用して、山中で伐採した木を運び出す作業のこと。手綱は補助として使い、「行け」「バック」といった言葉、声のトーン、態度によって馬を操り、大きな丸太をひかせる。人と馬との信頼関係がとても大切な仕事だ。馬搬に詳しい岩手大学森林科学科の立川史郎教授によると、馬搬は明治時代に入ってから馬産地である北日本を中心に盛んに行われるようになったという。第二次世界大戦頃まで続いていたが、林業の機械化が始まった昭和30年頃に転機を迎える。トラクターやブルドーザーなどの大型機械が林業で使われるようになり、昭和40年以降には急速に衰退していった。「危険な仕事であっても、かつて馬搬が盛んだったのは稼げる仕事だったからです」と一般社団法人馬搬振興会の代表理事である岩間敬さんは語る。日本の森は斜面が多い上に、丸太を運ぶ馬が暴れることもあるため、危険でお金にならない馬搬は姿を消していった。馬搬に関する論文を執筆し、2019年に日本森林利用学会で優秀賞を受賞した坂野昇平さんは、こう言う。「馬搬を生業としていた人は、平成初期にはほとんどいなくなりました。現在、馬搬ができる人は多く見積もっても全国に十数人しかいないです。かつてのように林業家として馬搬を生業にしているのは、西埜さんと馬搬振興会の岩間さんの2人だけだと思います。」西埜さんはなぜ、馬搬にひかれたのだろうか。「馬が森で働く姿を見に、たくさんの人が来てくれるんです。子どもたちの驚く声や笑い声が聞こえるなかで働くのはいいなと思って」そう西埜さんは話す。馬搬は、自然保護や生態系の保全を可能にするという。現在の林業では、大型の林業機械が使われている。現場の山林には、重機が移動する作業道をつくらなければならない。そのため、多くの木が伐採され、山の斜面が削られる。重機が何度もその道を通るので、土は重みで締め付けられ、跡も残る。一方、馬は、どんな場所でも移動でき、険しい斜面でも自由に昇り降りできる。馬のフンは自然の循環のなかに組み込まれ、もちろん排気ガスは出ない。馬搬は圧倒的に自然に優しいのだ。西埜さんは、大学卒業後、ネイチャーセンターで自然体験活動を教える仕事に従事していた。結婚を機に、林業会社に転職。そこで壁にぶつかった。重機を使ってどんどん木を切り、工事現場のような騒音を立てる林業現場と、会社での人間関係に馴染めなかったのだ。3年間働いたものの、仕事をやめたい思いが高まり、眠れなくなっていった。その頃に、たまたまYouTubeで目にしたのが馬搬だった。静かな森の中で、人と馬が一緒に働く「森に優しい」光景を見て、「こんな林業もありなんだ」と思った。2011年3月、西埜さんは林業会社を退職し、観光牧場で馬搬の仕事を始めた。●馬搬で家族は生活していけるのか観光牧場では6年ほど働いたが、経営体制の変化で雇用体系が何度も変わった。「これまでのように給料は出ないから」と言われ、馬搬で独立することを考え始める。「馬搬の仕事は、今はゼロなんだから、これから増えていくしかない。もし増えなかったら、他の仕事をしてでも稼いでいこう」そう西埜さんは思った。林業会社から観光牧場への転職、観光牧場の退職、どちらの節目の時も、妻は臨月を迎えていた。妻の朋子さんは、出産を控えたタイミングでいつも収入がなくなる夫に不安を覚えた。朋子さんは言う。「(夫は)『何とかなるよ』って。『今までだって何とかなってきたでしょう?』。『いや、私が何とかしてきたんだよ』って。その時は両方の親に『もうダメかも』と初めて相談しましたね」西埜さんにもプランがなかったわけではない。知人の紹介で応募した北海道厚真町の起業型地域おこし協力隊に、馬搬で起業を目指す西埜さんが選ばれたのだ。ハスカップが名産の厚真町は人口4,400人ほどの小さな町。厚真町に移住して、厚真町で起業することを条件に、事業の土台ができるまでの3年間、経済的な支援が得られることになった。2017年、そうして西埜さん一家は、北海道の大沼から厚真町に引っ越した。仕事のパートナーとして、ばん馬の「カップ」を購入。カップはばんえい競馬の能力試験を受けていたが、落第。熊本で馬刺しになる運命だったが、西埜家に買われて、馬搬の馬となった。値段は170万円。馬肉の値段を元に計算されていた。西埜さんは、カップのトレーニングや、生活環境の整備に時間を費やした。「馬が怪我や病気を教えてくれるわけではないので、こちらから気がついてあげないといけない」そう西埜さんは言う。機械であれば故障したパーツを新しいものに取り替えれば修理することができるが、生き物の場合にはそうはいかない。カップの怪我や病気は、仕事上の大きなリスクだ。一般的な林業のように、搬出した木材の総量でその対価を決めると、作業効率の悪い馬搬では利益を生むことができない。環境問題への意識が高く、馬搬の価値を理解した相手との仕事でなければ、仕事として続けていくことは難しい。西埜さんは言う。「機械と比べるとはるかに効率の悪いことをやっているわけだから、ただ木材の搬出というだけではなく、環境に配慮した森づくりをしたいという理由で仕事を依頼してくれていると思う」現在、馬搬を依頼する企業や行政は、山林の自然環境や生態系の保全することを第一と考え、豊かな森を次の世代に残していくことに価値を見出している。例えば、アイヌ文化の発信地の一つ、北海道平取町は、森の再生プロジェクトに馬搬を活用しはじめた。シマフクロウは、平取町周辺の森に生息し、村の守り神として崇められてきた。しかし、1970年頃にはその姿を見られなくなっている。高度経済成長期の森林伐採で、生息環境を奪われたからだ。シマフクロウが棲む、かつてあった豊かな生態系の森を再生させるプロジェクトには、間伐材の搬出も重要な作業となる。そこで馬搬が使われているのだ。環境問題に対する意識の高まりによって、馬搬の可能性も広がっていく。●地震で家が半壊。これからの西埜家は?移住して1年半が過ぎた2018年9月、北海道胆振東部地震が発生する。厚真町は最大震度7を記録。家族は怪我もなく無事だったが、暮らしていた築50年の家が半壊した。西埜家は、現在も厚真町から貸し出されたトレーラーハウスで暮らしている。夫の仕事に不安を感じていた朋子さんにとって、この地震は転機となった。「家がものすごく揺れた時、いつものんびりしている夫が『家にいたら危ないから外に出よう』と言って、まだ薄暗いなかでテントを張って、火を起こし始めたんです。この人についていけば、生き延びられるんだって、その時は思いました。今ある幸せに感謝してついていこうと思って、不安や不満が少し消えたような気がします」地域おこし協力隊での3年間の任期が終わり、2020年からは西埜馬搬は独り立ちした。子どもたちも、小学5年生と2年生。「馬を飼うのも楽しいし、いい仕事だと思う」と次女は言う。馬搬の仕事がない時には、植林や下刈といった造林作業、森林調査、ワイン園の馬耕など、さまざまな仕事をしている。どんなことでも断らずに何でもやる夫のことを、妻は今では「尊敬している」と言う。4年が経った今、西埜さんはこう語る。「まだ不安定ではあるけど、仕事は少しずつ増えてきました。馬と一緒に働くことで、一つの家族の生活が成り立つんだ、って周りの人に思ってもらえたらいい。このまま馬搬という仕事をずっと続けていきたいと思っています」今年の12月には、トレーラーハウスを返さなければいけない。カップが運んできた木を使って、新しい家を建てるのが今の目標だ。西埜さんのことは、個人的に以前から知っている。実は、私の旧知の知人の息子さんなのだ。随分前にその知人と会う機会があり、「みらいさんの息子さん、新規就農でワイン用ブドウ作っているんだって?実は、うちの息子も馬で木材伐採する仕事始めたのさー」と言っていた。「お互いに変わった息子育てちゃったね。きっとお金には縁のない一生になるね」などと、励ましあうのか慰めあうのかわからない会話をした。あれから数年が経ち、彼も随分頑張って仕事を開拓してきたようだ。実は私は、農業以上に馬搬で生計を立てるのは大変だろうと思って心配してきた。それでも「何とかなってきたし、何とかなるよ」という彼の言葉は頼もしい。もしも無理なら、どんな仕事をしても働いて家族を養っていくのだという、静かな覚悟が彼にはある。そして何よりも、自然や動物と共に生きることが幸せなのだという信念がある。そのような環境で育つ子どもには、心の豊かさが間違いなく育っている。この短い映像の中にそれが確信できる。彼の奥さんも大したものだ。どれほど不安があったかもしれないのに、あの穏やかさと温かさはどうだ。地震の時に「この人についていけば生き延びれると思った」と語る彼女の瞳には、人として生き物としての彼への信頼に満ちている。現代人が忘れかけている輝きがこの家族にはある。ぜひ多くの人に見てもらって、何かを感じてほしいと思う。
2021年05月09日
コメント(2)
-
かつての若者に「頑張って!」、そして自分に「良かったね」
夫が役員をしている特別養護老人ホームの事務長を辞して、新しい福祉事業に取り組むというY氏が挨拶に来た。実は彼とは、私が仕事をしていたころに出会っている。当時の私は、高校生のボランティア活動を推進する仕事をしていて、地域や福祉施設、中学生や高校生を巻き込んだ地域活動を根付かせようとしていた。仕事をしている人や高校生などと話し合いや活動をするのだから、当然仕事は休日や時間外となり、まだ私の子供たちは中高生であったから、まさに髪振り乱したように必死で仕事をしていた。しかし、意欲のある若い施設職員や、中高校生や大学生と様々なことを語り合い、彼らが障害者やお年寄りへのボランティア活動の中から様々なことを面白いように吸収し、企画などを思い切って任せたりすると目覚ましい成長をすることを目の当たりにして、喜びややりがいを感じていた。彼はボランティア活動をするなかで将来の仕事に「福祉」を考えるようになり、大学卒業後は病院や施設勤務を経て、現在の老人ホームで働くに至っていた。その間に私は退職し、成り行きのままに地域活動やボランティア活動に携わり、夫も退職後は地域活動や福祉団体の役員や、施設を運営する福祉法人の役員になって現在に至っている。そんな経緯もあり、今回訪れた彼とは、私とも夫とも縁があるのだ。私は当時の若者たちとは、数名と年賀状のやりとりや偶然に会ったりすることはあるが、それ以上の深い付き合いはない。それでも現在はFacebookなどで彼らの動向を知ることもでき、元気でやっていることを知る時にはなんだか嬉しくなる。彼から当時の仲間達のことや、次の仕事のことなどを聞くにつけ、あの頃蒔いた種が育ち実っていることを感じて感慨深いものがあった。私がその仕事をすることになった時、初任者研修の時に大学の先生が言った言葉が忘れられない。「あなたたちがこれから働く福祉の畑は、砂漠に種を蒔くようなものです。種を蒔き、水をやり一所懸命に世話をしても枯れてしまうかもしれない。それでも諦めずに種を蒔き、水をやり続けてください。それがいつか芽を出し花を咲かせ、砂漠が緑になることを信じて」正確には覚えていないが、そのようなことだった。私はその言葉を時々思い出しながら仕事をしたが、自分自身が疲れてしおれてしまい、新鮮な空気や水や栄養を求めて退職し、慶應通信に入学した。そして、まさに自分の乾ききった細胞に水分が満たされるように思いながら卒業し、並行して地域福祉活動を推進する側から活動する立場になった。その経験から、彼が新しい仕事に向かおうとする気持ちがとてもよくわかる。ある意味では、安定した収入の場から未知な仕事に向かうわけだから、新たな苦労も多いだろう。それでも彼は、かつて初めてお年寄りや障碍者に出会った頃の思いに立ち返ろうとしている。それがとても嬉しかった。「高校時代に出会った人たちの影響は大きいです。良くも悪くもですが」と彼は言った。私は教育者ではないけれど、先日恩師と教え子たちの展覧会で感じたことを思い出した。人は人によって影響を受け、学び、自分を育て、生きる道を探してゆくのだ。あの時に彼が出会った大人たちは、チャレンジャーばかりだった。自分なりの福祉観、人間観、福祉社会への理想を求め、旧態依然とした「保護し恵む」というような福祉観や奉仕活動ではなく、共に活動しながら理解しあい支えあい学びあう「共生社会」を模索していた。その種がここに生きていると感じて、かつての自分自身に「良かったね」と言ってやりたい気持ちである。彼もすでに中年に近い年齢。でも、まだまだチャレンジが出来る年齢だ。今の気持ちを大切にして頑張ってほしいと願っている。
2019年06月29日
コメント(2)
-
「こんな夜更けにバナナかよ」で思い出したこと
「こんな夜更けにバナナかよ」の映画が公開されている。主人公の鹿野靖明さん(故人)を演じているのが、北海道出身俳優の大泉洋ということで多くの人が劇場に足を運んでいるようだ。しかし、私はまた見ていない。誰かに誘われたら観に行くかもしれないが、まだその予定はない。でも、できるだけ多くの人に見てもらいたいと思っている。彼の名前を知ったのは、ずいぶん昔のことのように思う。彼が所属していた「札幌いちご会」の活動を知り、衝撃と感動を受けたのである。そういえば、はっきりとは覚えていないが、それより以前に「青い芝の会」という脳性麻痺者を中心とする会の集会にも行ったことがある。当時の私は、小さな心身障害児訓練室の指導員であった。私が関わっている障害児は学齢前だったが、やがて彼らも成長し大人になる。その子たちの将来のことを思うと、現在障害を持つ人たちがどのように暮らしているのかを知りたかったのだ。とにかく、私には決定的に知識や経験が不足していたから、そのような集まりにはできるだけ出かけていたような気がする。そんなこともあり、「青い芝の会」や「札幌いちご会」の集まりにも顔を出したりしていた。その当時、まだ重度の障害児は「就学免除」がされていて、公立小学校ではよほど軽度でなければ義務教育さえ受けられなかった。重度のハンディを抱えて生まれた子どもたちは、親が頑張れる間は在宅で家族と暮らせるけれど、将来は施設に入所して生涯を終える道しか想像できなかった時代だ。だから、「この子ができるだけ早く施設で馴染めるようにすることが、幸せにつながる」と思い、学齢時期になった頃に施設に入所させるのが珍しくなかった。私自身も、「重度の障害を持つ人は最終的には施設で暮らす」という発想で、ハンディを持つ子や保護者と向き合っていた。そんな私は、障害者自身の集まりに行って本当に驚いた。そのような会では、障害を持つ人(多分脳性麻痺)が「これから自立生活に向けて闘う!」などと発言していた。言語障害を持つ人の言葉は聞き取りにくかったけれど、叫ぶように全身で発言する姿は、「私たちだって人間らしく生きたい。自分の意志で生きたい」という魂の叫びのようだった。そんな発言を聞きながら、私は感動と共に複雑な気持ちも抱いていたと思う。「できるだけ他人に迷惑をかけないで生きる」ことが人としての道のように考える日本社会において、彼らの主張は「人の世話をあてにしながら、自分の思い通りに生きたい」という、わがままのように感じられるということだ。一言でいえば、それまでの障碍者観をひっくり返すようなことにもなり、ご本人たちもそれを十分自覚しながら、そんな世間に戦いを挑むような気負いが感じられた。私はなぜ彼らに感動したかと言えば、冷たい世間の目に負けずに自分の気持ちをはっきりと表明し、かつ行動しようというその勇気にであった。それまで、先天性障害や病気や事故で障害を持つようになった人たちは、社会で発言することは少なかった。発言しているのは、戦争で傷痍軍人になった人たちくらいで、当時の障害者団体はそのような人たちの集まりだったように思う。障害を持つ人たちへの偏見も、今とは比べられぬほど強かったのではないか。私自身、障害を持つ人たちを対等な人間として見ているというよりは、「気の毒な人。お世話をしてあげなくてはならぬ人」という見方だったと思うし、自分が我慢していることをその人たちが主張したら「わがままだ」と感じていたはずだ。しかし、彼らの発言を聞いていると、「わがままというより、当然の願いだ」と私には感じられるようになったのだ。しかし、同行した障害児父母の会の人は、「あの人たちに批判的な障害者もいるんだよね」とも言っていた。当時の私には、多少はその批判も上記のことから理解も出来た。つまり、それまで是としてきた「障害者としての生き方モデル」を否定しているようにも感じられるからだ。詳細は記憶してはいないが、これからのいちご会の道のりは「山あり谷あり、波乱万丈だろう」と思い、どこまで頑張れるだろうかと少し危惧したような気がする。しかし、いちご会の人たちは強かった。いちご会の中心メンバーとして今も頑張っている小山内美智子さんがいる。最初に彼女を知った時から、私は彼女のパワーに圧倒された。私には決定的に欠けている積極性や明るさがあった。脳性麻痺なので言語障害もあり、顔をゆがめながらも一所懸命に話すのだが、その笑顔はとても魅力的だった。私は、自分が関わっている何人もの脳性麻痺の子どもたちを思い浮かべ、ハンディはあってもそれを自分の個性として、堂々と生きて行ける、彼女のような人になってほしいと思った。いちご会のメンバーは、協力者と共に次々と新しい取り組みをはじめ、社会の偏見という壁をブルドーザーのように打ち壊していったという印象だ。その後私は、結婚や子育てと仕事に精一杯で、あまり彼女たちの活動を応援する力になることはできなかったが、障がい者関連の大会等で彼らの姿を見ることがあったし、その中に鹿野さんもいたと思う。彼らの活動は、多くのハンディを持つ人たちに勇気を与えたと思うし、ボランティアや支援者として関わる人たちに、本当に様々な学びの機会を与えてくれてきたと思う。直接関わってはいない私も、彼らの行動力、組織力、周りの人たちを巻き込む信念など、常に考えさせられて来た。きっと、「こんな夜更けにバナナかよ」も、多くの人に様々なことを感じさせるものだろうと思う。小山内さんは今どうしてるかなと検索したら、彼女のブログがありました。ぜひ読んでみてください。小山内美智子のブログ息子さんの大地君も結婚したんですね。私が仕事をしている頃、福祉関係の大会や集会で、元気な大地君がいつも小山内さんのそばにいたことを思い出しました。彼女が子どもを産むと知った時、正直なところとても複雑な気持ちになりました。小山内さんが恋をして子どもを産みたいと思うのは理解できる。でも、子どもにとってはどうなのだろうと。私のその時の思いは、まったく杞憂でした。多くの人に支えられ、愛されて育った大地さんは、本当に素晴らしい若者になりました。きっと小山内さんは、子どもにとって多くの人に愛され、可愛がられることが子育てに一番大切なことだと確信していたのでしょうね。あの時の私の危惧を、今の私は恥じています。
2019年01月19日
コメント(0)
-
外国人労働者受け入れ問題について
このことについても、私自身の今の気持ちを少し書いておきたい。今後この問題がどのように推移してゆくのかわからないし、私はこの問題についての国会審議を真剣に見ていないので、私の直感としてのつぶやきである。日本は労働力不足だという。確かに少子化は進行しているし、今後出生率が増えるとも思えないので、労働人口が減ってくるのは間違いがないだろう。だが、今必要な労働人口が絶対的に少ないとも思えないのだ。人手不足で今困っているのは、農業・建設・介護などの福祉職・飲食業・中小企業などであろう。ざっと見ても、「低賃金」の業種である。これらの業種を支えているのは、非正規の人たちや女性や高齢者であろう。低賃金でも働く人ばかりに依存しているということだ。このような業種に外国人労働者を受け入れたいということは、いくらきれいごとを言っても「低賃金で文句言わずに働く人」を求めていることだ。そのような人を大量に受け入れることは、これらの業種を低賃金業種として定着させ、さらに労働環境を悪化させることにつながるに決まっている。現在の日本には、まだまだ眠っている労働力がある。ニートやひきこもりに陥っている人たちである。内閣府が出しているデーターがある。第2節 若年無業者,フリーター,ひきこもり1 若年無業者,フリーター(1)若年無業者15~34歳の若年無業者は56万人,15~34歳人口に占める割合は2.1%。若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち,家事も通学もしていない者)の数は,平成14(2002)年に大きく増加した後,おおむね横ばいで推移している。平成26(2014)年は56万人で,前年より4万人減少した。15~34歳人口に占める割合は長期的にみると緩やかな上昇傾向にあるが,平成26年は2年連続で低下して2.1%となっている。年齢階級別にみると,15~19歳が8万人,20~24歳が14万人,25~29歳が16万人,30~34歳が18万人である。(中略)2)フリーター15~34歳のフリーターは179万人,15~34歳人口に占める割合は6.8%。フリーターを,15~34歳で,男性は卒業者,女性は卒業者で未婚の者のうち,雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」か「アルバイト」である者完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者非労働力人口で家事も通学もしていない「その他」の者のうち,就業内定しておらず,希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者の合計として集計すると,この数年はおおむね横ばいで推移しており,平成26(2014)年には179万人となった。年齢階級別にみると,15~24歳では減少傾向にあるものの,25~34歳の年長フリーター層は平成21(2009)年以降増加傾向にある。(第1-4-15図(1))フリーターの当該年齢人口に占める割合は平成20(2008)年を底に上昇傾向にあり,平成26年は6.8%である。特に,25~34歳の年長フリーター層では上昇が続いている。2 ひきこもり「ふだんは家にいるが,自分の趣味に関する用事の時だけ外出する」者を含む広義のひきこもりは,69.6万人と推計。内閣府が平成22(2010)年2月に実施した「若者の意識に関する調査(ひきこもりに関する実態調査)」18によると,「ふだんは家にいるが,近所のコンビニなどには出かける」「自室からは出るが,家からは出ない」「自室からほとんど出ない」に該当した者(「狭義のひきこもり」)が23.6万人,「ふだんは家にいるが,自分の趣味に関する用事の時だけ外出する」(「準ひきこもり」)が46.0万人,「狭義のひきこもり」と「準ひきこもり」を合わせた広義のひきこもりは69.6万人と推計される。これらの若者たちの単純合計が304万人である。重複している数字もあるだろうから、半分にしたとしても150万人だ。この中には何らかの病気になっていて就業が困難な人も多いだろうが、パートやアルバイトをしている人は就労の意欲があるということだ。この数字は35歳未満のようだから、35歳~60歳までの非正規就業の人たちを考えたらとんでもない数字となるだうし、今はひきこもりの高齢化が進んでいるから、どんな数字になるのか見当もつかない。正確なデーターがあれば教えていただきたい。日本国内の青年層までの仕事環境を整えなくては、日本の労働力の空洞化は進むばかりだし、そこに低賃金外国人労働者が流入するのは国の制度としてしっかり止めなくてはどうしようもない。今は少数派の外国人労働者だが、この割合が増加したらその人たちの不満が募るのは目に見えているし、ひょっとすると団結して経営者に立ち向かったり、業種を超えてデモやストライキならまだしも、暴動化する可能性もある。こうやって書いているだけでも次々と様々な問題が連想されてゆくのに、政治家や経済界の人たちは目先のことに目がくらんでそちらの方向については全く考えが及ばないのか、考えないようにしているのか。私はとにかく、今、希望を持てない形で働かざるを得ない若者たちの労働条件を改善してほしい。特に、介護や子育て関係は「女の仕事」とされてきた歴史の中で、軽く扱われてきたと思っている。介護職も、子育て関係の仕事(保育士・幼稚園・学童保育・放課後デイなど)も、専門的知識や経験がとても大切なのに、多くは非正規状態で経験者が長く続けることができにくい。これでは、大切な子どもたちを健全に育てることなんて難しいに決まっている。介護職だって同じである。最近の福祉施設での虐待や死亡事故だって、そこで働く人たちを大切にしていないのだから、入所者にストレスが向いたり命を軽んじることにつながるのは、ある意味当然の帰結だと感じている。先日、障がい者施設で働く知人と話したときに、「どうせボランティアみたいな仕事だし…」という言葉を聞いた。ボランティアみたいな仕事というのは、報酬が仕事に見合っていなくてバカバカしいという意味だろう。でも、私はムキになって反論した。「『ボランティア』と『ボランティアみたいな』とは全く違うよ。どんなに少額でも給料をもらっていたらそれは仕事なのだから、その言葉を使うなら『ボランティア精神を持たなくてはならない仕事』と言ってよ」と。私の「ボランティア精神をもつ」ということは、『自分がやりたいと思い主体的にかかわる』ということである。だから、人に関わる仕事にはそれがとても大切だと思っているので、単なるお給料をもらう仕事とだけ考えてはほしくないと思っているからだ。話がそれたが、外国人労働者を大量に受け入れるには、日本にとっての将来的なリスクや、現在の若者問題をしっかり考えてからにしてほしい。どうしても外国人を受け入れたいなら、難民を受け入れる方がずっと世界の人たちに喜ばれるだろうとも思っている。念のために付け加えるが、私は外国人を受け入れるのに絶対反対というつもりはない。様々な形で外国の人たちと共存協力しなくては今の日本は成り立たないし、日本が世界と仲良くしながら信頼されてゆくのは、日本という国の存続のために大切なことだと考えている。
2018年11月24日
コメント(4)
-
仕事には自己満足(納得)が大切!
この日は気温が25℃以下の予報だったので、久しぶりの農作業。作業は、ぶどうの花かすの掃除である。開花時期に雨が続き、結実しなかった実や花かすがついたブドウの房を、刷毛で一つ一つ掃除をする作業。最初にこの作業をした時には、「何という手間のかかることをするのだ!」と驚いた。中腰になったり膝をついたりしながらの細かい作業は、キツイ作業ではないけれど高齢者にはスクワットの連続で結構きついものがある。結局、午後からはビール箱を腰かけにしながら作業を続けた。結構葉が茂り蔓が伸びて暴れているので、脇芽や伸びすぎた枝を切ったりしながらで手間も時間もかかること、かかること。一緒に作業する夫は、「こんなことして、どれだけ良いブドウになるのか」とボヤいている。彼は、チマチマした作業が嫌いなので、できればザクザクと成果が見える作業(たとえば草刈り機を使うなど)をしたいのだ。私自身はこのようなチマチマ作業は嫌いではないのだが、ブツブツ言う夫の言葉には少しイラつく。息子たちがやってほしいということをやるのが手伝いだろう。どうせやるなら文句を言うなという気分である。夫が、「結局は自己満足に近いよなあ」と言った時には、私もついに反論してしまう。「仕事に自己満足は大切でしょう! 自分で納得して満足できない仕事じゃダメでしょう」夫は私の強い口調に少し引いてしまったようで、「それはそうだな…」とモゴモゴ…。きっと彼は、なんで私が強い口調になったかよくわからなかったのではないだろうか。ひょっとすると、黙って作業をする私も、この仕事に虚しさを感じていると思ったのかもしれない。でも、それは違う。私は職人気質の次男の仕事の姿勢が嫌いではないのだ。これだけのことをやっていても、病気になったり虫がついたりしてこの作業をした意味があまりないようになるかもしれない。それはわかっていても、やっぱり納得できることをしたいという息子を応援したい。夫だって基本的には同じ気持ちなのだけど、夫はチマチマ作業に苛立つ性質なのだ。それもまた仕方がないけれど、やっぱり「どうせやるならブツブツ言わないで!」と思うのだ。説明するのも面倒なので、彼の「それはそうだな…」に「そうだよ」と言っただけ。そしてひそかに思う。私もまた、自分なりの自己満足のために仕事をしたし、今もそんなことをやっているかも…と。
2018年08月04日
コメント(0)
-
Yちゃんのお父さんとの再会
昨日、某会合で同世代と思われる男性から「失礼ですが、以前うちの娘がお世話になったみらいさんですよね」と話しかけられた。この人とは何度か会っていて、苗字だけ知っていた人だった。そう声をかけられ、その苗字とかつての仕事で出会った子ども達のことを思い浮かべた時、すぐにYちゃんの顔が浮かんだ。彼女は、左のフリーページにも書いている、忘れられない子の一人なのだ。私が退職する時に、Yちゃんはまだ4歳くらいだったように思う。ボール遊びやリズム遊びが好きで、大声ではないけれど優しい笑い声が可愛い子だった。お母さんとはいつも会っていたが、お父さんとは最初の面談の時に会っただけのような気がする。「ああ、Yちゃんのお父さんでしたか」。そして私は、次に一番知りたいことを多少ためらいながら聞いた。「Yちゃん、お元気にしてますか?」。先天性の染色体異常による障害を持ちながら生まれた子は、合併症などで短命なこともあるので、うっかり聞いて悲しい事実を知ることもあり、いつもこのような場合には多少の緊張感を持ってしまう。でも、その返事はホッとするものだった。「おかげさまで元気にしています。今は施設に入っているのですが」。そうか、元気だったんだ。あの頃、私の長男が小学生になるころだったから、40歳くらいになったかなと思いつつ「おいくつになりましたか?」と聞くと、「39歳になりました」とのこと。私の記憶にある彼女は、年齢からすると小さくて体重も軽かった。彼女の柔らかい体や小さな手が、今も思い出すことができるが、39歳のYちゃんの姿は想像が出来ない。同じ染色体異常でもダウン症候群の人たちは多いので、中年になった姿は何となく想像もできるのだが、私はYちゃんと同じ障害の人にはまだ出会ったことがないのだ。でも多分、あの頃の個性はそのままに、おとなしくて優しい人になっていることだろう。目の前にいるお父さんは、温厚で優しい人柄だと思われるし、私の記憶にあるお母さんもまた、控え目で優しい人だった。障害による特徴があったとしても、間違いなく両親の性格は受け継がれるのだろうなと感じた。もっと色々と近況をお聞きしたかったのだが、お互いに次の用があり、そそくさと別れることになってしまった。今回で彼と会う機会はなくなってしまうので、多分お父さんも今日が最後の機会と思って声をかけてくださったのだろう。別れた後で思った。「Yちゃんは、私にとても大切なことを教えてくれた子だったのです」と、お伝えしたかったな…と。もしもまた再会できたら、そのことをお伝えしたいと思う。
2017年03月16日
コメント(2)
-
Nちゃんとお母さん、よく頑張ったね。
昨日、若い頃に出会った人から、寒中見舞いをいただいた。心身障害児の療育指導員をしていた頃に出会った人で、娘さんはダウン症候群だった。私がその仕事をやめてからは、隣市にお住まいだったこともあり、年賀状のやりとりだけは続いていた。しかし、今年は年賀状が来なかったので、どうしたのだろうと気になっていた。お手紙によると、娘さんは昨年春から体調を崩して入院していて、年末に41歳で亡くなったのだという。初めて出会った時は、多分3歳前後だったと思う。高齢出産で生まれたNちゃんは、ダウン症候群であった。心臓疾患があり(この障害には多い)、やせっぽちでいつも紫色の唇をしていた。「3歳くらいまでしか生きられないと言われたんだけど…」というお母さんだったが、「いつまでの命かわからないから」と、いつもとても可愛い服を着せていた。待ち望んだ女の子だったからなのかもしれない。それでも、よく体調を崩して入院などもしていたと思うが、元気になって会うときにはいつもニコニコしていて、音楽が大好きで、歩けない時でも体全体でリズムをとって、全身でリズムをとっていた姿が目に浮かぶ。そうか、41歳まで頑張ったのだな…。お母さんもNちゃんも本当によく頑張ったね。そんな思いが胸の中に渦巻いた。きっと、「いつまでの命かわからないから」との思いで、ずっと在宅で介護していたのだろう。施設入所をしたという話は聞かなかったから。お母さんだって、もう80歳近くになっていると思う。Nちゃんは、亡くなる二日前までは意識もあったが、食事を受付けなくなり点滴のみで頑張ったようだが、最後は眠るように旅立ったという。きっと最後まで、子どもの頃と同じような笑顔をお母さんに見せていたのではないだろうか。お母さんに、「今まで本当にありがとう」との思いを笑顔に託して…。お母さん自身、寂しさはあるだろうが、自分が看取ることができた安堵感を抱いているのだろう。障害を持つ子を育て介護するのは、間違いなく人並み以上の苦労はあるだろう。しかし、その分だけ人並み以上の喜びや感動の経験も重ねるし、苦労ではあっても不幸とイコールではない。初めて一人で立ったとき、初めて歩いた時、初めて靴を履いて散歩した時、どれだけの感動と喜びがあっただろう。三歳までと言われた命を、41歳まで支えたという誇りや喜びは、健康な子を持つ親には決して味わうことができないだろう。あの当時に出会った重い障害を持つ親の願いは、「子どもを私の手で見送りたい」ということだった。使命感で生きてきたであろうお母さんが、これからガックリとならなければいいと思う。Nちゃん、本当によく頑張りました。そちらの世界には、あの頃一緒に遊んだお友達もいるはずだから、きっと寂しくはないよね。これからは、お母さんをしっかり見守ってあげてくださいね。
2017年01月14日
コメント(6)
-
パラリンピック
パラリンピックが始まった。私はオリンピックでももちろん感動するけれど、パラリンピックの感動はまた別物なのである。かつての仕事柄、様々な障害を持つ人達と出会った経験があるので、人間の強さや可能性、本人の努力や周囲の人たちの支えなどを思うと、とにかく胸は熱くなり、クールを自認する私の涙腺もゆるんでしまうのだ。「障害は不便ではあっても不幸ではない」と、柔道で銀メダルをとった廣瀬誠さんがおっしゃっていたが、私は30年前にも同じような言葉を聞いた。当時、「ノーマライゼーション」の考え方を地域の人達と共有しようという活動&仕事をしていた頃、車椅子マラソンの草分けでもあるМさんが言った言葉だ。彼は20代の頃に事故で脊髄損傷となり、車椅子で暮らすようになった。出会った当時は多分30代後半で、まだあまり一般的ではなかった車椅子マラソンで頑張っていた。彼には本当に色々なことを教えてもらったのだが、とにかく明るく前向きにチャレンジする姿勢には感服していた。それまで出会ったどんな人よりも、彼は前向きだったし大らかだった。その生き方は、当時ボランティアとして関わった多くの若者たちに刺激を与え、人として生きる姿勢をその姿で教えてくれたと思う。彼の腕や肩は車椅子マラソンなどで鍛えていたので筋肉隆々で、その腕で多少の段差などは軽々と乗り越える姿に、「Mさんって鉄人28号みたいだね」と感嘆した高校生の言葉と表情が、今でも目に浮かぶ。もちろん、車椅子生活をする人にも中途障害の人もいれば生まれつきの障害の人もいるし、性格だって人それぞれだ。彼はきっと、元来の性格が明るく前向きでチャレンジ好き、スポーツ好きだったのだろう。当時は、スポーツ用の車椅子は日本には普及していなくて、アメリカから購入すると言っていた。彼のそばにはいつも笑顔の絶えない奥さんがいて、夫婦二人三脚で様々な大会や活動に取り組んでいた。そんな人だから、様々な人を巻き込んで障害者スポーツの普及・啓発に取り組み続けている。現在は年賀状のやりとりをするだけなのだが、きっと今でも自分の可能性を見つけてはチャレンジし続けているはずだ。そんな彼が、ある日雑談をしていた時に話していた。「僕は障害者になって、良かったとまでは言わないけど、悪くなかったと思ってる。 自分が障害者になって知ったことがたくさんあるし、健常者のままでは広がらない世界もあった。 でも、まだまだ障害者は社会的弱者で差別されていることは多いし、 自分の可能性に気づけないままでいる人たちも多い。 僕が車椅子であちこち走り回っているのは、そんな仲間たちに可能性があるということを伝えたいからだ。 同時に、多くの人に障害者について理解して欲しい。 障害は確かに不自由なことだから、周りの人に手伝ってもらわなくてはならないからね。 僕がスーパーに行くことで、車椅子はこのようなことで不便なのだとわかってもらえる。 そんな中で人との新たな出会いや交流も生まれるしね。 障害は不自由なことだけど、それを不幸にしてしまうのは本人と周りの人たちの気持ちだよ」彼の言葉は、私には目から鱗であった。それまで、私は乳幼児から学齢期までの障害児とその親とは付き合っていたけれど大人の障害を持つ人との出会いは少なかったから、そのような人と付き合うことに多少(いや、かなりかも)の遠慮があった。当時の障害者団体は、どちらかというと傷痍軍人のような人たちを中心に組織され、付き合うのがちょっと難しい印象があった。その人たちの言葉は「我々は大変な苦労をしてきた。今の人たちは幸せだ」のようなニュアンスが強く、Mさんのようなタイプには馴染めないようで、最初はその団体に入っていたが、やがて自分たちで別の団体を作ったため、市内の障害者団体からは少し距離を置かれていたような気がする。つまり、障害者同士でも意識や目的は同じではなく、時には反発しあうことにもなりうるのだ。私が出会った時のMさんはバリバリの障害者スポーツ分野のリーダー的な存在だったが、最初からそうではなかったはずだ。彼との縁から色々なタイプの障害をもつ人たちに出会ったけれど、本当に「障害は個性の一つだなあ」と実感することにもなった。しかし、そう思えるのはやはり当事者も含めて少数者なのかもしれない。今回のパラリンピックだって、何度も出場している人は注目もされているけれど、ほとんどの人は初めて知る人ばかりだ。なんといっても驚いたのは、出場者の中に地元出身の人がいたことだ。オリンピックに出場することになったら、市役所には「頑張れ!」の横断幕が掲げられ、応援団は結成され、地元の新聞にも取り上げられるのは必定。それなのに…と、唖然とする思いだった。多分、当市が出身地ということで、現在は別の地域で活動しているのだろうけど、それにしてもねえ。つまり、それだけパラリンピックは一般的に注目されていないという証のような気がする。試合は明日のようなので、応援したいと思う。Yさん、頑張れ\(*⌒0⌒)♪カテゴリーを何にしようか迷ったが、Mさんのことを書いたので「仕事」カテゴリーにする。
2016年09月10日
コメント(2)
-
仕事で出会った人…フミさん
「フミさん」との出会いは、もう35年くらいも前になる。仕事で、地域の老人クラブ連合会の事務局もしていたので、まず名簿で「山〇 文」という氏名を見て、てっきり女性だと思いこんだ。しかし、理事会に出席していたのは、全員男性だった。不思議に思った私は、「ひょっとして奥さんが来れないので、ご主人が代理で来たのかな!?」と思った。しかし、次の理事会も出席しているのは男性ばかり。さすがに変だと思った私は、事務局長に「山〇さんって、どの方ですか?」と聞いた。「フミさんかい? あの人だよ」と教えられた人は、小柄で細身の体の、白髪の男性だった。「えっ、やっぱりフミさんっておっしゃるのですか!? てっきり女性だと勘違いしてました」と驚く私に、局長は笑いながら言った。「そういえば女の名前だなあ。昔からフミさんって呼んでるから、俺たちは変だとも思ってなかったよ」。性が分かりづらい名前というのは今ではよくあるけれど、大正前期生まれの男性で、「文(フミ)」というのは珍しい。親しく話ができるようになってから、私は直接聞いてみた。「フミって、ご本名ですよね? 男性のお名前としては珍しいと思うのですが、何かいわれがあるのですか?」。すると、穏やかな笑顔でちょっといたずらっぽく教えてくださった。「最初は文男って言ったんだよ。でも、小さい頃に津軽海峡を渡った時に、男を落としてきちゃったんだよ」。あまりウイットに富んだ会話が得意でない私は、一瞬わけがわからず、返す言葉も持たずキョトンとするばかり。そんな私を面白そうに見ながら、それでもちゃんと説明してくださった。「北海道に移住した時、戸籍の届けを間違ったのか、間違えられたのか、文になっちゃってたのさ」。そんなバカな、どうして気づいたときに訂正しなかったのかと思う私に、続けておっしゃる。「まあ、ずっとフミって呼ばれていたしね、それでもいいかと思ってね」。納得できるようなできないような不思議な気持ちだったが、ご本人が納得しているのだからいいのだろう。そんな大らかなお人柄を、私はそれ以後ずっと尊敬してきた。「フミさんの怒った顔は見たことがない」と、彼を知る人は口を揃える。私が出会った頃は、老人クラブの会長や民生委員、保護司などをなさっていて、しょっちゅう私の勤める事務所に顔を出していた。私自身も、山〇さんが不機嫌そうな顔を想像できないし、目に浮かぶのは優しい笑顔だけだ。その頃はすでに奥さんを亡くされて、お一人暮らしと聞いていた。でも、近所にご長男も住んでいるとのことで、きっとお子さんたちがお世話をしているのだろうと想像していたのだが。フミさん(私は、いつも山〇さんとお呼びしていたが、今日はフミさんと書かせていただく)が亡くなったと知り、私は随分お会いしてはいなかったけれど、仕事をしていた頃に随分可愛がっていただいたし、お別れに行こうと思い、葬儀に参列した。そして、フミさんの経歴を知り、本当に驚いたしとても感動した。それを、覚書として書いておこうと思う。フミさんは福井県で生まれたのだが、四歳の時にお父さんが亡くなり、親戚を頼って北海道にわたってきたそうだ。四歳の子どもが自分で遠い親戚を頼ったわけではあるはずもない。多分母親と別れてきたのだろうが、最初は札幌の親戚宅、次に現在の地にやってきた。養子になったわけではないようで、いわば「里子」状態だったのだろう。その家は農業を営んでいたので、小学校卒業後農業に従事し、20歳ころに結婚。私はその頃の生活事情を、昔々実家の祖母から聞いたことを思い出した。どちらかというと、幼少期から農業で生活が安定するまでは、ご苦労が多かっただろうと思う。そんな中で、フミさんはとても家族を大切になさっていたそうだ。葬儀での経歴説明の中で、こんなことが語られた。「ご自分が家族に恵まれないお育ちだったせいか、大変家族を大切にする子煩悩なお父様だったそうです。雨が降って農作業ができない日は、お子さんたちと汽車で札幌にでかけ、映画を見たことが楽しい思い出で、お子さんたちはいつも、雨が降らないかと思っていたそうです」。フミさんは100歳まで一人暮らしをしていたのだが、全て身の回りのことは自分でなさっていたとか。近所に住む娘さんが、惣菜を持って行くと「甘えてしまうから、気を使わなくていいよ」とおっしゃったとか。100歳を超え、体調を悪くしたことをきっかけに、近くの特別養護老人ホームのショートステイ、そして入所をしてからは、お子さんたちが毎日面会に行かれていたそうである。ホームの職員が「毎日面会に来る家族は、本当に珍しいし、ほとんどいない」と言っていた。102年のご生涯であった。他人にはもとより、ご家族にも思いやり深く優しい父親でありおじいちゃん、ひいおじいちゃんだったようだ。奥様を亡くされてからの一人暮らしは長かったけれど、自分で出来ることは自分でと、生活はもとより地域のお世話役、相談役として、ずっと尊敬され信頼された人生は、ご本人の口癖「おかげさまで、ありがたい」が本音の、充実した幸せな人生となったのだろうと思う。しかし、親と離れて暮らすことになった幼少時代から、結婚し子どもを育てる日々には、口には出せない寂しさや悔しさ、悲しみを心にしまいこみ耐えた日もあっただろうと想像する。それを全てご自分の糧に変えてきたであろう生き方を思うとき、そのような人としてのお手本のような人と出会ったことを、本当にありがたいと思う。山〇フミさん、本当にお疲れ様でした。今頃は、先立たれた奥様やご長男と再会して、ご一緒に残されたお子さんやお孫さんたちを見守られているのでしょうね。仕事をしていた頃には、優しく励ましてくださってとても嬉しかったです。本当にありがとうございました。
2016年07月18日
コメント(2)
-
出会った人達…遺族会の人たち
二月に「出会った人達…地域のお年寄り 」を書いて、もう二ヶ月も経ってしまった。次の日曜日に、衆議院補欠選挙(北海道5区)があるので、毎日のように色々なチラシなどが入る。時折選挙カーの声も聞こえる。そこで思い出したのが、仕事で出会った遺族会の人たちのことだ。遺族会は、日本遺族会のホームページによると「日本遺族会は、「大東亜戦争」戦没者遺族の全国組織として昭和22年(当時は、日本遺族厚生連盟)に創設され、そして、28年3月、財団法人として認可されました。各都道府県には独立した遺族会が結成され、日本遺族会の支部としての役割も果たしています。市町村にも遺族会が結成されており、各々、さまざまな活動をしています」とある。私の職場は、当市の遺族会の事務局も担当していて、私はそこで初めて戦争で夫や兄弟等を亡くした人達と出会った。遺族会では、毎年の札幌護国神社や旭川の護国神社の例大祭に参列するが、親睦旅行も兼ねていたので、私はお世話係として一緒に泊まり、それまでは想像もしたことがなかった話を聞くことになった。当時私はまだ30代で子育て中の身であったから、戦後を夫を失って子どもを食べさせるため、必死で生きてきた人たちの話にはとても関心があったから、おばさんたちも夜が更けるまで色々と話をしてくださった。その中には、夫が戦死したので夫の弟と結婚した人もいたし、末っ子は出征中に生まれたので父親の顔を知らないという人や、子どもがないままに未亡人になり、そのまま一人で生きてきた人もいた。そんな苦労話の数々を聞くと、このような人たちがひたすら耐え忍んできたことで、やっと日本は立ち直れたのかもしれないとも思った。そして、口々に「あの頃を思えば、今は本当に幸せ」と言うのだ。その笑顔に、私は神々しさすら覚えることもあった。そんな私が、遺族会事務局としてやりたくない仕事があった。選挙が近くなると、みんな「自民党員」となるのである。つまり、遺族会まるごとの選挙協力である。どうも、毎年党費を払っているわけではなさそうで(中には純粋の自民党員もいたのだろうが)選挙になるとおばさんたちが「よろしくねー」などとお金と名前を書いた紙を持ってくる。そして、「自民党にはお世話になっているからね。協力しなくちゃ」なんて言う。私は笑顔でそれを受け取りながらも、お腹の中では複雑な気持ちが渦巻いていた。遺族会の人たちが自民党にどのようにお世話になっているのか、私にはわからない。しかし、みんな純粋に自民党のおかげで遺族年金ももらえるように思っているらしい。私は、戦争で多大な苦労をしたご遺族に遺族年金はあたりまえのことだと思うし、それに他の党が反対しているとも思えなかったので、遺族会の人たちがうまく自民党に丸め込まれているんじゃないかという気がしてならなかった。今ならインターネットで色々調べられると思うが、当時の私はそんなことができる時間もなかったので、モヤモヤ気分のまま事務処理をしていた。何年に一度は靖国神社参拝もしていたけれど、それには私は同行したことがない。子どもが小さいことを理由に他の人に行ってもらっていたが、本音は行きたくなかったのである。父の影響もあり、靖国神社は「死ねと命じた人」と「命じられて死んだ人」が同列なのが、どうにも納得できないことが一番の理由だった。その場所で、素直に頭を下げることができないような気がしたし、おばさんたちの気持ちを考えると、それも申し訳ないような気がしていた。当時親しくしたおばさんたちはほとんど亡くなっている。当然、遺族会の会員も減少していることだろうから、昔のような形での協力をしているのかどうかはわからない。おばさんたちは、異口同音に言っていた。「戦争だけはごめんだ。二度と私たちのような思いをする人が生まれる世の中にはなってほしくない」と。きっと彼女たちは、戦争をしない世の中を自民党が守ってくれるはずだと信じて、毎回投票していたことだろう。その切ない思いを裏切らないで欲しいと願うのだが…。
2016年04月21日
コメント(2)
-
出会った人達…地域のお年寄り
私の三度目の職場は、地域の福祉活動全般のお世話係のような社会福祉法人だった。もう、30年以上も前のことであるから、「ボランティア活動」という言葉も、私の住む町では一般的に使われておらず、仕事で目にしたスローガンは「市民みんながボランティア」(ちょっと記憶があやふやだが、そんな内容)だった。それを目にした時、私は正直なところちょっと違和感があった。私は昔から「みんなが一斉に何かをやる」ということが苦手なタチなのだ。「自分でやりたいと思わないのに、みんながやるからやる」ってことにつながるから、私の印象としては「それがボランティア活動か!?」という感じがあった。でも、まだボランティアという言葉が定着していないのだから、それもやむを得ないだろうとも思った。まだまだ「奉仕活動」という言葉の方が、多くの人には馴染みあるものだった。さて、当時の地域福祉の担い手といえば…。民生児童委員、日赤奉仕団、老人クラブ、町内会、婦人団体、青年団などなど、現在も続いている組織ではあるが、「ボランティア活動」とはちょっとニュアンスが違う。自治組織というか、同世代の親睦組織というような感じだろう。「ボランティア活動」という概念を広めるためには、「あなたたちの活動そのものが、ボランティア活動とも言えるのです」というような説明だったように思う。私は社会福祉について専門的な勉強はしていないし、私が与えられた仕事は事務仕事であった。具体的にいえば、それらの一部の団体の事務局仕事や、それらの団体をさらに組織化した会の事務局である。団体運営には費用も必要だから、自治体などからの補助金申請や、自ら寄付金を集めたりする仕事もある。私はその時初めて、住民の地域福祉活動の財源や、それらの確保のための仕組みを知った。そして、色々な団体の事務仕事をする中で、地域の人たちがこのように地域社会を支えているのだということを知った。前置きが長くなってしまったが、今日はその組織の中の「老人クラブ」との関わりで感じたことを書こうと思う。さて、当時わが町の老人クラブは十数団体あったと思う。私が関わるのは単位老人クラブではなく、老人クラブ連合会の役員の方々がほとんど。ほとんどがこの町で生まれ育ち暮らしてきたお年寄りたちで、つまりは私の祖父母や両親を知っている人が多かった。「あー、〇〇さんのお孫さんかい」とか、「あんたのおじいちゃんにはお世話になったんだよ」なんて声をかけられる。その祖父は私が中学生の頃に亡くなっているので、老人クラブの皆さんを通して若い頃の祖父に出会うことになった。最初、祖父母や両親がこの町の老人たちの中での知名度が高いと気付いたときは、はっきり言って「ゲッヽ(´Д`;)ノ」という気持ちだった。結局この私は、仕事をしていても「〇〇の孫」「〇〇の娘」ついでに「〇〇の妻」であるのだ。私のこの職場でのスタートは、地域の縁という糸にからめとられるものだった。その頃、あまり考えもしないで誘われるままその職場に入ったことを、少なからず後悔したものだ。しかし私は、とにかく仕事をしたかったのだから仕方がない。「あんたは旦那さんもいるし、このくらいしか給金出せないけど働いてくれるかい?」というのが、私の就職の条件だったのだから。しかし、最初は戸惑ったりゲンナリもしたけれど、お年寄りの話を聞くのは面白かった。ほとんどが尋常小学校を卒業して家業につき、やがて戦争の時代をくぐりぬけ、苦労してきた人ばかり。その当時の老人クラブの役員は男性が多かったので、幼少期の話から若い頃の「夜這い」の話、戦地での武勇伝まがいなこと、昔の農業の過酷さや、子どもが多くて食べることで必死だったことなど、私の知らない世界のことをたくさん聞いた。そんな話の時々に、私の祖父母も登場したりして、昔と現在は間違いなく続いているのだと実感することができた。その人たちには「ボランティア」なんて言葉はピンとこないけれど、間違いなくみんなで助け合い支えあってきた人生があった。ことあるごとに、「おかげさまで」「ありがたい」「おたがい様」が口癖のように語られていた。そして、「お互い様の助け合い」は、現在の「ボランテイア」とはまたちょっとニュアンスが違うし、同意語のように言われる「奉仕活動」でもなかった。本当に生きていく生活者としての助け合いが日常にあり、その上で公(おおやけ)のために汗をながしお金も出すことが「奉仕活動」のようだと、その頃の私は気付き始めた。そして、純粋なくらいに政治家や公務員は自分たちのために働いている」と信じているようにも見えた。それが私にはとても不思議なことだった。(だって、あの戦争でどれほど苦労してきたか身にしみて知っているはずなのに)それでも、私はその疑問を口にすることはできなかった。きっと、色々な苦労をしたからこそ、老人クラブなどで楽しい時間を過ごせるようになったことを、心から喜んでいるし感謝もするのだろうと思うと、そんな私の疑問はそれに水を差すことのように思えたからだ。とにかく私はお年寄りの皆さんには、とても可愛がられた。それは、やはり祖父母からのつながりという縁の賜物だったと思う。ことあるごとに自己嫌悪に陥りやすい私にとっては、お薬のような存在だった。とりあえず、今日はこれまでにしましょう。
2016年02月25日
コメント(2)
-
人としての一番の仕事は…生きること
前回の「人としての仕事とは」で書いた考え方は、約20年前の時期の考え方であった。つまり、人には「報酬を得ながら社会参加する仕事」と、「報酬がないからこそ社会参加してできる仕事がある」ということだ。つまり、その時でもまだ私は、「社会参加して人の役に立つこと、社会での役割を果たすこと」が仕事だと思っていた。しかし、その後少しゆとりを持って色々な人に出会い、教えられ、考えさせられてきた結果、今はかなり違う考えを持つに至った。「人としての一番大切な仕事は、その人が与えられた環境と生きる力で、精一杯生きること」だと思っている。とにかく、命を与えられたからには、辛くても生き抜くことが一番の仕事。「生きる意味」とか「役割」とか「役に立つ」ということは、それに自ずとついてくるもののように思う。人としての価値は、ただ精一杯生きることにあるのだと、今の私は思っている。ただし、生きることは一番重要なことだけど、生きるために何をしても良いとわけではないのは勿論である。かつての私は、「仕事ができない」ことや「きちんと責任を果たせない自分」はダメな自分で、価値がないと思っていた。人に迷惑をかけたり、傷つけたりするようなことがあったら、自己嫌悪で身動き取れないような気持ちに追い込まれることもしばしばだった。でもそれは、ある意味自分の能力を過大評価したい傲慢さがあったからだし、今の自分ではない「理想の自分」にならなくてはならないという、強迫観念もあったように思う。そして、自分以上にダメに見える誰かを、上から目線で見ていたようにも思う。「私はあれほどひどくはない」と思うことで、かろうじて自尊心を保っていたとも言える。「自分の今の力でできることをする」という気持ちになれた時、本当に私は楽になったと思う。若い頃、「生きる意味はわからないけど、お付き合いで生きよう」と思った時から45年。やっぱり、生きれる間は生きてみるもんだなあと思う。極論すれば、生きる意味や自分は何者かを考え続けている間は、決して自分を生きてはいないとも言える。ただ、そんなこともがわかるのに、少なくても私は長い年月が必要だった。それを少しずつわからせてくれたのは、沢山の無名(もちろん名はあるけれど、有名ではないという意味)の人たちだった。そんな人たちのことを書き残せたらいいなと思っている。
2016年02月23日
コメント(2)
-
人としての「仕事」とは
私は若い頃から、仕事をする女性になりたいと思っていた。それは、「社会で役立つ=仕事」という考え方だったから。社会に役立つ仕事をすることで対価としての報酬を得、それで生活してゆく。それこそが「自立」だと考えていた。結婚して専業主婦となり、夫のお給料によって生活するのは、自立と言えないような気がしていた。自分が働いたお金を自分で使えてこそ、本当の「自由」も得られると思っていた。だから私は、仕事を続ける事にこだわっていたし、夫との結婚の条件も「仕事を続ける」ということだった。どんなに好きになった人でも、「結婚したら主婦になれ」という人とは、私は結婚しなかっただろう。だから私は、自分は結婚には向いていないとも思っていた。そのような考えを持つ女はあまり好かれないということは、何となく感じていたし、結婚しても自分の価値観と合わなかったら、離婚だってありうると考えてもいたからだ。幸いに、そんな私でもいいという人が現れ、この機を逃しては結婚できないだろうと思った私は、仕事を認めてくれるなら頑張るぞと思って結婚した。ただ、まだまだ私は甘かったということを、結婚後にすぐに気づくことになるのだが…。はっきり言って、「仕事のカテゴリー」のブログでもわかるだろうけれど、私はまだ「自分がどんな人間か、どんな人間になりたいのか、どれだけの力と能力があるのか」わかっていなかった。だから、結婚しても常に自分自身との葛藤や悩みの渦中だったし、家族(夫や子供)のために心を砕くことができる状態ではなかったのだ。私は結婚直後から「私は結婚などすべきではなかった」と思い始めたし、それでも「結婚したのだから責任は私にある」とも思いながらずっと仕事と家事と育児との折り合いに、髪振り乱していた。多分夫も、そんな私と共に暮らす現実の厳しさに、頭を抱えていたことだろうが、私はそんな夫の気持ちを思いやることができる余裕なんてなかった。私は責任感は人並みにあるように思う。だから、家事も育児もほとんど私がしていた。夫は「仕事をしてもいい」とは言ったが、「家事や育児も一緒にやろう」という人ではなかったから。そのことは最初からわかったいたので、できることは自分でやるつもりだったが、保育所の送迎や、私が家事で手がまわらないときは子どもの相手などはしてくれた。毎日の食事も、どれほど手抜きであったとしても、用意したものは文句も言わなかった。当時の私の認識では、それが私への協力だと思っていたし、ましてや夫は「十分協力している」と思っていたはずだ。ただ、私がそれで満足し、夫に感謝していたかというと、そうとは言えないのが実情だった。だから私は、「私は結婚すべきではなかった」と思ったのだ。さて、これは私だけのことだろうか。多分、同世代で仕事との両立に葛藤した人はよくわかってくれるのではないかと思うし、「イクメン」という言葉が定着しつつある現在でも、同じような葛藤で悩んでいる後輩たちもいるのではないだろうか。どんなに疲労困憊し辛くても、私は「精神的自立は経済的裏打ちが必要」と信じていたので、「仕事をやめたい」とは言えなかったし、「仕事が辛い」とも夫に言えなかった。それを口にしたなら、「なら、仕事をやめればいいだろう」と言われると思っていたし、それは私には敗北であった。それでも私は何度も仕事をやめた。「もう限界、私がこの仕事を続けてはいけない」と思ったときに初めて、夫に「仕事をやめますから」と宣言し、夫はそれをあれこれ言わずに了解してくれた。振り返ってみると、本当にありがたいことだったと思う。43歳で一時は天職とも思った仕事を辞めるとき、「もう、報酬を得る仕事はしない」と決意した。その頃には、「自立」や「仕事」に対する私の考え方が変化していたのだ。人には「報酬を得ながら社会参加する仕事」と「報酬がないからこそ社会参加してできる仕事がある」と思うようになったからだ。そして今、私は自分なりに地域社会に参加して、経験を生かした仕事をしているつもりである。たとえそれが周囲からは自己満足に見られていたとしても、人はそれぞれだと気にもならない。思えば私も、随分たくましい「オバサン」になったものだと笑ってしまう。
2016年02月19日
コメント(4)
-
私の仕事遍歴の続きを書こうかな…
私のブログのカテゴリ「仕事」では、私の仕事遍歴について書いていた。しかし、12年ほど勤めた仕事については、まだ書かないままである。当時の仕事仲間もまだあちこちにいるし、関わった地域の人たちも多いので、どのように書けばいいのか迷う気持ちが今でも強い。しかし、その頃の思いや人との出会いが、現在の私の生き方にも深く関わっているので、いつか書いておきたいという気持ちは持ち続けている。そして、それまでの心身障害児に関わっていた頃とは違い、地域福祉やボランティア活動の振興がメインの仕事は、一時期「これが天職」とも思った仕事だった。それでも私は、大好きでやりがいのあったその仕事を辞める結果となった。今から思えは残念な気持ちもあるが、思い切ってやめたおかげで通信での学びもできたし、それを今の活動にも生かすことができている。でも、時々ふと思ったりもすることがある。あのまま続けていたら、私は今頃どうしているのだろうと。人間は自分の行動を合理化するものである。今の私は、「やっぱりこれで良かったんだ」と思う。人生二毛作というような感じで、無関係ではないけれど異なる世界の人にも出会い、私という根っこは同じでも、違う活動ができている。あのままの仕事を続けていれば、多分、もっと「福祉オタク」のような私だったかもしれない。今でも「福祉オタクっぽい」のは間違いないけれど。これから時々、その仕事をしていた頃に出会った人のことや、考えていたことなどを思い返し、ぼかしながら書いていこうかなと思っている。
2016年02月18日
コメント(2)
-
「私の仕事遍歴 その後2」
「私の仕事遍歴 その後」で書きたかったことを今日こそ書こうと思う。先日、以前の職場で出会って、その後も細々と交友関係が続いている友人と久しぶりに会った。私も職場遍歴をしたけれど、彼女も色々な職場で働いてきた。私が出会った時は「心身障害児療育センター」の肢体不自由児部門の指導員であったが、その後も福祉関係の主に相談業務に関わっていて、現在は大人の障害を持つ人たちの相談センターの責任者だ。同じ地域で暮らしながら仕事をしているので、かつて乳幼児だった頃に関わった障害を持つ子と、大人になって再会することも当然ある。彼女が、遠くを見るような目をしながらポツンと呟いた。「療育センターで関わった子が、相談に来ることが時々あるんだよね…」それは、ある意味当然のことである。そのような仕事をしていない私ですら、時々当時関わっていたお母さんに町で出会うことはあるし、子どものその後についての話を聞くことだってある。健康な子どもに関わる幼稚園や学校の先生なら、久しぶりに教え子やその保護者に出会ったら、純粋な懐かしさで、「久しぶりだねー。○○ちゃん大きくなったでしょ。元気にしてる?」なんて、ためらいなく声をかけられるだろうけれど、私の場合はなんて声をかけたらよいかと考えてしまうことがほとんどだ。私がかつて出会っていた子ども達は脳性まひ関連や自閉症・情緒障害、知的障害の子ども達ばかりなので、どれだけ治療や機能回復に努力したって、完全に障害がなくなるわけがない。それどころか、成長するにつれて障害が顕著になり、それに伴い思いがけない課題や二次障害が発現することも稀ではないのだ。だから、彼女のつぶやきがとても重いものであることは、十分に察せられるのだ。「そうだろうねえ。…複雑な気持ちになること、多いでしょ?」と問うと、「そう、あの頃の私がやっていたこと、何だったんだろうなって思うことあるよ」「うん、よくわかるよ。私だって、町で当時のお母さんに会ったりするとそう思う」と私。「でも、仕方ないよね。あの頃はそれが良いと信じてやっていたんだし、 今だって一番良いと思うことを信じるしかないもんね」「そうだよ。その結果がどうなるかなんて、誰にもわからないものね。 今の知識と経験で、精一杯の支援をすることしかできないもの」「そうだよね。それしかないよね…」私達の会話は以上である。彼女が再会した人は、多分私も知っている人かもしれない。具体的に聞きたい気持ちもあったけれど、彼女には職業上の守秘義務があるし、何より私が具体的に聞くことが怖いこともあった。多分聞いたら切なくなることも多いだろうし、どうにも理不尽なこの世に怒りが湧き上がるだろう。私が障害幼児に関わり始めた時からすでに40年がたつ。社会的な支援体制や制度は当時から比べると格段に良くなったとは言えるが、それでもハンディを持つ人たちの一人ひとりにとっては、辛い事や悲しいことが溢れている。さらに医療の進歩は、「諦める」ことを難しくさせている。私は、人間には「諦める」ということが、とても大切な知恵であるとも思っている。所詮人間の浅知恵でしかないことを、科学的な根拠として進めてしまうことがさらなる悲劇を生むことは、多少長生きしてきたらわかってくるのではないか。残念ながら、それができなくなっている人も増えてきて、人の苦しみ(恨み、憎しみ、後悔など)を増やすことがあるように思う。次の言葉が出ないままに話はそれで途切れ、別の話題へと移った。彼女と別れてからも、当時の様々な子ども達の顔が浮かんでは消えて、その夜はまたまた睡眠不足になってしまった。一つだけ、例をあげよう。当時、脳性まひ(特に筋緊張が弱い子ども)の訓練方法として、「ボ○○法」というのが日本で紹介され始めていた。まだ医師もPTも試行錯誤状態だったので、私も道のセンターで指導を受けてお母さん達と一緒に手がけたのだが、私はこれがとても苦手だった。この手技は、乳幼児を押さえつけて子どもにとっては不快な体勢を取り続け、それから子どもが逃げようとする反発力を利用して筋肉緊張を高めるものだった。当然、子どもは嫌だから泣くことが多く、「可哀そうに」と思う気持ちに耐えて押さえ続ける。同時に、そんな自分の葛藤に耐えながら、子どもの筋肉の反応に注意を向ける必要がある。当時の私は、感情が優位になると冷静な判断が難しくなる傾向が強かったのか、その筋肉の反応が的確に見極められないのだ。指導してくれたPTの先生に、「子どもに泣かれると可哀そうで、つい手をゆるめてしまう」と言った時、「それでは指導員として失格だ。子どものことを思えば、そこは乗り越えなくてはならない」と言われた。「あー、やっぱり私はダメなのだ」と思いながらも、心のどこかでその言葉に違和感があった。本当にこれを続けたら、この子の障害が治るって言うんなら、私だって頑張るよ。でも、どんなに心を鬼にしたって、多少改善されるだけでしょう?そんな気持ちが湧き上がるのを、抑えられなかった。多分、お母さんも涙を流しながら頑張ったあの方法で、あの子の障害は完治したわけではないだろう。私はそれよりも、それによって子どもの母親に対する気持ちの方が、今は心配になる。あの当時、十分に母子関係のフォローをする指導があっただろうか。目先の障害をいかに軽減するかの方にだけ、目が向いてはいなかったか。障害を持つ子どもを育てることの苦しさ切なさだけを、両親に伝える結果になってはいなかっただろうか。そのほかにも、色々な思いがある。でも、所詮は人間の浅知恵である。その時その時で、精一杯の方法をとるしかない。そして、その結果の反省を生かしながら次に進むしかない。それは、すべてのことに当てはまることだと思う。浅知恵しかない人間が、傲慢になったり盲信したりすることは、本当に怖いことなのだ。
2014年05月16日
コメント(0)
-
私の仕事遍歴 その後
以前、自分の携わってきた仕事について書いておこうと思い立ち、30代ちょっとまでの仕事について書いていた。仕事のカテゴリー参照。2012年11月09日に書いた「挫折した仕事に誘われたり、趣味探しをしたり… 」が最後の記事になっている。実は、その後の仕事は色々と面白いエピソードもあって、私自身が主張したいことも満載なのだけれど、具体的に書くことにはためらいがあるので、そのままになっている。職種だけを書けば、「社会福祉協議会職員」が11年間。仕事の内容は、事務職から始まり各種団体の世話係、ボランティア活動や地域福祉の推進、ハンディを持つ人たちと一緒に「ノーマライゼーションの推進事業」である。障害幼児の療育に関わる仕事をしていた時の問題意識から、特に「地域の福祉意識の醸成」としてのボランティア活動の推進や、様々なハンディを持つ人たちや若者たちとの「ノーマライゼーション」の理念に基づく様々な活動は、私の本当にやりたかったことでもあり、とても大変だったけれどやりがいがあった。私は一時期「これが天職」とも思い、ずっと仕事を続ける気持ちであったのだが…。やはり10年くらいで私の「挫折病」が発症。ちょうど更年期が始まる時期だったせいもあったのか、精神的・肉体的疲労の蓄積によるものなのか、もうヘロヘロになって、体力・気力の限界を超えてしまった。しかし、今はそう思うけれど、当時は「やっぱり私の能力が足りないから。私がやるのは無理なのだ」という思いに捉われて、「何か間違いを起こす前に辞めなくちゃいけない!」という、切羽詰まった思いで退職した。しかし、やはり私もタフになっていたのか、「転んでもただでは起きない」という気持ちが育っていたようで、次の目標を「自分には足りなかった勉強」に絞って、慶應大学の通信課程に取り組むことにしたのだ。その後は、お給料をいただく仕事はほとんどせず、それまで色々な人に助けられたり支えられたりした恩返しをしなくちゃと、最初は「来るものはできるだけ拒まず」のように、町内会の地域活動から始まり、前職のかかわりからの様々なボランティア的な活動を自分の仕事にしてきた。5年ほど前に、頼まれてつい引き受けた「就労支援事業所B型」の管理者を1年間勤めたが、これは仕事をしたうちには入らない程度である。それでも、それまではあまり関わることの少なかった精神の障害や病気の人たちと出会い、様々なトラブルと取り組む中で学んだことはとても多い。社会福祉協議会時代のことも、就労支援事業所のことも、あるいはボランティアや地域活動のことも、具体的に書けば個人や組織の深いことまで書かざるを得ないし、そこをごまかしては書きたいことは書けないような気がするので、やはりその後の仕事についてはまだ書けないままだ。ただ、今日これを書いているのは、肢体不自由児に関わる仕事をした時に出会った人と先日久しぶりに話す機会があって、ちょっと感じたことがあったので、書こうと思ったのだ。しかし、前段が長くなってしまったので、そのことは後で書こうと思う。今日はこれから出かけるので、多分明日以降のブログになると思う。
2014年05月14日
コメント(2)
-
挫折した仕事に誘われたり、趣味探しをしたり…
ひどい挫折感と、二度とあの職場には足を向けたくないという気分で退職した私。その時、ちょうど長男は小学一年生になった。今までは自分のことで精いっぱいで、子どものことは正直に言えば二の次、三の次の状態。それでも、保育園の先生たちにはずいぶん励まされ、支えられ、何とか息子たちも元気に育っていた。せっかく仕事を辞めたのだから、少しは良いお母さんになろうと思ったのだが、仕事での挫折感は、どうにも私の心を重くしていた。その上、悲しいことに私は家事一般が好きではない。人並程度にやればできるのだが、それに喜びを感じることができない性質なのだ。掃除・洗濯・炊事など、どの家事もやっては片付けの繰り返し。私は一生の間に何度この作業を繰り返すのだろうと思うと、本当に嫌気がさして仕方がなかった。暇な時間ができたので、専業主婦の友人・知人とおしゃべりしても、話題は子供のことや夫の話。そんなことを話していると、ついつい関わってきた子ども達のことが思い浮かぶ。学齢になっても在宅でいる子、施設に入所した子、入退院を繰り返している子。地元の小学校に入学することが親の夢だけど、「子供の将来のためには、早く施設に入れた方が良いのか」なんて、子どもへの愛情故の悩みに苦しんでいるお母さん達のこと。元気な子を持つ親の一般的な話にどうしても乗れないことと、自分の辛さのために、関わった子ども達から逃げたという思いに、どんどん私の心は重くなるばかりだった。「私には、障害児と関わる仕事は無理だったのだ」と思い詰めて仕事を辞めた私なのに、次の仕事がいくつか舞い込んできた。対外的には、「センターができたし、子どもも小学校に入学するし…」なんて、きれいごとの理由を言っていたこともあったのだろう。隣町の、同じような職種の仕事への誘いがあった。これについては、文句なくお断り。次は、子どもに関する相談員のお誘い。(当時は、何の資格がなくても、相談員になれた)これも、当然のようにお断り。不思議な気分であった。こんな私を、似たような仕事に声をかけてくれる人がいる。断りはしたが、ありがたかった。自分がやってきたことが、あながち否定されるものではなかったと実感することは、自己嫌悪病にこれ以上の薬はない。そうやって半年くらい過ぎたころに、何と元の職場から「指導員産休のため、その期間手伝ってほしい」という話。これには、参った。私の後任として新規に採用された女性が、妊娠して産休に入るのだという。私自身、子どもを出産する前後は、臨時に慣れない仕事を引き受けてもらったことがある。だから、「二度と足を向けたくない」とは思っていても、こればかりは断れなかった。ということで、3~4か月くらいだっただろうか、またまた元の職場に舞い戻ってしまうことになってしまった。体制は変化してはいたが、やはりそこはあまり居心地がよくはなかったが、久しぶりに再会した子供たちやお母さん達は、笑顔で私を迎えてくれた。「どう思われているだろう。冷たくされたらどうしよう」と怯えていた私は、みんなの笑顔に本当に救われた。そしてその時、同じ肢体不自由担当の人が(私が辞めた時点では二人体制だったが、三人体制になっていた)「お母さんや子ども達の表情で、先生が良い指導をしていたんだなと思った」と言ってくれたことが、私の自己嫌悪病へのさらなる薬となった。それだけで私はすっかりその人が好きになり、(ゲンキンですね)今でも、彼女との付き合いは続いている。中途半端な時期ではあったが、次男はまたまた保育所、長男は学童保育でお世話になった。自宅でのんびりする生活を味わった次男は、「保育園に行きたくない」を連発していた。「もうちょっとだから、我慢してね」を繰り返していたことを思い出す。その頃の思い出を、ブログのテーマには無関係だけど一つだけ書いておこう。知的障害・情緒障害部門に、勉強のために大学からのスタッフになっていた人が、手相占いを勉強しているということで、見てもらったことがある。すると、私の手相は「これから努力が実る時期になる」と出ているという。どこがそうなっていたのか覚えていないが、みんなに「いいなあ」と羨ましがられた。私は、占いは遊び半分でしか受け取らない性質なのだが、悪い気はしなかった。しかし、「努力が報われるったって、見当もつかない」と思っていた。もう、この世界での仕事をする気にはなれないし、母として、妻としても、家庭での充足感を覚えられない私は、「子どもを育て終えるまでは耐えなくてはならない」という気分でいたから。だから、せっかくの彼の「吉占い」に対しても、またまた仮面の笑顔で、「わー、嬉しいなあ。これからに期待しよう」なんて言ったはずだけど、(やっぱり、占いなんて当たるも八卦当たらぬも八卦だよ)と思っていたはずだ。産休補助の仕事が終了してからは、相変わらず鬱々とした気分を引きずりながら、約一年は「主婦生活」を続けていた。そうそう、この時期に、市の図書室(当時は図書館はなかった)に子供連れでよく通い、「読書サークル」にも参加した。その時の縁が、現在の図書館関係の活動につながっている。その他にも、市民サークルの「手芸講座」なんてものにも参加したり、子どもたちや夫のために、編み物なんてこともした。しかしどれも、その後も続く趣味にはなっていないし、今では私がそんなことをしていた時期があるなんて、家族のだれもが忘れていることだろう。その頃購入した編み機も、押入れの邪魔ものになっている。
2012年11月09日
コメント(0)
-
私の仕事遍歴 2の4 「心身障害児の療育指導員をやめる」
このテーマで最後に書いてから、もう1年たってしまった。実は、書き続ける意欲が低下してしまったのだが、やっぱり中途半端だなと思い直し、書き始めている。今日書くことは、私の仕事遍歴2「心身障害児の療育指導員その2」本文の補足みたいなものである。私は、ハンディを持つ幼児とその親たちとの出会いで、大切なことをたくさん教えてもらった。当時もその自覚はあったけれど、それ以上に自分の力量不足が申し訳なくてならなかった。地区会館の一室で始まり、たった一人の指導員として始まったその仕事も、時代の変化とともに乳幼児の障害児対策も行政の役割としてクローズアップされるようになってきた。重度心身障害児は学齢期になると、「就学免除」という制度があり、一部の学校が併設された施設などに入所する以外は、子ども同士で学ぶ場もなかったのだが、親や関係者の努力や陳情の成果もあり、どのような子供も就学できるようになった。しかし、一般の小中学校にすぐに入学できる体制はなく、多くは「訪問学級」ということで、週に数度先生が訪問してくれるという程度ではあったが、それでもどれほど重度の子供でも、その成長発達をその子に応じて支援するということは、私たちにとってはとてもうれしい一歩であった。私達の町でも、当初は「社会福祉協議会への委託事業」であったものが、市の事業として小規模な障害児通園センターも開設が検討されるようになった。それまでは「肢体不自由児、知的障害児、情緒障害児」など全部受け入れてきて、知識も技術もない私のような名ばかり指導員が、お母さん達とそれぞれの専門家の意見を聞きながらではあるが、ない知恵を絞ってそれぞれの発達を促そうと頑張っていた。私や親の会の人たちは開設当初から、何度も何度も福祉事務所の担当者には、「こんな状況では、だめです。これは一時しのぎです」と言っていたし、大都市の「障害児訓練センター」のようなものを作る必要は伝えてはいた。しかし、「そうだねえ」と理解は示してくれても、「財政が…」ということでチョン。それでも、社会の動向や、近隣の市町村の動きに連動する形で、7年目にやっと、障害児通園センターが開設される見込みとなったのだ。今思い返すと、当時の私はいじらしいほど精一杯ではあったが、常に私の心を苦しめていたのは「専門家でもない私が、こんなことをやっていていいのか」という思いと、遅々として成果の伴わない状況に、(それぞれの子供のこともであるが、行政の対応の遅さも)「私がやっているからダメなのだ」という辛さであった。かといって、その時の処遇では次の人にバトンタッチとはいかない状況もあった。せめて、幼児教育についての資格をと「保母資格」を試験で取ったけれど、私はもっと「障害児についての専門知識」がほしかった。まとまった研修を受けたくても、家庭では二人の子育てに追われ、そんな余裕もなかった。ぐるぐる考えると「やっぱり、私には無理だったんだ」という結論にしかいきつかない。障害児訓練センターの開所に合わせて、それなりに障害児教育・療育を学んだ人が市職員として採用される気配となったため、「やっとこれで辞めることができる」と思った。しかし、新人ばかりでは困るのでということで、1年間だけの約束で新しいセンターで働くことになった。しかしその1年は、私にとっては別の意味で辛いものだった。肢体不自由児部門は、私と保育士一人が担当。知的障害児・情緒障害児・言語障害児部門は、〇〇大学の障害児教育課程の教授や、その学生や卒業生たちが担当することになった。はっきり言って、大学の学閥の中にポツンと入り込んだ感じだったのだ。さらに、大学というものは「研究と教育」が重要視される。研究とは「仮説と証明」によるものだから当然ではあるのだが、大学関係者の子供たちへのまなざしが、どうにも私には違和感があった。私は「肢体不自由児部門担当」ではあったが、幼児の場合、体の障害だけが問題ということはほとんどない。言語や精神発達などはもとより、障害が重度であればあるほど、知的・情緒的・言語的なことは当然として、視覚・聴覚などにまで課題を含むのがほとんど。最初の頃は、専門家や大学の先生たちが身近にいることを喜んだが、その期待も束の間のものだった。詳細は省くが、私にとってはさらなるコンプレックスの戦いと、子ども達を「研究・実験対象」に扱っているように感じる違和感と、違和感すらも自分の知識のなさによるものかもしれないという葛藤とで、1年の後半は、職場に行くことが辛いという、ほぼ「職場拒否状態」に陥った。私はただ義務を果たすだけに職場に向かい、子どもたちやお母さん達の前では、辛さを表情に出さぬよう笑顔の仮面をかぶり、大学関係者とは必要以上の話もせず、かといって職場環境が悪くならないようにと言いたいことも言えずに不満をためこんだ。結果として、その仕事を辞めた時には「責任を果たした」という充足感はなく、「これで明日からこの玄関をくぐらなくていい」という安ど感こそあったものの、逃げ出してしまったような後味の悪さが私の心を苦しめた。それは、主観的には「挫折」以外の何物でもなかった。こうやって書いていても、本当に私って開放的・楽天的なタイプじゃないと思う。自分でできないことを、周囲のせいにしてしまう傾向もある。当時の「自己嫌悪感」が、改めて蘇ってきてしまった。
2012年11月07日
コメント(6)
-
私の仕事遍歴 2 「心身障害児の療育指導員時代 その3、思い出」
しばらくブログをあまり書く気になれなかったのだが、そういえば、私は自分の今までの仕事遍歴について書こうとしていたのだと思い出した。やり始めたことは最後までやらなくちゃ、と、最後に書いたのがいつだったか見直してみると、5月31日の日記だった。なんと、五か月以上も経ってしまっていたこの時に、私が精神的に煮詰まってしまって仕事をやめることになったことを書いているのだが、もちろんその仕事をしている間に様々な思い出がある。辛かったことも多いが、様々な障害を持った子ども達から学んだことは数限りない。短い命を生き切った子もいれば、「三年の命」と出生時に医師から宣告され、そのつもりで精一杯育てていたら、いつのまにか40歳を超えたという子もいる。その多くはダウン症候群の子で、その一人のお母さんは、高齢出産だったこともありすでに70歳を超えてしまい、「こんなに長生きするなんて、想像もしなかった」と苦笑いしながら、今は自分が先立つことが不安な様子。私自身も、当時の唇真っ青な様子にハラハラしたことを思い出し、(心臓疾患を抱えていたのだ)枯れ枝のようなお母さんの姿を思い浮かべながら、複雑な気持ちになってしまう。今までのブログに、この時代の思い出を書いたものがいくつかあるので、それをここにアップしておこう。「Yちゃん」2004年01月09日もっと書いていないかと、過去のブログを見直したが、自分が想像するよりブログの分量が多いので全部確認できず、さらにその時代の子ども達のことについてはYちゃんのことくらいしか見つからない。多分、その子ども達やその親が今も健在のため、書きたくても書くのを躊躇したままになっていたのだろう。でも、すでにあちらの世界に旅立った子ども達について、少しだけエピソードを書いておきたい。その子が、私に何を教えてくれたのか、その子がこの世に生きた証としても…。「あの子の笑った顔を見たいんです」Hちゃんは、重度の脳性まひ児と診断されていた。当時、一歳を超えていたと思うが、寝たきり状態であった。脳性まひは、大きく分けてアテトーゼ型(不随意運動型)、痙直型(四肢変形になりやすい)などがあり、そのほかにも失調型や混合型もある。Hちゃんは、強いて言えば失調型なのかもしれなかったが、なにしろ筋肉はグニャグニャで、自分で動くことはほとんどなく、空腹時に悲しげな泣き声は発するけれど、そのほかの不快を表現する力もないようだった。首もすわっておらず、当然お座りなどもできないし、あやしても笑ったりはしない。それでもお母さんは、首が座らずにグラグラする体を背中にくくりつけるようにして、徒歩や自転車で通って来ていた。私は、お母さんと一緒に医師やPTから指示された訓練メニューで、手足を他動的に動かしたり、抱っこして体を揺らしながらあやしてみたりと、試行錯誤してみたのだが、状態の改善はあまり見られなかった。それでも、他動的に動かすことで、多少ふにゃふにゃだった筋肉が、筋肉らしい張りを感じるようになってきたかなと思うようになった頃、熱心だった母親がピタリと訓練室に来なくなってしまった。しばらくして、心配になった私は家庭訪問をした。母親は、最近ある新興宗教の集まりに通うようになったのだと、申し訳なさそうに言った。聞けば、ずいぶんお金も払っているようだ。私は、神仏頼みでこのような障害が改善するわけがないと思っているのだが、藁をもすがるようにその信仰に頼ろうとする母親に、色々な危惧を言うことができず、やっとの思いで、「それでも、時々は顔を見せてください。他のみんなも待ってますし」と言った。それに対して、母親は遠慮がちではあるがキッパリと答えた。「先生、ごめんなさい。この子は訓練では良くならないって。 今の宗教の先生は、真剣に祈ったら絶対に良くなるからって言うの。 私は、歩けなくてもいい、話せなくてもいい、あの子の笑い顔が見たいんです。」私は、全身をハンマーで殴られたようなショックを受け、その衝撃から自ら逃げるように玄関を後にした。その家に背を向けて歩きだした途端、私はこらえきれず号泣した。何も言えなかった自分に対する情けなさ、母親の切ない思い、無責任に「祈れば良くなる」という宗教に対する怒り、そんな様々なものが全身を駆け巡り、嗚咽が止まらなかった。今でも、こうやって書きながら当時の思いがよみがえってくる。その後、彼女が訓練室に顔を見せることはなかった。祈りの場に連れて行かれたあの子が、せめて集まったみんなにかわいがってもらっていることを、私は祈るばかりであった。その数年後、新聞の死亡欄にHちゃんの名前を見つけた。私は迷ったけれど、葬儀には行かなかった。どうしても行く気になれなかったのだ。その宗教によって、母親とHちゃんは救われたのだろうか。Hちゃんは、笑顔を母親に見せることができたのだろうか。私は、彼女のことも含め、多くの宗教が障害を持つ子の親に優しい言葉をかけて近寄っていくのを見聞きしている。私は宗教を否定するものではないし、人間には宗教心は大切なものだとわかっているつもりだ。それでも、私自身は特定の宗教には決して所属しないとある時期に決めた。特に、強い勧誘や、金品を過剰に売ったりする宗教には、反射的に否定してしまう。今の私であれば、当時のお母さんになんと言うだろう。それでも、あの時のあのお母さんを説得できる自信もない私でもある。「シュウ君」この子もイニシャルはHなので、シュウ君としよう。彼も、重度の脳性まひという障害をもって産まれた。彼の場合は、「アテトーゼ型」だったと思うが、私が出会った当時は4~5歳くらいで、それまで十分な機能訓練もしていなかったらしく、手足には筋肉の緊張からくる変形もみられた。それによって、もともと困難な自分の意思による動きが制限され、不随意運動と筋緊張により、食事もとても困難だったし、言葉を発することもできなかった。お母さんが献身的に見事な介助・介護をする人で、私ならとても怖くてできない食事介助を、息子の様子や動きを見つめ、絶妙のタイミングで食事をさせる姿に、「母親の力ってすごいなー」と感心させられるばかりだった。彼は隣町から、母親が自動車を運転して通って来ていた。見た目は寝たきりの重度障害児であったが、彼は知的な遅れはあまりないように思われた。話すことはできないけれど、みんなが話していることはちゃんとわかっているし、様々な言葉かけや働きかけに、ちゃんと目や表情で意思を伝えてくれる。そして、自分の要求も彼なりに表現しているようで、それを母親が的確に受け止めて通訳をしてくれるのであった。この二人は、本当に一心同体状態に、私にも見えた。同じ時期に、同年齢のやはり脳性まひアテトーゼ型の男の子が通って来ていた。こちらの子の方が障害の程度が軽いのか、動きにくい足を必死に蹴って移動したり、言葉にはならない声を絞り上げるように発して自分の意思を伝えようとしたり、思いどうりにならなかったり、自分の思いがちゃんと伝わらないと泣いたりと、表情は格段に豊かであった。だから私は、シュウ君の方が障害が重いのだと思い込んでいた。ある時医師が「この二人の障害の程度はさほど違わない」と言った時、私は「そんなバカな!」と驚いた。「違うのは、その子の性格と母親の対応です」と言うのだ。シュウ君の方が性格的におとなしく、母親の対応が完璧なせいだというのである。うーん、なるほどと、一応は納得はしたものの、やはり私は半信半疑で、その後の二人の様子を観察した。そして、「やはりそうなのだろう」という気持ちになってきたのだ。難しいものである。母親が完璧に息子の気持ちを受け止めそれを表現したら、子ども自身が必死で訴えたり、悔しがったりしてバタバタする必要もないのだ。それはその子にとっても、母親にとってもストレスのない穏やかな時間となり、それが不幸なこととは決して言えない。しかし、そのことが子どもの「わかってもらいたい」という意欲を刺激しないとしたら…。これが、健康な子どものことであれば答えは簡単である。子どもの自立を願うのであれば、親は心を鬼にして突き放すことも必要なのだ。たとえ障害を持っていたとしても、原則はそうである。もしも、施設に入所しなくてはならないとなれば、やはり他人に意思を伝えられるようにするのも、大切な訓練なのだ。医師やPTはそれを視野に入れての指摘をしたし、私もそれには同感ではあった。しかし、まだ学齢に達していない子どもなのだ。普通の子どもたちでも、まだまだ親に甘えている年頃だ。心を鬼にしなくてはならないのかどうか、私にはよくわからなかった。あの当時、このような母子に対して、よく「母子分離の必要性」が医師やPTから言われることがあった。私は自分の確たる信念もないので、それをオウム返しのようにお母さんに伝えたり、「この子の将来のためには、必要なことだよね」なとと、知ったかぶりみたいに言うこともあった。しかし、内心は迷ってばかりであった。「本当に、この子にそんな将来はあるのか?」と思うことも多かったし、「将来は施設で暮らすしかないのか?」とも思ったり…。結局、いつだって私は中途半端の思いでお母さんや子ども達と向き合うことになっていた。隣町にも、母子通園施設ができて、その時からその親子とは接点がなくなった。シュウ君はどうしたかなあ、と思うことはあっても、確認することもなく年月は過ぎた。何年か前、その町で就労継続支援事業所で働いていた時、当時、いっしょに通っていた別の障害の若者と再会した。驚いたことに、その子も「長生きはできない」と言われていたのに、元気に自宅で生活して、障害者の活動に積極的に関わっていた。「ところで、シュウ君はどうしている?」と聞いた時、「あいつ、去年死んだよ。ずっとお母さんが家で面倒をみていた」と教えてくれた。そうだったのか、あのお母さん、最後まで面倒みていたんだと、私は二人の生き方に、心から拍手を送りたいと思うばかりだった。結局、あの頃の医師達が言っていた「母子分離」はあの親子にはなかった。できなかったのか、あえてしなかったのか、私にはわからない。しかし、その時その時精一杯、彼らににとって一番良いと思う生活を選んだことは間違いが無いだろう。私が彼らと関わった頃から比べたら、格段に福祉サービスは充実しているはずだ。彼らが、十分にそれを活用して、シュウ君なりに納得できる人生であったことを願っている。
2011年11月11日
コメント(0)
-
私の仕事遍歴 2 「心身障害児の療育指導員その2」 本文
私の仕事遍歴 2 「心身障害児の療育指導員」で書いたような経緯で、私は思いがけず「肢体不自由児療育指導員」になることになった。札幌の整肢園での研修は、初めて見聞きすることばかりで本当に大変だった。半年くらい精神薄弱児収容施設にいたからといって、障害について詳しくわかっているわけではない。私はその研修で初めて、脳性まひやポリオの重度障害の子ども達に出会い、それは「ショック」の連続だった。もちろん重度の障害の原因は、ポリオや脳性まひだけではない。毎日毎日、私は新しい病名を教えられ、その子どもたちへの治療やハビリテーションについての説明を受けたが、たった1ヵ月半でそんなことがわかるはずもない。研修を受け入れてくれた整肢園の医師も理学療法士も、そんなことが無理だということはわかりすぎるほどわかっていた。しかし、道内にはそもそも、このような子ども達を受け入れる施設も病院も足りず、主要都市には「マザーズホーム」はあっても、地方の市町村には親同士が集まる場もないのだ。だから、こんな小娘が指導員になることがどんなことかは想像はついても、「ないよりはマシ」ということで、精一杯指導をして下さった。必死に先生達が手渡してくれる参考書を読み、医師や理学療法士の方々にくっついて、お母さん達に語る言葉や、子どもたちへの対応を見逃すまいと努力はしたが、結果的には、多少障害について理解し、基本的な訓練の考え方や方法を知ったという程度にしかならなかった。「これでは、指導なんてできません」と叫びたかったが、もう開設の日は決まっていて、そのための準備にも私が関わらなくてはならず、暗澹たる思いで研修を終えた。それでも、「いつでもわからない時には電話をしなさい」と、色々な先生が声をかけて下さったので、私はそれを頼りに仕事につくしかなかった。その後、開設までに子ども達が使う玩具類や、最低限訓練に必要な器具をそろえたり、福祉事務所や保健婦さんたちに色々と話を聞いたり打ち合わせしたりで、あっという間に開設の日となった。さて、いよいよ「肢体不自由児訓練室」の開設の日がきた。肢体不自由児父母の会の親子が、会館の一室に集まった。これから私が付き合うことになる子どもと親とのご対面である。それ以前から、役員の人たちとは面識があったが、それ以外の人たちとは初めて合うのである。そして私は、集まってくる子ども達を見て「???」と頭の中がパチクリ。というのは、とうてい「肢体不自由児」とは思えない子どもがいたのだ。あとで詳しくそれぞれの子どもの障害や生育歴を聞くのだが、その時に私は、今まで聞いたことのない「自閉症」という病名を聞く。さらに、「ダウン症候群」の子どももいた。私が整肢園で研修を受けたのは、主にポリオと脳性まひについて。もともとはポリオ対応でできた病院&施設だったので、「脳性まひ」については、整肢園でも欧米の研究資料などを学びながらの試行錯誤状態だった。知的障害からくる運動機能の遅れの子どもへの対応は、あまり重要視されておらず、ダウン症候群をはじめとする知的障害についての話も、ほとんど聞いていない。10人前後集まった子ども達の中で、私が研修を受けた範疇に入るのは半分以下。あとは、知的障害と自閉症、さらに後で自閉症とわかる子どもであった。その時の私の気持ちをご想像いただけるだろうか。「私はいったい、どうすればいいの? 何ができるっていうの?」である。現実を知った私は、体の震えが止まらなかった。緊張と不安との塊というのは、あの時の私である。そんな私に、ダウン症候群の息子を持つ一人の父親が言った。「障害は違っても、親の気持ちはおんなじなんです。 今までは、このように集まる場所もなかった。 子どもが友達に会う場所もなかった。 みんな、先生に子どもの障害を治してほしいとか、良くしてほしいなんて思っていない。 ただ、子どもが楽しくなる場所にしてほしいんです」その言葉で震えが止まったかどうかは覚えていないが、私には暗闇に一筋の光のような言葉であった。自閉症の子は、一時もじっとしていられないようだった。常に猛烈な勢いで走り回っている。子どもの中にはごろんと転がっている状態の子も複数いたので、私は「この子がこの場に一緒というのは、危険ではないか?」と危惧した。そんな私の気持ちを察したのか、その母親が言った。「うちの子が肢体不自由児でないことは、よくわかっています。 この子がここにいるのは場違いだとも思います。 でも、この子には他に行くところが無いのです。 お願いですから、ここに通わせて下さい」私に、その痛切な母親の言葉を拒否できるはずがないではないか。そんなところから、私の悪戦苦闘が始まった。最初は、週3回訓練室を開き、あとの3日は在宅の子どもの訪問指導だった。指導とは名ばかりで、訪問して可能ならば子どもと遊び、母親の話を聞くだけ。私は当時も今も自動車を運転しないので、自転車で市内を回った。当時は、私だけではなく女性で車の免許を持つ人はとても少なく、開設日には、免許を持つ会長の奥さんが、ボランティアで各戸を回り送迎していた。ご自分のお子さんも一緒にではあるが。指導なんてできないことははっきりしているが、当時の私はやはり「私は指導員なんだから、それらしくしなくちゃ」と気負っていた。それが自分を苦しめることになるのだが、考えてみれば若い頃は多少の背伸びをして頑張らなくちゃ、成長もできない。私なりに、色々と指導計画を考えたり、一人一人の子どもに何ができるのか考えた。親子の関係、特に「母子関係」が指導に重要と研修で教わったので、そのあたりを観察したりもした。だが、当時の私は母親にもなっていない。そんな私がそんなことを考えて試行錯誤したり、時にはエラソーなことを言ったりして、今では穴があったら入りたいと思うくらいだ。そんな私であったが、お母さん達はみんな優しかった。そして、最初は「エッ?」と思うような障害を持つ子ども達も、次第にそれなりになついてきてくれて、みんな可愛く思えるようになった。視力が無いと言われていた子どもが、少しずつ動けるようになるにつれて、「目が見えるみたい」となり、やがてはお医者さんに「これは見えてますよ!」なんてびっくりされて、みんなで喜び合ったこともある。先天性の無眼球で、家の中をはいずりまわっていた子が、色々な刺激の中で好奇心や意欲も生まれてきて、機械的な筋力トレーニングも功を奏したのか、ちょうど訓練室に来ていた日に突然自分で歩き始め、私も勿論感動したけれど、そこに集まったみんなで涙を流し合った日もあった。今の私は、それは「奇跡」ではなくて当然の成長だったと思うが、当時の私には奇跡的なものに思え、日々のプレッシャーや悩みを瞬間的に忘れ、何とか仕事を続ける原動力になった。しかし、たった一人で毎日障害を持つ子と、その親達と向き合うのは、当時の私には本当に苦しいことであった。そして、そんなことは私でなくても無理な話であろうと今は思う。そんな中で、私は結婚し子どもを二人産んだ。健康な子どもを育てて、私は驚いたものだ。障害を持つ子どもが本当に苦労する壁を、健康な子どもはなんと易々と越えられるのだろう。親が何も教えなくても、訓練をしなくても、我が子は時期が来れば寝返りをし、はいはいしてやがて歩きだし、すぐに走り出す。そんな喜びも確かにあったけれど、やはり仕事と家事と育児の両立は大変だった。加えて、たった一人の指導員の苦しみは、年月がたったも少しも軽減されない。色々なことがわかるようになるにつれ、「こんな私が指導員をしているのが間違いだ」という気持ちになってくる。6年目頃から、私は今思えば鬱状態に近くなったと思う。そして、「心身障害児訓練センター」を市が開所するのをきっかけに、やっと私は仕事を辞めることができた。このセンターが開設されるまでが私の仕事と、思いつめたように日々を過ごしていたので、退職の日は本当に待ち遠しかった。もう2度と、この世界には足を踏み入れないぞとまで心に誓っていた。と同時に、猛烈な挫折感にも襲われていた。あれほど願った「福祉の仕事」を、達成感なしで去らねばならない情けなさ。結婚し子どもを育てながらも仕事をするという、理想を捨てる悔しさ。退職後の私は、解放感からとは程遠い自信喪失感・挫折感と向き合うことになった。蛇足であるが、私が仕事をやめることに決めた時、お世話になった道立肢体不自由児総合療育センターの理学療法士の先生にご挨拶に行った。その時先生は、「君は、孤独に耐えてこれまでよく頑張った。お疲れさん」と言って下さった。私はその先生に、そんなに愚痴をこぼしてはいなかったと思うのだが、(愚痴をこぼしたら自分が崩れそうになるので、誰にもあまり言えなかったと思う)先生は私の辛さをお見通しだったのだと思うと、有難いのと張りつめたものがはじけたように、涙がこぼれて困った。普段の私はあまり涙を流さない方なので、意思に関わらず涙が流れる状態は、やはり鬱だったように思う。
2011年05月31日
コメント(6)
-
私の仕事遍歴 2 「心身障害児の療育指導員」
最近の政治関係や国際的なニュースは、何とも力が抜けることばかり。加えて、年のせいか「ああ…、歴史は繰り返すのかも」なんて呟いていたり。経験というものは所詮個人のものであって、国や集団としての経験知として次代に生かせないものなのだろうか。とすれば、個人の経験が別の人の役に立つなんてありえないことなのかもしれない。結局、経験したことや思い出を書くことは、自分自身の懐古趣味というか、せいぜい自分の原点を確認したりすることでしかないのだろう。それでも、思い出そうとしなければ記憶のかなたに消えてゆくことばかりなので、自分のために一応書いておこうと思う。前に書いたように、精神薄弱児施設を挫折感と共に去ったのは夏であった。何とか自立しようと心に秘めて家を出たのに実家に戻った私は、解放感と共に「これからどうしよう…」という焦りと不安があった。施設に紹介してくれた恩師への申し訳なさもあり、とにかく早く仕事を見つけたかった。新聞の求人広告を見て、札幌の地下街にあるお店の面接に行ったこともある。しかし、どうしても自分が接客業の店員として働く自信がなく、多分、話を聞いただけで「申し訳ありません」と帰ってきたような気がする。そんな私に、遠縁のおじさんから仕事の話が舞い込んだ。その人は、地元の社会福祉協議会の役員をしていた。「今度、地元の障害児者の親達の要請で、市の委託事業として『心身障害児療育通園事業』をやることになったんだ。札幌にある整肢園やマザーズホームに通うのは、障害児を抱えた親にとっては大変なことだ。だから、会館の一室を『訓練室』にして、親達が自主的に訓練をする。でも、親だけでやるのでは運営面で負担が大きいので、指導員としてそこで子ども達と一緒に訓練をしてくれる人を探しているんだ。あんたは施設で仕事をしていたのだから、少しは障害児のことがわかるだろう?どうだい、やってみないか?でも、社会福祉協議会も金はないし、市からの補助金も多くはない。小遣い程度の報酬なので、引き受けてくれる人も正直なところ見つからないんだ」施設から逃げ帰ったとはいえ、福祉の仕事への希望を捨てたわけではない私は、深く考えることなくその仕事に飛びついた。自信なんてものは全くなかったし、どのような仕事を期待されているのかもよくわからない。とにかく、その親達が結成したばかりの「肢体不自由児父母の会」の人たちに会うことにした。中心となっていたのは、重度の脳性まひの子どもを抱える夫婦と、ダウン症候群の息子を持つ父親、サリドマイド障害の子を持つ夫婦であった。彼らはこんな小娘の私に、「ぜひ指導員になってほしい」と頭を下げた。「訓練の方法は親が病院や整肢園やマザーズホームで習ってくる。 自宅で訓練を継続するのは、親も子も意欲が湧きにくい。 あなたは、子ども達や母親達を励ましてくれるだけでいい」その言葉は、自分への自信を失っていた私には、それこそ「神の声」にも聞こえるものだった。こんな私でもいいのならと、私は引き受けることにしたのだ。それからは、十月の開設(なんと、一ヶ月半くらいしかなかった)に向けて、S市にあった、現在の「北海道立肢体不自由児総合療育センター」の前身である整肢園に研修に通うことになった。自宅からは電車とバスを乗り継いで一時間半くらいかかったと思う。今の感覚で考えると、たったの一ヵ月半で指導員になるなんて恐ろしいことだが、当時は通園施設もポリオの後遺症の子ども達を対象にした「マザーズホーム」が主要都市にある程度で、学齢前の障害を持つ子ども達が通う施設などは、地方の町にはほとんどなかったのだ。だから、そんな付け焼刃の知識しかない指導員だとしても、親子が通える場所を作るということ自体が重要だったのだろう。しかし、研修に通い始めて色々と知るにつけ、私は不安とかすかな後悔に心が揺らぐようになった。しかし、もう後戻りはできない。一ヶ月半後には、とにかく訓練室で子どもたちや親達と向き合うしかないのだ。
2011年03月09日
コメント(0)
-
私の仕事遍歴1の4 「施設での仕事の挫折」
さて、知的障害児施設での住み込みのその後である。その施設は、キリスト教系の施設であり、私以外の職員ほぼ全員が信者であった。なぜ私が受け入れられたかというと、まず厨房の職員補充ができていなかったことと、成人施設を開設するにあたり、信者限定ということでは職員が集まらないだろうということで、信者以外でも受け入れようということになっていたようだ。施設側の事情はよくわかるが、私自身はそれほど宗教色の強い施設と想定していなかったこともあり、最初の日から強い違和感を感じたのである。しかし、格別キリスト教に対して悪い印象もなかったし、最初はあまり深刻にそのことを考えずに飛び込んだというのが正直なところである。とにかく、福祉施設で働けるということの前には、どんな条件だって呑むような気持だった。しかし、日が経つにつれて、色々な思いが私の胸に次々に湧きあがり、まだ精神的に不安定だった時期でもあり、数か月でどうにもならない息苦しさが私を覆い始めた。職員の人たちが親切でキリスト教の事や自分が信者となった経緯などを話してくれても、それ自体が強いプレッシャーとなっていった。仕事自体も、子ども達との関わりも嫌ではなかったし、職員の人たちにいやな人がいたわけでもない。ただ、自分だけが信者ではない、キリスト像の前に素直に頭を垂れることが出来ないという疎外感や、色々な疑問を持ちながら、朝夕のミサに参加することに、とても罪悪感を抱くのだった。やがて、半年近くが過ぎる頃、「私はここにいてはいけない」という気持ちになってきた。私が存在することで、みんなの輪を壊してしまう。心から信じてもいないのに朝に夕に向き合うキリスト像が、とても怖くなってきた。「裁かれる、今に罰が当たる」という思いが、心の底に常にあった。しかし、それを園長先生にはもちろん、他の職員の人にも言うことはできなかった。ある日、色々と話をするようになった職員の一人がこう言った。私が迷い悩んでいることは、はっきりと口には出さなくても見え見えだったのだろう。「きっとみらいさんは、いつかベールを被ることになると思うよ」その言葉は励ましだったのかもしれないが、私にとっては最後通告であった。「このままでは、絡めとられて身動きが出来なくなる。まだ正職員ではないのだから、辞めるなら今しかない」どのような理由づけで、どのように辞めると言ったのか全く覚えていない。私の記憶は、「逃げ出した」ということだけである。多分、父が迎えに来てくれて身の回りの荷物と一緒に施設を後にしたのだろうが、その時の記憶もない。施設やキリスト教から解放されたという解放感も当然なかったはずだ。私に残ったのは、強い挫折感と「これからどうしよう」という思いだったはずだ。ただ、幸いなことに逃げ帰った私を家族は非難はしなかった。もともと、代々門徒(浄土真宗)の家庭だったので、特に祖母はホッとしたのではないかと思う。ともあれ私は家に戻り、また少しの間引きこもることになった。たった半年間の施設での仕事だったが、私には長い長い半年間であった。季節は夏になっていた。
2011年02月09日
コメント(0)
-
私の仕事遍歴1 「施設での住み込み(3) 様々な障害を持つ子ども達 」
さて、私の二十歳の頃の精神薄弱児入所施設の話を続けよう。私は、高校生の頃「福祉関係の仕事をしたい」とは考えたが、実際の福祉関係の知識は皆無に近かった。短大では、一応栄養士を目指した勉強だったので、ボランティアで老人ホームや養護施設を「慰問(当時はそう言っていた)」に行った程度。精神薄弱児施設にぞのような子ども達が生活しているのかは、単純に「知恵遅れの子ども達がいる場所」と想像していただけだった。しかし、今の言葉で知的障害と言っても、その原因は一人ひとり違う。最初に「ん?」と思ったのは、この施設には兄弟で入っている人が何人もいるのかなと思ったこと。つまり、とても顔が似ている人たちが何人もいたのだ。勘の良い人はすぐピンとくるだろうが、そう、「ダウン症候群」の子どもたちだった。私が職員に「兄弟で入所しているのですか?」と、今から思えば赤面するような質問をすると、笑いながら「蒙古ちゃん達よ」と教えられた。その頃は、ダウン症候群というより、「蒙古症」と呼ばれていた方が多かったのだろうか。そして、染色体の異常による先天的な障害だと知った。また、「あの子は分裂病だって」と教えられた子は、職員の言うことは全く聞かず、猛スピードで走りまわっていることが多かった。今思い返すと、彼は典型的な「自閉症」だったと思う。まだ当時は、「自閉症」という障害名はあまり知られていなかったようだ。言語障害があり、手足が変形し、不自由な体で何とか歩いている女の子は、脳性マヒであった。しかし、一応歩くこともできるし、身の周りのことも自分で出来る。掃除や配膳の仕事も、時間はかかるけれどできる子だったし、言語障害はあっても、私ですら「この子は知恵遅れじゃないだろう」と思った。まだまだ施設が不足していた時代だから、本来なら身体障害者の施設に入るべき人だったと思う。そうそう、軽度の知的障害ではあったかもしれないが、中学を卒業後入所した女の子もいた。彼女は中学で勉強した英語を知っているので、その施設ではエリート扱いであった。また、一般の家庭なら知的障害としてこの施設には入らなかっただろうと思われる少年もいた。どんな事情があったのかは知らないが、「知恵遅れ」として施設に入ることになったようだ。その施設では、その頃成人施設を併設する準備を進めていた。児童施設での年齢を超えた若者たちの、その後の受け皿がないということから、同じ敷地内に成人施設を作ろうとしていたのだ。台所の仕事をしながら、私は少しずつ彼らが抱えているハンディについて学んでいった。そして、人間の不条理さを改めて考えることになった。本人達には何も責任が無いのに、そのようなハンディを抱えて生を受けた人たちがたくさんいる。それはどういうことなのか。この人たちの幸せって何なのだろうか。さらに言えば、「生きている価値は何なのだろう」ということだ。自分自身の存在価値に疑問を抱いていた私には、彼らが生きているということ自体が謎に近いものがあった。しかし同時に、私の心の中にはとても自己中心的で姑息な感情も芽生え始めていた。「彼らが生きていて良いとするなら、私だって生きる価値があるはずだ」。大変申し訳ないことなのだが、私は自分を彼らの能力と比較して、自信を持とうとしていたのだ。そこはキリスト教を母体にした施設であった。園長先生は言った。「この子たちこそ、神様に愛されているのだ」と。私の頭は混乱した。神様に愛されるということは、理不尽にもハンディを持つということ?毎日、施設内の教会でミサがあり、園長先生が聖書の話をわかりやすくしてくれていた。なるほど・・と感じることもあったが、「どうしてそうなるの?!」という気持ちも同じくらい抱いた。教会に掲げられているキリスト像は、何とも悲惨な姿であった。神様って、どうしてそんなに試練を与えるのか。愛するってことは、試すことか?私以外の職員の人たちはみんなクリスチャンで、次々と参考書を貸してくれたが、私の心にストンと落ちる感じではなかった。色々な障害について知り、それぞれの子ども達のことを知るにつけ、私の胸の中は「?マーク」がどんどん膨らんでゆくのだった。だからこそ、私は仕事中は「没入、没入」とつぶやかなくてはならなかったと言える。
2011年01月26日
コメント(2)
-
私の仕事遍歴1 「施設での住み込み(2) 厨房にて」
さて、施設の自分の部屋に荷物を置くとすぐ、厨房での仕事が始まった。当時施設で生活していたのは、多分入所児童50人くらいと、園長先生をはじめとする職員が10数名だったと思う。現在はっきりとした人数がわかるのは、厨房担当は二人+私の3人。60~70人近くの朝・昼・夜の食事を3人で作るわけである。(職員は全員隣接する寮暮らし)3人いた厨房担当の一人が結婚退職して人手が足りなくなった時に私が現れたので、多分どんな人が行っても歓迎されたはずだ。ただ、炊事作業には施設で暮らす主に女性入所者が、毎日交代で手伝いに入っていた。多分、調理実習を兼ねていたのであろう。私よりも当然台所作業には慣れているわけで、色々と親切に教えてもらったという思い出が残っている。当時の私は、色々な意味で精神的に追い詰められていたこともあり、とにかく必死にその職場に慣れようとしていた。同時に、何とかここで一人前に認めてもらいたいとも思っていた。つまりは、厨房での仕事でちゃんと認められなくては、何事も始まらないのだから。そんな私が作業をしながら自分に言い聞かせていたのは、「没入」ということである。とにかく余計なことを考えず、今現在の作業をいかにきちんと行うかをに没入するということだ。ジャガイモの皮をむく時は、精神を皮むきに集中し、余計なことは考えないということである。ただし、台所の作業はそれだけではないので、例えばカレーを作るために皮むきをするならば、全神経をフルに稼働させて、可能な限り効率的な作業をするために集中するということだ。ということは、働いている人への余計な気配りは不必要ということになる。気配りをするとしたら、その作業効率の目的のためにだけ神経を使うということ。なぜこんなことを心がけていたか今でも覚えているかと言えば、それまでの色々なことでの精神的な悪循環が、余計なことを考え、必要のないことに精神を疲れさせていたからだろうという、自分なりの反省と結論があり、固く決意していたからである。私は(現在でも)何かしている時に別のことを考える癖があり、若い頃はもっとひどかったと思われる。結果的に「心ここにあらず」となり、仕事でも失敗するし余計なことまでやってしまい、非効率的なことになってしまう。ついつい別の事が心に浮かぶと、「没入、没入」とつぶやき、台所に他の職員が入ってきても、「今の私には関係ない」と意識的に目もくれず、「私は今、包丁なのだ」「私は今、タワシなのだ」なんて呟いてもいた。今こうやって書いていて、それは私にとって大事な修行の時間だったように思う。後にも先にも、そのことを常に意識して働いたのは、その時だけだったようにも思う。つまり、やがて台所の作業にも慣れ作業手順も体得し、包丁さばきなどのスキルも上がると、あえて「包丁と意識を一致させる」とせずとも、自然に作業ができるようになるからだ。どのような作業手順が効率的であり、どのような工夫が必要なのかを考えることを続けると、一つの作業で体得することは他にも応用がきくということでもある。さらに言えば、「効率的に」と考えることは「マンネリ」を打破することでもある。状況は日々変わってくるのだから、次なる意欲を喚起するためにも、時々は真剣に今の作業や活動を見直すことが必要だろう。今の私は「没入」なんて言葉忘れていたなあと、これを書いていて気付いた。はっきり言って、最近の食事メニューは究極のマンネリのような気がするし、私の意識は「効率的」というよりも、「いかに手抜きができるか」にのみ働いているように思われる。20歳の私に学ばなくちゃね。
2011年01月16日
コメント(4)
-
私の仕事遍歴1 「施設での住み込み(1)」
成人式も終わった。テレビなどで成人式の様子を見ると、女性は華やかな振り袖とフワフワの襟巻が制服のようである。男性は背広か羽織袴など、もう少し個性があるかな。私たちの頃は、女性も振り袖あり、ワンピースやスーツなどもう少しそれぞれだったのではないか。「ではないか」と書いたのは、私自身はその当時「ひきこもり状態」で、当然成人式などという晴れやかな場所には出られる状況になく、欠席していたからだ。「ひきこもり」は現代の若者の専売特許ではなく、40年前の若者(私のことだけど)にもいたのです。私の成人式は、自分の将来への不安と、両親への申し訳なさと、それよりも何よりも、自分が生きていてもいいのかという恐怖感に押し潰されそうな日だったように思う。さて、そんな私も成人となったわけですから、生きていていいのかどうかではなく、何とか生きる道を見つけなくてはならないと思いました。その時には、「死ぬわけにいかないなら、生きるしかない。生きる理由も見つからないならば、これからは周囲の人へのお付き合いで生きよう」と決めたのです。特に、息子を自殺という形でなくした祖母の気持ちを思うと、私までが自殺してはいけないのだという(その時は)絶望的な諦めがありました。「おばあちゃんが生きている間は生きなくては」、少し誇張したらそんな感じでしょうか。こんな私でも働かせてくれる場所として私が考えたのは、住み込みでの福祉施設での仕事でした。もともと福祉関係の仕事をしたいと思っていましたが、大学進学の時にスポンサーである両親から「お前に福祉の仕事ができるわけない」と断固反対され、やむなく、結婚しても役立つであろう「栄養士」養成の短大に進学しました。結果的に良妻賢母養成の短大にも、理系の学業にも適応できず、卒業間近にしてうつ状態→不登校→ひきこもりです。うつ状態と診断されたのは、当然ながらひきこもりと自殺願望状態になり、周囲からもおかしいとみなされて精神科に連れて行かれてからですけどね。前段はこのくらいにして、ともあれ私は「鬱」の診断のおかげで、苦痛だった短大からは解放されましたが、次は「居心地の悪い家庭」という牢獄に囚われの身となりました。だからこそ、何とか一人で生きる場所を見つけなくてはならなかったのです。中学時代の恩師に相談すると、親戚に精薄児収容施設(現在は知的障害児施設)の職員がいるということで紹介してもらい、食堂の仕事を住み込みでさせてもらえることになりました。40年前には、まだまだ福祉は陽の当らない世界で、好き好んで住み込みで働こうという人は少なかったようです。「給料はお小遣い程度でいいから」という私のような物好きは、施設側にとっても悪くない話だったのかもしれません。(食と住は、施設で賄ってくれました。空いている職員寮がありましたから)両親も、ひきこもり状態よりはマシということで、福祉施設で住み込みをするということには反対はしませんでした。実は、私自身が「就活」をしたのは、今までの人生の中でこれ一回のみなのです。そこは、人里離れた場所に建つ、カトリックの教会が母体となっている施設でした。ここが私の社会人としてのスタート地点であり、当時はわかりませんでしたが、私らしい人生のスタートともなったわけです。そして、あれほど苦痛だった短大での栄養士となる勉強は、ここではからずも役に立つことになったのです。これから少し、自分の今までを振り返ってみようと思います。固有名詞は出さないように気をつけながら、少しずつ書きすすめていこうと思います。
2011年01月12日
コメント(6)
-
昨日は開所一周年
昨日は、勤務する事業所の一周年の日だった。とはいっても、来賓なども呼ばずにささやかに職員と利用者の人たちだけで近くのホテルでの食事会であった。それぞれに、短いスピーチをしてもらったのだが、それを聞きながら、この一年の色々な出来事が頭をよぎる。全てのことが現在進行形での試行錯誤状態だから、まだしんみりと感慨にふけるという感じではないけれど、とにかくみんな(職員と利用者)と大波小波を乗り切ってきたという思いはある。一年間完全皆勤という人もいれば、途中で二度も入退院を繰り返した人もいる。今現在も調子が悪くて、どうしても来れなかった人もいる。事業所に通うことで少しずつ自信をつけ、現在は就労にこぎつけた人、相変わらず、周囲とのトラブルを繰り返す人など本当に個性的な面々だ。「いつまでもここにいる気はないけど、できるだけ早く本当の仕事に就きたいけど、今はここが楽しいのでもうしばらくいたいと思います」「ココに来るまでの十年間は、家にいるしかなかった。 ここに来て、自分で得たお金の価値というものが本当にわかった」「ココに来て、薬の量も減ったし、自分でも強くなったと思う」「ほかでは色々と排除されたりするけど、ここではみんなに許されて癒されて助かってます」と言ったのは、アスペルガー障害で周囲とのトラブルになりやすい青年。そんな言葉を聞くと、やっぱりグッとくるのは私だけではないだろう。そういえば、「私はここで骨を埋めます」という人もいたっけ。一般就労では相当に苦しい辛い経験があったようで、今は就職する気はないようだ。彼女が安心して骨を埋められるように、社長には会社が潰れないように頑張ってもらわなくちゃね。このままみんなのこれからを見て行きたい気持ちもないわけではないけれど、私は私なりに自分の身の丈に合った役割を、別のところで果たしたいと思っている。その後の会食中に、「○○さん、トイレで吐いてる」とのことで、別の職員が様子を聞くと・・。彼はこの数日、食事をあまり取れなかったと聞いていたので、「急にたくさん食べたせいか??」と思いきや何と「食べては吐く」の常習者だったことが判明。事業所のトイレは男女兼用の一箇所なので、今まで誰も気付かなかったということらしい。聞けば、そのことは主治医にも話していないとのこと。昨日の一番の収穫は、そのことがわかったことかもしれないな。とはいえ、私達が治療するわけではないが、その事実を職員にも隠し続けることはなくなり、悩みを共有することができるようになったのが良かったということである。
2008年05月15日
コメント(2)
-
やっと一段落
前の日記を書いてから、全力疾走のような毎日だった。昨日、事業に関する清算請求の書類をやっと作成し、あとでチェックかお叱りを受けるかは別として、関係行政に何とか提出することができた。その間にも、職場では様々な出来事があり、一応先週からは週2日の勤務にはなっているのだが、あまり今までと変わりのない一週間になってしまった。それでも、色々なことがとにかく山を越えたような感じなので、今日は久しぶりに仕事以外でパソコンで遊ぶ気持ちになれている。人はゆとりがなければ自分のこと以外のことに心を使えなくなる。この一ヶ月の私もそんな感じであったが、私の場合は自分自身のことで精一杯というよりは、自分がやらなくてはならないことで精一杯なので、(職員や利用者のことについては、目一杯心を砕いていたつもり)社会のこと色々については、新聞やテレビのニュースにその時々は色々と思うことがあっても、次の瞬間には当面の仕事の課題のことに気持ちが向かうので、社会情勢については「浦島太郎状態」に近くなっている。まあ、こんな時期があるということも、私には悪いことではないだろう。まだまだ色々な課題は継続する気配だが、徐々に自分の役割の範囲を縮小して、いつのまにか「そういえばみらいさん、いつからいなくなったのかな?」となれば理想だと思っている。いつのまにか、周囲は春の気配になっている。庭先のチューリップも一斉に芽を出している。今年は北海道の桜の開花も早いのかな。
2008年04月05日
コメント(2)
-
あと10日・・
現在の役割は、あと10日で卒業。しかし、諸般の事情であとしばらくの間は、パートの形で週2日程度の「助っ人要員」として仕事を継続することになった。それにしても、この一ヶ月はよく働いた。精神的にもかなりハードであったけれど、何とかみんなと乗り越えているという感じだ。おかげさまで、利用者は順調以上に増え続け、人が増えれば問題も起こりやすくなり、かつ仕事も増やさなくてはならないから、つまりは動ける職員が率先して働かなくてはならないということで・・。(実は、精神的にタフではない職員がダウンしてしまい・・)昔、定年退職する人が送別会の席上、「大過なく仕事を終えることができた」という言葉を使うのを聞いて、「たいして仕事もせず、よく言えるよ・・」と内心つぶやいたことがあったが、今は「大過なくあと何日かをしのげるように・・」なんて思う自分に苦笑する。(一応、今はこの事業所の責任者の立場なので・・)責任を取りたくないというのではない。この仕事を引き受けてからは、「何かあったら責任を取ることが私の一番の仕事」と思っていたから、この時期に大変なことが起きて、責任を果たせぬままに次の人に引き継ぐのだけは避けたいのだ。だから、毎日無事に終えると本当にホッとする。ゼロからの出発だったこの事業所を、もう少し見ていきたいという気持ちは無いでもないが、今はできるだけスムーズに、ズルズル引きずることなく卒業したい気持ちだ。それにしても、この一年くらいで私は自分を再発見した。精神的にはあまりタフではないと思っていたのだが、年のせいなのか、あるいはいつのまにか成長していたのか、私は結構、心身ともにタフな人間だったようだということだ。でも、これも「期間限定だ」と思うから頑張れたのかもしれないな。
2008年03月20日
コメント(2)
-
仕事もあと三ヶ月
昨日の職員会議で、4月から私の後任予定の人に了解していただくことができた。今の仕事は、昨年の3月末に突然やってきたもので、最初から「一年間だけ手伝う」という約束であったのだが、正直なところ、不確定な要素もあって不安であった。決して嫌いな仕事でも辛い仕事でもないが、色々な意味で葛藤も多く、私自身の精神衛生上、早期に良い人とバトンタッチしたいと思っていたから、本当に心が軽くなったというのが本音である。とはいえ、職員の中にも障害のある人がいるので、多分退職後もピンチヒッターとして時々手伝うことになるとは思うけれど。この7ヵ月、継続して利用している人たちの様子は、随分変化している。とにかくほとんどの人が明るくなっているし、意欲や責任感、そして体力が強くなっていると、(贔屓目だけではなく)感じる。もちろん、それぞれが病気やハンディを抱えていることは変わりがないし、人によっては、他の人たちの雰囲気になじめなかったり、諸事情により利用しなくなってしまった人や、プラスへの急上昇の反動のように落ち込んでいる人もいるのだが、継続して来ている人たちは、確実に元気になっていることが本当に嬉しい。利用者同士、あるいは職員間でも色々とぶつかり合ったりもめたりしたことは多々あるし、今もこれからも、それは絶え間なく繰り返されるだろうが、それらの波を何とか一緒に乗り越えてきたという実感がある。それが、一人一人の職員の成長にもなっていると思うし、この事業所全体の足腰の強さにつながっている。それらの輪の中にいることができたことは、私にとってとても大きなことであった。もう少し若ければ、あと数年は頑張ろうと思ったのかもしれないが、今は、最初に求められた役割だけは何とか果たして役目を終えたいという気持ちが強い。とにかく、笑顔で役目を終えることができるよう、あと3ヵ月は精一杯できるだけの仕事をして、責任を果たしたいと思う。
2008年01月11日
コメント(0)
-
自分を知り認める大切さ
「心の病」のテーマで書く事がふさわしいかどうかは少し疑問だが、他のふさわしいテーマもみつからないので・・。主に精神の障害を持つ人たちが通う「就労継続支援事業所(B型)」で働くようになって、半年が経過した。今までは精神疾患や精神障害の人たちとつきあう経験はほとんどなかったので、毎日が勉強というか、戸惑いというか、試行錯誤の連続である。その中で、強く感じていることがある。精神障害や精神的疾患(一般的に言うところの「心の病」)についての説明は専門家に任せるとして、今の私が痛感しているのは、自分の障害や病気について理解をしていることが、社会生活や人との付き合いにおいて、何よりも重要だということだ。自分の障害や病気についてちゃん理解をして受け入れることができたなら、かなり重度の障害があっても、何とかやっていけるのではないかと思う。もちろん、精神的疾患や障害についての世間の理解は低く、偏見はかなり強いので、それだけではどうにもならないと言われたらその通りだが、「己を知り、周囲に感謝やお礼を伝えることができた」なら、人というものは、ハンディのある人のかなりの失敗も許し、支えることができると思う。例をあげると利用者の中に、「アスペルガー障害」と思われる人が三人いる。そのうちの一人は、幼い頃から相談機関でその障害を指摘され、親も本人もその障害があるということを認めた上で育ってきた。強いこだわりや、パニックになりやすいこと、人の感情が読み取れずに場違いな反応や怒りを噴出させるなど、色々とトラブルはあるが、それを指摘すると「あ、またやってしまった。ゴメンナサイ」がいえる。あとの二人は、年齢が高いこともあり、今までにその障害を指摘されたこともなく、私に言わせたら、「その障害ゆえの周囲とのトラブルやそれによる精神的ストレス」により、結果的に「精神疾患」の治療を受けるようになったタイプだ。彼らは、いまだに自分がなぜトラブルに巻き込まれるか(本当は本人がトラブル源だが自覚がない)、理解できないままである。私としては、トラブルの都度「あなたにはこのような傾向があって、それが他人に不快感を与えるのだから注意して」と説得するのだが、それが自分の障害によるものだと思っていない彼らは、今までの体験の中で身につけてきた自己防衛反応であると思われる「言い訳や責任転嫁」を、これも障害のせいだと思うが延々とこだわり飽くことなく繰り返す。障害の程度は、後者の〔困ったさん〕の方がずっと軽度だと思うが、周囲とのトラブル度は、障害名がついていない方が重度だ。精神疾患として一般的に有名な「双極性うつ病(躁うつ病)」「統合失調症」は、入院体験などで病識があるので割合対応は楽であり、特に「統合失調症」の人たちは、病気のせいか薬のせいかはよくわからないが、穏やかで優しい人が多く、私の好きなタイプである。上記に書いた「アスペルガー的障害」よりもっと〔困ったさん〕は、「人格障害」の範疇に入ると思われる人たちだ。しばらく付き合ってみて色々な情報を総合すると、「この人は○○性人格障害だろう」と考えるととても納得できるのだが、この障害も病名として表現されていることはない。たいてい、「うつ」や「睡眠障害」などと、とても一般的な病気で通院している。しかし、問題の根っこは、本人の中にある一種の障害のはずだと思うが、それを正しく理解している人はいない。医師でもない私達がそれを指摘できるはずもなく、とにかく本人がトラブルを起こさないための工夫をしてゆくしかないのだ。本人が自分の欠点や弱点を自覚していたなら、たとえ何かトラブルや失敗が起きても、「ごめんなさい」「ありがとう」の二つのフレーズをとにかく口にすることで、何とか次に進むことができるのに、その二言が言えないばかりに、悪循環に陥ってゆくのだ。現在、発達障害のお子さんを育てている親御さんや、教育関係者に強くお願いしたい。「ごめんなさい」「ありがとう」が言える人間になるように育ててくださいと。失敗を怒られ続け、馬鹿にされ続ける体験を重ねると、自己防衛としての「いいわけ、責任転嫁、怒りのパニック」の反応が強化され、現在私達が関わっているような「大変な困ったさん」になってゆくような気がする。
2007年11月24日
コメント(4)
-
ピンチはチャンス
懸案だった問題が、解決とはいかないまでも対処の方向性が見えた。今週初めから、またまた問題(というより事件)が勃発し、いよいよ自分達だけでの問題解決は困難な事態となり、関係者や家族とも連絡を取り合い、今夜その「会議」が開かれた。具体的に書くことはできないけれど、お互いの情報を持ち寄り、それぞれがどのように対応してゆくべきかの役割分担とポイントを確認し、具体的な知恵を絞りあった。人間社会は捨てたモンではないとつくづく感じている。困った人を切り捨てたり排除するのはとても簡単なことだが、それでは本当の問題は決して解決はしない。何よりも、どのような人もなりたくて困った人になっているわけではなく、色々なことの悪条件や悪循環が重なり、結果としての現在がある。そのことの責任や結果は厳しく受けとめて貰うしかないが、決して見捨てたわけではないとのメッセージを伝え続け、可能な限り応援してゆくという覚悟と、やり直しのチャンスを用意し続けるのが、このような仕事をしているものの責任だと思う。今となれば、今週始めの事件はピンチではあったが、これがなければ次の展開にはなりにくかった。一瞬「ウワッ!」とは思ったが、次の瞬間に「私達はついているかも」と思ったのも本音。多分、このようなことを繰り返すのが私達の仕事なのだろう。そして、このような経験を積み重ねて、足腰の強い事業所と成長していくのだろうと思う。とはいえ、疲れた一週間がやっと終わった。次の段階にもまた、色々なこともあるだろうが、まあ何とか乗り切れるだろうと信じたい。
2007年10月26日
コメント(2)
-
どんな一週間になることやら・・
この二週間ほど、仕事上のトラブル対処に追われている。今までも色々な出来事が次々と起きてはいたが、一ヶ月前に「超トラブルメーカー」が利用するようになってから、気が休まる日がない。多分、今週が正念場になると思うが、ハッキリ言って「超平和主義者」の私には、ストレスフルな日が続いている。しかし、これが私の仕事なのだ。他の職員と協力し合って、何とか頑張りたいと思う。無事に乗り切れることを信じたいと思う。
2007年10月22日
コメント(4)
-
ガッカリする時
若い頃から、色々な「障害(ハンディ)を持つ人たち」と出会ってきた。今までは、主に身体や知的障害の人やその親との出会いが多かったが、5月からは「精神」の病やハンディを持つ人たちと付き合うようになっている。障害を持つ人たちに対して、昔に比べたら随分理解は広がったとはいえ、いまだに世間の目は優しいとはいえない。特に、今までは精神的疾患への偏見の強さや、医療での措置が多かったため、精神障害への理解は、身体や知的の障害よりもまだまだ浅い。だいたいこの私自身が「統合失調症(かつては精神分裂病)」とわかって付き合っていた人は、たった一人である。(多分、知らないだけで、この病気を抱えている人はもっといるはず)どのような障害であっても、ハンディを持つということで、みんな大なり小なりの辛い体験をしている。いわれなき偏見で心が傷ついた体験をしている。そのような経験をバネにして、多くの障害を持つ人たちは、自分の持っている能力を生かそうと努力しているし、それによって周囲の人の理解を得たり、尊敬や信頼を得たりもするし、健常者と言われる人や健康であることを自認している人は、「自分のあたりまえの状態」がいかに幸せなことかを確認したり、感謝することが多い。私自身、何人ものハンディを持つ人たちに、大切なことを教えてもらってきたと思っている。それだけに、時々とてもガッカリすることもある。それは、違う障害を持つ人たちへの思いやりのない言葉や行為を目にする時だ。障害による辛さを体験していない人が「つい、うっかり」相手を傷つけることは多いし、それはある程度やむを得ないこともある。しかし、時々、違う障害ならばまだ「理解不足」と思えるけれど、同じ障害を持つ人同士が、非難したり馬鹿にしたりすることがある。そんな時、本当に人間ってちっぽけなものだなと思う。傷ついて、自信を失っている分だけ、残ったプライドが肥大化しているのかもしれない。だから、自分より劣っていると思える人に対して尊大になったり、時には攻撃をしたりするのかもしれない。そんなことを思いながらも、そのような場面に出会うとガッカリするのだ。少しずつ自信を深め、心のキャパシティを広げていってほしい。そして、ハンディを持って辛い思いをくぐりぬけてきたからこそ、気がついてきた大切なことを、その生き方で発信していってほしいと願う。
2007年09月16日
コメント(7)
-
頭の痛いことが続き・・・
仕事をするということは、我慢も悩みも責任も引き受けるということはわかっているつもり。今の仕事は、全てが白紙状態からのスタートであり、色々と課題が出てくることは予想もしていた。それにしても、色々とあるもんだというのが現在の心境。その多くは、スタッフの約一人に、福祉的な考え方がなかなかわかってもらえないことに起因している。それも含めて、これが「精神の障がい、精神の病気」というものなのだということを学ぶ日々が続いている。またまた、ちょっとばかり眠りの浅い日が続いている。こればかりは、自分の意志では何ともならない。どんなことがあっても、布団に入ればすぐに眠れるという人がつくづく羨ましい。これが、私の弱点だなー。でも、基本的な方向性や職員やメンバーへの対応方針については、私には揺らぎはない。それを、どのように分かってもらったり気付いてもらうかに、あれこれと試行錯誤を続けているということだ。私には、まだまだ修行が必要だったということだろう。
2007年09月05日
コメント(0)
-
コムスンを他山の石に
厚労省がコムスンの指定打ち切りへ、政府は対策本部設置 6月6日17時53分配信 ロイター[東京 6日 ロイター] 厚生労働省は6日、グッドウィル・グループ の子会社コムスンに対し、新規事業指定と6年ごとに行われる指定の更新を行わないことを、各都道府県に通知した。政府は顧客流出に備え、受け皿確保のための対策本部を設置する方針。 コムスンは、グッドウィルの100%子会社で、24時間在宅介護サービスなどを行う総合介護サービス会社。今回の措置は、青森県と兵庫県で、コムスンが不正に介護事業所指定を受けたことによる行政処分。 2011年度まで新規の事業所指定を行わないほか、6年ごとの指定更新も受け付けない。コムスンは、今年5月末で2081カ所の事業所を持つが、来年4月以降2011年度までに、約1600カ所の事業所の更新期限が来るが、これらの更新は行われないことになる。 コムスンの顧客流出が懸念されることに関し、塩崎恭久官房長官は6日午後の会見で「受け皿確保のため、厚生労働省で対策本部を設置するなど、万全を期する考えだ」と述べた。 グッドウィルは6日、サービス継続と従業員の雇用確保を最優先するとのコメントを発表している。 <グッドウィル株はストップ安、介護関連株には買い殺到> グッドウィルの2007年6月期連結売上高予想は5000億円。このうちコムスンは700億円となっている。6日の市場でグッドウィル株はストップ安(比例配分)の7万1800円まで下落、約12万9598株の売り物を残した。 一方、ニチイ学館 や、やまねメディカル 、ジャパンケアサービス 、セントケア・ホールディング 、ツクイ など介護関連株には、顧客のシフトが予想されるとして買いが殺到した。コムスン、グループ内譲渡を発表…介護事業継続を狙う 6月7日3時5分配信 読売新聞 訪問介護大手「コムスン」(東京都港区)が、厚生労働省から介護事業所の新規指定などが認められなくなった問題で、親会社のグッドウィル・グループ(GWG)は6日、コムスンの全事業を、同グループ連結子会社の施設介護会社、日本シルバーサービス(東京都目黒区)に譲渡する方針を決めたと発表した。 GWGは、「顧客へのサービス継続と従業員の雇用の確保を最優先するため」としている。 厚労省の指導で介護事業所の新規指定と更新が5年間認められなくなり、コムスンの事業所は現在の2081事業所から2011年度には426事業所にまで減少する見通しとなった。GWGは、日本シルバーサービスに事業を譲渡することで、コムスンが行っている訪問介護事業は継続できるようになるとしている。 いよいよこのような事態になったという感じだ。企業論理で福祉事業を進めると、このようなことにつながるという教訓を「福祉関係事業」に関わる人たちは胸に刻まなくてはならない。このような事業を展開する時に一番重要なのは、その根本の【福祉の思想】だと思っている。つまり、「利用者(老人、障害を持つ人たち、子どもなどの社会的弱者と言われる人達)」の社会的な権利を守り「人間らしい生活」を支えるのが福祉事業の使命だという信念だ。そのような使命感を持つ人が上に立たなければ、このようなことになるということだ。目先の利益にとらわれず、福祉事業を展開する企業としての信頼を築くことが、結局は企業を守ることになるのだと思う。私自身、その仕事につく者として、しっかりと胸に刻んでゆかなくてはならないと思う。
2007年06月07日
コメント(6)
-
多忙につき、更新をご無沙汰しています
このところ、色々なことを考えたり処理しなくてはならないことが重なり、パソコンには向かうのですが『日記』にまで手も心も回らない状態です。でも、忙しいけれどそんなに疲れてはいません。いわゆる「張り切っている状態」で、元気です。放置状態なのに覗きに来てくださる方には申し訳ないのですが、あと1~2ヶ月はこんな感じだと思いますので、ご了承ください。
2007年06月05日
コメント(0)
-
仕方ない、やるしかない
十数年ぶりに仕事をするようになって、一ヶ月が経過。とはいっても、本来の業務が始まったのは今月半ばなので、役員やスタッフがそれぞれの役割で働き始めてから二週間。色々なことが具体的にわかってくるにつれ、頭を抱えたり不安に感じたりすることの連続である。利用者の人たちとの関係の問題については、ほとんど想定内なので驚きはしない。というより、想像よりも楽しい毎日だと言える。しかし、事業所として職員を雇い補助金を貰いながら運営するために必要な事務処理については、ほとんど「真っ白」であることを日々確認して、今週初めは「頭は真っ白、顔面蒼白」状態になりそうなのを堪える毎日でもあった。ある日突然、色々な経緯で声がかかり、はっきり言ったら「ドンと座っていてくれていいから」とまで言われて引き受けたのだが、とてもとても「ドンと座っていられる状態」ではない。熱意と志はとても大切だとは思うが、信頼を勝ち取ってゆくにはそれだけではダメだ。何しろ、日々色々と対応しなくてはならないこと、処理や整備が必要なことが起きるが、その都度右往左往していたのでは、どれもこれも中途半端になる。この二週間で私も覚悟を決めた。少なくてもこのメンバーの中では、私が仕切るのが一番のようだ。今日は、私がどうしても都合により休むことになるので、来週以降の仕事の課題や役割分担について話し合ったのだが、全ての情報は私を通して整理してゆくことを確認した。私はスタッフの中では一番の「新参者」なのだが、もう遠慮するのはやめることにした。しかし、それは自ら自分の仕事を増やしたということでもあり、「あーあ、また昔と同じパターンに入ってしまうのでは・・」という思いはある。しかし乗り込んだ船だから、この船をバタバタと転覆させるわけにはいかない。それにしても、自分が「優先順位判断力」が人よりあるとは思っていなかった。能力というものは《相対的》に見えるものだから、少なくても現時点では・・ということである。きっとそのうちに、若い人たちが育ってくれるだろう。それを期待したいと思っている。
2007年05月25日
コメント(0)
-
自宅でもあれこれと・・
職場にもパソコンはあるけれど、利用者の人たちが使ったり他のスタッフが使ったりで、なかなか私が使える状況にない。というわけで、自宅でも色々と仕事関係のことをすることになる。もう仕事をする気はなかったし、ましてや「仕事を持ち帰る」なんてことは絶対にしたくなかったのに、人生というものは思い通りにはいかないものだ。でも、久しぶりに「アレやらなくちゃ、コレはどうしよう・・」と考えるのは、新鮮な気分でもある。まあ、「臨機応変テキトウに」は随分体得してきているので、以前のように「煮詰まって背負い込んで苦しくなる」ということはないだろう。ボチボチやっていきます。でも、その分だけ、楽天日記はおろそかになることは確実ですので、ご容赦ください。
2007年05月20日
コメント(0)
-
またまた睡眠下手になってしまった
毎日、それなりに気を使ったり緊張もしたりするせいか、はたまた、体の方があまり疲れないせいなのか、布団に入ると目が冴えてくる悪い癖が出てきてしまった。とはいえ、短時間でも熟睡しているのかもしれず、さほど疲れる感じはしていない。それにしても、「ゼロからの出発」は楽しみでもあるがなかなかゆるくない。まあ、なるようになっていくのだとは思うが・・。社会では色々なことが起きているし、新聞などを見てそれなりに感じること考えることはあるが、今は、新しい仕事のことで頭が一杯。ブログ更新をしていないことも、あまり気にもならない。ということは、「ブログ中毒」ではなかったようである。事業所のホームページは、利用者の人たちに拙くても作成してもらうことにした。一つ一つみんなで考えて、みんなで創り上げてゆく充実感を共有したい。そんなあれこれを考えていたら、目が冴えて来るんだなー。
2007年05月17日
コメント(0)
-
初心を忘れないこと
今日は久しぶりに、ゆっくりパソコンに向かっている。障害者自立支援法による、「障害者就労継続支援事業B型」の事業所スタッフとなり、来週のオープンをめざして4月から準備を進めてきた。このブログではその事業所についての詳細は書かないつもりなのだが、この一ヶ月半で色々なことがわかってきた。この事業は、就労経験がある人で、障害や病気などで企業等で働くことが困難な人に、自分のできる範囲で働きながら自立をめざすための場を提供する。私達の事業所は、主に精神の障害や病気を持っている人を対象としているのだが、心ならずも精神の病や障害を抱えることになった人たちの現状が、この一ヶ月で実感として理解できるようになった。今までは、主に身体や知的なハンディを抱える人たちや親と出会うことが主だったので、色々とお話を聞けば「なるほどなー」と思うことも多い。一番痛感しているのは、病院や病院が運営する「デイケア」や、かつての「小規模授産施設」などから「地域生活支援センター」に転換したところとの綱引きである。私達の事業所は、昨年10月の法改正で認められるようになった「株式会社としての運営」なので、従来の福祉や医療分野からの抵抗感は、想像以上に強いというのが実感である。私自身、長年福祉分野で働いていた経験もあるので、その企業が福祉事業を行うことへの警戒感は理解できる。しかし、最初はそれは当然だと思っていた私も、実は「利用者の取り合い」という側面が強いということをやっと理解できるようになって来た。つまり、そこには「利用者(ハンディを持つ人)」の利益優先というよりも、自分の事業所の存続のために利用者や患者を抱え込みたいという構図がある。それも理解できないことはないが、何よりも大切なことは利用者がその間で翻弄されることがないことだろう。人は誰でも、働きたいという欲求がある。ましてや、かつては就労していたけれど病気のために働けなくなった人は、何とかしてまた働けるようになりたいと思うのが当然だ。そして、少しでも働いたらそれへの報酬があってこそ、働き甲斐や意欲も沸いてくる。「授産所」のように、毎日働いても利用料を払うと手元に残るのは一万円前後というのでは、あまりにも人をバカにしている。意欲も減退しストレスも増えるというのが、当然の成り行きではないか。もちろん、その人の状況によっては、まずは「人に慣れる」ことを目的とすることがあってもよい。家にいて孤独であるよりは、仲間のいる場で休んでいたい人がいてもよい。でも、働きたいという意欲のある人については、それを応援するのが病院や支援センター、そして私達のような事業所の使命だろう。とはいえ、私達だって運営して行く中で今の気持ちを見失うことだってあるかもしれない。(いや、確実にそのような落とし穴に遭遇する時は来るだろう)少なくても、私は「お給料が必要」で働き始めたわけではない。この事業所の社会的な役割を確認し続けることが、私の仕事なのかもしれないと思う。
2007年05月12日
コメント(4)
-
仕事が向こうからやってくる
人生は、地図のない旅のようなものだなと思う。二日前、突然私の携帯が鳴った。登録されていない番号だったので一瞬躊躇したのだが、出てみると旧知の友人だった。彼女とはしばらく会っていなくて、共通の知り合いから私の携帯番号を聞いたのだという。「ごめんね。どうしてもすぐに連絡が取りたくて・・」が、開口一番であった。彼女が4月から仲間と始めようとしている、「ハンディを持つ人たちの就労支援事業」に参加の要請であった。福祉の仕事から離れて十年以上もたつので、めまぐるしく変化する福祉制度についてはあまりよくわかっておらず、「とにかく詳しい話を聞いてから」ということになり、昨日、計画を進めている人たちと会って、その理念や方向性、私に協力を頼むに至った経緯などを聞いた。中心となっているのは30代の若者であった。先日、テレビで「社会起業をめざす若者が増えている」という報道を見た。かつては「社会福祉事業」といえば「障害を持つ人たちを助けるために自己犠牲で働く福祉従事者」というイメージが強かったが、やっと、「ハンディを持つ人たちと一緒に、社会貢献も目的とする企業」を考えられる時代になってきたのか、と、金儲けだけではなくて、社会貢献や生きがいを同時に求める意欲ある若者達が沢山存在することに、「今の政治や社会には色々腹立たしいことはあるけれど、世の中捨てたものではない」と、思ったばかりであった。かつて、福祉の仕事に従事していた頃、夢のように考えていたことを、具体的に実行しようとしている人たちがここにいる。この人たちを応援したい。一緒に試行錯誤をしてみたい。そんな気持ちが心の中に湧き上がってくる。しかし・・・私は、昨日まで全く仕事をしようとは考えていなかった。いや、正確に言うと「報酬を得る仕事は卒業した」と思っていた。だから、仕事を探そうなんて露ほども思っていなかったし、それを前提として、複数の地域活動に関わっている。それに、実家の両親のこと、あと半年で退職する夫のこと、いよいよ自分の畑で「農業」に取り組もうとしている長男家族のことなど、私ができる「人としての仕事」を必要とされる分だけやっていこうと思っていた。だから、「一緒にこの仕事をやってみたい」という気持ち以上に、これを引き受けたら全部中途半端になってしまうのではという懸念も強い。とりあえず、「もう少し考えさせて」ということで昨日は別れたのだが、昨夜は今までの自分の仕事や歩き方を振り返りながら、暗闇の中であれこれと考え続けてしまった。(いよいよ睡眠不足だー)私は、就職活動をしたのはたった一度しかない。それも、鬱状態で短大を中退し、やっと動き出せるようになった時、中学時代の恩師に、「中学生の頃からの希望だった福祉の仕事がしたい」と、話しただけだ。先生はすぐに、福祉施設の指導員の知人を紹介してくれた。その人のつてで、丁度調理の人が急に辞めて困っていた知的障害児・者(当時は精神薄弱者と言っていた)施設で、住み込みで働くことになった。もちろん、私はやっと鬱から回復傾向だったけど、まだ不安定だったし、「まあ、ちょっと働いてみたら」ということだったので、給料なんてお小遣い程度。(食・住は与えられたから、十分だったけど)その後、「煮詰まって退職」を三回繰り返したのが私の職歴だ。主観的には「煮詰まって逃避」だったのだが、そんな私に、ちょっと休むとすぐに次の仕事の声がかかった。「今度こそずっと頑張るぞ」と思うのだが、十年くらいで疲労困憊・酸欠状態。ヘロヘロになって退職してしまった。全部福祉関係の仕事だったし、「ご主人がいるから低報酬でも何とかなる人」ということで声がかかっているし、何しろ十年くらいで退職してるから、長く働いていたわりには報酬に恵まれた人生とはいえない。それでも、在職していた時には必死に働いたし、だからこそ次の声もかけていただけたのだと思う。最後の退職をしてから通信で勉強している間も、実は何度か福祉関係の仕事の声はかかった。しかし、「もう、報酬をいただく仕事は十分やった」と思ったし、人の仕事は、お金を貰う仕事でなくてもいっぱいあるということを実感したので、仕事を本当に必要としている人の場所を取る気にはならなかった。何より、本質的にはグータラで、家で一人で本を読んだりパソコンを使ったりするのが好きな性格なので、このまま老後に突入するのも悪くないと、つい二日前まで思っていたのに。こうやって書きながら、「これが私の宿命かも」と感じている。仕事が向こうからやってきて、「やってみたい」と心が動いて、その気持ちに突き動かされるように「やれるまでやってみよう」と思い、みんなに引っ張られながら動いてしまう。あまり主体的・意欲的とは言えない働き方だけど、こんな働き方をするように生まれついたとしか言えない感じがする。よし、引き受けてみるか。こんな個人的なダラダラとしたつぶやきに、ここまで付き合ってくださった方たち、ありがとうございました。また、必死に仕事を探していらっしゃる方には、不快な内容だったでしょうね。ごめんなさい。
2007年03月10日
コメント(4)
-
学生無年金障害者訴訟判決
昨日のニュースであるが、東京の地方裁判所で「障害基礎年金の支給を拒否されたのは違憲」として、国に年金不支給処分の取り消しと、総額8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決の記事を見た。実は私の知人の一人も、別の地方裁判所で原告になって、現在も裁判が続いている。この判決は、全国で訴訟を起こしている学生無年金障害者にとって、どれほど勇気付けられるものであったことか。知人は、大学卒業を目前にして、事故による頚椎損傷で首から下が不自由な身となった。就職先も決まり、希望と意欲に満ち溢れていた時のことであった。当時はまだ進学率も高くなかったし、今よりもずっと多かった貧乏学生のほとんどは、国民年金になど加入していなかったことであろう。彼が何年もの間入院し、リハビリの後に家族の介護による生活を在宅で始めたときには、30歳を超えていた。その後、わずかに動く指先でパソコンを使うようになり、障害者の小規模授産施設のような場所で、少しばかりの収入を得るようになった。私が彼と出会ったのはそんな時であったが、私はその頃彼が無年金であるとは、全く知らなかった。それでも、重い障害を持ちながらも積極的に障害者運動などに参加をする中で、生活を共にする女性と出会い、現在はその奥さんの収入によって生活をしているはずである。彼が「無年金訴訟」の原告になったというニュースを新聞で見て、私は初めてそのことを知った。結婚するまでは両親に生活費を依存せざるを得なかった彼は、親への遠慮もあったのか、親しい人にも自分が無年金であることを話していなかったのだ。そのような状況の彼と結婚し、生活全般を支え続けている奥さんには本当に頭が下がる。一日も早く、彼らが生活についての不安を解消できるようにと祈っている。そして、他の地域での裁判が、すみやかに行われるようにと願う。
2004年03月26日
コメント(0)
-
Yちゃん
まだパソコンを使っていなかった頃、思い出すままにワープロで「思い出の人」をエッセイとして書いていました。それを「ふと思い出す人達」というテーマで、順次書いていきたいと思います。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Yちゃん 20年以上も前、私は人生の迷路に迷い込み、生きることの意味を虚しく問い続けていた。障害幼児の母子通園センターで指導員の仕事をしていた私は、様々なハンディを持つ子どもや母親達の悩みや苦しみを見ていて、いよいよ人が何のために生きているのかわからなくなっていた。 そんなある日、新しい通園児が入ってきた。彼女の病名に私は目を疑った。そこには「猫泣き症候群」と書いてある。染色体の異常によるもので、心身の発達は著しく遅れ、か弱い泣き声が猫の声に似ていることから、その病名がついたのだそうだ。私達は初めて知ったその病名に驚き、かつ怒った。「こともあろうにこんな病名にするなんて、あまりにも失礼じゃない!」しかし、彼女「Yちゃん」と付き合うようになった私は、その病名しか思い浮かばなかった人の気持ちがわかるような気がした。いくら話しかけても視線は合わず、笑顔もなく、両手を前についてやっと座っている姿や、時折悲しげに「ミー、ミー」と泣く声は、猫とどう違うのかと思ってしまうのだった。(人間って何なの? 人間と動物の違いって、何なの?)私は何度となく心の中で呟いた。それでも私の仕事は、Yちゃんの発達を少しでも促すことだった。抱いている時には穏やかな表情をすることを手がかりに、彼女を抱いて体をゆすったり、一緒にブランコに乗ったり、歌を歌ったりくすぐったりを繰り返した。それをしている時すらも、か細い声を聞くたびに、「猫」の連想から逃れられないことがやりきれなかった。数ヵ月後であっただろうか。いつものようにYちゃんを抱き、耳元で手遊び歌をささやきながら彼女の身体をくすぐった私の耳に、「ハハ・・」とか弱い笑い声が聞こえた。ドキッとした私は、Yちゃんの顔を覗き込む。すると、どうだろう。彼女の丸い目と私の視線が、初めてしっかりと合ったのである。「Yちゃん、やった! Yちゃん、偉いね!」私は嬉しさのあまり、ただそう繰り返した。この子はYちゃんなんだ。病名なんて関係ない。私と遊ぶのを喜んでくれるYちゃんなんだ。その瞬間、私は「人間」とは何なのかを、漠然とではあるがわかったような気がした。彼女は私の迷路の案内人になってくれたのだ。 -1995年頃記す-
2004年01月09日
コメント(0)
全51件 (51件中 1-50件目)
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 人は性善でも性悪でもある。
- (2024-11-16 07:54:43)
-
-
-

- 株式投資日記
- ETHのステーキング報酬受け取った。E…
- (2024-11-16 16:39:19)
-
-
-

- 気になったニュース
- 兵庫県の闇をぶっ壊す!立花孝志さん…
- (2024-11-16 19:36:41)
-