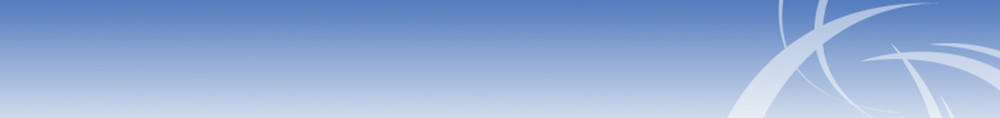13物質およびTVOCといわれる総揮発性有機化合物量の室内濃度指針値(別項表)
が設定されており、一般的にこの『個別の室内濃度指針値』の資料は、シックハウス問題に取り組んでおられる建設関連の会社資料や関連書籍などに記されています。
これら資料を参考にされる場合、
「どの化学物質が設定されているのだろうか」又、「設定された化学物質の指針値はいくら
だろうか」
というのがほとんどだと思いますが、ここではこの『個別の室内濃度指針値』の概要についてシッ
クハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会で報告された内容をA、B、Cの段落に分けて掘り
下げていきます。
A
現状の研究では指針値が策定された物質と体調不良との間に明確な対応関係は証明
されていないので、今後の研究、調査が必要とされるが、これらが明確になる前であっ
ても、現時点で入手可能な毒性に係わる知見からこれらの物質の指針値を定め、指針
値を満足するような建材等の使用、住宅や建物の提供並びにそのような住まい方を普
及啓発することで、多くの人たちが健康悪化を来たさないようにすることができるはずで
ある。
B
なお、指針値は、今後集積される新たな知見や、それらに基づく国際的な評価作業の
進捗に伴い、将来必要があれば変更され得るものである。 指針値の適用範囲について
は、特殊な発生源がない限り全ての室内空間が対象となる。
C
一方、指針値設定はその物質が「いかなる条件においてもヒトに有害な影響を与える」
ことを意味するのではない、という点について、一般消費者をはじめ、関係業界、建物
の管理者等の当時者には、正しく理解いただきたい。客観的な評価に基づく室内濃度
指針値を定めることは、化学物質が健康影響の危惧を起こすことがないように安全か
つ適正に使用され、化学物質が本来もっている有益性が最大限生かされることに大き
く貢献するはずだからである。
まずAの段落部分ですが、『 シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い その2
』においても、シックハウス症候群は「指針値が策定された物質と体調不良との間に明確な対応関係は証明されていないので医学の専門家には支持されにくい」と記しましたが、それが証明されるのを待って健康被害が出ては手遅れになるので、現状において知りえる情報を最善に生かし、対応していくという意味を込めて「個別の室内濃度指針値」が示されたといえます。
但し、指針値を遵守することで健康被害が起きないとは述べていません。その辺りについては、
あくまでも指針値であるということも認識する必要があります。
次に、Bの段落部分ですが、指針値は今後の新たな知見などによって変更されると記述があります。この辺りも先送りの形にならないように対応を望むところではあります。
最後にCの段落部分ですが、化学物質の毒性と危険性という意味を誤解することなく、正しく理解していく大切さを記されています。
このように表面的に室内濃度指針値の設定された物質やその設定濃度を知るだけでなく、室内濃度指針値の策定された根本を今一度理解していくことも大切なことだと思います。
最後に、この「個別物質の室内濃度指針値」が策定されたことがゴールではないということは心に留めておく必要があります。
-
シックカー症候群 2011.09.22
-
化学物質の危険性(リスク) 2011.09.13
-
毒性 2011.09.11
PR
カレンダー
サイド自由欄