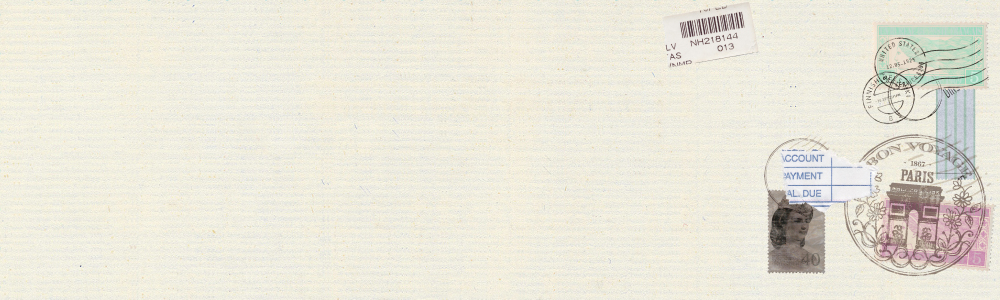2025年03月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
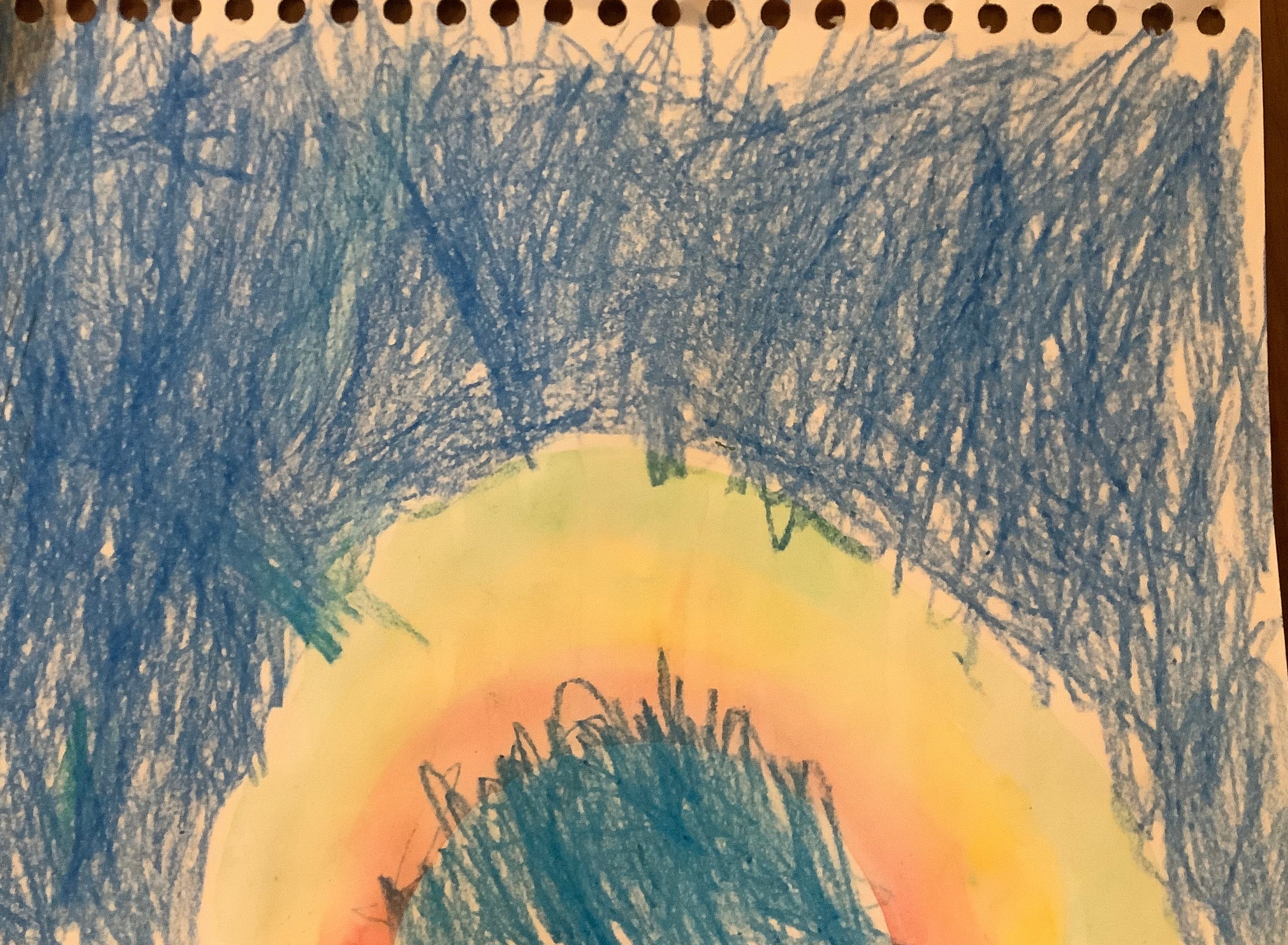
海外留学を希望されるあなたへ(特に米国)
留学の期間、タイミング、希望するプログラム、帯同する家族の有無、留学場所や所属機関によって留学体験は大きく異なるため留学に最適解はないということをまず最初に前置き(disclaimer)を述べた上で私が現在米国大学院留学について思っていることを率直に話していけたらと思う。2020年から2021年にかけて猛威を振るった新型コロナウィルス、そして歴史的な円安を経て海外留学はどこか遠い存在となりつつある。インターネットを介してアメリカ留学の様子をお届けすることが奨学金を得て教育分野の研究をしている自分に今できることなのではないかと思い今まで150を超える記事を書いてきた。くだらない記事が多い中、定期的にこのブログを訪れてくれる読者に感謝申し上げたい。留学は人生を変えるきっかけを与えてくれる貴重な体験であるという考えは留学当初から抱いている信念でもあるのだが、昨今留学する際のリスクも日に日に増している気もしている。留学生活は決してバラ色生活ではないし、むしろ自分は美しい花の下に隠れるイバラの道を歩んできたような気がする。留学に伴うリスクと留学で得られる対価を慎重に天秤にかけながら最終的な決断をしてもらえたらと思う。まず最大のリスクは長期的かつ記録的な超円安である。私が留学を開始した2023年から円安の状態が続いており、私が滞在している期間にも数度日銀による為替介入が行われた。一時は1ドル161円に近づくほど円の価値は毀損し続けたのは記憶に新しい。リーマンショックで1ドル89円まで下落したのを知っている自分としては当時から円の価値がその3分の2程度まで落ちていることに驚きを隠せない。大学院の留学で切羽詰まっているのだからこれから4年間の学費を納める保護者にとってはこの為替レートは非常に大きなリスクとなりうる。保護者の所得がドルであれば全く問題ないのだが、円をベースとする際には注意が必要である。次に米国内での長引く物価高騰も悩みの種である。私が通う大学では学費が物価の上昇に共に4%〜5%のペースで上がり続けている。2023年から2024年に切り替わるタイミングで授業料が一つあたり300ドルほど上がっていてプログラムの友人と授業料の値上げについて議論をしたほどだ。きっとこの授業料の上昇は今後もしばらく続いていくのだろう。LAやNYでは家賃が払えずホームレスにならざるを得ない人も出てきていて、治安も少しずつ悪化してきていると聞く。食品も日本と比べて高いし、卵12個が安いところで買っても$3〜5ほどしてしまう。四人家族で週末少し食品を買いだめするとあっという間にお会計が100ドルを超えてしまう。食費は必需品であって節約しても限界があり、削るに削れない部分がある。学費、食費、家賃、サービス全てに重くのしかかる物価の高騰は留学生にとってはまさに死活問題である。新政権が今年の1月に誕生してから米国政府が拠出するフルブライト奨学金の先行きも怪しくなっているのが新たな懸念である。以下の記事によると米国当局は教育分野や国際交流事業のファンディングを一時的に停止している。戦後75年以上に続くこの歴史ある奨学金事業が一時停止的に止まっていることに驚きを隠せないし、由々しき事態である。Xによると日本人フルブライターも3月1週目でspipendの支払いが終わっており今後の支払いについては非常に不透明な状況にあるという。この超円安時代にドル建てで支給される奨学金の停止は留学の継続可否に関わる大きな問題だ。私はもう時期日本に帰国する身だが、アメリカの向かっている将来が心配でならない。今年度のフルブライト奨学金の募集はすでにスタートしているようだが、次年度までにフルブライトの予算が確保されていることを切に願っている。“This effectively suspends international education and exchange programs including academic exchanges like Fulbright, Gilman, and IDEAS; professional exchanges like the International Visitor Leadership Program and young leaders initiatives; youth exchanges like YES, FLEX, and CBYX; virtual exchanges like the Stevens Initiative; and more.”Cited from “Statement: Suspension of International Education and Exchange Program Funding Threatens U.S. Economic and National Security”また、私が所属するペンシルバニア大学においても学長から以下のようなメールが届いた。(原文は英語)———金曜の夕方、米国国立衛生研究所(National Institutes of Health)から前例のない措置が発表されました。それによると、大学への研究助成金に対する施設・管理(Facilities & Administration)経費率が即時に15%に制限されるとのことです。この発表は、すでに多くの疑問や懸念を引き起こしている。現在、私たちは教員や職員への影響を最小限に抑えるための解決策を模索しており、ペンシルベニア大学で進行中の重要な研究や臨床試験に与える影響を軽減するための対応を進めていますので、ご安心ください。———噂によるとこの措置によって一部の大学ではPhDの合格取り消しが発生しているようだ。アメリカの大学ではPhDの学生は基本的にはTAをすることで授業の減免措置を受けることができる。国からの補助金カットによって米国大学の財政基盤にも影響が出始めているらしい。したがって新政権の政策はもはや留学生だけでなく大学で研究を行うPhDやポスドクの学者にも影を落とし始めている。留学に適したタイミングなんて一切ないのではないのではないかというのが私の考えだ。どのタイミングで留学しようとも失うものと得るものがあってそれらを天秤に計りながら決断していくしかない。そして慎重に判断したとしても為替レートや奨学金支給の一時停止など留学生自身がコントロールできないような出来事が次々と起こるのだ。「子どもがこの年齢になったら」、「TOEFLとIELTSがこの点数に達したら」、「貯金がこれほど貯まったら」、「仕事が落ち着いたら」、「奨学金が合格したら」、「大学院に合格できそうになったら」、「コロナと為替レートが落ち着いたら」……(社会人)留学を実現するためには数えきれないほどの条件が存在する。しかし、現実問題として全ての条件が綺麗に揃うことはほぼ不可能に近い。本当に留学することを希望されるならどれかを犠牲にする覚悟が求められる。矛盾していることは承知しているが、留学をするには様々な要素を慎重に天秤にかける慎重さと一度決めたらブレずに何がなんでも最後まで取り切る大胆さが必要な気がする。ここまでお読みの読者はすでにお分かりの通り、留学生の置かれている状況は刻々と変化しているし、学費、奨学金、生活環境も常に変動していて流動的である。巷に流布している情報に流されずにしっかり複数のソースで調べて裏をとるように心がけてほしい。渡米してから支出の多さに困っても時すでに遅しなのだ。特に米国の場合は新政権の影響でビザにも影響が出ているかもしれない。ホワイトハウスの動きにも注意していただきたい。それでは今日も良い1日を。写真:下の子どもが描いた虹の絵きたろう
2025.03.08
コメント(0)
-

咄嗟に言葉出てこない時に使うoff the top of my head
言おうとしていること咄嗟に出てこないことは往々にしてあることだ。日本語だと「あれだよ、あれ。なんだっけ」と時間を稼ぎつつ記憶を辿ることもあるだろう。私も加齢とともに言いたい単語がパッと出てこなくなってきているような気がする。前回とあるミーティングをしていた時にふとグループリーダーが以下のような発言をした。Ummm, I cannot name it off the top of my head, but there should be….オンラインCollins Dictionaryには以下のような説明があった。参考までに貼り付けておく。"If you say something off the top of your head, you say it without thinking about it much before you speak, especially because you do not have enough time."Collins Dictionary "off the top of my head"自分の発言の確証のなさを聞き手に伝える表現として”off the top of my head”という表現が使われるようである。ネットでコロケーションを調べてみるとなんとなくnegationと一緒に使われてるケースが多いことがわかる。例)I cannot tell you off the top of my head./ I cannot think of it off the top of my head.また、“Off the top of my head, that’s everything that I can think of right now.”というような言い回しも可能であることがわかった。正確ではないがざっと頭の中で考えたことを口に出す際に使われるようである。詳細な記述が求められる学術論文ではもちろん使えないが、親しい友人との会話など日常生活の中で使う機会がたくさんありそうだ。写真:バレンタインの日に並べられていたケーキ(ハートマークなのだろうが、私にはひらがなの「くろ」にしか見えない。)それでは今日も良い1日を。きたろう
2025.03.07
コメント(0)
-

Galentine’s Day
少し時間が経ってしまったが、面白い表現に遭遇したのでご紹介したい。2月14日はValentine’s Dayなのだが日本とアメリカではお祝いの仕方が異なる。日本では女性が男性、もしくは女性の友人にチョコ菓子を与えるのが通例である。気になっている異性にあげるチョコを本命チョコと呼びそうでないチョコは義理チョコと呼ばれる。バレンタインにチョコレートが選ばれるようになった理由は諸説あるらしいのだが、チョコレート会社がずっと昔にバレンタインデイにキャンペーンを行ったことから日本ではバレンタイン当日にチョコレートを交換することが定着したらしい。一方、アメリカのバレンタインは意味合いが異なる。アメリカでは性別は関係なくとにかく身近な大切な人にプレゼントを渡す日とされている。生花を持って歩く男性をこの日は多く見かけた。また、子どもの学校でもバレンタインデーに手紙や小さなおもちゃを交換するイベントが催された。日本で育ってきた自分にとってはバレンタインデーにチョコ菓子を見かけなかったのが非常に驚きであった。ちなみにアメリカでは3月14日に男性が女性にプレゼントを渡すホワイトデーの風習は一切ない。これもチョコレート会社が売り上げを伸ばすために企画したイベントが定着したものなのだろうか。日本のバレンタインデーは少し商業的な匂いがするが、アメリカのバレンタインデーは年齢や性別問わず大切な人にプレゼントをあげて愛を分かち合う日とれているようだ。日米間ではバレンタインデーの扱われ方が大きく異なるのは非常に興味深い。アメリカは日本に比べてバレンタインデーに参加する人の割合が多く、老若男女、性別を問わずこのイベントを楽しんでいる印象がある。そんな中social mediaを眺めていて出てきた表現がValnetine’s DayならぬGalentine’s Dayだ。ネットで調べてみるとGalentine’s Dayとは女性同士で友情を確かめ合うためにプレゼント交換をする日で通常Valentine’s Dayの前日2月13日に行われるらしい。手元の学習辞書にも数冊あたってみたがまだ搭載している辞書はなかった。写真:下の子どもがお友達からもらってきたプレゼントの品々それでは良い1日を。きたろう
2025.03.05
コメント(0)
-
2025年秋学期の振り返り(その3)
授業3:TESOL Seminarこの授業はいわゆるcapstoneと呼ばれる授業でプログラムの最後に履修授業とされる。教授のご指導をいただきながら最後に修士論文を仕上げる。この授業は学外でのコミュニティサービスとセットになっていて、毎週学外での活動をジャーナル形式でまとめて提出しなくてはならなかった。リーディング課題、学外での活動、そして活動の振り返りを15週にわたって絶え間なく続けるのは非常に骨の折れる作業であった。最後の立ちはだかった修士論文はまさに時間との戦いであった。完璧がない中でどこまで妥協せずに自分が納得いく論文を書き上げられるかがポイントとなるわけだが、完成度を高めようとすればするほど道のりが長く感じられ、最後は孤独との戦いでもあった。無事修士論文を書き上げられたことに今はホッとしている。さて、記憶を辿りながら孤独の戦いを記録に残しておこうと思う。Week 1 Introduction論文1本。シラバスの確認、コースの概要説明、自己紹介。シラバスはぎっしり10ページにも及び課題や修士論文のフォーマットに関するルールが記載されていた。毎週のように複数の課題をこなさなければならず少し圧倒され、自分が最後の山を果たして登り切れるのか不安になった。Week 2 TESOL as a profession & reflective practice教科書のチャプターリーディング(1章)、関連書物3チャプター。アクションリサーチのベースともなりうるreflective teachingの考え方をNunanの文献を読みながらおさらいした。また、TESOLが専門的職業としてどのように位置付けられているのか書かれた文献を読んでクラスでディスカッションをした。どうしても外国語はネイティブスピーカーに教わった方が習得が促進されるという迷信は今も根強く残っているようだ。研究論文を読んでいてもお分かりの通り、ネイティブスピーカーだからネイティブのように話せるようになれるという研究成果は残念ながら見つかっていない。年齢、インプットの量、学習環境、個人間の特性など複雑に絡み合った要因があるためネイティブスピーカーが教えるかどうかはさほど大事なことではないのである。ネイティブスピーカーでろうがノンネイティブスピーカーであろうが、教える技量が問われるのはいうまでもない。教える側も教わる側もそのことを認識した上で外国語学習に励む必要があるのだろう。ネイティブスピーカー至上主義が蔓延るアジア圏でそのような考えが広まるのはまだまだ遠い話のような気がしてならない。-Field Journal 1提出Week 3 Research Workshop教科書のチャプターリーディング(2章)リサーチワークショップでは図書館から司書をお招きして研究文献の探し方のレクチャーをしてもらった。私が所属している大学では学部ごとにその分野に詳しい専属の司書がいてアポイントを取ればすぐに1対1の面談ができるようになっていた。リテラチャーリビューの書き方がよくわからなかった自分はよくこの司書の方から貴重なアドバイスを幾度となくもらった。やはりアメリカの大学は学費が高いだけあってリソースに豊富である。ほとんどのジャーナルも教育機関の認証を受ければほとんどダウンロードができるようになっている。たとえアクセスがない論文でも司書の方に相談すれば取り寄せてもらえるらしい。またジャーナルではない学術書に関してもチャプターごとにスキャンしてもらえるのだ。大体申請をしてから1週間以内にスキャンされたPDFファイルが届くようになっている。つまり、この大学院にいる限り、気になる論文や書籍はほとんど手に入るのである。ダウンロードをしすぎていつも消化不良を起こしているのだが、読みたいものに常にアクセスできる環境は本当にありがたい。早く日本の大学も同じような対応をできるようにしてもらいたいものだ。-Field Journal 2提出Week 4 Revisiting methods and SLD教科書のチャプターリーディング(3章と4章)、論文2本。春学期に履修したSecond Language Development(SLD)というコースの復習をした。KrashenのInput hypothesis、SwainのOutput hypothesis、LongのNoticing Hypothesis、最近注目を集め始めているusage-based theoryなどの基本概念を学んだ。動機づけの部分ではGardnerの内的動機づけと統合的動機づけの違い、Dornyeiの外国語におけるモチベーションの考え方、95年以降社会のコンテキストとアイデンティティを意識した動機づけ理論を提唱したNortonのinvestmentという新しい枠組みについても触れた。また、ヴィゴツキーの理論を言語学習に取り入れたsociocultural theoryも近年注目を集めており、これからこの理論を用いた研究が活発に行われるのだろう。まだまだこれ以外にも沢山の理論と枠組みがあるのだがここでは割愛させていただくことにする。上記の概念が一つ一つ独立して存在しているわけではなく、幾重にも絡み合って存在していると考えた方が良さそうだ。さてこれらの理論をどのように実習に結びつけて論文に仕上げていくかが課題である。理論と実践を結びつける作業は想像以上に難しい。-Field Journal 3提出Week 5 Teacher identity & expertise教科書のチャプターリーディング(5章)、論文2本。外国語(英語)が理数科学系や人文科学系の科目と大きく異なるのは、単なる知識の量だけでなく技能や運用能力(コミュニケーション能力)も大きく関わってくることである。外国語を教授する者のアイデンティティや専門性とは一体どのようなものなのか議論した。Marr and Englishによると外国語教師はlinguistic expertise, pedagogical expertise, content expertiseの三つが必要となるらしい。これらの三つを厳密に定義することは難しいし、担当する学習者や教える環境下においてもこの専門知識の考え方は絶えず変化していくのだろう。また、帰国子女がEFL環境で外国語を教える教師よりも優れたスピーキング能力を有している場合に教師が感じる不安や劣等感について書かれた文章を読んだ。幼少期外国で過ごした帰国子女が英語教師の発音を指摘して関係性が悪化したという話は聞いたことがある。この問題も授業を通じて英語の知識の伝達を目指しているのか、技能の向上を目指しているのかわからない状況下におけるゴール設定の曖昧さに由来するものと考えられる。いずれにせよexpertiseもidentityも流動的で常に変化しているという考え方が主流になりつつある。研究はその一部を切り取り他者と共有できるように描写することにある。常に変化を遂げているものをどのように切り取り描写するかが大きな課題となりそうだ。実践と理論の乖離は流動的なものを無理やり枠にはめ込んで記述しようとすることに起因するのかもしれない。-Field Journal 4提出-Annotated Bibliography Draft提出Week 6 Social justice in TESOL教科書のチャプターリーディング(6章)、論文3本。言語はパワーを有している。話者が多く、その言語を学ぶ学習者が増えていけばその言語のパワーは増していくし、話者が減少していけばいつかは自然淘汰されてしまう。社会言語学の授業でも学んだが、言語は自然界のエコロジーに酷似している。-Field Journal 5提出-修士論文テーマ1提出Week 7 Individual Conferences課題なし。この週は修士論文の指導を個別で受けるため授業は行われなかった。ズームで教授と面談をしていただき論文の方向性やテーマについてご助言を受けた。「リテラチャーレビューばかりであなたのオリジナルな考えが出てきていない」とアドバイスをいただいた。自分の独創的なアイデアを含めたつもりだったが、抽象的で具体例に乏しく相手によく伝わっていなかったようだ。やはり第二言語である英語でわかりやすく、かつアカデミックなスタイルで英文を書くのは非常に難しい。読んでいて論点がわからないgenericな論文にならないよう、世界に一つだけの自分の論文を生み出したいと思う。そのためにも先行研究を読み込み自分の論文のポジショナリティを明確にしなくてはならない。論文の3分の1しか終わってないと思うと気が遠くなりそうだが、最後の最後まで駆け抜けるしかない。-Field Journal 6提出-Annotated Bibliography Draft2提出Week 8 Professional development workshop1教科書チャプターリーディング(7章)第8週から第11週は2人〜3人1組になってグループプレゼンを実施した。我々のグループはEllis(2018)を中心にTBLTの背景と導入の課題について話すことになった。-Field Journal 7提出-修士論文テーマ2提出Week 9 Professional development workshop2教科書のチャプターリーディング(8章)-Field Journal 8提出-Annotated Bibliography Final Draft提出Week 10 Professional development workshop3教科書のチャプターリーディング(9章)-Field Journal 9提出-修士論文テーマ3提出Week 11 Professional development workshop4教科書のチャプターリーディング(10章)-修士論文校正Week 12 Individual conferencesこの週は授業がない代わりに教授とズームで面談を行った。論文はほぼ完成しておりrevisionの段階に入っている。前回の面談よりもさらに細かい部分に関してフィードバックを受けた。自分にはなかった視点を沢山いただきありがたかった。自分では辻褄が合っているように見えても他人に読んでもらうと私の勘違いや説明不足の箇所が多々合ったりする。-修士論文校正Week 13 Final presentations教授からは「これが大学院生活で最後のプレゼンになる」とお話があった。アドバイスとして”Make it say something about yourself”という言葉をいただき、非常に気合が入った。このアカデミックジャーニーの集大成となるようなプレゼンになるよう手を抜かず仕上げようと心に誓った。自分の生い立ち、キャリアゴール、大学院で得た学びを7分以内に収めて発表を行なった。プレゼンが終わった瞬間にクラスメイトが大きな拍手を送ってくれた。最後の授業が終わり教室を離れると「終わったんだな」という実感が少しずつ湧いてきた。もうこの場所でプレゼンをすることはないと思うと寂しさが込み上げてきた。まだ博士課程に進むか決断はできていないが、自分の信じる道を進めば自ずと道は開けるのではないかと思っている。そう今までもそうであったように。-修士論文提出Week 14 No class (Thanksgiving)Week 15 Final Presentations同上講義の情報量としては受講した授業の中で一番少なかったと思うが、アウトプットの量は一番多かった気がする。毎週のように成果物が求められ、提出したかと思いきや次週には新たな課題の締め切りが設置されている。一度ペースを乱してしまったら取り返しのつかないことになっていただろう。とにかくリズムに乗って立ち止まらず進み続ける体力が必要な授業であった。蓋を開けてみたらこちらの授業においてもAをいただくことができた。コメントだらけのワードファイルを見て何度も落ち込んでいたが、この成績を見て少しだけ救われた気持ちになった。それでは今日も良い1日を。きたろう
2025.03.03
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- 北海道の歩き方♪
- 礼文利尻稚内の山旅53 バスで稚内空…
- (2025-11-10 14:20:41)
-
-
-

- ★☆沖縄☆★
- 沖縄の産業まつりへ🌺子どもたちと見…
- (2025-11-03 21:57:49)
-
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 2025年12月15日 静岡県袋井市 🏯 秋…
- (2025-11-15 00:00:10)
-