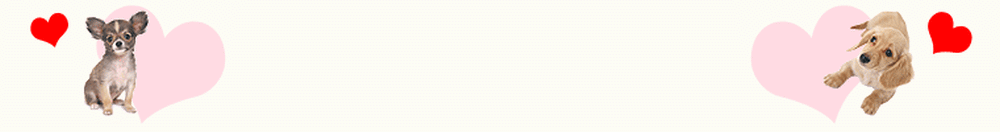全108件 (108件中 1-50件目)
-
ゆる体操でリラックス(頭痛や肩こり、不眠症を解決)
体のこりや疲れは、不快なだけでなく放っておけば大きな病気の原因にもなります。そんな状態を「ゆるめる」ことで改善するリラックス法が、ゆる体操。三重県熊野市を中心とした紀南地域など全国7の自治体が健康づくりに取り入れています。 (鈴木敦秋) 午後7時。熊野古道で知られる三重県熊野市の県民センターに、ゆっったりした服装の地元の人たちが集ってくる。 「気持ちよ~く、気持ちよ~く」 「ゆる体操教室」の講師を務める県職員の山口貴之さんと声をかけ合わせ、道前美重子さん(61)ら50歳代の後半から80歳代までの約20人が、ニコニコしながら動き出した。 左肩を少し下げ、右手で左肩や周辺いたわるようにさする。呪文のような言葉を唱えながら、手足をさすり、腰や背中をクネクネさせる。 肩こりなどに効くという「肩こりギュードサー体操」、頭痛や不眠などに効果が有るという「背もたれ首モゾモゾ体操」・・・・。激しい動きは何もないが、基本的なものだけで100種類はあり、そのうち8種類程度を行っていく。 道前さんは、38年間小学校の教員を務め、昨年3月の退職と同時に、不眠、胃痛、肩が抜けるような痛みに苦しむようになった。 「ゆる体操をすると、自分のからだっがこわばっているのが分かります。何よりリラックスできる。学校では、子供たちに『背筋を伸ばせ』『力を込めろ』と言ってきたのに」。全身の力をダラ~ッと抜きながら、道前さんが笑った。 この運動を考安した東京都で運動科学総合研究会を主宰する高岡英夫さん(58)は、「ストレス社会を生きてきた中高年の体は、自分が考える以上に痛んでいます。さびた自転車に乗っているようなもの。ゆるめることで、心身ともに本来の状態を取り戻すことができます」と説明する。 実際、「坂道を上るのも苦にならなくなった」「不眠症が解消された」などの声は多い。仲間と一緒に楽しく楽に行えることも人気の理由だ。 肥満の人を集め、2か月間ゆる体操を行った人と行わなかった人各30人のデーターを岐阜大医学部で分析したところ、肥満の改善などの効果がみられた。 いつでもどこでもできるが、1回30分程度がよく、やりすぎいは禁物。ゆる体操教室は、全国カルチャーセンターなどで開かれている。問い合わせは、運動科学総合研究所コールセンター(03・3817・0390)へ。 (2007年4月15日 読売新聞)◎私は、肥満で悩んでいます。目標体重は、5kgは落としたいと思っています。 今回の記事を読んで、これなら手軽に できるかなぁ? と期待を持ちつつ 今日から早速チャレンジしてよみようと思います。
Apr 21, 2007
コメント(71)
-
柏木先生の健康Q&A
*日常気になること、社会で話題になっている健康に関する質問に、国立病院九州センター名誉院長でいらっしゃる柏木征三郎先生よりお答えいただきます。今回は、緑内障について。☆40歳をすぎると一年に一度眼科での定期健診をおすすめします。<質問の内容>先日、めがねを作り直そうと検査を受けたところ、緑内障の疑いがあると言われてビックリしました。紹介された眼科で精密検査を受けたところ、緑内障の初期と診断されました。実はここ何ヵ月か字が読みづらくなっていました。緑内障とはどのような病気で、どのような治療が必要でしょうか? 緑内障とは眼圧(眼球内の圧力)が高くなり、視神経が圧迫されて視野が狭くなる病気です。これは数年前から数十年かけて症状が進み、放っておくと失明することもある病気です。原因は良くわかっていませんが、加齢と関連があり、年をとるに従って増えます。40歳以上では28人~30人にひとりは、緑内障だと言われています。 原発性、続発性、先天性の3種類がありますが、最も多いのは原発性緑内障で、この場合は、眼圧が高いものと正常眼圧のものがあるためちょっと複雑です。どういう病気かというと、角膜の内側に紡錘と言う液体が循環していますが、これが上手く流れないことによって、視神経が圧迫されるわけです。紡錘がまったく流れなくなり、数日で症状が進む急性型もあります。 治療の原則は眼圧を下げることです。プロスタグランジンの点眼液など、よい薬が開発されています。手術もありますが、とにかく眼科の先生に程度を診断していただき、一番よい治療法をみつけていただくのが大切だと思います。 (読むくすり箱 17号より)◎なかなか体の異常を感じないと、病院へは行きませんが、何事にも 早期発見・早期治療なのかなぁ? っと思いました。
Apr 19, 2007
コメント(2)
-
夫のB型肝炎 子にもうつる?
B型肝炎ウイルス(HBV)に感染すると、急性肝炎や慢性肝炎を発症することがあります。急性肝炎では発熱や黄疸がみられ、慢性肝炎になると、将来、肝硬変や肝がんにつながる恐れがあります。このような経過の違いは、感染時の年齢、ウイルス量などで決ります。 国内で感染経路としては問題になるのは、性行為、母子間、家族内感染です。夫婦間では、ご主人のウイルス量と結婚してからの年数により、感染の可能性が異なります。ご主人のウイルス量が多ければ、結婚から5年以内に感染しますが、多くは自然に治り、ウイルスに対する免疫がつきます。ただし、中には急性肝炎を起こすこともあります。 まず、ご自身が血液検査を受け、感染の有無を調べて下さい。感染の形跡がなければ、B型肝炎ワクチンの接種で感染予防できます。また、既に感染して免疫があると分かったら、ワクチン接種の必要はありません。 赤ちゃんへの母子感染は、生まれてすぐにワクチンを接種することで防ぐことが可能です。このほか唾液や血液を介して起こる父子感染でも、生後1歳ころまでに感染すると、慢性化する恐れがあります。これも、赤ちゃんにワクチンを接種することで予防できます。外国では、赤ちゃん全員にこのワクチンを接種している国もあり、安全性は確認されています。心配せずに、子供さんを産んでください。 (2007年4月15日 読売新聞) ◎肝炎と聞いただけで、少し怖いものを感じてしまいますが、治療さえ 正しく行えば、病状を抑えることができるみたいなので、少しでも お元気になられますように。
Apr 16, 2007
コメント(0)
-
最後の思いと向き合う(その2)
そんな男性が、暗闇の中で泣いている。臨床工学技士から、看護師に職を転じて2年半。安達さんは、かけるべき言葉を見つけられず、ただ手を握り、1時間一緒に泣いた。 結局、夜だけ一時的に鎮静をかけることになった。男性は妻や子供とじっくり語らい、息を引き取った。だが、「心が痛い」と言った男性の心の奥に、安達さんは迫れなかった。 葬儀で知った男性の医師としての使命感と絶望。安達さんは「自分に看護師を続ける資格はないのではないか」と思った。 治療が望めなくなった患者が「もう死にたい」「楽になりたい」と口にすることは、珍しくない。「大学病院の緩和ケアを考える会」代表世話人の高宮有介・昭和大専任講師は「死への不安、家族への思い、生きる意味など、患者の心に深く、複雑な思いが渦巻いている。それらを完全に理解することはできないが、理解しようと一緒に悩むことで、心の痛みを和らげることはできると思う」と語る。 悩む安達さんを、幸史看護師長(48)は「この経験こそ、今後に生かして欲しい」と励ました。安達さんは今も、同じ病棟で働く。「以前は病状の厳しい患者から逃げる気持があったけれど、あれ以来『厳しい患者さんこそ逃げちゃいけない』と思えるようになった」。将来はがんの専門看護師になりたいと、安達さんは思っている。 医学の進歩で、がんに伴う痛みを取り除く技術は向上している。だが、患者は体だけで無く、心の痛みにも苦しんでいる。だが、患者は体だけではなく、心の痛みにも苦しんでいる。今回は、終末期医療の現場で「心のケア」について考える。 (2007年4月3日 読売新聞)◎とても素晴らしい看護師さんの話でしたが、こういう看護師さんが増えて 何時でも病気の方の力になって、支えてくれることを、真剣に思います。 お仕事柄、色々と大変でしょうが、一緒に笑い・時には思いっきり泣く ことが、何よりの薬にもなると思いました。がんで亡くなられるかたも、 どんなにか、心励まされたことだろうと、思います。
Apr 14, 2007
コメント(0)
-
最後の思いと向き合う(その1)
「あの言葉の意味は、これだったのか」。熊本大病院・血液内科病棟の看護師、安達美樹さん(36)は2004年の暮れ、担当だった患者の男性(当時43歳)の葬儀に足を運び、愕然とした。 急性白血病で亡くなった男性は、優れた内科医だった。「患者の立場も経験した医師として、グレードアップしたい」。葬儀で読み上げられた参列者あての本人の手紙には、医者としての熱い思いと、それがかなわなかった無念さがつづられていた。 その悔しさに、寄り添う言葉がかけられなかった。安達さんは、死のふちに立った患者と向き合うの難しさを思い知らせた。 「心が痛いから、意識を消してほしい」 男性がこう言ったのは、亡くなる3週間ほど前のことだ。夜勤だった安達さんはこの言葉を伝え聞き、病室に駆けつけた。 男性が求めたのは「鎮静」と言う医療行為。苦痛から患者を解放するために、薬で意識を喪失させることだ。通常、対象となるのは体の痛みが激しい患者で、「心が痛い」という理由で行ったことは、この病棟ではかつてない。 男性の場合、体の痛みはコントロールできている。残された時間はわずかなのに鎮静を行えば、自分や家族と向き合う最後の時間の最後の時間を永久に失いかねない。 男性は安達さんに部屋の電気を消すように頼み、真っ暗な部屋で言った。 「希望がないまま生きるのは、つらいんだ」 熊本市内の病院長だった男性は、責任感が強く、患者思いで、周囲から慕われていた。病気が判明してからは、自ら検査データを確認し、骨髄移植などの治療法を綿密に選んだ。 1度は職場復帰を果たしたものの、10か月後に再発。自分の病状は良く分かっていた男性は、傍らで励まし続ける妻(45)に「君の気持ちは分かるが、あきらめてくれ」と言って、無理な延命を行わないよう希望した。 *続は次回載せますね。◎職業がら、自分の病気を理解しているので、余計怖いものを感じてしまう のではと思います。延命治療では、自分でもして欲しくないと思います。 でも、自分の家族には、少しでも永く生きて欲しいと延命治療を希望して しまうようにも思います。 (2007年4月3日 読売新聞)
Apr 13, 2007
コメント(0)
-
緩和ケアも「治療」 (その2)
悩んだ末、長女ら3人のきょうだいは母に会いに行った。「やっぱり怖い」と、布団にもぐっていた母は、恐る恐る子供たちの顔を見た。母も子供たちも、表情をこわばらせたまま、言葉が出ない。明神医師から息を詰めて見守る中、母は消え入るよう声で「ごめんなさい」「許してください」と言った。子供たちはただ、じっと聞いていた。翌日から、子供達は母を見舞うようになった。 明神医師は「ごめんと言ったことで、患者の心は随分楽になったと思う」と振り返る。 患者や家族には、人生の長い道のりがある。複雑で微妙な感情もある。医師や看護師は家族関係にどこまで振り込むべきか。 難しい問題だが、この病棟では、患者が望めば、断絶している家族と連絡を取ってきた。03年の病棟開設以来、これまで3人の患者が家族と和解を果たした。 同センターの堀泰祐・緩和ケア科主任部長は「家族の間の問題をぬきにして、患者の心の痛みには迫れない。薬や処置だけではなく、患者の心を和らげるために手を尽くすことも、医療だと思う」と話す。 長女は「母は私のことが嫌いなのではないか」と、幼いころ、思っていた。18年ぶりの再開を果たした今も、自分を避けている気がする。母と病室で2人きりの時、長女は思い切って「私には、会いたくなかったんやね」と聞いた。 母は何も言わずにゆっくり両手を広げて、抱きしめてくれた。長女は「ありがとう」と返すのが精いっぱいだった。再会から約2週間後、母は夫や肉親、そして子供たちに見守られ、息を引き取った。 「母が自分を嫌いでなかったとわかり、うれしかった。会わせてもらって、よかった」母の死から2年余。長女は今、そう思っている。 (おわり) (2007年19年4月7日 読売新聞 社会部・木下敦子)◎幾つになっても、母親の存在の大きさは、計り知れないように 思います。私の母も病気と闘っていますが、一日でも永く生きて 欲しいです。今回のこの記事は、親子についてとても絆が強く、 会ったことで誤解も解けて、それぞれに幸せになれて、本当に 良かったと 思いました。
Apr 10, 2007
コメント(0)
-
緩和ケアも「治療」 (その1)
「お母さんが、あなたたちに会いたがっています」名神徹郎医師(50)からの電話を受けて、長女(28)は一瞬、言葉を失った。 2004年の晩秋。滋賀県立成人病センター(守山市)の緩和ケア病棟に入院している母(当時53歳)は、末期の乳がんで、かなり容体が悪いという。 小学生の時に両親が離婚して以来、母とは18年間、会っていない。まだ幼かった弟と妹は、母の顔も覚えていないだろう。しかし自分は、自分たちを置いて出て行った母の姿を、はっきりと覚えている。 「いまさら・・・・」。長女の戸惑いは大きかった。ただ、死を前にして、自分達に会いたいという母親の気持を思うと、その場で断ることもできなかった。 当時、同センターの精神科医として緩和ケア病棟を担当していた明神医師は、この母親がいつも、「自分は子供を捨てた。だから罰が当たった」と言っていたのを、よく覚えている。 成長した子供たちの姿をこっそり見に行ったこともあったらしい。医師らが話を向けても、母親は決して「子供たちに会いたい」と言わなかったが、死期が近づいたある日、「本当に会いたくないでか」と明神医師が尋ねると、母親は初めて、「会いたいです」と、答えた。 母親には、再婚した夫(60)がいた。口数は少ないが思いやりがあり、身の回りの世話などこまめに焼いていた夫は、ひと言、「本人が会いたいなら、いいですよ」と明神医師が言った。 *続は、次回のお楽しみにしてね。 (2007年4月7日 読売新聞)
Apr 9, 2007
コメント(2)
-
不眠・・・まず生活改善を
東京都内のメーカーで働く女性(27)は、残業が続くと薬局で睡眠改善薬を購入する。終電で帰宅しても、頭がさえたままで、なかなか眠れないからだ。「翌朝も9時出勤なので、少しでも早く、ぐっすりと眠りたい」 睡眠改善策は、医師の診断を受けて処方してもらう睡眠薬とは違う。医師の処方せんが不必要な大衆薬(一般用医薬品)で、薬局などで気軽に買える。主成分は、塩酸ジフェンヒドラミン。風邪薬などに使われる抗ヒスタミン薬の一種で、飲むと眠気を催すという副作用を生かした。 国内では、エスエス製薬が2003年に発売した「ドリエル」が最初だ。当初、初年度6億円の売り上げを目標としたが、わずか1か月で達成する大ヒットに。05年度の売上高は27億を超えた。「不眠でつらいが、病院で薬をもらうには抵抗がある人がこれほど多くいた」と担当者。 不眠とは、健康を維持するために必要な睡眠が量的には質的に不足していること。1寝付きが悪い2眠りが浅い3夜中によく目が覚める4朝早く目が覚めるの4タイプに分けられる。エスエス製薬の06年の調査では、5人に1人が不眠に悩み、不眠の原因として約8割が「精神的疲労・ストレス」と回答した。 今年3月、グラクソ・スミスクラインは世界15か国以上で承認されている「ナイトール」を日本でも発売。同社は「生活の24時間化、ストレスの影響などで今後も市場は拡大する」と見る。大正製薬も同月「ネオデイ」を発売した。 ただ、睡眠薬改善は、あくまでも一時的な不眠症を緩和するためのもので、不眠症の治療薬ではない。日本大学医学部教授の内山真さんは「服用しても症状が改善しない場合は、すぐに医師に相談してほしい」と注意を呼びかけいる。不眠の背後には、うつ病などの病気が隠れている場合もあるからだ。 また、「安易に睡眠改善薬に頼らず、運動不足の解消やライフスタイルの改善なども心がけてほしい」とアドバイスしている。 (2007年4月2日 読売新聞ヨリ)
Apr 7, 2007
コメント(0)
-
わたしのPMS 知っていれば、ラクにすごせる(げんき講座)パート2
◎再開にあたって。体調を崩して、だいぶ長いこと ブログ掲載を休んでいましたが、また少しずつ始めたいと 思いますので、宜しくお願いしますネ。 <心配なことは、専門医に相談を> PMSのなかでも、うつの症状がつよくて日常生活が出来ない場合は、PMDD(月経前不快気分障害)かもしれません。PMSの人のうち、約5%がPMDDとも言われています。 子宮内膜症、子宮筋腫や卵巣のう腫などのときにも、PMSに似たおなかや腰の痛みが出ることがあります。これらの病気の場合はPMSの症状意外に、強い生理痛や月経量の多さにも悩む人が多いようです。 生理のたびに、PMDDや強い痛みなどの症状があれば、一度婦人科を受診してみましょう。 <じょうずに付き合っていくポイントとは?> PMSは、生理のある多くの女性が抱えるもの。生活を工夫して、症状をやわらげましょう。 まずは栄養バランスのよい食事で、元気な体を保ちましょう。体調がよくないときは、ダイエットはお休みにして。とくに摂りたいのは、女性ホルモンのバランスを整える豆腐や納豆などの大豆食品や、血液サラサラに働く魚。イライラにはカルシウムのほか豚肉や玄米に豊富なビタミンB6がおすすめです。イライラすると、甘いものやカフェインが入った飲み物が欲しくなりますが、肌荒れなどPMSを悪化させる原因にもなりますので、摂り過ぎにはご注意を。また、塩分や冷たいものを摂りすぎるとむくみやすくなるので、控えめにしましょう。 体が重いときは、軽いストレッチや入浴がおすすめです。血のめぐりがよくなって痛みやむくみがやわらぐ上、気分転換にもぴったり。併せて、PMSによいツボも試してみてください。 なんといっても、PMSの症状を強めるいちばんの原因はストレス。できるだけためずに、発散しましょう。PMSそのものをストレスに感じてしまうかもしれませんが、症状が軽いならあまり気にしないのがベター。女性特有のものだとポジティブに考えれば、心の負担が取れて、気分がふわりと軽くなりますよ。
Apr 3, 2007
コメント(2)
-
わたしのPMS 知っていれば、ラクにすごせる(げんき講座)
生理の前におなかが痛くなったり、ブルーになったりしませんか? そのせいで、仕事や家事がおっくうになっていませんか?それはPMSかもしれません。自分の症状を知って、ケアしましょう。 Ayako Onozuka(pict-web) <たくさんの女性がPMSを抱えています> PMSは生理の1~2週間前にあらわれる、おなかや腰の痛み、イライラなど、不快な症状全体を指します。日本語では「月経前症候群」、英語の”Premenstrual-Syndrome”を略してPMSとよばれています。生活に支障をきたすこともありますが、生理がくるとけろりと治るのが特徴です。 PMSの症状は体にも心にもあらわれ、人によってもさまざま。報告されているだけで、150種類くらいの症状があるとか。軽いものを含めると、生理のある女性の80%以上がPMSを経験しているそうです。 <PMSが起こるわけ> 生理のサイクルは、エストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンの分泌で成り立っています。排卵後の黄体期にエストロゲンが急に減ったり、プロゲステロンがぐんと増えたりしますが、PMSの症状が出るのはちょうどこのとき。ホルモンのバランスを調節する脳の視床下部が変化に驚き、対応しきれなくなるために起こります。 視床下部は、体と心をコントロールするところですから、調子が悪くなるといろいろ な場所に影響をおよぼします。たとえば、血圧や体温などを一定に保つ自律神経に作用すると、肩こりや頭痛、むくみ、のぼせなど体の深いな症状を引き起こしたりします。また、視床下部は本能や感情をつかさどるところでもあります。そのため、食欲や性欲が変化したり、感情が大きく揺らいだりするのです。 「20~30代を中心に、働く女性の90%以上が、PMSを経験している」という調査報告があります。はたらく女性の場合、ストレス、睡眠不足、かたよった食生活などが大きく関わっているようです。既婚者では、仕事と家事を両立させようと、過労気味になる傾向も。無理な生活が視床下部のはたらきを乱すと、逆に女性ホルモンのバランスがくずれ、PMSの症状を強めます。PMSのほか、生理不順や強い生理痛を引き起こすことも多いです。疲れたら、ひと休みして、リラックスしましょうね。*明日は、対策を紹介します。 (みんな、げんき? DHCの7月号より) ◎私の経験から言いますと、かなり生理痛がきつかったです。食事は摂れず、食べた 物は、みんな吐いていました。起きているのも辛くて、2日目は特に生理痛がきつくて、 市販の鎮静剤を飲んでいましたが、全然効果が無く、5年間苦しみました。その後、 体が成長したのか、今までの痛みが嘘のように取れて、今日に至っています。生理の せいで感情が左右されるのが、とっても嫌でしたが、実際にやはり生理前だと、普段 たいしたことでないことでも、イラついている自分に気付かされます。男性の方には、 理解に苦しむかもしれませんが、そう言う女性のデリケートな一部も、理解して欲しいと 思いました。私は、男性の方達のナイーブなところ優しさ・強さを、理解したいです。
Jul 8, 2006
コメント(2)
-
海岸に落ちた流木を 焚き火にくべてみてびっくり!
ロハスな生活を心がける人にとって「香」はつきものですよね。心も身体も清めるヨガや座禅ではよく使われています。ヨガまではしなくとも、普段の生活においても、いい匂いがしてきたら安らぐものです。 日本では最初に「香」が登場したのは、聖徳太子の時代、推古3年(595年)のことです。村人が海岸に流れ着いてきた流木を焚き火にくべてみたところ、とてもいい匂いがしたのに驚き、推古上帝に献上したそうです。 香木や香自体は、それよりも以前、中国から仏教と共に「祈りの香」として伝来して いました。それが、平安時代には「雅の香」として貴族に愛用されるようになりました。 仏前に供える他にも、部屋で炊き込めたり、衣装にたきしめたり(空薫)したそうです。 特に、女性の衣装は幾重にも重ね着をして、それはたいそうな重さでした。更には、その時代毎日お風呂に入る人はほとんどなく、5日に1度ほどしか入りません。たらいにお湯や水を溜めて体を洗うという行水でした。衣装は重くて汗はかくし、通気性もほとんどないので、かなり臭かったことと思われます。 昔はこのように利用されてきた「香」ですが、今ではリラックスを含めた心理的効果 としての「香」の方が注目されていますね。嗅覚を通して大脳辺縁系や脳幹に働きかけ、 ストレスを軽減したり、リラックスしたり、元気になったりします。この嗅覚は生き物の五感の中で一番本能に近いものと言われています。動物が敵から瞬時に逃げられるように、嗅覚が一番に働くようになっているそうです。ちょっと疲れたときに焚いてみたり、お客様のもてなしに玄関先に置いてみたりしてみるのもいいかもしれませんね。★代表的な香木★白檀・・・サンダルウッドとも呼ばれ、薬用、薫香用、彫刻工芸用、扇などに使用される 最もポピュラーな香木。上品でさわやかな香り。沈香・・・薫香用や薬用として知られている。清澄で上品な香り。加羅・・・沈香の一種。古来、ベトナムの限られたところから産出されていましたが、 現在では採取が非常に困難になり、貴重な香木となっている。幽玄な深い香り。 (2006年Vol6.自然がいちばん ビ・ーポコーポレーションより) ◎「佐賀のがばいばあちゃん」著者:島田洋七を読んでいるのですが、このおばあちゃんも 川から流れてくる気を集めて、焚き火をしていることが書かれていました。「香」を 楽しんだか? それまでは書かれていませんでしたが、きっと楽しまれたのではないかと 思います。とっても凄いことだと思いました。今は、家庭で燃やせる物は限られていますが、 使えるものは、なんでも無駄なく使って、少しでもゴミ削減に努力したいです。 「なんでもリサイクルできる時代になれば、良いなぁ」と思います。◎我が家でも、母も私も香りが好きで、白檀のお香を玄関で炊いています。
Jul 7, 2006
コメント(2)
-
点字シール 手軽に作成 文具メーカー「キングジムのラベル印刷機器 テプラ」
点字と文字を一緒に印刷できる機器や、ボタンの位置を区別するシールなど、視覚障害者のための識別グッズが増えている。手軽に取り付けられるため、「だれもが暮らしやすい街にするため気軽に使って」と関係者は期待する。 東京・目白の「ホテルメッツ目白」は今年4月から、一部の客室に点字を取り入れた。 車いすでも利用できるように扉を大きくし、湯船に手すりをつけた「ユニバーサルツイン」の部屋に、ルームキーや電話の受話器に部屋番号を明記したほか、トイレの温水洗浄便座、室内灯のスイッチなどに点字シールを張った。 「ホテルの基本は安心して快適に過ごせること。目の不自由な人も安心できるよう点字を取り入れた」と支配人の田中優子さん。 これから表示は、文具メーカー「キングジム」(東京)のラベル印刷機器「テプラ」が使われている。同社によると、点字も作れる「テプラ」は昨年5月に発売され、これまでに約1万台販売した。希望する文字を入力すると、自動的に点字に変換。また、上下を示すマークが印刷されるので、点字の知識がなくても取り付けやすい。 点字を作成する専門機器は通常10万円ほどだが、こちらは1台4万5150円。 「テプラ」を使って、東京・渋谷の東急百貨店本店では、購入した化粧品などの瓶に点字を張るサービスを始めた。また長野県のCD・書籍ショップ平安堂長野店でも、購入したCDに点字でタイトルを張ってくれるという。 視覚障害者向けの商品を販売している会社「大活字」(東京)では、凸型の小さなシールが人気商品となっている。16個入りで250円。1個は直径8ミリ、高さ2ミリほどで、携帯電話のボタンや部屋の照明スイッチなどに張れば、目の不自由な人向けの印になる。 これまでは透明のみだったが、最近黒色も登場。弱視の場合、目でもある程度判断が できるため、黒色なら手触りだけでなく、視覚を生かすことができる。色や突起などを組み合わせれば、障害のある人にもより使いやすくなる。 同社の市橋正光さんは「生活の中に様々な機械が増え、識別しなければならないボタンなどは増えている。こうした製品を手軽に使ってもらえれば、障害のある人も暮らしやすくなるはず」と話す。 (2006年7月5日 読売新聞) ◎とっても良い記事に、思わずブログに記載しました。目の見えない方の不自由さは、計り知れ ないことだと思います。昔、お世話になった先生に、お手紙を書きたくて、点字を習ったこと を、思い出しました。「先生は、お元気で居られるのかしら」私には、毎朝お祈りをすること しか出来ませんが、「先生とご家族の皆様が、お元気で居られますように」祈っています。◎北朝鮮、7発のミサイルを打ってくるなんて、信じられません。本当にいい加減にして欲しい です。言葉を話せるのだから、人間らしい対応を望みます。
Jul 6, 2006
コメント(2)
-
ありの体内に”歩数計” 巣穴までの距離正確把握
アリは、歩数を数えることで、移動距離を正確に把握している可能性の高いことをスイスのチューリヒ大の研究チームが突き止めた。体内に”歩数計”を持っていることを示す成果で、30日付の米科学誌サイエンスに発表する。 アリは、巣に戻る方向を光で探る。しかし、巣までの距離をどう把握しているのかは謎だった。 研究チームは、距離測定は歩数で行うとの仮説を立て、アフリカのサハラ砂漠に生息するアリの脚の長さを変えて、実験した。 巣穴から10メートル離れた場所でエサを与えたアリを、1.ブタの毛を竹馬のように履かせて、脚を長くする。2.一部を切断して脚を短くする。3.何もしない。 の3群にわけ、無事にゴールの巣穴に戻れるか調べた。 その結果、竹馬を履き、歩幅が広がったアリは、ゴールを通り過ぎ、逆に短く歩幅が狭まったアリはゴール手前で立ち往生した。通常のアリはゴール付近で巣穴を探しの行動をとった。脚の長さを変えたアリは慣れるにつれ、正確に巣に帰れたことから、体内に歩数計を持つことが示唆された。 (2006年6月30日 読売新聞) ◎アリは、お尻から臭いを出して、家に帰るのだと思っていました。実験で、 色々な事が分かってきましたが、そのために脚を切られたアリは、とても 可哀想だと思いました。動物実験や今回のような実験で、犠牲になった生き 物達がいることは、けっして忘れてはいけないことだと思いました。◎夕焼け小焼け~の~~~♪ 赤とんぼが、朝のぶん太の散歩の時に、一杯 飛んでいました。とんぼと言えば、夕方のイメージが強かったのですが、朝から 一生懸命飛んでいました。台風が近づいているせいか? 風が結構強く吹いて いるのに、力強く飛んでいました。凄いなぁ。あんな小さい体のどこに、そんな パワーが隠されているのか? 不思議に思いました。 それから、綺麗なお花が咲いていたので、撮影しましました。ブログの片隅に 載せますね。まだまだ上手に撮れませんが、その物の一番素敵な状態が撮れる ように頑張ります。 朝散歩すると、色々な発見があります。心が少し疲れたときに、散歩される ことを、お勧めします。きっと素敵な出会いが待ていますよ!!
Jul 5, 2006
コメント(2)
-
「命の共有」に胸熱く みやざき骨髄バンク推進連絡会議代表 中村福代さん(43)
運命を変える出会いが、2度あった。 骨髄移植の提供者として、数万人に一人とされる適合者に巡り合ったこと。「命を共有する感覚」に、胸を熱くした。 そして、もう一人。白血病に侵され、骨髄提供を受けたもの、亡くなった女性。「生きる希望を持って、最後まで病気と闘いたい」。そう誓ってくれた。 「この体験を無駄にしたくない。私にしかできないことがある」。決意を胸に深く刻み、ボランティア組織「みやざき骨髄バンク推進連絡会議」(33人)を2003年11月に設立。県内各地で、ドナー登録を呼びかけている。 02年度に103人しかいなかった県内の年間ドナー登録者は、05年度には638人と飛躍的に伸びた。 中村さんがドナー登録したのは、1995年。登録した姉が持っていた勧誘のパンフレットにあった「あなたを待っている人がいます」というフレーズに引かれたのがきっ かけだ。それから3年後、ドナー候補者に選ばれたと通知が届いた。待ち望んでいたはずが、体がガタガタ震え、立っていられなかった。 ほぼ100%の安全性が確立されている骨髄移植。それでも気持ちは揺れた。2児の母。「怖くてたまらない。もしも、なんて考えると・・・・」。気持ちを整理しようと便せんに向った。B5サイズで5枚。午前4時までかかったが、決心はつかなかった。 患者は、18歳の少年。「私に白血病の子供がいたら、命を引き換えにしても、下さいって言うだろうな」。1週間もすると、同じ白血球の型を持つ患者を、他人に思えなくなっていた。 およそ1か月後、提供に最終同意した。それからは「自分の体にもう一人の命を抱えている感覚」だった。患者は受け入れ準備に入って、もう後戻りできない状態。自分に何かあれば、死につながる。道路から常に1メートル離れて歩道を歩き、健康管理にも注意を払った。 骨髄移植はあっけなく終わった。「無事、患者さんに骨髄は届きました」という看護師の言葉に、ホッとした。 急患が入ったために移動した病室に、白血病の女性と夫がいた。「本当に提供したん ですか?」と突然声をかけられた。 夫婦は骨髄の適合者を探し回ったが、親類ですらドナー登録を断る人がいた。夫は、 「移植なんて、テレビの中の話だとばっかりに思っていた」と打ち明けた。希望を取り戻し、女性は笑顔を浮かべた。 別れ際に、自分の提供経験を生かした活動をすると約束し、お守りを贈った。「私にも、きっと(ドナーが)見つかるよね」。女性は、最後まで闘うと誓った。 女性は翌年、ドナーが見つかり、移植治療を受けた。しかし、合併症の肺炎を起こし、 亡くなった。手には、お守りの木彫りの人形を握りしめていた。 「寝たきりだったのが、今では筋肉痛になるぐらい友達と遊んでいます」。移植から4ヶ月後、骨髄を提供した少年から贈られてきた手紙に涙がこぼれた。 「人間っていうのは、つながっている。まったくの他人じゃないんです」。提供したことをきっかけに、そんな気持ちを強くした。 ドナー登録の呼びかけに、一人しか応じてくれない日もある。それでも、「もしかしたら、この人が提供者を捜し求めている患者さんのパートナーになるかもしれない」と、うれしく思うという。 「誰かを助けてあげたい。同じように、生きたい。志は、一つじゃないですか」。命の尊さをかみしめる言葉が胸を打つ。(坂田 元司) (2006年7月3日 読売新聞)◎なんて素晴らしい、体験談なんでしょう。最近は、悲しくなるようなニュースで一杯でしたが、 こんなにも、人間らしく温かな気持ちになれることって、本当に大切なことだと思いました。 「人間っていうのは、つながっている。まったくの他人じゃないんです」。この言葉に 感動しました。
Jul 4, 2006
コメント(0)
-
介護保険改正の3か月
「介護予防」の導入を柱とした改正介護保険法が施行されて3か月。筋力トレーニングなどで要介護度の悪化を防ぐ取り組みが進む一方、訪問介護を受けられる時間が減った利用者の間からは、戸惑いや不満の声が広がっている。 (社会保障部・中舘聡子、安田武晴)◆「足が軽くなった」 「足が軽くなった気がする。もっとやりたい」 東京都清瀬市のデイサービス施設。4月の要介護認定の更新で、「要介護1」から、介護予防サービス対象の「要支援2」 になった佐藤シヅ江さん(82)は汗をぬぐいながらそう話す。 脳こうそくの後遺症で左半身が動きにくくなったが、トレーニングマシンによる足の筋力強化でだいぶ改善した。「筋トレは敬遠されるのではないかと心配していたが、意外に喜んで挑戦してくれる高齢者が多い」と指導にあたる作業療法士の八並宏子さんは話す。 今回の改正の目玉が、軽度の要介者護向けに導入された介護予防サービスだ。筋トレや 栄養改善のほか、利用者の自宅に出向き家事を行う訪問介護も、予防重視の内容に改められた。軽度の認定者数が急増し介護給付費が上昇したことから、軽度者向けのサービスを従来の介護サービスと別建てにし、*支給限度額 も低くすることで給付費を抑制する狙いがある。 ただし、予防の効果は未知数。「今更鍛えても、ケガが心配なだけ」(70代女性)との声もあり、予防が政府の思惑通りに進むかどうかわからない。◆サービス削減 一方、制度改正で大きな影響を受けているのが訪問介護の利用者だ。報酬体型が変わり、サービス提供時間や回数が減ったためだ。 東京都板橋区の独り暮らし男性(67)は、5月の認定の更新で要介護1から要支援 2に変更された。週2回2時間ずつの訪問介護を受けていたが、週2回1時間半ずつに 減った。その結果、掃除の時間がなくなり、ヘルパーの調理時間も減って料理の品数も 減った。男性は、脳こうそくの後遺症で右手に力が入らず、かがみこむ動作ができないため、掃除は仕方がなく自費で民間の家事サービスを利用している。ただし30分1050円かかるため月2回にとどめている。 男性のように給付削減を受け、自費サービスを利用する例も増えている。 全国で在宅介護事業を展開する「やさしい手」(本社・東京目黒区)では、月500~600件台で推移していた保険外の家事・介護サービスの利用件数が4月は728件、5月も874件に増加した。「介護保険ではみてもらえなくなったニーズを補うためではないか」と同社ではみる。ただし、「自費サービスを使えるのは経済的に余裕のある人。みんなが利用できるわけではない」と都内の別の事業者は指摘する。◆福祉用具も制限 改正では、要介護1も含めた軽度者への福祉用具の貸し出しも制限された。都内のNPO法人サポートハウス年輪ケアマネジャーの木崎志づ香さんは、「軽度の人でも介護用ベッドを使うことで寝返りや起き上がりが可能になり、在宅生活が続けられる人がいる。一律カットでなく、ここの状況を良く見ないと、かえって要介護が重くなる懸念もある」と疑問を呈する。 東京都社会福祉協議会が改正に伴ってサービス内容が変わった利用者約660人に行ったアンケート調査では、49%が「今までより利用時間、回数を減らされた」、39%が「今までのサービスが利用できなくなった」と回答している。*支給限度額・・・介護保険制度の在宅サービスで、要介護ごとに定められた保険給付の 上限額。利用者は原則、その範囲内でサービスを使う。要支援2は月額10万4000円で、 要介護1だった人の場合、従来より6万1800円の減少となる。 (2006年7月2日 読売新聞)◎介護保険改正のために、今まで利用できていたサービスを受かられなくなっていることや、 筋トレをして体力づくりにに励んでおられる方達の、サポートを削減してまうとのこと、 本当に将来の日本の事を考えているのだろうか? 安心して少しでも健康で老後生活を 送るための援助は、惜しみなくして欲しいです。誰のための介護保険制度なのか? 考えさせられます。
Jul 3, 2006
コメント(2)
-
アイドリングストップと地球温暖化
最近の原油価格の高騰にともなって、ガソリンの価格も急騰しています。車に乗られる方には、以前よりガソリン代の出費がかさんで困っていらっしゃることでしょう。 ちなみに日本のエネルギー消費を見てみると、自動車が全体の消費の21%も占めているんです。これを家庭に絞って見てみると、なんと約48%が自家用自動車なんです。 そこで今回は、ガソリン代も抑えて、地球温暖化の原因になる二酸化炭素も減らせる術をご紹介します。それは、「アイドリングストップ」です。 たとえば信号待ちや駐車中に、こまめにエンジンを切り、一日10分間のアイドリングストップを実践することで、144ccのガソリンが節約されます。これで二酸化炭素329gが削減されます。これを一年続けると、51.1リットルのガソリンが節約され、120kgの二酸化炭素が削減されます。アイドリングスを少しやめるだけで、年間およそ6,700円の節約にもなり、地球に優しいんですね。 皆さんも実践されてみてはいかがでしょうか?ほんの5秒の信号待ちでも効果はあるそうですよ。 ちなみに最近では、路線バスにアイドリングストップ装置が搭載されたバスが普及しています。 (2006年Vol6.自然がいちばん ビ・ーポコーポレーションより)◎7年前、関西に住んでいましたが、その時からアイドリングストップ装置が搭載された バスは 何台か有りましたが、それから、余り普及されていなかったのでしょうか? 早く、自家用車もそうなれば良いなぁと思いました。
Jul 2, 2006
コメント(2)
-
尿使い がん診断 トランスジェニック
<測定方法と抗体で特許> バイオベンチャーのトランスジェニック(熊本市、東証マザーズ)は29日、採取した尿を使うがん診断に利用できる抗体と測定手法について特許を取得したと発表した。「患者の体に負担をかけずに検査できるうえ、早期がんの発見も可能」といい、診断薬としての商品化を目指す。 同社は九州大などと約5年かけて共同研究し、がん患者が排出することが多く、細胞分裂の際に発生する物質を検出する抗体を開発し、その測定方法を確立した。尿の採取から数時間でがんのおそれがあるのか確認できるという。 複数の診断薬メーカーにこの技術を提供中で、うち1社が製造承認申請に向けた臨床開発を進めており、商品化されれば特許使用料が得られる。米国でも特許を申請している。 日本臨床検査薬協会(東京)の小出博文常務理事は「今後は症例を増やして、がんの部位を特定するなど精度を高めていくことが課題になるだろう」と話している。 (2006年6月30日 読売新聞)◎なんと尿を使って、簡単にがん診断ができるようになって、素晴らしい事です。 患者の体に負担をかけずに検査できて、早期発見につながるとのこと、これからの 健康診断で取り入れられることでしょう。手軽にできるようになるので、本当に 良かったです。1日も早く、診断薬としての商品化を実現して欲しいと、思いました。◎昨日の記事の感想の中で、1文字違っていたことを訂正します。 「入院されている」が「入院させている」になっていたのです。慌てて編集で 訂正しました。1文字違いで全然受ける印象が違いますし、不快な気持ちになられた 方も居られると思いますので、お詫び申し上げます。今後も、注意していきたいと 思いました。
Jul 1, 2006
コメント(2)
-
心に残る医療 「ハッピー・エンドの介護」
【第23回 受賞作品 新潟県南魚沼市 阿部 久美子さん】 我が家では、私が物心ついたころから、いわゆる「嫁姑戦争」がすさまじかった。 母の涙を、今も時々、思い出すことがある。 祖母の足腰が弱まり、ほとんど寝たきりになってしまったのは、1989年の夏の終わりごろだった。原因は覚えていないが、突然のことだった。祖母は87歳だった。 まず、必ず毎日一番に入っていたお風呂に、父の介護なしでは入れなくなった。 ある日とうとう祖母はおしめをすることになった。その方が、トイレに行かなくて済むだろうと考えたからだった。でも、そうではなかった。おしめは、祖母の人間としてのプライドを、壊してしまった。泣くのだ。「大人なのにおしめなんかして、情けない」と、あの気丈だった祖母が私たちの目の前で、ぼろぼろと涙をこぼした。そして、これがきっかけとなって、祖母はだんだんとぼけていった。 だが、認知症の症状が進むにつれ、祖母の母に対する態度が変わっていった。身の回りの世話を、母以外の誰にもさせなくなったのだ。もう、完全に母だけに頼り切っていた。その証拠に、母の顔だけは最後まで忘れなかった。母はどんなにうれしかったことだろう。やっと思いが通じたのだから。母の苦労をずっとみてきた私も、本当にうれしかった。 その年の12月、祖母は亡くなった。脳梗塞で倒れてから、2日目のことだった。 葬儀が終わったあと、父が私に言った。「ご臨終です、と医者に言われたとき、いちばん最初に泣いたのが、お母ちゃんだった。本当にうれしかった。悲しいかったけれど、お父ちゃんはそれがうれしくて、大泣きしたんだ」。こんな両親を、私は心から誇りに思う。長い期間ではなかったけれど、祖母の介護経験は、私たちにとても大きな影響を与えた。 私たち家族は、祖母の介護を通じて、実に多くのことを学んだ。中でも、介護とは決してつらく苦しいことばかりでない、ということを知り、本当に良かったと思う。なにしろ「嫁姑戦争」を「嫁姑同盟」に変えてしまったのだから。 ハッピー・エンドの介護が、これからどんどん増えていけばいいな、と思う。 ☆受賞作品の詳細はホームページをご覧ください。 http://www.med.or.jp/kokoro/ 主催:日本医師会/読売新聞社 後援:厚生労働省 協賛:アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) (2006年6月29日 読売新聞)◎最近、病院へ入院されているお年寄りの着替をなかなか持ってきてくれないことや、 面会にも来ない家族が増えていることを、ほかの記事で読んで心寂しく思っていた ところに、今回の体験記は、心温まるもので、本当に両手一杯に拍手を送ることが 出来て、良かったです。とても涙が出るほど、お父さんの言葉に感動しました。 実話だけに、文の締めくくりにもあるように、”ハッピーエンドの介護が、増えたら 良いな”と思いました。真の、”人間の優しさに”触れる事ができて、良かったです。
Jun 30, 2006
コメント(2)
-
冷え症・肉体疲労・虚弱体質・胃腸虚弱 などの方に朗報???
[ナンパオ 華(はな)約1ヵ月分(商品64カプセル)を差し上げます] 疲れ、冷え症でお悩みの方へ。生薬のチカラをお試しください。 たなべ薬房(やくぼう)★今回は、女性に限定させていただきます。「ナンパオ華」を初めてお試しになる女性の方で、 日頃から、疲れ、冷え性、血色不良、食欲不振などでお困りの方を対象といたします。 *お申し込みの際には、最もお悩みの症状を必ずお答えください。(下記よりお選びください) 1.冷え症 2.疲れ 3.血色不良 4.食欲不振 5.虚弱体質 6.身体が弱く風邪などを引きやすい★約2週間以内に「ナンパオ華」64カプセルをお届けします。*1世帯様あたり、1回限りの応募といたします。*10種類の生薬配合の医薬品。肉体疲労・冷え症に効きます。 成分 ニンジン乾燥エキス・ハゲキテン末・ケイヒエキス・ニクジュヨウ乾燥エキス・ トチュウ乾燥エキス・トシシエキス・カラトウキ乾燥エキス・クコシエキス・ ジオウ乾燥エキス・ブクリョウエキス・*効能 次の場合の滋養強壮:肉体疲労・冷え症・血色不良・食欲不振・ 胃腸虚弱・虚弱体質・病中病後 *成人(15歳以上)1回1カプセルを1日2回、朝晩食後に服用してください。 64カプセル【通常価格】5775円(税込み・送料525円) 【毎月お届けコース】5486円(税込み・送料無料】 ★お申し込み締め切り:平成18年7月10日(消印有効)*当キャンペーンに関するご質問・お問い合わせ等は、 「たなべ薬房:フリーダイヤル0120-780-873」までお願いします。 (午前10:00~午後6:00の日・祝日除く) 携帯電話・PHSからもご利用できます。 お申し込みの際は、[あさがおー03]とお申し込みください。★FAX:0120-780-834(24時間受付、土・日・祝日も受付)薬剤師が お電話いたします。必要事項をもれなくご記入の上、送信してください。○〒、住所○氏名(ふりがな)○年齢○電話番号(FAX番号) eメールアドレス○「ナンパオ華」無料サンプル希望○最も悩みの症状 ★お葉書でのお申し込みの場合(上記の、必要事項をもれなく記入してください。 おハガキが到着後、薬剤師がお電話します) 〒104-0032 東京都中央区八丁目堀2-23-1 エンパイヤビル7F たなべ薬房 行 あさがお-03★たなべ薬房 URL http://tanabeyakubo.com 製造販売元 田辺製薬株式会社 製造元 たねべ薬房★今回申し込みされた方は、「ナンパオ華・モニター」に登録させていただきます。*ご提供いただきました個人情報は、「たなべ薬房」が適切かつ厳重に管理し、 商品の発送・代金決済・製品やキャンペーンに関する案内を目的として、 「田辺製薬」と共同でお取り扱いさせていただきます。 (2006年6月26日 読売新聞)◎冷え性で悩んでいるお友達がいます。また多くの女性が冷え性で悩んでおられるのでは ないかと思い、考えた末ブログに載せました。あくまでも、情報を提供するのでもの あって、これを試したから冷え性が治るとは言えませんが、自分の体に合ったものを 見つけるための参考にして戴けたら良いなぁと思い載せました。 今回は、残念な事に男性の方は、駄目みたいですが、男性の方でも効能に当てはまる のならば、是非お試しさせて戴きたいと思いました。
Jun 29, 2006
コメント(6)
-
体に良いと考えられている生活習慣
☆あなたのカラダが求めている食生活1.新鮮な有機栽培の果物=生又は絞りたてのジュースで摂る2.新鮮な有機栽培の野菜=生かゆでて食べる、野菜スープでも良い。 できるだけ色とりどりの野菜を選ぶ3.玄米、黒米など精米していないご飯または無精白のライ麦か小麦粉で作ったパン4.オートミールのようなものは頻繁に食べる5.甘味は赤砂糖、蜂蜜、メイプルシロップにする6.塩は天然の海水で作った塩にする7.タバコは止める8.アルコールはできるだけ減らす。その分搾りたてのジュースにする9.コーヒー、紅茶もできるだけ減らして、カモミールなどのハーブティーにする10.皮を除いた家禽類の肉、低脂肪のものにする11.クルミやアーモンドなどのナッツ類を食べる12.加工食品はできるだけとらないなどがお奨めです。 (2006年Vol6.自然がいちばん ビ・ーポコーポレーションより)◎初めて聞く物も中にはありますが、体に良い物だそうです。余りストレスに ならないように、「楽しく出来れば良いなぁっ」て思いで載せました。
Jun 28, 2006
コメント(8)
-
がん緩和ケア 治療全段階で
厚生労働省は、末期のがん患者の痛みや心労を取り除く「*緩和ケア」を、初期がんを 含むがん治療の全段階に導入するため、新しい医療体制を整備することを決めた。全国135か所の拠点病院に対し、2年以内に緩和ケア対応医療チームを設置するよう 求めるとともに、がん患者5000人に対し、緩和ケアを組み込んだ試行的な医療を開始する。緩和ケアの普及を目的とした基本計画を5年以内に策定することを目指す。 国内のがん発症者は、年間約60万人。患者は治療中にもがんや治療による苦痛を感じ、死への不安を抱えている。しかし国内の医療現場はがんの根治を重視し緩和ケア への理解が少なく、終末期にホスピスで初めて利用する患者が多い。 今月成立した「がん対策基本法」には、緩和ケアについて「早期から適切に行われる ようにする」と明記されている。緩和ケアの普及は患者に優しいがん医療体制づくりの 第一歩となる。 現在、地域のがん診療の中核となる拠点病院が全国で135施設選ばれている。厚労 省は拠点病院に対し、緩和ケアを医師、看護師、医療心理の専門家によるチーム医療と することを義務づけ、ホスピスだけでなく一般病棟や外来のがん患者にも、継続して施療できる院内体制の設備を求める。拠点病院への新規指定を希望する医療機関に対しても、 緩和ケアの充実を指定条件にする。 さらに、緩和ケアを全国に普及させる具体策を研究するため、リーダーとなる研究者を年内に公募する。リーダーは、拠点病院を中心にモデルとなる地区を選び、5000人の患者を対象に研究を進める。 具体的には、ケアに必要な知識や技術を各医療機関に広める教育プログラムを作り、 地域内の患者が必要とするときにすぐ緩和ケアを受けることが可能な医療体制の有り方を探る。在宅での緩和ケアプログラムも作成し、末期がん患者の自宅療養を増やす。通常のがん治療が行われている地域と比較し、モデル地区での緩和ケアの利用率を2倍にする ことが目標だ。*緩和ケア・・・がんによる痛みや不快感などを取り除くこと。モルヒネなどの薬や放射線に よる鎮痛、抗がん剤による吐き気など副作用の緩和、呼吸が苦しい患者への酸素の吸入など。 患者や家族の不安を軽減するカウンセリングも含まれる。 (2006年6月25日 読売新聞)◎がんの発症者は年間約60万人も居られるのに、緩和ケアが全国135か所の拠点病院しか ないのに、ビックリしました。これからの活動に期待したいです。また内容も充実し、 安心してがん治療と向き合えるようになれば、心強いと思いました。
Jun 27, 2006
コメント(8)
-
ヒトクローン胚研究解禁へ (その2)
ヒト胚をめぐっては、クローン技術は生命操作につながり、生命の萌芽(ほうが)である胚の研究利用は倫理的に問題とする批判が根強い。 米国のように、ブッシュ大統領が支持基盤である宗教右派の主張に配慮してヒトクローン胚の全面禁止を主張し,ES細胞研究に連邦資金の支出を厳しく制限している例もある。研究推進派との間の溝は埋まらない。 そうした状況に加え、改正案の審議には、ヒトクローン胚由来のES細胞作製の論文を ねつ造した韓国の黄禹錫(ファンウソク)ソウル大元教授の事件も大きな影を落とした。 黄教授は2061個の卵子を入手したが、結局ES細胞を作製できず、ヒトクローン胚研究 そのものが非常に難しいことがわかった。その結果、作業部会は、英国や韓国で認めら れている健康な女性ボランティアからの卵子提供について、提供者に身体的・精神的な 負担をかけるほど研究が進んでいないとして、当面容認しないと決めた。 事件では、論文ねつ造以外にも、卵子提供者への金銭の支払いや研究グループ内の女性から卵子提供を受けるなど倫理的な問題も明らかとなり、社会の大きな不信を招いた。こうした点も作業部会で問題視された。 厳しい規制の背景にはこんな事情があるが、京都大再生医科学研究所の中辻憲夫所長は「これだけ厳しいと、わが国では誰もヒトクローン胚の研究に取り組まないのではないか」と指摘する。 難病の患者団体も反発している。日本脊髄損傷の患者団体「日本せきずい基金」の大浜真理事長は「研究が進んでいないことは、ボランティアからの提供を認めない理由 にはならない。このままでは日本の研究の遅れ、他国の後塵を拝するだけだ」と訴える。 公的資金がES細胞研究に期待できない米国でさえ、ハーバード大が今月、独自にヒト クローン胚研究を始めると発表した。海外でクローン胚由来のES細胞の作製に成功し、 移植医療への応用が将来進んだ場合、国内の医療が見限られ、海外依存が強まる事も懸念される。 もちろんクローン人間の誕生を完全に防ぐとともに、第2、第3の黄教授が現れないよう、厳しい倫理的な規制が必要なのは当然であり、その点は譲れない。 同省は今後、改正案について患者団体や学会の意見を聞いた上で、総合科学技術会議に諮問する。国内のクローン研究に対する世論や海外の研究動向をにらみながら、研究と倫理の調和を、関係者は今後も考え続けて欲しい。 (2006年6月23日 読売新聞)◎クローン技術が発達すると、”人間は死なない”時代がくるんだと思いました。 傷んだ臓器は造りなおせば良いのだから。考えたらとても怖いものを感じました。 ”心”はどうなってしまうのだろうか? ふと心配になりました。
Jun 26, 2006
コメント(6)
-
ヒトクローン胚研究解禁へ (その1)
[理論とのバランス見極めた指針を] 文部科学省の作業部会が、ヒトクローン胚(はい)の研究解禁に向けて、クローン技術規制法の指針改正案をまとめた。韓国での論文ねつ造問題を教訓に、厳しい規制を課した。 ☆クローン技術規制法の指針改正案の骨子 <クローン胚作製に利用できる卵子>・不妊治療で不要になったか手術で摘出した卵巣から採取した卵子・提供は無償が原則・卵子の入手は提供者の自由意志に基づく・研究グループのメンバーや親族、難病患者からの提供は禁止・健康なボランティア女性からの提供は当面禁止 <クローン胚研究を行える研究機関>・ヒト受精卵からES細胞を作製した経験・マウスなどの動物のクローンES細胞を作製した経験・霊長類のクローン胚を製作した研究者の参加・クローン胚研究を審査する倫理委員会の設置 <その他>・ヒトクローン胚の輸出入禁止・信頼性、透明性確保のための適切な情報公開に努力 ヒトクローン胚は、核を取り除いた卵子に、別人の体細胞の核を入れて作製する。子宮に戻せば、クローン人間が誕生する恐れがあり、2001年に施行されたクローン技術規制法の指針で、クローン胚研究を当面禁止とした。 一方で、マウスのクローン胚からは、様々な臓器・組織に変化しうる胚性幹細胞(ES細胞)の作製に成功している。ヒトで成功すれば、体細胞提供者と同じ遺伝子を持つ臓器や組織作りが可能で、拒絶反応が起きない研究の移植医療も夢ではなくなる。 総合科学技術会議は04年7月、「ヒトクローン胚の作製・利用は原則認められない」としながらも、難病治療を目指す基礎研究であれば、例外的に認める方針を決めた。同省の作業部会はこの方針を受けて、研究を認める具体的な要件を検討したため、当初から厳しい内容が予想された。 実際、改正案は卵子の入手を制限、研究機関にも十分な実績を求めた(上に書かれて いる条件)。ここには、倫理上の問題が起きないよう、石橋をたたくような慎重さで研究を進めるべきだ、との強い意思が感じられる。 *長い文なので、続は明日にします。 ◎毎回クローン胚研究には、まだまだ沢山の疑問が出てきますが、難病の人の医療向上 のために、やはり必要なのかもしれないと思いました。でも、より一層優れた人間を 造るためのの技術になるようにも思いました。 (2006年6月23日 読売新聞)
Jun 25, 2006
コメント(2)
-
内戦のコートジボワール 国土分断 子供犠牲に
「武器にあこがれ、11歳で武装勢力に入った」 武装勢力支配地域の拠点都市ブアケにある元子ども兵の社会復帰支援センターで、サノゴ・ラシナ君(15)は小声でぼそぼそと話した。落ち着きがなく、家族については話したがらない。将来の夢を聞くと「兵士」と答えた。 世界有数のカカオ産地として安定成長していた同国は1999年のクーデター以来、民族問題も絡んで政情不安が続き、2002年に内戦が発生、子どもたちも戦乱に巻き込まれた。03年の和平締結後も政府が南部を、反政府勢力が北部をそれぞれ支配したまま分断が続く。 支援センターは地元NGOが国連児童基金(ユニセフ)の支援を得て運営しており、青少年約150人が読み書きを学んだり、機械整備、縫製などの職業訓練を受けたりしている。 大統領派とみられる民兵に故郷が襲撃され、「父母を守るため」に武装勢力に加わったという青年(19)もいた。両親とは4年間会っていない。武装勢力に加わった少年少女は推定3000人という。 ユニセフ親善大使として今月、反政府勢力支配地域を訪れた女優の黒柳徹子さん(72)は、「元子ども兵は心のよりどころを失っている場合が多い」と指摘し、「外の世界に心を開き、いい仕事につけることを願っている」と話した。 北部の町コロゴ近郊では内戦で建設が中断していた小学校がユニセフの支援で昨年完成、6村の子ども94人が通っていた。教師2人は地元のボランティアだ。 その一人、シルエ・バカレさん(28)「教育はすべての基本。子どもたちの役に立ちたい」と話すが、教員免許を持つ教師の大多数は政府統治下の南部に去り、約100万人が教育を受けられなくなっているとの数字もある。 反対政府勢力が支配する地域では医療事情も深刻。医療施設の80%が閉鎖、医療関係者も85%が南部に逃れた。医療機器やスタッフが不足し、妊産婦や乳幼児の死亡率が上昇している。 エイズウイルス(HIV)感染率は西アフリカでも最も高い7%。全国では約4万人の子どもが感染しているが、治療を受けているのは約1000人。エイズで親を亡くした子どもは31万人にものぼる。 ブアケのエイズ孤児施設で支援活動をしている地元の記者のアブ・サノゴさん(29)は 「親を失い、弟妹を養うために売春して感染した少女もいる」と沈痛な面もちで語った。 (2006年6月23日 読売新聞)◎最近、ユニセフの活動をよく紹介されていますが、どの記事を読んでも、恵まれない 子どもたちが、世界にホント沢山いるんだと知らされます。日本でも、恵まれない 人たちがいることを、忘れてはいけないと思いました。まだ、日本は戦争をしていない分、 恵まれているのでしょうが、訳あって、両親と一緒に住めない子どもたちが居ることを、 考えさせられました。実は、私は高校の3年間、恵まれない子ども達と一緒に寮生活をし、 貴重な体験をしました。
Jun 24, 2006
コメント(4)
-
自殺者の遺族らが冊子 支援組織向けにケア方法を説明
1年間の全国の自殺者が8年連続で3万人を超える中、自殺者の遺族らで作る全国組織が、遺族の心のケアの重要性や具体的なケア方法などをまとめた冊子を刊行した。遺族がつらい体験を語り合える場が徐々に増えているが、その運営方法についても具体的なアドバイスが紹介されている。 冊子をまとめたのは、遺族グループや医師らが昨年11月に発足させた「自死遺族ケア 団体全国ネット」(東京)。今年2月に初めて開催した「スタッフ研修会」の内容をまとめた。 この研修会は、全国で活動する遺族グループの運営スタッフらを対象に、よりよい遺族ケアのあり方を探るために開かれたもので東北、四国、九州などから34人が参加し、専門家らの話を聞いた。 遺族ケアに詳しい精神科医の平山正実さんは、残された家族の心理や精神構造について解説。言ってもらいたくない言葉として「時がすべてをいやします」「早く忘れなさい」などを挙げ、自死遺族を援助する際の注意点を分かりやすく紹介した。 NPO法人「生と死を考える会」(東京)副理事長で、20年以上、遺族が語り合えるグループに携わってきた杉本脩子さんは、グループ運営の重要性や具体的な手法、難しさなどを語った。 スタッフの役割として、「参加者の悲嘆感情に寄り添う姿勢」「指導したり、教示したりする立場に立たない」ことを挙げ、安易に慰めたり、理解したふりをしたりしない大切さなども説いた。また、会場の作り方や広報のしかたなどについても触れている。 同ネットによると、自死遺族のためのグループは全国に約30団体あり、ここ数年、増加傾向にあるという。 「遺族らが、自分の体験を役立てたいと、立ち上げるケースが多い。しかし、支援には特有の難しさがあり、継続させるのは簡単ではない、この冊子が、遺族支援のテキストとして活用されればうれしい」と、同ネット事務局長の藤井忠幸さんは話す。 ☆1冊1500円(送料別)。問い合わせは、同ネット (電話03-5775-3876、木・土の午前10時~午後4時)へ。 (2006年6月12日 読売新聞)◎遺族を亡くされた悲しみは、計り知れないと思います。少しでも 気持ちが軽くなって欲しいと 思ってかけた言葉でも、かえって傷つけてしまう事も多だ有ると思います。本当に、必要と している言葉がかけられる人になりたいです。
Jun 23, 2006
コメント(2)
-
自殺防止対策を急げ 大野 裕氏(56)
■自殺者が8年連続3万人を超えた。この現状をどうみるか。 年間自殺者数が3万人を突破したのは1998年。一挙に対前年比35%も増加し、死亡統計始まって以来の数値となった。現在まで3万人を割ることはないが、警察庁の調べでは、健康問題とみられる自殺が全体の半数近くで、うち3分の2が病苦、3分の1が精神障害となっている。身体疾患の患者の精神的ケアと、精神障害の治療の質の向上が、自殺対策のカギであることが分かる。 ■経済的問題も原因か。 3万人を超えた時に急増したのは50歳代の男性で、特に無職者と離職者が多かったため、背景として経済的問題が指摘された。事実、警察庁の発表では、経済・生活苦によるとみられる自殺は、97年の3556人から98年は6058人、03年には8897人へと急増している。 一方、若者の自殺が少ないのが日本の特徴だったが、近年増加しており、丁寧な分析が必要だ。過労死を巡る裁判や労働安全衛生法の改正で、労働環境が見直されているが、 中小企業などの深刻な過重労働は変わっていない。 ■対策法の成立で、自殺防止は進むのだろうか。 対策を確実にするには、正確な実態把握が不可欠だ。そのために国は、自殺未遂者を対象にした再発防止策の構築など、大規模な多施設共同研究を始めている。対策法は、自殺対策を、国と自治体の責務と位置づけたことで評価できる。法をいかに生かすかは今後の課題だ。 ■国内の自殺対策で成功している例はあるか。 全国の数字は一向に改善しないが、80年代以後、地域の取り組みで自殺率を減らした例がある。新潟県松之山町(現十日町市)の先駆的取り組みは有名だ。一次予防として市民への普及啓発活動と高齢者への集団援助、二次予防として精神科医らによるフォローアップなどが行われた結果、65歳以上の自殺率が10年で4分の1になった。 県別自殺率で常に上位の秋田、青森、岩手の3県も、熱心な取り組みで成果を上げている。活動の特徴は、保険師らを中心に、地域全体が町おこしや村おこしを通じて、住民の健康づくりの一環としてうつ病などの早期発見、支援をしていることだ。■自殺予防は背景にあるうつ病の対策だともいう。 世界保健機関(WHO)の報告では、自殺者の95%以上が、その直前に何らかの精神疾患になっていたという。ただ、自殺対策とうつ対策がしばしば混同されていることが問題だ。WHOの報告でも、自殺の要因になった精神疾患のうち、うつ病は30.2%でしかなく、アルコール依存症を含む薬物関連障害などが続く。決してうつ病対策だけが自殺対策ではない。 精神疾患を抱えながら医療施設を受診する人が全体の3割と少ないことも問題だ。心の健康を守って自殺を予防するには、保険師などを中心に住民啓発することが重要であるであることがわかる。 ■何か提言は。 誰かの役に立つ、ということも含めて「仕事」を喪失することの絶望感が日本人は強いので、人間関係の再構築や経済的やセーフティーネットの確保が自殺予防につながる。 医学や医療では全く不十分で、社会的要因を考慮した総合的支援が不可欠だ。☆大野 裕氏・・・・慶応大学保健管理センター教授。精神科医。日本認知療法学会理事長。 著書は「『心の病』なんかない」など。56歳 (2006年6月20日 読売新聞)◎自殺者が増えている現状、とても心寂しく思いました。物が溢れて豊かな生活を送れるようにな った日本だが、大切な心が満たされていない事、みんなでお互いの幸せを、考えられる世の中に成れば良いなぁと思いました。
Jun 22, 2006
コメント(4)
-
子供の臓器移植 ”海外の頼み”
左腕の黒い喪章が緑のグランドで揺れていた。5月17日の西京極陸上競技場(京都市)。サッカーJ1・鹿島アントラーズの選手が臨んだ試合は、この日他界した 小さな命にささげられた。 難病と闘った茨城県常総市の神達綾花(かんだつあやか)ちゃん(享年1)。両親は、 米国なら、小腸や大腸など5臓器の同時移植ができると聞き、渡米を決めた。しかし、 渡航費は約1億3000万円。それを救ったのが、サッカーだった。 父親の良司さん(35)がアントラーズの応援団員だった縁で選手やサポーターらが 募金に協力、2週間で目標額が集った。 そして渡航。昨年12月の移植手術は成功したが、5か月後に襲った感染症に綾花ちゃんの体は耐えられなかった。望みはかなわなかったが、良司さんはこう振り返る。 「短い間だったが、親子3人で貴い時間を過ごせました」 日本移植支援協会によると、綾花ちゃんのように、海を渡った国内の小児患者は1997年の臓器移植法施行以降も48人。大半は元気に暮らしている。だがなぜ海外か。 日本の臓器移植法は、脳死になった15歳未満の子供からの臓器提供を認めていない。 特に体の小さい乳幼児に大人の臓器が合う可能性は低い。 「脳死は人の死」という考え方が国民に浸透していないために、30年近くも議論した末、15歳以上の本人が書面で意思表示している場合のみ提供できる、という世界で最も厳しい法律が成立したのだ。 結果生じたのが、欧米の移植医療に頼り切る現状だ。15歳未満からの臓器提供に道をひらく同法改正案が先の国会に提出されたが、審議入りは先送りとなった。皆さんはどう考えるだろうか。(瀬畠義孝) (2006年6月20日 読売新聞) ◎日本の幼児や子供の臓器移植問題は、かなり昔から言われているのに対して、全然進歩 して いない事に、驚いています。助かる命も、海外へ行かないと助からないのだったら、殆んどの子供達は助からない事になってしまう。早く大人と同様、子供の移植も認められて、尊い小さな命を救って欲しいと思いました。
Jun 21, 2006
コメント(6)
-
3.5円で救える命 ユニセフ募金にご協力ください
私は、20年以上、ユニセフで仕事をしてきて、ここ数年はHIV(ヒト免疫不全ウィルス)・エイズ問題に取り組んでいます。子供たちは、世界のエイズ対策から、置き去りにされた状況にあります。 世界で今、15歳未満の子供が毎分1人感染し、同じ割合で亡くなっています。15歳~ 24歳の若者は毎分4人の割合で感染しています。エイズで親を失った子供は1500万人。 新たなHIV感染者のうち、7人に1人が子どもです。 最も大きな被害を受けているのは、サハラ砂漠以南のアフリカの国々です。世界の子どもの感染者の85%以上が、この地域に住んでいます。 アジアも事態は深刻です。子どもは2005年に1万1000人が新たに感染し、約8000人が 亡くなりました。現在、3万1000人の感染者がいます。インドネシア、インド、ネパール、ベトナム、中国の特定の地方では感染者が急増に増えています。 様々なエイズ対策が行われているのですが、子どもたちは忘れ去られています。対策のカギは四つあります。 1番目は、母子感染の予防です。何らかの予防措置を講じないと、感染した母親からの出産により、約3分の1の確率で、子どもに感染します。 2番目は、子どもの感染者に対する治療です。エイズを発症した子どもたちは免疫力が落ち、肺炎などの感染症にかかりやすくなり、命を落とします。 抗生物質・コトリモクサゾールを使えば死亡率を下げる事ができるのに、この薬を必要とする子どものうち1%しか手にしていません。子ども1人に必要な費用は1日わずか3セント(約3円50銭)なのに。 3番目は、若者の感染予防です。予防の知識を十分に持っていない人が多くいます。 最後は、エイズにより困難な状況にある子どもの保護です。サハラ砂漠以南のアフリカ地域では、2010年には1800万人以上の子どもたちが、エイズでどちらかの親を失います。これはイギリスの子どもの数に匹敵します。 次世代の子どもたちが、エイズの脅威にさらされない世界を実現しなくてはいけません。ユニセフは昨年から「子どもとエイズ」と題した世界的なキャンペーンを行っています。 皆さん一人ひとりがユニセフとともに立ち上がって、エイズと闘ってほしいと思います。 <基調報告 ピーター・マクダーモットさん>1.郵便振込みで 口座番号:00190-5-31000 口座名義:財団法人 日本ユニセフ 2.クレジットカードで フリーダイヤル:0120-88-1052 ☆9:00~18:00(土・日・祝休み) 3.インターネットで http://www.unicef.or.jp ホームぺじにアクセスしてください。クレジットカードによる募金となります。◎1日3.5円で救える命が有るのなら、できるだけ協力したいと思いました。エイズが世界から 無くなることを、願っています。
Jun 20, 2006
コメント(2)
-
検査の基準値 男女別・年齢別が登場
コレステロールなどの基準値は現在、各分野の医学会が定めているが、多くは男女、年齢は問わない一律の数値となっている。 これに対し、東海大医学部教授の大櫛陽一さん(医学教育情報学)は「検査の適正値は、性別や年齢によって異なる。高齢者に若い人と同じ基準値を適用すると、異常と判断される人が増えるなど問題が大きい」と指摘し、新たな基準値を提唱した。 全国で健康診断を受けた約70万人から健康な人のデーターを抽出、男女別、年齢別に解析し、数値の高い人と低い人を除く約95%の人が納まる範囲を適正な数値とする、国際的な方法で基準値を算出した。■コレステロール 既存の日本日本動脈硬化学会の基準では、総コレステロール値220以上で高コレステロール血症とされる。だが、大櫛さんは「高コレステロールは、若い人では心筋梗塞の要因になるが、年齢とともにその傾向は薄れ、70歳以上ではほとんど関係ない」と言う。 そこで今回の基準では、20歳前半こそ学会と同様220が正常の上限だが、50歳以上では男性が260、女性が280程度とした。 大櫛さんは、同様の大規模調査を行った三井記念病院(東京)総合健診センター所長の山門実さんとともに、高コレステロールの薬物療法を行う目安となる数値を公表した。 ■血糖値 今回の基準値は、男性は緩やかに、女性は厳しく設定されている。 日本糖尿病学会の従来の診断基準では、正常な血糖値(空腹時)の上限は110未満と されている。ところが大櫛さんによると、これでは若い女性の糖尿病が見逃されるという。 20~39歳の女性160人を調べたところ、空腹時血糖値が100~109と正常でも、ブドウ糖を摂取して2時間後に血糖値を測る負荷試験では、約6割に異常が見つかったからだ。空腹時血糖110未満では、負荷試験での異常は約2割にとどまった。大櫛さんは「若い女性の上限値は100未満に引き下げる必要がある」と話す。■肥満 肥満は心筋梗塞や脳卒中の要因とされ、日本肥満学会は体重(キロ・グラム)を身長(メートル)の2乗で割ったBMI(体格指数)で25以上を肥満としている。だが、実際はやせている人ほど死亡率が高く、「中高年は、小太りの人が長生きできる」(大櫛さん)ただ、若い男性は、BMIが25を超えると糖尿病になりやすい。 そこで、「上限値」「目標値」の2種類の基準が設定された。上限値を超えた場合は精密検査を行い、目標値を超えたら定期的に経過を見る。中高年男性の上限はBMI28程度、目標値は25程度。■血圧 高血圧の場合、「上限値」は、それを超えた場合に薬物療法を始める目安で、「目標値」を超えたら、運動や食事の改善を行う。 *今回の基準値については、大櫛さんの著書「検査値と病気 間違いだらけの診断基準」 (大田出版)に詳しい。 (2006年6月18日 読売新聞)◎新しく詳しい検査基準ができたので、これからの参考にしたいです。年齢や男女差で変わるの は、考えてみたら当然の事なのに、今まで余り言われてこなかったのが、不思議なくらいです。 そして、痩せている人より太っている人の方が、長生きするのには意外でした。 今回 表やグラフを載せる事ができなかったのが、残念です。すみませんでした。
Jun 19, 2006
コメント(2)
-
バイオディーゼル燃料 本格的に導入
■「揮発油等の品質に関する法律(品確法)が年内には改正されるようになり、バイオディーゼル燃料を5%以下混和した軽油が販売できる見通しですが、そもそもバイオディーゼル燃料とはどういうものですか?○地球温暖化の原因である二酸化炭素などの温室効果ガスを削減するための「京都議定書」が昨年発行されました。原油高騰のあおりも受け、現在、二酸化炭素を排出している石油・石炭などの化石燃料に替わるものとして、新エネルギーの開発が進めら れており、そのひとつとしてバイオディーゼル燃料が注目されています。 バイオディーゼル燃料は通称で、正式には「脂肪酸メチルエステル」といいます。植物油、あるいはその廃食油を原料にした燃料で、これらをアルコールとエステル交換して、ディー ゼル機関を搭載した自動車や船、農機などに利用しようというものです。 化石燃料、バイオディーゼル燃料とも燃焼すれば二酸化炭素を排出しますが、植物由来のバイオディーゼル燃料の場合、実は排出される二酸化炭素は地球温暖化効果ガスの増加にはカウントされません。それは、植物自身の生育過程で光合成によって、排出された二酸化炭素を再び吸収するからです。これを「カーボンニュートラル」と呼びます。このことから、バイオディーゼル燃料は化石燃料に代替することで地球温暖化対策に有効な再生可能エネルギーといえます。■改正品確法ではどのような点が改正されたのですか。○既にサトウキビなどを原料にしたエタノール3%を混和したガソリンが販売可能となっていますが、バイオディーゼル燃料の利用は、一部の自治体やNPOなど自主的な使用に限られています。今後は普及していくとみられることから、消費者の安全はもちろん、品質をも確保する必要があります。経済産業省総合資源エネルギー調査会石油分科会委員会規格検討ワーキンググループ(GW)では、これまで9回にわたって安全性や品質確保などについて討議してきました。 既販者の安全性の観点から、排ガスや車の部材に対する安全性試験、燃料漏れなどの様々な試験を経て、軽油に混和して販売することができるバイオディーゼル燃料は5%以下と定めました。つまり、5%以下であれば安全性には問題はないということです。 問題は品質をいかに確保するかです。これが法改正に向けた一番のキーポイントになります。GWでは強制規格に、エンジンにダメージを与えるおそれがある「酸価」、「酸化安全性」などの項目に規格値を定めています。このような規格値を守らなければ軽油に混和して販売することはできなくなり、もちろんまがいものは排除されることになります。 (2006年6月17日 読売新聞) ◎廃食油を使って、バスなどを運行している事は知っていましたが、今後は普及の見通しができて とっても嬉しく思いました。地球環境に優しい資源として、大切に使っていかなければいけない と思いました。呉々も、安全性に重点を置いて欲しいです。
Jun 18, 2006
コメント(6)
-
笑って治そう生活習慣病 立川らく朝氏(52)
元気で暮らすのに1番いいものは、何だかご存じですか。しかも、お金がかからない・・・、それは「笑い」です。なにがいいって、笑うことで、がんを予防してくれるんです。がんは生活習慣病の死亡原因の第一位。統計を見ると、3人に1人が、がんで亡くなっています。 がんのもとになるがん細胞は、毎日毎日、私たちの体の中で勝手に生まれています。1日のうちに幾つできると思いますか? 2000個以上ですよ。でも、人間はそう簡単に死なないようにできています。がん細胞を片っ端から壊してくれる「ナチュラル・キラー細胞」(以下NK細胞)というのが、体中にいるからです。 とはいえ、このNK細胞の元気がなくなったら、がんを壊さなくなっちゃう。その原因は、万病のもとのストレスです。そして、そのストレスを軽減してくれるのが、「笑い」なんです。笑うとNK細胞は元気になり、活性が高まる。がん細胞をどんどん壊してくれるわけですから、予防にもなるし、治療になる。これ、医学的にも証明されているんですよ。 それだけじゃないんですよ。ストレスを感じると副腎からアドレナリンが出て、このアドレナリンが動脈を縮めると、血圧が高くなる。それが、笑うことによってストレスが軽減されると、血圧が下がるんです。 さらに、ストレスから起きてくる病気は、やまのようにあります。動脈硬化も怖い。 皆さんもご存じの活性酸素の働きにより、動脈の壁の内側にコレステロールがたまりや すくなり、次第にその先の臓器が血液不足になって心筋梗塞や脳梗塞を引き起こします。 じつは、このプロセスを予防してくれるのは「笑い」なんです。活性酸素もストレスで増えるので、ストレスを軽減できれば、動脈硬化だって予防できるというわけです。 まだあるんです。最近のトピックスでは、笑うことで血糖値が下がるともいわれています。肥満も解消するし、糖尿病の予防にもなる。こんないいことないじゃないですか。なぜ笑うことによってストレスが解消されるのか・・・。笑うと頭の中がスポーンと真っ白になる。心の中が無になるんです。ほんとうですよ。もし疑うんだったら、これから笑いながら心配事をしてみてください(笑)。絶対できないですよ。昔の人は心を無にしようと思って座禅を組んだりしましたよね。今もビジネスマンの方たちが、ストレスを抱えると禅寺に行って、座禅を組む。だけどね、そんなことしなくてもいいんですよ。笑うだけでストレスがなくなっちゃうですからね。 そういうわけでございまして、「笑う」ということがどんなに健康にいいか、いろいろお話させていただきました。どうぞ健やかにお過ごしいただいて、あちこちご旅行も楽しんでいただいて、いつまでもお元気で長生きをしていただきたいと思います。 (2006年6月16日 読売新聞)◎文中より、「これから笑いながら心配事してください」と言う文に、とっても笑いました。 立川氏は落語家であり医学博士でもありますので、現在は表参道福沢クリニックを開設し 院長として内科診療にあたるかたわら、高座を務めてるそうです。「落語で健康教育」を テーマとした「健康落語」が好評を博している。
Jun 17, 2006
コメント(6)
-
「生活習慣病」に重点 予防対策 健康受診率など課題
年1兆円の伸びを示す医療費の抑制を目指し、政府が2008年度から新たに取り組むのが、生活習慣病予防だ。 糖尿病、高血圧症、高脂血症などの生活習慣病は、徐々に進行し、脳卒中や心筋梗塞の原因になるほか、人工透析や失明などの重い合併症を招く。このため、生活習慣病の医療費は国民医療費の3分の1を占め、高齢化の進展でさらに膨らむ。 生活習慣病予防のカギとなるのが、おなかにたまった内臓脂肪による、内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)だ。大阪大の船橋徹教授(内科学)は「一見すると肥満ではない中高年に突然起きる脳梗塞などは、内臓脂肪が引き金となることが分かってきた」と説明する。国民健康・栄養調査によると、中高年男性の2人に1人が、有病者・予備群とされる。 医療制度改革関連法では、市町村国民健康保険(国保)などの医療保険運営者に40歳以上を対象にした健診を義務づけ、保健指導などを徹底させる。内臓脂肪量の物差しとなる、おなか回り(腹囲)などの診断基準で、有病者・予備群と診断されると、医療機関で治療を受けたり、運動や食事に関する保健指導を受けたりすることになる。 また、医療保険運営者は、「有病者と予備群を計25%減らす」などの目標を達成できない場合、新高齢者医療制度での負担が増えるため、いや応なく取り組まざるを得ない。政府は、2025年で2兆円の医療費抑制効果を見込む。 しかし、医療費抑制を掲げて、生活習慣病予防に取り組むのは先進国でも例がない。「健康増進の意義は評価できるが、医療費を抑制できるのかは疑問」と言った異論もあり、政府が描く青写真を実現するためのハードルは高い。 健康対策は高度成長期後、日本の国民的課題とされてきた。2000年からは、糖尿病患者の数、適正体重などの具体的な数値目標を定めた「健康日本21」に基づき、国ぐるみで啓発活動に取り組んでいる。しかし、ほとんどの項目で目標値に達しておらず、日常生活での歩数や、20~60歳代の男性に占める肥満者の割合のように、策定時よりも実績値が大幅悪化している項目も少なくない。 今回の医療制度改革で、実効性を担保する目玉として打ち出された、健診と保健指導の義務化かも容易ではない。03~05年度の3年間、運動を主体にした保健指導を行った札幌市では、健診で予備群と判定された市民約3万7000人に案内状を送ったが、参加者は5%にも満たなかった。 保健指導の前提となる健診も全体の受診率は6割と低く、義務化への道は険しい。 立命館大学経済学部の柿原浩明教授(医療経済学)は、「保健指導の対象者は、もともと健康への自覚が薄い人が多い。小中学校の運動施設を利用しやすくするなど、 健康作りの環境を整えるとともに、健診や健康指導を受けない人の保険を高くするといった方策も検討すべきだ」と指摘している。 (2006年6月15日 読売新聞)◎内臓脂肪症候群は、男性に多いみたいですが、わが身を振り返ってみて、大いに反省 しなければいけにと思いました。体重を、落とすのことは本当に難しいです。 関西に居た頃は、プールへ歩きに行っていましたが、宮崎でも通える所を探したいと、 思っています。やはり運動して落とすのが、1番良いように思いました。
Jun 16, 2006
コメント(6)
-
健康食品 ちょっと待って
仙台市の主婦(61)は、83歳の母親が「元気になる」「健康にいい」などと言って、薬のような粉末や錠剤を「手当たり次第」に購入して飲むのを気にしていた。体に良いとされる特定の成分を抽出するなどした「健康食品」だった。「本当に効果があるのか」と疑問を持ち、時々注意をしたが、聞き入れてもらえず、市民センターで開かれた健康食品の講座を受講してみた。 講師は、市内の薬剤師、戸田紘子さん。戸田さんは、健康食品の現状に問題意識を持つ薬剤師らと一緒に情報発信する「ふぁるま・ねっと・みやぎ」を2年前に結成。出前講座や基礎知識を解説した冊子作りなどを続けている。 戸田さんの講演を聞いた主婦は「母が服薬する医療用薬との組み合わせ次第では、副作用を強めたり、効き目を弱くしたりするタイプがあることがわかりました」と話す。天然の素材を使ったものでも、それを濃縮した錠剤などを飲むと、取りすぎの危険があることなども知った。 「健康への影響を具体的に説明したら、母も納得し、余り手を出さなくなってきた。口の中へ入れる前に、私に聞いてと話しています」 太りすぎや栄養バランス、病気予防などを気にする日本人の食生活に浸透してきた健康食品。多くのタイプが出回り、業界紙「健康産業新聞」の推計では、昨年の市場規模は10年前の倍以上の約1兆2850億円(特定保健用食品を除く)に拡大している。 だが「サプリメントなどは安全性の確認を企業任せにした商品が多く、公のチェックが働かない。効能の真偽も不明なものが目立つ」と話すのは、「危ない健康食品から身を守る本」(コモンズ)の著者で科学ジャーナリストの植田武智さんだ。 先月には、キノコの一種「アガリクス」を含む健康食品の一製品に、発ガン促進作用があることが動物実験で確認され、この製品が販売停止になった。専門家が有害性を指摘するまで国は本格的な調査をしていなかった。 専門的な知識を持たない消費者が、素材の安全性や有効性をチェックするには限界がある。本当に必要な栄養素の量や種類も人によって違う。そこで最近注目されるのが、戸田さんのような薬局の薬剤師に相談する方法だ。 東京都が都薬剤師と連携して開設している「薬局検索サービス」http://www.toyaku.or.jp/pharmacy/topでは、健康食品の相談に応じる薬局の所在地を調べられる。「特定保健用食品」の相談が対象だが、将来は、他の健康食品についても応じる検討をしている。 戸田さんは「薬剤師といえども健康食品については知識が不十分な人がまだ多い」と”身内”の勉強会も続けている。「消費者が安心して相談できる『かかりつけ薬局』が広まることが理想ですね」と話している。 (2006年3月2日 読売新聞)◎健康食品を何気なく摂取していますが、今回の記事を読んで、色々考えさせられました。 当たり前の事ですが、サプリメントで摂取することを考えるのではなく、食物から摂取 できる方法を考えた方が、大変だけれど、大切だと分かりました。
Jun 15, 2006
コメント(6)
-
認知症の早期診断装置を開発した 武者 利光さん(74)
21個の電源が付いたヘルメット。これを5分間かぶる。頭部全体の脳波を計測し、波のゆがみから「正常」「準正常」「要治療」の3段階で認知症を診断する。こんな装置を世界で初めて開発した。 専門は物理学。「自分が認知症を研究するとは想像もしなかった」。というのも本人は、風の強弱など自然界にあって、人を快適にする「1/fゆらぎ」研究の第一人者。それが思わぬ分野へ進出した。 「ゆらぎ」は自然界にとどまらず、心拍や脳波など体の中にもあった。26年間勤めた東京工業大を退官後、深刻化していた過労死問題に注目、ストレスによる「ゆらぎ」をまずテーマに選ぶ。 「自給自足で研究する」とベンチャー企業の脳機能研究所を1994年に設立した。 最初に手がけたのが、喜怒哀楽を脳波で測る装置。人に装着してもらい新製品やテレビCMの客観的評価に使う。業界では有名なシステムだ。 そんな折、ある医師から「認知症患者の脳波は正常な人と違う」と聞く。脳波について「様々な情報を含み『宝の山』のよう」に感じていた。次なる挑戦だった。国立精神・神経センターと共同研究で、患者の脳波特有のゆがみを発見。装置を試作し数千回に及ぶ測定実験をこなした。 脳波の電圧を分析して指標化し、認知症の程度を鑑別する。大学病院などから約30台の注文があるという。 「面白くて続けた研究が、天の配剤でここまできた。早期診断で少しでも患者に役立てたい」 (科学部 藤田勝) (2006年5月27日 読売新聞)◎医学の進歩は、技術が進歩したお陰が大いにあると思います。このような影で 働かれてこられた方達の、努力が大いに有ってのことだと思いました。 これからも、より良い商品が開発されますように思いました。
Jun 14, 2006
コメント(6)
-
新聞で認知症予防 脳を活性化 簡単トレーニング
記憶が徐々に失われ、認知症を起こすアルツハイマー病。高齢者のアルツハイマー病では近年、症状の進行抑制や予防として「読み・書き・計算」のトレーニングが有効なことが分かってきた。東北大教授(脳生理学)の川島隆太さんに、新聞を活用したトレーニング法を聞いた(佐藤光展) 脳の神経細胞が徐々に破壊されるアルツハイマー病では、脳の中心部の海馬の萎縮などで記憶力の低下が起こる。失った脳細胞の回復は困難だが、大脳の前方にあり、思考やコミュニケーション、行動の抑制などをつかさどる「前頭前野(ぜんとうぜんや)」を活性化させると、「失った脳機能の一部が補われ、日常生活での支障を最小限に抑えられる」と川島さんは指摘する。 また、発病前から前頭前野を活性化させておけば「認知症の予防の効果も期待できる」という。 この前頭前野の活性化に有効なのが「読む・書く・計算する」。川島さんは3年ほど前から、軽度の認知症の高齢者らに音読などを続けてもらい、追跡調査をしているが、症状の改善などが報告され始めている。 川島さんが提案する新聞活用法はこんなやり方だ。[読む]新聞を開いてみましょう。ここでは、記事を黙読するのではなく、音読することが肝心。黙って読むと、視覚情報を脳が処理して終わるが、音読では口が動き、発生した音を 耳でとらえて意味を解釈するという複雑な流れができる。この時、前頭前野が活発に働く。読みやすい記事でも脳は十分に活性化するので、興味のあるコラムなどを選ぶのがポイント。 [書く]これも好きな記事を選び、まずひらがなで紙に書き写す。読みに自信がない漢字は事前に辞書で調べておく。精神を集中して行うが、スピードは無視してもよい。次に、このひらがなの文章を見ながら、漢字交じりの元の記事に書き直す。漢字が思い出せないときは、元の記事を見てもよい。出来上がった文章を音読すると、さらに効果が増す。[計算]新聞の隅々に目を凝らすと、プロ野球の打率や打数など、数けたの数字が並んだコーナーが意外に多いのが分かる。トレーニングはこうした数字の足し算だ。川島さんのお勧めは、天気予報のコーナー。主要都市の予想気温の最高と最低をできるだけ速く足していく。ストップウォッチか秒針付きの時計で、かかった時間を計る。集中して、計算を2~3分するだけで脳の働き全体が向上する。この時、暗算ではなく、紙に書いて筆算すると、「書く」作業も加わってより効果がある。 <朝食の後に毎日10分程度> 新聞を活用した簡単トレーニングだが、やりすぎは心理的なストレスにつながるので禁物。三つの課題は10分程度で終わる分量にとどめ、毎日続けることが大切だ。朝食をとり、脳にブドウ糖が 行き渡った後に行うのがお勧め。 これらの効果は、高齢者だけではなく、若い世代でも十分に得ることができる。 川島さんは「読み・書き・計算の3要素は、子供の脳を健康的に発育させるためにも欠かせない。毎朝10分のトレーニングを、幅広い世代で活用してほしい」と話している。 ☆川島さんの近著「脳を鍛える新聞の読みかた」は、中央公論新社刊、880円(税抜き) (2006年4月16日 読売新聞)◎やはり脳を活性化させるには、やり過ぎはいけないようだ。10分くらいで手軽にできて良い トレーニングだと、思いました。なるべく実践できるようにしたいです。
Jun 13, 2006
コメント(4)
-
塗り絵で脳イキイキ 無理せず30分
塗り絵が人気を集めている。それも、子どもにではなく大人に。絵が苦手な人でも夢中になれ、嫌なことを忘れてストレスを解消できるという。脳全体を活性化させる効果から、認知症患者のリハビリ法としても注目されている。 (佐藤光展) アニメキャラクターなどを使った子供の塗り絵とは異なり、大人の塗り絵は、ゴッホやミレー、葛飾北斎などの名画の下絵に、原画を参考にしながら色を塗る。子供が使う普通の色鉛筆や、水彩画のような表現ができる水彩色鉛筆で、原画のイメージを再現するのが基本だが、自分なりの色づかいで、印象が異なる作品に仕上げてもいい。 「塗り絵は単純な作業に見えますが、実は脳全体を活性化させる大変有効な作業です」 「脳をリフレッシュする大人のぬりえ」(きこ書房)の著者で、杏林大精神神経科教授の古賀良彦さんは、そう語る。 塗り絵の効果を見るため、古賀さんは脳波を測定する実験を行った。被験者に、塗り絵の前後に色を識別する簡単なテストを受けてもらい、脳波の出方を比較した。 塗り絵の前の測定は、脳の活性化を示す部分は見られない。これに対し、塗り絵の後の状態は、脳全体が活性化していることが画像で分かる。(画像があります) 古賀さんによると、塗り絵ではまず、視覚に関係する後頭葉が働き、側頭葉に蓄積された様々な記憶を参考にしながら、下絵を正確に把握していく。 どのような色を使うかなど、塗り方を決める段階では、前頭葉の前頭前野が活性化し、 絵全体のバランスなどを判断するために頭頂葉も働く。実際に色を塗る時には、前頭葉の運動野が活発に働く。このような一連の働きによって、脳全体が活性化する。 運動や簡単な計算など、脳の活性化によいとされる方法は多いが「最も手軽に、スト レスなく取り組める方法として、塗り絵は幅広い年代にお勧め」と古賀さん。ただし、やりすぎは禁物で「1日30分を目安に、無理なく、毎日取り組んでほしい」と呼びかける。 [認知症患者に人気] 大人の塗り絵は、認知症患者にも人気がある。 古賀さんは以前、塗り絵の効果をみるため、認知症の高齢者に子ども向けの塗り絵を提供したが、「プライドを傷つけてしまったようで、取り組んでくれたのは10人中2人くらい」。それが、大人の塗り絵を使ってからは「ほとんどの人が熱心に色を塗ってくれる。隣の人の出来栄えを見て、話を弾ませる人も多い」と話す。 特に、お年寄りには人物画や浮世絵が人気がある。 現在、人物画や浮世絵を多用した認知症患者向けの塗り絵づくりに取り組む古賀さんは「懐かしさや人恋しさから、お年寄りにはそれらの絵にひかれるのではないか。会話のきっかけにもなる塗り絵を、福祉施設などで積極的に取り入れてほしい」と話している。 (2006年6月11日 読売新聞)◎絵が描けなくても、色を塗るのは手軽にできる。脳の活性化がみられるみたいですが、 30分を目安にするのはどうしてでしょうか? 1時間では長いように思いますが、 30分だと物足りないように思いますが、きっと物足りないくらいが一番良いのだと 思いました。 ◎全然記事とは関係有りませんが、今朝5時ごろ大分県震源地の大きな地震が有りました。 宮崎は震度4でした。2回続けて揺れましたが、結構揺れました。被害が最小限に済めば 良いのですが・・・・。
Jun 12, 2006
コメント(8)
-
93歳 心臓手術に成功 (東大病院)
東大病院(東京都文京区、永井良三院長)は9日、心臓の右心室と左心室を隔てる壁に穴が開く「心室中隔穿孔(せんこう)」を発症した東京都内の女性(93)の手術に成功したと発表した。この手術の救命例としては国内最高齢とみられ、心臓手術としても90歳代の成功例は極めて珍しいという。 手術を担当した同病院心臓外科の小野稔講師によると、女性は、先月5日に心筋梗塞(こうそく)で倒れ、都内の病院に運ばれたが、翌6日には、高度な手術が必要な心室中隔穿孔を発症。このため、東大病院に搬送された。手術は約7時間にわたって行われた。術後の経過は順調で、現在、女性は歩けるまで体力も回復しており、11日には退院の予定だ。 今回の手術について、日本心臓血管外科学会理事の黒沢博身・東京女子医大教授は「93歳の患者を心臓手術で救った例は、世界的にも極めて珍しい」と話し、執刀医の小野講師は「元気なお年寄りが増えたことも、高齢での手術が可能になった理由の一つ」と語っている。 (2006年6月10日 読売新聞)◎心臓の手術を、93歳の方がされて、お元気になられたとのこと、 凄いニュースだと思いました。入院後40日も経っていないのに、 自分の足で歩かれて、今日退院されるとの事、本当に良かった です。これからも、お元気で長生きされますように・・・・・。
Jun 11, 2006
コメント(2)
-
『肛門疾患』 正しい知識と最新の治療法を探る
<成人の3人に1人> 肛門疾患の半分を占めえるのが痔で、痔核(いぼ痔)・裂肛(切れ痔)・痔ろう(穴痔)は 肛門の3大疾患と呼ばれています。 このうちいぼ痔は直腸や肛門の静脈がうっ血していぼ状にはれたもので、直腸にできる内痔核と肛門にできる外痔核があります。進行すると内痔核は外に脱出、外痔核は血豆のようになり強い痛みを感じます。 裂肛は肛門の上皮が切れるもので、硬い便をいきんで排出した時に起きますが、下痢で起きることもあります。一方、痔ろうは細菌感染で肛門腺が化膿し、トンネル状のろう管ができるやっかいな疾患です。 肛門科の疾患は約30種類もあり、ほかに肛門周囲の膿皮症肛門、ポリープ、そうよう症、直腸ポリープ、直腸や肛門のがん、クローン病、それに性感染症のコンジローマもあります。 最近は、肛門挙筋の緩みによる高齢者の粘膜脱出や直腸脱による排便障害や便失禁、 若い人では不規則な排便習慣からくる排便障害が増えています。 <非手術療法増える> 痔核の出血・痛み・腫れは座薬・軟こう・内服薬を使った薬物療法と食生活や排便習慣の改善でたいてい治ります。 しかし症状を繰り返す場合は硬化療法(注射療法)赤外線療法、レーザー療法、ゴム輪結紮(けっさつ)法などを行っています。メスを使う手術は大幅に減っています。 このうち昨年始まった注射療法は硬化剤の注射で痔核を硬化収縮させる治療法です。 これに対してゴム輪結紮法は痔核の根部をゴム輪で縛って壊死させる方法で、大きな痔核の治療に有効です。赤外線凝固療法は赤外線で痔核を硬化縮小させます。 一方、痔ろう治療は従来、ろう管を一気に切開開放する手術が行われてきましたが、 ろう管に通したゴムひもや糸で時間をかけて切開するシートン法がメインになりつつあります。 古典的な手法ですが技術が向上、ゴムで徐々に切開され跡は自然に接合し、90%以上の治癒効果があります。 <自己診断は禁物> 痔を放置すればQOL(生活の質)は低下しますし、「市販の薬でなかなか痔が治らないので」といらっしゃる患者さんにポリープやがんが見つかる例も少なくありません。 自己診断は重大疾患を見落とす恐れがあります。特に60歳以上の方はがんの早期発見・治療のためにも専門医の診断を受けられるようにお勧めします。 最近の肛門科は個室化し、診察の際は局部だけを診る穴の開いたシーツやモニター カメラを使用するなど、プライバシーへの配慮も進んでいます。 (2006年5月30日 読売新聞)◎肛門の記事は珍しく思い、載せました。私は、快食・快眠・快便の3拍子に恵まれていて、 痔の苦しみは分かりませんが、女性は便秘になりがちなので、肛門のトラブルを抱えている 人は多いと思います。是非 参考にしていただきたいと思いました。
Jun 10, 2006
コメント(4)
-
子宮がん検診で予防 若い世代上がる発見率
子宮の入り口にできる「子宮頸がん」予防のための取り組みや啓発活動が活発化してきた。若い世代についても、子宮頸がんの発見率が上がってきているためで、検診の無料化や、郵送での検診なども広がっている。 子宮がんには、子宮の奥の部分にできる「子宮体がん」と子宮の入り口部分(頸部)にできる「子宮頸がん」がある。頸がんは、出産や性行為などの刺激により頸部の細胞に傷がつき病変することが原因の一つ。最近の研究では、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが発生率を高めることが分かっている。 検診費用の一部を自治体が負担する集団検診では、頸がんを対象にしていることが多い。頸がん検診には、頸部の粘膜をこすり取って顕微鏡で検査する「細胞診」と、HPVに感染しているかを調べる「HPV検査」がある。集団検診では細胞診が多いが、細胞診とHPV検査を組み合わせることで、発見率が高まるという。 財団法人東京都予防医学協会では、一昨年までに延べ600万人に子宮がん検診を実施してきた。頸がんの場合、がんの前段階とみられる異常な細胞「異形成」の発見率は、30年ほど前は29歳以下でほとんどゼロだったが、ここ数年で1・2%以上になった。早期がんや進行がんの発見率も、伸びてきている。 このため子宮がん検診の受診を勧める取り組みが、各地で広がっている。群馬県健康づくり財団(前橋市)は今年2月から,HPVの郵送検診(4500円)を始めた。また福島県白河市は新年度から子宮がん検診を含む集団検診の自己負担を無料にした。東京都千代田区は昨年度から、20歳代の女性に1年おきに子宮がん検診の受診券を郵送、受診料の一部補助を始めた。金沢市では集団検診で異常があった人に、HPV検査を実施している。 昨年の3月に設立されたNPO法人「子宮頸がんを考える市民の会」(東京都千代田区)は、セミナーやインターネットなどで受診を勧めている。5月上旬に東京・代々木公園で開かれたイベントでも啓発活動を行った。 同会事務局代表の渡部享宏さんは「頸がんは定期的な検診で予防が可能。一人でも多くの女性が関心を持ち、検診を受けてもらいたい」と話している。 (2006年5月16日 読売新聞) <ヒトパピローマウイルス(HPV)検査 (女性) 郵送検査 さくら医科研究所 > http://www.sakura-ika.co.jp/hpv2.html 注)癌が100%わかる検査はありません。がんの検査としては、かなりの精度のものでも、 今の医療でがんを100%見つけ出すことが不可能なことはご承知のことと思います。郵送 検査は、便利な点は多くあります。たとえば、健康保険ではまだ行われていない様な新しい 検査を受けることができたり、病院で何時間も待たされることがなかったり、婦人科の診察 台の上に乗らなくても良かったり。そんないい点もありますが。欠点もあるわけです。郵送 であるがための欠点と、検査自体に欠点があったりもします。(どこの検査機関でも同様 です。) ◎どんな病気でも、早期発見が大切な事は良く分かっているのですが、子宮検査はなかなか 受診し辛い検査です。今は、とても便利な郵送検査で手軽に調べる事ができる様になった ので、病院へ行く前に、自分で調べられて良いなぁと思いました。郵送検査の注意事項は、 上記の注)を、お読み下さい。詳しくは、ホームページで調べて納得した上で、検査して 下さい。
Jun 9, 2006
コメント(2)
-
世界遺産 自然と共生 山に祈る 屋久島(その2)
標高約800メートルの白谷霊水峡は、樹齢1000年以上のヤクスギがそびえ、シダ、コケ類の緑に覆われていた。晴天で、リュックを背負った観光客が次々と姿を見せる。 人口約1万4000人の島には、年間約20万人の観光客が押し寄せるようになった。今春の大型連休でも、島のシンボル「縄文杉」につながる荒川登山口(標高約600メートル)の 駐車場で自動車の入場規制が行われたほどだ。 「切り株の上にこけが生え、そこからまた新しい木が育っていくんです」。屋久島環境文化研修センター(屋久町)の職員が観光客に説明していた。 「森は生きている。壊すのは簡単だが、つくるのは容易ではない。後世まで命をつないでいかなければ」。福岡から参加した主婦江頭喜代子さん(56)も感じ入っていた。 島内にいる約150人の民間ガイドも環境学習に力を注ぐ。美しい景観を楽しむ場所としてだけではなく、「環境教育の場」として島は確かに機能している。 だが木々の間には、美しい緑とは対照的な光景も広がっていた。空き缶、プラスチック、ビニール類・・・・。かつての島のゴミ最終処分場だ。世界遺産登録後の1997年、ダイオキシン排出規制でそれまで使っていた焼却場で紙類以外のゴミが燃やせなくなった。島民の15倍近い観光客が残していくゴミ。屋久、上屋久両町の施設に持ち込まれる量は年間2800トンにのぼる。小型の処理施設しかなく、多くが最終処分場に蓄積されていった。 今春ようやく新施設が稼働し始めたが、1日処理能力は14トンにすぎない。新しいゴミから処理し、最終処分場の「山」はなかなか小さくならない。 緑の山がぽっかりと海に浮かんで「洋上アルプス」の名が付く屋久島。国際的に重要な湿地を保護する「ラムサール条約」に2005年に登録された上屋久町の永田浜には、日本の海浜に上陸するアカウミガメの3割強が来るとも言われている。 しかし、浜でも変調が起きていた。永田浜には、いなか浜、前浜、四ツ瀬浜の三つの砂浜がある。NPO法人「屋久島うみがめ館」の調査では、以前はいなか浜への上陸が多かったが、最近、大勢の観察者が押し寄せる影響で少し離れた前浜や四ツ瀬浜に上がるカメが増えている。 このまま人が見に来れば、浜にはウミガメが近づかなくなるのではないか。浜にいる自分の存在さえ、気にかかる。 「多くの人に感動して欲しい。でも、人は近づかないのが本来の姿」。毎夜、浜で観察会を開く「永田ウミガメ連絡協議会」の大牟田幸久さん(55)は複雑な胸の内を明かす。協議会は今シーズンから、産卵見学の予約制を取り入れ、設けていなかった定員も1日80人までと定めた。 世界自然遺産登録後、多くの人たちが押し寄せた。島民はその変化に戸惑っている。観光客が地元経済を潤しながら、一方で森林というその観光資源に確実に負荷を与えている。二律背反の問題を解くはっきりした答えは、まだ見えてこない。 だが、世界に共有されたこの島で答えが見つかれば、人類は大きな知恵を得られるのではないだろうか。人と自然とが共生できるかどうか、屋久島はその試金石となる。そう思った。 (2006年6月3日 読売新聞) 記者・馬場 豊 25歳 Eメール:baba0194@yomiuri.com ◎世界遺産にも選ばれた、美しく素晴らしい島・屋久島ですが、自然と共生したいと思うのなら、 やっぱりそっとしておくのが、1番良いのではないのでしょうか? 私は、そう思いました。 環境教育の場として考えられていますが、車の規制をしたり産卵の見学の定員まで考えなくて はいけないのだったら、みんなで何もしないのが1番自然に優しいことだと思いました。 大切な森を失ってからでは遅すぎると思いますので、早急な対策を期待したいです。そして、 島の人たちの生活向上を考えるのならば、少し酷な事を言いますが、島を離れる事を考えざる 終えないと、思いました。
Jun 8, 2006
コメント(8)
-
世界遺産 自然と共生 山に祈る 屋久島(その1)
◎私が行ってみたい世界遺産の一つである、屋久島(鹿児島県)の森の記事です。 本文(明日 その2)で、ゴミの問題が上げられていますが、ゴミは当然持ち帰り、その他 人間が森へ踏み込み環境を破壊してしまうのならば、そっと見守りたいと思いました。 <9割が森林 九州一の高峰も> 屋久島は、日本本土最南端の鹿児島県・佐多岬から約60キロ南に浮かぶ。島の9割が森林で、うち8割以上が国有林。九州一の高峰である宮之浦岳(1936メートル)や永田岳(1886メートル)など標高1500メートル以上の山々がそびえる。 年間を通じて降雨量が多く、「一か月に35日雨が降る」と言われるほど。こうした自然条件から、推定樹齢7200年の縄文杉をはじめ、1000年以上のヤクスギ、多くの固有種や絶滅の恐れのある植物が生育している。 昨年5月、島のシンボルである縄文杉の樹皮がはぎ取られる事件が発生した。2004年5月には、熊本市のガイドが導く沢登りツアー客が遭難し、3人が死亡する事故が起きている。今年の大型連休時も登山客が島の縦走に出かけ一時行方不明になったり、登山道で足を滑らせ死亡したりした。 島のガイドのレベルアップを図るため、登録制度が昨年10月スタートした。「屋久島地区エコツーリズム推進協議会」のホームページで、名前や経験年数などを公開している。http://www.yakushima-eco.com/ <屋久島 古代の心学ぶ嶽詣(たけまい)り> 「古(いにしえ)の心を学ぶ嶽詣り」。のぼりにはこう記され、毎年春と秋に行う嶽詣りのことを知らせていた。 島内の多くの集落には、それぞれ"自分たちの山"があり、そこにそれぞれ神を祭っている。嶽詣りは、地区住民がその山に登り、山頂のほこらに祭られた神に手を合わせて山の霊気を里に持ち帰る、神聖な伝統行事だ。 しかし過疎が進み、この行事も昭和30年代ごろから次第に姿を消していった。永田地区では5年前、約40年ぶりに復活させた。 「もう一度伝統に戻り、昔の人がどうやって自然と共存してきたのかを学ぶ。そうすることで、何かが見えてくるのでは」。柴さん(上屋久町永田の民宿・『屋久の子の家』の経営者)はこう話す。この島で失われつつあるものを取り戻し、後世につなげなければ、との思いが伝わる。 柴さんの民宿の夜は、夕飯が一段落して宿泊客がみんなで芋焼酎のグラスを傾け始めた。 中国の芸術家、福岡の外科医一家、沖縄の夫婦、大阪から来た女性客・・・・・。様々な人が集まり、屋久島の山や海の素晴らしさを言い合う。「あんな森を見たのは初めて」 うっすらと顔を赤らめた柴さんも、沖縄の夫婦に歌をせがんだり、自ら島の歌を披露したりした。しかし、柴さんが口にしたひと言が胸を突いた。 「世界遺産になってから、屋久島に多くの人が訪れるようになった。自然環境は損なわれているけれど、世界の人たちと島を共有する事は大切」そして言葉を継いだ。「だけど共有された島の価値を守る方法を、私たちは知らない。だから嶽詣りをするんだ」 太平洋の片隅にポツンと浮かんだ島に、世界から人がやって来る。そのことへの喜びと戸惑いが、山の神に手を合わせて自然と共生してきた祖先の心をたぐり寄せることにつながった。 *長い記事なので、続きは明日に載せます。
Jun 7, 2006
コメント(6)
-
院内コンサート活動を続ける医師 上杉 春雄(39)
<病気を忘れさせるひとときを> 神経内科医として勤務する札幌山の上病院(札幌市)で、20回を超える院内コンサートを開いてきた。学生時代には国際コンクールで入賞した腕前。「本物にこだわりながら、患者と作り上げてきた音楽の温かさを感じてほしい」と、集大成のアルバム「トロイメライ」も出した。 ピアノづけの少年時代を送ったが、「仕事にすると苦痛になる」と、北大医学部に進学。新進ピアニストとして注目されたものの、卒業後、医師の仕事に専念しようと演奏活動を封印した。 余裕の出てきた4年目のある日、親しくなったパーキンソン病患者の会で演奏した。「病気になって10年、今の30分が初めて病気を忘れられた時間でした」と涙する患者の姿に、「音楽を聴くって、こういうことか」と気付かされた。完治しない病気は多いが、それを忘れられる時間は人生の質を高めてくれるだろう。「病気を自覚せざるを得ない病院という苦痛の空間に、そんなひとときを提供できないか」 実現したのは、札幌山の上病院に腰を落ち着かせた2001年。以来、演奏の合間に作曲家の人生を紹介したり、民謡を編曲するなどして、クラシックを知らない人も楽しめるコンサートを心がけた。院外での音楽活動も再開した。 癒しの音楽が流行だが、「音楽は、脳を活性化するもの。その結果、癒やされるなら、それでいい」神経内科医の顔をのぞかせた。
Jun 6, 2006
コメント(8)
-
ECO宣伝スペシャル番組。 坂本龍一さん。
◎昨日のテレビ番組で、東儀秀樹・青木さやか司会の 「ECO宣伝SP」と言う番組が、1時間半有りました。 とっても、勉強になり良かったです。その中でも、 音楽家の坂本龍一さんのお話が良かったので、 今日のブログに書き記します。 <坂本龍一さんのお話>☆ECOについての事を考えて、電気量を減らすために、 真っ暗な部屋で、苦労して仕事をしていた。もう、1年半前に 家では、風力発電に切り替えた。発電所から電気を引いた。 スエーデンと同じで、N.Y.でも電力会社との契約で電気の種類が 選べる。☆暑くなってきたなぁ。昆虫が自分の幼年期に比べて、減ってきたことに、 怖さを感じた。ここで環境にやさしく、健康的で無理をしないライフスタイル ロハス(LOHAS)について考える。 http://www.lohasclub.jp/ エゴイスティック生活=安全で美味しいお水を飲みたいし、美味しい物を 食べたいし、汚染されていない空気を吸いたいし、自分の子供達にも そうであって欲しい。 基本は自分のこうしたい・ああしたい。エゴから始まっているけれど、 それを追求していくと、どうしてもECOにならざるおえない。☆坂本龍一さんのお気に入りのもので、"マイお箸"を持っておられた。 お洒落で、コンパクトにおさめられるようになっていて、とても素敵に 見えました。写真で見てもらえれば良いのですが、無くてすみません。 色々想像してみて下さいね。みんなで持ち歩くようになれば、割り箸が 必要で無くなります。割り箸を作る木材で、他に必要な物が作れます。☆将来、来年の事もわからない。自分の子供が大人になったら、凄い 温暖化になって、暑くて台風がバンバン来る世の中に成ったら、 可哀想なので、今 大人の世代の人たちが、少しでもストップさせようと 考え努力するのが、当然だと思う。全然難しい事ではない。 エゴを追求して、エコへ 出来ることから少しづつ との事でした。<地球と宮崎の環境を考えるポータルサイト> http://eco.pref.miyazaki.jp/*大変な間違いをしました。青字のエコがコエになっていました。
Jun 5, 2006
コメント(8)
-
大豆イソフラボン摂取に上限値
◎5月18日に、大豆イソフラボンの事を載せましたが、より詳しい記事が 載っていましたので、ブログに書き留めておきます。大豆イソフラボンを、 多く摂りすぎると、女性は子宮内膜になりやすいとの報告があるそうです。 *女性コーナー~子宮内膜症・子宮筋腫~ http://www.takeda.co.jp/pharm/jap/seikatu/sns/index.html (記事には、子宮内膜しか書かれていませんが、子宮内膜には色々あります) ☆大豆イソフラボン・・・大豆の胚芽に多く含まれる天然化合物。女性ホルモンに似た作用があり、骨粗しょう症や更年期障害の予防効果が期待される。納豆やみそなどの発酵食品では、「大豆イソフラボンアグリコン」という物質に変わり吸収される。アグリコン換算で、納豆1パックには約30~40ミリ・グラムが含まれるが、含有量は商品によっても差が大きい。 健康食品は、医薬品とは違い、臨床試験のようにメーカーが厳密に安全性を証明する必要がない。食品は添加物などを除けば、長年の食習慣で安全性が立証されている成分が大半だ。しかし健康食品は、「体にいい」とされる成分を増量しているものが多く、含有量の多さを競う傾向もある。 大豆イソフラボンは、健康食品の中で人気成分のひとつ。大豆に豊富に含まれるため「いくら食べても安全」と信じられてきた。しかし、内閣府の食品安全委員会は、5月11日、大豆イソフラボンを含むトクホの安全性について、「1日摂取量目安は70~75ミリ・グラムまで」「食品以外の上限摂取量は30ミリ・グラム」「妊婦・子どもへの摂取は推奨しない」とする見解をまとめた。 大豆イソフラボンによる人間の健康被害が証明された例は1例もない。しかし海外では、大豆イソフラボンを5年間、毎日150ミリ・グラム服用した女性の子宮内膜が増えたとする報告がある。大量摂取が思わぬ悪影響を与える可能性は、否定できなくなった。 [健康食品の区分]○健康食品・・・法律上の定義はなく、一般に健康に関する効果や機能を表示して 販売されている食品。狭義では、保険機能食品を除いた健康食品 ○特定保健用食品・・・生活習慣病の予防など、健康に影響を与える成分を含み、 (トクホ) 効果が期待できる食品。国の審査が必要 ○栄養機能食品・・・国の基準に適合し、ミネラルやビタミンなど栄養成分の 機能を表示している食品 *トクホと栄養機能食品を総称して保険機能食品という (2006年6月1日 読売新聞抜粋)
Jun 4, 2006
コメント(6)
-
飲み物ゴクゴク ちょっぴり募金 チャリティー自販機
◎昨日に続いて、チャリティー自販機の記事を見つけたので、紹介します。 この記事の方が、昨日の記事より古いものでした。企業の皆様のお力と、 私たち一人ひとりの協力で、生きとし生けるものすべてに、もっともっと 世界が住みやすく、優しい世の中になれば良いなぁっと、思いました。 ペットボトルや缶入り飲料を買うと、代金の一部が環境保全や母子保護活動に寄付される「チャリティー自販機」が各地に広がっている。のどの渇きを癒やしながら、 関心がある社会問題にも貢献できると、自販機の設置者、消費者にも好評のようだ。 東京新宿区の保健会館新館前にある自動販売機には、「ホワイトリボン」のステッカーが掲げられている。缶やペットボトルの飲料を買うと、売り上げの一部が、開発途上国の妊産婦の健康と生命を守る「ホワイトリボン運動」に寄付される。地下鉄・市ヶ谷駅の入り口に面していることもあり、乗降客が次々と足を止めて買い求めていく。 飲料メーカーの伊藤園(東京)が、同会館に入居する家族計画国際協力財団(ジョイ セフ)と連携し、昨年からホワイトリボン自販機の設置を始め、これまで計8台が各地に設置された。商品管理や売上金の回収などは伊藤園が行い、設置者は1本につき2~5 円を運動への寄付金として、ジョイセフに寄託する。昨年度は計22万円余りが寄託され、アフガニスタン・ナンガハル州の母子保健プロジェクトに送られたという。 東京都武蔵野市の水口病院は昨年、病棟など院内2か所にこの自販機を設置した。「婦人科病院なので、母子保健の充実に貢献できる仕組み共感した」と同病院。 ポッカコーポレーション(名古屋市)は昨年2月から、紙製容器「カートカン」飲料の売り上げの一部を、森林育成に役立てる「緑の募金」に寄付している。カートカンの自販機は官公庁や病院など、全国に約3400台設置されている。 一方、地域密着型のチャリティー自販機に取り組んでいるのは、コカ・コーラボトリング各社。北海道コカ・コーラボトリング(札幌市)は、北海道斜里町内の自販機約180台の売り上げの一部を、知床の自然環境保護に寄付することにし、今年4月に同町と協定を結んだ。このほか兵庫県豊岡市にはコウノトリの野生復帰支援に寄付できる自販機(近畿コカ・コーラボトリング)、岡山県笠岡市には、カブトガニの保全に寄付できる自販機(コカ・コーラウエストジャパン)などがある。 企業の社会貢献や寄付に詳しい社団法人日本フィラソロピー協会(東京)理事長の高橋陽子さんは「企業が売り上げの一部を寄付する手法は以前からあるが、自販機を通じた寄付は、消費者にとってより身近で参加しやすい。協力したいと思う寄付を消費者が選べるよう、こういったチャリティー自販機が各地に増えるといい」と話している。
Jun 3, 2006
コメント(8)
-
南九州コカ・コーラーさん、ありがとう!
◎昨日の新聞の記事で、とっても嬉しいニュースが載っていま したので、紹介します。災害時、コカ・コーラさんの活躍が、 これからもっともっと大規模となり、他の企業の方達の協力も 得られ、災害時に備え安心を届けて戴けますように、心から お願いしたいです。 [災害時は無料自販機] 小林市と南九州コカ・コーラボトリング(熊本市)は31日、災害時に住民に飲み物を無料で提供する協定を結んだ。7月中にも市内の公共施設10か所に専用自販機を設置し、体制を整える。同様の協定は、県内で高鍋町、西都市に続き3例目。 専用自販機は、災害が起きた時にモードを切り替えると、ボタンを押すだけでジュースなどの商品が出てくる。通常の自販機より水とお茶を多く備蓄しており、本格的な救援物資が届くまでの、つなぎ役を果たす。また10台中6台がメッセージボードを備え、普段はニュースや地域のイベント案内を表示。災害時には、避難勧告などの情報を流す。 モードの切り替えは、市が同社の許可を得てインターネットや手動で行う。協定書で「震度5の地震相当の大災害」と基準が定められているが、臨機応変に対応する予定。災害対策本部の設置を目安にする。
Jun 2, 2006
コメント(9)
-
6月は環境月間 (福岡市)
「環境にやさしい都市」の実現をめざして 6月5日は「世界環境デー」。1972年6月5日に、ストックホルムで開かれた「第一回国連人間環境会議」で「人間環境宣言」が採択され、この日を「地球に住む一人一人が環境について考える記念日に」と定められた。 これを受けてわが国は、同5日から11日を「環境週間」、6月を「環境月間」と定めた。「環境にやさしい都市」の実現をめざす福岡市は平成8年に「環境基本条例」を制定、独自に毎年6月を「環境月間」と定めて環境問題について市民に正しく認識してもらうための運動と取り組んでいる。今年もNPO、ボランティア団体、 企業、市民、行政が連携して環境問題の解決に向けてさまざまなイベントが展開される。 一人一人が考えて変わる「地球温暖化」 環境問題は、平成17年2月に京都議定書が発効し、地球温暖化防止への取り組みが1段と求められるようになった。オゾン層の破壊や野生生物の絶滅の危機など地球規模で進んでいる環境破壊は深刻化するばかりだ。地球規模の問題であるが、「住みよい環境」を望むならば、私たち市民一人ひとりが考えていかねばならない身近な問題でもある。「環境の大切さはわかるが、どう取り組めばよいのか」という声もよく聞かれるが、身の回りを見渡せば、私たちができる事がたくさんある。 たとえば、節電。照明やテレビをこまめに消すこと。最近、増えているデジタル家電やパソコンの「待機電力」も実はバカにならない。歯を磨く時には蛇口を閉めるだけでも 節水につながる。こうした節電や節水は、ごみを減らす工夫など、「ちょっとした心がけ」で私たちの生活を見直すことによって、地球温暖化防止のための二酸化炭素削減や、限りある資源を無駄遣いしない循環型社会の実現に貢献できるのではないだろうか。 福岡市では、こうした「だれにでもできる環境への貢献」を市民に認識してもらうため、PR活動に力を入れるとともに、より具体的な行動へつなげていくため、市民参加型の催しを準備している。 (2006年5月30日 読売新聞)◎今日から、環境月間だそうです。素晴らしい活動です。☆1年中 常に心がけたいです。 「ちょっとした心がけ」に他にも色々と考えてみました。 買物へ行く時にレジ袋持参・食事へ行く時は、マイお箸持参と食べ残し物は戴いて帰る・ おトイレのお水を少なめにする(勿論、衛生上問題ないように。お風呂で残ったお湯を 洗濯機とトイレに使えば良いと思います。お風呂の排水溝が、洗濯機とおトイレに流れる 仕組みがあれば良いのにと思います。洗濯機には実際に外付けのポンプを使って残り 湯を利用しています)食材についてくるトレーのリサイクル(リサイクル出来ない物は、 企業は売ってはいけない事にすれば良い)・牛乳パックのリサイクル・アイドリングス トップ・お部屋の温度調節(クール・ビズ 冷温度は28℃に! )など、まだまだ気を 付けられる事一杯有ると思います。ごみはみんな土にかえる物だったら、もっともっと 地球に優しくなれます。☆なんて言っても、素人の考えです。理想を書きました。
Jun 1, 2006
コメント(4)
-
ジャワ島地震 死者数5427人 救援募金
インドネシア・ジャワ島中央部地震の被災地では、救援活動を担うはずの地元自体が機能不全に陥り、被災者に食料などが十分に行き渡らない状態が続いている。一方、インドネシア政府の災害対策本部は30日、地震の死者数が5427人に達したと発表した。 <ジョクジャカルタ(インドネシア)=石間俊充>「ご飯も水もいらない。安心がほしい」。インドネシア・ジャワ島地震の震源に近いジョクジャカルタ特別州の避難民キャンプを29日訪れたが、子どもたちに、笑顔や歓声はない。家も学校も倒壊し、けがをしたり、風邪をひいたりしながら余震におびえている。心に負った傷は深い。 [ジャワ地震救援募金]インドネシア・ジャワ島中部で発生した地震の被災者援助のため、読売新聞社と読売光と愛の事業団は、30日から募金を受け付けます。募金は、郵便振替(00190・8・72319、加入者名・読売光と愛の事業団=電話03・3216・4921)で、通信欄に「ジャワ地震救援」と明記し、お送りください。寄付者名は朝刊地域版に掲載します。掲載を望まれない方は、「匿名希望」と通信欄に明記してください。 (2006年5月30・31日 読売新聞)☆近所の郵便局では、(00110・2・5606、加入者名・日本赤十字社)で募金を募っていました。◎地震の怖さは阪神大震災の時に、京都に住んでいたので少しは分かりますが、 何時また大きな地震がきて、何処へ逃げれば良いのか? 逃げ場の無いのことが、 本当に怖いことでした。これからも沢山の方達が、援助を必要としています。 少しでも、皆様の温かいお気持ちを募金(食料や物資)として送って戴けます ように、宜しくお願い致します。
May 31, 2006
コメント(2)
-
コンタクトレンズと入院時の食費と内視鏡手術
◎ニコチンパッチの保険適用の記事と一緒に、コンタクトレンズと入院時の食費と 内視鏡手術の事も載っていましたので、記します。4月から医療費が改定されま したが、利用する側になって、これからも大切なみんなの医療費を使えるように して欲しいです。 <コンタクトレンズ> コンタクトレンズにかかわる診療では、個別の検査料を出来高方式で加えるのではなく、必要な検査を一括にした「コンタクトレンズ検査料」が新設された。初めてつける場合は387点(コンタクトレンズ患者が70%以上を占める診療所では193点)となる。医師の指示に基づき、再診した際の検査料は112点(同56点)だ。 ただし、医師の指示による受診とは別に、特に異常がないのにもかかわらず検査を受ける場合は、この4月から保険がきかないことになった。たとえばコンタクトを紛失して受診した場合は保険外になる。 <入院時の食費> 治療のために、1日3食とれないケースは多い。そこで入院1日当たり780円の負担(一般所得者の場合)だったのが、1食当たり260円へと、1食ごとの計算に変わった。 手術後などで、仮に1日の食事を4回以上にこまめに分けて食べたとしても、最大3食の計算となる。 <内視鏡手術> 内視鏡手術は、今回の改定で、これまで保険外だった前立腺がんの腹腔鏡手術が保険適用(4万5300点)になった。開腹手術と同じ扱いだった胃がん手術や整形外科関連の手術などでも、内視鏡手術の点数が新設され、高く評価されたものが多い。 *1点10円 (2006年5月28日 読売新聞)
May 30, 2006
コメント(4)
-
ニコチンパッチ 医療保険対象に(その2)
禁煙治療が、病気の治療として初めて保険で認められた。「ニコチン依存症管理料」と言う名称で、1回にの受診につき230点~180点(1点10円)が、初・再診料や処方せん料に加わる。3カ月間に5回通院するのが原則だ。 ただし、保険がきくには、条件がある。 まず、医療機関に対して、「敷地内が全面禁煙であること」といった条件がついた。禁煙推進に取り組む姿勢を問うものだが、建物内は禁煙でも屋外に喫煙所があることは多い。禁煙外来の看板を掲げているがん専門病院でも、この条件を満たさないために保険がきかない病院もある。 また、治療を受ける本人は、1日の喫煙本数×年数が200以上(1日20本なら10年以上と言った計算)などの、ニコチン依存が強いことを示す条件がある。このため喫煙歴の浅い未成年者らは事実上、保険の対象外となる。 禁煙治療には、皮膚にはってニコチンを徐々に吸収させ禁断症状を和らげる、禁煙補助薬(ニコチンパッチ)が処方されることが多い。ニコチンパッチは従来は保険外だったが、6月から、こういった条件がそろって保険で治療を受ける場合に限り、保険が適用されことになった。 ニコチンパッチは、1日1枚使い、大きさによって1枚約400円~355円。患者によって必要な枚数は異なる。 禁煙治療の費用は、これまでの自費診療では診察料などを含めて通常2~3万円前後かかっていたが、保険の3割負担になると1万円前後で済む計算になる。☆禁煙治療が保険で受けられる医療機関 基準を満たす医療機関が、都道府県の社会保険事務局に届け出るが、 現状ではまだ、まとまったものはない。受診前に個別に問い合わせよう。 民間団体の禁煙マラソンのホームページ (http://kinen-marathon.jp/info/hospital-01/)では、独自調査による 保険のきく医療機関名を掲載している。 (2006年5月28日 読売新聞)◎ニコチン依存症で、来月から医療保険が適用される事を知って喜んでいましたが、 あまりにも保険を適用させるには、条件が厳しすぎると思いました。喫煙歴が 短い人は、適用条件でないとの事、理解に苦しみます。未成年者に限らず、 健康に成ろうと、治療を受けに来られるんだったら、是非保険を適用して 欲しいと思いました。
May 29, 2006
コメント(3)
全108件 (108件中 1-50件目)
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- Black friday限定!もち吉 超お買得…
- (2025-11-19 22:16:48)
-
-
-

- 気になったニュース
- (藻緯羅の庵)韓国の特殊詐欺、1兆…
- (2025-11-19 20:06:06)
-