テーマ: 好きなクラシック(2399)
カテゴリ: カテゴリ未分類
「名曲100選」 モーツアルト作曲 交響曲第40番 ト短調
この曲を初めて聴いたのが確か高校1年生(1960年か61年)の時で、級友からLP盤を借りて聴いたのが出会いでした。 レオポルド・ルードヴィッヒ指揮のバンベルグ交響楽団の演奏でした。 今でも鮮明にその時のことを覚えています。第1楽章のあの有名な旋律が流れた途端に、金縛りにあったようにステレオ装置の前で聴き入っていました。 ビクターのトレードマークの白い犬さながらにじ~と聴いていました。
こんな早いテンポで、こんなに悲しみを表現できるものなのかと不思議でならなかったのが、まず印象として残りました。それまではチャイコフスキーの悲愴交響曲やサラサーテの「ツゴィネルワイゼン」、リストのハンガリー狂詩曲、グリーグのオーゼの死などを聴いていましたから、ストレートに悲しみを表現する音楽・曲に慣れていましたから、この40番の悲しみは何なんだろうと思ったことを覚えています。
後になって25番シンフォニーのト短調や、ホ短調のヴァイオリンソナタ、へ短調のピアノ五重奏曲、ト短調の弦楽五重奏曲、それにイ短調のピアノソナタを聴いて、モーツアルトの悲しみはいつもアレグロのような早いテンポで表現しているとわかりましたが、この40番のト短調交響曲は私にとっては衝撃的な旋律でした。しかも39番、40番、41番の交響曲を2週間の速さで書き上げたというからなおさらでした。 39番の明るい歌、華麗な41番に挟まれたト短調の悲しい、哀しみの表現は何を表そうとしたのかと思いながら、学校から帰るとすぐにこの曲を聴く毎日でした。
第1楽章の第1主題でヴィオラが刻む和声の上に、きわめてしなやかな悲しみの旋律が歌われているのですが、モーツアルト独特の「ト短調」(25番のシンフォニーや弦楽五重奏曲第4番など)での悲しみの表現ですが、私は、今もってこの短調のアレグロでの書法による彼の心象を探りあてずに今日に至っています。
評論家小林秀雄の言葉「疾走する哀しみ」は言い得て妙なるものがあります。
今から50年ほど前に聴いていたクラシック音楽はとても新鮮で、ラジオから流れる放送でよく聴いていました。何しろLP盤を買うお金がないから、ラジオ放送で聴くしかなく、それもこちらの選択ではなくて、NHKの番組編成で決められるのですから、まだほとんどクラシック音楽について知らなかった頃ですから、初めての曲ばかりでした。それでも楽しかった。 耳を澄まして聴き入ったものです。
現在はあの時のような純粋に音楽に浸る気持ちが失われているように思えてなりません。もう一度あの時のような気持ちで聴かねばと思っています。
愛聴盤
(1) ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団
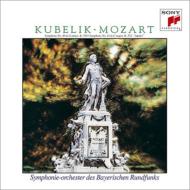
この人の指揮から生まれる音楽は実に「しなやかさ」があります。ベートーベンでも、モーツアルトでも、ドヴォルザークでも柔軟な「しなやかさ」がその作品の、音楽の特性を端的に表現していると感じます。 「端麗」という言葉でも当てはまるでしょうか。
響きが清澄になっており、それでいて空間に広がるのは相当な厚さの音楽。 決して刺激的に音楽を動かさずに、それでいて退屈などこれぽっちも感じさせない、悠々としたテンポを維持している、私にとっては理想的なモーツアルトの演奏です。
録音されてから既に30年が経ちました。「もうそんなに?」という感があるほどについ最近録音されたような感じがいつまでも続く、クーベリックの最高の遺産ではないでしょうか。
(2) ニコラス・アーノンクール指揮 ヨーロッパ室内管弦楽団
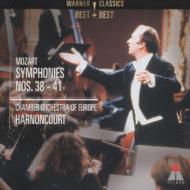
(テルデック原盤 ワーナー・クラシック WPCS10819/2 1991年録音)
クーベリックとは対称的な表現。 ピリオド楽器の奏法を採り入れて過激とも感じる表現方法でモーツアルトの音楽世界を描いている。ここにはゆったりと音楽に身を任せて聴いていられない、非常に高い音楽の劇性があり、アコーギク、アーティキュレーションなどで表現されています。
(3) ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団
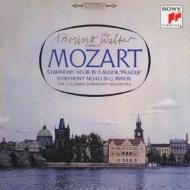
(ソニー・クラシック SRCR2303 1959年録音)
現在はソニーとなっているが、この録音当時はアメリカのCBSだった。LP初出以来何度再発売されたろうか? 今も再発売の連続。そして変わらぬ人気。 ワルターの指揮には「歌心」が溢れていると表現すればいいのか。 ベートーベンでもブラームスでもモーツアルトでも常に「歌」に溢れた表現となっている。アーノンクールを聴いた後にこのディスクを聴くと、喉の渇きを癒してくれる水のような感じを受けます。 これもワルター最高の我々への遺産だと思います。 いつまでも再発売を期待したい演奏盤です。
(4) ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団

(ソニークラシック SICC1073 1970年東京公演ライブ録音)
この演奏を聴いてまさに完璧としか表現する言葉を知らないくらいに、絶妙・精妙・精密なるオーケストラの演奏に驚かされる。 特にワルター指揮のコロンビア交響楽団を聴いた後では、ワルターには悪いが寄せ集めのオーケストラと厳しい管弦楽奏法の訓練を受けた団体の違いをまざまざと見せつけられる。
セルは、帰国後に急逝したので非常に貴重な日本公演の記録、セルの演奏記録となってしまった演奏。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
コメント新着
ifJU8X Really enjoyed this blog article.Much thank@ ifJU8X Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Great.
ifJU8X Really enjoyed this blog article…
ONY72s I cannot thank you enough for the post. Wil@ ONY72s I cannot thank you enough for the post. Will read on...
ONY72s I cannot thank you enough for th…
フリーページ
© Rakuten Group, Inc.











