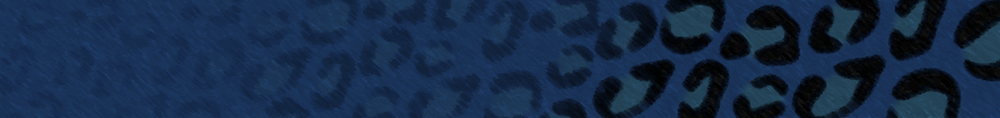2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年01月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
助動詞「けり」 は ディープ
古文文法に 再入門中なんだけど 受験生用の参考書での たとえば 助動詞 「けり」の説明。1、間接経験や伝聞の過去、2、または詠嘆 気が利いた説明では 3、気づき もはいっているようだ。簡単なようで どれで訳せばいいのか。こういう多義語は英単語の教授法で最近定着した「コアイメージ」をもちいる方法を取り入れたらいいみたいだ。多義語の複数の語義を別々に暗記するのではなくて、複数ある語義に共通するコアイメージを学習することで単語を把握する方法。「ケリ」にかんしては 「古典文法質問箱、大野晋」や「日本人の表現力と個性 熊倉千之」が納得の説明だったが、 「意識内になかったことだが 実はずっと前から存在していた事実が 今、意識の領域内にやって来た。」というのが「けり」のいろんな意義に共通するコアイメージらしいのだ。意識内にやってきた とは つまりは気づいたということだしどこからやってきたかというと過去からの場合が多くあるだろうどういう風にやってきたのかというと 想起や 伝聞で知った場合もあるだろう意識されてどうだというと 驚く場合も悲しい場合も あるだろうという風に コアイメージを掴んでおくと 派生的な訳がいろいろできることになる。たとえば 使用例として 源氏物語にある桐壺更衣の歌。ともに死出の道をと誓ったこともある帝への歌。 かぎりとて別るる道の悲しきに いかまほしきは命なりけり いままで受身であった桐壺更衣が ここで最初で最後の存在感をあらわす ぐっとくる歌。この最後の「けり」の訳を 単なる詠嘆ととらえて「~命であることよ」とか気の抜けた現代語訳をつけている解説書やら辞書がかなりあるようだ。誰か権威ある先生がまちがって訳して それがあちこちでひきうつされているらしい。せめて{命であったことよ} ぐらいがが納得の訳だろう。 「いかまほしきは命なりけり」という 桐壺更衣の欲求は 今まで意識内になかった事だが 実はずっと前から存在していた事であり 今、意識の領域内にやって来た。ということになるからたいへんなことだ。じぶんの欲求にきづいていなかったとは。ここは 単に詠嘆というよりは、心の深層にあった 本当は生きたい という欲求に いまごろ気づいた という驚愕と後悔を伴なった自己認識の「けり」であるようだ。 桐壺更衣の自己像はいままで帝との関係で得たものにすぎなかったろう。死に瀕することによって いままで想像的な仮面の自己像の下に隠されていたほんとうに主体的なるものが けり という助動詞ともに噴出する。命なりけり、と。紫式部は精神分析家のようだといわれるそうだけど、もともと「けり」自体の語義も なんと精神分析的なのだろう。
2009.01.12
コメント(2)
-
古文で作文する本
英語には英作文ってあるのになんで古文には古文作文ってないのだろう・・・と学生時代に疑問を持ちましたが、そんなもんがあったら受験勉強がたいへんだろー、なくてよかったなー、という話になって それっきり忘れてた話題。 「古文表現法講義 出雲路修」は 出版社/著者からの内容紹介によると「古文で物語を書いてみましょう.この講義では『伊勢物語』などでおなじみの平安時代の物語をつくることに挑戦します.古語辞典と簡単な文法書があれば,そんなにむずかしいことではありません.添削の実例に沿いながら,平安時代の日本語表現を実習すれば,古典との距離はぐっと縮まります.やればできます.めざせ,紫式部!」とのこと なんか簡単そうにおっしゃる。「現代語から古語を引く辞典」というのもでてる。 そんなことが できるようになったからってなーんの役にもたたなさそう ではありますが。製作者側に立ってみて みえてくる世界もあるかも。音楽の世界だと こんな和音進行で よくぞ こんなメロディーがのってるもんだなあ とか 感心することがあるし。
2009.01.06
コメント(1)
-
おめでとうございます
NHK教育 1月2日(金) の夜に「知るを楽しむ この人この世界 瀬戸内寂聴 源氏物語の男君たち」の再再放送を一挙にまとめてやってくれるそうす。年明け早々 また源氏かよー。アニメもあるしなー。いいかげんに 源氏物語から解放してくれー。という気分も。源氏物語に取り憑かれた研究者や作家、読者の人々の気持ちがだんだん わかるようになってきた。それってもう 楽しいんだか苦しいんだかな業病みたいなもの。 それこそ物語の女性たちのように出家でもしないと解放されない いや寂聴さんのように出家しても解放されないのでしょー。おそろしいことです。
2009.01.01
コメント(4)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-
-
-

- きょう買ったCDやLPなど
- KAN 全39曲をCD3枚に収録した『KAN …
- (2025-11-11 22:53:08)
-
-
-
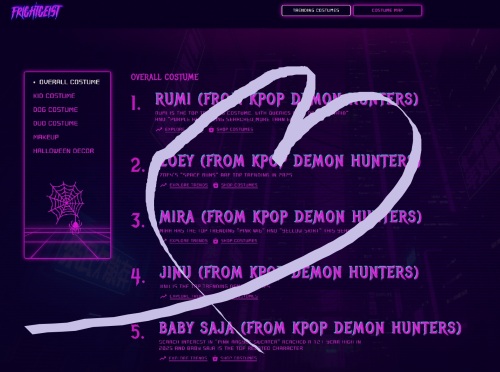
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-