2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年01月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
柳沢大臣の辞任要求問題/草加はまだ人権擁護法にご執心/プロムスをご存知ですか?
<政治家は聖人君子である必要がある?> ============== 柳沢伯夫厚生労働相が「女性は子供を産む機械」と発言した問題で、与党内から31日、辞任論が出るなど、波紋が続いた。安倍晋三首相は参院本会議の代表質問で「多くの女性の心を痛めたことに対し、私も深くおわびする」と述べ、任命権者として陳謝したものの、柳沢氏の辞任は否定した。ただ野党側は国会審議での対決姿勢を強めており、序盤国会の大きな焦点となっている。 首相は答弁の中で「極めて不適切な発言で、厳重に注意した。柳沢氏は全身全霊を傾けて職務を全うしてもらいたい」と述べ、柳沢氏も「改めて深くおわびする」と陳謝した。いずれも民主党の谷博之氏の質問に答えた。 ただ7月に参院選を控えた参院自民党側では「辞めるなら早く辞めた方がいい」(幹部)との辞任論が広がりつつある。別の参院幹部も「後は本人の判断だ」と自発的辞任を促した。矢野哲朗参院国対委員長は同日、二階俊博国対委員長と会談し、こうした早期の事態収拾を求める参院側の意向を伝えた。 これに先立ち、自民党の中川秀直、公明党の北側一雄両幹事長ら与党幹部は都内のホテルで会談し、「職務を全うしてもらう」(二階氏)として辞任の必要はないとの認識で一致。同日午後から始まる衆院予算委員会の審議を予定通り進めることを確認した。 北側氏は、その後の記者会見で「党内で(柳沢氏の)発言に厳しい意見が多いのは当然だが、それと閣僚辞任とは別の問題だ」と指摘。別の公明党幹部も「辞めて問題が決着するのかどうか。首相の任命責任に波及するのは避けたい」と語るなど、対応をめぐって与党内で溝が生じている。 一方、民主、社民、共産、国民新の野党4党は31日、国対委員長会談を開き、柳沢氏の辞任を求め、共闘していくことを確認。同日午後の衆院予算委で行われる平成18年度補正予算案の提案理由説明にも応じない方針だが、共産党は審議拒否に同調しない考えを伝えた。(2007/01/31 13:02) Sankei WEBより================ 各所で話題になっておりますが,ここで自分も一言。 その前にまず大前提として,この発言に問題があることは自分も共通認識として有していることを確認しておきます。 子供を産むという行為は,女性にのみできることであり,人類という種の存続のために重要かつ神聖な行為です。専ら単純行為のみをなすことをその任務とする機械の作業にこれを比することは不適切であり,かつ女性を機械に比することも同時に不適切なことです。当然,かかる発言をした大臣は非難をされねばなりません。謝罪することも当然のことです。 しかし,これと,この発言を原因として大臣という地位を去らねばならないのか,という問題とは別次元の問題であり,直ちにこれを地位の去就というイシューにつなげることは,妥当ではありません。仮にその二つの別次元の問題が何らかの連関関係にある,ということが証明されるのであれば別ですが。 もちろん,不穏当な発言を原因として大臣がその職を辞任する(または辞任させられる。以下「辞任する」という場合は,辞任させられることも含意するものとする)ということは,政治的判断としてはあり得ます。 しかし,大臣が辞任するか否かは,政治的判断の当不当の問題にはなり得ても,野党が審議に応じない(言い換えれば,国会議員が本来の職務を怠るという趣旨の主張)を正当化し得るものではありません。それは政治的な判断の当否(辞任するか否か)を,これとは全く別次元の法的な職務の放棄(審議を拒否するか否か)と関連付けるものであり,論点ずらしもいいところ。一種の詐欺的手法とさえ言い得ると思います。このようなめちゃくちゃな詭弁を弄する野党こそ,強く責められるべきだと思います。 まったく日本の野党は幼稚な野党です。それを特段攻め立てないマスゴミも幼稚ですが。 我々有権者はこのときにあたり,一体何が責められるべきかをきちんと認識しなければならないと思います。 <恐ろしいカルト>=============== 参院は31日午前の本会議で各党代表質問を続行した。公明党の草川昭三参院会長は、自民党内に反対論の根強い人権擁護法案の早期成立を求めたが、安倍晋三首相は「慎重の上にも慎重な検討を行うことが肝要だ」と答え、法案提出に改めて難色を示した。首相は就任前から法案に反対しており、法案を検討する自民党調査会は昨年10月以降、事実上廃止の状態となっている。 (以下略)(2007/01/31 11:37)Sankei WEBより=============== クソカルトが人権弾圧法の提出を急ぐようになどとほざいているようです。 この法案の恐ろしさについては既に各所で指摘されています。 首相が消極的でよかったですが,これが谷垣氏や福田氏だったらどうなっていたかと思うと背筋がぞっとします。 <これを見てアサヒの記者とかはどう思うのかな・・・> プロムスという行事があります。毎年一回英国で開かれる音楽祭みたいなものです。BBCが主催しています。 その最終夜は,日本にいても視聴することができます。NHKが配信していますので。 どんな行事か,ちょっと覗いてみて下さい。 2006年のプロムス。「Land of Hope and Glory」 これも2006年のプロムス。「Jerusalem」 これは2004年のプロムス。「God Save The Queen」 ちなみに,1曲目の歌詞はこんな感じ。 でもって,2曲目のはこんな感じで,3曲目は英国の国歌ですから特段説明の必要もないでしょうが,1番と3番を歌っています。 どうですか? いずれも愛国的な歌なんです。しかもみんなこんなに国旗を打ち振るって,しかも参会者が全員誇らしげに歌っています。もちろん国歌は立って歌っています。 日本でいえば,さながら戦時中の愛国歌を歌う会をNHKが主催しているという感じでしょうかね。とてもじゃないが,(局内の)反対が多くてできないでしょう。ましてアサヒがだまっちゃいないでしょう。うれしそうに 「ほら!軍国主義が復活した!」と書きたて,または報道するに違いありません。 これが海外じゃ普通なんですけどね。 サモアのこんな動画もありましたよ。もういっちょ。 アサヒ基準で行ったらこの子たちは「軍国主義者」なんでしょうね(笑)。
2007年01月31日
コメント(12)
-
ご訪問の皆様へ
お世話になっております,管理人のti2669こと,小市民です。本日2つ目の記事は,管理に関するお知らせです。 実はつい先日までTBを全面解禁しておりましたところ,今日新記事を挙げたとたんに多量のエロTB,コマースTBが入り,驚愕しました。 かかる悪意あるアクセスは明らかにyournet.ne.jpよりのものですが,楽天には特定ドメインを拒否するという機能はないようです(自分が知らないだけかもしれませんので,もしそうでしたら,どなたか「あるよ!」とお知らせください。)。 そこで,全面解禁からまだ間があいておりませんが,再び禁止を復活,というより今度はさらに規制を強化しました。以後,TBの受付を完全許可制にいたします。TBをご希望の方は,ご面倒をおかけしますが,コメント欄,掲示板,あるいはメールにて,管理人までお知らせください。 なお,TBの思想的な選別(除:アダルト,商業目的)は一切行いませんので,異論・反論TBをしたいという方も勿論歓迎いたします。 よろしくお願いします。
2007年01月28日
コメント(4)
-
やっぱり無視されていた豪首相のコメント2
1月23日に,マスコミがあまり取り上げなかったオーストラリアのハワード首相のコメントを取り上げました。 今回はその第二段目。2005年4月20日,来日したハワード首相が小泉前首相と共同記者会見をひらいたときに,記者から投げかけられた反日誘導質問に対して行ったコメントを取り上げたいと思います。 まずは英文を掲げ,後に訳文を掲げます。今回は,たまたま首相官邸にその訳文が残っていましたので,その訳文を掲げます。なお,英語原文はこちらでご覧になれます。 ==============JOURNALIST: A question directed to Prime Minister Howard. Now you visited China and Japan this time and the relationship between China and Japan at present are rather difficult and tough and the Chinese side have some views that Japan does not reflect on its past. As a country which fought against Japan during World War II, what are your views on these points made by the Chinese side? PRIME MINISTER HOWARD: Well Im not going to give this answer by reference to what China has said. Let me answer you directly on what I think about these matters. All countries must understand their history and their past and be candid about them. And that applies to all of us. Let me say in relation to Australia and Japan, yes we were enemies 60 years ago and particularly amongst older Australians there remains lingering resentment and bitterness and feeling - that is understandable. But one of the remarkable things about the relationship between Australia and Japan is that in 1957 we signed a landmark Commerce Agreement which was initiated by a government in Australia that included many men, I think at that time they were virtually all men, who had fought in the Australian Army in World War II, including in the Pacific theatre, including some who had been prisoners of war. And the point is that by agreeing to sign that landmark agreement, which actually laid the foundation of the modern strength of the relationship between Australia and Japan, those men were looking to the future. They were not reflecting on the past, they didnt forget the past, nobody can forget the past, but they were looking to the future. And that is my view and that is the way that Australia has always approached it. How other countries approach those things are a matter for them to articulate, Im not going to express a view about what China has done, let me simply say that we value very deeply our relationship with Japan, we dont pretend that there havent been tragedies in the past and I know that is the view of the Prime Minister. But we look to the future and if that generation of Australians who fought in the war could be part of a government that looked to the future then theres a message in that for current generations of Australians. (例の如く,カンマは無効なタグなのだそうなので,こちらで削除しました)訳【質問】ハワード首相にお伺いいたします。今回は日本と中国への訪問というふうに伺っております。現在、日本と中国の関係はなかなか厳しいものがありまして、中国側には日本は過去を反省しない、反省が足りないという意見も出ています。かつて日本と第二次大戦で戦った国として、この中国の指摘をどのようにお考えかお聞かせください。 【ハワード首相】 私の方からは、中国側が何を言ったかということを言及するつもりはありません。直接、私の考え方を申し上げたいと思います。 それぞれの国が、やはり過去の歴史というものは理解しなければいけないと思いますし、それに対応しなければいけない。これはどこの国でもそうであります。日豪の関係を見ますと、60年ほど前にお互いに敵対国であったわけです。特に高齢の豪州人の中には、まだそういった苦い気持ちというものが残っているかもしれませんし、それは理解できると思います。ただ、日豪関係のすばらしさというものはどういうところにあるかと考えますと、1957年に両国は節目となるような通商協定を締結いたしまして、これはそもそも私ども豪州政府がイニシアティブを取ったものでありまして、豪州軍で第二次大戦時に太平洋戦域などでも戦った、また捕虜になったような人々、そういう人がこの通商協定を手がけたということです。これは節目となる協定であり、これが1つの土台となって現在の日豪間の関係が力強いものになっております。 そういった人々は当時、将来に目を向けていたので、過去に目を向けていたわけではない。勿論、過去を忘れたわけではないわけですけれども、将来に目は向いていたということなんです。これが私の視点なんです。すなわち、オーストラリアはそういうアプローチを取っております。ほかの国がどうアプローチするかは、またそれぞれの国が説明すべき点でありまして、私の方から中国がどう自分で思っているのか申し上げるつもりはありません。 私どもは、勿論、日本との関係を非常に重視しております。だからと言って過去に悲劇がなかったということを言うつもりはありませんが、しかし、総理もおっしゃったように、我々は将来に目を向けているんだと。戦争で実際に戦ってきた人々も、当時は将来に目を向けて、そしてそれが今の世代にメッセージとして伝わっているわけです。 ============== わが国には,どこぞの国のスポークスマンかと思われるような政治屋がたくさんおりますが,この記者もハワード首相をそんなスポークスマンとして利用しようとしたんでしょうね。 首相はそれを察知されたようで,記者に対しバシッと 「私の方からは、中国側が何を言ったかということを言及するつもりはありません」 「私の方から中国がどう自分で思っているのか申し上げるつもりはありません」 と釘をさしています。 どこの記者だか知りませんが,悔しかったでしょうねぇ(嘲笑)。 何度も繰り返しますが,周知のように,オーストラリアは太平洋でわが国と直接干戈を交えた相手です。 翻ってわが国に対して「歴史認識」だ「謝罪と賠償だ」といってくる国のうち,大きな国の方は直接わが国と戦ったわけではありませんし,まして半島の2つの国はともに戦った仲間であったわけです。 昨年は,インドやヴェトナムの首相の演説を無視していました。一昨年は,ハワード首相のコメントを無視しました。 一体マスゴミは今年は何を無視してくれるのでしょうか。
2007年01月28日
コメント(8)
-
ご協力よろしくお願いします
来月22日は「竹島の日」,そう,あの半島に不法占拠されている「竹島の日」です。 当ブログは,わが国固有の領土である竹島について考え,その一日も早い復帰を願う日である「竹島の日」を広めんとする,フィオリーナの以心伝心さんの運動に賛同しております。 訪問いただいている方で,ブログをお持ちの同志の皆様のご参加を伏してお願い申上げる次第です。 参加希望の方はこちらから。 よろしくお願いします。 なお,「どうやれば??」という声があるので,ここでも簡単にやり方を説明しておきましょう。 ステップ1:竹島の画像,イラストを用意する。 ステップ2:自分のブログ,ホームページにその画像,イラストを配置する。うちは,こんな感じにしてます。 ステップ3:こちらのコメント欄に,参加希望のコメントを残す。その際,自分のブログやホームページのURLをのせるのをお忘れなく。 これで完了! 管理人
2007年01月25日
コメント(10)
-

世間話
なんだか,「新着記事なし」というさびしい状況に追い込まれてしまった(多分,今朝新しい記事をアップした直後に削除したからだと思うが)ので,生存証明のため,ちょっとした世間話をば。 実は昨日,友人と九段下の某インド料理屋に行ったんです。 目的は,その料理屋のティータイムだったんですが,なんといつのまにか終了していたようで,結局それを知らずに入店してしまった我々は,「3時のおやつ」として,通常のランチメニューを食べる羽目になってしまいました。 まぁ,おいしいし,腹もちょっとばかし減っていたので好都合でしたが・・・ と,これは本題ではなく,話はここから。 実は我々が食事をしていた後ろの席でお隣の半島のカップルが食事をしていました(言葉を聞きましたので,間違いありません)。自分は気が付かなかったのですが,友人は気付いていて,清算して,店を出た後,「ちょっとこの後どこへ行くか観察してみよう」ということになりました。 ・・・といっても別に変な意味ではなく,その店が非常に靖国神社に近い場所にあるので,「靖国に行くかどうか」というのをぜひとも知りたかったのです。 カップルが出てきました。後をついていきます。 すると・・・靖国神社の境内へ入っていきました。 「おぃおぃ,こいつらここが靖国だって分かってるのか???」 彼らは境内図を見た後,お土産屋の脇をとおって,灯篭へ。 靖国へ行ったことのある方ならご存知でしょうが,この灯篭では,日露戦争や,第一次大戦などで活躍した我が軍の英雄たちをレリーフを通して知ることができるようになっています。 彼らはそれを実に丹念に見ていました。我々はそれを水舎のところで,観察していました。 さぁ,これから参拝するのかな?と思っていたら・・・ どうやらここはまずい神社らしいと気付いたらしく,さっさと立ち去ってしまいました(w それにしても九段下なんてこの時期は見るところといったら,靖国くらいしかないはず。なんでこんなところに半島の人が来てたんだか・・・不思議ですね。 結局,我々だけできちんと参拝を済ませてきたのでした。 危く,ノの犬を連れて行くことによって,この規定に反するところでした(w
2007年01月24日
コメント(16)
-
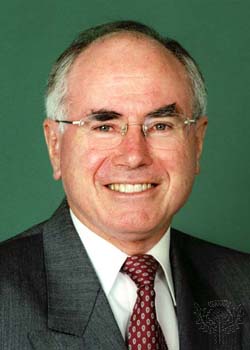
今更ながらだけど,やっぱり無視されていた豪首相のコメント
このあいだ,過去記事アーカイブを作成するのに,過去の自分のエントリーを読み返していたんですが,その時,2005年6月18日の記事が目に付きました。 そこでは,オーストラリアのハワード首相に関するこんな記事が掲載されていました。===========読売オンライン 2005年4月14日(木) 22時27分 豪首相、歴史問題で日本を擁護 【シドニー=樋口郁子】オーストラリアのハワード首相は14日、18日からの日中歴訪を前に両国記者団と会見した。 小泉首相の靖国神社参拝について、首相は「(第2次大戦終結は)60年前の出来事であり、日本はいまやアジアの偉大な民主国家の一つだ」と述べ、日本を"擁護"した。ただ、日中関係の緊張については、「両国とも豪州の重要なパートナーだが、それぞれの外交に口出しするつもりはない」とかわした。 =========== 最近英語にあんまり抵抗がなくなったので,この発言がどんなものだったのか知りたくて,オーストラリアの首相の公式ページを探し当て,そこでこの14日に行われた記者会見におけるコメントを捜したんですが見つかりませんでした。 でも,その代わりにこれに関連するコメントを二つ発見しました。今回はこれを2回にわたってご紹介しましょう(二つ目は今度のアップのときに)。 まず一つ目。 これは上記記事にあるハワード首相の歴訪の途中,4月19日に北京のSt. REGISホテルでの記者会見でのコメントです。記者の質問と一緒にご覧ください。なお,元記事はこちら。===========JOURNALIST: As someone who grew up in the shadow of World War II yourself, does Japans treatment of its war time record raise any questions in your mind and is this something that came up in your talks with the Chinese leaders or something you might raise with Mr Koizumi? PRIME MINISTER: I think its necessary for all countries to be frank about past events. I can understand the feeling of Australians who suffered at the hands of enemies when they were captivity during World War II and thats a view thats put to me from time to time by men and women in Australia of that generation. I have also been deeply impressed, particularly in the time Ive been Prime Minister by the readiness of many of that generation, including some who were prisoners of war of the Japanese, to look to the future and to assert that the important thing is to build a productive relationship between Australia and Japan. I think one of the most impressive acts of leadership in the immediate post-war years in Australia was that of the Menzies Government in negotiating the free trade agreement, or commercial agreement, between Australia and Japan at a time when that Government was almost totally dominated, with a few exceptions, by men who had served in World War II, many of them had been in prisoner of war camps run by the Japanese. (なお,上記文中の「カンマ」は無効のタグとされたので削除。楽天も変なリニューアルするんだったらこういうところ改善しろよ) 訳記者 ご自身第二次大戦中に育っておられますが,日本の戦時中の行いに関する態度について,何か疑問に思われるでしょうか?また,そのような日本の態度について,中国の指導者との会談において何か言及がありましたでしょうか,あるいは首相ご自身,小泉総理との会談でそのことについて何か言及されるおつもりでしょうか? 首相 すべての国家は,過去の出来事を直視すべきだと思います。第二次大戦において捕虜となり,敵から被害を被ったオーストラリア人の感情を,私は理解することができますし,そのような視点は,戦争経験世代のオーストラリア人によって,時々私に提起されています。しかし私は,日本軍の戦争捕虜となった方々も含めた戦争経験世代の人々が,進んで未来をみつめようとしていること,そして,豪日間に建設的な関係を構築することが重要であると強く主張していることに,大変深い感銘を覚えるのです。首相をやっていると,このことは特に強く感じられます。戦後直後のオーストラリアにおいて,もっとも感銘を受ける出来事として,メンジーズ政権下において,豪日間の自由貿易協定あるいは経済協定が交渉されていたことを挙げることができると思います。当時政府は,ほんの僅かの例外を除いてほとんどすべての者が,第二次大戦に従軍していた者より構成されており,そのうちの多くは戦争捕虜として日本軍の捕虜収容所に収容されていたのです。================ 誰なんでしょうかね,こんあアホな質問をするのは。どうせアサヒか,毎日か,共同通信かに決まってますが(w さて,このアホ質問に対するハワード首相の答えはこんな感じでした。首相は,戦争経験のある世代の態度を借用して豪日関係はこうあるべき,と主張されたんでしょう。 曰く 「すすんで未来を見つめようとしていること,そして,豪日間に建設的な関係を構築することが重要である」 世間で言われるところの未来志向という奴です。これは特定アジアの方々にはもつことのできない感情なんでしょうけど。 でも,まさに戦った相手そのものであるオーストラリアができるんですからねぇ,共産党も「日本と戦った」なんていっているんだったら,同じ戦った国のオーストラリアを見習ったら?なんていいたくもなります。 まして戦っていない(というより「ともに戦った」)半島の人々についてはいわずもがな。 アホ記者のお相手ご苦労様です,首相。 さて,このような未来志向を述べている方がもう一方おられます。若干,異論をさしはさみたくなる方もおられるでしょうが,どうか最後まで読んでみてください。 「われわれ東アジア諸国は,ヨーロッパ,特にフランス,ドイツに学ばねばなりません。自分の過ちを隠したり,いやしくもなかったことのように無視したりせず認めねばなりません。その過ちは実際に起きてしまったことであり真に悔いねばなりません。そして今日,明日の一層の幸せで豊かな生活をともに目指さねばなりません。 このことは戦勝国だけでなく,侵略と残虐行為を蒙った人たちにも当てはまるのです。賠償はしなければなりませんが,未来永劫に続くものであってはなりません。どれほど大きな金銭補償をもってしても失われたものは償えません。損害賠償請求と謝罪要求も現実的に,ある程度で抑えるべきです。」 (マハティール・ビン・モハマド 『東アジア共同体と日本の役割』 三田評論2004年10月号 p29~30 この記事は,2004年6月2日に行われた氏に対する慶応大学名誉博士の称号授与式の記念講演が基になっている)マハティール氏は,前マレーシア首相です。息子さんと娘さんをわが国に留学させるなど,親日家であられます。(wikiには,最近はそうではないなんてかいてあったけど,wikipediaはしばしば左巻きなので,客観的データー以外は意外と信用性が低かったりする) それにしてもまるで誰かさんを念頭に置いたかのような発言ですね(w 如何に,例の半島や大陸が異常かが分かるご発言でした。
2007年01月23日
コメント(4)
-
バックアッププランの準備
いつもご訪問いただきありがとうございます。管理人の小市民です。 楽天がブログの管理画面を変更して分かりにくくなったのですが(管理画面左端に表示される禿の四角頭のキャラクターも気に入らない),これを機に,仮に今後「改善」と称して楽天がより分かりにくい管理画面にするようならば,他所へブログを移転しようかと思っています。 ただ,新しい管理画面については猛烈なクレームの数があるようで,ひょっとすると以前の使いやすい管理画面に戻る可能性もあります。なのであくまでこの移転案はBプラン,バックアッププランです。要するに,管理画面が改善されれば,移転はなしです。 そこでご相談なのですが,どこか使いやすいブログってありますでしょうか?朝鮮・SB批判がタブーといわれているyahooと,同じく朝鮮様に弱いlivedoorは鼻から除外していますので,それ以外であれば教えてください。 管理人
2007年01月20日
コメント(3)
-
使いにくい
この記事はスタッフブログとやらに対するTBのために特別に作成されたものです。 新管理画面についての不満点。 1:新着コメントやTBがいちいち確認しなければ分からない(以前のは一目瞭然でした) 2:お気に入りに登録してある相手方のブログの更新の有無が容易に確認できない(これも以前は一目瞭然だった) 3:リンクスって何?そもそも存在もしらんかったんだが,今回はそれのユーザーを念頭においた「改善」のように見える。っぅーかそもそもリンクスって使ってる奴いるのか? 今日1日使ってみただけで,ざっとこれだけ不満点が出てきた。これからも続発することだろう。 それ以前に楽天には改善してもらいたい点がある。 エントリー入力の際にエラーがあった場合の表示の仕方が不親切すぎ。 どこに何のエラーがあるんだかさっぱりわからない。おかげで簡単な記事をあげるのにも時間がかかってしまう。エラーの修正に時間を取られすぎて! 現に,昨日のエントリーはあれだけの簡単な記事なのに2時間近くかかった。いつもなら他記事を扱って,全記事を推敲しても1時間くらいで済むのに,修正に時間がかかったせいで書く気を失った。 もう少し利用者のほうを向いた運営をしてもらいたい。正直,今日本気で他所への移転を考えた。
2007年01月19日
コメント(6)
-
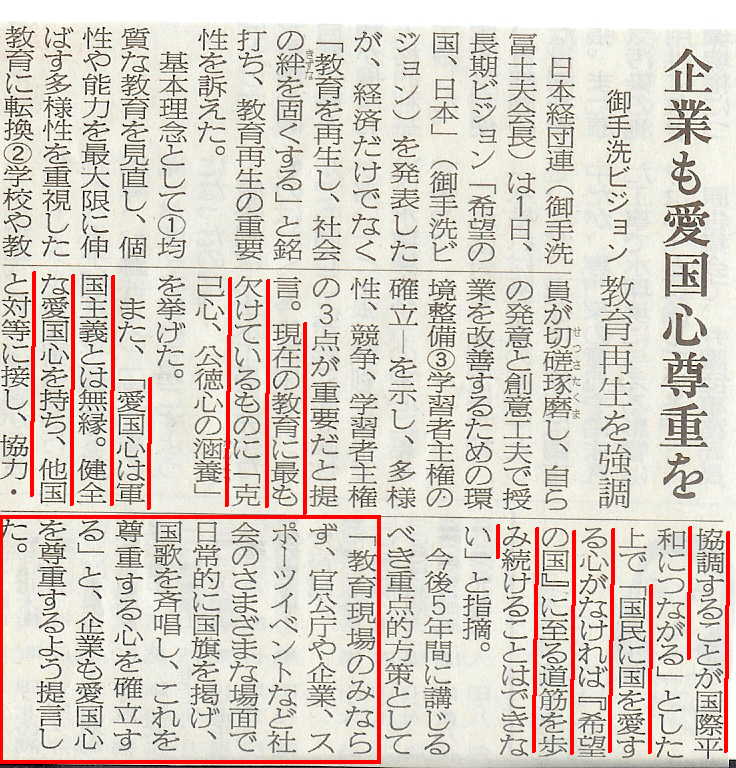
御手洗氏,「企業も愛国心を尊重すべき」/タイ首相,ASEAN地域における日本の役割に期待
<ちょっと古いですが> これは15日月曜に産経新聞28面に掲載された記事です。 現・経団連会長の御手洗氏は,靖国神社の問題にも干与しないことを明言するなど,なかなかな発言をされておりましたが,今回のこの「御手洗ヴィジョン」はなかなか魅力的ですね。 「愛国心は軍国主義とは無縁。健全な愛国心を持ち,他国と対等に接し,協力・強調することが国際平和につながる」 まさにおっしゃるとおり。 それにしても,同じ財界人でも経済同●会の誰かさんとは大違いですね(ちょくちょく見に行く「酒たまねぎや ura ホームページ」さんより)。 英国の学者アリソン氏は愛国心について次のように語っています。 「人生における心の満足を提供するとは思われないものは,「名声」,「成功」, 「社会主義」,「富」といった,抽象的状態の追及である。なんであろうとこれらは手段である。それらは目的としては恐ろしく捉えどころがないのである。虹の一番端と同じように,そこについてみると何ら実体がないのである。 対照的に,深く,永続的で,普遍であるという意味において,より「実態的」な若干の満足がある。忠誠心,帰属意識,すなわち,丘の上に立って生家がすぐ近くだと知り,胸がいっぱいになる感覚である。忠誠心は地域,町,国,あるいは自分自身で考え出した領域に対しても生じ得る。それは国家のように大きなものに対し,また家族のように小さなものに対しても生じ得る。それは大規模な実体に適用されると非常に抽象的となる傾向があるが,小さなものに関連するともろくなる。おそらく愛国心は忠誠心の最も重要な形態である。ジョンソン博士は,それは「悪党の最後の避難所」であると言ったが,彼は哲学的な知ったかぶりの馬鹿者であり,自分の国土に対する愛(それが普通の意味の愛国心である)と,他のあらゆる道徳的判断に優先する国家への支持とを区別していない。単純な意味での愛国心は何ら悪いことはない。それは一つの感情であり,道徳的立場ではない。」(リンカーン・アリソン著 藤原孝・杉本稔訳 『新保守主義の政治理論 ライト・プリンシプルズ』(三嶺書房) p249) <ASEANで行われた日タイ首脳会談要旨> タイ大使館ホームページより関係部分のみ抜粋============= 第10回ASEAN・日本首脳会談 スラユット首相 ・ 日本とASEANのパートナシップはASEAN地域の発展を充実させる。特に、交通網整備における日本の役割は大きなもので、第二メコン国際橋建設時の日本の協力に感謝を述べたい。 ・ タイは日本の東アジア経済研究所設立構想を歓迎する。 安倍晋三首相 ・安倍新政権の平和構築構想にそって、メコン川流域経済、東アジア経済研修所設立構想などASEAN経済の発展の他、鳥インフルエンザ、災害対策、人的資源開発などについて発言した。 (http://www.thaiembassy.jp/rte1/content/view/258/179/)============= 「特定アジア」以外の国の場合は恒例の,ODA給与に対する感謝の発言がなされました。 第二メコン国際橋とは,wikipedeiaの説明によれば以下のとおり。 「日本のODA融資資金(国際協力銀行)の円借款ローン(約80億円)によって建設の橋であり、ラオスとタイとを結ぶメコン川に架橋される第二番目の橋である。(ヴィエンチャン=ノーンカイ間の友好橋についで二番目に建設)2003年12月より工事が開始され、3年の期間を経て2006年12月に完成した。2006年12月20日に開通式が実施された。車両の通行は翌年2007年1月10日より正式に供用が開始された。ただし現在は朝6時から夜10時までしかラオスとタイの国境施設がオープンされていない。橋の全長は、川横断部が1,600m、取り付け部がラオス側とタイ側併せて450mで合計2,050mである。上下2車線の車道と歩道が整備されている。同橋の完成によって、ベトナム、ラオス、タイ、ミヤンマーの国々が東西に結ばれることになり、メコン川の南北の海運軸とともに、人的、物的交流を通じて、同地域の発展に寄与することが期待されている。」 そういえば,昨年タイのニュースを伝えるホームページで開通式の記事を見た覚えがありました。日本ではRed Flag様が扱っただけのようです(Googleで調べた結果)。この式典にはちゃんと日本の大臣も呼ばれたんですよね(タイの王女とヴェトナムの首相が参加してたとか書いてあった記憶はあります)。韓国や中国でこんなことしてもらった覚えはないわけですが(w またまた「特定アジア」が如何に異常かが分かっちゃいましたね。
2007年01月19日
コメント(6)
-

続報,毎日新聞社のサンフランシスコ講和条約11条の解釈
<やはり最初はまっとうな解釈をしていた> 昨日,毎日新聞社が講和条約の解説本のうち,いわゆる「東京裁判史観」の根拠となっているサンフランシスコ講和条約11条について「裁判」ではなく,「判決」と訳していたことを紹介しました。 今度は,同条約の解説部分を同じくオロモルフさんがアップしてくださったので,ご紹介します。(なお,元ページはこちら)。 注目すべきところを,赤線でしるしておきました。 まず,最初の赤線部分をご覧ください。 「戦争裁判は占領軍の軍事行動として行われた」とあります。 ここにいう「戦争裁判」は,当然いわゆる「東京裁判」です。 現在,靖国神社に祀られているいわゆる「A級戦犯」の分祀を推進しようとしている人々によって「A級戦犯は,戦死者ではないのだから,本来靖国神社に祀られるべき人々ではない」との主張が行われていますが,それに対して,これに反対する立場から「東京裁判は,軍事行動だったのだから,その結果刑死した人々は戦死者に準ずる(公務死)」とする反論がなされています。それと全く同様の趣旨の文章です。 奇しくもかつての毎日新聞がその主張の援護をしてくれました。「ありがとうございます」,というべきかも知れません。 さらに,11条の趣旨の説明においても,同条は,日本政府による占領終了後の戦犯の釈放を禁ずる旨の規定であることがはっきりと書かれています。 ちなみに,昨日も述べましたように,「11条によって東京裁判を受け入れた」と主張する人々は,このような解釈はとらないはずですので,この点からもかつての毎日新聞は今現在,「東京裁判史観」の見直しに奮闘されておられる人々を援護してくれた形になっています。
2007年01月17日
コメント(2)
-
毎日新聞も昔は「判決」/で,またも無視される写真家の方/
<「東京裁判史観」のキーポイントである11条> サンフランシスコ講和条約の11条という条文があります。このブログでも何度か紹介したところですが,こういう条文です。========== 第十一条 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。========== この条文の「裁判を受諾」という一文の「裁判」をそのまま裁判と考え,わが国は東京裁判の判決理由(日本はいわゆる侵略戦争をしたという内容の判決理由)をも受け入れた,と考えるのが従来の考え方。これはもっぱら「東京裁判史観」として揶揄されることもあります。 これに対して,この「裁判」は「判決」の誤訳または意図的な「偽訳」とでもいうべきものだとして,したがって,わが国は判決理由まで受け入れたわけではない,とするのが保守の立場を採る人々の主張。 本日はこの解釈を扱うわけではありません。当該条文の解釈については,近時ちょっと勉強を深めたので,そう遠くない将来に公開してみたいと思っています。 では,本日は何をするかというと,毎日新聞の変節っぷりを皆様にお示ししたいわけです。 毎日新聞といえば今はミニアサヒとでもいうべきリベラル紙の代表。現在では当然,「裁判」との立場をとり,わが国は東京裁判を受け入れた,とする立場にたっていると思われますが,かつては違うという証拠を,オンラインでお付き合いさせていただいている,オロモルフさんが発見されました。 こちらがその画像です。2枚目の画像の2行目にしっかり「判決」と書いてあります。 聞くところによると昔は結構まともだったころもあったそうですね。読売は昔に帰らなくてもいいから,毎日は昔に帰って欲しいものです。 <まだ「韓流」やってるんですか> janjanより==============(略) 2001年1月26日、東京・新大久保駅。酔って線路に落ちた男性を助けようとして、帰らぬ人となった韓国人留学生・李秀賢(イ・スヒョン)さん。彼の人生をもとにして作られた映画が、「あなたを忘れない」である。音楽とスポーツを愛する普通の青年。日本語学校に通いながら、アルバイトや富士登山を楽しみ、青春を謳歌していた彼の人生は、あまりにも早く幕を閉じてしまった。 「なぜ韓国の青年が、命を賭けて日本人を助けようとしたのか?」。恐らく日本中の人が抱いた疑問への答えは、この映画の中にあるだろう。映画化を許可したスヒョンさんの両親の言葉の中にも──。 「普通の人間なら当たり前のことです」 彼の生き方を、私たちは決して忘れない。 (略) (吉本紀子) (http://www.janjan.jp/culture/0701/0701087784/1.php)=============== 自己の命を捨てて他人を救う行為は尊いことです。自己犠牲とは究極の奉仕ですから。それは誰しも否定しないことでしょう。自分も勿論否定しません。 しかし,この映画の題材となった事件当時のマスコミの態度はいただけませんでした。過剰な持ち上げ方をするならまだ我慢もできますが,我慢ならないことは亡くなった韓国人留学生と共に泥酔者を救って同じくなくなった写真家,関根史郎さんはほとんどスルーという事実。 自己犠牲という行為の美しさを褒め称えるのであるならば,両者平等に扱うのが当然。それを一方の賛美に終始して,他方をまるで存在しなかったかのように扱うことは,不完全というより虚飾といっても過言ではない。ましてそれが報道機関という公的機関によって行われたのだから,その偏向っぷりはもはや「報道機関が報道機関たることを捨てた」(これ即ち報道機関の自殺)としか評価の仕様がない。 それがまだ当時の報道だけなら我慢もできたろうが,映画版にしてもその扱い方をするようです。 詳しくは公式サイトを参照して欲しいのですが,見たところキャストに関根さん役はないほか,ストーリー中にも関根さんに関する言及はなく,ただ,「2001年1月26日 新大久保駅でお亡くなりになりました、故・李秀賢さん、関根史郎さんにこの映画を捧げます。」という一文でのみ触れられているのみ。 なんだかもう嫌になりましたよ。 そんな気分を代弁してくれたのが,上記記事に対して寄せられたコメント。 全く同感なので引用させていただきます。 [23908] こんな映画を作っている限りは、日韓の友好なんてありえません名前:天地健日時:2007/01/15 14:21 予め申し上げておきますが、私はこの事件で死んだ韓国人青年に対し最大限の敬意を持ち、日本人を代表して感謝の意を表明したいと思います。 その上で申し上げますが、こんな映画を作っている限りは日韓の真の友好など訪れません。はっきり言って、こんな映画は不快です。 この映画の根底に流れるのは、韓国人の日本人に対する小中華主義に基づく猛烈な蔑視意識です。よく韓国人が主張する「韓国は日本の植民地支配によって被害を受けた」というアレは、「統治内容が酷かった」というのではなく、「本来うちのほうが偉いのに、見下しているはずの日本に統治されて悔しい」というものです。この「本来うちのほうが偉い」というのが小中華主義で、これはレイシズムに他なりません。 人が人を助ける、しかも自分の命を投げ打ってまで助けるという行為は世界普遍的に尊い行為であるはずなのに、この映画を始めとした政治的ヨイショの数々ですっかりしらけちゃいました(なお、この政治的ヨイショには死んだ青年自身が関係してないことは言うまでもありません)。 「見下しているはずの日本人を韓国人が助けたので凄い」「永遠の被害者である韓国人が永遠の加害者である日本人を助けたので偉い」こういうレイシズムはうんざりです。 単純に「人が人を助けた」いい話なんですけどね。 追伸:この事件では日本人カメラマンも救助のため死亡しているものの、韓国人一人に焦点が当てられた結果、彼の存在は完全に無視されていることも付け加えておきます。 これを読んで少し救われた気分になりました。まともな日本人も健在です。
2007年01月16日
コメント(8)
-
過去記事アーカイブオープン
リニューアルの目玉(?)としての,過去記事アーカイブをオープンしました。 これはこのブログを開設してから,昨年12月に至るまでに書かれた300にのぼるエントリーの中から,個人的に気に入っているもの,訪れてこられる方に見ていただきたいものなどをピックアップしてリンクを貼ってあります。 まじめな安全保障や皇室典範改正問題,核武装論を扱うものから,笑える電波モノを扱ったもの,初めての海外旅行の記録など,様々な種類を収めました。 よろしければごらんください。 管理人
2007年01月14日
コメント(0)
-
お知らせ
以前のデザインは,フリーページが極端に読みづらい配色になっていたので,読みやすい配色のデザインに変更しました。 同時に,サブメニューの文字も少し大きくしてみました。多分前より見やすくなったと思います。 全体として見やすくなっているといいのですが,もし見にくいところがあったらお知らせください。 それとともに現在,サブメニュー(リンクとフリーページ)の全面的な見直しを行っています。 リンクについてはリンク切れのものを削除したほか,自分が個人的にしか使わないような法律系のリンクは削除しました。その内容についても現在全面的見直しを行っています。それと,リンクの順番等についても考え直したいので,近日中に一旦登録されているリンクを全部削除し,それからもう一回最初から作り直そうかと思っています。 フリーページについても見直しを進めています。ちょっと古くなった内容のものや,あまり利用価値がないものは削除しました。同時に今回から新たに「過去記事アーカイブ」を設けて,過去のエントリーのうち,個人的に気に入っているものや力を入れたエントリーに直接アクセスできるようリンクを貼り,簡単な内容要約を付しておきました。作成途中ですが,興味のある方はご覧ください。
2007年01月13日
コメント(2)
-

今更ながらルイス・マウントバッテン卿の東京裁判批判
<すでに有名とは思いますが・・・> 昨年,英国外務省の文書からマウントバッテン卿が東京裁判を批判していたということが明らかになったという時事通信の記事が一部のブログ等で紹介されたことを記憶されておられる方もいらっしゃると思います。 ただ,同記事はマウントバッテン卿の「軍は純粋に政治的な性格の裁判にかかわるべきでない」という発言のみが紹介されているだけで,どのような理由で東京裁判を批判したのか,その根拠までは紹介されていませんでした。 実は今日調べ物をしていてたまたま見つけた記事に,その理由を示した記事を見つけたので,ここに先の時事通信の記事を補完する意味も込めて記事をアップします。 <マウントバッテン卿?> その前にマウントバッテン卿って誰?という方にちょっとした予備知識。 ルイス・マウントバッテン卿は,伯爵のタイトルを有する貴族です。上の写真を見ていただければいかにも貴族っぽいお顔立ちをされておられるのが一目瞭然です。 戦時中は海軍元帥として東南アジア地域連合軍総司令官を勤め,ビルマ(現・ミャンマー)でわが国と対峙しました。そのため,「ビルマのマウントバッテン」とも呼ばれています。 戦後は英領インドの総督に赴任。「日の沈まぬ帝国」を支えた財源であった英領インドがインド・パキスタンという独立国家になるのを見届ける役を務めました。 その後も要職を歴任しましたが,国防幕僚会議長を最後に海軍を退役。1979年,アイルランド沖で停泊中のヨットに仕掛けられた爆弾が原因でなくなりました。 現在のエリザベス女王の夫であるエディンバラ公爵フィリップ殿下の伯父様に当られる方でもあります。 <本題へ> 漸くというかんじですが,本題に入りましょう。 見つけた記事というのは世界週報の2006年2月14日のWorld NOW「東京裁判60周年,英提督の批判明るみに」と題された記事で,時事通信解説委員の富山泰氏が書かれておられます。 東京裁判が進行中の48年,英国のとある出版社が戦犯裁判についてのシリーズ物を企画。第1巻で英国軍が日本軍のBC級戦犯を裁いた最初の裁判を扱うことに決め,その序文の執筆をマウントバッテン卿に依頼してきたのがそもそもの発端だったといいます。 卿はこの依頼を受諾。ほどなく出版社に序文の草稿を渡されました。 そこには「軍は純粋に政治的な性格の裁判にかかわるべきでない」と主張がされていました。ここは時事通信の記事が伝えたところです。 ここから先が記事が伝えなかった部分。卿はそうした政治的な裁判の意義を疑う根拠を3点掲げていました。その根拠とは以下のとおり。 1:日本が戦争に勝っていれば,英国人を日本と戦った罪で裁くことができたと日本人に主張されてしまう。 2:この種の政治裁判には,法の特殊解釈か創作が必要になるので,そうした法に基づいて日本人を有罪にすると,正義に反すると被告の支持者に受け取られる。 3:政治裁判は被告に宣伝の場を与えてしまう。宣伝は弁護活動と不可分の形で行われるので,阻止することはできない。 卿が書くように頼まれたのはいわゆる「B・C級戦犯」,つまり通常の戦争犯罪を犯したとされる人々に関する書物の序文でした。これらは「政治裁判」というわけではありませんし,一応条約上の根拠があり,上記のような疑問は生じないところです。 なのにあえてこのような序文をしるしたということは,卿がこの序文を通じて当時進行中だった極東国際軍事裁判,いわゆる東京裁判を批判する意図を有していたということがうかがわれます。 なにせ,それは「勝者による裁き」として今でも批判を受けており,また「法の・・・創作」(事後法の創設)による裁判として近代裁判の原則である事後法の禁止という「正義」に反するとされているわけですから。 なお,記事によると,卿はこれ以前にも東南アジアに関する公文書で同じ主張を展開していたとのことです。 <反日家の主張だからこそ・・・> 実はマウントバッテン卿は根っからの日本嫌いでした。それゆえに先帝陛下訪欧の際のレセプション出席を最後まで辞退されておられたということです。 しかしそんな日本嫌いな,反日家な卿の発言であるからこそ,「政治裁判」の意義を疑う先の卿の主張はひいき目もなにもないということが保障されるのです。まさにその保障があるという点が,この卿の主張の価値をいやがうえにも高めているように思われるのです。 そしてその主張の根拠とするところの3つのうち2つが,現在東京裁判を批判している人々の根拠と重なっているということは意味のあることだと思われます。 そのことはとりもなおさず,東京裁判を批判する主張が決して日本が好きだから,とか愛国者だからという根拠のみから発しているのではない,ということの証左となるのですから。
2007年01月12日
コメント(635)
-
うれしい出来事。
こんな小さなことでも続けていると良いことがあるものです。 昨年にアップしたインド首相とヴェトナム首相の演説が,西村幸祐先生のブログ「酔夢ing Voice」にて取り上げていただきました(http://nishimura-voice.seesaa.net/article/31167359.html?reload=2007-01-11T23:11:07)。 報道ワイド日本の金曜日版「クリティーク」で先生のことは存じ上げておりましたし,リンクもさせていただいておりましたが,まさかご紹介いただけるとは・・・正直,たいへん感動しました。今年の感動第一号です。 それとともに,インド首相及びヴェトナム首相の演説の内容が多くの方に知っていただける契機ができたということに大変喜んでいます。正直,あれらの記事をアップした当時は「こんなことしても大して知られるわけはないんだから意味ないかもなぁ」と思っておりました。でもその心配ももうないですね。 今回西村先生に取り上げていただいたことは,自分にとって二重の喜びをもたらすものでした。本当にありがとうございました。
2007年01月11日
コメント(12)
-
やれやれ
なんとか風邪を退治しました。鼻声が残っていますが,近々なんとか普通の生活に戻れそうです。 それにしても久々に管理画面をのぞいてみたら,昨日今日となぜかアクセスが300を超えているんですが・・・ ひょっとしてまたどっかに貼られたかな? どの記事をどこに貼られたんだか興味があるので,もしご存知の方がおられましたならばご一報を。
2007年01月11日
コメント(8)
-
新年早々
風邪を引きました。なにもこんな時期に風邪を引かなくても,と自分の体に文句を言っております。多分,年始にWOWOWでやっていたドラマを欠かさず見ていたのがきっかけではないかと思われます(w 熱は下がりましたが,風邪との戦いで体力をすっかり消耗してしまいまして,しばらくまともな状態でパソコンには向えそうにありません。 なので,しばらくお休みします。すみません。
2007年01月08日
コメント(4)
-
恐ろしい在日の本性
※あの後いろいろと調べてみましたが,岸和田の掲示板に書き込まれていることは間違いありませんでした。ただ,いわゆる釣り記事ではないか,ということが各所で指摘されているようなので,ここに掲げるのみにし,コピペ推奨文言を削除しました。 以下のコメントはmurmurさんのブログのコメント欄で存在を知ったもので,岸和田市において外国人にも住民投票権を認める条例が可決された際,岸和田市の『岸和田掲示板』に書き込まれた在日コリアンの書き込み書き込まれた在日コリアンのコメントです。(http://www.city.kishiwada.osaka.jp/keijiban/Main.asp?Menu=Mes&GroupID=1&MesID=1211 参照)================タイトル これからは我々在日コリアンの時代 投稿者 李舜臣 投稿日 05/06/30 21:49:00 メッセージ 可決されましたか。いやめでたい。今なら言えるかな。関西在住の在日三世ですがこの日を待っていましたよ。我々は日本への帰化など望んでいません。日本の兄の国である韓国国民としてのプライドと誇りがありますからね。民団総連日本の市民団体の方々とともに手を組んで我々寄りの議員をどんどん送り込んでいきますよ。当然我々寄り議員は我々にメリットの大きい条例や法案を作ってくれるでしょう。これまで差別され虐げられてきた60万在日のパワーを見せつけてやります。日本人に一泡吹かせるどころかコリアン特区コリアン自治区を日本全国に広げます。韓流ブームなんてのはそのほんの入り口の更に手前の門扉の前の石ころ程度のものですよ。日本人は我々が大勢でちょっと大きな声をだしてやるだけですぐに動きますからね。この条例成立がそれを証明しているでしょ?まずはこの岸和田から。あとは日本中の在日コリアンコリア系日本人を総動員し日本中の都市街で投票条例を得最後は参政権を手中に収めます。必要があれば住民票を移したり引っ越しだってやりますよ。我々にはそれを実現するだけのパワーがありますから。この我々のパワーと勢いがあなたたち日本人との絶対的な差なんです。相互主義とか関係ないですよ。在韓外国人には今も投票権や参政権はありませんけどねこうして在日は相互主義に関係なく欲しいものは絶対に手に入れることができる圧倒的実力を誇るんです。独島も実質的に我らのものになっていますし強制連行や従軍慰安婦も我々の主張通りに認められました。今からこれからですよ。我らの先祖様たちが受けた36年にも渡る日本による圧政と搾取と略奪と蹂躙の歴史を挽回する時がやってきたんです。もう日本による歴史歪曲や妄言や差別はたくさん。これからの日本を作っていくのは我々コリアンです。どうせあなたたちは何も出来やしない。PCの前に座ってせいぜいこうやって掲示板に書き込むだけだ。デモの1つもできない。我々は民族の誇りをかけて日本を変えていく。あとは我々に任せてあなたたちは座して愚痴の1つでも編んでいなさい。================※平成19年1月12日,ジャンル替えのため更新
2007年01月05日
コメント(13)
-
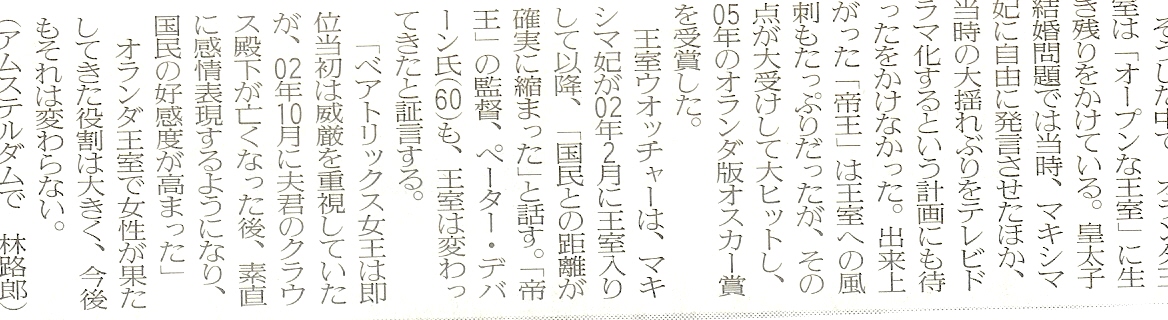
読売新聞の『世界の王室』記事に触発されて
元旦のエントリーコメント欄において,新年のご挨拶を下さった方々,あちがとうございました。 本年もよろしくお願いいたします。 <読売変節?> 新年早々,変な記事が読売に出ていました。記事A 記事B これらの記事は読売新聞の平成19年1月3日朝刊の9面にあったもので,『王室新時代』と称する,世界の王室を扱う特集の記事です。今回は『開かれた女帝の国』と題してオランダ王室が扱われていました。なお,記事Aは特集の本記事の一部,記事Bは特集記事の付属記事です。 ここで記事Aだけが掲げられていただけならば,まだ客観的事実を述べたものとして特段目に付くような記事ではなかったでしょう。問題はこの記事が記事Bと一緒に掲載されていることです。 記事Bをご覧ください。題名は『継承権 欧州では男女平等の流れ』とされています。その上で,この記事は一番下の段落の最初の行で,日本の皇室で皇位継承健について議論があるということに言及しています。 自分はこれを見たとき「日本の皇室も欧州の王室に倣って,女性にも継承権を与えるべき」というありがちな主張を展開する論調の記事のように読みました。 この記事が付属しているということを前提に先のAの記事を読むと,そこには「皇室はもっとオープンになるべき」というこれまたありがちな主張をするかのような記事に読めます。しかも題名が『開かれた女帝の国』。 読売は女系容認に流れたんでしょうか。これらの特集記事だけでは勿論断言できません。 しかし,最近この新聞の「主筆」と称するボケ老人は,アサヒと共闘宣言をするなど,目だって左翼的。もしかしたら,読売は今年から女系容認に乗り換える意向なのかもしれません。確か,昨年は慎重論のほうだったと思ったのですが。 読売がこれ以上,左の方に舵を切るようならば,不本意ながらもゴミウリとの名を献上せざるを得なくなります。 <ちょっとした資料> 皇室典範改定の議論は,秋篠宮悠仁親王殿下の御誕生により下火になっていますが,一応日本で一番読まれている新聞の変節が気になったついでに,少し資料を提供させていただきたいと思います。皆様のお役に少しでも立ったのならば,これに勝る喜びはありません。 次の記事は占領下で皇室典範改定作業が進められていた折,そのメンバーの一人としてGHQと折衝に当った井手成三氏の論文の一部です。その立場ゆえ,この方の発言は立法担当者に準ずるものとして解釈資料として重要であると考えます。 「皇室典範は,・・・普通の法律の一つであって,国会は,皇位の継承について,『世襲のものであって』の枠内で妥当と信ずるところにより条項を定め得ることは当然である。 しからば,憲法第二条の『世襲』とはいかなる意味に解することが正しいのであろうか。憲法第二条は,いかなる考えで,『世襲』の文字を使ったのであろうか。 憲法が定める天皇制は,もちろん,現天皇を念頭においた天皇制であり,抽象的な天皇制を構想したものでないことは,万人の認めるところであろう。憲法のこの『世襲』も,わが国において,古来伝承し来たった皇位継承の法則と無関係に規定せられたものではない。一つの予想された観念に基づいて表現せられているものと考えなければならない。 『世襲』という文字は,文字面のみからは,概念的には,『単純に血統のみに基いて一定の血縁関係にある者が当然に皇嗣となり皇位を継承する主義』と言えよう。この抽象的な概念のなかで,言はば思いつきの皇位継承を皇室典範の制定改正で定め得るという解釈の余地を持つものであると考える者があれば,それは,正鵠を得たものとは言えない。 すなわち,わが国における皇位の継承は,連綿として一定の内容をもち,不文律に伝承し来たった事実であり,その事実たる皇位の世襲制を率直に認め,それを眼中において,新憲法においても,皇位の世襲制を明記したものと解するのが正当である。 このことに関連して,新憲法制定議会,詳しく言えば,憲法改正案の貴族院特別委員会において佐々木惣一博士の,この世襲は,万世一系を意味するかという趣旨の質問に対し,政府側として,金森国務大臣より,旧憲法と異なるところなしとの答弁があったことは,大いに参照せらるべきものである。 今後,皇室典範改正の議が生ずるようなことがあった場合,この万世一系の原理,皇室に伝わり来たった皇位継承の不文法を破り,越えることはできない。」(愛知学院大学論叢法学研究12-2 p2~3。なお,注は一部後掲のものを除き他は省略) 井手氏は,この文章の注において次のようにも述べています。 「(注2) 我が国における皇位の継承について,旧皇室典範の義解には (一) 皇位を践むは皇胤に限る。 (ニ) 皇位を践むは,男系に限る。 (三) 皇祚は,一系にして分裂すべからず。 とあり,このことは歴史上一の例外もなく続いてきた客観的事実に基づく原理であり,成文法では破りえない不文の法であると考えるべきである。」(前同書 p4) ちなみに,文中にある金森国務大臣の答弁は以下のとおり(前同書同頁の注より編集して掲載。)「佐々木惣一君(無所属) ・・・皇位継承の資格と云ふことに付て御尋ね申上げたいのです。(中略)世襲のものであると云ふことは一体どんなものでせう。どう云ふ意味なんでせうか。所謂今日の現行憲法における万世一系と云ふのと違ふのでありませうか。違はないのであるか。・・・ 国務大臣 金森徳次郎君 本質的には現行の憲法(引用者注:帝国憲法。以下同じ)と異なるところはないと考へて居ります。ただ現行憲法は万世一系と云ふが如き多少比喩的な文言を使つて居りまして現実的な言葉ではありませぬ。それを現実世界の素朴なる言葉に表すと云ふことが主眼となつております。」 以上のように,皇室典範改定の作業においてGHQと折衝の任にあたった井手氏,及び現行憲法の立案担当者(とされている)金森徳次郎氏の両氏が「憲法の『世襲』は,男系男子による世襲である」という立場をとられていたという事実は,憲法2条の解釈において軽視することのできない事実であると思われます。 なお,この論文は「天皇制は憲法改正によっても廃止することはできない」「天皇制と国民主権は相容れる」という論題についても論じているので,図書館で触れることのできる方は,コピーして持っておいても損はないと思います。 ところで井手氏と同様,日本国憲法は男系男子による世襲を予定している,という解釈をとる学者として,故小嶋和司先生(東北大教授)がいらっしゃいます。 小嶋先生は旧皇室典範の制定経緯を丹念に調査され,憲法制定の過程において「天皇」条項がいかに定められたかをも調査し,その結果を踏まえて日本国憲法は男系男子による世襲制を前提とするものであり,女系天皇を認めるには憲法改正手続が必要であるとの結論に達しておられます。 その見事な省察はとても私がこの小欄で要約できるようなものではありませんのでここには掲げませんが,小嶋先生の見解をお知りになりたい方は,図書館で『小嶋和司憲法論集2 憲法と政治機構』(木鐸社)の『「女帝」論議』(45ページ以下)をご参照ください。自分はこれをコピーして教科書にはさんでいます。 ここでは先に紹介した記事Bとのかかわりで参考になる部分を抜粋しておきます。記事Bを書いた記者は以下の小嶋先生の言葉を熟読玩味すべきだと思います。 「男女差別の撤廃は,『人権』保障のあり方の問題である。が,皇位継承資格や皇位継承権は,およそ『人権』でありえない。論者は,この基本を忘れていないか」(前掲書p66)
2007年01月03日
コメント(11)
-
謹賀新年
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 年賀状を送っていただいた方々,ありがとうございます。明日にはお返事を出せると思いますので,気長にお待ちください。 さて,新年早々,バンコクでのテロなど幸先がよろしくないニュースが届いておりました。国内の地上波ではあいも変わらずわけのわからない番組が蔓延り,目も当てられません。当方は専らCSの海外ドラマや,チャンネル桜を視聴してこの状況をしのいでおります。 今年はいったいどんな記事をエントリーすることになるのやら・・・去年よりはマシな出来事をエントリーできることを願っております。 本日は挨拶のみということで。 平成19年元旦
2007年01月01日
コメント(5)
全20件 (20件中 1-20件目)
1









