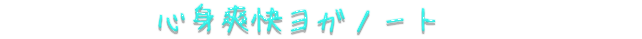2014年05月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
ちょっと自然治癒力
小さな切り傷をほっといても治す力、それが自然治癒力です。生きているはたらきです。お薬はそれを補助するはたらきをしているだけです。一部の人のように薬を毛嫌いすることもないし、また頼りすぎるのも問題ですね。文明の利器をちゃっかり利用する気持ちで、適度に使いましょう。
2014/05/31
-
鋤のポーズ・肩立ちのポーズ系が苦手な方。
鋤のポーズ(ハラーサナ)・肩立ちのポーズ(サルヴァンガアーサナ)系が苦手な方。首から肩が硬くなっています。体の中で首と呼ぶところは、互いに関連があります。足首を柔らかくする補助体操やアキレス腱周りを少し痛いぐらい刺激しマッサージしてみてください。関連部位操作です。
2014/05/31
-
ちょっとした合間に
デスクワークで目が疲れているのに,ちょっとした合間にスマホでTwitterとかしてませんか?その3回に1回は目の体操に使いましょう。縦・横動かし,右回し,左回し。 毎日繰り返す事を見直してみませんか
2014/05/31
-
鏡を見るたび
鏡を見るたび、作り笑いをしてみよー。最高の作り笑いの研究でもいいじゃない。(≧∇≦)そして心に向かい「いい笑顔だ」とつぶやく。3日間やってみ!変わるよ あなたの笑顔♪ 毎日繰り返してる事を見直してみませんか
2014/05/31
-
笑う呼吸法
笑うヨガというものが知られてきました。沖ヨガでは”笑いの行法”として50数年前から行っています。それをアレンジしたものをご紹介します。笑う呼吸法です。笑うヨガを簡単手軽に一人で行えるようにしたものです。人目につかないところを探しリフレッシュしてください。お腹をよじって笑っているときの感覚を思いだし、30秒だけ笑う呼吸をしてみてください。顔は作り笑いでいいでーす。声も出さないでいいでーす。お腹の動きと呼吸だけ再現するんです♪ とてもいい気分転換になります。だまされたと思って!(●⌒∇⌒●) わっはっは〜〜
2014/05/30
-
ちょっとした流れ
今はライフスタイルとしてヨガを始める人が多いけど、(第三次ブーム)昔(第一次ブーム)は難病の人・心が病んでる人などがすがるようにしてヨガの門を叩いたんだ。ちなみに第二次ヨガブームは、精神世界とかヒッピー文化の流れのころ。カルトの危ないのが出てきた負の歴史も含んでいる。で、社会的にカルトが弾劾されてから、しばらく経って出てきたのが”キラキラワクワク”のスピリチュアル系やファッションとしてのヨガなんだ。カルトのマイナスイメージを払拭したリメイク版と考えていいと思う。
2014/05/29
-
ねじるスクワット
前に、気を動かすためのスクワットや四股踏みの話を書きました。そのバリエーションを一つご紹介。ねじるスクワットです。気功体操(導引)として捻りのスワイショウがありますが、スクワットでも、それはできます。ねじるスワイショウは腕を体に巻きつけるように振ります。それに対しねじるスクワットはしゃがむ時、膝を左右交互に倒すようにします。顔と上半身は正面を向けたまま踵(かかと)をあげ、両膝・足先を右に向け下半身をねじるようにしゃがみ、腰をあげ、次は左に向けしゃがむを繰り返します。これをやると腰周り肚がぽかぽか暖かくなってきます。下半身の血行がよくなります。足を閉じて行ったり、適度に開いて行ったりと骨盤・股関節に対する刺激を変えて見てください。
2014/05/27
-
愛は?
愛は、相手をむりやりねじ曲げて手に入れることじゃない。言うこときかせることじゃない。それは心の方向性を見守ることだ。だから優しい顔だけが愛の表現じゃないんだ。愛する相手のために怒ることもあるだろう。これは恋人どうしの話だけじゃない。夫婦、親子、友人・・と広く考えたい。 しかし愛って照れくさい言葉だなあ (笑)
2014/05/26
-
アクセル(欲求)とブレーキ(反省)
自動車の運転のように人の生き方・行動にもアクセル(欲求)とブレーキ(反省等)が必要ですね。アクセルばっかりでは暴走!そのために抑制する心を持つのがいいです。そしてバランスを考えれば「アクセルをそんなに踏まなくてもいいじゃない」と気づく感じになるんです。
2014/05/26
-
ゆとり
ゆとりとは? 忙しさの中でも・ゆったりとする余裕夢を絵描いて・うっとりする心
2014/05/26
-
浄化?とは
よく聞く、【浄化】をわたしはこう考える。浄化とはものごとの複雑さを単純化することだ。生活を律する”戒(シーラ)”も生活の浄化を目的にしている。ヨーガスートラの説く【ヤマ・ニヤマ】もそうだ。余計なことはしない、良いことはする、それだけだ。混濁した生き方を単純にし丁寧に行うことが浄化なんだ。 (ちなみに浄化って言葉は私は好きじゃない。差別につながる怖れもあるから)
2014/05/26
-
広池ヨーガ
広池ヨーガ 作家でもある広池秋子先生(1919~2007)が始めたヨガで、コアラのポーズ、タツノオトシゴのポーズなど変わったヨガポーズ名に特色がある、ゆったり系ハタヨガ。高齢でも出来るヨガの見本。
2014/05/26
-
あなたのつとめは
「あなたのつとめは,存在することだ。このように存在するとか,あのように存在するとかというのではない」 ラーマナ・マハリシ
2014/05/26
-
上虚下実をつくる
上虚下実この言葉は藤田霊斎の丹田呼吸法から来ていて、実は、みぞおちは柔らかく力が抜けていて、臍下の丹田部は力が充実しているのが理想的だと言う意味なのです。腹部のエリア内の上と下です。部分は全体をあらわしますから、腹部の上部は上半身、下腹は下半身に対応します。(沖ヨガ関連部位)たとえばみぞおちのハの字部分は首に相当しています。ですから現在用いられている上虚下実の使い方も間違いではありません。上半身から力を抜く、下半身に力を入れるというのは、やはり東洋の身体躁法に関連しているしそれを実行することで状態をつくれます。たとえば相撲の四股踏み。インドのヒンズースクワット。中国の気功(武術)のタントウ(中腰の立禅)・スワイショウなども上虚下実を作ります。腕はスワイショウやヒンズースクワットのように力を抜いて振ってみましょう。腰は中腰になり丹田を充実させましょう。このとき胸の力は抜きみぞおちを落とし緩めます。上虚下実は体の状態だけでなく、頭の状態、心の状態にも繋がっています。実に落ち着いた実感がつかめます。
2014/05/24
-

歩く呼吸法その2(逆腹式呼吸法で歩く)
前に紹介した「歩く呼吸法」になれてきたら,次にこの方法に進んで下さい。歩きながらの逆腹式呼吸です。逆腹式呼吸は,息を吸うときにお腹を絞り,吐くときに緩める呼吸法です。ちょうど腹式呼吸とは腹部の動きが逆になるので、そう呼ばれます。逆腹式呼吸はお腹を大きく動かすことで胸も動かす”胸式(きょうしき)呼吸”です。肺も大きく伸縮させ、それに連れ動く肋骨や呼吸筋などの呼吸に関わる組織も大きく動かします。呼吸機能をトレーニングする呼吸法と言えます。普段の歩き方より少しゆっくりめに歩きましょう。リズムとスピードがつかめたら呼吸法に入ります。息を吸う:少しだけ長く鼻から息を吸い、1・2・3・4・5・6・・・ 歩数をカウントして下さい。 鼻から空気を吸い胸を膨らませると同時に お腹を凹ませ,お尻・肛門を絞め引き上げます。 凹ませたお腹の圧力を胸に引き上げ膨らまるように。息を吐く:歩きながらお腹・お尻を緩め息を吐きます。 口から細く長く息を吐いて下さい。 胸を絞りお腹・お尻を緩めましょう。 瓢箪(ひょうたん)型の風船の上と下を交互に握っているイメージです。この逆腹式呼吸の吸う・吐くをスムーズに切り替え歩いてみましょう。カウントは吸うときだけでいいです。吸う時の動き・カウントに意識を集め,吐く時はリラックス〜。Mind and body Refreshing YOGA NOTEBOOK
2014/05/23
-

歩く呼吸法
散歩などのとき試してください。歩く呼吸法です。散歩に出てしばらく歩いて、ご自分の歩くペースを感じましょう。(呼吸法として歩きますから、ゆっくり歩きます。)ペースが安定したところで、吐く息に合わせ、歩く数をカウントします。「1・2・3・4・5・6・7・8・・」と苦しくない範囲で吐ける息と歩数を数えます。吸うときは自然に入るだけ歩きカウントはしません。(第1ステップ)また吐く息にあわせ歩数をカウント。(吐くときは口から細く長くお腹とお尻を締めて、吸うときは鼻から自然に・お腹を緩め)これをしばらく繰り返して見ましょう。意識的に呼吸を長くしないでいいです。自分の歩く感覚と息をする感覚をつなげていきましょう。(なるべく空気のきれいなところで、また車などこない所で、周りに気をつけておこなって下さい。)Mind and body Refreshing YOGA NOTEBOOK
2014/05/22
-
先生いい子になったら殴ってくれますか?(再録)
キーワード☆愛沖 正弘先生のもとに、あずけられた子供のエピソードです。強暴性があり、両親が「この子といっしょに死のう」と思いつめるほど、すさんだ問題児が、沖 正弘先生のところへあずけられた偏食もすごく、肉類玉子類しか食べない子だ。もちろんヨガ道場の食事(自然食)など口にしない。問題行動の原因の一つが、生活の偏り弊害だと見てとった導師、何日も食事に手をつけないその子に 「野菜を食べた量だけ肉をあげよう。」そういって少しづつ野菜類を食べさせるようにしていた。でもその子は、食べたいものを、町の店にいって盗んで食べていた。当然道場に苦情、連絡が来る。でも導師は怒らない。黙って見つめている。 「先生!怒ってください。殴ってください。」 その子は言う。 「お父さんもお母さんも、怒ったり殴ったりしてくれた!」 「そうすると・・すっきりするんだ。」罪がそれで済んだ気持になってしまうのだ。 「良い子にしたら、殴ってくれますか?」 「だったら良い子にします。・・・」(その子は答えを出している!!)沖導師はその子に言った。「きみを殴ったら、僕の手が汚れてしまう。」「きみの手は盗みという行為で汚れているからだ。」「だから良い子になったら、殴ってあげよう!」「そのかわり、僕の手に罰を与える!!」「君の手が悪いことをしたのは、この先生の責任であるからだ!」沖 正弘導師は火をつけたローソクで手を焼き始めた! 「!!!!!」 その子は泣きじゃくりながらそれを止めた。・・・・・・ それ以来、見違えるようないい子にその子は変わったと言う。 出典 「実践 冥想ヨガ」生活編 沖 正弘 日貿出版社 ”愛” 沖ヨガの五つの重要キーワードのひとつであり 最高の人間的行為 定義:【愛とは正しく生きることに協力する事です。】 自分の命に他の命に (合掌)
2014/05/21
-

腰湯でぽかぽか
これから蒸し暑くなる季節です。シャワーを浴びるのは気持ちいいですね。でもお湯を流しっぱなしにするのは経済的にも、資源的にももったいないでしょう。そこでお勧めなのが腰湯です。腰湯とは文字通り腰までの湯につかる入浴健康法です。湯船の外で体の汚れを落としてから湯船の栓をして中に入り、坐ってシャワーを浴びます。坐ると膝の上ラインがちょうど腰のあたりですから膝小僧まで浸かるぐらいまでシャワーを浴びたら湯を止めます。立ち上がると分かると思いますがそこまで溜めても水の量は意外とすくないものです。後は軽く汗が出るぐらい身体を暖めます。手桶で上半身にお湯を掛けたり、タオルを湯に浸してから温めたいところにピタッと温湿布のように張るのもとてもいいです。首・肩・お腹・腰など・・。また、冷めないように湯船に蓋をして、首から上を出し、ゆ〜ったりとした腹式呼吸をするのもとてもよく暖まります。東洋の健康法の考えには頭寒足熱と言う、足(下半身)は暖かくするのが良いというものがあり、腰湯は手軽にその状態をつくるのです。鼻歌を歌いながら腰湯♪してみれば、ぽかぽか気持ちよく、心もほぐれます。お試しあれ〜。( ´ ▽ ` )ノMind and body Refreshing YOGA NOTEBOOK
2014/05/21
-
【ラジオ体操だってヨガになる】一つの名前で判断しない
体操を体操と思ってやれば体操の効果がありますが,気を流す気功と思ってゆっくり行えば、同じ動きで気功としてもできます。ラジオ体操をヨガだと思い、呼吸と動き、意識を合わせて、自分の息の出し入れのリズムで行えば、ラジオ体操だってヨガになります。同じ考えでヨガを体操と思ってやれば体操だし,呼吸法と思ってやれば呼吸法です。体を動かす瞑想だと思えばそれもしかり。もっといいのはその3つが融合してることなんだよー。なんだって考え方・意識の転換です。物・事を名前で判断しないと活用が広がります。
2014/05/20
-
顔を洗い気を動かす(朝の日課で)
みんなしている事。朝、冷たい水で顔を洗う、手を洗う、口をゆすぐ。ゆっくり動作を味わってみると、それだけで爽やかな気が動き出している。これは神社参拝でしている事と同じなんだ。そう気づけば洗顔だって自分の命への参拝になる。 「祓いたまえ 清めたまえ 神ながら 守りたまえ さきわい給え」
2014/05/19
-
心のためのスクワット♪
誰でも気分がもやもやするとき、むしゃくしゃするとき、ちょっとやる気が出ないときってありますよね。そんなとき気分転換に『スクワット(立って腰をおろす・腰を上げるを繰り返す)』を30回から50回するといいです。*最初はおろす腰を浅くでかまいません。*あと膝がつま先より前のラインに出ないようにしてください。*顔は正面を向くようにしましょう。スクワットを筋トレとしてではなく、気分・気持ちの流れを変えるためにするのです。これで頭の、胸のつかえを流しましょう。効果抜群です。まずはお試し下さいませ。
2014/05/18
-
坐禅・動かないでいること
瞑想に興味をお持ちの方多いと思います。でも本格的に瞑想を実際にどこかで習おうとするのは怖いですね。そこはカルトかも知れませんし、なにがしかの宗教的洗脳に遭うかも知れません。高いお金が掛かるかも知れません。その点、伝統的瞑想法といえる坐禅なら安心してできると私はお勧めしています。今回はその坐禅についてお話させていただきます。坐禅をすると言うことは坐ってじっとしていることから始まります。じっとしている事は辛いことです。「同じ姿勢で動くな」と他人に強制されたらそれこそ拷問のようなものです。それを自分から訓練するのが坐禅です。じっとし続けることで湧き上がる思考の苦しみ・体の苦痛にまず直面しなければなりません。試しに30分胡座(あぐら)でいいです。坐ってじっとしてみて下さい。坐って動くことを禁じていると動きたくなってきます。「動きたいよ,組んだ足が痛いよ,虫刺されが痒いよ。」と体の要求を叶えられない苦痛が出て来ます。これを超えなければ坐禅の意味がありません(笑)30分間それに耐えてみましょう。また不満の考えが大きくなっていきます。「こんな事がなんになるんだ」と分析・批判が始まります。自分の悪口や他人への悪口がどんどん出て来ることでしょう。出るままに出しましょう。心を鎮めるのに一旦掻き回してる段階です。もちろん心身の苦痛を避け、掻き回さず、上澄みだけの静寂を楽しむのだっていいと思います。騒々しい日常のストレスから離れリラックスする効果があります。スタジオヨガなんかでやる瞑想タイムはそういうものです。 ただ深く求めるなら心と体の苦痛、それに対する自分の弱さを掻き回すことが大事なのではないでしょうか。自分の心の澱(おり)を見つめ、整理し再沈殿させることで、より深い澄んだ部分が広がると思いませんか?この部分が、庭詰め(入門を請い、寺の玄関に頭を垂れ2日ほど座り込む)から始まる正式な修行禅の儀式作法の厳しさに秘められた意味です。何事も永遠に続かないように,坐るのを続けていると心も思念を吹き上げるのをやめる時がきます。”私”といつも思い込んでる働きがおとなしくなるのです。これは悟りとかではありません。「私が坐っている」から私が取れた状態です。私が坐っている。」のでなくただ「坐っている。」「私が息をしてい」るから,私が取れ、「息をしている」になります。私を取るため、自我(自尊心・プライド)を破壊することから始まる禅の修行生活はその点,生活のすべてにおいて徹底してます。まずは坐る苦痛とは何か実際に味わうことです。日曜坐禅会、早朝坐禅会など行われている禅宗のお寺を探してみてください。
2014/05/15
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
-

- 介護・看護・喪失
- 書いてないだけ、毎日想っている
- (2025-11-22 22:10:15)
-
-
-

- ダイエット!健康!美容!
- 本日限りのクーポン!半額からさらにオ…
- (2025-11-25 14:05:35)
-
-
-

- 今日の体重
- 2025/11/25(火)・「0・2減」(#^^…
- (2025-11-25 12:00:00)
-