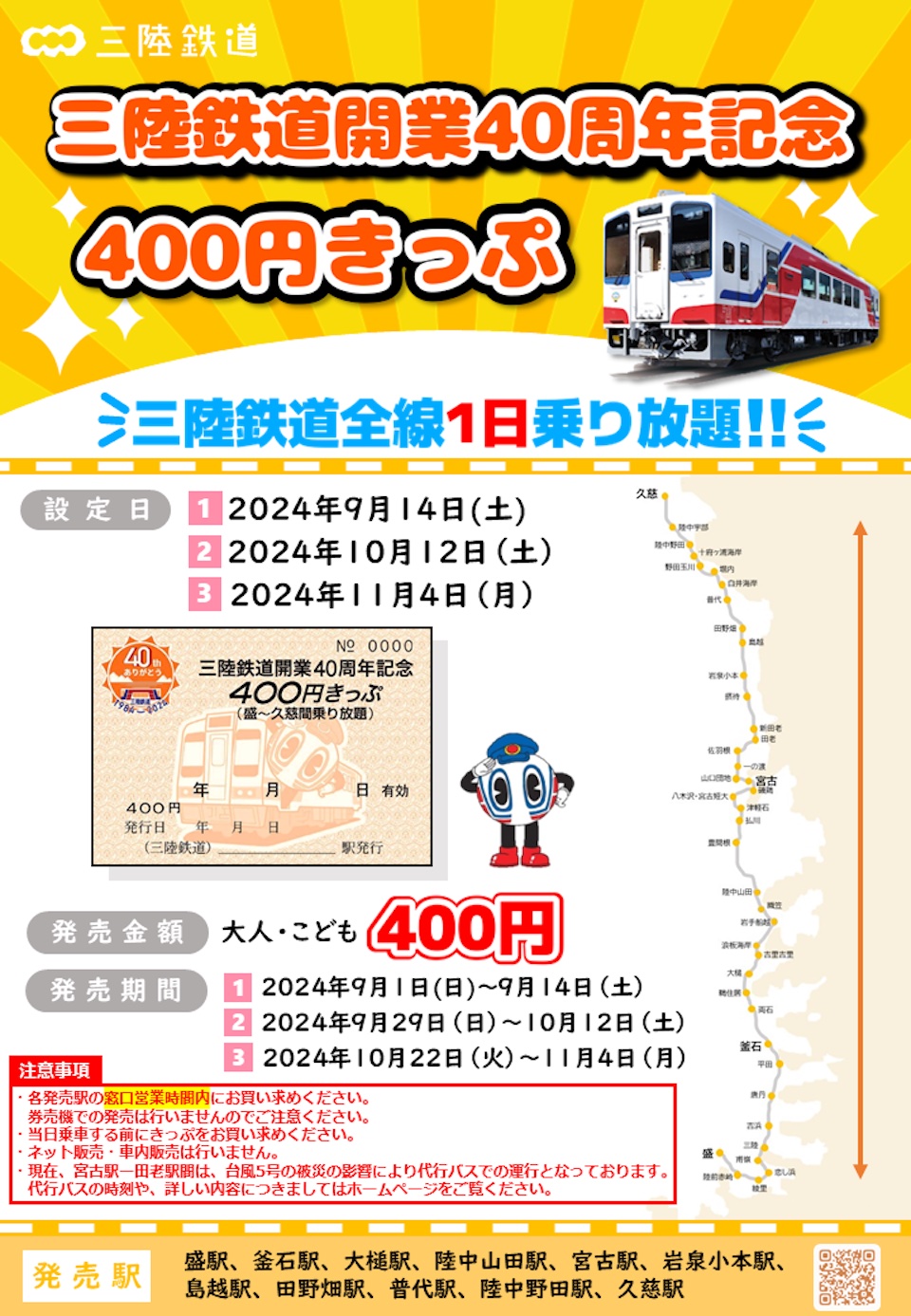カテゴリ未分類 0
[アメリカ紀行] カテゴリの記事
全40件 (40件中 1-40件目)
1
-

NY2015の記憶(1) "The King and I" 渡辺謙さんの挑戦に感動
仕事の環境の変化やプレッシャー、メンタル面での浮き沈み、体力や年齢的な不安、弱気になったり、気分が乗らず無為に過ごしたり、。。。そのまま怠けものになれるなら、そうなりたいなあと思ったりもする。そこで「もう歳だなあ」とか、「おじいちゃんになってしまったなあ」などと漏らそうものなら、カミさんに「そんなこと言っている50代、60代って回りにいない」と喝!!が入る。弱気の虫に冒されそうになるのを、頑張らねばと、肝心のところでは気持ちをピークに引き上げ、奮い立たせる。そんな繰り返しだが、そういう気持ちにさせるにも、自身をモチベートさせてくれるもの、力を与えてくれるもの、そして想いが必要だ。私にとってその一つは、信じるところをもって頑張っている人、そして物事に挑戦する人の姿だと思う。昨年それを求めてNYへと渡った。思い出せば、キッカケは2015年の4月某日、たまたま見ていたTVで、ブロードウェイのミュージカルへ挑戦する渡辺謙さんの生きざま、姿勢を見たこと。それは、王様と私"The King and I"の主演を演じる謙さん。"独眼竜政宗"でその人を初めて知ったのは数10年も前のこと。その後白血病を克服し、今や世界が認めるハリウッドスター。とは言え、本場ブロードウェイの舞台、いくら前評判が高くても酷評を受ければほんの数日で幕を下ろすショーもある厳しい世界(記憶にあるのは"赤い靴")での挑戦だ。初めてのミュージカル、その一瞬一瞬がやり直しの利かない勝負の世界、そこで英語で表現し、そして歌い踊る。それもミュージカル史上の名作中の名作"The King and I"。ユル・ブリンナーが演じ続けた王様を、渡辺謙がいかに演じきるか。当初、謙さんの話す英語が聞き取れないといった批評もあったようだが、果敢に挑戦された。それはご本人も曰く、55歳にしての人生一大の挑戦。そして2015年のGWを前に謙さんの舞台はいよいよ幕を明け、大変な評判になっていたが、同時に是非それを見に行きたいという想いが私の中で高まっていった。昔から好きだったミュージカル、中でも"The King and I"はお気に入りの一つ。デボラ・カーとユル・ブリンナーが主演した映画はもちろん、約25年前初めてロンドンを訪ねた時にはちょうど上演されていたその舞台を2度見に行ったほど。そういう背景もあって、挑戦する謙さんから力を貰おうと思った。NY行きに迷いは無かった。その舞台についてここで私が何かを述べることは畏れ多いこと。とにかくとても感動した。目の前で王様を演じる渡辺謙さんに鳥肌がたち、涙した。日本人の誇りだと思った。それはトニー賞の主演男優賞にノミネートされたことにも裏付けられるのだが、主演女優賞をとった共演のケリー・オハラの受賞直後の声にも凝縮されていた。"You are my King !!" そして勇気と力をもらった。さてその舞台は、私にとって2015年一番の感動の時間だったが、その場に身を置くことができたのは本当に幸運だったと言っていい。NY行きの航空券を手配した時、既に"The King and I"のチケットを取るのが不可能な状況で、あまりの人気ぶりに何倍ものプレミアがついたりもして半ば諦めていた。しかし、インターネットを調べて辿り着いた最後の砦、"あっとニューヨーク"でチケットを手配。それは出発前日の5月1日のこと。そして舞台の日程は、米国到着日5月2日の夜。時差と疲労を考えると一番過酷なスケジュールとも言えたが、滞在中唯一手配できた日程、価格は1人309ドルと高額となったが生涯1度のチャンス、決断したのであった。(その後、謙さんが演じた6月末までの講演は軒並み争奪戦で1000ドルを超える例もあったようである)ホテルで若干の仮眠をとって、訪れたのはブロードウェイの劇場ではなくて、マンハッタン随一の音楽・舞台芸術の殿堂、リンカーンセンター。他の劇場と比較すると、格の高い雰囲気、そしてオーケストラの質も高く、その後滞在中に見るミュージカル2本も、この日の"The King and I"にはとてもとてもとても及ばなかった。しかも日本からも結構見に来ているのかと思いきや、日本人は本当にまばらで、殆どがアメリカ人(欧米人)。その光景に、ブロードウェイで認められて、大いに受け入れられていることを実感したのであった。惜しまれるようにして、ブロードウェイでの王様役をやり遂げて日本へ帰国した謙さん。その王様が再び、この3月にブロードウェイに凱旋する(~4月)のはとても嬉しい。もちろん見にいくことは出来ないが、そのニュースにまた力を得る思いである。
2016.01.20
コメント(0)
-

2度目のボストン(4) デトロイト乗換50分
ボストンからの帰国便は、デトロイト乗り継ぎ。国際線へのトランジットにしてはわずか50分。そのため実際お土産を買う時間もラウンジで寛ぐ時間も無く、搭乗ゲートへと直行した。尤もデトロイトのトランジットに際しては何の期待もしていなかった。というのもデトロイトといえば、失業率が高く、アメリカで最も治安の悪い都市というイメージ。積極的にアメリカ渡航のゲートウェイにしたいとは思わなかった。そして降り立ったデトロイト。そこは他のハブ空港と何ら違わない空港の光景。搭乗券にそして発着ゲートの案内に成田行きのゲートを確認すると、それは遥か彼方の番号。見れば真っ直ぐに伸びる長ーいコンコース。既にそこがデトロイトなのか何処かは問題なく、足早に歩を進める。縮まってはいるが、なかなかに近づかない目的にゲート。それはあたかもマンハッタン島を縦に42nd, 41st, 40th, ...と、目的のストリートを目指し、1つ1つクリアしていくかのよう。 すると、頭上を走り抜ける赤い車両。見上げれば、すぐ上を何とレールが走り、長いコンコース上、真っ直ぐに伸びていた。その瞬間、"さすがはデトロイト!!"と思わず感嘆した。ターミナル間を走るシャトルトレインなら珍しくもないが、コンコース上ゲート間を結ぶシャトルを目にするのは初めて。それをアメリカの自動車産業の中心地デトロイトに見たのはまさにピッタリに思えたからだ。その名もEXPRESS TRAM。時間が許せば、これには乗りたかったなあと思う。きっと、これまで空港で見たことのない違った景色が見られだろうと想像。アメリカの自動車産業に打撃を加え、日本バッシングの象徴的都市でもあった筈のデトロイト。しかし多く目にする日本人に、そうは言っても自動車産業に日本の技術は欠かせないんだなあと感じた。そしてそこに思いきりの日本を見ると、搭乗ゲートもすぐそこ。足早に機内へと吸い込まれていったのだが、短い時間の中にもデトロイトを感じることが出来た。機会があればまたトランジットに使ってみたい。
2013.09.24
コメント(0)
-

2度目のボストン(3) プルデンシャルタワー朝昼晩
旅先のホテルのロケーション、そして部屋からの眺め。それは限られた旅の時間を有効に活用する上でも、そしてホテルの部屋で過ごす時間をリラックスしたものにするか否かを判断する上でも、重要な要素だ。1年前の9月、初めてのボストンを訪れた時、宿泊したホテルのロケーションが、どこに行くにも少し不自由で、そして部屋から臨む景色も落胆すべきものだった。そんな記憶が、2度目のボストンでの滞在先を決めるにあたって大いに影響したのは事実。そして今回、訪れた展示会がプルデンシャルセンターの一角で行われたこと、また昨年そのタワーを訪れながらも展望フロアに上がれなかったことが、プルデンシャルセンターをターゲット・エリアとして決定づけた。 何と言っても、プルデンシャルセンターは、ボストン美術館、フェンウェイパーク、さらにはトリニティ教会からパブリックガーデンへと、それらを徒歩圏内に中間的な位置にある非常に便利なロケーション。そしてショッピングにもこと欠かない。そして、プルデンシャルセンターとは、道路を挟んだ向いのシェラトンホテルの中を通って繋がる、ヒルトンホテルに宿泊する。そして部屋からの景色はというと、ラッキーだったのが、正面シェラトンホテルの後方に聳えるプルデンシャルタワーを臨み、また青々としたチャールズ・リバーをも遠くに臨めたこと。多くの時間を部屋で仕事に費やしていた私には、窓からの景色が潤滑油となり、また景色の移ろいに部屋にいてもカメラを手放せなくなった。というわけで、そんな景色をここにご紹介。シェラトンと背後のプルデンシャルタワー。そして、プルデンシャルセンターのドームのあるタワーの壁面には鏡となってビル群を映す。(中央:中秋の名月が、中右:ドームが朝焼け、下中:深い霧にタワーも隠れる)ホテルの部屋からは臨む、チャールズリバーにはヨットが浮かぶ。そして廊下に出ると、対岸のMIT(マサチューセッツ工科大学)のドームが川面に影を映す。 そして息抜きに、隣接するChristian Science Churchへと散歩すれば、池に映る夜景が美しい。 わずか2泊4日の米国ボストンへの旅。しかし、ホテルのロケーションの良さが、短い滞在時間を実に密なものにしてくれたと思う。これらの景色もまだその恩恵の一部、引き続きボストンの時間を記していきたい。
2013.09.21
コメント(0)
-

2度目のボストン(2) 1年越しのプルデンシャルタワー
ボストン滞在は9月19日から21日までの2泊。その間、プルデンシャルタワー50階にある展望フロアSKYWALKに足を運んだのは、19日昼と20日夜の2回。正確には19日の夜にも訪れたのが、フロアの半分が貸切りパーティに使われていたため、翌日の夜に出直す。ちょうど1年前に訪れた時、それは滞在最終日の夜だったが、イベントのため入場出来なかった。それから約1年、再びその地を訪れる機会に恵まれ、そして当時見ることの出来なかったボストンの眺め、その昼と夜との景色を目に焼き付けることが出来た巡り合わせには、まさに感謝する次第である。驚いたのが、1Fの専用エレベータに乗り込むと、一気に50Fの展望フロアの受付へあっさりと辿り着き、入場を果たしたこと。というのも、これまで幾多の国内外の名のある高層ビルやタワーに登った経験を振り返ってみて、入場までの長い列、荷物検査、展示、観光客狙いのお決まりの記念撮影、等々、そんなのが一切無縁だったこと。展望フロアに辿り着くまでに疲れ果ててしまったNYのエンパイアステートビルの記憶など全く嘘のように、実に快適至極だった。ともあれ、そのタワーからの素晴らしい景色をここに遺しておこうと思う。(左上:Charles RiverとBACK BAYのレンガ色、右上:BACK BAYをCommonwealth Ave.の緑が貫きPublic Garden, Boston Commonに至る、右手にJohn Hancock Towerが聳える、左下:MITのGreat Dome、右下:FENWAY)(左上:Boston Bayを臨む、左下:Logan Airportへの着陸機、右上:Fenway Park、右下:Trinity Church)夜の景色を見ようと再び訪れた最大のお目当ては、Fenway Parkでのレッドソックスのナイターを俯瞰すること。さすがに遠過ぎてプレイヤの姿を認めることは出来ないが、昼間の姿と一変した球場の熱気は伝わってきた。この時、知らなかったのだが、実はこの眼下で行われていたゲームが地区優勝を決定させたゲームだったとは、後からホテルの部屋に戻って知るところとなる。(左上:John Hancock Towerに満月が、右上:カクテル光線に輝くのはFenway Park、左のドームはChristian Science Church、右下:Fenway Parkに接近、左下:Purudential Centerのドーム)そしてこの日は満月。まさか中秋の名月をボストンで見ようとは、。。。
2013.09.20
コメント(0)
-

2度目のボストン(1) ボストン到着早朝
この日の早朝7時前、米国ボストンに到着した。約1年ぶり、2度目のボストンだ。天気は快晴。乗り込んだタクシーの運転手が言うには、朝はChilly(冷んやり)とのことだったが、それまでの猛暑の日本の気候と比べると、肌に感じる空気が心地よく感じた。それにしても昨年来、一体何度目の深夜便だろうか。今回の渡航、羽田を飛び発ったのが19日の深夜1時半。デルタ航空での8時間超の飛行は暦を1日逆戻りさせた18日夕刻、23年ぶりとなるシアトルへの入国。とは言え、シアトル・タコマ(SEA-TAC)国際空港から外に出ることなく4時間近く待つと、今度はアラスカ航空の深夜便で一気に西から東へ5時間かけての大陸横断。現地を夜10時半過ぎに出発すると、東海岸の朝6時半過ぎに到着。出発から約17時間超をかけて、19日の朝、ボストンに到着したのだった。 (左:SEA-TAC空港Central Terminal, 右:同Concourse Dから満月臨む)深夜便にも関わらず、予想に反して両便とも満席。その結果、幸いだったのは、羽田の搭乗口のところでエコノミーコンフォートからビジネスにアップグレードしてもらえたこと。フラットに身体を横たえられるのは、それだけで全然違う。もっとも、搭乗後間もなくのディナーに既にお休みモードだった私のお腹は活動を余儀なくされ、そのせいか意外と眠れなかったのではあるが。。。その分、アラスカ航空の深夜便では、リクライニングが殆ど無く、直ぐ真横のトイレの音を聞かされ続け、また寒くもあったのだが、終始寝ていた。そのため、早朝到着にもかかわらず、ボストンの1日を大した睡魔に襲われることなく、無事に過ごす。空港で軽くお腹を満たした後で、タクシーでホテルに到着したのが午前8時前。予めアーリーチェックインのリクエストを申し出ていたのだが、あいにく満室で部屋に入ることが出来ず、そのかわりフィットネスルームの鍵を貸してもらい、シャワーと着替えさせてもらうことに。狭い更衣室にはすぐにもう一人のゲストがやってくるが、申し訳さなげにスーツケースを広げて荷物の出し入れをする私。そして、ほどなく1人となると、ゆっくりと準備させてもらった。あまりに占有している時間が長かったからか、途中でホテルの人がチェックに入ってきたが、その時にはすでにシャワーに汗を流し、髭を剃り、そしてそれまでの私服からスーツへと着を包みかえた後だった。なんだか映画の中で見るロッカールームの光景だなあ、と鏡に映る自分を見て、そう思ったりもしていた。結果的にチェックイン出来たのは14時半過ぎとなるのだが、この朝はスーツケースを預けると、ビジネスバッグを肩に、すぐ近くにある展示会会場、コンベンションセンターへと出陣していったのである。その会場は、ボストン一の高層ビル、プルデンシャルセンターの一角。そのビルは、昨年、滞在最終日の夜、タワー展望フロアSKY WALKに上がろうと訪れて、上がることの出来なかったビルだ。今回、その近くにホテルを取ったのも、タワーに登ることを当然意識してのことだった。この日、朝9時に展示会のregistrationを済ますと、開場まで約1時間半。それならまずは展望フロアに上がろうと思ったのだが、その営業開始にも早すぎた。大きなショッピングセンタとなっているビルを歩き、タワーをカメラに収めると、ファストフードのカフェで資料を広げて、展示会会場歩きの下調べ(結果的にはあまり役立たなかったが)をしながら、開場を待ったのであった。
2013.09.19
コメント(0)
-

2011年10月再びの米国(4) 出迎えは紅葉とハロウィンの飾付け
今日はハロウィン。と言っても、私のこれまでの人生において、それは全く縁が無いと言ってもよい。街に見る、ハロウィンの装飾などから、それと意識するくらいだが、今年の秋はあまり賑やかなところに行っていないからだろうか、それを意識させる光景に出くわした記憶がない。但し、それも国内では、の注釈がつく。この週末大雪に見舞われて、非常事態宣言も出ていたニューヨーク州。その地を訪れたのはほんの2週間前のこと。秋晴れの穏やかな天気に、まさか紅葉まで見ようとは思いもしなかったのであるが、黄色やオレンジ、赤色に色づいた木々を飛行機から眼下に見下ろしながらの到着。その地は、ニューヨーク州の州都、Albanyアルバニーという都市であった。そして、その地に始まる1週間の滞在期間は、まさに米国ではハロウィン・シーズン。クリスマスの飾り付けのように、ハロウィンの飾り付けをしている家を多く見たものである。そして、決まって転がっていたのが、大きな黄色いカボチャ。そんな光景に目を楽しませてもらったものである。というわけで、今日、ハロウィンというこの日にちなんで、そんな写真を紹介しよう。アルバニーに到着し、空港近くのホテルに到着したのは、午後2時を回ったころ。ホテルのシャトルバスを下りた私を出迎えてくれたのは、ホテルの玄関のハロウィンの飾り付けであった(冒頭写真)。そしてチェックインしたものの、部屋の準備が出来ないということで、ホテルのロビーラウンジで休むこと1時間ほど。途中、40分ほど経って漸く割り当てられた部屋に先客があったりもして、なかなか部屋に入ることが出来なかったのであるが、そんな状況をハロウィンの飾り付けが和ませてくれた(下)。 さて、"Residence Inn"というホテルの名が示すとおり、家が集まったようなそのホテルの部屋は、長期滞在型の家と言った雰囲気(下左:私が宿泊したのは1Fの1室)。シティホテルとは全くことなり、暖炉のある部屋の雰囲気はまさに家に居るような、実に落ち着いた雰囲気であった。もちろん台所セットも完備し、食器類もフル装備。でも、1泊の滞在ではそれを使うこともない。唯一、特筆すべきことは、枕元に置いてあった耳栓。それが何故、そこにあるのか?それを知るのは、夜、寝床についた後のこと。空港の滑走路が寝床からすぐ近くにあったのだろう、その音の正体は、飛行機が離陸に向けて加速する轟音だったのである。おかげで早朝に目が覚めると、または転寝(うたたね)の状態において、忙しい飛行機の離着陸の音が耳に響く度に、頻繁に意識が戻るのであった。 さて、何となくお祭りのようになっているハロウィンも、今さらのように調べてみると、その期限はケルト人の収穫祭で、言わば宗教的儀式。一見、アメリカにおいてもイベント化しているように見えないでもないが、この日ばかりは、特別な儀式でもあったのだろうか?滞在中、目に留まったハローウィンの飾り付けがどうなったのか、関心深い。
2011.10.31
コメント(4)
-

2011年10月再びの米国(3) シカゴ。アルカポネの街は美しく
まさに映画の影響と言えるのだが、私にとってのシカゴのイメージは、暗黒街の顔役、アル・カポネ。そして時代は禁酒法、とそんな私はかなり旧い人間だ。そんな私のイメージを覆すには、実際にシカゴの街を歩くのが一番だ。(右:シカゴの街を走る高架鉄道、その彼方にはトランプ・インターナショナル・ホテル&タワー)最後の顧客訪問を終えて、テネシー州のノックスビルから滞在中2度目のシカゴを舞い戻ってきた21日(金)の夕刻、空港からブルーラインという名の鉄道に乗り、ダウンタウンへと向かった。時刻は既に17時になろうかというところ。そんな時間から訪れようと思った目的地はシカゴ美術館。ガイドブックに木曜と金曜は20時まで開館しているとの情報があったからだ。出張の最後にゆっくりと名画を鑑賞して、リラックスするつもりであった。ほんの数日前、ミネアポリスからシカゴへと飛んできた夜には、ミシガン湖の波が湖畔に打ち上げるほどの荒れ模様で、気温も一桁台。さらには、風雨に飛行機が100便以上が欠航するという中、幸いにして私の搭乗する飛行機は主翼が左右に揺られながらも無事着陸したという状況。しかし、それが嘘のように、この日は秋晴れに恵まれたのは幸運だった。 そして、シカゴの中心部に到着した私は、地図と方向感覚を頼りに、シカゴ美術館を目指すのである。さすがに4月にニューヨークを歩いた記憶もまだ新しく、街歩きにさほどの緊張感は無いばかりか、歩いていて心地よい。それも、振り返れば、シカゴの街に競い合う、新旧の建築美だったのかもしれない。それらの光景にカメラを向けながら、シカゴ美術館に到着する。(下左:オーディトリアム・シアター、中:シンフォニー・センター、右:シカゴ美術館) ところがである、シカゴ美術館の扉は閉ざされてビクともしなかった。良く見ると、金曜は18時までとある。20時まで開館しているのは木曜だけであった。"えっ、嘘だろう!"と思い、ガイドブックを見直すと、やはり金曜は20時までとの記述。しかし、それを言ったところで現実が変わるでなし。この瞬間、シカゴ美術館で会えるのを楽しみしていた、ゴッホの『アルルの寝室』、スーラの『グランド・ジャッド島の日曜日-1884』は、目前にして叶わぬものとなる。そういうことで突然、目標を失った訳であるが、そのまま引き返すのも勿体ない話。ここまで来たからには、シカゴの高層建築美を見てみようと、歩くこと7-8ブロック、アメリカで最も高いビル"ウィリス・タワー"、その展望台へと向かったのである。高さ443m、ほんの2年前までは"シアーズ・タワー"として世界一の高さを誇っていた建物である。展望台に辿りつくまでの長いアプローチ、それはチケットを買う列に、映像を見せられる等の時間だ。しかし、エレベータに乗り込み一気に103階まで上り詰めるとそんな浪費した時間もすっ飛んでしまった。眼下の高層ビル群と放射線状に広がる宝石のような輝き、そして真っ暗なミシガン湖のコントラスト。その光景に、アメリカの広さを体感させられたようであった。 そして、最後に誘導されるタワーにある売店、そこでアル・カポネの関連グッズがあり、思わずほくそ笑む。まだそれが今に生きていることを知ると、一路、来た道を引き返し、ホテルのある空港へとブルーラインで帰る。その間、私の頭の中では、フランク・シナトラの歌う"シカゴ"のメロディーが、心地よく響いていたのであった。
2011.10.30
コメント(2)
-
2011年10月再びの米国(2) ラスト・ミニッツ・イン・シカゴ、最後の失態
米国から帰国して6日、漸く迎える休日は実質3週間ぶりだ。帰国後も出張やら、ちょっとした歓迎会やら、期日に追われる仕事の処理にと、この日、久しぶりに目覚ましの無い朝を迎えて、疲れもだいぶ取れた感じである。そんなわけで先日の米国出張を振り返ってみることにする。但し、終わりからにしよう。初めてのシカゴからの出国。空港内のホテルに宿泊していた私は、チェックインのターミナルまで、地下の連絡通路を徒歩でいくといけるという便利さから、余裕でカウンターを訪れたのであるが、思わぬ誤算に見舞われる。一つは座席の確保、そしてもう一つは対応の遅さ。荷物を預けるカウンター数に対して、人が半分。なおかつ、目の前の客と係員との間で「ああでない、こうでない。。。」と始まると、ここでロスすることなんと約20分。そして、ボディ・スキャンを含む、長い荷物検査を終え、搭乗口に辿り着いた時には搭乗開始の15分ほど前となる。また、滞米中すっかり慣れた機械でのチェックイン手続きも、事前に席を確保していたというのに、何度やっても席を確保できない。係員に問えば、搭乗口で呼ばれるとのことで、密かに、これはアップグレードじゃないか、と期待した次第であるが、搭乗口に辿りつくと多くの人だかり。そしてそんな淡い期待も打ち砕かれる。気にせずカウンタを訪ねると、名前を呼ばれるまで待ってくれと、。。。そして、刻々と表示が変わるモニターには、アップグレードリストや、ウェイティングリスト、さらには乗れない人リストのようなものが、映し出される。そして何と、ウェイティングリストの14番目に自分の名前を見つけたからである。その時の状況としては、乗れない人としてリストアップされていなかっただけマシだと思った。何でそうなってしまったのか。それは後で知らされるのだが、機材(飛行機)が変わったこと、さらには何かの故障で本来搭乗する筈のなかった香港への乗客も搭乗したためであることと判明。要は、座席がオール・リセットされた状態となり、再割り当てが必要となった。なおかつ溢れてしまい、次の飛行機へのボランティアを募る状態にもなっていた、という訳である。そしてウェイティング・リスト上、少しずつ順位が上がっていくものの、やがて搭乗が始まると、"ひょっとしたら、今日帰れないんじゃないか?"と焦りの気持ちが増す。と共に、"これは不可抗力。その結果、一日遅れの帰国となれば、シカゴでの休日が出来るではないか?それも悪くない、でも月曜の朝、打合せだよなあ。。。"と正反対の気持ちも交錯する。幸か不幸か、搭乗が始まって10分ほどだろうか、リストの先頭に名前が現れると、ほどなく名前を呼ばれ、そして搭乗と相成ったのである。予約時、眼下のアメリカの景色を楽しもうと窓側を確保していたのも、こうなっては無意味な状況。座席はC、窓側2人掛けの通路席であった。さらには、この時、搭乗口で待たされた結果、お土産を買う時間まで失ってしまったのは大誤算であった。搭乗券を手にした私は、一旦、お土産を買おうと、最寄の店へと走るが、キャッシャーには5人ほどの列。これは断念するしかないと、搭乗口へと戻った。殆ど、最後の10人ほどの中に混じり、搭乗したのである。久々に搭乗する、米系キャリアの国際線。機体は、旧い機種に変更となったとのアナウンスがあり、そのせいか何とも狭く、機内エンタテインメントも制限あり。予約時、ANA機が既に満席だったので仕方がないのだが、こちらも満席での出発となったのである。そして機内はというと、離陸後すぐに隣の方が窓のシェードを閉められて、お休みモードに入ってしまったので、外の景色を遠めに見ることも叶わず、またエンタテインメントも番組が少なく、これと言って気になるものはなし。そしては食事も言わずもがな。すっかり楽しみを失った私は、窮屈な格好をしながらも、連日の移動の疲れもあり、実によく寝ていたのである。よってあまり機内での印象がないのだが、最後の最後で再びの誤算。それは、シカゴでお土産を買えなかった失態を、機内免税誌に目につけた'Made in NY'のチョコレート、それに託していたのであるが、まさかのことに買いそびれてしまう。注文しようと、フライトアテンダントを呼んだ時には、「成田到着まで2時間を切ったので、終了しました。」と、。。。すっかり安心して、寝すぎてしまったのである。航路上、北米大陸を後にしてから、おそらく4時間ほど寝ていたのかもしれない。過去にも、それほど寝てしまったことは記憶にないのだが、既に日本も目前のところまで来ていたのであった。結局、Duty Freeも何のお土産の袋も手にすることなく、成田に到着したのである。気がついた時にすぐにやる。そして、先延ばししない。それが機会を失わない行動術だ。そんな仕事でも言われそうなことが、出張土産にも当てはまってしまうとは。。。しかし、この海外出張土産の一つがまた、仕事上の潤滑油にもなることを考えると、大失態だったなあと、改めて思う次第である。PS. とは言いつつ、実は前日、唯一、テネシー州ノックスビルでチョコレートを買っていたので、辛うじて最悪の事態は免れたのであるが、数が足りなかったこと、そして特に世話になった人へのお土産を買えなかったことが後悔。そして勿論、今回ばかりは、家内へのお土産も無しということで、許してもらった次第である。
2011.10.29
コメント(0)
-

2011年10月再びの米国(1) シカゴ・オヘア空港にて
現在、米国イリノイ州、シカゴのホテルの一室。現地時間で間もなく朝6時になろうかというところ。この日も、時差ボケの影響で5時前には目が覚めたのであるが、あと6時間ほどの後には、雲上の人となる。出発を前にして漸く、ブログに文章を記す気持ちの余裕を持つに至った次第である。前週の韓国への出張から中2日、慌しく仕事の整理と出張の準備をして、10月16日に日本を飛び立った目的地は、ニューヨーク州のAlbanyアルバニー。その後、毎夜、飛行機で移動してチェックイン、チェックアウトを繰り返し、ピッツバーグ、ミネアポリス、シカゴ、ノックスビル、そして再びシカゴ、と乗り継いだ国内線の搭乗回数は8回に上った。とりあえずは無事仕事を終えて、とは言え勿論宿題も多く、その対応やら出張報告やらを考えると気も重くなるのだが、一旦それらも傍らに置いて、ジャズを聴きながら、出張の最後で初めて、リラックスしている。やはりシカゴと言えば、ジャズ。10年以上のブランクの後、今年2月に久々に出張した米国、その時、シカゴから入国するにあたりそんなことも思っていたが(関連ブログへ)、今回初めてシカゴの地に足を踏み入れて、それを実感した。空港のコンコース、カフェで寛ぐ人々の傍らではジャズの生演奏、そしてターミナル間を結ぶ地下にも路上奏者が、またシカゴの地下鉄のホームでもクラリネットの音が響いていた。というわけで、ホテルの部屋の中でも、TV番組でなく、ジャズをお供にすることに決め、そのままベッドに身を横たえたのであった。非常に心地良いのよい朝である。部屋の窓の外には、オヘア空港の景色が広がる。真っ暗な空港には、早朝にも関わらず、飛行機の離発着の音が響き、休んでいる暇はない、そんな感じである。そして、それは米国のビジネスマンも同じ。機動的に小型機で移動し、持ち込みの荷物も搭乗口で預けて、到着後に搭乗口で受け取る。"UNITED EXPRESS"など、命名されているとおり、スピード第一である。今回の出張においても、8回の搭乗のうち7回までもが小型機。機械でセルフチェックインすると搭乗口へと急ぎ、到着後は荷物を受け取ると、そのままレンタカーか、シャトルバスへと駆け込む。一方、チェックインで荷物を預け、バッゲージクレームで数10分も荷物を待った私は、その分時間を浪費し、そんな点でも現地同僚に多少なりともストレスを与えたところだろう。「何でそんなに荷物が多いの?」とか、「もう一回り小さいと持ち込めるのに、...」とか、聞こえてもくる。スピーディに国内を移動し、顧客の元に向かい、またホテルへとチェックインする。空港やカフェでは寸暇を惜しまず、WiFiに接続して、仕事のフォローアップ。月曜から金曜まで、現地スタッフと行動を共にしてみて、スピード感覚の違いを実感した。朝早くから夜遅くまで、そして頻繁な移動と、本当に良く働く。それがあるからこその、長期のバケーションなのだろう。そんな環境においては、宿泊出張とは言え、荷物の小型化がポイントだ。今年3回目の出張にして、漸くそれに気付かされたのである。そういうことを考えたりもした今回の出張、これから振り返って、ここに記しておこうかと思う。とは言え、前回のNY出張の記事も、端緒についたままなのだが、ボチボチゆっくりと綴っていくつもりである。そして、外に目をやると、空は明るくなり、管制塔に朝日が赤く影を映す(下)。私もいよいよ帰国に向けて、動き始めようと思う。 (・・・一部、帰国日の夜、加筆)
2011.10.22
コメント(2)
-

18年ぶりに訪れたNY (5)トラウマとの訣別
18年ぶりのNY、記事は前後して前回の記事で出国してしまったところだが、今一度滞在中の時間に戻って振り返り。それは18年という長いトンネルだった。憧れのNY、ブロードウェイ、エンパイアステートビル、自由の女神、、、。大好きなミュージカルを満喫し、映画の本やビデオをスーツケース一杯に買い込んだ(未だに封を開けていないものもある)のは18年前。その最後の最後にどん底に落とされ、失意の涙でNYを後にした記憶。以来、何度かアメリカの地を踏むことはあっても、トラウマになった悪夢の地を再び訪れることは無かった。それどころか最初で最後のNYの記憶、再びそこを訪れることも無いだろうと殆ど信じてもいた(当時の記事)。それを打破するキッカケを作ってくれたのは仕事での機会。顧客が出展する有望な展示会、それにあわよくば翌年自らも出展する可能性を探るつもりでNY行きを決めたのは自分自身。その決断を前に18年前の記憶も蘇ったのだが、そんなことに拘ってはいられない。現地の同僚も合流して行動を共にし、顧客とも会うことで、過去の記憶を上書きし克服するチャンスだと思った。展示会、そして顧客との面会、そこまではビジネス。その場所がたまたまNYであって、実際それがフロリダであろうが、シカゴであろうが関係ないのだが、過去の悪夢をひきずる私にとって、それらの時間は過去と現在とのギャップを埋めてくれた。夜、タイムズスクエアを歩き、ロックフェラーセンターの展望デッキに上り、1日早くNYを後にする現地同僚との最終日には、セントラルパークに面して佇むフリック・コレクションで時を過ごした。そういう積み重ねが私自身をNYの呪縛(大袈裟だ)、緊張から解き放ってくれたと言ってもいいだろう。 別れて1人となった後、18年前には訪れることのなかったメトロポリタン美術館を訪ね、夜9時の閉館まで約6時間ほど身を置いた。海外では美術館が身も心も落ち着かせてくれる。ましてやそれがメトロポリタンとあれば、なおさらのこと。ブロードウェイではお気に入りのミュージカルも上演されていたが、そんな余裕もなかったしで今回は封印。それでも次にまたこの地を訪れる予感を胸に「次回こそは!」と劇場街を歩いた。もうトラウマも振り切ったと確信した。結果的には最後(前回記したように)出国前に緊張のシーンがあって、恥をかきつつも最後まで油断することなく、徹底できたことで、しっかり悪夢と訣別、克服できたと思う。もう大丈夫。
2011.04.06
コメント(0)
-

18年ぶりに訪れたNY (4)出国土壇場でのトラウマ再燃
18年ぶりのNYは3泊5日の出張。仕事面では上々、プライベートでは18年前の悪夢を払拭し、意気揚々と帰国の途につこうというところ。しかし最後の最後、JFケネディ空港にてトラウマ再燃、ちょっとした騒動を起こす。それは国際線ターミナルの手荷物検査。例によって履き物からコートにベルト、PCをカゴに取りだし、ポケットは空、最後に航空券やパスポートまでもカゴに入れ、満を持してボディスキャンに。そこで引っ掛かったのだろう。荷物を受け取れない状況下、X戦スキャンを通った荷物を目で追っていたからだ。それでもなかなか出てこぬ荷物。コート類や持ち込む鞄とか出てきたが、先にX戦スキャンに通した筈のPCや小物が出ない。と、視線の先、私の1人前の男性(一見南欧風)が自らの鞄にPCやら小物を1個1個詰め込んでいる姿が映る。その瞬間、18年前のトラウマが甦り、そして2年間のパリ赴任で養われたスリへの警戒心が目覚めた。自然体で荷物を詰める姿、それこそスリの特徴。赴任直後、発射直前のTGV車内で鞄をスラれた悪夢も甦る。PCを鞄に詰め込んだ後ほどなくしてカゴが空っぽになると、私の中で躊躇していもたのが確信に変わる。これは一大事、パスポートも搭乗券も入れられたに違いない。そのままどこかのゲートかランウンジに消え去られる前に捕まえなければならない。ボディチェックを終えた私は、必死の形相、取り逃がすまいと、猛然と短いエスカレータを駆けあがる。靴も履かず、靴下のままで。そして上り切ったところで、’Excuse me!’と連呼し振り向かせた。そこで何と言ったのか今では覚えていないが、無我夢中だった。’Please show me your luggage. You put my PC ! Could you open your luggage ?’などと言ったに違いない。突然の乱入者に不機嫌そうな表情をしつつも、私に促されるまま鞄を開けた男性、そして'It's My PC !!'と私に見せる。鞄を覗き見るが、他にPCは無く、私のパスポートらしきものも見当たらなかった。なおも不機嫌そうなその男性に向かって、’I'm sorry.’と言う私も納得いかない表情だった。おかしいなあ、ここで引き下がる訳にもいかない筈だと思いつつ、エスカレータへと振り返り、X線スキャンを見下ろすと、そこに見覚えあるものがあった。PCもそしてパスポート等の貴重品を入れたカゴも出てきていた。その瞬間、ます安堵したのは言うまでもない。あわせて先走って問い詰めた自分の行動をやむをえなかったと納得させつつも、男性にとってはとんだトバッチリ。不愉快な思いをさせて申し訳なかったなと、心の中で同情した。今度こそ自分の荷物を鞄に詰め、靴を履くと、たった今上り下りしたエスカレータを荷物を持っ上り、搭乗フロア、免税品ショップへと向かっていった。歩いていて足裏がヤケに痛いということに気付いた私は、搭乗口近くの椅子に座ると靴を脱ぐ。するとどうだろう、靴下が赤く染まっていた。そして靴の中敷きまでも。おそるおそる靴下を脱ぐと痛い筈、足裏が切れていた。それはエスカレータを靴下のまま駆け上がった時に起こったに違いなかった。そこにあるエスカレータは、そのままドン!!と重いスーツケースを載せられようが、ビクともしない強度と鋭さ。その硬い溝と山が刃となり、いわば強靭な刃物と化したようなものだった。後で見て、靴下で上ったのでは仕方あるまい、と納得する。応急処置として、キオスクで薬付きのバンドエイトを購入すると、傷口に貼った。以上、最後の最後で乗り越えたと思ったトラウマが再燃し、お騒がせとなったが、念には念を入れて行動し、問題無いと安心できればそれでいい。18年前のNY、そして9年前TGVで味わった苦い思い出は決して繰り返さない、その一心での行動はやらねばならない。機を逸さない、そしてそこで遠慮して後悔することだけは避けたい。そして、無事に帰路の飛行機に搭乗。往路と同様に空いた機内、通常すぐに窓を下ろすところ、周囲に乗客がいないのをいいことに外の景色を暫し楽しんだ。
2011.04.06
コメント(0)
-

18年ぶりに訪れたNY (3)長いNYの1日にトラウマ払拭
18年前、初めてニューヨークを訪れた時、ジョンFケネディ空港からエアポートシャトルに乗り、マンハッタンに入ったのは夕暮れ時。当時、車窓の両側に初めて見上げるニューヨークのコンクリートジャングルには、ただただ息を呑んだものだ(関連ブログへ)。そして失意の帰国に、再びNYの地を踏むことは無いだろうと思った。あれから18年がたち、この日、空から俯瞰したマンハッタンの摩天楼群。その圧倒的な迫力に息を呑んだ私は高揚した気持ちのまま無事入国、NYへと帰ってきた。緊張感を持って、タクシーへと乗り込むとマンハッタンへ。大きな違いは、前回遊びだったが、今回は仕事だということ。前回人間不信に陥ったトラウマもこの地で仕事をするという使命感にかき消され、流れゆく景色を眺めた。時計の針は、日本時間では深夜になろうというところ、現地時間ではまだ午前10時台。この日、午後から仕事に入ること、そして夜にはビジネスディナーも予定されていたこともあり、それから始まる長い正念場に気を引き締め、高める。はっきり過去のトラウマを気にしている余裕は無い。そしていよいよ間近にマンハッタン島の摩天楼を臨み、それが徐々に近づいてくる中にエンパイア・ステート・ビルをみとめると、NYに来たとの意識も自然と高まる。海底トンネルを抜けて、マンハッタン島に顔を現すと、狭い通りの両側を摩天楼が壁を作って並ぶ。と、かつて息を呑んだ筈のその光景も、18年の年月がそれを掻き消してしまったのは自分のでも意外だった。ヨーロッパや高層ビル林立する中国を旅し、そして現在の日本でも、もはや摩天楼自身がさほど珍しくなくなったということだろう。ホテルにチェックインすると、先にNY入りしていた現地同僚と合流。食事をした後、NYの空気に慣れるのも兼ね、3キロほどの道のりを展示会会場まで歩いた。これが徹夜もどきの老体に後で響いてくる。夕刻より出展している米国のお客様メンバーとディナー。イタリアン、そしてワインは美味、しかし肝心の会話については英語への対応力が欠落し、頭の回転も何とやら。会話を理解する以前に、睡魔を堪えそれと格闘する自分。とうとうお客様の目の前で船を漕ぐ状態に。。。(ドイツのケルン以来)長い長い1日。漸くにベッドに入る時間、日本では既に翌日の太陽が空高く上がってしまっている時間となり、とにかく眠たい一心。トラウマがあったことさえ忘れ去る18年ぶりのNY初日の記憶。
2011.04.06
コメント(0)
-

18年ぶりに訪れたNY (2) ミシガン湖、エリー湖を経て、いざニューヨークへ
年度末の3月30日、約12時間のフライトを経て訪れたニューヨークへのアプローチ。最後にそこを訪れた時には、すっかり打ち沈んで、その地を後にしたものだが(関連ブログへ)、あれから18年。再びその地を訪れる私を、ニューヨークは感動的なクライマックスを以って、迎え入れてくれたのである。その時間を振り返ってみることとする。その始まりは、夜が明けた薄明かりの中、最初に眼下に飛び込んできたミネソタ州の銀世界。その寒々として景色も、陽が高くなっていくにつれて、だんだん明るくなり、やがて眼下には、青々とした五大湖の一つミシガン湖が広がる。それは、日本で言う湖の感覚を遥かに超越して、まるで海の上を飛んでいるようような感覚でもあった。(下左:ミシガン湖の輪郭が眼下に←下右:ウィスコンシン州アップルトン付近、中央奥に凍ったウィネベーゴ湖) (下左:ミシガン湖東岸←下中:眼下はまるで海←下右:ミシガン湖西岸) そしてミシガン湖上空を過ぎて、ミシガン州へ入ると、ほどなく五大湖のもう一つ、エリー湖上空へと至る。エリー湖に目にした光景で驚かされたのは、湖上に浮かぶ氷。それは冬の間湖面が凍っていたという証だろうか、溶けてバラバラになった氷(下左)、そしてエリー湖東岸に張り付いた氷(下中)は、まさにこの時期だったからこそ出会えた景色だろう。そして、そのエリー湖東岸の町、エリー上空(上右)をペンシルベニア州へと入ると、長い空の旅もいよいよ最終章。静かにニューヨークへのアプローチ、その瞬間を待った。その間、窓から眺める外の景色に、特筆すべきものもは無かったのであるが、いよいよ東海岸の海岸線が視界の先に入り(下左)、それがだんだん近づいてくると、そこにまさかの景色を発見する(下中、右)。 海に流れ込む川に浮かぶ大きな中州のような地形、それがマンハッタン島であり、その先に浮かぶ小さな島に"自由の女神"らしき輪郭を確信すると、俄然、興奮度が高まり、私の顔は窓に張り付く。そして、ついに予想だにしなかったクライマックスを迎える。それは、まさに圧倒的なインパクトで私の目に飛び込んできた。まっ平らなマンハッタン島に黒く林立する摩天楼。特にその先端部のロウアー・マンハッタン、海に面して張り付くように聳え立つ摩天楼に、まず息を飲む。そして、やがて眼下にセントラル・パークの全容が広がると、ついにマンハッタン島の全貌を視界に収める(下)。 セントラル・パークの一角にはメトロポリタン美術館、そしてミッドタウンの摩天楼群に、ロウアー・マンハッタンの摩天楼、さらには、その先のエリス島と、リバティ島には自由の女神像(下)。ニューヨークの全貌を一望にする、その圧巻の光景をカメラに収めることが出来たのは、本当に幸運だったと思う。そして、その直後に、機内放送で電子機器の使用を禁止するアナウンスが流れたのである。 その後、ジョン・F・ケネディ空港を上空から俯瞰し、その周囲の湿地と海の景色の中にはめ込まれた景色にも、思わずシャッターを押したい気持ちにさせられたのであるが、それは脳裏に焼き付けたのであった。そして、一旦、海上に飛び出して旋回した飛行機は、徐々に高度を落とすと、無事、ニューヨークへと着陸したのである。18年ぶりのニューヨーク。入国審査を済まし、タクシーでマンハッタン島へと向かう私の脳裏には、上空から目の当たりにしたマンハッタン島の光景が強烈に焼きついたままで、その興奮は、その日、1日を通して抜けることはなかったのである。(つづく)
2011.04.04
コメント(0)
-

18年ぶりに訪れたNY (1) 出国。震災の影響は如実に!
大震災後の復興作業、そして深刻な電力不足。それに伴う企業活動の鈍化は、身近にも感じるところで、色々な催し物や会議が中止になることも珍しくないのだが、そんな状況下の年度末30日、私はニューヨークへと飛び立つ。それは、傷心のままその地をあとにした1993年以来、18年ぶりのことであった。(関連ブログへ)ニューヨークへの出張。金融でも商社でもない電気業界に身を置く私にとって、そんな日が訪れようとは、到底考えられないことであったが、数ヶ月後に東京で開催される担当するイベントの成否に直接的に影響する案件があり、出張と相成ったわけである。とは言え、周囲の自粛ムードもあり、一旦はそれを諦めていたのだが、あとに後悔することのないよう、前に進むことを決心する。それは、出発直前のわずか6日前であった。 原発事故以来、外国人の日本からの脱出や、海外からの渡航自粛、さらには海外航空会社の便数削減など、ニュースで聞かされていたことがあり、さらに国内での自粛ムードに、震災後の交通機関への影響、等々、経済活動へのインパクトも危惧されていたところ。実際に今回、海外出張してみて、そんな現実と影響を肌身に感じることとなる。迎えた3月30日、フライトは午前11時。通常であれば、自宅からさほど遠くない駅から、成田エクスプレスで一気に空港まで行くところ、この日は朝5時半起床、そしてJRと私鉄を乗り継ぎ、地下鉄の水天宮前まで乗り入れ、東京・箱崎のシティターミナル(通称TCAT)からバスで成田空港へと向かったのである。かつては、航空会社のカウンタもあり、そこで搭乗、出国手続きも出来たTCATだが、それも無くなって以降、TCATを利用するのは初めてのことであった。そして、いつもより時間をかけて到着した成田空港の出国カウンタだが、そこに普段見慣れた手続きを待つ長蛇の列は無く、搭乗するANAのカウンタへあっさりと入っていくと、殆ど待たされることなく搭乗手続きは終了した。本来、他にも多くのフライトがあり、混雑している筈のターミナル内は客足もまばらで、飲食店や売店エリアも混雑とは全く無縁と言ってもいいような印象だった。そんな状況下、一体いかほどの乗客がNYに行くものだろうかと、思ったものだが、搭乗口に辿りついて、隣のシカゴ行きの乗客と合せても、随分と少ないなと驚く。そして、実際に搭乗してみて現実を見る。エコノミー、3人掛けの通路側の席の私の隣2席には乗客はなく、周囲を見回しても、連れと隣同士に座っている乗客を除くと、3人掛けあるいは、4人掛けのシートを1人で占拠する、そんな状況が広がっていたからである。想像するに、搭乗率は30%台底々だったのではなかろうか。ある程度、少ないだろうことは予測していたのだが、まさかこれ程まで酷い状況とは思ってもいなかった。その光景は、定期航路として、とても航空会社の採算に合わず、収益への影響が甚大であろうことは、明白であり、これでは、航空会社も、また日本の経済活動も、収縮してしまう、と思ってしまった。 さらには、乗客の中にすぐに外国人を見つけられないほどで、それは多くの外国人ビジネスマンも観光客も日本を訪れていないことを裏付けていた。またクルーまでもが、国際線でありながら、全て日本人という、通常考えられない状況だったので、また驚いた。どこかの航空会社が、韓国のインチョン空港で外国人クルーを日本人クルーに交替して、日本に入るというニュースを耳にもしていたが、それと共通する状況をそこに見たわけである。そしてそれら光景は、4月2日のNY発の帰国便でも共通で、同じようにクルーは全て日本人、そして30%台底々の搭乗率、乗客も殆ど日本人という状況だったのである。今や、自粛ムードが経済活動を停滞させるという危惧も叫ばれているが、成田-NY間の飛行機の中に見た光景は、まさにそれが早くも現実のものになっているように思えたのである。実際、我が社においても、震災以降、海外からの顧客や仲間を迎い入れての打合せがキャンセル、延伸となり、メドも立っていないが、こんな時期こそ、自ら海外に出て行くことで、日本の元気を発信し、ビジネスの活性化を図らねばならないだろう。今回見た光景から、そんな思いを強くした次第である。さて、NYまでの12時間強のフライトは、13時間の時差を逆戻りする。夜のタイムゾーンを飛び続けて、再び迎えた3月30日の朝、窓のカバーを上げると、飛行機はちょうどTWIN CITY(ミネソタ・ツインズの由来もそこにあるのだが)、ミネアポリスとセントポールの上空にさしかかっていた。氷結した窓の外、眼下には、3月末というのにまだ雪に覆われた世界が広がっていた。 そして、ここからNYまでのフライトは、眼下の景色の変化が旅の友となるのだが、引き続き記していくこととする。(つづく)
2011.04.03
コメント(2)
-

2011年冬・米国出張(8) サンフランシスコで日本を考え、日本を見る
2011年冬、久方振りの米国出張も、この日、帰国日を迎える。最後まで狂い続けた私の体内時計は、一度も現地時計に合うことなく、この日も朝2時に起きてしまうが、それでも前日までのアメリカ東海岸時計では朝5時。その意味では、1週間を通して、大体このあたりの時間で一定していたとも言えようか。 最終日、サンフランシスコを飛び立つ飛行機の時間は午前11時前。そして、カリフォリニア州はサンタクララ、まさにシリコンバレーの中にあるホテルに宿泊したものの、その地の雰囲気を殆ど肌に感じることなく、ホテルを出発したのは朝7時。前夜、現地同僚が予約してくれていたリムジンが、まだ日の明けない7時前から玄関に付けて私の到着を待っていたのであった。サンタクララからタクシーでサンフランシスコ国際空港(以下SFO)までは100USD以上。それに対して、リムジンは確か82USD。安い上に、ゆったりとエグゼクティブ感覚を味わえるのがいい。しかも、ホテルのコンシェルジェでリムジンを頼むと100USD以上の値段が提示されていたので、直接予約したことで、その差額からチップ代も出たというものである。重い荷物をトランクに積み込むと、私を乗せたリムジンは、夜が明ける中をSFOへと向かったのであった。前日サンノゼ国際空港に降り立った私が、この日SFOから飛び立つ。その2つの国際空港の距離が近いことに驚かされたのは、ホテルを出てわずか40分ほどでSFOに到着したからのこと。その間、リムジンのドライバーとの会話が弾んだことも、時間を短く感じさせられた要因。私が日本人であることを知り、「沖縄のことをどう思うか?」に始まった日本の話、その背景にはそのドライバーがアフガニスタン出身だったこともあり、色々と社会問題について率直に語り合ったものである。日本の景気、そして就職難、晩婚少子化に伴う人口構成と高齢化社会の問題、その一方で外国人労働者として、近年東南アジアから看護士や介護士を受け入れる状況、しかし一定の期間に試験に合格する必要がある等、永続的に働くにはハードルの高さがあること、等々。そんな中で、「日本のPolitical refugees(政治難民)の受け入れ態勢は?」といった質問もあり、頭をひねりながらコメントしたものだが、そんな話題となったのもそのドライバーが混乱のアフガニスタンから逃れてきたという苦難の過去の裏返しゆえのこと。今ではアメリカで平和な生活を送っているという彼、そこに機会を与えてくれたアメリカの包容力があるのかもしれない。それでも母国アフガニスタンを愛しているという彼から、両親の住む故郷に毎年帰っているということを聞くと、嬉しくもなるのであった。日本でも外国人労働者受け入れが待った無しの一方で、外国人が多く入ってくることで独自の文化が希薄化している国々もあるという現実も語られ、なるほど単に外国人受け入れと言っても、匙加減も重要だなあと考えさせられたものである。さて、午前8時前に到着したSFO、搭乗カウンタはまだ閑散として、日本行きの飛行機の搭乗手続きが始まっておらず、だいぶ早すぎたようである(冒頭写真、下左)。こんなことならリムジンにちょっとサンフランシスコのダウンタウンまで走ってもらっても余裕だったのかな、とも思ったもので、以後、出発までの約3時間を空港でゆっくりと過ごす。 そんな中、出国フロアを歩いていて、片隅に目にしたのが、日本の陶磁器や茶道具の展示の数々。まさかサンフランシスコでそれを見ようと思いもしなかった茶碗や水差、茶壷(右上)。それらの説明に、思わずにやりとしてしまう横文字が並ぶ。Iga(伊賀)、Tokoname(常滑)、Shigaraki(信楽)、Raku(楽)、...とあり、中でも目立ったのが"Gyokuso Kilns, Kyoto area, Japan"。京焼にGyokusoなんて聞いたことが無いなあと思っていたのだが、後で調べてみて、どうやら、それは高松の玉藻焼であることを確信する。TamamoをGyokusoと呼んでしまったところが、知らない人が訳したのだろうことを物語っているが、しかも場所までKyotoとなっているので、細かくチェックが入っていないようである。玉藻と言えば、別名玉藻城とも呼ばれる高松城(関連ブログへ)。そして、その地は、武者小路千家にゆかりの地。千利休から数えること3代目宗旦の息子たち、宗左、宗室、宗守がそれぞれ表千家、裏千家、武者小路千家を起こし、三千家が始まるが、宗守が仕官していたのが、高松・松平家である。そこから連想するに、次期家元の千宗屋さんが活躍されているアメリカの地でもあり、武者小路千家から出品されていたのかもしれない。そんな最後のアメリカでのひと時を過ごすと、今回のアメリカ出張もいよいよ終わりである。真っ青な空の下、飛行機が飛び立つと、通路側の自席から、窓越しに目に入ってきたのは、初めて目にするサンフランシスコのダウンタウン、そしてゴールデン・ゲート・ブリッジ。街を歩く時間は無かったが、こうして振り返れば、思い出深い1週間であった。(終わり)
2011.02.05
コメント(2)
-

2011年冬・米国出張(7) デンバー~サンノゼ、遥かなる大西部
この日、デンバー国際空港を飛び立ったのは13時過ぎ。定刻より1時間以上遅れての出発となる。デンバーから、この日の目的地カリフォリニア州サンノゼまでの飛行時間は、2時間40分。その飛行ルートは、コロラド州からユタ州、ネバタ州上空を通ってカリフォルニアに入るというものである。この区間、実は、今回の出張における飛行ルートにおいて、私が一番楽しみにしていた区間であるが、それはアメリカ西部ユタ州の砂漠地帯の光景を目にできるからに他ならない。というのも、全米において私の最も好きな州が、アリゾナ州とユタ州であり、そこに見る荒涼とした砂漠、そして自然の造形と言える奇岩や、川の浸食により出来たスケールの大きい景色の数々は、まさに遥かなる大西部、ジョン・フォード監督の世界と重なる。(右:ユタ州東部、Green Riverが切り裂く岩塊)そんな楽しみにしていた区間であるが、私にしては迂闊だったのが、予約の際に、窓側を指定していなかったことである。そして、ノックスビルでチェックインした際には、この区間、既に窓側に空席は無かったのである。しかし、それにめげることなく、再びデンバーの搭乗口カウンタで窓側の空席状況を尋ねたところ、私の願いは通じ、空席があったのは幸いであった。そして実際、デンバーで諦めなかったことが、2時間40分のフライトを、エキサイティングな時間に変えてくれたのである。デンバーを飛び立ったユナイテッド航空機は、雪をかぶるロッキーの山々を越え、そしてユタ州の浸食された台地と寒々した砂漠地帯の上空を飛ぶと、やがてネバタ州の荒涼として砂漠地帯を経て、最後に雪に覆われたシエラネバタの山々を越えて、緑溢れる明るい土地、カリフォリニアへと入る。ユタ州上空を通過するにあたっては、南部のレイク・パウエルや、グランドサークルと呼ばれる国立公園群の一つでも垣間見たいとも期待もしていたが、シートポケットに入った機内誌中の路線図から、ちょうどユタ州の中央部を横断するように飛行することを知り、その期待は潰える。しかし、それでもなお、眼下の景色は、実に変化のあるもので、自然とデジカメのシャッターを押さずにはいられない私であった。もっとも、国際線のように、ルートマップと現在地を示すような、案内でもあれば、時々に目に留まる景色が、一体どのあたりなのか、すぐに分かっていいのだが、残念ながら、路線図を見ながら、大雑把に今、このあたりだろうか、などと想像するしかない。カメラに収めた景色も、とりあえずはユタ州の景色、ネバタ州の景色として、記憶されたのであった。しかし、世の中、便利になったものである。そんなカメラに収めた写真や、見た光景の中には特徴的な景色がある。飛行ルートから、Google Map上に、その景色と似たところを探す作業をしたところ、断片的ではあるが、それらの景色の場所を特定することが出来たのである。(コロラド西部~ユタ州東部:台地を刻む造形美。この後冒頭写真) (ユタ州の砂漠の景色の変化) (荒涼としたネバタ州、Goldfield北部) (左:砂漠に輝くブルーの泉(右下)が印象的なネバタ州の鉱山SilverPeak、右:カリフォルニアとの州境の町Dyer) (左:カリフォルニアへ、右:シエラネバタの山々) (いざサンノゼへ。左:ミラートン湖、右:サンルイス貯水池) シエラネバタを越えると、緑が広がり、そして家々が集まり車が走る、まさしく町が、眼下に入ってくる。そして、燦燦と輝く太陽の光がまぶしい。そこにある世界は、寒々とした東海岸の景色とはまるで正反対であり、またこの日、テネシーを飛び立ち、ミズーリ、カンザス、コロラド、ユタ、ネバタと眼下に目にしてきた景色とも、まるで異なる別世界のようであった。サンノゼ空港に足を下ろしたのは、私にとっては初めてであった。時間は、デンバーからさらに1時間逆戻りして、午後3時前だったろうか。そして、空港の外に出ると、そこは春、いや初夏を思わせるような青空が広がり、開放的であった。(下:サンノゼ国際空港) シリコンバレーの玄関口でもあり、辺りを歩くビジネスマンにネクタイをしている人など目にしない。現地同僚も、「今ではここを訪れるビジネスマンで、ネクタイを締めているのは日本人くらいだろう。しかも、今日はカジュアル・フライデーだ。」と口にすると、『郷に入りては郷に従え』、それまで纏っていたコートを脱ぎ、そしてネクタイも外した。そして、この日の大陸横断と、カリフォルニアの陽光に、すっかりリゾート気分になりそうなところ、出張最後の仕事、現地法人との打ち合せの場へと向かったのである。
2011.02.04
コメント(0)
-

2011年冬・米国出張(6) ノックスビル~デンバー、大平原を眼下に
かつて初めて訪れたアメリカの地を無我夢中に旅したのも、早や20年以上も前のこと(関連ブログへ)。当時、旅の楽しみと言えば、飛行機から眼下に眺める、広大なるアメリカの台地。そして遙かなる大西部の景色だった。そんな過去の記憶との再会、その記憶が呼び起こされるのも、今回の出張も5日目のこと。この日、テネシー州のノックスビルを朝9時に飛び立ち(右)、向かう先はコロラド州のデンバー。そして、そこで乗り換えてカリフォルニア州のサンノゼへと飛ぶ、1日がかりの大陸横断は、まさにアメリカを体感する時間だったと言ってもよかろう。シカゴから入国して以来、ピッツバーク、フィラデルフィア、ワシントンDC、ノックスビル、と訪れた地。それらの街に一歩の足跡を残すことなく、移動する日々の私にとっては、空から眺めるアメリカの景色が、今回の出張では最大の楽しみ。従って、国内線に搭乗するに当たっては、窓側を確保するのが鉄則。そして、ノックスビルからデンバーまでの約3時間半の長いフライトにおいても、搭乗口のカウンタにおいて、辛うじて窓側をゲットしたのであった。ノックスビルを飛び立った飛行機は、テネシー州からミズーリ州を上空を経て、カンザス州、ネブラスカ州の大平原をデンバーへと向かう。離陸後、しばらく下界の景色もすっかり雲に隠れてガッカリしていた私だが、ふと気がつけばアメリカのまっ平らの景色が広がっていた。それは、かつて『オズの魔法使い(1939)』の舞台、カンザスを訪れた時(関連ブログへ)にも見た景色。農場の円型模様(下左)は、当時の私にも新鮮だった。 そして、カンザス州の北隣、当時、いつかは訪れようと思いながら訪れることのなかった、ネブラスカ州への想いも頭をよぎる。青年期を古きアメリカ映画や西部劇に感化された私にとって、ネブラスカと言えば、オマハOMAHA。そして、西部開拓期のマイルストーン、ユニオン・パシフィック鉄道の起点となったのもオマハだ。オマハから西に延びた鉄道が、やがてカリフォルニアから延びるセントラル・パシフィック鉄道との結合し、大陸横断鉄道として結ばれるが、それは、巨匠セシル・B・デミル監督の『大平原Union Passific(1939)』にも描かれているところ(忘れてしまったが)。そして、皆が知る"線路は続くよどこまでも♪"も、まさにこの鉄道労働者の歌だ。 そんな光景を遮るものなく広がる大平原の中に思い浮かべているうちに、やがて外の景色に雪を認められると、そこはもうコロラド州。そして、雪景色の中、ロッキー山脈の山影を、遠く反対側の窓に見ながら、デンバー国際空港へと降り立つのであった(下)。デンバー到着は、時計の針が2時間逆戻りして10時半。その地は、まさにカンザスを訪れた時以来、約20年ぶりのことであった。当時、利用したコンチネンタル航空のハブ空港でもあったデンバーは、今やユナイテッド航空のオンパレード。コンチネンタル航空とユナイテッド航空との合併しより誕生した、新生ユナイテッドを象徴するかのように、駐機する元祖ユナイテッドの機体群に混じって、尾翼にコンチネンタルのマーク、そして機体には"UNITED"と記された、飛行機が並ぶ光景が、また印象的であった。
2011.02.04
コメント(2)
-

2011年冬・米国出張(5) テネシー州・ノックスビルでの1日
日本では季節の節目となる節分。今年は毎年恒例の豆撒きや恵方巻には無縁、そしてそんなニュースを目にすることもなく、テネシー州ノックスビルでその日を迎える。時差ボケの影響と、この日の業務へのプレッシャから、朝4時には起床。携帯電話に、父親からの節分の由、福を呼び込むメールを受け取ったのはその30分後のことであった。実は、まさか私が米国にいることなど想像していない父親にとっては、その後で私が日本を離れていることを知って驚くのであるが、起床したばかりのところで知らされた節分に、新たな気持ちで1日を始動する。前夜の飛行機遅延の影響もあり、ノックスビル空港近くのホテルにチェックインしてからまだ4時間しか経っていなかったが、睡眠時間3時間で目を覚ますと、栄養ドリンクでパワーを補給。そして、その日の資料の最終準備にかかると、それを終えたのは8時前、何とか間に合った。この日のお客様との打合せは丸1日の長丁場。素早く身支度を整えると、1階に下りて軽く朝食。お客様がピックアップにやってくる8時半までのわずか10余分のまさにExpress Breakfast。そして、最後、コーヒーを飲みながら、その時を待っていると、この日初めて会うお客様が訪ねてきた。そこに現地同僚も加わると、そのまま3者コーヒーを飲みながら、リラックスした雰囲気でビジネスの話に突入。といっても、ここはイントロダクション。それでも途切れることのない話にあっと言う前に15分ほどが経つと、いざ打合せの場所へと車で向かったのである。ある意味、我々にとってはビッグプロジェクト。途中、ランチを挟んでのこの日のミーティングは、8時半のピックアップに始まって何と9時間。最後ホテルまで送ってもらい、そこで再び仕上げのコーヒーを飲みながらの3者ラップアップ。再開を誓って分かれたのは、17時半のことであった。この日、寝不足もあってか、直前2日間の打合せと比較すると、顧客の話す英語にキャッチアップできないケースが多く苦戦したのだが、現地同僚にだいぶ助けてもらった。そして同時に、緊張感から開放されてか、一気に眠気と疲れに襲われる。この日、幸いだったのは、打合せの後で、次の目的地への移動が無かったこと。当初はこの後に極寒のミネアポリスに飛ぶことも目論んでいたのだが、顧客との日程調整が付かずにキャンセルになっていた。連日の移動に、前日この地に到着したのが深夜になっていたことを考えると、その時間からの移動が無くて良かった、と心底思ったものである。さて、ノックスビルで宿泊したホテルは、空港まで歩いても15分ほどと思えるほどの近さにあり、周りの景色もいかにも空港の近くといった感じで、これと言って何もない。連日、空港近くのホテルに宿泊し、空港と顧客との間を行き来する日々の中、この夜は唯一、街の空気を吸いに行くチャンスだったに違いなかったのであるが、翌朝も8時台の飛行機に乗るとあっては、そんな余力は残されていなかった。小1時間ほどの休憩の後、私と同僚の2人がディナーに向かったレストランは、ホテルから歩いてほんの5分ほどのところに立つ、Ruby Tuesdayというアメリカン・レストラン。私はその名を聞くのは初めてだったが、実は、全米では有名なレストランで、WEBを見てみると、900店舗近くを展開しているという。テネシー大学のキャンパスの近くで生まれたという、そのレストランの始まり。その記念すべき第1号店こそが、実は私達が訪れたノックスビル空港の近くにある、そのレストランだったのである(下左)。それを教えてくれたのは、この日のお客様であった。そして、滞在4日目の夜にして漸く、まさにアメリカという感じの、リブステーキを胃袋に入れたのであった。(オーダしたのは、ハーフサイズ。それで十分だった。) 食事をしながら店内を見回していると、前日、ワシントンダレスからノックスビルに飛んできた飛行機のキャビンアテンダントの姿も。。。きっと毎日、ノックスビルに飛んできているのだろうか、実は、その飛行機のクルーも同じホテルに宿泊していて、そしてここRuby Tuesdayが最寄のレストラン。お決まりのコースなのかもしれない。昨夜も、飛行機が遅れなければ、ここで寛いでいた筈だろう。さて、この夜、Ruby Tuesdayでディナーをしていなければ、決してその名が目に留まることもなかっただろう、その名前。翌朝、ノックスビル空港でチェックインの手続きを済ますと、さすがは地元、早速その名が目に留まる(上右)。また再び、アメリカの何処かで、その名を目にすることがあれば、この夜のノックスビルのレストランのことを思い出すに違いない。PS. ノックスビルKnoxvilleという地名、実は今回の出張を機に初めて知ったのであるが、その周囲を見てみると、あるある。エルビス・プレスリーゆかりのナッシュビルNashville始め、 Greenville, Asheville, Louisville, Huntsville, Evansville,...。こんな発見をするのもまた、面白い。
2011.02.03
コメント(0)
-

2011年冬・米国出張(4) ワシントン・ダレスでのStupidな悪夢(2/2)
この日、いかにもLuckyとも言えるフライトの遅れで、フィラデルフィアからワシントン・ダレス空港に入った私と現地同僚の2人が、一転して、Stupidな悪夢に見舞われるとは、予想だに出来なかったことである。テネシー州ノックスビル行きのフライト情報を示す、Departureの電光掲示板、それを恨めしくも、何度、眺めたことだろう。ワシントンダレス空港の、小型機専用のゲート。通路を挟んだ両側に4つ配置されたそのゲートには、United Expressと機体に記された小型機がそれぞれに2機、駐機し、Expressという名前の通り、機動的に離発着が繰り返される。まさに1ストップでスピーディに目的地への飛行機に乗り換える乗客、その光景は私の感覚的には、電車の乗り換えの如くである。その背景には、飛行機社会のアメリカ、そして、都市が集中する東海岸の事情。そこでは、近距離を小型機で頻繁に結ぶ、その機動性がきっと求められているのだろう。つまり、ノックスビル行きの飛行機も、小型機であることを理解するのであるが、ともかく、ゲートを行き交う人々の光景を目にしながら、傍らのバーで、リラックスしていた私達2人である。その間、現地同僚が手にするBlackberryには、フライト情報の変更のメールが飛び込んで来る。17:45とされたフライトは、まずは18:05に変更、そして18:10、さらには18:30。。。ゲートには、まだ飛行機がおらず、到着機の遅れがそのまま遅延となったのである。カウンタからも再三の遅延を告げるアナウンスがあり、さすがに疲れの出てきたところ、バーを出て、ゲートの椅子で休むと、時差ボケと寝不足、そして連日の移動に、ついうたた寝を繰り返す私であった。そして、なかなか飛行機が到着しないところで、悪夢のように、到着機がキャンセルとなったとの連絡。そして、フライト時刻も、20:05と発表されたのである。オリジナルのスケジュールが17:13だったので、この時点で約3時間の遅れとなる。そして、この瞬間、ノックスビルでディナーをすることを諦めた。限られた選択肢、ゲート近くのハンバーガー・ショップに入ると、コーラとチーズバーガが、この日のディナーとなる。そこで食事する人の多くは、同じ飛行機を待つ人々だ。そして、出発1時間ほど前の19時過ぎに立ち上がり、Departureの電光版を見ると"Depart 9:10p"、すかさず同僚のBrackberryにも新たな遅延情報が飛び込んだ。しかし、既に乗るべき飛行機は、ゲートの先に配されていた。そして、遅延の理由に驚愕した。それは、「フライトアテンダントがいないので、飛べない。今、フライトアテンダントの到着を待っている。」というものだった。そして以降、同じ理由を繰り返し聞かされることとなる。ワシントンダレス空港という大きな空港にあって、ユナイテッド航空には、小型機に回せるフライトアテンダントの1人も居ないのか?と、内心、その理由に呆れてしまった私である。ともかくフライトアテンダントを待つこと数時間、やがてそのフライトアテンダントが、ジョージア州のサバナSavannahから飛んでくることを知らされるのだが、その間、遅延情報が続いた。もしかしたら、このまま飛ばずに、翌朝になるのではないか、との心配も頭をよぎりもしたのだが、漸く待ちわびた瞬間が訪れた。それは、ワシントンに到着してから待つこと5時間のこと、漸く、ゲートへと足を運ぶと搭乗機に乗り込んだ(下)。 ワシントンダレス空港を離陸した時には、既に時計の針は22時。そして、テネシー州ノックスビル空港に到着したのは23時30分。フィラデルフィア郊外の顧客のもとを出てから、実に10時間を要した長旅。それは、日本からアメリカ西海岸まで飛んで来る時間と変わらないじゃないか、と呆れてしまったのだが、とにかく同じ日のうちに到着してホッとしたのであった。すっかり静まりかえった、ノックスビル空港。そこは、水と緑が溢れた、とてもきれいな空港であった(下)。その一角に座るクマさんに癒されると、バッゲージクレームで荷物を受け取り、空港近くのホテルへと向かうシャトルを外で待つ。静寂の中、外気はおそらく氷点下で冷たいが、雪の無い景色を見るのは、滞在3日目の夜にして初めてのことであった。 ホテルにチェックインしたのは、まさに日も変わろうとする時間。そして漸く、長い長い1日が終わったのである。
2011.02.02
コメント(2)
-

2011年冬・米国出張(3) ワシントン・ダレスでのStupidな悪夢(1/2)
この日、深い雪に覆われた、フィラデルフィア郊外の小さな田舎町にある顧客を訪れた私と現地同僚の2人が、その地を後にしたのは、13時20分。2時間ほどだろうと目してした打合せが、白熱して3時間以上に渡り、最後はフィラデルフィア名物の"フィリー・チーズ・ステーキ"を食しながらのランチ・ミーティングとなったのは、嬉しい誤算。しかし、それが、この日の悪夢の幕開けとなる。(右:顧客の駐車場で)この日、フィラデルフィアから、ワシントン・ダレス空港を経由して、最終目的地のテネシー州ノックスビルKnoxvilleに行く飛ぶ予定だった私達。その旅程は、フィラデルフィア14:55発-ワシントン・ダレス15:55着/17:13発-ノックスビル18:41着というものである。顧客のある田舎町からフィラデルフィア空港までは少なくとも50分。1時間前にチェックインと荷物預かりを行うには、遅くても13時前に出発したいと考えていたのだが、現実は、「もう間に合わないだろう」という状況下での出発となる。日本の国内線の感覚では、15分前までのチェックインでも搭乗できるものだが、米国ではその感覚はまるで当てはまらない。というのも、国内線といっても、一つの大陸。ヨーロッパ域内を移動するより遙かにスケールが大きく、全米の空港の数は何と600。そのうち国際空港やハブとなる空港の場合、それ自身の規模も大きいため、ゲートに行くまで時間、さらには荷物検査の時間を考えると、1時間前までにチェックインするのが安全というのが、現地同僚の考えであった。特に、私が大きなスーツケースを運んでいただけに、荷物預かりの締め切り時間が鍵になると思われた。さらに、フィラデルフィア空港の場合、考慮しなければいけなかったのが、レンタカーの場所が、空港ターミナルから、かなり離れていることで、そのため、その移動時間として、送迎バスで少なくとも5分以上を見込んでおく必要があったのである。そういうわけで、9割以上、絶望だろうと思いながらも、かすかな望みを信じて空港に車を走らせたのであった。この日の天気は曇り、時々小雨、そして空港が近づくにつれ雲が低くなっていた。濡れた路面に注意しながら急ぎ、フィラデルフィア空港のレンタカー・リターンに到着したのは、13:59。トランクからスーツケースを取り出し、ターミナルへのバスストップに先に向かう私、その一方で、レンタカーの精算を待つ同僚。そこにいたのは、「お前が飛行機に間に合おうが遅れようが俺の知ったことではない」といった風に、ノロノロと自分が決めたペースで仕事をするレンタカーの従業員。しかし、辛うじて次の連絡バスに間に合った。そして、小走りにチェックインカウンターに到着したのが、搭乗40分前の14:15。機械に通すと、"TOO LATE"との表示、と同時に、カウンターの女性から、「ワシントン行きの飛行機はDelayしていて、15:15発になった」と。。。それは、まさに、願ったり叶ったりで、天は我々に味方してくれた。というのも、2人ともFIXチケットだったため、乗り遅れた場合には、新たに航空券を購入する必要があったからで、助かった。一方で、それはワシントンでの乗り継ぎ時間が短くなることも意味していたため、代替案も提案されたが、到着時間が22時くらいになるとあって、予定通りの飛行機で飛ぶことにしたのである。搭乗券に記された搭乗時刻は、14:35。荷物検査を通過すると、広いターミナルを息を切らして走るが、搭乗口にはまだ乗るべき飛行機は到着しておらず、面食らう。しかし、おかげで、無理だろうと思われたお土産屋での買い物も出来、フィラデルフィア・フィリーズのトレーナーを購入。さらには、ワシントンでの乗り換え便も17:45に変更されたことが告げられたので、心配された乗り換え時間にも余裕が出来た。と、ここまでは、まさに万事順調に運んでいたのである。結局、フィラデルフィア空港を離陸したのが、15:40。機体は、シカゴ-ピッツバーグ間と同様、またしても50人乗りほどの小型機で、ワシントン・ダレス空港へのアプローチに当たっては、不安定な気流のため、かなり揺られたものだが、無事に到着した。私の革靴の中は、汗だく、しかし通路を挟んで座っていた男性は、揺れがあっても終始、平然と足を組んでいたのが印象的であり、それが私を落ち着かせてくれたとも言えよう。 さて、飛行機は小型機専用の駐機場に停まり(上)、そこは地上1階のターミナルのゲートに向かってスピーディにアクセスできるように4機ほどが停まれるようになっていた。そして、ターミナルに入り、まず最初にノックスビル行きのゲートを確認すると、それは幸いにも、通路を挟んで反対側のゲートにあった。そして、出発までの暫しの時間、ゲート隣りのバーで、ビール休憩することにしたのである。(つづく)
2011.02.02
コメント(0)
-

2011年冬・米国出張(2) トンネルを抜ければ、ピッツバーグ
この日、ピッツバーグを発ち、フィラデルフィア空港の近くのホテルにチェックインしたのは夜8時半。降雪は無いが、既に降り積もった雪で、真っ白な景色が暗がりの中に、一層、輝きを増す。積雪量は、ピッツバーグよりも多い。そして、部屋に入り、空港から聞こえてくる飛行機の離着陸の音を耳にしながら、その日の出来事を振り返っていた。前夜、"ice pick"と予報されていた、この日の天気。高速道路を走るゆえに、レンタカーを運転する現地の同僚も、この日、何とか天気が持ち応えたのに安堵する。周囲は雪景色だが、すっかり除雪された高速道路を順調に走行すると、一番大事なピッツバーグ近郊のお客様に早めに到着、そして打合せも良好であった。そんな中で、後悔したことは、良くあることだが、シャッターチャンスにカメラを携帯していなかったことだ。朝10時過ぎ、ピッツバーグ空港も近いホテルを出発した私と同僚の2人は、これと言って特筆すべきことのない景色の中を、順調に高速道路を走っていた。今回、ピッツバーグを訪れたと言っても、ホテルはダウンタウンから遠く離れた場所、しかも訪れる客もピッツバーグから離れた場所ということを聞かされていたので、その街の景色を見ることは無いと思っていた。しかし、突然、それが目の前に現れたのは、走り始めて20-30分ほどのことだったろうか。それはアメリカでは珍しい、トンネルに入ることに始まる。"FORT PITT TUNNEL"と記された名前から、かつてそこに、"FORT PITT"という名の砦が置かれたのであろうと連想させられるのだが、それはまさに"FORT(砦)"というに相応しい、建物のような入口が印象的なトンネル。そして、一直線に長く延びるトンネルだった。『トンネルを抜けると、...』という表現、それがピッタリ当てはまるように、川に架かる橋に飛び出した眼前に突然現れたのは"Skyscrapers(摩天楼)"。横で運転する同僚から、「ピッツバーグのダウンタウン」と知らされて、初めてそれと認識する。と同時に、写真を撮りたいと思ったものの、この時、後部座席のカバンの中に入れていたカメラを取り出せるような状況になかった。そして実際、そこから展開する、時間にして何10秒かの光景は、2度と訪れることのないシャッターチャンスであった。「アメリカの景色はどこも同じで面白くない」と語る同僚の会話を聞き流し、カメラの無い状況に歯がゆさと後悔を感じつつも、私は目の前に展開する光景を目に焼き付けていたのである。どんよりした冬の空、聳え立つビルの屋上から、水蒸気がモクモクと吹き上がる光景は、まるでニューヨークのマンホールから吹き上げる蒸気と重なる。それが、ビル群のあちらこちらで見られるのは、印象的な光景であり、そこに、私のイメージの中にある、古いアメリカの風景が現れたような気がした。ちょうど2つの川に挟まれた三角州のような形で飛び出したところに立つ摩天楼群、それをかすめて走ると、目の前に現れるのが、まさに桑田真澄投手がマウンドを踏んだピッツバーグ・パイレーツのスタジアム、PNC PARK。再び川に架かる道路は、そのスタジアムに沿うように、グルリとカーブを切ると、スタジアムは車窓の間近、手が届くような距離にあり、私はそれを目に焼き付けたのであった。そして帰路、今度はカメラを手にして、シャッターチャンスを待った私の前に、再び同じ光景が現れることはなかった。"FORT PITT TUNNEL"のある山肌には、ケーブルカーが走るのが見え、「きっとあの場所からピッツバーグの町を見下ろすと最高だろうなあ。」と思いつつも、そんなチャンスは望むべくもない。私にとってのピッツバーグの思い出は、車窓の景色として記憶されることとなった。その一方で、カメラに収めた写真もある。それは、お客様の打合せを終えた帰路、来た道をピッツバーグへと向かう途中、岩肌に見られた、大きな氷柱の連続。それは鍾乳洞の中に見る景色が地上に出現したかのようなもの。それはこの時期だからこそ、遭遇することの出来た景色だったと言えよう。 さて、空港で買ったポストカード(冒頭写真)、それは私の記憶を呼び起こす貴重な証。しかし、"トンネンを抜ければ..."の景色も、YOU TUBEで検索してみると、出てくるではないか。勿論、そこに私の見た同じ景色は無いのであるが、それを再生するには十分に思えた。つくづく、世の中、便利になったものだと思う。
2011.02.01
コメント(2)
-

2011年冬・米国出張(1) シカゴからピッツバーグへ
シカゴと耳にすれば、すぐにお気に入りのフランク・シナトラのスインギーな歌声が、自然と流れ出してきては、口ずさんでしまう私である。♪Chicago, Chicago, that toddlin' town / Chicago, Chicago, I will show you around - I love it...♪ と、シナトラの歌声を脳裏に再生しながら、この日、シカゴ行きの飛行機に搭乗しようとは、ほんの10日ほど前には予想だにしなかったことである。仕事でアメリカを訪れるのは、約14年ぶりのこと。過去の出張は、専ら、オレゴン州ポートランド(関連ブログへ)だったので、シカゴへと飛ぶのは初めてである。遠い昔には、"暗黒街の顔役"アル・カポネが支配したシカゴ、またニューオーリンズに始まるジャズがミシシッピー川を上って最後に辿りついたのもシカゴ。そんなことを思い浮かべると、何か感慨深さと一方で緊張感も感じていた私である。その地に向かっていること自体が不思議な気持ちだったと言ってもいいだろう。夜間の飛行、アメリカ本土に深く入り込み、モニター上に表示されるフライトマップ上に、アルフレッド・ヒッチコックの"北北西に進路をとれ"でも有名なマウント・ラシュモアや、"未知との遭遇"にも出るデビルス・タワーの文字を認めると、初めてアメリカを訪れた23年前、そのあたりを訪ねた記憶も懐かしく思い出される。しかし、幸か不幸か、この日の最終目的地はシカゴではなく、ピッツバーグ。あの桑田真澄投手がメジャー登板の夢を実現した、ピッツバーグ・パイレーツの本拠地でもある。さて、シカゴでの入国審査。予想通り、長蛇の列にはなったが、昨年より義務付けられたESTA(電子渡航認証)が導入されたせいだろうか、心なしか入国審査も多少はスピーディになったようにも感じられたものである。少なくとも、両手の指紋採取や眼鏡を外しての写真撮影など、旅行者もだいぶ慣れているようで、導入当初のころと比べると、手際よく対応されているように、見受けられた。そして、やがて自分の順番が来るのだが、あまりにも心構えをしていなかったせいか、いろいろな事を聞かれて多少面食らう。"For Business"と答えたことに対して、「何のビジネスか」(「ビジネス・ミーティング」と回答)、「何についてのビジネス・ミーテングか?」、「何という会社名か?」と、質問は続く。これまでパリやドイツで、殆ど会話を交わすことのない入国審査に慣れっこになっていたのが、いけなかった。すっかり我に返ると、一生懸命答えて無事、入国を果たす。入国審査を終えると、一旦、荷物を受け取り、次は税関検査。まるで「徹底的に調べてやるぞ」という体で、手ぐすね引いて待ち構える検査官へと、旅行者を振り分けるのは、税関の係官の裁量次第。検査官を横目に、係官に歩み寄り、税関申告書を手渡すと、Exitへ行くようにとの指示。とりあえず安堵した。そして、トランジットゆえに、ここで再び荷物を預け直すのだが、このことが一つの制約を生んだことも覚えておきたい。それは、成田出発直前の免税店でのことだが、今回の出張で世話になる現地同僚へのお土産として、日本酒を買おうと、会計を目前に、トランジットを理由に、買えなくなってしまったことである。つまり、一度、降機することで、必然的に、乗り継ぎする飛行機に液体を持ち込むこととなり、搭乗前に捨てることになるという事実だ。モノレールでターミナル2へと移動すると、早速に手荷物検査。その成田の出来事もあって、この場面で、お酒没収という悲しいことは起こらないのだが、結局、お酒を買っていけなかったので、ある意味、これは学習である。検査では、当然のように上着を脱いでカゴに入れると、靴も脱いでトレイへ。そして、レーンのコロコロのところまで、自分で全ての荷物を押し進めていく。そして、最後の荷物を押し込むと、ゲート通過。必ずどこかが反応してボディチェックを受ける羽目になる、日本国内のどこかの空港の機械と違って、何のアラームも無く通過したのは、きっと感度が最適化されていたからだろう。時計を見れば、2時間以上あったトランジット時間も、気がつけば、次の搭乗まで50分ほど。私にとって、旅先ではお決まりのポストカードを購入すると、暫しベンチで疲れた身体を休め、ピッツバーグ行きの飛行機の搭乗時刻を待つのであった。シカゴ・オヘア空港のターミナル2は、予想に反して、通路も狭く、天井もさほど高くなく、古い印象だった。そして、ピッツバーグ行きの搭乗カウンタもまた小さくて、すぐに下へと降りる階段があったのだが、予感は的中。人々の流れに従って、そこに入ると、背後の階段上でゲートを閉める金属音がガチャと響き、意図せずして自分が最後の搭乗者だったことに気付くと共に、地上に出る。そして外気の冷たさ(-6℃)を感じと次の瞬間、その先に前を歩く人々が搭乗する飛行機が飛び込んできた(下)。やはり、小さい飛行機だった。 通路を挟んで、片側2人の12列と13列の計50席の機内は、狭いだけに心もとない。その最後尾13列の窓側に座った私。ほぼ満席で、空席は2席ほどだったが、その1つが私の隣だったのは幸いだった。車輪の格納がすぐ真下にあるようで、それが格納され、また着陸直前にカバーが開いて車輪が飛び出す音と振動を間近に感じたのには、驚かされたもだが、それでも安定飛行だったは幸いだった。離陸直後、眼下に五大湖の一つ、ミシガン湖の雪で白くなった輪郭を見ると、やがて白い雲の中に入って消えてしまうのだが、ほどなく白い雲の下にさらに白い光景が広がっているのに気付かされる。そこにあるのは、川も湖も凍っている(下右)ような、寒々とした光景だ。そんな光景を眺めながら、よくぞこんな時期に来たものだと、思ったものである。 その光景は、ピッツバーグまで続くのであるが、到着するころには青空が広がってきたのは、幸いだった。成田を飛び立ってから15時間半、ついにピッツバーグに到着する。そして、ピッツバーグ、フィラデルフィア、テネシー、サンノゼと、金曜まで続く出張生活が幕を開ける。
2011.01.31
コメント(2)
-
ポートランドの思い出(4) 悲しい知らせに、当時の出張生活を偲ぶ
今年も早や、11月に入り、残すところ2ケ月を切ってきた。月日が経つのは実に早いが、それも年々、加速するようである。私の両親もすっかり歳をとってしまったが、今年の年末年始も、皆が無事で、元気な姿で顔を合せたい、と切に望む。そんな想いは年々強くなる一方である。 昨日までの10月を振り返ると、この月は、まさにお茶会三昧だったと言っても良い。忙しい週末の連続であった。しかし、そんな中、とても悲しい出来事もあった。それは堺に飛び立つ前日のこと。海の向こうから、慕っていた方の訃報が飛び込んできた。しかし、既に半年ほど前に、亡くなっていたという知らせ。やりきれない思いがした。アメリカ西海岸の北部、オレゴン州ポートランド。ローズシティとも呼ばれ、背後に先の尖ったマウント・フッドを臨む美しい町は、今から20年前の1988年、私が初めて海外渡航した地であり(こちら)、縁あって1995年秋から1997年春にかけては、延べ1年ほど滞在させてもらった。最後に訪れたのは、1997年の4月だったと思うが、既に10年以上も前のことになる。亡くなったのは、当時、現地関連会社で、通訳をされていた女性の方である。横浜で育った日本人女性で、アメリカ人男性と結婚されてその地に住まれていた方である。年上の方で、優しい方だったので、出張者や現地駐在の日本人からも、慕われる存在であった。当時、出張者としてホテル(正確にはBest Westernのモーテル)暮らししていた私は、2ケ月ほど米国に滞在して帰国しては、数週間の後、また出国し2ケ月ほど滞在する、といったような生活を繰り返していた。1年の大半を、同じホテルと会社との往復で費やすという生活をしていると、心身の健康を保つことがとても重要に思える。つい働きすぎたり、不規則な食生活とその超ド級な量とから、急激に体重が増えたりもした。事実、最初の数ケ月で、体重が10キロほども増えたりもしたので、夜、ホテルのジム(一人用の部屋で、毎回、鍵をもらって行った)で汗を流したり、毎週1回ダンス教室に通ったこともあった。しかし、日々の心の安らぎという意味では、その方の存在は大きかった。当時、ある製造ラインを構築するプロジェクトを進めるメンバの一人として、派遣されていた私である。現地スタッフと共に、10人弱が入るほどの小さな部屋によく集結して仕事をしていたのだが、その部屋の隅にあった、通訳の方のブースは、私の隠れ家であった。そこで、いろいろと身の上話やら、週末の出来事などを聞いて頂いたりするのが日課であり、また安らぎの時間でもあった。宿泊していたホテルで受付をしていた、可愛いアメリカ人女性のことを好きになって、書いたレターを見てもらい、相手がどう感じるかと意見を求めたこともある。そのアメリカ人女性とお付き合いすることは出来なかったのだが、懐かしい思い出である。また、その方が、横浜・鶴見にある三ツ池公園という、桜の名所に良く出かけていたことを話されていたことがある。それを聞いて、ちょうど桜の時期に帰国した際に、私もその公園を訪れてみた。そして、次の渡米の時に写真データを持っていったのであるが、とても喜んでくれて、PCの壁紙に設定されてくれたのも思い出す。滞在も最後の頃、駐在の日本人、そして多くの日本からの出張者が招待されて、ポートランドとは大河コロンビア川を挟んだ対岸、ワシントン州側にあるその方の家で、バーベキュー・パーティが行われた。既に日も長く、夜8時を過ぎてもまだ明るい時期である。春の暖かい陽光を浴び、デッキに出て、バーベキューを楽しんだ光景は、最後の素晴らしい思い出となった。この訃報の連絡を受ける前日のこと、ちょうどグーグル・アースで、当時働いていた場所や、ホテルのあった生活圏、そして良く車を走らせたコロンビア川のビューポイント"クラウンポイント"あたりをバーチャルツアーしていたのだが、それは偶然だろうか。地図を追っていて、その方が住まれていた地名も目に留まり、懐かしく思い出していたばかりだったので、この日の訃報には声を失ったものである。 この日、当時のことを思い出しながら、通訳仲間だった方にメールを差し上げたのだが、書きながら涙が溢れてきた。惜しむらくは、5年以上もの間、メールの一つも差し上げなかったことである。この日は事務所にいても仕事にならず、夜、当時アメリカで一緒に働いていた上司と二人で、ご冥福をお祈りし、思い出の日々を語り合い、当時を偲んだのであった。安らかに。。。
2008.11.01
コメント(0)
-
ポートランドの思い出(3) クリスマスの過ごし方
アメリカ・オレゴン州のポートランドでは、1995年、1996年とクリスマスを過ごした。その時の思い出である。この時期になると、もうホリデーシーズンで、町はクリスマス一色。そして、私が出張で滞在していたモーテル(ベスト・ウェスタン)の近くのスーパーなどでも、サンタさんの格好をした伯父さんが入口にたって、鐘を鳴らして、募金を呼びかけていた光景を思い出す。1995年、初めてのクリスマスの当日、私は現地アメリカ人の同僚に、ホームパーティに誘われた。誘われたのは、私ともう一人、日本から来ていた出張者の2人である。休日のその日、ランチに合わせて誘われた私達を同僚が車で迎えに来てくれた。既に、その同僚の年老いた母親も同乗していて、クリスマスを家族、皆で祝うというわけである。私達はワインを携えて、その家を訪れた。家には、その同僚の兄弟など、大きなテーブルを囲むだけの人々が集まった。ペットのイグアナも部屋の中を自在に動き回っていた。この日は、皆でワイワイと、一日中、食べて、歓談して、ゲームをして過ごすのである。昔ゲームセンターで見たような懐かしい、しかし立派なサッカーのゲームが、ある部屋の真ん中に設置されてあって、そこの子供と一緒に遊んだ。食卓にあったのは、ターキー。これに、ジャムのようなソースをかけていただく。アメリカではごく当たり前のこのフルーティなソースには、最初、「えっ、肉にジャムをつけるの?」と抵抗を覚えた記憶があるが、食べてみると美味しかった。その日、延々と夜まで続くファミリーのパーティなのだが、数時間ほどいて、我々2人は「仕事があるので」と言って、帰ることにした。その同僚、「楽しくないの?」かと心配顔だったが、そういう訳ではなかった。その日、会社で少し仕事をした後、タクシーでモーテルまで戻り(この当時は足がなかった)、夕食にしようと思ったのだが、実はそれからが大変だった。モーテルの近く、そして数100メートルの徒歩圏内には、いろんな種類のレストランがある。アメリカン、中華、スイス、ケンタッキー、マック、等々。しかし、どこも開いていないのである。マックさえである。良く利用していた、近くのレストランからのデリバリも、この日の午後から休みだった。年末のこの時期、ポートランドはとても冷たく、体感気温(ウインドチルWind Chill)は、信じられないがマイナス30度を越えたりもしていた。朝、起きると路面、そして車の窓もバリバリに氷が張り、道路の木々には樹氷が出来ている、という光景は日常的だった。歩くにも歩けない、気温だ。そんな中、我々2人は、どのくらい歩いたのだろう、レストランやファストフードを求めて彷徨った。そして漸く、ampmだったと思うが、コンビニ(日本ほどには点在していない)を見つけた。今、日本にあるコンビニと比べると、非常にしょぼい品揃えと、雰囲気であるが、とにかく、そこでサンドイッチを見つけた。棚には、品物が殆ど残っておらず、不味そうなサンドイッチであったが、漸くたどり着いた食料。モーテルに持ち帰って、貪り食った。クリスマス当日のランチとディナーの余りにも違う落差。こんなことだったら、そのままアメリカ人のパーティに一日中、お世話になるのだった、と後悔した2人だった。私は、翌1996年もクリスマスを、ここポートランドで過ごすことになるのだが、その時は、日本からの赴任者の家に招かれて食事をさせてもらった。私は、前年同様にワインを携えて伺い、一晩中、お世話になった。前年の経験はもうコリゴリだった。また、この年は、現地の人でメキシコ人と結婚されている方の家にも招待されて、クリスマスのホームパーティに行ったのだが、多くのメキシコ人の親戚が集まっていて、実に賑やかだったのを覚えている。車が何台か入る広いガレージをパーティ会場にして、食べて、歌い、踊り、ゲームしてと、思い返すと懐かしい。
2007.12.22
コメント(0)
-

ポートランドの思い出(2) クリスマス電飾
勤務する会社で、クリスマスの電飾が賑やかになっている。数年前までは、ビルの明かりでサンタを表現したりしていたのだが、今年は、庭の木々にも電飾が散りばめられていて、点滅を繰り返している。サンタやツリーもたくさん設置されている。どうも新しい総務部長さんが赴任してきてから、電飾が始まったようである。今日はクリスマスの電飾についての思い出を書いてみようと思う。華やかな電飾を見ると、初めてこの季節を海外で過ごしたオレゴン州、ポートランドの冬を思い出す。私は、ポートランドで、1995年、1996年と2年続けて、クリスマスシーズンを過ごした。今でこそ、首都圏の住宅街では、サンタや電飾に華やかに飾りつけされた家を見ることは、さほど珍しくない。日本で、クリスマス用に家の飾りつけを始めるようになったのは、せいぜいここ10年以内の出来事だと思う。しかし、それらは私がポートランド滞在中に見た電飾と比較すると、まだまだおとなしい。アメリカ、オレゴン州のポートランド郊外、瀟洒な一戸建ての住宅が立ち並ぶ住宅街、またそれほど瀟洒でなくても、一歩足を踏み入れると、果たしてここは電飾のテーマパークかと見間違うような住宅街というのは良く目についた。そこらかしこの家が、その輪郭を電飾で華やかに点滅させている。そんな中でも特に素晴らしい地域は、有名になっている。そのコミュニティで、クリスマスの飾りつけが入居の条件として義務づけられているところもあるくらいである。そういう場所は、観光名所と化していて、車で多くの近隣住民や遠くからやって来る人々の車列で混雑している。交通規制とかもあるほどだ。一方、日本から赴任していた人々。当然、日本にいる時には、そういうことをしていなかった人々だが、”郷に入りては郷に従え”だ。クリスマス電飾を怠けるわけにはいかない。周囲の家に負けじと年々、気合が入っていた。家の輪郭を電飾が取り囲み、エントランスから玄関口まで電飾の列が走る。芝生の庭も、サンタやソリや動物たちと、ミニ遊園地のごときである。一種、家庭の年中行事だ。そういう情景を見て、私はアメリカという国は、なんと豊かな国なのだろう、と思ったものだ。当時、独身だった私は、狭いワンルームとか、1Kのアパートに住んでいたのだが、似たような生活環境から赴任した人々も、立派な一戸建てに住んでいて、日米の生活環境の差に愕然としたものである。(今も、自分のアパートを見るかぎり、1部屋増えたくらいで、さほどレベルアップしていないが。。。)残念ながら、電飾が点滅する、住宅街の写真というのは、一枚も撮っていないので、ここに掲載できない。ただ、クリスマスシーズンの風物詩として、こんな写真があった。ポートランド郊外のどこかレース場(サーキット)だったと思う。クリスマス電飾の野外展示場のようになっていて、車で定められたコースをゆっくりと走るのだ。会場からは、長い車の列が出来ていて、数10分並んで漸くゲートで、入場料を払うと、そのまま車をゆっくり走らせ、コースの左右に作られた電飾のオブジェや、また(写真のように)ゲート状に設置された電飾などを楽しんだ。いかにも車社会のアメリカならではの催しモノ。赴任していた、上司の家族と一緒に、訪れたのを、久しぶりに思い出した。11年前のことだ。この年、初めてデジカメを使い始めたが、当時は、まだ30万画素だ。懐かしい思い出である。
2007.12.10
コメント(0)
-
オレゴン州シスターズ(2) シェーンとの出会い
1996年4月、シスターズの町を出て約10キロ車を走らせたところで、ロックアウトされてしまった私である。この状況を抜け出すには、私を助けてくれる人との出会いが必要だった。その場所は、高原の田舎道で、交通量はさほど多くないものの、適度な間隔で車の往来がある。私は、シスターズからやってくる車を待った。どういう人が車を停めてくれてくれるのか不安ではあったが、運を天に任すしかなかった。間もなく、遠くからヘッドライトを照らした車を先頭に数台の車がやってくるのが見えた。だんだん、そのヘッドライトが近づいてきたが、どうもヘッドライトは1つ。そして間もなく、それがサイドカーであることが分かった。私は、とにかく、(半信半疑に)親指を立てて、その車にサインを送った。そして、早速、そのヘッドライトを照らしたサイドカーは、私に気付き、停車信号を点滅させて、減速し、私の目の前で停車してくれた。この時、不安感よりも、まずは停まってくれたことが、嬉しかった。さて、そのサイドカーのライダー。フルフェイスのヘルメットを脱ぐと、若い爽やかな感じのお兄さんだった。雰囲気は、今思い起こせば、トム・クルーズのような雰囲気ではなかったろうか。「どうしたのか?」と問われ、ロックアウトされた旨を伝え、一緒にドアが開かないことを確認した。そして、すぐに彼は、私をシスターズの町に連れていくと言う。どうやら、彼は、シスターズの住人だった。「直接、鍵屋に連れていくので、ここに乗るように。」と言い、誰も乗っていないサイドカーの側車の席を整えてくれた。私は、鍵が挿されてエンジンがかかったままの車を置き去りにして、さらにパソコンも入っていたので、この場を離れた隙に、車を奪われてしまうのではないか?との不安も一瞬、よぎったものだ。しかし、私が行かずして、その彼に行ってもらうのはナンセンスな話だ。しかも、これ以上の人は望めないと言っても言い過ぎでないような人だ。私は彼の言うことに従った。サイドカーに乗るのは、この時の経験が、私にとって最初であり、また最後である。サイドカーの側車は、本当に地面に近いところを走る。タイヤの振動が直接、身体に響く感じだった。彼は、まるでマラソンの先導車の白バイのように、低速でていねいに走ってくれた。確か、私の分のヘルメットはなく、高原の風を浴びて、シスターズの町に向かった。サイドカーに乗っているというのは、照れくさいような、恥ずかしい気持ちであった。しかも、旅の日本人、不思議なシチュエーションである。さすがに、シスターズの町に入ってからは、人通りもさることながら、観光客もいて、特に信号待ちで停まっている時など、その思いが強くなったのを覚えている。しかし、背に腹はかえられない。また、サイドカーに乗ることなど、逆に幸運とも言える。サイドカーは、シスターズのメインストリートから直ぐに路地に入り、住宅地へ入っていった。と言っても小さな町、メインストリートから数ブロックのところだ。そして、ある家の玄関先で停車し、彼は私をそこの主人、つまり鍵屋の主人に紹介すると共に、そして状況を説明してくれた。彼は、その鍵屋とも顔見知りだったのである。話はすぐについた。私は、その場を立ち去ろうとする、爽やかな青年を慌てて止めて、名前と住所を聞き出し、そして感謝の念を述べた。彼は、サイドカーで立ち去っていった。そして私は、今度は、鍵屋の主人の車に乗り込み、現場に向かうことになった。やがて、シスターズの町から約10キロ離れた現場が見えてきた。するとどうだろう、路肩に停車したウインカーの点滅する私の車の横で、さきほどの青年が私達の到着を待っているではないか。なんと彼は、別れた後すぐに現場に戻り、私の車を見張ってくれていたのである。そして、十分お互いを確認できた距離で、彼は右手を上げて合図を送り、サイドカーのエンジンを噴かせて、走り去っていったのである。そのシーンは、ある日突然現れ、そして役目を終えて何も言わずに去っていく、西部劇の名作『シェーンSHANE(1953)』のラストシーンを彷彿させられた。私は、その姿を、鍵屋の車の中から、ただただ目で追うだけだった。映画では、ワイオミング州が舞台で、背後にはロッキー山脈のグランド・ティートンGRAND TETONが聳えていたが、この時、舞台設定が、オレゴン州のカスケード山脈THREE SISTERSにかわった。そして、馬ではなく、サイドカーで、主人公は去っていった。さて、鍵屋の伯父さんは、手際よく鍵を開けてくれた。払った金額は30ドルだった。私は、少し動揺していたのだろう、鍵屋との別れ際に、またロックアウトしてしまった。が、危うく、鍵屋が車を走り出させようとする前に、泣きついて事なきを得た。「おい、大丈夫かい?」と笑って、鍵屋は再び道具を取り出してきて、鍵を開けてくれた。そして、「今度は、絶対大丈夫。どうもありがとう。」と、礼を言い、鍵屋ともお別れしたのである。私は、何と運がいいのだろうと、思ったものだ。異国の地、しかも誰とも連絡のとりようもない高原の田舎道でロックアウトされてから、なんと1時間とたたないうちに、トラブルは解決したのである。まさに、シェーンと出会えたことに尽きたと言える。その青年には、滞在中のポートランドからお礼の手紙を出した。何だったか忘れたが、日本の民芸品を沿えて。
2007.12.01
コメント(0)
-

オレゴン州シスターズ(1) ロックアウト&ヒッチハイク
オレゴン州ポートランドには、初めて渡米した1988年以来、暫く訪れることはなかった。しかし、仕事の関係で1995年に再訪。そして、1996年にいたっては、1年の半分以上をポートランドで過ごした。1~2ケ月滞在し、数週間帰国して再び出張して1~2ケ月滞在、ということを繰返していた。その1996年4月の週末に訪れた地が、オレゴン州シスターズSISTERS。セントラルオレゴンのカスケード山脈CASCADE RANGEに位置するこの地には、忘れられない思い出がある。そのことについて語ろうと思う。それまで、シスターズという町については何も知らなかった私だが、ここを訪れようと思ったキッカケは、美しい絵葉書の写真だ。THREE SISTERSという名前の山(連峰)と、それを背に広がる牧歌的な風景、この景色に憧れた。地図で調べると、ポートランドから約200キロ南下した場所だ。ポートランドのシンボルと言ってもいいマウント・フッドMt. Hoodを間近に山を越え、セントラルオレゴンの砂漠地帯(アリゾナやネバタの荒涼としたものではないが)にある、インディアン・リザベーション(居留地)を通り抜けて南下していくと、ベンドBENDに至る。この町の背後にはカスケード山脈が連なっている。ここで1泊して、翌日、シスターズを訪れた。山を縫い、丘を越えて約40キロ走り、突然、現れた小さな町が、シスターズ。それは、昔の西部の面影をそのまま残したような町だった。メインストリートは、端から端まで歩けるほどの小さな町である。そしてカスケード山脈の山々が間近に迫る、緑豊かな、のどかな町だった。この町を散策し、食事した(と思うが)のち、この町を後にした。町の周囲には、絵葉書に見るように、牧場があり、牛や羊を多く見た。今、絵葉書を見て気付いたが、ここに写っているのは、アルパカ。当時、アルパカのことを知らなかった私。もしかしたら、羊だと思って見ていた動物が、実はアルパカだったのかもしれない。さて、シスターズからの帰路、REDMONDという町に向けて車を走らせるが、暫く素晴らしい景色が続く。横目にのどかな景色、そしてバックミラーに映る山々の景色に、私は度々、車を路肩に止めた。そして、エンジンをかけたまま、カメラを持って車を飛び出し、いいアングルの場所からシャッターを押した。(写真は、Three Sistersの山々:左からSouth Sister, Middle Sister, North Sister)そして、何度目かに停車した時であった。それまでと同じように、エンジンをかけたまま、車を飛び出した。が、田舎道の路肩だ。その時、路肩に傾くようなに停車していた車の、運転席のドアが軽くしまる音がした。「もしや!」と思ったのだが、時すでに遅し、内側からロックされていた。とにかく軽く閉じたので、完全な半ドア状態なのだが、力づくで開けようとしても開かない。私は、エンジンのかかった無人の車の前で、外に放り出されてしまったのだ。既に、シスターズの町を出てから10キロ。周囲は牧場。車の外で、1人呆然とした。哀れな光景である。たまたま、その場所から数100メートルほど先に、農家が1軒見えた。しかし、いくら田舎と言っても、銃社会のアメリカ、オレゴン州でも当たり前のように銃が売られている。突然、30を過ぎた東洋人が玄関先に現れたらなら、対応を間違えると不測の事態さえ、起こりかねない。ルイジアナ州バトンルージュで日本人留学生がハロウィンに、玄関先で射殺された事件(1992年)もまだ記憶に新しかった。その家にお願いに行くことなど、まず考えられなかった。さて、携帯電話もないし(当時、ポートランドでは、すでに携帯電話を手にしている人も見たが、極めて稀だった)、もちろん、近くに電話ボックもない。私がとりうる行動は、とにかく車を止めることしかなかった。そして、シスターズの町から、鍵屋をここまで呼んでもらうということだった。ただ、一体どうやって車を止めればいいのか、わからなかった。その時、私の中に、ある映画のワンシーンが甦った。フランク・キャプラ監督の『或る夜の出来事 It Happened One Night (1934)』である。クラーク・ゲーブルとクローデット・コルベールが共演したこの映画の中で、ヒッチハイクを試みる有名なシーンがある。自信満々の新聞記者クラーク・ゲーブルが、右手の親指を立て、通る車に向けて構える。しかし、なかなか止まってもらえず、最後は、指を振ったりしてやけくそになる。それをベンチで横になって見ていて、笑い転げるクローデット・コルベール。見かねて、「今度は私が止めてみる」と出てくる。「お前に出来るワケないだろう」と言うクラーク・ゲーブルを尻目に、車が来るなり、いきなりスカートの裾をめくりあげて、車を止めてしまうのである。私は、このシーンを思い出し、意を決した。そして、向かってくる車に対して、右手の親指をつき立てたのである。クラーク・ゲーブルのように、ならないことを祈りながら。
2007.11.29
コメント(0)
-

ポートランドの思い出(1) 初めての海外渡航
アメリカ西海岸北部、オレゴン州ポートランドPORTLAND。シアトルのあるワシントン州との境に位置するこの都市は、バラが市の花であり、CITY OF ROSESとも呼ばれる。このポートランドは、私にとって、アメリカで最も愛着のある都市である。1988年4月、私は初めて海外渡航したのだが、その場所がポートランドであった。その当時の思い出の一端を書いてみる。初めてポートランドを訪れた時、2ケ月半、滞在したのだが、この時の経験は私の人生においては、大きい経験となった。まさに井の中の蛙が、大海に出るようなものであり、良くも悪くも、その後の人生に、勇気と自信(過信と言ってもいいが)を持つキッカケとなったのは確かだ。日本列島の南端、鹿児島で育ち、就職を機に初めて、東京の地を踏んだくらいの私だ。鹿児島の地から見れば、東北や北海道さえも、遥か遠い場所であり、一生のうちに1度や2度か、訪れることがあるだろうか、と思っていた。当時の私にしてみれば、海外に飛ぶことなど、夢にも描いたことがなかったのである。どちらかというと「海外、海外!」と騒いでいる人々に対しては、「わざわざ海外に行かなくても、日本にはたくさん見るべきところがあるじゃないか?」と、冷ややかな目を向けていた私だ。しかし、とにかく、そういう”井の中の蛙”である私にも海外出張する機会が飛び込んできた。当時、頭の中では、海外はまだまだ庶民には手が届かない場所で、またアメリカといえば地球の裏側、飛行機代も高い場所という意識が高かった。そのため、もしかしたら2度とないチャンス、せっかく行くからには悔いのない2ケ月半を過ごそう、と私は決意したのであった。そうと決まったら、あとは早かった。思う存分、楽しむには、英語が出来ないとダメだと思い、英会話学校に通うことにした。幸い、出張日程が決まった後、まだ出発まで1ケ月半ほど時間があった。私は、都内に教室を展開するチケット制の英会話学校を選び、この短期間に集中的に、30回ほど通った。レベルに合ったレッスンが行われている時間にあわせて、新宿、六本木、五反田、赤坂、蒲田、渋谷、横浜、と仕事帰りに休日にと、教室を渡り歩いた。出張中の名古屋でも1回教室に行ったことがある。今思うと、脱帽する。最初の体験レッスンでは、先生が質問している意味も単語も理解できず、自身のレベルに愕然としたものだが、目標のために、とにかく通った。当初、割当てられたレベルの教室でも、なかなか会話に参加できなかった私であったが、何回目かのレッスンでたまたまマンツーマンになったのをキッカケに、ぎこちなくも身振り手振りで会話に参加できるようになった。そして、出発前には、何とか会話する度胸と、外人慣れし、それなりの準備は整った。当時、若くもあり、また好奇心旺盛の時期だった。また、アメリカは、当時親しんでいたアメリカ映画そのものの地。せっかく行くからには、ハリウッド、そして西部劇の名作ゆかりの場所も、行けるものなら行きたいと思った。そして私は、最初の1週間で出来るだけアメリカ慣れし、最初の週末に、ハリウッドに行こうと決意した。そのチケットも予め日本で購入した。そういうことが、さらに私の英会話熱を後押ししたのだ。一方で、初めての海外、田舎の親は心配したものである。この時の渡米は、日本企業の海外製造拠点の立上げということで、100人を超えるであろうほどの出張者が渡米したので、その点では不安感は少なかった。しかし、当時、海外旅行は、まだ田舎においては、現在ほどまでに手軽なものでなかった時代である。地方出身の後輩には、親族総出で見送りされた者や、海外に出張するだけで出世したなあと言われる者もあったと聞く。今思えば、考えられないようなことである。当時、ポートランドへのフライトは、デルタ航空52便。ポートランド経由アトランタ行きである。この年は、バブル絶頂の前年で、まだ会社も羽振りがよかった。私のような若輩も皆、海外出張は決まってビジネスクラスだった。こうして思い出すと、実に懐かしい。
2007.11.28
コメント(0)
-

カンザス州ダッジシティ(4) 無法者の町、牛の集散地
再びカンザス州ダッジシティでの出来事を思い出してみようと思う。1990年10月シカとの衝突事故に見舞われた翌日、無事に代替の車を得たところまでは前回書いた。その後のことを回想してみる。その日、ダッジシティでの滞在に残された時間は、約1時間。日本からわざわざ、カンザスのこの田舎町までやってきたのだ。私にとって、とにかくこの1時間の時間を得たことに感謝し、スピード観光するのみであった。 今でこそ田舎町だが、この町は19世紀末には無法者の町で有名であり、ワイアット・アープが保安官として、治安を守った時期があったことは前回述べた。そして、その歴史を肌で感じとる場所がここにはある。それがブート・ヒル・ミュージアムBoot Hill Museumだ。ここには当時の町並みと建物が復元されている、酒場(サルーン)、ドラッグストア、散髪屋、学校、牢屋、いろいろな店、牛追い人の家、サンタフェ鉄道の線路と機関車、等々。そして、博物館では、ダッジシティの歴史が写真を交えて紹介されている。当然、ワイアット・アープも出てくる。当時のものの展示物の中には、映画でもあったが、ウィンチェスター銃もあった。そして、ダッジシティを舞台にした映画を紹介するコーナーがあり、裏手には、墓場であるブート・ヒル・セメトリーがある。このミュージアムは、表通りである、ワイアット・アープ通りに面している。当時、アメリカの西部を旅していた私は、決まってカウボーイ・ハットを被って、自ら、西部劇の景色の中に溶け込み、その気になっていたものだが、まず日本人を見ることもない土地である(モーテルの人も言っていた)。カウボーイ・ハットを被った日本人が、表通りを歩き、ワイアット・アープ通りの道標をカメラに収めている。そんな光景を見て、走る車の中から大声で笑われたりもしたものだが、気にはならなかった。ちなみに、そのカウボーイ・ハットは、その前年に、アリゾナ州のツゥームストーンTombstone(OK牧場の決闘で有名な地だが)で、タクシーの運転手から贈られたものであった。このあたりの話は、また別に機会に書くことにしよう。さて、Boot Hill Museumを見た後は、ダッジシティの町中で駐車し、少し写真撮影。通りには"DODGE CITY"の文字が目につく。そして、牛の集散地としての象徴だろう、立派な角をもつ牛の像もあった。そんな感じで、慌ただしかったが、ダッジシティを1時間ほど観光し、この町を後にした。帰路は、事故を起こした道路を避け、別のルートで、カンザスの真っ平な平原をウィチタに向けて走った。7時間運転してやってきた、ダッジシティ。観光できたのはわずか1時間だったが、温かい人々に囲まれた、思い出深い滞在となった。
2007.11.19
コメント(0)
-
カンザス州ダッジシティ (3) モーテルでの朝
カンザス州ダッジシティを目前にしての、悪夢のような事故から一夜明けた4日目の朝。まずは早めに朝食をとり、部屋でHertzレンタカーからの連絡を待っていたのだが、連絡がなかった。ウィチタ発デンバー行きの帰りの飛行機は、コンチネンタル航空で17時20分発(当時、デンバーはコンチネンタル航空のハブ空港だった)。この時間に間に合うには、午後1時頃にはダッジシティを出発したいと思っていた。もちろん、ダッジシティには、目的をもってやってきたわけであり、午前中は観光する筈であったのだが、車の手配がつかないことには話にならないし、帰れない。さて、ダッジシティは、昔の西部劇映画には良くその名前が出てくる西部開拓(?)史上、有名な町である。砦が築かれ、鉄道(サンタフェ・トレイル) が通り、またキャトルドライブ(カウボーイが牛の群れを運ぶ)の中継地でもあった。が、あわせて多くの無法者が集まり、ガンファイト(撃合い)の絶えない、無法の町としてその名を高めた。町にはブーツ・ヒルBoot Hillという名の墓場もある。ブーツを履いたまま、ガンファイトで死んでいったガンマンたちが葬られている。そして何よりもこの町を有名にしているのは、"OK牧場の決闘 Gunfight at OK CORRAL"でも有名な、ワイアット・アープWyatt Earpが保安官としてこの無法者の町の治安を守っていたという史実だろう。ジェームズ・スチュワートが主演した『ウィンチェスター銃'73 Winchester'73 (1950)』の中でも、ダッジシティは舞台となっているが、町に入ってくる流れ者たちの銃をワイアット・アープが預かり、町の治安を守っている。そのワイアット・アープもこの町にいたのは数年で、OKコラルのあるアリゾナ州トゥームストーンTombstoneに着任する。そして、西部史上に残るガンファイトでその名を後世に残すのだが、この町のヒーローであることには変わらないのだろう。ダッジシティのメインストリートの名前は、"ワイアット・アープ通りWyatt Earp Blvd."(写真)である。(余談だが、私はアリゾナ州のOKコラルにも行った。)本題に戻る。すでに私の拙い英語で、Hertzと交渉するには荷が重く、状況を打開するには、モーテルの人々に助けてもらうしかなかった。ロビーには昨夜の女性がいたので、さっそく状況を話した。その女性にHertzレンタカーに電話してもらったのだが、Hertzの担当者がまた変わっていて、また最初から説明することになった。前夜の状況が全く伝わっていないようであった。ロビーの女性は、前夜と同じように、私の代わりに電話している理由から説明していた。私自身、荷物が殆どない(リュック1個)ので、さっさとチェックアウトを済ませ、あとはロビーに佇み、今後の対応を進めることになった。無力な私は、モーテルの女性の対応をただ見守り、必要に応じて質問に答えることを繰り返した。宿泊客もだいぶチェックアウトしてしまい、モーテルの従業員も集まってきて、私の状況を知ることとなった。ロビーの女性には、代替車の手配について、Hertzと交渉してもらっていたのだが、すぐ解決できず、時間をおいて何度か電話確認する状況が続いた。問題は、一番近い営業所がどうやら150マイル(240キロ)離れたウィチタ空港であるということらしかった。ウィチタまで事故車を運転してこられないかとの質問もあった。少し太った従業員の男性と一緒に車をチェックしたが、彼が見てもこれはダメだろうとの見解だった。1時間、2時間と時間が経過していき、時計は午前11時になっていた。その間、その男性は事故車を点検修理してくれる、修理屋を調べて連絡をとってくれたりした。雰囲気としては、車を点検した上で、ウィチタまで運転せざるを得ない状況だった。もう観光どころではない感じだった。そして、11時を数10分ほど過ぎたころだったろうか、代替車の手配が出来そうだという連絡が入ったのだ。その従業員の男性が、代替車のある場所まで連れていってくれるという。そして、私はそこで車を受け取り、もうモーテルに戻ってくる必要はない、という。モーテルの駐車場にとめた事故車の処理については、モーテルの人が「(対応するので)心配しないでいいよ」と言ってくれた。私は、モーテルの女性、そしてそこに居合わせた従業員に、感謝の気持ちを込めて何度も、"THANK YOU."を繰り返した。「気をつけてウィチタへ運転して帰るように、そして無事、日本に帰れるように」と見送られ、私も嬉しかった。男性の車(軽トラックだったか)に同乗し、モーテルを後にした。車は、ダッジシティの町はずれの高台にある、ダッジシティのローカルの飛行場に到着した。建物の中に入るとすぐに管制室も見え、まさに個人が使用する飛行場という、小さな飛行場だった。そして、そんな場所にも、Hertzのロゴの入った看板と簡単な窓口があった。通常のレンタカーと同様に手続きをし、保険もフルカバレッジでお願いした(もちろんタルサで借りた際もフルカバレッジだ)。飛行場の建物のすぐ横に、新しく借りる車があった。そこには車は2台しかなかったと記憶している。田舎の飛行場のレンタカーは、都市の空港にあるレンタカーのように新しい車はなく、古く特徴のない車ではあったが、とにかく新しい車を得られた安堵感で一杯であった。飛行場まで連れてきてくれた男性とも、ここでお別れとなった。握手して、感謝の気持ちを伝えた。もう時間は、正午くらいになっていたが、何とか1時間くらいだが観光する時間も出来た。ダッジシティのモーテルの女性、そして従業員の方々には実に親切にしてもらい、本当に助けられた。こういう親切にしてもらった体験は、時を経ても忘れてはならないと思う。
2007.11.04
コメント(0)
-

カンザス州 ダッジシティ (2) POLICEとの対面
1990年10月、カンザス州ダッジシティで宿泊した思い出のモーテルは、BEST WESTERN SILVER SPUR LODGE。その当時の旅行の記録、痕跡を掘り返していたら、そのモーテルのレシートが出てきたが、宿泊費は30.31ドルだった。当時、アメリカを車で旅行していた時は、そのくらいの値段を中心に、たいてい50ドルを下回る金額で、モーテルを泊まり渡っていた私であった。その夜、とりあえずチェックインをしたが、まずはPOLICEに事情を説明するところから始まった。衝突したのはシカではあるが、一応、交通事故である。しかも、事故の衝撃で、車のナンバープレートを始め、ライトかフロントのカバーなど破片を現場に残している。また、レンタカー会社に事故報告をし、保険の申請や代替車の手配を進める必要もあり、そのためにはPOLICEが作成した事故証明書が必要であった。もちろん、その時の私は、ただ動揺していて、そういうことを冷静に考えられる状況ではなかったのだが。さて、ロビーに入ってきたPOLICEは、私と同年代くらいの若い男性とそのアシスタントの女性(2人とも純粋な白人ではないようだった)。もちろんシェリフのバッジを付けているのだが、いかにも警察という人が来るのを想像していた私は、まず安堵した。彼らは、突然、カンザス州の片田舎に現れた不安顔の日本人に対して、実に優しく接してくれた。小さな町である。モーテルの人々とも、顔見知りという感じで、まずはにこやかに会話して簡単に状親を聞いていた。それを見ていて私もなんとなく安心したものである。そして、私に向かい、にこやかに、いつ、どこで、何が起こったのか?について質問された。私も、英単語を考え、選びながら、ゆっくりと口頭で答えていった。現場の位置を正確に言うことは出来なかったので、だいたいの場所(Fordという町を数キロ過ぎたあたり)と、そして、現場を確認せずに、そのままこのモーテルまでやってきたことを伝えた。また、現場にナンバープレートなどを落としてきていることも伝えた(これらはモーテルに到着して初めて事故車を見て気付いたのであった)。また、「シカはどうしたのか?死んだのか?」と質問されたのに対しては、「おそらく死んだと思う。」と答えた。その後すぐ、「それでは車を見せてくれ」ということになり、私は駐車場に止めた車を再び動かし、モーテルのロビーの横につけた。 白のポンティアック・グランダムは、そのスポーティな姿が見る影もなかった。ボンネットがシカと衝突した右側からつぶれて山のように盛り上がり、助手席のドアは開閉不能。右側のライトは破損、そしてフトントのカバーとナンバープレートも脱落という状態。露出したラジエタにはシカの毛らしいものも付着していた。この状態で、翌日、150マイル(240キロ)離れたウィチタまで、走ることなど、考えられなかった。POLICEの2人も、苦笑していて、これは無理で、なんとか変わりの車を手配するか、修理に出さないとダメだろう、と言った。再び、ロビーに戻り、POLICEと事故証明書の作成にとりかかった。まずは、私の個人情報からだ。パスポート番号、住所、米国滞在スケジュール、そして日本の勤務先の連絡先を含めて記入させられた。私も和英辞典を片手に、若い彼の質問に、辞書を引きながら英語で対応した。個々の詳細は、全て彼が作成していく。1時間近くかかっただろうか、とにかく報告書の作成を終えた。そして、彼は何か問題があったらここに連絡するように、と連絡先のメモを置いて、アシスタントと共にモーテルを後にし、事故現場へと向かったのである。別れ際、笑顔で握手し、「Good Luck!」、そして気を付けて日本に帰るように言われ、嬉しかった。Policeが帰った後は、レンタカー会社に提出する、事故報告書を作成する必要があった。事故に対する保険を申請するための書類であり、これは私自身が記入、作成する必要があった。POLICEとの質疑の間に、レンタカー会社にはまず、モーテルの受付の女性にお願いし、オクラホマ州タルサのHertzに一報を入れてもらっていた。その上で、この書類の作成が必要であることを通知されていた。これまで、そういうものを書いたことがなく、ましては英語であるので、適切な表現というものが良くわからなかった。そこで、受付の女性にも助けてもらえるようお願いした。私はロビーのカウンタで辞書を引きながら英文を作成し、それが適切であるかどうかを、その女性に確認してもらった。幸い、その後、訪れる客も殆どなく、その女性はにこやかに、不運な日本人の対応をしてくれ、無事、事故報告書を作成することができた。一方で、代替車の手配についても、レンタカー会社と話をする必要があったので、私は部屋に戻り、(車を借りた)オクラホマ州のHertzレンタカーに電話をかけた。事情を説明し、代替車を準備してほしい旨を伝えた。しかし、私は、電話の向こうで対応する人に、上手に伝えられなかった。何かを言われても、私が理解できなかったりして、すぐに言葉が出てこなかった。そして、「代替車もないし、近くに営業所もないので、(返却する)ウィチタまで運転してくるように」と言われ、電話を切られたのである。そして、また、ロビーの女性の世話になることになる。かわりにHertzに電話をしてもらい、事情の説明から始まった。電話の向こうで、「何で、貴方が電話しているのか?」とも聞かれた風であったが、「日本人である当事者の英語が不自由であるから、代わりに電話しているのだ」と答えて、会話を続けていた。しかし、既に時間は12時くらいになっていた。Hertzも代替車の手配について、その場で確約することができず、結局、翌朝、確認して連絡するということになった。翌朝を待つということになったが、親切に助けてくれた、モーテル、そしてPOLICEの力もあり、何とかなりそうな安心感はあった。その夜の礼をロビーの女性に述べ、自分の部屋に戻った。部屋は駐車場を取り囲むように、1階建ての建物があり、各部屋のドアが直接、外に面している。そのうちの一つのドアをあけて、部屋に入り、その日の出来事を振り返った。長い1日だった。夜、何も食べていなかったので、自販機でスナックを買って食べたと思う(覚えていない)。翌日は、午後、再び、240キロ離れたウィチタまで車を走らせなければならない。夕方の飛行機で、ウィチタからコロラド州のデンバーを経由し、西海岸ワシントン州のシアトルまで一気に移動する旅程だった。翌日の幸運を祈り、眠りについた。
2007.11.03
コメント(2)
-

カンザス州 ダッジシティ (1) シカとの衝突
札幌でシカがマンションに入りこんで、大捕物となったというニュースがあった。シカは森に返される筈だったのだが、収容された動物園で死んでしまったという。きっとショックが大き過ぎたのだろう、かわいそうなことだ。そういう私も1度だけ、シカにかわいそうなことをしたことがある。死なせてしまった(確認したわけではないが、そう思う)。それは、1990年10月、場所は、アメリカ中西部、カンザス州。今思えば無謀にも思えるのだが、冒険心に溢れた若き日の思い出である。その日のことを語ろうと思う。「オズの魔法使いThe Wizard of OZ」の舞台でもあるカンザス州は、遮るもののない大平原だ。空から見ると、いかに真っ平らであるかが良くわかる。その北のネブラスカ州、そして南のオクラホマ州と共に、頻繁に竜巻がよく発生する地帯でもある。「オズの魔法使い」の中でも、主人公のドロシーと犬のトトが、竜巻に巻き込まれて、小人の国、ムンチキンに迷い込む。映画の中で、ジュディー・ガーランド演じるドロシーが、カンザスに帰りたいと涙するシーンを思い出す。さてシカとの出会い、それは4泊6日の旅程で、オクラホマ州とカンザス州を旅行した、3日目のことだった。前夜、オクラオマ州のタルサTULSA空港に一人降り立ち(TULSAはオクラホマ州の文化都市で、スーザン・ヘイワードが主演した同名映画もある)、空港のHertzレンタカーで、白のポンティアックGRANDAMを借りた。この日、午後2時を回ったころだったと思うが、オクラホマ州の小さな町クラレモアCLAREMOREから、カンザス州ダッジ・シティDODGE CITYへ向けて、車を走らせた。距離にして、320マイル(515キロ)の長丁場のドライブである。当時、カーナビなど無い時代である。ランドマクナリー社のオクラホマ州とカンザス州のマップを助手席に、一路、目的地を目指した。そうは言っても、延々と続く真っ直ぐの道を走るのが、かなりの部分であり、難しくはない。単調である。まずは、南はテキサス州のダラスDALLAS,フォートワースFT.WORTHから、オクラホマシティOKLAHOMA CITY、そしてカンザス州のウィチタWICHITAへと南北に貫くルート35に合流するまで約100マイル、のどかな田舎道を走る。この間は、草を食む牛も目につく。しかし、オクラホマ州は、なんといってもテキサス州とならぶ石油の産地。大平原のいたるところで、小さな油井が点在し、そのポンプがせっせと上下運動していた(石油を汲み上げている)。ルート35に合流し70マイルほど走ると、カンザス州で一番の都市ウィチタ(と言っても、日本の地方都市のイメージ。ちなみにカンザス州の州都はトペカTOPEKA、大リーグで有名なカンザスシティKANSAS CITYはミズーリ州で、州境にある)に入るが、この中心部をかすめると、西に進路をかえる。ここから延々100マイル強、進路を変えることなくカンザス州を横断する。この時間帯、帰宅時間とも重なり、交通量も多くなったが、ウィチタを離れるにつれ、交通量も次第に減っていった。やがて、日も落ちて、夜となった。町と町の間が10マイル以上も離れているのは当たり前で、明かりも何もなく、星明かり(月も出ていたかは覚えていない)にのみ照らされた道を延々と走り続けた。その100マイルを走りBucklinという町(町と言っても家が目につくわけではないが)に入ると、最後の右折をきる。この辺りまで来て、漸く道標に"DODGE CITY ○Mile"と出てくる。いよいよゴールのダッジシティは目前で、残り20マイル真っ直ぐ走れば到着、というところまできた。とにかく、大平原の真ん中。右折してからは、前後に走る車もなく、対向車とすれ違うのも数えるほどの回数だった。真っ暗な道、隣に平行してサンタフェSantaFe鉄道が走っているのが分かったが、その時間、電車が通ることはなかった。この日、走ったのは7時間くらいだったのだろうか、私も気がはやった。75マイル(120キロ)くらいに速度を上げ、暗闇の中を急いだ。そして、それは残り20マイルの中間点、Fordという小さな町を過ぎてすぐのところだった。突然、前方左、サンタフェ鉄道から道路の路肩にかけて、2つの光る目が視野に入り、すぐにシカの輪郭がヘッドライトに映し出された。私も驚いて、アクセルから足を離し、少し減速したのだが、一方のシカも、私の車を向いたまま路肩に立ち、微動だにしなかった。車が近づき、このまま、シカを横目に通り過ぎると思ったまさにその瞬間だった。突然、シカが駆け出し、目の前を横断してきたのだった。信じられなかった。急ブレーキを踏んだが、避けられず、シカの右腰(右尻)に衝突。ドスンという衝撃と共に、何かが割れるような、そして落ちるような音。ボンネットもゆがんだ。そして、シカの悲鳴とも聞こえる声が耳に入り、シカは腰から暗闇の草原に跳ね飛ばされた。跳ね飛ばされながらも、シカの両目はこちらを見ているように見えたが、それが悲しそうにも見えて、今でもよく覚えている。一瞬の出来事だった。あまりの急な出来事に私は動揺した。何をすればいいのか判断がつかず、車は速度を落としながらも走っていたが、心の状態を反映したように進路が落ち着かず、暫くセンターラインを跨いで走っていた。また、片方のヘッドライトが破壊したようで、前を照らすライトも暗くなりしかも明るさが揺らいでいた。しかし、回りは真っ暗、気温も下がり、車を止めて待つということはあり得なかった。もちろん携帯電話も無い時代なので、連絡の仕様もない。町はその先10マイルのダッジシティまで無く、とにかく、ダッジシティまで辿りつくことだけしか考えられなかった。そのうち、後続車が追いつき、ピタッとくっ付いてきたが、追い越せない。相変わらず動揺していた私は、呆然としたまま蛇行気味に走行していたので、クラクションを鳴らされた。私は、それでふと我に返り、しっかりしないといけない、と気合が入った具合である。そして、暫くの後、ダッジシティの町の端にある、サンタフェ鉄道の駅に差しかかった。そしてすぐに、ダッジシティの町に入った。やがてすぐに宿泊するモーテルであるベストウエスタンのマークが目に入ってきた。21時すぎだったろうか、ベストウエスタンの駐車場に車を止め、モーテルの入り口に向かった。チェックインの手続きをする以前に、これから何をすればいいのか、というのがまずは心配だった。入り口のガラスの扉を開けるとすぐにチェックイン・カウンタがあったが、接客中で私はそれが終わるのを、落着きなく待っていた。そして、ふくよかなカウンタの女性、彼女にはそれからの時間、大いに世話になることになるのだが、にこやかに私を迎えてくれた。私も、固まりながらも、笑顔を作って、名前と予約している旨を伝えたが、チェックイン手続きを始める以前に、まず言った。I have a problem. I hit a deer ! I hit a deer on the way to the hotel. What should I do ? などと言ったのを覚えている。その彼女は、動揺している私から、状況を再確認し、そして言った。POLICEを呼ぶ必要がある!と。えーっ警察?と思った。何もかも経験したことのないシチュエーション、何をやればいいの分からない。しかも、場所は、アメリカのど真ん中、かつ主要都市から200キロも離れた辺鄙な場所。しかし、無力な自分。ここは言われるままに、従うのみだった。しばらくすると、POLICEのサイレンが近づいてきて、モーテルの前でパトカーが止まった。そして、これから、長い夜が始まることになる。
2007.11.02
コメント(0)
-
NYの思い出(8) 観客参加型ミュージカル
1993年にNYに行った時に見たミュージカルの中で、緊張しながら見たミュージカルがある。『FIVE GUYS NAMED MOE』という、黒人ミュージシャン、ルイ・ジョーダンを描いたミュージカルである。このミュージカルは思い切り観客参加型のミュージカルであった。このミュージカル、出演者は確か6人で、自らバンドで演奏し、歌い、踊る、というミュージカルである。ルイ・ジョーダンというのは、ブラック・ミュージックの神様とも言われるミュージシャンで、その音楽はブルース、R&B、ロックンロール、そしてファンクとして花開いていく。そう言う私も、ルイ・ジョーダンのことは良く知らなかった。シアターガイドに載っていた写真から、ジャズをふんだんに楽しめるミュージカルだろうと期待して、5番街にあるJALチケットセンタでチケットを取った。そのチケット、前から2番目だったろうか、舞台のパフォーマーの表情や汗までがはっきり見える位置だった。最前列に誰もおらず、私の正面は、6人のパフォーマのうちの一人のいわば定位置であり、よく目が合った。実は、私は一番前で観劇するというのが、どうも苦手である。パフォーマーと目が合うとそれだけで緊張してしまい、リラックスできないのだ。JAZZのライブだったが、過去に2回、苦い思い出があった。話がそれてしまうが、少しだけ紹介する。15,6年前だが、独特なスキャットが素晴らしいアニタ・オデイが来日した時だ。当時原宿にあったKEYSTONE CORNERで、私は真正面の席だった。ある歌のフィニッシュで、私はアニタ・オディに人差し指で指されて、見つめられた。私は硬くなり、どうリアクションすればよいか分からず、とっさに視線を外してしまったのだ。その直後、何か言われたのが分かった。私はすぐに周りの人の視線を感じた。以来、そのステージでは、心にその事を引きずりながら、そして目を合わすのが怖くなった。もう1回は、20年前だか、西麻布にあったROMANISCHES CAFE(今、六本木ヒルズが建っているあたりだろうか)に、ジャズピアニストのレイ・ブライアントが来た時だ。私の席は、レイ・ブライアントが真正面で何も遮るものがなかった。ピアノを弾いている表情を、横から見つめるそんな位置だった。しかし、あろうことか走ってきた疲労と、緊張感から、寝てしまったのである。たまに目が合い、実に気まずい思いをし、失礼なことをした。そういう経験もあり、このNYのミュージカルにおいても、目が合うことが自分自身に圧迫感を与えた。しかも、言葉が聞き取れないこともあったが、音楽や展開に溶け込めず、自分自身も全くノリ切れていなかったので、目は合うが、私の方はなんとなく冷めている、そんな感じだったのである。一方、観客はというと、たいへんなノリである。そして、大勢が立ち上がり、舞台と観客とが手拍子と歌で一体となった。そのうち、観客が列をなして舞台に上がり、お客さんが主役となり舞台で音楽に合わせてリズムに乗り、踊る。そんな、とんでもない展開となった。立ちあがっていた観客も、その座席の列が、そのまま舞台へ上がる人々の列に加わり、途切れることなく続いた。その時、まだ私は座っており、左隣に座るカップルも、座って手拍子を送っていた。しかし、一旦その両人が立ち上がって、人の流れに合流すれば、成り行き上、私も立ち上がり、後を追って舞台に上っていかざるを得ない、そんな状況だった。まさに『郷に入りては郷に従え』。私は、その二人が、立ち上がらないことを祈り続け、舞台はそっちのけだった。そして、その思いは通じた。終わってホッとしたミュージカルも珍しい。ノリきれないが、一人だけ冷めているわけにもいかず、乗っているフリをしながら見るというのは、本当に苦痛である。 幸い、それ以降、舞台を見に行って、こんな思いをしたことはない。
2007.10.28
コメント(0)
-
NYの思い出(7) 緊張の日々(2/2)
1993年当時、ニューヨークの地下鉄は怖いというイメージがあった。まだ、落書きだらけの車両が走っていたころだ。そういうイメージも先行して、タイムズスクエアから先端のバッテリー・パークまでバスで行ったりもしたのだが、車の多いマンハッタン、やはり時間がかかる。1時間ほどもかかった。移動距離が長い場合は、やはり地下鉄を使うことになり、結局、4~5回ほど乗ることとなった。実際、一般人も乗っているのだから、そんな怖いこともなかろうと思って乗り込んだのだが、その地下鉄の表情は、曜日や時間帯によって変化した。同じ路線、同じ駅でも、緊張感を感じる時があり、一方でファミリーが多く平穏な時もあった。夕方の帰宅の時間帯や、平日昼間の空いた時間帯は、多少、緊張感を覚えた記憶がある。中でも、地下鉄のタイムズスクエア、ここは多くの路線が入っていて、混雑した駅だが、獲物を狙うハイエナどもが多く、緊張を強いられたものだ。乗り換え通路には、至る所にハイエナがいて、獲物を求めて鋭い目を輝かせていた。またホームでは、黒人のハイエナが群衆の中から頭一つ出して、入線してくる車両の内外に視線を向けていた。私は、乗り換えに自信がなくても、観光マップを広げて確認することなどは当然出来ず、立ち止まることなく、前を見据えてひたすら歩き、正しいルートを見つけたのである。その駅構内にいるハイエナどもは、地下鉄の改札を飛び越えてどんどん入ってくるのである。係員がいるにも関わらず、それもお構いなしに、強面の面々は、堂々と改札を飛び越え跨いでいた。係員はそれを黙認するだけで、無政府状態だった。そういうのを目の当たりにすると、やはり怖いものだった。そういうタイムズスクエアの駅には、2度と近づかないようにと、避けたものだが、一度だけ快速電車に乗ってしまい、目的駅を通り越してタイムズスクエアの駅に入ったことがあった。しまったと思ったが、その時は意を決して、風を切って出口に急いだものだ。しかし、この時は何故か同じ駅と思えないほど、平穏だった。一方、地下鉄の車内では、空いた時間帯のことだったが、背の高い黒人が、缶詰の空き缶を手にカランカラン言わせながら、乗客に小銭を催促している場面に遭遇した。隣の車両から歩いてきて、私は目の前で立ち止ってくれないことを祈りつつ、目線を下にして固まっていたものだ。やり過ごした時は、ホッとしたものだ。あれから14年。現在のNYはどうなのだろうと、ふと思う。私がパリに駐在していた時、パリ北駅(Gare du Nord)のRERのホームの雰囲気が、当時のタイムズスクエアを思い出させることもあった。パリの地下鉄やRERの改札の一部は、扉みたいになっていて、乗り越えて入れないようにしているところもあった(それでも無理やり入る輩はいた)のだが、今のNYはどうなのだろう。多少、興味はある。とにかく、当時のNYの地下鉄には緊張したものだが、地下鉄に乗らなくても凄まれたこともあった。ある日、NUNSENSEというオフ・ブロードウェイのミュージカルを見に行ったときのことだった。劇場が離れていたのでタクシーに乗ったのだが、途中、右折すべきところ、違う方向に走っていった。そこで、そのことを運転手に正したところ、「お前はそう言わなかった。お前が言ったから、この方向に走っているのだ。お前がそう言った。(力を込めて、You said !と繰り返す)」と凄い剣幕。身体の大きい黒人に凄まれるとやはり怖い。私も、争うつもりもないし、勝ち目もないので、「私が悪かったので、こっちに行ってください。プリーズ」とお願いした。このように当時のNYでは、観光するにも、ミュージカルを見に行くにも、緊張を強いられたものであったが、見たいものは見たいという気持ちが、私を動かせていたのである。
2007.10.16
コメント(0)
-
NYの思い出(6) 緊張の日々(1/2)
再び1993年ゴールデンウィークのNYについて回想しよう。私が詐欺師の餌食になる伏線、それはNYの日々の緊張感にあったでのはないかと思う。当時、NYというと、人種の坩堝(るつぼ)と言われるように、世界中から人と金が集まる、世界を動かす中心。そして、犯罪の多い街。NYにミュージカルを見るのが目的だったが、初めて滞在する大都会NY、私は最初から緊張していた。実際、緊張感を感じることも多々あった。NYに行くに当たっては、私の母親も、「今回ばかりは生きて帰れないんじゃないか」と電話の向こうで漏らしていたほどだ。さて、日本からの直行便でNYに入った私は、JFケネディ国際空港からシャトルバンに乗って直接ホテルに向かった。同乗の乗客が宿泊するホテルに順番に立ち寄っては下ろしていき、私が宿泊するPresident Hotelは一番最後だった。空港を出る時まだ明るかった外の景色も、マンハッタン中心部に入って間もなく、日が沈み、ホテルに到着したときには外は暗くなっていた。シャトルバンで、マンハッタンのホテルを巡りながら、道路の両側に縦横に聳える摩天楼には、とにかく圧倒された、それがNYの第一印象だった。来たという喜びよりも、とうとう来てしまった、という気持ちが大きかった。そういう私なので、到着初日の夜は、さすがに緊張感から外に出られず、ホテル1階の小さいバーで夕食することしたものの、そもそもレストランでないので、冷めたサンドイッチか、タコスのようなものしかなく、お寒い夕食となった。翌日、朝の出勤時間に合わせて、意を決してホテルを出て、暫く歩き、ブロードウェイの雰囲気に身体を慣らしていった。朝、マンホールから上る噴気にニューヨークを感じたものだ。そして問題の食事も、この日以降は、大体、昼夜を問わず、ブロードウェイに点在するデリカテッセンや、グロサリー(今でいうコンビニに近いか)の惣菜のお世話となる。特に、グロサリーの惣菜は、レストランのバイキングのように品数が豊富で、好きなものをとって(その上の階で、選んだものをそのまま食べることもできたのだが)、部屋に持ち帰り、食べていたものである。当初、その惣菜が秤売りであることに気付かず、バイキングのつもりで、容器一杯に詰めていたので、10ドルを大きく越えることあったりした。当時、そういうシステムを体験すること自体が初めてだった。ところで、そのグロサリーは、韓国人が経営していて(結構、韓国人が経営する店というのは多かった)、とても感じのいい店主だったのだが、一度だけ凄みを見せつけられたことがあった。それは、レジ待ちしていて、ちょうど目の前で、男が何気にレジ前のガムを手探りしていたと思うと、盗ってまさに店を出ようとした時だった。レジにいた店主は、それを見逃さずに大声を出して身体をレジから乗り出し、その男の手を捕まえようとした。男も手を振りきろうと応戦し、たまらず手からガムを落としてしまうのだが、さらに店主は、逃げる男を店の外まで追いかけて捕まえ、叩き、そして殴り、蹴った。さんざんな目に会った男は、倒れそうになりながら、走り去っていった。私は、目の前の出来事のあまりの迫力に圧倒されてしまった。レジで自分の番が来たとき、その店主は何ごとも無かったかのように笑顔で対応していた。実に逞しい。マンハッタンに店を持つマイノリティは、この位の力強さがないと、やっていけないんだな、と感じた瞬間だった。
2007.10.15
コメント(0)
-
NYの思い出(5) ダメ押し
1993年にNYで会った詐欺。引っかかってしまった私も問題ではあるのだが、人の善意につけ込んだ詐欺、弱みにつけ込んだ詐欺、というのは許せない。ここ数年、日本でも後を絶たない、振り込めサギも似たようなものだ。その詐欺師は、私がPRESIDENT HOTELに連泊し、タイムズスクエア界隈を毎日のように歩いているのに目をつけていたのかもしれない。毎夜のようにミュージカルに出かけていた私は、ジャケットを着て歩いていた。その詐欺師、同じホテルにあるガイドマップを手に持ち、しかも同じホテルに泊まっていることを自ら申し出ることで、私の彼に対するハードルは一気に低くなってしまった。そして、涙を流してまで感謝する演技。深夜、早朝という寝静まった時間帯、冷静に判断すれば、夜中に両替のため街をさまよい歩いていることや、ホテルに泊まっている筈なのに何故ホテルで寝ていないのか、等おかしなことだと思う。また早朝わざわざ外に呼び出したのは、向こうも発覚を警戒してのことだろうが、そのあたりの判断力も私には欠けていた。初心(うぶ)だったとも言える。寝させてもらえないことで、考える暇を与えられなかった。とにかく、私はこの事件で、人間不信に陥ってしまった。帰国して後も、ショックが数週間続いたものだ。当時、私はジャズピアノを習い始めていた。フランスの女優、ジュリエット・ビノシュにも似たピアノの先生に私は恋心を抱いてしまっていたのだが、その先生にこの話をしたところ、「生きて無事で帰ってきたことだけでも良かったと思うよ。部屋で2人きりになったら何が起こってもおかしくない状況だったわけだから」と言われ、”その通り、最悪、お金を奪われて殺されることだってあり得たかもしれない”と気持ちを入れ替えたものである。さて、NY7日目の朝、ラ・ガーディア空港を発つ飛行機の出発時刻は7時台だった。タクシーでセントラル・パークの中を通り抜け、朝霧の中マンハッタン島にかかる大きな橋を渡り、空港に向かったのを覚えている。その日は、ノース・ウェスト航空でミネソタ州のミネアポリスまで飛び、そこで乗り換えてラスベガスに向かうという、大陸横断ルートだった。窓際に座り、ずっとショックにうつむいていた私、時折、呆然として涙を目に浮かべたりもしていた。隣に座っていた女性が、私のただならぬ様子に、どうしたのだろうとしきりに気にされていたことを記憶している。私は機内食や飲み物を回される時に、THANK YOUと声に出す以外には、何も語ることもなかった。連日の寝不足だったが、心のショックが大きくで、機内で眠ることさえできなかった。ラスベガスには1泊だけして、翌朝の飛行機で、サンフランシスコ経由で日本に帰国するという短い滞在だったのだが、ラスベガス空港には私の荷物が届かなかった。バッゲージクレームから人々が消えていき、1人残された私は、ノース・ウェスト航空のカウンターに行き、調べてもらった。その結果、私の荷物はミネアポリスから何故かコロラド州のデンバーに飛んでいることが分かった。そして、ユナイテッド航空で、デンバーからラスベガスへ荷物を飛ばすよう、指示がなされた。ニューヨークとラスベガスの時差は4時間である。早朝、ニューヨークを出たが、ホテルにチェックインしたのは夕方。そして、部屋で荷物が届くのを待った。夜8時ころ、漸く荷物を受取ったのだが、この出来事は、傷心の私にとって、ダメ押しようなモノだった。この詐欺事件以来、私は何度か渡米することもあったが、NYには行っていない。
2007.10.13
コメント(0)
-
NYの思い出(4) 失意の夜
1993年5月、NY滞在6日目となるこの日の朝、ジャマイカ人学生Trevonにメッセージを残しホテルを後にした。この日、NYでの楽しい思い出、そして人助けをしたという充足感も、一転することになるのだが、知るすべもなかった。この日の午前、自由の女神に行き、冠の部分の展望台まで登った。その数日前に行った時には、人の長い列で展望台まで登ることを断念していたのだったが、この日はその雪辱を果たした。展望台は狭い螺旋階段、ここからマンハッタンを臨んだ。自由の女神で思い出すのが、アルフレッド・ヒッチコック監督の『逃走迷路、Saboteur(1942)』、映画ではこの窓から外に飛び出したのか、と重ね合わせた。その後、ワシントン・スクエア周辺のグリニッチ・ビレッジを散策し、ビデオ屋で映画関係のビデオを物色したりした後の夕暮れ、滞在するホテルPresident Hotelに戻ってきた。ホテルのフロントで、私宛てに例のジャマイカ人からのメッセージがないか尋ねたが、なかった。そして、そのジャマイカ人から聞いていた部屋に電話をかけてみたが、お前は誰だ?みたいな感じで、寝ていたところを起こされたようで不機嫌だった。どうも違う人間のように思えた。そのNY最後の夜は、44丁目のSHUBERT THEATREで、ジョージ・ガーシュインの名曲に彩られたミュージカル、(日本でも劇団四季でお馴染みの)『CRAZY FOR YOU』を見に行く予定だった。私はジャケットを着用し、再び、フロントにメッセージを残して、急いでホテルを後にしたのである。しかし、この時から疑念の思いが湧いてきたのであった。ミュージカルが終演し、ホテルに戻ってきた私は、フロントで聞いた。「○号室にTrevonという男が宿泊しているか?」と。答えは「No!」だった。愕然とした。このホテルはセキュリティはしっかりしていて、常に警備員がロビーに張り付いていて、私も毎日、顔を合わせていたのだが、その警備員に状況を話した。話をしたところで、どうなるものでもないのだが。そして彼は言った。「NYでは、表通りを歩いている人に声をかけられても、相手をしてはいけない。誰も信用できないと思わなければいけない。前にも言ったじゃないか。どうして初めて会う人間に気を許してしまったのだ。」と。確かに、そういうことを滞在したばかりのころに言われたこともあったのだ。私は、逆に説教されてしまった。部屋に戻った私は、悔しさと悲しさで一杯だった。そして深夜、警備員のシフトが変わった後で、前夜、顔を合わせた警備員が私の部屋を訪ねてきた。前のシフトの警備員から伝え聞いていたらしく、様子を伺いにきたのだ。前夜、その自称ジャマイカ人を部屋に通した後で、彼は2度に渡り、私に何も問題はなかったか?と確認していた。うち1回は、部屋に直接来て、問題ないか確認に来たくらいだ。私は2度とも「No Problem.」と答えていた。この夜、彼は言った。「どうして、お前は、あの時No Problemと答えたのだ。どうしてお金を要求されたことを言ってくれなかったのだ。」と。彼はその時の警備員として、そういう状況を起こしてしまったこと、正直に話をしてもらえなかったことについて、思いがあったようだ。私は、前日のタイムズスクエアでの出会いから、早朝の出来事まで全てを話した。説教され、慰められ、しかし数10分くらい、その警備員は私と向き合ってくれた。私は失った金額以上に、親切心を踏みにじられたことが悔しくて、警備員と話をしている間じゅうも、涙が止まらなかった。警備員が帰った後も、私は茫然自失の体だったが、時間は止まってくれない。翌朝、早朝の飛行機でラ・ガーディア空港を発たなければいけなかった。ほとんど寝ずに、荷物を纏め続けた。
2007.10.13
コメント(0)
-
NYの思い出(3) 詐欺師の夜討ち
1993年5月、NYで迎える5回目の夜。翌日が滞在最終日となるこの夜、十分睡眠をとるつもりであったのだが、その大事な夜の時間、詐欺師に攪乱されることとなる。宿泊していたPresident Hotelの自室、すっかり眠りに落ちていた夜中の1時、真っ暗な部屋に電話が鳴り響いた。フロントから外線が入っているとの連絡。寝ぼけた状態のまま、取り敢えずとりついでもらった電話の向こうから聞こえてきた声、それはタイムズスクエアで出会ったジャマイカ人の学生だった。何と、まだ両替のために表通りを歩いているとのことだった。彼は、「HOLLIDAY INNにいるのだが、両替してもらない」と嘆いている。「明日の朝、10ドルを返せそうにない」と言う。こちらも寝ぼけていて頭が回転しない。良く覚えていないが、「翌日、学校に行くのに、50ドルが必要で貸してもらえないか?」といったようなことを言っていた。私も、「こんな時間でなくても、明日の朝でもいいんじゃないの?」と言ったと思うのだが、「今から会いたいので、部屋に行ってもいいか?」という。そして、「この時間だと、あなたもセキュリティが気になるだろうから、下のホテルフロントを通して連絡する」と言ってきた。まあ、同じホテルに泊まっているのだし、フロントを通して部屋に来る、とそこまで言うのであればいいかと思った。(彼からは、前夜、別れ際に、部屋番号と名前を書いた紙切れを渡されていたので何も疑わなかった)間もなく、ホテルフロントから電話が入り、「お前に会いたいと言っているが、部屋に上げてもいいか?」という。許可した。彼が、タイムズスクエアで会ったままの姿で部屋にやってきた。ベッドに2人腰かけ、彼の話を聞いた。それまで両替するために、ずっと歩いていた、という。とりあえず、現金が30ドル少ししか持ち合わせていなかったので、これが全部だと言い、渡した。礼を言って、彼は立ち去った。すぐに、ホテルフロントから電話が入り、「何も問題ないか?」と言われたが、私は「No Problem」と答えた。そして、3時過ぎだったろうか、また彼から電話がかかってきた。まだ、外にいるという。どういうことなんだと思ったが、私も寝ぼけていて冷静さを失っていた。どこから電話してきたのかよく覚えていない(と言ってもまだ携帯電話とか無い時代である)。「両替するためには、銀行に口座開設しないといけない。しかし、ニューヨークシティタックスを払う必要があると言われた。50ドル必要なので貸してもらえないか。今から部屋に行っていいか」と言う。私は「現金がなく、トラベラーズチェックしかない」と言ったのだが、「ホテルのキャッシャーでトラベラーズチェックを両替してもらえばいい」と。そして暫くして、数時間前と同じように、ホテルフロントを通して電話が入り、また彼を部屋に迎えた。また、ベッドに2人座るが、さすがに彼は汚れている。ベッドの布団が汚れるのを私が気にして、彼は少し位置をかえた。彼は、「ジャマイカの通貨が弱くて、日本円のように簡単に両替してもらえない」と嘆いた。私は、財布に現金が入っていないのを見せたが、50ドルのトラベラーズチェックを見て、「それを今から両替してくれ」と言う。「こんな時間に両替なんか出来るわけないもないだろう」と言う私に構わず、彼は部屋の電話からフロントに連絡し、両替できることを確認した。2人でロビーフロアに下りていき、私はキャッシャに行って、50ドルのトラベラーズチェックの両替を依頼した。その間、彼は、ホテルロビーにいる、警備員と歓談していた。警備員にも顔を見せていて、確認した上で部屋にあがっている、しかも同じホテルに宿泊している。そういう状況下では、私も全く彼を疑わうことがなかった。再び部屋に戻り、彼に50ドル渡した。「翌朝、お金を返すので、ロビーで○時に会おう」と言い残して、彼は部屋を去った。彼が居なくなった後、ホテルの警備員が私の部屋にあがってきた。「何も問題ないか?」と聞いた。再び私は、「No Problem」と答えたのであった。そして、朝6時くらいだったろうか、また彼からの電話に起こされた。今度はブロードウェイの表通りからだった。「一晩中、両替するために、歩き回っていたが、ジャマイカの通貨が弱くて、どこも相手にしてくれない。NYに来た最初の夜から、さんざん日だった」と、疲れきった風で、不満を口にしていた。そして、「これから漸く銀行口座を開設できそうなのだが、口座開設する当り、イニシャルのデポジットがさらに50ドル必要だそうだ。外に出てきてくれないか」という内容だった。当時、私も若かった。海外で口座開設するということがどういうものなのか、知らなかった。また、ジャマイカの通貨が弱くて、簡単に両替してもらえないのだ、と言われるとそうなのだと思った。ホテルに泊まっている筈なのに、わざわざ外で会わなくてもいいじゃないか、とも思ったが、早く口座を開きたいという彼が気の毒に思えた。そして、私は、ビジネスピープルの出勤が始まる前の朝の時間、ブロードウェイの表通りで彼と出会った。彼は疲弊していた。一緒に歩きながら、彼は、一晩中歩いたが、結局両替出来ずにさんざんだったこと、そして、出会ったばかりの私の親切に感謝し、何と目から涙をこぼし、身体を震わせていた。私は、「気にしないでいい」と肩をたたいた。彼は、口座を開設するためにさらにデポジットが必要であったので、「(私の)トラベラーズチェック50ドルを(前方に聳えたつホテル)Marriott Marquisで現金化してほしい」と嘆願した。私は、わざわざそのホテルまで行くのがおっくうだった。そして、非常時のために、Gパンの前ポケットに折り畳んで入れていた100ドル札に手をかけ、これを使ってくれと差し出した。一緒に、銀行の入口までやってきた。そこで、彼が言った。「ここから先はセキュリティが厳しいので私だけ入っていくよ。あなたは、そこのカフェで朝食をとってゆっくり待っていてくれ。そこで、借りたお金を全部返すから」と。私にとって、NY最終日のその日、ゆっくりカフェで朝食をとる時間が惜しかったので、「ホテルのロビーで○時に会おう」と約束し、ホテルに戻った。私も寝不足で疲れきってしまったが、彼の涙を見て感動した。NYの地で、人の役に立ったことに満足していた。約束の時間、彼はロビーに現れなかった。私は、フロントで彼の部屋番号にメッセージを託し、外出した。「Mr.Trevon、待っていたけれど、時間がないので外出します。また、夜電話します」と残して。
2007.10.12
コメント(0)
-

NYの思い出(2) 火花タクシー
1993年5月、詐欺師との第1ラウンドが終了した後、エンパイア・ステート・ビルに行ったのだが、思わず笑ってしまう出来事があったので、それについて書いてみよう。夜のエンパイア・ステート・ビルで思い出すのは、1949年のMGM映画『踊る大紐育(ニューヨーク)、ON THE TOWN』。MGMのミュージカルを語る上では欠かせないジーン・ケリー、フランク・シナトラ、そしてタップの女王アン・ミラーに、ヴェラ・エレン、ベティ・ギャレット、とオールド・ファンにはたまらない、ミュージカル・コメディだが、その中で、夜、エンパイア・ステート・ビルの上で、恋人たちが待ち合わせて、"New York, New York, A Wonderful Town,......"と歌って、街に繰り出していくシーンがある。 そういう映画のシーンを重ね合わせながら、夜のニューヨークの夜景を味わった。もう少し、明りが多いものと過大に期待していたので、周りのビルの窓の明りが少なくて、拍子抜けしたのを覚えている。そしてエレベータで下へ降り、表通りでタクシーを捉まえ帰路についたのだ。通りの名前は覚えていないが、どこかの通りを真っ直ぐ走り、正面にラジオ・シティ・ホールが現れたところで左折し、ブロードウェーに出るというルートを帰ったのだが、そのラジオ・シティ・ホールに向かう途中だった。突然、ガクンと衝撃があり、タクシーが傾いた。どこか縁石に乗り上げた衝撃だったのかと思った。しかし、タクシーは右に傾き、ガリガリ音を立てながら走り続けた。パンクしてしまったのだと思った。ラジオ・シティ・ホールで左折し、ブロードウェーまで来たところで信号待ちとなった。するとどうだろう。タクシーの前、横断歩道を渡る人々がタクシーをジロジロ見て、そして指差して、笑いながら、通り過ぎていくのである。笑い者になっている状況に、タクシードライバーは、何か「クチショー」という感じでブツブツ言っていた。私もその見世物の中で、ちょっと恥ずかしい思いをしたものである。信号が青に変わり、タクシーは左折、ガリガリ音をたてて少し走ったところで、止まった。お金を払って、外に出て様子を見てみると、何とタイヤが無くなっていたのである。さきほどの衝撃は、タイヤが外れて、ガクンときた衝撃だったことにこの時、気付いた。私を下ろした後、タクシーは安全な路肩へと車を移動させたが、タイヤが無くなった車軸は路面と擦れて、火花を散らせて走っていた。その姿が滑稽で、私も思わず笑ってしまったものである。タクシーを止めたドライバーは、公衆電話に駆けてきて、どなって喋っていた。会社に必死で状況を説明していたように見えた。私は、この時、タイヤが外れてまで、よくぞ私を最終目的地まで運んだものだと、ドライバーとしてのプロ根性に感心したものだ。しかし、あとで冷静に考えると、火花を散らしながら走り続けて、仮に引火でもしていたら、大変じゃないか、と逆にゾッとした。ドライバーが必死で電話しているのを横目に、私はグロサリー(今でいう深夜スーパーみたいなもんだ)に飛び込み、夜の食料を買い込んだ。その後に、詐欺師との第2章が待ち受けていようとは、考えも及ばなかった。
2007.10.11
コメント(0)
-
NYの思い出(1) タイムズスクエアの詐欺師
ニューヨークには、1回行ったことがある。1993年のゴールデンウィーク、時の流れは早い、もう14年も昔のことである。この時、NYには6泊した。場所は、48丁目にあるPresident Hotel。ミュージカルを見る目的で単身NYを訪れた私は、ブロードウェイの中心部にありながら、リーズナブルな値段であるこのホテルを選んだのである。NYにもすっかり慣れた滞在5日目、この日、日没後の夜景を見ようと、エンパイア・ステート・ビルに向かうところだった。ホテルから出て、ブロードウェイ沿いを歩き、まずはお土産屋をちょっと物色した後、43丁目あたりだったろうか、交差点で信号待ちをしていた。そして小柄でデイバッグを背負い、一見ちょっと気の小さそうな男性に声をかけられた。「銀行に行ってお金を両替したいのだが、どこにあるか知りませんか?」という内容だった。既にその周辺、だいぶ歩いていた私である。CHEMICAL BANKというのが近くにあることを知っていた。また、人との触れあいに飢えてもいた。人助けと思い、「その先、数ブロックのカドにあるが、もう開いていないかもしれない。」と言いながら、私もちょうど歩く方向だったので、一緒に歩いていった。その間、お互いどこから来たのか?という話になり、その男性は、その日ジャマイカからやってきたばかりだ、ということを知る。そして翌日、コロンビア大学に入学するのか何か手続きをしに行くのだという。確かに、言われるとおり、歳、格好とも学生のような雰囲気で、垢抜けしない感じだったので、そうと信じてしまった。「どこに泊まっているのか?」と言われた。さすがにホテルの名前は言えないだろうと、「このあたりのホテルに泊まっている」と答えた。すると彼から、「私はPresident Hotelに泊まっている」と言ったのである。それを聞いた私は驚いて、「Oh, Really ? Me, too.」と言ってしまったのである。彼が言うには、ホテルでジャマイカの通貨を両替してもらえなかったので、銀行に行くように言われたということだった。そして、そうこう歓談しているうちに、CHEMICAL BANKの入口についたのだが、日没の時間、予想通り閉まっていた。彼は途方にくれた。初めて訪れたNY、到着して以来、まず米ドルさえ調達できずに何も食べていないという。「せめて夜の食料だけでも買いたいので5ドルだけ貸してもらえないか? 明日の朝、銀行で両替した後で、ホテルのロビーでお金を返しますから」と言われた。私は見るに見かね10ドルを手渡した。彼は、私の好意に感謝し、「初めて会ったばかりなのに、親切にしてくれてありがとう」と言った。彼はポケットから、NYの観光ガイドを取り出した。それはPresidennt Hotelに置かれていたものであり、私も持っているものだった。そして、あるページを破りとり、部屋番号と名前を書いて私に渡した。ピンと来ない名前だったが、TREVONとか書かれていた。そして、私も何号室かと聞かれたので、その観光ガイドに部屋番号と私の名前を書き残したのである。実は、この瞬間に明暗が決したようなものだった。10ドルをケチったばかりに深みにハマってしまうのだが、この時は、いいことをした、と清々しい気分になったのである。そして、足早に、エンパイア・ステート・ビルに向かった。
2007.10.10
コメント(0)
全40件 (40件中 1-40件目)
1