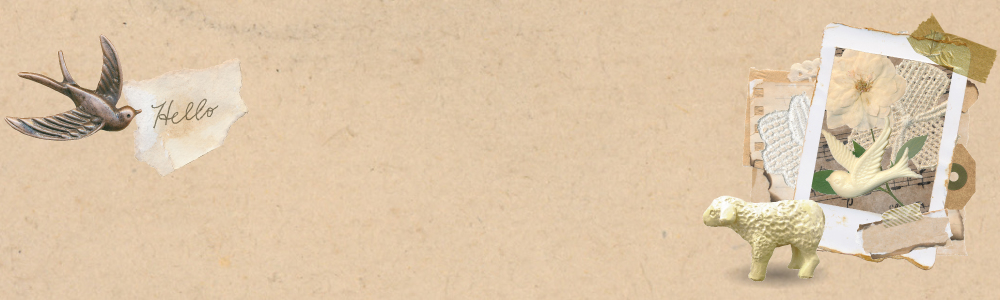7月
8月
9月
10月
11月
12月
2017年05月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
こども保険について考えてみた(3)
(2)より続く最後にもう一つ。厚生年金には上限があるため、一定以上の給与月額の人は全て620円の負担という事になります。所得税のように、所得 x 税率で計算し累進性が保たれる、という訳ではありません。なぜ月給(標準報酬月額)が60万円の人も、200万円の人も、皆同じ保険料になるのでしょう。単純に厚生年金に上乗せする、という安易な制度設計にしたために「高所得者に応分の負担を求める」という点が不十分になってしまったのではないでしょうか。元々は別の制度であった厚生年金と国民年金ですから、今の段階で多少の齟齬が見られるのは仕方のない事でしょう。しかし、せっかく新たな制度を設計するのですから、このような一つ一つは小さいけれど現実にこのような経験をした方には無視できない、我慢できない矛盾のある制度設計になってしまったのは、努力不足のそしりを受けても仕方がないのでは?という気持ちが抑えられません。もう一度繰り返します。1.保険という名称は不適切で、名を変えた増税である2.昨今の情勢で増税は景気回復の足かせとなり、別の手段(教育国債の発行など)を講じることがより効果的な施策であろう3.「高所得者や企業に応分の負担を求める」とあるが、高所得者の負担が不十分4.2とも関わるが、現存する社会保障制度の不備を無視して制度が構築されており、粗製濫造との批判を免れない
2017.05.23
コメント(0)
-
こども保険について考えてみた(2)
(1)より続くこども保険と消費増税や教育国債を比較する中に(資料9ページ)「こども保険は勤労者と企業が負担、高所得者や企業に応分の負担を求める・・・」という説明がありますが、この点における矛盾にお気づきでしょうか?こども保険は保険料額決定について、厚生年金は保険料率に0.1%を上乗せして徴収、国民年金は一律160円を徴収としています。まず、国民年金保険加入者は、無収入であっても、年収一億円超の自営業者などという高所得者であっても、一律160円の負担となります。何処が応分の負担でしょう。保険料が一律なので仕方がない、負担が無理な場合は免除制度がある、という反論もあると思いますが、高所得者に応分の負担、ということを謳うのであれば、一律ではなく所得に応じて保険料が決まるべきでしょう。しかし、それでは同額の保険料に一律の上乗せ、という簡便性が削がれてしまいます。この点については誰かが批判することは容易に想像できると思えるのですが、無視して制度設計を進めたのでしょうか?それとも気づかなかったのでしょうか?筆者には大いに疑問です。次に厚生年金について、です。厚生年金は世帯単位が基本となるのはご存じでしょう。つまり、独身の方も結婚して扶養家族がいらっしゃる方も、給与額(正確には標準報酬月額)が同じであれば毎月支払う保険料は同じ金額です。ただし、共稼ぎで夫と妻がそれぞれ厚生年金に加入している場合は、給与に応じた額をそれぞれが負担しています。三号被保険者である配偶者がいるかいないかで公平感が削がれてしまうのはいかがなものでしょうか。更に、国民年金と厚生年金を比較すると、もっと公平感が削がれる事例を指摘することもできます。自営業者と無職のご夫婦の場合、収入がいくらであっても一律320円を負担します。ところが、保険料が0.1%上乗せであれば、サラリーマンや公務員は標準報酬月額が33万円を超えない限り、月額320円以下(標準報酬月額に応じて88円から320円と段階的に増加)を負担します。賞与に関しては特段の計算式が記載されていませんでしたので、極端な例を挙げれば年収300万円の自営業夫、専業主婦(無収入)、子供2人の4人家族は320円/月の負担ちなみに、年金保険料は世帯で3万2980円/月。夫に万一の事があっても100万~120万円程度の遺族基礎年金は第二子が高校卒業年齢になったら打ち切り年収400万円、標準報酬月額24万円のサラリーマン夫、パート勤務で90万程度収入のある第三号被保険者の妻、子供2人の4人家族は240円/月の負担厚生年金保険料は世帯で1万8938円/月。ただしボーナスからも別途保険料は引かれます。金額に変動はあるものの、上出の遺族基礎年金以上の金額の遺族年金が生涯支給される。参考までに、年収400万円、標準報酬月額24万円の独身者は男性であれ女性であれ240円/月の負担となります。これで応分の負担といえるのでしょうか、なんだか不公平な気がするのは筆者だけでしょうか。<続く>
2017.05.22
コメント(0)
-
こども保険について考えてみた(1)
「こども保険の導入 ~世代間公平のための新たなフレームワークの構築~」をネット上で見つけました。読後の感想は。保険という名称は不適切で、名を変えた増税である昨今の情勢では増税は景気回復を妨げるため、別の手段(教育国債発行など)を講ずるべきであろう「高所得者や企業に応分の負担を求める」とあるが、高所得者の負担が不十分である。3とも関わるが、現存する社会保障制度の不備を無視しており、粗製濫造との批判を免れないでは、1に関してこども保険の目的は「喫緊の課題である子育てに社会保険がない・・・子供が必要な保育・教育を受けられないリスクを社会全体で支える・・・」とあります。子供が必要な保育や教育等を受けられないリスクは確かに存在します。それを社会全体で支える事には何の疑問もなく賛同できます。しかし、何故ここで唐突に、「子育てに社会保険を導入し、それを原資として現在の児童手当に上乗せして給付する制度」を作る必要があるのか、ワタシにはさっぱりその理由がわかりません。土台となる児童手当は税と企業からの拠出金で運用されているのでは?日本国憲法が保障する「社会保障」を構成するのは公的扶助=税で運営 生活保護など社会保険=保険料の応分負担( + 税の投入) 年金や医療、介護保険などという区別があります。保険という仕組みについて考えると、その成立過程には種々の説がありますが、一つには大航海時代、イタリアの貿易商たちが所有する船の難破等商売の損失に備えて共同で積立金を準備していた、同様に船員組合が組合員が航海中に死亡した場合など残された家族救済のために共同で積立金を準備していた、などがあります。共同体の中に避けがたいリスクが平等に存在し、構成員が万一の場合に備える、というのが保険であると私は理解します。民間のこども保険について、考えてみてください。よくあるパターンは親や祖父母が、子や孫の進学、成人、結婚等の費用を準備するために加入、でしょう。共同体は子や孫を案じる人、リスクは子や孫に必要な資金を準備できない(死亡や高度障害で)、と言って良いでしょう。悲しい事ですが、子供の成人を待たずに生涯を終えるリスクは親にとって平等に存在します。いつ、どこで、事故にあったり病気になるかは、誰にもわからないわけです。特に生計を支えている方にとって、万一の事が起これば、種々の保障(遺族年金、母子家庭への補助等)はあるものの、そこへの上積みが必要だと思われるでしょう。その場合に納得して保険に入るわけです。満期前に万一の事があれば、それ以降保険料の負担なく満期時に保険金が受け取れます。何事もなく母娘健康で満期を迎えれば、すべての回数の保険料を負担して保険金を受け取ります。この差は当然納得している訳ですよね。このような共同体に、強制的に子供のない、あるいは子育てをすでに終えた中高年を引き入れるのはどうでしょう。(あえて中高年と書きました。高齢者は負担のもとになる年金の保険料はもう払っていません)町を歩いていたら突然ウィルス性の感染症に罹患、運転していたら突然交通事故に、このようなリスクは老若男女誰にでも起こりえます。しかし、街を歩いていて突然子供を授かり親になった、車を(以下略)、、、当然ありえないことですよね。それでも保険への加入が納得できるでしょうか、最初から掛け捨て損になるのがわかっているのに。もちろん少子高齢化の中で社会保障の変革の必要詠を理解する国民は、納得して金銭的な負担を引き受けるとは思います。しかしそのかたちは現役世代だけが負担する「保険」でよいものでしょうか?現役世代より裕福な高齢者世代に負担をお願いしないのは何故なのでしょう?一般的に保険よりは税が適切だと思われます。そしてこのこども保険は新たな税を保険と詐称して、日本人の保険好きと公共心を悪用し、あまつさえ票田である高齢者に媚びていると思えて仕方ない私は、、、相当にねじくれ曲がった根性の持ち主なのでしょうか?
2017.05.21
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1