2022年11月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
ゆうとののヴォーカル教室 4 [リズム感と表情]
(※この記事は2013年3月に「ニコニコ」の「ブロマガ」で連載したものです。「ブロマガ」が消滅してしまったので、こちらに残しておきます。) 6. リズム感 まあ、世に、ウォークマンとディスコというものが登場して以来、リズム感の悪い人間は、めっきり少なくなりました。 昔から、リズム感の良さは、若者の専売特許ですから、これについては、あまり心配していません。ですので、一応、念のため、ということで述べておきます。 まずは、何はともあれ、アフタービートを、覚えてください。 1小節には、ふつう、4分音符(♩タン)が、4つあります。 ♩ ♩ ♩ ♩ タン タン タン タン 1拍 2拍 3拍 4拍 1小節に、8分音符(♪タ)は、8つあります。 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ タ タ タ タ タ タ タ タ 1拍 2拍 3拍 4拍 これで、手拍子を打つとき、どこで打つか。手拍子は、2拍めと、4拍めで、打ちます。 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ タ タ タン タ タ タン 1拍 2拍 3拍 4拍 タ、タ、タン!、タ、タ、タン!、と、タンのところにアクセントをおいて、タンのところで手を打ってください。 身体全体を揺らしながら(シェイク)、リズムに乗って、手拍子します。この「乗り」が、8ビートの基本です。 今度から、カラオケでは、必ず、アフタービートで手拍子をするようにします。 これは、ドラムスのスネアを叩く位置と、一緒です。 歌を歌うからには、リズム楽器のドラムスの音も、よく知っておかなければいけません。 ドラムスは、基本、3種類の音を出しています。 1. バスドラ ~ 「ドゥン」、「ボォン」、といった低い、大太鼓の音です。 2. スネア ~ 「パァン」といった少し高い、小太鼓の音です。 3. ハイハット ~ 「チッ」という、クローズド・ハイハットと、 「チーッ」という、オープン・ハイハットがあります。 シンバルの音です。 バスドラは、1拍めと、3拍め(たまに3.5拍め)で、鳴ります。スネアは、2拍めと、4拍めで、鳴ります。ハイハットは、1~4全部で、鳴ります。 プロは、音楽を聴きながら、「手拍子で、バスドラの音を消す、あるいは、スネアの音を消す。」という遊びを、よくやります。ドラムを叩く人間は、ジャスト・ビートを打つ感覚が優れているので、本当に、ドラムの音が、消えます。みなさんも、挑戦してみてください。 一般に素人は、ジャスト・ビートより、わずかに遅れてしまいやすいのです。 あと、シャッフルやシンコペーションの話も、した方がいいのかも知れませんが、みなさんは、おそらく大丈夫だと思いますので、割愛します。 7. 表情 音程をしっかり取れて歌えるようになったら、歌に、表情をつけることを、考えます。表情ゆたかな歌声は、聴き手を魅了します。 笑顔で、歌えば、歌声も笑顔になります。哀しい顔をして歌うと、歌声も哀しく聴こえます。 ため息まじりの、歌声。フレーズの終わりで、わざと音程をなくす、歌声。昔のアイドルがやってた、フレーズの最後をキュッと上げる、歌声。これらは、いずれも、表情のひとつです。表情も、フレーズの終わりに、現われやすいです。 昨今では、ボーカロイドというのが、流行ってますが、あれは、無表情なのが、逆に、いいんですかねぇ。 以上で、今回のヴォーカル教室は終了です。最後まで読んでいただいた、あなたの歌は、もう、昨日までとは違います。自信を持ってください。 これからは、カラオケに行っても、音程を気にする、声量を気にする、そんな、あなたは、もう素人では、ありません。
2022年11月13日
コメント(0)
-
ゆうとののヴォーカル教室 3 [声域と発声法]
(※この記事は2013年3月に「ニコニコ」の「ブロマガ」で連載したものです。「ブロマガ」が消滅してしまったので、こちらに残しておきます。) 4. 声域 声域とは、自分が歌うことのできる、音の高低の範囲(音域)です。 通常は、ファルセット(うら声)を含まない、地声の範囲を言います。 昔から、なぜか、高い方(高音)の声域が広いことが、偉いとされて来ました。プロは、高音が出せることにプライドを持ってますし、実際、プロの歌のキーは、素人より高いことが多いです。 チューニングされたギターやピアノで音を出して、一度、自分の声域を調べてみてください。 普通の男性は、オクターブ下の「ラ」(ギターの5弦)から、オクターブ上の「ミ」(ギターの1弦)ぐらいまで出ます。 ちなみに僕は、オクターブ上の「ラ」まで出せます。僕の音楽仲間は、オクターブ上の「ド」まで出せる奴がいます。 女性の場合は、…よく知りません。 スマン。 声域が、あまり狭いと、歌えない歌、というのが出て来ますので、声域は、ある程度広い方が望ましいです。 ただ、上に書いたような高音を出せるのが偉い、なんていうのは、ヴォーカリストの迷信ですので、気にする必要はありません。 声域は、ある程度、持って生まれたものなので、なかなか、すぐに広げることはできませんが、歌の練習をしたことがない人なら、練習すれば、一定のところまでは、すぐ広がります。 また、歌いこんで来ると、不思議なことに、少しずつですが、高い音が出せるようになります。 素人がよく誤解していることに、歌いすぎると、声がかれて出なくなる、というのがありますが、全く逆で、ある程度までは、歌えば歌うほど、声はよく出るようになります。 カラオケで、ちょっと歌って、声がかれたと思うのは、歌い慣れてないだけで、実は、その後から、本当の歌声が出て来ます。 プロは、一度声がかれた後に、本当の声、本当の声域で歌える、ということをよく知っています。 ファルセット(うら声)を使うときの、注意点を述べておきます。 ファルセットは、地声より、音量が下がります。ですから、ファルセットになったとき、その直前までの地声に比べて、音量が下がりすぎないよう、意識する必要があります。特に高い音というのは、盛り上がる場面であることが多いので、音量が下がってしまってはシラケるときなど、注意しましょう。 ファルセットは、地声より、発音が不明瞭になります。ファルセットでは、はっきり言葉を歌うよう、心がけましょう。 どこから、声をうら返すか、については、地声が出ないところから、うら声にする、というのが普通です。 地声が出るのに、わざとファルセットを使う場合は、音量、音程が不安定になりやすいので、特に注意して、しっかり歌うことが大事です。素人は、やらない方がいいでしょう。 地声の音質が高い女性の場合などで、音量、発音を変えずに、ファルセットを使うと、どこから、うら声なのか、わからないように歌える人がいます。まさに天使の歌声ですよね。 一般に素人は、ファルセットの練習なんてことを、したことがありません。ファルセットは、磨けば、すごい武器になりますし、自分の歌の世界を広げることができます。何より、歌う楽しさが広がります。 ですので、しっかり、ファルセットの練習を、しませう。 5. 発声法 僕は、声楽家でもなんでもないので、みなさんに、知ったかぶりに、発声法を講義するつもりはありません。 が、素人がカラオケなどで歌っているのを聴いて、どうしても気になる点を、述べておきます。 みなさんに多いのは、好きなプロ歌手の発声を真似て歌う、ということです。気持ちは、わかりますが、これは、お薦めできません。クセが抜けなくなる前に、やめた方がいいです。 まずは、自然に、自分の歌い方で、しっかり歌えるようになることが大事です。 自分の歌を録音して、聴いて、また歌って、というのを繰り返しているうちに、自分の発声法、個性、というのは、できあがって行くものです。 ビブラートについて、ですが。どうも、勘違いしている人が多いようですが、ビブラートは、高度なテクニックでもなんでもありません。誰でも、できることです。 ビブラートをかけると、音程に少し幅が生まれるため、歌に味わいを持たせると同時に、音程を取りやすい、という利点があります。自前のエコーのようなものです。 逆に言うと、ビブラートをかけずに歌うと、音程は取りにくい、ということです。 1. 音程、のところで述べた、フレーズの終わりの長い音。フレーズの最後の、伸ばすところを、ビブラートで歌うと、音程をあまり気にせず、楽に歌えます。 ビブラートなしで、フレーズの終わりを歌ってみてください。音程が、危うくなります。 というわけで、素人は、ビブラートは使わない方が、いいと思います。ビブラートを多用していては、歌は上手くなりません。 国内のアーティストで、ボーカルをコピーするのが、最も難しいのは、誰か、知っていますか? オフコースの小田和正です。彼のボーカルは、ビブラートなんて、もちろん使いませんし、フレーズの終わりにおいても、ボーカルが減衰しません。全く譜面通りに、丁寧に歌います。さらに、声域が異常に高いと、きています。 カラオケで、オフコースの歌を上手く歌うことは、至難のわざです。 歌声は、話し声とは違います。歌声は、基本、口の中の上側の壁(口蓋)で、音を反響させてから、外へ出します。 あと、素人が練習しなければいけないのは、何と言っても、発音です。いわゆる、滑舌です。 まあ、舌の長さもあるでしょうが、聴き手に、言葉が鮮明に伝わるよう、しっかり発音を、練習しましょう。 巻き舌は、個人差があるでしょうが、くちびるの振動は、誰でも、できるはずです。「プルルルルルルルル…。」と、くちびるを、よく振動させてください。これは、歌のウォーミング・アップにも、なります。 さてさて、次は、6. リズム感、ですな。それでは、また、明日。
2022年11月12日
コメント(0)
-
ゆうとののヴォーカル教室 2 [全身で歌う]
(※この記事は2013年3月に「ニコニコ」の「ブロマガ」で連載したものです。「ブロマガ」が消滅してしまったので、こちらに残しておきます。) 2. 声量 声量とは、歌声の音量、声の大きさのことです。 声量は、ないより、あった方が良く、一般に、プロと素人との違いは、この声量があるかないかだと思われてます。また、プロには、声量の大きさにプライドをかける傾向があります。 さて、声量をアップするコツですが、それは、歌う姿勢と歌い方です。 まず、姿勢ですが、立って歌うのが、当たり前です。脚は、肩幅に開きます。軽くジャンプして、肩幅で着地した姿勢が、基本になります。 マイクを持つ側の脚を、前に出す姿勢もOKです。 そして、背中から、声を前に出す、つもりで全身で歌います。自分の体全体から、音を出すつもりで、歌ってください。 上を向いて歌うことは、僕は推奨しません。上を向くと、首の後ろが圧迫されて、音程が取りづらい気がするからです。 呼吸は、もちろん腹式呼吸です。結婚披露宴などで、久しぶりに歌を歌わされると、後から、お腹が痛くなります。急に腹筋を使ったからで、こうなるのが当たり前です。 声量も、練習すれば上げることができます。毎日歌っていれば、少しずつ声量は上がります。マイクやエコーに頼らず、大きな声で歌うようにしましょう。エフェクトのない、自分の生声が一番だというプライドを持ってください。静かな曲も、しっかりした音量で、歌ってください。 カラオケなどで、よく座って歌う人がいますが、「座った姿勢で、ちゃんと音程を取る自信があるのか。君は、そんなに上手いのか。」と、ツッコミたくなります。 声量について、もう一つ大事なことがあります! それは、一曲の中での、声量の変化です。声の音量は、一曲の中で、あまり変化しないのが望ましいのです。 素人は、意識しないため、一曲の歌の中で、音量が大きくなったり小さくなったりします。曲の最初から最後まで、一定の音量が維持できるよう、意識して練習してください。 プロが音量に強弱をつけるのは、あくまで、わざと小さく歌っているのです。歌に表情を持たせるために、楽譜に指示されて、わざと音量を抑えてるのです。 素人はまず、大きな音量で、一曲を歌いきれるようにならねばいけません。 声量の出しにくい、言葉や音符というのがありますので、自分の歌を録音して、聴こえにくい部分はないか、よくチェックしてください。 レベルメーターがあれば、自分の声量を目で見ながら歌うことができます。声量のバラバラな歌手のレコーディングは、ミキサーが大変です。実は、スタジオ・レコーディングでは、ピーク・レベルというものが設定でき、ピーク・アウトの心配がないので、ヴォーカリストは、とにかくマイクに近づいて、大きな声で歌います。 3. 声質 声質とは、声の質、声色のことです。ギター、ピアノ、ストリングスといった楽器によって違う、音色に相当します。 顎骨の形や声帯の形によって決まるのですが、いずれにしても、持って生まれたものであり、練習によって、どうこうなるものではありません。 ただ、要素としてあるので、仕方なくあげただけです。よって、パスします。www さあ、次は、4. 声域、です。が、続きまする。
2022年11月11日
コメント(0)
-
ゆうとののヴォーカル教室 1 [一瞬で歌が上手くなる方法]
(※この記事は2013年3月に「ニコニコ」の「ブロマガ」で連載したものです。「ブロマガ」が消滅してしまったので、こちらに残しておきます。) ニコ生をご覧の皆さんに、歌の上手くなる方法を伝授いたしまする。これを読んでいただければ、誰でも一瞬で、歌が上手く歌えるようになりますと思いまする。 まず、結論を先に言うと、「自分の歌声を録音して聴くこと!!」これに尽きまする。 それでは、参ります。 歌(歌うこと)には、7つの要素があります。それを知ってくださいませ。 1. 音程 2. 声量 3. 声質 4. 声域 5. 発声法 6. リズム感 7. 表情 じゃあ、各要素を詳しく説明しますね。 1. 音程 まあ、これが全てと言っても過言ではありません。音程がしっかりしていれば、他の要素は好みの問題でもあるので、誰にも文句は言わせない、というのはアリです。逆に、どんなに声量があって声が綺麗でも、音程があまいと、話になりません。 自分の歌を録音して聴いてみてください。音程のあまい箇所はありませんか? 自分の声というのは、耳の外から聴こえますが、実は、耳の内側からも聴こえています。録音された自分の声は、内側から聴こえてた部分がありませんので、思ってた自分の声とは違うように感じます。また、歌ってる時には、外からの声と内側からの声とで、ユニゾンの効果が生まれますので、声が綺麗に聴こえると同時に、音程にわずかな幅が出ます。これが、音程があまくなる最大の理由です。 ですから、外に出ている自分の声だけを聴いて歌うことが重要です。これは、訓練によって、誰でもできるようになります。スピーカーから出ている自分の声を聴く、ということを意識しましょう。 ライブ・コンサートでは、ステージの上にモニターアンプというものが置いてあります。ヴォーカリストは、そのアンプから出ている伴奏と自分の声を聴きながら、歌っているのです。もし、モニターアンプが故障したら、プロの歌手でも上手く歌うことはできません。 スタジオ・レコーディングの時は、ヘッドホンから聴こえる自信の声に集中して、プロは歌っています。 楽曲において、歌声も楽器の一つだと考えることができます。ギターやピアノ、ストリングスの伴奏の上に、歌声を乗せて行く、歌声という楽器を演奏する、という気持ちで歌いましょう。 さて、音程がぶれない特効薬をお教えします。 実は、音程がぶれやすいのは、メロディの中の長い音です。タタタといった短い音は、ぶれにくいと言うか、聴き手に気づかれにくいのです。ですから、長い音を歌う時に、音程のぶれに注意します。 メロディ(旋律)の中の、小さな、ひとまとまりを、フレーズと言います。長さで言うと、2小節くらいです。フレーズの最後の音、終わりの音は、長い音であることが多いです。 というわけで、フレーズの終わり、フレーズの最後の音だけ、音程に気をつけて歌う、ようにするだけで、一気に歌は上手くなります。「歌うまいね。」と、人に言われるようになります。歌のうまさは、フレーズの終わりに、現われるのです。 フレーズの終わりでは、ブレス(息)が苦しくなることがあります。そのために音程がぶれないよう、しっかり腹筋を使って、息を吐ききって、音程を維持します。 フレーズの終わりが低い音になる場合も、よく音程がぶれます。気をつけましょう。 フレーズの最後の音の長さを、素人はよく、いい加減に歌ってしまいます。終わるときの音の長さについても、何拍で切るのか、しっかり決めて歌いましょう。 特効薬を、もう一つ。 正しい音程をキープするために、視覚を利用すると効果的です。右手にマイクを持って歌うとき、左手を軽く開いて、首の高さぐらいに上げます。全音符で「ハアーー」と歌います。そのとき、左手で音をつかむ感じで、そして音をキープするために左手を止めます。ちょっと文字では伝わりにくいですが、要は、音程をキープするために、左手の動きを使うと言うことです。 なんと、これは、意外に効果的です。実は、プロもよくやっています。 ついでに、コーラスの発声法を、ぜひ覚えてください。全音符で「ハアーーー」と歌います。このとき、声の音量を感覚で表すと、パッと出て、すぐに音量を下げ、そしてゆるやかに音量を上げて行きます。音量の変化を数値で表すと、Max10として、7 → 5 → 6 → 7 → 8 → 8 という感じになります。 左手を見て、ぶれないよう、しっかり音程をキープします。音量を変化させても、音程は変わらないよう、しっかり練習してください。 歌は、車の運転と同じです。毎日歌っていれば、誰でも歌は上手くなります。ただ、哀しいことを一つ述べますが、歌は、自分の音感以上には、上手くなりません。音感とは、音程の違いを聴き分ける感覚のことです。 しかし、素人の我々でも、毎日音楽を聴いていれば、この音感は、少しずつ良くなります。たくさん、音楽を聴きましょうね。できれば、音程を意識しながら。 次は、2. 声量、です。続きまする。
2022年11月10日
コメント(0)
-

譜割りがおかしくない? という歌謡曲[その2]
「なんか、譜割りがおかしくない?」という歌謡曲、第2弾です。その曲は、なんと「日本レコード大賞」大賞を獲った曲です。 ちあきなおみ 「喝采」作詞:吉田旺 作曲:中村泰士 ♪ いつものように幕が開き♪ 恋の歌うたうわたしに 問題は、その次。 ♪ 届いた報せは 黒いふちどりがありました 前回は「遅かった」のですが、今回は、「届いた」の出だしが「早い」。これも、カラオケで歌ってもらえば、すぐ解ります。初見では、まず歌えません。 その部分の譜面が以下です。 ♩ ♩ ♩ ♩ |♩ ♪♪♪♪♪♪♩ こ い の |うーーたうたうわ ♩ ♪♪♩ ♪|♩ ♪♪♩ ♩ たーしにーー♪|とーどいたーーー ♪♪♪♪♩ ♩ |♩ ♩ ♩ ♩ しらせはーーーー|♩ く ろ い ※歌詞の部分の♩♪マークは4分休符(1拍休み)(または8分休符、半拍休み)です。どう書こうか迷ったのですが、多分これが解りやすいでしょう。「とどいた」の「と」が(おそらく)半拍(♪)早いので、さらに今回は、帳尻を合わせて元に(普通に)戻ることはないので、普通に譜面を書くと、ぐちゃぐちゃになります。(2番もあるし。)そこで、「(わ)たしにー」の小節を7/8拍子にしました。多分、この曲の譜面は、こうだと思います。 まあ、普通は(正しくは)、以下のようになります。 ♩ ♩ ♩ ♩ |♩ ♪♪♪♪♪♪♩ こ い の |うーーたうたうわ ♩ ♪♪♩ ♩ |♩ ♪♪♪♪♩ たーしにーー♩ |とーどいたーーー ♪♪♪♪♩ ♩ |♩ ♩ ♩ ♩ しらせはーーーー|♩ く ろ い これだと、気持ちよく歌えるでしょ?「(わ)たしに」の後は、ふつうならオブリガードを入れたいところです。より一層気持ちよく歌えるでしょう。 というわけで、思うに、今回は、譜面の表記ミスでしょう。作曲者が間違えたか、作曲者から受け取った曲を譜面起こしの際、誤ったか。テレビで歌う時など楽団演奏が付いてるので、ぜひ譜面を見てみたいですよね。(多分、1小節だけ7/8になってると思うなあ。) ちなみに、私は、「ちあきなおみ」が大好きでした。「四つのお願い」で鮮烈デビュー?小学生の私たちは、いつも歌ってました。続く「X+Y=Love」。♪ イコォーォラウ、イコォーォラウ、ラォラォアーラゥユーー ♪その後、鳴かず飛ばずでしたが、「喝采」で大復活!!大人の女性になって、再び我々の前に登場しました。(まるで、奥村チヨの「終着駅」のようですね。)なので、「譜割りが変」の件は、仲間うちでは話題になりました。そして、あの、至高の名曲…「夜間飛行」! 「最後の最後まで あいは 私を傷つけた…」
2022年11月03日
コメント(0)
-

譜割りがおかしくない? という歌謡曲[その1]
「なんか、譜割りがおかしくない?」ということが、ごく稀にあります。歌謡曲に多いです。そんな例を紹介しましょう。 岩崎宏美 「センチメンタル」作詞:阿久悠 作曲:筒美京平 ♪ 夢の ようね今の私 しあわせ♪ あの日 めぐり逢えたあなた 恋のめばえ 問題の箇所は、この次 ♪ とーきめく胸を あなたにー伝えたいのーこの部分の、譜割りが(譜面が)おかしい。♩ ♩ ♪♪♪♪ | ♩ ♪♪♩ ♪♪と ― ―きめく | む ねをー ーあ ♪♪♩ ♪♪♪♪ | ♩ ♪♪♩ ♪♪なたに ―つたえ | た いのー すき となってますが、正しくは(ふつうは)、 ♩ ♩ ♪♪♪♪ | ♩ ♪♪♪♪♪♪と ― ―きめく | む ねをーあなた ♩ ♩ ♪♪♪♪ | ♩ ♪♪♩ ♪♪に ― ―つたえ | た いのー すき となります。 比べて見ていただければ解ると思いますが、「あなたに」の出だしが1拍遅いのです。 「とーーきめく」と「にーーつたえ」は、対になるべきフレーズです。 なぜ、おかしいのか、の説明(証明)をします。カラオケで歌ってみれば解りますが、歌いにくいです。素人は、初見では、おそらく歌えません。 「歌いにくい」といことは、「譜割りがおかしい」ということなのです。 人間は、4拍、8拍、4小節といった、本能というか体内リズムを持っています。(3拍子もありますが。)その規則に入っていると、落ち着くのです。 音楽や作曲に慣れてくると、自然にフレーズの先を予測するようになります。ですから、音楽に親しんでる人ほど、譜割りが異常だと「あれ?」となって、譜面をのぞき込む事態となります。 音楽の苦手な人は、気づきにくいかも知れません。(そもそも全部が歌いにくい。) ただ、譜面は、すぐ普通に戻ります。「あなたに」の「に」が1拍短いのです。 それで元に?戻ります。なので、全体的な譜面、小節数には問題ありません。一般に、「譜割りがおかしい」と指摘すると、このようなプロの作品だと、「間違い」でなく「変化」だと言って、「わざとそうした」のだとして、「そこが良い。 味わい、特徴なのだ。」という反論が返ってきます。 が、私が納得できたことは、ほとんどありません。もう直せないので、言い訳を作ってるとしか思えないことが多いです。もし、納得できるものがあるとすれば、規則的に異常な譜割りを使ってるとか、「意表をつきたい」「不自然さを出したい」「強調したい、盛り上げたい」などの「必然性」が感じられるものです。まあ、ふつうは、「挿入節」や「コーダ」が使われます。 さて、しかし、「筒美京平」先生が、譜割りを間違えたり、おかしいのに気づかないなんてことがあるでしょうか。 ここからは、私の推測ですが、1つは、歌い手のブレス(息継ぎ)を気遣って音を長くした。 もう1つは、譜面作成過程のどこかでミスプリントがあった、あるいは先生の手書きの譜面が汚かった。 バスドラの位置とか伴奏を細かく聴いてみれば、手掛かりがつかめるかも知れません。真相は、どうなんでしょうかね。 歌詞が「あなた(に)」と3語じゃなくて、「君(に)」とかの2語だったら、ふつうの譜割りになってたかも知れませんね。
2022年11月01日
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 好きなアーティストは誰??
- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…
- (2025-10-26 11:00:38)
-
-
-
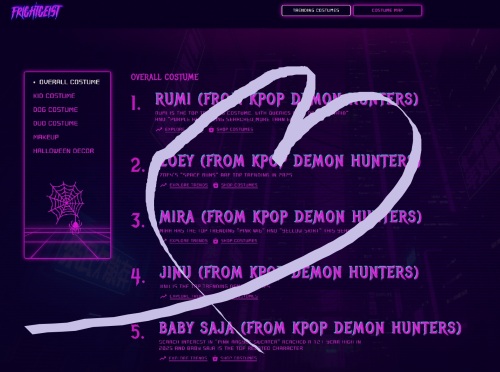
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-







