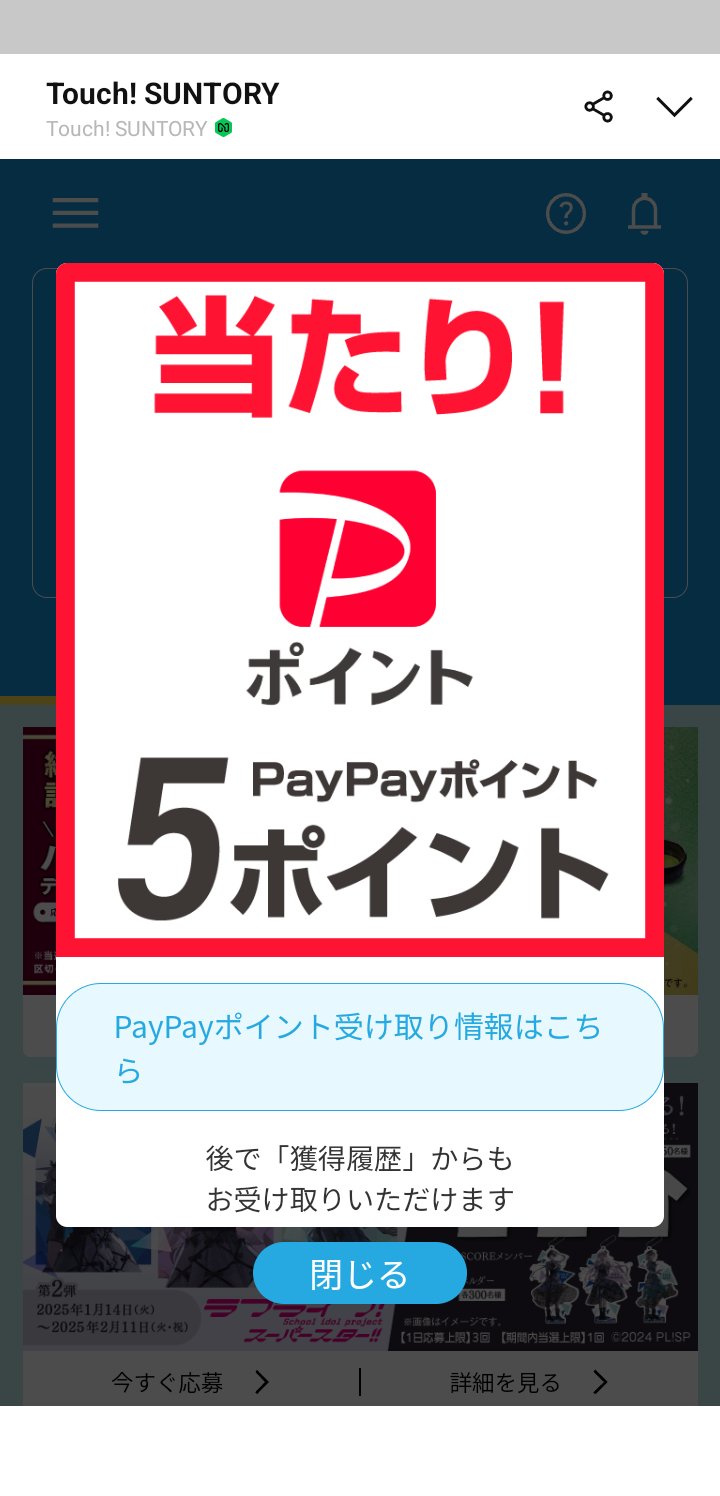2012年08月の記事
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-
大韓航空007便がサハリン上空で撃墜されて29年経つが、未だに謎は解明されないままで、偽装撃墜を含むノースウッズ作戦とのつながりを疑う声も消えない
29年前の8月31日18時26分(UTC)にサハリンの上空で大韓航空007便がソ連の戦闘機に撃墜された、少なくともそう考えられている。日本時間では9月1日3時26分、夜が明ける前の出来事だ。民間旅客機を撃墜したとアメリカ政府は激しくソ連政府を非難、日本のマスコミは事実関係を調べることなくアメリカ政府に同調、憑かれたようにソ連を批判することになる。 007便はニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港から韓国の金浦空港へ向かう予定になっていた。中継地のアンカレッジを13時(UTC、以下同じ)に離陸、10分も経たないうちに航路からそれはじめ、民間機の飛行が許されていない「バッファー・ゾーン」へ向かう。 14時34分に管制官と思われる人物が「警告しなければならない」と口にしたことが記録されている(アメリカ政府は「聞こえない」と言い張っていた)が、危ないと思った人もいたのだろう。 しかし、14時50分頃に航空機はバッファーゾーンへ入り、15時過ぎには「飛行禁止空域」へ侵入したはずだ。「飛行禁止空域」では、特別な許可を受けた航空機でなければ、飛行が禁止されている。 NORAD(北米航空宇宙防衛司令部)のアラスカ航空指揮規則によると、飛行禁止空域に迷い込みそうな航空機を発見した場合はすぐに接触を試み、FAA(連邦航空局)へ連絡しなければならないのだが、アメリカ軍は撃墜も予想される飛行禁止空域へ向かう民間機に対して何もアクションを起こさなかった。アメリカ軍のスタッフが信じがたいほど怠慢だったのか、事前に飛行許可を受けていたのだろう。 15時51分頃にはソ連防空軍の早期警戒管制レーダーに捕捉された。カムチャツカが目の前に迫り、近くではアメリカ軍の戦略偵察機RC135が飛行していた。 航空機は大きくSの字を描いてからソ連の領空を侵犯するのだが、その直後、ソ連側は航空機を10分足らずの間、見失っている。このときに航空機が入れ替わってもわからないだろう。再び姿を現した航空機はサハリンに接近し、18時頃にはソ連軍が複数の迎撃機を発進させる。【コックピットの会話】 18時4分:税関を通過するのは、かなり複雑なことになりそうだ。 18時5分:まだ向かい風を受けている。 18時11分にソ連防空軍の司令部は迎撃機に対し、ロックオン・モードにセットするよう命令。【コックピットの会話】 18時11分:ドルから韓国の通貨にするのは大丈夫。 当時、韓国ではウォンをドルに替える際には制限があり、韓国人のクルーならドルのまま持っているのが自然だろう。また、007便の到着予定時刻に金浦空港で通貨の交換はできなかった。 18時13分に迎撃機は司令部に対し、ターゲットが呼びかけに応じないと報告、15分には司令部はターゲットと迎撃機がスクリーンから消えたと発言した。そして17分、領空を侵犯したとして撃墜命令が出る。 19分には強制着陸させるように命令、迎撃機はロックオンを解除し、警告のために銃撃。21分にミサイルの発射が命令されるが、22分に再びスクリーン上から航空機が消えてしまう。23分に司令部は銃撃での破壊を命令するが、迎撃機からミサイルを発射すると伝え、26分にターゲットを破壊した報告。その後、ターゲットは右へ螺旋を描きながら降下していると迎撃機のパイロットは言っているが、レーダーの記録では左へ旋回している。 少なくとも記録上、空中で分解、あるいは海面に突入する様子を誰も目撃していないだけでなく、事実上、遺体や遺留品が見つかっていない。遺体はタカアシガニが食べたとする説もあるのだが、それなら骨が残っているはずで、説得力は全くない。ソ連が回収したとする証拠もない。 事件の直後、「自爆説」を唱えるアメリカ軍の退役将校がいた。おそらく、1960年代にキューバへ軍事侵攻する口実を作るために考えられたノースウッズ作戦を連想したのだろう。マイアミなどアメリカの主要都市でキューバ人を装って「テロ」を実行し、最後に自動操縦の無人旅客機を自爆させ、キューバ機による「旅客機撃墜」を演出しようというシナリオだった。 しかし、この作戦はジョン・F・ケネディ大統領に阻止され、計画の中心的な存在だったライマン・レムニッツァー統合参謀本部議長の再任を拒否、欧州連合軍最高司令官としてヨーロッパへ追放している。レムニッツァーは1955年から57年にかけて琉球民政長官を務めた人物だ。
2012.08.31
-
シリアでの戦闘が泥沼化、反政府軍の残虐さが広く知られるようになり、早く決着をつけたいNATOは軍事介入を承認、ロシアは艦船をシリアの港から避難させているという話も
8月27日に開かれたNATOの会議でシリア攻撃が承認されたという話をイランのテレビ局が伝えている。ダラヤでシリア政府軍による虐殺があったと「活動家」が宣伝を始めた直後の決定ということになる。 この情報が正しいとしても、実際に攻撃する場合、国連の承認なしに行わなければならない。拒否権を持つロシアと中国の存在するからだ。アメリカ、イギリス、フランス、トルコはともかく、ほかの加盟国は国連の承認なしにシリアを攻撃することに抵抗があるはずで、差し迫った話とは言えないだろう。 ただ、ロシアに関しては気になる情報もある。シリアのタルトゥースにあるロシアの軍港からロシア艦船が引き上げ、シリアへの軍事物資輸送も中断したといういうのだ。すでにNATOや湾岸産油国が事実上の軍事介入をしている中、エスカレートする戦闘に巻き込まれるのを避けるためだという見方、あるいは外部からの本格的な軍事介入がありえるとロシアの情報機関が判断しているともいう。 日本人ジャーナリストが殺された翌日、ロシア海軍のビクトル・チルコフ総司令官はタルトゥースからの避難に言及していたとも伝えられているのだが、ニコライ・マカロフ参謀総長はチルコフ総司令官の発言を28日に否定している。ただ、ロシア側の行動が慎重になっていることは確かなようで、NATOの動きがそれだけ攻撃的な方向に動いているのかもしれない。 そうした中、エジプトのムハンマド・ムルシー大統領は中国を訪問、イランで開かれている非同盟運動の会議ではシリアを罵倒、アメリカ政府の手駒として動いているようだ。ムスリム同胞団の幹部でアメリカの教育を受け、NASAで働いたこともあるムルシー。背後にはサウジアラビアやアメリカが存在しているわけで、こうした言動は必然なのだろう。 勿論、NATOや湾岸産油国が好戦的な姿勢を強める理由はある。シリアの体制転覆を未だに実現できず、反政府軍の残虐性、正体を隠しきれなくなってきたということだ。昨年春どころか、1990年代の初頭、ジョージ・H・W・ブッシュ政権の時代から世界支配戦略が始動、そのターゲットにシリアも含まれていることが明らかになっている。 現在、日米欧は政治経済的に危機的な状況にある。整備されたオフショア市場のネットワークで多国籍企業や富裕層は資産を隠し、税金を回避できるようになったが、当然のことながら国家システムは破綻状況で、庶民の怒りは膨らむ一方である。しかも戦費負担がのし掛かる。略奪の仕組みを再構築しないことには現在の支配システムを維持できなくなっている。
2012.08.30
-
ロシアのアクラ級原潜が米国側に気づかれずメキシコ湾に入ったと報道されているが、背景にはネオコンとロシアとの軍事的な緊張があり、中東/北アフリカ情勢にも関係
ロシアの「アクラ級」原子力潜水艦がメキシコ湾の中へアメリカ軍に気づかれないまま侵入に成功、しかも数週間にわたって留まり、この侵入が発覚したのは潜水艦が去ってからだとワシントン・フリー・ビーコンが伝えている。 国防総省のスポークス・パーソン、ウェンディ・スナイダーはこの報道を否定しているので、情報が正しいかどうかは不明。情報の真偽はともかく、報道が軍事予算の削減問題に絡んでいることは確かだろう。 2009年にも同じタイプの潜水艦2隻がアメリカの東海岸近くに来ているので、アメリカの領海近くに出現したことだけなら驚きではないが、アメリカ側に探知されなかったとすると、ステルス能力が飛躍的に改善されたことになり、衝撃が走っても不思議ではない。対抗するためには予算が必要・・・というシナリオを海軍の誰かが考えてリークした可能性はある。 アメリカ領海の近くにロシアの潜水艦が現れても不思議ではない雰囲気になっていることも確かだ。今年の6月、ロシア軍はアメリカ政府への通告なしに北極圏で軍事演習を実施、7月にはロシアの戦略爆撃機がカリフォルニア近くに飛来するなど示威行動を繰り返している。 勿論、ロシア側に示威行動を行う理由は存在する。1990年に東西ドイツが統一される際、アメリカのジェームズ・ベーカー国務長官(当時)はソ連のエドゥアルド・シュワルナゼ外相(当時)に対し、ドイツが統一された後にNATOが東へ拡大することはないと約束していたのだが、この約束は全く守られていない。当然、ロシア側は怒り心頭であり、アメリカのミサイル配備計画に激しく反発している理由のひとつだ。 NATOの拡大を推進しているグループで中心的な役割を果たしてきたのは、例えば、ジョン・マケイン上院議員の顧問に就任するランディ・シューネマン、あるいは軍の情報部出身で、2002年まで巨大軍需産業、ロッキード・マーチンの副社長を務めたブルース・ジャクソンたち。 ジャクソンは同社を辞めてからイラク攻撃を実行するべきだというロビー活動を展開した・・・要するに仕事のために肩書きを消したわけだ。現在、この軍事企業に最も近い政治家と言われているのがヒラリー・クリントン国務長官である。 シューネマンとジャクソンにはPNACという共通項もある。言うまでもなく、PNACはネオコン(親イスラエル派)のシンクタンク。2001年9月11日の直後には、攻撃予定国として、イラク、イラン、シリア、リビア、レバノン、ソマリア、スーダンをジョージ・W・ブッシュ政権はリストアップしていたとウェズリー・クラーク元欧州連合軍最高司令官は語っているが、その計画を作り上げた勢力にシューネマンやジャクソンも含まれているといういわけだ。 現在の中東/北アフリカ情勢にはこうした背景がある。このことを考えないと、アメリカ(ネオコン)やロシアの動きは理解できないだろう。
2012.08.30
-
ヤセル・アラファトとオサマ・ビン・ラディン、ふたりの死に対する疑惑が再浮上し、NATOや湾岸産油国が攻勢をかけている中東/北アフリカ情勢へも影響する可能性
ふたりの死者が中東/北アフリカ情勢を動かすかもしれない。そのふたりとは、アル・カイダを率いていたオサマ・ビン・ラディンとパレスチナ人のカリスマ的な指導者だったヤセル・アラファトである。 オサマ・ビン・ラディンを殺害したとアメリカ政府が発表したのは昨年5月のこと。このタイミングを逸したなら、リビアやシリアでアル・カイダ系武装集団を使うということは困難だったかもしれない。 パキスタンのアボッタバードにいたビン・ラディンを襲撃したのはアメリカ海軍の特殊部隊SEALだとされている。このときの襲撃チームに参加していたというマット・ビッソネットが「マーク・オーウェン」の名前で本を書き、9月4日に売り出されるという。その中で、ビン・ラディンのいる部屋へ入った時に本人はすでに死んでいて、ビン・ラディン側からの攻撃もなかったとしているようだ。 銃撃戦がなかったということは、周辺住民の証言などでわかっていたが、今回の話では近くにいた誰かが、部屋にSEALが突入する前に殺したというように読める。 SEALが襲撃した時だけでなく、「ビン・ラディン暗殺」の話には納得できない点が少なくない。例えば、ビン・ラディンが隠れていたという邸宅のあるアボッタバードは多くの将軍が住んでいる地区で、士官学校もある。つまり警戒が厳重な場所。飛行許可を受けていないヘリコプターが飛んでいれば、すぐに撃墜されるような環境ということだ。 その邸宅をCIAのチームが数カ月にわたって監視していたというが、そのはるか前、建設された当時からパキスタンの情報機関、ISIは監視、アメリカの情報機関も2005年には監視下に置いていたとも言われている。要するに、CIAが監視していた期間は数カ月だとする説明は信用されていない。 アル・カイダのナンバー2と言われていたアイマン・アル・ザワヒリが裏切り、ビン・ラディンを処分したという話も流れていた。ザワヒリはエジプト出身だが、同じエジプト人のサイフ・アリ・アデルが2010年秋にパキスタンへ入り、その頃からビン・ラディン排除の策略が始まったというのだ。 2001年から11年にビン・ラディンが殺されたと発表されるまで、アル・カイダをアメリカ政府は「テロとの戦争」の象徴として利用、軍事侵攻を正当化していた。2011年から現在に至るまで、リビアやシリアへの軍事介入ではNATOや湾岸産油国と手を組んで戦闘に参加している。この辺の謎を解く鍵がオサマ・ビン・ラディンの死に隠されているかもしれない。 アラファトの死も注目されている。2004年11月に死んだのだが、その当時から暗殺説は流れていた。最近になって毒殺説が浮上しているのだ。 その「毒物」とは放射性物質、ポロニウム210。アラファトの家族は真相の究明をフランス当局に要求、フランス側も調査の開始を認めたという。フランス支配層の内部にも米英両国にベッタリの政策に反発している勢力もいるようなので、この調査にも注目する必要があるだろう。 1967年の第3次中東戦争でアラブ諸国が不甲斐なく敗北する中、イスラエル軍を苦しめたのがファタハ。そのファタハでスポークス・パーソンを務めていたのがアブー・アンマール、つまりヤセル・アラファトだ。1969年にはPLO(パレスチナ解放機構)の執行委員会議長に就任する。それ以来、パレスチナ人の戦いを率いることになった。 アラファトに対抗させるためにイスラエルが目をつけたのがアーマド・ヤシンなる人物。当時、ムスリム同胞団のメンバーとしてパレスチナで活動していた。彼はシン・ベト(イスラエルの治安機関)の監視下、1976年にイスラム協会を設立し、翌年にはイスラエル政府から人道的団体として承認され、サウジアラビアの資金援助を受けながらパレスチナで勢力を伸ばしていった。ハマスを組織するのは1987年のことだ。 その間、イスラエルはアラファトのグループが弱体化するように工作していたが、イツハク・ラビン首相はアラファトと和平交渉を始めてしまう。そして1993年9月、ラビンとアラファトは「暫定自治原則宣言」(オスロ合意)に正式署名した。 合意の当事者、アメリカのビル・クリントン大統領に対する好戦派/ネオコンによるスキャンダル攻勢が本格化するのは1993年、イスラエルのイツハク・ラビン首相が暗殺されるのは1995年、そしてアラファトは2004年にパリで死亡した。
2012.08.29
-
ベネズエラ最大の製油所で火災があり、多くの死者が出ているのだが、その約1カ月前に米国大使館員が10月に予定されている同国の大統領選を左右する出来事を予言していた
今月の25日、ベネズエラのアムアイ製油所で爆発があり、大規模な火災が発生して48名が死亡、その多くは製油所を警備していた国家警備隊の隊員だと伝えられている。28日には鎮火し、精製機能への損害はなかったようだ。 この火災が起こってから、7月22日に伝えられた報道が注目されている。ベネズエラでは10月7日に大統領選挙が予定されているが、その前に尋常でない出来事が起こると、ベネズエラにあるアメリカ大使館の職員が語ったという予言めいた内容だったからである。 現在、「先進国」と自称するアメリカなどの国々は、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)や南アメリカ諸国と政治経済の分野で鋭く対立している。(アフリカはリビアの体制転覆で弱体化した) 中でもベネズエラのウーゴ・チャベス大統領はアメリカ支配層にとって不倶戴天の敵。次の大統領選で負けて欲しいとアメリカ側は願っているのだろうが、世論調査ではチャベスが有利な展開になっている。 このアメリカ政府にとって好ましくない調査結果をベネズエラのジャーナリストが現地のアメリカ大使館員にぶつけたところ、選挙結果に影響を及ぼすような尋常でない出来事が選挙前に起こり、チャベスの優位は消えると語ったというのだ。今回の火災で、大使館員の「予言」が注目されることになった。 チャベス大統領は火災の原因を突き止めるため、緊急調査を実施するように命じたというが、その一因はこの報道にあるのだろう。アメリカには破壊工作/テロ活動の伝統がある(詳しくは拙著『テロ帝国アメリカは21世紀に耐えられない』を)わけで、製油所を爆破したとしても驚きではない。 アメリカ政府が破壊活動/テロを目的とした組織を創設したのは、第2次世界大戦の最中、1944年のこと。戦時情報機関のOSSはイギリスの情報機関MI-6と共同でジェドバラを編成、大戦後のOPC(当初の名称は特殊作戦局)につながる。このOPCが母体になってCIAの計画局ができ、議会で活動の一端が明らかになった1970年代前半には作戦局へ名称を変更、9/11後の2005年に国家秘密局(NCS)へ吸収された。 ところで、中国で共産党の体制が成立する直前、OPCの東アジアにおける拠点は上海から日本へ移動している。1949年のことだ。下山事件、三鷹事件、松川事件という国鉄を舞台にした「怪事件」が起こったのは、この年の夏だった。つまり、OPCは日本とも深い関係がある。OPCがベースになって「NATOの秘密部隊」も組織された。 破壊活動/テロを目的とした組織として、「SOA(アメリカ大陸訓練所)」も忘れてはならない。1946年にパナマで創設、反乱鎮圧の技術、ゲリラ戦や心理戦の戦い方、狙撃の訓練、さらに拷問や暗殺のテクニックまでを教えている。つまり、アメリカの支配層がラテン・アメリカを支配するための手先養成機関だ。 アメリカ政府はラテン・アメリカに軍事独裁政権を作り上げた。人びとを暴力的に支配することも目的のひとつで、死の部隊が編成される。その中心には、勿論、SOAの出身者がいた。 軍事独裁体制は巨大金融機関の略奪システムにも組込められている。つまり、巨額の融資を独裁者は「北側」の金融機関から流れ込んだ公的な資金を「北側」の金融機関が作り上げたタックス・ヘイブン/オフショア市場へ個人的に還流させ、庶民に借金を返済させるという仕組みだ。「北側」の債務問題を作り出している仕組みも基本的に同じ。緊縮財政や消費税で解決できるはずがないのだ。 それはともかく、SOAは1984年にパナマから追い出される形でアメリカのジョージア州にあるベニング基地に移動、2001年にはWHINSECへ名称を変更しているが、その実態に変化はないと言われている。勿論、ベネズエラは南アメリカの国である。
2012.08.29
-
破壊と殺戮で苦しめられているパレスチナ人を支援していた米国人をイスラエル軍がブルドーザーでひき殺した事件で、イスラエルの裁判所は本人の責任だと結論
2003年3月、パレスチナ人に対するイスラエル政府の弾圧に抗議する活動を続けていたアメリカ人女性、レイチェル・コリーがイスラエル軍のブルドーザーにガザで押し潰され、殺された。そのとき、パレスチナ人の家を破壊しようとしていたブルドーザーに向かい、オレンジ色のジャケットを着た彼女は拡声器で抗議していたのだ。 コリーの友人や家族が主張するように、イスラエル兵は目の前に女性が立っていることを認識した上でブルドーザーを前進させた、つまり意図的にひき殺した可能性がきわめて高い。ドライバーは彼女が逃げると高を括ったのかもしれないが、足場が悪く、4メートル離れた場所から早歩きの速度で向かってくるブルドーザーをよけきれなかった。 そこで、彼女の家族はイスラエルで民事訴訟を起こしたのだが、裁判所は偶発的な出来事で政府に責任はないとして、原告の訴えを退けた。責任は本人にあるというわけだ。この決定にはイスラエル駐在のアメリカ大使も不満を表明している。 イスラエルの国内事情を考えると、パレスチナ人やその支援者が公正な裁判を受けられる状況にないことは明らか。レイチェルの家族も勝訴するとは思っていなかったらしい。裁判を通じ、イスラエルの姿を世界に知らせようとしたわけだ。 裁判が始まるとイスラエル政府は目撃証人4名の入国を拒否、アメリカ政府からの圧力で渋々、入国を認めることになる。コリーは平和運動の団体「国際連帯運動」に所属していたのだが、ヨルダン川の西岸にある団体の事務所はイスラエル軍によって何度も家宅捜索を受けたという。イスラエルの首相だったアリエル・シャロンは徹底した、信頼できる、透明性のある調査を約束しているが、約束が守られたとは言えない。 調査の妨害で中心的な役割を果たしたのはドロン・アルモグ少将(事件当時の南部方面司令官)。イスラエルの憲兵が当事者から事情聴取しているとき、アルモグ少将が派遣した陸軍の大佐が現れて証言を止めさせたという。 パレスチナ人は1948年4月のイスラエル建国以来、弾圧に苦しんできた。建国の最終段階でシオニストはパレスチナ征服を目的とした「ダーレット作戦」を発動、デイル・ヤーシーン村で254名のアラブ系住民を虐殺、恐怖に駆られた多くのアラブ系住民は難民化した。この間、アラブ諸国は傍観している。 イスラエル建国前、パレスチナには約140万人のアラブ系住民が住んでいたのだが、5月だけで42万人以上がガザやトランス・ヨルダン(現在のヨルダン)へ逃れ、85万人以上が難民生活を強いられることになった。イスラエルの地域にとどまったパレスチナ人は11万人余りにすぎない。 1967年の第3次中東戦争でイスラエルはエルサレム、ガザ、シナイ半島、ヨルダン川西岸、ゴラン高原などを占領したが、今でも領土の拡大プロジェクトは続き、破壊と殺戮は続いている。 しかし、イスラエルに飛行禁止空域を設定するべきだとか、制裁するべきだとか、体制を転覆させるべきだといったことを「人権」や「民主化」に敏感らしい「西側」の政府は言わない。多いとは言えない個人が声を上げているだけである。そのひとりがレイチェル・コリーだった。
2012.08.28
-
シリアの反体制派に対し、オランド仏大統領は臨時政府を樹立すれば承認すると呼びかけたが、この手法は旧ソ連圏を切り崩す際に使われている
フランソワ・オランド仏大統領はシリアの反政府派に対し、臨時政府を樹立するように呼びかけた。樹立すればすぐに承認するというのだ。反政府軍が一部の地域を制圧できたなら、シリアのバシャール・アル・アサド体制を倒そうとして事実上の軍事介入をしている国々は、その地域の「独立」を宣言させるかもしれない。フランス、アメリカ、イギリス、トルコ、サウジアラビア、カタールなどが独立を承認、シリア政府軍と反政府軍の戦闘は「国際紛争」だと主張し、本格的に軍事介入するというシナリオもありえる。 このシナリオは一度、使われたことがある。NATO諸国は旧ソ連圏の国々の「西側派」に独立を宣言させ、最終的にはユーゴスラビアに軍事侵攻している。コソボもこうして独立した。 NATOは軍事介入の環境作りをするため、残虐なユーゴスラビア政府/セルビア人というイメージを広め始めたのだ。そのキーワードは「人権」。1992年8月、ボスニアで16歳の女性がセルビア兵にレイプされたとニューズデーのロイ・ガットマンは報道したのが手始めだった。 ガットマンはドイツのボン支局長で、バルカンに常駐しているわけではない。ヤドランカ・シゲリという「活動家」の作り話を垂れ流したのである。1980年代にニカラグアの革命政権を攻撃したIGfM(国際人権協会)もシゲリの話を広める上で重要な役割を果たしている。 コソボをユーゴスラビアから分離させようとしていたのはアルバニア系の人びとだが、そのアルバニアへアル・カイダのメンバーが1994年に入ったと言われている。1996年には「西側」と協力関係にあったKLA(コソボ解放軍)が台頭、コソボの北部にいたセルビア人難民を襲撃しはじめた。 KLAの資金源は、アフガニスタンとパキスタンの国境地帯で栽培されたケシを原料とするヘロイン。アフガン戦争でソ連と戦ったイスラム武装勢力もヘロインを資金源にしていた。欧州会議の報告書やガーディアン紙の記事によると、KLAは臓器の密売にも手を出している。 1998年秋にアメリカのマデリーン・オルブライト国務長官がユーゴスラビア空爆を支持すると表明、NATO軍のウェズリー・クラーク司令官も賛成した。そして1999年1月にウィリアム・ウォーカーなる人物が登場、コソボにあるユーゴスラビアの警察署で45名が虐殺されたと宣伝しはじめる。実際は戦闘での死者だった。 ウォーカーはエルサルバドル駐在大使だった1989年に軍事政権の虐殺事件をもみ消そうとした経験の持ち主。この年、カトリックの指導的立場にあった司祭やハウスキーパーたちがエルサルバドル軍によって殺害されたのだが、この事件に関する調査をウォーカーは妨害したのである。 殺害の様子を目撃したを隣人をカトリック教会側は国外へ避難させようとする。この脱出にはフランス外務省が協力していたが、そうした動きを察知したウォーカーたちは目撃者に接触し、証言内容を変えなければエルサルバドルに送り返すと脅したという。 ユーゴスラビアに対する空爆が始まるのは1999年3月のこと。4月にはミロセビッチ大統領の自宅が、また5月には中国大使館が爆撃され、犠牲者が出ている。中国大使館は3方向からミサイルを撃ち込まれている。アメリカ政府は「誤爆」だと主張したが、それを信じる人は少ないだろう。 この当時、アメリカ陸軍の第4心理作戦グループの隊員が2週間ほど、CNNの本部で社員と同じように働き、ニュースにも携わっていたこともわかっている。 今年に入り、NATOや湾岸産油国は「リビア方式」から「コソボ方式」に切り替えるという話が流れた。確かにNATOや湾岸産油国はコソボ方式でシリアを攻撃しているように見える。
2012.08.27
-
非同盟運動の会議や国連安全保障理事会の緊急閣僚会議が開かれるのにタイミングを合わせるようにして、ダマスカス近くで虐殺があったと反政府軍は宣伝しはじめた
シリアの首都、ダマスカスから近いダラヤで政府軍による虐殺があったと「活動家」が宣伝している。8月24日に政府軍が攻勢をかけ、反政府軍は大きなダメージを受けたとも伝えられているが、この攻撃で「スンニ派の市民」が殺されたと言いたいのだろう。伝えられる死体の数は200人以上、300人、600人とエスカレートしているが、詳しい状況は明らかになっていない。 イランで8月26日から31日にかけて非同盟運動の会議が開かれている。アメリカやイスラエルなどの国々はイランを孤立化させようと働きかけてきたが、エジプトのムハンマド・ムルシー大統領や国連の潘基文事務総長も出席することになった。 これに対し、イギリスやアメリカと同じようにシリアの体制転覆に協力しているフランス政府が主導する形で、国連の安全保障理事会は8月30日から緊急閣僚会議を開く予定になっている。このタイミングに合わせるように「虐殺話」も持ち上がった。 反政府軍側の話を無条件に信じる人もいるようだが、ホウラ地区での虐殺以降、反政府軍寄りのメディアでも表現が慎重になっている。当初、ホウラで住民はシリア軍の攻撃で殺されたとされたのだが、すぐにこの話が嘘だと判明、次に政府側の民兵が実行したと主張されたのだが、これも嘘だということが明らかになる。 例えば、東方カトリックの修道院長やドイツの有力紙が虐殺の実行者を反政府軍だとしている。修道院長は、反政府軍に参加しているサラフィ主義者や外国人傭兵が虐殺したと報告、キリスト教徒も政府派だと見なされて犠牲になったが、スンニ派でも国会議員の家族は殺されたとフランクフルター・アルゲマイネ紙は伝えている。 「もし、全ての人が真実を語るならば、シリアに平和をもたらすことができる。1年にわたる戦闘の後、西側メディアの押しつける偽情報が描く情景は、地上の真実と全く違っている。」と修道院長は主張、キリスト教の聖職者、マザー・アグネス・マリアムは外国からの干渉が事態を悪化させていると批判している。「人道」や「反独裁」を掲げて介入している「西側」が殺戮の原因だということである。 1990年代の初め、少なくともネオコン(アメリカの親イスラエル派)は「唯一の超大国アメリカ」による世界支配構想を作り上げていた。1992年に書き上げられたDPG(国防計画指針)の草案はその構想を文書にしたものだと言える。ただ、草案の段階で外部に漏れて批判され、書き直されている。 リチャード・チェイニー国防長官の下、この草案を作り上げたのは、国防総省のスタッフだったI・ルイス・リビー、ポール・ウォフォウィッツ、ザルメイ・ハリルザド。アンドリュー・マーシャルONA(ネット評価室)室長の弟子にあたる人たちだ。 ウェズリー・クラーク元欧州連合軍最高司令官によると、旧ソ連圏の国々、シリア、イラン、イラクを掃除すると1991年にウォルフォウィッツ国防次官は話していたという。また、2006年に実施された「ビジラント・シールド07」では、ロシアや中国との戦争も想定しているとも言われている。 ビル・クリントン政権の8年間、ネオコンはホワイトハウスで主導権を握れなかったのだが、2001年にスタートしたジョージ・W・ブッシュ政権で復活、この年の9月11日以降は完全に主導権を握った。 言うまでもなく、9月11日にはニューヨークの世界貿易センターに立っていた超高層ビルに航空機が突入、ペンタゴンが攻撃されたわけだが、その直後には攻撃予定リストが作成されていたともクラーク大将は語っている。そのリストに載っていた国は、イラク、イラン、シリア、リビア、レバノン、ソマリア、スーダン。 ニューヨーカー誌の2007年3月5日号に掲載されたシーモア・ハーシュのレポートによると、アメリカはイランとシリアに狙いを定めた秘密工作をすでに開始、スンニ派の過激なグループ、要するにアル・カイダを含むイスラム武装集団を支援することも戦術に含まれていたようだ。ハーシュのレポートが出た頃には、ブッシュ・ジュニア政権がシリアの反政府派を組織し、プロパガンダ・システムの準備を始めていることがウィキリークスの公表した外交文書で明らかにされている。 アメリカの支配層は他国の体制を転覆させたり、軍事侵略を正当化するための「標語」をいくつか持っている。第2次世界大戦の後、しばらくの間は「アカ」、1970年代の終盤には「国際テロリズム」が登場、黒幕はソ連だと主張し、そのソ連と戦う「自由の戦士」としてアル・カイダを作り上げた。ソ連が消滅するとアル・カイダがテロリズムの象徴となり、リビアやシリアの体制転覆プロジェクトで「西側」はアル・カイダ系の武装集団と手を組んでいる。 アメリカ、イギリス、フランス、トルコといったNATO諸国やサウジアラビア、カタールなどの湾岸独裁産油国は反政府軍を支援しているだけでない。この軍隊を組織したのである。その反政府軍に従軍して取材することは、アメリカ軍に埋め込まれて取材することと大差がない。このことを自覚する必要がある。
2012.08.27
-
WikiLeaksのアッサンジ逮捕をめぐり、英国は南米諸国と対立することになったが、その背景ではチリの独裁者ピノチェトを英国政府が助けたという事実も影響していそうだ
ラテン・アメリカ諸国がイギリスの前に立ちはだかった。内部告発を支援する目的で創設されたウィキリークスの看板、ジュリアン・アッサンジをイギリスの警察が逮捕しようとしているのに対し、エクアドル政府が「亡命」を認めたことで両国の対立が深刻化しているのだが、この対立でUNASUR(南米諸国連合)はエクアドルに「連帯」することを明確にした。ロンドンにあるエクアドル大使館には、各国の大使が支援を表明するために訪れている。 アメリカ軍のヘリコプターが非武装の人びとを銃撃する映像や外交文書を公表したことでアメリカ政府から敵視されていたアッサンジを「お尋ね者」にする出来事が起こったのは2010年8月20日のこと。この日、ふたりの女性がスウェーデンの警察に出向き、アッサンジにHIVの検査を受けさせられるかと相談したのだという。 この訴えを受けて逮捕令状が出され、スウェーデンのタブロイド紙が警察のリーク情報に基づいて「事件」を報道して騒動が始まるのだが、翌日には主任検事のエバ・フィンが令状を取り消してしまう。レ○プした疑いがあるとは認めなかったのである。 ところが、9月1日にこの決定を検事局長のマリアンヌ・ニイが翻して捜査を再開を決めるのだが、9月27日にアッサンジはスウェーデンを離れた。ニイが逮捕令状を請求したのは11月のことだ。 メディアは容疑をレ○プというショッキングな表現を使っていたのだが、実際は合意の上で始めた行為におけるコンドームをめぐるトラブルのようで、しかもアッサンジ側は女性の訴えを事実無根だとしている。 時間の経過とともに、事件の胡散臭さを感じさせる事実も浮かび上がってくる。被害者とされる女性はアンナ・アーディンとソフィア・ウィレンのふたりなのだが、アーディンは「不実な男」に対する「法的な復讐」を主張するフェミニストで、ふたりの女性と同時につきあう男を許さないタイプであり、彼女のいとこであるマチアス・アーディンがスウェーデン軍の中佐で、しかもアフガニスタン駐留軍の副官を務めた人物だという話が出てきた。 しかし、最も驚かせた事実は、彼女が反カストロ/反コミュニストの団体と結びついているということ。この団体はアメリカ政府から資金援助を受けていて、CIA系の「自由キューバ同盟」と関係がある。彼女自身も国家転覆活動を理由にしてキューバを追放された過去があるようだ。彼女がキューバで接触していた「フェミニスト団体」は、CIA系のテロリスト、ルイス・ポサダと友好的な関係にあるとも言われている。 このアーディン以上に興味のある人物がフレデリック・レインフェルト首相。スウェーデンでは2010年9月19日に総選挙が予定されて、与党は苦戦が予想されていた。このレインフェルトがコンサルタントとして雇っていた人物がカール・ローブ。 ローブはジョージ・W・ブッシュ米大統領の次席補佐官を務めた人物で、意に添わない連邦検察官10名近くを解雇、最終的には93名の検察官を解雇しようとしたとされている。スウェーデンでは、カール・ビルト外相と個人的に親しい。 これに対し、アッサンジ側はスペインの元判事、バルタサール・ガルソンを雇った。判事だった2009年、ガルソンはブッシュ・ジュニア政権の高官6名を起訴しようとしたことでも知られている。6名とは、拷問などアメリカ憲法を無視する政策を推進する際、法律面で中心的な役割を果たしていた人びと。司法長官を務めていたアルバート・ゴンザレス元司法長官、法律顧問だったジョン・ユー、国防次官だったダグラス・フェイスも含まれていた。 その前にはオーグスト・ピノチェト元チリ大統領を起訴しようとしたことがある。ピノチェトは1973年9月11日、軍事クーデターでサルバドール・アジェンデ政権を倒し、独裁者になった。このクーデタはCIAに支援されていたが、その背後にはヘンリー・キッシンジャーがいた。 民主的に選ばれた政権を破壊工作や軍事力で倒すというアメリカ支配層の得意技が出たということだが、ピノチェトを起訴するということは、こうしたアメリカの得意技を問題にするということになる。 ラテン・アメリカの独裁者(いずれもアメリカ支配層の傀儡)は連合していたので、ピノチェトの問題はラテン・アメリカ全域に広がる。それだけでなく、ピノチェトはNATOの秘密部隊やナチスにつながる人物とも交流があったので、こうした問題にまで波及する可能性があり、世界を支配しているシステムが揺らぎかねない。 詳しい話は割愛するが、ともかく1998年にガルソンはイギリス政府にピノチェトの逮捕を要請した。治療のため、ピノチェトはイギリスを訪問していたのだ。言うまでもなく、コンドームの装着をめぐる問題よりも重大な事件である。 この要請を受けてイギリス政府は一旦、ピノチェトを拘束するのだが、米英の支配層は激しく反発する。中でも積極的に動いたのがマーガレット・サッチャー元首相。こうした働きかけもあり、イギリス政府は2000年、「進行性脳障害」を理由にしてピノチェトを釈放した。このケースとアッサンジのケースを比較して、イギリス政府の対応を批判する人もいる。ガルソンを雇ったというだけでも、こうしたことを思い出させる効果があったかもしれない。
2012.08.26
-
アレッポで日本人ジャーナリストをシリア政府軍が殺したとされていたが、いつのまにか民兵がやったということになり、謎は深まるばかりで、詳しい調査をする必要がある
アレッポで撮影されたという映像が反政府軍の「戦争犯罪」を明らかにしていると話題になっている。反政府軍が拘束していた親政府派の兵士を「捕虜交換」で自由になると騙し、爆弾を搭載した小型トラックの「自動操縦装置」にしようとする様子が撮影されているのだ。計画通りにことが進めば兵士は爆破で死んでしまったはずだが、このときは爆破装置の不調で失敗したらしい。それを残念がる反政府軍兵士の姿も映っている。 反政府軍にとって捕虜の処刑は普通のことのようで、「自爆攻撃」に利用することに問題を感じていないのだろう。ちなみに、問題の映像をニューヨーク・タイムズとBBCが公開したが、BBCは後に自身のサイトから削除したようだ。 反政府軍は住民も虐殺している。ホウラ地区でのケースが典型例だ。ここで虐殺された住民が発見されたのだが、当初はシリア政府軍の攻撃で殺されたと宣伝、これが否定されると政府側の民兵が実行したと言われるようになる。が、これを否定する複数の報告もあった。 そうした報告のひとつは、東方カトリックの修道院長が行っている。虐殺の実行者は反政府軍に参加しているサラフィ主義者や外国人傭兵だというのだ。キリスト教徒も反政府軍のターゲットになっている。現在、アメリカ、イギリス、フランス、トルコ、サウジアラビア、カタールなどはイスラム武装勢力や傭兵を使ってシリアに軍事介入しているが、こうした外国からの干渉をキリスト教の聖職者、マザー・アグネス・マリアムは批判している。 ドイツの有力紙、フランクフルター・アルゲマイネ紙も反政府軍がホウラで虐殺したと報道、スンニ派でも国会議員の家族は政府派だとして殺され、キリスト教徒も犠牲になったという。ドイツではほかの新聞、例えばビルト紙やディ・ベルト紙もホウラでの虐殺が反政府軍によるものだと報道している。 反政府軍やその後ろ盾であるNATOや湾岸産油国は、シリアのバシャール・アル・アサド体制を倒そうとしている。現段階で和平ということになると、この目的を達成できないわけで、だからこそ、戦争の継続を主張している。 リビアが攻撃された際も似たことが起こっている。ベネズエラのウーゴ・チャベス大統領は話し合いによる解決を提案、ムアンマル・アル・カダフィは受け入れる姿勢を見せたのだが、反政府軍は拒否して戦争を続けたのだ。 リビアとシリアでは大きく違う点がある。リビアには分離独立派が存在、それなりの影響力を持っていたのだが、シリアにそうした存在は見当たらない。しかも、ロシアと中国が「飛行禁止空域の設定」、つまり空爆に反対している。この障壁を突破するため、化学兵器(大量破壊兵器)を強調したり、「政府軍の残虐性」を宣伝しているわけだ。 この宣伝で中心的な役割を果たしてきたのは、イギリスのメディアやカタールのアル・ジャジーラ。そうした中、イギリスのテレビ局、チャンネル4は反政府軍だけでなく政府軍も取材してきたと評価されているが、そのテレビ局のチームが危うく戦闘に巻き込まれそうになったという。取材チームに参加していたアレックス・トンプソンによると、彼らは反政府軍の罠にはまり、危うく政府軍から射殺されるところだったというのだ。 そして今月の20日、ジャパンプレスに所属するジャーナリスト、山本美香がアレッポで殺された。当初、外務省や日本テレビは同行していた佐藤和孝の証言として、「政府軍から攻撃された」としていた。つまり政府軍だと断定しているように発表している。 その後、政府軍だと断定しているわけでないことが明らかになる。「先頭にいた男がヘルメット姿だった」ので佐藤は政府軍だと思ったというのだ。 ジャパンプレスのふたりが歩いていたというスレイマニヤ地区で戦闘が激化していたことはシリアの反政府派も認めている。勿論、のんびり散歩できる状況ではなく、いつ銃撃戦が始まってもおかしくなかった。そうした地区に入ると事前に説明を受けていたのだろうか? ここにきて報道されている話によると、山本と佐藤を含む一団が歩いているいるとき、歩道を歩いていた男が突然、日本人がいると指さしながら叫び、その知らせを受けて「政府側民兵」が狙い撃ちしてきたという。いつの間にか政府軍の兵士が民兵に替わってしまった。 山本と佐藤を見て日本人だと断定したのは、日本人がいることを知っていたからだろうが、日本人を狙う理由が問題。日本のマスコミがシリアでの戦闘の内幕に迫る報道をしているとは思えない。反政府軍のプロパガンダ機関化しているBBCやアル・ジャジーラ、公正な立場で報道しようとしていたチャンネル4、反政府軍の残虐行為を明らかにしたドイツのメディアなどが狙われるなら、わからないでもないが、なぜ日本人なのか。報道内容とは関係ない何らかの目的があったのだろう。
2012.08.25
-
冷戦時代に米国から敵視されていた非同盟運動の総会がイランで開かれるのだが、その会議にエジプトのムルシー大統領と国連の潘基文事務総長も参加すると伝えられている
今月の26日から31日にかけて、イランのテヘランで非同盟運動の会議が開かれる。イランの孤立化を狙うアメリカやイスラエルなどは様々な妨害活動を展開しているようだが、イランと友好的ではない、あるいはアメリカの影響下にあると見られていたエジプトのムハンマド・ムルシー大統領や国連の潘基文事務総長も出席する意向だと伝えられている。 非同盟運動は1961年、「西側」にも「東側」にも属さずに独立国家として平和共存の道を探るという目標を掲げて始まった。その中心にいた人物は5名、つまりエジプトのガマール・アブデル・ナセル、ユーゴスラビアのヨシップ・チトー、インドのジャワハルアル・ネール、ガーナのクワメ・エンクルマ、インドネシアのスカルノ。最初の総会は1961年9月にユーゴスラビアのベオグラードで開かれている。 創設当初からこの運動を敵視していたのがアメリカ。植民地だった国が自立するということは、植民地で潤ってきた人びとが利権を失うことを意味するわけで、大多数の欧米諸国の支配層はこの運動を嫌っていたことだろう。 1945年にオランダからの独立を宣言したインドネシア。その初代大統領に就任したスカルノの場合、非同盟運動が始まる前からアメリカから睨まれていた。1957年にCIAはスカルノ政権を倒すための秘密工作を開始、反政府派のメンバーを訓練し、武器を供給している。最初の蜂起は、スカルノが日本を訪問した1958年のことだった。 インドネシアの反政府派は旧貴族階級や地主が中心で、実行部隊はスマトラ島を拠点にしていたインドネシア軍の将校たち。CIAの爆撃機や米海軍の潜水艦が蜂起を支援、訓練や兵站のための基地として沖縄も重要な役割を果たしたというが、これは失敗に終わる。 こうした軍事支援だけでなく、「教育」の力もアメリカ支配層は利用する。フォード財団が貴族階級出身のインドネシア人をアメリカの有力大学へ留学させ、反スカルノ派の指導者候補として育成している。「バークレー・ボーイズ」とか「バークレー・マフィア」と呼ばれる若者たちだ。幹部が親米派で占められていたインドネシア軍とともに、スカルノ政権を倒す主力部隊になる。 そして1965年9月30日、小集団の若手将校が6名の将軍を誘拐のうえ殺害、ジャカルタの主要箇所を占拠した。そのとき、自分たちはCIAの支援を受けている反乱軍の一部だと放送、スカルノから権力を奪取すると宣言したという話も伝えられているが、真相は明らかになっていない。 この混乱を利用し、スハルト将軍が率いる反スカルノ派の軍隊が若手将校たちを制圧、そして親米派による大量虐殺が始まる。翌年の3月にスカルノは排除されて親米派の政権ができあがった。この間、犠牲になった人数は30万から100万人と推計されている。 この出来事を「共産党のクーデター未遂事件」と表現する人たちもいる。もし共産党がクーデターの準備をしていたなら、一方的な虐殺という事態にはならず、内戦、少なくとも大規模な戦闘に発展したはずである。世界的には、アメリカ主導のクーデターだと信じられている。ともかく、非同盟運動を創設したひとり、スカルノは排除された。 19世紀の後半からエジプトはイギリスに支配されていた。1922年にイギリスは間接支配の道を選び、成立したのがエジプト王国。言うまでもなく、この王制はイギリスの傀儡にすぎなかった。この王制を倒すクーデターが1952年にあり、自由将校団のリーダーとしてナセルも参加している。 王制を倒した後、クーデター派で内部対立が激しくなり、1954年にムスリム同胞団はナセルの暗殺を試み、失敗した。ムスリム同胞団と結びついていたムハンマド・ナギブ大統領は解任され、同胞団は非合法化される。 その際、約4000名が逮捕され、6名が処刑されたというが、数千名のメンバーはサウジアラビア、ヨルダン、レバノン、そしてシリアなどへ逃げたという。この出来事を切っ掛けにしてムスリム同胞団はサウジアラビア王室と緊密な関係を結ぶ。現在、シリアの反政府派、SNC(シリア国民評議会)でもムスリム同胞団が中心的な役割を果たしているとされている。 1956年にナセルはエジプト大統領に就任、非同盟運動を始めた後の64年、収監されていたムスリム同胞団のメンバーを恩赦で釈放する。ところが、自分たちへの警戒心が緩んだと判断したのか、同胞団は新たにナセル暗殺を3度試みる。いずれも失敗に終わるわけだが、幹部は処刑され、多くのメンバーが逮捕された。そして1970年、52歳のときにナセルは心臓発作で急死する。 そうした背景のあるムスリム同胞団の幹部、ムルシー大統領が非同盟運動の会議に出席するのは興味深い。それだけ非同盟運動の影響力が大きくなっているということなのだろう。 このムルシー大統領はアメリカと緊密な関係にあることでも知られている。カイロ大学を卒業後、1982年に南カリフォルニア大学で博士号を取得、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校で教鞭を執る一方、NASA(国家航空宇宙局)にエンジニアとして務めた経験があるのだ。勿論、ムスリム同胞団の幹部としての顔もある。現在、ムルシーが党首を務める「自由と公正党」はムスリム同胞団が母体だ。 そして潘基文。ハーバード大学のジョン・F・ケネディ行政大学院へ留学した経験があるのだが、そこで担当教官だった人物が「あのジョセフ・ナイ」である。潘基文がナイの影響を受けていないとは言えないだろう。その潘も国連事務総長としてテヘランの会議に出席する。
2012.08.24
-
明治以降のアジア侵略には英国の影が見え隠れするのだが、ここに来て活発に動きはじめた「大日本帝国の亡霊」は米国の戦略家の影響を強く受けている(その2)
アンドリュー・マーシャルは冷戦を飯の種に生きてきたような人物で、ソ連が消滅してからは「中国の脅威」を叫び続けている。生まれたのは1921年。シカゴ大学で経済学を学び、49年に国防総省系のシンクタンク、ランド・コーポレーションに入った。ランドでマーシャルは核戦争について研究したと言われ、リチャード・ニクソン政権の時代にONA(ネット評価室)が設置されると、室長に就任した。 ネオコンの思想的な基盤を築いたと言われているレオ・ストラウスがシカゴ大学の教授に就任したのも1949年。ネオコンの大物、ポール・ウォルフォウィッツはマーシャルとストラウス、ふたりと関係が深い。なお、新自由主義経済の教祖的な存在、ミルトン・フリードマンは1946年から76年までシカゴ大学で経済学の教授を務めている。 マーシャルがランド入りした頃、アメリカ軍の内部ではソ連に対する核攻撃計画が練られていて、ロバート・マックルア将軍は核攻撃に続く全面的なゲリラ戦計画を統合参謀本部(JCS)に承認させた。 このゲリラ戦を目的として創設されたのが特殊部隊のグリーン・ベレー。1949年に出されたJCSの研究報告では、70個の原爆をソ連の標的に落とすという内容が盛り込まれていた。こうした好戦的な流れにマーシャルは乗ったと言えるだろう。 1950年代の半ばにはアメリカは約2280発の核兵器を保有するようになり、57年にはソ連に対する核攻撃の準備を始めている。そうした準備の一環として、アメリカ東海岸のアレゲーニー山脈の中、高級ホテルとして有名なグリーンブライアの下に地下司令部が作られている。完成は1962年。 ソ連がキューバにミサイルを持ち込んでいることが発覚したのはこの年の8月だった。アメリカの核戦争計画に気づいたソ連が、核弾頭の運搬手段の劣勢を補うため、アメリカの近くにミサイルを運び込んだと考えるのが自然だろう。 勿論、アメリカ側もこうした展開を予想していたはず。ドワイト・アイゼンハワー政権の時代にキューバ侵攻作戦が作成され、ジョン・F・ケネディが大統領就任して間もない1961年4月に軍事侵攻が試みられているが、こうした軍事作戦も核戦争の前哨戦と考えればわかりやすい。 ところが、キューバ侵攻作戦はケネディ大統領がアメリカ軍の直接介入を拒否したことで挫折してしまう。そこでキューバを装ってテロ活動を実施、最後には自動操縦の旅客機を自爆させ、キューバ軍に撃墜されたと宣伝、軍事侵攻の口実にしようというノースウッズ作戦が作成されたのだが、これも実行できなかった。ノースウッズ作戦において中心的な役割を果たしたひとりがライマン・レムニッツァーJCS議長。1955年から57年にかけて琉球民政長官を務めている。 こうした軍事作戦の前に立ちはだかったジョン・F・ケネディ大統領が暗殺されたのは1963年11月、アメリカン大学の学位授与式でソ連との平和共存を訴えてから5カ月のことだ。 ニクソン政権はデタント(緊張緩和)を目指すが、この流れはウォーターゲート事件で止まり、替わって登場したジェラルド・フォード政権で実権を握ったのが好戦派。ウォルフォウィッツ、リチャード・チェイニー、ドナルド・ラムズフェルドといったマーシャルの弟子たちもこのときに台頭している。ジョージ・H・W・ブッシュがCIA長官に就任したのもこのときだ。 当時、ブッシュを「素人長官」と呼ぶ人もいたが、実際はエール大学でCIAにリクルートされた可能性が高い。少なくともケネディ大統領暗殺の時点でCIAの幹部だったことがFBIの文書で確認されている。 そのブッシュが大統領を務めていた1992年、国防総省にいたマーシャルの弟子たちは唯一の超大国を維持するという立場からDPG(国防計画指針)の草稿を作成した。この草稿が外部へ漏れ、問題になって書き直されてようだが、2000年にネオコンのシンクタンクPNACが公表した「米国防の再構築」という報告書で復活している。2000年の大統領選で何とか勝利したジョージ・W・ブッシュ大統領を支えたのは、こうしたネオコン人脈だった。 このDPGを出発点とする戦略の延長線上にあるのがイラク、イラン、シリア、リビア、レバノン、ソマリア、スーダンを攻撃するという攻撃予定国リスト。そして中国敵視政策である。 石原親子の放火で予想外に火が燃え広がるということも考えられ、そうなるとマーシャルの原点回帰、つまり核戦争という可能性も出てくる。そこまでに至らなくても、中国なしには存在できなくなっている日本経済が大きなダメージを受けるような事態は十分にありえる。
2012.08.23
-
明治以降のアジア侵略には英国の影が見え隠れするのだが、ここに来て活発に動きはじめた「大日本帝国の亡霊」は米国の戦略家の影響を強く受けている(その1)
中国の体制を暴力的に転覆させようという勢力がアメリカには存在する。このところ、そうした勢力の動きが目立つ。その影響からか、「大日本帝国」の亡霊のような人たちが日本で息を吹き返したようだ。そうした中で尖閣諸島/釣魚台群島や竹島/独島の問題に火がつき、日本は東アジアで孤立する道、つまりアメリカへの従属を強める道を歩き始めた。 海外との交流が制限されていた徳川時代、日本は隣国と友好的な関係を築いていた。状況が大きく変わるのは明治以降。友好的な関係は崩れ去り、現在に至っている。明治政府の背後にイギリスが存在していたことは言うまでもない。 当時、イギリスは貿易で清(中国)に完敗、経済的に追い詰められていた。そこで考えられたのが麻薬取引。清にアヘン(ケシから作られる麻薬の一種)を売りつけることで窮地を脱しようと計画、麻薬取引を禁止しようとする清と対立する。そして1840年にアヘン戦争が始まった。 その戦争で大儲けしたジャーディン・マセソン商会が1859年に日本へ送り込んできたのがトーマス・グラバーである。緑茶を買い付けるためということだったが、すぐ武器商人へ変身する。 1859年にはイギリスから駐日総領事としてラザフォード・オールコックが赴任してくる。そして決められたのが長州藩の若者をイギリスへ留学させる話。そして選ばれた井上聞多(馨)、遠藤謹助、山尾庸三、伊藤俊輔(博文)、野村弥吉(井上勝)の5名は1863年にロンドンへ渡った。このとき、グラバーの仲介でジャーディン・マセソンの船が手配された。勿論、物見遊山の旅ではない。長州藩にもイギリスにも将来を見据えた思惑があった。 1867年の大政奉還、68年の戊辰戦争などを経て長州藩と薩摩藩を中心とする明治体制へ移行し、71年に実施したのが廃藩置県。中央集権体制、天皇制官僚国家への第一歩と言えるだろう。 ところが、藩を廃止した後、1872年に琉球藩が新たに設置される。琉球王国の滅亡と言えるだろう。そして1879年に沖縄県が置かれた。 この不自然な動きは、台湾の問題と結びついている。1871年に宮古島の漁民が難破して台湾へ漂着、現地の人に何人かが殺されるという事件があった。日本政府は清(中国)の政府に賠償や謝罪を要求、1874年には軍隊を台湾へ送り込むのだが、そのためには宮古島は自分たちの領土だということにしなければならない。つまり、琉球王国を乗っ取る必要があったわけだ。 日本の派兵は台湾で止まらなかった。1875年には李氏朝鮮の首都、漢城(現在のソウル)に通じる要衝だった江華島に軍艦「雲揚号」を派遣して軍事衝突に発展、「日朝修好条規」を結ばせることに成功した。 1894年に朝鮮半島南部で甲午農民戦争(東学党の乱)が起こると日本政府は「邦人保護」を名目にして軍を派遣、朝鮮政府の依頼で出兵してきた清と軍事衝突、日清戦争が始まって日本が勝利、95年に下関で講和条約が締結された。日本が尖閣諸島の領有を宣言し、朝鮮王朝の閔妃らを陵辱の上で日本の公使たちが殺したのはこの年のことである。その7年後、日英同盟が結ばれた。 1921年に四カ国条約が結ばれたことにともない、日英同盟は22年に廃棄される。その翌年に起こったのが関東大震災。復興のため、日本政府が頼った相手がJPモルガンで、それ以降、日本経済はJPモルガンの支配下に入る。 1933年にこの関係はギクシャクしてくる。「ニューディール」という看板を掲げ、植民地やファシズムに反対、巨大企業の活動を規制して労働者の権利を拡大するという方針のフランクリン・ルーズベルトが大統領に就任したのである。 大統領就任前の銃撃事件を生き抜いたルーズベルトだが、1933年になるとJPモルガンを中心とするウォール街の勢力がクーデターを企てる。この計画は海兵隊のスメドリー・バトラー退役少将が議会で証言したことで頓挫する。当然、日米関係にも大きな影響を及ぼすことになった。(詳しくは拙著『テロ帝国アメリカは21世紀に耐えられない』を) 第2次世界大戦で日本は敗北、連合軍、事実上のアメリカ軍が日本を占領した。言うまでもなく、最高司令官はダグラス・マッカーサー元帥。当初はマッカーサーのスタッフが日本を動かしていたのだが、1948年には別の力が日本に及んでくる。この年、ワシントンDCで創設されたACJ(アメリカ対日協議会)を実働部隊とするジャパン・ロビーだ。 そうした勢力には、ジョン・フォスター・ダレス、ジョージ・マーシャル国務長官、ロバート・ラベット国務次官、ジェームズ・フォレスタル国防長官、陸軍省のケネス・ロイヤル長官とウィリアム・ドレーパー次官、ロックフェラー財閥と関係の深いジョン・マックロイ、アレン・ダレスの腹心で極秘の破壊工作部隊OPCを指揮していたフランク・ウィズナーなどが含まれていた。1949年からOPCの東アジアでの拠点は日本になっている。この組織に触れず、下山事件、三鷹事件、松川事件を語ることはできない。 この勢力はマッカーサーの政策を攻撃、ニューズウィーク誌などのメディアを使って影響力を拡大、関西学院大学の豊下楢彦教授によると、日米関係の枠組みはジョン・フォスター・ダレスと昭和天皇によって決められるようになる。 この当時、中国では天皇が恐怖する展開になっていた。圧倒的に有利だと見られていた国民党軍が敗北、コミュニストの体制が樹立される可能性が高まったのである。そこでアレン・ダレスたちは天安門で共産党の主要幹部を一気に暗殺し、偽装帰順していた部隊を蜂起させるという作戦の準備を進めたのだが、途中で発覚して中止になった。国民党軍を率いて軍事侵攻を試みたが、これも失敗している。 そのころからアメリカの軍事戦略に関わり、今でも大きな影響力を持っている人物がいる。アンドリュー・マーシャルだ。中東/北アフリカに対する軍事介入にしても、中国に対する軍事的な圧力にしても、この人物を抜きに語ることはできない。
2012.08.23
-
シリアの体制を転覆させるため、NATOや湾岸産油国は資金、武器、軍事拠点を提供、兵士を訓練し、軍事情報を知らせているが、それでは足りず、直接介入を狙っている
シリアで戦闘が続く中、「西側」は直接介入を狙っている。今年の5月頃から「化学兵器の脅威」を「西側」のメディアは強調していたが、この辺を軍事侵攻の口実にする可能性がある。 イラクを先制攻撃する前にもアメリカ政府は「大量破壊兵器」を攻撃の理由にしていたが、存在しなかった。アメリカにしてみれば、嘘だとわかっても目的を達成してしまえば、知らぬ顔の半兵衛を決め込めば良いということだったのだろう。実際、大した問題にならなかった。 今年の春頃から「西側」のメディアはシリアの化学兵器を取り上げるようになっていたが、7月にはUPIが匿名のアメリカ政府高官の話として、シリア政府は化学兵器を使用する準備を始めたと書いている。兵器庫の所在地など具体的な話はしていないようで、単なる「お話」のレベルなのだが、ロシアや中国の抵抗で直接的な軍事介入が難しい現在、その抵抗を突破する手段として化学兵器を政府軍が使ったという場面を作るかもしれない。 実は、反政府軍が化学兵器をリビアから入手したという話が今年の6月にシリアで流れている。反政府軍に肩入れしている人たち、要するにアメリカ、イギリス、フランス、トルコ、サウジアラビア、カタールといった国の政府を信じている人びとは端から信じないだろうが、十分にありえる話だ。 リビアでムアンマル・アル・カダフィ体制が倒された後、アル・カイダ系の武装集団がシリアへ移動しているが、その時に武器も運び出された。マークを消したNATOの輸送機が武器をリビアからトルコの基地まで運んだとも伝えられている。言うまでもなく、トルコは反シリア政府軍の拠点があり、米空軍インシルリク基地でNATOから訓練を受けてきた。 そのシリアと友好的な関係にあるイランもNATO、湾岸産油国、そしてイスラエルから圧力を加えられている。金融や経済面での攻撃は実行されているが、エフライム・ハレビ元モサド(イスラエルの情報機関)長官は、アメリカの大統領選より前にイランを攻撃するとイスラエルのテレビ番組で語ったという。 こうした発言はハッタリにすぎないと考えることもできるのだが、1990年代の初めからアメリカのネオコン(親イスラエル派)が練り上げてきた戦略を考えると、口先だけだとは言い切れない。 ウェズリー・クラーク元欧州連合軍最高司令官によると、ニューヨークの世界貿易センターに航空機が突入し、ペンタゴンが攻撃された日、つまり2001年9月11日の直後にジョージ・W・ブッシュ政権は攻撃予定国リストを作成していた。そこにはイラク、イラン、シリア、リビア、レバノン、ソマリア、スーダンが載っていたというのだ。 2006年に実施された演習「ビジラント・シールド07」ではイランのほか、ロシア、中国、朝鮮も攻撃のターゲットにしているようだが、ネオコンの戦略ではアメリカの超大国体制を維持するため、「潜在的ライバル」を潰すことになっている。現在、ロシアや中国にインド、ブラジル、南アフリカを加えたBRICS影響力を強めているわけだが、この勢力が真のターゲットなのかもしれない。
2012.08.22
-
アレッポで取材中の日本人記者が殺されたが、同行していたという反政府軍は英国のテレビ局のチームを交戦地帯に誘導、政府軍に殺させようとしたことも明らかになっている
シリアのアレッポで日本人ジャーナリスト、山本美香が戦闘に巻き込まれ、首を撃たれて死亡したというが、実際にどのような状況で殺されたかは、今後の調査を待つべきだろう。 彼女は反政府軍のFSA(自由シリア軍)に同行して取材していたようだ。そのFSAは今回の件に絡んでYouTubeにアップされた映像でも、自分たちを住民の守護神であるかのように宣伝している。が、実態はかなり違うということを、本ブログでは指摘してきた。 シリアを取材する記者の多くはトルコから密輸ルートを使い、シリアへ入国しているようなので、それだけでも危険が伴う。しかもFSAはジャーナリストの死を望んでいる節がうかがえる。アメリカはベトナム戦争以来、自立したメディアを嫌っていることも忘れてはならない。 例えば、イギリスのテレビ局、チャンネル4のケース。チームの中心的な存在だったアレックス・トンプソンによると、彼らは反政府軍の罠にはまり、危うく政府軍から射殺されるところだったという。取材していたチームを反政府軍の兵士は交戦地帯へと導き、政府軍に銃撃させるように仕向けたというのだ。 イギリスやドイツなどの情報機関から政府軍の位置は知らされているはずで、意図的だったとしか考えられない。トンプソンたちは危険を察知して逃げることに成功したが、危うく殺されるところだった。今回のケースを彷彿とさせる。 サウジアラビアなどはシリアの反政府軍を雇うと公言しているが、実際、傭兵やアル・カイダ系の兵士は多いようだ。例えば、反政府軍に拘束されていたフリーランスのフォトジャーナリストによると、連れて行かれたキャンプにシリア人は見当たらず、少なくとも6名はロンドンやバーミンガムの地域で使われている発音をしていて、その中には強いロンドン南部訛りのある人物が含まれていたという。 FBIの元翻訳官で内部告発者として知られているシベル・エドモンズによると、FSAは昨年春、つまり反政府運動の開始とほぼ同じ聞きからトルコにある米空軍インシルリク基地で訓練を受けてきたと言われている。教官はアメリカの情報機関員や特殊部隊員、あるいはイギリスとフランスの特殊部隊員。 一般にFSAはシリア政府軍からの離脱組が参加していると言われているのだが、実態は傭兵やゴロツキの集まりだとする人も少なくない。何らかの形で反政府軍に接触した人は、スンニ派のサラフィ主義者がいると話している。サラフィ主義者はムスリム同胞団と同様、サウジアラビアの支配層と密接な関係にある。 ホウラ地区での住民虐殺を調べた東方カトリックの修道院長によると、虐殺を実行したのはスンニ派のサラフィ主義者や反政府軍に参加している外国人傭兵。アラウィー派やシーア派だけでなく、反政府軍を支持していないと見なされた住民はキリスト教徒であろうと、スンニ派だろうと殺されたという。
2012.08.21
-
ブラック・パンサーを武装闘争へと導いた日系米国人がFBIの情報屋だったことが発覚、ウェザーマンのケースもあり、過激な言動に振り回されてはいけないことを再認識
かつて、アメリカにはブラック・パンサーと呼ばれる団体が存在した。公民権運動が盛り上がり、泥沼化したベトナム戦争の実態が明らかになって反戦運動が活発化しつつあった1966年に創設されている。 創設当初は警察の暴力から身を守るというアフリカ系住民の組織だったが、次第に反資本主義、反ファシズム、反帝国主義、反シオニズムというような看板を掲げるようになり、次第に武装闘争へと傾斜していく。 武装路線へと導いたのは日系のリチャード・アオキなる人物。1982年にブラック・パンサーが解散した後、教育者や大学のカウンセラーとして活動していたようだが、過激派の「元活動家」で武装闘争で重要な役割を果たした人物に対し、FBIやCIAは寛容な姿勢を見せたと言えるだろう。 しかし、通常、支配グループに睨まれると、社会から抹殺される。場合によっては冤罪で刑務所に入れられ、殺される恐れさえある。例えば、アリゾナ州立大学の講師だったモーリス・スタースキー場合、FBIは彼に関する偽情報を流し、実在しない人物の名前で誹謗中傷する投書をライフ誌に送り、大学上層部にも同じ趣旨の匿名の手紙を送った。結局、彼は大学から追放されてしまう。FBIに批判的だったエドワード・ロング上院議員もライフ誌に彼を攻撃する記事が掲載され、政治的に大きなダメージを受けた。こうした例は枚挙にいとまがない。 1950年代からFBIはCOINTELPROと呼ばれる国民監視プロジェクトを実行していた。当然、ブラック・パンサーもターゲット。女優のジェーン・フォンダやジーン・セバーグ、あるいはビートルズのジョン・レノンも監視対象だった。 アオキを支配権力が受け入れた理由を明らかにしたのは、サンフランシスコを拠点とする調査ジャーナリストのセス・ローゼンフェルド。アオキは「T-2」という暗号名で呼ばれていたFBIの情報屋だったというのだ。この事実を示す文書を発見、FBIの元エージェントの証言を得ている。 アメリカの武装闘争といえば、ウェザーマンを思い出す人もいるだろう。1969年に創設された組織で、爆弾闘争を展開していた。こうした暴力的な運動を支持する環境にないアメリカでは、政府に批判的な人びとへの風当たりを強めることになり、運動に大きなダメージを与えた。日本の場合、爆弾闘争の前に大多数の「活動家」は集団転向してしまったが。 ウェザーマンの幹部で後に結婚したふたり、ウィリアム・エアーズとバーナディーン・ドールンの場合、今ではエスタブリッシュメントの一員である。 エアーズの父親、トーマス・エアーズはコモンウェルス・エジソン(電力会社)のCEOを務めるほどの大物で、その影響だろう。単純にふたりは「転向」したのか、あるいは最初から反戦運動にダメージを与えることが目的だったのか・・・。ふたりを疑惑の目で見る人がいることは確かだ。 捜査機関にしろ情報機関にしろ、支配システムにとって好ましくない団体にエージェントを送り込み、情報を入手するだけでなく、影響力を行使しようとする。場合によっては組織ごと乗っ取ることもある。 イタリアで爆弾闘争を展開したとされる「赤い旅団」は組織ごと乗っ取られたと考えられている。このグループを作ったのはトレント大学の学生。1969年のことだ。当初は比較的穏健で、理想主義的な雰囲気の漂う集まりだったという。 そのグループが武闘路線へ大きく舵を切ったのは1974年。創設メンバーでリーダー格だったふたりが逮捕され、替わって組織を率いるようになったマリオ・モレッティの影響だと言われている。ある会議のあと、その出席者が逮捕されるという出来事があったのだが、モレッティだけが逮捕を免れたということもあるようだ。赤い旅団との関係が指摘されているパリの語学学校とCIAとの関係も噂されている。 1970年代の終わりから1980年代にかけて、アメリカの情報機関と軍はイスラム(スンニ派)武装集団を組織、その中にはアル・カイダも含まれていた。このプロジェクトにサウジアラビアが協力していたことも有名だ。 アル・カイダの象徴的な存在だったオサマ・ビン・ラディンはサウジアラビア王室とも関係の深い大富豪の一員。一応、王室や一族とは仲違いしたことになっているのだが、これを信じていない人もいる。 1990年代から昨年まで、アル・カイダはアメリカの「不倶戴天の敵」だと宣伝されてきた。民主主義を破壊する口実に使われてきた「テロとの戦争」もアル・カイダが敵として想定されている。 ところが昨年、アメリカの支配層はアル・カイダと「縒りを戻した」ようだ。リビアやシリアの体制転覆プロジェクトでは、アメリカ、イギリス、フランス、トルコ、サウジアラビア、カタールなどとアル・カイダは協力関係にある。
2012.08.21
-
シリア軍の動きを正確に把握して反政府軍に知らせるため、英国の電子情報機関とドイツの情報機関が活動していると報道されているが、これも西側による軍事介入の一貫
UNSMIS(国連シリア監視団)がシリアから撤退するようだが、シリア軍を監視しているグループは存在し続ける。ドイツの情報機関がシリア軍の動きを追いかけていると書いたのはビルト紙の日曜版、ビルト・アム・ゾンターク。サンデー・タイムズ紙はイギリスの情報機関がシリア軍の動向を監視していると伝えている。 もっとも、イスラエルではイギリスとカタールの特殊部隊がシリアへ潜入していると報道、民間情報会社ストラトフォーの電子メールには、アメリカ、イギリス、フランス、ヨルダン、トルコの特殊部隊が入っているという推測が書かれているわけで、今回の報道が驚きというわけでもないが、より具体的な話が出てきたことは重要だ。 イギリスの場合、SAS(特殊部隊)やMI6(情報機関)がシリア領内で活動していると思われるが、サンデー・タイムズで登場するのは電子情報機関のGCHQ。イギリスはキプロスに中東/北アフリカを監視するための基地があり、今回もそこが使われているわけだ。 地図を見ればわかるように、キプロスは地中海の東に位置する島で、中東/北アフリカの油田やスエズ運河を守る前線基地として、また旧ソ連の通信を傍受する基地として使われてきた歴史がある。アメリカも1950年代からキプロスを利用してきた。1953年に米英両国がイランの民族主義政権を倒した際にもキプロスは重要な役割を果たしている。 キプロスは1960年に独立、マカリオス大司教(ミカエル・モースコス)が大統領に選ばれるのだが、米英の支配層は自立を許さない。1963年11月、ジョン・F・ケネディ米大統領の暗殺にタイミングを合わせるようにしてギリシャ系住民とトルコ系住民が軍事衝突、内戦になるのが序章。 マカリオス追放はギリシャのクーデターから始まった。1967年4月のことである。その結果、内務大臣だったディミトリオス・イオアニデス准将の軍事政権が成立するのだが、この背後でアメリカ政府が蠢いていたと言われている。6月にはイスラエルが奇襲攻撃でエジプト、ヨルダン、シリアなどに勝利した。第3次中東戦争だ。 そして1974年7月、ギリシャの軍事政権がキプロスでクーデターを起こした。裏でCIAが動いたと言われている。クーデター軍はマカリオスが死んだと宣伝していたが、実際はイギリスの特殊部隊に助けられ、ロンドンへ亡命している。このときのイギリス首相が労働党のハロルド・ウィルソンだったことでマカリオスは命拾いしたと言えるだろう。 その後、トルコ軍がキプロスに軍事侵攻、島はふたつに分割される。アメリカの支配層が描いていた通りの展開になったわけだ。そしてギリシャの軍事体制は幕が引かれる。 ドイツの情報機関BNDの場合、シリア沖に浮かべた船から監視、海岸線から内陸に向かって600キロメートルのあたりまでをカバーしているという。それだけでなく、トルコにあるNATOの基地でシリア軍の電話や無線を傍受し、反政府府軍に伝えられている。 ジョージ・W・ブッシュ政権が民主主義を破壊するために利用した標語、「テロとの戦争」の主役であるアル・カイダ系も反政府軍には含まれている。この矛盾しているように見える事実の中に、おそらく真実が隠されている。
2012.08.20
-
石原親子の尖閣発言を切っ掛けにして日本と中国との関係は急速に悪化、東アジアの軍事的な緊張は高まっているが、その背景にはネオコンの戦争戦略
歴史の流れは動き出したら止められなくなることがある。 今年の4月に石原慎太郎都知事はアメリカのシンクタンク、ヘリテージ財団で講演、その際に「東京都が尖閣諸島を購入することにした」と発言、中国や台湾を挑発した。その挑発に乗ったグループのメンバーが尖閣諸島に上陸、中国と台湾の国旗を掲げるのだが、それに対して日本の地方議員5名を含む10名が上陸し、日の丸を掲げた。 勿論、選挙で選ばれた議員の行動となると重みが違う。しかも、国会議員を含む約150名が「慰霊祭」を名目にして21隻の船で尖閣諸島の周辺に集まっていた。上陸したのもその参加者だという。 この船団が尖閣諸島へ向かおうとしている段階で中国政府から日本側へ「警告」がきていた。中国、香港、台湾を刺激することは明らかで、収拾不能の状態になる可能性もあるからなのだが、日本側は真剣に考えていないのか、それを願っているようだ。 現在、中国各地で抗議活動が展開され、日本製の自動車や日本関係の店が襲われる事態になっていると伝えられているが、その直接的な引き金になったのは議員による挑発行為にほかならない。今のところ抗議活動は警察が何とか抑え込める規模に留まっているが、日本側の対応次第では規模は拡大する可能性がある。 こうした抗議活動が反体制運動に発展することを願っている勢力もあるだろうが、その前に日本が困難な状況に陥る。日本の少なからぬ企業が生産拠点を中国へ移し、中国市場がなくなれば利益が出ない会社もある。エンジニアも中国やインドの若者に頼り始めているようで、外交関係だけでなく、中国の国内情勢の影響は大きい。 石原知事が購入発言をした後、丹羽宇一郎駐中国大使(当時)がイギリスのフィナンシャル・タイムズのインタビューで都の購入計画について、「日中関係に極めて重大な危機をもたらす」と語っているが、その通りの展開になっている。 ところで、ヘリテージ財団といえば、ロナルド・レーガン政権と緊密な関係にあったことで知られる団体で、情報機関/秘密工作(テロ)部隊とも近い好戦的なスタンスで知られている。1973年にエドウィン・フュルナーとポール・ウェイリッチが大手ビール会社のオーナーで有名なジョセフ・クアーズの助けを借りて創設している。 しかし、最大の資金提供者はこの3人でなく、メロン財閥のリチャード・メロン・スケイフ。情報機関と緊密な関係にあり、理事会の副理事長を1985年から務めている。この人物に触れず、アメリカの秘密工作、破壊活動を語ることはできない。 1993年からアメリカではビル・クリントン大統領に対するスキャンダル攻勢が強まるのだが、その攻撃を仕掛けていた「アーカンソー・プロジェクト」の主要スポンサーもスケイフだった。そのほか、ニュート・ギングリッジ下院議長(当時)の後ろ盾だったピーター・スミスもこの攻撃に資金を提供していた。 そうした人間が関係している団体で石原慎太郎は講演、息子の石原伸晃は昨年12月、ネオコンと好戦派の拠点であるハドソン研究所で興味深い話をしている。尖閣諸島を公的な管理下に置き、自衛隊を常駐させ、軍事予算を大きく増やすべきだとしたうえ、TPPにも好意的な姿勢を見せていた。日本をアジアで孤立させ、アメリカの巨大資本に隷属する国にしようというわけだ。 野田佳彦首相も尖閣諸島の問題に絡み、自衛隊に言及してる。7月26日の衆院本会議で「尖閣を含む領土・領海で不法行為が発生した場合は、自衛隊を用いることも含め毅然と対応する」と発言、その翌日には森本敏防衛相も尖閣諸島で「自衛隊が活動することは法的に確保されている」と述べている。これを受け、岩崎茂統合幕僚長は対処方針の策定を指示したという。野田と森本の発言ということは、アメリカ側の少なくとも一部支配層から了解を得ているのだろう。 今年に初め、アメリカでは軍事戦略の変更が伝えられた。東アジアへシフトするというのだが、これは「冷戦の亡霊」、アンドリュー・マーシャルがソ連消滅を受けて唱えていた筋書き。この新戦略によると、アメリカはステルス機と潜水艦で中国のレーダー・システムを破壊し、ミサイルで内陸深くにある施設を破壊することになっているようだ。 ネオコン(新保守)の軍事戦略はマーシャルに負うところが大きく、大統領に就任した直後のジョージ・W・ブッシュが中国脅威論を唱えたのも彼の影響であり、中東/北アフリカへの軍事侵攻もマーシャルの「御託宣」に従って行われたと言えるだろう。イラクを攻撃する前、戦争は簡単に勝利でき、支配できるとしていたが、未だに泥沼から抜け出せないでいる。
2012.08.20
-
選挙で新体制への移行が演出されているリビアだが、アル・カイダ系武装集団がシリアへ移動しても戦闘状態は続き、宗教問題や人種問題も解決されていない
リビアの混乱が続いている。新体制へ平和的に移行しつつあるかのように演出されているが、分離独立派やスンニ派の武装集団、あるいはカダフィ派などが入り乱れ、爆破事件や誘拐が横行、見通しは明るくない。リビアの資源を手に入れ、アフリカが自立するのをとりあえず阻止した「西側」の支配層にとっては問題ないのかもしれないが。 ムアンマル・アル・カダフィ体制が崩壊した後、反政府派による宗教的、人種的な弾圧が続いた。こうした問題が解決されないまま、8月19日にはトリポリの内務省ビルと女子警察学校の近くで爆破があり、死者が出ているようだ。殺し合いは御免だと考えているリビア人は少なくないだろうが、その期待が実現する目処はたっていない。 こうした混乱の中、7月に選挙が行われ、マフムード・ジブリールを代表とする「国民勢力連合」が39議席を獲得して第1党になった。リビアの場合、200議席のうち120議席は個人、80議席が政党に割り当てられているので、政党分の半分近くを獲得したことになる。 ジブリールは国民評議会の元執行委員長で「リベラル派」とされているのだが、アメリカで博士号を取得した「親米派」。昨年5月にはブルッキングス研究所で講演、リビアでカダフィ体制を転覆させる動きが出てきたのは、1980年代の半ばに始まったグローバル化の中での必然だとしている。金融のグローバル化によって多国籍企業や大富豪による富の独占システムが整備され、社会も経済も破壊されてきたことは本ブログでも触れたことがある。要するに、ジブリールは「西側巨大資本」の手先ということだ。 選挙の頃、カダフィの息子を裁く準備のためにリビアを訪れたICC(国際刑事裁判所)のスタッフ4名が4週間にわたって拘束されている。解放後、拘束されていた弁護士のメリンダ・テイラーは、リビアで公正な裁判は不可能だと語っている。それが現在のリビア。 反カダフィ派は人種差別的な色彩も濃い。サハラ以南の出身者の大半は労働者だと言われているが、「傭兵」だとして有無を言わせずに拉致し、一部は処刑されていた。「民族浄化」とも批判されている。住民が行方不明になった村もある。国連によると反カダフィ軍は約7000人を拉致、劣悪な環境の中、不当に拘束されている。この問題は未解決のまま、現在に至っている。 今月に入ってベンガジの軍情報部の建物が爆破され、刑務所が武装集団に襲われ、赤十字国際委員会(ICRC)のスタッフが誘拐され、ベンガジの東にあるミスラタではICRCのビルが爆破されている。地域間、宗派間の戦いというだけではない。 最近ではカダフィのシンパによるとみられる攻撃も報告されている。例えば、新リビア軍の装備を担当することになっていたモハメド・ハディヤ・アル・フェイトウリが射殺され、元情報将校のスレイマン・ボウズリダも頭部を撃たれている。ふたりとも早い段階でカダフィ軍から反政府軍に寝返った人物だ。 カダフィ体制を倒した主力はNATOの空軍とアル・カイダ系武装集団の地上軍。そこに分離独立派や旧王党派が加わっていた。アル・カイダ系のグループは武器と一緒にシリアへ移動、その分はリビアの安定にとってプラスかもしれないが、それだけでは混乱を終わらせることはできない。 米英仏軍が行った空爆も問題になっている。細心の注意を払って空爆したとNATOのアナス・フォー・ラスムセンは主張しているが、実際は多くの住民が犠牲になったようだ。細心の注意を払って住民を殺害したのかもしれないが。アムネスティー・インターナショナルも空爆による犠牲を調査するように求めている。
2012.08.19
-
シリアの反政府軍や背後のNATOや湾岸産油国は外部の目を嫌っているようで、メディアや国連を攻撃しているが、これはイラク戦争の初めと似た展開
シリアではジャーナリストや国連が反政府軍のターゲットになっている。イラク戦争を彷彿とさせる事態だ。 これまで反政府軍はシリアの放送局を襲撃してスタッフを殺害してきたが、それだけでなく、外国のメディアも狙っている。例えばイギリスのテレビ局、チャンネル4のアレックス・トンプソンによると、彼の取材チームは反政府軍の罠にはまり、危うく政府軍から射殺されるところだった。ホムスで取材していたそのチームを反政府軍の兵士は交戦地帯へと導き、政府軍に銃撃させるように仕向けたというのだ。 また、8月15日には国連シリア監視団が使っているダマ・ロゼ・ホテルの近くで爆発があった。国連に対する脅しだと見る人もいるが、国連はこの破壊行為を非難していないようだ。 監視団はNATOと敵対関係にあるとは思えず、レバノンのアッディヤール紙によると、ロベルト・ムード准将はアメリカ政府のためにスパイ活動をしていると、ヨルダン人の監視団メンバーがは匿名で語ったという。そうした噂の監視団も今後の作戦にとっては邪魔になってきたということかもしれない。また、アメリカ政府がシリアの反政府軍への支援を強化することを決めたと報じられた直後、コフィ・アナンも和平工作から手を引いた。 こうした展開はイラク戦争と似ている。 2003年3月にアメリカ軍を中心とする軍隊が国連を無視する形でイラクを先制攻撃、サダム・フセイン体制を倒した。侵攻軍の構成はアメリカ軍が14万8000名、イギリス軍が4万5000名、オーストラリア軍が2000名、ポーランド軍が194名。そのほか反体制派や分離独立派も参加しているようだ。 圧倒的な軍事力でフセイン体制を倒すことは容易だったが、予想されていたように、それから泥沼化していく。新体制をアメリカ、あるいはアングロサクソンにとって都合良く作り替えることは容易でなかったということだが、アメリカの内部にはイラクで混乱が続くことを願っていた勢力も存在していた可能性が高い。 その目的はともかく、アメリカのネオコン(親イスラエル派)はソ連が消滅する1991年の頃には、旧ソ連圏の国々、シリア、イラン、イラクを掃除するビジョンを持っていたようだ。欧州連合軍の最高司令官を務めた経験のあるウェズリー・クラーク米陸軍大将がそのように語っている。 この計画が実行に移される切っ掛けは2001年9月11日の出来事。この日、ニューヨークの世界貿易センターにあった超高層ビル2棟に航空機が突入、ペンタゴンが攻撃されたのである。事件の直後にアメリカ政府はアル・カイダの犯行だと断定する。 このアル・カイダは1970年代の終わりから1980年代にかけてアメリカの情報機関や軍が作り上げたスンニ派の武装集団の一部で、イラク、シリア、リビアなどでは徹底的に弾圧されていた。逆に、密接な関係にあった国がスンニ派の支配するサウジアラビア。 クラーク大将によると、9/11から10日目の時点でアメリカ政府はイラク攻撃を決定、その数週間後にはイラクだけでなく、シリア、レバノン、リビア、ソマリア、スーダン、そしてイランが攻撃予定国に名を連ねていたという。9/11の報復でないことは明らかだ。 調査ジャーナリストのシーモア・ハーシュは、2007年にニューヨーカー誌でアメリカがサウジアラビアなどと手を組み、シリアやイランを攻撃する秘密工作を始めたと警告している。 イラクへ軍事侵攻する際、ベトナム戦争での反省だろうが、アメリカ軍は情報操作を徹底しようとした。そこで記者を軍隊の中に「埋め込む」という方式。自由に取材させず、軍にとって都合の良い情報だけを発信させようとしたわけである。 しかし、それでも独自に取材しようというジャーナリストはいる。そうした中、記者の宿泊場所になっていたパレスチナ・ホテルをアメリカ軍の戦車が砲撃する。2003年4月のことだ。その後もジャーナリストがアメリカ軍によって殺されている。 その4カ月後、8月には国連支援ミッションが拠点にしていたカナル・ホテルが攻撃されて22名以上が死亡、犠牲者の中には国連事務総長特別代表だったセルジオ・ビエイラ・デメロも含まれていた。アル・カイダ系の武装グループが実行したとされている。その翌月にもミッションは攻撃され、国連のスタッフはイラクから引き上げることになった。 要するに、ジャーナリストや国連の目を嫌がる勢力が存在するということだろう。そうした勢力とは、アメリカ軍とアル・カイダと考えるの自然だ。同じようなことがシリアでも起こっている。
2012.08.18
-
民主化運動を潰すために血まみれの弾圧をしているバーレーンで人権活動家のラジャブに懲役3年が言い渡されたが、この国の民主化と人権に「西側」の政府とメディアは鈍感
バーレーンで人権と民主化を求める活動をしているナビール・ラジャブに対し、同国の裁判所は懲役3年を言い渡した。抗議活動に参加した人びとの中には死刑や終身刑の判決を受けた人、あるいは射殺されたり行方不明になった人も少なくない。政府の弾圧で負傷した人を治療したということで、多くの医師や看護婦が逮捕されている。 独裁体制に抗議する運動がバーレーンで始まったのは昨年の2月中旬。抗議活動とは言うものの、平和的で武器を持っているわけでもないのだが、政府は暴力的に弾圧、初日にひとり殺され、翌日には葬儀に参列していたひとりが射殺された。 その後も抗議活動に参加する人が次々と殺され、数十人が行方不明者になる中、2月22日には20万人が参加したと言われるデモがあった。その直後、サウジアラビアからバーレーンへ約30両の戦車が運び込まれ様子も目撃されている。3月に入ると約1000人のサウジアラビア軍兵士とUAE(アラブ首長国連邦)の警官約500名がバーレーンへ派遣された。こうした弾圧にもかかわらず、今年3月には10万から25万人が参加したデモが実行されている。 バーレーンの場合、「西側」が反政府派に資金や武器を提供するわけでもなく、反政府軍が編成されるわけでもなく、したがって戦闘と呼べるような事態にはなっていない。まさにバーレーンこそが真の「アラブの春」なのだが、「西側」は政府もメディアも冷淡。 何しろ、この国は歴史的にイギリスと関係が深く、現在はアメリカ海軍の第5艦隊が司令部を置いている。また、エジプト、ヨルダン、シリア、イラク、イエメン、パキスタンなどから傭兵を雇う伝統もある。 こうした湾岸産油国がアメリカ、イギリス、フランス、トルコなどと手を組んでイスラム世界の再編成を目指し、リビアの体制を転覆させ、今はシリアに軍事介入している。こうした「新秩序」はアメリカのネオコン(親イスラエル派)が1991年頃から練り上げてきた作戦と合致している。 アル・カイダを含むイスラム武装勢力を1970年代の終わりに組織、手駒として使ってきたのはアメリカの軍や情報機関だが、サウジアラビアを初めとする湾岸産油国はこのプロジェクトに協力、支援してきた。1980年代にサウジアラビアはニカラグアの反革命ゲリラ、コントラも支援している。
2012.08.17
-
シリアの戦闘は民主化闘争でも内戦でもなく、外国からの軍事侵攻だとする報告がこれまでも伝えられていたが、ここに来て国連も反政府軍を善玉と言い切れなくなった
シリアで激しい戦闘が続いている。そうした戦闘の中で破壊、誘拐、拷問、虐殺などが繰り返されているのだが、その責任は政府側と反政府側、双方にあるとする報告書を国連がまとめた。戦闘が長引くにつれ、「民主化を求める運動」という宣伝文句が効力を失いつつあり、バシャール・アル・アサド政権を一方的に非難することが難しくなっている。 発端は、昨年3月に民主化を要求するデモだとされている。このデモを政府軍が暴力的に弾圧したというのだ。この情報を否定している人は少なくなかったが、そのひとりとしてシリア駐在のエリック・シュバリエ仏大使が加わった。 シュバリエによると、運動は外国から入ってきたグループに扇動されたもので、報道とは違い、緊張が高まるにつれて運動は小さくなって激しい弾圧という事態にはならなかった。 そこで、そのように政府へ報告したわけだが、その報告に怒った人物がいる。アラン・ジュペ外務大臣兼国防大臣(当時)だ。流血の弾圧になっていると書き直せと言われたという。フランスの通信社、AFPも大臣から圧力が加えられたようだ。 今年1月にフランス人ジャーナリストのジレ・ジャキエがシリアで殺されている。この事件が起こった後、メディアの人間として活動しているDGSE(フランスの情報機関)のエージェントを引き上げさせるように大使は命令されたとも伝えられている。ジュペはシリアで秘密工作を実行していたとシュバリエは理解したという。 今年の3月、シリア軍は18名のフランス人将校と100名の戦闘員を拘束したとレバノンの議員は主張、後に拘束されていた3名のフランス人が、フランスのエドアール・ギヨー参謀総長に引き渡されたとも伝えられている。ただ、どの程度、信頼できる情報なのかは明確でない。 シリアで戦闘が始まった当初から外国から侵入した戦闘員は住民を殺害、恐怖で社会を混乱させようとしたとも報告されている。反政府軍の主力と言われる「FSA(自由シリア軍)」も実態は傭兵が中心のようで、トルコにある米空軍のインシルリク基地で訓練を受け、アメリカの情報機関員や特殊部隊員、あるいはイギリスやフランスの特殊部隊員が教官を務めているという。コソボで訓練を始めるという話も伝わっていた。シリアへの攻撃拠点はトルコのほか、ヨルダンやレバノンにもあると言われている。 シリアの北部で反政府部隊に拘束されていたフリーランスのフォトジャーナリストも解放後、反政府軍は外国人によって編成されていたと証言している。キャンプにシリア人は見当たらず、ロンドンやバーミンガムの地域で使われている発音をする人間も複数いて、中には強いロンドン南部訛りのある人物が含まれていたという。 ホウラ地区で住民を虐殺も当初はシリア軍による攻撃が原因だとされた。この嘘がばれると政府派の武装集団が実行したとする報道があふれたが、ドイツのフランクフルター・アルゲマイネ紙は反政府軍が虐殺したと伝えている。この情報はローマ教皇庁のフィデス通信が伝えた東方カトリックの修道院長の話に合致する。ドイツではフランクフルター・アルゲマイネ紙だけでなく、ビルト紙やディ・ベルト紙もホウラでの虐殺が反政府軍によるものだと報道している。 カトリックの聖職者が語ったように、全ての人が真実を語れば、シリアに平和が訪れることだろう。真実を語っていないのは、勿論、アメリカ、イギリス、フランス、トルコ、サウジアラビア、カタールといった国々である。国連もその影響下にある。
2012.08.16
-
ポツダム宣言の受諾を連合軍に通告した翌日、昭和天皇の「終戦勅語」が放送されたのだが、この天皇には戦争責任だけでなく「戦後責任」もあることが明らかになっている
広島と長崎に原子爆弾が投下され、ソ連が日本に宣戦を布告した直後に開かれた「御前会議」で日本はポツダム宣言の受諾、つまりアメリカ、イギリス、中国、ソ連に降服することを決め、8月10日夜半には同盟通信の海外向け放送でこの決定を明らかにしている。最終的な受諾通告は8月14日。日本軍に停戦命令が出たのは放送の翌日、降伏文書に調印したのは、つまり正式な降服は9月2日ということになる。 ポツダム宣言受諾通告の翌日、「終戦勅語」がラジオで放送された。堀田善衛氏の言葉を借りるならば、その内容は「負けたとも降服したとも言わぬ」不審なもので、日本に協力させられた国々に対しては、「遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス、という、この嫌みな二重否定、それきり」で、「その薄情さ加減、エゴイズム、それが若い私の軀にこたえた」(堀田善衛著『上海にて』)代物だった。 戦後日本の出発点はポツダム宣言にあるわけだが、その第8条には次のように書かれている。「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」 カイロ宣言は、「第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国カ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト」、また「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」としているだけでなく、「暴力及貧慾ニ依リ日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルヘシ」としている。 そして1946年1月に出された「連合軍最高司令部訓令」によると、日本の領土とは「4主要島と対馬諸島、北緯30度以北の琉球諸島等を含む約1000の島」で、竹島、千島列島、歯舞群島、色丹島などは除かれている。(孫崎享著『日本の国境問題』) 近代日本の侵略は琉球処分から始まる。琉球/沖縄は15世紀の初めに尚巴志によって統一され、明(中国)に朝貢し、貿易で栄えるのだが、その繁栄に目をつけたのが薩摩藩で、17世紀には支配下に入れ、富を奪うようになった。ただ、そうした状態になっても琉球は中国との外交や貿易を続けている。 19世紀になると、薩摩藩は長州藩と手を組み、徳川幕府を倒すことになった。1868年に新政府がスタート、71年に「廃藩置県」を実施している。幕藩体制との決別だ。 ところが、翌1872年に琉球藩が設置され、79年に沖縄県がおかれた。最初から計画していたなら、琉球藩をでっち上げてから廃藩置県に進んだのではないだろうか。この不自然な動きは、廃藩置県の後に琉球を乗っ取る何らかの事情が生じたことを暗示している。 琉球藩を設置する前年、宮古島の漁民が難破して台湾へ漂着、現地の人に何人かが殺されるという事件があった。日本政府は清(中国)の政府に賠償や謝罪を要求、1874年には軍隊を台湾へ送り込んだ。この侵略を正当化するためには、宮古島は日本領だということにする必要があった。 翌1875年には李氏朝鮮の首都、漢城(現在のソウル)に通じる交通上の要衝だった江華島に軍艦「雲揚号」を派遣して挑発、軍事衝突に発展、「日朝修好条規」を結ばせることに成功、この条約で清国の宗主権が否定される。 1894年に朝鮮半島南部で甲午農民戦争(東学党の乱)が起こると日本政府は「邦人保護」を名目にして軍を派遣、朝鮮政府の依頼で出兵してきた清と軍事衝突、日清戦争が始まった。琉球処分から日清戦争まで、ひとつのシナリオになっている。そしておそらく、幕の後ろにはイギリスがいた。 結局、戦争は日本が勝利、1895年に講和条約(下関条約)が結ばれ、朝鮮の独立(清国の影響力排除)、遼東半島、台湾、澎湖諸島の割譲、庫平銀2億テール(約3億円)の賠償金支払い、威海衛の一時占領等々が決められた。日本政府が尖閣諸島を日本領にすると閣議決定したのはこの年である。 こうした歴史を考えると、日本が第2次世界大戦で敗北した後、沖縄は独立しても不思議ではなかった。 そうした状況の中、1949年9月、昭和天皇は、アメリカによる沖縄の軍事占領が「25年から50年、あるいはそれ以上にわたる長期の貸与(リース)というフィクション」のもとでおこなわれることを求めるというメッセージを出したという。(豊下楢彦著『安保条約の成立』)また、『入江相政日記』には「アメリカに占領してもらふのが沖縄の安全を保つ上から一番よからうと仰有つたと思う旨の仰せ」とある。 関西学院大学の豊下楢彦教授が明らかにしたように、戦後の日米関係は昭和天皇とジョン・フォスター・ダレスたちによって築かれている。吉田茂やダグラス・マッカーサーは途中から脇役にすぎなくなる。つまり、対米従属の責任を吉田に押しつけるのは間違っているということである。
2012.08.15
-
米国大統領選の投票日より前にイスラエルはイランを攻撃するという話が広がる中、パネッタ米国防長官はイスラエル政府に自重するよう求めたが、攻撃は90年代初頭からの計画
イスラエル政府はイランを攻撃すると脅している。こうした中、アメリカのレオン・パネッタ国防長官はイスラエルを訪問、攻撃を思いとどまるように説得を試みたというのだが、そのとき、エフライム・ハレビ元モサド(イスラエルの情報機関)長官は、12週間以内にイランを攻撃するとイスラエルのテレビ番組で語ったという。アメリカの次期大統領を決める投票日より前に開戦するという脅しだ。イスラエル国民の多くはイラン攻撃に反対しているのだが、政府は強硬姿勢を見せている。 しかし、アメリカの支援なしにイスラエルがイランを攻撃することは難しい。そこでバラク・オバマ政権はイスラエルに対し、イラン攻撃にアメリカ軍が参加するとは考えないように伝えているのだが、「経済攻撃」を強化する方針を明らかにした。 ただ、武器による攻撃を回避するために経済戦争を強化しても平和には向かわない。かつて、アメリカの軍や情報機関の好戦派がソ連に対する核攻撃を計画していた際、ソ連はアメリカに近いキューバへ核ミサイルを持ち込んでいる。核弾頭の運搬手段の劣勢をカバーするためだったのだろうが、このときにジョン・F・ケネディ米大統領は海上封鎖をした。 この対応でキューバへの軍事侵攻を主張する意見を押さえる一方、ソ連政府と直接、対話している。つまり、海上封鎖しただけなら核戦争に突入した可能性が高かった。このあと、ケネディ大統領は1963年6月、暗殺される5カ月前にアメリカン大学でソ連との平和共存を訴える演説を行っている。 しかし、オバマ政権の場合、軍事的な緊張を緩和するためにイランと体を張って話し合っているようには見えない。つまり、イランに対する経済戦争は軍事衝突への一里塚ということになりかねないということだ。経済戦争の強化に反対するロシア政府から強い反発があり、非常に危険な方向へ進んでいる。 本ブログでは何度も書いてきたが、ウェズリー・クラーク元欧州連合軍最高司令官によると、ジョージ・H・W・ブッシュ政権の時代に、ポール・ウォルフォウィッツ国防次官(当時)は旧ソ連圏の国々、シリア、イラン、イラクを掃除すると発言している。ソ連が消滅し、「唯一の超大国」として潜在的なライバルを潰すという目的もあったようだ。 この戦略に基づいて「DPG(国防計画指針)」が作成され、この指針も基づいてネオコンのシンクタンク、PNAC(新しいアメリカの世紀プロジェクト)は2000年に「米国防の再構築」を公表した。 ジョージ・H・W・ブッシュの息子、ジョージ・Wが大統領に就任した2001年の9月11日、ニューヨークの世界貿易センターとペンタゴンが攻撃された。その直後に国防長官の周辺はイラク、イラン、シリア、リビア、レバノン、ソマリア、スーダンを攻撃する計画を始動させている。「911」はアル・カイダが実行したのブッシュ・ジュニア政権は主張していたにもかかわらず、アル・カイダと敵対関係にあったイランを先制攻撃、計画の第一歩を踏み出した。 2007年になると、ジョージ・W・ブッシュ政権はサウジアラビアなどと手を組み、シリアやイランを攻撃する秘密工作を始めたと調査ジャーナリストのシーモア・ハーシュは警告している。実際、工作を始めたようだ。 この記事が出る前年、アメリカは「ビジラント・シールド07」という演習を実施しているのだが、その仮想敵にはロシア、中国、朝鮮も含まれていた。イラク、リビア、シリアに続いてイランに対する攻撃を「西側」は準備しているが、その先にはロシアや中国も見えている。 そこでロシアや中国はシリアへの軍事介入にブレーキを掛けているのだが、アメリカ、イギリス、フランス、トルコ、サウジアラビア、カタールといった国々は軍事介入をエスカレートさせている。 ところが、シリア政府は「西側」が想定したよりもしぶとく、未だに潰れていない。戦闘が長引くうちに反政府軍が傭兵を主体とした残虐な殺人集団にすぎないことが明らかになりつつある。こうした状況を打開するため、アメリカ政府はシリアの反政府軍への支援を強化することを決めたと報じられている。その直後にコフィ・アナンは、和平工作から手を引いた。 シリアの体制転覆を目指している国々は、政府軍機を撃墜させるため、ポータブル型の地対空ミサイル、スティンガーをトルコ経由で反政府軍に供給、さらにロシア製のT-62戦車をリビアから運び込んだという。いずれもアル・カイダ系武装集団の手に渡ることを意味している。
2012.08.14
-
ウィキリークスが公表した文書の中にトラップワイヤという不審者を捜し出す監視システムが登場、改めて個人の顔を認識する仕組みを警戒する声が挙がっている
監視カメラを使い、街を行き交う全ての人を監視するシステムに関する新しい情報が出てきた。内部告発支援サイトのウィキリークスが公表した民間情報会社、ストラトフォーの電子メールの中に登場する話で、アブラクサスというアメリカの会社が開発したトラップワイヤが問題のシステム。創設メンバーは「元CIAエージェント」だという。 このシステムは不審な行動、例えば破壊活動の事前調査や兵站計画を察知するというのだが、これに似たシステムがイラクで使われているという話も何年か前に流れていた。当然、間違いもあるわけで、戦闘とは無関係に人びとが犠牲になっているようだ。 顔の認識や行動パターンの分析をするシステムが単独で動くということは考えにくい。アメリカ国防総省のDARPA(国防高等研究計画局)が研究開発していたTIA(総合情報認識)なるプロジェクトでは、個人の学歴、銀行口座の内容、ATMの利用記録、投薬記録、運転免許証のデータ、航空券の購入記録、住宅ローンの支払い内容、電子メールに関する記録、インターネットでアクセスしたサイトに関する記録、クレジット・カードのデータなど、あらゆるデータの収集と分析がテーマになっていたが、こうした情報と連携したシステムになるはずだ。 このプロジェクトの存在が発覚すると問題になるが、似たようなプロジェクトは次々に出てくる。表面的には中止したことになっていても、実際は研究開発が進んでいるとも言えるだろう。 そうした監視システムのひとつがMATRIX。このシステムを開発したフロリダ州の会社、シーズント社にはジェブ・ブッシュ、つまりジョージ・W・ブッシュ前大統領の弟も関係している。 この会社はスーパー・コンピュータを使い、膨大な量のデータを分析、「潜在的テロリスト」を見つけ出そうとしていたとも言われている。どのような傾向の本を買い、借りるのか、どのようなタイプの音楽を聞くのか、どのような絵画を好むのか、どのようなドラマを見るのか、あるいは交友関係はどうなっているのかなどを調べ、分析しようというのだ。自分たちの支配体制に歯向かいそうな人間を早い段階にあぶり出そうと考えているわけであ。 こうした監視システムの開発と利用はアメリカとイギリスが共鳴し合いながら進められている。今年の夏にロンドンで開かれたオリンピックも「監視の祭典」だった。何しろ、イギリスには420万台とも言われる監視カメラが設置される「監視先進国」だ。 日本はアメリカを追いかける。つまり、「防犯」という名目で監視カメラのネットワークを強化してきた。住民基本台帳ネットワークがシステムの背骨になる可能性が高い。顔の認識システムに関しても日本の技術力は高く評価されていて、1秒間に3600万人の顔を認識、ターゲットを探し出すシステムを日立国際電気が開発したことも話題になった。 日本の支配層を過小評価してはならない。彼らは優秀だ。「日本」をひとつの集団だと考えるから政治家や官僚が愚かに見えるだけのこと。一部の多国籍企業や富裕層(日本人とは限らない)のために働いていると考えれば、合理的な判断をしていることがわかる。庶民が貧困化し、餓死したところで彼らは気にもしないことだろう。早死にしてくれれば「年金問題」も「健康保険問題」も解決する・・・その程度のことを考えていたとしても不思議ではない。 もっとも、彼らの仲間に入れて貰えたと思っているマスコミは本当に愚鈍だが。
2012.08.14
-
27年前に御巣鷹山で日航123便が墜落した原因はボーイング社の修理ミスが原因だとされているが、このシナリオは穴だらけで全く信用できない代物
今から27年前、1985年8月12日に日本航空123便が群馬県南西部の山岳地帯に墜落、乗員乗客524名のうち520名が死亡した。羽田空港を離陸、伊丹空港に向かっていたのだが、18時24分頃、相模湾上空のあたりで異常事態が発生したと考えられている。 運輸省航空事故調査委員会は、ボーイング社の「修理ミスが原因」だとしている。「飛行中に後部圧力隔壁が客室与圧に耐えられなくなって破壊し、客室内与圧空気の圧力によって尾部胴体、垂直尾翼が破壊され、油圧系統も破壊され操縦不能となり墜落した」というのだが、再現実験で客室ないの急減圧がなかったことが確認され、委員会のシナリオに説得力がないことが示されている。 急減圧した場合、酸素マスクをつけなければ、3分程度で小学校1年の国語教科書を読む速度が遅くなり、6分30秒を経過すると手に痙攣が見られるようになり、チアノーゼで指先が紫色に近くなることがわかっている。ところが、異常が発生してから約9分後でも123便の機長は酸素マスクをつけていないにもかかわらず、手の痙攣や意識障害はなかった可能性が高い。 123便に異常事態が発生した頃、大島の上空をアメリカ軍の輸送機C-130が飛行していた。そのクルーだったマイケル・アントヌッチは、1995年8月27日付けの「星条旗」で興味深い話を明らかにしている。 彼によると、18時40分には叫び声のようなコールを聞いている。明らかに尋常ではなかったので、横田基地の管制から許可を受けた上で日航機に接近を図ったという。 日航機は18時56分には墜落したが、その地点を彼らの輸送機は19時20分に特定、報告している。運輸省に捜索本部が設置されたのは19時45分。この時点で正確な墜落地点を捜索本部、そして日本政府は把握していたはずである。地上でも、住民などから正確な墜落地点が伝えられていたようだ。 米軍機の報告を受け、厚木基地から海兵隊の救援チーム(後に座間の陸軍と訂正されたようだ)が現地に向かい、20時50分には救援チームのヘリコプターが現地に到着した。早速、2名の隊員を地上に降ろそうとしたのだが、このときに基地から全員がすぐに引き上げるように命令されたという。日本の救援機が現地に急行しているので大丈夫だということだった。21時20分に日本の救援部隊を乗せた航空機が現場に現れたのを確認してからC-130と米軍の救援チームはその場を離れた。 墜落から間もない段階で自衛隊が現場にいたことは明らかにされていなかったが、今では百里基地のヘリコプターが救援に向かったとされているようだ。自衛隊が現場に到着したのは20時42分だという。すでのC-130はいたはずだが、米軍のヘリコプターが到着する8分前ということになり、アントヌッチの証言と矛盾する。 それはともかく、到着した自衛隊は救援活動を行っていない。「本格的な夜間救援装備がない」ので隊員を降下させなかったというのだが、では、何のために現場へ向かったのだろうか。もし、救援に向かいながら救援に必要な装備を持っていかなかったという間抜けな話が事実なら、自衛隊機の後に来たアメリカ軍の救援活動を止めるべきではなかった。もし、自衛隊側が自分たちのヘリコプターが到着した時刻を間違っていて、米軍側が正しかった、つまり自衛隊の方が後から来たということなら、すぐに米軍に引き返してもらうべきだった。結局、長野県警の機動部隊員がヘリコプターから現場へ降下したのは翌日の8時半頃だ。 自衛隊は何かを隠そうとしている・・・そう思われても仕方がない。何らかの形で尾翼が関係している可能性が高い。そういう事実があるならば、勿論、アメリ政府は真相を知っているだろう。その内容によっては、日本政府を脅す材料になる。 事実を隠して責任を回避するという日本政府の体質は、東電福島第一原発の事故への対応と基本的に同じなようだ。
2012.08.13
-
レビン米上院議員から「詐欺的で反道徳的」な取り引きをしていると批判されているゴールドマン・サックスを起訴しないと司法省は発表、国民からの信頼をなくすことに
ゴールドマン・サックスの取り引きについて調べていたアメリカの司法省は8月9日、同社や同社の社員を起訴しないと発表した。この決定はゴールドマン・サックスには朗報かもしれないが、司法省は国民の信頼をなくすことになるだろう。 司法省に調査を要求していたのはアメリカ上院の調査小委員会。2008年に始まった金融危機は、ゴールドマン・サックスが主導したサブプライム・ローン不動産投資が原因になっているとされていて、カール・レビン委員長はゴールドマン・サックスの行ったことは詐欺的で反道徳的だと批判している。ゴールドマン・サックスは責任をとらないまま逃げ果せるだろうか? この委員会では約2年間にわたって不動産取引について調査、2011年春には詳細な報告書を発表している。レビン委員長の発言はこの調査に基づくものだった。司法省の調査終了宣言を受け、法律が貧弱なのか、捜査機関が貧弱だとレビン委員長は批判したのも、そうした背景があるからだ。 確かに、国際化した金融取引を規制する法律は存在しないに等しい。つまり無法地帯。その無法地帯を利用して蓄財している議員も多いはずで、今回の問題で不正行為に批判的な議員は少数派だろう。 委員会では、次のような有名なやりとりがあった。レビン委員長の質問に答えているのは、ゴールドマン・サックスで不動産取引の責任者だったダン・スパークスである。【レビン】もし、顧客とゴールドマン・サックスとの間で利害の相反があった場合、顧客に商品を売るとき、その利害相反を顧客に伝える義務があなた方にはありますか?【スパークス】委員長、利害の相反が何を意味するかを理解しようと試みています。【レビン】いや、あなたは理解していると思う。あなたに答える意志があるようには思えない。 要するに、ゴールドマン・サックスは顧客と会社との間で利害が対立する場合、その事実を顧客に伝えないというわけだ。レビン委員長が「詐欺的で反道徳的」と表現した意味が、このやりとりの中に凝縮されている。 サブプライム・ローン不動産投資とは、通常なら住宅を買うことが難しい低所得者に高い金利でカネを貸し、住宅を購入させる取り引きに基づいている。少し考えれば、「持続可能」な仕組みではないことがわかる。一種のマルチ商法だとも言えるだろう。 勿論、不動産相場が上昇していれば物件の担保価値は膨らみ、さらに顧客は資金を借りることができる。が、相場が天井を打ったとき、この錬金術は一気に破綻してしまう。それが2006年から07年。当然、相場が下がり始めると借金を返済できなくなる人が増えてくる。相場の下落は不動産の売却を導き、さらに値下がりする。負の連鎖。 庶民が自分自身の資産で不動産を購入できていれば、これほど大きな問題になることはなかった。1980年代から急速に進んだ富の集中で庶民は貧困化、経済活動や社会生活はその時点で破綻していたのだが、これを誤魔化すために考えられたのが借金だった。借金で不動産を買わせ、その不動産を使った金融商品が売られたわけである。 一部の多国籍企業や富裕層に富を集中させるためにタックス・ヘイブンが利用されてきた。1970年代に登場したロンドンを中心とするオフショア市場ネットワークは資産を隠し、税金を逃れるために大きな役割を果たしている。世界の富はオフショア市場を通って地下経済の世界に吸い込まれ、地上は「恐慌」から抜け出せない。 こうした地下経済の世界で主要なプレーヤーと言われているのがリーマン・ブラザーズ、ベア・スターンズ、モルガン・スタンレー、メリル/ボア、シティーコープ、JPモルガン、そしてゴールドマン・サックスだ。 サブプライム・ローンの問題では、メリル・リンチ、シティーコープ、UBS、モルガン・スタンレー、HSBC、ベア・スターンズなどが大きな損を出している。これだけみると仲間内での問題のように見えるが、尻ぬぐいは庶民に押しつけられる。 ギリシャの債務危機も原因を作ったのはゴールドマン・サックス。巨大企業や富裕層がオフショア市場を使って資産を隠し、税金から逃れてきたことが根本だが、2001年にこの銀行はギリシャに財政状況の悪さを隠す手法を教え、債務を膨らませたことで問題は深刻化することになった。日本のマスコミは巨大企業や富裕層の問題には目をつぶり、「労働者の搾取が足りない」と宣伝する。救いがたい連中だ。 この問題でもゴールドマン・サックスの責任が問われることはなさそうである。なにしろ、ヨーロッパ中央銀行のマリオ・ドラギ総裁は2002年から2005年までゴールドマン・サックスの副会長を務めた人物であり、アイルランドのピーター・サザーランド元司法大臣はゴールドマン・サックス系列のゴールドマン・サックス・インターナショナルの会長であり、1998年から2006年までヨーロッパ中央銀行役員会メンバーだったオトマール・イッシングはゴールドマン・サックスの顧問。イタリアのマリオ・モンティ首相もゴールドマン・サックスの顧問。ヨーロッパにも強力なネットワークがある。 この銀行は日本とも関係が深い。小泉純一郎政権の時代に西川善文や竹中平蔵はゴールドマン・サックスのヘンリー・ポールソンCEO(後の財務長官)やジョン・セインCOOと会談、「郵政民営化」の動きが本格化した。
2012.08.12
-
米国でシーク教の寺院が襲撃されたが、犯人は特殊部隊の心理戦専門家だった人物で、襲撃犯は複数という証言もあり、フランスやノルウェーの事件と同様、疑惑の目
今月の8日、アメリカのウィスコンシン州にあるシーク教の寺院で銃撃事件があり、6名が殺され、4名が負傷した。銃撃したウエイド・マイケル・ペイジは腹部に銃弾を受けた後、死亡している。最初は警官に射殺されたと伝えられたが、後に自分で頭部を撃ち抜いたと訂正された。 最近、何らかの事件があると、監視カメラの映像が出てくるのだが、このケースでは寺院のカメラが肝心なときに切られていて、映像はないという。現場にいた人の証言によると、寺院に押し入ったのはひとりでなく複数、4名だとする人もいる。こうした証言が正しいとするならば、ペイジのほかにも銃撃犯はいることになるのだが、警察はこうした証言を無視しているようだ。 ペイジの経歴も注目されている。1992年から98年まで陸軍に所属しているのだが、95年には特殊部隊の本拠地、ノースカロライナ州にあるフォート・ブラグへ配属、そこで心理戦の専門家になっている。ちなみに、ペイジが退役した直後、複数の心理戦の専門家がCNNの内部で数週間、テレビ局員として活動していたことが2000年2月に発覚している。 このところ、人の集まる場所で銃を乱射するという事件が繰り返されている。例えば、今年3月にフランスのトゥールーズでユダヤ人学校が襲われた事件、昨年7月にノルウェーで77名が殺害された事件。 トゥールーズの事件で犯人とされているモハメド・メラは警察の特殊部隊に射殺されたという。この人物、アル・カイダとの関係が指摘されているのだが、その一方でフランスの情報機関DGSEや治安機関DCRIの協力者だという情報も流れている。 メラは2010年にアフガニスタンを訪れているのだが、その前にトルコ、シリア、レバノン、ヨルダン、そしてイスラエルに立ち寄ったとも言われている。イスラム圏の国々を立て続けに旅行してからイスラエルへ入るというのは不自然な気もするのだが、イスラエルへの入る際、DGSEが便宜を図ったとも伝えられている。そこから兄弟のいるエジプトへ行き、アフガニスタンへ向かったようだ。 この事件では、銃撃の様子を撮影したビデオがカタールのテレビ局、アル・ジャジーラへ郵送されている。消印は事件の当日。自分自身で投函できる状況ではなかったことから「単独犯」という公式見解も揺らいでいる。 ノルウェーの事件では、まずオスロの政府ビル前に駐車していた自動車が爆発して8名が死亡、その2時間後に与党である労働党の青年部が企画したサマーキャンプが襲撃されて69名が殺されている。アンネシュ・ブレイビクが単独で実行したということになっているが、複数の目撃者が別の銃撃者がいたと証言している。ブレイビクはテンプル騎士団との関係を口にしているようだが、真相は不明。 ちなみに、ノルウェーはNATOの加盟国としてリビアへの空爆に参加していたのだが、ノルウェー政府は8月1日までに部隊を引き上げると事件の前月に発表していた。
2012.08.11
-
シリア国民と遊離した反政府軍はNATOや湾岸産油国から資金や武器の支援を受け、拠点を提供され、訓練も受けているのだが体制転覆に成功せず、飛行禁止空域の話も出てきた
昨年春から中東の体制転覆運動が続いている。NATOや湾岸産油国は当初から反政府軍を支援してるのだが、いまだにシリア政府は倒れていない。その間、反政府軍の残虐行為が明らかにされ、「民主化を求める運動」というスローガンは血まみれだ。 そうした中、バラク・オバマ米大統領の対テロ上級顧問のジョン・ブレナンは「飛行禁止空域」の設定を否定していないと発言した。シリアを空爆することもありえるということだが、そうなると、中国やロシアとの戦闘に発展する可能性が出てくる。つまり第3次世界大戦。 リビアやシリアの場合はイギリスの積極性が目につくのだが、中東/北アフリカの制圧は1990年代、アメリカのネオコン(親イスラエル派)が打ち出した戦略。2007年になると、アメリカのジョージ・W・ブッシュ政権はサウジアラビアと手を組み、シリアやイランに対する秘密工作を始めたと伝えられていた。こうした流れを無視して現在の状況を判断することはできない。 アメリカ、イギリス、フランス、トルコ、サウジアラビア、カタールといった国々はすでにシリアの体制を倒すため、軍事介入している。反政府軍を編成、資金や武器を提供、将兵を訓練、トルコ、ヨルダン、レバノンなどに軍事拠点を作り、自国の特殊部隊を潜入指せている国もあるとイスラエルや報道されたほか、ウィキリークスが公表した文書の中にもそうした推測が書かれている。 また、アレッポでトルコとサウジアラビアの将校が拘束されたとシリアでは伝えられている。反政府軍側は否定しているようだが、実際に拘束されていたとしても、不思議ではない。 こうした状況は、シリア国民の多くが反政府派より政府を支持していることを示唆している。実際、反政府軍に拘束されたフリーランスのフォトジャーナリストによると、連れて行かれたキャンプにシリア人は見当たらず、少なくとも6名はロンドンやバーミンガムの地域で使われている発音をしていて、その中には強いロンドン南部訛りのある人物が含まれていたという。 革命が成功するためには、国民の支援が不可欠。例えば、マエストラ山脈でキューバ革命を始めたのは10名余りにすぎないが、それでも革命が成功したのは庶民の支持があったからにほかならない。第2次世界大戦で日本が降服した翌年、中国ではアメリカの支援を受けた国民党軍が紅軍(コミュニスト軍)と衝突する。総兵力で比較すると約430万人と約120万人の戦いだが、最終的に勝利したのは紅軍(途中、人民解放軍に改称)だった。これも農民が紅軍/人民解放軍を支持したからである。 リビアにしろシリアにしろ、民主化を求める国民を政府が暴力的に弾圧しているというシナリオが使われている。つまり、反政府軍は「民主化勢力」という位置づけ。日本に限らず、「左翼」を自称している人びとがこのシナリオに乗っているらしい。 もしアドルフ・ヒトラーが自分たちの政党名を「自由」とか「民主主義」とか「人権」といった名詞で飾り立てたなら、ヒトラーの政党は実態に関係なく、自由で民主的な人権を尊重する集団だということになるのだろうか? 自分が住んでいる国の権力者がそう言っているなら、自分たちもそう思っているということにする。そうした方が平穏な生活を送れる。中には権力者の主張を自動的に信じるという思考回路ができあがっている人もいるだろう。万一、その権力者が失脚したら、そうした人びとは「騙された」と弁明することだろう。(こうして「原子力安全神話」も作られた) ソ連が消滅した後、アメリカは「唯一の超大国」になったと信じた人たちがいた。そして打ち出したのが「潜在的なライバル」の破壊。その青写真として1992年に作成されたのがDPG(国防計画指針)で、その指針に基づいてまとめられたのが2000年に公表されたPNAC(新しいアメリカの世紀プロジェクト)の報告書、「アメリカ国防の再構築」。この報告書を作成したメンバーが動かしていたのがジョージ・W・ブッシュ政権だ。オバマ政権になってもこの戦略は生きている。 今年に入ると、本ブログでは何度も書いているように、反政府軍の残虐行為が表面化している。NATOの中でも軍事侵攻と一線を画しているドイツでもこの事実を複数のメディアが報道、ローマ教皇庁の通信社も同じ内容の報告を伝えている。 ロシア、シリア、イランなどの報道なら「プロパガンダ」で誤魔化すこともできるだろうが、ローマ教皇庁やドイツの有力新聞となると難しい。そこで登場したシナリオは、全て国外から入り込んだ「イスラム過激派」の責任というもの。 ここでもアル・カイダを利用しているのだが、リビアではアル・カイダ系のLIFG(リビア・イスラム戦闘団)が地上軍の主力。ベンガジで裁判所の建物にアル・カイダの旗が掲げられている光景という映像がインターネット上で流れていた。 そもそも、アル・カイダを含むイスラム武装勢力は、1980年代にアメリカの情報機関や軍が作り上げたモンスター。パキスタンやサウジアラビアも支援している。2001年9月11日以降、アメリカはアル・カイダを「テロリスト」の象徴に祭り上げ、「不倶戴天の敵」であるかのように宣伝してきたのだが、昨年来の出来事は、この宣伝が怪しいことを示している。
2012.08.10
-
富裕層や多国籍企業がオフショア市場などを使って税金を回避する中、日本の庶民は消費税という形で搾り取られて社会システムは崩壊、国家財政は止めを刺されることに
野田佳彦首相と自民党の谷垣禎一総裁は8月8日に国会内で会談、「消費税増税関連法案」とやらを今の国会において成立させることで合意したらしい。「財政赤字」だから消費税率を上げるというのだが、大企業や富裕層の負担は軽減する。今、こんな法案を成立させたなら日本の社会生活や経済活動に止めを刺すことになりかねず、財政破綻を招くことになる可能性が高い、と少なからぬ人から批判されている。 しかし、多国籍企業や官僚は、庶民増税に熱心だ。巨大企業は税金や社会保障に関連した負担を軽くできるとほくそ笑み、官僚はこの増税で天下り法人を支えようとしている。小泉純一郎政権が労働基準法と労働者派遣法を改め、非正規雇用者の割合を大幅に増やしたこと、あるいは多国籍企業が参加した秘密討議で進められているTPPを野田政権が導入しようとしていることも「庶民から搾り取る」という点で軌を一にしている。 こうした政策の源は、言うまでもなく、アメリカの支配層。1980年代には日本の支配構造を作り替える作業を本格化させている。そのスタート時点で登場したのが中曽根康弘(岸影内閣とも呼ばれた)であり、打ち出した政策が新自由主義化、つまり規制緩和や私有化の推進。国鉄の債務を国民に押しつけた上、解体、売却したのは象徴的な出来事だった。 日本は基本的に無能な支配層を有能な庶民が支えるという構造になっている。生産活動も無能な大企業を有能な中小企業が支えていた。この仕組みをアメリカは「ケイレツ」と呼び、問題にしたのも1980年代だ。 1990年代に入ると金融スキャンダルで日本企業は大揺れになる。まず1991年、証券会社が大口顧客に「損失補填」していたことが明らかになる。政財官界の要人や大企業を儲けさせることが証券会社の与えられた役割であり、一種の「伝統」だが、大手マスコミは「かまとと」ぶって大騒ぎしていた。 そして発覚するのが銀行の不正融資。例えば、富士銀行の支店幹部が架空の預金証書を発行、ノンバンクから約2600億円を引き出し、東南アジアに流出したと言われている。 東洋信用金庫の場合、広域暴力団、山口組との関係が噂されている大阪の料亭経営者に対して額面3400億円余りの架空預金証書が発行され、この証書を使った不正融資が行われるのだが、この件では興銀が注目された。一時期、料亭オーナーの借入総額は5000億円に達したとも言われている。勿論、架空の証書を使っての不正融資は典型的なマネーロンダリンの手法だ。 アメリカ支配層の日本に対する「改革命令」も出されるようになる。かの有名な「日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく要望書」(年次改革要望書)」は2001年に最初のものが作成されたようだが、1990年代の前半には要求が出され始めたともいう。「ケイレツ」問題のときとは違い、日本側は命令に従うことになる。 アメリカ側の青写真は、「日米21世紀委員会」の報告書に描かれている。この委員会は「21世紀の日米関係をどうするか」を議論するために設立され、1996年にアメリカのメリーランド州で第1回目の会合が開かれている。日本側の名誉委員長は宮沢喜一、委員長は堺屋太一、副委員長は田中直毅、また委員として土井定包、福川伸次、稲盛和夫、猪口邦子、小林陽太郎、中谷巌、奥山雄材、山本貞雄、速水優が名を連ねていた。そのほか顧問として日本経済新聞の小島明も参加していた。 1998年にこの委員会は報告書を発表、その中に目指す方向が示されている。つまり、小さく権力が集中しない政府(巨大資本に権力が集中する国家)、均一タイプの税金導入(累進課税を否定、消費税の依存度を高めることになる)、そして教育の全面的な規制緩和と自由化(公教育の破壊)だ。 すでに巨大企業が日本を支配する仕組みはできあがり、野田政権は消費税の導入に邁進中。橋下某のような人間による政権ができれば、公教育に止めを刺すことになるだろう。 以前にも書いたように、多国籍企業や富豪たちは資産を隠し、税金を回避するシステムを持っている。スイス、ルクセンブルグ、モナコなど古くからあるタックス・ヘイブンだけでなく、1970年代からはロンドンを中心として、旧大英帝国のつながりを利用したオフショア市場ネットワークが登場した。今ではアメリカのIBF(インターナショナル・バンキング・ファシリティー)や日本のJOM(ジャパン・オフショア市場)もある。 金融システムの中で肥大化したオフショア市場。この化け物は経済活動だけでなく、社会生活を破壊しているのであり、この問題を放置して経済活動の復活を望むことはできない。勿論、金融システムの最終形態、カジノで経済を再生させることは不可能だ。 オフショア市場の規制強化/廃止は社会/経済活動を再生させるためには避けて通れない問題なのだが、多くの多国籍企業/富裕層は現在の仕組みを変えたくないと思っているようだ。その結果、利害の反するふたつの階級が形成され、アメリカでは「1%」の富裕層と「99%」の庶民と表現されている。 すでに、このふたつの階級が衝突し始めている。これを力で封じるのか、ある程度妥協して懐柔するのか、支配層の内部は割れている。ただ、アメリカ、イギリス、日本などを見ると、支配層は情報の漏洩を防ぎ、監視システムを強化し、闇の中で逮捕、拘束できる社会を築き上げようとしている。半世紀以上前に腐り果てたことになっている仕組みを復活させようとしているとも言える。「ファシズム化」だ。
2012.08.09
-
67年前の8月9日に長崎市に原爆が投下され、多くの市民が殺されたが、その爆心地近くにあったカトリックの教会が破壊されたのは、米国の反キリスト教的な本質を象徴
1945年8月9日、アメリカ軍のB29爆撃機は、プルトニウム239を利用したタイプの原子爆弾「ファット・マン」を長崎市に投下、直後に数万人が死亡している。 爆心地から500メートルほどの場所に建っていたカトリックの浦上天主堂(浦上教会)も破壊され、「赦しの秘跡(洗礼した後に犯した罪の許しを与える秘跡)」を行っていた司祭や数十名の信徒が殺された。浦上天主堂は「隠れキリシタン」の歴史を背負った教会。その教会を原爆で破壊した事実は、欧米の好戦派が何者なのかを示す象徴的な出来事だった。 ニューヨークの世界貿易センターとペンタゴンが2001年9月11日に攻撃されたあと、ジョージ・W・ブッシュ大統領は「テロとの戦争」を「十字軍」とも表現しているが、その実態は「反キリスト教」的でさえある。 アメリカ、イギリス、フランス、トルコ、サウジアラビア、カタールなどの国々は昨年の春からシリアで反政府軍を組織、シリアの隣国に軍事拠点を提供、資金や武器を提供、兵士を訓練して体制転覆を目指している。 そのシリアでアラウィー派(イスラム教シーア派の分派)やキリスト教徒を反政府軍、この場合はスンニ派のサラフィ主義者(ムスリム同胞団とつながる)や傭兵が襲撃、殺害しているという。東方カトリックの修道院長によると、アラウィー派の場合は皆殺し状態。ちなみに、サラフィ主義者の背後も、傭兵の雇い主も、サウジアラビアなどの湾岸産油国だ。 「西側」のメディアや「人権団体」、あるいは自称「左翼」が民主化勢力であるかのごとく表現してきたシリアの反政府軍は、虐殺のターゲットにキリスト教徒を含めている。バシャール・アル・アサド政権が信教の自由を保障していることもあり、キリスト教徒は政府を支持する住民が多いことが「民主化勢力」に憎まれている一因。現在、多くのキリスト教徒が首都のダマスカスやレバノンへ逃れているようだ。こうした中、潘基文国連事務総長は反シリア政府の立場を堅持している。 勿論、チュニジアで始まった「アラブの春」に触発されてシリアの体制転覆運動が始まったわけではない。そのはるか前、1990年代からアメリカの好戦派が予定していたことなのである。 ウェズリー・クラーク元欧州連合軍最高司令官によると、ジョージ・W・ブッシュの父親、ジョージ・H・W・ブッシュが大統領だった1991年の段階で、ポール・ウォルフォウィッツ国防次官(当時)は旧ソ連圏の国々、シリア、イラン、イラクを掃除すると語っている。そのバックには「戦略家」のアンドリュー・マーシャルがいた。ソ連消滅後、中国脅威論を唱えていることでも知られている。現在、東アジアでの軍事的な緊張を高めようとしている連中の「参謀」でもある。 また「911」の直後には、攻撃予定国として、イラク、イラン、シリア、リビア、レバノン、ソマリア、スーダンがリストアップされていたともいうが、これはリチャード・チェイニー副大統領、ドナルド・ラムズフェルド国防長官、ウォルフォウィッツ国防副長官のラインで決められた話だった。ちなみに、ブッシュ・シニア政権の時代、チェイニーは国防長官、ウォルフォウィッツは国防次官だ。 さらに、ジョージ・W・ブッシュ政権がサウジアラビアなどの国々と手を組んでシリアやイランを攻撃する秘密工作を始めたと、2007年に調査ジャーナリストのシーモア・ハーシュはニューヨーカー誌で警告している。 ブッシュ・ジュニア政権以降、アメリカはイラク、リビア、シリアなどを攻撃、体制を転覆させつつある。この攻撃におけるイギリスやサウジアラビアの役割も大きい。攻撃されている体制の共通項のひとつは、スンニ派武装集団/アル・カイダを弾圧してきたということ。一方、この攻撃でNATO/湾岸産油国はアル・カイダ系武装集団と手を組み、キリスト教徒も攻撃している。ブッシュ・ジュニアが言うところの「十字軍」とは、反キリスト教集団なのだろうか?
2012.08.08
-
福島第一原発で過酷事故を起こした東電は重要証拠であるテレビ会議の映像をいまだに管理、隠蔽しているのだが、その背後では兵器級プルトニウムの蓄積に協力している疑い
昨年3月11日に東京電力の福島第一原発は過酷事故を起こし、いまだに大量の放射線物質を環境中に放出し続けている。その事故を受け、東電では本社と福島第一原発などを結んでテレビ会議が開かれているが、その様子を記録した映像が存在、その一部が加工した上で公開された。要するに、公開拒否が難しい状況になったので、アリバイ工作的に形だけ公開したわけだ。 この会議にはアメリカ軍や自衛隊の人間が参加しているという噂もある。この話が正しいならば、東京電力は日米の軍事組織が管理してきたと疑われても仕方がない。ジャーナリストのジョセフ・トレントによると(原文、日本語訳)、日本はアメリカ側の支援を受け、1980年代から昨年3月までに70トンの「兵器級プルトニウム」を蓄積、その隠れ蓑に電力会社が利用されてきたという。 それはともかく、事故後のテレビ会議を記録した映像を今でも事故の当事者である東電が管理していること自体が異常だと多くの人が感じているだろう。こんな事故を起こした会社が倒産せず、歴代重役は責任をとらず、今でも情報の隠蔽を図っているのが現実。政治家、官僚、学者、マスコミなどの責任も重いが、第一義的な責任者は電力会社の重役である。 こうした事故が起こる可能性があることは以前から指摘され、電力会社側も予見できたはずなのだが、それでも対策を取らずにきた結果、日本の国土は汚染され、少なくとも一部は人が住めなくなった。 今年に入り、東電は今回の事故に伴う放射性物質の放出総量がチェルノブイリ原発事故の約17%に相当すると発表した。当初は1割程度としていたので、それよりは増えているのだが、計算方法に問題があるとも指摘されている。 計算の前提では、放射性物質は圧力抑制室(トーラス)の水で99%が除去されることになっているのだが、今回は水が沸騰していたとみられ、ほとんどの放射性物質が環境中に漏れ出たと考えるべき状況。その結果、チェルノブイリ原発事故で漏洩した量の2〜5倍に達するというのだ。(アーニー・ガンダーセン著『福島第一原発』集英社新書) それでも今回は奇跡的な幸運が重なっている。事故直後の風が太平洋に向かっていたこと、定期点検中の4号機で炉内の大型構造物の取り替え工事でミスがあって使用済み核燃料プールの水がなくならなずにすんだこと、福島第二、女川、東海第二も紙一重のところで冷却不能、メルトダウンを何とか避けることができたことなどだ。 勿論、事故が収束したわけではなく、再び大きな地震に襲われて4号機の使用済み核燃料プールが崩壊したなら、1号機から6号機まで冷却作業が難しくなる可能性が高い。セシウム137で比較すると、チェルノブイリ原発の事故で環境に出た量の約85倍が放出されるという。 こうした状況の中、いまだに事故の当事者が重要な証拠を隠すことが許される日本の支配システムは速やかに造り直す必要がある。
2012.08.07
-
シリアの首相が亡命、ヨルダン経由でカタールへ行くとも言われているが、なぜ政府の内部に留まって情報を提供したり、要人暗殺に協力したりしなかったのだろうか?
シリアのリアド・ヒジャブ首相が解任された。つまり反政府軍側に寝返ったと伝えられている。家族とヨルダンへ逃げ、そこからカタールへ移動するとも報じられているが、ヨルダン政府はヒジャブが国内にいることを否定しているという。 湾岸の産油国はシリアの反政府軍に武器を提供するだけでなく、特殊部隊を派遣したり傭兵に給料を出している。シリアの要人に多額のカネを提供したとしても驚きではない。 ただ不思議なのは、なぜ亡命してしまったのか、ということ。敵対国の要人が亡命を求めてきたなら、通常は思いとどまらせ、情報を提供させたり工作に利用させたりするものである。かつて、こんな出来事があった: 第2次世界大戦が終わって間もない頃、ポーランドの秘密警察、UBの幹部、ヨゼフ・スビアトロがイギリスの情報機関MI6へ亡命を打診してきた。この幹部はポーランド政府や共産党を監視する部署の次長。その部署はソ連の秘密警察、NKVD(内務人民委員部)を統括していたラブレンチ・ベリヤが直接、指揮していたと言われている。 この亡命打診をイギリスはアメリカのアレン・ダレスに伝える。言うまでもなく、ダレスはウォール街の弁護士で、大戦中は破壊工作を指揮していたのだが、戦後は「民間人」に戻っていた・・・ことになっていた。アメリカの情報/破壊活動をこの民間人が指揮していることををイギリス側は承知していたわけだ。 ダレスは亡命を思いとどまらせ、ソ連圏の内部にダメージを与える工作に協力させようとした。彼を使い、東ヨーロッパの共産党幹部を「アメリカのスパイ」にでっち上げ、国民に支持されそうなコミュニストの指導者を潰していったと言われている。いわゆる「スプリンター・ファクター作戦」だ。 この工作がはじまる1948年にアメリカでは破壊工作(テロ工作)を目的とする極秘組織、OPC(政策調整局)が創設されている。その局長に就任したのはダレスの腹心で、やはりウォール街の弁護士だったフランク・ウィズナー。この組織の母体は、大戦中にイギリスのSOE(特殊作戦執行部)とアメリカのOSS(戦略事務局)が共同で組織していた破壊工作部隊、ジェドバラだった。 1953年3月、この「スパイ狩り」はヨシフ・スターリンの死によって終わる。7月にはベリアが解任され、12月には処刑された。ベリアの処刑を横目に見ながらスビアトロはアメリカへ亡命する。 どの国の政府でも、首相と言えば機密情報に接することのできる人物。シリア国内では反政府軍の破壊工作が頻発している。亡命の宣伝効果ということもあるだろうが、NATO/アメリカ、湾岸産油国に情報を提供したり秘密工作、例えばシリア政府の要人暗殺に協力せず、ヒジャブは単純に亡命したのだろうか?あるいは・・・
2012.08.06
-
広島に原爆が落とされて67年目の現在、米国は英国、仏国、トルコ、サウジアラビア、カタールなどと手を組み、アル・カイダを使ってシリアの体制転覆、国家乗っ取りを目指す
67年前の8月6日、アメリカはウラン235を使った原子爆弾「リトルボーイ」を広島市の投下、十数万人を一瞬のうちに殺害した。その時に放射性物質を浴びた多くの人がいまだに殺され続けている。この事実に歴代日本政府は目をつぶってきたが、今、東電福島第一原発の事故でも同じことを繰り返そうとしている。 広島に原爆が投下される21日前、アメリカはニューメキシコ州のホルナダ・デル・ムエルト(死者の道)砂漠でプルトニウムを使った原爆の爆発実験が行われた。実験の翌日から8月2日の期間にベルリン郊外で開かれたのがポツダム会談である。アメリカのハリー・トルーマン大統領は実験が終わるまで会談を引き延ばしていたという。 4月に急死したフランクリン・ルーズベルト大統領は、2月に開かれたヤルタ会談でソ連に対日参戦を求めていたが、トルーマン大統領は原爆の独占によってソ連の影響力を排除したいと願っていたという見方もある。 ヤルタ会談の取り決めによると、ドイツ敗戦の90日以内にソ連は日本との戦争は始めなければならない。ドイツは5月7日に降服しているので、8月5日までにソ連は日本に宣戦布告しなければならなかったが、実際に参戦するのは8日、広島に原爆が投下された後のことである。 9日から10日にかけて日本では「御前会議」が開かれ、ポツダム宣言の受諾を決定、スイスの日本大使館を経由して連合国へこの決定を伝えている。15日の「終戦勅語」は「臣民」に対し、負けたとも降服したとも言わない発表にすぎない。日本軍に停戦命令が出たのは16日、降伏文書の調印は9月2日である。 この段階で日本は「ポツダム宣言」に基づく戦後が始まったはずだが、日本の支配層はその事実を認識できなかったらしく、思想犯の釈放や治安維持法の廃止は考えていなかった。何しろ、10月の段階で山崎巌内相は特高警察を使い、天皇制に反対する人間を逮捕すると公言している。そのひとつの結果が三木清の獄死である。 日本が戦後の第1歩を踏み出すのはその直後、ダグラス・マッカーサー連合軍最高司令官が「政治、信教ならびに民権の自由に対する制限の撤廃、政治犯の釈放」を指令、政治犯が釈放されたときである。が、その後も特高は「公安警察」として生き残り、思想検察などと同様、国民弾圧の責任者たちは戦後も支配的な地位に居座り続けた。 アメリカが日本の体制を変えるということは、それなりに合理的な理由はある。ほかの連合国を無視するという問題はあるが、それでもアメリカは日本との戦争に勝利し、日本は連合国に無条件降服している。日本は敗戦国であり、アメリカは戦勝国である。しかも日本の支配層に対する対応は優しかった。ほかの連合国を無視する形で天皇制を維持する憲法を作り、「戦前レジーム」を残したのも一例。 ところで現在、シリアでは「民主化運動」を支援、政府軍の弾圧を止めさせるという口実でアメリカは軍事介入している。シリアという国と戦争しているわけではない、ということになっている。そうした状況の中、アメリカはイギリス、フランス、トルコ、サウジアラビア、カタールなどと同盟を組み、特殊部隊を潜入させ、傭兵を雇い、アル・カイダ系のイスラム武装集団と手を組んで破壊と殺戮を繰り返している。この事実は隠しようがなくなっている。 どうやら、最近、アメリカはシリア国民を無視する形で、シリアの新体制をアメリカに都合良く作り替えようとしている。要するに、植民地化しようとしている。 本ブログでは何度も書いているように、反政府軍の編成、訓練、資金や武器の提供という形で軍事介入してきた。現在、トルコ、レバノン、ヨルダンなどの拠点からシリアへ部隊を軍事侵攻させている。 昨年の春から、トルコにある米空軍インシルリク基地でアメリカの情報機関や特殊部隊、イギリスやフランスの特殊部隊が反政府軍のFSA(自由シリア軍)を訓練していると伝えられていたが、ここにきて反政府軍のプロパガンダ機関と化しているBBCもこの事実を認め始めている。ただ、訓練は次の段階に移っているようだが。 アメリカはシリアと戦争しているのではなかったはず。「弾圧されたシリア国民」を支援するというなら、主役は国民でなければならないのだが、困ったことに反政府軍の主力は外国人である可能性が高い。イスラエル建国時のように、恐怖(テロ)戦術を使い、住民を入れ替えるつもりなのだろうか?
2012.08.05
-
米国の電子情報機関がシリアのテレビを乗っ取る一方、NATOや湾岸産油国の支援を受けたシリアの反政府軍はシリアのテレビ局を襲撃、スタッフを殺害して事実を隠そうとする
NATO/アメリカ軍はシリアでプロパガンダに力を入れている。「西側」の有力メディアを使って情報を操作するだけでなく、6月には反政府軍、つまりFSA(自由シリア軍)がシリアのテレビ局を襲撃、施設を破壊し、7名のスタッフを殺害(処刑)している。 先月にはシリアのテレビ番組に似せて作られた映像が流されたようだ。その偽番組の発信元はオーストラリアのパイン・ギャップにあるアメリカの電子情報機関、NSA(国家安全保障庁)の基地ではないかと疑われている。かつて、この基地を守るため、アメリカ政府はイギリス側の協力を得てオーストラリアのゴフ・ホイットラム政権を潰したこともあった。 シリアのテレビ局が襲撃する直前、反政府軍はテレビ番組の司会者だったモハメド・サイードをダマスカスで拉致したが、最近、反政府軍によって処刑されたと伝えられている。 プロパガンダは一種の幻術と言える。この幻術をアメリカの支配層は重視、第2次世界大戦が終わって間もなく、メディア支配の仕組みを作り上げた。いわゆる「モッキンバード」だ。 幻術を使う人びとが最も嫌うものは「事実」。2010年4月にウィキリークスが公表した映像では、アメリカ軍のアパッチ・ヘリコプターに乗った兵士が戦闘行為と関係のない十数名の人々を殺害する様子が映っていた。この映像(事実)が外部に漏れたこともダメージだろうが、犠牲者の中にはロイター通信のスタッフ2名も含まれていたことも偶然とは思えない。 この銃撃は2007年の出来事だが、その前、イラクへアメリカが2003年3月に軍事侵攻を始めた直後、イギリスの番組制作会社ITN(独立テレビニュース)の記者、テリー・ロイド記者をアメリカ軍は射殺している。交戦中ではなく、取材中に拘束されてからのことだ。 その翌月には、イラク戦争を取材する目的で各国から集まったジャーナリストが宿泊していたパレスチナ・ホテルをアメリカ軍の戦車が砲撃、ロイターのカメラマンとスペインのテレビ局テレチンコのスタッフが殺され、3名が負傷している。 5月にはバグダッドから約30キロメートルほど南の地点で日本人ジャーナリスト、橋田信介と甥の小川功太郎が殺されている。当時、日本のメディアは「交戦熱」に浮かされ(今は少し症状が軽くなっただけ)、戦争に反対したり、開戦の障害になるようなことをする人物を激しく攻撃していた。そうした中、橋田は熱に浮かされていない希有な人物。つまり、日本やアメリカの政府にとって邪魔な存在だった。 こうした犠牲は氷山の一角にすぎないわけだが、アメリカ軍に「はめ込まれた」形で「取材」しているメディアの記者も多い。これがアメリカ版の「大本営発表」である。 1970年代の後半からメディアの締め付けが厳しくなり、気骨のある記者は追放されてきた。その一方で1980年代からメディアと支配システムは一体化してくる。その一例がBAP(英米次世代プロジェクト)。このグループが創設される際、ルパート・マードックやジェームズ・ゴールドスミスの名前が出ていた。後にBAPはイギリスのトニー・ブレア政権を支えてることになる。日本にも似た仕組みがあるようだ。
2012.08.04
-
アナン元国連事務象徴がシリア特使を辞任する意向を示す直前、オーストリアのメディアがシリアの戦乱を強調するために写真を改竄して掲載、話題になっている
シリアの戦乱がコントロール不能の状況、つまり外部からの働きかけがないと収拾がつかないというイメージを広めたいのか、オーストリアのメディアが写真を改竄、背景を普通の街中でなく、廃墟に変えて掲載したことが発覚、インターネット上で話題になっている。 この新聞が出た直後、コフィ・アナン元国連事務総長はシリア特使を辞任する意向を示した。戦闘が泥沼化して調停作業が困難になっているということのようで、アメリカ政府は辞任の原因はロシアや中国にあると主張しているようだ。シリアのバシャール・アル・アサド体制を転覆させようというNATO/アメリカの計画に逆らうロシアや中国がいるから戦闘が長引いているということのようだ。 これに対し、虐殺のあったホウラを訪れた東方カトリックの修道院長は「皆が真実を語れば平和は回復する」と語っている。「西側」のメディアがホウラでの虐殺を政府軍側によるものだとしていたのに対し、サウジアラビアの支援を受けたスンニ派のサラフィ主義者(ムスリム同胞団とつながる)や反政府軍に参加している外国人傭兵が虐殺を実行したとしていた。つまり、「西側」が真実を語らないことが戦乱の原因だと言っているのだ。 ベトナム戦争のフェニックス・プログラムにしろ、ラテン・アメリカの親米独裁政権が実行した「死の部隊」による虐殺にしろ、アメリカの「テロ人脈」は自分たちに服わない政権を暴力的に倒し、住民を容赦なく殺してきた。(詳しくは拙著『テロ帝国アメリカは21世紀に耐えられない』を)シリアでも同じことをしているだけだ。
2012.08.03
-
強引に原発の再稼働した野田首相は命をかけて消費税の税率を引き上げようとしているが、天下りやオフショア市場の問題は放置しておく決意のようだ
消費税の引き上げが大企業/富裕層の負担軽減とセットになっていると多くの人が指摘している。おそらく、この指摘は正しい。野田佳彦政権は社会保障改革や財政健全化など意に介していないようだ。 原発の再稼働やTPPと同じように、消費税増税関連法案を成立させるため、野田首相は不退転の決意で、政治生命を懸けて、命を懸けて頑張るらしい。かつて彼は「税金に天下り法人がぶら下がっている」と主張、この「シロアリ」を退治しないで消費税率を上げるべきでないとしていたのだが、そんなことは忘れたようで、天下りを放置したまま消費税を引き上げようとしている。 自分自身の政治生命に終止符を打ち、民主党どころか日本を「ぶっ壊す」ことに成功しても、支配階級の一員として安穏に暮らせることが約束され、どこかのオフショア市場の金融機関に口座を持たせてもらえるなら、安心だ。 このオフショア市場は経済をぶっ壊す存在である。これが存在する限り、財政を健全化させることは不可能である。天下りを根絶するだけでなく、オフショア市場の取り引きを透明化しなければ、何も解決しない。「金融のグローバル化」にメスを入れる必要があるということだ。 昔からヨーロッパには富裕層の資産を隠すオフショア・システムが存在した。スイス、ルクセンブルグ、モナコなどが代表例だ。 そうした富裕層の資産の源をたどると、十字軍に突き当たる。11世紀から13世紀にかけて中東から北アフリカにかけての地域を侵略し、財宝だけでなく重要な知識(文献など)を手に入れたのだが、こうした略奪を抜きに近代ヨーロッパを語ることはできない。 近代ヨーロッパを作り上げる基盤としてラテン・アメリカでの略奪も無視できない。先住民が保有していた貴金属や財宝だけでなく、ポトシ銀山から膨大な量の銀が持ち出されているのだが、いまだに総量は明確になっていない。ただ、近代ヨーロッパ経済の原資になったと推測する人がいるほど膨大な量だとは言える。 イギリスの場合、破綻寸前の資本主義経済を建て直すため、麻薬貿易にも手を出している。その前段階として1840年に引き起こしたのがアヘン戦争だ。いわば、強盗と麻薬取引で近代ヨーロッパ、資本主義は幕を開けた。 ただ、19世紀は今と違ってオフショア市場が整備されていなかった。この当時、アメリカでは不公正な手段で巨万の富を築いた富豪が出現、「泥棒男爵」と呼ばれている。ジョン・D・ロックフェラーやJ・P・モルガンが代表的な存在だが、資産の隠し場所が限られていたため、彼らは産業に投資することになり、結果としてアメリカの生産基盤を築くことになった。 ヨーロッパで所得や資産を隠すシステムが拡大する切っ掛けは、第1次世界大戦だという。戦費を調達するために政府は増税するのだが、金持ちは税金を逃れるために資産をタックス・ヘイブンへ沈めたのである。 それ以上に大きな変化が1970年代に起こる。経済活動の国際化が進むにつれ、税金をどうするかが大きな問題になったのだが、そうした中、多国籍企業の要望に応える形でロンドンを中心とするオフショア市場ネットワークが出現したのである。単に資産を隠すだけでなく、税金を回避する手段を提供した。 ロンドンに対抗する形で1980年代に出現したのがアメリカのIBF(インターナショナル・バンキング・ファシリティー)や日本のJOM(ジャパン・オフショア市場)だ。巨大企業や大富豪はこうしたシステムを使い、税金から逃れることができる。勿論、このシステムには犯罪組織や独裁者の資産も流れ込んでいる。1980年代にオフショア市場と日本の大企業を結ぶパイプのひとつとして機能したのが無担保の転換社債やワラント債だ。 規制緩和や私有化を掲げる新自由主義経済の広がりもあり、この時期から富の集中が急速に進み、経済活動が停滞していく。「泥棒男爵」とは違い、産業を育成する必要がなくなったことが大きい。21世紀版の「泥棒男爵」を象徴する人物といえば、ボリス・エリツィン時代のロシアで巨万の富を獲得したボリス・ベレゾフスキー(現在はプラトン・エレーニンに改名)だろう。 南北問題を深刻化させたのもオフショア市場である。国際機関なり欧米の金融機関が親米独裁者が君臨する発展途上国へ「融資」、その資金は独裁者の資産としてオフショア市場へ流れ込み、欧米の銀行に戻る。独裁者が失脚すれば、その資産はどこかへ消えてしまい、残された国民は借金を返済させられる。早い話、大銀行とはタチの悪い高利貸しにすぎない。 アメリカにしろ、EUにしろ、日本にしろ、オフショア市場の問題を抜きに財政を論じることはできないはずなのだが、大多数の学者やメディアは避けている。つまり、大多数の学者や記者は「御用の筋」だ。言うまでもなく、オフショア市場の問題に触れない消費税論議もインチキである。そのインチキを維持するため、支配層は「秘密」を強化しようとしている。
2012.08.03
-
シリアのアレッポで反政府軍が捕虜にしていた政府軍側の兵士を大量処刑している光景とされる映像が流されているが、反政府軍の残虐行為は昨年の春から続いていること
シリアのアレッポで政府軍と反政府軍の戦闘が続いているが、反政府軍が捕虜にしていた政府軍側の兵士を大量処刑している光景とされる映像がインターネット上で流れている。 イギリスのウィリアム・ヘイグ外相と緊密な関係にある「シリア人権観測所」はこの虐殺を「報復」と表現したが、反政府軍は昨年春から「死の部隊」を編成し、住民を殺害しているとする報告もある。今回の一件はその延長線上にある。 サウジアラビアやカタールの管理下にあるイスラム武装勢力、その中にはアル・カイダも含まれているのだが、そうしたグループの戦闘員は多くがシリア国外から入ってきている。一方、FSA(シリア自由軍)の主力は傭兵とゴロツキだと言われ、暴力的な行為に走りやすい体質を持っていると言える。 リビアでNATOは分離独立派を使っていたが、シリアには利用できる「少数派」がいない。むしろキリスト教徒など少数派は政府を支持している。分離独立派がいたリビアでも地上軍の主力はアル・カイダ系のLIFG(リビア・イスラム戦闘団)。シリアでイスラム武装勢力に頼るのは必然だろう。 戦闘が始まった直後から、「残虐な政府軍」が「民主化を求める国民」を暴力的に弾圧しているというシナリオは嘘だと主張するウェブスター・タープレーのようなジャーナリストはいたが、今年3月にはシリア駐在フランス大使のエリック・シュバリエも報道されたような弾圧はなかったと語っている。 「政府軍による弾圧」を有力メディアが伝え始めた頃、報道は嘘だということをシュバリエ大使はアラン・ジュペ外務大臣兼国防大臣(当時)に報告しているのだが、これを聞いて外相は激怒する。残虐な弾圧が行われていると書き直せというわけである。外相は事実が知りたかったわけではなく、シリアに軍事介入する口実が欲しかっただけということである。 7月19日にシリアの北部、トルコとの国境に近くで数十名の反政府部隊に拘束されていたフリーランスのフォトジャーナリストも26日に解放されてから反政府軍は外国人によって編成されていたと証言している。ジハード集団のキャンプにシリア人は見当たらず、少なくとも6名はロンドンやバーミンガムの地域で使われている発音をしていて、その中には強いロンドン南部訛りのある人物が含まれていたという。 反政府軍の残虐性が明らかにされた出来事のひとつがホウラでの虐殺。当初、「西側」は政府軍の攻撃で住民が殺されたとしていたが、事実に反することがわかると親政府派の武装グループによる犯行ということにされた。 ところが、現地を取材したロシアのジャーナリストは反政府軍による虐殺だと報告、続いてローマ教皇庁のフィデス通信は東方カトリックの修道院長の報告として、サウジアラビアの支援を受けたスンニ派のサラフィ主義者(ムスリム同胞団とつながる)や反政府軍に参加している外国人傭兵が虐殺を実行したと語り、フランクフルター・アルゲマイネ紙も同じ内容の報道をしている。ドイツの場合、ビルト紙やディ・ベルト紙もホウラでの虐殺が反政府軍によるものだと伝えている。 こうした中、シリアの体制転覆を支持し続けている潘基文国連事務総長の姿は哀れだ。
2012.08.02
全38件 (38件中 1-38件目)
1