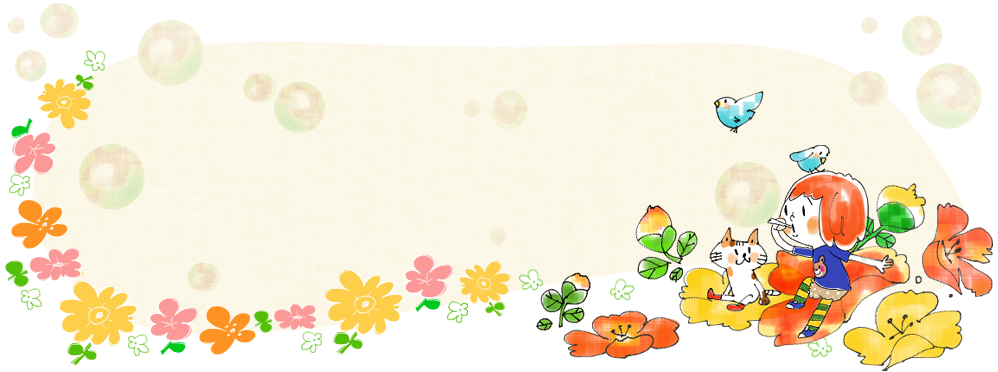5月17日(金)
近藤芳美「土屋文明」より(71)
岩波書店近藤芳美集第七巻「土屋文明 … 鑑賞篇」よりの転載です。
第八歌集『山下水(やましたみず)』より(2)
夕のかげ早く及べる谷の田よいなごも乏し青きにすがりて
(昭和二十年)
せまり合った谷に、山の夕影は早く這い寄って来る。峡の田の、稔りのおそい青い稲にすがっているいなごの数も乏しい。この疎開のむらにはもはや冷えびえとした秋が来ているのであろう。
前の歌と同じく、「川戸雑詠」と題する作品群のなかの一首。敗戦後間もない時期の作品である。乏しいいなごが「青きにすがりて」いる、という把握がするどい。その一点に集点のしぼられて行くような表現技巧が効果的であるといえる。それと共に、この歌からも亡国の日本に生きる民の一人の悲しみのようなものを感じる。読後、静かな悲哀感が、作品の背後にしだいにひろがって行くようである。
「いそしみて蒔きたる蕎麦の大方はこほろぎ食ひきそれも憤らず」「片よりに野分は吹けり庭草の茎を透きたる日の光もよし」などの歌が並んでいる。日本人みな虚脱した顔をして、食を求めて焼あとの街をさまよっていた時代である。
この谷や幾代の飢えに瘠せ瘠せて道に小さなる媼(おうな)行かしむ
(昭和二十年)
土屋文明が疎開した川戸という部落の様子は、戦後しばらく「アララギ」に連載された「日本紀行」という文章に語られている。榛名山の背後の、吾妻川渓谷の奥の貧しい農村である。村民たちは渓谷に棚田を作り稲をうえた。しかし山水に頼るだけの棚田は冷害を受けやすく、敗戦の年も、ほとんど一粒も稲の稔らない田さえあったと彼は記している。そのようなわずかな土地にすがり、農夫らは幾代も幾代も飢餓に耐えながらこの渓谷に生きてきたのであろう。作者は田の畦をたどたどと歩む一人の老婆の姿を見送っている。その老婆の姿に農民たちの苦渋の人生を感じている。
「苦しみて柄鍬に弾かれし記憶さへ農の君等に語るはたのし」「麦ふに代へてローラー引き給へ少しは君の安からまくに」などの作がある。彼自身が農民であった。そのことの共感が疎開地の生活からしだいに歌われて行く。
(つづく)
-
近藤芳美『短歌と人生」語録』 (28)… 2024.06.20
-
歌集「未知の時間」(前田鐵江第一歌集)… 2024.06.20
-
近藤芳美「土屋文明:土屋文明論」より 2024.06.20